引田康英の九品塾・選択講座
時間=歴史を考える 日本史話三講
第Ⅰ講:統治変遷のプロセス
遺伝適性を知るための民族ルーツ論
出発点として己を知り他人を知る=他人との違い認め争わない=自己の特徴伸ばし不得意なものカバー=日本人単一民族論や血液型による性格断定から脱するために>これから述べることはかなり刺激が強いので前もっての心構えが必要?
日本人は多様な民族によって形成されてきた
日本人はかつて自身を単一民族であるかのように思ってきたが,多様な民族によって形成されてきたことは明らかである。
まず,日本人自身が風貌その他を特定しにくい。様々な外国人によく似た風貌の日本人がいるのは誰しも思うところであろう。たとえば,韓国人の集団や中国人の集団と比べた場合,日本人は韓国人や中国人と同じような風貌も含めて,そのバリエーションが極めて広いことに気づかされる。外国人からも,日本人と特定しにくいらしく,ベトナム人,中国人などと言われる場合が多い。
次に,日本人のシンボルとされる長島茂雄が三代前はスペイン人だったと言われるように,たいていは日本に来た外国人も三代もすれば日本人と見分けつかなくなる(私の事務所にも,三代前がハンガリー人だったという所員がたし,長島に限らず有名なスポーツ選手にも少し前の代には外国人だったというのが多い)。>世界中の人たちが混血すると日本人的になるという説=優性遺伝(優れているという意味でなく遺伝比率が高いということ)の結果(たとえば金髪から黒髪へ)
最近の考古学やさらに進んだ遺伝子学等の成果から,南方の島々や中国南部,あるいは北方シベリアや中央アジアなどから多くの民族が流入し,それらが混然として日本人が形成されてきたと考えられる。その裏付けとして,日本の国はユーラシア大陸の縁辺部にあり,暖流,寒流の終わるところに位置するため,流入はしやすいが,流出はしにくく,古くから何回にもわたって様々な民族が流れつき,また,わが国は世界的に見ても土地生産性が高く,比較的温暖で住みやすいということもあって,これらの民族が欧米等にみられるように大々的な戦争などによって,一方的殺戮という形で抹殺されることなく,狭い島国に留って,必然的に密度が高まっていったと言える。幾重にも混血を重ねた結果,前述のようにあたかも単一の日本人のような風貌になり,こういった日本人の有り方(狭い土地に多様な人達が生活しなくてはならない)が一方で天皇の存在を特別なものにして,あたかも単一民族として振る舞わざるを得ないようにした。
このように,多民族で形成されてきたことが,日本が歴史時代に入ってからでも2000年の長期にわたって活性を維持できた理由でもあり,日本の商品と商社の活動が世界どこででも受け入れられて経済繁栄につながり,また,オリンピックなどでかなり幅広い種目に選手が出場して,多くの競技を知り楽しむことができると考えられる。この矛盾した存在が今まさに国際社会から問われていると言えよう。
このように見かけ上単一民族であるかのように混血がすすんできたのであるが,冒頭に述べたように,容貌のバリエーションは大きく,メンデルの遺伝の法則を持ち出すまでもなく,こういった民族性は意外なほど温存されており,個々人にその民族性が表出しているといえよう。また,混血でなく住み分けという形で調整している部分も多い。
狭い島国にこういった多様な民族が住んでいる国を統治するために,第二部。第三部で述べるように,天皇というものが創出され,さらに,その天皇を利用する政権が支配,武家社会では,度重なる大名の配置によって,地域の民族をシャッフル,その究極が徳川幕藩体制であったと考えられる。唐突かもしれないが,秋田美人などの特徴は,そういった歴史によって生まれてきたといえよう。
具体的な事例から,日本人の民族の多様性や個別の特性が分かる
そもそもこういうことを気にするようになったのは,まず,各地の計画などに携わるようになって,それぞれの地域の人達の違いや思わぬ特性以上に,同じ地域の中での各部分の間の違いに驚かされたことが大きい。
よくいわれる農耕・海洋・騎馬の三大民族という点から,まず,鹿児島の西に浮かぶ甑島に行った時,本土との間の航路で島の人達が船酔いに弱く,到着後は漁業にもあまり熱心でないことを知った。普通に考えれば島なのだから海に強く,振興策として漁業を取上げるのは当然であろう。要するにこの島の人達の多くは流れついた農耕民族であったのだ。その証拠に殆ど平地の無く大部分が険しい地形の甑島では今も天まで登る段々畑を維持している。勿論,海洋民族が主体の集落があって(あとで触れるが地名も平良,鹿島というように海洋系である),その村だけは漁業が極めて盛んである。同じ島の中にいながらこれら二つのタイプの集落の間には殆ど交流が無く,両者を繋ぐトンネルづくりにも熱心でなかった。江戸時代には,隠れキリシタンの村もあったように,日本の縮図のさらなる縮図くらいの狭い島のなかで,必死に住み分けていたとも考えられる。この時の産業振興策のひとつの解答は,養殖漁業,つまり農耕的な漁業ということだ。
こういった例は他にいくらでも見られ,各地域においてデザインを構築するにあたっては,民族特性の面から,得手,不得手をよく理解することが必要である。そいうしないと「海に囲まれているから漁業を」というようなワンパターン的な発想になる危険がある(もちろんこのことが差別につながるのではいけないのであって,相手の役に立ち,自らのアイデンティティを確立することにのみとらえるべきものである)。
また,平家の落人の村々については,一軒のなかの大家族や山菜・川の様々な生き物を食するといった共通の文化があることを多くの人たちが知っているが,源氏の落人といわれる長野県の川上村に行ってみると,カラマツだけで貧しくツケモノを食する慣習もなかったが,その後,レタスづくり始めるや一面に生産し,大型の保冷車が列をなす(まさにコンボイ)金持ち村に変貌した。これは,騎馬民族のアメリカの農業がまさにそうであるように,騎馬民族は大規模均一型農業に強いということで,思えば,騎馬民族が主体の山梨県の葡萄畑も同じように思える。アメリカやオーストラリアなど,騎馬民族の大規模農業を思い出せば,一層良く分かる。これらは,農耕民族化した騎馬民族といえる。本来の農耕民族なら,中国人のように,土地の細かな部分に対応したち密な植栽(垣根・枝豆・鶏など)から芝桜の石垣などに自然に現れる。ついでに,騎馬民族が海洋民族化したものとして,すぐ思いつくのはバイキングであり,ノルウェーの水産業はトロールで一斉に漁獲するもので日本のち密な水産業とは違う。
さらに,鹿児島の隼人を祖とする人たちがラード好きなのにも奇妙な感じを持ったが,そのルーツが,トカラ列島の名が示すように,中央アジア由来のいわゆる韃靼人だということに気がつけば合点が行く。この他,北から挙げれば,流れ者によってできている下北(熊野から伝わる能舞,一部の焼酎文化,隣接する部落の間の言葉の違い等々)と全く逆の津軽(すべてが均等でなければならない),全国に知られる富山県のユニークさ,飛騨高山の木の文化,そして九州各県の間の突張り合い,とくに一匹狼ばかりの鹿児島県,さらに沖縄の人達とアイヌの人達の類似などでさまざまな現れ方がある。
その他,下北半島で隣あう部落間で言葉が相当に異なることを知り,新潟県では相互に通じないくらい違うのもあると聞いている。
もう一つ,自分と弟の違いの大きさからも考えるようになった。というのは,両親ともO型,兄弟皆O型で,ほぼ同じ年代で同じ家庭環境に育った以上,似ている面の方がずっと大きくて当然のようであるが,例えば自分はツケモノというものを一切口にしないのに,弟の方はそれこそツケモノだけで御飯を食べるのである。自分は反抗的,弟は従順など,性格的にも正反対。他の点についてもおして知るべしという違いである。実は血液型は一家を挙げて同じなので,これはもう民族型の違いとしか思えなくなった。こういった疑問を抱いている人も多いと思う。
それがなぜ個々人に出てくるのかは,既に述べたように,メンデルの遺伝の法則からすれば当然で,多くの人達が混血を重ねても,個々の人間には先祖のいずれかの遺伝子が表れ,兄弟でも性格や嗜好が正反対になったりする。ただし確率として多く出るのであって逆は成り立たない。とくに近傍で交わっている国民や民族は全体的に共通する特徴に持つようになることは言うまでもない。このことによって世界の民族やある国の人達がそれぞれ個性豊になっている。これら個々の人や民族の特徴を知ることによって,相手の身になって感じることができるようになり,余計な摩擦を減じ,真の交流が出来るようになる。かって民族型や血液型の一面だけを採り出して差別に結びつけた歴史は葬り去らなければいけない。近年多くのことが遺伝子によって証明されるようになって来ている。
農耕・海洋・騎馬の三大民族が登場する以前
最も古い段階で日本列島に住みついたのは,1万年以上前にアジアから今のベーリング海峡を渡っていったインディアン(インディオ)と同じと考えられる。インディアンがアメリカ大陸に渡った1万年以上前は,血液型が分化する前だったため,全てO型のようである。その後中南米で花開いた石造文化を思うと,東南アジアや太平洋の島々などの石造文化も含めて,つながりを感じざるを得ない。
ちなみに,血液型の進化はO型がもとで,人類発祥の地アフリカも本来はO型のみ,中近東(メソポタミア)でB型が派生,インドや中国に広がり,ヨーロッパでA型に進化,もちろんAB型はその後である。輸血について,O型が全ての血液型に供給できるのに,逆が成り立たないのもそのためである。ヨーロッパではA型が広がり,古いO型はアイルランドのケルト人など辺境に押しやられた民族に残り,民族差別が極端になったのがナチスでは,A型の純血主義をも採用していた。ちなみに,オウム真理教もそうだったらしい(幹部に一人だけ見ただけでO型と分かる人物もいたが)。他方,アジアにおいては,日本人にA型が際立って多いことから,ヨーロッパ人が準白人扱いしたともいわれている。なぜ多いかは,第二部を読むと分かるであろう。このように,血液型からも多民族で構成されていることが証明される。なお,漢民族は農耕民族である一方,B型が多いことから,万元戸や反日暴動など極端な行動が出やすいとも考えても良いのかもしれない。
その後,縄文人といわれる人たち(インディアンともつながっているのかもしれない)が全土に展開し,やがて,当時の地球上では最先端となる土器文明を拓く。このことは,日本文化のベースとして技術+芸術があることを示す。また,縄文人の焼畑(地名は木場など,紀氏(木野氏などの表記も)などはこの段階から続く古い氏族の可能性)が農耕民族(畑作型)に,漁労が海洋民族に,狩猟が騎馬民族にと,いわゆる三大民族につながって行くことは言うまでもない。
次に,主に大陸方面から弥生人が流入し,縄文人を列島の東北や西南に押しやって行く。その名残が,南北に押しやられたアイヌや琉球人,あるいは高いところに押しやられた,飛騨や紀伊,陸奥の山林民族(マタギ・山窩の世界)ともいわれる。
弥生人は騎馬(牧畜・酪農まで)・海洋(漁労から航海まで)・農耕(畑作から稲作まで)と大きく三つの分野で民族形成してきたものとして,大陸から朝鮮半島経由のものを主体に,中国南部稲作地帯から,あるいは南方諸島から黒潮にのって,あるいは北方の樺太方面から南下して,流入してきたと考えられる。
農耕民族:
日本の基幹を占める農耕民族。畑作型・稲作型・養蚕型へと展開。
一般に離島の人たちは海に囲まれているので漁業などに強いと思われているが,既に述べた甑島での経験のように,島のごく一部の集落を除いては,漁業はおろか,船に乗っただけでも酔ってしまうほど海に弱い人たちが多い場合がある。こういう人たちも,こと農業となると,険しい山に天まで登る棚田をつくって生産性をあげてきている。このことは,この島の人たちが本来的には農耕民族であって,たまたま流れついたと考えれば納得がいく。とくに中国に近い側でもあり,その関係にも注目する必要があろう。
*農耕民族の種類
農耕民族にはいくつかのタイプがある。
まず,麦などをつくる平原対応の畑作型である。焼畑農業から進んできた稲作よりも古い段階のもので,古代からのエジプトやインドなど大人口を支える民族,ヨーロッパの三大民族ではスラブ民族がそれに該当するだろう。
つぎに,日本の農耕民族の主たる部分を占める稲作型で,低湿地の氾濫原を本拠地とするものである。日本の稲作民族は呉太伯の伝説に見られるように中国の揚子江下流域から渡来した人達が中核をなしている(ちなみに呉越同舟という故事にあるようにその昔中国でライバルとみなされていた二つの民族のひとつが呉すなわち日本であり,もうひとつが越すなわちベトナムである。ベトナムがアジアの将来にとって期待されるのもなるほどと思われる)。日本国内でも佐賀平野,濃尾平野,関東平野などの低湿地帯は相互に似た環境や住民で,とくに濃尾平野では江や蘇など中国の揚子江下流域の文字を使った地名が多い。
さらに養蚕民族(台地や山地の農耕民族)とでも言うべき特殊なグループがあり,第二部で詳述されることになるが,日本においてとくに重要な役割をしている。この民族の源流は言うまでも無く始皇帝の秦の国すなわち秦(はた)氏,つまり機織りを仕事とする一派である。その後山東省から新羅を経て日本海側から日本に入って来た。琵琶湖の南岸に佐々木神社というのがあるが,そこには佐々木という姓をもつすべての人達の家系が収められている。滋賀県の語も新羅からと思われ,天智天皇の都が置かれたのもその関係だろう。佐々木氏だけでなく姓にササのつく人達のルーツは新羅(シルラ)であり,山東省の地名をそのまま頂く山東氏ともども養蚕民族として共通する特性を有している。つけくわえれば新羅に由来する信楽,信貴山などは新羅の文化を今に伝える地である。養蚕民族はその流動が騎馬民族と重なる部分が多く,馬頭観音の分布とも重なり,騎馬民族的な性格も持つ。徳川家康の三河の国がまさにそうであり,隣の尾張の国と比べるとよく分かる。養蚕民族はまたカイコとそのマユ,さらにキヌという白いものが生活の中心を占めており,白はまさに神聖な色である(白の民族)。新羅(シラギ)は国名そのものに白をいれ,その名残か朝鮮半島では今も白い衣裳が儀式上重要でそれが日本にも影響している(自動車まで白一色なのは世界的に見ると奇異な感じがする)。この白に対する特別な意識の具体化したもののひとつが白山信仰であり,もうひとつがオシラサマである。両者はほぼ一体となって北陸地方から東北地方に展開し,その到達点が下北半島の恐山である(文字はそれこそ恐ろしげだがオソレという音はオシラから展開したものであろう。実際恐山の山頂一帯は硫黄によって白一色の風景になっている)。
*農耕民族の特徴
土地に定着し,季節に従って手順を踏み,毎年繰り返すというような農業の特徴がそのまま民族の特性になっている。すなわち手順をいとわず細かいことを積み重ねていくことが得意な一方,新しいことや変化には弱い。世界最大の農耕民族国家である中国では漢字という複雑な文字を使い,膨大な史書を残し,刺繍や象牙細工に気の遠くなるような細かさの積み重ねが見られる。
農耕民族の国は,人々が土地に密着して生活しているため,地続きで領土を拡大し,それを守ることには熱心であるが,遠く離れたところに植民地を持って支配することはない。海外に出てもそこで自分たちの世界を別に作ってしまう。こういったことも中国が典型的であるが,ヨーロッパの三大民族ではスラブ民族がまさに農耕系であり,領土を拡大しようとする意識はロシア人にとくに強いようである。西ヨーロッパではフランスが例外的に農耕民族であり,その他エジプトやインドなど連綿と続く極めて長い歴史を持ちながらほとんど変化していないように見える国もある。
海洋民族:
原点としての縄文人の漁労につながる漁業型から,商業型(沿岸貿易),さらに航海型(大洋,貿易,軍事)へ展開,
中間段階では,九州北部から朝鮮半島南部多島海を拠点として多島海国家をつくった漢の奴の国が代表的,世界でみるとエーゲ海文明や東南アジア島嶼部のマレー人国家が特化している。さらに,商業的,軍事的なものを持ったものとして日本では平氏が代表,世界では,スペイン,ポルトガルからイギリスなど,海洋国家といわれる国々,そういった国家をつくれなと海賊的なものに展開。
*奴の国の展開
奴の国から現代につながる長崎県=福岡からアクセスする壱岐+対馬が長崎県に属することも奴の国の末裔であることを示す=唐津半島名護屋も。"なが~"という地名の,はじめの「な」は,かっての奴の国を表し,次の「が」は「か」と同じで所属を示す「の」であり,あるいは「すみか」,「どこか」など場所を示す。
唐突と思われるが,長野は陸封された海洋民族の県なのである。つまり,奴の国の人達が住む野である。全国の海岸部に長崎や長島(別に長い形を表しているのではない),中野や中村(これも真ん中を示すものではない)があること,名古屋もそのひとつであることなどに思い至る。そしてこれらの姓を持つ人達には海洋民族の血の流れている確度が高い。念のため加えれば地名や名字の漢字の多くは古くから日本語(やまとことば)で言われてきたコトバへの当て字である。
長野県には長野市のすぐ近くに中野市があるほか,広い範囲を示す安曇野という地名は海そのもののこと(ワタツミに同じ)であるが,海洋民族の文化が伝統的に保たれている極めつけが諏訪大社の御柱祭である。諏訪神社の元祖はそれこそ典型的な海洋民族の地である長崎である(五島列島ばかりでなく,壱岐,対馬まで長崎県であることを知ればなるほどと思われる)。長がつく両者はまさに兄弟県なのである。御柱祭を見たことのある人ならすぐに想像がつくと思うが,太い丸太に沢山の氏子が跨がって斜面を滑りおり,諏訪湖に飛込む様は船の進水式そのものである。陸封された海洋民族の海へのノスタルジアが結晶した迫力あるものである。
"ナカ"系展開ルート=名古屋市(熱田神宮・中村区+中川区)>岐阜県那珂+中津川>長野県南木曽>諏訪周辺(中洲+中沢+長門)>長野市周辺(長久保+長和)>中野市>新潟県長岡市周辺(中沢+中山+中野+中之島+中条+中ノ口川)。全国郡名"那珂"など"ナカ"系多い・中村市など都市名も。那珂湊から那珂川を遡った先の栃木県も,長野県と同様陸封された海洋民族の県で,騎馬民族の群馬県とは対照的である。(別添地図参照)
またまた唐突と思われるが,サッカー日本代表のなかでも有力な選手にはナカ・ナガ系多い=中山から長友まで(サッカー協会長沼健氏も)=その他,中田2人+中村3人+中沢2人+中山2人+中西,平瀬・平山(新人平井)・三浦2人など海洋系が多い。ヨーロッパでサッカーが強い(とくにFW)のはその出先でもある南米を含めて,海洋民族のラテン系である。DFは体格に優れる騎馬民族(体格に劣る日本人には不得意),日本人の多民族性がMFを量産している理由なのかもしれない(露骨に言うと問題かもしれないが,とくに南米では貧しく学歴のない若者の出世の場であって,本能がそのままFWの力になっているのに対し,日本は学歴高く知的な能力の求められるMFに適しているともいえる)。もちろん,自らの弟との違いの大きさやメンデルの法則で述べたように,"ナカ"系の苗字だからサッカーに向いていると決めることはできないが,その苗字の家系にはサッカーに向いた海洋民族の遺伝が出現する確率が高いということは否定できないだろう。なお,野球のように分業システム型スポーツは監督・選手とも騎馬民族向きといえよう。
*平氏については,
五島列島の平田氏,先述した甑島の漁業集落の平良など平の字のつく氏名,地名には平氏の血を引くものが多い。この端的な例が富山県の平家の落人部落といわれる五箇山であり,平村,上平村などそのまま地名になっている(ついでに言えば熊本の五箇庄,宮崎の五ヶ瀬なども一族を示す地名と思われる)。平家の落人部落のようなものが大きなスケールでできているのが長野県であると考えれば良い。
五箇山,五箇庄ほか平家の落人部落(平村のように地名そのものに表れているところも多い)は山に閉じ込められた海洋民族がどういう文化を創り出すかという点で格好の答えになっている。これら落人部落では木を用いて大きな船を作ってきた技術により合掌造りという建築を産み出した(実は一族郎党が一緒に暮らす大家族制そのものが海洋民族の特徴でもある)。ついでに言えば,日本の大工さんの主な出身地は瀬戸内海や三陸海岸などであり,船を作ってきた技術が活かされている。実際,海洋民族にとっては,動的な海で受ける力のかかり方に比べれば,静的な建築の組み立てなどたやすいことであろう。このことを裏付けるように,上棟式で屋根に祭られる神様は船の神様なのである。海草を採って食してきた生活は多様な山菜料理を,その他川魚を始め,山椒魚,昆虫などの食べ方にも表れる(海の産物に準じ,獣類を食することは少ない)。歌謡曲(港の歌が多い),芸能人(福岡や長崎)。ヤクザもルーツは海賊倭寇であり,現代も中国の偽物や北朝鮮麻薬と暴力団がつながっている。
陸封された海洋民族の長野県をみると,佐久の鯉,各地のソバ,山菜,アリやハチノコなど平家の落人部落に共通する食文化が広がっていること,観光において先進地であるのは単に地理的に大都市の間にあるというだけではなく,常に外の世界と付きあってきた海洋民族の開かれた意識の役割も大きいのではないだろうか。
*海洋民族の特徴
海洋民族はまさに海が生活の場である。代表的な海洋民族であるマレー人の国マレーシアなど海上1000kmも離れた二つの島で一つの国になっている。インドネシアやフィリピンなど無数の島々が一つの国家になっているのも驚異である(既に述べたように日本でも,奴の国の核であった典型的な海洋民族の県である長崎県は海上遠く離れた壱岐,対馬も含め,多数の島々からなっている)。ヨーロッパではエーゲ海(現在は海を跨がる国が無い=ギリシャ,トルコが騎馬系のため)やアドリア海,さらに地中海全体に渡って国家が形成されたことは歴史に見るとおりである。
ヨーロッパの三大民族のうちラテン民族が海洋系である。現在の国としてはスペイン,ポルトガルが代表的であり,この二国は海を支配するという特技を活かしてラテンアメリカに植民地を創ったが,海洋民族の性格がイギリスとは異なる結果を招いた。
海洋民族の性格は海での漁からつくられている。明日は豊漁か不漁か全く予測のつかないことから,計画的でなくなる一方,漁れる時にはやたらに水揚げのあることからお祭り好きになった。また,漁は皆が力を合わせなくてはできないこと,それも天候次第で一斉に動く必要のあることなどから,集まって住み(漁業集落の密度を見よ),公私の境目が不分明になるところがある。ついでに言えば船を漕ぐということに適するよう胴が長めである(いわゆるストライド)。念のため加えると農耕民族の胴の長さは植物繊維を消化するための腸が長くなることによる。
時代の流れの上でいえば,海洋民族は次の時代を開く前に,時代を破壊する役割をしている。公家政権から武家政権に移る時代では,平氏がその役割を担い,明治維新では長州がそうであった。織田信長も自らの言う通り平氏であれば,それに全く相応しい。
また海洋民族は激情的で,これが良くでると感性に訴えるもの,芸術の天才や一流のデザインを産み出し,歌や踊りも盛んで優れたものになる。イタリアやスペインを挙げるだけで充分であると思うが,インドネシア(とくにバリ島)の?や日本の演歌でも大部分が港町のものであることなど海洋民族としての共通性が感じられる。これが逆にでるとやや残酷なものになる。スペインには今も闘牛が残り,ラテンアメリカに行った植民当初のスペイン人の行動は本国からのコントロールがきかず,インディオに対し残虐な殺戮を行った。最近の例でその特性が良く見えたのは東欧解放の時であった。各国が次々と解放されて行く中で,唯一ラテン系の国ルーマニア(ローマ人の末裔であることを示す国名)では解放が実現した途端,前の支配者チャウシェスクを射殺してしまったのである。
騎馬民族:
原点としての狩猟民族から牧畜型(食肉・酪農・牧羊・・・),軍事型(モンゴルや源氏,ゲルマン)へ
*騎馬民族の再発見
繰り返しになるが,源氏にも落人部落がある(平家のように人を惹きつける魅力的な文化を創って来なかったため知られないでいるが)。長野県の東端部の川上村は近年まで落葉松だけの貧しい村であったが,レタス栽培を始めてから一躍大産地になった。現在では村の中を大型の保冷車が走り廻っている。こういった村の歴史がそのまま騎馬民族の特徴を表している。騎馬民族には獣を取る以外には海洋民族のように山の幸を活用する術がなく,また農耕民族のように土地を耕すこともできなかったのである。ところが一度マニュアル化された技術が導入されると,今度はシステマティックに一面に展開することができるのである。同じ農業をやっていても農耕民族の肌理の細かい土地利用とは全く違ったものである。
山梨県の一面の葡萄畑を見ると騎馬民族の農業がどんなものであるかを感じさせる(次いでで,また非難するようで申し訳ないが,豊でない食文化や長野とは違う掠奪型に近い観光のあり方なども騎馬民族の特徴であろう)。世界に目を向けると,典型的な騎馬民族の農業国はアメリカでその特徴が極めて強く表れている。最も地についた農耕民族の農業は中国に見られ,土地を肌理細かく利用して多様なものを産出し,10億を超える民を飢えさせないできた。
なお川上村ではツケモノも無かったそうであるが,これも民族の違いであり,日本人ならすべてツケモノが好きであるというような認識を改めることの必要性を示す。これに関して,天皇家にもツケモノの習慣がなかったこと,聖徳太子の誕生にまつわる伝説とキリストのそれとがほぼ同じであり,奈良時代には牛乳を扱う役所があって,酪(今でいうヨーグルト)を盛んに食べていたことなども思い起す必要がある。維新時に三井の番頭として近代化を果たした三野村利左衛門は騎馬民族の出身らしく,私の会ったその末裔の人はツケモノどころか味噌汁も全くダメであった。
*騎馬民族の特徴
騎馬民族の最も原初的な姿は中央アジアの草原を駆回るモンゴル人やかってのトルコ人,そしてヨーロッパの三大民族のうちのゲルマン人などに求められる。馬に騎乗することから短躯・軽量であり(現在でも競馬の騎手の条件),陸地における行動範囲は極めて広く,戦において掠奪を尽くす一方,地についた生活が不得意のため,領土を支配するにあたっては先住民の文化を尊重するなどの特徴がある。
言うなれば細かいことは不得意だが大局を掴むことが得意なので,世界の国々の支配層には騎馬民族が多い。日本の天皇家の騎馬民族王朝説を始め,典型的な農耕民族の国である中国でも,随,唐から元,清まで歴史の大半は騎馬民族の王朝である(漢と明が農耕民族の国家)。ついでに言えば中国では国土を大人口の農耕民族が肌理細かく耕し,自らの食料を確保してきているため,支配層は治水と潅漑のほか,国民が安心して暮らせるように管理することがすべてであり,国民のあり方と関係の無いところで支配層が交替してきた。そういう意味では現在の共産党政権も過去にみられた王朝のひとつであるとも言えよう。ヨーロッパにおいて各国の王朝がその国民と関係なく血縁ネットワークを作り上げてきたのもこれに類するものであろう。
騎馬民族は,世界中にどんどん広がって行こうとする傾向があり,かっての元ばかりでなく,海洋化した騎馬民族であるバイキングは世界中の海に進出し,ゲルマンの一派であるアングロサクソンによってアメリカという国が創られ,いまや宇宙にまで進出しようとしている。そして支配が得意はあるが自らの文化を持たず,支配地域の農耕民族に同化されていく(隋・唐をはじめ清に至るまで中国の支配者は大部分騎馬民族,ロシアもスウェーデンからのルスにより建国された。イングランド人は支配の天才(意の分野)であるが,イギリスの科学者は(知の分野)スコットランド人が,芸術(情の分野)はアイルランド人が主である)。
念のため触れておくと,アイスランドに進出したノルウェイ人や,なぜグリーンランドがデンマーク領になっているのも,騎馬民族が海洋化したものである。なお,現在のデンマーク人のほとんどは,騎馬民族が高度に農耕民族化したもとと言える。実際,デンマーク人の闘争性はすっかり失われ,冬季オリンピックはまさにゲルマン民族のためにあるというほど,諸国のメダル獲得数が多いなか,デンマークが今までにとったメダルがたった一つと聞いて,驚愕した覚えがある。
騎馬民族はまた,一旦事あれば集まって統率のとれた行動をするが,普段は群れて暮らしておらず独立の気概が強い(悪くいえば一匹狼的でバラバラである)。何度もでてきているアメリカや鹿児島がその端的な例である。そして騎馬民族のする農業は土壌保全もせず,一面同じな大規模農業になる。かっての植民地のプランテーション,現代のアメリカの農業などを見れば明らかだ(大体植民地を広げるのは騎馬か海洋であり,遠方から経営をするのは騎馬の方がうまい。海洋民族の大植民地ラテンアメリカを見よ)。
さらに時代の流れの上では騎馬民族は細かいことを積み上げるのが不得意なため安定期には向かないが,海洋民族の破壊した前時代の後を統一し,新たな時代を構築するのが得意であり,源頼朝が鎌倉幕府を開き,徳川家康が江戸幕府を開いたのが,そうである。
騎馬民族がもう少し土地に定着し,牛や羊を飼うようになったのが牧畜民族である。牧畜の歴史もすでに長きに亘っており,騎馬民族の遺伝子を受けた者にはその食生活の名残が生きている。つまり肉類,牛乳類などが好きであり,マトンなどの獣臭さや動物性油脂の脂っこさに抵抗が無い。
網野嘉彦の天皇と被差別民等との関係について>騎馬民族が一方では天皇とその周辺の支配の象徴とされるようになり,他方では肉を扱う民として最下層になっていったと考えれば良く分かる
自らの民族性の見分け方
自らの民族の遺伝子を知るには食べ物で見るのが手っ取り早い。環境や躾によって何でも食べるようになり,新鮮なもの,普段と違うものをおいしく感じることが多いので気が付きにくいが,生のものを大量に出された時に記憶が呼び覚まされる。結論を言えば,肉のケモノクササが平気でいくらでも食べられるのが騎馬民族(ジンギスカン料理などで気が付く),魚のナマクササに強いのが海洋民族(海岸の民宿などで),野菜のアオクササをおいしく感じるのが農耕民族である。南九州は全体に騎馬民族が多いが,日本史上有名な隼人族はかなり古い段階で中央アジアから渡ってきたダッタン人の末裔といわれており,魚よりもラードのようなものを好むひとが多いのを見るとなるほどとおもわれる。なお鹿児島の南にトカラ列島という島々があるが,この不思議な地名も中央アジアのトカラ国からきているそうで,先に述べたように現実の風土とそこに住んでいる民族とが一致していない例は多い。
さらにかっての原住の地の風土がもたらす一連の食べ物の組合わせも好き嫌いとなって表れることが多い。騎馬民族の発祥の地の風土は北方の内陸部であり,ミカンよりもリンゴ,コーヒーよりも紅茶,醸造酒(ワインなど)よりも蒸留酒(ウィスキーなど)を好む。日本で南方にある鹿児島,宮崎が他と全く異なる焼酎文化であるのもこのためであろう。
@民族型を基本に,血液型・気質型を組み合わせから見た人間社会
(血液型による性格判断もそれなりの傾向があることは事実であるがそれによって断定してしまったり差別につながったりするため'科学的根拠が無い'とされている(かっての自民党大物政治家ほかO型多かった・田中角栄はB型で特有だり切り開くタイプであるとともに危険視された・最近の国会議員はA型多く,仲良しクラブになるのも頷ける)=血液型進化の話(ナチスやオウムの話・ヨーロッパはA型多い・日本はアジアでは特異的にA型多い=農耕民族多いことと相まって,伝統にこだわる保守性が強く,新しいものへの挑戦を避ける。
さらに言えば,少なくとも血液型(A・B・O)と民族型(農耕・海洋・騎馬)さらには気質型(分裂・躁鬱・癲癇)の三つの複合によって判断すべきである。先取りすれば漢民族は農耕民族であるがB型多いため株などへ集中しかっては麻雀禁止)>性格,特性,自らに出現している民族を知るには=食べ物(普段おいしいと思うのとは別に特定のものを大量に出された場合に分かる)=適性>農耕民族は血液型でのAに近く,気質型では癲癇に近い・海洋民族はB型・躁鬱気質に近い・騎馬民族はO型・分裂気質に近い=単純な組み合わせ数で3の三乗の27タイプになるが民族・血液・気質とも似た型の組み合わせでは際立って強く表れ,相反する組み合わせではケースバイケースになったりする
血液型(進化順):O=意的>B=情的(刹那的)>A=知的(過去にこだわる)
民族型(進化順):騎馬=意的(未来指向)>海洋=情的(現在指向)>農耕=知的(過去指向)
血液型の発現史
人類の血液型が,O型,B型,A型,AB型の順に発現してきたことは,世界における分布からも証明されると思われる。とすれば,それぞれの血液型に,発現した当時の人類の姿が刻み込まれているとしても不思議ではない。
そういった観点でみれば,O型は,人類が,家族単位で狩猟採集していた時代に対応,まだ社会的組織のない,それぞれが個人的な時代に形成されたため,福間進「"血液型と性格"の基礎理論」で,彼が指摘するように,O型の人間は,一人でいることが好きな,自由平等な個人主義的政治を指向することになる。この段階では,家族のなかの成年男子が動物を狩猟していたことから,個人的に調査したり計画したりする能力を磨かざるを得ないこともあって,O型は,のちに登場する騎馬民族型との親和性が高いということにもなる。
B型は,人類が,大きな獲物をとるべく,集団的に狩猟あるいは漁労をするようになった時代に対応,いわゆるボス的リーダーが必要になり,それが,福間のいうように,力の論理,最高指導者が目標になるといった政治指向になるのであろう。他方,大きな獲物は偶然に左右されることが多く,非計画的になってしまうが,力を合わせるべく歌を唄い,とれた時には大歓声をあげるお祭り型の人間になるといったことから,B型が,のちに登場する海洋民族型との親和性が高いということにもなる。ヨーロッパのラテン系のように,例えは悪いが,ヤクザなど徒党を組むタイプであり,熱しやすくさめやすい,行動が過激で独裁者も出やすいが,芸術などで天才的な力を発揮することが多い。
そして,人類が農耕・牧畜の時代に入るとともに登場したのがA型で,いうまでもなく,集団的かつ計画的に,力を合わせて取り組み,大きな施設も必要になってくることから,いわゆる国家に対応,福間のいうように,相互に協調することが全てで,勝手な行動は許されない,周囲の人間のことばかりが気になる,言い方は悪いが,全体主義的な指向をもち,まさに農耕民族そのものといえよう。ヨーロッパの大陸部はA型が飛びぬけて多く,たしかに,全体主義的傾向が強いが,縁辺のイギリスにはO型が多く,彼らが,世界を支配する自由で民主的な制度を生み出したのである。人種差別の著しかったナチスは,血液型でもA型に限ろうとしたほどだったことを思えば,英独の対決は,まさに,血液型集団の戦いでもあったといえよう。それゆえ,ヨーロッパをはじめ,世界が,血液型をタブー視するに至ったのである。
AB型は,B型,A型のハイブリッドとして登場したもので,それぞれの,長所のみが強く出現すると傑出した人間になることから,その人口に比して,歴史的に著名な人物が多いのも頷ける。
新型コロナウィルスの世界的流行のなかで,各国,地域による感染率や重症化率などに大きな差があることから,さまざまな説が唱えられているが,そのなかで,科学的データに基づくものとして,血液型について,O型が感染しにくく,A型が感染しやすいという研究結果が出たが,もともとO型は病気全般に強く(セキリなどお腹にくるものは弱いという),A型は弱い,とくに感染症に弱いということが指摘されている。
上述のような歴史をみれば,個人的に狩猟・採集していたO型には,何かに当たれば,その個人・家族が消えるだけで,きわめて多様な免疫が獲得され,社会も形成されていないため,感染という現象も無かったといえる。その反対に,農耕・牧畜社会を形成したA型の人たちは,感染が広がりやすかったのはもちろんであるが,それで獲得した免疫も一様であったため,異なる感染源がでてくると,対応できないともいえよう。とくに,新型コロナウィルスのように,動物由来のものということになると,狩猟・採集でそれらも口にしていたと思われるO型と,まったく口にすることの無くなったA型には,大きな差があっても不思議ではない。
輸血するにあたって,血液型の最初にあったO型は,他の血液型全てにできるのに対し,O型が輸血を受ける時や,他の血液型の人が輸血するには,同じ血液型でなければならないということも考えさせられるところである。
現在の日本での都道府県別の血液型分布を調査した資料をみてみると,O型トップは北海道,2位が沖縄県,その他,千葉県,福井県が多く,世界における分布と同様,最も古いO型が縁辺部に押しやられてきたとみられる。アイヌ等,縄文人の血が残っている度合いが高いことによるのはもちろんであり,東北地方全般も多めである。
福岡県,徳島県をはじめ,西日本全般にA型が多いのは,弥生人が大陸から新しく流入してきたことを示すことはもちろんであるが,佐賀県ではB型が多くなっているのは,まさに,末盧国が中国南部からきた呉の国の民族によってできたという説を裏付けるものであろう。長野県が,周辺と異なり,B型が際立って多いことも,日本史のなかで,大和朝廷に最後まで抵抗したのが,現在の長野県の地域であったこと,おそらく,大和朝廷を開いた民族より前に,日本を支配していた民族(出雲族?)が,彼らによって,押しやられた最後の砦だったのではなかろうか。
静岡・愛知・三重の東海三県は,A型がかなり少なく,土着民族が多かったことを示しているが,戦国武将が多く輩出し,安土桃山文化のように,特異な時代があったことにも対応するであろう。
東北地方諸県もB型が多いが,これも世界全体と同じく,O型のあとからやってきて,その後,A型におしやられた民族であるとみられる。呉の国の民族より前に,中国方面から流入した民族であろう。
ワダツミ族の代表安曇氏(関東農政局ホームページより)
安曇野(あずみの)を拓いたという安曇氏の起源は非常に古く,古事記には安曇族の祖先神は「綿津見命(わだつみのみこと)」とその子の「穂高見命(ほたかみのみこと)」であると書かれています。旧穂高町は安曇族の祖先神を地名としていることになります。
彼らの分布は,北九州,鳥取,大阪,京都,滋賀,愛知,岐阜,群馬,長野と広範囲にわたっており,「アツミ」や「アズミ」の地名を残しています。その北限が安曇野ということになります。
博多湾(はかたわん)の志賀島(しかのしま)には海神を祀った志賀海神社(しかうみじんじゃ)が現存し,全国の綿津見神社(わたつみじんじゃ)の総本宮となっており,安曇氏の発祥地とされています。神職は今も阿曇氏が受け継いでいます。
彼らはすぐれた航海術と稲作技術を持ち,古代の海人族の中でも最も有力な氏族でした。連(むらじ)という高い身分を大和朝廷から受け,中国や朝鮮にもたびたび渡っていたとも言われており,663年の白村江(はくすきのえ)の戦いでは,安曇比羅夫(あずみのひらふ)が大軍を率いて朝鮮にわたり,陣頭指揮にあたっています。また,788年には宮中の食事を司る長官奉膳(ぶんぜ)の地位についていることからも,安曇氏は大和朝廷を支えた有力氏族であったことがうかがえます。
彼らがなぜこんな北の山国へ来て住み着いたのか,またどんなルートでたどり着いたのかよく分かっていませんが,おそらくは蝦夷(えぞ)の征伐が目的であり,ルートとしては,
北九州から日本海→姫川谷(青木湖から糸魚川に流れる川)から来たという北陸道説
北九州から瀬戸内海・大阪(安曇江)経由の東山道説
北九州から瀬戸内海→渥美半島(安曇族の開拓地)→天竜川を上った天竜川筋説
などがありますが,定かではありません。
安曇野へは4~5世紀に入ったという説もあります。その時代によりここを開拓した理由も異なってくるはずですが,今となっては謎のままです。しかし,安曇野という地名,あるいは穂高神社(ほたかじんじゃ)の存在だけでも大きな文化財を残したとも言えるでしょう。
熊野神社の分布,三陸方面への展開
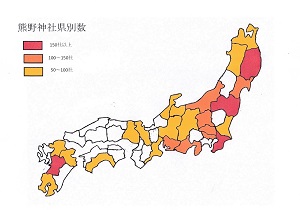
現地の友人から聞いた話では,新宮には現在も歌われている漁民の歌の詞は,古代ヘブライ語でしか解釈できないもので,また,熊野新宮からは鈴木氏を代表に漁民が三陸海岸に渡って技術等を伝えているが,その代表地気仙沼の言葉もケセン語といわれるくらい一般の日本語と異なっていて,やはり古代ヘブライ語に繋がるらしい。崎谷満氏の研究では,HTLV-1のキャリア分布を詳しく見ると,長崎を中心に九州一帯から南海道にかけて高い値であるが,紀伊半島から遠く離れた気仙沼でも高い値を示すことが注目され,ナカ系・クマ系の展開や,熊野と気仙沼には近い民族の人が多いということになろう。
さらに,熊野の鈴木氏が「ナカ」系と同じような役割をしてきたことに触れておきたい。鈴木氏のルーツは表向き物部氏稲穂からきているとされるが,ツングースにしろ稲作にしろ熊野の地に全く合っていない。多分,熊野水軍ということに本質があり,サカナの鱸の文字も当てられるように,東シナ海から対馬海流にのる「ナカ」系とは別の黒潮本流の海洋民族と思われ,熊野周辺の漁師の唄,「尾鷲節」「伊勢音頭」「崎浜大漁唄込」などに古代ヘブライ語がそのまま残されているということにも驚嘆するが,当地の海洋民族がユダヤ人の徐福一族から新たな技術を教えられ,漁獲などに大きな成果が上がるようになったことを感謝するべく,歌詞になっているのではないかと思われる。その後,「ナカ」系と同じようにユダヤ人を太平洋岸の北の方に案内していったと考えられ,その象徴的なものとして,気仙沼が鈴木氏由来であり,ここにケセン語という特殊な言語があることが指摘できる。否定疑問文に対する「はい・いいえ」の応答形式が標準語とは反対になる点などは基本的に日本語とは別系列なものと思わせる。気仙沼の少し北には,例の吉里吉里人の話があるが,吉野ヶ里を思い起こさせる表記である。さらに,2011年の三陸大津波の後の国際救援活動のひとつとして,南三陸町にイスラエルの医療団が来たことが話題になったが,実は南三陸にユダヤ系が多いという伝承から,遺伝子を調べるための材料集めが目的だったともいわれる。ずっと北に行くと,最近原発で名が知られるようになった東通村があり,この村の国の無形文化財の能舞は熊野から伝えられたといわれ,毎年正月には熊野に能舞を奉納している。能楽者のルーツが秦氏であると聞けば,これまた謎は解決する。おそらく,昔からキリストが日本に来たという証拠として盛んに出て来る青森県の戸来岳(ヘライはヘブライの約まったもの)も,鈴木氏によるユダヤ人の案内によるものではないか。また,この戸来岳はじめ,日光の二荒山,串木野の冠嶽,新潟の弥彦山など,ユダヤに関わるらしい聖なる山が皆,三つの峰を持つ同じような形をしていることも気になるところである。近代に入って,東北地方にキリスト教が広がっていったのも,素地があったからではないかなど,色々考えさせられる。
さらに,熊野鈴木氏は古代インドのガンジス川下流域にあった滅亡したマガダ王国から渡来したといわれ,その王国が鉄鉱石を核に水運と森林資源で繁栄していたと聞けば,熊野そのものであることからさもありなんと思われる。そして,マガダ王国が紀元前に滅亡したことから,いわゆる黒潮族とともに渡来したと考えられる。西暦718年,鈴木氏は崇神東征後,代々紀伊国支配をまかされた紀伊国造の紀忍勝とともに,多賀城に向かい,気仙沼に大漁唄込を伝えたが,その中の囃子詞に古代ヘブライ語が使われていること,紀忍勝の名に「オシ」が含まれ,さらに,その何代か前は紀忍,すこし後に紀忍穂がいることを見れば,今まで述べてきたように,半分ユダヤ系となった紀伊国造であったことまで判明,前述のことが裏付けられる。
ナカ系・マツ系民族の展開
ナカ系民族の展開:サッカーの日本代表クラスの選手には,ナカ系苗字が多い。
全国のナカ系地名の分布図を見ると,県名,旧国名,旧郡名はじめ,いかにナカ系地名が多いか分かる。かつて奴国のあった福岡から長崎にかけてナカ系地名が多いのは当然で,いわゆる長州もその延長であるが,太平洋側を見ると,宮崎県,次いで徳島県,その向かい側の和歌山県に那珂郡があり,ずっと北に上がって,茨城県那珂郡には那珂湊から那珂川を遡ってナカ系地名が多く,実際,栃木県北部から福島県にかけて海洋系といわれる渡辺姓が非常に多い。信濃川の方を見ると,最上流部から山を越えて中津川に出,木曽川を下って名古屋に至る,日本海と太平洋を結ぶ幹線ルートが形成されていたことが伺える。そしてこの海洋民族によるルート開発の上にのって,徐福一族をルーツとするユダヤ系の人たち移動や物部氏の潜行が行われたと考えれば,さまざまな話の辻褄が合ってくる。
飛躍するようであるが,人名としてのナカ系も同じで,サッカーの日本代表クラスの選手に,二人の中田,二人の中村,中沢や中西,現在イタリアで活躍する長友など,ナカ系苗字の多いことにも気がつけば,これは海洋民族の血筋だということで,世界でみてもスペインやイタリア,南米などラテン系すなわち海洋系の得意とする競技と言える。ついでにいえば,日本人が多民族によってつくられてきたことから,オリンピックなどで,イタリアほどではないにしても,多様な競技に日本人選手が出場してそれなりに活躍し,それが日本人のオリンピック好きにもつながっている。もう一つ,日本では商品開発が難しい,あるいは日本で売れれば世界で売れるというのも,多様な民族の指向の反映か。
魏志倭人伝の頃には奴国は随分小さくなっているようであるが,このように全国展開しているのを見れば当然とも言えよう。ついでに,邪馬台国周辺を見ると,今でもその名の独立した島としてすぐ分かる対馬,壱岐は別にして,末盧国は松浦のことと言われ,江戸時代の平戸藩主松浦静山が有名であるが,末盧国からも「ナカ」系と同じように「マツ」系の人名を思い出してみると,プロ野球でトップクラスになった選手には何人もの松井や松阪,松田,松中など実に多いことに気づく。伊都国は糸島半島が対応するというのも自然であり,不弥国が筑豊周辺らしい他は良く分からないようだ。
マツ系民族の展開:プロ野球の強い選手には,マツ系が多い。
魏志倭人伝の末ら国,現在の長崎県北半から佐賀県北半を占める松浦地方をルーツとする。
既述したように,奴の国をルーツとするナカ系民族が大陸との間を往来するような船舶型海洋民族であるのに対し,沿岸で貝類などを採取する漁撈型海洋民族。
中臣氏のルーツで天皇家に従うことになるナカ族の圧力により,いわゆる神武東征以前に東方に展開,各地に松字のつく有力な地名が見られる。現在の長崎県から福岡県に広く展開する奴の国に囲まれるように孤立して残ったのが,魏志倭人伝の末ら国。松尾の姓は佐賀県を筆頭に,長崎県,福岡県に非常に多く,マツ族を代表する氏族になっている。
北ルートでは島根県松江周辺を拠点とし,南ルートでは愛媛県松山から香川県高松を経(備中松山もその一環),両ルートから近畿に入ってヤマト国以前の出雲国を形成(国つ神),その名残として,京都に松尾神社。天皇家の東征に対して国譲り,その結果,出雲大社の建設と引き換えに,松江周辺の出雲国に閉じ込められ,特別な存在となる。
国譲り以前に,近畿から三重県松阪周辺に展開(的矢湾も),伊賀松尾氏からは松尾芭蕉が出ているが,実家は料理人であり,現在の長崎県出身の松尾氏が有名レストラン"シェ松尾"を営んでいるのにも通じる(海洋民族はグルメ)。愛知県経由で,静岡県浜松周辺に展開,天竜川を遡って,諏訪湖に至り,長野県全体に展開するが,既述のように,後に,新潟県方面からナカ系民族が展開してきたため,松本市を中心とする安曇野側に押し込められてしまった。現代でも,全体が海洋民族といわれる長野県が東西で大分性格が異なるといわれている所以である。長野市に松代があり,群馬県側の松井田や新潟県側にもマツ系地名が残る。
浜松から太平洋沿いに行けば,伊豆の長八を生みだした松崎があり(海洋民族は芸術家),神奈川県の松田,さらには千葉県松戸市を中心にマツ系地名の集積がみられる。
京都に戻って,今度は北陸方面を見ると,石川県に松任市があり,その近くからは,ヤンキースで活躍した松井秀樹選手が出ている。念のためであるが,小松は本来,高麗(コマ)の津(ツ),すなわち朝鮮半島との往来の港であったこと示す地名で,当て字であり,マツ系とは関係が無い。既述のように,サッカーの有力選手にはナカ系の苗字が多いが,野球では,松井稼頭央選手,松阪投手,ソフトバンクの松中選手,松田選手というように,マツ系の苗字が多いことに気づく。長野県のところで述べたように,同じ海洋民族ながら,微妙な違いのあることも分かる。
そして,藤井耕一郎「サルタヒコの謎を解く」で指摘されているように,マツ系民族の分布は,発掘された銅鐸の分布と極めて良く重なっている。銅鐸が忽然と消えてしまったのは,その祭祀権が,つまりサルタヒコが消されたことに相通ずると思われるが,地中からまとまって発見されることから,意図的に隠したのではないかとされることについては,マツ系民族がまた貝塚をつくる民族であることから,毎年特定の場所で,その都度,銅鐸を埋めることが祭祀のあり方だったと思えば,それほど不思議ではない。さらに,銅鐸の生産地が九州北部であることから,マツ系民族が末ら国をルーツに展開したことも,納得できよう。
ナカ系・マツ系苗字の分布
別冊歴史読本「日本の苗字ベスト10000」(発行は2001年)により,歴史的由来の全く異なる北海道と沖縄は除き,各都府県で99位以内のナカ系苗字の都府県別上位リストを作成してみると,次表のようになる。ナカ系苗字密度を{苗字数×100-順位の計}として計算すると,その結果は下図のようになる。ちなみに,全国での99位以内のナカ系苗字は,"中村"が8位,"中島"が28位,"中川"が49位,"中野"が50位,"中山"が58位となっており,中・長・永・那珂などで始まるナカ系の姓は全部で310姓もある。
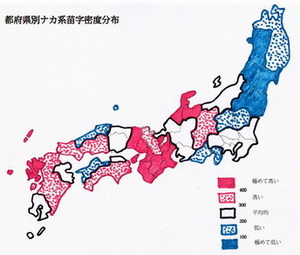
ナカ系苗字密度の分布図から,特徴として,次のようなことが指摘できる。
1:中部以西に多く,関東以北は少ない。東西日本の違いをつくっている原因の一つ。
2:当然ながら,ルーツたる奴(ナ)の国の長崎県まわりが極めて高い。
3:近畿一帯が極めて高いのは,ナカ系民族がヤマトを支える主要民族の一つだったことを示す(天皇に従った中臣氏の東征)。
4:東征の途中の中四国が高いのも当然であるが,そのなかで,出雲の地島根県と大山祇の支配する愛媛県が低く,ナカ系民族の入りにくい地であったことが分かる(従って山陽と南海ルートが主体だったと思われる)。
5:石川県と富山県に多いことは,コシの国が近畿と強い関係にあったことを示す(朝鮮との交流=小松は高麗の津)。
6:コシの国を経由する北回りで終着地長野県に入ったことを示す。
7:さらに東を見れば,太平洋側はやはり(三島神社)大山祇の支配する静岡県を超えて関東に,日本海側は新潟県に至ったことが分かる。
同様に作成したマツ系苗字の都府県別分布は下図のようになる。また,全国では,48位に"松田",91位に"松井",95位に"松尾"が登場するだけであるが,松で始まるものを主にマツ系は全体で94姓ある。
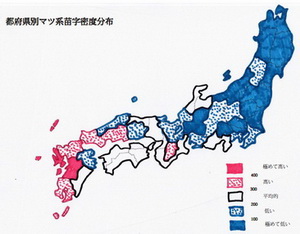
マツ系苗字密度の分布図から,その特徴を挙げれば次のようになる。
1:近畿を境に,西が高く,東が低い。とくに関東以北は極めて低くなっている。
2:当然ながら,ルーツたる末盧国の長崎県周りが極めて高く,遠ざかるに連れて低くなるが,なかでも,出雲の地島根県,吉備の地岡山県,そして後述のオホ族の地大分県が低くなっているのに対し,大和の地奈良県が飛び地のように高くなっていることから,やはり,天皇権力との関わりをめざして東征したものと考えられる。
3:ナカ系ではとくに高かったコシの地(石川県と富山県)は,マツ系でも滋賀県周りや岐阜県を飛び越して,平均的な値を示しているのも,ルーツが近いことに関係しているとみられる。
4:愛媛県や静岡県でも平均的な値になっていることから,後述のオホ系との関係は,ナカ系のそれよりは良好であったようだ。
5:また中部以北の極めて低い地域のなかで,山あいの長野県・群馬県が,太平洋岸の神奈川県・千葉県が相対的に高くなっているのも,地名分布との関係で頷けるところであろう。
6:地名分布との関係で言えば,河内が東西を結節する拠点であったとみられ,松原の周辺には応神・仁徳天皇陵はじめ,巨大古墳が集中しており,海神を祀る住吉大社も存在している。堺が早くから商業都市として自立し,江戸時代以降,大坂が商業の中心になっていくのにも関係があろう。
以上のように,ナカ系とマツ系が東に広がっていったことが,現代日本語の基盤が西海語になっていることの理由でもあり,両者がともにそれ以上進まなかった東北地方の言葉がかなり異なるとともに,いまだに差別されている原因にもなっていると考えられる。
同じ海洋民族ながら,ナカ系とマツ系は大きく異なっていた。ナカ系が,奴の国がルーツであるように,大陸との間を自由に往来していた航海型民族で,いわゆる倭寇の主体にもなり,平氏という武士にもなっていった(厳島神社の祭神は宗像神社と同じ)のに対し,末盧国をルーツとするマツ系はおそらく沿岸漁業型民族で統制がとられ,それが天皇家の支配に従わない民族でもあっといわれている原因とも考えられる。中国江南の呉の国から日本列島に流入した民族との類似性にも注目したい。現在のスポーツ選手を見ると,チームメンバーが自由に連携して動くサッカーにナカ系が多く,管理のもとに選手が分業して動く野球にマツ系が多いことが面白い。
さらに,「新撰姓氏録」に印されている海洋系氏族の三分類についてみると,宗像氏はタケミナカタと同じでナカ系に対応,安曇氏は長野県松本周辺が安曇野であるようにマツ系に対応,大和氏とされているのは,おそらく,愛媛県と静岡県に代表される大山祇神に対応する民族で,オホ族(多氏)とも考えられる。多氏は伊余(与)国造であったし,大山祇神社は大三島にあり,周辺には大のつく地名が多く,極めつけは大洲であり,西向かいは大分である。瀬戸内海賊の代表で,大山祇を氏神とする越智氏のルーツが良く分かっていないこと,静岡県の伊豆には(大)三島神社があり,伊都国が伊豆につながっているという話にも関係あると思われる。神奈川県の大山も本来は大山祇神社であり,太平洋側の入り口が大磯で,伊豆大島も大きい島という意味ではなくオホ島である。また,大山祇神は別名和多志大神で,まさにワタツミすなわち海そのものを指し,渡辺氏のルーツでも
あると思われ,後述するように,渡辺氏がナカ系・マツ系に押される形で関東以北に展開したこと,
桓武平氏の出身とされる千葉氏(源頼朝に従った千葉常胤)も多氏の出といわれることなどから,ナカ系出の平氏に支配されるも反発した民族であることも伺われる。
東北地方に偏って存在する苗字
なお,別冊歴史読本「日本の苗字ベスト10000」によって,分布図を作成してみると,ナカ系・マツ系とは逆に東北地方に偏って存在する苗字として,以下のようなものが挙げられる(別添図参照)。全国1位の"佐藤",2位の"鈴木",3位の"高橋"はじめ,全国有数の姓が東北地方に偏って多くなっていることを,まず指摘しておきたい。
まず,ナカ系・マツ系のような海洋民族について,
1:渡辺姓 (全国5位) 海すなわちワタツミそのものを表す苗字で,瀬戸内海東端の摂津周辺を本拠としていたとされ(住吉三神はワタツミ三神に対応,その中心が摂津一宮の住吉大社),ナカ系・マツ系の東征によって,関東以北に押し出されていったと思われる。
2:鈴木姓 (全国2位)よく知られているように,和歌山県熊野の神官をルーツとする苗字 で,黒潮にのって,静岡県からさらに東北地方の太平洋岸に展開したもので,やはり,ナカ系・マツ系の東征によって押し出されたと思われる。気仙沼との強い関係はもちろん,能舞が下北半島にまで展開していることにも関わっている。
3:高橋姓 (全国3位) 代々,日本料理の神膳部氏族であったが,同僚の安曇氏すなわちマツ系と衝突したため,東北地方に展開したと思われる。
4:三浦姓 苗字の表す通り,神奈川県三浦半島を本拠とし,桓武平氏の出と(全国45位) 僭称していたが,源頼朝の決起に従い,奥州藤原氏征伐に参加したことから,宮城県以北に展開したと思われる。
それ以外については,
1:阿部姓(全国23位) 陸奥北部の古来からの豪族安東氏をルーツとしていることから当然多いが,西日本で徳島・愛媛・大分が相対的に多いのは,坂上田村麻呂の蝦夷征伐に際し俘囚として連れてこられたからで,安倍首相もその末裔といわれる(安部・安陪なども同じ)。
2:佐藤姓 (全国1位) 藤原秀郷の子孫といわれる奥州藤原氏をルーツとしており,秀郷が左衛門尉であったことから,佐藤になったともいわれる。
3:斎藤姓 全国16位) 藤原利仁の子孫といわれ,中部日本が本拠地であったらしい。奥(州藤原氏とは全く別なことは,宮城県・岩手県の周囲の県で多くなっていることからも明らかであろう。なお,美濃をルーツとする遠藤姓も多く,まさに都から遠い藤原氏ということだろう。
4:佐々木姓(全国13位) 近江(滋賀県)に佐々木神社があって,全国の佐々木氏全ての系図が納められているといわれる。騎馬民族をベースに養蚕民族化した新羅系をルーツとし,白山信仰から東北地方のオシラサマ(蚕)へと展開したと思われる。
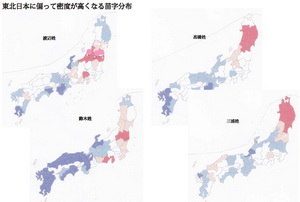
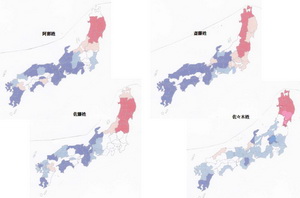
参考:諏訪神社の分布
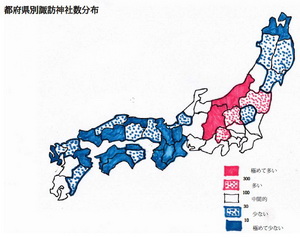
酒に強酒いか弱いか(都道府県別の図)
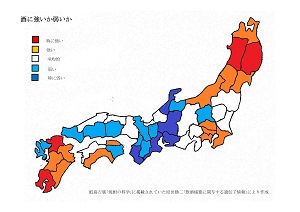
萩原秀三郎「稲と鳥と太陽の道」からの知見
吉野ヶ里遺跡の調査から,紀元前1世紀頃,それまでの集落がいきなり廃絶され,新たに登場した首長の墓と見られるものが,中国の高度な技法によって築造されていることが判明したようで,まさに徐福一族の登場を思わせます。また,祭祀空間と見られる巨大な高床の建物が建っていましたが,後述しますように,大和を平定した応神朝の秦氏が,出雲族のために建設して贈った出雲大社の原型とも考えられます。
弥生時代の遺跡から鳥形木器が夥しく出土しますが,鳥霊信仰は中国南部の楚から流入し,墓を造ると,そこに柱を立ててその天辺に鳥形彫刻を載せていたらしく,これが鳥居のルーツということです(現在でも朝鮮半島には豊穣・安全・子孫繁栄祈願のために,同様の風習が残ります)。吉野ヶ里遺跡の復元に際して,入口に雲南省のものを参考にした鳥の門が造られていますが,神社の鳥居は,神殿を建てることで,単なる柱から太陽を迎える門に移行したもので,神社に必ず鎮守の杜があるのも,鳥に棲み処を提供するためのものと考えられています。また,太陽信仰では,空を飛ぶ鳥が太陽に近い生き物であるということで,鳥が止まる樹を大事にする風習もありましたが,一層鳥居に近いものだったと思います。日の出を告げる鳥としてニワトリが重視されるようにもなりました。ついでながら,鹿島神宮(タケミカヅチ)が東面,諏訪大社(タケミナカタ)が南面,そして出雲大社(オオクニヌシ)が西面し,ほぼ北緯36度付近に東西に並んでいるのは,太陽の通り道を示すものではないかと考えられています。
八咫烏の話は,古代の天の鳥舟に対応するもので,船の舳先に止まった鳥が水先案内を務めるという伝承(実際,鳥が船に飛来することは,陸地の近いことを示すものです)と,太陽と一体である鳥という太陽信仰が重なったものでしょう。従来シャーマニズムは北方(ツングース)系とされてきましたが,それが中国の殷に伝播し,さらに南方稲作民族に広がって,太陽信仰とつながるシャーマニズムに変化,それが稲作民族の渡来とともに日本に伝わったといえます。巫女はまさに太陽の昇降を司祭する者でした。中村修也「秦氏とカモ氏」でも,八咫烏を鳥文化の象徴として,中国南部(東南アジア,鳥居のルーツにもつながる)出身民族,すなわち,前述の,大和の地先住民族たるマツ系が,東征してきた神武(といわれている)天皇を受け入れたことを示すものとして捉えています。
日本の稲作の起源は長江流域から山東半島さらに朝鮮半島南西部を経て流入しましたが,まさに徐福渡来ルートそのものです。日本はまたモチ文化圏であることから,ミャオ族との関係が深いと考えられますが,ミャオ族の家屋はチガヤ葺きで鰹木・千木を頂き,日本の高千穂民家に伝わり,神社の基本様式として採用されるに至りました。さらに,日本では大陸と違って,稲作が先に登場し畑作が後になったということからも,まさに稲作民族が主体ということになりますが,焼畑を示す"畑(田+火)"が,その他の畑を示す"畠(田+白)"が,それぞれ国産の漢字として作られたことからも明らかです。
「吉野ヶ里」こそ邪馬台国の都(1989年記)
邪馬台国の位置を特定する材料としては,いうまでもなく魏志倭人伝であり,そこに記載されていることを出来る限り素直に読むこととする。少なくとも,末盧国・伊都国・奴国については,ほとんどの人に意見の違いは無く,現存地名から見ても特定されていると考えて良い。今の博多付近とみられる奴国の次の不弥国から問題になるわけであるが,倭人伝では不弥国までは里数で示してあり,方位についての誤差(磁石があったわけではないので,日の出の方向が基準になったと思われるが,東は冬至に近ければ南東に偏り,夏至に近ければ北東に偏って,その差は45度以上にもなる)を含めて,不弥国はおおむね現在の宗像一帯と考えるのが自然である。不弥国から先は里数でなく日数で表されている。これは単純に次の国(都)までの到達時間を示しており,途中の抵抗が多ければ当然日数もかかるのであって,距離とは無関係である。また,邪馬台国近畿説の不合理は,不弥国と次の投馬国の間に全く国のようなものが存在しなかったようであり,当時の航海技術から見れば,穏やかな瀬戸内海を通ったであろうし,そこにはかなりの人口集積もあったと考えるのが自然である。そこで,次のような考え方をしてみる。
まず,諸国の間に対立のあったことは倭人伝そのものに記載されており,例えばのちの大宰府のあたりは,その役割からも判断できるように防備上の要衝であって,両側の国の対立が厳しく通れなかったと考えられる。不弥国まで円滑に行けたのは,強大であった奴国を中心に他が属国のような存在になっていたと考えれば良い。地図を見て頂くと分かるが,対馬・壱岐を介して朝鮮半島と日本を結ぶ軸線と並行して,博多の沖には小呂島と能古島(あわせてオノコロ島)が,宗像神社の中津宮と沖津宮の配置があり,このことは半島を介して大陸から渡ってきた人たちが対馬・壱岐ををミニサイズで転写するとともに,望郷のしるしとして位置づけたものと看做すことができる。さて,次の投馬国へは遠賀川ルートで南行したが,当時はおそらく一面の湿地帯すなわち豊葦原で,その間を縫いながら様々な抵抗にあったり,睡眠をとり,流れも遡る向きだったこともあって20日もかかってようやく都についたのであろう。その都は今の飯塚市王塚古墳周辺だったのではなかろうか。その後,水行10日,陸行1ケ月かかって邪馬台国の都に行くわけであるが,その方向はおおむね南ということで,水陸の順に特に意味はなく,全体としてそれだけかかったということであろう。おそらく道なき山越えをし,筑後川の上流に出て,やはり豊葦原を水行して邪馬台国の都に出たのである。そして,吉野ヶ里遺跡の示すところが,まさに倭人伝が記したところであった。
ここで「史記」に書かれた徐福の話を思い起こして頂きたい。わが国の多くの場所にいわゆる徐福伝説があるが,そのうち史記の記載にある徐福が定住した平原広沢に一致するのは佐賀県諸富町だけであって,吉野ヶ里のすぐ近くである。徐福は一族を率いて大船団でわが国にやってきたが,最近判明したところでは,始皇帝の支配をのがれるために亡命してきたのであって,わが国に上陸後も大陸からの追及を逃れるために心を砕いたといわれる。このことから徐福一族は先進的な技術などによって最も強大な国すなわち邪馬台国の建設に寄与しただろうということ,同時に大陸に対して厳重な防備の体制を敷いたであろうことが想定される。以上,倭人伝の各国を特定したわけであるが,結果的に見ると,各国の戸数すなわち人口規模がその地理的受容力と極めて良く辻褄が合い,このことも本説を支える根拠となろう。そして,不弥国までの大陸とむすびついた海洋系諸国と大陸から離れたい農耕系諸国の間には大きな緊張があり,それぞれの雄の奴国と邪馬台国が大宰府という要衝を挟んで対峙していたと考えられる。さらに,大陸に対して恐怖感を抱いていた邪馬台国が動乱を機に。さらに逃れるべく近畿の地へ移ったのである。その東征伝説を裏付けるのが,近畿における吉野の里の役割であり,笠置山・三輪山などの配置の北九州と近畿の一致である。これらの山は邪馬台国にとって重要な目印として特別な意味を持たされ,近畿の地にその想い出として地形を活かして転写されたのである。
卑弥呼の倭迹迹日百襲姫命説の妥当性について
「日本書紀」で孝霊天皇の皇女とされ,大和における最初の巨大前方後円墳の箸墓古墳の埋葬者ともみなされます,倭迹迹日百襲姫が,卑弥呼ではないかという説が強まっていますが,以下に述べる様々な理由から,妥当であると思われます。だからといいましても,邪馬台国と大和にあり,その女王といわれる卑弥呼が大和にいたということにはならないことも,認めなくてはならないでしょう。
倭迹迹日百襲姫命が孝霊天皇の皇女とされてますから,崇神天皇にとっては,孝元天皇の同じ祖父母の代にあたりますが,「魏志倭人伝」によりますと,卑弥呼の没後,倭国は大乱に陥ったとあり,このことが,邪馬台国そのものの消滅,その支配者が,現在の大和の地に東征してしまったことを示すものでして,神武東征が,実は,崇神東征であったことにそのまま対応するものです。倭迹迹日百襲姫命は,巫女的な人物で,大物主を呼び出すことができたといわれ,大物主は大国主命の別名といわれますから,国譲り問題に対応できたということでしょう。
邪馬台国は徐福の末裔によってつくられた国で,中国には,神武天皇が徐福であったという説すらあります。第2代綏靖天皇から第9代開化天皇までは,「日本書紀」に,事績等に関する記述がないため,欠史八代と呼ばれますが,おそらく,徐福・神武天皇に対応する九州北部の邪馬台国時代を埋めるべく創出された天皇たちで,倭迹迹日百襲姫命が,実際に天皇の位置,つまり女王であったと考えられます。そして,「日本書紀」の系譜に従えば,女王を支えていたといわれる弟は,吉備津彦命ということになり,おそらく,徐福とともに渡来した物部氏の出で,一足早く東征して,吉備の国を開いたとみて良いでしょう。なお,崇神天皇の前が,開化天皇という名になっていますのは,「大和」の地を(文明)開化することに思え,意味深長です。
倭迹迹日百襲姫は,「古事記」では,「夜麻登登母母曽毘売(やまととももそびめ)」と表記されていますことから,「やまととびももそひめ」と読み下されますが,「やまと」は,邪馬台国を指し,大和の祖であることを強調するためでしょう。「ととび」は「鳥飛」の意とされますが,まさに,鳥が飛んできたように,大和の地におりたった,つまり,東征してきた崇神天皇によって,新たな王朝が登場したことに対応するとみられます。近年,纒向遺跡の発掘が進み,なぜ,このような巨大で複合的な施設が忽然と登場したのかについての議論がさかんですが,崇神東征によって,邪馬台国での宮殿をそのまま再現したとみれば,納得できます。邪馬台国が畿内にあったという説が止まないのは,東征があまりに短期間になされたため,同時代のものとみられるためでしょう。
そして,大和において,飛鳥の地が特別になりましたのは,「ととび」の地であったからとも見えます。「もも」が百を表すことに異存はありませんが,「そ」の漢字に「襲」という文字を当てていますのは,世襲という語にみられますように,代々継いできたことを意味していまして,徐福から百代(単に長い間を意味し,実際は,もっと少ないと思われます)ということなのでしょう。巨大な前方後円墳の嚆矢として,箸墓古墳が忽然と登場したことも同様で,これが,宮内庁が認定していますように,倭迹迹日百襲姫命の墓だとしますと,大和に王朝を開いた崇神天皇が,敬うべき先祖として,新たに埋葬し直したということも考えられるのです。卑弥呼の墓は,「魏志倭人伝」の記述から,前方後円墳ではないとみられていまして,平原遺跡など,北部九州にいくつか可能性が指摘されています。
ところで,「日本書紀」の系譜のなかで,「やまと」がつく,もう一人の重要人物に日本武尊(やまとたけるのみこと)がいまして,応神天皇の祖父になっています。卑弥呼没後,長年の敵であった狗奴国が一気に伸長,邪馬台国があったことで,連合的に安定していた北部諸国もバラバラになり,倭国は大乱に陥ったといいます。卑弥呼の後を継いだ,臺與(台与=とよ)という女性は,東に逃げて,豊の国を開いたとみられます。その大乱を平定したのが,熊襲伝説のある日本武尊とみて良いのではないでしょうか。狗奴国が熊襲であり,名に「やまと」がつくことで,邪馬台国を正統的に継ぐ位置にある人物であったようで,これらの結果,後述するように,応神天皇が新羅から渡来(母が神功皇后とされることで説明できます)し,豊の国をてこに東征,崇神王朝と半ば平和的に交替し,新たな王朝になったということでしょう。
巨大古墳について
今年(2020年),吉川弘文館から出版された国立歴史民俗博物館編の「日本の古墳はなぜ巨大なのか~古代モニュメントの比較考古学」は,その副題が示しますように,世界各地に残る巨大墳墓を数多く紹介・詳説した極めて興味深いものです。本題の日本の古墳については,第2部として,最後の四分の一を割いているだけですが,現在のところ最新の知見と思われますので,そのうちの,清家章「古墳時代における王墓の巨大化と終焉」,福永伸哉「古代日本の古墳築造と社会関係」に従って補足してみたいと思います。
3世紀中頃,突然のように,それまでの古墳とは隔絶するような巨大な箸墓古墳が登場しまして,以後,急速に,全国各地に前方後円墳が築造されるようになりましたから,この時に,新たな王朝が始まったのではないかとみるのが自然でしょう。その年代からみまして,埋葬者は卑弥呼で,ここに邪馬台国があったという説も強く主張されているようですが,卑弥呼の死去後,内乱となり,弟王が継いだとされる話からしまして,すでに述べましたように,その弟王こそ,東征して大和王朝を開いた崇神天皇ではなかったかと思われます。のちに,神武東征伝説となりますが,崇神が神武と同じハツクニシラススメラミコトの名をもつことから,実は,崇神東征であったということだろうと思われます。
この箸墓古墳を第一波として,以後2回,王墓の巨大化の波が訪れます。2回目の波は,数代後の5世紀末から4世紀にかけて,大和ではなく,河内に,応神天皇陵とされるものを含む古市古墳群,和泉に,仁徳天皇陵とされるものを含む百舌鳥古墳群と,まさに,世界最大級の王墓が多数建設された時代で,謎の4世紀,倭の五王に対応,五王の特定には諸説ありますが,応神王朝に対応することはいうまでもありません。五王の最後の武が雄略天皇であることは学界でも一致しているようで,この雄略天皇陵とされるもの以降は急速に小型化していきます。
6世紀半ば,継体天皇陵とみなされている摂津の今成塚から,巨大化の第三波が訪れ,宣化天皇陵の可能性の高い河内の大塚山の後,欽明天皇陵節が有力な大和の見瀬丸山を最後に,巨大王墓は終焉を迎えます。天皇の跡継ぎがいなくなって断絶しそうになった時,応神天皇の末裔として迎えらた継体天皇の陵は,大和に受け入れられず,摂津という遠隔地にされましたが,その後,宣化天皇で河内に,欽明天皇は大和になったように,継体王朝が定着,その後は巨大墳墓が全く見られなくなるのは,権力が確立した証左でしょうか。
掲載されている畿内における大型古墳変遷図をみますと,第二波の応神朝,和泉・河内に政権があった時代,大和ののちの平城京の北側の佐紀にも,粒のそろった巨大古墳群がありまして,これを,大和に残る別の王朝とみる説もあるようですが,神功皇后陵とされるものが含まれますように,有力な皇后の墳墓群とも考えられ,すでに述べたことからしますと,オシ系の血を温存,継体天皇を迎える際に,皇后に,オシ系を配して正当化を図ったことにつながるのではないかとも思われます。
王墓を示す巨大墳墓はいわゆる前方後円墳で,それ以前は,大多数が方形周溝墓という,いわゆる氏族の墓でした。大和における箸墓古墳の登場はあまりに突然でしたが,両者の間を埋めるものとして,岡山県楯築墳丘墓が注目されています。弥生時代としては異例の規模で,形態的にも前方後円墳につながるものでして,所在地から見ましても,総社の吉備古墳群に近く,吉備氏につながるものと考えられます。すでに述べましたように,徐福の末裔が神武天皇で,吉備氏は徐福とともに来日した物部氏の末裔とみられますので,箸墓古墳へのつながりも当然ではないでしょうか。弥生時代終末期の代表例になっていますホケノ山墳墓も,箸墓古墳に近いですから,崇神朝との関係,その露払いの役割をした者の墳墓と思われます。
弥生墳丘墓と古墳つまり前方後円墳の間には,規模にとどまらず,精美さや構造の複雑さ,副葬品の豊富さなど,不連続な飛躍がみられるという指摘も,ほぼ突然,大和に王朝が出現したこと,つまり,東征説を裏付けるものといえるでしょう。その直後には,全国的に前方後円墳が一斉に出現しますが,大和朝廷との関係を示し,その支配が確立したことも示すもので,ここでも,物部氏の役割が想定できます。また,いわゆる仁徳陵を筆頭に,応神朝の墳墓が一段と巨大になるのは,応神天皇とともに渡来した徐福につながるユダヤ系の秦氏によると考えられます。そして,歴史的存在が明確になる推古天皇の代には巨大古墳が消滅していることは,まさに支配が確立した故,権威を示すような墓が不要になったといえるでしょう。創造をたくましくすれば,推古天皇を擁立した蘇我氏,その後,天皇を擁立し続ける藤原氏にとっては,天皇そのものの権力を見せつけたくなかったからかもしれません。
いわゆる仁徳天皇陵が世界最大というのは,地表を覆っている面積の大きさで,日本では,権威は遠くから見える立体的な巨大さではなく,平面的にどれだけ占めているかということでした。古墳の巨大さばかり言われますが,その後の,東大寺と大仏,近年の新幹線,明石大橋,青函トンエルほか土木建造物など,日本には,一時的なものも含めて,世界一の規模の建造物は多数あります。大仏の造営を司ったのは,秦氏と同族の佐伯今毛人であり,満濃池を造った空海も佐伯氏であったことから,これらの技術が秦氏の子孫に依存すること,さらに明治維新後の土木の権威の一人物部長穂が,その名のとおり,物部氏の末裔であることなどから,古墳以来,現代まで,巨大なものの築造は,物部氏の末裔たちの力があったからと考えることができるでしょう。
世界の墳丘墓を参照した時,日本の古墳によく似たケースとして挙げられるのが秦の始皇帝陵ということですから,始皇帝の家臣だった徐福が物部氏らを従えて来日,始皇帝の語と,ハツクニシラススメラミコトの語が同じということなども合わせて,大和朝廷の始まりには,始皇帝の記憶が刻み込まれていると考えても不思議ではないでしょう。
参考文献
NHKスペシャル「日本人はるかな旅1,2,3,4」,
沖浦和光「渡来の民と日本文化―歴史の古層から現代を見る」
中野美代子「日本海ものがたり~世界地図からの旅」
崎谷満「DNAでたどる日本人10万年の旅―多様なヒト・言語・文化はどこから来たのか?」「DNA・考古・言語の学際研究が示す新・日本列島史―日本人集団・日本語の成立史」,「ヒト癌ウィルスと日本人のDNA」,
篠田謙一「日本人になった祖先たち DNAから解明するその多元的構造」,
斎藤成也「核DNA解析でたどる 日本人の源流」,
梅原猛・埴原和郎対談「アイヌは原日本人か」,
西岡秀雄「日本人の源流をさぐる-民族移動をうながす気候変動」,
松本克己「世界言語のなかの日本語―日本語系統論の新たな地平」,
李炳銑「日本古代地名の研究~日韓古地名の源流と比較」,竹竹村公太郎「日本史の謎は"地形"で解ける」「日本史の謎は"地形"で解ける【文明・文化篇】」,
倉史人「土偶を読む―130年間解かれなかった縄文神話の謎」,
松田薫「"血液型と性格"の社会史-血液型人類学の起源と展開)」,
福間進「"血液型と性格"の基礎理論」,
八切止夫「日本原住民史」,
菊池俊彦「オホーツクの古代史」,
正木晃「宗像大社・古代祭祀の原風景」,
戸矢学「諏訪の神 封印された縄文の血祭り」,
宮元健次「善光寺の謎」,
関裕二「信濃が語る古代氏族と天皇 善光寺と諏訪大社の謎」,「神社が語る古代12氏族の正体」,「物部氏の正体」,「藤原氏の正体」,「蘇我氏の正体」,
川原裕子「スサノヲと枌の謎解き」,
岡本雅享「出雲を原郷とする人たち」,
藤岡謙二郎編「日本歴史地理総説1総論・先原史編」「2古代編」,
森浩一編「日本の古代1倭人の登場」「2列島の地域文化」「3海をこえての交流」,
米山俊直「日本人ことはじめ物語」,
下村巳六「熊野の伝承と謎」,
澤村経夫「熊野の謎と伝説」,
ネリー・ナウマン「久米歌と久米」,
宮本徳蔵「力士漂泊-相撲のアルケオロジー」,
網野善彦・宮田登・上野千鶴子「日本王権論」,
藤井耕一郎「サルタヒコの謎を解く」,
宮内則雄「新説 日本人の苗字とその起源―縄文人・弥生人のあだ名としての苗字」,
石井好「忘れられた上代の都"伊都国日向の宮"」,
西谷正編「伊都国の研究」,
上田篤「呪術がつくった国 日本」,
羅其湘・飯野孝宥「弥生の虹桟・徐福」
エドヴァルド・ルトヴェラゼ「考古学が語るシルクロード史」,
レイモンド・P・シェインドリン「ユダヤ人の歴史」,
坂東誠「古代日本、ユダヤ人渡来伝説」,
ヨセフ アイデルバーグ「日本書紀と日本語のユダヤ起源」,
飛鳥昭雄「失われたイエスの12使徒"八咫烏"の謎」,
渡辺紀彦「代官川崎平右衛門の事績」,
山本殖生「熊野 八咫烏」,
日高正晴「西都原古代文化を探る~東アジアの観点から」,
飛鳥昭雄「失われた徐福のユダヤ人"物部氏"の謎」,
西條勉「"古事記"神話の謎を解く~かくされた裏面」,
戸部民夫「日本の神様の"家系図"」,
大野七三「日本国始め 饒速日大神の東遷」,
内倉武久「卑弥呼と神武が明かす古代―日本誕生の真実」,
倉塚曄子「古代の女―神話と権力の淵から」,
長田夏樹「新稿・邪馬台国の言語~弥生語の復元」,
萩原秀三郎「稲と鳥と太陽の道―日本文化の原点を追う」,
菊池秀夫「邪馬台国と狗奴国と鉄」,
田中勝也「日本原住民と神武東征-失われた"クマビト"の歴史」,
井上宏生「謎とき伊勢神宮-神々と天皇と日本人のDNA-」,
澤田洋太郎「天皇家と卑弥呼の系図―日本古代史の完全復元」,
松原弘宣「熟田津と古代伊予国」,
宝賀寿男「尾張氏」,
山田安彦「古代の方位信仰と地域計画」,
小和田泰経「朝鮮三国志 高句麗・百済・新羅の300年戦争」,
朝鮮文化社編「日本文化と朝鮮(第1集)」「日本文化と朝鮮(第2集)」,
荒野泰典・石井正敏・村井章介編「アジアのなかの日本史1アジアと日本」,
鈴木武樹編江上波夫ほか「(論集)騎馬民族征服王朝説」,
江上波夫・金達寿・李進煕・上原和「倭から日本へ」,
谷有二「日本山岳伝承の謎-山名にさぐる朝鮮ルーツと金属文化」,
松木武彦「日本の古墳はなぜ巨大なのか: 古代モニュメントの比較考古学」,
大塚初重「古代天皇陵の謎を追う」,
若狭徹「東国から読み解く古墳時代」,
大分県宇佐風土記の丘歴史民俗資料館図録「八幡大菩薩の世界」,
三橋健「日本書紀に秘められた古社寺の謎─神話と歴史が紡ぐ古代日本の舞台裏」,
逵日出典「八幡神と神仏習合」,
徳丸一守「卑弥呼と21世紀をつなぐ宇佐神宮―神仏習合の神示」,
出羽弘明「新羅神と日本古代史」,
中村修也「秦氏とカモ氏―平安京以前の京都」,
宝賀寿男「秦氏・漢氏―渡来系の二大雄族」,
水谷千秋「謎の渡来人 秦氏」,
前田速夫「海を渡った白山信仰」,
武光誠「蘇我氏の古代史―謎の一族はなぜ滅びたのか」,
水谷千秋「継体天皇と朝鮮半島の謎」,
藤井輝久「新・騎馬民族征服王朝説―奈良朝は新羅占領軍の政権 平安朝は百済の亡命政権」,
石井良助「略説 日本国家史」,
水野祐「日本古代の民族と国家」,
武光誠「蘇我氏の古代史―謎の一族はなぜ滅びたのか」,
中塚明編「古都論―日本史上の奈良」,
藤巻一保「役小角読本」,
新野直吉「田村麻呂と阿弖流為-古代国家と東北」
奥富敬之「天皇家と源氏: 臣籍降下の皇族たち」,
野口実「伝説の将軍藤原秀郷」,
桜井哲夫「一遍と時衆の謎 時宗史を読み解く」,
田中健夫「倭寇―海の歴史」,
吉成直樹「琉球王国は誰がつくったのか 倭寇と交易の時代」,
伊藤幸司編「室町戦国日本の覇者 大内氏の世界をさぐる」,
鷹橋忍「水軍の活躍がわかる本」,
海老沢有道「日本キリシタン史」,
木村一信編「国際堺学を学ぶ人のために」,
ロックリー・トーマス「信長と弥助 本能寺を生き延びた黒人侍」,
岩生成一「南洋日本町の研究」,
(論文)吉本道雅「中国先秦史の研究」,
(論文)林伯原・周佩芳「古代中国における武士及び武士階層に関する研究~日中比較の視点を含めて~」,
大室幹雄「園林都市~中世中国の世界像」,
佐藤健一「江戸のミリオンセラー『塵劫記』の魅力―吉田光由の発想」,
藤田覚「光格天皇:自身を後にし天下万民を先とし」,
第Ⅰ講:統治変遷のプロセス
いわゆる天皇制によって,世界史の上では異常な,一つの王朝が続く日本であるが,その統治の変遷をみると,実に,複雑な道を歩んできた。
簡単にいえばと,日本列島が,世界地理上の位置から,多様な民族が渡来しながら,出て行くことは極めて少ないために,世界有数の多民族の国になり,狭い国土故,混血も進んで,いわゆる日本人という互いに似た姿になっているのである。仮に,世界中の人々が混血すると,顕性遺伝(かつて優性遺伝といわれた)によって,皆,今の日本人のようになってしまうそうだ。
しかし,良く知られているメンデルの法則によって,混血というのは,完全に混ざり合うのではなく,受け継いだ遺伝子のいずれかが,一定の確率で発現するのであり,いわゆる騎馬民族,海洋民族,農耕民族といった大枠で分けただけでも,それぞれの人物に,いずれかの特徴が強くみられることになる。とくに,特徴が強く現れる男系の遺伝子は,代々発現する確率も高く,民族を反映した姓の人たちには,その民族の特徴を表す人物が多く現れるといって良いだろう。
ノーベル賞の受賞者の多いこと,最近の,大谷祥平はじめ,様々なスポーツ,建築,美術,音楽など,ほとんどあらゆる分野で,世界一流といわれるような人物が登場するのは,このように,様々な民族が混ざり合い,そのいずれかの特化した遺伝子が発現していると考えるのが自然だろう。
国土の面積に比して,多種大量に渡来した民族が,互いに抗争することなく生活して行くために,統合のシンボルとして天皇というものを考えだし,その天皇を擁立する形で実権を振るう支配層(平安時代の藤原氏公家から鎌倉時代以降の将軍武家,維新後の官僚)が,自らの権力が隅々にまで及ぼすような仕組みをつくりだし,それが,いわゆる天皇制であり,そのことがどのようになされてきたのか,「古事記」「日本書紀」の,いわゆる日本神話にも何かしらの真実が隠されていることを前提に,さまざまな事実も踏まえつつ,年代を追って,少しずつ暴いて行くのが,本講義の趣旨である。
最近知られるようになったことであるが,日本が,世界的に見ても豊かな国に属するにもかかわらず,日本人は,将来を不安に思う人,自分を不幸だと思う人が際立って多いのは,その原因が,人を落ち着かせるセロトニンの分泌が非常に少なくなるように進化したことによっており,そのように,進化したのが,水田稲作という手間と時間のかかる農業に対して,台風その他の自然災害の多く,それに対応すべく,いつも不安に思うようになったらしい。そうであれば,天皇制というのは,国民の不安を和らげる精神的な装置として,極めて有効なものであり,そのことによって続いていると考えても良いだろう。
ところで,日本人に限らず世界各地でのDNA分析によるルーツを探るにあたっては,前提とすべき大きな問題があると思われる。というのは,支配する側の民族は,日本の場合でも,天皇家にしろ,公家にしろ,大名にしろ,いずれも支配される側から女性を娶って,大量の子孫を残すことに努めてきたからで,現在の日本人のDNAを分析すれば,かなり支配側の民族のものに偏っているはずであり,以下に述べる統治の変遷に纏わる民族との関係を明らかにするようなDNA分析を期待したい。
本来ならば,本文を読み終えてからにしたいところではあるが,自分には,どんな民族的遺伝子の特性が現れているかを,知りたい人のために,とりあえず,まとめてあるものを,コラムに紹介しておく。本文を読みながらでも,参照したり,思い出して貰うのが良いだろう。⇒コラム「遺伝適性を知るための民族ルーツ論」
序論:統治が始まる以前の状態~いわゆる縄文時代
----第1話:最古層の日本人~氷河期に形成された環太平洋民族の核
----第2話:いわゆる縄文文化を担った北方アジア民族の南下~環日本海民族の形成
----第3話:海洋民族ワダツミ族の形成と,縄文人最後の砦となった信濃
第1論:いわゆる弥生人の渡来で統治(国)が始まる~九州北部の小国家群
----第1話:照葉樹林帯の民族クメール人による狗奴国(クマ系)
----第2話:黄海から渡来した航海民族による奴の国(ナカ系)
----第3話:中国春秋時代の呉人によって形成された末盧国(マツ系)
第2論:九州北部小国家群を支配した二つの強国~伊都国と邪馬台国
----第1話:大陸からの認知を受け,諸国連合の王を務めた伊都国(アマ系に支えられたイト系)
----第2話:小国家群から大和国家への契機となる,秦帝国からの徐福の渡来(オシ系)
----第3話:徐福(の子孫)によって,アマ系戴くオシ系の邪馬台国が建国される~神武皇統
第3論:オシ系の神武(実は崇神)東征による大和国家形成~崇神皇統
----第1話:徐福に従って渡来した技術者集団物部氏の東進(フヨ系)
----第2話:オシ系と別れて東進し,大和国家の支配に微妙に関わることになる海部・尾張氏(アマ系)
----第3話:アマ系と別れたオシ系の神武(実は崇神)東征によって大和朝廷が始まる
第4論:新羅から渡来した秦氏の長による応神皇統~古墳時代
----第1話:日本に影響を及ぼす朝鮮半島の三国時代
----第2話:秦帝国からの繋がりによる,オシ系からハタ系への王朝交替
----第3話:秦氏による神社統治システムの構築~諸民族支配の方法
第5論:継体天皇を契機に,蘇我氏,藤原氏が登場し,天皇制が確立~古代
----第1話:推古天皇・聖徳太子を戴く蘇我馬子による日本統治のプロトタイプ
----第2話:中臣鎌足と天智天皇,天武・持統天皇,そして藤原不比等による,天皇神話の確立
----第3話:クダラ系藤原氏の(陰謀によるライバル追放の)長期政権~平安時代
第6論:平将門の乱を契機に登場した,坂東武家三流の盛衰~平安時代後半
----第1話:平清盛を生み出し,武家政権への端緒となる桓武平氏(イト系)
----第2話:源頼朝を生み出し,武家政権を確立した清和源氏(シラギ系)
----第3話:将門の乱を制して東国武士の祖となった藤原秀郷から,奥州藤原氏へ(秀郷流)
第7論:天皇の権威を背景とする武家政権時代~中世
----第1話:天皇戴くクダラ系藤原氏に倣い,将軍を戴いて覇権を握ったイト系北条氏~鎌倉時代
----第2話:シラギ系足利氏による武家政権の建て直しから,公武一体化で破綻するまで~室町時代
----第3話:大内氏が将軍代役になるも,下克上で,武家政権の秩序が崩壊~戦国時代
第8論:それまで支配とは無縁だった町人が活躍する時代~近世
----第1話:大航海時代に対応,旧体制を破壊して新たな時代の幕を開けた織田信長(イト系)
----第2話:マツ系による国の奪還~露払いとしての豊臣秀吉
----第3話:徳川家康が覇権を握り,朝廷をも超える全国支配を確立(崇神東征時の国譲りの奪還)
第9論:長州支配で,クダラ的藤原政治が復活する~近現代
----第1話:権威までも失った天皇家の長い抵抗が,明治維新につながる
----第2話:長州人を軸にしてみた維新前後(大塩平八郎の乱から,明治14年の政変まで)
----第3話:山県有朋による陰謀型長州人の覇権の確立
特論:天皇制の枠組~諡号と神話と元号と
----第1話:天皇神授と皇位継承
----第2話:記紀神話と諸民統合
----第3話:天皇交替と元号変更
はじめに,統治の前から存在した日本人,いわゆる縄文人について見ておく。
近年,DNAの研究が進むとともに,原日本人はバイカル湖沿岸にいたモンゴロイドが,数万年前に,西方からのより新しい人類に押される形で,氷河期で陸続きだった(日本海は湖状)朝鮮や樺太から日本列島に入ってきたことがほとんど確実になっている。その際,そのモンゴロイドの一部は,人類大移動の一環として,やはり陸続きであったベーリング海峡を通って,アメリカ大陸に渡り,1万年前までには南アメリカの最南端にまで達した,いわゆるアメリカ・インディアンやインディオになったわけで,最近では,日本人の持つ文化と彼らの文化の共通するところに注目が集まり始めている。近年発見された,南米ペルーのカラル遺跡は,アンデス文明の原点で,5000年前,まさに,四大文明といわれるメソポタミア,インダス,エジプト,黄河と同時期に発展をしたものであり,アメリカ・インディアンなる人たちが,縄文人と同じであるとすれば,縄文文明もまた,かなりのハイレベルにあったといえる。実際,縄文土器は,その時代では,世界の最先端をいくものであったようだ。
崎谷満の遺伝子研究によると,人類は,いわゆる出アフリカ後,まずメラネシア型が分岐,アフリカで中央アフリカ型が分岐,残りはコスモポリタン型になり,その中で,早くに分岐したアイヌクラスターの人たちが,次に分岐した極東クラスター(サハリンのニブフ族型でアメリカインディアンへも展開)に押し出される形で,北海道から東日本に展開して日本列島固有民族になる一方,極東クラスターの人たちは,朝鮮から九州へ南下したが,次に分岐した九州・西日本型(琉球も含む)によって,さらに南に押し出され,鹿児島から琉球に孤立する固有の民族になったという。したがって,原日本人は,以上の九州・西日本型,アイヌクラスター,極東クラスターの三つで構成され,そのまま,(弥生人とみなされてきた)西日本人型,(縄文人と見なされてきた)東日本人型,琉球人型の違いに対応することになる。おって詳述することになるが,大和政権ができた頃には,現在の岐阜県や長野県あたりで東西日本人が衝突,その後,西日本人型が次第に東上・北上して行くのが日本人史の骨格になっており,南方に押されて,これ以上行き先の無い琉球人は今なお苦難の場に置かれてしまっているのである。
篠田謙一の研究によって,日本人集団の成立を整理してみても,まず,Y染色体の最も古い層(D2)が流入して,大陸に近い九州という核が独立,その影響を受ける西日本に対し,影響を受けない東日本に分かれ(縄文土器は東日本のもので,西日本は非縄文),その境目は,前述と同様,長野県あたり(大和王朝成立時点では伊吹山が東西日本の境界と思われる)で,北方から先に流入して定着した流入民族は,九州から東征した大和王朝の最大の敵だったということになる。また,西北九州の海洋性漁労文化は朝鮮半島南部にも広がっていたので,氷河期のもとではつながっていた,日本列島と朝鮮半島はかなりの面で一体であったというのも当然であろう。二番目のC1層は日本列島に固有で太平洋岸に集中,最後のO層が稲作やいわゆる照葉樹林文化をもたらし,その結果,稲作の北九州と漁労の西九州という構図が生まれたということである。
最近出版され,もっとも簡潔にまとめられた斎藤成也(国立遺伝学研究所)「日本人の源流」をみておくと,永年懸案だったアイヌ人については,アイヌ人が縄文人そのものの末裔ではなく,オキナワ人とのの共通性が証明されたという。つまり縄文人以降最初に流入してきた人たちで,縄文人との混血があってその残滓を今に残しているのだが,その後に流入してきたいわゆる弥生人によって,列島の北方と南方に押し出されたということらしい。その他のいわゆるヤマト人は,その後数千年の間に大陸から流入してきた人たちの混血によって形成され,現在では,朝鮮人を除く大陸の人たちとはかなり遠い存在になってしまったという。もちろん,アイヌ人,オキナワ人との混血もあるので,この四つの民族は連続しているともいえ,冒頭で述べたことを証明するものにもなっている。
かつては,柳田国男の「海上の道」などに見られたように,日本人のルーツは黒潮に乗ってきた南方の民族だいうのが分かりやすかったこともあって,固定観念のようになっていたが,そもそも黒潮のもとになる太平洋の赤道近くに,遺伝子からみて日本人の母体となるような民族はおらず,東南アジア方面を見ても,台湾と八重山列島の間は距離的には近いものの動植物相も含めて強い分断線になっていることも知られている。近年明らかになってきたことであるが,トンガやフィジーを経て,最終的にハワイやイースター島に至ったポリネシア人の出発地が台湾だということ,つまり南方から民族が来たのとは正反対の流れであったということなのだ。
ロイ・アンドリュー・ミラーによる古日本語の解析でも,モンゴル,ツングース,チュルクなど,バイカル湖周辺の民族の言語たるアルタイ系に近いことが判明しつつあり,松本克己「世界言語のなかの日本語―日本語系統論の新たな地平」によれば,朝鮮語やアイヌ語・ギリヤーク語という環日本海言語圏を形成する言語が,アメリカ・インディアンやインディオなどの言語のでき方と共通する環太平洋言語圏のひとつの核であったという極めて納得しやすい説も登場している。環太平洋言語圏という語が示すように,太平洋岸を海岸伝いに展開したアメリカ・インディアンやインディオと同系であるが,北方のエスキモーなどは,シベリアの内陸部から,陸路で展開した全く別の語族になるという。いずれにしても,かつては,日本列島の沖縄から北海道,樺太に加え,朝鮮半島までが地域として一体であったといえるが,現在の朝鮮語と日本語がほとんど関係無い言語のように見えるようになってしまったのは,大陸と日本列島のつながりが早くに切れたため,それぞれ独自の発展をしてきたためということのようだ。
日本人のベースに,いわゆるアメリカ・インディアン,インディオとつながるところがあると思わせるのは,インカ帝国の名残のあるペルーで,あらゆるところに神が宿るという意識,それ以上に,人工物にまで人格を感じる,例えば,コップを落した時,「コップが自ら落ちた」というのと同じようなところが,日本人にもあって,近代になって登場した機械までも人に例えることがあることにも通じるものであろう。
余談であるが,DNAからみると,漢民族は最も新しく分岐した層で,中国大陸から他の層を追い出して行ったため,現在の中国人の構成はきわめて単純になってしまっているようだ。
紀元前1500年から1000年頃,つまり弥生人渡来以前に,ツングース系の有力な民族ながら国を持たず,中国から侮蔑的にワイ(濊)と呼ばれていた民族が,現在の黒竜江のあたりから,のちの満州あたりを一大拠点にするようになる。それと並行するように,樺太から蝦夷を経て,日本列島を南下し,信濃,越を経て,最後は出雲にまで至ったといわれ,陸奥,出羽も彼らのつけた名に由来するという。船を操ることにも長じたワイ族は,いわゆる日本海交易圏を形成して行き,崇神天皇東征以前から大和の有力氏族の一つになっていたアベ(アエ=阿部,安倍)氏もおそらくこの民族といわれる。大和朝廷の伸長とともに,かつての東北地方に戻って,交易を握って繁栄,その代表の安倍貞任が,前九年の役で征伐されて後,その子宗任ほか一族は伊予方面に移住させられ,その末裔が安倍晋三ということになるの。名字由来ネットでみても,阿部,安倍氏が東北地方と四国西部に多いことが分かる。
あらかじめ述べておくと,大陸側では,同じツングース系の有力な民族で,国造りもできる扶余氏に土地を奪われ,朝鮮半島を南下して新羅人のもとになり,物部氏の出身地ともみなされる扶余氏は,のちに高句麗を建国,さらに分家が百済王族になるのである。>物部氏
氷河期には,本州,九州,朝鮮全体が陸続きで,日本海は巨大な湖のようであり,主としてツングース系民族が南下し,最終的には九州,朝鮮両側から,再び出会うことになる。オホーツク海系アイヌ人は,大陸と分離し始めた後に,日本列島にのみ南下した民族であるという。とすれば,アイヌの民族詩ユーカラと,アジア系の民族の国フィンランドのカレワラとが,あまりにも似ているのに驚き,ともに,特別に限られた存在にされてしまった少数民族ではないか,現在の地域でいえば,ヨーロッパのバスク人のようなものだったのではないかと想像してしまうのである。
Wikipediaから,ツングース系民族について確認しておくと,満州からシベリア・極東にかけての北東アジア地域に住み,ツングース語族に属する言語を母語とする諸民族で,北方の,エヴェンキ族,オロチョン族や,南方の満州族が代表的で,日本には,かつてオロッコと呼ばれた民族が流入してきた。習俗からみると,馴鹿の飼養を生業とする民族,遊牧を生業とする民族,農業で生活し定住化した民族に大別されるが,狩猟は,家畜の飼養,農業,馴鹿の飼養に適した地方を除くすべての地方において,主要な生業であり,栗鼠,狐,熊,山猫,黒貂,野猪,鹿など,獲物は主に食用や毛皮の供給源になっている。遺伝子からみると,Y染色体ハプログループのC2系統が高頻度に観察されるが,エヴェンキ族,オロチョン族に比して,満州族はかなり少なく,2000年前には,分岐が始まっていたと考えられる。ツングース系民族による国には,満州語族による粛慎,靺鞨,女真などといわれた国,扶余語族による高句麗などがあり,古代出雲の住民はツングース族で,いわゆる"ズーズー弁"はツングース語起源とする説もある。結論からいえば,日本の歴史との関係で,高句麗を建国した扶余語族が大きな意味を持つことになる。>高句麗
松本克己によると,縄文人は最終氷河期の最寒期の頃,つまり日本列島と周辺の列島,さらにはアメリカ大陸まで陸続きとなった2~3万年前に日本列島に流入し,1万数千年前には千島,アリューシャン列島経由でアメリカ大陸に渡っている。その後,温暖化が始まり,日本列島は大陸と分離,日本語が朝鮮語とかなり異なる方向に進みながら縄文文化が花開く間,中国の長江流域でさまざまな民族による稲作文明が次々と起るが,紀元前4000年頃に,海洋民族と騎馬民族のハイブリッドとして生まれた漢民族(主要な漢字に貝がつくもの,羊がつくものが多いことでも証明され,漢語がいわゆるクレオール語だという指摘には鋭いものがある)によって,次第に押し出され,その一部は山東半島から朝鮮を経由して日本列島に渡っていわゆる弥生人となり(後述するように,主たる民族は呉人),他は南に押し出されて東南アジアの主要民族(主たる民族はベトナムをつくった越人)になっていった。
崎谷満の説で補足すると,日本語の形成については,日本列島が5000年前に大陸から分離したことから,他の言語とのつながりが分からなくなっているが,上記D2層とされる民族が原日本語をもたらしたのは間違いなく,伝播の核となった九州では,当初から西九州語,南九州語,東九州語,北九州語など相互に異なる言語に分かれ,他は,琉球を別として,西日本語,関西語,東日本語にくくることができるということである。西九州語が最も多様性に富むことから,日本語普遍化の核になったと考えられ,後述するように,その主体であった奴の国の人たちの東方への展開に対応して,西九州語が日本語の共通になっていくようである。つけくわえれば,上代奈良語には九州諸語の影響が見られるということで,いわゆる神武東征伝説を裏付けるものになっているともいえよう。
縄文土器が,その当時の世界を見渡した時に,かなり高度な文明であること,のちにアメリカ・インディアンが創生したマヤやインカの文明が石造を基本とした高度なものであることなどから,そもそも技術的能力の高い縄文人がのちの技術立国日本のルーツであり,同じ民族をルーツとする朝鮮の人たちの技術力も,かつての石工や製陶や現代の先端製品まで全てつながっているといえるのではないだろうか。北方由来の縄文人は森林の木の実をはじめ植物を主食に,川や湖の鮭や鱒など淡水魚を栄養源にしており,南方に広がってゆくうちに,沿岸の貝類を食べるようになって,大森貝塚が発見された東京湾岸,とくに世界最大の貝塚密集地帯になっているという千葉市を代表に,多くの貝塚を残している。ついでながら,最近出版された竹倉史人「土偶を読む~130年間解かれなかった縄文神話の謎」は,土偶のもつ不思議な形を,植物祭祀論をもとに,面白いように暴いているが,とくに,貝は,海を森とみなした時,木の実そのものであるという指摘には,目からウロコの落ちる思いがする。
話は飛ぶが,日本人に関心の高い血液型からみると,O型をルーツに,B型,A型と進化してきたといわれ(AB型がさらにその後のものであるのは当然),早くに分離したインディアンはほとんどがO型らしいので,日本人の血液型のO型は縄文人由来といってよいだろう。A型がきわだって多いヨーロッパでも,縁辺部に追いやられたアイルランドなどではO型が多く,より古い民族であったことが知られる。アジアのなかで日本人が際立ってA型が多いのは,後述するように,西アジアで発生したA型人類が,一方では西のヨーロッパに至り,東方で日本に至ったということによると考えられる。余談であるが,民族のDNAで最も新しく分岐してできたといわれる漢民族の血液型はB型が主体になっているらしく,農耕民族としてのじっくりさよりも,B型の人たちは,すぐに新しいものに飛びつくなどという巷の見方が,かなり当たっていることが多いと思われるが如何だろうか。実は,欧米人はほとんど興味を抱いていない,自分の血液型すら知らないそうであるが,どうも,ナチスがA型の民族が優れていると,差別をしたことの歴史へのトラウマが反映しているようだ。⇒コラム「血液型の発現史」
氷河期が終わって温暖化するに従い,大陸から切り離されただけでなく,本州,九州,四国も分離され,居住地が狭められた西日本の縄文人から,最初の海洋民族たるワダツミ族が登場する。ワダというのは,海を示す古代語であり,日本神話では,イザナギの子で,住吉三神とならぶ海の神ワタツミノカミとして位置づけられている。後述するように,大陸から渡来する航海等に優れる海洋民族(ナカ系,イト系,アマ系)に押される形で,ワダツミの名を残す渥美半島を経由し,天竜川を遡って,すでに,縄文人のメッカであった諏訪湖に至り,その北部に安曇野として展開,穂高神社は,穂高山頂にありながら,海の神ワタツミノカミを祀っていて,祭りも全く海洋民族のものになっているのである。有名な諏訪大社の御柱祭りをみれば,船の進水式そのもののようなところがあるのも頷けるが,渡辺姓の分布は,諏訪神社分布と重なっているのである。
2017年,宗像大社が世界遺産に登録されたが,正木晃「宗像大社・古代祭祀の原風景」によると,その原点とされる沖の島は,縄文人にとって理想的な食糧となったニホンアシカの繁殖地であり,荒海の困難を乗り越えてその捕獲を行い,アイヌ人が熊祭りをするように,祭祀を行ったことが,そもそもの始まりということらしく,その担い手こそ,ワダツミ族であったのではないだろうか。そもそも,博多湾の志賀島には海神を祀った志賀海神社が現存し,全国の綿津見神社の総本宮となっており,安曇氏の発祥地とされ,神職は今も阿曇氏が受け継いでいるのである。⇒コラム「ワダツミ族の代表安曇氏」
渡辺姓は,「ワタ」つまり「海」,「ナ」つまり「の」,「ベ」つまり「民」を表すように,そのままワダツミ族の末裔の人たちであるとみられるが,その分布は,関東以北に多く,安曇野を拠点に北方に広がったと考えられる(現在では数少なくなった本来の安曇姓が集中するのは宮城県)。栃木県北部に集中的に多いことが知られるが,内陸県ながら,魚の需要が多いほか,平家の落人など,長野県に類似する海洋民族県(隣の群馬県がその名の通り騎馬民族であるのと対照的で,足利,新田という騎馬民族源氏の名門の地。両県を繋ぐ部分に福田姓が多い)である。マツ系・ナカ系の人たちの東進によって押し出されたより古い海洋民族であることを証明しているといえよう。
公式には,渡辺姓は嵯峨源氏渡辺綱を祖としているが,Wikipediaに記されているように,その後裔が,摂津の渡辺津という旧淀川河口辺の港湾地域を本拠地として,武士団を形成し,瀬戸内海の水軍の棟梁的存在になっているように,本来,海洋民族で,後述する桓武平氏,清和源氏などと同じく,臣籍降下した嵯峨源氏を祖としたに過ぎないと思われる。
この後,後述するように,国譲りした出雲族の代表のような存在であったマツ系の人たちが,ワダツミ族同様,浜松(マツ)から天竜川を遡って諏訪湖に至り,安曇野を控える松(マツ)本を最終的な到達地にすることになる(神話にも,神武に追われた出雲族の一人伊勢津彦が,最終的に信濃に至ったとされている。諏訪神社の神は,タケミナカタノカミであるが,神話の上では,オオクニヌシノミコトの子で国譲りに徹底抗戦し,信濃の諏訪湖に逃れ,先住の神々を征服し,諏訪神になったとされている。>マツ系
戸矢学「諏訪の神 封印された縄文の血祭り」にはずばり,そのルーツは中国の海洋民族呉人(マツ系)であり,ミシャクジ神が呉人信仰に対応する神であると書かれている。そもそも"諏訪(スハ)"という語は,古代支那の特別な階級で用いられた宗教用語で,呉音ではスホウと読み,「神の意志・判断を問い・諮ること」を意味していて,重要な行事の一つにかつて生贄を捧げていた名残があり,また独特な鉄製の祭具"宝鈴"は,銅鐸を起源とするもので,やはり南九州に渡来した呉人が伝えたと考えられるという。その呉人たちは,その後も長く中央に抵抗していたが,邪馬台国の卑弥呼に象徴される銅鏡を祭器とし,東征して大和朝廷を開いた鉄器民族に打ち破られたということになる。
ついでながら,東奈良遺跡から発掘された小さな銅鐸は,銅鐸としては,最も古いものらしいが,その表面には,縄文の紋様が描かれており,銅鐸をもたらしたと考えられる弥生人中国呉地方の民(マツ系)が,縄文人と親しくつきあっていたことが偲ばれ,諏訪の話につながるのはもちろん,いわゆる出雲族とされるのが,マツ系とその背後にいた縄文人全体であったことを思わせる。
また,諏訪には,北方から,ツングース系の有力な民族ワイ族も流入して,トーテムや牛を生贄にするなどの文化ももたらしているから,あらゆる意味で多くの民族が衝突する場になり,最後に,大和朝廷が派遣したヤマトタケルによって平定されたということになるのだろう。国譲りというのは,結局これら異質の民族全てを出雲に封じ込めたということで,出雲と諏訪とが結び付けられ,神無月が出雲では神有月になっているわけである。その後の展開をみると,いわゆる国つ神の出雲族は,東征してきた民族すなわち天つ神に国譲りした全ての民族を表すものとしても,その核になっているのは,マツ系民族とみて良いのではないかと思われる。
さらに,後述するように,海洋民族ナカ系の人たちが,日本海側の信濃川を遡って諏訪湖に至り,その間,まさに,長野というナカ系の地名を残しているように,信濃(長野県)は,海のない県にもかかわらず,海洋民族が集中した特殊な県(陸封された海洋民族の県)になったのである。これらの積み重なって,信濃の地は,西南日本と東北日本を分け,神話上でも特別な位置を占めることになる。>ナカ系
ところで,諏訪大社の,御柱祭りの四本の柱組は,出雲大社を支える四本柱を表現しているようにも思える。関裕二「信濃が語る古代氏族と天皇 善光寺と諏訪大社の謎」によれば,諏訪大社には本殿が無く,南にそびえる守屋山が御神体で,蘇我馬子に敗れた物部守屋のことを表しているらしく,諏訪大社に近くて古い長野の善光寺がなぜあれほど全国からの人を集めるのかというと,その創建が諏訪大社下社の社人によってなされ,神長官守谷氏が物部守屋の末裔で,その怨霊封じのためだったようで,善光寺では本尊が本来のあるべき位置には無く,そこには守屋柱があり,守屋山~諏訪大社~善光寺が南北軸上に並んでいるということである。物部神社の伝説では,宇摩志麻遅命は当初弥彦のあたりに拠点を作ったらしいので,弥彦山が,日本海側の重要なシンボルであったことも伺える。信濃は,あらゆる敗者の集合地でもあったといえよう。
いずれにしても,次項で述べる弥生民族渡来以前の様々な人たちをひっくるめて出雲人と捉え,その人たちが弥生人の支配下に入ったとして,それ以上詮索しないことにしたい。また,後述するように,いずれもユダヤ系あるいはそれに近い,徐福の末裔と,応神朝の頃に大量に渡来した秦氏が,日本全体の統治の仕組みとして,神社体系を確立するわけであるが,その際,この様々な出雲人たちの様々な神まをひっくるめて,出雲大社に祀ったと考えておきたいと思う。
この章TOPへ
ページTOPへ
日本列島に国といわれるようなものが,いつ頃登場したのかは分からない。歴史的な文献として,国の名が初めて登場するのが,邪馬台国論争で取り上げられる「魏志倭人伝」で,西暦297年に没する西晋時代の陳寿が,その前の三国時代の歴史書をまとめたうちの「魏書」のなかの一つの巻で,西暦240年前後の日本の諸国について記述しており,古代日本を考える上での基礎文献になっていることは言うまでもない。当時の諸国のなかで抜きんでた存在で,現在の日本国のルーツではないかされる邪馬台国のあった場所についての記述の解釈では,諸説紛々ではあったが,ようやく北九州説に定着しつつあり,朝鮮半島から邪馬台国に到着するまでに登場する国について,一番目の狗邪韓国が現在の朝鮮半島内に,伊都国が現在の福岡県の糸島周りに,末盧国が現在の松浦周りにあったこと,そして,奴の国が玄界灘周りに展開していたこと,熊本県周りに狗奴国があったことなどは,おおむね意見が一致していると思われる。そこで,邪馬台国を除く,これらの国の形成について,まず,考えてみよう。
序章で取り上げた斎藤成也は,いわゆる出雲族の末裔とみられる日本海岸の人たちに,DNA上でヤマト人の平均とズレがあることをもとに,大陸からの流入に,大きく四つの波があったという説を提示している。その説をもとに,第1波は,いわゆる照葉樹林文化に対応する民族,つまり(1)のクマ系に対応,第2波は大量の海洋民族で,九州北部から全国に展開し,原日本語を伝えた民族は,(2)ナカ系に対応,第3波は中国南部の稲作民族が大量に流入してきたということなので,(3)マツ系民族に対応するものと考え,以下,順に考察する。最後の第4波は朝鮮半島経由が主体のようなので,その後に渡来し,日本全体を統治することになった民族として,次章で考察することになる。
邪馬臺国周辺図
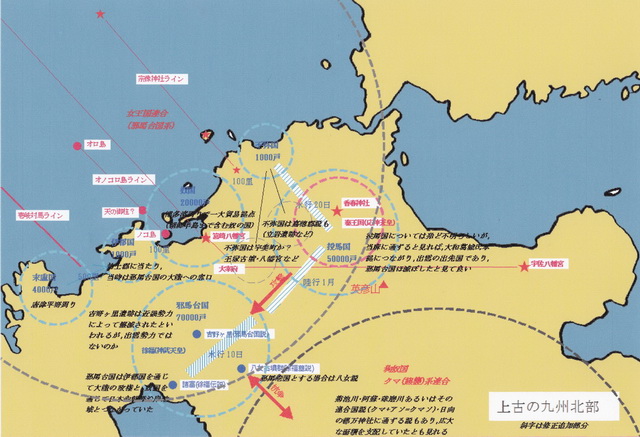
神武東征神話では,出発地が南九州,到達地が熊野ということになっているが,両者に共通するのが,日本列島のなかでは限られた,照葉樹林帯に属していることである。文化人類学者の中尾佐助,佐々木高明らが提唱して以来,日本文化のルーツの一つが照葉樹林帯の民族によるものであると考えられるようになった。
照葉樹林の食料生産の基本は焼き畑農業で,縄文的なレベルであったことから,照葉樹林文化が,日本の縄文文化そのものではなかったかとの誤解が生じたが,前述したように,日本の縄文文化は北方民族によるもので,弥生人の渡来によって,大半は北方に押し戻されるが,遺伝子の解析によって,明らかになったように,沖縄県人は,アイヌ民族とも相通ずる部分が多く,南部に押し出され,取り残された縄文人の末裔ということになるのだろう。
その故郷は中国雲南省周りで,言語から見ると,チベット・ビルマ語族,チワン・トン語族,ミャオ・ヤオ語族,モン・クメール語族の人たちがその担い手であり,その多くは,漢民族の膨張とともに外部に押し出された。このうち,クメール人は,1世紀頃には現在のベトナムで王朝を開くものの,その後に,やはり漢民族に押し出されてベトナムを建国することになる越の民族にも押されて,最終的に,現在のカンボジアに至り,有名なアンコールワットを築いた王朝を開いたように,国をつくる力のあった民族であった。
そのクメール人が,雲南省と同じ照葉樹林帯に含まれる日本の九州南部に渡来して建国したのが狗奴国と考えられるわけで,狗奴(クナ)すなわちクマが,クメール人のクメを表していると考えられる。現在でも,東南アジアで,雲南省に最も近いラオス北部に残るクメール人の言葉が,クム語といわれていることも傍証になろう。ついでながら,カンボジアにはタケオという町があり,酒造や鵜飼なども,雲南省由来の照葉樹林文化という,きわめて古い文化である。国家をつくる力のあったクメール人の石造技術は,のちの熊本城の石垣や通潤橋につながっているとも想像できる。
南九州には,球磨(クマ)という地名があり,熊襲という民族がいたことを見れば,熊野との地名的関係も明らかであり,狗奴(クナ)国は,クマと同じで,それこそ球磨周辺に展開していたことになる。のちに,その北側に,邪馬台国ができたことで,両者の紛争が続き,東征して大和朝廷になった後も,その平定に苦労したのは当然の帰結であったろう。同じように南九州にある地名の大隅の隅は,大隈の隈とも通じて,熊(クマ)に同じであり,炭や墨のスミ,目のクマなど,黒いものに共通する語であるといえる。
ついでながら,国をつくる力のあったもう一つの民族チベット人は,ヒマラヤに阻まれてそれ以上進めず,現在の苦難の道に至ることになってしまっている。
神武東征を警護したとされる大伴氏は,もともとは久米(クメ)氏,まさにクメール人を名乗る氏族であったということから,その末裔とみて良いといえる。その久米氏と同族とされる紀氏が,熊野に定着して,紀の国をつくることになるが,そもそも和歌のもとになった最古の歌が,久米歌といわれ,大伴,紀氏とも,和歌に優れた氏として知られており,照葉樹林文化の特徴の一つの歌垣に直結するものといえるだろう。
ところで,焼き畑の名残を示す地名や人名には,木野,木場,木田などがあるといわれ,徐福伝説にかかわる串木野は,クシフルのクシをも冠していることも含めて代表例になるが,紀氏はキノ氏といわれ,そのまま木野名につながり,まさに,焼き畑民族で,狗奴国の本拠地だったという熊本県菊池郡に木野神社があることも,なるほどといえる。友人だった木野という人物も,その由来を彷彿とさせるところがあった。
余談として,2004年に中国で唐の時代の日本人井真成の墓誌が発見され,玄宗に愛された極めて優秀な人物であったことが記されていて大きな話題になったが,この井氏は,後に井伊直弼らを生む井伊家の祖で,熊本の阿蘇を本拠としおり,邪馬台国が狗奴国から奪った有力な部族の一つであったらしいことを付け加えておく。
日本の神様の体系については,「日本書紀」が完成するに際して,時の権力者藤原不比等が自らの正統性を示すべく変更したとか,神社の体系は,その骨格を秦氏がつくったなどと言われるが,いずれにしても,渡来してきた諸民族の,拠って立つ所を何らかの形で留めていると考えて良いだろう。その全体像については,終章にまとめたものを掲載しておき,それぞれ民族の神様や神社については,その項ごとに,適宜述べることとするが,全国に展開するものとして,その第一号になるのが,クマ系に対応する熊野神社ということになる。>神様の家系図
熊野神社は,総数としては,稲荷神社や八幡神社からみれば一桁少ないとはいえ,全国に3000を超え,その総本山が,神武東征に際して上陸地点になった現在の新宮市にある,いわゆる熊野三山で,熊野速玉大社には,神武天皇を案内したとされるアメノカカグヤマノミコトが祀られ,それに次ぐのが,国譲りの関係で,出雲の熊野大社ということになるが,そもそも,新宮の熊野本宮大社のご本尊がスサノオノミコトであり,さらに,熊野神の元神様は,イザナギ神・イザナミ神ということなので,神様から人間世界への移行を示しており,国土から,諸生産物まで,あらゆるものの原点になっている。院政時代を頂点に,熊野詣が,天皇家の重要な行事になったのも,これらすべてに対応する精神的な拠所であったからにほかならないだろう。
分布状況をみると,九州の熊本県に多いのは当然としても,中部地方以西ではかなり少なく,千葉県から岩手県にかけての太平洋岸諸県に際立って多くなっている。ということは,クマ系の民族が,後から渡来して大和朝廷を開いた諸民族に排除され,かつて,南九州から紀伊半島に渡ったように,太平洋岸を北上していったということだろう。最北端の下北半島東通村に残る伝統芸能の能舞は,毎年正月,熊野新宮に奉納に上るといったことにも,歴史が遺されている。後述するように,物部氏の末裔で,熊野に本家のある鈴木氏が三陸に多いことも,関連していると思われる。⇒コラム「熊野神社の分布,三陸方面への展開」
最後に,熊襲とセットで語られることの多い隼人族は,中央アジアのトハラ人で南西諸島吐噶喇(トカラ)列島にその名を残し,海洋民族ではない中央アジアの遊牧民トハラの末裔で,邪馬台国の時代よりかなり後に,戦乱の結果,流れ着いた人たちであったと考えられる。
トハラ(吐火羅)人は,スキタイ系の遊牧民で,タシケント付近にいたが,紀元前129年頃に,大月氏の侵攻を受け,以後,行方不明になった。隼人について,「言語が大いに異なっている」,「五島列島の海士と似ているが,騎射を好む」といわれたこと,甑隼人もいることなどから,九州西岸を南下してトカラ列島に至ったと考えられる。私の友人がそうであったように,隼人出身の人はラードを好むなど,中央アジア人の典型的な嗜好を示す。
「日本書紀」に初めて登場するのが,西暦682年と,全く新しい民族であることも明らかで,古事記で神武天皇の出は隼人族と書かれているなど,熊襲伝説に隼人を絡めるものが多々あるが,時代的にあり得ないことを付け加えておくとともに,神武天皇が西方から渡来した人物であることが暗示されているともいえる。
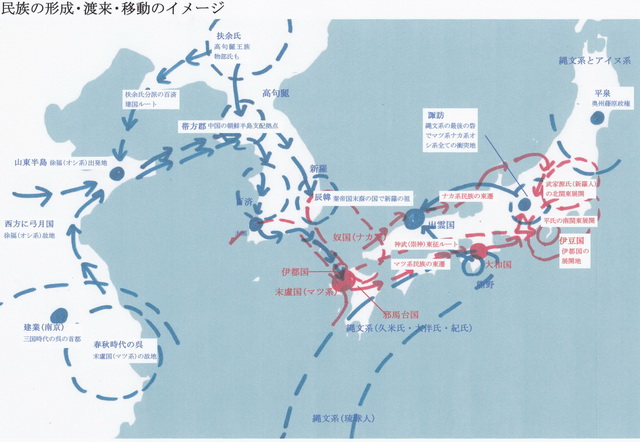
中国と朝鮮の間にあって,主たる渡航の足場になった山東半島の内側がいわゆる黄海であるが,早くから,これら渡航によって,交易圏がつくられていたと考えられる。この担い手だった民族が,さらなる発展を求め,造船や渡航の技術の向上とともに,日本の方に展開していったことは想像にかたくない。
序章のワダツミ族のところで取り上げた宗像神社の原点たる沖ノ島では,気候変動などの理由でニホンアシカがいなくなり,陸地も減少して,縄文人の祭祀は途絶えるが,今度は,朝鮮半島から日本列島をめざす海洋民族の格好の目印・聖地(地図をみれば一目瞭然)となり,結果として,博多から長門に至る九州北部沿岸と朝鮮半島西南側とを一体とする海洋国家を形成,これが,奴国("私の"が"我が"になるように,ナノはナカでもある)ということになり,第3章の徐福渡来のところでも取り上げるように,中国の山東半島は,朝鮮を経由して,日本に渡来するメインルートとなり,その航海を請け負ったのが奴国の民族ナカ系であったということになる。
航海は星を頼りにするので,占星術が発達,神事を司る中臣氏が形成されていったと考えられる。付け加えておくと,宗像大社の三女神は,応神天皇の妃とされ,後述する新たな海洋民族アマ系に属するように,沖ノ島の支配者が変わり,そのアマ系の代表たる卑弥呼のような巫女的な世界,シャーマニズムに近い神秘的なものになっていったといえるだろう。
沖の島の位置
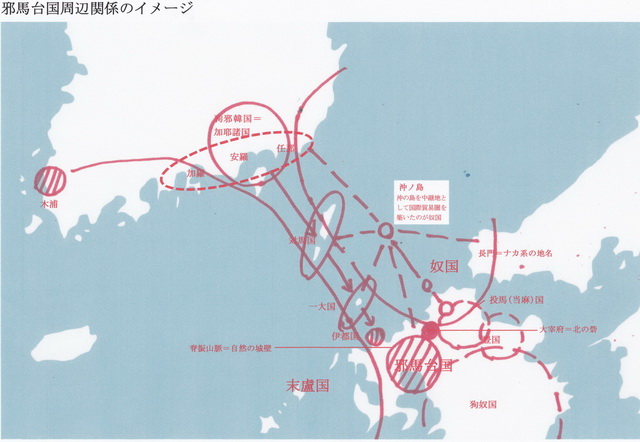
ところで,志賀島から出土し,西暦57年(場合によっては紀元前109年)に中国から授与されたとされる有名な漢委奴国王印は,漢の委(倭)の奴(ナ)の王と読まれてきたため,卑弥呼よりも2,300年前には,奴国が日本を代表する国として認知されていたと思われていたが,内倉武久「卑弥呼と神武が明かす古代―日本誕生の真実」によれば,漢音では奴はドと読まれるので,後述の伊都国王のことであったといい,その存在からみて,その通りのようだ。しかしながら,次節のマツ系の到来した頃には建国されていて,後述のように,邪馬台国建国に関わる徐福渡来は漢より前のことなので,すでに漢字も入っていたことを考えれば,自ら奴(ナ)と名乗っていたと考えられ,後に,「魏志倭人伝」に記載された時も,漢字で表記されたものをそのまま記し,漢音でドと読んでいたと考えても矛盾しないと思われる。内倉も指摘しているように,後の松浦であることが疑いない末盧(マトラ)国も,漢音では全く異なる音になってしまうということなので,すでにそれ以前の江南の発音を用いて表記されていた漢字をそのまま記していたということだろう。>伊都国
任那(ミマナ)のナとの関係も指摘されているが,"ナ"は,古朝鮮語では,村,郷,国,現代朝鮮語では,私,自分,僕などにあたる極めて原初的語で,他の国に比べて,その範囲を特定しにくい。想像をたくましくすれば,奴の国の人たちは,自分中心の民族であったともいえ,中臣氏にもつながるようだ。また,古代朝鮮で,"ラ"という語は,のちに新羅(シルラ),百済(クダラ)というように,国のことを示しており,「魏志倭人伝」の頃に,その"ラ"がついたのは,次節の末盧(マトラ)だけであり,それだけ,国の体を成していたということを示している。そして,オシ系が大和に移って,国譲りされ,それを支えたナカ系の奈良(ナラ=まさに奴の国,前節に従えば,自分の国)ができたということになろう。
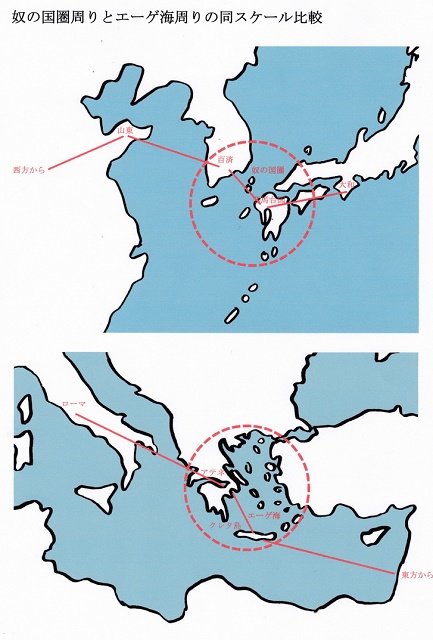 ヨーロッパの古代の,エーゲ海の島々から起る地中海文明は,そのスケールや大陸との関係が,奴国とほとんど同じで,イメージを膨らませてくれる。続くギリシャ文明は都市国家連合で,九州北部の女王国連合に瓜二つ,アテネとスパルタの戦争が,邪馬台国と狗奴国との抗争に対応し,さらにローマ帝国へと展開して行くのが,大和や京都への展開に対応するというように見て行くと,まさに,東西を反転させた相似形であるといえよう。
ヨーロッパの古代の,エーゲ海の島々から起る地中海文明は,そのスケールや大陸との関係が,奴国とほとんど同じで,イメージを膨らませてくれる。続くギリシャ文明は都市国家連合で,九州北部の女王国連合に瓜二つ,アテネとスパルタの戦争が,邪馬台国と狗奴国との抗争に対応し,さらにローマ帝国へと展開して行くのが,大和や京都への展開に対応するというように見て行くと,まさに,東西を反転させた相似形であるといえよう。
奴国形成の過程で,航海の安全を基本とする祭祀をつかさどる中臣(ナカトミ=奴の臣)氏が,大陸と日本を結ぶ護衛のような存在として大きな役割を持つようになったと思われる。「魏志倭人伝」によれば,邪馬台国周辺諸国は,みな中国に倣う三官制であったが,邪馬台国にのみ第四の役職ナカチがあったと書かれていて,これこそ祭祀を扱う中臣氏のことであったと思われる。
後述するように,中臣鎌足は,日本に亡命してきた百済の王族で,奴国,すなわち中臣氏に受け入れられ,その姓を名乗ったと考えられるが,最近,奴国の,日本本土の都であったと考えられている福岡県春日市の須玖遺跡の発掘が進み,吉野ヶ里の4倍ほどの集落があって,そこでは,鉄器,ガラス,銅器を製作する専門集団も多くいて,まさに,弥生時代のテクノポリスであったといい,奴国が,早くから,朝鮮半島の百済地方と強い縁のあったことが判明した。先取りしてつけくわえれば,春日(カスガ)という地名は,藤原氏の本拠地だった奈良の春日そのものに対応する,カ(伽耶)のスカ(村),すなわち,百済のもとになった国の人たちの場所であったことを示しているのである。
ついでながら,日本で漢字を使用するようになったのは,古墳時代になってからと考えられてきたが,奴国のネットワーク下にあった,現在の島根県松江の宍道湖岸の田和山遺跡から発掘された板石硯に漢字が記されていたことが判明,その他多くの弥生時代の遺跡から,板石硯が発見されているが,当然のことながら,文字,すなわち漢字を書くために使われていたと考えられ,邪馬台国時代の九州北部諸国に,書記のような人たちがいたのは当然であったといえよう。
ところで,神武天皇(実は崇神)東征以前には大和の有力氏族で,その後急速に衰退してしまう倭漢氏については,わざわざ倭と書かれ,その祖珍彦が神武東征の水先案内人であったとされることから,神武朝時代のヤマト族で,その実態はおそらく奴国の氏族であったと思われる(かの金印がかつて漢の倭の奴の国王と読まれたように)。大和を制圧した崇神朝に,大和に実在して倭直の祖になった珍彦(ウズヒコ)は椎根津彦に対応し,応神朝になって登場する太秦と同じ"ウズ"であることから,徐福一族から特別の待遇を受けていたことも分かる。そもそも中臣氏は日本史上祭祀を司る最大の氏族とされながら,その本拠や神社との関係が不明になってしまっているのは,後述するように,藤原氏の祖鎌足が,本来中臣氏ではなく苗字を借りただけのことであったことを隠蔽すべく「日本書紀」が書かれたためであろう。
奴国をルーツとみなせるナカあるいはナガのつく地名を調べてみると,まさに奴国の一部であった長門国や,かつて末盧国の範囲も取り込んだ長崎県はじめ,日本海岸,太平洋岸ともに多いように,ナカ系の人たちが,航海能力を発揮して次第に東進したこと,さらに,ナカ系地名が全国の主要な川沿いに広がっていて,内陸部に遡上していったことが分かる。その最たるものが,太平洋側の木曽川から遡上するものと,日本海側の信濃川から遡上するものが,諏訪湖において結ばれる大横断ルートで,そこの地名が長野県になったのも当然ということになろう。
実際,海洋民族になったつもりでみると,海から来た時に,信濃川の河口部の位置の目印となったのが弥彦山で,河口から遡って行くと,新潟県の中条・中野から,大きな長岡市を経て,中山の後,しばらくして長野県に入り,中野市(すぐ近くに中山)を過ぎて,県庁所在の長野市まで,"ナカ"系の地名が続き,(千曲川でない)犀川の方をさらに遡って行くと,すでに,ワダツミ族が開いていた安曇野(中村・中川・中山,さらには"なぎさ"という地名まである)に至り,塩尻峠を越えたところで諏訪湖を目にして,海に出たと感激し,精神的な本拠地にしたのではないだろうか。同時に,最も古くからいた縄文人と,その後に到来したマツ系民族と出くわして,諏訪大社や善光寺にまつわる複雑な神々の歴史に関わることにもなって行く。
くりかえしになるが,海のない内陸県たる長野県は南北から到来した海洋民族が主体となる不思議な存在になって行き,その象徴が,船の進水式そのものにも見える諏訪の大祭ということだろう(長崎県にも諏訪神社があり,いわば兄弟県になる)。地名の分布図からも分かるように,後述するマツ系と同様,長野県までであり,少し広げても関東甲信越までが限界で,東北地方以北は縄文人,アイヌ人,後述するワイ系民族の世界として,なお中央に抵抗する存在として残ったのである。
とくに,茨城県の那珂湊から那珂川を遡上して栃木県に至る地域には,ナカ系の地名が多数存在することから,中臣氏の本拠地の一つだったようで,のちに,中臣鎌足が,その地の,実際には物部氏の神社であった鹿島神宮を自らのものにした上,大和の春日神社に勧請しと考えられる。
ナカ系民族が全国展開していったのは,海洋民族たるナカ系として海産物を野の幸・山の幸と交換しようとしたことはもちろんであるが,天日による製塩も当然行っていて,岩塩などの無い日本の野の民・山の民からの強いニーズがあったことに対応したものと思われ,その際,必須な飲料水を欠くことがないよう,川沿いのルートを遡って行ったと考えるのが自然だろう。日本各地にはさまざまな方言があるが,序章で述べたように,日本語が,全体としては西北九州をルーツとしているのは,ナカ系とマツ系が全国展開したことによると考えれば納得できよう。
ナカ系地名の展開図

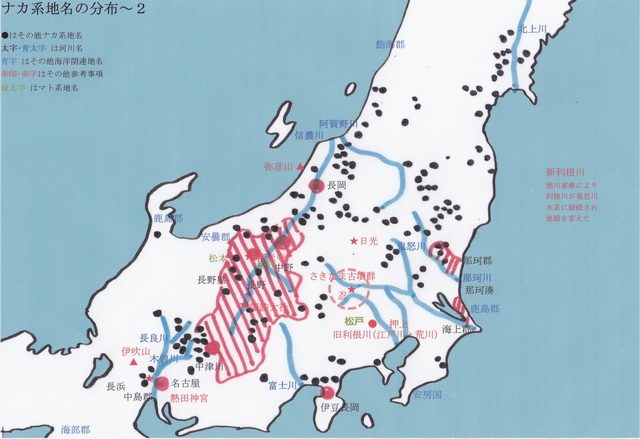
網野善彦・宮田登・上野千鶴子「日本王権論」によると,古代の朝廷支配で,一般の平民(公民)は,調・庸を貢納しているが,それとは別に,とくに海の幸を贄という形で奉るかなり特定された集団がいるといい,その分布を示した図を見ると,一目瞭然,ほとんどナカ系の地名の分布と一致する。おそらく,後述する徐福以来の天皇家につながるオシ系民族を支えたナカ系民族が,各地に展開,その後も,天皇家とのつながりを維持すべく贄を奉り続けたと考えられる。「続日本紀」に出てくるという"鹿嶋の神賤"という人々こそ,藤原氏が鹿島神宮を氏神にしたこととつながる話なのだろう。古代から続くといわれる美濃の"鵜飼"も,贄を貢納していたというが,その場所は長良川で,まさにナカ系の地名である。
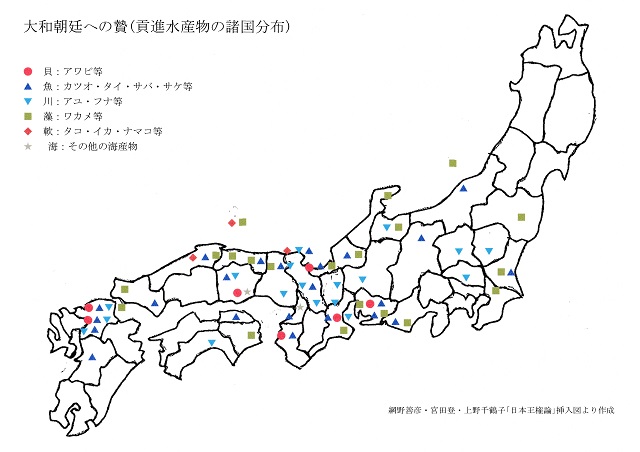
別冊歴史読本「日本の苗字ベスト10000」によって,ナカ系苗字(苗字全体の5%程度)について見てみると,大阪・奈良・和歌山の府県の10をトップに,兵庫県の9,石川・高知県の8を挟んで,新潟・愛知・三重・滋賀・京都・鳥取・広島・長崎・宮崎の9府県が同じ7,富山・岡山・山口・徳島・香川・福岡・佐賀・熊本の8県が6で並び,群馬・埼玉・神奈川・福井・山梨県が5,茨城・栃木・東京・長野・岐阜・静岡・愛媛・大分・鹿児島の9都県が4,あとは,青森・千葉県が3,岩手・秋田・山形・島根県が2,宮城・福島県が1と,ナカ系の全国展開をほとんどそのまま示す分布となっていて,とくに西日本にありながら極端に少ない島根県が大和朝廷とは全く異なる出雲の存在をそのまま伝えていることも示される。ちなみに,サッカーの強くて有名な選手には,ナカ系が多いが,世界でも,海洋民族のラテン系の国(スペイン,イタリア,ブラジル,アルゼンチンなど)がサッカーに強いことにもつながるだろう。⇒コラム(ナカ系・マツ系民族の展開)
中国の長江下流域の沿岸海洋民であるとともに稲作民であった民族の一部が,とくに,紀元前770年からの中国春秋時代という動乱期に,朝鮮半島経由で日本に渡来してきたのがいわゆる弥生人の中核だと言われており,序章で触れたDNA分析によっても,その系統の比率がかなり高いことが指摘されている。最近,稲作を基準とした弥生文明と縄文文明の境目が不分明になっているといわているのも,これら,中国南部の人たちの流入を考えれば,矛盾はなくなるのではないだろうか。
その中国には,「倭人は呉の太伯の末裔である」という伝説があるが,周王朝の祖の長子太伯が現在の蘇州周辺を拠点に建国した呉の国は,紀元前473年,越によって滅ぼされたため,沿岸海洋民族でもあった呉人が大量に日本列島に流入して,新しい文明をもたらしたと考えられる。呉太伯の末裔という人たちがつくったのが末盧(マトラ)で,前節で触れたように,「魏志倭人伝」の頃に,国を表す"ラ"がついたのは,末盧(マトラ)だけであり,それだけ,国の体を成していたということになろう。現代でも,中国観光旅行をすると,最も落ち着くのは,蘇州の庭園群などと言われるように,日本人にとって,一つの故郷になっているようだ。
その呉人がどうして末盧国とつながるのかというと,その拠点であった九州西北部に極めて多い松尾姓はじめ,松の字のつく苗字を持った人たちが皆,"松野連(マツノムラジ=松一族)"と称し,「自分たちは呉太伯の子孫である」と言い伝えきていることによる。つまり,呉の国の滅亡によって,その王族が亡命してきたことにより,魏志倭人伝に記述される末盧(マトラ)国が形成されたと考えられるのである。繰り返しになるが,古代朝鮮による国名が,日本に直接つながるといわれる安羅(アラ),加羅(カラ)はじめ,新羅も本来シルラ,そして百済(クダラ)というように,ラは国を表し,末盧(マトラ)は,まさに松の国ということになるわけである。
「魏志倭人伝」では,倭の人は断髪・裸で刺青だったと書かれているが,呉を滅ぼした越の国が人々が断髪・裸で刺青だったといわれていることからも(両民族は混同されていた),まさに末盧国の呉人のことと思われる。沿岸海洋民である末盧の人たち(呉人)は,おそらく朝鮮半島で地形的にも似ている後の百済や済州島などにつながる国家として,日本で最も早くに国をつくったと考えられる。
さて,呉人が日本に伝えた文明であるが,青銅器や生贄・占いなど,古くからのものはもちろん,日本の神話が中国の道教の影響を色濃く受けているという点で,その原点と言われる老子が,少し前の紀元前6世紀に,隣国の楚で誕生し,周の図書室を管理する役人であったといわれるから,少なくとも,呉太伯の末裔というような人たちには,その思想も伝えられていて,のちに,道教を身につけて渡来した徐福一派(オシ系)や秦氏(ハタ系)とも,なにがしかの接点があったと考えられる。
ついでながら,呉を滅ぼした越は,その後,楚に滅ぼされて南下,のちにベトナム国をつくることになる。「呉越同舟」という語があるように,いわゆる漢民族からは,それぞれ能力ある民族と見られていたのだろう。日本とベトナムそれぞれが,中国とほぼ対等に複雑な関係を築いてきたことを思うと,不思議な感じもする。
この後,中国では後漢が滅んだ後のいわゆる三国時代に,その一つの国として長江下流域に再び同名の呉国が登場,かつての呉の国の民族に近く,ほぼ卑弥呼の時代に対応する西暦223年~280年に存在した同国の人たちも多く渡来して,漢字の読みにおいて,日本には漢音よりも先に呉音が普及,現在でも多くの読み方が残ることになり,同国の首都で現在の南京になった建業は,園林都市としての魅力を有し,庭園や文学はじめ,日本文化に本質的な影響を与えることになる。
松(マツ)の字のつく主要な地名を追って行くと ,四国の松山,高松を経て,現在の大阪府松崎から,大和の地に入ることになるが,おそらく,そこでの初めての国をつくったと考えるのが自然であろう。神武東征神話では,河内から入った神武が長髄彦の抵抗を受けて退却し,南下して熊野から入らざるを得なかったと書かれているすが,その長髄彦の祖の名は観松彦(ミマツヒコ)で,マツ系,すなわち呉太伯の末裔だったようだ。蛇足であるが,長髄彦一族について,記紀では風貌賎しくなど蔑む言葉が書かれているのは,単に敗者を蔑んでいるのではなく,朝鮮経由できた鉄器民族の人たちには,長江河口部の東南アジアに近い民族が異質に見えたことを示すものとも考えられ,北方アジアの民族と融合を図れず,国譲りに至ったと思われる。もちろん,王族とともに,多数の被支配層の呉人も,全国に展開していっただろう。
ところで,島根県の宍道湖に面する荒神谷遺跡で,1983年,大量の銅剣,銅矛,銅鐸が,それも未使用の状態で発見されて学界に衝撃を与えたが,松江に近いことからも,マツ系の人たちの最後,まさに出雲の国譲りに対応するものと考えられよう。出雲地方には,独特の形をした,方形古墳が多くあるのも,国譲りをした人たちに関係するのかもしれない。
神武東征,実は崇神天皇の東征に敗れて,国譲りしたマツ系の人たちは,東に逃亡,伊勢の松阪を経て,名古屋方面に向かうが,その近傍には有松(マツ)が存在する。濃尾平野のいわゆる木曽三川が呉の国の地のように"江"と呼ばれるのをはじめ,岐阜あるいは"蘇"のつく地名など中国南部に類似するものが多く見られ,鵜飼など極めて古い文化を有している。のちに,有力武将を輩出するなど,日本史上重要な役割をし,関東・関西の中間に位置しながら,なぜ首都になれなかったのか,まさに,抑えられた民族マツ系の地であったからなのだろうか。後の章で明らかになるが,猿のような風貌だったといわれる豊臣秀吉に続いて,徳川家の家紋が三つ葵であることなど,マツ系の人物が,再び国を取り戻すのである。>豊臣秀吉,>徳川家康
その後,浜松から,ワダツミ族と同じように,天竜川を遡って,諏訪湖に至り,安曇野の地の松本が,最後の拠点になることは,前章の,信濃の項で述べた。
ちなみに,野球の強くて有名な選手に,マツ系が多いのは何故だろうか。⇒コラム(ナカ系・マツ系民族の展開)
マツ系地名の展開図
(藤井耕一郎「サルタヒコの謎を解く」を参考に)
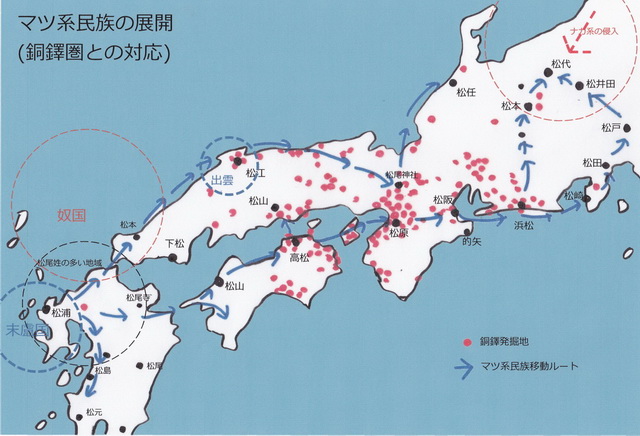
先取りするようであるが,秦氏が創建したとされる有名な神社に京都の松尾大社があり,その名がマツ系そのものである上,中村修也「秦氏とカモ氏」によると,その祭神は秦氏の神ではなく,その近くの,鴨氏の上賀茂神社,下鴨神社と同じであるという。つまり,国譲りしたマツ系の人たちを,支配下に取り込む装置として,これらの神社が創建されたと考えられよう。この両神社は葵祭りで有名であるが,鴨という動物,とくに家畜化されたアヒル(家鴨)と,葵という植物をセットで考えれば,まさに,中国南部の揚子江下流域のもので,マツ系がすなわち旧呉人であるという有力な証拠になるだろう。このことと関係するかもしれないが,大和最古とされる三輪山をご神体とする大神神社は,オオモモヌシが祭神で,鴨氏の祖とされることから,マツ系が大和を支配していた時の名残ではないかと思われる。
後述するように,鉄器文明を携えて渡来した徐福の末裔が創始し,後に大和王朝を開くことになる邪馬台国が,奴国をもとりこんで,北九州の覇権を握り,やがて東征してきたことで,忽然と消えてしまった(国譲りした)銅鐸文化を支えていたのが,マツ系民族であるらしいことは,その出身地江南の地で使われていた祭器にそっくりだということからも明らかで,鉄を銕と書いて蔑み,青銅器を崇拝する江南の文化を受け継いでいたマツ系の人たちが,先進的な鉄器を持って登場したいわゆる天孫族にあっさり敗れてしまったということだろう。平安京遷都以前に,その地に,鴨氏の神社があったということは,かつて大和の地を支配していたマツ系の民族が,崇神朝以降,圧迫されて,山背国方面に退避させられていたことを示すものともいえよう。
蛇足になるが,著名な歌人柿本人麻呂は鴨氏の出といわれ,繰り返しになるが,蘇我氏,藤原氏らに排斥された(クマ系の)大伴家持,紀貫之,さらには鎌倉幕府に配流された後鳥羽天皇まで,和歌は,敗れた側の人たちの世界を救うものとして,大きな役割を担って行くが,それを象徴するのが,まさに鴨氏直系の鴨長明ということになる。
唐突であるが,マツ系に絡んで,酒の話をしておくと,世界で,酒に弱い人の多い国のトップは中国で,実に半数以上,次が日本で約4割,3番目が韓国で約3割という。欧米諸国などにも,酒に弱い人が少しはいるのではないかと思われるが,実は全くいないということだ。酒に弱いというのは,すぐ赤くなる,吐き気がする,二日酔いになるといったようなことで,そういう人はおらず,アル中が多いのは,あくまでも肝臓の能力を超えてまで飲んでいるからということのようである。中国について見ると,揚子江の南側に集中していて,呉の国は,まさにその中心に位置していた。実際,中国の北部では,茅台酒というやたらに強い酒が有名であるが,南部に行くと,紹興酒というかなり弱い酒が一般的になる。呉の国の人たちが,日本に大量に入ってきたとすると,日本の酒に弱い人たちが多いのも無理はないだろう。すでに述べてきたように,呉の民族はマツ系で,その氏神が松尾大社であるとすれば,松尾大社が,なぜ酒の神になっているのかも,分かるといえるのではないだろうか。
さらに付け加えると,酒に弱いというのは,肝臓が,アルコールをアセトアルデヒドに変換後,すぐに酢酸に変えることができず,有毒なアセトアルデヒドがたまりやすい身体であるということであるが,ある遺伝子学の人によれば,酒に弱い人が登場したのと,稲作が始まったのとは,ほぼ同じ1万年ほど前で,稲作は暑い中に水を張るため,感染症の原因になる病原体が繁殖しやく,それを防ぐべく,アセトアルデヒドの力を借りる,つまり,毒をもって毒を制するという進化を選んだということのようである。してみれば,東アジアの人たちは感染症に強いということであるから,今まさに流行している新型コロナウィルスの感染者数,死者数などが,欧米諸国等に比べて桁違いに少ないのも当然なのかもしれない。
2001年に発表された,原田勝二の「飲酒様態に関与する遺伝子情報」によって,都道府県別に,アルコールを分解するALDH2遺伝子の頻度をランキング表にしたものを図化してみると>コラム,まず,言えることは,弥生時代に入って,大陸から渡来した人たちが,日本の中央部に広がって行くに伴って,縄文時代の人たちが,南北に押し分けられていったことを,そのまま示すように,東北と九州の人たちが,日本人のなかでは,とくに酒に強い人たちということが示される。
渡来した弥生人のなかでも,とくに酒に弱いとされる揚子江下流域からきたのが,マツ系であるとすれば,かつての末盧国,すなわち,現在の長崎県,佐賀県が,九州のなかで,異質の酒の弱さを示していることが,末盧国がマツ系の人たちの国であったということを示す根拠になろう。そして,近畿方面に展開していったことも,図から読み取れ,崇神天皇が大和に入る前,この地方を支配していたのがマツ系であったことを想像するのも容易である。神武伝説で,天皇が,瀬戸内から難波方面に入った際に,抵抗したとされるナガスネヒコもマツ系であっただろう。
それより以上に,とくに酒に弱いのが東海地方であるが,その中心の尾張は,日本の中でも,とくに揚子江下流域と似た風土であることから,この方面に大量のマツ系の人たちが定着したと考えられる。それ故に,大きな川のことを,「江」と名付けたり,蘇原や岐阜など,中国的な地名が多くみられるということでもあるだろう。のちのち述べるように,豊臣秀吉,徳川家康がマツ系の可能性が高いという根拠にもなろう。
面白いのは,首都圏が酒に強い側にあるということで,東京の人たちのベースは,東北,新潟の人たち,さらには,九州の人たちであることが窺え,このことが,関西と関東の文化の違いを示す一つの理由であると言えよう。
この章TOPへ
ページTOPへ
奴の国の項で述べたことの繰り返しになるが,志賀島から出土し,西暦57年(場合によっては紀元前109年)に中国から授与されたとされる有名な漢委奴国王印は,漢の委(倭)の奴(ナ)の王と読んで,奴国の王であるとされてきたのが,内倉武久「卑弥呼と神武が明かす古代―日本誕生の真実」によると,漢音では奴はドと読まれるので,委奴(イド)すなわち伊都国王のことであったということである。ナカ系の奴国(玄界灘国家)とマツ系の末盧国(黄海圏国家)の間にあって,倭の北岸といいながら朝鮮半島内にあった狗邪韓国(おそらく後にも統一新羅までは倭の一部として半島内に存在し続ける伽耶)から,対馬,一大国(一般には一支国の書き違いで壱岐とされているが,内倉によれば,天(アマ)国であった天の字が二つに分けて書かれてしまった可能性があり,伊都国がアマ系と一体であったということを示す)を経て,九州北岸の現在の糸島(怡土郡)が,日本における首都にあたる地であった。中国が半島支配の拠点としていた帯方郡と直接繋がっていて,祖は現在の韓国の蔚山で,おそらく伊都を示す現在の糸島を前衛基地にしていたとも考えられる。対馬の厳(イヅ)原は伊都(イト)を表し,福岡県の板付(イタツケ)も伊都が語源のようである。つまり,のちの伽耶・任那にあたるとされる狗邪韓国から,対馬国,一大国(壱岐)経て,伊都国(糸島)に至るルートが大陸からの支配軸で,日本本土の玄関が伊都国になり,そこまで全体が,伊都国の支配下にあったということになる。
石井好「忘れられた上代の都"伊都国日向の宮"」,西谷正編「伊都国の研究」によると,次節で述べる徐福の渡来以前には成立していたとみられる伊都国(現在の糸島周り)は,朝鮮半島南部と同様,鉱物資源の宝庫で,とくに玉の生産を中心とした一大貿易港でもあって,壱岐,対馬を介して大陸と深くつながっていたことから,倭のなかで伊都国だけに王が存在し続けたと言われるのも当然であったと思われる。大陸との間で,朝貢だけでなく,外交・貿易を行っていたということは,「魏志倭人伝」以前から,すでに漢字が用いられ,それを理解する人たちが少なからずいたことを示しているが,それが一部に限られ一般化していなかったため,文字遺跡が無いのだろう。当然のことながら,中国の銅銭も盛んに使われており,造船業もかなりのレベルにあったようだ。
大和朝廷のルーツとみられる邪馬台国の勃興は,次節で述べるように,徐福渡来によるものと考えられるが,徐福一族は,朝鮮半島南部から伊都国に到着,そこで伊都王に迎えられ,携えてきた先進的技術などによって重鎮となり,やがて婚姻関係を結ぶに至って,そのまま滞在することになったと考えられる。その場所の名が日向(ヒムカ)の宮であり,神武東征伝説の重要な土地,現在の宮崎県に当たる日向国の名の由来になったこと,さらに言えばと,卑弥呼の読み方も弥生時代の発音ではヒムカであったことなど,神話を理解する上でポイントになろう。後述するように,徐福一族は道教の神仙思想をもって渡来,一大国では,遺跡から,卜骨を用いた占いが盛んであったことが知られ,後の卜部氏のルーツとも考えられているくらいなので,そのアマ系の巫女文化と結び付いて,神社など道教用語が統治の体系を創る基本になったとみれば,その後の展開も良く見えてくる。
結論的に言えば,大陸との間の交易で覇権を握ったイト系の王が,アマ系の巫女に支えられて国家を形成していたということになり,後に,徐福の末裔が邪馬台国を建国するにあたって,アマ系の巫女を戴く形で支配する新たな国家を形成,のちの天皇制を先取りするような形で覇権を握り,その結果,アマ系を支配下においていた伊都国(イト系)との間は緊張をはらんだものになっていたようである。アマの国から来たということを示すアマギすなわち甘木が,重要な参詣地となったらしく,アマ系たる卑弥呼がアマテラス大神のモデルになったと考えるのが極めて自然といえよう。
なお,桓武平氏梶原氏の祖や額田王で知られる額田氏は,一大国すなわちアマ出身であり,紀元前221年に秦に滅ぼされた中国の晋の王族田氏も一大国に逃亡してきたといい,のちに天皇側近の氏族とみられる倭漢氏になったらしく,その末裔の坂上田村麿の子孫が田氏を名乗っていることにもつながるようだ。
伊都はまた伊勢とも言われたというから,のちに崇神天皇が大和の地に至って,その地にいた神を遠ざける形で伊勢神宮を創建したことにもつがるのだろう。
話は飛ぶが,後に平清盛を生む平家の棟梁は,その風貌からも,伊都国王族(イト系)の末裔ではないかと考えられる。と言うのは,代々厳島神社(伊都国から来たことを示すイツク島で,宗像三女神のうちの,伊都国から来た名のイチキヒメミコが祭神)を崇めていたこと,伊都国には強力な水軍があって玄界灘を支配する貿易国家であったこと,中国の威信を背景に伊都国が支配していた被支配層の海洋民族は,後に,海賊化し,現在のヤクザにまでつながるが,その海賊を統率できたのも,中国南部の宋との貿易に通じていたことからも頷けるからである(現在でも長崎県と福建省のつながりは強い)。さらに,平氏直系の北条氏の根拠地伊豆国は伊都国であると言われているばかりか,伊豆のシンボルが(アマギすなわちアマの国から来たことを示す)天城山であることからも,伊都国の人たちが伊豆に辿りついたのは,ほぼ確実で,第5章で記すように,平氏は,伊豆を拠点に関東の太平洋側一帯を支配するようになったのである。>伊都国の東進,>桓武平氏
後述するように,伊都国は,支配下にあったアマ系の民を戴く形で登場する徐福の末裔が建国した邪馬台国と抗争を繰り返すようになり,卑弥呼没後の九州北部全体の動乱によって,邪馬台国は東征して大和朝廷を開いたが,伊都国は当地では滅亡し,東進して,伊豆を拠点とする平氏を生み出したと言うことになるが,そのことが,のちのちの歴史において,大和朝廷にたてつく形で,所々に登場することと関係するとみて良いだろう。
前掲文献で,律令国家以降の地名で怡土郡の北に志摩郡があることから,「魏志倭人伝」で,邪馬台国から相当先にある国としてあげられている斯馬(シマ)国にあたるのではないかといい,中国の別書にも伊都国の傍らに斯馬国あると記されているので,斯馬国は「魏志倭人伝」時代より前に,何らかの理由で東遷して,現在の三重県志摩にまで至ったとも考えらる。日本書紀では,後に統一百済ができた際,倭との交流に従来の対馬~伊都国ルートが使えなかったためか,沖ノ島経由の新たなルートを教えて交渉に当たったという斯馬宿禰が登場するが,その名の通り斯馬国出身の人物と思われ,このことはまた,もともと斯馬国が伊都国と敵対する関係にあったことも想像させる。
紀元前3世紀頃,朝鮮を経由して弥生文化が入って来たという見方に対応するのが,日本各地に残る徐福渡来伝説ではないかと思われる。各地に伝説が残るのは,渡来する段階で相当に分散して漂着したことにもよるとも考えられるが,後述するように,徐福の末裔が展開していったことによる方が大きいのではないかと考えると辻褄が合うようだ。徐福は,徐市(じょふつ)とも書かれ,山東半島一帯にあった斉の国の方士(道教の神遷思想に強い関心を抱修行者)であったらしいが,徐福にしろ,徐市にしろ,ユダヤ系の名ヨブの漢字表記である,つまり,ユダヤ人であった可能性が高いのである。最近になって,中国で徐福の墓が見つかったところは徐阜村というが,これもヨブの漢字表記である。
徐福は,秦の始皇帝が天下巡遊した際に出会い,東海すなわち日本に派遣され,その際,あらゆる職能の数千人の船団を組んで渡来したといわれ,日本の文明を一気に進ませるとともに,それ以前の縄文時代以来の自然の神々から,先進的な道教の体系をもとにした神話体系を構築していったと考えられる。第4章に記すように,応神天皇渡来時には,やはりユダヤ系とされる秦氏(ハタ系)が,その当時の朝鮮の道教にもとづいて,神社体系を再構築し,のちには唐が道教を重んじた国であったことから,遣唐使によって,道教の思想が,さらに強化されて行ったということのようだ。山東省は,のちのちも,道教の拠点として,宗教としての体系化を進めていく場になって行く。
始皇帝の意を受けた徐福は,さらに東方の日本での建国をめざして渡来したといっても差し支えないので,その始皇帝によるほとんど突然のような中国統一について,見直してみよう。秦国そのものは,紀元前770年に,現在の中国の西端部に興ったといわれ,さらに西方の中近東由来の養蚕・機織りなど先端技術得て勢力を振るい始めて,同325年に初めて王を名乗り,その後諸国を次々と滅ぼしてはいったのであるが,あくまでも多数あった国の一つでしかなかった。そこに,同221年に登場した始皇帝が一気に中国全土を統一したわけであるが,わずか15年で滅亡してしまうという奇跡的な状況を説明するには,特別な状況があったと考えざるを得ない。
ところで,旧約聖書のなかの「ヨブ記」は,「義人の苦難」を扱った文献として知られているが,紀元前5世紀から前3世紀にかけて成立したようで,まさに,徐福の時代の直前にあたる。作者に擬せられているヨブはウツ(太秦のウズの語源ともいわれる)の地の住民のなかでもとくに高潔で,ヘブライの神の不可解なやり方を問題視,その答えを出すべくヨブ記をまとめたと言われるから,のちのキリストのように,逸脱したユダヤ人であったと思われる。サタンによる襲撃にも屈せず,神を勝利に導いたことで,羊,らくだ,牛,ロバ,あわせて3万頭以上を与えられたが,次項で述べるように,中央アジアの民族を象徴するものではないだろうか。七人の息子と三人の娘をもうけたらしいので,その後,一族が各地に展開していったと考えてもおかしくないだろう。
後述するように,神武天皇からのいわゆる欠史八代は,単に神話の世界ということでなく,崇神天皇になって大和入りする(いわゆる神武東征)までの,徐福の末裔による北九州の邪馬台国時代を示すものになっていると考えられる。中国には神武天皇と徐福が同一人物であったという説まであるが,神武天皇の倭名カムヤマトイワレヒコの,不明とされてきイワレの語について,古代ヘブライ語にあたってみると,なんとイワレ(イヴレ)はヘブライ人そのものを指す語だといい,神武天皇・崇神天皇とも倭名がともにハツクニシラススメラミコトというように,始皇帝と全く同じ名づけられ方になっているのも,つながりを示しているのではなかろうか。
ここまでくると,ユダヤ人の中国方面への展開の歴史を,さらに遡ってみたくなろう。いわゆるユダヤ人の離散(ディアスポラ)は,BC722年アッシリアによって北イスラエルの12支族が流浪の途に出,そのうち10支族は行方知れずなったとういうのが始まりで,紀元前587年のバビロン捕囚によって拡大し,同332年のアレクサンダー大王のパレスチナ征服によって決定的なものになった。ユダヤ人の多くは西方に向かい,後にヨーロッパで嫌われる民族になることは良く知られているが,東に向かった一部については,あまり知られていない。
「宋氏日本伝」には,最初の神・天之御中主の23世後の彦ナギサが筑紫日向の地,つまり伊都国に着いたと書かれているらしいが,彦ナギサがすなわち徐福で,ディアスポラによって故地パレスチナから出た時からの歴史を,この23世にこめたものと思われる。とすれば,戦前に紀元2600年と言っていたのが,まさにパレスチナ出地からの年数を表しているのだと気づかされる。
紀元前4世紀には,現在のキルギス周辺にユダヤ人がいたことが確実になっている。キルギスの古都オシ(まさにオシ系のルーツを表している)には聖なるソロモン山(現在はイスラム教なのでスレイマン山と呼ばれる)があり,アレクサンダー大王の東征は紀元前320年に,この少し西側でストップするが,おそらくキルギス側に,すでにユダヤ人が建国した月氏国(砂漠の民であることを示し,後の弓月国にもつながる)があったことによると思われる。そして,アレクサンダー大王の圧力を受けて東進し,秦を支配することになったのが,月氏国の支配者であった始皇帝だったのではないか,つまり,当時の中国で隔絶した技術などを有するユダヤ人に近かったからこそ奇跡が実現したのではないかと考えられるのである。実に,キルギスには「自分たちは西方(つまり砂漠の地)から来てここに止まったが,さらに東に行ったのが日本人である」という言い伝えがあるのである。そして,現在のオシには"ルフ・オルド"というイスラム,正教会,カトリック,ユダヤ教,仏教の五大宗教を合わせた公園が作られており,このことからもキルギスにおけるユダヤの存在が大きいことが分かるのである。
中国のことを秦といい,音が転じてCHINAというようになったばかりか,秦の始まりと同じ頃に登場した古代ローマも,紀元前27年に諸国を統一してローマ帝国となり,皇帝が登場すること,大秦国という漢名なったことなどからみても,やはりユダヤ人がその創設に寄与したと考えても良いだろう。いずれにしても,シルクロードは,ユダヤ人が商いの中心になっていたのである。 タクラマカン砂漠にいたというシルクロードの謎の民「楼蘭」は,始皇帝時代に隆盛であった月氏の勢力圏内にあったが,BC176年に,匈奴の支配下になって以降,その存在が消えていったといい,ユダヤ人に近い人たちであった可能性もあるといえよう。
秦帝国,ローマ帝国に共通するのは,大規模な土木・建築という建造技術と国家支配システムの構築であるが,前者が一瞬にして終わってしまったのは,漢民族という大きな塊に屈してしまったから,もしかしたら,徐福のような有能な人材がいなくなってしまたからかもしれず,後者が極めて長く続いたのは,ユダヤ人の持つ能力が発揮され続けたからではないかとも考えられる。ユダヤ人の国家支配システムを構築する能力は,その後,金融によって世界支配システムになり,GAFAなど,現代のインターネットによる世界支配につながっている。その上,アインシュタインやマルクスなど,世界を支配する知的な思考や思想の面でも,世界を支配するようなものを生み出しているのである。
余談ながら,イスラエルの失われた12支族の中の,マナセという名は,戦国時代に登場した名医曲直瀬道三の不思議な苗字に関係していると思えてくる。
キルギスの古都"オシ"の語は,重要な意味をもっているらしく,神話時代の天押帯日子命・屋主忍男武雄命などにはじまり,6代孝安天皇(日本足彦国"押"人天皇)・9代開化天皇の弟(彦太"忍"信命)・12代景行天皇(景教と関係するか・大足彦"忍"代別天皇)・17代履中天皇(もとに復する意か)の子(磐坂市辺"押"羽皇子・"忍"海飯豊青尊・忍坂大中姫)・30代敏達天皇の子("押"坂彦人大兄皇子)など,その後も忍熊皇子・刑部親王・他戸親王など,また皇族外でも,神部直忍・神人部子忍男・穂積臣押山・穂積忍山宿禰・敢臣忍国・紀忍人・忍海氏など,古代の天皇やそれに近い人物の倭名に"オシ"が入っているものが多いことから,"オシ系"民族として位置付けられることになる。藤原仲麻呂が,尊称として,恵美押(オシ)勝を名乗ったという理由も,これで判明し,皇族でもないのに名乗った傲慢さが,孝謙上皇を諫めて怒りを買ったという以上の結果を招いたと考えられるのである。
さて,海を渡った経験の無いユダヤ人にとって,日本へ大船団で向かうというのは容易ではない。そこで登場するのが,第1章に記した,海洋民族の奴の国の人たちだったと考えられ,のちの邪馬台国に特別の官職ナカチが設けられたことからも,如何に重要な役割を担っていたか分かるのである。実際,徐福集団が後の百済地域を経由して渡来したことは,現在の全羅南道の木浦に,押(オシ)海島があり,その主峰が忍(オシ)海山であることから推測され,押海島は,のちに公孫氏が滅ぼされた年に,卑弥呼が帯方郡に朝貢した際に使者が経由した地ともいわれている。その後も,徐福一族の子孫たちは,ナカ系の人たちに誘導されて日本各地に展開して行くことになるのである。
オシという地名で唯一良く知られているのは,埼玉県行田市にある忍城,つまり江戸時代の忍藩であるが,この不思議な地名こそ,古代からのオシ系の拠点であったことを示すもので,さきたま古墳群があるのも当然であった。そして,地名の由来が定かでないとされて来た東京の押上は,オシ族が上陸したところで,そこから荒川を遡上して再上陸したのが行田の忍(オシ)の地であり,それを裏付けるように,行田の荒川沿いにも押上の地名があるとなれば,もはや,疑いようがないだろう。
その押上にできた東京スカイツリーであるが,そもそもなぜあんなに狭いところに,それも大地震時には東京内で最も危険とされるようなところに無理して建てたのか,さらに着工までとその後しばらくはほとんど報道されなかった(地元ではかなりの反対運動があった)のはなぜか,さまざまな疑問が湧いてくる。というのも,知る人ぞ知るように,東京タワーがフリーメーソンアジア支部の位置を示すところに建設されたということもあるからである。
東京スカイツリーは東武鉄道が本店のある押上一丁目一番地周りの車両基地の跡地に建設したもので,今述べたように,ユダヤ人の上陸した地点であり,戦前にユダヤ人アインシュタインが来日した時,なぜか分野的には全く関係のない東武鉄道創業者の根津嘉一郎をわざわざ訪ねていること,そして,ルーツが秦氏つまりユダヤ人と思われる豪商三井が江戸にでてきた時,守護神としてきた京都太秦の木嶋神社(蚕の社ともいわれユダヤにつながる)と同じ型の三柱鳥居を奉納した三囲神社があること(実に,スカイツリーの形をデザインした芸大の先生が,テレビ番組で,分かっていてか,知らずにか,イメージの源泉を問われて,すぐ近くにある三囲神社の三柱鳥居であると話していた)などから,疑問は氷解してくるのである。
東武鉄道の基本である伊勢崎線は,東京スカイツリーが建設された押上(オシ系)を始点に北上し,忍城の名に残るようにオシ系の拠点さきたま古墳群の近傍を通過(羽生から秩父鉄道ですぐ先,忍城のある行田市にも荒川の旧流路沿いに押上町がある),そして江戸時代に徳川綱吉が5代将軍になる前に藩主を務めたほどの地で,11代将軍家宣と側室(オシ系の押田敏勝の娘)の子が12代将軍家慶になるなど,まさにオシ系ラインなのである。>新・上州遷都論
全く別の話として,ヤマトタケル伝説のうち,熱田神宮に近い,亀山市に伝わるものに触れておきたい。明治政府は,市内田村町の丁字塚を,「日本書紀」に書かれたヤマトタケルの墓が営まれた能褒野と比定して,能褒野王塚古墳と名づけているが,ヤマトタケルの妃オトタチバナヒメが,市内の忍山(オシヤマ)神社の祇官の娘であったいうことが最大の理由のようで,忍山神社がかつてあったところが,押田山という名になっている。もしかしたら,伊勢神宮を全国に広げる役割をした人たちは御師と書いてオシと読んでいるのは,オシの名を残すためなのか,伊勢近傍には押(オシ)田姓が多いらしく,最近でも,高校野球となでしこリーグのいずれにも,押田選手のいることが知られる。また,代々押田氏の京都の染物屋「京明」が,2013年の伊勢神宮遷宮に当たり,神宝製作者に選ばれたのも関係するかもしれない。
また,徳川吉宗時代に,広大な武蔵野新田の開発を任されたばかりでなく,その後,美濃の輪中地域の整備,石見銀山の再興など,さまざまな面で,地域の開発や経営の面で,優れた才能を発揮した,川崎平右衛門定孝は,豊臣秀吉の小田原征伐に敗れた後北条氏の家来で,東京府中の押立(オシタテ)村に定着し,代々,名主を務めた家柄であるが,この地名も,押上同様,多摩川からの,オシ系の上陸地点であったように思われる。その下流ほぼ全域が,現在,川崎市となっているように,一族が連綿と繋がっているようでもあるが,なんと,川崎定孝は,屋敷内に,家祖を祀る押田稲荷の社を建てていたということなので,オシ系そのものの人物で,その才能は,まさに,ユダヤ人の血を引いていたからともいえるだろう。このような例は,他にも多々あると思われる。
ちなみに,名字由来のホームページをみると,川崎氏は,武蔵国橘樹郡河崎庄が起源とあり,橘樹郡の名は,ヤマトタケルの妃弟橘媛(オトタチバナヒメ)に由来するといい,亀山の押田山の話につながるばかりか,地図で確認すると,橘樹郡はそのまま,現在の川崎市の範囲である。自民党の大物議員で2021年に引退した川崎二郎は,亀山と接する伊賀の名門といい,川崎姓の多いのが,邪馬台国のあった佐賀県と,神武東征の本拠日向の国すなわち宮崎県であるということからも,川崎氏はオシ系であったことが示される。
あらかじめ確認しておくが,邪馬臺国の臺(台)の字が壹(壱)の誤記とする説について,長田夏樹「新稿・邪馬台国の言語~弥生語の復元」・渡辺義浩「魏志倭人伝の謎を解く」(本来の三国志から)などでは,逆に壹(壱)こそ,臺(台)の誤記であるとして,再び邪馬臺国が正しいとされるようになってきている。そして,所在地論争にも,様々な理由から,九州北部説に落ち着きつつあり,言語学的に見ても,方言の残り方などから,邪馬台国は九州北部であったと考えられるという。ついでながら,古代日本にすでに方言があったということは,大陸での出身地が様々であったといことを示すものに他ならないだろう。
全国各地にある徐福伝説のうち最も濃密なのが佐賀県で,ほぼ全域に伝説が残っており,その中心は吉野ヶ里遺跡近くの金立山で,上陸地点は諸富町寺井津とされている。徐福は渡来当初は,前述したように,伊都国に止まったが,何代かあとに登場する徐福の末裔が伊都国に離反し,後の大宰府経由で佐賀平野に入り,邪馬台国を建国したと考えられ,この人物こそが神武天皇ということになろう。中国の言い伝えには,徐福は最後に肥沃な平野に到達したとあり,神武天皇は徐福であったというものすらあることから,佐賀平野周辺が邪馬台国で,その中心が,南に平野を望む日向(ヒムカ)の地吉野ヶ里にあったと考えて良いのではないだろうか。
吉野ヶ里周辺図
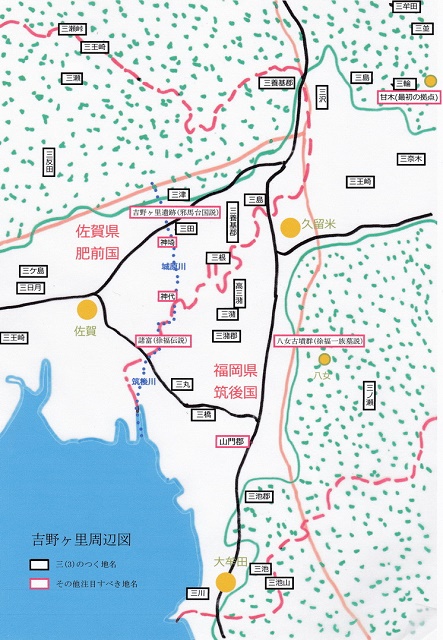 神武天皇の倭名のカムヤマトイワレヒコの,ヤマトが邪馬台国を意味するのは勿論,繰り返しになるが,イワレは古代ヘブライ語でユダヤ人そのものを指すことから,徐福ユダヤ人説は否定しようないだろう。ということで,改めて佐賀県の地図を見直してみると,三(3)のつく地名がやたらに多いことに気づかされる。ユダヤ人にとって三は基本数字であり,ダビデの星は三角形を重ねたもので,三種の神器があり,キリスト誕生時の東方の三博士から後の三位一体にまでつながるのである。さらに,吉野のヨシというのは,ヘブライ語でイエスをヨシュということがもとになっているともいわれるので,熊野と大和の間の吉野が,吉野ヶ里とつながるユダヤの道であるとも言える。「ヶ里」のつく地名は,律令制による区画整理がされた土地を示すというから,後述するように,神話体系がまとまる時代と重なることも,その証になるだろう。
神武天皇の倭名のカムヤマトイワレヒコの,ヤマトが邪馬台国を意味するのは勿論,繰り返しになるが,イワレは古代ヘブライ語でユダヤ人そのものを指すことから,徐福ユダヤ人説は否定しようないだろう。ということで,改めて佐賀県の地図を見直してみると,三(3)のつく地名がやたらに多いことに気づかされる。ユダヤ人にとって三は基本数字であり,ダビデの星は三角形を重ねたもので,三種の神器があり,キリスト誕生時の東方の三博士から後の三位一体にまでつながるのである。さらに,吉野のヨシというのは,ヘブライ語でイエスをヨシュということがもとになっているともいわれるので,熊野と大和の間の吉野が,吉野ヶ里とつながるユダヤの道であるとも言える。「ヶ里」のつく地名は,律令制による区画整理がされた土地を示すというから,後述するように,神話体系がまとまる時代と重なることも,その証になるだろう。
吉野ヶ里遺跡は,発掘が進むにつれ,邪馬台国の都に相応しい施設群を有していたことも明らかになりつつある。紀元240年には,帯方郡使が詔書・印授のための正式な冊封使として,邪馬台国の王都(おそらく吉野ヶ里)まで赴いており,卑弥呼が没したのは247,8年頃と言われるので,在位期間は60年以上,二十歳頃になったとしても,90歳近い長寿であったことになる。卑弥呼は故地伊都国に還ったともいわれ(近年,糸島で発見された平原遺跡が,卑弥呼の墓ではないかといわれる),東征したのは男王すなわちオシ系の崇神天皇ということになるのだろう。次章で述べるように,崇神東征は,南九州から熊野という南海道ルートであるが,アマ系の人たちは九州北部から丹後,尾張に至るように,山陰・山陽道のルートであって,両者は近畿において再会,伊勢神宮が誕生する。
北九州の八女丘陵にある古墳群のうち童男山古墳が徐福の墓ではないかという説も登場,最近,卑弥呼の鏡といわれる三角縁神獣鏡が極めて精度の高い魔鏡であると分かり話題になったが,これもユダヤ人の技術によるものと見れば納得できるし,その鏡の威力が,天照大神のご神体の八咫鏡になり,さらに,三種の神器という象徴化そのものがユダヤを継承するものなのである。
邪馬台国があった当時の絹織物の出土は九州北部北部に限られ,中国への朝貢品にもなったことから,邪馬台国が日本列島において唯一の養蚕・絹織物の国であり,秦帝国とのつながり,すなわち徐福集団によってもたらされた技術であることは疑いないだろう。偽書説もある史書に,卑弥呼は白山比咩神社の娘と書かれているのも,養蚕と絹織物につながる民族の出であったことを示すもので,中国でそこから太陽が昇るとされる宇宙樹"扶桑"は,そのまま日本についての異称になったが,ここに桑の文字が入っていることにも,養蚕民族との関係,徐福・秦氏などとの関係が窺える。
また,当時は大変な貴重品であった真珠を多量に朝貢していたことも知られているが,生産適地としては末盧国の範囲しか考えられず,すでにその地を支配していたということを示し,近代に入って養殖真珠の産地となった志摩地方に,的矢(マトヤ)湾があるが,マツ系が東遷する際に,末盧と名付けられた可能性も考えられる。さらに,邪馬台国は当時の先端文明鉄器の国でもあり,これによって諸国を服属させたと考えられるが,朝鮮半島南部で倭の領域であったとされる辰韓・弁韓が有数の鉄鉱石の産地であったといい,おそらく邪馬台国が諸国制覇するのに合わせて組み込んでいったと思われる。北九州の製鉄遺跡についての最近のC14調査では,そのいくつかは紀元前200年前後であったということなので,まさに,徐福渡来の時期と符合する。
邪馬台国のイメージをさらに深めるため,萩原秀三郎「稲と鳥と太陽の道~日本文化の原点を追う」による知見を,コラムに示しておく。
徐福の子孫(オシ系)は,卑弥呼の先祖になる伊都国支配下の一大国(アマ系)の人たちとともに,まさに,アマから来たことを示す地名の甘木(アマギ)の地に,ひとまず定着,やがて吉野ヶ里に出て,邪馬台国を開いたのが,神武天皇ということになるが,その時すでに,のちの,卑弥呼のように,アマ系の巫女的女王を戴く形で統治したと考えられる。天皇神話の祖アマテラス大神は,卑弥呼に対応するとされるが,その子がアメノオシホノミコトになっているように,アマ系とオシ系が結びつけられている。
奴国のところで述べたように,邪馬台国において,周辺諸国と同じ官職とは別に,付け加えるように置かれた職名にナカチの語が見えるのは,おそらく,徐福渡来の時に世話になり,古くから日本の代表していたと思われる奴国(ナカ系)を服属させた時に,とくに祭祀を扱う役職として,中臣氏を取り込んだものと考えられる。そのことが,天皇神話以前のすべての神々の祖たる,造化三神の第一つまり最高神が,アマ系とナカ系を合わせたアメノミナカヌシになっていることに反映していると思われるが,ここでも,第二のタカミムスビノカミが,徐福のことを指しているという説があり,終章で示したように,そのように見ると,そこから派生する神々の存在が矛盾なく説明できるのである。なお,第三のカミムスビノカミは,その他もろもろの神々をまとめる役割をしている。
改めて確認できるのは,日本神話の原郷に当たるのがアマ系を支配する伊都国で,徐福が渡来して滞在した場所が伊都国の日向(ヒムカ)の宮であったことは既に述たが,さらに驚かされるのは,糸島半島のすぐ前には能古(ノコ)島があり,宗像三神や壱岐・対馬と同じ角度で,玄界灘の方に線を延ばすと,そこには小呂(オロ)島があって,イザナギ・イザナミのミコトの国生みの地,オノコロ島は,この二島を組み合わせた名なのである。石井好が言うように,イザナに当てられた漢字伊邪那が,伊都国・邪馬台国・奴(那)国を合わせたものであるとすれば,もはや否定することもできないだろう。さらに,付け加えれば,伊都国の官のトップの職,爾支(ニギ)は,神武天皇の祖とされるニニギノミコトに対応するもので,徐福一族そのものを指しているに違いない。
ところで,中国の山東省で,道教が宗教的な体裁を整えたのが,ちょうど卑弥呼の頃で,卑弥呼が中国に使いを出したという話もあるというから,徐福の子孫の神武皇統において,日本神話の骨格がつくられたことが想像できる。道教における最高神は三清といい,元始天尊,霊宝天尊,道徳天尊の三神であるが,なんと,そのまま日本神話の造化三神の,天之御中主神,高御産巣日神,神産巣日神に対応し,神の名でミコトを表す際の漢字に"尊"を用いることなど,その影響は明らかだ。なお,道教でも,三清はじめ,三気,三才,三君,三界三十六天など,ユダヤ人と同じように,すべてを三の倍数で組み立てるというから,山東省が徐福の故郷であることもふまえると,両者は深く関わっていると考えざるを得ない。
当然のことであるが,離反した伊都国との緊張関係は続いたため,後の大宰府の地が邪馬台国の北の砦的な役割を持つことになり,伊都国はまた大陸の出先でもあったから,そのまま,日本における大陸への防衛線になっていったと考えられる。「魏志倭人伝」に記述されているように,倭国大乱後,邪馬台国は女王卑弥呼を立てて収めたとされているが,内倉武久によれば,この大乱の相手はまさにその伊都国だったという。この乱は,140年頃から180年頃にかけて続いたらしく,卑弥呼が女王になったのは決着した180年頃と思われ,この時から,邪馬台国が倭を代表する国,それも大国的存在になったと考えられる(それまでは中国とつながる伊都国のみ)。この内乱などで,多くのアマ系が東進し,卑弥呼の死去後は九州北部諸国全体の秩序も崩壊して,イト系民族も東進して,前述の平氏になった人たちであったと考えられるが,次章において解説する。
伊都国は大乱後衰えたとはいえ,油断ならない敵であり続けたため,「魏志倭人伝」で,伊都国から邪馬台国に至る行程が分かりにくくなっているのも,大宰府の地が通過できず,遠回りして行ったと考えれば氷解する。また,伊都国には中国風の名称の一大率(天子直轄の軍隊)がいたといわれるが,強国になった邪馬台国が,奴国はじめ諸国を服属させていくなかで,中国の権威を背景とする伊都国の反乱を抑えるために置いたものともいわれる。邪馬台国では,卑弥呼が神の託宣を受け,弟たる者が権力を行使したとされているが,その弟が神武皇統すなわち徐福の子孫で,卑弥呼が魏と円滑に話をすることができたのも,その存在を抜きには考えられないだろう。⇒コラム(「吉野ヶ里」こそ邪馬台国の都(1989年記))
大宰府については,近年,発掘調査が進み,朝鮮の扶余羅城と同じように,一つの街を城壁(土塁)で囲み,周辺から独立したものであるとされるようになった。「日本書紀」には,大宰府が,滅亡した百済の遺臣によって建設されたと記されており,百済の王族が,高句麗の王族扶余氏の分派であったことから,極めて自然のことだったと思われる。ただ,この地につくられるにあたっては,それ以前に,大宰府と同じような役割をするものがあったと考えられるが,それが,「魏志倭人伝」に指摘されている一大率であったという。「魏志倭人伝」には,「女王国は,北側に一大率を置いて厳しく検察,諸国はこれを畏れて気を使っている」と書かれており,女王国とは卑弥呼の国,すなわち邪馬台国であるから,伊都国の監視が最大の目的であったとみなされる。つまり,「魏志倭人伝」における,伊都国から邪馬台国の距離が,やたらに長い日数になっているのは,直接向かうことができず,諸国も気を使っていると分かれば,矛盾は無くなるのである。そして,邪馬台国をつくったのが,徐福の末裔と,徐福が連れてきた物部氏であり,その物部氏が扶余氏であると知れば,すべての話がつながるのである。念のためであるが,卑弥呼は,伊都国支配下の一大国の人間であり,伊都国は一大国によっても支えられていたから,邪馬台国との間の関係は極めて複雑かつ緊張したものであったのである。
倭国大乱後,男王では収拾つかず,女王卑弥呼を立てて決着したのが,その後の天皇制につながる日本独特の支配方式のルーツで,おそらく徐福一族の智恵であっただろう。もともと,ユダヤ人は,移動した先では,その地の言語を使うようになり,権力を狙うようなところは無く,権力をサポートすることで自らの集団を生き延びさせてきた。ユダヤ人はまた,民族が形成された当初は,養蚕も含む農耕民族であったことから,すでに九州北部に広がっていた稲作農耕民族と調和できたともいえよう。迫害を受けて流浪するようになったユダヤ人は農耕することができなくなり,神の名のもとに団結して民族を継続,やがて商業民族となって,シルクロードの担い手となり,さらに権力との関係で金融業に活路を見出し,それがまたヨーロッパでの迫害の理由にもなったが,押上の地名のところで取り上げた三井に限らず,オシ系,のちには,ハタ系というユダヤ人の血をもった人たちは,大航海時代に多数渡来したと思われるユダヤ商人に触発されて,江戸の繁栄をもたらしたことについても頭にいれておきたい。
ところで,統治の基本は,"技術"と"文字"と"神"といわれるが,徐福一族は多くの先端技術と神をもたらす一方,地域に溶け込むという特性から文字については出てこない。しかし,その後の現在に至る日本語表記は,世界でも例をみない平仮名・カタカナ混じりになっていて,それが漢字からつくられたものであるはいいながら,なぜそのような文字が簡単に生まれたのかについて,ユダヤ系秦氏のヘブライ文字の記憶があったからではないかという説があり,仮名をつくったのが秦氏出身の空海であるという伝説もそれを裏付けるものかもしれない。さらに,アメリカ大統領を迎えた時の,宮中晩餐会のメインディッシュが羊の肉であるということが,天皇家のルーツが,羊を食する民族であったことを示し,ユダヤ人であっても不思議ではないことを示している。
この章TOPへ
ページTOPへ
ここまで,徐福が引き連れてきた数千人の技術者集団について全く触れてこなかったが,中国がのちに朝鮮半島を管理すべく置くことになる山東半島の向かいの帯方郡あたりにいた有力な扶余氏一族こそ,最古の氏族物部氏だった可能性が高い。そこで,扶余氏とはどんな民族であったかを,とりあえず紹介しておこう。
Wikipediaをベースに述べると,扶余氏は,ツングース系で,現在の中国東北部(満州)を本拠としていた民族およびその国家で,夫余とも表記される。扶余が建国する以前のこの地にはツングース系の有力な氏族ながら,国をつくることのなかったワイ(濊)族が住んでいたと思われ,遺跡も発見されている。扶余氏に排除されたワイ族は,後述するように,南方の朝鮮半島に移動し,新羅人のルーツになったと考えられる。
扶余系騎馬民族が,南朝鮮を支配し,その後弁韓から日本列島に入り,大和朝廷の前身になったとするのが,江上波夫が提唱した騎馬民族制服王朝説で,現在では,かなり否定されているが,江上が,諸資料に基づいて,扶余系としたことは,それほど日本への影響の大きかった民族であるということで,物部氏が扶余系であることを補強するものといえるだろう。
扶余国は,その後も,三国時代から北魏の時代まで存在したが,494年,勿吉に滅ぼされた。夫余族の苗裔(北扶余)は豆莫婁国と称して唐代まで続いた。「魏書」や「三国史記」によれば,高句麗の始祖朱蒙も扶余の出身であり,衆を率いて夫余から東南に向かって逃れ,建国したという。言語学的にも,扶余語は高句麗の言葉に同じだったようだ。「三国史記」や「三国遺事」には,解夫婁が治めていたがのちに太陽神の解慕漱が天降ってきたので解夫婁は東に退去して別の国(東扶余)を建てたといい,太陽神,東征など,のちの日本の姿にもつながる。扶余氏はのちに高句麗を建国,さらにその分派が百済を建国することになるが,その際も,単に南方に下ったのではなく,中国から山東半島経由で朝鮮に渡ったといわている。扶余氏によって建国された百済が,ワイ族がベースの新羅と相容れないのは当然といえよう。
扶余の生業は,アワ・ヒエ・キビ等の雑穀を主とした畑作農業であり,遺跡では早い時代の層からも大量の鉄製農具が見つかるなど,農業技術や器具は,同時代の東夷の中で最も発達していた。また,金銀を豊富に産出する土地であり,金属を糸状に加工して飾り付けるなど,金銀の加工に関しては非常に高い水準だったとされる。紡績に関しても養蚕が営まれ絹や綵など様々な種類の絹織物が作られたほか,麻織物や毛織物が作られ東夷の中で最も発達していたとされる。物部氏は,これらの技術を日本にもたらしたと考えられる。

その後さまざまな職種を表す部全てを総括するような物部の名こそ,この時渡来した最も古い氏族に相応しいものだろう。物部氏は鉄器という先端的なものによって,旧来の銅器民族を制圧した軍事を司る氏族とされるが,鉄器はまた農業生産にも画期をもたらしたので,徐福一族が九州北部を一気に支配することになったのは言うまでもない。物部氏はさらに,道教を背景にしたオシ系による神話と祭祀をも差配する,つまり神道の主宰者にもなり,そのことが,のちに蘇我氏に滅ぼされる原因になるのである。かつて単なる装飾品のように考えられてきた勾玉が測量機器らしいこと,三種の神器のひとつの鏡が太陽の動きを測定するためのものらしいことなども,物部氏の先端性を示しているのではないだろうか。
邪馬台国に諸国を服属させる功績をあげたのも物部氏であったが,人数が多かったこともあって,渡来直後から東征始め,まず,遠賀川流域にあったと見られる投馬国(物部氏に関わる遺跡が多数存在する)を拠点にするが,投馬国が百済と関係深いことは,大和のマツ系の葛城氏の領域にある当麻(タイマ=トマ)寺が百済人の氏寺であったことでも推測できる。そこから,瀬戸内を東へ進んで,おそらく吉備で拠点を設け,そこに定着した人たちが吉備氏になる(後の大人物吉備真備も物部氏らしくあらゆる面に秀でていた)。
傍証として,吉備氏がヤマトタケル(オシ系)と密接につながっていたらしいこと,吉備の地もまた日向のような土地であり,付け加えれば,日向の国は勿論,前述の現在の埼玉県行田の忍(オシ)の地も日当たりよく開けた平野で,近畿以外ではほとんど限られる巨大な前方後円墳が存在していること(そもそも,邪馬台国の都と考えられる吉野ヶ里も日向の地であった)などが挙げられる。三橋健編の「日本書紀に秘められた古社寺の謎」によれば,天理市にある石上神宮は,「古事記」のなかで,伊勢神宮以外に「神宮」と称された唯一の神社で,崇神天皇の時代に創建され,布留御魂神(フルノミタマノカミ)を祭神とするように,朝廷の武器庫のような役割をして,神宮に対応する格をもった物部氏が管掌していたが,岡山県赤磐市,すなわち,かつての吉備国のなかにある石上布都魂(フツノミタマ)神社から勧請したものといわれ,吉備氏は,物部氏と同族であったということが明らかであろう。
さらに東進して大和に入るに際しては,自らの先端技術などを武器に,その地を支配していたマツ系の長髄彦を支えて行くことになり(「記」では長髄彦の妹と結婚),その地を邪馬台の語に対応するよう大和と名付けたのである。良く知られているように,邪馬台国周辺に現在でも残る地名群が,まるで転写したかのごとく,大和盆地に存在していることもその証となるだろう。
「日本書紀」でも,物部氏の祖ニギハヤヒが神武天皇より前にヤマト入りし,そのことを神武天皇も知っていたとされているので,実際に東征してきた崇神天皇を迎え,その支配を円滑に実現するのに貢献したといえる。大和における物部氏の拠点が河内国との境生駒山周辺であったことも,西側から渡来して力を確保するには当然の地であった。また,「先代旧時本紀」によると,中臣氏は物部氏の支配下にあったとされているので,ニギハヤヒが大和入りする時に,中臣氏が供奉してきたとされていることも裏付けになるだろう。後の話になるが,中臣氏は単に天皇側近として神事を担当していたようで,もう一つの神祇職斎部氏が職務を中臣氏に奪われたことも,物部氏の力が減じたことと関係するようであり,さらに,中臣氏を利用した藤原氏が台頭するにあたって,物部氏の秘密を受け継いだとされることにも,大きな意味があると考えられる。
物部氏は,ヤマトの語に深く関係し,すべて倭名にヤマトがつく神武朝に対応するが,崇神天皇の後の天皇からは,倭名にヤマトがつかなくなるので,物部氏の力が相対的に弱くなったと考えられる。しかし,崇神朝では,天皇にならなかった日本武尊というヤマトの語をもつ特別な存在があり,物部氏の力をどうしても借りねばならなかったことが伺える。藤井耕一郎「サルタヒコの謎を解く」で指摘されているように,ヤマトタケル伝説のルートとマツ系民族の展開するルートは大きく重なっていて,クマ系民族はじめ,国譲りしたはずのマツ系民族による反動を抑えることがその役割だったと思われる。
大和で邪馬台国時代の前方後円墳が発見されたとして,邪馬台国が大和にあったとする言説があるが,規模は小さいし,今まで述べて来たように,邪馬台国が北九州にあった神武皇統時代に,すでに物部氏が大和入りをしているので,神武東征が実は崇神東征であったとみれば,全く矛盾なく説明できまよう。さらに,前方後円墳が最も多く残っている茨城県,すなわち常陸の国はまた,那珂川があるように,ナカ系の人たちが多く到来した地でもあるが,邪馬台国が奴国を服属させて以降,物部氏の東遷にナカ系の人たちが大いに協力したと考えられ,また,後に藤原氏の神社とされる鹿島神宮が実は物部氏のものであったということも当然といえよう。
付け加えれば,(西都原,吉備,さきたまなど)オシ系の陵,大和でも天皇陵は大規模なものが多いのに対して,物部氏のそれは,数は多くとも規模は小さい。
蘇我氏に討たれて後も,わずかながら物部姓が残っていて,日本史上の大学者の一人で,中野剛志によれば,徹底したプラグマティストであったという荻生徂徠の本姓は物部氏であったし,秋田出身の大土木学者物部長穂は自らの出自を強く意識していた。物部氏の流れの最初の姓は石上氏であり,その他,穂積,内田,大宅氏などが直系といわれる。穂積氏については,継体天皇に仕えたものに,穂積押山という人物がおり,まさに,オシ系としての役割を果たしたのではないかと思われる。
全国の姓の分布からみると,藤原氏から派生したことで多いのは当然のような"佐藤"姓に次いで多い"鈴木"姓は,その本家が熊野で,物部氏直系の穂積氏をルーツとしており,家紋は実に,オシ系徐福を表すというタカミムスビの神から派遣された八咫烏であることから,その通りであると考えられる。その分布をみると,東海,関東,東北に広がっているが,西日本には極めて少ないことが,蘇我氏に討たれたことを,そのまま反映している。とくに,三陸方面への展開が知られ,気仙沼の古舘鈴木家は,1675年,紀州熊野から鰹釣り溜漁を伝え,のちに漁業や醸造業など,時代に合わせた多角的な家経営を展開し,江戸時代には,鹿折金山などの金山開発や砂金徴収を任され,明治時代には大谷鉱山の再開発も手掛けている。そして,気仙沼地域の言葉が独特で,ケセン語とまでいわれて,古代ヘブライ語との類似も指摘されているが,(前述のように)神武東征,つまりオシ系の上陸地になった新宮には,古代ヘブライ語が今も残っているということなので,そのつながりも明らかである。
いずれにしても,"鈴木"姓が,2番目に多いことは,それだけ広く,様々な技術を各地に伝え,(農水産業の生産方法も含めて)現代の技術立国日本に繋がって行ったことに対応しているといえよう。ちなみに,歴史的人物から,鈴木姓を拾ってみると,異色の国学者鈴木朖,ビタミンを発見した鈴木梅太郎,仮名草子の先駆者鈴木正三,音楽教育スズキ・メソッドの鈴木鎮一,禅を世界化した鈴木大拙,錦絵を創始した鈴木春信,労働運動指導者鈴木文治,「北越雪譜」の鈴木牧之,「赤い鳥」の鈴木三重吉と,幅広い分野に人材を輩出している。
卑弥呼が死すると,長年対立してきた伊都国との間の歯止めがなくなって,本格的戦争になり,アマ系を支えるオシ系という邪馬台国の根幹が崩れ,周辺諸国も巻き込んで,それまでの九州北部の国の間の秩序が崩壊,「魏志倭人伝」によれば,倭国は,弟王を立てるも収まらず,卑弥呼の宗女だったという臺與(台与・トヨ,235年生まれで13歳だったという)がたって,ようやく決着したというが,以後,中国の史書からは,邪馬台国はもちろん,他の諸国の記述も消えてしまう。オシ系とアマ系は別離を余儀なくされたのである。
このことから,弟王とされるのが,オシ系の崇神天皇,いわゆる神武東征伝説の当事者で,次節で述べるように,南九州ルートで東進し,大和に至ったのに対して,トヨの登場で収拾したとあるのは,アマ系は,トヨの名が示すように,日田を経由して,豊の国(のちの豊前・豊後)に至り,定着したものと考えられる。そして,豊の国に向かわなかった,イト系率いるアマ系の民は,オシ系とは全く別に,北ルートで,丹後に至り,そこで,大和に東征してきたオシ系崇神天皇と連絡がつけられて,両者は再び結ばれることになるが,アマ系は,伊都国の末裔でもある故,様々な曲折が,アマテラスを祀る伊勢神宮定着までの転変に反映することになる。
第4論で述べるように,豊の国は,新羅からハタ系応神天皇が渡来した時の受け入れ地となり,秦の国がつくられるとともに,応神を祀る宇佐八幡宮が創建され,応神の妃となったアマ系が宗像三女神でとされることになり,九州に残ったイト系・アマ系は,のちの倭寇の核になって行ったとみて良いだろう。>前期倭寇
イト系率いるアマ系の民は,現在の地名にもその名が示される,板付から,糸田を経て,山陽道に向かい,すでに述べたように,イト系の末裔平氏の氏神・厳島神社は,もとは,伊都岐島と記されていたように,まさに,伊都国から来たことを示し,すぐ近くには。アマ系の海部郷,阿満もあるのである。そこから,一団は,山陰に向かい,イト系の到達を示す但馬国糸井郷を拠点に,アマ系が,丹後の地に広く展開,もう一団は,紀伊国伊都郡を経て,伊都にも通じるという伊勢に至り,丹後のように,アマ系は尾張国海部郡周りに展開,ヤマトタケルノミコトを祀る熱田神宮大宮司を代々務めることにもなる,古代における大豪族の尾張氏の祖になるのである。イト系の本体が,さらに東進して到達したのが,伊豆であり,坂東平氏の拠点になったのである。丹後の国は,浦島太郎伝説の地であり,半水上集落と言っても良い独特の景観をした伊根があるなど,まさに,海洋民族の国である。>桓武平氏
唐突であるが,今年(2022年),阪神タイガースを引退して話題になった糸井選手に,超人伝説があるのは,その野球の能力以上に,体躯,風貌のなせるわざと思われる。そこで,彼の出身地を調べてみたところ,京都府の日本海岸の与謝野町ということで,その西隣は,兵庫県の出石と朝来,まさに,但馬国糸井郷の地で,現在も糸井の名のつく施設等が分布している。糸井選手には,伊都国の王族の末裔,桓武平氏の血が流れているのだろう。桓武平氏の代表平清盛や,自ら桓武平氏と名乗った織田信長らは,八頭身の大柄な体躯であったといわれ,糸井選手は,その姿を彷彿とさせているのではないだろうか。
ところで,丹後には,元伊勢神宮なるものがあるが,崇神天皇39年の時に,アマテラス大神を,丹波の吉佐の宮に遷したという伝承になっているものの,アマ系の地としては,当然のごとく,卑弥呼を祀っていたと考えられる。崇神天皇紀では,大和で疫病がはやった時,土地の神ヤマトオオクニタマとアマテラスを同じ宮殿に祀るのは良くないということになって,皇女のトヨスキイリ姫に命じて,アマテラスを北方の笠縫に遷し,次代の垂仁天皇が,ヤマトヒメ命に命じて,大和から連れ出し,近江・美濃など各地を遍歴した後,伊勢の五十鈴川のほとりに定着したとされていることから,オシ系とアマ系は再会はしたものの,邪馬台国の時代をそのまま再現するには無理があったと思われる。
丹後にはまた,籠(コモ)神社という神社があるが,太秦の蚕の社と同じく,秦氏の氏神であったといい,アマ系が,ハタ系の応神天皇渡来時に,天皇を支えたことを思えば当然であるといえる。その籠神社のもととされる,真名井神社には,豊受大神が祀られていたが,この神こそ,卑弥呼の後を継いだ台与(トヨ)であり,伊勢神宮の外宮が豊受大神宮といわれることに対応,応神朝になって,台与を,卑弥呼と対等な神とすることで,ようやく修復が成り立ったともいえ,ここにも,神社体系を確立させたのが秦氏であったことが示されるといえる。伊勢外宮の祭祀に長く関わった磯部氏(渡会氏)は,磯城県主の流れをくむ丹後国造の支流ということも,補強材料になろう。

上古代に后妃を輩出した尾張氏は,中央で政治力を発揮したことがほとんど無いにもかかわらず,同族を名乗る諸氏が極めて多い,地方豪族としては特異な存在で,西方から来た海人ではないかということまでは共通認識になっているようであるが,あまり研究されていない謎の氏とされている。そんなところに,澤田洋太郎が「天皇家と卑弥呼の系図」の冒頭で,尾張氏の系図が,海部氏のそれと似ているばかりでなく,その何れにも,卑弥呼を表すとみられる日女命の名のあることから,同族であると指摘,前項の図も,それに基づいており,尾張の地は,伊都国アマ系の人たちが到達した最後の大拠点であると推定したのである。それが成り立つかどうか,古代氏族の研究シリーズの宝賀寿男「尾張氏」のページをめぐりながら,検証してみよう。
確実なところでは,継体天皇の妃で,安閑・宣化天皇を産んだ目子媛が尾張氏の出であり,壬申の乱に際しては,海部氏(アマ系)に養育された大海人皇子を全面的に支援して,天武天皇を誕生させ,熱田神宮宮司家としては,近代まで続くのであるが,偽書説があるとはいえ,「旧事本紀」の「天孫」の部では,アマテラス,アメノオシホ,ニギハヤイの次に,尾張氏の系譜,その次に物部氏の系譜を示しているのは,すでに述べたように。アマテラスすなわち卑弥呼を戴く,アメノオシホすなわち徐福(オシ系)の末裔の国邪馬台国とすれば,アマテラスに直結する尾張氏が,徐福を支えて渡来した物部氏より上位に置かれているのも当然であろう。そして,尾張氏の直接の祖とされる成務天皇時代の尾張国造の乎止与(オトヨ)命は,小豊とも書かれることから,卑弥呼の後を継いで豊の国をつくることになった台与の子孫であることを示している。
上古代に后妃を輩出し,平安時代にも,尾張氏に対して,容貌端正な者を采女を,毎年1名貢進するよう命が出ているように,卑弥呼以来,アマ系の女性の存在は際立っていたのだろう。6世紀前半になって,突然,尾張に巨大な古墳が一基だけ出現するが,時期から見て,その断夫山古墳(151mで65位)は,継体天皇の太田茶臼山古墳(226mで21位)との関係からも,妃目子媛の陵と考えられ,尾張氏が,継体天皇の実現に如何に大きく貢献したかを示している。壬申の乱に際しての尾張氏の支援は,美濃国の野上(伊富岐神社隣)に行宮を提供して,不破の関(関ヶ原)を抑えることができるようにしたことが大きいといわれるが,そこには,尾張氏一族の伊福部氏がいた(イブキに対応すると思われる姓。現在,伊福部姓は,全国で数十名しかいないが,著名人は数名おり,その比率は異常に高い)。
尾張氏の系譜のうち,とくに難解なのが,オシ系高倉下につながる神統譜とされているが,これを,オシ系の崇神東征後,尾張を拠点とするアマ系に再会したことを表すものとみれば納得いくのではないだろうか。伝承では,尾張大海媛が,崇神天皇の妃になったことが記され,これこそが,再会の実であったろう。そして,大海媛の生んだ娘の一人が,前後関係はおかしくなるが,崇神天皇の同母姉(妹)で,卑弥呼その人ではないかともされる倭迹迹日百襲姫の同人か近縁とみられるのも,再会説を補強することになろう。ついでながら,初期大王(いわゆる欠史八代)の后妃伝承をもつのは,それこそ,邪馬台国時代に,オシ系の王がアマ系の女王を戴いていたことを示すものだろう。⇒コラム「卑弥呼の倭迹迹日百襲姫命説の妥当性について」
とはいえ,天武天皇後,政治的な力は発揮されず,熱田神宮の神階授与も,平安時代になってからで,822年,従四位下が初見で,859年には,正二位と昇叙,延喜式で,ようやく正一位の名神大社となっており,それでもなお,尾張一ノ宮ではなく,三ノ宮に留まっているのである。この熱田神宮に関わるのが,ヤマトタケル伝説であるが,「古事記」には,ヤマトタケルが東征の途上,伊勢から尾張に至り,国造の祖・美夜受比売(ミヤズヒメ)と結婚しようとしたが,帰還後と思い直し,科野(シナノ)から戻って結婚したとある。いずれにしても,ヤマトタケルの東征に,尾張氏が大きな役割をしたことを示すものである。また,東征において,のち壬申の乱同様,伊吹山が特別な場所であったことは言うまでもない。5,6世紀に,尾張東部丘陵地に,大型の前方後円墳が多く築造されるが,海産物や海上輸送に貢献した尾張氏のものと考えられる。
尾張氏は初期段階で,北部や美濃の丹羽県君氏と通婚して,開発に努め,次第に南下して,当時,海に突き出た岬状の熱田に達し,到達点としての意識もあって,熱田神宮のもとを創建したと考えられる。前項で述べた,アマ系の到達地の丹後は,もともとは広大な丹波の国の一部であったこと,丹波はタニハの当て字で,そのまま,丹羽姓にもつながるとみられることから,丹後に留まらなかった,イト系,アマ系の人たちは,そのまま東進,近江を経て,関ヶ原,伊吹山方面に至り,南下していったと考えるのが自然だろう。そして,イト系の人たちは,伊豆に向かったのである。大和の尾張氏の分布状況からみて,尾張氏は,大和から尾張に遷ったのではなく,尾張から大和に移住するものがでてきたということになろう(すでに述べたように,崇神東征前の大和の地はマツ系の人たちの支配地であって簡単には入れなかったとも考えられる)。
ところで,熱田神宮は,かつては尾張造という,回廊を有する左右対称の,朱色に塗られた建築群であったというから,アマ系としては,自分たちの従ってきたイト系の氏神厳島神社をまねたようなものであったのではないだろうか。
ずっとあとの水軍のところで述べるが,伊勢平氏の末裔ともみられる九鬼嘉隆は,尾張氏の末裔であるという(伊勢あたりは,イト系とアマ系がなお一体であったらしい)。赤い彩色と紋様を持つパレス式土器は,弥生時代後期の尾張地方を代表,三河,尾張,伊勢一帯に広がる,尾張氏,海部氏に関わる重要な土器で,東海地方に多い古墳のスタイルや,多孔銅鏃との関係も指摘されており,土師氏との関係,のちの陶器生産との関係も気になるところである。
いずれにしても,尾張氏の存在が,のちのち,この地域での大武将の輩出につながるものの,日本のほぼ中央に位置しながら,一度も,首都にならなかったことに関係があるように思われる。
卑弥呼没後の大動乱で,諸国が崩壊し,それぞれが東進することになるが,アマ系を戴くオシ系という形だった邪馬台国では,イト系の支配下にはいったアマ系とは一旦離別し,彼らが瀬戸内から,近畿,山陰方面に展開する北ルートをとるのに対し,オシ系は,神武東征神話で知られているように,南九州から熊野へと,南ルートをとることになる。
邪馬台国,すなわち神武皇統の時代はその南の狗奴(クナ)国との紛争が絶えなかったというが,その間に,そのクマ系民族のなかから,大伴氏という,東征を警固してくれる強い氏族を味方につけることに成功している。大伴氏も,もとはクマ系そのものを示す久米氏であったから,大伴の名は,まさに大いなる伴(警固者)という意を表して,神武皇統によって与えられたと考えられる。ヤマトタケル伝説は,おそらく邪馬台国が狗奴国との長年にわたる抗争の末,ついに狗奴国を征圧したことを伝えるもので,その結果,いわゆる神武東征,実は,崇神東征は,まず,九州西部を南下し,徐福伝説の代表地の一つ南九州の串木野から霧島を経て,日向に至ることになる。
そのルートを詳しく見てみよう。吉野ヶ里の地,現在の佐賀県から九州西海岸を南下して行くと,まるで目印となるように串木野の冠嶽(徐福が冠を納めたからこの名がついたといわれ,後述の四国祖谷の剣弥山あるいはキルギス・オシのソロモン山のような存在と言える)が見え,そこから川内川を遡って,霧島の高千穂峰(霧島神宮がかつてあった場所で,山頂には,坂本竜馬が引き抜いてその豪胆ぶりを示した天の逆鉾もある)に至る。天孫降臨したと伝えられるクシフル山は宮崎県北の高千穂とされているが,実は,日向(ヒムカ)の地は,伊都国(糸島)であったことが判明しつつあるので,あまり気にしなくて良いだろう。東の宮崎に下った麓には,神武天皇の名を示す狭野神社があり,近くの曽於市末吉の深川熊野神社には,神武東征と関係すると思われる奇習「鬼追い」が伝えられている。そこから,押田(古くからの村に一旦居を定めたらしく「オシ」系地名になっている)に出て,宮崎県の大淀川に沿って東へ向い,神武天皇が東征前に宮を営んだとされる地に建つ宮崎神宮の場所に至ったと考えられる。鹿児島県から宮崎県にかけて,串木野,串良,串間とクシのつく地名が連なり,神武東征伝説での上陸地熊野にも串本があることも,そのまま東征ルートを示している。
とくに強調したいのは,串木野の冠嶽で,1990年頃に高野山の僧が新たな寺を開創したが,その伽藍建設工事に多くのイスラエル人が参加していたことからも,徐福がユダヤ人であったことは疑いなく,ユダヤ系の秦氏の出身という高野山の祖空海も,聖徳太子以上の頭脳の良さが伝説化しているように,ユダヤ人の血を引いているといわざるを得ない。なお,若狭の徐福伝説の地は冠島で,串木野の冠嶽に対応するものだろう。
長田夏樹「新稿・邪馬台国の言語~弥生語の復元」によると,卑弥呼について,当時の中国音なら"ヒムカ"になるといい,伊都国の日向そのものということになる。神話の国とされる日向国(今の宮崎県)も卑弥呼に由来,卑弥呼の娘臺与(トヨ)の名を示す豊の国とも繋がっていたと考えら,熊襲征伐時に誕生した豊国別皇子が日向国造の祖になっている。この,日向国と豊国との繋がりが,後述の,崇神皇統と応神皇統への政権交代が円滑に行われたらしい理由になるのではないかと思われる。西都原には皇室司祭賀茂氏の荘園があったし,物部氏が支配していた吉備を,物部氏を討滅した蘇我氏が再開発したこともあったらしく,蘇我馬子が聖徳太子とともにまとめたとされる「天皇記」「国記」は,蘇我氏支配の正当性を確立するための創作された歴史で,この段階で,崇神朝の故郷日向国と応神朝の故郷豊の国が一体のものになるようになされたことも含めて,のちに藤原不比等が藤原氏支配の正当性を確立すべく「古事記」「日本書紀」をまとめたモデルになったと考えられる。
菊池秀夫「邪馬台国と狗奴国と鉄」によると,弥生時代末期に九州の北部,続いて中部に鉄器が急速に広がり,やがて中部が北部を凌駕,その後畿内に広がるとともに,九州の鉄器が急速に衰退したということなので,まさに鉄器民族の(オシ系)神武東征伝説に対応するものといえる。ついでながら,九州中部の鉄器を担ったのが狗奴国で,魏志倭人伝で狗奴国の官職とされる狗古智卑狗(ククチヒク)は,おそらく鞠智彦(ククチヒコ),すなわち菊池氏の祖のことではないかという。邪馬台国は長年にわたる狗奴国からの攻撃に対して支援を求めるため,魏に朝貢,魏も狗奴国が呉(マツ系のところで話した春秋時代の呉ではなく,三国時代のものあるが,民族的には近いと思われる)と連携していたことから,邪馬台国を積極的に支援したらしい。
いわゆる倭国大乱は鉄器普及によって起こり,その鉄器によって決着,さらに,鉄器を得たからこそ東征が可能になり,大和を制圧したと考えられ,ずっと後の鉄砲伝来によって,戦国時代に決着をつけた織田信長の話にも近い。邪馬台国が女王国連合であったように,狗奴国もまた九州中南部一帯を抑えていた国家であったと考えられ,両者の境界部から多数の鉄器製造遺跡が発掘されることから,熾烈な戦いをしていたことが分かるが,大型武器は,魏から技術支援を受けた女王国連合に集中していて,狗奴国は阿蘇山に鉄鉱石産地を有していたにも拘わらず,突如消滅してしまったといい,ヤマトタケル伝説にもつながっていると考えられる。
「日本書紀」には,神武天皇(実は崇神天皇)の大和入りに大きく貢献し,日本最古の歌を残した氏族として久米(来目・クメ)部が出てくるが,焼畑を基本としていた久米部は,前述したように,狗奴(クナ)国の民族クマ系であった。神武皇統が狗奴(クナ)国を制圧した際に,天皇に服属してその護衛を務めることになった久米氏の一派には,大いなる伴を意味する大伴氏の名が与えられたのであり,両氏は同族である。大伴氏の存在は,西都原との間の障害が無くなった上,軍事サポートまで得るようになって,いわゆる神武東征(実は崇神)が可能になったことをそのまま示しているといえよう。
大和の宇陀の地を拠点にしていた久米氏が集会施設を持っていた地の名が忍坂(オシサカ)であることから,そこが(オシ系)天皇家の大和支配の出発地になったと考えられる。この久米氏と,沖縄の久米島,琉球王国に明の皇帝から下賜された現在の福建省の職能集団の人たちが住んだのが那覇の久米村であったこと,さらには,道教のシンボル仙人の話の"久米の仙人"伝説などとの関係についても,解き明かすことが期待される。
さて,卑弥呼の死後,弟が王として立つもおさまらず,娘臺与(トヨ)を立てて再び収まったといわれるが,この時点つまりAD300年頃,邪馬台国の話が消えてしまうのは,臺与(トヨ)が収めたのは豊の国であったこと,卑弥呼の弟がいわゆる神武東征をした,つまり邪馬台国自身が東遷してしまったことによると考えられる。その人物こそ崇神天皇で,瀬戸内海経由で河内に至るも大和の地を支配していた長髄彦に阻まれ,やむを得ず大迂回し,最も有名な徐福伝説を有する現在の熊野新宮に至るのである。
崇神天皇の登場するのが邪馬台国の終わった頃だということ,その倭名ハツクニシラススメラミコトは神武天皇のそれと全く同じであること,ここには初代という意と同時に,統べるという意につながるスメラという語,さらにミコトまであわせて古代ヘブライ語ではないかということばかりか,徐福渡来のところで述べたように,(秦の)始皇帝とほとんど同じことを意味していることなどを知ると,神武東征は,実は崇神東征であった考えれば全て氷解する。徐福という名は,おそらく一個人でなく代々引き継がれる(オシ系)族長名であり,神武天皇から崇神天皇の前までは邪馬台国の時代であったということになろう。ついでながら,新宮の友人から聞いた話では,当地で現在も歌われている漁民の歌の詞は,古代ヘブライ語でしか解釈できないものということなので,徐福ユダヤ人説の裏付けになるのではないだろうか。
倉塚曄子「古代の女」によって補足すると,上古の日本では,ヒメミコ制と呼ばれる,霊能を持つとされた女性とその兄か弟が一体となって国(地域)を支配する体制があって,史料で明らかになっているヒミコとその弟王がその典型であった。しかしながら,大陸と対等な関係となる古代国家を成立させるためには,姉妹,すなわち女王の聖なる支配力から,兄弟,すなわち男王の実力による支配への集中,一元化が必要になってきて,おそらく,ヒミコ亡き後の争乱はそれに対応するもので,女王の方は娘が継いだようであるが,行方知らずとなった弟の男王,つまり崇神天皇は,大和に東征して,支配の一元化を図ったのではと考えて良いだろう。
崇神天皇は新宮から大和に向かったが,早くから大和入りして,マツ系の長髄彦を支えていた物部氏が,崇神天皇に呼応して長髄彦を裏切って国譲りが実現,ここに,大和の地で神武皇統を引き継ぐオシ系の崇神王朝が始まる。その記憶は,クマ系の久米氏が支配していて大和制覇のポイントとなった地忍(オシ)坂に刻まれている。前述したように,アマ系の卑弥呼の娘臺与(トヨ)は,後にその名によって呼ばれる豊の国に移ってしまったようで,のちに,新羅からハタ系の応神天皇が渡来するに際し,豊の地は重要な役割をし,宇佐八幡宮が置かれることになる。ついでながら,アマテラスは,子のアメノオシホノミコトに,'以後この鏡をワレと思って祀れ'と言って,宝鏡を授けたということだから,(アマ系の)卑弥呼が(オシ系の)崇神天皇に遺言したものともとれよう。
ところで,邪馬台国の畿内説が相変わらずまかり通っているのは,前項で触れた菊池も指摘しているとおり,邪馬台国東征のスピードが早すぎて,九州説の証拠が見つけにくいのが要因のようである。崇神天皇による大和支配が如何に短時間になされたのかは,銅鐸のほとんどが大和の外側の地(おそらく出雲民族による支配圏域)で埋められた状態で発見され,大和の地には残っていなかったことからも(実際,奈良時代に,たまたま大和で見つかった銅鐸についてもすでに当時の人たちには珍しいものと見られただけで過去のことは忘れられていた),あわてて祭祀用のものを敵方から隠そうとしたことが窺える。あまりに短時間に東征がなされたため,遺跡の年代からは,北九州か畿内かを特定できないでということなのだろう。中国の文献からも,以後,倭の朝貢の記事が長期にわたって消えてしまうのは,倭王が大和という遠隔地に行ってしまったことに加え,朝貢先の地であった朝鮮半島の中国の出先帯方郡が314年に高句麗によって滅ぼされてしまい,現実に朝貢が不可能になってしまったことにもよるのだろう。
物部氏の節でも述べたが,長髄彦については,風貌異様であったという伝説からも,全く異なる民族,春秋の呉国からのマツ系の流れであったと考えられる。末盧国のところで述べたように,ナカ系,オシ系より前に東遷して大和に国をつくったのがマツ系の民と考えられることからも納得できる。松のつく主要地からみたマツ系の動きによっても示される通り,彼らこそが国譲りした民族だったと思われ,長髄彦の別名がトミヒコと言われるように,投馬国にもつながる。敗れたマツ系の末裔の豪族として葛城氏が大和西南部を占めていたが,そのルーツの末盧国の朝鮮側がのちに百済に取り込まれたこともあって,百済からの渡来者も多く,その精神的な核となる当麻寺はトマに当てた漢字で,やはり百済のルーツにつながる投馬国の名残ともいえよう。
記紀に書かれた崇神天皇以降の宮都や陵墓の位置が,大和における崇神皇統の支配の確立プロセスと矛盾が無いのに対して,それより前の(神武皇統の)天皇のそれが,全く異質なばかりか,服属させることができていない葛城氏の支配していた領域にあるように書かれていることからも,崇神天皇後に,神武皇統を記憶すべく,適当に配して築造したのが明らかで,神武天皇は大和国の前段階の北九州の邪馬台国の創始者としてのハツクニシラススメラミコトだったのである。崇神天皇以降の古墳時代になって,大和に突然巨大な鏡が出現したということも,その証左になるだろう。既に述べたように,崇神天皇以前の天皇の和名にはほとんど倭(ヤマト)の文字が入るのが,以後無くなるのは,倭が九州北部にあって大陸から認知されていた邪馬台国を表すものだからということでもあろう。
さらに,案内役として登場する高倉下や八咫烏などもマツ系に近いらしく,天孫降臨(徐福渡来時)のサルタヒコと同じような存在であったと思われる。高倉下は,強力なマツ系豪族の祖とされており,八咫烏というのは,鳥をトーテムする一族ということで,神社の鳥居のルーツが中国南部の稲作民族が村の入口に鳥を載せた門を置いていたことに由来すると考えられることから,マツ系(呉太伯)の子孫が日本に亡命してきたのと前後して渡来してきた一族であると考えられる。繰り返しになるが,神社体系のなかで独自の位置を占め,天皇家と極めて近い上賀茂神社・下鴨神社に結束している賀茂(加茂・鴨)氏は,マツ系の末裔で朝廷と敵対していた葛城氏と同族とされているので,八咫烏一族と同じように渡来し,天皇に服属を誓ったことから特別扱いを受けることになったと考えられる。賀茂のもとが(鳥の)鴨であること,葵祭で有名なように,水田と一体の植物の葵をシンボルとしていることからも間違いないだろう。
邪馬台国が東遷して大和国になったことは,朝廷が対馬,壱岐ほかの国々を以前と同様に支配していることや,大和の地名の多くがその位置関係とともに邪馬台国周辺の九州北部の多く地名を転写したものではないかという指摘からも証明される。ついでながら,紀伊熊野の地名が出雲国に転写されていることからは,この地にいた諸氏族も出雲の地に封じ込められたことを意味するのかもしれない。崇神朝がかつての邪馬台国の名残をとどめようとし,後述する応神朝に登場する宇佐八幡宮の地図上の位置と伊勢神宮のそれが類似していることも注目される。
東征に際して,天皇を親衛したといわれる大伴氏は,日向国のところで述べたように,クマ系の久米氏が神武皇統に服属を誓ったことで,大いなる伴の名を与えられ,神話では,その祖がニニギノミコトに随伴した天忍日命となっているように,アメ・オシを含むまさに皇族なみの扱いを受けることになった氏族で,熊野に入って以降,この地を古くから支配していた,やはりクマ系の紀氏と連携して,大和平定に奮闘,応神皇統を雄略天皇が確立すると,急に勢力を伸ばして全盛期を迎える。後に,大伴金村が継体天皇を迎えたのも,当然の役割であったといえ,早く没落していった紀氏と違って,以後も勢力を保つが,蘇我氏,さらに藤原氏の登場とともに,天皇直属の軍属として目の敵にされ,抵抗した大伴家持は強く抑え込まれて,その鬱憤を万葉集編纂にも結びつけるなどしたが,以後,衰退を続け,後に有能な伴善男が出るものの,応天門の変で追放されてしまい悲劇の一族になってしまう。
ついでながら,大和の豪族和爾氏は,そのルーツが神武皇統時代にあり,継体天皇の前まで天皇家に妃を供給し続けながら,男子についてはほとんど事績がないため謎の豪族とされているが,前述のように,卑弥呼の末裔のアマ系は全く別になって東進していることを踏まえると,それとは別に,崇神東征に際して,すでに妃の位置を占めていた一族を伴って来たと考えれば辻褄が合うのではないだろうか。継体天皇以後,諸豪族が女性を宮廷にいれて権力を争うようになったことで,妃を提供できなくなってしまうが,一族からは,後にも,女性では古代の美人の代表小野小町,男性では,政治的には無力でも,柿本人麿,小野道風,山上憶良ら独特の役割をする人物が輩出する。本拠としていた若草山も和邇氏に相応しい場所ではないだろうか。
崇神天皇はマツ系を代表とする出雲族を支配下に置くべく,自らの持てる技術を誇示することを兼ねて,壮大な出雲大社をつくることで納得させたと言われる。その上で,自らの神を祀る伊勢神宮を整備するわけであるが,良く知られているように,様式は全く異なるものになっていて,神との関係も陰陽の関係に置いている(神無月と神有月など,国譲りに対して神譲りで返したということか)。また,先に大和入りして,崇神王朝の実現に貢献した物部氏に対しては,あらゆる仕事を管轄する地位を与え,その祖とされる饒速日尊の正式名称を天照國照彦天火明櫛玉饒速日尊とし,頭の部分に天皇の祖と同じ天照をつけることで,納得させたようだ。
伊勢神宮の地が決着するまでに曲折があり,近畿各地に元伊勢なるものが残っているが,そのなかで,第2論で述べたアマ系の東進の最後の地の丹後の元伊勢が重要で,東征してきた崇神朝と何らかの形で再会,再び,卑弥呼との神話を確認する上で,両者の間に,確執のあったことが窺え,それ故,近畿各地を変遷,大和の地から遠ざけるということを前提に,ようやく現在の地に落ち着くことになったと思われる。同時に,丹後半島付け根に位置する籠(コモ)神社は,のちの応神朝の蚕の社にもつながるものとみられ,伊勢神宮と反対の役割をしていることが考えられる。
補足すれば,スサノオノミコトと天照大神の衝突は,マツ系の多神教とオシ系(ユダヤ人)の一神教との衝突で,岩戸伝説を経て,形式的には一応一神教とするも,実態は多神教を存続させ,つまり出雲に神譲りして国譲りされたので,以後,物部氏は軍事力その他諸技術以上に民間信仰を取り仕切ることで,天皇による人民支配(親政)を支えて行くことになる。神道の矛盾は始めから組み込まれていたわけで,後の天皇をして祟りを恐れさせ,また,多くの呪詛事件が発生する要因にもなるのである。伊勢神宮のご神体は八咫鏡で,その裏面には古代ヘブライ文字が刻まれているといわれ,参道の灯篭にはダビデの星がついていることなどからも,その内実が想像できる。ついでながら,菊の御紋について,メソポタミア由来など諸説あるが,とりあえず単純に太陽を表したものと見てよいと思われる。
いずれにしても,天皇にとって,熊野詣は,祖先が上陸した地点として,吉野がかつての吉野ヶ里の代替であるように,重要な場所になっていったと思われる。
この章TOPへ
ページTOPへ
崇神王朝以降しばらくの間,大陸からの直接的な影響は無かったが,朝鮮半島に,百済や新羅が建国されると,以前からあった高句麗も含めた三国間の力関係に巻き込まれるようになる。そこで,小和田泰経「朝鮮三国志 高句麗・百済・新羅の300年戦争」に従って,朝鮮半島情勢を,簡単に整理しておこう。
紀元前100年頃,漢の武帝が抵抗続ける衛氏朝鮮に侵攻して制圧,4つの郡を置いて統治し始めたが,朝鮮民族の抵抗が続いて後退,楽浪郡と玄莵郡の2郡に再編成するも,紀元前75年には北側にあった玄莵郡が廃止に追い込まれ,その地を管理していた高句麗が独立した国になった。
その高句麗は,北方で勢威を振るう物部氏,すなわち,のちの満州にもつながるツングース系のなかでも有力な氏族であった扶余の拠点で,彼らと抗争するうち,その扶余から亡命した王族を受け入れ,典型的な騎馬民族国家として成長する(前述したように,江上波夫の騎馬民族制服王朝説のキーになっている)。その後は,漢,その後の魏から圧力を受けるも,朝貢などによって避け,あるいは鮮卑や燕の侵攻を次々受けるも,それらを跳ね返して,朝鮮北部の広域を支配し,したたかな国として存在し続けて行く。
高句麗で391年に即位し,領土拡大に最大の功績のあった広開土王は,412年の死後,業績を称えて建てられた広開土王碑が有名であるが,碑文には,倭(日本)と組んだ百済が反抗してきたため,新羅と組んで両者を撃破したことが記されている。
現在の,いわゆる北朝鮮は,かつての高句麗の範囲であり,同じ朝鮮民族とはいえ,物部氏と同じ扶余氏の末裔の多いことも当然で,それが,北朝鮮の技術力を示すとともに,ルーツを同じにするかもしれない森喜朗元首相らと,特別な関係を有する理由になっているとも想像される。
三国時代が始まる以前の朝鮮半島南部には,馬韓,弁韓,辰韓といわれる3つの地域があったが,その地理的配置からみて,馬韓は末盧国と,弁韓は伊都国と,辰韓は奴国と境目なくつながっていて,日本と朝鮮の間に実質的な境界はなかったと考えられる。馬韓が百済にとりこまれ,滅亡した秦の支配層,すなわち徐福一族に近いユダヤ系の秦氏が,山東半島から朝鮮に渡って建国したといわれる辰(秦)韓が(次項の)新羅になることによって,日本との関係は弁韓に限定され,九州北部の諸国連合に対応する伽耶諸国連合になるが,邪馬台国以前に,細々ながらも,日本を統治することになった末盧国すなわちマツ系との関係で,百済王族に支配される周縁小国家群といったものになり,いわゆる任那(日本府)も,その一つに置かれることになった。
百済の国名は中国の史書では372年に初めて見え,高句麗が314年に帯方郡を滅ぼした際に,派遣した扶余王族によって興され,いわば高句麗の分家の存在であったが,346年王位についた肖古王の時代に独立し,372年に晋に朝貢を果たして国として認められたという。その後は,本家高句麗と抗争を繰り返しながら,次第に南下し,現在の朝鮮半島西南部を占めるようになったが,475年の高句麗の攻撃によって首都漢城が陥落,その2年後には部下解氏のクーデタもあり,何とか乗り越えるも以後,凋落して行く。再興を図るべく王子を人質として倭(日本)に送る方式で,その支援を求めて行くが,478年には,倭王武(雄略天皇)が,百済の衰退によって朝貢ができなくなった旨,宋の順帝に上奏文を送るほどになる。その後,501年に即位した武寧王によって一時的な復興が実現し,朝鮮半島にわずかに残っていた倭系の国の一つ加羅が百済の一部のようになるが,その加羅も562年に新羅によって滅亡させられる。
554年に百済は新羅に完敗するが,関裕二「藤原氏の正体」にあるとおり,その後,百済の再興を図るべく日本に亡命した王族のなかに,(中臣姓を借りた)鎌足がいたらしく,631年に人質として来日していた王子扶余豊璋その人だったという説さえある。641年,27歳の時に歴史に忽然と登場した鎌足は,631年には18歳ということで,まさに王子扶余豊璋にふさわしい年齢であり,645年に中大兄皇子を唆して蘇我氏を討ち,まさに百済政権を成立させ,天智天皇(中大兄皇子)に新羅征討軍を派遣させるも,結局は白村江の戦で唐・新羅連合軍に大敗,半島の新羅勢力の強大化を受けて,壬申の乱によって天武天皇戴く親新羅政権になってしまう。
ところで,朝鮮では村のことをスカということと知れば,白村江と書いて,なぜハクスキノエと読むのか,フィギュア・スケートで有名だった村主選手が,なぜスグリと読むのかということも氷解し,横須賀は,横が"日の横"で東を意味することから,東向きの村であること,ついでに,横浜が東向きの浜であることも判明する。とすれば,藤原氏の本拠が春日神社のあるカスガということは,朝鮮半島で縁のあった加羅(ラは国を示す)のスカ(村)であること,つまり,百済と一体だった加羅の出身だったことを思わせ,蘇我氏の本拠地の飛鳥(アスカ)は,安羅(アヤ)の村ということで,より新羅に近い国の出身だったことも地名に記されていることになろう。
深入りすれば,中臣鎌足が百済王族,すなわち扶余氏であるとすれば,物部氏と同族であることになり,物部氏のものだったという鹿島神宮を横取りしたのではなく,譲り受けた可能性もあるといえる。
また,現代朝鮮でみれば,金大中がそうであったように,民主党系の地盤である半島西南部はかつての百済であり,同じ朝鮮民族とはいえ,東部の保守党の地盤がかつての新羅であったのとは,相容れないことが多いのもやむを得ないかもしれず,とくに,最近の民主党系の親北朝鮮ぶりを見ると,扶余氏の影すら感じざるを得ない。
序論や物部氏のところでも述べたように,ツングース系の有力な民族ながら,国を造るまでに至らなかったワイ(濊)族は,のちの満州あたりを一大拠点にしていたが,同じツングース系の有力な民族の扶余氏が建国するに際して追い出され,朝鮮半島を南下していく。最後に着いたのが,秦帝国の末裔秦氏が流れてきてつくった辰韓で,秦氏は,ワイ族を取り込んで,新羅を建国する。いわゆる新羅人の多くは,ワイ族をルーツとするということなのであり,当然のことながら,扶余氏の国,高句麗や百済とは,敵対関係になるのはやむを得ないところだろう。
ワイ族は,現在の北朝鮮の聖地白頭山から太白山脈に沿って,慶州近くの聖地太白山に向かったのであるが,"白"の字をつけた山が多数存在するように,白(シロ)を崇拝する民族であり,秦氏の得意とする絹織物のもとになる蚕もまた白い神様で,ヨーロッパではsilk(シルク)と呼ばれるように,音とイメージ全てが通じる(つまり白と新は同じという)ことから,両者あいまって新羅(シルラ)という国名ができと思われる。秦氏のハタは機織りのハタで,ワイ族に技術を伝えて養蚕民族にもしたのである。
ワイ族はさらに,日本海を横断して,日本の北陸地方に至り,そこで東北地方から南下していた仲間と合流することになる。石川県の小松(コマツ)は,本来,高麗の津(朝鮮の港)で,福井県の海岸まで含めて,朝鮮半島からの漂着も含めて渡来人が多かったと考えられる。白を崇拝するワイ族によって,日本の白山信仰が生まれ,ワイ族のつながりを辿って北上し,東北地方ではオシラサマ(オシラサマは蚕がルーツといわれる)になり,最後はオソレ山に至るのである。白山神社の祭神とされる菊理媛(ククリヒメ)については,日本神話のなかでの位置づけがあいまいで,いわば,宙に浮いていることから,統治に関わる諸民族と渡来とは全く別系統であったことが分かる。
中国との間に高句麗と百済があって,何れかの協力が無ければ朝貢できなかったため,新羅の名が中国の書に登場するのは,377年に金氏の奈忽王が高句麗とともに前秦に朝貢した時になる。391年,高句麗に広開土王が登場すると,その圧力のもと半ばその属国となって百済攻撃に加担,百済から支援を求められた倭は,399年に新羅に攻め込みに次々と攻略するが,新羅の訴えで支援に現れた広開土王軍の前に敗退してしまう。高句麗の属国であった間に,本来海洋民族に近かったワイ族をルーツとする新羅人の騎馬民族化が一気に進んだと考えられる。
ワイ族だけでなく,新羅の建国に関わった人たちも,日本海を渡って北陸地方に展開したと思われるが,秦氏に近い有力者で,おそらく安羅の王族でもあった蘇我氏もこの段階で渡来,ワイ族阿部氏とともに,近江を経て,大和に入ったと考えられる(大和での両氏の本拠地は隣あっている)。後述するように,応神天皇渡来時に円滑に大和に入れたのも,蘇我氏の存在があったからで,崇神天皇東征時に物部氏が果たしたのと同じ役割をしたと考えられる。のち,蘇我入鹿が,百済系の中臣鎌足に滅ぼされ,その子藤原不比等による「日本書紀」で,蘇我氏は徹底的に悪人とされ,侮蔑的に,馬子,蝦夷,入鹿の名がつけられている。蘇我氏を名乗ることが憚られ,その改名が進んで,現在ではほとんどいなくなってしまったが,拉致被害者として帰国した曽我ひとみのように,曽我と名乗る人たちが新潟県から岐阜県にかけて多いことが,日本海を経由して渡来してきた名残を示すものと思われる。千葉市に取り込まれてしまった蘇我町は,地名故にそのままの文字が保たれているが,逃亡した蘇我一族の来たところかもしれない。
参考図

歴代天皇の名で"神"の字がつくのは,神武天皇,崇神天皇のほかには応神天皇しかおらず,神武・崇神天皇と同じように国の始祖になった天皇ということを示していると思われる。しかも,その母とされる神功皇后にまで,"神"の字が入っているのである。すでに述べたように,これら天皇のいわゆる漢風諡号は,だいぶん後の,「懐風藻」を撰したことで知られる淡海三船が,孝謙上皇の命で,一括撰進したもので,終章で詳しく紹介するように,実に的確に名づけているため,皇位の継承が手に取るように分かるのである。>漢風諡号
秦氏がワイ族を取り込んで建国した新羅の隆盛に伴い,かつて,徐福が,秦の始皇帝によって日本建国に派遣されたように,新たに,日本の政権を握ろうとしたのか,応神天皇擁する秦氏一族が,おそらくアマ系のサポートを受けて航海し,九州の,アマ系卑弥呼の後継者壹与(トヨ)が拠点にした豊前の地に渡来,そこに,秦の国をつくり,のちに応神天皇を祀る八幡宮の本山として,宇佐八幡宮が創建されるとともに,アマ系の女性3人を妃にしたことから,古くから神事の行われていた沖ノ島をシンボルに,三女神として祀るユニークな宗像神社も創られた。
そこから,崇神天皇に見倣うかのように,東征して河内入り,親百済の崇神皇統に代って親新羅の応神皇統の時代を実現することになる(これもまた一つの国譲りであったと言える)が,応神天皇の母神功皇后が新羅の神アメノヒボコの子とされ,渡来前の応神天皇は,(推古天皇に対する聖徳太子のように)神功皇后の摂政のような存在であったともいわれることからも,ほとんど新羅と一体であるような政権が始まるのである。応神紀には,朝鮮の騎馬戦の叙述が多数みられ,新羅を馬飼として隷従させたという記述があり,応神天皇が騎馬民族新羅人とともに渡来したことを示すものと考えられ,いわゆる騎馬民族征服王朝説の理由の一つになったようだ。ちなみに,のちに蝦夷征伐で登場する坂上田村麻呂の祖先も,応神天皇とほぼ同時期に渡来した東漢(ヤマトノアヤ)氏で,劉氏の末裔といわれる。
ここで,同じユダヤ人とされる徐福一族と秦氏との相異を考えるため,その後のユダヤ人の歴史をみておくと,徐福渡来から邪馬台国滅亡までの間,ユダヤ人の故郷イスラエルでは,キリストが登場して,宗教上の大変革が起きるが,キリストは勿論ユダヤ人で,当初は,信者もほとんどがユダヤ人であり,その時点では,キリスト教は新興宗教で,古来のユダヤ教信者から排斥されたのもまた当然だった。そういった原始キリスト教のユダヤ人が再び,徐福一族と同じような道を辿って東へ向かい,キルギスの東北方にキリスト教国の砂漠の民であることを示す(三日月)弓月国をつくり,さらに中国を通過し,山東半島経由で朝鮮半島に入って新羅の秦氏になったといわれる。新羅はもと辰韓で,秦韓とも表記するように,始皇帝の秦国の滅亡後,朝鮮に渡った秦氏が建国したといわれるので,そこで,両者が出会ったのである。ちなみに,秦氏,徐福とも,本姓は,始皇帝と同じ嬴であったと言う。
応神朝の天皇などの倭名にも"オシ"のつくものも多いので,新羅から渡来した秦氏も,徐福系のユダヤ人とのつながりは認識されていて,すでに,大和に崇神朝ができていることを知っていて,日本列島をめざしたと思われる。そのルートをかなり正確に後追いすることができる。というのは,応神天皇を祭神とする八幡宮は,その名が「ヤ(尊称か量の多いことを示す語)」+「ハタ」であり,宮ということは,単なる神社ではなく天皇の所在地を示していると考えられるからだ。その八幡宮の数や格を見れば,対馬,壱岐を経て,福岡の筥崎八幡宮の当たりで上陸,かつて秦の宮と呼ばれていた香春神社のところを拠点に秦王国を築き,のちに宇佐八幡宮が八幡宮全体の最上格とされることになる。
三橋健編「日本書紀に秘められた古社寺の謎」によれば,八幡神のルーツはもっと古いようで,神武東征の話に,すでに宇佐氏が登場しており,宇佐八幡宮の神官が,大和朝廷に対応する大神氏と,新羅から渡来した応神天皇に対応する辛島氏の2者であること,宗像三女神も祀られているのは,新羅から渡来するに際して,その力が大きかったこと,欽明朝に示現したということは,その頃,創建されたとみられるということである。他方,神功皇后,応神天皇とも「古事記」には登場しないということなので,新たに,新羅から渡来して新王朝を開いた天皇を,うまく天皇神話体系に組み込むことができなかったと思われる。八幡神社は,その数が最も多いにもかかわらず,八幡神すなわち応神天皇は,日本神話の家系図には登場しない,宙に浮いた神なのである。
蛇足だが,応神天皇は秦氏を引き連れ,高度な鉄器文明を日本にもたらして,八幡神社の祭神になった故,明治維新後の国営で創設された製鉄所の地が八幡であったのも当然であった。また,宇佐八幡宮には卑弥呼が比売神として祀られ,崇神朝と応神朝を繋げるようになっている。「景行紀」に,突然日向地方の伝説が登場するが,そのルートを見ても,崇神皇統と応神皇統の九州のルーツ,つまり,ヒムカ(卑弥呼)とトヨ(臺与)を結び付けるべく,吉野ヶ里の邪馬台国から崇神(神武)東征,その後の応神東征を逆行するものとして見ると,よく分かるのである。
「新撰姓氏録」の仲哀天皇8年のところに,'秦始皇帝の子孫功満王が日本に来る'という記述があり,秦氏は功満王が祖先である,つまり始皇帝の末裔であるとしている。秦の国が滅亡した際に,その多くが,徐福の出身地の山東半島を経由して,朝鮮半島に渡り,すでに述べたように,辰韓を建国,その後,南下してきたツングース系のワイ族を取り込んで新羅を建国したのである。「日本書紀」の応神14年の項に,'弓月王が百済より来朝し,自国の民120県が新羅のために加羅に足留めされていると訴える'という記述があるが,要は,秦氏は,新たな新羅王族とうまく行かず,応神天皇を戴いて,日本に渡来したことと,後述するように,「日本書紀」によって日本を支配しようとした藤原氏のルーツが百済王家だったらしいこととを整合させようとしたといえよう。
秦帝国の皇帝の末裔を称する秦氏の応神朝が,崇神朝と大きな混乱なく交替(国譲り)できたのは,崇神朝が徐福の末裔で,その徐福が始皇帝の家臣であったこと,つまり,同じユダヤ人でも上下のあったことによるのではないかと考えられる。後述するように,そのやり方は違ったとはいえ,蘇我氏から藤原氏への交替,豊臣秀吉から徳川家康への交替も,同様の関係にあったとみられるのである。仲哀天皇の子の忍(オシ)熊王が反乱したという記事のあることが,応神天皇が別の王朝を拓いたことを示し,秦氏系図のちょうどその頃に,忍(オシ)秦公と,両者をつなげるような名の人物がいることも,それらを裏付けるものだろう。
ここで,倉塚曄子「古代の女」を参考に,応神天皇が新羅から渡来したことを裏付けてみよう。応神天皇は神話では胎中天皇といわれて,母神功皇后が新羅遠征時に神様のお告げで懐妊した,つまり処女懐胎で,まさにキリストがマリアの処女懐胎によって誕生したという伝説そのままである。キリスト教のネストリウス派の教義が秦氏渡来とともに日本に伝わったともいわれ,秦氏出身の厩戸皇子といわれる聖徳太子の誕生伝説もキリストのそれにそっくりだと言われている。いずれにしても,こういった神話をつくらなければならなかったこと自体,日本で生まれた皇族では無かった(その父祖を説明できなかった),つまり,渡来してきたことを裏付けるのである。倉塚は,いみじくも,神功皇后の新羅征討物語が,天孫降臨神話とパラレルであるといっているので,処女懐胎の場所糟屋郡が,そのまま渡来地を示しているのであろう。
さて,糟屋には,神功皇后を祀る香椎宮があるが,大陸では多いものの,日本にはほとんど無い廟宮とされ,ふつうの神社の扱いを受けていないのは,皇后が新羅王子の血を引く,つまり新羅人であり,応神渡来前にすでに没していたか,ともに来日するも,この地で没したことから,大陸と同じ風習である廟に祀ったと考えるしかないだろう。
その秦氏集団が,族長すなわち応神天皇戴いて東征するのだが,伝説でしかなかった崇神東征と異なり,前項で述べたように,八幡宮の分布を見れば,良く分かる。まず,宇佐八幡宮のある豊の国から,(以後,現在の地名を用いると)愛媛県八幡浜(通り道であったことを証明するような地名)に出て,新居浜あたりを経て,香川県に入ると,八幡宮は高松のものを始めかなり集中する。
おそらく,渡来した筑紫糟屋で,皇后に当たる妻を迎えて東征,途中讃岐で,子(後の仁徳天皇)が誕生する。金比羅宮はかつて旗(ハタ=秦)宮と言われていたらしいことから,そこに,応神天皇が滞留したのだろう。讃岐の国には,応神天皇とともに渡来した秦氏の子孫が多いことで知られ,その代表が,ユダヤ人的天才ぶりを発揮した空海ということになる。
そして,瀬戸内海を越えて吉備氏の地域に入り,抵抗されるも,前述したように,吉備氏は物部氏と同族で,かつて崇神天皇が東征した時にそのサポートをした氏族であったから,吉備津彦神社や先端技術を付与することなどによって決着したようで,続いて入った播磨でも,先住豪族(のちの赤松氏の祖)の抵抗を受けるが,姫路市の白国神社(シロすなわち新羅),その北の広峯神社(のちの吉備真備創建という)の祭神が新羅訓明神であるように,新羅人が多く居住する地域となって行くが,のちに聖徳太子の死で一気に没落する秦河勝の逃亡先にもなって,太子町と斑鳩神社まである。播磨はまた,のちの佐用町から赤松一族が出たように,有能な悪党が多く,中央の支配が及びにくかった地方でもあるが,赤染氏も秦系で,秦氏がとくに多いとされる赤穂にも,太秦と同じ大酒神社があり,のちに赤穂浪士など,一連の話につながって行くのである。明石も「アカ」系の地名とみられる。
さらに進んで,摂津の海岸沿いに河内,すなわち,既に大和にいた崇神皇統の天皇の支配領域に着いたことになる。河内では,崇神朝に抵抗されたため,そのまま,近江を経て,日本海の,新羅をはじめ大陸との交流の拠点であった角鹿(現在の敦賀)に至る。琵琶湖擁する近江は,一つの国のような地域であったことから,秦氏と新羅人ともに定着し,のちのち,子孫がさまざまに活躍することになる。角鹿で,おそらく現地の豪族の娘を一時的な妻とし,子も生まれたことが,のちに,天皇の跡継ぎが断絶した際に,越前でようやく応神天皇の血を引く継体天皇を見出すことができたという話につながり,神功皇后の伝説が集中して記載されるのも,継体宣化朝の項であることがそれを裏付けるであろう。
応神天皇渡来時の神は,イト系支配下のアマ系のムナカタ神であり,渡来後,アマ系の豊の国にあったが,東征にあたっては,もはやイト系とは関係ないアマ系の人たちに支えられ,無事,難波に到着して,河内王朝を拓くことができたことから,航海守護神の住吉大社が創建されたというわけであるが,宗像,綿津見と同様,海の神として,底・中・上の筒男(ツツノオ)三神になっている。その名の由来には諸説あるが,新羅から出てすぐのところの,対馬の南端に位置して,ユニークな文化を伝えている豆酸(ツツ)が語源ではないかというのに説得力がある。そこが,難波の住吉三神の故郷ということ,日本への出発地だったというになり,もちろん,上陸した九州の博多にも住吉神社がある。その後,住吉(スミヨシ)神が,筑紫まで,皇后の征討ルートに対応する要所に配置され,ムナカタ,ワダツミ両神の存在が消されていったのは,応神天皇の渡来を隠さなければならなかった神話創作者によるものと考えられる。
讃岐の国名を考えてみると,仁徳天皇の倭名には「ササギ」と読まれる讃の文字が入り,後漢書で倭王讃とあるのが仁徳天皇なのはほぼ確実で,その名をもって,讃岐国の名にもなったのではないかと考えられる。この「ササギ」は,天皇の陵墓が「ミササギ」,韓国の国鳥が「カササギ」と呼ばれるように,新羅国の基本を成す語とも思われるが,実際,佐々木(ササキ)氏はその祖が明確になっている姓のうち最大のもので,滋賀県近江八幡にある沙沙貴(ササギ)神社に,全ての家系が登録されているという。所在地八幡は,秦氏の神応神天皇を示すことから,まさに,生粋の新羅人であり,六角氏,京極氏も,佐々木氏から派生しているので,武力に優れているといえよう。佐々木氏につながる名字として,笹のつくものを見てみると,戦後政界の仕掛け人で黒幕だった笹川良一の,笹川姓を筆頭に,何十もあり,その分布も,苗字ごとに異なりながら,全国に広がっていて,シラギ系の人たちの多いことが分かる。鹿児島県の幹部だった笹田氏,コンサルタント界の重鎮だった笹生氏など,今までに会った人たちの風貌や振舞いには,共通したものが感じられる。ルーツが関係深い中国の山東を姓とする人たちも新羅人であったようだ。ついでながら,近江草津にある安羅神社の祭神は新羅王子アメノヒボコである。
既に述べた蘇我氏を別にしても,滋賀県の滋賀はじめ,この地域を中心に,志賀,信貴山,信楽,曾我など,新羅と近い発音のものも多い。武烈天皇の倭名にも「ササギ」の語が含まれ,大和の主要豪族の一つ巨勢氏も,その祖は雀部臣といわれて,仁徳天皇と同じ「ササギ」を含み,のち朝鮮半島との軍事に活躍する人材が多くでることから,新羅系と見て間違いないだろう。
京都の太秦には蚕の社という神社があり,養蚕を敬うユダヤ人のメッカとされているが,後の三井財閥はこの社を氏神にし,江戸進出に当たって,三本柱の奇妙な鳥居も移して三囲神社を創建,三がユダヤの基本数字であることなどから,多くの点で金融を支配するユダヤ人とつながっていることが分かる。蛇足ながら,その三井財閥の出発となった三井高利は,もともと近江(京に近い)の家ながら,伊勢の松坂に出て財を成したということであるが,中村修也「秦氏とカモ氏」には,秦氏のなかで,商人的性格を持つ人物として「日本書紀」に登場する秦大津父という人物がおり,伊勢に商売に行って財を成し,天皇に貢献したということであり,大津が,まさに近江の首都なので,そのまま,三井の祖先と考えてもおかしくないだろう。邪馬台国のところで述べたように,「三」という数は,ユダヤ系にとって大きな意味を持つのである。
太秦のすぐ北に,秦氏が大々的に開発した嵯峨野があるが,それが新羅由来の地名と考えられるように,また,播磨のところでも述べたように,全国に広がる秦氏の回りには新羅人が必ず付帯している。太秦はまた,近代に入って映画のメッカとなるが,アメリカのハリウッドがユダヤ人の支配下にあったことを思えば,その日本版であるといえよう。
ところで,太秦はウズマサと読まれるが,この"ウズ"は"ウル"がなまったもので,古代ヘブライ語で光を意味する。奈良県御所市には蘇我馬子の墓とされる石舞台に次ぐ大きさの條ウル神古墳があるが,"ウル"がヘブライ語であるとすれば,応神天皇に近い位置にあった人物の可能性が高いといえるだろう。実際,條ウル古墳のまわりは,豪族羽田氏すなわち後に応神天皇とともに渡来したユダヤ系秦氏の支配地であった。
崇神・応神東征ルートのイメージ
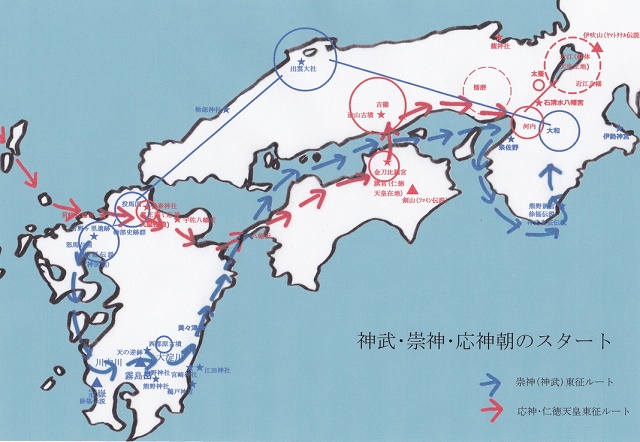
葛城襲津彦~ハタ系の応神朝渡来人をオシ系とつなぐ葛城地方の有力者~
古代史の会「人物で学ぶ日本古代史 1:古墳・飛鳥時代編」(2022年)では,「伝説と史実のあいだ」のサブタイトルのつけられている葛城襲津彦は,一般には葛城氏の祖として知られるが,4世紀後半から5世紀初頭にかけて活動した人物で,当時,葛城氏という集団があったわけではなく,単に,葛城地方の襲津彦ということらしく,「日本書紀」で,2世紀も前の,応神朝の祖神功皇后との関係で記述されているのは,襲津彦が,新羅から多数の俘人を連れてきて,葛城の地に集住し,瀬戸内海ルートを確保したこと,その後の大王家と外戚関係を維持したことなどで,蘇我馬子が,推古天皇に対して,葛城県を本拠と奏上したように,多くの民が自らの祖としていったとある。>蘇我氏は,一般には百済系とされているが,その氏名や伸長,さらには,百済系の中臣鎌足(藤原氏)に滅ぼされたのをみると,ハタ系の応神朝とともに,新羅から渡来したと考える方が自然だろう。また,次の飯豊青皇女のところで述べるように,オシ系の拠点たる忍海が葛城地方にあることも,その有力性を考える上で見逃せない。
飯豊青皇女(いひとよあおのひめみこ)~ハタ系を,それ以前の正統なオシ系に繋げる象徴的な存在
オシ系の崇神朝からハタ系の応神朝に交替するわけであるが,そのルーツは秦の始皇帝でつながっており,ある意味,交替は円滑に行われたと思われるが,応神朝の正統性を保証するためには,オシ系からの流れを受け継ぐ必要があった。それを裏付けるように,古代史の会「人物で学ぶ日本古代史 1:古墳・飛鳥時代編」(2022年)には,大和王朝の祖オシ系崇神天皇と,応神朝の祖ハタ系神功皇后の間に飯豊青皇女という人物が,皇位継承の結節点のサブタイトルがつけられている人物が登場する。奈良県葛城市南端の忍海(オシミ)という地域に宮があったと伝えられ,仁徳天皇の長子履中天皇の子で,市辺忍歯王の妹で,雄略天皇が市辺王らを殺害して皇位につくも,その子清寧天皇のは子が無く崩御,皇統が途絶えようとした際,播磨に逃れていた市辺王の二王子を迎えて,顕宗天皇,仁賢天皇とするにあたり,宮に迎える役を担った。つまり,清寧天皇と顕宗天皇の間の短いながら空位を埋め,「日本書紀」では,用語が天皇と同等に表記され,履中の娘も青海と市辺の娘の飯豊が結合された名で,埋葬地も天皇と同じ陵になっており,女性天皇の先駆とも言える存在であった。>徐福渡来のところで,朝鮮にも忍海の地名があり,オシ系の根拠として忍あるいは押の字を含む皇族を列挙し,継体天皇を迎えるところで妃に迎えたなかに,オシ系があるように,応神天皇を祀る八幡宮をつくったほどのハタ系ですら,その正統性はオシ系との繋がりが必要であったし,卑弥呼が祖であるように,女性天皇が登場する根拠にもなっていると言えよう。
応神皇統は,倭の五王としても話題になるが,その最後の倭王"武"とみられる雄略天皇は,最後まで抵抗し続けた(出雲族の支族高志系ともいう)マツ系の大豪族葛城氏を滅ぼして大和盆地を平定し,応神皇統を確立すると,まず先代の功績を敬うべく巨大な応神・仁徳天皇陵を築造して政権の力を誇示する。そして一代前の安康天皇までの大古墳を築造し,自らの古墳(宮内庁指定の雄略天皇陵)は小さくなっているが,実は,仲哀天皇陵とされているミサンザイ古墳が,巨大で雄略天皇にふさわしい陵ではないかともいわれる。ここで,最大なのが仁徳天皇陵とされ,応神天皇陵とともに,大和から最も遠い海側に築造されていることこそ,崇神朝から国譲りを受けたのが仁徳天皇であった証ではないかと思われる。応神朝の天皇陵の大部分が河内にあるのは当然で,邪馬台国時代の神武皇統の天皇陵は畝傍山周辺に配し,崇神皇統の天皇陵は巻向山麓に,そして神功皇后はじめ妃の陵は和邇氏の支配地に築造されたのもなるほどと思える。なお,雄略天皇によって葛城氏が滅ぼされた後を継いだのが平群氏であるが,武烈天皇時には大伴金村によって滅ぼされてしまい,大神神社の祭事が始まったのも,雄略天皇時代ということなど,その支配が完璧なものになったことを示すものだろう。
松木武彦「日本の古墳はなぜ巨大なのか: 古代モニュメントの比較考古学」によれば,世界遺産に登録された仁徳天皇陵は,平面としては,世界最大の陵墓であり,それに次ぐのが応神天皇陵で,その他,応神朝の天皇陵が全体として図抜けた建造物であること,その時期に造られた各地の巨大陵墓などをみると,秦氏のもつ技術力によって造られたこと,さらには,秦氏が始皇帝の末裔であることを頷かせるものではないだろうか。後述するように,世界の巨大墳墓を比べてみると,日本の古墳は秦の始皇帝の墳墓(いわゆる兵馬俑)と類似し,仁徳陵の規模は,それをも上回るということなので,いかに巨大であるか分かる。蛇足ながら,秦氏の技術力を裏付けるものとして,秦氏出身の空海が満濃池を築造したこと,東大寺の大仏を造るにあたって,その総指揮をとったのが,やはり秦氏出身の佐伯今毛人だったことなどを挙げれば十分だろう。
また,荒川の河口(かつてはこの辺まで海だった)近くに押上があり,上流に行くと江戸時代に忍藩だったところのさきたま古墳群があることはオシ系のところで述べたが,そこの稲荷山古墳から発見された刀の銘に雄略天皇の倭名「ワカタケル」が刻まれていたように,関東でも古墳の築造によって,勢力を展開するなど,全国的支配体制を整えて行ったと考えられる。この先の北関東には,のちに有力武将として登場する新田氏・足利(アシカガ)氏など新羅由来の氏族がいるが,秦氏回りの新羅人としてこの時期あたりから始まったのではないだろうか。関東の西の山地沿いには,埼玉県の高麗・飯能・新座や,神奈川県では秦氏の入った秦野回りの寒川など新羅人の入植が多く,そのまま日本のシルクロードといわれる地帯になっている。ついでながら,吉備古墳群のなかで特別に大きい造山古墳も吉備族のものではなく,応神皇統のものらしいので,支配の役割を担ったものだろう。ずっと後,蘇我氏が吉備に派遣されたのも,これまでの推移を見れば当然のようにみえる。
そもそも,ユダヤには古墳は無く,高句麗の古墳や百済に前方後円墳があったことが知られているように,前方後円墳は朝鮮半島の文化で,応神朝が新羅からもたらしたものと考えられる。ということは,応神天皇より前の崇神・神武朝の古墳も,雄略天皇以降,過去の天皇を敬う形で築造され,また,大和や全国の豪族たちも,巨大墳墓をみせつけられて,場合によっては,許可を得て築造していったということまで考えられる。天皇陵については調査研究が禁止されているため,実際の築造年代が分からず,というよりも分かってしまうことを避けるために,禁止しているとさえ思える。想像をたくましくすれば,多数の大古墳を築造していったことが,人民の疲弊や豪族の不満を招き,武烈天皇の時代,ついに行き詰まって,後述する継体天皇の登場になるのではないかとも思われ,実際,それ以後,古墳の築造は小規模になり激減して行くのである。
各天皇陵配置図(宮内庁の指定による)
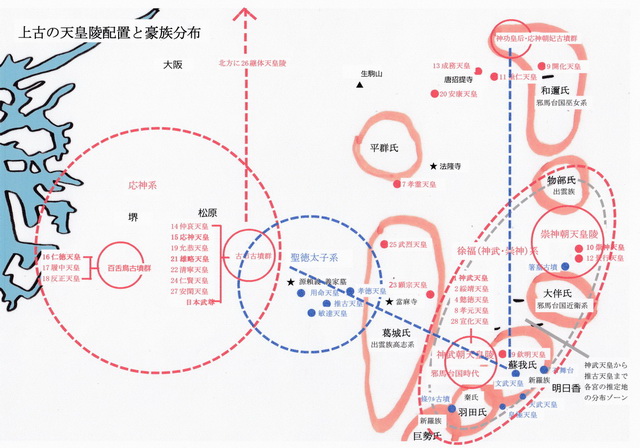
ヲワケとムリテ~ハタ系の応神朝が敬意を表したオシ系ルーツの東西の最有力者~
古代史の会「人物で学ぶ日本古代史 1:古墳・飛鳥時代編」(2022年)には,ワカタケル大王すなわち雄略天皇から銘鉄研(国宝)を贈られた,現在の埼玉県行田市埼玉稲荷山古墳のヲワケと,熊本県玉名郡和水町江田船山古墳のムリテという同時代の人物がいて,サブタイトル「刀剣銘に名を遺した倭王権下の地方豪族」が示すように,それぞれ,北関東と北九州の有力な首長であったとある。>想像をたくましくしてみると,前者に関わる行田は,忍城のある地で,東京の押上から遡って当地に入り,北関東を支配するようになったオシ系の末裔,後者は,邪馬台国に近いことから,当地に残って支配を続けたオシ系の末裔と思われ,飯豊青皇女のところで述べたように,オシ系とルーツを同じくするハタ系の応神朝が,政権交替にあたって,接続を図ったことに関係し,全国支配の確立を図ろうとする雄略天皇にとって,東西の最有力者であったとみられる。
秦氏はまた,桂川水利工事などの土木技術や製鉄技術のほか,北関東にまで革新的養蚕技術を伝えたが,多民族の日本列島を統治するため,出雲や吉備の方式が上手くいったことから,各民族の氏神となるように,全国チェーン化して行ったらしい。広大な境内に壮麗な神殿を建立し,現世利益を神に請願するという,現在の神社の様式を持ち込み,応神天皇を祀る(尊称ヤ+ハタを示す)八幡神社を軸に,マツ系のために松尾神社,稲作民のために稲荷神社を創設,出雲大社には神事を司る宮司を秦氏から派遣(現代に伝わる千家家)するなど,多様な民族を支配すべく神社体系を構築した。とくに,八幡神社は,新羅系騎馬民族の源氏の人たちが崇拝する神社になって,著しく広がって行くのである。>神様の家系図
八幡神は,もともと応神天皇を戴いて渡来した秦氏の氏神として,"ハタ"に尊称"ヤ"をつけた,まさにハタ系の氏神であり,オシ系とアマ系によってつくられていた神話体系には乗らない神であった。漢字2文字に天皇をつけて呼ぶ,いわゆる漢風諡号というものが始まったのは,聖武天皇の娘の孝謙天皇(重祚して称徳天皇)の時代に,その命で,当時一流の文人官僚だった大友皇子の曽孫淡海三船が,神武天皇から聖武天皇まで一括撰進したもので,神がつくのは,神武,崇神のように,王朝創始者であることを示しているようで,応神天皇もまさにそうであり,その母神功皇后にまで神がつくのであり,八幡神は,結局,応神天皇その人になってしまう。応神天皇が角鹿から河内に戻る間,成人した仁徳天皇は,その名が示す通りの仁徳だけでなく,妃の一人(磐之媛)をマツ系の葛城氏から,もう一人(髪長媛)を日向系(アマ系)の巫女の流れから娶ることで統一を成し遂げたが,伝承では伊勢神宮に嫌われたため(つまり本来のユダヤ教と,キリスト教とは相受け入れられないものであったため),新たに石清水八幡宮を創出し,前述したようにその出先の神宮を,応神天皇が辿ってきたルートに配したらしい。
その本山とされる宇佐八幡宮は,元々は大漁旗を意味する海神で,つまりアマ系台与の末裔宇佐氏が崇敬した地方神であったが,前述したように,応神天皇の渡来時に,アマ系が重要な役割をしたことで,571年,神託によって,応神天皇の化身となり,土着的な神と天皇の神霊が結びつく特別な神になった。新たに登場してきたため,オシ系とアマ系でその基礎がつくられた記紀神話の体系に入っておらず,天皇神授の神話デザインにおいて,取り込みようがなかったと思われる。秦氏は,原始キリスト教になっているとはいえ,崇神皇統と同じユダヤ人であり,前述のように徐福一族の後を辿ってきたこともあって,何らかの調整があったと考えられる。いきなり大和に入らず,京都の方へ展開し,太秦という一大拠点をつくる一方,すでにある伊勢神宮を尊重して敬うことで,崇神皇統から国譲りされ(かつて崇神朝がマツ系・出雲族の神を最大限に尊重して国譲りされたように)。とはいっても,その後の宇佐八幡宮のご神託の強さを見ると,まるで第二の伊勢神宮のような存在で,どういう訳か分からないが,その名も,地形的な立地もよく似たものになっているのである。
その後の天皇は,当然のことながら,応神天皇から始まることになるため,伊勢神宮と同様,皇室の祖神とされ,のち,源氏の氏神になり,武家の守護神となった。新興の神であるにもかかわらず,八幡神社の数は,ダントツの一位になっている。宇佐神宮が総本宮で,応神天皇の上陸地と思われる福岡の筥崎宮,畿内に入った証の京都の石清水八幡宮と,かなり後になるが,源氏の氏神となった鎌倉の鶴岡八幡宮をあわせて,日本三大八幡宮とする。具体的な人物が祭神となった最初の例で,のちに,雷神信仰が,菅原道真を天神様として,畏怖・祈願の対象にするようになったのに通じるものといえよう。
なお,祭祀と技術両面で優れていた秦氏は,徐福渡来時における物部氏と同じように,国家支配システムを構築するのに大きな役割をしたと考えられるが,実際の政治は蘇我氏が得意としたらしい(後述するように,蘇我氏の渡来は応神朝末期かもしれない)。また,蘇我氏とつながり,東日本一帯を広く占める阿部(安倍)氏の役割も大きかったと思われる。名字由来ネットによれば,応神天皇渡来に関わって秦の国があったとされる現在の大分県に秦氏が集中しているのはもちろんであるが,藤原氏から排斥されて名乗ることを憚られ,わずかに残る蘇我氏はほとんどが大分県におり,阿部氏もまた飛び地のように大分県では多いというように,宇佐八幡宮のある大分県は応神天皇の大和進出への一大拠点であったことが伺えるのである。
応神皇統になって,天皇の祭祀を担当するのが,それまで中臣氏だけだったところに,忌部氏(のち斎部氏)が登場する。当然のことながら,応神天皇の渡来ルート上に多く分布するが,なかでも阿波(アワ)忌部氏の格が高いらしく,その拠点は祖谷で,そこの剣山にはソロモンの秘宝が埋蔵されているという伝承すらあるのである。房総半島南端にあった安房(アワ)の国は,阿波から渡来した人たちによってつくられたことから同じ名になり,安房神社の祭司は忌部氏とである。後に,中臣氏の苗字を借りたクダラ系藤原氏が覇権を握ったことによって,急速に衰えてしまうのは,まさに新羅由来の氏族だったからだろう。
日本に古くから土着していたり,度々渡来してきた様々な民族の調和を図るべく,それぞれの神々に対応する神社体系をデザインしたのが秦氏で,ともに渡来した応神天皇を祭神とする八幡神社の数が,記紀神話には出てこない神ながら,一番多くなっていることが,その証左となろう。デザインの際,キーになったのが,徐福一派よりかなり前に,春秋中国の,越に敗れたために渡来した呉の民で,現在も松の字が入った名字をもつ人たちの間に伝わる,呉太白の末裔の扱いであったと思われる。秦の始皇帝による統一時に,現地にもなお呉王の末裔が残っていて,秦氏とマツ系の関係がつくられていた可能性も否定できない。
魏志倭人伝に出てくる末盧(マトラ)は,マツの国という意味で,九州北部に松尾姓が非常に多く,既に詳述したが,松の字のつく地名を追えばわかるように,彼らも東征していて,先に,大和を支配していたと考えられ,いわゆる神武東征で,葛城の地を離れて,山城に移ったらしい。秦氏が拠点としていたのは,地名そのものが示す太秦で,平安京をはさんで,東の下鴨神社と反対側の西側になる。秦氏の本来の氏神は,蚕の社と呼ばれるように,絹にかかわる民族そのままの名であるが,正式には,木嶋坐天照御魂(アマテルミムスビ)神社といわれ,まさに,造化三神を一つにしたような名になっている。財閥三井家の氏神でもあったとされ,江戸進出で創建された三囲(ミメグリ)神社と同じ,三柱鳥居があることでも知られる。
秦氏が創建したとされる有名な神社に京都の松尾大社があるが,その名がマツ系そのものである上,中村修也「秦氏とカモ氏」によると,その祭神は秦氏の神ではなく,その近くの,鴨氏の上賀茂神社,下鴨神社と同じであるという。つまり,国譲りしたマツ系の人たちを,支配下に取り込む装置として,これらの神社が創建されたと考えられる。この両神社は葵祭りで有名であるが,鴨という動物,とくに家畜化されたアヒル(家鴨)と,葵という植物をセットで考えれば,まさに,中国南部の揚子江下流域のもので,マツ系がすなわち旧呉人であるという有力な証拠になるだろう。神様の話を記しておくと,マツ系を取り込んだ松尾大社(スサノオ系(出雲)のオオヤマクイノカミが祭神=マツ系のところで述べた感染症の話,酒の神)と上賀茂神社(オシ系タカミムスビ系のタマヨリヒメノミコトとオオヤマクイノミコトの間に生まれたカモノワケイカヅチノミコトを祭神としている)・下鴨神社(イザナミ系のハニヤス男女神=ハニは土(土着を示す・ハニワ))ということである。>豊臣秀吉,>徳川家康
次論で述べるように,王権を簒奪したことになったアマ系天武天皇の皇后持統が,自ら天皇になることを正当化すべく,伊勢神宮を軸とする形で現在につながる日本国と天皇制を創始するが,その伊勢神宮にも,ダビデの星刻まれた灯篭があって,神輿はじめ日本人の祭祀のしかたがユダヤ人に近いといわれることなど,秦氏の力によるものだろう。かつて来日したユダヤ人の富豪ロスチャイルドが神輿を見て,ユダヤ教とのあまりの類似に絶句したとも伝えられる。住吉神社は,神功皇后をも祀っていることから,シラギ系の海洋民族のためのものだろう。それに対してエビス神社はインドの神にもつながることから,縄文時代からの海洋民族に対するものと思われる。氏神の「うぢ」も古代ヘブライ語のウルに対応するらしく,太秦の「うず」と同じかもしれない。
終論で,地図を示すように,平安京遷都以前に,秦氏は,前述した松尾大社,上賀茂神社,下鴨神社とともに,もう一つの大神宮稲荷大社も創建したが,全国で八幡神社に次いで多い稲荷神社の総本宮で,多くの渡来した(マツ系ではない)稲作弥生民族を支配下に治めるためのものであったといえるだろう。このように,遷都以前に,要所が重要な民族の神社によって抑えられていたのである。
やはり,数の多い日枝(日吉・ヒエ)神社は,山王信仰に基づいて,比叡山麓の日吉大社より勧請を受けた神社であり,比叡山が,仏教のメッカになったことからも,相当に古くからのものだったと思われる。現代では,東京山王の日枝神社が,都心の重要な場所にあって,あたかも日枝神社のトップのようになっているが,大山咋(オオヤマクイ)神を主祭神とするように,山王信仰はすなわち山岳信仰であり,最も古い形態の信仰であり,神社を守っているのが,狛犬ではなく,猿であることからも,縄文時代からのものを感じさせる。とすれば,物部氏のところで述べた扶余族の故郷の畑作物,つまり,ヒエは,穀物の稗であり,黍(キビ)から,吉備の国,吉備津神社ができたり,粟(アワ)から,阿波,安房の国ができたりしたのと,同じなのかもしれない。
巨大だった出雲大社についても,国譲りした諸民族を懐柔すべく,秦氏のもつ技術力を発揮して贈ったといわれる。
白山神すなわちククリヒメノカミ=黄泉の国神話に登場し,伊邪那岐命・伊邪那美命の諍いを調停した白山神社の祭神,つまり白山信仰に対応する神で,日本海経由で新羅から北陸に入ってきた騎馬系の養蚕民族と考えられる。新羅はシルラで白の国を意味し(シルクの語源?),蚕のマユの白さや,かつては太白山と呼ばれた北朝鮮の白頭山につながる。そのまま,東北に広がり,最後は,オシラサマになった。ククリは糸を括るの意であり,いずれにしても,国つ神ではなく,九州方面からの天つ神でもない,全くの別ルートで渡来した神であることから,それまでの神話体系に組み込めず,宙に浮いてしまった。
白山信仰を確立した泰澄も秦氏の出で,白山神社の祭神・菊理媛(ククリヒメ)は,糸を操ることと同義,養蚕民族のためのものであることを示している(ククリは高句麗という説もある)。朝鮮半島から入ってきた白山信仰は,社会の最下層の人たち,生贄や屠殺に関わる人たちを対象としていたため,殺生を禁じる仏教を背景とした国家によって,社格は極めて低い位置に据え置かれたままになる。泰澄はまた,国譲りで敗れた側のシンボル役小角(持統天皇のところで説明予定)とも連動していたといわれる。桓武天皇の時代に,伊勢・尾張・近江・美濃・若狭・越前・紀伊等の国に対して,牛を殺して漢神を祀ることを禁じたとあるが,このうち近江・美濃・若狭・越前が白山信仰に関わるものである明らかで,伊勢・尾張・紀伊については,マツ系のところで述べたように,春秋時代の呉の風習を伝えてきていたためと思われる。
物部氏のところで取り上げたワイ族(新羅人の主流)が大量に流入して,白山信仰を伝えたのがのちの加賀国であるが,当時は,のちの越前国の一部でしかなかったといわれるので,ワイ族が多くなって異なる地域になったことで,独立した加賀国になっていったと考えられる。その流入の主たる入口が高麗の津,すなわち現在の小松(コマ・ツ)であったことも既述したが,後に,農耕民を対象とした浄土真宗が広がったのも,越すなわち北陸地方で,そのなかで農耕民が自らの地位を確認すべく最下層の白山信仰者を殲滅しようと一向一揆が激しくなったのも加賀国で,その一向一揆を抑えて,前田藩の加賀百万石ができることになる。ついでながら,敦賀は本来ツヌガで,新羅が琵琶湖経由で日本と往来する港であった(琵琶湖を囲む近江国は滋賀(シガ=シラギ)県になるように,全体として新羅人の国である)。
いかにも多様な神社があるように見えても,神輿など全く共通する様式であり,さらに,全ての神社を統括するのが伊勢神宮といいながら,実質的な力を発揮していたのは宇佐八幡宮であることは,その後の歴史が示す通りで,出雲大社を裏の統括として,神無月に対する神有月とするなどして,神社全て,すなわち民族全てを,秦氏がコントロールできるようにしていることが分かるだろう。唐突ではあるが,現代の甲子園野球なども,そういった多様な民族の血の調和や統合を図る仕組みといえよう。さらに,常に一つのもの(ナタデココのバカ騒ぎなど)や一人の人(長島茂雄など)に指向を集中させようとするのも,何とか多様な民族を繋ぎとめようとするためで,その極端なものが日本人単一民族説になったといえるのだろう。
ついでながら,日本神話に関わる道教がどうなったかを確認してみると,応神天皇渡来時の中国(三国時代)は,道教の仙人を崇める宗派の反乱が相次いでいたといわれる一方,山東省を中心に,宗教としての体系化も一気に進められて,徐福も担った神仙思想の経典の筆頭「三皇経」が重視され,そのなかには,世界に最初に登場する三人の帝王として,天皇・地皇・人皇が挙げられている。道教は,新羅にも伝わっていて,秦氏がそれらの知識を携えて渡来し,天皇中心の神話体系の構築に関与していったとも考えられるのである。
最後に,神社とともに日本を支配することになる仏教について触れておくと,神社体系が,民族それぞれをまとめて国家に統合しようとしたのに対して,仏教は,階層それぞれに対応するものとして,各宗派が登場する。律宗・三論宗・華厳宗などは大陸から移入したままのものであったが,空海の真言宗,最澄の天台宗が朝廷(天皇と公卿),浄土宗が広く貴族に,禅宗では,道元の曹洞宗が個人の確立を求めて広がらなかったのに対して,栄西の臨済宗が武家政権と密接につながり,親鸞の浄土真宗は農耕民族の救済に,日蓮宗は主として商人に対応,そしてあたかも白山信仰のようなものとして,社会の最下層の人たちに対応する時宗が登場するのである。
この章TOPへ
ページTOPへ
ここから先は,いわゆる歴史時代に入るので,日本史話の第二講の「時代循環のパターン」も参照してもらいたい。この章が「古代」で,のちの章では,「中世」「近世」「近代」という枠が登場する。>時代循環のパターン
(マツ系の名残の)葛城氏と(物部氏系の)吉備氏をともに制圧して統一を実現した雄略天皇が,倭の五王の最後になっているのは,国土を確立して中国の力を必要としなくなったのか(江戸時代の鎖国のように),中国側の動乱によって朝貢そのものができなくなったのか分からないが,中国のお墨付きが無くなり,雄略天皇が覇権をとるにあたって有力な対抗馬を次々と消していってしまったため,その後は天皇家自身も力が急速に衰退,天皇陵も急速に小型化して行き,武烈天皇に至って,ついに,後を継ぐ子がいないという事態に陥る。
天皇の血が途絶えるのを阻止すべく大伴金村が活躍して,前述したように,渡来した応神天皇が越前の角鹿(ツヌガ・現在の敦賀)まで至った際に,土地の豪族の娘に産ませたと思われる子の末裔という由緒ある人物を探し出し,507年に,継体天皇として擁立する(まさに体を継ぐというこの名は,前述したように,ずっと後になって,淡海三船が歴代天皇の漢風諡号を一括撰進した時につけられたもので,この天皇の役割を直截に示している)。継体天皇擁立時に越(古志)つまり現在の北陸地方の話が登場するが,のちに,大和にある山と同名の二上山を足場とする大伴家持に古志の歌があるように(ついでながら万葉仮名,つまり漢字を用いた音表記は朝鮮のものとほぼ同じであった),大伴氏と越の関係が深かったからと思われる。>漢風諡号
すでに述べてきたように,大伴氏は(オシ系の)崇神東征を支えた氏族で,継体天皇にオシ系の妃を迎えさせ,後継した三人の皇子,安閑,宣化,欽明の三代の天皇は,いずれもその倭名にオシを含むように,継体天皇を利用して,徐福につながるオシ系皇統が再興されたことにもなり,物部氏の勢力が伸長するように見えたが,継体天皇陵とされる古墳は再び大きなものになるものの,その場所は北摂の淀川沿いで,大和や河内の天皇陵から遠く離れた場所であり,つまり,継体天皇が,大和からは受け入れられなかったということも示され,そのことが,次の蘇我氏による王権簒奪の傍証になっているように見える。
水谷千秋「継体天皇と朝鮮半島の謎」によって,継体天皇のことを少し詳しくみてみると,かつて仁徳天皇が河内入りした時,秦氏と新羅人の一部は,そのまま淀川を遡り,途中で太秦という秦氏の拠点(その背後には新羅人の広がる嵯峨野がある)を造った後,近江に至り,高島郡を秦氏の拠点として,近江全体が新羅人の広がる滋賀の国になって行くが,継体天皇を生み出すことになる秦氏は,ここで新羅人とともに,故郷の朝鮮半島と交易し,財政基盤を固めて行く。ついでながら,高島郡(現在は高島市)は,その後も,すべての政権にとって,歴史的な要所であると認識されていたようで,足利の代々の将軍も,ここに,立派な庭園を持つ別邸を造っていたといわれる。また,近年,衰退の著しい百貨店業界で,唯一,健闘している「高島屋」は,創業者飯田新七が婿養子に迎えられた,高島郡出身の米屋の屋号によるのであり,三井はじめ,いわゆる近江商人と同様,秦氏すなわちユダヤ人と関係していると思われる。
継体天皇当時,関東最大の氏族は上毛野氏であったが,一族から朝鮮半島に渡航した者が多いことから,新羅人だったと思われ,のちの新田氏,足利氏の祖になったとも考えられる。河内国の仁徳天皇ゆかりの地を示す讃良郡には,そのまま馬飼首一族が残っていて,継体天皇家とも繋がっていた。この近くの寝屋川には京都と同じ太秦の地名もあり,秦氏のもう一つの本拠地であったし,淀川流域には秦氏が広く分布し,継体天皇を支える役割をしたと思われる。
継体天皇は,九州有明海沿岸勢力(かつての狗奴国(クマ系)の末裔が主体)と組んで,マツ系・出雲族の末裔葛城氏に対抗し,継体天皇が大和で居を定めた磐余玉穂宮は,当然のことながら,もともと(クマ系)大伴氏の本拠地で,その前にいたのは妃の実家にあたる忍坂宮(オシ系)だった。継体天皇とともに近江から大和に進出したシラギ系とみられる蘇我氏は,衰退した葛城氏の権益を相続して,急速に伸長して行く。磐井の乱後は,有明海沿岸勢力と疎遠になって行くが,百済の武寧王と密接な同盟関係を結び,五経博士が来日,蘇我氏が仏教を背景に覇権を狙うようになって行くのである。
その間,朝鮮半島では,532年に任那が新羅に降伏,任那の王族が新羅の最高官位を与えられるが,朝鮮半島における倭の国際交易上の権益は失われた。任那の王族が丁重に扱われたのを見て,安羅の王族が新羅に接近,562年には安羅その他を含む加羅が新羅に制圧され,倭とつながった加耶諸国全てが滅亡するに至って,朝鮮半島は名実ともに三国時代に入り,564年には新羅は北斉に朝貢して初めて(高句麗の属国でなく)独立した王国として認められる。新羅の高官として扱われる安羅の王族で日本に渡来したのが,蘇我馬子その人ではなかったかという説すらあり(中臣鎌足が百済の王子だったという説を彷彿とさせる),自らの出身を示す(安羅国の村)アスカ,すなわち飛鳥を本拠地とすることになる。滋賀県草津に新羅王子が祭神の安羅神社があるのも関係しているかもしれない。つまり,蘇我氏は,仏教を採用したことで,みかけは親百済でも,もとは新羅に近かった可能性が高いと考えられるのである。
そして,581年に建国した隋が,589年中国全土を再統一すると,百済と新羅が積極的に朝貢するなか,高句麗は距離を置き,半島全土を支配すべく百済・新羅への侵攻を企図,両国から助けを求められた隋の2代目煬帝が高句麗征討に乗り出すと,その間を狙って,百済が旧加耶諸国領を回復すべく新羅に侵攻する。
以上のように,継体天皇の側近として伸長したとされる蘇我氏であるが,朝鮮半島で日本とつながりの深った百済系の伽耶諸国のうち,とくに,日本府が置かれていたという安羅の王族出だという蘇我稲目が,継体天皇の子の2人天皇を弑殺し(後を継いだ形跡が無い),欽明天皇を擁立して,新たな文明たる仏教を武器に覇権を握ろうと,親百済政権を樹立(王権簒奪)したらしく,大伴氏が再び勢力を拡大するはずのところ,直後に金村が失脚する事態になったのは,その陰謀によるものと考えられる。蘇我氏にとって,残る大きなライバルは,オシ系以来の神道を支える物部氏ということになり,神道を支配する物部氏に対して,仏像崇拝問題を利用して,暗躍することになるのである。
筑紫磐井~オシ系のルーツたる九州北部の有力者で,抵抗するもハタ系王朝に敗れた~
継体天皇21年(西暦527年)に起きた「磐井の乱」は,筑紫磐井が,新羅の支援を受けて倭王権と対峙した大事件として「日本書紀」「古事記」に記され,任那復興のために派遣された近江毛野を阻止したことに始まり,毛野が'昔は同じ釜の飯を食ったではないか'というも,'使者になんか従わない'と戦を起こしたため,物部麁鹿火によって討伐された。古代史の会「人物で学ぶ日本古代史 1:古墳・飛鳥時代編」(2022年)によれば,「反逆者か,もう一人の王か,それとも」のサブタイトルがつけられている磐井が生前に造った自らの墓は,福岡県八女市岩戸山古墳とされ,北部九州では最大規模で,ムリテの江田船山古墳に近いことからも,倭王権の最有力者であったとみられ,この事件は,倭王権が,新羅を中心に独自の外交ルートを持って危険な存在となっていた磐井を討伐して,その一元化を実現したこと,それ以上に,磐井の力の象徴だった糟屋屯倉が献上されて,ミヤケ制が始まり,それによって国造制が成立したことが大きく,歴史のターニングポイントであったという。
欽明天皇~その子は,敏達,用明,崇峻から,歴史上,生没年の明確な最初の推古天皇まで兄弟~
一般には,継体天皇をして,現在の天皇に至る一つの王朝としているが,古代史の会「人物で学ぶ日本古代史 1:古墳・飛鳥時代編」(2022年)によれば,継体は,前大王との血縁関係で正統性が無く,仁賢天皇の娘手白香と結婚したことによって担保されており,厳密には,両者の子の欽明天皇によって誕生したことになる。継体に続く,尾張連草香の娘目子媛との子,安閑,宣化天皇については,即位年,没年にいろいろ矛盾があり,欽明を認めないグループとの対立があったためで,両者の存在さえ疑わしいとする説すらあり,また,天皇の権威を確立する部民制,ミヤケ制の導入,任那復興会議が開催されること,日本独自の厚葬墓である前方後円墳に葬られた最後の大王であることなどから,現在に続くサブタイトルにあるように,「世襲王権の始祖」とみなせるという。実際,欽明没後に即位したのは宣化の娘との子敏達,その没後は蘇我稲目の娘との子用明,続いて,稲目の別の娘との子崇峻,そして,用明と同母で,敏達の皇后であった推古が,歴史上,生没年の明確な最初の人物として登場,欽明から世襲王権が開始され,政体の安定化,国家の形成が大きく前進したのである。
隋という強力な帝国が中国に登場したことを背景に,(後に,織田信長がキリスト教を笠に着て,既成仏教を叩いたように)蘇我馬子が百済伝来の仏教を笠に着て,オシ系がつくった神道を支える物部守屋を討滅するという,史実が明確になっている日本史上最初の大事件(587年の丁未の変)を起こし,倭名に「ササギ」が入る崇峻天皇を擁立するものの,意のままにならないことから,弑殺するという恐るべきことまでして,いずれも血縁のある推古天皇を擁立,聖徳太子を摂政にして,まさに,蘇我王朝を実現するのである。
ここで再び倉塚曄子「古代の女」によって補足すると,日本古来のヒメミコ制,つまり,霊的能力をもった女王と,その兄・弟の男王による国家支配の名残がまだ生きていて,推古天皇を戴かざるを得なかったということになり,男王として,甥の聖徳太子が摂政にされたと考えることができるだろう。
実に,中国では蘇我馬子が王であると思われていたということで(後の江戸時代に徳川将軍が王と思われていたように),有名な小野妹子も,中国で蘇因高と名乗っているので,蘇我馬子その人ではないかとさえ言われるほどであった。伝説にすぎないかもしれないが,憲法十七条など,日本の原型を創り出すとともに,「天皇記」「国記」などの史書編纂をしたというから,(政権の正統性を示すべく)日本神話の第一段がまとめられたと考えられる。
守屋の遺族たちは諏訪へ落ち延びてモレヤ神となり,善光寺には守屋柱,諏訪大社のご神体守屋山となるに至ったことは既に述べたが,そのことが物部氏がいかに全国的に強大な勢力を持っていたかを示すものといえるだろう。いずれにしても,蘇我氏が陰謀をもってライバルを潰して行き,天皇を戴いて実権を握る姿は,次に登場する藤原氏を彷彿とさせる。しかし,百済王族出身の中臣鎌足からみれば,蘇我馬子は配下の一小国の王子に過ぎず,滅ぼされることになるのである。ずっと後,(マツ系とはいえ,呉では被支配層の末裔)豊臣秀吉と(マツ系本流の呉太白の末裔)徳川家康の関係と同じように見える。
以上見て来たように,徐福渡来後,さらに言えば卑弥呼登場後,いわゆる天皇を擁立して実権を振るう支配層が,朝鮮半島との関係で親百済,親新羅のような形で交替してきたが,朝鮮半島での相克が高まるのに対応して,この傾向が明確になって行く。これまで,当然のごとくに,天皇の呼称を使ってきたが,実際は,大王(オオキミ)といわれ,各豪族間の綱引きの力関係で定まるものであった。史実が明確になっている日本史上最初の大事件(587年の丁未の変)を制した蘇我馬子が,推古天皇を擁立したのは,それまでの豪族間の調整を無視する力づくのものであったことで,新たな時代に入ったことを示すと同時に,推古天皇もまた生没年が確実な初めての天皇ということで,587年は,日本史年表の起点となり,ようやく歴史時代に入るわけである。
物部氏の滅亡によって,神武・崇神・応神・継体皇統という形で続いてきたオシ系とそれにつながるハタ系の天皇による支配も終わったと言える。聖徳太子は厩戸皇子であり,その生誕伝説がキリストのそれに極めて似ていると言われるが,おそらく太子も頭脳明晰であったことなどユダヤ人であり,その伝説は,秦氏を介して中国から伝来したネストリウス派キリスト教(景教)の影響で,キリストに並ぶ天才として創り上げられたのだろう。本拠地が斑鳩の里で,まさに河内と大和の境界であること,秦河勝が広隆寺を建てるのを支援したこと,平安京遷都の前にすでにあったとされ,聖徳太子によって造られたという六角堂も,その形は,ダビデの星に由来すると考えられることなど,秦氏と極めて強い関係にあり,なお応神皇統が続いていることにもなるが,聖徳太子の死とともに,秦氏すなわちユダヤ系の人たちの力は一気に没落,蘇我馬子の子蝦夷が一族を無きものにしてしまうに至り,応神皇統は完全に終わりを告げる。
聖徳太子に関連する史跡は,推古天皇陵などとともに,応神皇統の天皇陵の集中する河内と大和を結ぶ斑鳩にあるが,聖徳太子はオシ系(ハタ系)最後の華であり,それが太子信仰を生んだのだろう。フリーメーソンとの関係が取り沙汰される日本銀行発行の高額紙幣に聖徳太子像が使われたのもムベなるかなだ。太子の遺児一族も抹殺されてしまうと,ユダヤ系の秦氏を繋ぎとめるものもなくなり,ヨーロッパのユダヤ人と同じように,次第に差別され貶められ,芸能などを業とするいわゆる河原者にもなって行ったようだ。
ところで,天皇制のことを考えてみると,その権威が,位階の授与と元号をはじめとする暦によっているのはいうまでもないが,その二つともが,大陸から輸入されたもので,日本古来のものでは無く,大和魂などを強調する面々にとっては最大の矛盾といえ,天皇の存在を危ういものにすることも否めない。その解決策として創り出されてきたのが,聖徳太子という人物と,その伝説であろう。それ故,近年,「聖徳太子はいなかった」というような過激な書物が出たし,確かに,聖徳太子の具体的な史実はあまり定かではなく,今後,蘇我氏との関係も含めて,見直しが求められる。
こうして,蘇我氏のいわゆる専横が始まるが,大陸では,隋は4度にわたって高句麗に侵攻するも成果があげられなかったばかりか,隋本体の疲弊を招き,部下の反抗を受けて618年煬帝は暗殺され,李淵が唐を建国するに至る。唐は,隋を超える圧倒的な力を背景に,朝鮮の三国をそれぞれに,中国支配の古地である遼東郡,帯方郡,楽浪郡に割り当てる形で冊封し(高句麗はランクとして一つ上に扱われた),安定を図ろうとしたが,唐の権威を背景に百済が新羅への侵攻しようとすると,新羅は隋との戦いで疲弊していた高句麗への侵攻を図るというように抗争は続く。新羅に初の女王が登場後,642年に,百済は旧加耶諸国領の回復を実現し,久しぶりの隆盛迎えるが,新羅の力を得られなくなった直後の645年に,百済王族と思われる中臣鎌足が中大兄皇子を唆して蘇我氏を討滅(乙巳の変)するに至るのである。
一行にまとめてしまえば,百済王族中臣鎌足が天智天皇とともに端緒を開き,王権簒奪した天武天皇が天皇,日本の称号はじめ骨格をつくり,持統天皇が天皇を神にし,藤原不比等が日本神話を仕上げ,クダラ的藤原氏の時代の礎をつくったということになろう。全く別の角度からみれば,皇極(斉明)天皇に始まり,持統天皇という存在感大きい天皇を経て,不比等が擁立した元明,元正天皇,そして,不比等の娘で,聖武天皇にもまさる存在だった光明皇后,そして,その娘の孝謙(称徳)天皇が天皇制の危機を招くという,実に,転変著しい女帝の時代でもあった。
専横はなはだしい蘇我入鹿は,蹴鞠を通じて親しくなったという中臣鎌足に唆された中大兄皇子により,645年に,滅ぼされるのであるが(乙巳の変),張本人たる中臣鎌足が,突然のように歴史に登場してくることが,かねてより,謎であった。このことについて,朝鮮三国時代の百済のところでも触れた,関裕二「藤原氏の正体」のいうとおり,554年に新羅に完敗した百済から,再興を図るべく日本に亡命した王族のなかに,中臣鎌足がいたとみるのが分かりやすく,631年に人質として来日していた王子扶余豊璋その人だったとしても不思議はないと考えられる。前節で,安羅出身だった蘇我氏が,アスカ(飛鳥)を本拠地にしたのと同様,おそらく支配地だった伽耶(カ)出身を示す村(スカ),すなわち春日(カスガ)を本拠地としていたことからも予想されることではあるが・・・。
641年,27歳の時に歴史に忽然と登場した鎌足は,631年には18歳ということで,まさに王子扶余豊璋にふさわしい年齢であり,百済滅亡翌年には各地で百済の遺臣らによる復興軍が蜂起,そのうちの鬼室福信が倭に渡来して,631年以来人質に置かれていた百済王子扶余豊璋の帰国を要請している。(新羅で武烈王が崩御した)661年には,中大兄皇子が,その帰国を認めるとともに派兵も決定するが,662年に帰国した扶余豊璋は,翌年,鬼室福信の謀叛を疑って殺害させるなど内部抗争もあって,倭・百済復興軍は有名な白村江の戦で,唐・新羅連合軍の前に大敗してしまう。中大兄皇子が政権奪取した乙巳の変には大々的にでてくる中臣鎌足が,その後の動静についてほとんど明らかになっていないことも,このように動いていたのだとすれば頷けよう。なお,新羅の配慮で,倭の残兵は百済の遺臣とともに帰国し(新羅のやり方には常に敗者を丁重に扱う特徴が見られる),倭に残っていた扶余豊璋の弟はそのまま帰化して百済王(コニキシ)という姓を与えられている。
ところで,のちに,大内氏の本拠になる山口の西側部分は吉敷川を軸にした吉敷とういう地域で,そのまま名字にしている人たちもおり,"キシキ"と読まれている。もともとの"キシキ"という語に,漢字を当てたものであることは,当然とみられ,歴史との関係で,各所に見られる"〇〇キ"という語と同様,"キシ"という人たちが来たところを示すだろう。そこで,"キシ"とは何ものかを調べてみると,なんと,「釈日本紀」の秘訓に,百済の王族を示すものとして,"君"を"キシ"といい,"王"は"コキシ",大王になると"コニキシ"という訓みが伝えられているのである。扶余豊璋の弟に与えられた百済王(コニキシ)という姓のもとの語が"キシ"なのであるから,まさに,吉敷の地は,百済王族がまとまって亡命してきたこと場所だったのである。>大内氏
ついでながら,百済亡命後,倭に亡命し,百済復興をめざした百済王族鬼室福信の姓「キシツ」は奇妙な感じがするが,"キシ"が百済王族のことを指す語であると知れば,「"キシ"つ」は,すなわち「"百済王族"の」と単刀直入の姓であることも分かり,百済奪還をめざして,斉明天皇率いる倭軍が潮待ちをした伊予国熟田津の近くには,来住と書いてキシと読む町もあることにも興味が惹かれよう。
その山口のすぐ北側が長門国,すなわちナカ系の本拠地のひとつであったことから,そのナカ系の支援も得て渡来した百済王族が,中臣氏の姓を借りることになったのは自然の成り行きだっただろう。そして,古代では,皇子の名に,乳母の家柄の名が入れられるのが習わしだったということなので,中大兄皇子の乳母がナカ系であったことが知られ,鎌足との縁が,幼い時からのもので,以心伝心の関係にあったことすら示しているのである。鎌足の死去から,その子の藤原不比等が登場するまでの様子も不明であり,長州(山口県)が,重要な役割をしていたとみて良いだろう。
神武東征伝説から,応神東征説までを,振り返ってみても,どういうわけか,現在の大分県,宮崎県から,四国に渡り,そのまま東進,あるいは岡山県を経て東進というように,山口県が避けられており,朝鮮半島の諸国との関係で,奴の国を迂回しなければならなかった事情があったと考えられるので,百済王子を匿うには絶好の場所でもあったのではないだろうか。
さらに,内倉武久「謎の巨大氏族・紀氏」によれば,年号(元号)が日本全体に行き渡る正式なものになったのは,大宝律令による大宝からで,それ以前には,いわゆる私年号があちこちで使われており,そのほとんどが朝鮮で使用されていた年号で,九州年号といわれる。"市民の古代研究員"によって発掘された一覧を見ると,長野県善光寺のように存在そのものが特別なものは別にして,山口県での使用例が異常に多いことが分かる。つまり,長州では,百済の年号を使い続けていたと考えられるのである。
鎌足の本姓は,藤氏だったことから,藤原姓を与えられ,のちに藤原不比等が,わざわざ藤原姓を自らの一族のみに限るとして,中臣姓の痕跡をも消そうとしたのも当然であった。蛇足ながら,鎌足は当初,鎌子と呼ばれており,"子"というのは,孔子,孟子と同様,単なる敬称であるとすれば,鎌(カマ)の語に意味があるように見える。鎌の字がそのままを表しているとすれば,まさに鉄器文明化した農耕民族,つまり百済に近いことが示され,長州の本拠地萩に鎌浦の地名があり,カマが釜の字になると,現在でも,長州の下関とフェリーで直結する韓国の釜山につながることになる。
(付)最新の資料による中臣鎌足の百済王子説の再検討。
新古代史の会「人物で学ぶ日本古代史 1: 古墳・飛鳥時代編」(2022年)において,まず「中臣鎌足~積善藤家の祖~」の項をみると,知られている鎌足の伝記は,「日本書紀」には極めて簡単に,「大織冠伝」には,かなり詳しく記述されているものの,前者は藤原不比等が藤原氏の正統性を示すべく差配し,後者は藤原仲麻呂が,藤原氏の祖たる中臣鎌足の偉大さを強調すべく独自のアレンジを加えたものであって,そもそも,資料としての価値が疑われるものであるが,後者に従えば,まず,「舒明朝の初めに良家の子を簡び錦冠を授け朝廷の祭祀を掌る中臣氏の宗業を嗣がしめたが,鎌足だけは固辞して摂津三国の別業に退いた」という。>そもそも中臣氏ではなかったということではないだろうか。また,中大兄皇子が天智天皇になったことを禅譲と強調しているのは,孝徳と対立して飛鳥に帰還した直後に,紫冠と封戸が与えられたということなどから,そもそも,鎌足は軽皇子(孝徳天皇)の即位を画策し,孝徳天皇とは良好な関係にあったが,天智天皇に乗り換えたのであり,蹴鞠伝説などは,大陸の類似の話の借用という。>いずれにしても,皇位に就き得る人物を利用して権力を築こうとしたということになる。究極の創作は,孝徳天皇が即位した大化元年に大錦冠を授けられたという話で,大錦冠が制定されたのは大化3年であり,そもそも,鎌足の改新に関わる事蹟は,ほとんど史料上にみられないという。>要するに,全く異なる扱いを受ける立場にあった人物ということになろう。鎌足は死の直前に,天智天皇から大織冠と大臣の位と藤原姓を賜与されたが,大織冠は後述する百済王子豊璋のほかに例はなく,死去すると,百済からの亡命者沙宅紹明がその碑文を撰したという。さらに,正室は鏡女王とされているが,王族を妻とするのはあり得ないと,虚構説もあるという。>鎌足が百済王子であったことを示しているといえるのではなかろうか。
もう一つ「余豊璋と百済王子~百済王家の滅亡とその後裔~」の項をみると,百済王子余豊璋は,倭に滞在中,百濟が新羅に滅ぼされたため,その翌年の661年,復興を目指す鬼室福信ら遺民の要望で帰国し,百済王に冊立されるも,その翌年,確執を生じていた福信を斬殺,白村江の戦に敗れ,高句麗に逃亡し,以後,消息不明とされいて,本当に百済王子であったのか,いつ来日し,それは,亡命か,使者か,人質かが謎とされている上,帰国に際して,中大兄皇子から織冠の位を授けられ,多氏の娘を妻に与えられて故国に護送されたという。そして,兄豊璋とともに来日したという弟善光が百済王氏(クダラノコニキシ)の祖になり,有名な百済王敬福らを輩出したという。>前述の話と符合する上,その後は不明になっていることから,鎌足百済王子説を否定し去るには不十分で,百済王族を示すキシの名が後々大きな意味を持って行くことも,大内氏の項で述べることにつながると言えよう。
なお,政権獲得にあたって,蘇我氏によって没落させられた物部氏の復活の願望も取り入れたとすれば,本来物部氏のものであった鹿島神宮を自らのものにしてしまうことができたと思われる。
この間,大陸では,唐の太宗も相変わらず目の上のタンコブのような高句麗の存在に,同じ645年には,その征討を企図して出兵し,各地で激戦を繰り広げるが,結局全軍の撤退を余儀なくされ失敗に終わる。その後,新羅の内紛に乗じて百済が再び侵攻したため,新羅は倭に助けを求めるも,乙巳の変後で叶わず,新羅の金春秋は,649年から,唐の服装採用を許可されてその権威が利用できたのも束の間,太宗の崩御によって窮地に陥いるが,この年侵攻してきた百済を,軍事力というより軍の統制が断然上回っていたことで撃退すると,654年,群臣に奉じられて武烈王になり,早速,唐の律令を模範に格を制定する(日本で天武天皇が中国の諸制度を採用するのに対応するといえよう)。翌年,百済は再び新羅に侵攻するが,659年,武烈王の要請を受けた唐の高宗が出兵し,ついに滅亡してしまう。余談であるが,後の日本の源平の戦いで,源氏が勝利したのはその統制力であったとされ,源氏がシラギ系であったことを示すものでもあろう。
(付)伊予国,そして熟田津
滅亡した百済を奪還すべく,斉明天皇が率いた軍が,潮待ちのために滞在した伊予の熟田津について,額田王の有名な歌があるが,額田王は壱岐国の出であり,アマ系すなわち卑弥呼の末裔にも当たる巫女的な女性であったと思われる。卑弥呼が死んだ後を継いだのが臺(台)与(トヨ)で,トヨの国のもとになったとされるが,トヨはまた,壱岐由来を示すように,壱与すなわちイヨとも表記され,伊予の旧表記が伊与であったことを見れば,そのまま壱与であり,豊後灘を挟んで,豊の国の向いの伊予国のもとにもなったと考えられる。想像をたくましくすれば,トであり,イであるのは,ものとの伊都国を二つに分けたものでもある。とすれば,額田王にとっては,熟田津こそ,自らの原郷であり,それ故にこそ,あの傑作が生まれたともいえよう。
その伊予では,崇神朝との微妙な関係をともにし,すでに支配していたクマ系の久米氏と一体になったようである。ついでながら,同じクマ系の紀貫之が土佐に出向したのも,照葉樹林民族としては当然であったろう。そして,周防灘を挟んで向かいの周防国の吉敷(キシキ)が百済王族末裔の地であることを示すように,伊予にもまた,来住と書いて,キシという地があるように,百済王族末裔もいたようである。実際,百済奪還をめざす倭軍には,百済王族の鬼室(キシ・ツ=の)福信が将軍としていたのである。しかるに,歴史時代に入ると,伊予の国衙は,物部氏出身とされる越智氏が支配する現在の今治に置かれようになったのである。記紀には,伊予国についての記載が非常に少ないということであるが,大和朝廷には記すのが困難な地でもあったのだろう。
(付終り)
ここでまた,道教の話になるが,大帝国だった唐は,実は,仏教を蔑み,道教を重んじた国だったため,仏教を究めるべく遣唐使の船で唐に渡った日本の僧は,有名な円仁をはじめ,苦労することになる。そもそも,あの鑑真が,あれほどまでの困難を乗り越えて日本に来ようとしたのも,唐の仏教の行く末に絶望していたからと考えられる。いずれにしても,政権のために,遣唐使が持ち帰ったものは,道教にかかわるものが多かったということになり,後述するように,神話体系の再構築にも大きな影響を及ぼしたといえよう。
ようやく即位できた天智天皇が,670年に,日本で最初の整った形での全国的な戸籍「庚午年籍」を始めたこと,現代の戸籍が,明治維新後の,明治5年式戸籍(一般的には「壬申戸籍」に始まることは,良く知られているが,戸籍が,日本人全てを登録したものであると言いながら,天皇には戸籍が無く,苗字も無いのである。このことは,天皇のルーツはもちろん,その時代における,天皇の血のつながりをも隠そうとするもので,結果として,いわゆる万世一系が成り立っているのである。おそらく,ルーツに関わったユダヤ人の知恵だったのだろう。
さて,中臣鎌足の登場は,新羅が支配する朝鮮半島を追われた百済が日本を支配しようとしたことによるものではあるが,乙巳の変で蘇我入鹿を滅ぼすものの,天皇家そのものは新羅渡来の応神皇統の延長にあり,蘇我氏全体との関係も途切れず,親新羅の姿勢を変えなかった孝徳天皇が654年に崩御して後も,斉明天皇の力が強く,なかなか即位できないうち,鎌足の意向に添うべく新羅に侵攻して,663年,白村江の戦で大敗,その圧力を避けるべく667年,大津京に遷都,翌年に母天皇が死去して,ようやく即位し,鎌足に藤原姓を授与するものの,まもなく死去,壬申の乱に突入することになる。
斉明天皇は,中大兄皇子の母で,史上初めて皇后から天皇になった皇極天皇が,史上初めて重祚して斉明天皇になったのであるが,庭園等の大きな施設を造ったことが,遺跡の発掘で明らかになっており,そのなかで,「天宮」とも呼ばれた両槻宮(フタツキノミヤ)という建物は,道教の,仏教でいえば寺院にあたる道観である可能性が高く,庭園も,道教の神仙思想にもとづく様式であったようで,それほど,道教の影響の大きかったということである。
ここでまた,倉塚曄子「古代の女」をみてみると,大化の改新とはいいながら,なお,ヒメミコ制の名残は続いていて,国家の安定支配のためには,霊能の力を持った女王の存在が必要であったことから,母に重祚してもらった(この場合のミコは兄弟でなく男子ということになる)といえるが,「日本書紀」には,斉明天皇は巨大な土木事業などによって人民を苦しめたというのをはじめ,きわめて悪い女帝として描かれていて,律令国家にとって,霊能は排除されるべきものという建前もさることながら,自らの支配の正統性を示すことを目的として神話「日本書紀」をまとめた藤原不比等の意図が反映しているようである。つまり,自らの父が担いだ天智天皇の立派さを示すため,その時代に生じたマイナス面は全て斉明天皇に押しつけようとしたということである。
いずれにしても,中臣鎌足の段階では,蘇我馬子が,推古天皇を戴いて覇権を握ったようにはいかず,その方式を確立するのは,子の藤原不比等に託されるのである。
天智天皇が崩御すると,その翌年の672年に,その後継の大友皇子に対して,天智の弟の大海人皇子が謀叛,大内乱となった壬申の乱を制して,天武天皇として即位,まさに,王権簒奪であり,大海人皇子は,その名が示すようにアマ系の海部氏,すなわち,応神天皇を支えた氏族に養育されていることから,シラギ系の巻き返しでもあった。新羅からの圧力への恐怖から,諸豪族の間に,親新羅の強力な天皇を求める意識が芽生えたことが,その背景にあったともみられ,後の元寇や明治維新など,日本人は内部では抗争していても,大きな外圧が生じると一気に神国として一体となってしまうあり方がこの時生まれたともいえるだろう。
天武天皇は,皇族を重視する親政により,ヒメミコ制から男王支配への一元化を完成させただけでなく,浄御原令によって本格的な律令制の導入を図るとともに,初めて,日本という国名や,天皇という呼称を用い,史書「日本書紀」編纂に着手するなど,現在につながる枠組みをつくり,さらには,本格的な首都となる藤原京の建設も企図したが,志半ばで倒れてしまう。一つだけ触れておくと,天武天皇は,国土支配の枠組みを評制から,郡制へ変えたのであるが,その令を諸国に出すにあたって,長門国のみ除外していて,学界の謎とされてきたが,長門がそもそも藤原氏の支配下にあったことを考えれば当然であったといえよう。
クダラ系天智天皇の娘でありながら,諱が鸕野讚良(ウノノササラ)というように,シラギ系であるままに,天武天皇を支え続けた持統皇后は,夫の遺志を継ぐべく,とりあえず称制し,天武天皇との間の子である草壁皇子を皇位につかせようとするものの,夭折してしまったため,自らが天皇に就くことを企図するが,そこで障害になったのが,夫の天武天皇が王権を簒奪したという事実であった。そのため,天皇の地位というものが,神から授かれるもの,いわゆる天皇神授による正当化を図るべく,現在では当たり前のように思われている,天照大神から始まる神話や,それに対応する儀式などを創り上げたのである。>神様の家系図
何度か触れてきたように,神武天皇からの歴代天皇の漢風諡号は,孝謙上皇皇時代に,淡海三船が一括して撰進したものであるが,持統の名は,継体持統という熟語からとったもので,継体天皇同様,断絶を回避する役割を担った天皇であることを示しているので,その存在は,正確に認識されていたといえよう。ついでながら,天智,天武と,神でなく,天を用いて両者をセットにしたことは,その後の日本の創始者であることも示そうとしたものだろう。>漢風諡号
壬申の乱によって,中臣鎌足の試みは頓挫するかに見えたが,その子藤原不比等が,持統天皇に仕え,天皇の覚え目出度かった女官県犬養(のちに橘姓を与えられる)三千代に接近して,婚姻関係を結ぶと,持統天皇が天智天皇の娘であったこともあって,おそらく,前述の天皇神話づくりの相談にものるなどして地位を築き,藤原姓を自らの一族,すなわち正統的百済王族に限ることを実現し,百済に学んで,日本史上最初で最大の都城であるとともに,藤原の名を冠する藤原京の建設や,大宝律令の編纂も主導,その完成直後に,持統天皇が死去すると,以後,蘇我馬子が推古天皇を戴いたのと同じように,藤原不比等は,元明天皇,元正天皇を擁立して覇権を確立するのである。
この間,朝鮮半島では,百済滅亡後,高句麗内に政治的混乱が起きたのを知った唐の高宗が,前回の失敗を取り戻すべく,666年に出兵を決定,668年,扶余城を落としたのに続いて,新羅にも出兵を命じ,平壌城を陥落,こうして,朝鮮において,最も歴史が古く勢威もあった高句麗もついに滅亡してしまう。その結果,唐の圧力が直接及ぶ状態になるとともに,高句麗遺臣らの復興運動にも悩まされた新羅が,高句麗王族高安勝に金姓を与えて新羅の貴族とし取り込むうち,かつての高句麗北部に靺鞨や渤海が勃興,成長して,唐も朝鮮半島から手を引かざるを得なくなり,735年,唐の玄宗は大同江以南の地を新羅に割譲,以後,統一新羅は安定して成長して行くことになる。
付け加えると,律令国家の形成とともに,巫術・卜術の役割は減じて行くが,なお,諸儀礼の卜定などにおいて重要な役割をしていて,神祇官には卜部が置かれ,かのアマ系卑弥呼のルーツで伊都国に属していた対馬・壱岐から選ばれていたというから,その名残の強さが知られる。その他,伊豆国からも選ばれていたというから,伊豆国が九州北部を追われた伊都国の人たちによってつくられたことも間違いなく,平氏のルーツがイト系であることへの傍証にもなるだろう。
蛇足ながら,仏教史上,聖徳太子や行基と並ぶ重要人物で修験道の祖ともされながら,699年,伊豆に流されたという役小角(エンノオヅヌ)は,かつてマツ系(出雲族)の後裔が拠点とし,百済ともつながっていた大和の葛城の地で生まれ,呪術その他極めて道教的要素を備えた人物であったが,本姓は賀茂氏だったといい,まさに,日本に渡来した当時の呉の国人の遺伝子を体現していて,国譲りして敗れたマツ系のシンボルになったと考えられる。ずっと後の徳川家康が,マツ系の復活であったことを説明する際に,再び登場するだろう。
前項末を繰り返すことになるが,持統天皇が皇后の時以来側近であった橘三千代に,鎌足の子不比等が接近して結婚,権力を握るようになり,藤原姓を自らの一族に限定することにも成功する。702年持統天皇が死去すると,あとを継ぐ適当な男子がいないのをいいことに,蘇我氏の方法をなぞるように,繋ぎとして,未婚皇女を元明天皇,元正天皇としてたてるとともに,新たに平城京という本格的な首都を建設して,単に守旧派を遠ざけただけでなく,天皇,貴族,寺社などが活動する舞台を生み出し,持統天皇が創り上げた"神授による天皇"を支える藤原氏という形で支配を正当化するように,それまでの神話体系「日本書紀」をクダラ系の立場で書き換えて(蘇我氏を貶めて)完成,以後の日本の神話の決定版にしてしまうに至る(「播磨風土記」などの編纂者もクダラ系らしく,不比等が自ら都合よくなる方向でまとめさせた可能性がある)。
この間も,親新羅のアマ系天武天皇系が続いており,その不比等が死去すると,皇族の巻き返しが始まるが,不比等の男子が策謀して長屋王の変を起こし,ついに不比等の娘を,民間初になる光明皇后にして,蘇我氏の血統から,藤原氏の血統への転換に成功するものの,今度は,天然痘の流行で不比等の男子4人が全て死去してしまい,再び天皇側(聖武天皇と橘諸兄)が巻き返しにでるが,光明皇后の存在によってつながれたばかりか,光明皇后が天皇を唆せて,東大寺・大仏や国分寺・同尼寺などの大事業で浪費させ,藤原仲麻呂の智恵で,正倉院に名を借りて,シラギ系が持つ武器その他財宝一切を取り上げてしまったという説まである。
聖武天皇の死で藤原一族も巻き返し,なお親新羅勢力が強いなか,光明皇后の存在を背景に,藤原仲麻呂が覇権を握るが,その専横ぶり以上に,皇族に限られる(オシ系の称号)恵美押勝を名乗ったため,光明皇后が死去すると,その娘で,母と対立していた孝謙上皇に討滅されてしまい,孝謙が重祚して称徳天皇になると,そこに,物部氏に近いとされる弓削氏(弓月国をルーツとする秦氏の可能性もある)から出た道鏡が登場して,称徳に接近して権力を振るうようになり,天皇制自体が危機に陥るに至る。
ここで,クダラ系藤原氏得意の策謀で,769年宇佐八幡宮の神託のバクチを打つことになる。宇佐八幡宮は応神天皇を祀る,つまりシラギ系のシンボルで,神託を受けに行った和気清麻呂の和気氏は吉備地方の出ながら,応神皇統の天皇の倭名に"ワケ"の含まれることが多いように,新羅時代からの天皇側近であったと考えられ,藤原百川らは,これを利用して,クダラ系(天智系)天皇の復活を策し,あまり意味の無い存在だった光仁天皇を介在させた後,ついに,のちに偉大な天皇とされる桓武天皇を登場させ(これが,平成の天皇が述べた百済との関わりの原点),以後,天皇を戴く藤原氏という構図(すなわちクダラ系藤原氏)が長く続いて行くことになる。
この間,すでに,蘇我氏に排除され,藤原氏の覇権で,復活する可能性の無くなった大伴氏の末裔家持による「万葉集」の編纂がなされるが,そののち,紀貫之の「古今集」,後鳥羽上皇の「新古今集」が誕生するように,和歌をして,敗者の生きる道を開いたのである。
ついでながら,この頃活躍する行基の祖の王仁氏は,徐福の故郷山東省出身の漢族学者の家系で,戦乱を避けて,朝鮮北部の漢が建国した楽浪に行き,その滅亡で,4世紀後半に百済経由で日本に渡来したといわれる。
シラギ系が武力によって直截に覇権を握るのに対し,クダラ系は陰謀によって覇権を握るのが得意で,クダラ系藤原氏は,良く知られているように,天皇の利用と陰謀によるライバル氏族の排除によって,覇権を維持し続けるのである。
桓武天皇が,現代までつながるクダラ系天皇の祖として特別な存在になっているだけでなく,その子の嵯峨天皇も,天皇権力をいかんなく発揮したが,その間,桓武天皇を生み出した事実を背景に,藤原氏は,入内によって天皇家の外戚になるという直接な方法とともに,得意の陰謀で,勢力を伸長していく。その端的なものが,皇族がライバルになることを未然に防止することで,有名な桓武平氏を端緒とする,(それまでは,橘諸兄ぐらいしかなかった)臣籍降下で,源氏も,その皮切りは嵯峨源氏であった。桓武天皇が,平城京のしがらみを排すべく,平安京を建設したのも,藤原氏が活躍しやすい舞台を提供したことになり,長く都になるのである。>桓武平氏
桓武天皇は,父光仁天皇の死去で,44歳になってようやく即位したが,すでに十分に実力が培われていて,早くも784年,平城京のしがらみから脱すべく,長岡京遷都を企図するが,翌年,この事業を推進していた藤原種継が暗殺され,しかも皇太弟早良親王が連座して廃され,淡路国へ流される途中死ぬという事件によって,中断しただけでなく,以後,早良親王の怨霊に悩まされることになる。その10年後,ようやく平安京という新首都を実現させると,国土統一のため,蝦夷征討にも本格的に取り組み始め,801年,渡来系の坂上田村麻呂を抜擢して征夷大将軍とし,その巧妙な戦略によって,奥地の胆沢地方まで平定するに至るが,両者に要した巨額の費用が財政の圧迫,民生の窮乏を招き,805年に,参議藤原緒嗣の意見を用いて両事業を停止,翌年,没した。このことからも,独裁的天皇とはいえ,その意見を聞かざるを得ないほど,藤原氏の存在は大きいのである。
桓武天皇の皇后はもちろん藤原氏の乙牟漏で,その第2皇子に誕生した嵯峨天皇は,806年,父桓武天皇の死去後,同母兄平城天皇を支え,3年後,病気になった平城天皇の譲位をうけて践詐したが,810年,平城上皇が寵妃藤原薬子らとともに,多数の官人をひきいて平城旧京に移り,"二所朝廷"の観を呈したため,坂上田村麻呂以下の兵を発して征圧,薬子は自害,その兄仲成を射殺した。いわゆる薬子の変で,その後,都での処刑は保元の乱まで,350年行われないことからも,平安時代は,ある意味で江戸時代と同様,平和な時代でもあった。
ようやく独裁的な力を握ると,朝廷行事の再構築を始め,多くの皇子を臣籍降下し,皇女を貴族に降嫁させたが,とくに寵愛する藤原冬嗣の子良房に,皇女を降嫁させたことが,藤原氏覇権の因になる。820年には,基本法たる律令を補足・修正するための法令集「弘仁式」「弘仁格」を,翌年には,朝廷の儀式を整備して「内裏式」をまとめた後,823年,37歳になると,側近がこぞって反対するのを押し切って,異母弟淳和天皇に譲位,自らは人臣の列に入ろうするも,太上天皇の尊号を贈られて君臨,以後,自動的に上皇になるのでなく,天皇によって与えられる地位となり,存する空間も天皇の内裏とは別にすることが定まった。10年後,淳和天皇が,嵯峨天皇の子の仁明天皇に譲位して後も,上皇のままで,842年,没した。直後に,藤原良房の陰謀による承和の変で,政局はたちまち不安定化,摂関政治の幕が開かれる。
嵯峨上皇の覚え目出度かった父冬嗣以上の力量を発揮するようになっていた藤原良房は,842年,38歳の時に,嵯峨上皇が死去するや,皇位継承の問題から春宮坊で起きた不穏な動きを利用して,伴健岑・橘逸勢らを謀反の罪で捕え,淳和天皇の皇太子を廃し,妹順子の生んだ仁明天皇の子道康親王を皇太子にして,一気に覇権を握る。右大臣に昇り,娘明子を皇太子のもとに入内させ,太政官符や宣旨発給の上卿を独占するうち,850年,良房の専横におされて仁明天皇が死去,文徳天皇が即位すると娘明子は皇后となり,皇子惟仁親王を出産,外祖父となるや,先例を無視して,親王をわずか生後8ヵ月で立太子させる。
857年には,90年ぶりに生前太政大臣に任じられ,翌年,文徳天皇が急逝すると,惟仁親王を,初の幼帝清和天皇として即位させ,事実上の摂政をつとめることになる。世情不安が広がるなか,866年,応天門放火事件が勃発すると,真相究明が進まないうちに,人臣の初の摂政となり,結局,大伴氏末裔で,有能な伴善男に責任を負わせて配流に処し,源信,弟良相らライバルの芽も摘んで,872年,没した。
良房の養嗣子になった藤原基経は,当然のごとく,順調に出世し,872年,36歳の時,養父良房が死去するとともに,初の藤氏長者となり,4年後,清和天皇が自分の妹高子を母とする陽成天皇に譲位すると,摂政に就任,884年,乱行が絶えなかった陽成を退位させ,当時55歳の仁明天皇の皇子時康親王(光孝天皇)が即位。すでに太政大臣になっていたが,光孝の外戚ではなく,地位が不安定なことから,職務内容の明示を求め,実質上の関白となる。ところが,887年,光孝が崩ずる直前に,臣籍に下っていた第7子源朝臣定省が皇太子に立てられ,宇多天皇として即位すると,関白の任務に問題が生じ,職を解かれたのも同然と,政務を行なわず,宇多は結局,屈服させられた。もはや,天皇すら,その職を左右できないほどに,藤原北家を隆盛させて没した。
そして,陰謀の仕上げになったのが,基経の長男藤原時平が仕掛けた,あまりにも有名な菅原道真の左遷であるが,これは,自らも百済王の末裔と称していた三善清行が方略試を受けた際,問答博士だった道真によって不合格になり,一夜にして白髪になったことに始まり,清行は,その後,国司となって「意見十二箇条」を出すほど有能で,その怨念が,時平を動かすもとになったのである。道真の祖はまた,学者家系大江氏の祖でもある土師氏であるが,その名の通り,ルーツは土器(今で言えば陶磁器)製造に携わった氏族で,その先進地の出雲から呼ばれたということなので,遡ればマツ系だったかもしれない。
900年頃に統一新羅の分解が始まり,907年にはあの唐すら滅亡してしまい,918年,王建が,高句麗王を追放し,三国を統一した高麗国を建国するなど,外国からの圧力が無くなっていたことから,藤原氏が,陰謀に明け暮れることができた。909年に,時平が早世すると,兄と違って温厚聡明な弟の忠平が,朝廷の首班となり,930年に,朱雀天皇が即位すると,醍醐天皇の親政で,長期にわたって置かれてこなかった摂政になる。その間,地方の支配は行き届かなくなっており,935年に,ついに新羅が滅亡して,新羅軍兵士が大量に渡来してくると,問題が一気に噴出,日本南関東全体に勢力を広げていた平氏間で覇権を獲得した平将門が,新皇を名乗って,中央に対して反乱を起こし,それに呼応するように,瀬戸内海で,藤原広嗣も反乱を起こすなど,天皇制の危機といえる事態になり(いわゆる承平天慶の乱),辞意を上奏したが認められず,941年,全てが平定されると,何事もなかったかのように,関白になるほど信頼されて,藤原摂関家隆盛の祖になったのである。しかし,次論で述べるように,平将門の乱は,源平はじめ武家勃興の契機となり,結果として,クダラ系藤原氏の政治に引導をわたすことになるのである。
その後は,969年の,いわゆる安和の変で,源高明を排除して後は,ライバルとなるような他の氏族はいなくなるが,陰謀の血筋は,藤原摂関家内での抗争に至り,転変の後,覇権を獲得した藤原道長による最盛期となって,王朝文化が花開くのである。道長の栄華ぶり等は,あまりに知られているので,省略するが,清少納言,紫式部をはじめとする,世界でも類をみない,女流文学の隆盛は,承平天慶の乱の前に,早くに排除されていた豪族紀氏の末裔の紀貫之が,のちに,古今伝授という伝統ができるほどの「古今集」を編纂したこと,それ以上に,'男もすなる日記といふものを女もしてみむとてするなり'の冒頭で知られる「土佐日記」を著したことが契機になっていることを指摘しておきたい。
なお,表向き藤原氏の出自が中臣氏とされていたこともあって,応神天皇以後の皇室の祭祀を司って来た忌部氏の力が削がれ,忌部氏が復活を訴え出るようなことも起こっている。マユツバとも思われるが,'くだらない'の語源は'百済でない','しらじらしい'の語源は'新羅らしい'というように,日本のなかでは,クダラ系の人たちが,シラギ系の人たちを蔑む傾向になったのも,クダラ系政権が長く続いたことによるのだろう。
藤原氏の時代,内部抗争のある間は,優秀な人材が育ち,政権は維持されたが,藤原北家が覇権を握り,世襲化が進むに従って人材不足に陥り(まるで自民党の歴史を見ているよう),道長の死の直後に,再び関東で平忠常が乱を起こし,道長の子頼通には入内させるべき女子が誕生せず,東北地方で前九年合戦が起こるとともに,末法思想が登場したこともあって,衰退が始まる。1068年には,藤原氏系の出生でない後三条天皇が登場,頼通も摂政を辞めざるを得なくなって,衰退が加速する。後三年合戦の最中の1086年に,白河上皇が院政を始め,1107年,自らの子鳥羽天皇を即位させて院政を確立,クダラ系藤原氏政権は終焉を迎える。
院政時代を始めた白河法皇の特異な性格,その最期を飾る,後白河法皇の今様の評価や,絵巻物の創作など,ユニークな文化には,天皇であればできなかった活動が反映されているように見える。また,院政時代の上皇は,盛んに熊野詣でをしたことで知られ,その理由は主として末法思想によるものとされるが,神武天皇が熊野に上陸して大和入りしたことへの回帰,つまり,天皇自身の拠り所を確認して権威を高めようとしたものとも考えられる。
院政時代,藤原摂関家が重用した源氏に対抗して,院を警固すべく重用したのが平氏で,これが,結局,平氏の覇権を招き,源平の戦を経て,朝廷が支配する体制そのものまで,終わらせることになる。また,後三年合戦の終わった1087年,いわゆる奥州藤原氏政権が確立,以後,まさに都での非クダラ系政権の院政に対峙するかのように,東北地方でクダラ系政権の時代に入り,都をも凌駕するような文化を花開かせることになるのである。つまり,院政時代は,平将門の乱で登場する,武家三流の伸長と重なっているので,以下,次論に委ねることとする。
この章TOPへ
ページTOPへ
あらかじめ,平将門の乱直前の坂東の支配状況を,地図にして,みておくことにする。
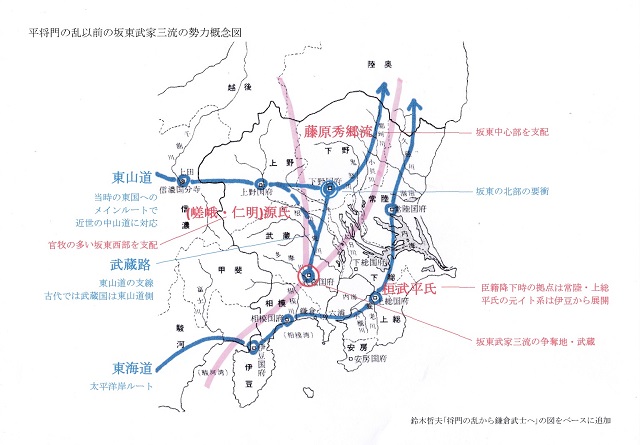
前論同様,第二講「時代循環のパターン」も参照してもらいたい。>時代循環のパターン
早くに拡がったナカ系と,邪馬台国との抗争で東進を余儀なくされたイト系にそれが率いるアマ系という,海洋民族特有の派手さ・乱暴さが,新たな時代を開く一方で,命取りになる。
臣籍降下(皇族に姓を与えて民間人としてしまうこと)は,敏達天皇の末裔葛城王が橘諸兄になったのが始まりとされる。藤原不比等が覇権を握ったことから,妻の県犬養三千代が女帝元明天皇から橘姓を賜り,その三千代が不比等の前に結婚していた美奴王との間の子が葛城王で,生母の姓になったと思われる。
皇位継承を確実なものにするため,天皇には皇子が多く誕生するように図られるが,皇子の子王子以降の皇族はどんどん増えてしまうことになり,その結果,皇位継承が争いの原因にもなってくるため,まず,その数を減らすべく考案されたのが臣籍降下ということになる。不比等の死,その4人の男子が天然痘の流行で死去したために,藤原氏の覇権は失われていたが,宇佐八幡宮の神託によって,権力を回復し始めると,皇位継承問題以上に,藤原氏自身が自らの権力を行使しやすくするために,皇族の数を減らすべく,臣籍降下を天皇に働きかけることによって,平氏は桓武天皇から光孝天皇までの4流24氏,源氏は嵯峨天皇から正親町天皇までの21流(男子に限っても)何百氏にもなるが,臣籍降下した皇族は自らの力で生きるのはやはり困難で,ほとんどは3代もたたないうちに消えてしまう。
坂東諸国においては,826年に,上総・常陸・上野の三国が,親王任国とされ,葛原親王が,これら三国の太守を歴任している。中央での地位向上の可能性を失った王臣貴族は,フロンティア東国に活路を見出すべく,現地留任を望んだが,そのためには,現地豪族と婚姻関係を結ぶことが必須条件であった。葛原親王の孫の高望王が,889年に,臣籍降下して平氏姓を賜り,高望王とその子孫が,(すでに述べたように)東進し,伊勢を経て,伊豆を拠点に,太平洋沿岸部を常陸国方面まで展開していた上古の伊都国の末裔(イト系)たちと婚姻,彼らが,高望王を祖とする家系図をつくっていったことによって,桓武平氏が形成されていったと考えられる。>「平将門の乱以前の坂東武家三流の勢力概念図」
蛇足ながら,長崎県五島出身の平田敬一郎(開銀と地域公団総裁)や,まさにナカ系の那珂氏を祖とする常陸江戸氏の末裔の江戸英雄(三井のリーダー)は,かつての平氏を彷彿とさせるような堂々とした体躯と容貌をしていたことで有名であった。
在地豪族だけでなく,後述する源氏や秀郷流との間にも様々な婚姻関係が結ばれ,源氏化する平氏もでてくるなど,源平という単純な区別はできなくなっていくが,海洋民族型の平氏と,騎馬民族型の源氏という血は争えず,場面に応じて,出現することになろう。
高望王が臣籍降下した同じ889年に,鎮守府将軍良持の子に生まれ,その遺領を継いだ平将門は,伯父の良兼一族と対立,良兼の舅で前常陸大掾の源護と戦って,その子扶らを討ち,それを助けた伯父平国香を殺し,叔父良正の軍を打ち破って以降,一族の間で,大規模な私闘を繰り返し,勝ち抜くことで,武士としての盛名を挙げ,朝廷の政策に対応して,国司と地方豪族との紛争の調停に乗り出すが,失敗して,939年,常陸国衙を攻略,印縊を奪って国司を捕らえ,ついに,国家に叛乱,短時日のうちに坂東を占領して,新皇を名乗り,一族配下を国司に任命して,独立を宣言するに至ったが,朝廷の将門追討軍参加要請に応えた藤原秀郷の前にあっけなく討ち死にしてしまった。海洋民族特有の派手さ・乱暴さで,新たな時代を開こうとしたとたん,命取りになったといえよう。
とはいえ,将門の乱の結果,秀郷が一気に東国武士の祖として登場,末裔からは奥州藤原氏が誕生し,秀郷の軍に加わった平貞盛は,西上して中央軍事貴族化,末裔の清盛が平家政権に至り,ひょんなことから,将門の乱を予告したことになって評価された清和源氏の経基の末裔の頼朝が,ついに,武家政権を誕生させるに至るなど,平将門の乱は,日本史上,実に大きなできごとであったといえよう。
940年,藤原秀郷に従って,将門の乱を制した桓武平氏国香流の貞盛は,恩賞として従五位下に叙せられ,京の右馬助に任じられると,翌年,瀬戸内海で反乱を起こした藤原純友対策に,配下兵士が閲兵を受けるなど,早速,中央軍事貴族として活動を開始,947年には,藤原秀郷の後を継いで,鎮守府将軍にもなっている。
貞盛の四男維衡は,イト系が東進した際に一拠点になった伊勢に本拠を移し,同じように伊勢に移っていた叔父良兼流の致頼と抗争するも勝利して,伊勢平氏となり,その曽孫正盛は,瀬戸内を支配するようになって,密貿易を通じて財力を貯え始め,院政を開いていた白河上皇に伊賀の所領を寄進するなどして,清和源氏頼義の子,義家が後三年の役後冷遇されるのと対照的に,1095年に設置された(院警固の)北面の武士となり,義家の嫡男義親を追討して武名を上げるなどして,院政時代における桓武平氏興隆の基礎を築いた。
東端に厳島神社,西端に壇之浦がある周防国は,いわば平氏の原郷ともいえる場所で,その中ほど,現在の山口市近くに,平安時代において銅銭を製造した唯一の場所の名残である鋳銭司(すぜんじ)村があるが,そこが藤原純友に襲撃された後に登場する平氏は,この地の銅を活用し,大陸との交易を通じて財をなし,やがて覇権を握ることになる。のちの,大内氏時代初期に,京都代官に任にあったのが,平井俊治・道助だったということなので,姓からみて平氏出身といえよう。
その子忠盛は,さらに重用されて,藤原宗子(池禅尼)を正室とし,山陽・南海両道の海賊を追捕使に抜擢され,直後に白河上皇が死去するも,鳥羽上皇に引き継がれ,1132年,ついに,武家初の内昇殿が認められるに至った。その直後には,大宰府を無視して日宋貿易に関与,大宰府が強制監査に入ろうとするも,鳥羽院の威を借りて拒否し,巨利の一部を鳥羽院に還元することで,さらに関係を強化,続けて,山陽,南海の海賊追討となって,多数の海賊を降伏させた上,自らの家人に組織化して,日宋貿易を飛躍的に強化するという知恵者ぶりを発揮,藤原家成が院近臣筆頭の地位を確立すると,妻の宗子が家成の従兄弟であったことから,親密な関係を築いていく。受領の最高峰となる播磨守に転じ,右京大夫も兼任,公卿への昇進も間近となったが,果たせずに,没した。
そして,忠盛の子清盛となり,1156年,鳥羽上皇の死去とともに勃発した保元の乱と,その3年後の平治の乱を制して覇権を握り,栄華の極に達したわけであるが,良く知られているので,1164年に,イト系のシンボル厳島神社に,有名な平家納経をしたことのみにとどめて後は省略,後白河院との間に確執が生じたところから述べる。
1172年,高倉天皇への,清盛が娘徳子の入内で専横ぶりが高まり,1177年,耐えきれなくなった後白河法皇の近臣による"鹿ケ谷の陰謀(平氏打倒の謀議)"が,密告により発覚,死罪,配流になり,翌年に,徳子が高倉天皇の皇子を出産すると,すぐに皇太子にしたことで,対立は激化,翌年,清盛が"治承のクーデター"を起こし,軍勢を率いて京都を制圧して,後白河院政を停止,1180年,ついに,日宋貿易・海賊支配の拠点であった大輪田泊(現在の神戸)福原に遷都を強行する。
高倉天皇が京都に留まるうち,後白河法皇の皇子で,自らも清盛に所領を没収された以仁王が,清和源氏の長老で,突出して従三位に叙せられていた源頼政の勧めで,平氏追討の令旨を全国に雌伏する源氏に発し,自らも挙兵するも追討軍に追われて戦死したが,源氏の一斉蜂起となり,京都に還都した清盛は,開戦間もなく熱病に倒れ,5年に渡る源平合戦の末,平家滅亡に至った。源頼朝は,1159年の平治の乱で清盛に敗れた義朝の嫡男で,死罪になるところを,清盛の母池禅尼の助命嘆願で伊豆への流罪になったのであるから運命は皮肉なものである。
源平合戦は,典型的な騎馬民族と海洋民族の戦いでもあったが,戦い当初,平清盛の命を受けた平重衡ら平氏軍が,東大寺・興福寺など奈良の仏教寺院を焼失させた"南都焼討ち"は,まさに海洋民族の乱暴さが現れたものといえよう。
平清盛の登退場は,弱体化した王侯貴族が軍人の力を利用してその地位を引き上げた結果,ついには軍事クーデターを招き,政権をとった軍人が独裁政治を行って自滅するという,近年においても発展途上国でよく見られるパターンが,我が国では800年あまり前に起こっていたといえる。華美を求め恐怖政治を行う(派手で乱暴)というやり方は,ラテン系など海洋民族出身者に共通し,古い体制を変えるべく破壊するには,こういった存在が必要なようであるが,それがまた,命取りになったといえる。>のちに,下克上の口火を切った北条早雲も,決着をつけた織田信長も平氏である。
平将門の乱後,東国に残された桓武平氏諸流からは,北条,千葉,畠山,三浦,梶原などの氏が発生し,貞盛流,良兼流が伊勢に去った後に入ってきた清和源氏に従属,しだいに騎馬民族化して行き,源頼朝に従って,伊勢平氏と戦うことになったことから,源平合戦は,平平合戦でもあった。このうち,北条氏は格が高かったらしく,坂東平氏のルーツたるイト系の拠点伊豆国に住して,平治の乱後,池禅尼に命を救われた幼い源頼朝が,北条時政のもとに預けられ,その娘政子と結婚,頼朝が初の武家政権鎌倉幕府を開いた後,死去するや,主にライバルとなる平氏諸氏を排除して,執権北条氏として,覇権を握ることになるのである。
源平合戦の結果,平家は滅亡,陸に残った者は,のちに有名になる多くの平家の落人部落を生み出すが,白川郷はじめ合掌造りは,農家としては大建築であるが,船をつくる平家にとって,建築構造はずっと簡単であったこと,船を漕ぐことはもちろん,漁業集落を見てもすぐ分かるように,海洋民族は,密集するのが自然であり,それが,大家族として合掌造りに対応しているともいえよう。栃木県の法師温泉も,平家の落人で有名であるが,多様な山菜はもちろん,山椒魚まで食するのは,海藻や様々な海産物のことを思えば,きわめて当然といえよう。
ほとんど知られていないが,源氏の落人の村というものがあり,長野県の川上村はその典型で,農業が不得意なことから,落葉松林のなかの貧しい村で,漬物が無かったことからも騎馬民族らしいところであったが,近年,レタスの大産地として有名になっている。騎馬民族の農業は,アメリカの農業を見れば分かるように,広い面積を同じ作物で埋め尽くし,収穫したものをコンボイで出荷するといったものになるが,川上村のレタス栽培はまさにそれに対応する。山梨のブドウも,騎馬民族による同一作物の大面積栽培と考えられる(あまり言いたくないが,かつての勝沼など,観光客から収奪するという感じでもあった)。
いずれにしても,源平の合戦は,騎馬民族と海洋民族が激突した点で,典型的な民族戦争だったともいえる。ここで,改めて,自分の民族の遺伝子を確認してみるのも,一興だろう。⇒コラム「遺伝適性を知るための民族ルーツ論」
大和朝廷の成立過程で,アマ系を中心に,海洋民族のうち,陸上で定着し得なかった者たちが,海賊化していったことは想像に難くないが,平将門の乱が武家勃興の原因になったように,同時期(939年)に起きた藤原純友の乱は,伊予で瀬戸内海の海賊の鎮圧にあたっていたのが,逆に,海賊の頭目になり,陸上にも進出,大宰府まで襲撃し,朝廷に反乱,以後,海賊たちが陸の抗争に巻き込まれていくということで,海賊の歴史を変えた。純友は藤原北家支流の藤原良範の子といいながら,生年が定かでなく,伊予の豪族越智氏一族の子が,良範が伊予国司であった時代に養子になったという説があり,純友の乱の時には,越智氏は朝廷側についたというから,純友に利権を奪われたことも考えられる。
藤原純友が討たれて,支配者を失った海賊らは行き場を失うが,海賊は平将門が討伐されたことで,貞盛流が西上し,平正盛の代には,(前述したように)イト系の本領を発揮して,これら海賊を配下に納めて,日宋貿易を主導して巨利を得,白河上皇に接近,子の忠盛は武家初の院昇殿を認められ,その子清盛の栄華に至るも,源平の合戦で平家は滅亡,支配者となった源氏は騎馬民族で,海への眼が少なく,戦功を挙げた者への恩賞は土地であったため,海賊らにとって,何のメリットも無く,さらに,元寇というとてつもない外圧を受けたため,海岸線は防衛の場となり,行き場を失った海賊らは,かつての日宋貿易の伝手を頼ってか,大陸との間に,倭寇として展開するようになる。>前期倭寇
平家の末裔を示すものが多いとされる頭に「平」の字のつく苗字を,マツ系,ナカ系などと同様に,「日本の苗字ベスト10000」で拾って,その分布を見てみると,87位の平野を筆頭に,平田,平井,平山,平川,平松,平岡,平林,平そのもの,平尾,平沢,平塚,平賀が1000位以内にあるように多く,これらを合計しただけでも,全苗字で10番目に多い加藤を上回る人口を占める。それぞれの,苗字には,地域的な偏りがみられるが,全体として,①千葉はじめ南関東や瀬戸内海周辺など,もともと平氏の根拠地であった地域,②栃木はじめ山間地の多い,平氏の落人として知られる地域,③西南九州(島嶼部を含む。沖縄に特化して多い平良姓も平氏に関係があるかもしれない)という,後述する倭寇にかかわる地域に多いことから,確かに,平氏の末裔たちである可能性が高いようだ。
新羅から応神天皇戴く秦氏が渡来した時,多くのシラギ系の人たちも渡来し,ともに,九州から東進して,秦氏の本拠地太秦の北に,シラギ系地名を示す嵯峨野があり,秦氏が集中するという近江の国には,シラギ系も集中し,近江八幡つまり応神天皇を示すところには,シラギ系の人たちと思われる全国の佐々木氏すべての家系が収められ,仁徳天皇の和風諡号にもふくまれるササギの名にもつながる沙沙貴神社があるなど,つねにセットになっている。
東進の最後の地,坂東の北部には,上野国のものを表す大豪族上毛野氏がいたことが知られているが,対朝鮮・対蝦夷関係での軍事・外交伝承として,神功皇后49年,荒田別と鹿我別は将軍に任命され,新羅に派遣された。そして新羅の軍を破り7国を平定してのち,百済の近肖古王と貴須王子と会見した。応神天皇15年,荒田別・巫別(鹿我別と同一人物とされる)が百済に派遣され,王仁を連れ帰った。仁徳天皇53年,竹葉瀬が,貢調しない新羅の問責のため派遣された。途中で白鹿を獲たため,一旦還って仁徳天皇に献上し,再度赴いた。のち,弟の田道(たぢ)も新羅を討ったとあるように,応神天皇が新羅から渡来したことを隠すような神話に対応している。神功皇后が新羅の神の末裔であることと同様,応神天皇とともに渡来した新羅人とみても良いだろう。
おそらく,応神天皇渡来時に同行してきた新羅人であった可能性があり,新田,足利氏など,のちに源氏の主流とされる氏族も,その名から見て,シラギ系で,上毛野氏の末裔とみて良いかもしれない。埼玉県新座郡は,もとは新羅郡といわれ,758年に,政権によって移住させられた新羅人の地域であるが,このほか,高麗人の地とされるものも,民族としてはシラギ系であると考えられることから,稲作には適さない坂東の北西部は,主として騎馬民族のシラギ系の人たちが住んでいたとみて良いと思われる。のちに,養蚕が盛んになり,近年に至るまで,現在の八高線のルートが"日本のシルクロード"と言われるようになったのも,(すでに述べた)養蚕民族の神白山神社にもつながるシラギ系の人たちの地帯であることを示している。
以下,奥富敬之 「天皇家と源氏 臣籍降下の皇族たち」をベースに,清和源氏の展開をみていくこととする。桓武平氏の桓武天皇に続く嵯峨天皇も,王子を臣籍降下させて嵯峨源氏が生まれ,以後,正親町天皇まで18流の源氏が誕生する。その大部分は文人で,村上源氏を筆頭に,公家として勢力を築いて行くが,安和の変で源高明が失脚したように,藤原氏の陰謀の前に衰退を余儀なくされる。9世紀後半,俘囚の叛乱や群盗の蜂起が相次ぐ坂東で,とくに西部に多かった官牧を守るべく配置された王臣貴族は,名が一字の嵯峨・仁明源氏であった。官牧を実際に運営していたのは,前述の騎馬民族のシラギ系であったと考えられる。>「平将門の乱以前の坂東武家三流の勢力概念図」
嵯峨源氏の源融流には,摂津国の渡辺氏とその分流松浦氏(いずれも海洋民族側なのでかなり異質),宇多源氏の一部には,新羅系の拠点である近江国の佐々木氏が取り込まれて武家となり,六角氏・京極氏などが派生する。魏志倭人伝の末盧国からつながるとみられる肥前松浦氏は嵯峨源氏の祖渡辺綱の支流を名乗るが,源氏といいながら渡辺姓が示すように海洋民族で,結局水軍松浦党を率いて平氏に属すことになった。
平将門の乱当時,武蔵介であった源経基は,軍事貴族としてのダメぶりが知られていて,単なる噂の段階で,京に逃亡して訴えたところが,のちに現実になったことから一気に評価され,翌年の藤原純友の乱に押領使として起用され,純友の部将を生け捕りにして,面目をほどこした。その後,経基流の清和源氏は,貞盛流の桓武平氏,秀郷流藤原氏とともに,中央軍事貴族の一角を担うことになるが,その契機になったのが,経基の子満仲が,969年に密告によって,安和の変を起こし,源高明を失脚させ,以後,経基流の清和源氏が摂関家に奉仕することになったことによる。
清和源氏の武蔵国進出は,それ以前に当地に権益を有していた名が一字の嵯峨・仁明源氏と婚姻関係を結んで権益を継承していったことにより,満仲も,武蔵守源俊の娘と結婚して頼光をもうけるなど,武蔵国に根付くようになり,摂関家の傭兵になったことで,自らも坂東ほか諸国の国司を歴任し,鎮守府将軍にまでなる。その間,平将門の乱を平定後,武蔵国司,武蔵守となっていた藤原秀郷の子千晴とライバル関係になっていたが,安和の変では,源高明に仕えていた千晴をまず失脚させるという,摂関家と,自らの障害を一挙に排除する政治的才覚を発揮したのである。
ちなみに,大江匡房が著した「続本朝往生伝」の武士の項では,ベスト5の筆頭に挙げられ,次が弟の満政,5番目には嫡男の頼光まで入っている。頼光が武名を轟かせることは,ついに無かったが,以後の清和源氏は,名に"頼"の文字を入れることが,清和源氏の嫡流であることを示すことになる。
坂東においては,将門の乱後,秀郷の子千晴が武蔵国の将門の勢力を奪取し,桓武平氏と藤原秀郷流の間,あるいはそれぞれの一族間での紛争が頻発,中央の強権者藤原道長が死去するや,1028年,平将門の叔父平良文の子孫で,道長の子の教通の家人であった平忠常の乱として爆発,朝廷は平直方を追討使するも鎮圧できずにいたが,3年後,頼光の異母弟で,兄と違って坂東武士の棟梁になろうとしていた頼信を起用して,ようやく平定,頼信の武名は一気にあがり,面目を失った平直方は,娘を頼信の嫡男頼義に嫁がせ,それまで桓武平氏の勢力圏だったところが,清和源氏の勢力圏に一変するに至る。直方から5代目の子孫が北条時政で,その娘政子が,頼義から5代目の義朝の子頼朝に嫁いだのだから,歴史は面白い。
次いでながら,頼信が石清水八幡宮に納めた告文が発見され,清和源氏は,実は陽成源氏だったことが判明,陽成は祖とするには問題の多い天皇であったことから,白河院政で冷遇された八幡太郎義家が,重用されている桓武平氏に対抗すべく清和源氏に書き換えたらしい。同時に,さらに遡った祖を"武の神"応神天皇とする八幡信仰であった由来も明らかにしているが,このことが,すでに坂東に展開していた騎馬民族のシラギ系を取り込んで,有力な武家として飛躍する契機になったとも考えられる。
避けては通れない話として触れておきたいのは,被差別民の話で,屠殺や皮革業に携わっていたため,殺生を禁じる仏教社会から排除されていった人たちであるが,彼らもまた,シラギ系騎馬民族が主体で,当然のように八幡神を祀っている。また,シラギ系の本国朝鮮では,なぜ日本のような軍事政権にならなかったのだろうかということについては,儒教にもとづく文民支配の思想の中国の影響がそれほど強かったからと思われる。
源頼義は,騎馬民族を代表するように際立った馬好きの一方,父頼信を裏切って不貞を働いた生母を許さず自分から義絶,さらに,藤原道長に忌まれて逼塞していた小一条院に仕えるなど,その正義感は異色で,武人としての血は高齢になっても衰えないという人物であったから,坂東武士のほとんどがその指揮に従うようになったという。63歳になって,陸奥守に就任すると,勇躍して現地に赴任,俘囚の安倍頼良を挑発し続け,1051年,前九年の役が始まるが,安倍頼良を討つものの,その子貞任,宗任の巻き返しで劣勢に陥り,1062年,出羽の俘囚清原武則の援を得てようやく,貞任を討ち,宗任を捕らえて乱を平定するが,陸奥国は清原氏に併呑されてしまう。命じられて,宗任らを伊予に住まわせ,皇民としたが,それが,安倍晋三のルーツである。
平定翌年,相模由井郷に石清水八幡宮を勧請して,鶴岡八幡宮の起源とし,嫡男義家が,石清水八幡宮で元服して"八幡太郎"と称し,三男義光が, 近江国の新羅明神で元服して"新羅三郎"と称したように,源頼義は,応神朝八幡宮の秦氏を支えたシラギ系を結集するシンボルになるに相応しい人物であったといえよう。のち,近江国の佐々木氏や京極氏はじめ,全国のシラギ系を核に武家源氏として統合されて行くことになる。
八幡太郎義家は,前九年の役で,父頼義に従い,窮地の父を助けて,安倍兄弟と激闘,終結した時は24歳で,陸奥国の果実を清原氏にさらわれたことに怨念を抱いていて,21年後の1083年,ようやく鎮守府将軍になって現地に赴任するや,清原氏の内紛につけこみ,私兵をもって,戦闘を開始したが,敵もさるもので,3年後に,ようやく鎮定するも(後三年の役),陸奥国は手に入らず,藤原清衡による,奥州藤原氏という地方政権を誕生させ,源頼朝によって滅ぼされるまで続くのである。
悪いことに,この間に,中央では,白河上皇による院政が開始され,対立する摂関家が重用していた清和源氏に冷たくあたるようになっていて,朝廷はこの争乱を私闘と断じて恩賞を行わず,かえって陸奥守を解任されたことから,私財を投じて部下に褒美を与え,人望が高まって東国武士との間の主従結合が強化され,"天下第一武勇之士"と評され,義家の名声を頼って諸国の在地有力者がその田畠を義家に寄進したため,ついに荘園の停止を命じられる。
さらに,院の嫌がらせは続き,次男義親が,源氏の御曹司というのに,辺境の対馬国司に任じられた上,理由も分からず謀叛人とされ,こともあろうに,その討伐の任を下されるが,その苦悩に耐えられなかったためか,まもなく死去して,親子相撃の悲劇は回避されるも,追討の後任には桓武平氏正盛が選ばれ,義親の首を持って帰る前に恩賞を与えることが決定しているほど,院政は平氏を重用した。三男の義国も叔父の新羅三郎義光と私闘していたため,結局,四男の義忠が後継者になる。ところが,またしても,白河院政の陰謀で,義忠は叔父義光に暗殺され,義忠の子で14歳の為義が後を継ぐが,検非違使に任じられたのは50歳で,同じ年齢の平忠盛は刑部卿で,院昇殿を許されているほどの屈辱であった。
1145年頃,為義が坂東の地盤を任せていた嫡男義朝が上洛,摂関家に従順だった父と異なり,鳥羽院に仕えたことから,すぐに昇進を重ね,1153年には,従五位上の下野守となって,父の位階を一段追い抜くことになって,親子対立,1156年に勃発した保元の乱で,崇徳上皇側になった為義に対し,義朝は,自らの献策で圧勝した後白河上皇側ということになった。義朝は,自首してきた父為義の助命を必死に願うも,強硬な後白河院側近信西により,自らの手で斬首するように迫られ,実行を配下に委ねて逃れるも,信西に対する怨みが胚胎,1159年,藤原信頼と組んで,信西の首を斬るに至るが,帰京した平清盛に討たれ(平治の乱),以後,平家の専横時代となる。
この時,清盛の母池禅尼に命が救われ,伊豆に配流されていた義朝の嫡男頼朝が,1180年に挙兵し,平家を滅亡に追い込んで,それまで耐え忍んできた清和源氏代々の労が報われるのである。以仁王に,頼朝ら清和源氏に決起を促す令旨を出すよう働きかけた源頼政は,武名を轟かせることのなかった頼光の5代末裔で,保元の乱と平治の乱で勝者の側に属し,平氏政権下で源氏の長老として中央政界に留まった上,平清盛から信頼され,1178年,74歳になって,武士としては破格の従三位に昇り公卿に列するが,その直後に,清和源氏の目を覚まさせる役割を果たしたことになる。
1180年に,以仁王の令旨を受けて,平氏打倒に決起した源頼朝は,早速,御家人制度を始め,侍所を設けて和田義盛を侍所別当に任じ,平広常を誅滅するなど,強い態度で,独立心の強い坂東武士を次々と配下に取り込み,1185年には,平家を滅亡に追い込むとともに,鎌倉には公文所,問注所を設けて,統治の機関を整備。1190年に,はじめて上洛して後白河法皇に対面,権大納言・右近衛大将に任ぜられるも固辞,1192年,法皇が死去して,ようやく征夷大将軍に補任され,武家政権の首長が征夷大将軍に任ぜられる慣例がひらかれる。
源平の合戦は,いうまでもなく騎馬民族の源氏と海洋民族の平氏が起こした内戦で,アメリカの南北戦争のように,大国の発展には避けて通れない,新たな時代を開くための内乱,まさに民族戦争と言っても良いようなもので,実際,その後の武家政権は,アメリカの南北の意識のように,源平交替という意識の上に動いて行くことになる。騎馬民族源氏による武家政権は,戦功のあった武士に所領を与えることで報い,確実に配下にする方式をとったことから,滅亡に至った平家ばかりでなく,陸の土地に関係のない海洋民族は,見捨てられ,自ら生きるべく,海賊化,倭寇化して行くことになるのは,すでに述べた通りである。
その間,弟義経が,弟であることを理由に,御家人になることを拒絶,それに乗じた後白河法皇が,義経を配下に入れて,頼朝追討の院宣を出すに至るが,他の御家人に応じるものはなく,義経は潜行の挙句,奥州藤原氏秀衡のもとに逃れて匿って貰ったのも束の間,秀衡が死去すると,子の泰衡は,頼朝の圧力に耐えきれず,義経の首を鎌倉に届けるも,時すでに遅く,1189年,奥州藤原氏は滅亡させられた。頼義,義家の前九年,後三年の役以来の宿題は,4,5代後の頼朝によって,ついに果たされたのである。
1184年には,参議藤原光能の子で,学問の名門大江家の養子になっていた大江広元を招き,公文所(政所)を開設して別当とする。以後,事務官僚のトップとして,数多くの政策に関与,幕府の基礎固めをするとともに,ことあるごとに上洛して,朝幕関係の安定化に努め,1199年の頼朝没後も,政子の信任を受けて将軍側近の立場を保持し,執権政治確立の基礎固めをして行く。頼朝が,いわゆる貴種(皇族がルーツ)であったことから,天皇の権威は存続,シラギ系武家政権ができたとはいえ,クダラ系藤原氏のやり方が浸透していくことにもなった。
なお,頼朝は,南九州薩摩を中心に秦氏出身の島津氏を大将に相模の有力武士らを配置,以後,島津氏は大大名として,長期にわたって独立性を保ち,琉球を配下に収めて後には,大陸との貿易で富を蓄え,同じく,大陸との貿易で富を蓄える長州とともに,明治維新を実現することになる。薩摩藩島津氏が,秦氏出身であることがイギリスとの連携を生み出し,後述するように,長州が,中臣鎌足とつながる特別な存在であった大内氏をルーツとすることが大きな意味を持つのである。
源平の歴史はかなり知られているが,秀郷流についてはあまり知られていないので,野口実「伝説の将軍 藤原秀郷」をベースに,少し詳しく述べる。
坂東に在留した王臣貴族は,在地の豪族との婚姻などにより,武力を高めることになったが,850年頃から,坂東の俘囚の叛乱や群盗の蜂起が相次ぎ,それを鎮圧するためにも,これら軍事貴族の配置が求められるようになった。藤原秀郷の登場は,曾祖父で魚名の子藤成が下野国に赴任した際,在地の土豪鳥取氏の娘と結婚し,その子豊沢が,中央での栄達を求めず,下野の在庁官人になったことに始まる。下野の国府(現在の栃木市)は東山道の陸奥への拠点にあることから,俘囚・群盗を鎮圧する役割を課されるようになったが,下総・常陸方面で,その子村雄も下野大掾を継ぐとともに,鳥取氏との婚姻で,不動の在地有力者になった。>「平将門の乱以前の坂東武家三流の勢力概念図」
藤原村雄の子に生まれた秀郷も,有力土豪鹿島氏の外孫になっていて,下野掾になっていたところに,939年,平将門の乱が起きるが,889年に高望王が臣籍降下して始まった桓武平氏よりも,すでに在地性はかなり濃厚になっていた。一説によれば,この889年に,将門と同じく秀郷も誕生している。史料上の初見は,「日本紀略」916年の記事で,一族を主体に武力集団を率いた反国衙的行動によって配流の処罰が下されるも,国司に再度の命が下されていることから,簡単には手を出せないほどの力を有していたことが分かる。929年にも,その濫行に,近隣諸国からの兵士が動員されており,ことによれば,将門と立場が入れ替わるような存在になっていた。蛇足ながら,江戸時代に博徒が,近代に入ってヤクザが,反社会的悪党でありながら,国家等の手先として,他の悪党を制するという存在になるのと同じようにみえる。
将門の乱に,京の人々が怯えるなか,翌940年,朝廷が,藤原忠文を征東将軍とし,在地土豪の将門討伐への決起を促したのに応え,8人の追捕凶賊使(押領使)の一人として参加すると,征討軍が到着する以前に,平国香の子貞盛らを従え,老練な計略を用いて,将門の軍を一気呵成に破り,自身で将門の打ち首にし,自らの使者が,京にもたらして,獄門にかけられた。名声は一気に高まって,東国武士の祖として伝説化されるともに,子孫は"都の武者"(中央軍事貴族)として活躍することになる。"老練な計略を用いて"とあるように,深謀遠慮型の秀郷は,およそ武人的でなく,クダラ系藤原氏そのものの人物であった。
ちなみに,将門の乱に呼応するように,(あわせて承平天慶の乱と呼ばれる)瀬戸内海で乱を起こした藤原純友は,藤原北家の右大弁藤原遠経の孫であるが,海賊を取り締まる伊予掾となって赴任すると,その後も現地に留まって,逆に海賊を率いるようになり,ついに,国家に叛乱するようになったという点で,地理的には遠く離れているとはいえ,同時代的現象であったといえよう。そして,純友の乱平定後,行き場を失った海賊たちが倭寇化していくのである。
将門の乱鎮定における抜群の功績で,従四位下と,地方豪族として破格の位階に叙せられて,下野守,武蔵守となり,将門と同類であったにもかかわらず,存在を国家から認められ,坂東北部に軍事的覇権を確立する。平貞盛のように,自身が京に上って,中央軍事貴族になる選択はしなかったが,関白藤原忠平の日記の947年の記事に,秀郷が権中納言源高明を通じて,平将門の遺された兄弟が謀叛を起こそうとしていると奏上していることから,源高明を中央権門として存立基盤を固めていたことが分かる。958年に死去したと伝えられている。
弓射騎兵の武芸故実の祖として"秀郷将軍"と呼ばれ,鎮守府将軍に任じられたことも確実で,清和源氏の征夷大将軍に拮抗する,というより,"将軍"といえば鎮守府将軍のことをいうように,名誉の表徴として,時々間をあけながらも,百年近く,子孫に世襲された。鎮守府とは,古代蝦夷経営のために,陸奥国に置かれた軍政府で,当初は国司と兼任であったが,やがて,独立性を強めて行き,秀郷が任じられた頃には,奥六郡の地域の徴税権を持ち,蝦夷との交易にも独自の権限を持つに至るとともに,鎮守府の活動の兵站基地が坂東諸国であったことから,俘囚・群盗の鎮圧に活躍した軍事貴族が続々と任じられるようになっていた。
967年の村上天皇崩御の際,秀郷の子千晴と源満仲が,固伊勢関使に任じられることになり,ともに辞退するも,満仲のみ受理されていることから,2年後に,満仲の密告で勃発した安和の変で,源高明よりも前に,千晴が検挙され,隠岐に流されたことに関係するとみられている。とはいえ,秀郷流藤原氏の族長権は弟の千常に移って,中央軍事貴族としての地位は失われることなく,やがて武蔵介になった千常を中心に,秀郷流藤原氏が勢力を拡張していく。史料で,鎮守府将軍への補任が明らかになるのは,千常の子文脩からで,その記事から,秀郷流藤原氏が摂関家を本主と仰いでいたことも知られる。
1045年に,寛徳の荘園整理令が発せられると,北坂東での利権を保持すべく,秀郷流藤原氏のうち,本流というべき文脩の子兼光の系統は,中央軍事貴族の地位を捨てて,在地領主となる道を選択したが,その弟文行の系統は,その子が佐渡守に任じられたことから,佐藤氏と呼ばれ,摂関家の家人として,"都の武者"の立場を維持し続ける。曽孫季清の代に,院を警固する,いわゆる"北面の武士"になり,その孫が,かの有名な西行(佐藤義清)で,歌人としてつとに知られているが,実は,秀郷流故実を伝える弓馬の芸の達人でもあった。
「吾妻鏡」に書かれている,源頼朝と西行の邂逅は偶然のようにとれるが,西行が奥州藤原秀衡のもとに東大寺再建の資金の勧進に向かう途中で,頼朝にも資金を約束させるため,秀郷流武芸の第一人者で,東国の武士にとって垂涎の的である自らを売り込むべく図ったものとみられ,頼朝にとっても,奥州藤原氏の動向が気になるところであったから実現したらしい。実際,頼朝は自ら樹立した武家政権の正統性を確立すべく,武芸の作法の統合を図るにあたって,秀郷流を重視していたことも知られている。
のちにつくられる"俵藤太"伝説も,その多くが京都で成立していることから,中央軍事貴族としての存在が大きかったことも伺える。鎌倉幕府の成立後,頼朝が,それまで秀郷流嫡流とみなされていた足利氏に替わって,小山氏を嫡流とみなしたことなどによって,坂東に割拠する在地武士団の勢力図は大きく塗り替わることになり,のちに,足利氏が鎌倉幕府を倒す伏線になった。
平泉の奥州藤原氏は,1047年の「藤氏長者宣」に,陸奥国在住と記された藤原経清の子孫であるが,同文書に,その父とある正頼は,実に,前述の秀郷流藤原氏のうち,本流というべき文脩の子鎮守府将軍兼光の子であることから,秀郷を祖とすることに矛盾はない。11世紀半ば,陸奥国で,安倍氏が国司と争い,これに清和源氏の源頼義が介入して前九年の役なり,足掛け12年の戦いののち,(のちの出羽国の)清原氏の加勢を得た頼義が勝利,敗死して滅亡した安倍貞任の姉か妹が嫁いだ藤原経清も斬首されたが,清原氏に再嫁,経清との間の子が長じて清原清衡を名乗ることになる。
清衡は,一族の内紛によって,後三年の役となり,白河上皇による院政が始まった年とされる1086年の翌年に,源頼義の子義家の援軍を得てようやく勝利,陸奥全体を実質的に支配するようになり,1092年,平泉の地に,自立した政権を樹立して,奥州藤原氏が成立した。1124年には,有名な中尊寺金色堂を建立し,1128年に死去,その翌年には白河上皇も死去している。
後を継いだ基衡までは,実質的支配力はあるものの,形式上は在庁官人でしかなかったが,院の近臣で陸奥守として下向してきた藤原基成の娘を子の秀衡の嫁に迎え入れ,院に影響を及ぼしたことから,鳥羽上皇が死去して勃発した保元の乱の翌年1157年に父の死で後を継いだ秀衡が,1170年に,鎮守府将軍に任じられたことで,陸奥の権益が決定的なものになった。このことは,中央を実質的に支配していた平家が,陸奥における秀衡の実力を認めて軍事警察権を委任したものであると同時に,平家の経済基盤たる日宋貿易が陸奥の砂金によって支えられていたことによる。
秀衡は,源氏が一斉蜂起した翌年の1181年には,源氏を背後から牽制したい平氏政権によって陸奥守に任じられ,武門としての地位も飛躍するが,1185年に平氏が滅亡,逸脱した行為をとったため,兄源頼朝から追捕されることになった義経を匿い,頼朝からの引き渡し要求を拒み続けるうちに死去,1189年,子の泰衡は,義経を自殺に追い込んで,頼朝との和平を模索するもかなわず,滅亡させられるに至った。清衡が白河上皇と,基衡が鳥羽上皇と,秀衡が後白河上皇とそれぞれ同時期に権力を握っているさまは,まさに,院政と奥州藤原氏政権が並行した現象であったことを示しているといえよう。
念のためつけ加えておくと,埴原和郎によれば,奥州藤原氏三代の遺体計測結果は,京都人の体形を示しており,藤原秀郷の末裔とみて間違いないという。
のち,南北朝動乱期の1335年に,高位の北畠顕家が鎮守府将軍に任じられたことを端緒に,秀郷流小山氏が台頭,足利氏による源氏の正統性が流布したため消えるとはいえ,秀郷流の血統が脚光を浴びるとともに,"俵藤太"伝説の完成をみる。秀郷の居宅のあった地が田原だったことから,伝説化される際に,俵藤太の名がつけられたという。
さて,桓武平氏や清和源氏と同じように,それまで土着していた様々な民族の武士が,秀郷流藤原氏と婚姻関係を結ぶことによって,その出であることを語るようになる。小山氏のほか,シラギ系と思われる足利氏,イト系と思われる下河辺氏など実に様々であるが,藤原秀郷直系の西行すなわち佐藤氏はじめ,伊藤,進藤,武藤,加藤,後藤など,始祖とする人物の,あるいは世襲した"官職の一字"と氏名の"藤"をつなげた苗字は,藤原氏出身の武士にのみ見られる現象で,11世紀後半から始まり,宮城県にやたらに佐藤姓が多いのは,奥州藤原氏の政権を支えた信夫郡司流の佐藤氏で,その佐藤氏から,(山内)首藤氏が生まれている。最近,注目されるようになった渋沢栄一は,埼玉県深谷の名家の出であるが,そのルーツは,秀郷流であった。
ついでながら,摂関家を戴く藤原本家の方は,五摂家の近衛・鷹司・九条・二条・一条を筆頭に,歌の冷泉,あるいは富小路まで,主として,邸宅のあったところの名で呼ばれ,明治維新後,そのまま姓になっていて,藤の文字は含まれない。
この章TOPへ
ページTOPへ
前論同様,第二講「時代循環のパターン」も参照してもらいたい。>時代循環のパターン
1199年,圧倒的権威と武力で,北条,千葉,畠山,三浦,梶原氏など,桓武平氏出身も多い坂東武士たちを御家人として統率してきた将軍源頼朝が(不慮の事故で?)死去すると,それぞれが覇権を握ろうと,平氏ゆえの乱暴さが爆発する。長男頼家は伊豆修善寺に幽閉されて死に,次いで嗣立された次男実朝も1219年に,頼家の遺児公暁に暗殺されて,貴種たる源氏将軍家は三代で断絶してしまう。この危機的状況に,頼朝の妻,北条政子は,頼朝が信任していた大江広元のアドバイスを得ながら,次々と的確に対応し,北条氏の覇権を確立し,さらには,朝廷の権威まで減じてしまう。
1199年,頼朝が死去,跡を頼家の外家である比企能員が権力を狙ったのに対し,頼家がみずから訴訟を裁くのを停め,有力御家人の合議によることにし(危機①,以下,北条政子が大江広元のアドバイスを受けながら,対処し解決したこと),1203年,頼家が重病になったことから,地頭職を実朝や頼家の長男一幡に分与する案にも,比企能員が不満を示すと,時政とともに比企氏を滅ぼし,一幡を殺し,頼家を出家させて伊豆の修禅寺に幽閉,実朝を将軍に擁立し,時政を執権とする(危機②)。この結果,桓武平氏の北条氏が実権を握るが,1205年,時政が後妻牧の方(政子の継母)と謀って実朝を廃し,女婿の平賀朝雅を将軍に立てようとしたのに対し,弟の義時とともに実朝を守り,父を伊豆に隠退させる(危機③)。
1213年には,和田合戦を乗り切って,北条氏の覇権を確立(危機④),1219年,実朝が頼家の遺子公暁に殺されると(危機⑤),後鳥羽上皇の皇子を鎌倉に迎えようとするも許されず,かわりに摂関家から,頼朝の遠縁のわずか2歳の藤原頼経を迎えて,自らが実質上の将軍(鎌倉殿)となり,俗に"尼将軍"と呼ばれるに至る。1221年,ついに,後鳥羽上皇が討幕の兵を挙げる最大の危機「承久の乱」になるが,御家人たちに幕府の恩を説いて奮起を促し,都に攻め上らせ,勝利を収めた(危機⑥)。そして,1224年,義時が没し,その子泰時が執権となると,泰時の継母伊賀氏が,子の政村を執権,女婿の一条実雅を将軍にしようとしたが,これも抑えて泰時を救い,執権政治を安泰ならしめて,直後に,没した(危機⑦)。大江広元も,後を追うように,没している。
1224年,41歳で,3代執権になった北条泰時は,まず,執権嫡流の得宗家を確立,1225年,実質的な将軍の役割を果たしていた伯母政子が死去すると,政治改革を行い,独裁から合議に転換させて,執権政治を確立。1232年には,御家人間の相論における公平な裁判の規範となる,初の武家法典「御成敗式目」を制定,この間,大飢饉には,領民の救済に努め,並行して,都市鎌倉も整備し,興福寺,延暦寺など,武装僧徒には断固たる態度で抑圧するなど,善政を謳われたが,1242年,四条天皇が没し後嗣が問題になると,皇位に干渉し,貴族たちの反対を抑えて土御門上皇の皇子(後嵯峨天皇)を即位させて,のちの南北朝への原因をつくったところで死去した。
兄の経時を継いで,1246年,19歳で5代執権になった北条時頼は,直後に一族の名越光時を誅し,将軍藤原頼経を追放(宮騒動),翌年には,安達景盛と計って,三浦泰村一族を滅ぼし(宝治合戦),1252年には,将軍藤原頼嗣を追放して,待望の皇族将軍(後嵯峨天皇の皇子宗尊親王)を実現,北条政子を彷彿とさせる陰謀ぶりで,執権北条氏の権威の増大を図る間,御家人を公平に扱うとともに,撫民的な善政を行い,1256年,病気になると,出家。追慕する御家人が多く,何度も出家制止令を出すほどであった。その後も,院政のように,権力を保持し,公家権力の背景となる天台宗の寺院を,臨済宗へ宗旨替えさせて,武家体制仏教を確立,後に,回国伝説を生み出す自由な活動をし,1260年,日蓮が「立正安国論」を呈じてくると,伊豆に配流したが,1263年,36歳という若さで没した。
泰時,時頼までは,源氏化していた平氏の良さが表れて,名執権といわれる人物であったが,根っこの方では海賊などともつながっているため,いわゆる得宗による恐怖政治の萌芽が生じ,地方では,例の播磨国を代表にいわゆる悪党が跋扈し始める。そうしたところに,史上かつてない国難といわれる蒙古襲来(元寇,実質的には,シラギ系の多い高麗人との戦)が起きる。
1268年,17歳の時,高麗使藩阜の渡来直後に,時頼の子北条時宗が8代執権に就任,3年後にも,モンゴル使趙良弼が渡来するも無視,1274年,ついに,元寇(文永の役)になるも,元使杜世忠を竜ノ口に斬るなど一貫して対モンゴル強硬政策をとり,国難を理由に,高麗進攻計画,防塁築造,非御家人の軍役動員など,まさに総動員体制をすすめ,幕府を独裁政権にしてゆくと同時に,守護職や重要所領を北条一門で独占する,いわゆる得宗専制を強化,1281年の再度の元軍の来寇も退け,幕府の権威は絶大になるが,3年後,33歳の若さで没した。
時宗という強力な執権が没するや,平氏の乱暴さが一挙に噴き出し,後を継いだ執権貞時の乳母の夫で内管領になった平頼綱が,元寇で御家人をまとめる役割を果たしていた安達泰盛とその一族を滅ぼし(霜月騒動),専制による恐怖政治を実施,8年後,ようやく,その権勢を警戒した貞時によって討たれるが,以後,平氏の乱暴さばかりの,いわゆる得宗専制,悪党横行時代となり,これといった文化を生むことなく崩壊して行く。
そのなかで,信仰心の厚かった北条時宗は,蘭渓道隆,大休正念に深く師事し,その招きで無学祖元が来朝し建長寺の住持となり,円覚寺を建て祖元を開山とするなど,元との間の交易は成り立っていて,以後も,交易船を利用した,元,日いずれの禅僧の往来も盛んで,五山文化を準備することになる。
「高麗史」の,1223年の項に,「倭が寇する」という記事が初めて登場,源平合戦に敗れた海洋民族平氏と,その平氏が支配していた海賊たちが行き場を失って進出したものと思われるが,その50年後には,熟字「倭寇」として使われるようになるほど頻繁になるのは,元寇によって,海防が一気に強化され,もはや,日本の側では活動できなくなったことに対応しているようだ。
なお,高麗国は,形式的には,高句麗の後継のようにみえるが,日本との距離関係でみれば,実質的には,新羅人が多い国であったといえる。
後醍醐天皇という特異な天皇が政権を取り戻すべく立ち上がり,新田・足利氏ら正統的源氏の支えを得て,1333年鎌倉幕府を滅亡に追い込み,建武の中興を実現するものの,足利尊氏の反抗で,1336年あっけなく崩壊,単に中世の中間点を示すに留まり,いわゆる室町幕府が樹立される一方,混乱の南北朝時代となるとともに,北朝が正統とされてする。
北条執権の介入によって,皇統は大覚寺・持明院両統に分裂していたが,北条執権政治の弱体化を見た後醍醐天皇は,1318年に,即位を勝ち取るや,その特異な個性を発揮,幕府によって制限された王権を回復すべく,3年後の親政開始とともに,専制的支配をめざし,1324年には,早くも討幕を企てて失敗(正中の変)するもくじけず,再び計画して失敗(元弘の変),捕らわれて隠岐に流されたが,なおめげず,1333年,隠岐を脱出,諸国に挙兵を呼びかけると,源氏嫡流ながら北条氏の配下になっていたことに我慢できずにいた足利高(尊)氏が呼応,ついに幕府を滅ぼす。
建武新政を開始するも,その専制ぶりが,武将・貴族たちの強い反発を招き,足利高(尊)氏の離反で,3年後にはあっけなく瓦解,結果として,シラギ系の足利政権が誕生し,北朝が正統とされ,シラギ系天皇も復活。後醍醐天皇は,吉野に南朝を開いて,幕府に対抗し,1339年の没後も,南北朝時代が続くことになる。
足利氏は,源氏将軍断絶後,清和源氏の嫡流として御家人の間で重んじられ,北条氏と肩を並べる存在であったが,しだいに圧迫を受けるようになり,尊氏の祖父家時のころから源氏再興の志を抱くようになっていた。1331年,討幕めざす後醍醐天皇による元弘の乱が起こると,前執権北条高時から,父貞氏の死去にあったばかりのところに出陣を命じられ,深い憤りを覚えて,北条氏打倒の決意,天皇側について,討幕を実現させる。すると,本来の源氏再興の志から,後醍醐天皇による建武の中興に謀反し,持明院統の光厳上皇の院宣を受け,後醍醐天皇側の楠木正成軍を破って入京,光厳上皇の弟光明天皇を立て,新幕府の開設を宣言。後醍醐天皇は吉野に逃れて,朝廷を開き,南北朝対立の時代となる。尊氏は北朝から将軍宣旨を受けるもののまだ弱く,後醍醐天皇が死去した後も,北畠親房の指導で南朝の抵抗が続くうち,尊氏の弟直義が南朝側についたことで観応の擾乱が始まり,1352年,尊氏が直義を毒殺してようやく決着,幕府は安定するが,なお,南朝の抵抗は続く。
尊氏の嫡男義詮は,関東を重視する父の命により,東国武士結集の役割を果していたが,,鎌倉に弟基氏をおいて上洛し,観応の擾乱に対処。尊氏の死で,将軍職を継ぐと,細川清氏を執事に任じるが,南北朝動乱で,清氏が従兄弟の細川頼之に討たれると,足利一門中将軍家につぐ高い家柄をもち,清氏と対立していた旧直義党の斯波高経に幕政の補匠を要請するとともに,関東でも旧直義党の上杉憲顕を招いて関東管領の任務を委ね,その子憲春を関東執事として,基氏との関係を修復。さらに,南朝方の大内弘世や,直冬党の山名時氏も幕府に復帰させて,幕府体制をほぼ安定させる。そして,死を目前にすると,お目付け役に細川頼之を初の管領につけて,子の義満に将軍職を譲る(時あたかも大陸で明が建国された年)。
義詮の弟,鎌倉に残った基氏は,初代の鎌倉公方になり,自らも時期将軍を狙っていたが,義詮の死の直前に死去,子孫が幕府と対立していくことになり,また,義詮は,将軍を継いだ当初,細川清氏を執事に採用したが,死の直前に,鎌倉幕府における執権のような役の管領を設け,清氏を討った従兄弟の細川頼之をつけたこともまた,細川一族の間の抗争を招くなど,幕府が弱体化していく種も撒かれたのである。
古代(奈良・平安時代)最強の公卿クダラ系藤原氏の道長に対応するように,中世(鎌倉・室町時代)最強の将軍になる足利義満は,将軍職を継ぐも,幕政はなお管領細川頼之が取り仕切っていたが,1378年,20歳になると,華麗な室町御所を造営し,後円融天皇の行幸を仰いで誇示,翌年には,政変で頼之が追放されて,実権を掌握,24歳には,父祖を超えて,左大臣に上り,二条良基を摂政に,自らは内覧となって,全権を掌握し,翌年,源氏の長者となり,武家で初めての准三宮に至る。1392年,南北朝の合一を実現し,翌年,後円融上皇が死去すると,自ら上皇相当の位置から政務を処置,翌1394年,36歳になると,将軍職を長子義持に譲って太政大臣に昇り,翌年,出家するも,依然として政務を見る。翌年には,九州探題今川貞世(了俊)を突然罷免したことで,朝鮮貿易の利権を得た大内義弘が,一気に伸長したため,1399年,彼を討って抑え(応永の乱),天下統一事業の仕上げとして,明との交渉を開始,明からの倭寇禁圧要請に応え,1404年,明帝から,日本国王と認められて冊封関係を結び,日明公貿易(勘合貿易)の制度を成立させ,1408年,後小松天皇の北山第行幸直後,ついには,王権簒奪かと思われた矢先に,没したのである。
足利義満は,室町御所を造営してまもなく,左大臣に上り,二条良基を摂政に,自らは内覧となって,全権を掌握すると,尊氏,義詮が進めてきた王朝・本所権力の幕府吸収政策の総仕上げ,「北野天神縁起絵巻」制作に続いて,「融通念仏縁起絵巻」を制作して全国流布させるという壮大な絵巻プロジェクトを立ち上げ,1393年,後円融上皇が死去すると,自ら上皇相当の位置から政務を処置,1397年には,金閣寺ほか多数の殿舎より成る北山第(鹿苑寺)を造営,政庁を兼ねて,絵合せの一大イベントをするなど,公武社交の場とした。
義満はまた,禅宗寺院統制のために五山制度を整備し(五山・十刹・諸山),義堂周信,春屋妙葩らの禅僧を重用したほか,自身も,和歌,連歌,楽,書に秀で,猿楽を好んで,観世親子を見出し,中国渡来の文物を愛玩するなど,文化の面でも傑出した指導者で,藤原道長による王朝文化が古代の絶頂であったのと同様,義満によるいわゆる北山文化は,中世の絶頂であったが,同時に,公武合体が一気に進み,義満没後,シラギ系足利政権は,クダラ系藤原氏の文化に飲み込まれて弱体化していくことになる。
源氏を始め騎馬民族は,王侯貴族などの守旧派をうまく使い,農民ら土着の人たちを支配するのが得意で,中国においても歴代王朝の多くは騎馬民族であるが,彼らはまた自らの文化を欠くため,結局上下の文化の中に埋没して弱体化しモラルも崩壊して行く。足利将軍時代は,まさに,その典型といえよう。
後を継いだ将軍義持が,父義満の威光に抵抗して逆の政策をとるようになるものの,その遺産の上で平和が保たれるが,ほぼ同時に鎌倉公方になった足利持氏の反抗に悩まされるうちに出家,義持は子の義量に将軍を譲るも義量は早世,その後再び政務を司った義持が,後継将軍や嗣子を定めることもせずに没したため,,将軍不在になってしまい,側近協議の上,候補者のうちから籤引きで選ぶことになり,1428年足利義教が将軍に就くが,その正当性に不安があったのか,恐怖政治を敷いて独断専行したため(世阿弥の配流もその犠牲),地方で土一揆が起こり始めるなど,周囲の反発が強くなって行き,1441年,ついに将軍義教は暗殺されてしまう(嘉吉の乱)。
以後,将軍の力は落ちて行き,管領が頻繁に交替,嫌気した将軍足利義政が政務を放棄してしまい,妻の日野富子が表に出るようになるなか,管領家を中心にさまざまな確執が重なって,応仁の乱の勃発に至る。
クダラ系藤原氏の側でも,2代将軍義詮の時代の関白二条良基が武家と融合する連歌文化を創始,8代将軍義政は政治から逃避して,1467年には,戦国時代の幕開けとなる応仁の乱を引き起こす原因をつくるに至るものの,他方,東山文化として,現在につながる多くの様式の創始に関与,義政時代にほぼ重なるように,公家の側には,文化的巨人といわれる関白一条兼良が存在,兼良はじめ,応仁の乱で疎開を余儀なくされた一流の公家たちが地方に京文化を広めるというおまけまでついた。
義満が,南北朝合一を実現するに際し,皇位は大覚寺統(南朝)・持明院統(北朝)を交互にたてるようにしたことで,皇位継承に問題を残したが,足利義教は,自らの正統性のためにも,天皇の権威を高めることに努め,1428年,呼応するように傍流から践祚した後花園天皇が,義教暗殺後も長く在位,学問諸芸に通じることによる天皇の権威を確立し,"中興の英主"になった。1464年に,譲位して上皇になると,左大臣(将軍)足利義政を院執事として院政を敷き,猿楽,蹴鞠という共通の趣味で気の合った義政夫妻と親交するうち,応仁の乱が勃発,戦乱を終わらせようと執念を燃やすもまもなく没したが,義政夫妻がその最期を看取っただけでなく,義政は戦乱中の外出に反対する細川勝元の反対を押し切って,葬儀から四十九日の法要まで全てに参列しており,まさに,天皇家と将軍家が一体になるような公武合体の極に至っている。
足利義満の北山文化の観阿弥・世阿弥から,義政の東山文化の善阿弥・能阿弥・芸阿弥・相阿弥まで,阿弥号を持ち,独自の才能を発揮して,武家文化の興隆に貢献した人たちがいたことも指摘しておきたい。桜井哲夫「一遍と時衆の謎」から導かれるのは,戦で負けたり,主君の命に背いたりして,逃げ込む先にあったのが一遍の時宗であり,いわゆるアジールで,当然,都市の匿名性のなかに紛れこむことから,時宗は都市型宗教でもあった。とくに,南北朝の動乱は,他の戦とは全く異なり,それ以上の権威が無い天皇を戴いて,南北朝に別れて戦うのであるから,精神的障害が大きかった可能性が高く,それが,時宗が飛躍的に伸張した原因と考えられる。もともと武士である故,陣僧となって,戦う武士をサポートするとともに,同朋衆になるなど,生計を確保すべく,それぞれが,何らかの特技を身につける必要があったことから,多様な人材が登場,近世を準備することになる。南北朝合一後も,戦国時代においては同様の役割を果たすことになるが,真宗が一向宗化することで吸収され,織田信長によって,戦国時代が終わるとともに,一気に衰退していったのも,当然であったといえよう。江戸幕府初期の,万能の芸術家として知られる本阿弥光悦が最後になるのだろう。
足利義満の死は,大内氏の朝鮮利権を復活させ,倭寇禁圧の結果,琉球王国を代表に,倭寇末裔による地域政権ができ,また,水軍化して,戦国武将の抗争も激化していくことになる。>水軍
田中健夫「倭寇~海の歴史」をベースに,若干付け加える形で述べると,「高麗史」の,1223年の項に,「倭が寇する」という記事が初めて登場(倭は,大陸から見た日本の蔑称で,中国正史で,呼び名が倭から日本に替わったのは,天武天皇が国名を正式に日本としたことに対応して,「唐書」からになる),その50年後には,熟字「倭寇」として使われるようになるほど頻繁になり,太宰少弐資頼が勝手に高麗と交易し,その高麗が,元の圧力を受けて弱体化したことで,高麗の賤民とも結びつき,日本で観応の擾乱の起きた1350年には一気に本格化。造船ばかりか,医療まで,技術を持っていた者も多く,高麗に投降した場合でも,重用され,政府の中枢にまで入る者までいた。三港には,大きな日本人居留地ができ,対馬の宗氏や,大内氏,少弐氏などを特別扱いにして限定するも,多数の倭人が渡航,接待の費用も増大し,その結果,朝鮮の人たちの経済を圧迫して,窮した人たちが,倭寇に頼るという悪循環になった。
元と日本は,国としては対立する一方で,市舶司をおいた慶元に限って,正式な貿易船の往来を認めていたことから,それを利用した日元の禅僧の往来も頻繁で,幕府が警固していたため,通商がうまく行かない時に,官憲に乱暴狼藉を働く程度ことが専らで,倭寇の記事そのものが少なかったが,明が登場すると,連年のように倭寇の記事がでるようになり,朝貢体制を重視する明は,倭寇の禁圧を様々なルートで日本に求め,やがて,圧倒的な権力を握った義満によって禁圧され,日明間の正式な勘合貿易に一元化される。行き場を失った倭寇のうち,武力に優れる者は,その後に輩出する戦国武将らの水軍になり,また,琉球王国を建国した尚巴志や,肥前の大村氏のように,交易をしやすく,陸上の支配者の強くなかった土地に,根拠を定めるようになる。
義満は,日明通交のため,博多商人の肥富(コイツミ)の言に従い,同朋衆祖阿(ソア,素阿弥)を正使に,使節を派遣した。祖阿は異色の商人楠葉西忍の父で義満の時代に渡来した天竺聖と同一人物といい,天竺はインド以西を指し,西忍の幼名がムスルであったというから,中東アラビア方面の出身であったとみられる。肥富は安芸小早川氏の一族小泉氏の出身とされ,小早川氏のルーツは相模国足柄郡小早川村であったとされることなどから,肥富という奇妙な名が先で,それを小泉にするようになったとも考えられる。余談ながら,その子孫ともみられる小泉純一郎の風貌がユダヤ人的でもあり,肥富がユダヤ商人であった可能性も否定できない。
足利義満の死に続く,対馬の宗貞茂の死というスキをついて,1419年,明が倭寇の中国側の本拠地を徹底的に攻撃し,ほぼ同時期に,李氏朝鮮が対馬に侵攻(応永の外寇)したこともあって,壊滅的な打撃を受けた前期倭寇は終焉を迎え,倭寇が転じた水軍をも配下に置く本格的な戦国武将の抗争の時代になっていく。博多などに代わって,琉球那覇の地位が一気に向上,琉球王の使者になることで,朝鮮での扱いが格段に良くなることから,博多商人などが,盛んに偽称して問題になっている。遣明船については,大内氏は,もっぱら博多商人を使っていて,堺商人を使う細川氏の勢力と抗争,1528年,中国の寧波で,自らの使者が細川氏の使者と争いを起こして勝利,以後,遣明船の権利を独占することになる。
吉成直樹「琉球王国は誰がつくったのか 倭寇と交易の時代」によれば,
琉球語は北部九州語がルーツで,南下していく都度分岐,最後は南九州語から分かれて,11~12世紀に,琉球列島に到達した人たちによると考えられている。それまでは,(前述したように)北方の蝦夷と近い縄文人,つまり弥生人の渡来で押し出されてきた人たちの住むいわゆる未開の地で,本土ではとうの昔に無くなっていた縄文文化が保たれていた。最大の島(沖縄本島)ですら農業に適さない土地柄であったことから,交易というより,海賊的で,1243年に漂着した本土の人の記録でも,頭目が武装集団を従える異人と記されている。
喜界島は,平安時代には,大宰府と密接につながる,南方諸島支配の拠点であったことから,北部九州人は,喜界島において,早くから,朝鮮ともつながって,南方交易を支配し,11~12世紀には,中国の陶磁器も流通するような勢力で,おそらく平氏とも関係していたことから,1188年,源頼朝に征討された。この時期が,琉球正史で初の王とされ,1187年に即位して1237年に死去したという舜天王と,時期的に重なることや,鎮西八郎為朝が王になったという伝説もあることから,喜界島から逃亡してきた人たちによって,琉球国の歩が始まったとみて良いと思われる。
そして,13世紀後半から大型グスクの造営が始まり,14世紀後半には,高麗国の影響で構造的な革新がなされ,いわば,本土における戦国時代のように,群雄割拠の状態になった。勝連グスクの王は,阿麻和利(アマワリ)というから,アマ系であった可能性があり,その前の王は,茂知附(モチヅキ)すなわち望月と日本の姓そのものであった。その望月氏は,信濃国滋野氏の流れと伝えられることから,海洋民族であったと考えられる。
この間,13世紀半ばから広がってきた倭寇の勢力圏にとりこまれ,1389年に,倭寇が高麗で略取した奴隷を,中山王察度が高麗に送還したという記録があるように,奴隷貿易までしていたことが知られる。1360年に即位に即位して王統を開いたという察度は,朝鮮語のサトが地方官などを意味したことから,高麗から渡来したのではないかといわれる。いわゆる琉球三山時代においては,それぞれが東シナ海交易圏の主体者になっていたが,いずれも,中国との交渉ができたのは,中国人居住地久米村があったことによる。北山王国は全く異質であったとようで,明の建国により,元に仕えていたイラン系遊牧民アラン人が渡来し,居住して交易商人になったといわれる。隼人が中央アジアの遊牧民トカラ族であったことにもつながる話といえよう。
1368年に,中国で建国された明の洪武帝は,倭寇禁圧を,とりあえず日本の王とみなされていた(九州にいた)南朝の懐良親王に要求するも埒が明かず,琉球に鉾先を向け,1372年,招諭に応えて朝貢してきた察度に対して,破格の待遇をしている。やがて,将軍足利義満が明から国王として認知されるようと,その要請に応じて,1406年に倭寇を禁圧,勘合貿易を開くに至り,倭寇の頭目たちは一気に新たな場を求めざるを得なくなる。
1410年即位した尚巴志は,まさにそれに対応するように渡来,鉄器製造,交易に優れて,父の思紹をたてて,一気に琉球を統一したと考えれる。その本拠地佐敷グスクは,それまでのグスクとは異なり,本土中世の城郭そのものであった。琉球王国は明の倭寇対策によってできたといえよう。ついでながら,肥前国大村氏も,15世紀前半に突如登場したこと,交易を主体にして勢力を伸ばしたこと,藤原純友の末裔つまり海賊がルーツであることを自称していたことなどから,琉球と同様,倭寇であったと考えられる。
なお,琉球建国に,平氏が関わっていたとすれば,糸満という地名や,糸数という名字など,伊都国の末裔を示すイト系が多いのも,頷けよう。イメージをたくましくすれば,琉球列島の日本本土と中国や南方との関係が,航海技術の発展によるスケールの違いを別にすれば,上古の時代の伊都国のあり方に,良く似ているようにみえる。そして,敵対することになった邪馬台国に当たるのが強藩薩摩であり,その先の場が無かったことが,結局,薩摩藩の支配下に置かれてしまうという不幸の始まりになったのである。
ところで,源頼朝による武家政権発足とともに,相模の国から島津氏が薩摩に配されることになりi,その島津氏の本姓は秦氏をルーツとする惟宗氏であることはすでに述べたが,ここで,中国に対する琉球以上に,朝鮮に対して,地理的。歴史的に密接な関係を有している対馬についても触れておこう。荒木和憲「対馬宗氏の中世史」を読みながら勝手に解釈をしてみると,江戸時代には,対馬の主が宗氏であることは,当然のようになっていたが,その宗氏もまた,島津氏と同様,惟宗氏すなわち秦氏をルーツとし,鎌倉幕府発足の頃,幕府の守護の埒外ながら,対馬に進出していたらしく,北条執権の頃には,守護代のような位置になっていたらしい。そして,琉球の王国発足前と同じように,宗氏一族の間で抗争が絶えなかったが,倭寇の活動が禁止されたことから,琉球王国が成立し,肥前国に大村氏が登場したのと同じ頃に,対馬においても,倭寇の主体たる平氏(イト系)の参入があったらしく,それを利用する形で,のちに藩主になる宗氏の覇権が確立,いわば宗王国が成立したと見られる。こうしてみれば,大陸との関係は,全く倭寇によって築かれたと言わざるを得ないだろう。
戦国時代に入ると,百済の末裔と称し,朝鮮との貿易で財力を蓄えた周防の大内氏が,公家その他京の文人を救済する形で,雪舟を代表に,山口に芸術を花開かせ,大内義興時代には,京都に在留して,将軍の代役を務めるに至る。1573年に,織田信長によって,将軍義昭が追放され,足利幕府が滅亡するまで,細々と,足利将軍は続くが,その間も,公卿の三条西実隆が文化面で大きな役割を果たすなど,足利時代は全体を通して,支配者はシラギ系ながら,文化的にはクダラ系の時代であったといえる。足利将軍が藤原氏に取り込まれたことが,応仁の乱を勃発させ,中世の幕府体制を壊すとともに,クダラ系藤原氏といえる大内氏の覇権を招いたといえよう。大内氏はまた,第9論で述べるように,長州人のルーツにもなったのである。
桓武平氏のところで述べたように,いわば平氏の原郷ともいえる周防の瀬戸内海沿岸中ほどには,平安時代において銅銭を製造した唯一の場所の名残である鋳銭司があり,そこが藤原純友に襲撃された後に登場する平氏は,この地の銅を活用し,大陸との交易を通じて財をなし,やがて覇権を握ったという。その鋳銭司に関連するが,大内氏は,古代からの長登銅山に関わり,世界遺産になった石見銀山を発見,朝鮮半島から当時の先端精錬技術灰吹法を導入したことなどでも知られる。
ところで,明治維新の主役は長州人という言い方がされるが,長州とは,現在の地名では山口県で,旧国名では,長門国と周防国を合わせたものであり,中臣鎌足のところで述べたように,百済王族だった鎌足を受け入れ,中臣姓を称することができるようにして,ナカ系の乳母に育てられた中大兄皇子と乙巳の変を起こして,歴史に登場させた場所なのである。その証拠として示したように,大内氏の都山口の西半に広く吉敷(キシキ)という地名が広がり,キシすなわち百済王族が,キすなわち来たところを示しているからで,戦後の長州人を代表する岸信介の「岸」姓は,百済王族の「キシ」そのものを表し,その正統な末裔であることになり,岸信介の弟の佐藤栄作,外孫の安倍晋三が,ともに長期政権を担った,影の理由である気さえしてくる。
その長州一帯を支配した大内氏は,自らのルーツは百済であるとし,京の貴族,すなわち藤原氏ときわめて近しい関係にあったこと,戦国時代に入ると,山口に公卿らを招いたばかりか,一時は,京で将軍の代わりまで務めたことなど,権謀術数にたけた百済人ぶりを発揮したといえ,何事も武力で決着しようとした源氏に代表される新羅人とは対照的なのである。以上のことからだけでも,長州人,そのもとになった大内氏は,かつての藤原氏の遺伝子を強固に持っていることが推測されるのである。
大内氏を飛躍させたのは,1395年,大内義弘が,(まさに,クダラ的藤原氏のやり方の)讒言によって,九州探題の今川貞世を左遷させて,朝鮮の利権を奪取して巨利を挙げるようになったことによる。金の力だけでなく,藤原氏との歴史的関係もあって,応仁の乱では,政広が将軍の代わりをし,1491年には,義興が入京して,将軍そのもののような存在になり,遣明船の利権をも独占するようになるが,1518年には,山口に戻り,1528年,中国の寧波で,自らの使者が細川氏の使者と争いを起こしたりして威信も低下,戦国武将が次々と登場するようになるなか,義隆が,ザビエルの布教を許可した翌年,家臣の謀反により滅亡に至り,交替するように,織田信長が登場するのである。
ここで,大内氏について,どんな存在であったかを,改めて検証してみよう。
はじめ,多々良姓を名乗っていたのは,東国の三浦氏などと同様,平氏出身を示すとともに,古代のタタラ製鉄,そこから起こった'タタラを踏む'という言葉があるように,鉄器民族を示すものでもあが,その一方,自らの氏族のルーツを,百済王としていて,一般の解説では,朝鮮半島との交易を有利に進めるためにそうしたのだろうといわれ,確かに,朝鮮貿易を通じてつくりあげた多額の財を寄付することで,皇室や公家を味方につけたといわれるすが,それだけではとても,大内氏が京都の公家,さらには朝廷と特別な関係を結ぶことができたことを説明しきれないと思われる。もともと周防の在庁官人であった大内氏の,初期の当主盛見がいみじくも,'武将としての才能に欠ける自分が,戦乱を勝ち抜いて周防・長門両国を支配できるようになったのは仏神のおかげだ'と述べていることに,そもそも武家ではないと自覚していたことが示されているようであり,他の守護には見られないシステマティックで整然とした統治機構を確立したことからも,武家(武闘)の才より,公家(文治)の才があったといえるのではないだろうか。
タイミングよく出版された伊藤幸司編「大内氏の世界をさぐる」を読んでみると,大内氏が京都の公家たちと関係を結ぶことができたのは,長門国に転法輪三条家の荘園があり,それを守ってきたことによるということで,転法輪の語がつくのは,ほかにもある三条家と違い,藤原北家直系,つまり,摂関家に極めて近いことを示しているという。なぜ,ここに,そんなにも大事な荘園があったのかを考えてみれば,それが,中臣鎌足の時以来のもの,百済王子であった鎌足が一時的に中臣姓を借りた土地であったが,鎌足の息子不比等が藤原氏を独占して以降,中臣氏が忘れ去れたように消されてしまうこととも符合,何よりも,大内氏が,わざわざ百済王子の子孫であることを表明したことから,本当に,鎌足以降の藤原氏と血のつながりあった可能性すら考えられるのである。それが全く分からなくなっているのは,絶対に明らかにしてはいけない秘密,タブーになってしまったからだろう。百済王の末裔を示そうとしてつくあげた神話もまた,藤原不比等が「日本書紀」によって支配を確立したことを彷彿とさせる。
だとすれば,大内氏が異例な官位昇進をしたことや,実質的に南北朝合一を実現し得たこと,維新前夜に起きた"七卿落ち"のトップが,転法輪三条家の実美であったことなど,全てが符合してくる。そして,大内義興が,追放された将軍足利義尹を奉じて上洛し,覇権を握ったのは,織田信長が足利義昭を奉じて上洛したのより60年も前であるが,そもそも,鎌足が中大兄皇子を奉じて,覇権を握ろうとしたことの再現でもあったろう。また,豊臣秀吉が死後神格化されたのを遡ること100年以上,大内政広が亡父教弘の神格化を実現しているが,これには,吉田神道の事実上の創始者吉田兼倶が深く携わったといい,のちの靖国神社の話につながることは言うまでもなかろう。ただ,神格化の話そのものは藤原氏とはつながらないので,神事を司ったとされる中臣氏の血がでたものかもしれない。
さらに,政広の運動の結果,教弘に,従三位が追贈されたが,室町将軍家ですらなかったことで,武家秩序を覆すものであったといわれる。上洛した義興は,将軍足利義尹が沙汰始すると,帰国を示唆,京都を治めるには義興しかいないと考える朝廷自らが慰留に乗り出し,義興がそれに応えるや,従四位下に叙し,続いて,生前の大内当主としては初めてとなる従三位,それも朝廷自身の意志によるという異例の昇進をさせるのである。大内義隆に至っては,武士としては破格の従二位に叙せられ,位階の上では,将軍と主従逆転してしまうのである。このような扱いがありうるのは,前述したように,藤原摂関家との特別な関係なくしては考えられないだろう。
それだからこそ,勘合貿易を独占し,南北朝合一をもなしえたということで,その結果,大内氏は中央にも匹敵する地方政権を確立したが,このようなものは,奥州藤原氏を彷彿とさせるところがある。存在は全く異なるものであったとはいえ,奥州藤原氏も,前述したように,藤原氏の末裔であったのである。
そして,小京都の代表山口は,数ある小京都とは比較にならず,極めて多数の公家,それに付帯する形で,雪舟や宗祇など一流文化人が来訪・滞在して形成されたのであり,その象徴として,関白でもあった二条良基と大内政広が合作「新撰菟玖波集」を残しており,朝廷公認のもと,戦国時代に唯一,伊勢神宮を山口に勧請することができたのである。その後も,関白にして大学者の一条兼良,内大臣にまで上がった三条西実隆という,文化面での公家による武家支配を象徴する人物とも,最も親しく付き合っていることから,やや強引ではあるが,時代の流れの上に位置付けてみると,大内氏は,源頼朝の起こした鎌倉幕府を,平氏系の北条氏が牛耳ったように,源氏の足利将軍を牛耳る藤原氏として,武家社会に抑えられていた平安貴族を復活させる役割を担っていたかに思える。
北条早雲は,伊勢新九郎長氏と称されたように,桓武平氏で,室町幕府政所を世襲した伊勢氏の一族の出身と言われるが,若い頃の経歴は全く不明で,1467年,35歳の時に,応仁の乱が勃発した際には,将軍足利義視に仕えていて,義視が伊勢に下るのに従ったが,翌年に,義視が帰洛するのに従わず,伊勢にとどまり,駿河の守護大名今川義忠に嫁いでいた義視の妹北川殿の縁によってか,招かれて駿河下向。今川氏に身を寄せ,石脇城を居城としたらしい。10年後の今川家の内紛に際して,扇谷上杉家から派遣されてきた太田道潅と出会い,調停によって収拾したことから,ようやく,歴史に登場。1486年に,道潅が謀殺されるや,犯人の今川氏の庶家小鹿範満を駿府の館に攻めて自害させ,竜王丸を駿府に移して今川家の家督とし,この功績により,興国寺城主となる。
1491年,60歳を目前にして,堀越公方の足利茶々丸を討ち,平氏のルーツたるイト系の坂東の拠点,かの北条政子の故郷,伊豆に到達する。戦国時代を告げる事件としても名高く,伊豆を平定後,目的を達したと思ったのか,出家するが,1495年には,相模の小田原城を攻めて,これを奪い,関東進出の拠点を確保するとともに,韮山に城を築いて居城とする。1504年,72歳にして,今川氏親とともに,扇谷上杉朝良を助けて顕定と武蔵の立川原で戦い勝利をおさめ,京都の医者陳定治を小田原に招いて透頂香(外郎)の製造販売を行わせるなど,城下の整備を図り,翌年には,「伊勢宗瑞十七カ条」を制定して,検地を始め,領国支配体制を基礎固めした上,相模の征服を開始,鎌倉へ入ると,荒廃した鎌倉の再興を誓ったことが知られる。1516年,ついに三浦氏を滅亡させて,相模を征服,その3年後,87歳という長寿で,伊豆の韮山城で没した。
こうして,北条早雲は,いわゆる後北条氏の祖となり,その末裔は,北条氏政・氏直父子が,豊臣秀吉に滅ぼされるまで,町民が城主を慕う小田原城下町を経営し続けた。
以後,いわゆる下克上の世となり,武将が乱立し,諸民族がシャッフルされることになるが,1543年の鉄砲伝来,1549年のザビエルの来日後に登場した,平氏の織田信長が,鉄砲,キリシタンに素早く対応して,ライバル(寺院勢力も含む)を撃破,最後は,源氏の足利将軍を追放して覇権を握ることになる。それとともに,源平交代という観念ができ,後述するように,源氏に関係なかった徳川家康が源氏と名乗ることになるのである。
鷹橋忍「水軍の活躍がわかる本: 村上水軍から九鬼水軍,武田水軍,倭寇…まで」によれば,水軍とは,海賊,傭兵,輸送人,交易人を兼ねたような存在で,大名,領主などの軍事組織に組み込まれながら,主従関係は無く,より良い報酬を求めて寝返りも頻繁であった。語源が,そもそも兵士,軍隊のことであって,海の技術・技能者を表している海賊とは異なり,合法的な存在であるとは言っても,陸の土地に執着しないため体制外にあり,それゆえ歴史に記載されず,分かりにくくなった。主な収入源は,海上警固,(海の)関料,傭兵であった。前述したように,1406年に将軍足利義満が倭寇を禁圧したことから,水軍化したものが多い。
倭寇時代の商用船が使われていたが,16世紀に大型の軍事専用船が登場して本格化,織田信長が覇権を握る1570年頃に最盛期となる。有名な村上水軍はずっと毛利氏の支配下にあったが,1578年,これを破った織田信長が,瀬戸内海の制海権を握り,飛躍することになる。豊臣秀吉の朝鮮出兵においても,九鬼嘉隆の日本丸など安宅船多数が渡航,嘉隆は,その後も大規模な安宅船をつくるも,諸大名の力を削いで,交易を中央に一本化しようとする秀吉のバハン政策,徳川家康による安宅船没収によって一気に衰退,鎖国政策により,船は無用になり進歩は止まった。
水軍の最初に登場するのが,宗像大社の宮司一族が率いた宗像水軍で,難破船の引揚げ修理が大きな収入であったといい,村上水軍はじめ,瀬戸内海の島々を本拠地とするもののほか,後北条氏の支配する伊豆(八丈島まで支配し,小笠原諸島を発見したともいわれる),安宅船づくりの中心になった九鬼水軍(九鬼嘉隆は大名にまでなった)の志摩つまり伊勢平氏の本拠地など,平家のルーツたるアマ系,イト系のシンボル宗像はじめ,まさに源氏につぶされた平家の生きざまが露わになる。また,松浦党(水軍)は,後期倭寇の中核になるが,中国南部呉の末裔のマツ系として当然かもしれない。>後期倭寇
最も有名になった村上水軍は,源頼義の甥仲宗が村上源氏の娘と結婚,名にナカが入ること,その子が信濃に土着したことから,海洋民族の血が出てくることになったと思われ,その孫の定国が,平家の勃興期に,瀬戸内海に進出したことに始まる。伊予の新居大島を拠点に,芸予諸島の塩を抑え,源氏出ながら,平氏が主体の(後白河法皇)院近臣となり,海上警固を担った。源平合戦においては,棟梁だった清長は,平家の策謀に引っ掛かって破れ,一旦は消えるが,義弘の時代に,越智氏の流れで,もともと伊予の有力な水軍河野家が危機に陥った時,その要請に応えて救い,英雄になって再登場,毛利家の水軍として活躍し,最後の村上武吉はさまざまな作品に取り上げられる人物になった。
全く異なるものとして,津軽十三湊を拠点にした安東水軍がある。前九年の役で征討された安倍貞任の子の末裔で,蝦夷を背景に,朝鮮,中国,琉球までもと交易して巨利を得たが,南部氏に敗れた上,大津波に襲われて,跡形も無く消え去った。(前述したように)北方から南下してきたツングース系で,刀伊の寇をおこした女真族と同様,騎馬民族が海洋民族化したものと考えられる。ついでながら,貞任の子宗任は伊予に連れてこられ,安倍晋三はその末裔にもあたるという。
この章TOPへ
ページTOPへ
前論同様,第二講「時代循環のパターン」も参照してもらいたい。>時代循環のパターン
ポルトガルの商売は,南アジアでは胡椒という産物をヨーロッパの銀・銅と交換することに意味があったが,日本では産物でないのはもちろん,肉食文化でないため,商品にもならず,それどころか,日本の金・銀・銅の保有・生産額自体が驚くべき多額で,それに対するニーズも無かったことから,はじめから植民地化する理由は無く,倭寇とのつながりもあって,ほとんど密貿易的状態が続くことになる。
田中健夫「倭寇~海の歴史」をベースに,若干付け加える形で述べると,1547年に,大内氏が滅亡して,遣明船が終わるとともに,明の福建省を中心とした南部沿海商人が倭寇化,(かつて呉の民族が日本に渡航したように),日本の海賊・水軍を取り込んでいく形で,いわゆる後期倭寇の時代になる。1514年には,マラッカのポルトガル人が中国に進出し始め,これら南部沿海商人と結託,植民地化の志向の無い彼らは,交易拠点の確保が目的で,やがて,琉球王国人と出会って高く評価することになる。そして,戦国武将のように,有力な海賊と頭目が輩出するようになって,明による討伐が繰り返され,1526年に,許棟4兄弟が滅ぼされた後に登場したのが,最後の大頭目とされる王直で,日本の五島列島を活動の根拠地とした上,(マツ系直系であった故に,話も通じたと思われる)松浦氏に招かれて平戸に居住した(長崎県と福建省は現在でも深いつながりがある)。
平戸という地名も,平氏との関係を思わせるが,苗字の平戸のルーツは,常陸国那珂郡平戸村といい,桓武平氏が展開していたところで,平戸のほか,関東の後北条氏や伊勢の港なども活動拠点にしたというから,まさに,平氏の末裔たちとのつながりが深かったといえるだろう。ちなみに,開銀の名総裁であった平田敬一郎は,平氏の棟梁を思わせる風貌としても知られたが,先祖は五島列島の人であったといい,三井のリーダーだった江戸英雄は,茨城県出身であったが,やはり,平氏の末裔を思わせるところがあった。
キリシタン時代に入ると,ポルトガルの貿易にも関与,種子島への鉄砲伝来も,王直の密貿易船によるものとされるなど,キリシタン宣教師の渡来も合わせて,その後の平戸の大発展の礎をつくり(かの有名な明の遺臣鄭成功もここで生まれている),1545年には,博多商人の助左衛門を仲間に引き入れ,大友氏,大内氏とも交渉をもつようになって,倭寇国王といった存在にまでなったが,1553年,中国側の拠点が掃討され,平戸に逃げ帰ると,以後数年,大船団を率いて,中国の沿岸を襲い,後期倭寇の最盛期になるものの,1557年に降伏し,翌々年に斬首された。その後も,倭寇の残党が,台湾を基地に,フィリピンはじめ南方へ襲撃したりするが,オランダの登場,明の海禁令の解除,豊臣秀吉の海賊(バハン)禁止令などによって,一気に衰退し,16世紀末には終息,江戸時代の博徒,明治維新後のヤクザへと繋がって行くことになる。
中国側の史料によれば,倭寇の日本人には,薩摩,肥後,長州の三州が最も多いと書かれており,この時に培われた密貿易のルートが,徳川幕府時代にも続けられて,巨富を蓄えることになり,結果として,明治維新につながったともいえよう。大友宗隣は,明の鄭舜功が倭寇の禁圧を要請すべく来訪してきたように,日本側倭寇のボスであり,(九州探題今川貞世を,讒言によって左遷させ,朝鮮の利権を奪取した)大内氏は海賊と癒着していて,いずれもキリシタンを容認していることから,倭寇とキリシタンが一体であったことが伺える。平氏出身の織田信長は,鉄砲や宣教師の活用はもちろん,これら密貿易とつながって,水軍の活用にも優れたことから,覇権を握るに至ったのである。
大友宗麟という,ユニークなキリシタン大名について補足しておくと,まず,鎌倉時代初期から,大友氏が豊後を支配し続けたのは,瀬戸内海の海賊とつながって,物資だけでなく,中央の情報入手にも長けていたらしいこと,そのルーツが相模国足柄であることから,一般に言われているように,藤原秀郷流でなく,平氏すなわちイト系であると思われる。宗麟が,日向にキリシタンの理想郷をつくろうとしたのは,一つには,天皇を超える神を認めるという,伊都国と邪馬台国の対立がもとにあって,平将門が関東に王国をつくろうとしたこと,もう一つは,北条早雲に始まる後北条氏が,領民一体となる国をつくったことに通じるところがあるように感じられる。
平氏出身の織田信長は,まず海洋民族一般の開放性で際立ち,渡来した鉄砲という物理的武器と,キリシタンという精神的武器をいち早く受け入れ,平氏特有の派手さと乱暴さでも際立って,戦国時代に終止符を打った。
キリシタンの影響については,海老沢有道「日本キリシタン史」に従うこととするが,同書には,鉄砲のことも触れられているので,まず,述べておくと,種子島への鉄砲伝来の評判はたちまち全国に広まり,紀伊根来の杉之坊は津田堅物を種子島に派遣し,屏太郎または皿伊且侖に製法を伝習せしめ,堺の鍛工芝辻清右衛門にも伝えられ,堺ではまた,橘屋又三郎が直接種子島から習得したほか,平戸や豊後にも伝えられ,伝来後,数年もたたないうちに,将軍足利義輝の耳に入り,島津・大友両氏は,度々,鉄砲を献上,それによって,近江の国友らが直ちに製造を開始,1549年,信長が五百挺の製造を依頼し,翌年には納めたとの記事があるなど,国産化は急速に進み,普及したことは間違いなく,1565年には,福田入港のポルトガル船が,平戸・堺の商船隊と交戦したばかりか,朝鮮や明に,日本の銃が伝わるほどになっていた。信長は,単に,鉄砲を使用するだけでなく,隊列を組ませて,銃撃させるなど,戦法をも工夫することで,他の武将たちを圧倒していった。
大航海時代そのものが世界史的動きであったが,同時に起こったイエズス会の世界布教も内実がつまったものとして,世界史的事象であり,日本の近世化を一気に促進させる一方,ヨーロッパからは想像もできなかった高度な文明に直面したことでも,他に類例を見ない事例であったといえる。織田信長は,1568年に入洛して,覇権を握ったとはいえ,戦国大名はなお,それぞれに王国的主権をもっていて,いわゆるキリシタン大名もかなりいたが,信長にとっての統一事業の当面の障害は,延暦寺を頂点とする仏教勢力であって,1570年,まさに平氏の乱暴さをもって,比叡山を焼討ちしたことは,新井白石も,残忍とはいえ,功績であると認めざるを得ないものであった。しかるに,もう一つの勢力,石山本願寺を核とする国家のような真宗教団が,戦国大名や,追放したはずの,将軍足利義昭と連携して立ちはだかり,その他,法華宗,興福寺などの仏教勢力を潰すことに注力しているところに,新たな思想と文化をもたらしたキリシタンはまさに願ってもないもので,宣教師を厚遇して,仏教の腐敗を痛罵させたりしているが,キリシタン大名高山右近を味方につける際,そうしなければ,信者を皆殺しにすると脅していることからも,信仰とは全く関係ないものであった。いずれにしても,仏教の教団は支配力を失い,徳川時代には,行政の(とくに戸籍管理の)出先機関にまで成り下がるのである。
戦国時代という,命を守ることの困難さや,下克上はじめ,究極の利己主義がはびこる世の中で,既成仏教の僧侶は堕落して救済にならず,一向一揆,法華一揆は,戦国の混乱を一層増すだけという時代に,キリシタンが登場,それまでの日本人に欠けていた合理的(科学的,実践的)思考をもたらすのである。
イエズス会のザビエルは,マラッカで,鹿児島出身のヤジロウに巡り合い,文明のレベルの高さを知って,日本布教を志し,ポルトガル国王などの意向を無視して,独断で来日する。のちに,織田信長の信頼を得ることになるヴァリニャーノとともに,宣教師としてはトップレベルの人材で,彼らキリシタンが,日本文明に対応した布教ができるよう賢明な努力をしたことも,日本の近世化という点で,幸いしたといえるだろう。1592年,天草で,日本での布教手引書として,「ドチリナ・キリシタン」が刊行され,以後,さまざまな工夫をしていく一方,一度,信者になった不干斎ハビアンが棄教し,1605年に,これに反論する形で,キリシタンを排撃する書「妙貞問答」を刊行することにもなる。
天正期(1573~1592年)には,連年,1,2万名の新信者が増加,1587年に,豊臣秀吉が「伴天連追放令」を出して後も,勢いは落ちず,1590年代に最盛期を迎え,30数万人に達したものと推定される。当時の日本の全人口を2,700万人とすれば,1.3%ほどの信者がいたことになり,東日本への布教はなされていなかったので,西日本では,2%に達していただろう。維新後,明治15年のキリスト教信者は,わずか5,000人で,全人口の0.013%にしかならないのに,当時の社会にもたらした影響の大きかったことを思えば,キリシタン時代は,その100倍以上の勢力であって,如何に影響が大きかったか想像できよう。それ故に,激しい弾圧を招くことになるのである。
弾圧の時代,大名や武家層,そこにつながる特権階層や貿易商人らが,次々脱落するのに対し,一般庶民の信仰は根強く,禁教によって,それまでの社会のつながりが断ち切られ,かえって純粋なものになって行く。「ドチリナ・キリシタン」などによって,初めて文字を与えられ,文化思想に開眼させられ,それを自己のものにする能力を与えられ,つまり,キリシタンの教育が,自立した庶民層の形成,女性の解放に寄与し,近世を準備したといえるのである。戦国武将松永久秀の命で,ある訴訟事件を担当した結城忠正は,偶然,京都の町人ディエゴと接し,キリシタンは追放される旨,脅したところ,堂々と論じたてたことに驚嘆,入信まもない町人が,これほど確信に満ち,論理的に説明できるのなら,その教育は本当に優れたものと,パアデレの来訪を求め,自らキリシタンになったという。
キリシタンの話を横に置くと,おそらく宣教師らともにユダヤ系商人が多数来日,ハタ系につながる商人的な人たちの血を目覚めさせ,蒲生氏郷や後の三井高利など,いわゆる近江商人が勃興,伝来した鉄砲の製造管理を担わされた堺の商人は,のちの「死の商人」を先取りする茶人となって暗躍,吉田光由の「塵劫記」に始まり,のちに関孝和という天才を生む和算の勃興も,そういったユダヤ人の影響抜きには考えにくいと指摘する人さえいる。そもそも信長が安土の地を選んだのは,秦氏を祖とする伊賀・甲賀の忍者などとの連携を考えてのことだったともいわれる。
信長が戦国時代を終わらせたところに,ポルトガル商人が登場,キリシタン以来,戦国武将の戦のレベルも知っているポルトガルは,日本を植民地化することは及びもつかず,世界の銀を支配することになって,繁栄を謳歌するようになり,その象徴が自由都市堺であった。
前話文献からの引用になるが,ポルトガル貿易が広まるとともに,博多などの貿易都市において町人意識の高まりがみられ,とくに,京に近い堺では,細川氏が貿易権を失うにつれて独立的機運が強まり,会合(えで)衆によって市政が運営され,戦国の争乱をよそに,自由都市的発展をしていった。宣教師らの書簡にも,堺は広大で人口多く商人が集住し,ヴェネチアの如く,元老たちによって治められており,日本国中,堺ほど安全なところは無く,戦の勝敗にかかわらず,この町に来れば,皆が平和に仲良く暮らし,礼節をもって交際していると記されるほであった。
「国際堺学を学ぶ人のために」の中で,中村博武が記すところによれば,堺商人の活躍は,応仁の乱によって,瀬戸内航路が閉鎖されたことから,南海航路に進出し,琉球貿易を通して鹿児島と密接につながり,進出してきたポルトガル商人と連携することで,繁栄を謳歌するようになる。ザビエルが京都に向かおうとして堺に至り,大内氏から紹介された豪商日比屋了桂の家に滞在,堺の街の繁栄を目の当たりにして,国王に,堺にポルトガル商館を設置するよう建言するも実現しなかったが,イエズス会士は,ポルトガル商人を介して,長崎・マカオ間の日明貿易に深く関与するようになり,堺の豪商も,大型船を使用して参加,平戸には,10隻近くが碇泊していたという。
堺の自治は,1419年,相国寺の子院の崇寿院領となっていた堺南荘の住民が,訴えを起こして認められ,1431年,住民自らが年貢を請け負う組織を形成したことが契機になり,町内での争いごとを禁ずることで,自治都市となり,畿内で迫害や動乱が起こるたび,宣教師らにとって,格好の避難場所になった。この平和主義の根源は,仏教寺院の集積によるもので,堺商人が,戦乱の波及を防ぐとともに,寺院を通じて,権力者とつながることで,貿易利権を守ろうとしたことによる。しかるに,反キリシタンの急先鋒たる法華宗が多かったため,堺には,キリシタンは,あまり広がらなかった。了桂の家の蔵の一つをミサのための集会場として,毎日密かに集まったという。
数は少なかったが,小西立佐・行長父子のような優れたキリシタンも登場,立佐は,1566年頃,ハンセン病者救護のための慈善病院を設立,50人ほど収容するほどになり,1625年まで存続した。のち,豊臣秀吉からは,生糸貿易のために重用されて,堺政所(奉行)に任じられ,行長は,瀬戸内航路監視の任にあたり,キリシタン大名になるのである。新たに来日したヴァリニャーノが織田信長の信頼を得たこともあって,1585年には,堺にも,教会堂が完成,住宅や病院が建設され,南蛮医学も伝わり,呉服屋安右衛門の島田清庵は,教会で医療を学び,医を生業にしたといわれる。これまた,庶民のレベルの高さを示しているだろう。
キリスト教の根源の一つ,霊魂不滅を説くことが最大の目的となったザビエルは,日本人の理性の高さを認め,学殖豊かなヌエスに,日本赴任を命じた。ヌエスは,プラトン,アリストテレスなどの蔵書を携えて来日,当代随一の医者で学者曲直瀬直三が,1584年に受洗したのは,霊魂不滅の問答の結果によるという(オシ系のところで触れたが,マナセという特異な姓は,おそらくユダヤ人の支族の名からきており,彼自身に,キリスト教の問答を受け入れる要素があったとも思われる)。堺でキリシタンになった人物には,僧侶,医師,武士など知識階級が多く,畿内全域でもそうであったことから,プラトン由来の魂の永遠論が,日本の知識人に説得力を発揮したことを示しているといえよう。
堺の製造業としては,絹織物,鉄砲鍛冶,金細工などが栄えており,前話で述べたように,1565年には,製造した鉄砲を用いて,小豆島の福田港で,ポルトガル船が,平戸・堺の商船隊と交戦している。職人のレベルも高く,キリシタンになった金細工師が制作した祭壇画は,宣教師自身が,ヨーロッパ本家のものより優れていると認めている。そして,有名な千利休による茶振舞が,富裕な町衆の間で流行,了桂の客人として招かれたアルメイダは,茶道具が宝石のように高価で取引されること以上に,振舞の様式の洗練ぶりに感嘆している。堺では,民間人による出版も盛んで,1528年に「医書大全」,1590年に「節用集」など,実用書が出版されている。
織田信長は,平氏の派手さと乱暴さの代表選手ではあるが,ロックリー・トーマス「信長と弥助」によれば,謁見の際,宣教師ヴァリニャーノが護衛のために連れてきた黒人奴隷を,その肌の黒さが本物だと分かった途端,人物の優れていることを見抜き,敬して接したどころか,弥吉という名を与え,自らの小姓にまでしてしまう海洋民族らしい開明的なところがあった。その弥吉は,本能寺の変で,信長の側にいながら,唯一殺害を免れた人物でもあったが,それは,清和源氏の嫡流を自認して周囲のものを見下していた明智光秀が,殺すに値しないもの,それどころか,動物のような存在とまでいっているのと対照的であり,ここにもなぜ,光秀が信長に謀叛を起こしたのかの理由が垣間見えるようである。一介の黒人が,一国を支配する者の側近になったと言うことで,世界史上,稀有な事件として,近年,各国の意識ある人たちにおいて,弥助は,シンボル的な存在になっている。
同書にはまた,マカオの開拓者で,日本ビジネスにも精力的に取り組んだランディロという人物が,ポルトガル王族の末裔と称してはいたが,実は,海賊船船長として貿易を営んでいたユダヤ人であったということ,それどころか,マカオの商人の大半が,隠れユダヤ人だったということ,つまり,ポルトガル商人の実質は,ユダヤ人が握っていたことが書かれており,堺の商人の主な取引先がマカオであったことから,堺を介して,ユダヤ人による日本人への影響があったことは,否定しようがないだろう。ルーツがユダヤ人である可能性の高い,近江の蒲生氏郷,三井らは,ユダヤ人と出会い,お互い分かっていなかったかもしれないが,触発された可能性があり,また,和算など江戸時代の文化につながって行く。家康の顧問,ウィリアム・アダムズ,ヤン=ヨーステンらの存在も,すでに,ヨーロッパトップの国々の人との交際になじんでいたからこそ,可能になったといえよう。
下克上によって,武士の間での上下が意味なくなった上,キリシタンの影響で,庶民が人権に目覚めたように,源平でなかった豊臣秀吉,徳川家康が,自らの力を再認識し,国家権力奪取に目覚めたとみることができる。秀吉が,全国統一を成し遂げたことで,日本人としての国民意識も芽生えたと考えられよう。
出自すら分からないような身分(河原乞食,非人説すらある)から,全国統一に至った豊臣秀吉こそ,究極の下克上であったといえるだろう。年譜を簡単に辿れば,18歳の時に,信長の草履取りになって以降,次々と,戦功や築城能力で累進し,近江長浜城主になってなお奮闘,1582年,46歳の時,備中高松城での毛利氏との決戦を目前に,信長暗殺の報に接する(本能寺の変)や,直ちに毛利氏と講和を結んで兵をかえし,山崎の戦で明智光秀を破るとともに,信長の後継を宣言,反対する宿老の柴田勝家をも滅ぼして,覇権を握るや,全国制覇にのり出す。外交的手段で家康をも臣従させる手腕を見せ,朝廷の権威をかりて,関白,太政大臣となり,まさに,身分制社会の頂点に立つに至り,堺の千利休・津田宗及らを茶頭に,北野大茶会を催すなどしながら,1590年,小田原の後北条氏を滅亡させて,全国統一を達成すると,かねてから服属を求めていた明国を討つため,2度にわたって朝鮮出兵にしたが苦戦に陥り,1598年に没したということになり,それぞれの事柄については,様々に解説されてきている。
ところが,その出自については,公式には,尾張国中村で,織田信秀に仕えた足軽木下弥右衛門の子に生まれたというが,それも養父であったというから,それまでの支配層とは全く別の民族であったと考えて良いだろう。唯一の手掛かりとなるのが,養父の木下姓ということになるが,この姓が,上鴨社氏人・下鴨社祠官膳部などに見られるということから,次節の家康のところで詳しく述べることを先取りしていえば,崇神東征で大和朝廷ができる際に,国譲りした,あのマツ系であった可能性が高い。
そもそも,秀吉は,猿のような風貌だったといい,国譲りする際に登場した長髄彦を思い起こさせ,大坂城という,それまでになかった広い低湿地帯の城と城下町は,かつての呉の地に似ており,家康の江戸城に引き継がれるのである。末盧国のところで述べたように,濃尾平野のいわゆる木曽三川が,呉の国の地同様,"江"と呼ばれるのをはじめ,岐阜あるいは"蘇"がつく中国南部に類似する地名が多く見られ,鵜飼はじめ極めて古い文化を有しているなど,マツ系の民の集積地にふさわしい。有力武将の輩出はじめ,日本史上重要な役割をし,関東・関西の中間に位置しながら,なぜ首都になれなかったのか,まさに,抑えられた民族マツ系の地であったからとさえ思えるのである。>末盧国
そして,紛争を禁止する惣無事令,正確な土地を保障する太閤検地,治安維持の根本になる刀狩り(一般人は武器を持たない,現代の鉄砲所持禁止にまでつながる),身分を保障する士農工商ほか,新たに登場した庶民(町民)に対応する,それまでになかった支配システムを創出し,これまた,家康は,それを引き継ぎ,具体的な施策にしただけともいえるのである。付け加えれば,戦に優れていたのは,春秋の呉と同時代の「孫子の兵法」を身につけていたと想像するのも一興である。
家康と何が違ったかといえば,松の字の入った姓でなかった,やはり,末盧国のところで述べたように,呉太白の子孫,すなわち王族でなく,支配されていた側と思われ,それが,松平の徳川家康にとって,潰す対象になったのだろう。にもかかわらず,マツ系であるゆえ,アマテラスに対抗するように,自ら神になることを目的とし,家康の東照宮とは比較にならないが,秀吉も豊国神社に祀られているのである。源氏であれば八幡神があるのはもちろん,平氏,藤原氏なども,自ら神になろうとはしないはずである。天皇家との関係でみれば,出自の低さ故か,その権威に頼ろうとしており,王族末裔だった家康との差も歴然とする。さらに,中国まで支配を夢見たのも,先祖が支配されていた側の末裔としては,当然の心情だったのかもしれない。
それらを別にしても,秀吉が一代で終わらざるを得なかったのは,実子ができなかったことであろう。正妻北政所に子が無く,側室らにも全くできなかったことから,秀吉はいわゆる男性の不妊症であったと考えられ,おそらく自ら出身の部落の男子を利用して,寵愛する淀殿に長男鶴松を誕生させるも夭折,同じ頃,片腕だった弟秀長が病死,実母大政所も死去して,心境が一変し,千利休を自刃させたともいう。そこで再び,やはり極秘に部落の男子を利用して秀頼が誕生すると,表向きはあくまでも実子であったことから,政権を支えてきた甥秀次との関係が不和となり,一族もろとも,切腹させられたが,その残酷さには,秀頼が実子でなかったことを隠すのが如何に大きなことであったのかも示しているのではないだろうか。
前述のように,それまでの,源平という正統的な武家とは全く異なるマツ系の豊臣秀吉は,それら先輩の武家の支配はもちろん,それ以前の,クダラ系藤原氏とも異なる,全く新しい統治方式を打ち出し,その後を受けて,長い江戸時代を築いた同じマツ系の徳川家康の施策の多くが,秀吉の施策を受け継ぎ,さらに,徹底させたものになっているのである。
本能寺の変の翌年の1583年,豊臣秀吉は,大坂の築城を開始する。もともとこの地は,石山本願寺があった場所であったが,織田信長の安土城ですら,山上に築造され,広い城下町を意識したものでは無かったのに対し,単に,地の利が優れていただけでなく,低湿地帯とはいえ,平らで広い土地に,町人たちをも集まる城下町を整備して行こうとするもので,ルーツが低湿地帯を臨む呉の国の,マツ系ならではの発想で,着々と整備して行くが,城下町までを囲み込む惣構を築いたところで,1598年,秀吉は死去,徳川家康の支配下になって,ストップしてしまうだけでなく,大坂の陣によって,灰燼に帰してしまう。しかしながら,大坂城の発想は,同じマツ系の家康が,江戸の城下町整備の先行モデルになったことは,間違いないだろう。
関白となって国政を行うようになった秀吉は,1585年,全国各地の大名に,世の中の争いを無くすことを目的とする「惣無事令」を発した。法令の主な内容は,大名間の領土紛争,村同士の水論・山論を禁止することであったが,この政策に従わなかったことを大義名分に,関東の後北条氏を滅ぼすことになる。
全国統一を前にした秀吉は,1588年,海民の武装解除を目的に,海賊,水軍の首領に,海賊行為をしない旨の連判の誓紙を出させる「海賊停止令」を発する。倭寇を意味するバハンの禁止令ともいわれるように,織田信長時代に隆盛だった後期倭寇は,中国人主体であったとはいえ,日本の大名と関係して,その警固や経済的繁栄に貢献,全国統一をめざす秀吉にとっては,排除すべきものであったのである。それも,「豊臣政権体制の大名となるか,特定の大名の家臣団となるか,武装放棄して百姓となるか」いずれかを迫り,海での警固料を徴収する権利も禁止したため,倭寇,海賊,水軍は消滅するに至るのである。同年に出された「刀狩令」と同等の兵農分離策でもあり,海商を自らの政権下に組み込み,明朝との勘合貿易はじめ,海外貿易を完全に支配しようとするものでもある。そして,徳川家康が,関ヶ原の戦が終わるや,御朱印船を始めること,1609年に,個々の大名が勝手に貿易をしないようにする大船建造の禁を発令したことにつながるのである。
倭寇・水軍は,その活動の場を失い,その多くは,東南アジアの日本町で,その後のオランダ貿易にも関わり,陸に上がらざるを得なかった者が,おそらく博徒などになり,明治維新後のヤクザにもつながる,反社会的ながら,国家権力を行使する上で欠かせない存在になった。また,倭寇時代には,その取り締まりの過程で,一部は,朝鮮や中国の地にいつくようになったことから,現在もなお,大陸と裏でつながる,様々な犯行組織が存在することにもなるのである。
「海賊停止令」と同じ1588年に,「刀狩令」を発令,武士が,農民を完全に支配でき,反乱を未然に防止するため,農民たちが独自に隠し持っていた武器を接収したのであるが,江戸時代が,長く平和であったことに直結しているばかりか,近年になって,銃社会アメリカの悲惨な事件を見たり,聞いたりする時,日本が銃砲所持を禁止していることの良さ,そのルーツでもあることを思えば,如何に優れた施策であったか思い知る。
全国統一を達成した秀吉は,その翌年の1591年に,「身分統制令」を発令,その内容は,侍(若党),中間,小者ら武家奉公人が百姓・町人になること,百姓が耕地を放棄して商いや日雇いに従事すること,逃亡した奉公人をほかの武家が召抱えることなどを禁じたもので、,文禄・慶長の役を控えて武家奉公人と年貢を確保する意図があったとされている。これまた,江戸時代の士農工商の先取りともいわれるが,そのような社会全般の身分統制でなく,武家奉公人の身分統制を目的とした法令で,むしろ,江戸時代の奉公人制度に関する法令の先がけとされるようになった。とはいえ,家康が士農工商の制度を考える契機になったことは間違いないだろう。
織田信長時代から,奉公人木下藤吉郎(豊臣秀吉)は,検地の実務を担当しており,本能寺の変後,明智光秀を山崎で討つと,山崎周辺の寺社地から台帳を集め権利関係の確認を行うなど検地を本格化させていく。1591年に,太閤を名乗って以降,全国的に実施して行くのが,「太閤検地」で,その土地がどれだけの量の米を生産出来るかを,隅々まで綿密に調べて行く。同時に,生産量を示す単位を統一すべく,「石高制」を導入,米の量を計る秤の単位まで統一させたが,江戸時代が,年貢によって長期に存続する根本的な制度になるのである。
1592年関白豊臣秀次の名で出された「人掃い令」は,いわゆる戸籍調査の実施で,一村の人数や性別,職業を書類に明記する事を義務付けたものであり,これによって,士農工商の基礎が出来上がり,身分制度はさらに進化して,江戸時代が長く続くことになる。
なお,秀吉においては中途半端であった「バテレン追放令」は,徳川2代将軍秀次の時代に,とてつもなく強化され,3代将軍家光の時代には,鎖国に至るのであるが,貿易に関心の高かった秀吉においては,思いもよらないことであったろう。
ついでながら,下克上の典型とされ,一目置かれた信長にまで反抗して,自刃に至ったことで毀誉褒貶の大きい松永久秀(弾正)は,近年,事務・交渉能力が優れていたことで登場し,朝廷と関係を築くことで権力を握るようになったもので,信長への反抗も,本能寺の変の先駆ではないかと再評価されるようになってきたが,松永の姓からしてマツ系であり,出自が明らかではないという点からも,秀吉に先駆する,近世への露払い的な人物であったと考えられる。松永久秀は,美濃の斎藤道三の傘下にあったと言われるが,実は,道三の父で別名が松波と言われた人物についていたらしく,また,久秀が最後に本拠とした生駒の近くには,松尾山があり,日本最古の厄除け寺といわれる松尾寺があって,かつてのマツ系の本拠地であったと見られることなども,裏付けになろう。
後期倭寇の間に日本の利権が東南アジア方面に広がり始め,その終焉をもたらした,豊臣秀吉,徳川家康の御朱印船によって,本格的な展開が始まる。岩生成一「南洋日本町」によれば,ご朱印船以前の,1593年,秀吉による呂宋(ルソン)派遣に始まり,1604年に,家康によって,正式な御朱印船となって以降,1636年に鎖国となるまでの間,御朱印船360隻近く,その他も15隻あって,ポルトガルから利権を奪うとともに,南洋移住が進み,フィリピンのマニラ東南郊に2か所(ディラオとサン・ミゲル),交趾(コーチすなわちハノイで,後のベトナム)の現在のダナンに2か所(フェフォ,ツーラン),柬埔寨(カンボジヤ)のピニャールとプノンペン,暹羅(シャム)のアユタヤには独立した日本町が形成された。
最大であった交趾の2か所には,最盛期に,それぞれ数十軒の日本人の家があったといい,町長役であった林喜右衛門や角屋七郎兵衛は交趾の名士でもあった。柬埔寨では,新興ながら,鎖国後,唯一の交易相手になったオランダ人との共存のような状態で,最盛期には3~400人の日本人がいたと考えられる。近年もなお,東南アジアで,唯一カンボジヤと安定的な関係なのは,この時からと考えられ,第1章で述べたように,日本にも,クメール人の血が入っていることも大きいであろう。暹羅(シャム)のアユタヤは,最盛期に600人で,日本町として最大であった。
そのアユタヤは,かの山田長政が渡航した地でもあるので,少し立ち入ってみる。山田長政は,駿府の商人の家に育っていたが,1607年,17歳の時,徳川家康が新築なった駿府城に来て,海外貿易に従事する豪商らが集結し,町が俄かに活気づくにも拘らず,放浪に出,沼津藩主大久保忠佐の駕籠かきになるが,1612年,沼津藩主が死去すると,駿府の豪商滝佐右衛門・太田治右衛門の船で堺から長崎に渡り,長崎から台湾を経てシャムに入る。1620年,30歳で,アユタヤ日本町の頭領となる。翌年には,シャム国王の使者が江戸城で秀忠に謁見して,以後,日本とシャムが親密になり,オランダを次第に駆逐するなか,日本人部隊を率いてスペイン艦隊を破り,オーククンに任ぜられる。翌年,日本町が全焼するも,再建し,翌々年には,オークルオングに昇進。再び,スペイン艦隊を破り,アユタヤ王朝防衛に貢献して,1626年,36歳にして,オークプラ・セーナピモックに昇進して絶頂期となり(日本人傭兵700人前後を率い,町の人口は3000人余りだったという),1629年,酒井忠世に書状を出すとともに,長政の船が長崎に到着し,シャムの使節が将軍家光に謁見。酒井忠世より長政に返事が出され,ついに最高位のオークヤー・セーナピモックに昇進するが,直後に,王が暗殺されたため,アユタヤを脱出,ナコンシータマラートを平定して,リゴール王になるものの,翌年,毒殺されてしまう。
山田長政は,鎖国前に死去してしまったが,その他の,東南アジアの日本人のほとんどは,鎖国とともに,現地に取り残されたのであり,東南アジア諸国のうち,とくに日本人の多かった4カ国との関係が,現在でも良好なのは,この人たちのお蔭であろう。
豊臣秀吉軍侵攻による朝鮮との敵対関係は,秀吉の死後,1600年の関ヶ原の戦を制して1603年に幕府を開いた徳川家康の登場によって修復され,朝鮮通信使まで往来する友好的関係になるが,なぜこんなにすぐに関係を修復できたのか謎であり,それ以上に,以後,1868年の明治維新まで265年平和が保たれ,鎖国までしながら,江戸の人口が世界一になっただけでなく,当時の世界各国を凌駕するようなハイレベルの文化を実現するなど,実際,欧米の歴史家から,パックス・トクガワーナと呼ばれ,オスマン帝国,清帝国に並ぶ本格的な帝国であったさえいわれるほどになったのはなぜなのか,という途轍もない謎を解明するキーは,前項で述べたように,徳川家康こそ,マツ系の支配者の呉太白の末裔で,徳川時代はその復活であったということなのである。してみれば,豊臣秀吉は,まさに,その露払いの役であったということになろう。
まず言えるのは,江戸時代は,一面,平安時代に類似するクダラ的な時代であり,家康が自称する通りの清和源氏の出身ならば,シラギ的な時代となるはずなのだ。彼のルーツは良く知られているように松平氏すなわちマツ系で,そのマツ系が伊勢の松阪から渥美半島を経て浜松に至る途中の三河国加茂郡松平郷に由来するということなので,末盧国のところで述べたように,呉太伯の子孫であった可能性が高いのである。家康にはまた,富士講行者の長谷川角行と密かに親交していた逸話があるが,その角行は,名前に角の字を入れているように,役小角の霊告によって行者になったといわれ,その役小角は,持統天皇のところで述べたように,マツ系の本拠地葛城の賀茂氏の出であったということなので,加茂郡は,応神朝秦氏が,マツ系を特別に処すべく,松尾大社と一体のものとして創建した上賀茂,下鴨神社の領地であったことを示している。賀茂神社は葵祭りで有名であるが,徳川将軍が三つ葵の御紋を使っていたのだから疑いようもなく,天皇家とは特異な関係を有していたということにもなろう。末盧国のところで,中国でも倭人を"呉の太伯の子孫"とする説があることを述べたが,徳川家康が重用した儒学者林羅山がこの話を支持していたことも裏付けになるだろう。つまり,徳川家康が長期にわたって安定的に続くような幕府の仕組みを創り得たのも,呉の国の歴史に学んだ可能性が高いということである。
さらに付け加えれば,家紋の,葵は「アフヒ」で日向と同様,太陽に逢う意とされ,葵科でない菊科のヒマワリも漢字で向日葵と表記されるなど,いわば天照大神の代用になっているようである。これらことを本当だと思わせるのは,家康自身が神になりたがっていたことで,歴代天皇で神がつくのは全て王朝の開祖であることと関係し,東照宮に照の文字が入っているのは,天照大神との繋がりを意識していると考えて当然だろう。ついでながら,上賀茂,下鴨神社と一体とされる松尾大社は,その名が示すように,マツ系のために創られた神社であるが,その社領は,徳川将軍の朱印状によって許されていて,社職の最高位の正神主に,その差配が任されたということなので,徳川氏自身が,マツ系であることを認めているのである。>松尾大社
良く知られているエピソードで,家康は長篠の戦に出た時,恐怖に震え,大便を漏らしてしまったことを自らの戒めにしていが,とても新羅的武将の姿とはいえない。上野国新田氏の支流で得川(エガワ・現在の太田市)の出であるとして,清和源氏の出身と偽ったのは,征夷大将軍の資格を得るために必要だったからで,徳川姓が得川を読み替えたものと説明できたからだろう。しかもルーツたる得川氏は時宗の僧であったというから,時宗が河原乞食など,最も下層の人たちに対応した宗教であることからも,豊臣秀吉にも重なる話で,国譲りしたマツ系との関係が裏付けられるだろう。そして,末盧国そのものが,朝鮮半島で百済領域になるところと繋がっていて,百済建国後も,マツ系の末裔葛城氏以来関係が深く,秀吉が朝鮮を蹂躙して間もないのに,再び友好関係を結べたのも何らかのルートがあったとしか考えられないのである。江戸幕府は,クダラ系政権というより,マツ系政権であったというのが結論になろう。文化面でも,平安時代は文学,室町時代は庭園がピークとすれば,江戸時代は絵画がピークになるが,そのルーツを辿れば,室町時代の水墨画,さらにいえば中国江南の文化につながるのである。
秀吉同様,自ら神になることを求め,東照宮がつくられる。源平交代説から,平氏信長の次ということで源氏を名乗ったが,本当に源氏の出であるとすれば,八幡が神様であり,自らが神になろうとすることはない。菅原道真を代表に祟りを怖れて神にするか,善政や治水事業などで恩恵を受けた人たちが,してくれた人を祀るか,明治維新後の軍神思想など,色々あるが,自ら求めて神になろうとするのは異例であり,東照宮はまた,その規模,華麗さにおいて際立ったものである。
家康が祀られた日光は,820年に空海がこの地を訪れた際,二荒山(ふたらさん=語源は補陀洛)の「二荒」を「にこう」と音読みし,「日光」の字を当てたという,アマテラスそのものを表す畏るべきものなのであるが,西すなわち京都に対して,東は自らが照らしているのだという強い自覚を示すとともに,マツ系の最終的拠り所の諏訪大社に対置(諏訪湖に対する中禅寺湖)させたものと思われる。徳川家康と日光の関係についてさらにつめてみると,家康は江戸の開発を円滑にできるようにするため,現在の江戸川を河口としていた利根川が氾濫を繰り返していたのを防ぐべく,現在の関宿あたりで利根川を分流させて,ナカ系に対応する別の水系であった鬼怒川につなげて,現在の銚子の方に注ぐようにしたのであるが(水運で野田が醤油を中心に発展する契機にもなった),その結果,鬼怒川水系最上流部に当たる日光の神様が,江戸すなわち徳川家の守護神になったということでもあるようだ。>新・上州遷都論
ところで,なぜ日光の地が選ばれたかということも,地名そのものが太陽であるからといえるが,さらに,なぜ特別の地になったのか考えてみると,海洋民族ナカ系に案内されて,オシ系が全国に展開した際,押上から利根川(荒川も)を遡上して忍(オシ)の地に王国をつくり(ついでながら,家康は忍藩重視していて,"知恵伊豆"こと松平信綱を配置した),さらに支流の鬼怒川を遡上したところで,華厳の滝に遭遇,その姿が東征した崇神の上陸地熊野の神々しい目印那智の滝と類似していたことから,特別の地と意識されたと考えられる。そして,日光の地名は,前述したように,ユダヤ系の秦氏出身の空海が名付けたということにも鍵があろう。
話は別になるが,徳川家康がイギリス人ウィリアム・アダムズを重用したことも,ユダヤ人レベルの話で通ずる部分があり,明治維新時のグラバーに近い役割であったと考えられる。すでに触れたように,三井財閥はその氏神が蚕の社ということで,秦氏に直結しているが,このことが,江戸時代に三井が飛躍した大きな理由であるような気さえしてくるのである。
網野義彦・宮田登・上野千鶴子「日本王権論」によると,江戸幕府は,天皇の賀茂への行幸の復活は認めるものの,禊だけはやらせなかったといい,今までの話からいえば当然であるが,本書はじめ,(世界も含めて)多くの歴史研究において,「なぜ,徳川幕府時代になってもなお,天皇家の存在を必要としたのか」「なぜ,明治天皇がすんなりと徳川将軍の江戸城にはいり,そのまま皇居になったのか」などが問題になっている理由も明らかなのではないかと思われる。維新時の江戸城の無血開城は,まさに,崇神東征時の国譲りの再現であったのだ。
最近,ふるさと納税のことで,泉佐野市と政府との間の戦いが話題になったが,市長の苗字が千代松であるばかりでなく,泉佐野とその周辺には松のつく苗字が多いことからも(松井知事,松浪健太・・・・),この辺りはマツ系の拠点ようである。泉佐野が,江戸時代に天領であったのは,マツ系である徳川氏にとって大事な場所だったということ,それ故,維新後の政府に反抗的なことが判明し,とくに,安倍政権が明治維新の中核の長州人であることで一層強くなっているのだろう。さらに,佐野(サノ)が神武天皇を表すことはよく知られているが,崇神東征の際,ここで上陸しようとして,長髄彦の一族に抵抗され,熊野の方に廻ったということなので,すでに述べたように,長髄彦もマツ系であることなど,泉佐野から,さまざまな疑問が氷解していくようにみえる。
江戸時代の日本は,小さいながらも,同時代の清やオスマンのように,一つの帝国であったといわれ,独特の幕藩体制で,戦を失った武家が支配し,いわゆる町人が大衆文化を先駆,世界的にも稀有な鎖国下の繁栄を現出したのであるが,もし,前項で示したように,徳川がマツ系であったからとすれば,一層,納得いくものになろう。そこで,たまたま発見した二つの論文によって,考察してみよう。
第一の論文は,京都大学の吉本道雅による「中国先秦史の研究」で,その要旨によると,まず,呉のあった春秋時代,諸侯国が都城を強化すべく軍役負担者を集住させ,この都城が"國"と称されるようになり,春秋的な"國人"も成立したといい,そのまま,幕藩体制における城下町をイメージさせる。ついで,春秋時代の"國人"には,恩恵授受を媒介とする私的な人的結合関係がみられ,それまでの,個々の利害にもとづく単純な君臣関係でなく,「道」という客観的規範にもとづく新しい君臣関係になったといい,これまた,幕府と藩主,各藩主とその家臣の関係に,そのまま当てはまるように見える。さらに,春秋時代の国制を特徴づけている「世族支配体制」について,複数の世族が,「卿」という地位を独占して世襲し,それが,諸侯国の統治機構として維持され,覇者体制と相互補完的に政治社会秩序を構成したが,その覇者体制が弛緩すると,国君が世族を打倒して"国君専権"を樹立することもあり,また,国君専権を安定的に維持するため,統治機構が全面的に官僚制によって編成されていったといい,やはり,幕藩体制そのものを見ている感じである。
なお,本論文では,呉について,わざわざ一章「系譜の分析」をたてて,呉が春秋諸国のなかでは,辺境にあって,もともと長江流域で最強であった楚の分族であることを主張していたが,楚と対抗して中原と交流するようになって,周の分族太伯の後裔を自称するようになったという。つまり,マツ系は,彼らが主張する呉太伯その人の末裔ではないことになるが,日本における諸家系,源平のところでも述べたように,それら氏族が力量を発揮するには,どうしても貴種性が必要で,それが,臣籍降下と結びついて,桓武平氏,清和源氏などになり,現在でも,ふつうには,桓武平氏の祖は高望王,清和源氏の祖は経基王とされているのと同じことであろう。
もう一つは,国際武道大学の林伯原・周佩芳による「古代中国における武士及び武士階層に関する研究~日中比較の視点を含めて~」で,春秋戦国時代は,文武がともに重視され,どちらを軽視しても政治を円滑に運用することができないと強く認識されていた。とくに,孔子の弟子で侍衛であった子路ほか,門下の侍が,孔子の教え「礼,楽,射,御,書,数」を良く守って行動したのをはじめ,孔子の影響が強かったことを指摘している。また,司馬遷の祖先が,代々剣術を教えることを職業としていたというは,戦を失った武士の生き方のモデルになったであろう。いずれにしても,武士階層は文士階層に対して,有力な社会階層であった,つまり,武士が支配する社会は必ずしも否定されていなかったらしい。
春秋戦国時代を終わらせた秦の始皇帝は,中央専制支配を強めるため,民間の武器を没収・焼却しただけでなく,以後,その所有や武芸の訓練も禁止,そして,漢の武帝が,国家統一の体制に理論的な根拠を与える指導理念を確立するため,大臣董仲舒の策を用いて,儒学を官学とし,その他の諸子百家の学派すべてを排斥するに至る。マツ系の出で,その後の中国の歴史も知っている徳川家康が,官学として,朱子学を採用するようになったことも当然であったといえよう。
まず,織田信長のお蔭で,既成の仏教が叩き潰され,庶民は,坊さんのくだらない説教を恭しく聴く必要がなくなり,同じく,信長のおかげで,楽市楽座など,自由に商売ができるようになったこと,次に,下克上を目の当たりにして,自らの生まれにかかわらず,道が開かれる可能性のあることを知ったところに,キリシタンのお蔭で自意識に目覚め,キリシタンとともに来日したユダヤ人はじめ,様々な人たちに,学問や仕事について触発されたところに,徳川家康のお蔭で,ついに戦のない世の中が訪れたのである。江戸時代の日本が,前述のように,一つの帝国で,パックス・トクガワーナといわれるのは,身分を逸脱さえしなければ,ほとんど自由であったことである。その点,ヨーロッパがなお,キリスト教の強い支配下にあったのとは,対照的であった。
当時,すでに,世界一識字率が高かったといわれる状況において,僧侶や武士には,それなりに教養等を身につけた人たちがいたのはもちろんで,仕事が無くなって,生活のために稼がざるを得なくなった彼らにとって,自意識に目覚めた庶民(町人ばかりか農民まで)を相手にすることが早道なのは当然であっただろう。というわけで,鎖国下にありながら,ヨーロッパをすら先行するような文化が醸成されて行くのである。そこで,以下に,江戸の初期から,幕末(シーボルト以前)にかけて,どのような人物によって,どのように展開していったのかを,簡単に,辿ってみよう。すでに,権力者たる武将らに取り入る術を身につけていた一部町人らは,いわゆる豪商になるが,その後は,その他の町人も含めて,まさに資本主義を先行するような方法を次々と開発していったことも忘れてはならない。
マツ系の観点から補足しておくと,首都江戸は,中国の(春秋だけでなく三国時代の)呉の地に,のち(日本の古墳時代)に花開いた晋の首都健康について,大室幹雄が著した「園林都市~中世中国の世界像」の目次にある,「自然を愛して開いた都市」「ランドマークの文化と自然」「牛車とおしゃべり文化」「園芸的世界」等々,まさに,園林都市そのものを再現するような都市でもあったといえる。
その嚆矢であるとともに,幕末まで衰えることなく続いたのが和算,西欧でいえば数学であり,脳の構造上,基本になるものであることは言うを待たず,算盤も普及させて,江戸時代の日本人の基礎をつくったものともいえるので,少し詳しく記す。
その和算の祖吉田光由は,佐藤健一「江戸のミリオンセラー'塵劫記'の魅力」などによれば,豊臣秀吉が死去した1598年に,豪商角倉了以の分家の医師の子に生まれ,数学に興味を持ち,「割算書」の著者毛利重能に学ぶもすぐに理解してしまい,吉田流算術元祖の角倉了以につき,来日まもないイタリア人宣教師で数学に優れるスピノラにも接触した可能性がある。了以の死去後は,子の素庵について,吉田流算術を伝授される。1622年の元和の大殉教で,スピノラは殉教,毛利重能の消息も不明,同年,数学書「諸勘分物」を刊行した百川治兵衛も佐渡に逃避行していることから,数学の知識の多くが,キリシタンによってもたらされたことが推定できると同時に,豪商も単なる商人でなく,数学を身につけていたことも分かる。素庵から蔵書全てを譲られると,それらを手本に,1627年,29歳の時,「塵劫記」を刊行。内容はもちろん,素庵の親友本阿弥光悦の挿絵装幀を得,普及し始めた算盤のマニュアルの役割もあって,大ヒット,その後も追加,編纂し直し,多色刷りと刊行し続け,1634年刊行の普及版「新編塵劫記」は,江戸時代を通してベストセラーとなる。その後転変とするうち,同じ毛利門下だった今村知商が和算書を刊行したのに対抗,1641年,43歳の時,根本的に書直した「新編塵劫記」を,末尾に12の遺題をつけて刊行,1653年,55歳の時,この遺題に初めて挑戦した榎並和澄が「参両録」を書いて,答術を発表するとともに,自ら新たに8つの遺題を提出,以後,遺題継承が流行,和算が大いに発達,幕末まで続くのである。キリシタン取調べが一段と厳しくなるなか,61歳で,筆を断ち,74歳で,没したが,角倉一族の墓所に埋葬できず,弟子渡辺藤兵衛により密かに豊後国西国東郡夷に移されたという。
そして,松尾芭蕉や井原西鶴といったほぼ同年齢の天才と同じ元禄時代に,和算の天才関孝和が登場する。1642年に誕生し,独学で「塵劫記」を読んで,高次方程式の解法「天元術」をマスターするとともに,次々と遺題の答えを出し,「古今算法記」の15問全部を一気に解いて,1674年,32歳の時,「発微算法」と題して発表,算盤を使わずに手計算できる「傍書法」を確立して,和算を飛躍的に発展させる。ライプニッツが行列式を考案したのより10年も前(1683年)に,自著のなかで,同じ解法を示し,ベルヌーイ数についても,その1年前に,算木で説明するため見かけは全く異なるものの,内容は正確に対応するもの発表するほどであった。関流の和算の祖になるものの,あまりに難解だったところ,20歳ほど年下の愛弟子建部賢弘が,1685年に,「発微算法」の解説書「発微算法演段諺解」を刊行して,多くの人が理解できるようにしただけでなく,関が,円周率について,多角形を細かくしていく方式で,小数点以下11桁まで導いたのに対し,無限級数展開を世界に先駆けて行い,一気に,41桁まで導いたほどのレベルであった。いずれにしても,天才においては,一般人との間をつなぐ人物の存在が,社会全体に普及させるのに不可欠であるが,そういう役割をする人物もまたいたことが,文化の厚みを示しているといえるだろう。
その他については,いくつか拾って,簡単に記すこととする。
官学の朱子学に対し,民間では,陽明学が学ばれるようになるが,その嚆矢も,開府まもない頃の中江藤樹で,単なる知識でなく,行動を伴うことにこそ意味があるする,陽明学の根本を示す"知行合一"の思想は,民間思想のベースとなる。陽明学ではないが,孔子・孟子など直接原典にあたり字句の忠実な解釈から研究すべきとして,古文辞学を唱えた荻生徂徠(1666~1728)は,中野剛志のいうとおり,日本史上,最もプラグマティックであった天才的思想家で,世が世ならば,同時代のイギリスの天才的思想家ジョン・ロック(1632~1704)あたりと,知能指数の高さを争ったと思われる。民間の学は,陽明学をベースにしていたことから,救荒作物の甘藷でばかり知られる青木昆陽が,徳川吉宗に召されて後は,蘭学の開祖のような役割をすると,有名な杉田玄白ほかを契機に,蘭学は,抵抗なく本格化して行き,幕末にかけて,宇田川家,桂川家など,世襲するような学者一族を生み出し,シーボルトを経て,欧米の近代科学が容易に受け入れられる素地をつくることになる。吉宗の時代には,官学の「湯島聖堂」に対抗するように,大坂で,幕府公認の学校「懐徳堂」が設立されたことも忘れてはならない。
天文学においては,幕末近くになっての在野の大学者麻田剛立の存在が大きく,弟子で天文方になった高橋至時が,かの伊能忠敬の師になったのは良く知られている。その麻田剛立と親交のあったのが,孤高の大哲学者三浦梅園である。科学思想家・啓蒙家としては,長崎の商家出の西川如見が,1695年,47歳の時に,日本で最初の世界商業地理書というべき「華夷通商考」を,1708年,60歳の時には,その増補版を刊行して,海外事情の普及に貢献,鎖国下で合理的認識を先駆し,富永仲基,海保青陵,山片蟠桃など天才的な人物も含めて,幕末にかけて,いわゆる経世家を多数輩出,これまた,文明開化を準備していたといえよう。全く別に,江戸の身分制度を根本から否定する独創的な思想家安東昌益,女性解放思想の先駆只野真葛も忘れることはできない。農業については,武家出身ながら,浪人となって,近畿・中国・九州を巡遊して農業調査し,自ら開墾して農業生活,その後も,諸国を巡遊して老農の意見を徴し,貝原益軒とも親交するようになって影響を受けながら,生涯をかけて著述に専念し,1696年,73歳,日本初の体系的農書「農業全書」を著して,まもなく没した宮崎安貞に始まり,幕末には,農業組合を先駆した大原幽学,そして有名な二宮尊徳に至る。幕末にかけて,国友藤兵衛,久米通賢,工楽松右衛門ら,すぐれた技術家が輩出,極めつけは,明治維新まで生きて,東芝の祖になった田中久重で,まさに,近代工業にそのまま移行するのである。
落語は,僧侶の安楽庵策伝が,1628年に,噺の種になる「醒睡笑」を著したのに始まり,1681年,鹿野武左衛門が座敷で,1684年に,露五郎兵衛が,京の祇園・北野天満宮・四条河原などの盛り場や神社仏閣の祭礼開帳の場所で,群集を前に演じたことで流行するが,寛政の改革で禁止されたのを,1816年に,烏亭焉馬(初代)が再興,幕末の桂文治以降,現代につながる落語家の輩出になって行く。僧侶から転じたものとして,囲碁の本因坊算砂,美術の本阿弥光悦が,同じく開府まもなくの人物であり,光悦は俵屋宗達を見出して,のちの尾形光琳につながる絵画の分野を開く。伊丹城主荒木村重の末子に生まれるも,父が,織田信長に反抗したため,落ち延びることになった岩佐又兵衛は,1615年には,越前の藩主松平忠直に買われて恩顧を受けて,次々,傑作を描いて,浮世絵の祖とされるが,いわゆる,浮世絵の様式になるのは,1660年に,初めての挿絵画家として登場する菱川師宣からで,1765年に,鈴木春信が本格的カラーの錦絵を描き,喜多川歌麿など,なお美人画,役者絵が中心だったものが,幕末に,葛飾北斎という天才を産むに至る。北斎より前の,伊藤若冲や,与謝蕪村の登場する天明期の画家は,浮世絵ようなローカルなものを超え,世界の画家と並べても,一流といえるような作品を次々と創作している。
戦を失った武士が転じた先の典型は剣術指南であろう。その皮切りになったのは,薩摩の島津氏に仕えていた東郷重位で,27歳の時,京都で,もと佐竹家臣で天寧寺の僧善吉から天真正自顕流を学び,以後,生涯にわたって不敗。戦の無くなった開府まもなく,初代薩摩藩主島津家久に知られ,1604年,43歳の時,家久師範の体捨流東新之丞と立合わされ,一瞬にして勝利し,逆に師に迎えられ,薩摩示現流創始者になった。61歳の時,家久の参勤交代に従って江戸に出た際,柳生流の旗本二人から試合を申し込まれ,あっという間に勝利,最後の立合いになった。以後,伝書の編纂に取り組み,82歳にして,没した。最後の相手,あまりにも有名な柳生流の,柳生宗矩は,1601年に,徳川家師範,1623年に将軍になった家光の師範になり,禅僧沢庵とも親交があって,67歳の頃,沢庵から「不動智神妙録」を書き与えられて,柳生新陰流兵法の理論体系の完成,家光,沢庵,宗矩3者の身分を超えた人間関係は,江戸幕藩体制の完成に大きな力となった。70歳の時,子の十兵衛に授けた「兵法家伝書」は,近世剣術界に大きな影響を与える。続いて登場した,伝説の宮本武蔵が,1645年,61歳に死去する直前に,究極の書「五輪書」を書き上げ,そして,200年後の幕末に,千葉周作,斎藤弥九郎の道場が,維新の志士を鍛えることになるのである。
武士から転じて,新たな文化を拓いたのが,鈴木正三で,大坂の陣が終わるとまもなく,禅僧になり,1624年,45歳の時には,庶民へも説法し始め,53歳の頃の「二人比丘尼」はじめ仏教説話で,仮名草子を先駆,続いて,僧侶浅井了意が,1657年,45歳の頃から,仮名草子を書き始め,70歳頃まで書き続けて,質量ともに最大の作家となった。それに代わるように,1682年,浮世草子「好色一代男」で登場したのが,天才作家井原西鶴で,1692年の「世間胸算用」まで,傑作を書き続けて,翌年,没したが,その年には,天才俳人松尾芭蕉が「奥の細道」を完成させて,翌年に没しただけでなく,先述したように,天才数学者関孝和,さらには,天才言語学者契沖,少し後になるが,天才ミュ-ジカル作家近松門左衛門と,かの犬将軍徳川綱吉のもと,元禄時代はまさに,天才の時代であった。念のため,芭蕉の登場も,開府まもない頃の,松永貞徳,西山宗因による,俳句の確立があってのことである。天才とはいえずとも,同時代の貝原益軒は,綱吉が将軍になった年,50歳頃から,死の直前の有名な「養生訓」まで,30年以上にわたって,啓蒙書を書き続けた,今でいえば,売れっ子評論家であった。江戸時代後半になると,西沢一風,江島(屋)其磧など,自ら著作しながら,印刷出版する者が現れ,山東京伝に続いて,出版だけでなく,メディア支配を先駆するような蔦屋重三郎が登場する一方,十返舎一九のような,近代につながる職業作家も登場する。
現在においても,日本を代表する財閥系企業の住友の祖の一人とされる蘇我理右衛門(あの蘇我氏の末裔か)は,1590年,18歳の時,豊臣秀吉が大仏をつくるというので,多くの銅吹き屋の集まる京都で,{泉屋}と号する吹屋を開業,一家あげて熱心な涅槃宗門徒だったことから,門兄住友政友の姉を妻に迎え,友以が誕生,友以が住友政友の養子となり,1702年,別子銅山の永代稼行権を獲得し,幕府の御用銅増産のため,多大の援助を受けて,住友家の発展はゆるぎないものにしたことで,政友とともに,住友の祖になった。住友に並ぶ三井もまた,伊勢の豪商の娘で,織田信長に滅ぼされた近江の武士三井高安(ハタ系といわれる)の長男で,松阪に新居を構えた高俊に嫁いだ三井殊法が,もともと,聡明で優れた商才を持ち,武家の出で商売に疎い夫に替わって,家業の質屋と酒・味噌の商いを順調に伸ばし,4男それぞれには商売をさせ,4女は次々と有力な商家に嫁がせ,夫の死後,1635年,末子の高利を江戸にやり,その高利が,1652年に金融業を始め,1673年,江戸および京都に店を開き呉服業(越後屋)を創業,店前売りの新商法を始めて大ヒットさせた翌年に没し,三井の祖になった高利の母として,今なお,尊崇されている。少し前までは,財閥の一つとして有名だった鴻池も,武士の子に生まれ,父が討たれたことから,商売に関わるようになった山中新六が,1598年,28歳の時,四斗入の酒樽二個を一駄として江戸送り,他に先駆けて大量輸送を始め,44歳の時に,家憲「子孫制詞条目」を定め,多くの男子それぞれに商売をさせるとともに,1619年,大坂に鴻池屋を開き,以後,事業を拡大させていくことに始まる。この他,開府当初には,和算のところで登場した角倉了以・素庵,淀屋个庵,茶屋四郎次郎3代,河村瑞賢など,名だたる豪商が多く登場している。
以上の他,賀川玄悦,山脇東洋,吉益東洞,華岡青洲,浅田宗伯など,医者の鑑とでもいえそうな人や,浄瑠璃の竹本義太夫,歌舞伎の市川團十郎家など,まさに,現代のアメリカのブロードウェイのような娯楽の提供者であったし,断片的ながら,文楽や川柳のようなユニークな文化を生み出した人など,まだまだいくらでも思いついてくるが,この辺にしておこう。
この章TOPへ
ページTOPへ
武家政治がいかに定着していたかは,明治維新も,武家が主導したことから明らかであるが,その主体は,ハタ系をルーツとする島津氏の薩摩と,大内氏以来のクダラ系を主体とする長州との連携であり,それまで続いてきた北朝すなわちシラギ系の孝明天皇に替わって,南朝すなわちクダラ系の明治天皇を立てることで実現する。足利氏は,後醍醐天皇に謀叛したとして嫌われ者になり,関係者は肩身の狭い思いをすることになる。マツ系の徳川氏から,オシ系の天皇への大政奉還,無血開城は,古代の国譲りの再現であったように見える。天皇側近のクダラ系藤原氏が巻き返しはじめたことや,島津氏がハタ系であったことから,イギリスとの連携,さらにはフリーメーソンのグラバーに繋がって,維新への強力な援護射撃を受けることができたのも大きい要因だっただろう。
前論同様,第二講「時代循環のパターン」も参照してもらいたい。>時代循環のパターン
世界的にも不思議がられているように,無くしてしまっても良かったと思える天皇家を存続させたのは,秦氏により,天皇家と一体化される仕組みがつくられていたからだろう(松尾大社,上賀茂・下鴨神社,葵祭)。天皇の権威は利用されるだけになった。
桓武平氏出の織田信長は,上洛することが支配の源泉であること,すなわち,天皇の権威を十分に認識しており,マツ系とはいえ下層の出であった豊臣秀吉も,天下を掌握するためには,天皇の権威を借りざるを得なかったが,呉太白の末裔を自認する徳川家康においては,天皇すら,支配下に置くようになり,徳川将軍が,家臣らを掌握するための官位の出どころとして,利用するだけになってしまったといえる。
戦国時代の動乱で,朝廷の財政は逼迫し権威も地に落ちかけていたことから,織田信長は,時の正親町天皇を保護するという大義名分によって京都を制圧すると,様々な政策や自身の援助によって財政を回復させるとともに,敵対する勢力だった朝倉義景,足利義昭,石山本願寺との戦いにおける講和に,正親町天皇の勅命を利用,その間に,信長に,貴重な蘭奢待の切り取りを許可したことが,今でも話題になるといった関係であった。
豊臣秀吉も,正親町天皇に御料地や黄金を献上して,関白の座を得,後を継いだ後陽成天皇には,信長に追放されていた将軍足利義昭を伴って参内,義昭が,征夷大将軍職を朝廷に返上したことで,室町幕府は正式に滅亡したのである。秀吉の演出した天皇の聚楽第行幸は,自らが天下を支配したことを演出したもので,朝鮮出兵は,明を征服した暁には後陽成天皇を明の皇帝として北京に遷すという誇大妄想から来ており,さすがに,秀吉に対して"無体な所業"であると諭すなど,天皇の権威は高まった。
1600年に,徳川家康が政権を握るに至って,状況は一変,自らの後継について干渉され,武家伝奏が設置されて,天皇が監視されるという事態になり,直後に,相次いで発覚した宮中女官の密通事件(猪熊事件)に激怒するも,幕府の措置は手ぬるいものに終って不満を抱き,以後,孤独の中で暮らし,やがて退位するに至ったのである。この間,家康は政仁親王(後水尾天皇)への徳川秀忠の娘和子(東福門院)の入内を求められ,先例のないこととして拒否するも,圧力に屈して,応じることになり,以後,父子も不和になった。
後水尾天皇は,1611年,15歳で,後陽成天皇のあとをうけて即位したが,将軍徳川秀忠から禁中並公家諸法度や,所司代,付武家などを通して種々の干渉が加えられるなか,1620年,秀忠の娘和子が女御となり,天皇の母中和門院と対面,その配慮で,和子を受入れ,親密になって行く。幕府は皇居を造営し,新たに1万石の御料を加え,4年後には,和子を中宮に冊立,形式的には尊崇される。1626年に,中宮御所法度も制定され,秀忠,続いて将軍家光が上洛し,二条城に行幸するが,以後幕末まで,非常時除いて天皇が禁中を出ることも,将軍の上洛も止むことから,朝廷の存在は,ほぼ,無視されるものになったといえよう。翌年の紫衣事件で,朝廷の面目は完全につぶされた上,翌々年,将軍家光の乳母春日局が無位無官の身で拝謁するという前例のないことが敢行され,ついに,不満を爆発させ,突如,和子所生の興子内親王(明正天皇)に譲位,和子は東福門院となり,以後,明正・後光明・後西・霊元の4天皇,51年にわたり院政をしき続け,東福門院も国母であり続けることになる。この間,天皇が,幕府にあてつけるように,朝廷文化を育むことに努めるのと並行するように,東福門院は,毎年雁金屋に膨大な注文を出し続け,この間,幕府が度々倹約令を出すも意に介さず,道楽し続け,1678年,重病で死去,天皇は,後を追うように,その2年後,時代を画すことになる将軍が家綱から綱吉に替わる1680年,84歳という長寿をもって没している。余談ながら,東福門院が死去して,雁金屋への注文が激減,道楽できなくなり,画家として稼ぐことになったのが,御曹司尾形光琳である。
1758年,のちに,尊皇思想が具体化ししていく端緒として,宝暦事件として有名になる事件が起きる。ことの次第は,儒者,神道家で,家塾を開いていた竹内式部が,武家に政権を奪われた朝家の政権回復の心構えを説く一方,激しく将軍を誹謗したことに,現状に不満をもつ門弟の徳大寺公城,正親町三条公積,烏丸光胤,西洞院時名ら公卿が感銘を受け,朝権回復を志すようになったことから,朝幕間の関係悪化に発展するのを恐れた前関白一条道香らが,彼らを永蟄居など処罰して,天皇の周囲から排除,式部については,京都所司代松平輝高に連絡して幕府にゆだね,翌年,京都町奉行は式部を重追放に処し,宇治山田へ退去させられたが,この頃になると,幕府の支配力に陰りが見え始め,その他にも,尊皇論者が輩出する。
この宝暦事件で,竹内式部の弁護を行った山県大弐は,甲斐国に生まれ,若くして,幕藩体制への批判思想を身につけ,内部からの革命をと思っていたところ,将軍側用人大岡忠光に見出され,取り込まれてしまうが,宝暦事件直後には,のちに吉田松陰にも影響を与える「柳子新論」を脱稿,1760年,忠光が死去すると大岡家を辞し,家塾を開いて,大きな影響を及ぼし,いよいよ行動に移そうとした矢先,門弟に密告され,1767年,式部父子はじめ,国学の師や藩主名代・門人ら多数とともに捕縛,江戸に送還され,首謀者として斬罪となった(明和事件)。処刑に際しての立派な態度が獄吏をも感銘させたという。山県姓のルーツは美濃国ながら,現在も,長州に集中的に多いことから,維新後,長州閥を主導する山県有朋にもつながると思われる。
そのような時代状況のなか,皇位継承危機に,傍流から天皇になり,長期に在位,幕府に対抗して,復古再興に努め,権威を高めたのが光格天皇といわれるので,藤田覚「光格天皇 自身を後にし天下万民を先とし」に従って,やや,詳しく生涯を追ってみることにしよう。
田沼意次が老中になる前年の,1771年に,中御門天皇の弟直仁親王に始まる最も新しい宮家閑院宮2代典仁親王と第六王子に生まれるが,母も異例に身分が低い浪人医師の娘であったことから,皇位には程遠い存在であったが,8歳の時,後桃園天皇が急逝,それを秘しての朝幕の交渉で,白羽の矢が立ち,形式的に天皇の養子にされ,江戸時代初の実子でない異例の天皇になり,父たる上皇はおらず,最後の女性天皇だった後桜町上皇がそのまま続く。まもなく,実父閑院宮典仁親王の御所内での席次が,父の弟の左大臣鷹司輔平より下という低さに驚愕,太上天皇の尊号宣下を願い,幕府から拒否されるも,経済的な優遇措置を引き出すなど,有能ぶりを発揮していく。
1786年,15歳の時,田沼意次の失脚に続く,将軍家治の死去による幕府の動揺をみすかしてか,早くも自ら朝廷政務を主導,強引に,朔旦冬至旬,新嘗祭を実施し,復古再興に取組み始める。翌年,松平定信が寛政の改革を始めた年,米価高騰に,御所千度参りが始まると,追い散らさないように指示,参加者は約五万人になり,直訴も受け入れて,幕府に,空前となる窮民救済を申し入れて実現させ,古儀採用の新御所造営について,幕府の了解を勝ち取ると,(30年にわたって)平安時代の大内裏の考証に没頭してきた裏松光世(固禅)をブレーンに,御所を復古造営し遷幸,華麗な行列が人々に強烈な印象を与え,公家の間でも,空前の復古ブームになる。
その間,実父閑院宮典仁親王への太上天皇尊号宣下の沙汰書が老中松平定信に達して,問題が本格化するが,関白鷹司輔平が幕府よりのためラチが開かず,1791年(20歳),鷹司輔平を更迭して,一条輝良を関白にし,尊号宣下について公卿群議で圧倒的支持を得るも,松平定信の不信を買い,翌年,中止するに至り,完全な敗北に終わる。朝廷の権威を回復すべく,神武天皇から120代という皇統意識をもった署名を始め,高位高官を含む,前代未聞の多数の堂上公家を一度に処分,'図らずも天皇になった'という意識から,残っていた石清水・賀茂臨時祭の再興を表明するなどするうち,尊号事件を素材に広く流布した実録物では,朝廷が勝利した筋書きで,偶然即位することになった天皇への同情がみられるなど,庶民の間では,朝幕の力関係は逆転し始める。
1807年(36歳)のロシア船狼藉事件では,ついに,幕府から報告がなされ,以後,対外情勢も朝廷報告の対象になり,開府初期からの大政委任論は衰えて行く。1813年,石清水臨時祭が380年ぶりに再興,後桜町上皇が死去すると,供養のための真言百八遍奥書に「大日本国天皇兼仁合掌敬白」と自署,当時,ほとんど使われていなかった天皇という意識を明確にした後,1817年(46歳),恵仁親王(仁孝天皇)に譲位。在位年数38年は,後花園天皇を超える異例の長さで,2019年に明仁天皇が生前退位して,"光格天皇以来"と表現され,にわかに注目されることになった。仁孝天皇もすでに18歳になっていて,形式的な院政ではあったが,多くのことについて,意見を聞かれ,指示を与えており,まさに,最高実力者であった。
1822年(51歳),将軍徳川家斉が,従一位左大臣,将軍就任前の世子家慶が,正二位内大臣,御台所も従二位と,いずれも先例を超える昇進を認めたお礼に,幕府から修学院御幸の再興を勧められ,翌々年,90年ぶりの修学院御幸,その行列を多くの町民が見学した。以後,毎年のように,修学院御幸をしていたが,大塩平八郎の乱の翌年,中風を発し,1840年,69歳で没した。翌年,874年ぶりに天皇号が贈られ,諡号も合わせると954年ぶりの再興で,再興にかけた生涯を象徴するものとなった。
光格天皇の朝廷復古活動に対応するように,民間でも,急速に尊皇思想が高まってくる。
林子平・蒲生君平と並ぶ"寛政の三奇人"の一人として知られる高山彦九郎は,上野国新田郡で桓武平氏秩父氏の末裔に生まれ,宝暦事件が起きた年は,まだ11歳であったが,「太平記」を読み,南朝の忠臣たちが志を遂げられなかったことを憤って,尊王の志を抱き,1764年,17歳に家出,諸国を回遊して,一流学者を訪ね,江戸では,細井平洲の学塾に出入り,禁裏に入って幾度か節会を拝観などするうち,1783年,36歳になる頃には,堂上公卿との親交も強くなり,1789年,尊号事件が起こると,公卿らと結託して薩摩藩を味方に引き入れる計画をたてるなどして,光格天皇の耳にも名が聞こえるまでになったが,林子平が拘引されて身の危険を感じ,島津氏への説得を行う役を担って九州に旅立つも,1793年,尊号事件の処理に怒り,久留米まで引返し,幽囚中の子平の死を追うように,憤慨のあまり自刃した。急速に尊皇思想が高まった時代を象徴する存在であったといえよう。
同じく"寛政三奇人"の一人として知られる蒲生君平は,下野国宇都宮の生まれであるが,田沼意次が失脚した1786年,18歳の時に,自らの祖が蒲生氏郷の庶族から出ていることを知り,名門の名を辱しめないことを誓って,自ら蒲生氏を名乗り,別に家を興した。1790年には,高山彦九郎の後を追って陸奥国に赴いたが会えず,帰路,仙台に林子平を訪ねるなど,三奇人は相互に認めあっていたようで,ロシア南下にともなって北方問題がやかましくなってくると,「今書」2巻を著わして時弊を論じるなどしていたが,1796年,28歳になると,歴代天皇の陵墓が荒廃していることをなげいて,「山陵志」論述を志し,各地の陵墓を調査,5年がかりで完成,その後も,国防と尊王を論じ続けるうち,知己友人の援助により,1808年,ようやく「山陵志」の出版が実現,幕末尊王論の先駆をなすものとなったが,5年後,45歳で病没した。蒲生氏のルーツは秦氏とも,鴨氏ともいわれる。
孝明天皇は,徹底した攘夷指向を持つように育ち,1846年,15歳で,父仁孝天皇の崩御のあとをうけて践昨するや,早くも,海防を厳重にするよう,歴代天皇として初めて,対外問題について,幕府に勅命。ペリー来航後,アメリカの圧力を受けた幕府は,1858年,日米修好通商条約調印の勅許を奏請,27歳の天皇は当時の大多数の公家衆と同様に開国を憂慮して勅許を見合わせたが,幕府は,勅許を待たずに調印したばかりか,蘭・露・英の諸国とも条約を締結したため,激怒して譲位を決意,幕府と水戸藩に勅諚を下して,叡旨の貫徹を図るも,幕府が釈明し続けた上,反対派の抑圧を始めたため,不満ながら受け入れる。以後も,盛んに勅下して,朝廷権威を回復して行く。
1860年,桜田門外の変で,大老井伊直弼が暗殺されると,幕府は低下した威信を回復するため,公武の融和を策し,皇妹和宮の将軍徳川家茂への婚嫁を奏請,天皇は,和宮の不同意を知って退けるも,再三の懇請を拒否しがたく,ついに勅許。結果として,朝廷は幕府に対して優位に立つことになる。この間,朝廷内では,攘夷派公卿の勢力が伸長,志士らとともに,攘夷親征を企図して,大和行幸を求めるに至るが,天皇は,これを無謀の挙とするとともに,討幕へと突き進む情勢を深く憂い,密かに中川宮尊融親王(朝彦親王)をしてその阻止を謀らしめ,八月十八日の政変となり,以後,政局が禁門の変・長州征討と目まぐるしく推移するうち,内外の情勢は次第に天皇の素志と反対の方向に進み,1865年,英・米・仏・蘭4国公使共同の要求によって,ついに条約を勅許,翌年,薩長両藩の盟約が成り,政局が討幕に向けて急展開するなか,痘瘡に罹って没した。そのタイミングから,暗殺説も絶えないことになる。
京都守護職の会津藩主松平容保への信任は特に厚かった一方,尊攘派公家が長州勢力と結託して様々な工作を計ったことなどから,長州藩には最後まで嫌悪の念を示し続けたという。
孝明天皇が践祚した年,その妹として誕生した和宮は,5歳の時,有栖川宮熾仁親王の婚約者になったが,日米修好通商条約の勅許問題や,将軍継嗣問題によって悪化した朝幕関係を融和するために,1860年,14歳の時,幕府から,徳川家茂へ降嫁するよう求められ,兄の孝明天皇は拒絶しするも,朝権の回復の足がかりとしようとする岩倉具視の献策で,攘夷鎖国の実行を条件に勅許,本人は強く固辞するも,周囲の説得に抗しきれず,これを受けいれ,翌年,江戸城に入り,翌々年には,婚儀がおこなわれ,御台所と称した。その翌年,1864年には,上洛直前の家茂に対して,攘夷を実行するように求めるなど,自らの使命を自覚して実行するうち,翌々年,20歳になったところで,第二次幕長戦争(長州征伐)の渦中,家茂が大坂城で死去すると,徳川家に嫁いだ身を自覚して,徳川家存続や無血開城に尽力,戊辰戦争に際しては,皇族の出でありながら,降嫁した徳川家の救済や,征東軍の江戸進撃の猶予を政府に嘆願する健気さを見せ,終戦後,徳川家の駿府移封を待って,京都に移住,28歳になって,東京に移住,家茂の眠る増上寺目前の麻布の地に邸を賜ったが,3年後に,急逝した。
その和宮の姑にあたるのが,徳川家茂の父将軍家定の正室天璋院(篤姫)で,今和泉島津家当主島津忠剛の娘に生まれたが,将軍世子家定の室候補の問い合わせに,ペリーが来航した1853年,18歳の時,島津斉彬の偽装工作で,その実子とされ,篤姫と名を改め,江戸芝藩邸到着直後に,家定が13代将軍となる。いよいよという時,安政大地震が起こって,婚姻延期,3年後,近衛家の養女となり,名を敬子と改めて,江戸城入城して婚礼,御台所となるが,翌々年には,島津斉彬に続き,家定も死去してしまい,天璋院と号する。1861年に,江戸城に入った和宮と初対面で,礼節を欠いたと朝廷側で問題になるも,本人間は不仲にならず,養父島津斉彬に逆らって擁立に反対した一橋慶喜が,1867年に大政奉還して裏切られ,幕府表方が不甲斐ないところ,徳川家存続のために,和宮とともに,目を見張る奔走,江戸城開城後は,潔く退城して,一橋邸に移居し,家茂が次期将軍に内命しながら慶喜に奪われた田安亀之助の養育に専念し,和宮の6年後に没した。
さて,維新の実現は,いわゆる薩長土肥でなされたが,維新後すぐに,土肥を外して薩長だけになり,ついには薩摩すら排斥されて,長州が覇権を握るに至る。長州は維新前,天皇にたてついて征伐されたように朝敵とされながら,本来天皇の最大のサポート役であった会津藩などを朝敵にしてしまった上,天皇を左右して大戦にまで至らしめ,靖国神社を武器に国民を誘導するなど,その専横ぶりは,まさにかつての藤原氏を彷彿とさせるもので,大内氏のところで述べたとおり,長州人は,いわばクダラ系藤原氏の末裔のような存在なのである。>大内氏
余談ながら,敗戦に至る最大の問題は,海洋民族が主たる長州が陸軍を支配,それに対して,本来騎馬民族である薩摩が海軍を担うという,根本的なネジレがある上,統治の不得意な海洋民族が軍を握ってしまったことによるとも考えざるを得ない。前章で述べたように,マツ系だった徳川の葵の紋は別にして,天皇家が菊の御紋であるのに対し,将軍家は桐の紋章であったのを,維新後の日本政府が使用していることも,クダラ系藤原氏のしたたかさが見えるようである。
「日本史リズム」のところで述べたように,維新前後というのは,出発点になったとみられる1837年の大塩平八郎の乱から,近代に向けて決着した1881年の明治14年の政変までということになる。そこで,長州を軸に,維新を実現したいわゆる薩長土肥に,尊皇攘夷論に大きな影響を与えた水戸藩の動向など加えながら,その経緯を辿ってみよう。
1837年に起きた大塩平八郎の乱を受けて,幕府が始めた天保の改革に対応するように,長州藩でも,1840年代から,毛利藩政への改革に向けての動きが始まり,それを進めようとする(革新)正論派と,それまでの藩政を守ろうとする(保守)俗論派の対立が生じる。こういった動きは,他の諸藩にもみられるが,すでに述べたように,長州人は,意見の合わないものを受け入れない,排除するという性格が強いため,1860年代にかけて,その対立が激化して行く。
1937年,大塩平八郎の乱は全国に衝撃を与え,越後の生田万が決起し,摂津でも騒動が起きるなか,水戸藩の藤田東湖が,乱の記録「浪華騒擾記事」をまとめ,それも受けて,翌年,藩主徳川斉昭が,幕府に内憂外患の意見書を提出,長州萩藩では,村田清風を起用して改革開始,1841年には,水戸藩校弘道館が開設され,翌々年,萩藩でも,村田清風の改革案を実施に移す。
その後は,大石学「幕末維新史年表」によれば,1844年,佐賀藩では,大砲の設置や,銃の製造を開始。水戸藩主徳川斉昭が,藩政改革の行き過ぎを問われて,隠居・謹慎処分。長州では,(正義派)村田清風が失脚し,(俗論派)坪井九右衛門一派に戻る。1846年には,前論で取り上げたように,践祚した孝明天皇が,歴代天皇として初めて,対外問題で,幕府に勅命し,水戸藩主徳川斉昭が,海外情勢についての意見書を提出,翌1847年,佐賀藩は,種痘でも全国に先駆けるなど,この段階では,明らかに近代化の先陣を切っていた。続くように,薩摩藩が,砲術館を設け,野戦砲や火薬の製造を開始し,水戸藩主徳川斉昭が,外国人追放の意見書を提出,長州では,藩政改革に失敗した(俗論派)坪井が失脚するなど,足元が定まらない。
1848年,薩摩藩で,密貿易によって藩の財政を立て直し,家老に昇進した調所広郷が,密貿易が幕府に露見した責任をとって自害し,土佐藩が,山内豊重(容堂)が新藩主となって,ようやく登場した翌1849年,薩摩藩で,お由良騒動が起き,改革の英主島津斉彬の登場に待ったがかかる。翌1850年,佐賀藩は,ついに反射炉を完成させ,大砲を製造するに至り,翌1851年,土佐出身の捕鯨家で,太平洋で遭難し,アメリカで教育を受けた中浜万次郎が帰国,独自の役割を果たして行く。薩摩藩では,島津斉彬がようやく藩主となり,一気に近代化が進む。そして,翌1852年,脱藩して遊学していた長州藩士吉田松陰が,強制送還されて謹慎処分となるが,翌年には,不憫に思った藩主の配慮で,10年間諸国遊学の許可をもらったところに,ペリー来航となるのである。
1853年のペリー来航を契機として日本中に広がる攘夷運動のなかでも,排他性の強い長州人の攘夷ぶりは際立ったものになるが,そこに吉田松陰という,自らも老中間部詮勝の暗殺を企てるなど,テロリスト的要素をもつ稀有のアジテーターが登場,わずか数年の間しかなかった松下村塾を通じて,絶大な影響を及す。
藩主から,10年の遊学許可を貰った直後,ペリー来航の報に接するや,浦賀に出かけて黒船をまのあたりにし,翌年,再来中のアメリカ艦に,闇にまみれて漕ぎ着けるも送り返され,江戸の獄に入れられたのち,引き渡された藩によって,萩の野山獄に投じられると,教育者の資質を発揮し始め,1855年に出獄すると,叔父が開いていた"松下村塾"で講義,思想が過激になるとともに,公然と通う者も輩出,以後,長州の維新の志士の多数が学ぶに至るも束の間,幕府に睨まれ,斬首刑に処せられ,わずか4年で終わる。その後,維新に至っていなければ,志士らはテロリストでしかなく,松陰は天才的アジテーターといわれるに留まったかもしれない。
孝明天皇も攘夷の思想が強かったため,尊皇攘夷へと飛躍するが,井伊直弼が暗殺された1860年を経ると,"松下村塾"トップ高杉晋作がイギリス大使館焼き討ち事件を起こし,1863年,開明派の代表たる長井雅樂が謹慎・自刃に追い込まれたように攘夷運動がピークになるなか,開国しようとする幕府の意向で,朝廷では公武合体派の力が強まり,八月十八日の政変となり,すでに述べたように,敗れた攘夷派が長州に"七卿落ち"する(応仁の乱時の山口大内氏のところに公卿らが都落ちするのに対応)。すると,その翌年には,朝廷を攻撃する暴挙に出て,朝廷を守ろうとする京都守護職の会津藩はもちろん,前年の薩英戦争に敗れて早くも公武合体派に転じていた薩摩藩などが参加した幕府軍に敗れる。この段階では,薩長は敵対関係で,長州藩こそ朝敵だったわけである。
同じ頃,前年の外国船に対する砲撃に報復すべく,下関に来訪した四国艦隊に砲撃されて敗退,講和したこともあって,攘夷派の公家中山忠光が下関で暗殺されるなど,開国派に転じるかに見えたのも束の間,1865年には,正義派を称する高杉晋作が再び決起(この時には伊藤博文すら参加していた),第二次長州戦争が始まる。ここまでみていると,長州藩というのは,朝廷・幕府・外国すべてを敵にし,しかも内乱状態が続いているということで,ほとほと,異なる意見を受け入れることができない人たちだと思えてしまう。
吉田松陰と違って,全く知られていないが,太平洋戦争の敗戦によって,その存在が,一つの国家支配の装置になっている靖国神社のもとをつくった青山清もまた,生粋の長州人であった。青山幹雄ほか「靖国の源流」によれば,松陰より15年前,萩の産土神椿八幡宮宮司の長男に生まれ,中年になるまでは,目立った動きはなかったが,1863年,48歳の時に,八月十八日の政変の七卿落ちに触発されて,(本講義で述べていることを裏付けるかのように)大内氏時代の"国風振興"調査を始め,同志と「神祇道建白書」を藩に提出し,翌年,"七卿落ち"の一人錦小路頼徳が,現地で病死してしまうと,彼を神として祀るように申し出た。第一次長州征討で福原越後が自刃すると,藩政府に申し出て,国のために死んだ人を神として祀ることを許され,福原越後の神霊を祀り,下関の桜山招魂社で初の招魂祭を斎行,同時に,松陰の神霊も祀っている。
明治維新に向けた藩のエネルギーのようなもの考えると,薩摩藩の場合,鎌倉時代からの大名,支配が得意なハタ系をルーツとする島津氏のもとで育まれた藩民性のようなものがあって,それが,徳川幕府から,圧力をかけ続けられたことに反発,まさに幕府を倒すことが目的であったという点でわかりやすいが,長州の場合,戦国時代までは,大内氏支配のもと,いわば一つの地域国家だったところ,毛利氏の支配に代わって,徳川幕藩体制に組み込まれたわけで,おそらく,毛利氏支配への反発が先にあっての,反幕だったように見える。それ以上に,尊皇攘夷,とくに,外国人(ヨソ者)を排除しようとする攘夷のエネルギーは強烈で,それが,一度は朝敵になり,いわゆる"七卿落ち"として知られる事件にもなったのであるが,攘夷派の公家が山口に落ち延びてきたのも,大内氏時代の縁がもとになっているといえよう。
長州藩中心に述べてきたため,付け加えのようになるが,薩摩藩では,藩主の島津久光自らが主導して,急進派を粛清,生麦事件後の薩英戦争で,一気に開国派に転じて行くのは,ユダヤ系秦氏出身ゆえ,イギリスと相通じた可能性があり,さらに,薩長同盟に至る前段としてのフリーメーソンのグラバー,そして,薩長同盟を実現させた土佐藩坂本龍馬の役割の存在の大きかったことを指摘しておく。
1866年,薩摩藩も本格的に反幕になり,坂本龍馬のおかげで,いわゆる薩長同盟が実現,第二次長州戦争では幕府に勝利,さらに,孝明天皇が崩御して明治天皇が践祚,高杉晋作も死去してしまい,一気に白紙転換するチャンスが到来するや,まさに手の平を返すのである。討幕の密勅が最初に出されたのが長州藩だったのは,大内氏のところで述べてきたことと関わりがありそうだが,それはともかく,大政奉還,王政復古となり,新政府が覇権を握るための最後の戦い戊辰戦争に突入,ここでも,長州藩が主力部隊になった会津藩への攻撃とその後の処理の残酷さが際立つ。薩摩藩の方は,西郷隆盛が江戸城の無血開城を実現し,箱館で,最後の最後まで戦った幕臣榎本武揚はじめ主要な人物を,戦後早くに赦免し,政府の重要なポストに登用しているのである。
ところで,いまだに不審がられている最後の将軍徳川慶喜の行動については,江戸城の無血開城とあわせてみると,徳川氏がマツ系であったことを知っていれば,1500年前,崇神東征の時に,マツ系民族が国譲りしたことを,再び,実行したに過ぎない,つまり,血を流すことを避けることの方に意味があり,それだからこそ,250年の平和の時代も続いたということなのである。
ここで改めて,徳川慶喜についてみてみると,吉宗以来,紀州系の将軍が続くなか,盛んに意見をすることで幕閣と対立した,御三家水戸の徳川斉昭の七男という末流ながら,俊才を見込まれ,家康の直系筋ということもあって,改革派の幕閣や諸藩から,将軍継嗣の候補に挙げられるも,井伊直弼の登場で排除されてしまう。直弼が暗殺されるや,改革派の期待がますます高まるも,母親が皇族出身だったことから,孝明天皇に配慮して,攘夷を支持する姿勢を示し,"二心殿"と呼ばれる矛盾した状態になるが,八月十八日の政変で,情勢が一変すると,朝廷からの,軍の最高司令官任命を受諾して,禁門の変などで大活躍しながら,幕政改革も指揮する力量を発揮,木戸孝允をして,家康の再来とまで畏怖させるほどで,将軍就任直後に,孝明天皇が死去し,攘夷派に配慮する必要が無くなると,兵庫開港を実現して,開国への道を一気に広げるのである。さらに,薩長の機先を制して,大政奉還したが,王政復古のクーデタによって,官位を剥奪され,駿府で謹慎生活となると,家康の遺産を守るべく,江戸を火の海にしないよう苦心,その後の長い人生を,多趣味に暮らし,まさに,近代的個人主義を先取りした,国譲りに相応しい傑物であったといえよう。
徳川慶喜は,家康直系であることによって登場し,そのことが,大政奉還という国譲りによって,幕府を終わらせる役割を担う大義でもあったのである。
戊辰戦争も終わったことから,1869年,長州の軍政トップ大村益次郎によって招魂社が建立されるが,その直後に彼が暗殺されてしまう。長州の大半の兵に帰郷命令が出て不満が爆発したからで,その後も諸隊の反乱が続き,やはり開明派ですぐれた人物といわれる広沢真臣も暗殺されるが,やがて鎮圧される。その後は,後述するように,クダラ系藤原氏そのもののような陰謀によるライバル排除が続くようになり,新政府の軍という重要な部署については,軍制改革を任された山県有朋の力が急成長,のちに,伊藤博文が暗殺されると,いわゆる権力の専横ぶりが見られるようになる。いずれにしても,自らの藩にいた優れた人材を次々と亡き者にしてしまう,その結果,二流の長州人が支配するようになっていくことを,どのように考えたら良いのだろうか。
ところで,太平洋戦争後の日本を統治する上でかかせないものになった靖国神社のもとつくった長州人青山清の幕末の活動については前項に記したが,その後,1867年に,長州藩が,朝廷から討幕の密勅受けると,密かに錦の御旗(官軍旗)を制作し,翌年,維新がなると,東征大総督有栖川宮熾仁親王の命で,江戸城で官軍側戦没者のための招魂祭を主宰。1689年,大村益次郎が九段坂上に招魂社を仮設(東京招魂社)した直後,刺客に襲われ死去すると,その遺志を受けて,宇部に維新招魂社を建立。1871年には,太政官布告で神官の世襲が禁止されて,国家神道が始まるとともに,兵部省に出仕して招魂社御用掛となり,翌年,兵部省が陸軍省になるとともに,山県有朋を祭主に,棟上式と遷宮式で祭典掛を務め,1874年の東京招魂社への明治天皇の初行幸で奉仕(祭主は山県有朋),以後,毎年御親幸に参列,1879年,別格官幣社に加えられて,靖国神社になるとともに,初代宮司に就任し,西南戦争の官軍側戦没者の招魂祭を行い,12年,在職のまま,没している。
戦後,靖国神社に対する国民の複雑な思いが消えないのは,そのルーツに長州支配があり,それが,長州人の排除の論理で,戦死したものは敵味方なく弔うという博愛の論理とは正反対,朝敵であった奥州列藩の人たちはもちろん,西郷隆盛すら祀られていないという徹底ぶりなのである。
ついでながら,長州藩の無謀ぶりがあっても,維新そのものを成し遂げられ,覇権を握ろうとする長州人を抑えることができたのは,軸になる人物として,公平無私といわれる薩摩藩の大久保利通がいたからであることはいうまでもない。蛇足ながら,薩摩の軍人の代表東郷平八郎の軍人としてのすごさに対して,長州の代表乃木希典は,戦地で多くのミスを犯し,多くの兵士を失った,とても優れた将とは言えない軍人で,明治天皇崩御に殉死したことでのみ,神様になったということになろう。太平洋戦争に至って,一層,開明的な海軍の薩摩,陰謀的な長州の陸軍の違いが鮮明になるのである。
明治維新に至る過程で,朝廷を守っていた会津藩などに戦争を仕掛け,まさに朝敵そのもであったのに,戊辰戦争になるや,手の平を返して,会津藩などを朝敵として苛酷に攻め,維新後は,まず薩摩と組んで,土肥を排除,薩長という言葉の影に隠れて,実際には,薩摩をも排除,山県有朋に代表されるように,国民の意向はおかまいなしに,弾圧政策をとり,かつて敵であった奥州などの諸藩出身者も都合よければ味方に取り入れ,最後は,天皇をも利用して,日本を戦争に持ち込みながら,戦後,まもなく,安倍晋三の祖父岸信介が素知らぬ顔で復活するという有様である。平安時代の,天皇など,時の権力に取り入って,登場の機会をつくり,一旦登場してしまうと,陰謀でライバルとなる氏族を次々排除,摂関となって天皇を思うように利用した,あの藤原氏そのものであるといえよう。
明治維新は薩長が主導したとはいえ,当初は土佐・肥前藩も一緒になった薩長土肥という四藩であったことが大きかったのはいうまでもないが,岩倉使節団の米欧歴訪で,大久保利通らが不在になるなか,西郷隆盛を主とする征韓論が起こる。1873年の使節団の帰国とともに,長州人木戸孝允の意見により,公家岩倉具視が上奏するという形で否定されたことから,政変となり,西郷とともに,土佐の板垣退助,肥前の江藤新平,副島種臣など,優れた人材も一緒に下野してしまう(明治六年の政変)。
大久保利通が薩摩の同胞西郷を切ったのは,近代化を定着させるために涙を呑んでのことであったが,大政奉還の動きをつくった土佐藩のシンボルともいえる板垣は,下野すると,自由民権運動という,さらに時代を先取りするような行動を起こし,肥前の江藤新平は司法制度はじめ近代国家の基本設計をし,副島種臣は維新直後の外交で日本の存在を世界に示して一目を置かれるほどの人物であった。要するに,長州主導で薩長土肥のうちの二藩が排除されたのである。岩倉具視の役割を考えてみると,公家と密接につながった大内氏の話そのままで,見ようによっては,明治維新は,一部とはいえ,平安時代の公家支配の復活をも含んでいるといえよう。
そして,佐賀の乱,西南戦争などの内乱,大久保利通の暗殺などを経て,維新体制が確立したのが1881年の,いわゆる明治十四年の政変であるが,生前の大久保の後継指名もあって,長州の伊藤博文が覇権を握り,残っていた肥前の大物大隈重信を追放してしまう。まるで,平安時代の,藤原良房による承和の変をみているようだ。伊藤博文は,長州人としては珍しく,世界的視野を持ち,異なる意見にも耳を傾けるという点で首相に相応しかったといえるが,内閣制度,議会制度ができると,内閣と議会の,要するに,官僚と民間人の争いのなかで,一方的に官僚側に立ち,かつ軍部を押さえる山県有朋の力が次第に強くなっていく。さすがに排除できなかった薩摩については,とりあえず,体よく利用して行くことなるのである。
山県は伊藤よりも年上であったが,人を見る目のある大久保によって伊藤が後継者になったので,その伊藤が暗殺されるや,山県の傍若無人ぶりが露わになってくる。世間では,薩長支配として,常に薩摩とセットにされているが,薩摩藩出身者は,西郷隆盛と大久保利通の狭間でうかつに政治的に動けなかったことに加え,優秀な軍人たちが政治的野心を持たなかったこともあって,たくみに利用され,実質は長州閥のみの支配にされていったといえるだろう。伊藤博文を朝鮮総督に祭り上げ,結果として排除することになったのは,かつての,藤原摂関家内の抗争を思わせる。
近代日本が,長州人支配のもとにあることを確認するため,首相官邸のホームページで歴代総理大臣の在職日数をみてみると,1875(明治18)年12月に内閣が発足して,長州人伊藤博文が総理大臣になって以降,わずかな総理大臣不在の時期を除いて,安倍晋三首相が退陣する2020(令和2)年9月までの52,122日間に,62人の総理大臣が誕生した。そのうち,山口県すなわち長州出身者は,戦前は,伊藤に加えて,山県有朋,桂太郎,寺内正毅,田中義一,戦後は,岸信介,佐藤栄作,安倍晋三と,人数は8人で,13%とすくないが,在職日数は,延べ15,569日と30%を占め,一人当たり平均でほぼ2000日,6年近くになり,これに,藤原氏的政治の復活ということから,近衛秀麿,西園寺公望の公家トップ,皇族の東久邇宮,さらに,実質長州人といわれる菅直人の4人を加えると,在職日数は18,510日で,35.5%にもなる。残りの50人で,33,612日ということは,一人当たり672日で,長州人首相の3分の1に過ぎなくなる。ちなみに,薩長のもう一派,鹿児島県出身の総理大臣は2代目の黒田清隆,4,6代目の松方正義,22代目の山本権兵衛の3人しかおらず,在職日数の平均も678日で,以後は,全く出ていない。これらのことだけでも,長州人がいかに策謀に優れて長期政権をつくってきたか,薩長とはいいながら,薩摩人が権力を握ったことはほとんど無かったことが分かってもらえるだろう。以下,段階に応じて,簡単に整理しておく。
覇権が確立したのは,桂太郎からで,桂自身通算2886日と,安倍晋三に追い越されるまでは1位の長さであり,公家西園寺公望と交替する"桂園内閣"というたくみな方法で続けたことから,両者を一人とみれば,4300日近く,つまり12年近くにもなる。桂,寺内正毅,そして,張作霖爆殺事件爆殺事件を起こし,即位まもない昭和天皇から叱責されて,内閣総辞職,まもなく急死してしまう田中義一まで,いずれも陸軍軍人出身であり,長州人内閣はまた陸軍内閣でもあったといえよう。その結果,国民的人気を背景に登場した,世が世なら,摂関家トップの近衛秀麿は,日中戦争を泥沼化させ,日米開戦への道づくりをしてしまったのである。
大正デモクラシーを謳歌し,社会主義が広がる間,長州支配の陸軍が伸長,山県有朋が大正天皇をバカにし,のちの昭和天皇の妃選定に口を出すなど,天皇をも見下す姿勢が,結局は大戦を招き,国民を悲劇に落とし込んだことは言うまでもない。はじめは,宮内大臣になっていた大久保利通の息子牧野伸顕が抵抗していたが,親英米派として狙われ,二二六事件によって,ついに失脚させられてしまう。そして,近衛文麿首相は,藤原摂関家の筆頭家の出なので,関白が実質国家の宰相だった平安時代の藤原道長,遅くとも,その子の頼通までとすれば,実に,900年ぶりの宰相関白の復活だったといえるだろう。
敗戦直後は,新憲法制定前ではあるが,戦前からの首相選びというわけにもいかず,最初の首相には,皇族の東久邇宮稔彦王がなった。戦前に,満州国のトップ官僚であった岸信介は,敗戦で,A級戦犯になったが,アメリカが,共産主義と戦うことが至上命題になって,手の平を返して釈放されると,1955年,保守合同で,自由民主党が実現する波に乗ったばかりか,国民はじめ誰もが認めた合同後最初の首相石橋湛山が,わずか2か月で,病気のために引退という,思わぬことから,首相の座を射止め,戦後の,長州人内閣の幕を開ける。
長州陸軍による無謀な戦争が,天皇や国民に苛酷な運命をもたらしたにもかかわらず,その反省もないうちに復活した岸首相の姓は,前述したように,百済王族を示すキシそのものであり,クダラ系藤原氏的時代の到来を,これほど象徴する人物はいない。いわば,現代政界の貴種であり,その弟の佐藤栄作,孫の安倍(安倍貞任の末裔というものも加わる)が強かったのも当然だろう。あの平安時代に,天皇制の危機とさえいわれた平将門の乱後,何事もなかったかのように,摂政藤原忠平が復活し,道長の栄華に至ったことを思い起こさせるようだ。
念のため,第2次世界大戦における戦没者数を,都道府県別に集計したものを見てみると(ホームページ「みちのく歴史フォト散歩」),東京大空襲,広島,長崎の原爆という,本土に住んでいるだけでの一般住民の大量の死は別とし,実際の戦闘による死者数で,当時の人口比では,長州の山口県の1.9%を基準に,それよりも多いのが,特別に悲惨な状況に追い込まれた沖縄の21.3%を別格に,多い順に,三重県,香川県の4.4%,福島県の4.1%,佐賀県の4.0%,福井県の3.8%,宮崎県の3.7%,山形県,宮城県の3.6%,山梨県の3.3%,岩手県,長野県の3.2%,鳥取県の2.9%,栃木県,奈良県,高知県,長崎県の2.6%,岡山県の2.5%,群馬県の2.4%,和歌山県,茨城県の2.3%,千葉県の2.2%,岐阜県の2.1%,青森県,新潟県,静岡県の2・0%で,都道府県数で過半になるだけでなく,一見して分かるのは,近代以前から差別的扱いを受けている沖縄はもちろん,戊辰戦争に敗れた東北諸県(福島,山形,宮城,岩手,青森,新潟),維新後に排除された土肥(佐賀,高知,長崎),そして,徳川御三家(和歌山,茨城,静岡)であり,やはり,意図的に,より厳しい戦線に送られたと考えて良さそうだ。
岸首相と同じ頃,全く反対側の共産党議員だった野坂参三も,生粋の長州人で,1955年に,中国から復帰して,共産党第一書記になっていて,保革対決のなか,国民を欺いたまま,熱狂的支持を得続けている。
安保闘争後の,国民の政治離れ,経済優先ムードのなか,政界有力者を互いに戦わせる人事を駆使,クダラ系藤原氏そのままのような,陰謀による長期政権で,東京オリンピックから大阪万博までの高度成長を実現させた佐藤栄作は2798日(8年近く),そして,戦う敵すらいなくなった安倍晋三は,ついに,桂太郎を超える3188日という最長記録になったのである。その安倍の長期政権を実現させることになったのは,小沢一郎のしかけによる小選挙区制の導入で,あり得なかったと思えた民主党政権が実現したものの,準長州人の菅直人が,国民のためにではなく,自らの権力維持にしか関心がない,まさに長州人的なところが露わになって破綻したことによるのである。
戦後の自民党政治の政策の大半は,庶民出身の稀有の政治家田中角栄によるものであり,佐藤栄作後,後継になると思われていた福田赳夫が敗れ,田中角栄が首相になるや,いわゆるエスタブリッシュ勢力は,アメリカとともに,金権問題で退場させ,それでも力足りず,ロッキード事件で失脚させたが,優れた人材多くを見出し,多くの弟子を教育していた田中の勢力はその後も続く。いわば,藤原氏が菅原道真を追放したようなもので,その祟りはずっと続いているようだ。その後も,陰謀によって,少しずつ田中系の有能な政治家を排除してきたが,田中直系の小沢一郎が,ついに,民主党政権を実現させるも,その政権のダメぶりが露わになると,止めを刺すように,残った人材すべてを排除,ライバルがいなくなって,安倍長期政権が実現した。そのダメぶりを示した張本人が,準長州人といえる菅直人であったのだから,なんとも言いようがない。
安倍政権の傲慢ぶりにアイソをつかしている人は多いのに,何故か居座り続けていること,彼自らが長州人であることを誇りにし,明治維新が,あたかも長州人にのみ成し遂げられたように言っていることなどを見ていると,長州人とは一体何者なのかを考えざるを得ない。お友達,つまり自分にとって都合の良い人は何が何でも大事にし,少しでも反対なら,すぐにでも排除,国民はおろか,天皇をも見下す姿勢,まさに「桜を見る会」に象徴される人間性は何処から生まれてきたのだろうか。安倍晋三の傲慢さは,彼固有の性格に由来するのではなく,長州人共通の性格であることを示すため,野党の側の代表的長州人を挙げて見よう。
そもそも,第一次安倍政権が崩壊したことを端緒に,民主党が政権を握るという二大政党定着への足掛かりができたというのに,菅直人が党首になるや,原発事故への対処だけでなく,消費税アップなどで,国民を裏切り,その結果,民主党が自滅したことが,現在の安倍政権を生んだといえる。安倍首相は,臆面もなく,'悪夢の民主党時代'と言っているが,その菅直人も,父の勤務地の山口県宇部で生まれ育っているから,半ば長州人で,彼の政界での出世を見ると,社会党のシンボル土井たか子に付き添う形で登場,草の根風に振舞って国民の人気を得ていたが,小沢一郎のお蔭で民主党ができ,最初は,鳩山由紀夫というお坊ちゃんを立てて政権を握ったとたん,若手を利用して,まず小沢一郎を,続けて,鳩山由紀夫を平気で斬ってしまうという冷たさで,その結果が,どうしようもない野党の状況を招いているのに,何の反省もない。
さらに思い出すのは,前項の繰り返しになるが,萩の商家に生まれた正真正銘の長州人,共産党の野坂参三で,100歳という人生の最後の最後になって明らかになったのは,戦前に,ソ連で日本人の同胞を裏切って刑死させ,戦後は,仲間を裏切り,国民を騙して,圧倒的人気を得たことなど,やはり長州人の体質そのもののように見える。
安倍長期政権を可能にした最大の理由が,強力なライバルがいなくなったことにあるのは,共通認識と思うが,確かに,気配りの竹下登元総理が死去して以降,自民党内でも,それなりに見識や力を持った野中務,亀井静香,鈴木宗男はじめ,多くの人たちが,極端な場合は犯罪のでっち上げまで含めて,排除されたり,牙を抜かれたりしてきた。
明治維新において,当初は朝敵だったものが,薩摩を利用して維新を達成するや,天皇を支配するに至り,吉田松陰をシンボルに,長州の神社をルーツにする靖国神社を利用,国家を支配する存在になる。無謀な大戦によって国民に犠牲を強いたにもかかわらず,岸信介首相によって復活,今や,その孫たる安倍首相の独裁といった状況になり,モリカケ問題はもちろん,世界遺産になった近代産業遺産も,本来なら九州のみであったところ,産業には関係のない松陰の存在を理由に,山口県までゴリ押しで入れてしまう。安倍首相に限らず,かつて共産党委員長として絶大な人気を誇った野坂参三,近い所では,民主党党首だった菅直人など,長州出身の人たちは,自らの権力を振るうためには,同志や国民をも平気で裏切るという点で共通しているのは否定しようがないだろう。いずれにしても,戦後も,長州の,あるいは長州が差配できる首相を戴いてきたことからでも,世界からは,日本国民が本当に反省しているとは見えなくてもやむを得ないだろう。
全くの付けたしではあるが,近現代の芸術分野を象徴する映画や漫画のルーツを辿ると,平安時代末の絵巻物であり,振り返れば,武家政権の登場は,天皇家がクダラ系藤原氏に支配されてしまったことにもよるのであり,その後の武家政権時代を通じて,朝廷との関係がぎくしゃくするのも当然であったといえるが,その底流で,没落した秦氏由来の芸能民との関係が,後白河法皇の白拍子や今様,足利時代の能役者や義政の善阿弥起用から,織豊政権の茶人,徳川時代の将棋・囲碁の棋士など闘いの芸能,さらに家康の本阿弥優遇など,連綿と続いていることも,藤原氏を除いた部分での,天皇家との関係を示唆するものではないかと思われる。
この章TOPへ
ページTOPへ
歴代の天皇や記紀に登場する神については,それぞれ該当する項で,断片的に取り上げてきたが,天武・持統天皇と藤原不比等によって編纂されたものが元になり,漢風諡号を撰進した淡海三船は桓武天皇の時代に没していることから,新天皇の誕生を機会に,改めて,天皇の名前や日本神話の構成を見直してみるべく,一覧で見ることのできる図を作成したところ,かなり,簡潔に証明できるものになった。ついでに,元号についても,始まりは「大化」であるが,定着したのは,持統天皇時代の「大宝」なので,「令和」になったのを機会に,改めて,見直してみたい。
中大兄皇子(天智天皇)の娘で,父の弟の大海人皇子の妃になった後の持統天皇は,父が死に際して,子の大友皇子(異母弟)に皇位を継がせようとしたのに対して,夫が壬申の乱を起こすと,それを支えて勝利に導き,夫が天武天皇として即位すると,皇后になる。天武天皇は,律令制の確立をはじめ,日本国としての統一を図るべく,神話の蒐集編纂と,初の本格的な都・藤原京の建設にとりかかるが,志半ばで倒れてしまう。皇后であった持統は,子の草壁皇子が幼かったことから,自ら天皇になろうとするが,夫はいわば皇位の簒奪者で,天智天皇の皇子も遺っていて,群臣の意見をまとめることができないため,自ら皇位に就く正統性を,神から授かったものにすべく,天皇が天照大神の子孫であると,神話を再構成し,儀式を整えて,突破する。それまでの,天皇は,群臣らの総意に基づいて選ばれていたので,平成や令和になっての新天皇にみるような,いわゆる万世一系の,神がかった即位というものは,まさに,持統天皇によって始められたのである。
我々はまた,戦前なら,神武天皇から歴代の天皇の名を諳んじ,戦後は,戦争への反省もあって,古い天皇の存在に疑いを抱くようになったとはいえ,応神天皇以降の天皇の名など,かなりの天皇の名を,歴史的な事件とも対応させて,自然に覚えるようになっている。ところが,このように漢字2文字に天皇をつけて呼ぶ,いわゆる漢風諡号というものが始まったのは,聖武天皇の娘の孝謙天皇(重祚して称徳天皇)の時代に,その命で,当時一流の文人官僚だった大友皇子の曽孫・淡海三船が,神武天皇から聖武天皇まで一括撰進したものなのである。これらの名を誰がいつつけたのか何の疑いも持たずに,歴代天皇の系図などが作られ,かなり自然に名を覚えてしまうのは,淡海三船の名づけ方が,それほど的確で優れたものであったということだろう。彼は,桓武天皇の代にもなお要職についていたが,その在位中に死去してしまうので,桓武天皇以後の天皇の名は,淡海三船に倣ってつけられていくことになった。
そこで,天照大神からの皇祖神,神武天皇から桓武天皇に至る歴代天皇のつながりがどのようになっているか,本文中で述べて来たことに対応してみることができるよう,以下に,示す。
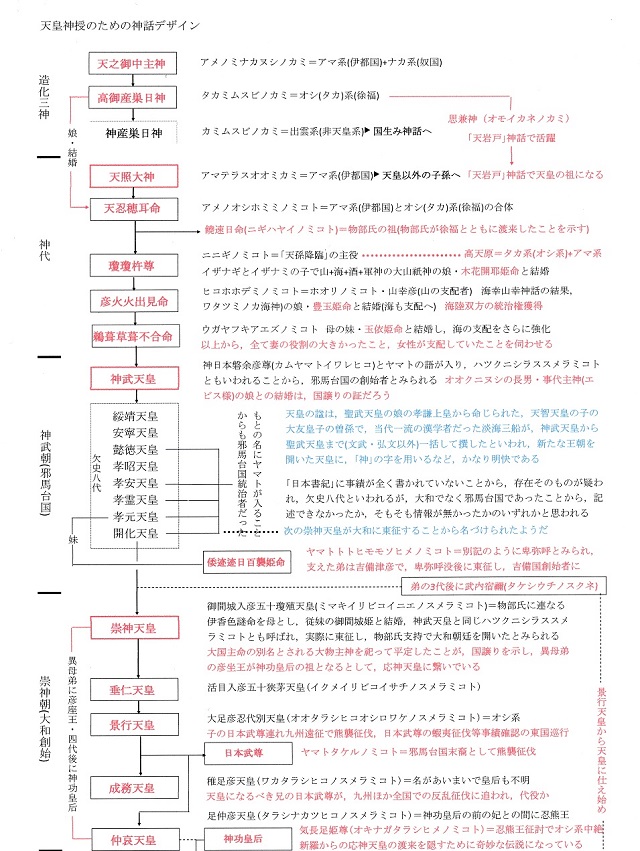
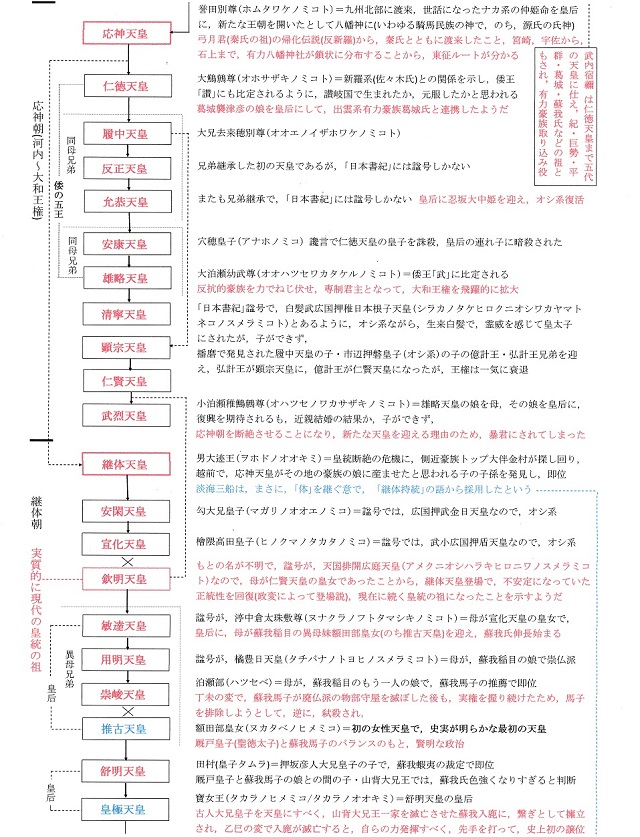

天皇を戴いて統治するという仕組みが藤原氏によって確立したことに異論は無いと思われる。その張本人たる藤原不比等は,持統天皇を支えて,天皇神授への神話の再構成から,藤原京の建設,大宝律令の完成まで貢献し,父の中臣鎌足が天智天皇から与えられた藤原姓を,自らの家族に限り,他家は中臣姓に戻すことに成功する。持統天皇が死去すると,記紀の編纂を利用して,一族の祖となる神を皇族につながる位置に収めるなどして,権威を高めて覇権を獲得,自らは死去してしまうが,娘の光明子が民間出身としては初の(聖武天皇の)皇后になるに至り,子孫が天皇を戴いて国を支配する道を開いたのである。
とはいっても,彼がなした改変はほんの一部でしかなく,そもそもの記紀神話は,各地に伝えられた話をまとめたものから編纂されていて,八百万の神々の体系がどのようにつくられているかを,最近出版されたばかりの,戸部民夫著「日本の神様の"家系図"」を参考に分析したところ,渡来した徐福集団が,邪馬台国を建設していく過程で,様々な氏族との融和を図るべく,道教の体系をベースに語り始め,崇神天皇の東征による国譲りの諸問題を経て,応神天皇とともに渡来した(徐福が仕えた秦の始皇帝家臣の末裔)秦氏が,神社の創建とあわせて詳細に固めていった様子がうかがえる。
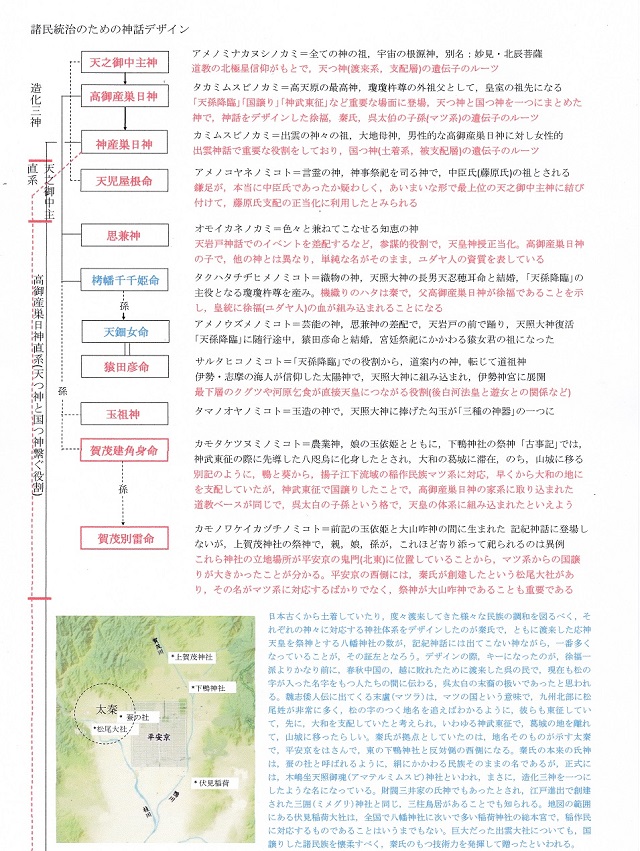
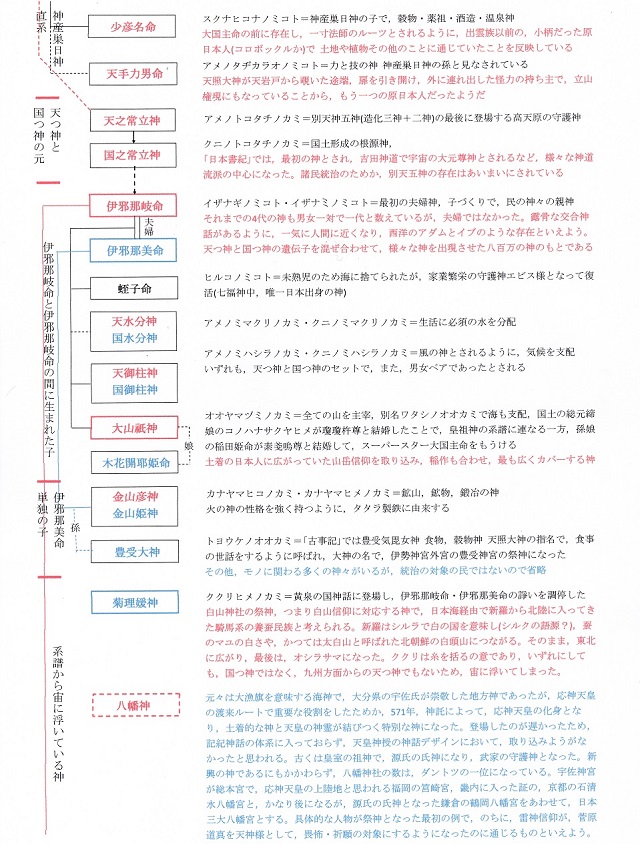
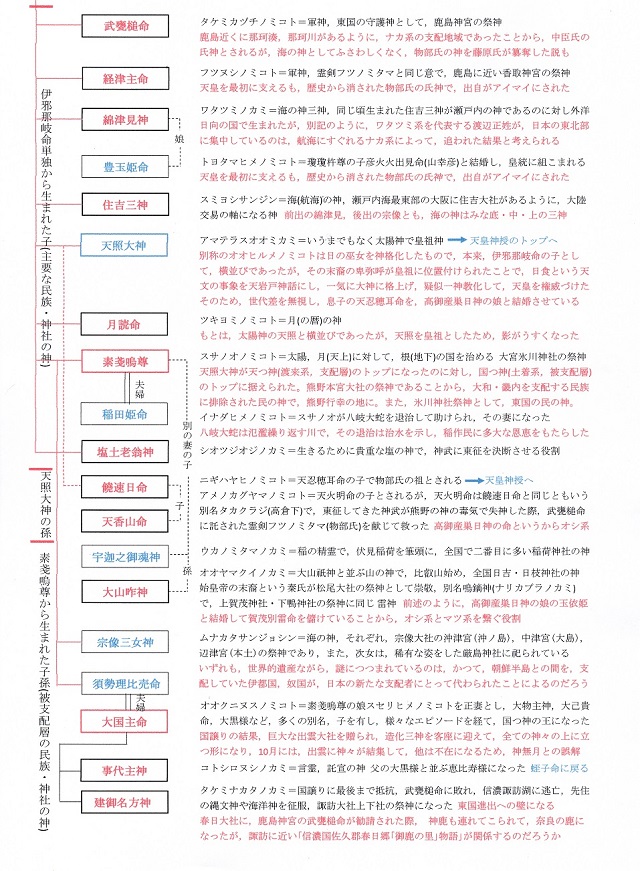
明治維新後の初めての(異例な)天皇の生前退位によって,新天皇が即位し,元号が「令和」に変わった。「令和」の語そのものも話題になったが,この機会に,天皇の交替と元号の変更との関係を振り返ってみるべく,詳細な対照年表を作成してみたところ,そこからも,日本史の大きな状況を捉えることができる。
よく知られているように,元号は中国起源のもので,その昔,朝貢国であった韓国やベトナムなど広く使われていたが,近代に入ると,皇帝や王制の廃止とともに,本家の中国,台湾も含めて,使われなくなり,今や,天皇制の続く日本でのみ使われるものになってしまった。それほど,元号と天皇制とは一体のもので,日本文明の特徴の一つになってしまっているため,廃止論が出ても広がらないのだろう。
したがって,天皇の交替の際に元号を変更するというのが,原則であるのはもちろんであるが,それが法制度的に固定化されたのは,明治維新後のことで,かつては,天皇の権威を示すため,あるいは,利用するため,瑞兆や凶事等があった際にも,簡単に,元号が変更された。元号が頻繁に変更され,天皇すら交替が多くなるのは,その時代が,何等かの意味で,不安定であったことを示し,逆に,元号の変更が少ないほど,さらに,天皇の交替が少ないほど,その時代が,天皇の権威によって安定的に保たれていたことを示しているといえるだろう。
日本における元号の採用は「大化の改新」で有名な「大化」をもって始まるとされている。「大化の改新」そのものについては,その後の研究によって,「改新」そのものの存在が疑われ,時代のエポックとしては,「乙巳の変」というのが一般的になっているが,暦という人々の生活を制約するものに,初めて元号を採用したこと,つまり中国の方式を取り入れたという点に限ってみれば,日本史上の大きなエポックであったことは確だろう。
しかしながら,「大化」の次の「白雉」の後は,「大宝律令」で有名な「大宝」が登場するまで元号は無かった,つまり,天智,天武,持統天皇の間は,中国方式を取り入れることに抵抗が強かったか,躊躇したか,意識されなかったのか,いずれにしても,「大宝律令」という中国の法制度の整備とセットになって,ようやく定着したということになる。つけくわえれば,「大化の改新」の際には,法制度の整備が無かった,つまり「改新」はなかったということになるのではないだろうか。
持統天皇の没後,覇権を握った藤原不比等から,転変を経て,天皇制の最大の危機になった道鏡を,宇佐八幡宮の神託によって追放するまでの,いわゆる奈良時代は,「和銅」や「養老」など,主として瑞兆による元号や,孝謙(称徳)天皇時代に限られる四文字元号があったこと,どうも,新たな文化たる元号を楽しんでつけていたように見える。そのなかで,聖武天皇の在位に対応して「天平」が長く続いたことから,「天平文化」というように,その時代の文化を元号で一括表現できる利点も生まれ,のちの江戸時代の「元禄文化」「天明文化」「化政(文化・文政)文化」というように,気楽に使うようにもなっている。
宇佐八幡宮の神託で,新たに即位することになったのは,八親等も離れた光仁天皇で,その子桓武天皇へのつなぎの役割をし,さらに,その子の嵯峨天皇が主役の,いわゆる大天皇の時代(平安初期)になる。個々の天皇の寿命は短いながらも,「延暦」「弘仁」など,明治維新後のように,天皇交替と元号変更が,1対1で対応しているので,天皇の権威が強かったことも示される。
そして,再び藤原氏が覇権を握ることになるのが,嵯峨上皇崩御とともに起こした「承和の変」で,長かった承和の時代が終わるとともに,元号が立て続けに変更されることから,確かに,政治的危機があったことが伺える。その後は,「貞観」「延喜」など,時代を象徴する元号を代表に,天皇交替と元号変更がほぼ1対1に対応しているので,藤原摂関が他の氏を抑えて,それなりの安定を現出していたということになろう。
「承平・天慶の乱」,すなわち,平将門の乱と藤原純友の乱という天皇制をゆるがす大事件が起きて,平安時代も後半に入るのであるが,今度は,藤原一族のなかでの覇権争いから始り,東北地方での反乱や,仏教の末法思想も重なって,人心が不安定になったのを示すかのように,元号が頻繁に変更される時代が続く。白河上皇による本格的な院政に入ると,権威の異常化を示すように,元号の変更はさらに頻繁になり,そのまま,平家の登場から,鎌倉時代の武家政権へとなだれ込み,天皇の交替も,幕府の思惑によって,頻繁になってきて,天皇にとっては,元号変更でしか権威を示せなくなったこともあって,超頻繁といった状況になる。
執権北条時頼・時宗時代は,支配力が強かったこともあって,元号変更はやや減るが,その後は,後醍醐天皇が登場して鎌倉幕府が滅亡するまで,元号変更は超頻繁になり,時代の不安定さが強く示される。南北朝に入って,二つの元号が併存するという異常事態が続いた後,足利義満の力で南北朝が統一され,その子の足利義持もなお力をもっていたことから,元号「応永」が長く続くが,「嘉吉の変」から「応仁の乱」に至る,室町幕府崩壊のプロセスにそのまま対応するように,長く在位した,後花園天皇は,光仁天皇以来の八親等も離れた皇族から即位したため,自らの権威を高めるべく,頻繁に元号変更して権威を回復,「中興の英主」と評されるに至った。
その後は,戦国時代から江戸時代全般にかけて,天皇交替は,在位期間もそれなりに長く安定的になるが,天皇が完全に影のような存在になってしまったこと,将軍側からの圧力を受けるまでもない存在として,元号変更の頻度も少なくなったといえるのだろう。そのなかで,江戸幕府に抵抗して権威を発揮しようとした後水尾天皇が,結局,幕府の圧力に屈して譲位してしまい,後水尾上皇がなお存命中に登場した霊元天皇が再び権威を回復しようとするまでの期間と,桜町天皇時代,そして,維新前夜の孝明天皇時代に,一時的に元号が頻繁に変更されることからも,やはり,時代の不安定さを示すものになっている。
明治維新後の一天皇一元号という定めのもとでは,元号変更の頻度等から時代状況を推量することはできなくなってしまうのである。
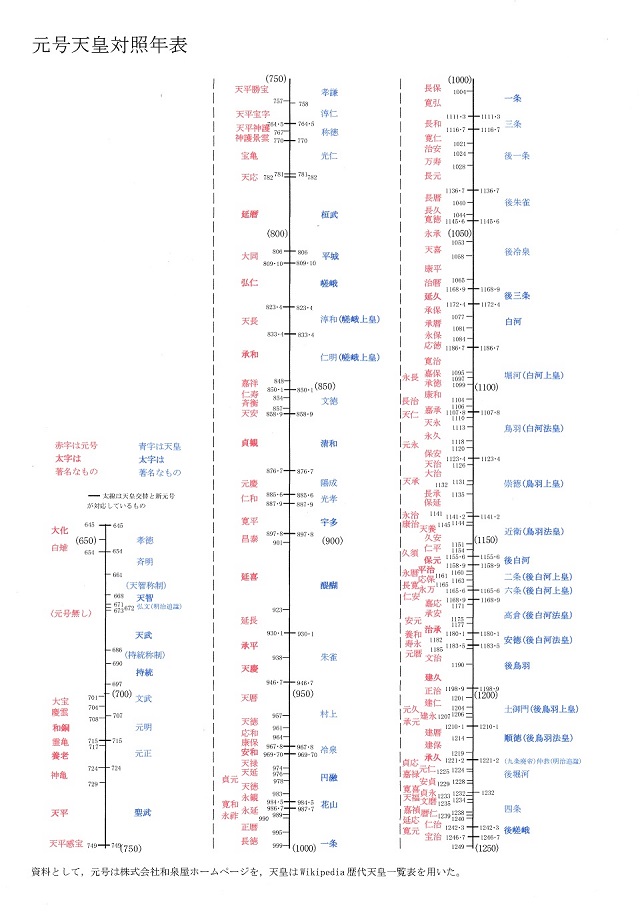

この章TOPへ
ページTOPへ
はじめに
いわゆる天皇制によって,世界史の上では異常な,一つの王朝が続く日本であるが,その統治の変遷をみると,実に,複雑な道を歩んできた。
簡単にいえばと,日本列島が,世界地理上の位置から,多様な民族が渡来しながら,出て行くことは極めて少ないために,世界有数の多民族の国になり,狭い国土故,混血も進んで,いわゆる日本人という互いに似た姿になっているのである。仮に,世界中の人々が混血すると,顕性遺伝(かつて優性遺伝といわれた)によって,皆,今の日本人のようになってしまうそうだ。
しかし,良く知られているメンデルの法則によって,混血というのは,完全に混ざり合うのではなく,受け継いだ遺伝子のいずれかが,一定の確率で発現するのであり,いわゆる騎馬民族,海洋民族,農耕民族といった大枠で分けただけでも,それぞれの人物に,いずれかの特徴が強くみられることになる。とくに,特徴が強く現れる男系の遺伝子は,代々発現する確率も高く,民族を反映した姓の人たちには,その民族の特徴を表す人物が多く現れるといって良いだろう。
ノーベル賞の受賞者の多いこと,最近の,大谷祥平はじめ,様々なスポーツ,建築,美術,音楽など,ほとんどあらゆる分野で,世界一流といわれるような人物が登場するのは,このように,様々な民族が混ざり合い,そのいずれかの特化した遺伝子が発現していると考えるのが自然だろう。
国土の面積に比して,多種大量に渡来した民族が,互いに抗争することなく生活して行くために,統合のシンボルとして天皇というものを考えだし,その天皇を擁立する形で実権を振るう支配層(平安時代の藤原氏公家から鎌倉時代以降の将軍武家,維新後の官僚)が,自らの権力が隅々にまで及ぼすような仕組みをつくりだし,それが,いわゆる天皇制であり,そのことがどのようになされてきたのか,「古事記」「日本書紀」の,いわゆる日本神話にも何かしらの真実が隠されていることを前提に,さまざまな事実も踏まえつつ,年代を追って,少しずつ暴いて行くのが,本講義の趣旨である。
最近知られるようになったことであるが,日本が,世界的に見ても豊かな国に属するにもかかわらず,日本人は,将来を不安に思う人,自分を不幸だと思う人が際立って多いのは,その原因が,人を落ち着かせるセロトニンの分泌が非常に少なくなるように進化したことによっており,そのように,進化したのが,水田稲作という手間と時間のかかる農業に対して,台風その他の自然災害の多く,それに対応すべく,いつも不安に思うようになったらしい。そうであれば,天皇制というのは,国民の不安を和らげる精神的な装置として,極めて有効なものであり,そのことによって続いていると考えても良いだろう。
ところで,日本人に限らず世界各地でのDNA分析によるルーツを探るにあたっては,前提とすべき大きな問題があると思われる。というのは,支配する側の民族は,日本の場合でも,天皇家にしろ,公家にしろ,大名にしろ,いずれも支配される側から女性を娶って,大量の子孫を残すことに努めてきたからで,現在の日本人のDNAを分析すれば,かなり支配側の民族のものに偏っているはずであり,以下に述べる統治の変遷に纏わる民族との関係を明らかにするようなDNA分析を期待したい。
本来ならば,本文を読み終えてからにしたいところではあるが,自分には,どんな民族的遺伝子の特性が現れているかを,知りたい人のために,とりあえず,まとめてあるものを,コラムに紹介しておく。本文を読みながらでも,参照したり,思い出して貰うのが良いだろう。⇒コラム「遺伝適性を知るための民族ルーツ論」
目次
序論:統治が始まる以前の状態~いわゆる縄文時代
----第1話:最古層の日本人~氷河期に形成された環太平洋民族の核
----第2話:いわゆる縄文文化を担った北方アジア民族の南下~環日本海民族の形成
----第3話:海洋民族ワダツミ族の形成と,縄文人最後の砦となった信濃
第1論:いわゆる弥生人の渡来で統治(国)が始まる~九州北部の小国家群
----第1話:照葉樹林帯の民族クメール人による狗奴国(クマ系)
----第2話:黄海から渡来した航海民族による奴の国(ナカ系)
----第3話:中国春秋時代の呉人によって形成された末盧国(マツ系)
第2論:九州北部小国家群を支配した二つの強国~伊都国と邪馬台国
----第1話:大陸からの認知を受け,諸国連合の王を務めた伊都国(アマ系に支えられたイト系)
----第2話:小国家群から大和国家への契機となる,秦帝国からの徐福の渡来(オシ系)
----第3話:徐福(の子孫)によって,アマ系戴くオシ系の邪馬台国が建国される~神武皇統
第3論:オシ系の神武(実は崇神)東征による大和国家形成~崇神皇統
----第1話:徐福に従って渡来した技術者集団物部氏の東進(フヨ系)
----第2話:オシ系と別れて東進し,大和国家の支配に微妙に関わることになる海部・尾張氏(アマ系)
----第3話:アマ系と別れたオシ系の神武(実は崇神)東征によって大和朝廷が始まる
第4論:新羅から渡来した秦氏の長による応神皇統~古墳時代
----第1話:日本に影響を及ぼす朝鮮半島の三国時代
----第2話:秦帝国からの繋がりによる,オシ系からハタ系への王朝交替
----第3話:秦氏による神社統治システムの構築~諸民族支配の方法
第5論:継体天皇を契機に,蘇我氏,藤原氏が登場し,天皇制が確立~古代
----第1話:推古天皇・聖徳太子を戴く蘇我馬子による日本統治のプロトタイプ
----第2話:中臣鎌足と天智天皇,天武・持統天皇,そして藤原不比等による,天皇神話の確立
----第3話:クダラ系藤原氏の(陰謀によるライバル追放の)長期政権~平安時代
第6論:平将門の乱を契機に登場した,坂東武家三流の盛衰~平安時代後半
----第1話:平清盛を生み出し,武家政権への端緒となる桓武平氏(イト系)
----第2話:源頼朝を生み出し,武家政権を確立した清和源氏(シラギ系)
----第3話:将門の乱を制して東国武士の祖となった藤原秀郷から,奥州藤原氏へ(秀郷流)
第7論:天皇の権威を背景とする武家政権時代~中世
----第1話:天皇戴くクダラ系藤原氏に倣い,将軍を戴いて覇権を握ったイト系北条氏~鎌倉時代
----第2話:シラギ系足利氏による武家政権の建て直しから,公武一体化で破綻するまで~室町時代
----第3話:大内氏が将軍代役になるも,下克上で,武家政権の秩序が崩壊~戦国時代
第8論:それまで支配とは無縁だった町人が活躍する時代~近世
----第1話:大航海時代に対応,旧体制を破壊して新たな時代の幕を開けた織田信長(イト系)
----第2話:マツ系による国の奪還~露払いとしての豊臣秀吉
----第3話:徳川家康が覇権を握り,朝廷をも超える全国支配を確立(崇神東征時の国譲りの奪還)
第9論:長州支配で,クダラ的藤原政治が復活する~近現代
----第1話:権威までも失った天皇家の長い抵抗が,明治維新につながる
----第2話:長州人を軸にしてみた維新前後(大塩平八郎の乱から,明治14年の政変まで)
----第3話:山県有朋による陰謀型長州人の覇権の確立
特論:天皇制の枠組~諡号と神話と元号と
----第1話:天皇神授と皇位継承
----第2話:記紀神話と諸民統合
----第3話:天皇交替と元号変更
序論:統治が始まる以前の状態~いわゆる縄文時代
はじめに,統治の前から存在した日本人,いわゆる縄文人について見ておく。
第1話:最古層の日本人~氷河期に形成された環太平洋民族の核
近年,DNAの研究が進むとともに,原日本人はバイカル湖沿岸にいたモンゴロイドが,数万年前に,西方からのより新しい人類に押される形で,氷河期で陸続きだった(日本海は湖状)朝鮮や樺太から日本列島に入ってきたことがほとんど確実になっている。その際,そのモンゴロイドの一部は,人類大移動の一環として,やはり陸続きであったベーリング海峡を通って,アメリカ大陸に渡り,1万年前までには南アメリカの最南端にまで達した,いわゆるアメリカ・インディアンやインディオになったわけで,最近では,日本人の持つ文化と彼らの文化の共通するところに注目が集まり始めている。近年発見された,南米ペルーのカラル遺跡は,アンデス文明の原点で,5000年前,まさに,四大文明といわれるメソポタミア,インダス,エジプト,黄河と同時期に発展をしたものであり,アメリカ・インディアンなる人たちが,縄文人と同じであるとすれば,縄文文明もまた,かなりのハイレベルにあったといえる。実際,縄文土器は,その時代では,世界の最先端をいくものであったようだ。
崎谷満の遺伝子研究によると,人類は,いわゆる出アフリカ後,まずメラネシア型が分岐,アフリカで中央アフリカ型が分岐,残りはコスモポリタン型になり,その中で,早くに分岐したアイヌクラスターの人たちが,次に分岐した極東クラスター(サハリンのニブフ族型でアメリカインディアンへも展開)に押し出される形で,北海道から東日本に展開して日本列島固有民族になる一方,極東クラスターの人たちは,朝鮮から九州へ南下したが,次に分岐した九州・西日本型(琉球も含む)によって,さらに南に押し出され,鹿児島から琉球に孤立する固有の民族になったという。したがって,原日本人は,以上の九州・西日本型,アイヌクラスター,極東クラスターの三つで構成され,そのまま,(弥生人とみなされてきた)西日本人型,(縄文人と見なされてきた)東日本人型,琉球人型の違いに対応することになる。おって詳述することになるが,大和政権ができた頃には,現在の岐阜県や長野県あたりで東西日本人が衝突,その後,西日本人型が次第に東上・北上して行くのが日本人史の骨格になっており,南方に押されて,これ以上行き先の無い琉球人は今なお苦難の場に置かれてしまっているのである。
篠田謙一の研究によって,日本人集団の成立を整理してみても,まず,Y染色体の最も古い層(D2)が流入して,大陸に近い九州という核が独立,その影響を受ける西日本に対し,影響を受けない東日本に分かれ(縄文土器は東日本のもので,西日本は非縄文),その境目は,前述と同様,長野県あたり(大和王朝成立時点では伊吹山が東西日本の境界と思われる)で,北方から先に流入して定着した流入民族は,九州から東征した大和王朝の最大の敵だったということになる。また,西北九州の海洋性漁労文化は朝鮮半島南部にも広がっていたので,氷河期のもとではつながっていた,日本列島と朝鮮半島はかなりの面で一体であったというのも当然であろう。二番目のC1層は日本列島に固有で太平洋岸に集中,最後のO層が稲作やいわゆる照葉樹林文化をもたらし,その結果,稲作の北九州と漁労の西九州という構図が生まれたということである。
最近出版され,もっとも簡潔にまとめられた斎藤成也(国立遺伝学研究所)「日本人の源流」をみておくと,永年懸案だったアイヌ人については,アイヌ人が縄文人そのものの末裔ではなく,オキナワ人とのの共通性が証明されたという。つまり縄文人以降最初に流入してきた人たちで,縄文人との混血があってその残滓を今に残しているのだが,その後に流入してきたいわゆる弥生人によって,列島の北方と南方に押し出されたということらしい。その他のいわゆるヤマト人は,その後数千年の間に大陸から流入してきた人たちの混血によって形成され,現在では,朝鮮人を除く大陸の人たちとはかなり遠い存在になってしまったという。もちろん,アイヌ人,オキナワ人との混血もあるので,この四つの民族は連続しているともいえ,冒頭で述べたことを証明するものにもなっている。
かつては,柳田国男の「海上の道」などに見られたように,日本人のルーツは黒潮に乗ってきた南方の民族だいうのが分かりやすかったこともあって,固定観念のようになっていたが,そもそも黒潮のもとになる太平洋の赤道近くに,遺伝子からみて日本人の母体となるような民族はおらず,東南アジア方面を見ても,台湾と八重山列島の間は距離的には近いものの動植物相も含めて強い分断線になっていることも知られている。近年明らかになってきたことであるが,トンガやフィジーを経て,最終的にハワイやイースター島に至ったポリネシア人の出発地が台湾だということ,つまり南方から民族が来たのとは正反対の流れであったということなのだ。
ロイ・アンドリュー・ミラーによる古日本語の解析でも,モンゴル,ツングース,チュルクなど,バイカル湖周辺の民族の言語たるアルタイ系に近いことが判明しつつあり,松本克己「世界言語のなかの日本語―日本語系統論の新たな地平」によれば,朝鮮語やアイヌ語・ギリヤーク語という環日本海言語圏を形成する言語が,アメリカ・インディアンやインディオなどの言語のでき方と共通する環太平洋言語圏のひとつの核であったという極めて納得しやすい説も登場している。環太平洋言語圏という語が示すように,太平洋岸を海岸伝いに展開したアメリカ・インディアンやインディオと同系であるが,北方のエスキモーなどは,シベリアの内陸部から,陸路で展開した全く別の語族になるという。いずれにしても,かつては,日本列島の沖縄から北海道,樺太に加え,朝鮮半島までが地域として一体であったといえるが,現在の朝鮮語と日本語がほとんど関係無い言語のように見えるようになってしまったのは,大陸と日本列島のつながりが早くに切れたため,それぞれ独自の発展をしてきたためということのようだ。
日本人のベースに,いわゆるアメリカ・インディアン,インディオとつながるところがあると思わせるのは,インカ帝国の名残のあるペルーで,あらゆるところに神が宿るという意識,それ以上に,人工物にまで人格を感じる,例えば,コップを落した時,「コップが自ら落ちた」というのと同じようなところが,日本人にもあって,近代になって登場した機械までも人に例えることがあることにも通じるものであろう。
余談であるが,DNAからみると,漢民族は最も新しく分岐した層で,中国大陸から他の層を追い出して行ったため,現在の中国人の構成はきわめて単純になってしまっているようだ。
紀元前1500年から1000年頃,つまり弥生人渡来以前に,ツングース系の有力な民族ながら国を持たず,中国から侮蔑的にワイ(濊)と呼ばれていた民族が,現在の黒竜江のあたりから,のちの満州あたりを一大拠点にするようになる。それと並行するように,樺太から蝦夷を経て,日本列島を南下し,信濃,越を経て,最後は出雲にまで至ったといわれ,陸奥,出羽も彼らのつけた名に由来するという。船を操ることにも長じたワイ族は,いわゆる日本海交易圏を形成して行き,崇神天皇東征以前から大和の有力氏族の一つになっていたアベ(アエ=阿部,安倍)氏もおそらくこの民族といわれる。大和朝廷の伸長とともに,かつての東北地方に戻って,交易を握って繁栄,その代表の安倍貞任が,前九年の役で征伐されて後,その子宗任ほか一族は伊予方面に移住させられ,その末裔が安倍晋三ということになるの。名字由来ネットでみても,阿部,安倍氏が東北地方と四国西部に多いことが分かる。
あらかじめ述べておくと,大陸側では,同じツングース系の有力な民族で,国造りもできる扶余氏に土地を奪われ,朝鮮半島を南下して新羅人のもとになり,物部氏の出身地ともみなされる扶余氏は,のちに高句麗を建国,さらに分家が百済王族になるのである。>物部氏
第2話:いわゆる縄文文化を担った北方アジア民族の南下~環日本海民族の形成
氷河期には,本州,九州,朝鮮全体が陸続きで,日本海は巨大な湖のようであり,主としてツングース系民族が南下し,最終的には九州,朝鮮両側から,再び出会うことになる。オホーツク海系アイヌ人は,大陸と分離し始めた後に,日本列島にのみ南下した民族であるという。とすれば,アイヌの民族詩ユーカラと,アジア系の民族の国フィンランドのカレワラとが,あまりにも似ているのに驚き,ともに,特別に限られた存在にされてしまった少数民族ではないか,現在の地域でいえば,ヨーロッパのバスク人のようなものだったのではないかと想像してしまうのである。
Wikipediaから,ツングース系民族について確認しておくと,満州からシベリア・極東にかけての北東アジア地域に住み,ツングース語族に属する言語を母語とする諸民族で,北方の,エヴェンキ族,オロチョン族や,南方の満州族が代表的で,日本には,かつてオロッコと呼ばれた民族が流入してきた。習俗からみると,馴鹿の飼養を生業とする民族,遊牧を生業とする民族,農業で生活し定住化した民族に大別されるが,狩猟は,家畜の飼養,農業,馴鹿の飼養に適した地方を除くすべての地方において,主要な生業であり,栗鼠,狐,熊,山猫,黒貂,野猪,鹿など,獲物は主に食用や毛皮の供給源になっている。遺伝子からみると,Y染色体ハプログループのC2系統が高頻度に観察されるが,エヴェンキ族,オロチョン族に比して,満州族はかなり少なく,2000年前には,分岐が始まっていたと考えられる。ツングース系民族による国には,満州語族による粛慎,靺鞨,女真などといわれた国,扶余語族による高句麗などがあり,古代出雲の住民はツングース族で,いわゆる"ズーズー弁"はツングース語起源とする説もある。結論からいえば,日本の歴史との関係で,高句麗を建国した扶余語族が大きな意味を持つことになる。>高句麗
松本克己によると,縄文人は最終氷河期の最寒期の頃,つまり日本列島と周辺の列島,さらにはアメリカ大陸まで陸続きとなった2~3万年前に日本列島に流入し,1万数千年前には千島,アリューシャン列島経由でアメリカ大陸に渡っている。その後,温暖化が始まり,日本列島は大陸と分離,日本語が朝鮮語とかなり異なる方向に進みながら縄文文化が花開く間,中国の長江流域でさまざまな民族による稲作文明が次々と起るが,紀元前4000年頃に,海洋民族と騎馬民族のハイブリッドとして生まれた漢民族(主要な漢字に貝がつくもの,羊がつくものが多いことでも証明され,漢語がいわゆるクレオール語だという指摘には鋭いものがある)によって,次第に押し出され,その一部は山東半島から朝鮮を経由して日本列島に渡っていわゆる弥生人となり(後述するように,主たる民族は呉人),他は南に押し出されて東南アジアの主要民族(主たる民族はベトナムをつくった越人)になっていった。
崎谷満の説で補足すると,日本語の形成については,日本列島が5000年前に大陸から分離したことから,他の言語とのつながりが分からなくなっているが,上記D2層とされる民族が原日本語をもたらしたのは間違いなく,伝播の核となった九州では,当初から西九州語,南九州語,東九州語,北九州語など相互に異なる言語に分かれ,他は,琉球を別として,西日本語,関西語,東日本語にくくることができるということである。西九州語が最も多様性に富むことから,日本語普遍化の核になったと考えられ,後述するように,その主体であった奴の国の人たちの東方への展開に対応して,西九州語が日本語の共通になっていくようである。つけくわえれば,上代奈良語には九州諸語の影響が見られるということで,いわゆる神武東征伝説を裏付けるものになっているともいえよう。
縄文土器が,その当時の世界を見渡した時に,かなり高度な文明であること,のちにアメリカ・インディアンが創生したマヤやインカの文明が石造を基本とした高度なものであることなどから,そもそも技術的能力の高い縄文人がのちの技術立国日本のルーツであり,同じ民族をルーツとする朝鮮の人たちの技術力も,かつての石工や製陶や現代の先端製品まで全てつながっているといえるのではないだろうか。北方由来の縄文人は森林の木の実をはじめ植物を主食に,川や湖の鮭や鱒など淡水魚を栄養源にしており,南方に広がってゆくうちに,沿岸の貝類を食べるようになって,大森貝塚が発見された東京湾岸,とくに世界最大の貝塚密集地帯になっているという千葉市を代表に,多くの貝塚を残している。ついでながら,最近出版された竹倉史人「土偶を読む~130年間解かれなかった縄文神話の謎」は,土偶のもつ不思議な形を,植物祭祀論をもとに,面白いように暴いているが,とくに,貝は,海を森とみなした時,木の実そのものであるという指摘には,目からウロコの落ちる思いがする。
話は飛ぶが,日本人に関心の高い血液型からみると,O型をルーツに,B型,A型と進化してきたといわれ(AB型がさらにその後のものであるのは当然),早くに分離したインディアンはほとんどがO型らしいので,日本人の血液型のO型は縄文人由来といってよいだろう。A型がきわだって多いヨーロッパでも,縁辺部に追いやられたアイルランドなどではO型が多く,より古い民族であったことが知られる。アジアのなかで日本人が際立ってA型が多いのは,後述するように,西アジアで発生したA型人類が,一方では西のヨーロッパに至り,東方で日本に至ったということによると考えられる。余談であるが,民族のDNAで最も新しく分岐してできたといわれる漢民族の血液型はB型が主体になっているらしく,農耕民族としてのじっくりさよりも,B型の人たちは,すぐに新しいものに飛びつくなどという巷の見方が,かなり当たっていることが多いと思われるが如何だろうか。実は,欧米人はほとんど興味を抱いていない,自分の血液型すら知らないそうであるが,どうも,ナチスがA型の民族が優れていると,差別をしたことの歴史へのトラウマが反映しているようだ。⇒コラム「血液型の発現史」
第3話:海洋民族ワダツミ族の形成と,縄文人最後の砦となった信濃
氷河期が終わって温暖化するに従い,大陸から切り離されただけでなく,本州,九州,四国も分離され,居住地が狭められた西日本の縄文人から,最初の海洋民族たるワダツミ族が登場する。ワダというのは,海を示す古代語であり,日本神話では,イザナギの子で,住吉三神とならぶ海の神ワタツミノカミとして位置づけられている。後述するように,大陸から渡来する航海等に優れる海洋民族(ナカ系,イト系,アマ系)に押される形で,ワダツミの名を残す渥美半島を経由し,天竜川を遡って,すでに,縄文人のメッカであった諏訪湖に至り,その北部に安曇野として展開,穂高神社は,穂高山頂にありながら,海の神ワタツミノカミを祀っていて,祭りも全く海洋民族のものになっているのである。有名な諏訪大社の御柱祭りをみれば,船の進水式そのもののようなところがあるのも頷けるが,渡辺姓の分布は,諏訪神社分布と重なっているのである。
2017年,宗像大社が世界遺産に登録されたが,正木晃「宗像大社・古代祭祀の原風景」によると,その原点とされる沖の島は,縄文人にとって理想的な食糧となったニホンアシカの繁殖地であり,荒海の困難を乗り越えてその捕獲を行い,アイヌ人が熊祭りをするように,祭祀を行ったことが,そもそもの始まりということらしく,その担い手こそ,ワダツミ族であったのではないだろうか。そもそも,博多湾の志賀島には海神を祀った志賀海神社が現存し,全国の綿津見神社の総本宮となっており,安曇氏の発祥地とされ,神職は今も阿曇氏が受け継いでいるのである。⇒コラム「ワダツミ族の代表安曇氏」
渡辺姓は,「ワタ」つまり「海」,「ナ」つまり「の」,「ベ」つまり「民」を表すように,そのままワダツミ族の末裔の人たちであるとみられるが,その分布は,関東以北に多く,安曇野を拠点に北方に広がったと考えられる(現在では数少なくなった本来の安曇姓が集中するのは宮城県)。栃木県北部に集中的に多いことが知られるが,内陸県ながら,魚の需要が多いほか,平家の落人など,長野県に類似する海洋民族県(隣の群馬県がその名の通り騎馬民族であるのと対照的で,足利,新田という騎馬民族源氏の名門の地。両県を繋ぐ部分に福田姓が多い)である。マツ系・ナカ系の人たちの東進によって押し出されたより古い海洋民族であることを証明しているといえよう。
公式には,渡辺姓は嵯峨源氏渡辺綱を祖としているが,Wikipediaに記されているように,その後裔が,摂津の渡辺津という旧淀川河口辺の港湾地域を本拠地として,武士団を形成し,瀬戸内海の水軍の棟梁的存在になっているように,本来,海洋民族で,後述する桓武平氏,清和源氏などと同じく,臣籍降下した嵯峨源氏を祖としたに過ぎないと思われる。
この後,後述するように,国譲りした出雲族の代表のような存在であったマツ系の人たちが,ワダツミ族同様,浜松(マツ)から天竜川を遡って諏訪湖に至り,安曇野を控える松(マツ)本を最終的な到達地にすることになる(神話にも,神武に追われた出雲族の一人伊勢津彦が,最終的に信濃に至ったとされている。諏訪神社の神は,タケミナカタノカミであるが,神話の上では,オオクニヌシノミコトの子で国譲りに徹底抗戦し,信濃の諏訪湖に逃れ,先住の神々を征服し,諏訪神になったとされている。>マツ系
戸矢学「諏訪の神 封印された縄文の血祭り」にはずばり,そのルーツは中国の海洋民族呉人(マツ系)であり,ミシャクジ神が呉人信仰に対応する神であると書かれている。そもそも"諏訪(スハ)"という語は,古代支那の特別な階級で用いられた宗教用語で,呉音ではスホウと読み,「神の意志・判断を問い・諮ること」を意味していて,重要な行事の一つにかつて生贄を捧げていた名残があり,また独特な鉄製の祭具"宝鈴"は,銅鐸を起源とするもので,やはり南九州に渡来した呉人が伝えたと考えられるという。その呉人たちは,その後も長く中央に抵抗していたが,邪馬台国の卑弥呼に象徴される銅鏡を祭器とし,東征して大和朝廷を開いた鉄器民族に打ち破られたということになる。
ついでながら,東奈良遺跡から発掘された小さな銅鐸は,銅鐸としては,最も古いものらしいが,その表面には,縄文の紋様が描かれており,銅鐸をもたらしたと考えられる弥生人中国呉地方の民(マツ系)が,縄文人と親しくつきあっていたことが偲ばれ,諏訪の話につながるのはもちろん,いわゆる出雲族とされるのが,マツ系とその背後にいた縄文人全体であったことを思わせる。
また,諏訪には,北方から,ツングース系の有力な民族ワイ族も流入して,トーテムや牛を生贄にするなどの文化ももたらしているから,あらゆる意味で多くの民族が衝突する場になり,最後に,大和朝廷が派遣したヤマトタケルによって平定されたということになるのだろう。国譲りというのは,結局これら異質の民族全てを出雲に封じ込めたということで,出雲と諏訪とが結び付けられ,神無月が出雲では神有月になっているわけである。その後の展開をみると,いわゆる国つ神の出雲族は,東征してきた民族すなわち天つ神に国譲りした全ての民族を表すものとしても,その核になっているのは,マツ系民族とみて良いのではないかと思われる。
さらに,後述するように,海洋民族ナカ系の人たちが,日本海側の信濃川を遡って諏訪湖に至り,その間,まさに,長野というナカ系の地名を残しているように,信濃(長野県)は,海のない県にもかかわらず,海洋民族が集中した特殊な県(陸封された海洋民族の県)になったのである。これらの積み重なって,信濃の地は,西南日本と東北日本を分け,神話上でも特別な位置を占めることになる。>ナカ系
ところで,諏訪大社の,御柱祭りの四本の柱組は,出雲大社を支える四本柱を表現しているようにも思える。関裕二「信濃が語る古代氏族と天皇 善光寺と諏訪大社の謎」によれば,諏訪大社には本殿が無く,南にそびえる守屋山が御神体で,蘇我馬子に敗れた物部守屋のことを表しているらしく,諏訪大社に近くて古い長野の善光寺がなぜあれほど全国からの人を集めるのかというと,その創建が諏訪大社下社の社人によってなされ,神長官守谷氏が物部守屋の末裔で,その怨霊封じのためだったようで,善光寺では本尊が本来のあるべき位置には無く,そこには守屋柱があり,守屋山~諏訪大社~善光寺が南北軸上に並んでいるということである。物部神社の伝説では,宇摩志麻遅命は当初弥彦のあたりに拠点を作ったらしいので,弥彦山が,日本海側の重要なシンボルであったことも伺える。信濃は,あらゆる敗者の集合地でもあったといえよう。
いずれにしても,次項で述べる弥生民族渡来以前の様々な人たちをひっくるめて出雲人と捉え,その人たちが弥生人の支配下に入ったとして,それ以上詮索しないことにしたい。また,後述するように,いずれもユダヤ系あるいはそれに近い,徐福の末裔と,応神朝の頃に大量に渡来した秦氏が,日本全体の統治の仕組みとして,神社体系を確立するわけであるが,その際,この様々な出雲人たちの様々な神まをひっくるめて,出雲大社に祀ったと考えておきたいと思う。
この章TOPへ
ページTOPへ
第1論:いわゆる弥生人の渡来で統治(国)が始まる~九州北部の小国家群
日本列島に国といわれるようなものが,いつ頃登場したのかは分からない。歴史的な文献として,国の名が初めて登場するのが,邪馬台国論争で取り上げられる「魏志倭人伝」で,西暦297年に没する西晋時代の陳寿が,その前の三国時代の歴史書をまとめたうちの「魏書」のなかの一つの巻で,西暦240年前後の日本の諸国について記述しており,古代日本を考える上での基礎文献になっていることは言うまでもない。当時の諸国のなかで抜きんでた存在で,現在の日本国のルーツではないかされる邪馬台国のあった場所についての記述の解釈では,諸説紛々ではあったが,ようやく北九州説に定着しつつあり,朝鮮半島から邪馬台国に到着するまでに登場する国について,一番目の狗邪韓国が現在の朝鮮半島内に,伊都国が現在の福岡県の糸島周りに,末盧国が現在の松浦周りにあったこと,そして,奴の国が玄界灘周りに展開していたこと,熊本県周りに狗奴国があったことなどは,おおむね意見が一致していると思われる。そこで,邪馬台国を除く,これらの国の形成について,まず,考えてみよう。
序章で取り上げた斎藤成也は,いわゆる出雲族の末裔とみられる日本海岸の人たちに,DNA上でヤマト人の平均とズレがあることをもとに,大陸からの流入に,大きく四つの波があったという説を提示している。その説をもとに,第1波は,いわゆる照葉樹林文化に対応する民族,つまり(1)のクマ系に対応,第2波は大量の海洋民族で,九州北部から全国に展開し,原日本語を伝えた民族は,(2)ナカ系に対応,第3波は中国南部の稲作民族が大量に流入してきたということなので,(3)マツ系民族に対応するものと考え,以下,順に考察する。最後の第4波は朝鮮半島経由が主体のようなので,その後に渡来し,日本全体を統治することになった民族として,次章で考察することになる。
邪馬臺国周辺図
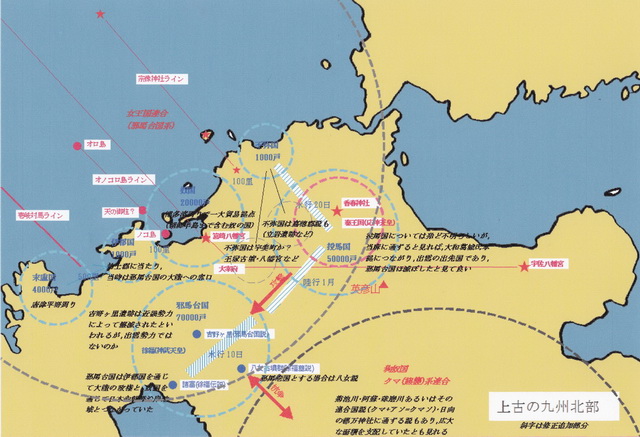
第1話:照葉樹林帯の民族クメール人による狗奴国(クマ系)
イ:神武東征神話の南九州と熊野をつなぐのは,同じ照葉樹林帯
神武東征神話では,出発地が南九州,到達地が熊野ということになっているが,両者に共通するのが,日本列島のなかでは限られた,照葉樹林帯に属していることである。文化人類学者の中尾佐助,佐々木高明らが提唱して以来,日本文化のルーツの一つが照葉樹林帯の民族によるものであると考えられるようになった。
照葉樹林の食料生産の基本は焼き畑農業で,縄文的なレベルであったことから,照葉樹林文化が,日本の縄文文化そのものではなかったかとの誤解が生じたが,前述したように,日本の縄文文化は北方民族によるもので,弥生人の渡来によって,大半は北方に押し戻されるが,遺伝子の解析によって,明らかになったように,沖縄県人は,アイヌ民族とも相通ずる部分が多く,南部に押し出され,取り残された縄文人の末裔ということになるのだろう。
その故郷は中国雲南省周りで,言語から見ると,チベット・ビルマ語族,チワン・トン語族,ミャオ・ヤオ語族,モン・クメール語族の人たちがその担い手であり,その多くは,漢民族の膨張とともに外部に押し出された。このうち,クメール人は,1世紀頃には現在のベトナムで王朝を開くものの,その後に,やはり漢民族に押し出されてベトナムを建国することになる越の民族にも押されて,最終的に,現在のカンボジアに至り,有名なアンコールワットを築いた王朝を開いたように,国をつくる力のあった民族であった。
そのクメール人が,雲南省と同じ照葉樹林帯に含まれる日本の九州南部に渡来して建国したのが狗奴国と考えられるわけで,狗奴(クナ)すなわちクマが,クメール人のクメを表していると考えられる。現在でも,東南アジアで,雲南省に最も近いラオス北部に残るクメール人の言葉が,クム語といわれていることも傍証になろう。ついでながら,カンボジアにはタケオという町があり,酒造や鵜飼なども,雲南省由来の照葉樹林文化という,きわめて古い文化である。国家をつくる力のあったクメール人の石造技術は,のちの熊本城の石垣や通潤橋につながっているとも想像できる。
南九州には,球磨(クマ)という地名があり,熊襲という民族がいたことを見れば,熊野との地名的関係も明らかであり,狗奴(クナ)国は,クマと同じで,それこそ球磨周辺に展開していたことになる。のちに,その北側に,邪馬台国ができたことで,両者の紛争が続き,東征して大和朝廷になった後も,その平定に苦労したのは当然の帰結であったろう。同じように南九州にある地名の大隅の隅は,大隈の隈とも通じて,熊(クマ)に同じであり,炭や墨のスミ,目のクマなど,黒いものに共通する語であるといえる。
ついでながら,国をつくる力のあったもう一つの民族チベット人は,ヒマラヤに阻まれてそれ以上進めず,現在の苦難の道に至ることになってしまっている。
ロ:神武東征を支えた,大伴・久米氏は,狗奴国の民であった
神武東征を警護したとされる大伴氏は,もともとは久米(クメ)氏,まさにクメール人を名乗る氏族であったということから,その末裔とみて良いといえる。その久米氏と同族とされる紀氏が,熊野に定着して,紀の国をつくることになるが,そもそも和歌のもとになった最古の歌が,久米歌といわれ,大伴,紀氏とも,和歌に優れた氏として知られており,照葉樹林文化の特徴の一つの歌垣に直結するものといえるだろう。
ところで,焼き畑の名残を示す地名や人名には,木野,木場,木田などがあるといわれ,徐福伝説にかかわる串木野は,クシフルのクシをも冠していることも含めて代表例になるが,紀氏はキノ氏といわれ,そのまま木野名につながり,まさに,焼き畑民族で,狗奴国の本拠地だったという熊本県菊池郡に木野神社があることも,なるほどといえる。友人だった木野という人物も,その由来を彷彿とさせるところがあった。
余談として,2004年に中国で唐の時代の日本人井真成の墓誌が発見され,玄宗に愛された極めて優秀な人物であったことが記されていて大きな話題になったが,この井氏は,後に井伊直弼らを生む井伊家の祖で,熊本の阿蘇を本拠としおり,邪馬台国が狗奴国から奪った有力な部族の一つであったらしいことを付け加えておく。
日本の神様の体系については,「日本書紀」が完成するに際して,時の権力者藤原不比等が自らの正統性を示すべく変更したとか,神社の体系は,その骨格を秦氏がつくったなどと言われるが,いずれにしても,渡来してきた諸民族の,拠って立つ所を何らかの形で留めていると考えて良いだろう。その全体像については,終章にまとめたものを掲載しておき,それぞれ民族の神様や神社については,その項ごとに,適宜述べることとするが,全国に展開するものとして,その第一号になるのが,クマ系に対応する熊野神社ということになる。>神様の家系図
熊野神社は,総数としては,稲荷神社や八幡神社からみれば一桁少ないとはいえ,全国に3000を超え,その総本山が,神武東征に際して上陸地点になった現在の新宮市にある,いわゆる熊野三山で,熊野速玉大社には,神武天皇を案内したとされるアメノカカグヤマノミコトが祀られ,それに次ぐのが,国譲りの関係で,出雲の熊野大社ということになるが,そもそも,新宮の熊野本宮大社のご本尊がスサノオノミコトであり,さらに,熊野神の元神様は,イザナギ神・イザナミ神ということなので,神様から人間世界への移行を示しており,国土から,諸生産物まで,あらゆるものの原点になっている。院政時代を頂点に,熊野詣が,天皇家の重要な行事になったのも,これらすべてに対応する精神的な拠所であったからにほかならないだろう。
分布状況をみると,九州の熊本県に多いのは当然としても,中部地方以西ではかなり少なく,千葉県から岩手県にかけての太平洋岸諸県に際立って多くなっている。ということは,クマ系の民族が,後から渡来して大和朝廷を開いた諸民族に排除され,かつて,南九州から紀伊半島に渡ったように,太平洋岸を北上していったということだろう。最北端の下北半島東通村に残る伝統芸能の能舞は,毎年正月,熊野新宮に奉納に上るといったことにも,歴史が遺されている。後述するように,物部氏の末裔で,熊野に本家のある鈴木氏が三陸に多いことも,関連していると思われる。⇒コラム「熊野神社の分布,三陸方面への展開」
ハ:熊襲とともに語られる隼人は,ずっと後に中央アジアから渡来した民族である
最後に,熊襲とセットで語られることの多い隼人族は,中央アジアのトハラ人で南西諸島吐噶喇(トカラ)列島にその名を残し,海洋民族ではない中央アジアの遊牧民トハラの末裔で,邪馬台国の時代よりかなり後に,戦乱の結果,流れ着いた人たちであったと考えられる。
トハラ(吐火羅)人は,スキタイ系の遊牧民で,タシケント付近にいたが,紀元前129年頃に,大月氏の侵攻を受け,以後,行方不明になった。隼人について,「言語が大いに異なっている」,「五島列島の海士と似ているが,騎射を好む」といわれたこと,甑隼人もいることなどから,九州西岸を南下してトカラ列島に至ったと考えられる。私の友人がそうであったように,隼人出身の人はラードを好むなど,中央アジア人の典型的な嗜好を示す。
「日本書紀」に初めて登場するのが,西暦682年と,全く新しい民族であることも明らかで,古事記で神武天皇の出は隼人族と書かれているなど,熊襲伝説に隼人を絡めるものが多々あるが,時代的にあり得ないことを付け加えておくとともに,神武天皇が西方から渡来した人物であることが暗示されているともいえる。
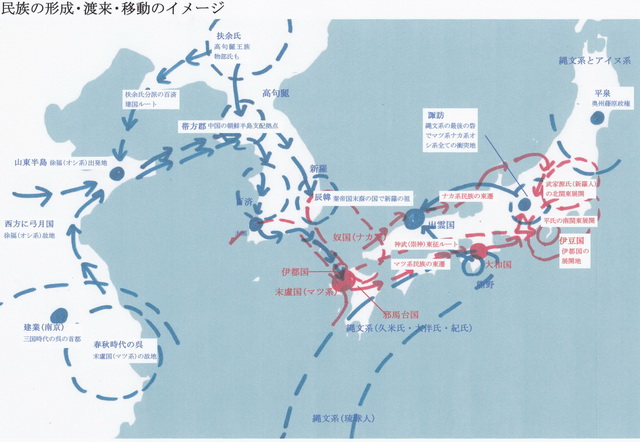
第2話:黄海から渡来した航海民族による奴の国(ナカ系)
イ:九州北部を拠点に,朝鮮,中国ともつながる海洋国家・奴の国
中国と朝鮮の間にあって,主たる渡航の足場になった山東半島の内側がいわゆる黄海であるが,早くから,これら渡航によって,交易圏がつくられていたと考えられる。この担い手だった民族が,さらなる発展を求め,造船や渡航の技術の向上とともに,日本の方に展開していったことは想像にかたくない。
序章のワダツミ族のところで取り上げた宗像神社の原点たる沖ノ島では,気候変動などの理由でニホンアシカがいなくなり,陸地も減少して,縄文人の祭祀は途絶えるが,今度は,朝鮮半島から日本列島をめざす海洋民族の格好の目印・聖地(地図をみれば一目瞭然)となり,結果として,博多から長門に至る九州北部沿岸と朝鮮半島西南側とを一体とする海洋国家を形成,これが,奴国("私の"が"我が"になるように,ナノはナカでもある)ということになり,第3章の徐福渡来のところでも取り上げるように,中国の山東半島は,朝鮮を経由して,日本に渡来するメインルートとなり,その航海を請け負ったのが奴国の民族ナカ系であったということになる。
航海は星を頼りにするので,占星術が発達,神事を司る中臣氏が形成されていったと考えられる。付け加えておくと,宗像大社の三女神は,応神天皇の妃とされ,後述する新たな海洋民族アマ系に属するように,沖ノ島の支配者が変わり,そのアマ系の代表たる卑弥呼のような巫女的な世界,シャーマニズムに近い神秘的なものになっていったといえるだろう。
沖の島の位置
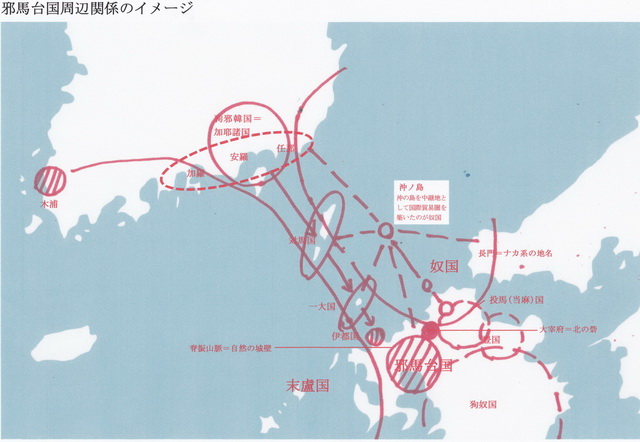
ところで,志賀島から出土し,西暦57年(場合によっては紀元前109年)に中国から授与されたとされる有名な漢委奴国王印は,漢の委(倭)の奴(ナ)の王と読まれてきたため,卑弥呼よりも2,300年前には,奴国が日本を代表する国として認知されていたと思われていたが,内倉武久「卑弥呼と神武が明かす古代―日本誕生の真実」によれば,漢音では奴はドと読まれるので,後述の伊都国王のことであったといい,その存在からみて,その通りのようだ。しかしながら,次節のマツ系の到来した頃には建国されていて,後述のように,邪馬台国建国に関わる徐福渡来は漢より前のことなので,すでに漢字も入っていたことを考えれば,自ら奴(ナ)と名乗っていたと考えられ,後に,「魏志倭人伝」に記載された時も,漢字で表記されたものをそのまま記し,漢音でドと読んでいたと考えても矛盾しないと思われる。内倉も指摘しているように,後の松浦であることが疑いない末盧(マトラ)国も,漢音では全く異なる音になってしまうということなので,すでにそれ以前の江南の発音を用いて表記されていた漢字をそのまま記していたということだろう。>伊都国
任那(ミマナ)のナとの関係も指摘されているが,"ナ"は,古朝鮮語では,村,郷,国,現代朝鮮語では,私,自分,僕などにあたる極めて原初的語で,他の国に比べて,その範囲を特定しにくい。想像をたくましくすれば,奴の国の人たちは,自分中心の民族であったともいえ,中臣氏にもつながるようだ。また,古代朝鮮で,"ラ"という語は,のちに新羅(シルラ),百済(クダラ)というように,国のことを示しており,「魏志倭人伝」の頃に,その"ラ"がついたのは,次節の末盧(マトラ)だけであり,それだけ,国の体を成していたということを示している。そして,オシ系が大和に移って,国譲りされ,それを支えたナカ系の奈良(ナラ=まさに奴の国,前節に従えば,自分の国)ができたということになろう。
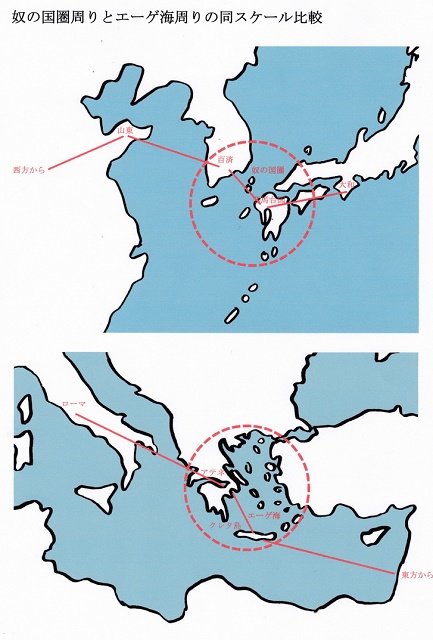 ヨーロッパの古代の,エーゲ海の島々から起る地中海文明は,そのスケールや大陸との関係が,奴国とほとんど同じで,イメージを膨らませてくれる。続くギリシャ文明は都市国家連合で,九州北部の女王国連合に瓜二つ,アテネとスパルタの戦争が,邪馬台国と狗奴国との抗争に対応し,さらにローマ帝国へと展開して行くのが,大和や京都への展開に対応するというように見て行くと,まさに,東西を反転させた相似形であるといえよう。
ヨーロッパの古代の,エーゲ海の島々から起る地中海文明は,そのスケールや大陸との関係が,奴国とほとんど同じで,イメージを膨らませてくれる。続くギリシャ文明は都市国家連合で,九州北部の女王国連合に瓜二つ,アテネとスパルタの戦争が,邪馬台国と狗奴国との抗争に対応し,さらにローマ帝国へと展開して行くのが,大和や京都への展開に対応するというように見て行くと,まさに,東西を反転させた相似形であるといえよう。ロ:徐福渡来に貢献し,祭祀をつかさどる中臣(ナカトミ)氏になる
奴国形成の過程で,航海の安全を基本とする祭祀をつかさどる中臣(ナカトミ=奴の臣)氏が,大陸と日本を結ぶ護衛のような存在として大きな役割を持つようになったと思われる。「魏志倭人伝」によれば,邪馬台国周辺諸国は,みな中国に倣う三官制であったが,邪馬台国にのみ第四の役職ナカチがあったと書かれていて,これこそ祭祀を扱う中臣氏のことであったと思われる。
後述するように,中臣鎌足は,日本に亡命してきた百済の王族で,奴国,すなわち中臣氏に受け入れられ,その姓を名乗ったと考えられるが,最近,奴国の,日本本土の都であったと考えられている福岡県春日市の須玖遺跡の発掘が進み,吉野ヶ里の4倍ほどの集落があって,そこでは,鉄器,ガラス,銅器を製作する専門集団も多くいて,まさに,弥生時代のテクノポリスであったといい,奴国が,早くから,朝鮮半島の百済地方と強い縁のあったことが判明した。先取りしてつけくわえれば,春日(カスガ)という地名は,藤原氏の本拠地だった奈良の春日そのものに対応する,カ(伽耶)のスカ(村),すなわち,百済のもとになった国の人たちの場所であったことを示しているのである。
ついでながら,日本で漢字を使用するようになったのは,古墳時代になってからと考えられてきたが,奴国のネットワーク下にあった,現在の島根県松江の宍道湖岸の田和山遺跡から発掘された板石硯に漢字が記されていたことが判明,その他多くの弥生時代の遺跡から,板石硯が発見されているが,当然のことながら,文字,すなわち漢字を書くために使われていたと考えられ,邪馬台国時代の九州北部諸国に,書記のような人たちがいたのは当然であったといえよう。
ところで,神武天皇(実は崇神)東征以前には大和の有力氏族で,その後急速に衰退してしまう倭漢氏については,わざわざ倭と書かれ,その祖珍彦が神武東征の水先案内人であったとされることから,神武朝時代のヤマト族で,その実態はおそらく奴国の氏族であったと思われる(かの金印がかつて漢の倭の奴の国王と読まれたように)。大和を制圧した崇神朝に,大和に実在して倭直の祖になった珍彦(ウズヒコ)は椎根津彦に対応し,応神朝になって登場する太秦と同じ"ウズ"であることから,徐福一族から特別の待遇を受けていたことも分かる。そもそも中臣氏は日本史上祭祀を司る最大の氏族とされながら,その本拠や神社との関係が不明になってしまっているのは,後述するように,藤原氏の祖鎌足が,本来中臣氏ではなく苗字を借りただけのことであったことを隠蔽すべく「日本書紀」が書かれたためであろう。
ハ:ナカ系人々の東進~標準日本語を広げながら,信濃に至る
奴国をルーツとみなせるナカあるいはナガのつく地名を調べてみると,まさに奴国の一部であった長門国や,かつて末盧国の範囲も取り込んだ長崎県はじめ,日本海岸,太平洋岸ともに多いように,ナカ系の人たちが,航海能力を発揮して次第に東進したこと,さらに,ナカ系地名が全国の主要な川沿いに広がっていて,内陸部に遡上していったことが分かる。その最たるものが,太平洋側の木曽川から遡上するものと,日本海側の信濃川から遡上するものが,諏訪湖において結ばれる大横断ルートで,そこの地名が長野県になったのも当然ということになろう。
実際,海洋民族になったつもりでみると,海から来た時に,信濃川の河口部の位置の目印となったのが弥彦山で,河口から遡って行くと,新潟県の中条・中野から,大きな長岡市を経て,中山の後,しばらくして長野県に入り,中野市(すぐ近くに中山)を過ぎて,県庁所在の長野市まで,"ナカ"系の地名が続き,(千曲川でない)犀川の方をさらに遡って行くと,すでに,ワダツミ族が開いていた安曇野(中村・中川・中山,さらには"なぎさ"という地名まである)に至り,塩尻峠を越えたところで諏訪湖を目にして,海に出たと感激し,精神的な本拠地にしたのではないだろうか。同時に,最も古くからいた縄文人と,その後に到来したマツ系民族と出くわして,諏訪大社や善光寺にまつわる複雑な神々の歴史に関わることにもなって行く。
くりかえしになるが,海のない内陸県たる長野県は南北から到来した海洋民族が主体となる不思議な存在になって行き,その象徴が,船の進水式そのものにも見える諏訪の大祭ということだろう(長崎県にも諏訪神社があり,いわば兄弟県になる)。地名の分布図からも分かるように,後述するマツ系と同様,長野県までであり,少し広げても関東甲信越までが限界で,東北地方以北は縄文人,アイヌ人,後述するワイ系民族の世界として,なお中央に抵抗する存在として残ったのである。
とくに,茨城県の那珂湊から那珂川を遡上して栃木県に至る地域には,ナカ系の地名が多数存在することから,中臣氏の本拠地の一つだったようで,のちに,中臣鎌足が,その地の,実際には物部氏の神社であった鹿島神宮を自らのものにした上,大和の春日神社に勧請しと考えられる。
ナカ系民族が全国展開していったのは,海洋民族たるナカ系として海産物を野の幸・山の幸と交換しようとしたことはもちろんであるが,天日による製塩も当然行っていて,岩塩などの無い日本の野の民・山の民からの強いニーズがあったことに対応したものと思われ,その際,必須な飲料水を欠くことがないよう,川沿いのルートを遡って行ったと考えるのが自然だろう。日本各地にはさまざまな方言があるが,序章で述べたように,日本語が,全体としては西北九州をルーツとしているのは,ナカ系とマツ系が全国展開したことによると考えれば納得できよう。
ナカ系地名の展開図

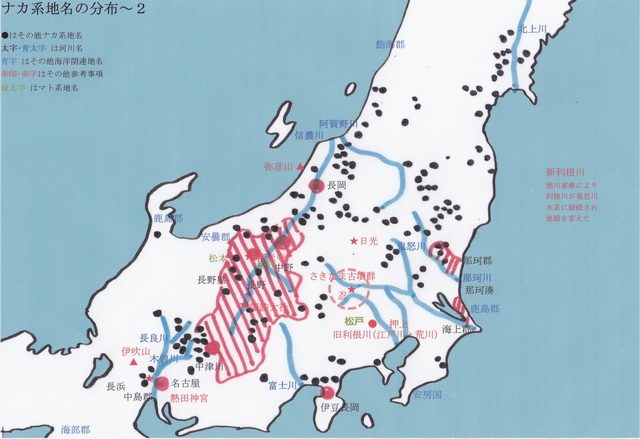
網野善彦・宮田登・上野千鶴子「日本王権論」によると,古代の朝廷支配で,一般の平民(公民)は,調・庸を貢納しているが,それとは別に,とくに海の幸を贄という形で奉るかなり特定された集団がいるといい,その分布を示した図を見ると,一目瞭然,ほとんどナカ系の地名の分布と一致する。おそらく,後述する徐福以来の天皇家につながるオシ系民族を支えたナカ系民族が,各地に展開,その後も,天皇家とのつながりを維持すべく贄を奉り続けたと考えられる。「続日本紀」に出てくるという"鹿嶋の神賤"という人々こそ,藤原氏が鹿島神宮を氏神にしたこととつながる話なのだろう。古代から続くといわれる美濃の"鵜飼"も,贄を貢納していたというが,その場所は長良川で,まさにナカ系の地名である。
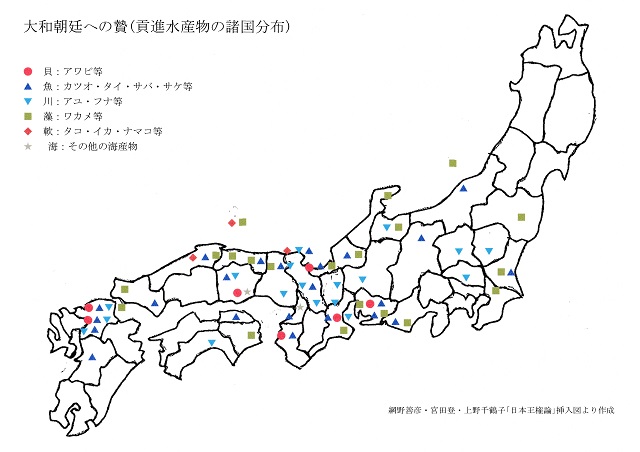
別冊歴史読本「日本の苗字ベスト10000」によって,ナカ系苗字(苗字全体の5%程度)について見てみると,大阪・奈良・和歌山の府県の10をトップに,兵庫県の9,石川・高知県の8を挟んで,新潟・愛知・三重・滋賀・京都・鳥取・広島・長崎・宮崎の9府県が同じ7,富山・岡山・山口・徳島・香川・福岡・佐賀・熊本の8県が6で並び,群馬・埼玉・神奈川・福井・山梨県が5,茨城・栃木・東京・長野・岐阜・静岡・愛媛・大分・鹿児島の9都県が4,あとは,青森・千葉県が3,岩手・秋田・山形・島根県が2,宮城・福島県が1と,ナカ系の全国展開をほとんどそのまま示す分布となっていて,とくに西日本にありながら極端に少ない島根県が大和朝廷とは全く異なる出雲の存在をそのまま伝えていることも示される。ちなみに,サッカーの強くて有名な選手には,ナカ系が多いが,世界でも,海洋民族のラテン系の国(スペイン,イタリア,ブラジル,アルゼンチンなど)がサッカーに強いことにもつながるだろう。⇒コラム(ナカ系・マツ系民族の展開)
第3話:中国春秋時代の呉人によって形成された末盧国(マツ系)
イ:滅亡した春秋時代の呉の国の人々(呉太白の子孫と自称)が末盧国をつくった
中国の長江下流域の沿岸海洋民であるとともに稲作民であった民族の一部が,とくに,紀元前770年からの中国春秋時代という動乱期に,朝鮮半島経由で日本に渡来してきたのがいわゆる弥生人の中核だと言われており,序章で触れたDNA分析によっても,その系統の比率がかなり高いことが指摘されている。最近,稲作を基準とした弥生文明と縄文文明の境目が不分明になっているといわているのも,これら,中国南部の人たちの流入を考えれば,矛盾はなくなるのではないだろうか。
その中国には,「倭人は呉の太伯の末裔である」という伝説があるが,周王朝の祖の長子太伯が現在の蘇州周辺を拠点に建国した呉の国は,紀元前473年,越によって滅ぼされたため,沿岸海洋民族でもあった呉人が大量に日本列島に流入して,新しい文明をもたらしたと考えられる。呉太伯の末裔という人たちがつくったのが末盧(マトラ)で,前節で触れたように,「魏志倭人伝」の頃に,国を表す"ラ"がついたのは,末盧(マトラ)だけであり,それだけ,国の体を成していたということになろう。現代でも,中国観光旅行をすると,最も落ち着くのは,蘇州の庭園群などと言われるように,日本人にとって,一つの故郷になっているようだ。
その呉人がどうして末盧国とつながるのかというと,その拠点であった九州西北部に極めて多い松尾姓はじめ,松の字のつく苗字を持った人たちが皆,"松野連(マツノムラジ=松一族)"と称し,「自分たちは呉太伯の子孫である」と言い伝えきていることによる。つまり,呉の国の滅亡によって,その王族が亡命してきたことにより,魏志倭人伝に記述される末盧(マトラ)国が形成されたと考えられるのである。繰り返しになるが,古代朝鮮による国名が,日本に直接つながるといわれる安羅(アラ),加羅(カラ)はじめ,新羅も本来シルラ,そして百済(クダラ)というように,ラは国を表し,末盧(マトラ)は,まさに松の国ということになるわけである。
「魏志倭人伝」では,倭の人は断髪・裸で刺青だったと書かれているが,呉を滅ぼした越の国が人々が断髪・裸で刺青だったといわれていることからも(両民族は混同されていた),まさに末盧国の呉人のことと思われる。沿岸海洋民である末盧の人たち(呉人)は,おそらく朝鮮半島で地形的にも似ている後の百済や済州島などにつながる国家として,日本で最も早くに国をつくったと考えられる。
さて,呉人が日本に伝えた文明であるが,青銅器や生贄・占いなど,古くからのものはもちろん,日本の神話が中国の道教の影響を色濃く受けているという点で,その原点と言われる老子が,少し前の紀元前6世紀に,隣国の楚で誕生し,周の図書室を管理する役人であったといわれるから,少なくとも,呉太伯の末裔というような人たちには,その思想も伝えられていて,のちに,道教を身につけて渡来した徐福一派(オシ系)や秦氏(ハタ系)とも,なにがしかの接点があったと考えられる。
ついでながら,呉を滅ぼした越は,その後,楚に滅ぼされて南下,のちにベトナム国をつくることになる。「呉越同舟」という語があるように,いわゆる漢民族からは,それぞれ能力ある民族と見られていたのだろう。日本とベトナムそれぞれが,中国とほぼ対等に複雑な関係を築いてきたことを思うと,不思議な感じもする。
この後,中国では後漢が滅んだ後のいわゆる三国時代に,その一つの国として長江下流域に再び同名の呉国が登場,かつての呉の国の民族に近く,ほぼ卑弥呼の時代に対応する西暦223年~280年に存在した同国の人たちも多く渡来して,漢字の読みにおいて,日本には漢音よりも先に呉音が普及,現在でも多くの読み方が残ることになり,同国の首都で現在の南京になった建業は,園林都市としての魅力を有し,庭園や文学はじめ,日本文化に本質的な影響を与えることになる。
ロ:マツ系の人々の東進~大和(近畿)に国をつくり,信濃に至る
松(マツ)の字のつく主要な地名を追って行くと ,四国の松山,高松を経て,現在の大阪府松崎から,大和の地に入ることになるが,おそらく,そこでの初めての国をつくったと考えるのが自然であろう。神武東征神話では,河内から入った神武が長髄彦の抵抗を受けて退却し,南下して熊野から入らざるを得なかったと書かれているすが,その長髄彦の祖の名は観松彦(ミマツヒコ)で,マツ系,すなわち呉太伯の末裔だったようだ。蛇足であるが,長髄彦一族について,記紀では風貌賎しくなど蔑む言葉が書かれているのは,単に敗者を蔑んでいるのではなく,朝鮮経由できた鉄器民族の人たちには,長江河口部の東南アジアに近い民族が異質に見えたことを示すものとも考えられ,北方アジアの民族と融合を図れず,国譲りに至ったと思われる。もちろん,王族とともに,多数の被支配層の呉人も,全国に展開していっただろう。
ところで,島根県の宍道湖に面する荒神谷遺跡で,1983年,大量の銅剣,銅矛,銅鐸が,それも未使用の状態で発見されて学界に衝撃を与えたが,松江に近いことからも,マツ系の人たちの最後,まさに出雲の国譲りに対応するものと考えられよう。出雲地方には,独特の形をした,方形古墳が多くあるのも,国譲りをした人たちに関係するのかもしれない。
神武東征,実は崇神天皇の東征に敗れて,国譲りしたマツ系の人たちは,東に逃亡,伊勢の松阪を経て,名古屋方面に向かうが,その近傍には有松(マツ)が存在する。濃尾平野のいわゆる木曽三川が呉の国の地のように"江"と呼ばれるのをはじめ,岐阜あるいは"蘇"のつく地名など中国南部に類似するものが多く見られ,鵜飼など極めて古い文化を有している。のちに,有力武将を輩出するなど,日本史上重要な役割をし,関東・関西の中間に位置しながら,なぜ首都になれなかったのか,まさに,抑えられた民族マツ系の地であったからなのだろうか。後の章で明らかになるが,猿のような風貌だったといわれる豊臣秀吉に続いて,徳川家の家紋が三つ葵であることなど,マツ系の人物が,再び国を取り戻すのである。>豊臣秀吉,>徳川家康
その後,浜松から,ワダツミ族と同じように,天竜川を遡って,諏訪湖に至り,安曇野の地の松本が,最後の拠点になることは,前章の,信濃の項で述べた。
ちなみに,野球の強くて有名な選手に,マツ系が多いのは何故だろうか。⇒コラム(ナカ系・マツ系民族の展開)
マツ系地名の展開図
(藤井耕一郎「サルタヒコの謎を解く」を参考に)
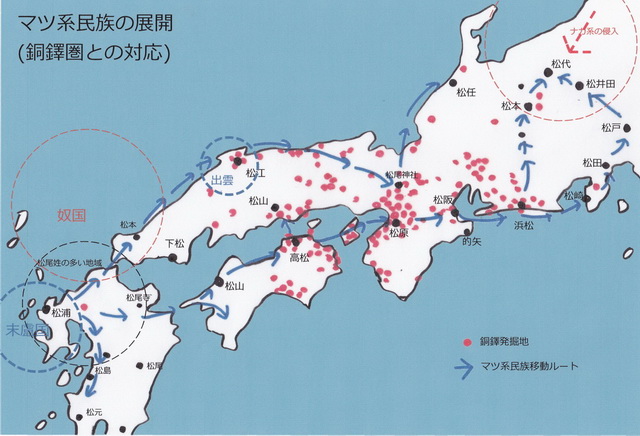
ハ:国譲りした主体はマツ系であった~松尾大社・上賀茂神社・下鴨神社が一体である理由
先取りするようであるが,秦氏が創建したとされる有名な神社に京都の松尾大社があり,その名がマツ系そのものである上,中村修也「秦氏とカモ氏」によると,その祭神は秦氏の神ではなく,その近くの,鴨氏の上賀茂神社,下鴨神社と同じであるという。つまり,国譲りしたマツ系の人たちを,支配下に取り込む装置として,これらの神社が創建されたと考えられよう。この両神社は葵祭りで有名であるが,鴨という動物,とくに家畜化されたアヒル(家鴨)と,葵という植物をセットで考えれば,まさに,中国南部の揚子江下流域のもので,マツ系がすなわち旧呉人であるという有力な証拠になるだろう。このことと関係するかもしれないが,大和最古とされる三輪山をご神体とする大神神社は,オオモモヌシが祭神で,鴨氏の祖とされることから,マツ系が大和を支配していた時の名残ではないかと思われる。
後述するように,鉄器文明を携えて渡来した徐福の末裔が創始し,後に大和王朝を開くことになる邪馬台国が,奴国をもとりこんで,北九州の覇権を握り,やがて東征してきたことで,忽然と消えてしまった(国譲りした)銅鐸文化を支えていたのが,マツ系民族であるらしいことは,その出身地江南の地で使われていた祭器にそっくりだということからも明らかで,鉄を銕と書いて蔑み,青銅器を崇拝する江南の文化を受け継いでいたマツ系の人たちが,先進的な鉄器を持って登場したいわゆる天孫族にあっさり敗れてしまったということだろう。平安京遷都以前に,その地に,鴨氏の神社があったということは,かつて大和の地を支配していたマツ系の民族が,崇神朝以降,圧迫されて,山背国方面に退避させられていたことを示すものともいえよう。
蛇足になるが,著名な歌人柿本人麻呂は鴨氏の出といわれ,繰り返しになるが,蘇我氏,藤原氏らに排斥された(クマ系の)大伴家持,紀貫之,さらには鎌倉幕府に配流された後鳥羽天皇まで,和歌は,敗れた側の人たちの世界を救うものとして,大きな役割を担って行くが,それを象徴するのが,まさに鴨氏直系の鴨長明ということになる。
唐突であるが,マツ系に絡んで,酒の話をしておくと,世界で,酒に弱い人の多い国のトップは中国で,実に半数以上,次が日本で約4割,3番目が韓国で約3割という。欧米諸国などにも,酒に弱い人が少しはいるのではないかと思われるが,実は全くいないということだ。酒に弱いというのは,すぐ赤くなる,吐き気がする,二日酔いになるといったようなことで,そういう人はおらず,アル中が多いのは,あくまでも肝臓の能力を超えてまで飲んでいるからということのようである。中国について見ると,揚子江の南側に集中していて,呉の国は,まさにその中心に位置していた。実際,中国の北部では,茅台酒というやたらに強い酒が有名であるが,南部に行くと,紹興酒というかなり弱い酒が一般的になる。呉の国の人たちが,日本に大量に入ってきたとすると,日本の酒に弱い人たちが多いのも無理はないだろう。すでに述べてきたように,呉の民族はマツ系で,その氏神が松尾大社であるとすれば,松尾大社が,なぜ酒の神になっているのかも,分かるといえるのではないだろうか。
さらに付け加えると,酒に弱いというのは,肝臓が,アルコールをアセトアルデヒドに変換後,すぐに酢酸に変えることができず,有毒なアセトアルデヒドがたまりやすい身体であるということであるが,ある遺伝子学の人によれば,酒に弱い人が登場したのと,稲作が始まったのとは,ほぼ同じ1万年ほど前で,稲作は暑い中に水を張るため,感染症の原因になる病原体が繁殖しやく,それを防ぐべく,アセトアルデヒドの力を借りる,つまり,毒をもって毒を制するという進化を選んだということのようである。してみれば,東アジアの人たちは感染症に強いということであるから,今まさに流行している新型コロナウィルスの感染者数,死者数などが,欧米諸国等に比べて桁違いに少ないのも当然なのかもしれない。
2001年に発表された,原田勝二の「飲酒様態に関与する遺伝子情報」によって,都道府県別に,アルコールを分解するALDH2遺伝子の頻度をランキング表にしたものを図化してみると>コラム,まず,言えることは,弥生時代に入って,大陸から渡来した人たちが,日本の中央部に広がって行くに伴って,縄文時代の人たちが,南北に押し分けられていったことを,そのまま示すように,東北と九州の人たちが,日本人のなかでは,とくに酒に強い人たちということが示される。
渡来した弥生人のなかでも,とくに酒に弱いとされる揚子江下流域からきたのが,マツ系であるとすれば,かつての末盧国,すなわち,現在の長崎県,佐賀県が,九州のなかで,異質の酒の弱さを示していることが,末盧国がマツ系の人たちの国であったということを示す根拠になろう。そして,近畿方面に展開していったことも,図から読み取れ,崇神天皇が大和に入る前,この地方を支配していたのがマツ系であったことを想像するのも容易である。神武伝説で,天皇が,瀬戸内から難波方面に入った際に,抵抗したとされるナガスネヒコもマツ系であっただろう。
それより以上に,とくに酒に弱いのが東海地方であるが,その中心の尾張は,日本の中でも,とくに揚子江下流域と似た風土であることから,この方面に大量のマツ系の人たちが定着したと考えられる。それ故に,大きな川のことを,「江」と名付けたり,蘇原や岐阜など,中国的な地名が多くみられるということでもあるだろう。のちのち述べるように,豊臣秀吉,徳川家康がマツ系の可能性が高いという根拠にもなろう。
面白いのは,首都圏が酒に強い側にあるということで,東京の人たちのベースは,東北,新潟の人たち,さらには,九州の人たちであることが窺え,このことが,関西と関東の文化の違いを示す一つの理由であると言えよう。
この章TOPへ
ページTOPへ
第2論:九州北部小国家群を支配した二つの強国~伊都国と邪馬台国
第1話:大陸からの認知を受け,諸国連合の王を務めた伊都国(アマ系に支えられたイト系)
イ:大陸とつながる日本を代表
奴の国の項で述べたことの繰り返しになるが,志賀島から出土し,西暦57年(場合によっては紀元前109年)に中国から授与されたとされる有名な漢委奴国王印は,漢の委(倭)の奴(ナ)の王と読んで,奴国の王であるとされてきたのが,内倉武久「卑弥呼と神武が明かす古代―日本誕生の真実」によると,漢音では奴はドと読まれるので,委奴(イド)すなわち伊都国王のことであったということである。ナカ系の奴国(玄界灘国家)とマツ系の末盧国(黄海圏国家)の間にあって,倭の北岸といいながら朝鮮半島内にあった狗邪韓国(おそらく後にも統一新羅までは倭の一部として半島内に存在し続ける伽耶)から,対馬,一大国(一般には一支国の書き違いで壱岐とされているが,内倉によれば,天(アマ)国であった天の字が二つに分けて書かれてしまった可能性があり,伊都国がアマ系と一体であったということを示す)を経て,九州北岸の現在の糸島(怡土郡)が,日本における首都にあたる地であった。中国が半島支配の拠点としていた帯方郡と直接繋がっていて,祖は現在の韓国の蔚山で,おそらく伊都を示す現在の糸島を前衛基地にしていたとも考えられる。対馬の厳(イヅ)原は伊都(イト)を表し,福岡県の板付(イタツケ)も伊都が語源のようである。つまり,のちの伽耶・任那にあたるとされる狗邪韓国から,対馬国,一大国(壱岐)経て,伊都国(糸島)に至るルートが大陸からの支配軸で,日本本土の玄関が伊都国になり,そこまで全体が,伊都国の支配下にあったということになる。
ロ:卑弥呼を産んだアマ系
石井好「忘れられた上代の都"伊都国日向の宮"」,西谷正編「伊都国の研究」によると,次節で述べる徐福の渡来以前には成立していたとみられる伊都国(現在の糸島周り)は,朝鮮半島南部と同様,鉱物資源の宝庫で,とくに玉の生産を中心とした一大貿易港でもあって,壱岐,対馬を介して大陸と深くつながっていたことから,倭のなかで伊都国だけに王が存在し続けたと言われるのも当然であったと思われる。大陸との間で,朝貢だけでなく,外交・貿易を行っていたということは,「魏志倭人伝」以前から,すでに漢字が用いられ,それを理解する人たちが少なからずいたことを示しているが,それが一部に限られ一般化していなかったため,文字遺跡が無いのだろう。当然のことながら,中国の銅銭も盛んに使われており,造船業もかなりのレベルにあったようだ。
大和朝廷のルーツとみられる邪馬台国の勃興は,次節で述べるように,徐福渡来によるものと考えられるが,徐福一族は,朝鮮半島南部から伊都国に到着,そこで伊都王に迎えられ,携えてきた先進的技術などによって重鎮となり,やがて婚姻関係を結ぶに至って,そのまま滞在することになったと考えられる。その場所の名が日向(ヒムカ)の宮であり,神武東征伝説の重要な土地,現在の宮崎県に当たる日向国の名の由来になったこと,さらに言えばと,卑弥呼の読み方も弥生時代の発音ではヒムカであったことなど,神話を理解する上でポイントになろう。後述するように,徐福一族は道教の神仙思想をもって渡来,一大国では,遺跡から,卜骨を用いた占いが盛んであったことが知られ,後の卜部氏のルーツとも考えられているくらいなので,そのアマ系の巫女文化と結び付いて,神社など道教用語が統治の体系を創る基本になったとみれば,その後の展開も良く見えてくる。
結論的に言えば,大陸との間の交易で覇権を握ったイト系の王が,アマ系の巫女に支えられて国家を形成していたということになり,後に,徐福の末裔が邪馬台国を建国するにあたって,アマ系の巫女を戴く形で支配する新たな国家を形成,のちの天皇制を先取りするような形で覇権を握り,その結果,アマ系を支配下においていた伊都国(イト系)との間は緊張をはらんだものになっていたようである。アマの国から来たということを示すアマギすなわち甘木が,重要な参詣地となったらしく,アマ系たる卑弥呼がアマテラス大神のモデルになったと考えるのが極めて自然といえよう。
なお,桓武平氏梶原氏の祖や額田王で知られる額田氏は,一大国すなわちアマ出身であり,紀元前221年に秦に滅ぼされた中国の晋の王族田氏も一大国に逃亡してきたといい,のちに天皇側近の氏族とみられる倭漢氏になったらしく,その末裔の坂上田村麿の子孫が田氏を名乗っていることにもつながるようだ。
伊都はまた伊勢とも言われたというから,のちに崇神天皇が大和の地に至って,その地にいた神を遠ざける形で伊勢神宮を創建したことにもつがるのだろう。
ハ:平氏のルーツになるイト系~アンチ大和朝廷的役割をして行く
話は飛ぶが,後に平清盛を生む平家の棟梁は,その風貌からも,伊都国王族(イト系)の末裔ではないかと考えられる。と言うのは,代々厳島神社(伊都国から来たことを示すイツク島で,宗像三女神のうちの,伊都国から来た名のイチキヒメミコが祭神)を崇めていたこと,伊都国には強力な水軍があって玄界灘を支配する貿易国家であったこと,中国の威信を背景に伊都国が支配していた被支配層の海洋民族は,後に,海賊化し,現在のヤクザにまでつながるが,その海賊を統率できたのも,中国南部の宋との貿易に通じていたことからも頷けるからである(現在でも長崎県と福建省のつながりは強い)。さらに,平氏直系の北条氏の根拠地伊豆国は伊都国であると言われているばかりか,伊豆のシンボルが(アマギすなわちアマの国から来たことを示す)天城山であることからも,伊都国の人たちが伊豆に辿りついたのは,ほぼ確実で,第5章で記すように,平氏は,伊豆を拠点に関東の太平洋側一帯を支配するようになったのである。>伊都国の東進,>桓武平氏
後述するように,伊都国は,支配下にあったアマ系の民を戴く形で登場する徐福の末裔が建国した邪馬台国と抗争を繰り返すようになり,卑弥呼没後の九州北部全体の動乱によって,邪馬台国は東征して大和朝廷を開いたが,伊都国は当地では滅亡し,東進して,伊豆を拠点とする平氏を生み出したと言うことになるが,そのことが,のちのちの歴史において,大和朝廷にたてつく形で,所々に登場することと関係するとみて良いだろう。
前掲文献で,律令国家以降の地名で怡土郡の北に志摩郡があることから,「魏志倭人伝」で,邪馬台国から相当先にある国としてあげられている斯馬(シマ)国にあたるのではないかといい,中国の別書にも伊都国の傍らに斯馬国あると記されているので,斯馬国は「魏志倭人伝」時代より前に,何らかの理由で東遷して,現在の三重県志摩にまで至ったとも考えらる。日本書紀では,後に統一百済ができた際,倭との交流に従来の対馬~伊都国ルートが使えなかったためか,沖ノ島経由の新たなルートを教えて交渉に当たったという斯馬宿禰が登場するが,その名の通り斯馬国出身の人物と思われ,このことはまた,もともと斯馬国が伊都国と敵対する関係にあったことも想像させる。
第2話:小国家群から大和国家への契機となる,秦帝国からの徐福の渡来(オシ系)
イ:徐福伝説は,事実を反映しており,オシ系のルーツになった
紀元前3世紀頃,朝鮮を経由して弥生文化が入って来たという見方に対応するのが,日本各地に残る徐福渡来伝説ではないかと思われる。各地に伝説が残るのは,渡来する段階で相当に分散して漂着したことにもよるとも考えられるが,後述するように,徐福の末裔が展開していったことによる方が大きいのではないかと考えると辻褄が合うようだ。徐福は,徐市(じょふつ)とも書かれ,山東半島一帯にあった斉の国の方士(道教の神遷思想に強い関心を抱修行者)であったらしいが,徐福にしろ,徐市にしろ,ユダヤ系の名ヨブの漢字表記である,つまり,ユダヤ人であった可能性が高いのである。最近になって,中国で徐福の墓が見つかったところは徐阜村というが,これもヨブの漢字表記である。
徐福は,秦の始皇帝が天下巡遊した際に出会い,東海すなわち日本に派遣され,その際,あらゆる職能の数千人の船団を組んで渡来したといわれ,日本の文明を一気に進ませるとともに,それ以前の縄文時代以来の自然の神々から,先進的な道教の体系をもとにした神話体系を構築していったと考えられる。第4章に記すように,応神天皇渡来時には,やはりユダヤ系とされる秦氏(ハタ系)が,その当時の朝鮮の道教にもとづいて,神社体系を再構築し,のちには唐が道教を重んじた国であったことから,遣唐使によって,道教の思想が,さらに強化されて行ったということのようだ。山東省は,のちのちも,道教の拠点として,宗教としての体系化を進めていく場になって行く。
始皇帝の意を受けた徐福は,さらに東方の日本での建国をめざして渡来したといっても差し支えないので,その始皇帝によるほとんど突然のような中国統一について,見直してみよう。秦国そのものは,紀元前770年に,現在の中国の西端部に興ったといわれ,さらに西方の中近東由来の養蚕・機織りなど先端技術得て勢力を振るい始めて,同325年に初めて王を名乗り,その後諸国を次々と滅ぼしてはいったのであるが,あくまでも多数あった国の一つでしかなかった。そこに,同221年に登場した始皇帝が一気に中国全土を統一したわけであるが,わずか15年で滅亡してしまうという奇跡的な状況を説明するには,特別な状況があったと考えざるを得ない。
ところで,旧約聖書のなかの「ヨブ記」は,「義人の苦難」を扱った文献として知られているが,紀元前5世紀から前3世紀にかけて成立したようで,まさに,徐福の時代の直前にあたる。作者に擬せられているヨブはウツ(太秦のウズの語源ともいわれる)の地の住民のなかでもとくに高潔で,ヘブライの神の不可解なやり方を問題視,その答えを出すべくヨブ記をまとめたと言われるから,のちのキリストのように,逸脱したユダヤ人であったと思われる。サタンによる襲撃にも屈せず,神を勝利に導いたことで,羊,らくだ,牛,ロバ,あわせて3万頭以上を与えられたが,次項で述べるように,中央アジアの民族を象徴するものではないだろうか。七人の息子と三人の娘をもうけたらしいので,その後,一族が各地に展開していったと考えてもおかしくないだろう。
後述するように,神武天皇からのいわゆる欠史八代は,単に神話の世界ということでなく,崇神天皇になって大和入りする(いわゆる神武東征)までの,徐福の末裔による北九州の邪馬台国時代を示すものになっていると考えられる。中国には神武天皇と徐福が同一人物であったという説まであるが,神武天皇の倭名カムヤマトイワレヒコの,不明とされてきイワレの語について,古代ヘブライ語にあたってみると,なんとイワレ(イヴレ)はヘブライ人そのものを指す語だといい,神武天皇・崇神天皇とも倭名がともにハツクニシラススメラミコトというように,始皇帝と全く同じ名づけられ方になっているのも,つながりを示しているのではなかろうか。
ロ:ディアスポラしたユダヤ人が,秦帝国の統一に関与するまで
ここまでくると,ユダヤ人の中国方面への展開の歴史を,さらに遡ってみたくなろう。いわゆるユダヤ人の離散(ディアスポラ)は,BC722年アッシリアによって北イスラエルの12支族が流浪の途に出,そのうち10支族は行方知れずなったとういうのが始まりで,紀元前587年のバビロン捕囚によって拡大し,同332年のアレクサンダー大王のパレスチナ征服によって決定的なものになった。ユダヤ人の多くは西方に向かい,後にヨーロッパで嫌われる民族になることは良く知られているが,東に向かった一部については,あまり知られていない。
「宋氏日本伝」には,最初の神・天之御中主の23世後の彦ナギサが筑紫日向の地,つまり伊都国に着いたと書かれているらしいが,彦ナギサがすなわち徐福で,ディアスポラによって故地パレスチナから出た時からの歴史を,この23世にこめたものと思われる。とすれば,戦前に紀元2600年と言っていたのが,まさにパレスチナ出地からの年数を表しているのだと気づかされる。
紀元前4世紀には,現在のキルギス周辺にユダヤ人がいたことが確実になっている。キルギスの古都オシ(まさにオシ系のルーツを表している)には聖なるソロモン山(現在はイスラム教なのでスレイマン山と呼ばれる)があり,アレクサンダー大王の東征は紀元前320年に,この少し西側でストップするが,おそらくキルギス側に,すでにユダヤ人が建国した月氏国(砂漠の民であることを示し,後の弓月国にもつながる)があったことによると思われる。そして,アレクサンダー大王の圧力を受けて東進し,秦を支配することになったのが,月氏国の支配者であった始皇帝だったのではないか,つまり,当時の中国で隔絶した技術などを有するユダヤ人に近かったからこそ奇跡が実現したのではないかと考えられるのである。実に,キルギスには「自分たちは西方(つまり砂漠の地)から来てここに止まったが,さらに東に行ったのが日本人である」という言い伝えがあるのである。そして,現在のオシには"ルフ・オルド"というイスラム,正教会,カトリック,ユダヤ教,仏教の五大宗教を合わせた公園が作られており,このことからもキルギスにおけるユダヤの存在が大きいことが分かるのである。
中国のことを秦といい,音が転じてCHINAというようになったばかりか,秦の始まりと同じ頃に登場した古代ローマも,紀元前27年に諸国を統一してローマ帝国となり,皇帝が登場すること,大秦国という漢名なったことなどからみても,やはりユダヤ人がその創設に寄与したと考えても良いだろう。いずれにしても,シルクロードは,ユダヤ人が商いの中心になっていたのである。 タクラマカン砂漠にいたというシルクロードの謎の民「楼蘭」は,始皇帝時代に隆盛であった月氏の勢力圏内にあったが,BC176年に,匈奴の支配下になって以降,その存在が消えていったといい,ユダヤ人に近い人たちであった可能性もあるといえよう。
秦帝国,ローマ帝国に共通するのは,大規模な土木・建築という建造技術と国家支配システムの構築であるが,前者が一瞬にして終わってしまったのは,漢民族という大きな塊に屈してしまったから,もしかしたら,徐福のような有能な人材がいなくなってしまたからかもしれず,後者が極めて長く続いたのは,ユダヤ人の持つ能力が発揮され続けたからではないかとも考えられる。ユダヤ人の国家支配システムを構築する能力は,その後,金融によって世界支配システムになり,GAFAなど,現代のインターネットによる世界支配につながっている。その上,アインシュタインやマルクスなど,世界を支配する知的な思考や思想の面でも,世界を支配するようなものを生み出しているのである。
余談ながら,イスラエルの失われた12支族の中の,マナセという名は,戦国時代に登場した名医曲直瀬道三の不思議な苗字に関係していると思えてくる。
ハ:オシ系の展開を示す地名・人名~古代皇族の名から東京スカイツリーまで
キルギスの古都"オシ"の語は,重要な意味をもっているらしく,神話時代の天押帯日子命・屋主忍男武雄命などにはじまり,6代孝安天皇(日本足彦国"押"人天皇)・9代開化天皇の弟(彦太"忍"信命)・12代景行天皇(景教と関係するか・大足彦"忍"代別天皇)・17代履中天皇(もとに復する意か)の子(磐坂市辺"押"羽皇子・"忍"海飯豊青尊・忍坂大中姫)・30代敏達天皇の子("押"坂彦人大兄皇子)など,その後も忍熊皇子・刑部親王・他戸親王など,また皇族外でも,神部直忍・神人部子忍男・穂積臣押山・穂積忍山宿禰・敢臣忍国・紀忍人・忍海氏など,古代の天皇やそれに近い人物の倭名に"オシ"が入っているものが多いことから,"オシ系"民族として位置付けられることになる。藤原仲麻呂が,尊称として,恵美押(オシ)勝を名乗ったという理由も,これで判明し,皇族でもないのに名乗った傲慢さが,孝謙上皇を諫めて怒りを買ったという以上の結果を招いたと考えられるのである。
さて,海を渡った経験の無いユダヤ人にとって,日本へ大船団で向かうというのは容易ではない。そこで登場するのが,第1章に記した,海洋民族の奴の国の人たちだったと考えられ,のちの邪馬台国に特別の官職ナカチが設けられたことからも,如何に重要な役割を担っていたか分かるのである。実際,徐福集団が後の百済地域を経由して渡来したことは,現在の全羅南道の木浦に,押(オシ)海島があり,その主峰が忍(オシ)海山であることから推測され,押海島は,のちに公孫氏が滅ぼされた年に,卑弥呼が帯方郡に朝貢した際に使者が経由した地ともいわれている。その後も,徐福一族の子孫たちは,ナカ系の人たちに誘導されて日本各地に展開して行くことになるのである。
オシという地名で唯一良く知られているのは,埼玉県行田市にある忍城,つまり江戸時代の忍藩であるが,この不思議な地名こそ,古代からのオシ系の拠点であったことを示すもので,さきたま古墳群があるのも当然であった。そして,地名の由来が定かでないとされて来た東京の押上は,オシ族が上陸したところで,そこから荒川を遡上して再上陸したのが行田の忍(オシ)の地であり,それを裏付けるように,行田の荒川沿いにも押上の地名があるとなれば,もはや,疑いようがないだろう。
その押上にできた東京スカイツリーであるが,そもそもなぜあんなに狭いところに,それも大地震時には東京内で最も危険とされるようなところに無理して建てたのか,さらに着工までとその後しばらくはほとんど報道されなかった(地元ではかなりの反対運動があった)のはなぜか,さまざまな疑問が湧いてくる。というのも,知る人ぞ知るように,東京タワーがフリーメーソンアジア支部の位置を示すところに建設されたということもあるからである。
東京スカイツリーは東武鉄道が本店のある押上一丁目一番地周りの車両基地の跡地に建設したもので,今述べたように,ユダヤ人の上陸した地点であり,戦前にユダヤ人アインシュタインが来日した時,なぜか分野的には全く関係のない東武鉄道創業者の根津嘉一郎をわざわざ訪ねていること,そして,ルーツが秦氏つまりユダヤ人と思われる豪商三井が江戸にでてきた時,守護神としてきた京都太秦の木嶋神社(蚕の社ともいわれユダヤにつながる)と同じ型の三柱鳥居を奉納した三囲神社があること(実に,スカイツリーの形をデザインした芸大の先生が,テレビ番組で,分かっていてか,知らずにか,イメージの源泉を問われて,すぐ近くにある三囲神社の三柱鳥居であると話していた)などから,疑問は氷解してくるのである。
東武鉄道の基本である伊勢崎線は,東京スカイツリーが建設された押上(オシ系)を始点に北上し,忍城の名に残るようにオシ系の拠点さきたま古墳群の近傍を通過(羽生から秩父鉄道ですぐ先,忍城のある行田市にも荒川の旧流路沿いに押上町がある),そして江戸時代に徳川綱吉が5代将軍になる前に藩主を務めたほどの地で,11代将軍家宣と側室(オシ系の押田敏勝の娘)の子が12代将軍家慶になるなど,まさにオシ系ラインなのである。>新・上州遷都論
全く別の話として,ヤマトタケル伝説のうち,熱田神宮に近い,亀山市に伝わるものに触れておきたい。明治政府は,市内田村町の丁字塚を,「日本書紀」に書かれたヤマトタケルの墓が営まれた能褒野と比定して,能褒野王塚古墳と名づけているが,ヤマトタケルの妃オトタチバナヒメが,市内の忍山(オシヤマ)神社の祇官の娘であったいうことが最大の理由のようで,忍山神社がかつてあったところが,押田山という名になっている。もしかしたら,伊勢神宮を全国に広げる役割をした人たちは御師と書いてオシと読んでいるのは,オシの名を残すためなのか,伊勢近傍には押(オシ)田姓が多いらしく,最近でも,高校野球となでしこリーグのいずれにも,押田選手のいることが知られる。また,代々押田氏の京都の染物屋「京明」が,2013年の伊勢神宮遷宮に当たり,神宝製作者に選ばれたのも関係するかもしれない。
また,徳川吉宗時代に,広大な武蔵野新田の開発を任されたばかりでなく,その後,美濃の輪中地域の整備,石見銀山の再興など,さまざまな面で,地域の開発や経営の面で,優れた才能を発揮した,川崎平右衛門定孝は,豊臣秀吉の小田原征伐に敗れた後北条氏の家来で,東京府中の押立(オシタテ)村に定着し,代々,名主を務めた家柄であるが,この地名も,押上同様,多摩川からの,オシ系の上陸地点であったように思われる。その下流ほぼ全域が,現在,川崎市となっているように,一族が連綿と繋がっているようでもあるが,なんと,川崎定孝は,屋敷内に,家祖を祀る押田稲荷の社を建てていたということなので,オシ系そのものの人物で,その才能は,まさに,ユダヤ人の血を引いていたからともいえるだろう。このような例は,他にも多々あると思われる。
ちなみに,名字由来のホームページをみると,川崎氏は,武蔵国橘樹郡河崎庄が起源とあり,橘樹郡の名は,ヤマトタケルの妃弟橘媛(オトタチバナヒメ)に由来するといい,亀山の押田山の話につながるばかりか,地図で確認すると,橘樹郡はそのまま,現在の川崎市の範囲である。自民党の大物議員で2021年に引退した川崎二郎は,亀山と接する伊賀の名門といい,川崎姓の多いのが,邪馬台国のあった佐賀県と,神武東征の本拠日向の国すなわち宮崎県であるということからも,川崎氏はオシ系であったことが示される。
第3話:徐福(の子孫)によって,アマ系戴くオシ系の邪馬台国が建国される~神武皇統
イ:邪馬台国の所在地は吉野ヶ里周辺であった
あらかじめ確認しておくが,邪馬臺国の臺(台)の字が壹(壱)の誤記とする説について,長田夏樹「新稿・邪馬台国の言語~弥生語の復元」・渡辺義浩「魏志倭人伝の謎を解く」(本来の三国志から)などでは,逆に壹(壱)こそ,臺(台)の誤記であるとして,再び邪馬臺国が正しいとされるようになってきている。そして,所在地論争にも,様々な理由から,九州北部説に落ち着きつつあり,言語学的に見ても,方言の残り方などから,邪馬台国は九州北部であったと考えられるという。ついでながら,古代日本にすでに方言があったということは,大陸での出身地が様々であったといことを示すものに他ならないだろう。
全国各地にある徐福伝説のうち最も濃密なのが佐賀県で,ほぼ全域に伝説が残っており,その中心は吉野ヶ里遺跡近くの金立山で,上陸地点は諸富町寺井津とされている。徐福は渡来当初は,前述したように,伊都国に止まったが,何代かあとに登場する徐福の末裔が伊都国に離反し,後の大宰府経由で佐賀平野に入り,邪馬台国を建国したと考えられ,この人物こそが神武天皇ということになろう。中国の言い伝えには,徐福は最後に肥沃な平野に到達したとあり,神武天皇は徐福であったというものすらあることから,佐賀平野周辺が邪馬台国で,その中心が,南に平野を望む日向(ヒムカ)の地吉野ヶ里にあったと考えて良いのではないだろうか。
吉野ヶ里周辺図
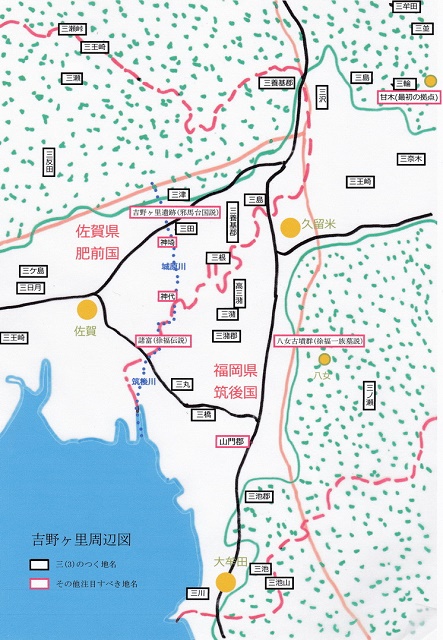 神武天皇の倭名のカムヤマトイワレヒコの,ヤマトが邪馬台国を意味するのは勿論,繰り返しになるが,イワレは古代ヘブライ語でユダヤ人そのものを指すことから,徐福ユダヤ人説は否定しようないだろう。ということで,改めて佐賀県の地図を見直してみると,三(3)のつく地名がやたらに多いことに気づかされる。ユダヤ人にとって三は基本数字であり,ダビデの星は三角形を重ねたもので,三種の神器があり,キリスト誕生時の東方の三博士から後の三位一体にまでつながるのである。さらに,吉野のヨシというのは,ヘブライ語でイエスをヨシュということがもとになっているともいわれるので,熊野と大和の間の吉野が,吉野ヶ里とつながるユダヤの道であるとも言える。「ヶ里」のつく地名は,律令制による区画整理がされた土地を示すというから,後述するように,神話体系がまとまる時代と重なることも,その証になるだろう。
神武天皇の倭名のカムヤマトイワレヒコの,ヤマトが邪馬台国を意味するのは勿論,繰り返しになるが,イワレは古代ヘブライ語でユダヤ人そのものを指すことから,徐福ユダヤ人説は否定しようないだろう。ということで,改めて佐賀県の地図を見直してみると,三(3)のつく地名がやたらに多いことに気づかされる。ユダヤ人にとって三は基本数字であり,ダビデの星は三角形を重ねたもので,三種の神器があり,キリスト誕生時の東方の三博士から後の三位一体にまでつながるのである。さらに,吉野のヨシというのは,ヘブライ語でイエスをヨシュということがもとになっているともいわれるので,熊野と大和の間の吉野が,吉野ヶ里とつながるユダヤの道であるとも言える。「ヶ里」のつく地名は,律令制による区画整理がされた土地を示すというから,後述するように,神話体系がまとまる時代と重なることも,その証になるだろう。吉野ヶ里遺跡は,発掘が進むにつれ,邪馬台国の都に相応しい施設群を有していたことも明らかになりつつある。紀元240年には,帯方郡使が詔書・印授のための正式な冊封使として,邪馬台国の王都(おそらく吉野ヶ里)まで赴いており,卑弥呼が没したのは247,8年頃と言われるので,在位期間は60年以上,二十歳頃になったとしても,90歳近い長寿であったことになる。卑弥呼は故地伊都国に還ったともいわれ(近年,糸島で発見された平原遺跡が,卑弥呼の墓ではないかといわれる),東征したのは男王すなわちオシ系の崇神天皇ということになるのだろう。次章で述べるように,崇神東征は,南九州から熊野という南海道ルートであるが,アマ系の人たちは九州北部から丹後,尾張に至るように,山陰・山陽道のルートであって,両者は近畿において再会,伊勢神宮が誕生する。
北九州の八女丘陵にある古墳群のうち童男山古墳が徐福の墓ではないかという説も登場,最近,卑弥呼の鏡といわれる三角縁神獣鏡が極めて精度の高い魔鏡であると分かり話題になったが,これもユダヤ人の技術によるものと見れば納得できるし,その鏡の威力が,天照大神のご神体の八咫鏡になり,さらに,三種の神器という象徴化そのものがユダヤを継承するものなのである。
邪馬台国があった当時の絹織物の出土は九州北部北部に限られ,中国への朝貢品にもなったことから,邪馬台国が日本列島において唯一の養蚕・絹織物の国であり,秦帝国とのつながり,すなわち徐福集団によってもたらされた技術であることは疑いないだろう。偽書説もある史書に,卑弥呼は白山比咩神社の娘と書かれているのも,養蚕と絹織物につながる民族の出であったことを示すもので,中国でそこから太陽が昇るとされる宇宙樹"扶桑"は,そのまま日本についての異称になったが,ここに桑の文字が入っていることにも,養蚕民族との関係,徐福・秦氏などとの関係が窺える。
また,当時は大変な貴重品であった真珠を多量に朝貢していたことも知られているが,生産適地としては末盧国の範囲しか考えられず,すでにその地を支配していたということを示し,近代に入って養殖真珠の産地となった志摩地方に,的矢(マトヤ)湾があるが,マツ系が東遷する際に,末盧と名付けられた可能性も考えられる。さらに,邪馬台国は当時の先端文明鉄器の国でもあり,これによって諸国を服属させたと考えられるが,朝鮮半島南部で倭の領域であったとされる辰韓・弁韓が有数の鉄鉱石の産地であったといい,おそらく邪馬台国が諸国制覇するのに合わせて組み込んでいったと思われる。北九州の製鉄遺跡についての最近のC14調査では,そのいくつかは紀元前200年前後であったということなので,まさに,徐福渡来の時期と符合する。
邪馬台国のイメージをさらに深めるため,萩原秀三郎「稲と鳥と太陽の道~日本文化の原点を追う」による知見を,コラムに示しておく。
ロ:ナカ系に支えられたオシ系が,アマ系を戴く形が,日本神話の原型になる>神様の家系図
徐福の子孫(オシ系)は,卑弥呼の先祖になる伊都国支配下の一大国(アマ系)の人たちとともに,まさに,アマから来たことを示す地名の甘木(アマギ)の地に,ひとまず定着,やがて吉野ヶ里に出て,邪馬台国を開いたのが,神武天皇ということになるが,その時すでに,のちの,卑弥呼のように,アマ系の巫女的女王を戴く形で統治したと考えられる。天皇神話の祖アマテラス大神は,卑弥呼に対応するとされるが,その子がアメノオシホノミコトになっているように,アマ系とオシ系が結びつけられている。
奴国のところで述べたように,邪馬台国において,周辺諸国と同じ官職とは別に,付け加えるように置かれた職名にナカチの語が見えるのは,おそらく,徐福渡来の時に世話になり,古くから日本の代表していたと思われる奴国(ナカ系)を服属させた時に,とくに祭祀を扱う役職として,中臣氏を取り込んだものと考えられる。そのことが,天皇神話以前のすべての神々の祖たる,造化三神の第一つまり最高神が,アマ系とナカ系を合わせたアメノミナカヌシになっていることに反映していると思われるが,ここでも,第二のタカミムスビノカミが,徐福のことを指しているという説があり,終章で示したように,そのように見ると,そこから派生する神々の存在が矛盾なく説明できるのである。なお,第三のカミムスビノカミは,その他もろもろの神々をまとめる役割をしている。
改めて確認できるのは,日本神話の原郷に当たるのがアマ系を支配する伊都国で,徐福が渡来して滞在した場所が伊都国の日向(ヒムカ)の宮であったことは既に述たが,さらに驚かされるのは,糸島半島のすぐ前には能古(ノコ)島があり,宗像三神や壱岐・対馬と同じ角度で,玄界灘の方に線を延ばすと,そこには小呂(オロ)島があって,イザナギ・イザナミのミコトの国生みの地,オノコロ島は,この二島を組み合わせた名なのである。石井好が言うように,イザナに当てられた漢字伊邪那が,伊都国・邪馬台国・奴(那)国を合わせたものであるとすれば,もはや否定することもできないだろう。さらに,付け加えれば,伊都国の官のトップの職,爾支(ニギ)は,神武天皇の祖とされるニニギノミコトに対応するもので,徐福一族そのものを指しているに違いない。
ところで,中国の山東省で,道教が宗教的な体裁を整えたのが,ちょうど卑弥呼の頃で,卑弥呼が中国に使いを出したという話もあるというから,徐福の子孫の神武皇統において,日本神話の骨格がつくられたことが想像できる。道教における最高神は三清といい,元始天尊,霊宝天尊,道徳天尊の三神であるが,なんと,そのまま日本神話の造化三神の,天之御中主神,高御産巣日神,神産巣日神に対応し,神の名でミコトを表す際の漢字に"尊"を用いることなど,その影響は明らかだ。なお,道教でも,三清はじめ,三気,三才,三君,三界三十六天など,ユダヤ人と同じように,すべてを三の倍数で組み立てるというから,山東省が徐福の故郷であることもふまえると,両者は深く関わっていると考えざるを得ない。
ハ:卑弥呼の死でアマ系と離別,オシ系神武(実は崇神)は東征して,大和朝廷を産む
当然のことであるが,離反した伊都国との緊張関係は続いたため,後の大宰府の地が邪馬台国の北の砦的な役割を持つことになり,伊都国はまた大陸の出先でもあったから,そのまま,日本における大陸への防衛線になっていったと考えられる。「魏志倭人伝」に記述されているように,倭国大乱後,邪馬台国は女王卑弥呼を立てて収めたとされているが,内倉武久によれば,この大乱の相手はまさにその伊都国だったという。この乱は,140年頃から180年頃にかけて続いたらしく,卑弥呼が女王になったのは決着した180年頃と思われ,この時から,邪馬台国が倭を代表する国,それも大国的存在になったと考えられる(それまでは中国とつながる伊都国のみ)。この内乱などで,多くのアマ系が東進し,卑弥呼の死去後は九州北部諸国全体の秩序も崩壊して,イト系民族も東進して,前述の平氏になった人たちであったと考えられるが,次章において解説する。
伊都国は大乱後衰えたとはいえ,油断ならない敵であり続けたため,「魏志倭人伝」で,伊都国から邪馬台国に至る行程が分かりにくくなっているのも,大宰府の地が通過できず,遠回りして行ったと考えれば氷解する。また,伊都国には中国風の名称の一大率(天子直轄の軍隊)がいたといわれるが,強国になった邪馬台国が,奴国はじめ諸国を服属させていくなかで,中国の権威を背景とする伊都国の反乱を抑えるために置いたものともいわれる。邪馬台国では,卑弥呼が神の託宣を受け,弟たる者が権力を行使したとされているが,その弟が神武皇統すなわち徐福の子孫で,卑弥呼が魏と円滑に話をすることができたのも,その存在を抜きには考えられないだろう。⇒コラム(「吉野ヶ里」こそ邪馬台国の都(1989年記))
大宰府については,近年,発掘調査が進み,朝鮮の扶余羅城と同じように,一つの街を城壁(土塁)で囲み,周辺から独立したものであるとされるようになった。「日本書紀」には,大宰府が,滅亡した百済の遺臣によって建設されたと記されており,百済の王族が,高句麗の王族扶余氏の分派であったことから,極めて自然のことだったと思われる。ただ,この地につくられるにあたっては,それ以前に,大宰府と同じような役割をするものがあったと考えられるが,それが,「魏志倭人伝」に指摘されている一大率であったという。「魏志倭人伝」には,「女王国は,北側に一大率を置いて厳しく検察,諸国はこれを畏れて気を使っている」と書かれており,女王国とは卑弥呼の国,すなわち邪馬台国であるから,伊都国の監視が最大の目的であったとみなされる。つまり,「魏志倭人伝」における,伊都国から邪馬台国の距離が,やたらに長い日数になっているのは,直接向かうことができず,諸国も気を使っていると分かれば,矛盾は無くなるのである。そして,邪馬台国をつくったのが,徐福の末裔と,徐福が連れてきた物部氏であり,その物部氏が扶余氏であると知れば,すべての話がつながるのである。念のためであるが,卑弥呼は,伊都国支配下の一大国の人間であり,伊都国は一大国によっても支えられていたから,邪馬台国との間の関係は極めて複雑かつ緊張したものであったのである。
倭国大乱後,男王では収拾つかず,女王卑弥呼を立てて決着したのが,その後の天皇制につながる日本独特の支配方式のルーツで,おそらく徐福一族の智恵であっただろう。もともと,ユダヤ人は,移動した先では,その地の言語を使うようになり,権力を狙うようなところは無く,権力をサポートすることで自らの集団を生き延びさせてきた。ユダヤ人はまた,民族が形成された当初は,養蚕も含む農耕民族であったことから,すでに九州北部に広がっていた稲作農耕民族と調和できたともいえよう。迫害を受けて流浪するようになったユダヤ人は農耕することができなくなり,神の名のもとに団結して民族を継続,やがて商業民族となって,シルクロードの担い手となり,さらに権力との関係で金融業に活路を見出し,それがまたヨーロッパでの迫害の理由にもなったが,押上の地名のところで取り上げた三井に限らず,オシ系,のちには,ハタ系というユダヤ人の血をもった人たちは,大航海時代に多数渡来したと思われるユダヤ商人に触発されて,江戸の繁栄をもたらしたことについても頭にいれておきたい。
ところで,統治の基本は,"技術"と"文字"と"神"といわれるが,徐福一族は多くの先端技術と神をもたらす一方,地域に溶け込むという特性から文字については出てこない。しかし,その後の現在に至る日本語表記は,世界でも例をみない平仮名・カタカナ混じりになっていて,それが漢字からつくられたものであるはいいながら,なぜそのような文字が簡単に生まれたのかについて,ユダヤ系秦氏のヘブライ文字の記憶があったからではないかという説があり,仮名をつくったのが秦氏出身の空海であるという伝説もそれを裏付けるものかもしれない。さらに,アメリカ大統領を迎えた時の,宮中晩餐会のメインディッシュが羊の肉であるということが,天皇家のルーツが,羊を食する民族であったことを示し,ユダヤ人であっても不思議ではないことを示している。
この章TOPへ
ページTOPへ
第3論:オシ系の神武(実は崇神)東征による大和国家形成~崇神皇統
第1話:徐福に従って渡来した技術者集団物部氏の東進(フヨ系)
イ:物部氏の出自は,ツングース系扶余氏
ここまで,徐福が引き連れてきた数千人の技術者集団について全く触れてこなかったが,中国がのちに朝鮮半島を管理すべく置くことになる山東半島の向かいの帯方郡あたりにいた有力な扶余氏一族こそ,最古の氏族物部氏だった可能性が高い。そこで,扶余氏とはどんな民族であったかを,とりあえず紹介しておこう。
Wikipediaをベースに述べると,扶余氏は,ツングース系で,現在の中国東北部(満州)を本拠としていた民族およびその国家で,夫余とも表記される。扶余が建国する以前のこの地にはツングース系の有力な氏族ながら,国をつくることのなかったワイ(濊)族が住んでいたと思われ,遺跡も発見されている。扶余氏に排除されたワイ族は,後述するように,南方の朝鮮半島に移動し,新羅人のルーツになったと考えられる。
扶余系騎馬民族が,南朝鮮を支配し,その後弁韓から日本列島に入り,大和朝廷の前身になったとするのが,江上波夫が提唱した騎馬民族制服王朝説で,現在では,かなり否定されているが,江上が,諸資料に基づいて,扶余系としたことは,それほど日本への影響の大きかった民族であるということで,物部氏が扶余系であることを補強するものといえるだろう。
扶余国は,その後も,三国時代から北魏の時代まで存在したが,494年,勿吉に滅ぼされた。夫余族の苗裔(北扶余)は豆莫婁国と称して唐代まで続いた。「魏書」や「三国史記」によれば,高句麗の始祖朱蒙も扶余の出身であり,衆を率いて夫余から東南に向かって逃れ,建国したという。言語学的にも,扶余語は高句麗の言葉に同じだったようだ。「三国史記」や「三国遺事」には,解夫婁が治めていたがのちに太陽神の解慕漱が天降ってきたので解夫婁は東に退去して別の国(東扶余)を建てたといい,太陽神,東征など,のちの日本の姿にもつながる。扶余氏はのちに高句麗を建国,さらにその分派が百済を建国することになるが,その際も,単に南方に下ったのではなく,中国から山東半島経由で朝鮮に渡ったといわている。扶余氏によって建国された百済が,ワイ族がベースの新羅と相容れないのは当然といえよう。
扶余の生業は,アワ・ヒエ・キビ等の雑穀を主とした畑作農業であり,遺跡では早い時代の層からも大量の鉄製農具が見つかるなど,農業技術や器具は,同時代の東夷の中で最も発達していた。また,金銀を豊富に産出する土地であり,金属を糸状に加工して飾り付けるなど,金銀の加工に関しては非常に高い水準だったとされる。紡績に関しても養蚕が営まれ絹や綵など様々な種類の絹織物が作られたほか,麻織物や毛織物が作られ東夷の中で最も発達していたとされる。物部氏は,これらの技術を日本にもたらしたと考えられる。

ロ:物部氏の東進~技術とともに,神話(神道)も伝えた
その後さまざまな職種を表す部全てを総括するような物部の名こそ,この時渡来した最も古い氏族に相応しいものだろう。物部氏は鉄器という先端的なものによって,旧来の銅器民族を制圧した軍事を司る氏族とされるが,鉄器はまた農業生産にも画期をもたらしたので,徐福一族が九州北部を一気に支配することになったのは言うまでもない。物部氏はさらに,道教を背景にしたオシ系による神話と祭祀をも差配する,つまり神道の主宰者にもなり,そのことが,のちに蘇我氏に滅ぼされる原因になるのである。かつて単なる装飾品のように考えられてきた勾玉が測量機器らしいこと,三種の神器のひとつの鏡が太陽の動きを測定するためのものらしいことなども,物部氏の先端性を示しているのではないだろうか。
邪馬台国に諸国を服属させる功績をあげたのも物部氏であったが,人数が多かったこともあって,渡来直後から東征始め,まず,遠賀川流域にあったと見られる投馬国(物部氏に関わる遺跡が多数存在する)を拠点にするが,投馬国が百済と関係深いことは,大和のマツ系の葛城氏の領域にある当麻(タイマ=トマ)寺が百済人の氏寺であったことでも推測できる。そこから,瀬戸内を東へ進んで,おそらく吉備で拠点を設け,そこに定着した人たちが吉備氏になる(後の大人物吉備真備も物部氏らしくあらゆる面に秀でていた)。
傍証として,吉備氏がヤマトタケル(オシ系)と密接につながっていたらしいこと,吉備の地もまた日向のような土地であり,付け加えれば,日向の国は勿論,前述の現在の埼玉県行田の忍(オシ)の地も日当たりよく開けた平野で,近畿以外ではほとんど限られる巨大な前方後円墳が存在していること(そもそも,邪馬台国の都と考えられる吉野ヶ里も日向の地であった)などが挙げられる。三橋健編の「日本書紀に秘められた古社寺の謎」によれば,天理市にある石上神宮は,「古事記」のなかで,伊勢神宮以外に「神宮」と称された唯一の神社で,崇神天皇の時代に創建され,布留御魂神(フルノミタマノカミ)を祭神とするように,朝廷の武器庫のような役割をして,神宮に対応する格をもった物部氏が管掌していたが,岡山県赤磐市,すなわち,かつての吉備国のなかにある石上布都魂(フツノミタマ)神社から勧請したものといわれ,吉備氏は,物部氏と同族であったということが明らかであろう。
さらに東進して大和に入るに際しては,自らの先端技術などを武器に,その地を支配していたマツ系の長髄彦を支えて行くことになり(「記」では長髄彦の妹と結婚),その地を邪馬台の語に対応するよう大和と名付けたのである。良く知られているように,邪馬台国周辺に現在でも残る地名群が,まるで転写したかのごとく,大和盆地に存在していることもその証となるだろう。
「日本書紀」でも,物部氏の祖ニギハヤヒが神武天皇より前にヤマト入りし,そのことを神武天皇も知っていたとされているので,実際に東征してきた崇神天皇を迎え,その支配を円滑に実現するのに貢献したといえる。大和における物部氏の拠点が河内国との境生駒山周辺であったことも,西側から渡来して力を確保するには当然の地であった。また,「先代旧時本紀」によると,中臣氏は物部氏の支配下にあったとされているので,ニギハヤヒが大和入りする時に,中臣氏が供奉してきたとされていることも裏付けになるだろう。後の話になるが,中臣氏は単に天皇側近として神事を担当していたようで,もう一つの神祇職斎部氏が職務を中臣氏に奪われたことも,物部氏の力が減じたことと関係するようであり,さらに,中臣氏を利用した藤原氏が台頭するにあたって,物部氏の秘密を受け継いだとされることにも,大きな意味があると考えられる。
物部氏は,ヤマトの語に深く関係し,すべて倭名にヤマトがつく神武朝に対応するが,崇神天皇の後の天皇からは,倭名にヤマトがつかなくなるので,物部氏の力が相対的に弱くなったと考えられる。しかし,崇神朝では,天皇にならなかった日本武尊というヤマトの語をもつ特別な存在があり,物部氏の力をどうしても借りねばならなかったことが伺える。藤井耕一郎「サルタヒコの謎を解く」で指摘されているように,ヤマトタケル伝説のルートとマツ系民族の展開するルートは大きく重なっていて,クマ系民族はじめ,国譲りしたはずのマツ系民族による反動を抑えることがその役割だったと思われる。
大和で邪馬台国時代の前方後円墳が発見されたとして,邪馬台国が大和にあったとする言説があるが,規模は小さいし,今まで述べて来たように,邪馬台国が北九州にあった神武皇統時代に,すでに物部氏が大和入りをしているので,神武東征が実は崇神東征であったとみれば,全く矛盾なく説明できまよう。さらに,前方後円墳が最も多く残っている茨城県,すなわち常陸の国はまた,那珂川があるように,ナカ系の人たちが多く到来した地でもあるが,邪馬台国が奴国を服属させて以降,物部氏の東遷にナカ系の人たちが大いに協力したと考えられ,また,後に藤原氏の神社とされる鹿島神宮が実は物部氏のものであったということも当然といえよう。
付け加えれば,(西都原,吉備,さきたまなど)オシ系の陵,大和でも天皇陵は大規模なものが多いのに対して,物部氏のそれは,数は多くとも規模は小さい。
ハ:鈴木氏はじめ,全国に展開し,様々な技術を伝えた物部氏の末裔たち
蘇我氏に討たれて後も,わずかながら物部姓が残っていて,日本史上の大学者の一人で,中野剛志によれば,徹底したプラグマティストであったという荻生徂徠の本姓は物部氏であったし,秋田出身の大土木学者物部長穂は自らの出自を強く意識していた。物部氏の流れの最初の姓は石上氏であり,その他,穂積,内田,大宅氏などが直系といわれる。穂積氏については,継体天皇に仕えたものに,穂積押山という人物がおり,まさに,オシ系としての役割を果たしたのではないかと思われる。
全国の姓の分布からみると,藤原氏から派生したことで多いのは当然のような"佐藤"姓に次いで多い"鈴木"姓は,その本家が熊野で,物部氏直系の穂積氏をルーツとしており,家紋は実に,オシ系徐福を表すというタカミムスビの神から派遣された八咫烏であることから,その通りであると考えられる。その分布をみると,東海,関東,東北に広がっているが,西日本には極めて少ないことが,蘇我氏に討たれたことを,そのまま反映している。とくに,三陸方面への展開が知られ,気仙沼の古舘鈴木家は,1675年,紀州熊野から鰹釣り溜漁を伝え,のちに漁業や醸造業など,時代に合わせた多角的な家経営を展開し,江戸時代には,鹿折金山などの金山開発や砂金徴収を任され,明治時代には大谷鉱山の再開発も手掛けている。そして,気仙沼地域の言葉が独特で,ケセン語とまでいわれて,古代ヘブライ語との類似も指摘されているが,(前述のように)神武東征,つまりオシ系の上陸地になった新宮には,古代ヘブライ語が今も残っているということなので,そのつながりも明らかである。
いずれにしても,"鈴木"姓が,2番目に多いことは,それだけ広く,様々な技術を各地に伝え,(農水産業の生産方法も含めて)現代の技術立国日本に繋がって行ったことに対応しているといえよう。ちなみに,歴史的人物から,鈴木姓を拾ってみると,異色の国学者鈴木朖,ビタミンを発見した鈴木梅太郎,仮名草子の先駆者鈴木正三,音楽教育スズキ・メソッドの鈴木鎮一,禅を世界化した鈴木大拙,錦絵を創始した鈴木春信,労働運動指導者鈴木文治,「北越雪譜」の鈴木牧之,「赤い鳥」の鈴木三重吉と,幅広い分野に人材を輩出している。
第2話:伊都国崩壊で東進し,大和国家の支配に微妙に関ことになる海部・尾張氏(アマ系)
イ:脱九州(オシ系の南ルートに対して北ルート)
卑弥呼が死すると,長年対立してきた伊都国との間の歯止めがなくなって,本格的戦争になり,アマ系を支えるオシ系という邪馬台国の根幹が崩れ,周辺諸国も巻き込んで,それまでの九州北部の国の間の秩序が崩壊,「魏志倭人伝」によれば,倭国は,弟王を立てるも収まらず,卑弥呼の宗女だったという臺與(台与・トヨ,235年生まれで13歳だったという)がたって,ようやく決着したというが,以後,中国の史書からは,邪馬台国はもちろん,他の諸国の記述も消えてしまう。オシ系とアマ系は別離を余儀なくされたのである。
このことから,弟王とされるのが,オシ系の崇神天皇,いわゆる神武東征伝説の当事者で,次節で述べるように,南九州ルートで東進し,大和に至ったのに対して,トヨの登場で収拾したとあるのは,アマ系は,トヨの名が示すように,日田を経由して,豊の国(のちの豊前・豊後)に至り,定着したものと考えられる。そして,豊の国に向かわなかった,イト系率いるアマ系の民は,オシ系とは全く別に,北ルートで,丹後に至り,そこで,大和に東征してきたオシ系崇神天皇と連絡がつけられて,両者は再び結ばれることになるが,アマ系は,伊都国の末裔でもある故,様々な曲折が,アマテラスを祀る伊勢神宮定着までの転変に反映することになる。
第4論で述べるように,豊の国は,新羅からハタ系応神天皇が渡来した時の受け入れ地となり,秦の国がつくられるとともに,応神を祀る宇佐八幡宮が創建され,応神の妃となったアマ系が宗像三女神でとされることになり,九州に残ったイト系・アマ系は,のちの倭寇の核になって行ったとみて良いだろう。>前期倭寇
ロ:東進して,丹後に至り,オシ系の天皇と再会,伊勢神宮が成立する
イト系率いるアマ系の民は,現在の地名にもその名が示される,板付から,糸田を経て,山陽道に向かい,すでに述べたように,イト系の末裔平氏の氏神・厳島神社は,もとは,伊都岐島と記されていたように,まさに,伊都国から来たことを示し,すぐ近くには。アマ系の海部郷,阿満もあるのである。そこから,一団は,山陰に向かい,イト系の到達を示す但馬国糸井郷を拠点に,アマ系が,丹後の地に広く展開,もう一団は,紀伊国伊都郡を経て,伊都にも通じるという伊勢に至り,丹後のように,アマ系は尾張国海部郡周りに展開,ヤマトタケルノミコトを祀る熱田神宮大宮司を代々務めることにもなる,古代における大豪族の尾張氏の祖になるのである。イト系の本体が,さらに東進して到達したのが,伊豆であり,坂東平氏の拠点になったのである。丹後の国は,浦島太郎伝説の地であり,半水上集落と言っても良い独特の景観をした伊根があるなど,まさに,海洋民族の国である。>桓武平氏
唐突であるが,今年(2022年),阪神タイガースを引退して話題になった糸井選手に,超人伝説があるのは,その野球の能力以上に,体躯,風貌のなせるわざと思われる。そこで,彼の出身地を調べてみたところ,京都府の日本海岸の与謝野町ということで,その西隣は,兵庫県の出石と朝来,まさに,但馬国糸井郷の地で,現在も糸井の名のつく施設等が分布している。糸井選手には,伊都国の王族の末裔,桓武平氏の血が流れているのだろう。桓武平氏の代表平清盛や,自ら桓武平氏と名乗った織田信長らは,八頭身の大柄な体躯であったといわれ,糸井選手は,その姿を彷彿とさせているのではないだろうか。
ところで,丹後には,元伊勢神宮なるものがあるが,崇神天皇39年の時に,アマテラス大神を,丹波の吉佐の宮に遷したという伝承になっているものの,アマ系の地としては,当然のごとく,卑弥呼を祀っていたと考えられる。崇神天皇紀では,大和で疫病がはやった時,土地の神ヤマトオオクニタマとアマテラスを同じ宮殿に祀るのは良くないということになって,皇女のトヨスキイリ姫に命じて,アマテラスを北方の笠縫に遷し,次代の垂仁天皇が,ヤマトヒメ命に命じて,大和から連れ出し,近江・美濃など各地を遍歴した後,伊勢の五十鈴川のほとりに定着したとされていることから,オシ系とアマ系は再会はしたものの,邪馬台国の時代をそのまま再現するには無理があったと思われる。
丹後にはまた,籠(コモ)神社という神社があるが,太秦の蚕の社と同じく,秦氏の氏神であったといい,アマ系が,ハタ系の応神天皇渡来時に,天皇を支えたことを思えば当然であるといえる。その籠神社のもととされる,真名井神社には,豊受大神が祀られていたが,この神こそ,卑弥呼の後を継いだ台与(トヨ)であり,伊勢神宮の外宮が豊受大神宮といわれることに対応,応神朝になって,台与を,卑弥呼と対等な神とすることで,ようやく修復が成り立ったともいえ,ここにも,神社体系を確立させたのが秦氏であったことが示されるといえる。伊勢外宮の祭祀に長く関わった磯部氏(渡会氏)は,磯城県主の流れをくむ丹後国造の支流ということも,補強材料になろう。

ハ:さらに東進して,独自の存在になった尾張氏
上古代に后妃を輩出した尾張氏は,中央で政治力を発揮したことがほとんど無いにもかかわらず,同族を名乗る諸氏が極めて多い,地方豪族としては特異な存在で,西方から来た海人ではないかということまでは共通認識になっているようであるが,あまり研究されていない謎の氏とされている。そんなところに,澤田洋太郎が「天皇家と卑弥呼の系図」の冒頭で,尾張氏の系図が,海部氏のそれと似ているばかりでなく,その何れにも,卑弥呼を表すとみられる日女命の名のあることから,同族であると指摘,前項の図も,それに基づいており,尾張の地は,伊都国アマ系の人たちが到達した最後の大拠点であると推定したのである。それが成り立つかどうか,古代氏族の研究シリーズの宝賀寿男「尾張氏」のページをめぐりながら,検証してみよう。
確実なところでは,継体天皇の妃で,安閑・宣化天皇を産んだ目子媛が尾張氏の出であり,壬申の乱に際しては,海部氏(アマ系)に養育された大海人皇子を全面的に支援して,天武天皇を誕生させ,熱田神宮宮司家としては,近代まで続くのであるが,偽書説があるとはいえ,「旧事本紀」の「天孫」の部では,アマテラス,アメノオシホ,ニギハヤイの次に,尾張氏の系譜,その次に物部氏の系譜を示しているのは,すでに述べたように。アマテラスすなわち卑弥呼を戴く,アメノオシホすなわち徐福(オシ系)の末裔の国邪馬台国とすれば,アマテラスに直結する尾張氏が,徐福を支えて渡来した物部氏より上位に置かれているのも当然であろう。そして,尾張氏の直接の祖とされる成務天皇時代の尾張国造の乎止与(オトヨ)命は,小豊とも書かれることから,卑弥呼の後を継いで豊の国をつくることになった台与の子孫であることを示している。
上古代に后妃を輩出し,平安時代にも,尾張氏に対して,容貌端正な者を采女を,毎年1名貢進するよう命が出ているように,卑弥呼以来,アマ系の女性の存在は際立っていたのだろう。6世紀前半になって,突然,尾張に巨大な古墳が一基だけ出現するが,時期から見て,その断夫山古墳(151mで65位)は,継体天皇の太田茶臼山古墳(226mで21位)との関係からも,妃目子媛の陵と考えられ,尾張氏が,継体天皇の実現に如何に大きく貢献したかを示している。壬申の乱に際しての尾張氏の支援は,美濃国の野上(伊富岐神社隣)に行宮を提供して,不破の関(関ヶ原)を抑えることができるようにしたことが大きいといわれるが,そこには,尾張氏一族の伊福部氏がいた(イブキに対応すると思われる姓。現在,伊福部姓は,全国で数十名しかいないが,著名人は数名おり,その比率は異常に高い)。
尾張氏の系譜のうち,とくに難解なのが,オシ系高倉下につながる神統譜とされているが,これを,オシ系の崇神東征後,尾張を拠点とするアマ系に再会したことを表すものとみれば納得いくのではないだろうか。伝承では,尾張大海媛が,崇神天皇の妃になったことが記され,これこそが,再会の実であったろう。そして,大海媛の生んだ娘の一人が,前後関係はおかしくなるが,崇神天皇の同母姉(妹)で,卑弥呼その人ではないかともされる倭迹迹日百襲姫の同人か近縁とみられるのも,再会説を補強することになろう。ついでながら,初期大王(いわゆる欠史八代)の后妃伝承をもつのは,それこそ,邪馬台国時代に,オシ系の王がアマ系の女王を戴いていたことを示すものだろう。⇒コラム「卑弥呼の倭迹迹日百襲姫命説の妥当性について」
とはいえ,天武天皇後,政治的な力は発揮されず,熱田神宮の神階授与も,平安時代になってからで,822年,従四位下が初見で,859年には,正二位と昇叙,延喜式で,ようやく正一位の名神大社となっており,それでもなお,尾張一ノ宮ではなく,三ノ宮に留まっているのである。この熱田神宮に関わるのが,ヤマトタケル伝説であるが,「古事記」には,ヤマトタケルが東征の途上,伊勢から尾張に至り,国造の祖・美夜受比売(ミヤズヒメ)と結婚しようとしたが,帰還後と思い直し,科野(シナノ)から戻って結婚したとある。いずれにしても,ヤマトタケルの東征に,尾張氏が大きな役割をしたことを示すものである。また,東征において,のち壬申の乱同様,伊吹山が特別な場所であったことは言うまでもない。5,6世紀に,尾張東部丘陵地に,大型の前方後円墳が多く築造されるが,海産物や海上輸送に貢献した尾張氏のものと考えられる。
尾張氏は初期段階で,北部や美濃の丹羽県君氏と通婚して,開発に努め,次第に南下して,当時,海に突き出た岬状の熱田に達し,到達点としての意識もあって,熱田神宮のもとを創建したと考えられる。前項で述べた,アマ系の到達地の丹後は,もともとは広大な丹波の国の一部であったこと,丹波はタニハの当て字で,そのまま,丹羽姓にもつながるとみられることから,丹後に留まらなかった,イト系,アマ系の人たちは,そのまま東進,近江を経て,関ヶ原,伊吹山方面に至り,南下していったと考えるのが自然だろう。そして,イト系の人たちは,伊豆に向かったのである。大和の尾張氏の分布状況からみて,尾張氏は,大和から尾張に遷ったのではなく,尾張から大和に移住するものがでてきたということになろう(すでに述べたように,崇神東征前の大和の地はマツ系の人たちの支配地であって簡単には入れなかったとも考えられる)。
ところで,熱田神宮は,かつては尾張造という,回廊を有する左右対称の,朱色に塗られた建築群であったというから,アマ系としては,自分たちの従ってきたイト系の氏神厳島神社をまねたようなものであったのではないだろうか。
ずっとあとの水軍のところで述べるが,伊勢平氏の末裔ともみられる九鬼嘉隆は,尾張氏の末裔であるという(伊勢あたりは,イト系とアマ系がなお一体であったらしい)。赤い彩色と紋様を持つパレス式土器は,弥生時代後期の尾張地方を代表,三河,尾張,伊勢一帯に広がる,尾張氏,海部氏に関わる重要な土器で,東海地方に多い古墳のスタイルや,多孔銅鏃との関係も指摘されており,土師氏との関係,のちの陶器生産との関係も気になるところである。
いずれにしても,尾張氏の存在が,のちのち,この地域での大武将の輩出につながるものの,日本のほぼ中央に位置しながら,一度も,首都にならなかったことに関係があるように思われる。
第3話:アマ系と別れたオシ系の神武(実は崇神)東征によって大和朝廷が始まる
イ:脱九州(イト系・アマ系の北ルートに対して南ルート)
卑弥呼没後の大動乱で,諸国が崩壊し,それぞれが東進することになるが,アマ系を戴くオシ系という形だった邪馬台国では,イト系の支配下にはいったアマ系とは一旦離別し,彼らが瀬戸内から,近畿,山陰方面に展開する北ルートをとるのに対し,オシ系は,神武東征神話で知られているように,南九州から熊野へと,南ルートをとることになる。
邪馬台国,すなわち神武皇統の時代はその南の狗奴(クナ)国との紛争が絶えなかったというが,その間に,そのクマ系民族のなかから,大伴氏という,東征を警固してくれる強い氏族を味方につけることに成功している。大伴氏も,もとはクマ系そのものを示す久米氏であったから,大伴の名は,まさに大いなる伴(警固者)という意を表して,神武皇統によって与えられたと考えられる。ヤマトタケル伝説は,おそらく邪馬台国が狗奴国との長年にわたる抗争の末,ついに狗奴国を征圧したことを伝えるもので,その結果,いわゆる神武東征,実は,崇神東征は,まず,九州西部を南下し,徐福伝説の代表地の一つ南九州の串木野から霧島を経て,日向に至ることになる。
そのルートを詳しく見てみよう。吉野ヶ里の地,現在の佐賀県から九州西海岸を南下して行くと,まるで目印となるように串木野の冠嶽(徐福が冠を納めたからこの名がついたといわれ,後述の四国祖谷の剣弥山あるいはキルギス・オシのソロモン山のような存在と言える)が見え,そこから川内川を遡って,霧島の高千穂峰(霧島神宮がかつてあった場所で,山頂には,坂本竜馬が引き抜いてその豪胆ぶりを示した天の逆鉾もある)に至る。天孫降臨したと伝えられるクシフル山は宮崎県北の高千穂とされているが,実は,日向(ヒムカ)の地は,伊都国(糸島)であったことが判明しつつあるので,あまり気にしなくて良いだろう。東の宮崎に下った麓には,神武天皇の名を示す狭野神社があり,近くの曽於市末吉の深川熊野神社には,神武東征と関係すると思われる奇習「鬼追い」が伝えられている。そこから,押田(古くからの村に一旦居を定めたらしく「オシ」系地名になっている)に出て,宮崎県の大淀川に沿って東へ向い,神武天皇が東征前に宮を営んだとされる地に建つ宮崎神宮の場所に至ったと考えられる。鹿児島県から宮崎県にかけて,串木野,串良,串間とクシのつく地名が連なり,神武東征伝説での上陸地熊野にも串本があることも,そのまま東征ルートを示している。
とくに強調したいのは,串木野の冠嶽で,1990年頃に高野山の僧が新たな寺を開創したが,その伽藍建設工事に多くのイスラエル人が参加していたことからも,徐福がユダヤ人であったことは疑いなく,ユダヤ系の秦氏の出身という高野山の祖空海も,聖徳太子以上の頭脳の良さが伝説化しているように,ユダヤ人の血を引いているといわざるを得ない。なお,若狭の徐福伝説の地は冠島で,串木野の冠嶽に対応するものだろう。
長田夏樹「新稿・邪馬台国の言語~弥生語の復元」によると,卑弥呼について,当時の中国音なら"ヒムカ"になるといい,伊都国の日向そのものということになる。神話の国とされる日向国(今の宮崎県)も卑弥呼に由来,卑弥呼の娘臺与(トヨ)の名を示す豊の国とも繋がっていたと考えら,熊襲征伐時に誕生した豊国別皇子が日向国造の祖になっている。この,日向国と豊国との繋がりが,後述の,崇神皇統と応神皇統への政権交代が円滑に行われたらしい理由になるのではないかと思われる。西都原には皇室司祭賀茂氏の荘園があったし,物部氏が支配していた吉備を,物部氏を討滅した蘇我氏が再開発したこともあったらしく,蘇我馬子が聖徳太子とともにまとめたとされる「天皇記」「国記」は,蘇我氏支配の正当性を確立するための創作された歴史で,この段階で,崇神朝の故郷日向国と応神朝の故郷豊の国が一体のものになるようになされたことも含めて,のちに藤原不比等が藤原氏支配の正当性を確立すべく「古事記」「日本書紀」をまとめたモデルになったと考えられる。
ロ:そのルートは,狗奴国から熊野への照葉樹林帯であった(クマ系)
菊池秀夫「邪馬台国と狗奴国と鉄」によると,弥生時代末期に九州の北部,続いて中部に鉄器が急速に広がり,やがて中部が北部を凌駕,その後畿内に広がるとともに,九州の鉄器が急速に衰退したということなので,まさに鉄器民族の(オシ系)神武東征伝説に対応するものといえる。ついでながら,九州中部の鉄器を担ったのが狗奴国で,魏志倭人伝で狗奴国の官職とされる狗古智卑狗(ククチヒク)は,おそらく鞠智彦(ククチヒコ),すなわち菊池氏の祖のことではないかという。邪馬台国は長年にわたる狗奴国からの攻撃に対して支援を求めるため,魏に朝貢,魏も狗奴国が呉(マツ系のところで話した春秋時代の呉ではなく,三国時代のものあるが,民族的には近いと思われる)と連携していたことから,邪馬台国を積極的に支援したらしい。
いわゆる倭国大乱は鉄器普及によって起こり,その鉄器によって決着,さらに,鉄器を得たからこそ東征が可能になり,大和を制圧したと考えられ,ずっと後の鉄砲伝来によって,戦国時代に決着をつけた織田信長の話にも近い。邪馬台国が女王国連合であったように,狗奴国もまた九州中南部一帯を抑えていた国家であったと考えられ,両者の境界部から多数の鉄器製造遺跡が発掘されることから,熾烈な戦いをしていたことが分かるが,大型武器は,魏から技術支援を受けた女王国連合に集中していて,狗奴国は阿蘇山に鉄鉱石産地を有していたにも拘わらず,突如消滅してしまったといい,ヤマトタケル伝説にもつながっていると考えられる。
「日本書紀」には,神武天皇(実は崇神天皇)の大和入りに大きく貢献し,日本最古の歌を残した氏族として久米(来目・クメ)部が出てくるが,焼畑を基本としていた久米部は,前述したように,狗奴(クナ)国の民族クマ系であった。神武皇統が狗奴(クナ)国を制圧した際に,天皇に服属してその護衛を務めることになった久米氏の一派には,大いなる伴を意味する大伴氏の名が与えられたのであり,両氏は同族である。大伴氏の存在は,西都原との間の障害が無くなった上,軍事サポートまで得るようになって,いわゆる神武東征(実は崇神)が可能になったことをそのまま示しているといえよう。
大和の宇陀の地を拠点にしていた久米氏が集会施設を持っていた地の名が忍坂(オシサカ)であることから,そこが(オシ系)天皇家の大和支配の出発地になったと考えられる。この久米氏と,沖縄の久米島,琉球王国に明の皇帝から下賜された現在の福建省の職能集団の人たちが住んだのが那覇の久米村であったこと,さらには,道教のシンボル仙人の話の"久米の仙人"伝説などとの関係についても,解き明かすことが期待される。
さて,卑弥呼の死後,弟が王として立つもおさまらず,娘臺与(トヨ)を立てて再び収まったといわれるが,この時点つまりAD300年頃,邪馬台国の話が消えてしまうのは,臺与(トヨ)が収めたのは豊の国であったこと,卑弥呼の弟がいわゆる神武東征をした,つまり邪馬台国自身が東遷してしまったことによると考えられる。その人物こそ崇神天皇で,瀬戸内海経由で河内に至るも大和の地を支配していた長髄彦に阻まれ,やむを得ず大迂回し,最も有名な徐福伝説を有する現在の熊野新宮に至るのである。
崇神天皇の登場するのが邪馬台国の終わった頃だということ,その倭名ハツクニシラススメラミコトは神武天皇のそれと全く同じであること,ここには初代という意と同時に,統べるという意につながるスメラという語,さらにミコトまであわせて古代ヘブライ語ではないかということばかりか,徐福渡来のところで述べたように,(秦の)始皇帝とほとんど同じことを意味していることなどを知ると,神武東征は,実は崇神東征であった考えれば全て氷解する。徐福という名は,おそらく一個人でなく代々引き継がれる(オシ系)族長名であり,神武天皇から崇神天皇の前までは邪馬台国の時代であったということになろう。ついでながら,新宮の友人から聞いた話では,当地で現在も歌われている漁民の歌の詞は,古代ヘブライ語でしか解釈できないものということなので,徐福ユダヤ人説の裏付けになるのではないだろうか。
倉塚曄子「古代の女」によって補足すると,上古の日本では,ヒメミコ制と呼ばれる,霊能を持つとされた女性とその兄か弟が一体となって国(地域)を支配する体制があって,史料で明らかになっているヒミコとその弟王がその典型であった。しかしながら,大陸と対等な関係となる古代国家を成立させるためには,姉妹,すなわち女王の聖なる支配力から,兄弟,すなわち男王の実力による支配への集中,一元化が必要になってきて,おそらく,ヒミコ亡き後の争乱はそれに対応するもので,女王の方は娘が継いだようであるが,行方知らずとなった弟の男王,つまり崇神天皇は,大和に東征して,支配の一元化を図ったのではと考えて良いだろう。
ハ:大和に入り,アマ系と再会して,伊勢神宮が成立する
崇神天皇は新宮から大和に向かったが,早くから大和入りして,マツ系の長髄彦を支えていた物部氏が,崇神天皇に呼応して長髄彦を裏切って国譲りが実現,ここに,大和の地で神武皇統を引き継ぐオシ系の崇神王朝が始まる。その記憶は,クマ系の久米氏が支配していて大和制覇のポイントとなった地忍(オシ)坂に刻まれている。前述したように,アマ系の卑弥呼の娘臺与(トヨ)は,後にその名によって呼ばれる豊の国に移ってしまったようで,のちに,新羅からハタ系の応神天皇が渡来するに際し,豊の地は重要な役割をし,宇佐八幡宮が置かれることになる。ついでながら,アマテラスは,子のアメノオシホノミコトに,'以後この鏡をワレと思って祀れ'と言って,宝鏡を授けたということだから,(アマ系の)卑弥呼が(オシ系の)崇神天皇に遺言したものともとれよう。
ところで,邪馬台国の畿内説が相変わらずまかり通っているのは,前項で触れた菊池も指摘しているとおり,邪馬台国東征のスピードが早すぎて,九州説の証拠が見つけにくいのが要因のようである。崇神天皇による大和支配が如何に短時間になされたのかは,銅鐸のほとんどが大和の外側の地(おそらく出雲民族による支配圏域)で埋められた状態で発見され,大和の地には残っていなかったことからも(実際,奈良時代に,たまたま大和で見つかった銅鐸についてもすでに当時の人たちには珍しいものと見られただけで過去のことは忘れられていた),あわてて祭祀用のものを敵方から隠そうとしたことが窺える。あまりに短時間に東征がなされたため,遺跡の年代からは,北九州か畿内かを特定できないでということなのだろう。中国の文献からも,以後,倭の朝貢の記事が長期にわたって消えてしまうのは,倭王が大和という遠隔地に行ってしまったことに加え,朝貢先の地であった朝鮮半島の中国の出先帯方郡が314年に高句麗によって滅ぼされてしまい,現実に朝貢が不可能になってしまったことにもよるのだろう。
物部氏の節でも述べたが,長髄彦については,風貌異様であったという伝説からも,全く異なる民族,春秋の呉国からのマツ系の流れであったと考えられる。末盧国のところで述べたように,ナカ系,オシ系より前に東遷して大和に国をつくったのがマツ系の民と考えられることからも納得できる。松のつく主要地からみたマツ系の動きによっても示される通り,彼らこそが国譲りした民族だったと思われ,長髄彦の別名がトミヒコと言われるように,投馬国にもつながる。敗れたマツ系の末裔の豪族として葛城氏が大和西南部を占めていたが,そのルーツの末盧国の朝鮮側がのちに百済に取り込まれたこともあって,百済からの渡来者も多く,その精神的な核となる当麻寺はトマに当てた漢字で,やはり百済のルーツにつながる投馬国の名残ともいえよう。
記紀に書かれた崇神天皇以降の宮都や陵墓の位置が,大和における崇神皇統の支配の確立プロセスと矛盾が無いのに対して,それより前の(神武皇統の)天皇のそれが,全く異質なばかりか,服属させることができていない葛城氏の支配していた領域にあるように書かれていることからも,崇神天皇後に,神武皇統を記憶すべく,適当に配して築造したのが明らかで,神武天皇は大和国の前段階の北九州の邪馬台国の創始者としてのハツクニシラススメラミコトだったのである。崇神天皇以降の古墳時代になって,大和に突然巨大な鏡が出現したということも,その証左になるだろう。既に述べたように,崇神天皇以前の天皇の和名にはほとんど倭(ヤマト)の文字が入るのが,以後無くなるのは,倭が九州北部にあって大陸から認知されていた邪馬台国を表すものだからということでもあろう。
さらに,案内役として登場する高倉下や八咫烏などもマツ系に近いらしく,天孫降臨(徐福渡来時)のサルタヒコと同じような存在であったと思われる。高倉下は,強力なマツ系豪族の祖とされており,八咫烏というのは,鳥をトーテムする一族ということで,神社の鳥居のルーツが中国南部の稲作民族が村の入口に鳥を載せた門を置いていたことに由来すると考えられることから,マツ系(呉太伯)の子孫が日本に亡命してきたのと前後して渡来してきた一族であると考えられる。繰り返しになるが,神社体系のなかで独自の位置を占め,天皇家と極めて近い上賀茂神社・下鴨神社に結束している賀茂(加茂・鴨)氏は,マツ系の末裔で朝廷と敵対していた葛城氏と同族とされているので,八咫烏一族と同じように渡来し,天皇に服属を誓ったことから特別扱いを受けることになったと考えられる。賀茂のもとが(鳥の)鴨であること,葵祭で有名なように,水田と一体の植物の葵をシンボルとしていることからも間違いないだろう。
邪馬台国が東遷して大和国になったことは,朝廷が対馬,壱岐ほかの国々を以前と同様に支配していることや,大和の地名の多くがその位置関係とともに邪馬台国周辺の九州北部の多く地名を転写したものではないかという指摘からも証明される。ついでながら,紀伊熊野の地名が出雲国に転写されていることからは,この地にいた諸氏族も出雲の地に封じ込められたことを意味するのかもしれない。崇神朝がかつての邪馬台国の名残をとどめようとし,後述する応神朝に登場する宇佐八幡宮の地図上の位置と伊勢神宮のそれが類似していることも注目される。
東征に際して,天皇を親衛したといわれる大伴氏は,日向国のところで述べたように,クマ系の久米氏が神武皇統に服属を誓ったことで,大いなる伴の名を与えられ,神話では,その祖がニニギノミコトに随伴した天忍日命となっているように,アメ・オシを含むまさに皇族なみの扱いを受けることになった氏族で,熊野に入って以降,この地を古くから支配していた,やはりクマ系の紀氏と連携して,大和平定に奮闘,応神皇統を雄略天皇が確立すると,急に勢力を伸ばして全盛期を迎える。後に,大伴金村が継体天皇を迎えたのも,当然の役割であったといえ,早く没落していった紀氏と違って,以後も勢力を保つが,蘇我氏,さらに藤原氏の登場とともに,天皇直属の軍属として目の敵にされ,抵抗した大伴家持は強く抑え込まれて,その鬱憤を万葉集編纂にも結びつけるなどしたが,以後,衰退を続け,後に有能な伴善男が出るものの,応天門の変で追放されてしまい悲劇の一族になってしまう。
ついでながら,大和の豪族和爾氏は,そのルーツが神武皇統時代にあり,継体天皇の前まで天皇家に妃を供給し続けながら,男子についてはほとんど事績がないため謎の豪族とされているが,前述のように,卑弥呼の末裔のアマ系は全く別になって東進していることを踏まえると,それとは別に,崇神東征に際して,すでに妃の位置を占めていた一族を伴って来たと考えれば辻褄が合うのではないだろうか。継体天皇以後,諸豪族が女性を宮廷にいれて権力を争うようになったことで,妃を提供できなくなってしまうが,一族からは,後にも,女性では古代の美人の代表小野小町,男性では,政治的には無力でも,柿本人麿,小野道風,山上憶良ら独特の役割をする人物が輩出する。本拠としていた若草山も和邇氏に相応しい場所ではないだろうか。
崇神天皇はマツ系を代表とする出雲族を支配下に置くべく,自らの持てる技術を誇示することを兼ねて,壮大な出雲大社をつくることで納得させたと言われる。その上で,自らの神を祀る伊勢神宮を整備するわけであるが,良く知られているように,様式は全く異なるものになっていて,神との関係も陰陽の関係に置いている(神無月と神有月など,国譲りに対して神譲りで返したということか)。また,先に大和入りして,崇神王朝の実現に貢献した物部氏に対しては,あらゆる仕事を管轄する地位を与え,その祖とされる饒速日尊の正式名称を天照國照彦天火明櫛玉饒速日尊とし,頭の部分に天皇の祖と同じ天照をつけることで,納得させたようだ。
伊勢神宮の地が決着するまでに曲折があり,近畿各地に元伊勢なるものが残っているが,そのなかで,第2論で述べたアマ系の東進の最後の地の丹後の元伊勢が重要で,東征してきた崇神朝と何らかの形で再会,再び,卑弥呼との神話を確認する上で,両者の間に,確執のあったことが窺え,それ故,近畿各地を変遷,大和の地から遠ざけるということを前提に,ようやく現在の地に落ち着くことになったと思われる。同時に,丹後半島付け根に位置する籠(コモ)神社は,のちの応神朝の蚕の社にもつながるものとみられ,伊勢神宮と反対の役割をしていることが考えられる。
補足すれば,スサノオノミコトと天照大神の衝突は,マツ系の多神教とオシ系(ユダヤ人)の一神教との衝突で,岩戸伝説を経て,形式的には一応一神教とするも,実態は多神教を存続させ,つまり出雲に神譲りして国譲りされたので,以後,物部氏は軍事力その他諸技術以上に民間信仰を取り仕切ることで,天皇による人民支配(親政)を支えて行くことになる。神道の矛盾は始めから組み込まれていたわけで,後の天皇をして祟りを恐れさせ,また,多くの呪詛事件が発生する要因にもなるのである。伊勢神宮のご神体は八咫鏡で,その裏面には古代ヘブライ文字が刻まれているといわれ,参道の灯篭にはダビデの星がついていることなどからも,その内実が想像できる。ついでながら,菊の御紋について,メソポタミア由来など諸説あるが,とりあえず単純に太陽を表したものと見てよいと思われる。
いずれにしても,天皇にとって,熊野詣は,祖先が上陸した地点として,吉野がかつての吉野ヶ里の代替であるように,重要な場所になっていったと思われる。
この章TOPへ
ページTOPへ
第4論:新羅から渡来した秦氏の長による応神皇統~古墳時代
第1話:日本に影響を及ぼす朝鮮半島の三国時代
崇神王朝以降しばらくの間,大陸からの直接的な影響は無かったが,朝鮮半島に,百済や新羅が建国されると,以前からあった高句麗も含めた三国間の力関係に巻き込まれるようになる。そこで,小和田泰経「朝鮮三国志 高句麗・百済・新羅の300年戦争」に従って,朝鮮半島情勢を,簡単に整理しておこう。
イ:高句麗(フヨ系)
紀元前100年頃,漢の武帝が抵抗続ける衛氏朝鮮に侵攻して制圧,4つの郡を置いて統治し始めたが,朝鮮民族の抵抗が続いて後退,楽浪郡と玄莵郡の2郡に再編成するも,紀元前75年には北側にあった玄莵郡が廃止に追い込まれ,その地を管理していた高句麗が独立した国になった。
その高句麗は,北方で勢威を振るう物部氏,すなわち,のちの満州にもつながるツングース系のなかでも有力な氏族であった扶余の拠点で,彼らと抗争するうち,その扶余から亡命した王族を受け入れ,典型的な騎馬民族国家として成長する(前述したように,江上波夫の騎馬民族制服王朝説のキーになっている)。その後は,漢,その後の魏から圧力を受けるも,朝貢などによって避け,あるいは鮮卑や燕の侵攻を次々受けるも,それらを跳ね返して,朝鮮北部の広域を支配し,したたかな国として存在し続けて行く。
高句麗で391年に即位し,領土拡大に最大の功績のあった広開土王は,412年の死後,業績を称えて建てられた広開土王碑が有名であるが,碑文には,倭(日本)と組んだ百済が反抗してきたため,新羅と組んで両者を撃破したことが記されている。
現在の,いわゆる北朝鮮は,かつての高句麗の範囲であり,同じ朝鮮民族とはいえ,物部氏と同じ扶余氏の末裔の多いことも当然で,それが,北朝鮮の技術力を示すとともに,ルーツを同じにするかもしれない森喜朗元首相らと,特別な関係を有する理由になっているとも想像される。
ロ:百済(クダラ系)
三国時代が始まる以前の朝鮮半島南部には,馬韓,弁韓,辰韓といわれる3つの地域があったが,その地理的配置からみて,馬韓は末盧国と,弁韓は伊都国と,辰韓は奴国と境目なくつながっていて,日本と朝鮮の間に実質的な境界はなかったと考えられる。馬韓が百済にとりこまれ,滅亡した秦の支配層,すなわち徐福一族に近いユダヤ系の秦氏が,山東半島から朝鮮に渡って建国したといわれる辰(秦)韓が(次項の)新羅になることによって,日本との関係は弁韓に限定され,九州北部の諸国連合に対応する伽耶諸国連合になるが,邪馬台国以前に,細々ながらも,日本を統治することになった末盧国すなわちマツ系との関係で,百済王族に支配される周縁小国家群といったものになり,いわゆる任那(日本府)も,その一つに置かれることになった。
百済の国名は中国の史書では372年に初めて見え,高句麗が314年に帯方郡を滅ぼした際に,派遣した扶余王族によって興され,いわば高句麗の分家の存在であったが,346年王位についた肖古王の時代に独立し,372年に晋に朝貢を果たして国として認められたという。その後は,本家高句麗と抗争を繰り返しながら,次第に南下し,現在の朝鮮半島西南部を占めるようになったが,475年の高句麗の攻撃によって首都漢城が陥落,その2年後には部下解氏のクーデタもあり,何とか乗り越えるも以後,凋落して行く。再興を図るべく王子を人質として倭(日本)に送る方式で,その支援を求めて行くが,478年には,倭王武(雄略天皇)が,百済の衰退によって朝貢ができなくなった旨,宋の順帝に上奏文を送るほどになる。その後,501年に即位した武寧王によって一時的な復興が実現し,朝鮮半島にわずかに残っていた倭系の国の一つ加羅が百済の一部のようになるが,その加羅も562年に新羅によって滅亡させられる。
554年に百済は新羅に完敗するが,関裕二「藤原氏の正体」にあるとおり,その後,百済の再興を図るべく日本に亡命した王族のなかに,(中臣姓を借りた)鎌足がいたらしく,631年に人質として来日していた王子扶余豊璋その人だったという説さえある。641年,27歳の時に歴史に忽然と登場した鎌足は,631年には18歳ということで,まさに王子扶余豊璋にふさわしい年齢であり,645年に中大兄皇子を唆して蘇我氏を討ち,まさに百済政権を成立させ,天智天皇(中大兄皇子)に新羅征討軍を派遣させるも,結局は白村江の戦で唐・新羅連合軍に大敗,半島の新羅勢力の強大化を受けて,壬申の乱によって天武天皇戴く親新羅政権になってしまう。
ところで,朝鮮では村のことをスカということと知れば,白村江と書いて,なぜハクスキノエと読むのか,フィギュア・スケートで有名だった村主選手が,なぜスグリと読むのかということも氷解し,横須賀は,横が"日の横"で東を意味することから,東向きの村であること,ついでに,横浜が東向きの浜であることも判明する。とすれば,藤原氏の本拠が春日神社のあるカスガということは,朝鮮半島で縁のあった加羅(ラは国を示す)のスカ(村)であること,つまり,百済と一体だった加羅の出身だったことを思わせ,蘇我氏の本拠地の飛鳥(アスカ)は,安羅(アヤ)の村ということで,より新羅に近い国の出身だったことも地名に記されていることになろう。
深入りすれば,中臣鎌足が百済王族,すなわち扶余氏であるとすれば,物部氏と同族であることになり,物部氏のものだったという鹿島神宮を横取りしたのではなく,譲り受けた可能性もあるといえる。
また,現代朝鮮でみれば,金大中がそうであったように,民主党系の地盤である半島西南部はかつての百済であり,同じ朝鮮民族とはいえ,東部の保守党の地盤がかつての新羅であったのとは,相容れないことが多いのもやむを得ないかもしれず,とくに,最近の民主党系の親北朝鮮ぶりを見ると,扶余氏の影すら感じざるを得ない。
ハ:新羅(シラギ系)
序論や物部氏のところでも述べたように,ツングース系の有力な民族ながら,国を造るまでに至らなかったワイ(濊)族は,のちの満州あたりを一大拠点にしていたが,同じツングース系の有力な民族の扶余氏が建国するに際して追い出され,朝鮮半島を南下していく。最後に着いたのが,秦帝国の末裔秦氏が流れてきてつくった辰韓で,秦氏は,ワイ族を取り込んで,新羅を建国する。いわゆる新羅人の多くは,ワイ族をルーツとするということなのであり,当然のことながら,扶余氏の国,高句麗や百済とは,敵対関係になるのはやむを得ないところだろう。
ワイ族は,現在の北朝鮮の聖地白頭山から太白山脈に沿って,慶州近くの聖地太白山に向かったのであるが,"白"の字をつけた山が多数存在するように,白(シロ)を崇拝する民族であり,秦氏の得意とする絹織物のもとになる蚕もまた白い神様で,ヨーロッパではsilk(シルク)と呼ばれるように,音とイメージ全てが通じる(つまり白と新は同じという)ことから,両者あいまって新羅(シルラ)という国名ができと思われる。秦氏のハタは機織りのハタで,ワイ族に技術を伝えて養蚕民族にもしたのである。
ワイ族はさらに,日本海を横断して,日本の北陸地方に至り,そこで東北地方から南下していた仲間と合流することになる。石川県の小松(コマツ)は,本来,高麗の津(朝鮮の港)で,福井県の海岸まで含めて,朝鮮半島からの漂着も含めて渡来人が多かったと考えられる。白を崇拝するワイ族によって,日本の白山信仰が生まれ,ワイ族のつながりを辿って北上し,東北地方ではオシラサマ(オシラサマは蚕がルーツといわれる)になり,最後はオソレ山に至るのである。白山神社の祭神とされる菊理媛(ククリヒメ)については,日本神話のなかでの位置づけがあいまいで,いわば,宙に浮いていることから,統治に関わる諸民族と渡来とは全く別系統であったことが分かる。
中国との間に高句麗と百済があって,何れかの協力が無ければ朝貢できなかったため,新羅の名が中国の書に登場するのは,377年に金氏の奈忽王が高句麗とともに前秦に朝貢した時になる。391年,高句麗に広開土王が登場すると,その圧力のもと半ばその属国となって百済攻撃に加担,百済から支援を求められた倭は,399年に新羅に攻め込みに次々と攻略するが,新羅の訴えで支援に現れた広開土王軍の前に敗退してしまう。高句麗の属国であった間に,本来海洋民族に近かったワイ族をルーツとする新羅人の騎馬民族化が一気に進んだと考えられる。
ワイ族だけでなく,新羅の建国に関わった人たちも,日本海を渡って北陸地方に展開したと思われるが,秦氏に近い有力者で,おそらく安羅の王族でもあった蘇我氏もこの段階で渡来,ワイ族阿部氏とともに,近江を経て,大和に入ったと考えられる(大和での両氏の本拠地は隣あっている)。後述するように,応神天皇渡来時に円滑に大和に入れたのも,蘇我氏の存在があったからで,崇神天皇東征時に物部氏が果たしたのと同じ役割をしたと考えられる。のち,蘇我入鹿が,百済系の中臣鎌足に滅ぼされ,その子藤原不比等による「日本書紀」で,蘇我氏は徹底的に悪人とされ,侮蔑的に,馬子,蝦夷,入鹿の名がつけられている。蘇我氏を名乗ることが憚られ,その改名が進んで,現在ではほとんどいなくなってしまったが,拉致被害者として帰国した曽我ひとみのように,曽我と名乗る人たちが新潟県から岐阜県にかけて多いことが,日本海を経由して渡来してきた名残を示すものと思われる。千葉市に取り込まれてしまった蘇我町は,地名故にそのままの文字が保たれているが,逃亡した蘇我一族の来たところかもしれない。
参考図

第2話:秦帝国からの繋がりによる,オシ系からハタ系への王朝交替
イ:応神天皇は新羅から渡来した(秦帝国の末裔を自称する)秦氏の長だった(ハタ系)
歴代天皇の名で"神"の字がつくのは,神武天皇,崇神天皇のほかには応神天皇しかおらず,神武・崇神天皇と同じように国の始祖になった天皇ということを示していると思われる。しかも,その母とされる神功皇后にまで,"神"の字が入っているのである。すでに述べたように,これら天皇のいわゆる漢風諡号は,だいぶん後の,「懐風藻」を撰したことで知られる淡海三船が,孝謙上皇の命で,一括撰進したもので,終章で詳しく紹介するように,実に的確に名づけているため,皇位の継承が手に取るように分かるのである。>漢風諡号
秦氏がワイ族を取り込んで建国した新羅の隆盛に伴い,かつて,徐福が,秦の始皇帝によって日本建国に派遣されたように,新たに,日本の政権を握ろうとしたのか,応神天皇擁する秦氏一族が,おそらくアマ系のサポートを受けて航海し,九州の,アマ系卑弥呼の後継者壹与(トヨ)が拠点にした豊前の地に渡来,そこに,秦の国をつくり,のちに応神天皇を祀る八幡宮の本山として,宇佐八幡宮が創建されるとともに,アマ系の女性3人を妃にしたことから,古くから神事の行われていた沖ノ島をシンボルに,三女神として祀るユニークな宗像神社も創られた。
そこから,崇神天皇に見倣うかのように,東征して河内入り,親百済の崇神皇統に代って親新羅の応神皇統の時代を実現することになる(これもまた一つの国譲りであったと言える)が,応神天皇の母神功皇后が新羅の神アメノヒボコの子とされ,渡来前の応神天皇は,(推古天皇に対する聖徳太子のように)神功皇后の摂政のような存在であったともいわれることからも,ほとんど新羅と一体であるような政権が始まるのである。応神紀には,朝鮮の騎馬戦の叙述が多数みられ,新羅を馬飼として隷従させたという記述があり,応神天皇が騎馬民族新羅人とともに渡来したことを示すものと考えられ,いわゆる騎馬民族征服王朝説の理由の一つになったようだ。ちなみに,のちに蝦夷征伐で登場する坂上田村麻呂の祖先も,応神天皇とほぼ同時期に渡来した東漢(ヤマトノアヤ)氏で,劉氏の末裔といわれる。
ここで,同じユダヤ人とされる徐福一族と秦氏との相異を考えるため,その後のユダヤ人の歴史をみておくと,徐福渡来から邪馬台国滅亡までの間,ユダヤ人の故郷イスラエルでは,キリストが登場して,宗教上の大変革が起きるが,キリストは勿論ユダヤ人で,当初は,信者もほとんどがユダヤ人であり,その時点では,キリスト教は新興宗教で,古来のユダヤ教信者から排斥されたのもまた当然だった。そういった原始キリスト教のユダヤ人が再び,徐福一族と同じような道を辿って東へ向かい,キルギスの東北方にキリスト教国の砂漠の民であることを示す(三日月)弓月国をつくり,さらに中国を通過し,山東半島経由で朝鮮半島に入って新羅の秦氏になったといわれる。新羅はもと辰韓で,秦韓とも表記するように,始皇帝の秦国の滅亡後,朝鮮に渡った秦氏が建国したといわれるので,そこで,両者が出会ったのである。ちなみに,秦氏,徐福とも,本姓は,始皇帝と同じ嬴であったと言う。
応神朝の天皇などの倭名にも"オシ"のつくものも多いので,新羅から渡来した秦氏も,徐福系のユダヤ人とのつながりは認識されていて,すでに,大和に崇神朝ができていることを知っていて,日本列島をめざしたと思われる。そのルートをかなり正確に後追いすることができる。というのは,応神天皇を祭神とする八幡宮は,その名が「ヤ(尊称か量の多いことを示す語)」+「ハタ」であり,宮ということは,単なる神社ではなく天皇の所在地を示していると考えられるからだ。その八幡宮の数や格を見れば,対馬,壱岐を経て,福岡の筥崎八幡宮の当たりで上陸,かつて秦の宮と呼ばれていた香春神社のところを拠点に秦王国を築き,のちに宇佐八幡宮が八幡宮全体の最上格とされることになる。
三橋健編「日本書紀に秘められた古社寺の謎」によれば,八幡神のルーツはもっと古いようで,神武東征の話に,すでに宇佐氏が登場しており,宇佐八幡宮の神官が,大和朝廷に対応する大神氏と,新羅から渡来した応神天皇に対応する辛島氏の2者であること,宗像三女神も祀られているのは,新羅から渡来するに際して,その力が大きかったこと,欽明朝に示現したということは,その頃,創建されたとみられるということである。他方,神功皇后,応神天皇とも「古事記」には登場しないということなので,新たに,新羅から渡来して新王朝を開いた天皇を,うまく天皇神話体系に組み込むことができなかったと思われる。八幡神社は,その数が最も多いにもかかわらず,八幡神すなわち応神天皇は,日本神話の家系図には登場しない,宙に浮いた神なのである。
蛇足だが,応神天皇は秦氏を引き連れ,高度な鉄器文明を日本にもたらして,八幡神社の祭神になった故,明治維新後の国営で創設された製鉄所の地が八幡であったのも当然であった。また,宇佐八幡宮には卑弥呼が比売神として祀られ,崇神朝と応神朝を繋げるようになっている。「景行紀」に,突然日向地方の伝説が登場するが,そのルートを見ても,崇神皇統と応神皇統の九州のルーツ,つまり,ヒムカ(卑弥呼)とトヨ(臺与)を結び付けるべく,吉野ヶ里の邪馬台国から崇神(神武)東征,その後の応神東征を逆行するものとして見ると,よく分かるのである。
「新撰姓氏録」の仲哀天皇8年のところに,'秦始皇帝の子孫功満王が日本に来る'という記述があり,秦氏は功満王が祖先である,つまり始皇帝の末裔であるとしている。秦の国が滅亡した際に,その多くが,徐福の出身地の山東半島を経由して,朝鮮半島に渡り,すでに述べたように,辰韓を建国,その後,南下してきたツングース系のワイ族を取り込んで新羅を建国したのである。「日本書紀」の応神14年の項に,'弓月王が百済より来朝し,自国の民120県が新羅のために加羅に足留めされていると訴える'という記述があるが,要は,秦氏は,新たな新羅王族とうまく行かず,応神天皇を戴いて,日本に渡来したことと,後述するように,「日本書紀」によって日本を支配しようとした藤原氏のルーツが百済王家だったらしいこととを整合させようとしたといえよう。
秦帝国の皇帝の末裔を称する秦氏の応神朝が,崇神朝と大きな混乱なく交替(国譲り)できたのは,崇神朝が徐福の末裔で,その徐福が始皇帝の家臣であったこと,つまり,同じユダヤ人でも上下のあったことによるのではないかと考えられる。後述するように,そのやり方は違ったとはいえ,蘇我氏から藤原氏への交替,豊臣秀吉から徳川家康への交替も,同様の関係にあったとみられるのである。仲哀天皇の子の忍(オシ)熊王が反乱したという記事のあることが,応神天皇が別の王朝を拓いたことを示し,秦氏系図のちょうどその頃に,忍(オシ)秦公と,両者をつなげるような名の人物がいることも,それらを裏付けるものだろう。
ここで,倉塚曄子「古代の女」を参考に,応神天皇が新羅から渡来したことを裏付けてみよう。応神天皇は神話では胎中天皇といわれて,母神功皇后が新羅遠征時に神様のお告げで懐妊した,つまり処女懐胎で,まさにキリストがマリアの処女懐胎によって誕生したという伝説そのままである。キリスト教のネストリウス派の教義が秦氏渡来とともに日本に伝わったともいわれ,秦氏出身の厩戸皇子といわれる聖徳太子の誕生伝説もキリストのそれにそっくりだと言われている。いずれにしても,こういった神話をつくらなければならなかったこと自体,日本で生まれた皇族では無かった(その父祖を説明できなかった),つまり,渡来してきたことを裏付けるのである。倉塚は,いみじくも,神功皇后の新羅征討物語が,天孫降臨神話とパラレルであるといっているので,処女懐胎の場所糟屋郡が,そのまま渡来地を示しているのであろう。
さて,糟屋には,神功皇后を祀る香椎宮があるが,大陸では多いものの,日本にはほとんど無い廟宮とされ,ふつうの神社の扱いを受けていないのは,皇后が新羅王子の血を引く,つまり新羅人であり,応神渡来前にすでに没していたか,ともに来日するも,この地で没したことから,大陸と同じ風習である廟に祀ったと考えるしかないだろう。
ロ:(アマ系の東進・崇神東征に重なる)応神東征~河内を経て,近江に至る
その秦氏集団が,族長すなわち応神天皇戴いて東征するのだが,伝説でしかなかった崇神東征と異なり,前項で述べたように,八幡宮の分布を見れば,良く分かる。まず,宇佐八幡宮のある豊の国から,(以後,現在の地名を用いると)愛媛県八幡浜(通り道であったことを証明するような地名)に出て,新居浜あたりを経て,香川県に入ると,八幡宮は高松のものを始めかなり集中する。
おそらく,渡来した筑紫糟屋で,皇后に当たる妻を迎えて東征,途中讃岐で,子(後の仁徳天皇)が誕生する。金比羅宮はかつて旗(ハタ=秦)宮と言われていたらしいことから,そこに,応神天皇が滞留したのだろう。讃岐の国には,応神天皇とともに渡来した秦氏の子孫が多いことで知られ,その代表が,ユダヤ人的天才ぶりを発揮した空海ということになる。
そして,瀬戸内海を越えて吉備氏の地域に入り,抵抗されるも,前述したように,吉備氏は物部氏と同族で,かつて崇神天皇が東征した時にそのサポートをした氏族であったから,吉備津彦神社や先端技術を付与することなどによって決着したようで,続いて入った播磨でも,先住豪族(のちの赤松氏の祖)の抵抗を受けるが,姫路市の白国神社(シロすなわち新羅),その北の広峯神社(のちの吉備真備創建という)の祭神が新羅訓明神であるように,新羅人が多く居住する地域となって行くが,のちに聖徳太子の死で一気に没落する秦河勝の逃亡先にもなって,太子町と斑鳩神社まである。播磨はまた,のちの佐用町から赤松一族が出たように,有能な悪党が多く,中央の支配が及びにくかった地方でもあるが,赤染氏も秦系で,秦氏がとくに多いとされる赤穂にも,太秦と同じ大酒神社があり,のちに赤穂浪士など,一連の話につながって行くのである。明石も「アカ」系の地名とみられる。
さらに進んで,摂津の海岸沿いに河内,すなわち,既に大和にいた崇神皇統の天皇の支配領域に着いたことになる。河内では,崇神朝に抵抗されたため,そのまま,近江を経て,日本海の,新羅をはじめ大陸との交流の拠点であった角鹿(現在の敦賀)に至る。琵琶湖擁する近江は,一つの国のような地域であったことから,秦氏と新羅人ともに定着し,のちのち,子孫がさまざまに活躍することになる。角鹿で,おそらく現地の豪族の娘を一時的な妻とし,子も生まれたことが,のちに,天皇の跡継ぎが断絶した際に,越前でようやく応神天皇の血を引く継体天皇を見出すことができたという話につながり,神功皇后の伝説が集中して記載されるのも,継体宣化朝の項であることがそれを裏付けるであろう。
応神天皇渡来時の神は,イト系支配下のアマ系のムナカタ神であり,渡来後,アマ系の豊の国にあったが,東征にあたっては,もはやイト系とは関係ないアマ系の人たちに支えられ,無事,難波に到着して,河内王朝を拓くことができたことから,航海守護神の住吉大社が創建されたというわけであるが,宗像,綿津見と同様,海の神として,底・中・上の筒男(ツツノオ)三神になっている。その名の由来には諸説あるが,新羅から出てすぐのところの,対馬の南端に位置して,ユニークな文化を伝えている豆酸(ツツ)が語源ではないかというのに説得力がある。そこが,難波の住吉三神の故郷ということ,日本への出発地だったというになり,もちろん,上陸した九州の博多にも住吉神社がある。その後,住吉(スミヨシ)神が,筑紫まで,皇后の征討ルートに対応する要所に配置され,ムナカタ,ワダツミ両神の存在が消されていったのは,応神天皇の渡来を隠さなければならなかった神話創作者によるものと考えられる。
讃岐の国名を考えてみると,仁徳天皇の倭名には「ササギ」と読まれる讃の文字が入り,後漢書で倭王讃とあるのが仁徳天皇なのはほぼ確実で,その名をもって,讃岐国の名にもなったのではないかと考えられる。この「ササギ」は,天皇の陵墓が「ミササギ」,韓国の国鳥が「カササギ」と呼ばれるように,新羅国の基本を成す語とも思われるが,実際,佐々木(ササキ)氏はその祖が明確になっている姓のうち最大のもので,滋賀県近江八幡にある沙沙貴(ササギ)神社に,全ての家系が登録されているという。所在地八幡は,秦氏の神応神天皇を示すことから,まさに,生粋の新羅人であり,六角氏,京極氏も,佐々木氏から派生しているので,武力に優れているといえよう。佐々木氏につながる名字として,笹のつくものを見てみると,戦後政界の仕掛け人で黒幕だった笹川良一の,笹川姓を筆頭に,何十もあり,その分布も,苗字ごとに異なりながら,全国に広がっていて,シラギ系の人たちの多いことが分かる。鹿児島県の幹部だった笹田氏,コンサルタント界の重鎮だった笹生氏など,今までに会った人たちの風貌や振舞いには,共通したものが感じられる。ルーツが関係深い中国の山東を姓とする人たちも新羅人であったようだ。ついでながら,近江草津にある安羅神社の祭神は新羅王子アメノヒボコである。
既に述べた蘇我氏を別にしても,滋賀県の滋賀はじめ,この地域を中心に,志賀,信貴山,信楽,曾我など,新羅と近い発音のものも多い。武烈天皇の倭名にも「ササギ」の語が含まれ,大和の主要豪族の一つ巨勢氏も,その祖は雀部臣といわれて,仁徳天皇と同じ「ササギ」を含み,のち朝鮮半島との軍事に活躍する人材が多くでることから,新羅系と見て間違いないだろう。
京都の太秦には蚕の社という神社があり,養蚕を敬うユダヤ人のメッカとされているが,後の三井財閥はこの社を氏神にし,江戸進出に当たって,三本柱の奇妙な鳥居も移して三囲神社を創建,三がユダヤの基本数字であることなどから,多くの点で金融を支配するユダヤ人とつながっていることが分かる。蛇足ながら,その三井財閥の出発となった三井高利は,もともと近江(京に近い)の家ながら,伊勢の松坂に出て財を成したということであるが,中村修也「秦氏とカモ氏」には,秦氏のなかで,商人的性格を持つ人物として「日本書紀」に登場する秦大津父という人物がおり,伊勢に商売に行って財を成し,天皇に貢献したということであり,大津が,まさに近江の首都なので,そのまま,三井の祖先と考えてもおかしくないだろう。邪馬台国のところで述べたように,「三」という数は,ユダヤ系にとって大きな意味を持つのである。
太秦のすぐ北に,秦氏が大々的に開発した嵯峨野があるが,それが新羅由来の地名と考えられるように,また,播磨のところでも述べたように,全国に広がる秦氏の回りには新羅人が必ず付帯している。太秦はまた,近代に入って映画のメッカとなるが,アメリカのハリウッドがユダヤ人の支配下にあったことを思えば,その日本版であるといえよう。
ところで,太秦はウズマサと読まれるが,この"ウズ"は"ウル"がなまったもので,古代ヘブライ語で光を意味する。奈良県御所市には蘇我馬子の墓とされる石舞台に次ぐ大きさの條ウル神古墳があるが,"ウル"がヘブライ語であるとすれば,応神天皇に近い位置にあった人物の可能性が高いといえるだろう。実際,條ウル古墳のまわりは,豪族羽田氏すなわち後に応神天皇とともに渡来したユダヤ系秦氏の支配地であった。
崇神・応神東征ルートのイメージ
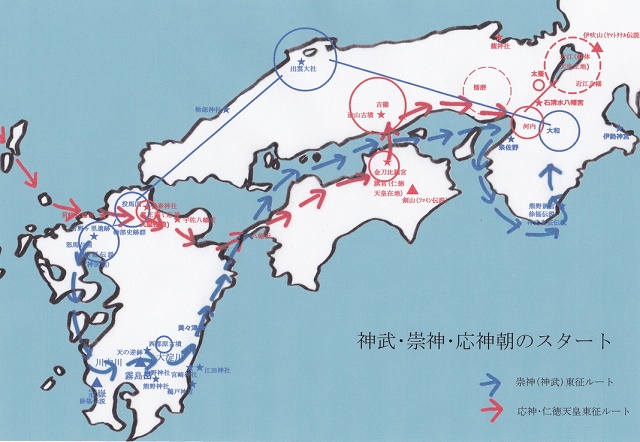
葛城襲津彦~ハタ系の応神朝渡来人をオシ系とつなぐ葛城地方の有力者~
古代史の会「人物で学ぶ日本古代史 1:古墳・飛鳥時代編」(2022年)では,「伝説と史実のあいだ」のサブタイトルのつけられている葛城襲津彦は,一般には葛城氏の祖として知られるが,4世紀後半から5世紀初頭にかけて活動した人物で,当時,葛城氏という集団があったわけではなく,単に,葛城地方の襲津彦ということらしく,「日本書紀」で,2世紀も前の,応神朝の祖神功皇后との関係で記述されているのは,襲津彦が,新羅から多数の俘人を連れてきて,葛城の地に集住し,瀬戸内海ルートを確保したこと,その後の大王家と外戚関係を維持したことなどで,蘇我馬子が,推古天皇に対して,葛城県を本拠と奏上したように,多くの民が自らの祖としていったとある。>蘇我氏は,一般には百済系とされているが,その氏名や伸長,さらには,百済系の中臣鎌足(藤原氏)に滅ぼされたのをみると,ハタ系の応神朝とともに,新羅から渡来したと考える方が自然だろう。また,次の飯豊青皇女のところで述べるように,オシ系の拠点たる忍海が葛城地方にあることも,その有力性を考える上で見逃せない。
飯豊青皇女(いひとよあおのひめみこ)~ハタ系を,それ以前の正統なオシ系に繋げる象徴的な存在
オシ系の崇神朝からハタ系の応神朝に交替するわけであるが,そのルーツは秦の始皇帝でつながっており,ある意味,交替は円滑に行われたと思われるが,応神朝の正統性を保証するためには,オシ系からの流れを受け継ぐ必要があった。それを裏付けるように,古代史の会「人物で学ぶ日本古代史 1:古墳・飛鳥時代編」(2022年)には,大和王朝の祖オシ系崇神天皇と,応神朝の祖ハタ系神功皇后の間に飯豊青皇女という人物が,皇位継承の結節点のサブタイトルがつけられている人物が登場する。奈良県葛城市南端の忍海(オシミ)という地域に宮があったと伝えられ,仁徳天皇の長子履中天皇の子で,市辺忍歯王の妹で,雄略天皇が市辺王らを殺害して皇位につくも,その子清寧天皇のは子が無く崩御,皇統が途絶えようとした際,播磨に逃れていた市辺王の二王子を迎えて,顕宗天皇,仁賢天皇とするにあたり,宮に迎える役を担った。つまり,清寧天皇と顕宗天皇の間の短いながら空位を埋め,「日本書紀」では,用語が天皇と同等に表記され,履中の娘も青海と市辺の娘の飯豊が結合された名で,埋葬地も天皇と同じ陵になっており,女性天皇の先駆とも言える存在であった。>徐福渡来のところで,朝鮮にも忍海の地名があり,オシ系の根拠として忍あるいは押の字を含む皇族を列挙し,継体天皇を迎えるところで妃に迎えたなかに,オシ系があるように,応神天皇を祀る八幡宮をつくったほどのハタ系ですら,その正統性はオシ系との繋がりが必要であったし,卑弥呼が祖であるように,女性天皇が登場する根拠にもなっていると言えよう。
ハ:応神皇統に対応する大古墳群の盛衰(いわゆる倭の五王前後)⇒コラム「巨大古墳について」
応神皇統は,倭の五王としても話題になるが,その最後の倭王"武"とみられる雄略天皇は,最後まで抵抗し続けた(出雲族の支族高志系ともいう)マツ系の大豪族葛城氏を滅ぼして大和盆地を平定し,応神皇統を確立すると,まず先代の功績を敬うべく巨大な応神・仁徳天皇陵を築造して政権の力を誇示する。そして一代前の安康天皇までの大古墳を築造し,自らの古墳(宮内庁指定の雄略天皇陵)は小さくなっているが,実は,仲哀天皇陵とされているミサンザイ古墳が,巨大で雄略天皇にふさわしい陵ではないかともいわれる。ここで,最大なのが仁徳天皇陵とされ,応神天皇陵とともに,大和から最も遠い海側に築造されていることこそ,崇神朝から国譲りを受けたのが仁徳天皇であった証ではないかと思われる。応神朝の天皇陵の大部分が河内にあるのは当然で,邪馬台国時代の神武皇統の天皇陵は畝傍山周辺に配し,崇神皇統の天皇陵は巻向山麓に,そして神功皇后はじめ妃の陵は和邇氏の支配地に築造されたのもなるほどと思える。なお,雄略天皇によって葛城氏が滅ぼされた後を継いだのが平群氏であるが,武烈天皇時には大伴金村によって滅ぼされてしまい,大神神社の祭事が始まったのも,雄略天皇時代ということなど,その支配が完璧なものになったことを示すものだろう。
松木武彦「日本の古墳はなぜ巨大なのか: 古代モニュメントの比較考古学」によれば,世界遺産に登録された仁徳天皇陵は,平面としては,世界最大の陵墓であり,それに次ぐのが応神天皇陵で,その他,応神朝の天皇陵が全体として図抜けた建造物であること,その時期に造られた各地の巨大陵墓などをみると,秦氏のもつ技術力によって造られたこと,さらには,秦氏が始皇帝の末裔であることを頷かせるものではないだろうか。後述するように,世界の巨大墳墓を比べてみると,日本の古墳は秦の始皇帝の墳墓(いわゆる兵馬俑)と類似し,仁徳陵の規模は,それをも上回るということなので,いかに巨大であるか分かる。蛇足ながら,秦氏の技術力を裏付けるものとして,秦氏出身の空海が満濃池を築造したこと,東大寺の大仏を造るにあたって,その総指揮をとったのが,やはり秦氏出身の佐伯今毛人だったことなどを挙げれば十分だろう。
また,荒川の河口(かつてはこの辺まで海だった)近くに押上があり,上流に行くと江戸時代に忍藩だったところのさきたま古墳群があることはオシ系のところで述べたが,そこの稲荷山古墳から発見された刀の銘に雄略天皇の倭名「ワカタケル」が刻まれていたように,関東でも古墳の築造によって,勢力を展開するなど,全国的支配体制を整えて行ったと考えられる。この先の北関東には,のちに有力武将として登場する新田氏・足利(アシカガ)氏など新羅由来の氏族がいるが,秦氏回りの新羅人としてこの時期あたりから始まったのではないだろうか。関東の西の山地沿いには,埼玉県の高麗・飯能・新座や,神奈川県では秦氏の入った秦野回りの寒川など新羅人の入植が多く,そのまま日本のシルクロードといわれる地帯になっている。ついでながら,吉備古墳群のなかで特別に大きい造山古墳も吉備族のものではなく,応神皇統のものらしいので,支配の役割を担ったものだろう。ずっと後,蘇我氏が吉備に派遣されたのも,これまでの推移を見れば当然のようにみえる。
そもそも,ユダヤには古墳は無く,高句麗の古墳や百済に前方後円墳があったことが知られているように,前方後円墳は朝鮮半島の文化で,応神朝が新羅からもたらしたものと考えられる。ということは,応神天皇より前の崇神・神武朝の古墳も,雄略天皇以降,過去の天皇を敬う形で築造され,また,大和や全国の豪族たちも,巨大墳墓をみせつけられて,場合によっては,許可を得て築造していったということまで考えられる。天皇陵については調査研究が禁止されているため,実際の築造年代が分からず,というよりも分かってしまうことを避けるために,禁止しているとさえ思える。想像をたくましくすれば,多数の大古墳を築造していったことが,人民の疲弊や豪族の不満を招き,武烈天皇の時代,ついに行き詰まって,後述する継体天皇の登場になるのではないかとも思われ,実際,それ以後,古墳の築造は小規模になり激減して行くのである。
各天皇陵配置図(宮内庁の指定による)
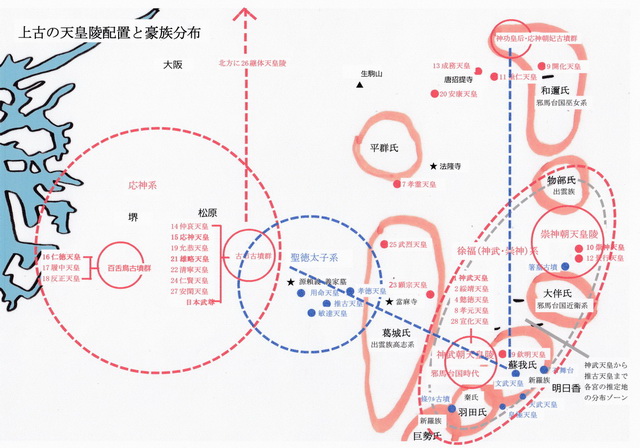
ヲワケとムリテ~ハタ系の応神朝が敬意を表したオシ系ルーツの東西の最有力者~
古代史の会「人物で学ぶ日本古代史 1:古墳・飛鳥時代編」(2022年)には,ワカタケル大王すなわち雄略天皇から銘鉄研(国宝)を贈られた,現在の埼玉県行田市埼玉稲荷山古墳のヲワケと,熊本県玉名郡和水町江田船山古墳のムリテという同時代の人物がいて,サブタイトル「刀剣銘に名を遺した倭王権下の地方豪族」が示すように,それぞれ,北関東と北九州の有力な首長であったとある。>想像をたくましくしてみると,前者に関わる行田は,忍城のある地で,東京の押上から遡って当地に入り,北関東を支配するようになったオシ系の末裔,後者は,邪馬台国に近いことから,当地に残って支配を続けたオシ系の末裔と思われ,飯豊青皇女のところで述べたように,オシ系とルーツを同じくするハタ系の応神朝が,政権交替にあたって,接続を図ったことに関係し,全国支配の確立を図ろうとする雄略天皇にとって,東西の最有力者であったとみられる。
第3話:秦氏による神社統治システムの構築~諸民族支配の方法
秦氏はまた,桂川水利工事などの土木技術や製鉄技術のほか,北関東にまで革新的養蚕技術を伝えたが,多民族の日本列島を統治するため,出雲や吉備の方式が上手くいったことから,各民族の氏神となるように,全国チェーン化して行ったらしい。広大な境内に壮麗な神殿を建立し,現世利益を神に請願するという,現在の神社の様式を持ち込み,応神天皇を祀る(尊称ヤ+ハタを示す)八幡神社を軸に,マツ系のために松尾神社,稲作民のために稲荷神社を創設,出雲大社には神事を司る宮司を秦氏から派遣(現代に伝わる千家家)するなど,多様な民族を支配すべく神社体系を構築した。とくに,八幡神社は,新羅系騎馬民族の源氏の人たちが崇拝する神社になって,著しく広がって行くのである。>神様の家系図
イ:秦氏の神(ヤハタ)・八幡神(すなわち応神天皇)の創出
八幡神は,もともと応神天皇を戴いて渡来した秦氏の氏神として,"ハタ"に尊称"ヤ"をつけた,まさにハタ系の氏神であり,オシ系とアマ系によってつくられていた神話体系には乗らない神であった。漢字2文字に天皇をつけて呼ぶ,いわゆる漢風諡号というものが始まったのは,聖武天皇の娘の孝謙天皇(重祚して称徳天皇)の時代に,その命で,当時一流の文人官僚だった大友皇子の曽孫淡海三船が,神武天皇から聖武天皇まで一括撰進したもので,神がつくのは,神武,崇神のように,王朝創始者であることを示しているようで,応神天皇もまさにそうであり,その母神功皇后にまで神がつくのであり,八幡神は,結局,応神天皇その人になってしまう。応神天皇が角鹿から河内に戻る間,成人した仁徳天皇は,その名が示す通りの仁徳だけでなく,妃の一人(磐之媛)をマツ系の葛城氏から,もう一人(髪長媛)を日向系(アマ系)の巫女の流れから娶ることで統一を成し遂げたが,伝承では伊勢神宮に嫌われたため(つまり本来のユダヤ教と,キリスト教とは相受け入れられないものであったため),新たに石清水八幡宮を創出し,前述したようにその出先の神宮を,応神天皇が辿ってきたルートに配したらしい。
その本山とされる宇佐八幡宮は,元々は大漁旗を意味する海神で,つまりアマ系台与の末裔宇佐氏が崇敬した地方神であったが,前述したように,応神天皇の渡来時に,アマ系が重要な役割をしたことで,571年,神託によって,応神天皇の化身となり,土着的な神と天皇の神霊が結びつく特別な神になった。新たに登場してきたため,オシ系とアマ系でその基礎がつくられた記紀神話の体系に入っておらず,天皇神授の神話デザインにおいて,取り込みようがなかったと思われる。秦氏は,原始キリスト教になっているとはいえ,崇神皇統と同じユダヤ人であり,前述のように徐福一族の後を辿ってきたこともあって,何らかの調整があったと考えられる。いきなり大和に入らず,京都の方へ展開し,太秦という一大拠点をつくる一方,すでにある伊勢神宮を尊重して敬うことで,崇神皇統から国譲りされ(かつて崇神朝がマツ系・出雲族の神を最大限に尊重して国譲りされたように)。とはいっても,その後の宇佐八幡宮のご神託の強さを見ると,まるで第二の伊勢神宮のような存在で,どういう訳か分からないが,その名も,地形的な立地もよく似たものになっているのである。
その後の天皇は,当然のことながら,応神天皇から始まることになるため,伊勢神宮と同様,皇室の祖神とされ,のち,源氏の氏神になり,武家の守護神となった。新興の神であるにもかかわらず,八幡神社の数は,ダントツの一位になっている。宇佐神宮が総本宮で,応神天皇の上陸地と思われる福岡の筥崎宮,畿内に入った証の京都の石清水八幡宮と,かなり後になるが,源氏の氏神となった鎌倉の鶴岡八幡宮をあわせて,日本三大八幡宮とする。具体的な人物が祭神となった最初の例で,のちに,雷神信仰が,菅原道真を天神様として,畏怖・祈願の対象にするようになったのに通じるものといえよう。
なお,祭祀と技術両面で優れていた秦氏は,徐福渡来時における物部氏と同じように,国家支配システムを構築するのに大きな役割をしたと考えられるが,実際の政治は蘇我氏が得意としたらしい(後述するように,蘇我氏の渡来は応神朝末期かもしれない)。また,蘇我氏とつながり,東日本一帯を広く占める阿部(安倍)氏の役割も大きかったと思われる。名字由来ネットによれば,応神天皇渡来に関わって秦の国があったとされる現在の大分県に秦氏が集中しているのはもちろんであるが,藤原氏から排斥されて名乗ることを憚られ,わずかに残る蘇我氏はほとんどが大分県におり,阿部氏もまた飛び地のように大分県では多いというように,宇佐八幡宮のある大分県は応神天皇の大和進出への一大拠点であったことが伺えるのである。
応神皇統になって,天皇の祭祀を担当するのが,それまで中臣氏だけだったところに,忌部氏(のち斎部氏)が登場する。当然のことながら,応神天皇の渡来ルート上に多く分布するが,なかでも阿波(アワ)忌部氏の格が高いらしく,その拠点は祖谷で,そこの剣山にはソロモンの秘宝が埋蔵されているという伝承すらあるのである。房総半島南端にあった安房(アワ)の国は,阿波から渡来した人たちによってつくられたことから同じ名になり,安房神社の祭司は忌部氏とである。後に,中臣氏の苗字を借りたクダラ系藤原氏が覇権を握ったことによって,急速に衰えてしまうのは,まさに新羅由来の氏族だったからだろう。
ロ:なお抵抗続けるマツ系を取り込む,上賀茂神社・下鴨神社・松尾大社の創出
日本に古くから土着していたり,度々渡来してきた様々な民族の調和を図るべく,それぞれの神々に対応する神社体系をデザインしたのが秦氏で,ともに渡来した応神天皇を祭神とする八幡神社の数が,記紀神話には出てこない神ながら,一番多くなっていることが,その証左となろう。デザインの際,キーになったのが,徐福一派よりかなり前に,春秋中国の,越に敗れたために渡来した呉の民で,現在も松の字が入った名字をもつ人たちの間に伝わる,呉太白の末裔の扱いであったと思われる。秦の始皇帝による統一時に,現地にもなお呉王の末裔が残っていて,秦氏とマツ系の関係がつくられていた可能性も否定できない。
魏志倭人伝に出てくる末盧(マトラ)は,マツの国という意味で,九州北部に松尾姓が非常に多く,既に詳述したが,松の字のつく地名を追えばわかるように,彼らも東征していて,先に,大和を支配していたと考えられ,いわゆる神武東征で,葛城の地を離れて,山城に移ったらしい。秦氏が拠点としていたのは,地名そのものが示す太秦で,平安京をはさんで,東の下鴨神社と反対側の西側になる。秦氏の本来の氏神は,蚕の社と呼ばれるように,絹にかかわる民族そのままの名であるが,正式には,木嶋坐天照御魂(アマテルミムスビ)神社といわれ,まさに,造化三神を一つにしたような名になっている。財閥三井家の氏神でもあったとされ,江戸進出で創建された三囲(ミメグリ)神社と同じ,三柱鳥居があることでも知られる。
秦氏が創建したとされる有名な神社に京都の松尾大社があるが,その名がマツ系そのものである上,中村修也「秦氏とカモ氏」によると,その祭神は秦氏の神ではなく,その近くの,鴨氏の上賀茂神社,下鴨神社と同じであるという。つまり,国譲りしたマツ系の人たちを,支配下に取り込む装置として,これらの神社が創建されたと考えられる。この両神社は葵祭りで有名であるが,鴨という動物,とくに家畜化されたアヒル(家鴨)と,葵という植物をセットで考えれば,まさに,中国南部の揚子江下流域のもので,マツ系がすなわち旧呉人であるという有力な証拠になるだろう。神様の話を記しておくと,マツ系を取り込んだ松尾大社(スサノオ系(出雲)のオオヤマクイノカミが祭神=マツ系のところで述べた感染症の話,酒の神)と上賀茂神社(オシ系タカミムスビ系のタマヨリヒメノミコトとオオヤマクイノミコトの間に生まれたカモノワケイカヅチノミコトを祭神としている)・下鴨神社(イザナミ系のハニヤス男女神=ハニは土(土着を示す・ハニワ))ということである。>豊臣秀吉,>徳川家康
ハ:その他の諸民族を取り込む神社群の創出
次論で述べるように,王権を簒奪したことになったアマ系天武天皇の皇后持統が,自ら天皇になることを正当化すべく,伊勢神宮を軸とする形で現在につながる日本国と天皇制を創始するが,その伊勢神宮にも,ダビデの星刻まれた灯篭があって,神輿はじめ日本人の祭祀のしかたがユダヤ人に近いといわれることなど,秦氏の力によるものだろう。かつて来日したユダヤ人の富豪ロスチャイルドが神輿を見て,ユダヤ教とのあまりの類似に絶句したとも伝えられる。住吉神社は,神功皇后をも祀っていることから,シラギ系の海洋民族のためのものだろう。それに対してエビス神社はインドの神にもつながることから,縄文時代からの海洋民族に対するものと思われる。氏神の「うぢ」も古代ヘブライ語のウルに対応するらしく,太秦の「うず」と同じかもしれない。
終論で,地図を示すように,平安京遷都以前に,秦氏は,前述した松尾大社,上賀茂神社,下鴨神社とともに,もう一つの大神宮稲荷大社も創建したが,全国で八幡神社に次いで多い稲荷神社の総本宮で,多くの渡来した(マツ系ではない)稲作弥生民族を支配下に治めるためのものであったといえるだろう。このように,遷都以前に,要所が重要な民族の神社によって抑えられていたのである。
やはり,数の多い日枝(日吉・ヒエ)神社は,山王信仰に基づいて,比叡山麓の日吉大社より勧請を受けた神社であり,比叡山が,仏教のメッカになったことからも,相当に古くからのものだったと思われる。現代では,東京山王の日枝神社が,都心の重要な場所にあって,あたかも日枝神社のトップのようになっているが,大山咋(オオヤマクイ)神を主祭神とするように,山王信仰はすなわち山岳信仰であり,最も古い形態の信仰であり,神社を守っているのが,狛犬ではなく,猿であることからも,縄文時代からのものを感じさせる。とすれば,物部氏のところで述べた扶余族の故郷の畑作物,つまり,ヒエは,穀物の稗であり,黍(キビ)から,吉備の国,吉備津神社ができたり,粟(アワ)から,阿波,安房の国ができたりしたのと,同じなのかもしれない。
巨大だった出雲大社についても,国譲りした諸民族を懐柔すべく,秦氏のもつ技術力を発揮して贈ったといわれる。
白山神すなわちククリヒメノカミ=黄泉の国神話に登場し,伊邪那岐命・伊邪那美命の諍いを調停した白山神社の祭神,つまり白山信仰に対応する神で,日本海経由で新羅から北陸に入ってきた騎馬系の養蚕民族と考えられる。新羅はシルラで白の国を意味し(シルクの語源?),蚕のマユの白さや,かつては太白山と呼ばれた北朝鮮の白頭山につながる。そのまま,東北に広がり,最後は,オシラサマになった。ククリは糸を括るの意であり,いずれにしても,国つ神ではなく,九州方面からの天つ神でもない,全くの別ルートで渡来した神であることから,それまでの神話体系に組み込めず,宙に浮いてしまった。
白山信仰を確立した泰澄も秦氏の出で,白山神社の祭神・菊理媛(ククリヒメ)は,糸を操ることと同義,養蚕民族のためのものであることを示している(ククリは高句麗という説もある)。朝鮮半島から入ってきた白山信仰は,社会の最下層の人たち,生贄や屠殺に関わる人たちを対象としていたため,殺生を禁じる仏教を背景とした国家によって,社格は極めて低い位置に据え置かれたままになる。泰澄はまた,国譲りで敗れた側のシンボル役小角(持統天皇のところで説明予定)とも連動していたといわれる。桓武天皇の時代に,伊勢・尾張・近江・美濃・若狭・越前・紀伊等の国に対して,牛を殺して漢神を祀ることを禁じたとあるが,このうち近江・美濃・若狭・越前が白山信仰に関わるものである明らかで,伊勢・尾張・紀伊については,マツ系のところで述べたように,春秋時代の呉の風習を伝えてきていたためと思われる。
物部氏のところで取り上げたワイ族(新羅人の主流)が大量に流入して,白山信仰を伝えたのがのちの加賀国であるが,当時は,のちの越前国の一部でしかなかったといわれるので,ワイ族が多くなって異なる地域になったことで,独立した加賀国になっていったと考えられる。その流入の主たる入口が高麗の津,すなわち現在の小松(コマ・ツ)であったことも既述したが,後に,農耕民を対象とした浄土真宗が広がったのも,越すなわち北陸地方で,そのなかで農耕民が自らの地位を確認すべく最下層の白山信仰者を殲滅しようと一向一揆が激しくなったのも加賀国で,その一向一揆を抑えて,前田藩の加賀百万石ができることになる。ついでながら,敦賀は本来ツヌガで,新羅が琵琶湖経由で日本と往来する港であった(琵琶湖を囲む近江国は滋賀(シガ=シラギ)県になるように,全体として新羅人の国である)。
いかにも多様な神社があるように見えても,神輿など全く共通する様式であり,さらに,全ての神社を統括するのが伊勢神宮といいながら,実質的な力を発揮していたのは宇佐八幡宮であることは,その後の歴史が示す通りで,出雲大社を裏の統括として,神無月に対する神有月とするなどして,神社全て,すなわち民族全てを,秦氏がコントロールできるようにしていることが分かるだろう。唐突ではあるが,現代の甲子園野球なども,そういった多様な民族の血の調和や統合を図る仕組みといえよう。さらに,常に一つのもの(ナタデココのバカ騒ぎなど)や一人の人(長島茂雄など)に指向を集中させようとするのも,何とか多様な民族を繋ぎとめようとするためで,その極端なものが日本人単一民族説になったといえるのだろう。
ついでながら,日本神話に関わる道教がどうなったかを確認してみると,応神天皇渡来時の中国(三国時代)は,道教の仙人を崇める宗派の反乱が相次いでいたといわれる一方,山東省を中心に,宗教としての体系化も一気に進められて,徐福も担った神仙思想の経典の筆頭「三皇経」が重視され,そのなかには,世界に最初に登場する三人の帝王として,天皇・地皇・人皇が挙げられている。道教は,新羅にも伝わっていて,秦氏がそれらの知識を携えて渡来し,天皇中心の神話体系の構築に関与していったとも考えられるのである。
最後に,神社とともに日本を支配することになる仏教について触れておくと,神社体系が,民族それぞれをまとめて国家に統合しようとしたのに対して,仏教は,階層それぞれに対応するものとして,各宗派が登場する。律宗・三論宗・華厳宗などは大陸から移入したままのものであったが,空海の真言宗,最澄の天台宗が朝廷(天皇と公卿),浄土宗が広く貴族に,禅宗では,道元の曹洞宗が個人の確立を求めて広がらなかったのに対して,栄西の臨済宗が武家政権と密接につながり,親鸞の浄土真宗は農耕民族の救済に,日蓮宗は主として商人に対応,そしてあたかも白山信仰のようなものとして,社会の最下層の人たちに対応する時宗が登場するのである。
この章TOPへ
ページTOPへ
第5論:継体天皇を契機に,蘇我氏,藤原氏が登場し,天皇制が確立~古代
ここから先は,いわゆる歴史時代に入るので,日本史話の第二講の「時代循環のパターン」も参照してもらいたい。この章が「古代」で,のちの章では,「中世」「近世」「近代」という枠が登場する。>時代循環のパターン
第1話:推古天皇・聖徳太子を戴く蘇我馬子による日本統治のプロトタイプ
イ:応神朝の行き詰まり
(マツ系の名残の)葛城氏と(物部氏系の)吉備氏をともに制圧して統一を実現した雄略天皇が,倭の五王の最後になっているのは,国土を確立して中国の力を必要としなくなったのか(江戸時代の鎖国のように),中国側の動乱によって朝貢そのものができなくなったのか分からないが,中国のお墨付きが無くなり,雄略天皇が覇権をとるにあたって有力な対抗馬を次々と消していってしまったため,その後は天皇家自身も力が急速に衰退,天皇陵も急速に小型化して行き,武烈天皇に至って,ついに,後を継ぐ子がいないという事態に陥る。
天皇の血が途絶えるのを阻止すべく大伴金村が活躍して,前述したように,渡来した応神天皇が越前の角鹿(ツヌガ・現在の敦賀)まで至った際に,土地の豪族の娘に産ませたと思われる子の末裔という由緒ある人物を探し出し,507年に,継体天皇として擁立する(まさに体を継ぐというこの名は,前述したように,ずっと後になって,淡海三船が歴代天皇の漢風諡号を一括撰進した時につけられたもので,この天皇の役割を直截に示している)。継体天皇擁立時に越(古志)つまり現在の北陸地方の話が登場するが,のちに,大和にある山と同名の二上山を足場とする大伴家持に古志の歌があるように(ついでながら万葉仮名,つまり漢字を用いた音表記は朝鮮のものとほぼ同じであった),大伴氏と越の関係が深かったからと思われる。>漢風諡号
すでに述べてきたように,大伴氏は(オシ系の)崇神東征を支えた氏族で,継体天皇にオシ系の妃を迎えさせ,後継した三人の皇子,安閑,宣化,欽明の三代の天皇は,いずれもその倭名にオシを含むように,継体天皇を利用して,徐福につながるオシ系皇統が再興されたことにもなり,物部氏の勢力が伸長するように見えたが,継体天皇陵とされる古墳は再び大きなものになるものの,その場所は北摂の淀川沿いで,大和や河内の天皇陵から遠く離れた場所であり,つまり,継体天皇が,大和からは受け入れられなかったということも示され,そのことが,次の蘇我氏による王権簒奪の傍証になっているように見える。
ロ:継体天皇の登場を契機に,蘇我氏が王権簒奪を画策
水谷千秋「継体天皇と朝鮮半島の謎」によって,継体天皇のことを少し詳しくみてみると,かつて仁徳天皇が河内入りした時,秦氏と新羅人の一部は,そのまま淀川を遡り,途中で太秦という秦氏の拠点(その背後には新羅人の広がる嵯峨野がある)を造った後,近江に至り,高島郡を秦氏の拠点として,近江全体が新羅人の広がる滋賀の国になって行くが,継体天皇を生み出すことになる秦氏は,ここで新羅人とともに,故郷の朝鮮半島と交易し,財政基盤を固めて行く。ついでながら,高島郡(現在は高島市)は,その後も,すべての政権にとって,歴史的な要所であると認識されていたようで,足利の代々の将軍も,ここに,立派な庭園を持つ別邸を造っていたといわれる。また,近年,衰退の著しい百貨店業界で,唯一,健闘している「高島屋」は,創業者飯田新七が婿養子に迎えられた,高島郡出身の米屋の屋号によるのであり,三井はじめ,いわゆる近江商人と同様,秦氏すなわちユダヤ人と関係していると思われる。
継体天皇当時,関東最大の氏族は上毛野氏であったが,一族から朝鮮半島に渡航した者が多いことから,新羅人だったと思われ,のちの新田氏,足利氏の祖になったとも考えられる。河内国の仁徳天皇ゆかりの地を示す讃良郡には,そのまま馬飼首一族が残っていて,継体天皇家とも繋がっていた。この近くの寝屋川には京都と同じ太秦の地名もあり,秦氏のもう一つの本拠地であったし,淀川流域には秦氏が広く分布し,継体天皇を支える役割をしたと思われる。
継体天皇は,九州有明海沿岸勢力(かつての狗奴国(クマ系)の末裔が主体)と組んで,マツ系・出雲族の末裔葛城氏に対抗し,継体天皇が大和で居を定めた磐余玉穂宮は,当然のことながら,もともと(クマ系)大伴氏の本拠地で,その前にいたのは妃の実家にあたる忍坂宮(オシ系)だった。継体天皇とともに近江から大和に進出したシラギ系とみられる蘇我氏は,衰退した葛城氏の権益を相続して,急速に伸長して行く。磐井の乱後は,有明海沿岸勢力と疎遠になって行くが,百済の武寧王と密接な同盟関係を結び,五経博士が来日,蘇我氏が仏教を背景に覇権を狙うようになって行くのである。
その間,朝鮮半島では,532年に任那が新羅に降伏,任那の王族が新羅の最高官位を与えられるが,朝鮮半島における倭の国際交易上の権益は失われた。任那の王族が丁重に扱われたのを見て,安羅の王族が新羅に接近,562年には安羅その他を含む加羅が新羅に制圧され,倭とつながった加耶諸国全てが滅亡するに至って,朝鮮半島は名実ともに三国時代に入り,564年には新羅は北斉に朝貢して初めて(高句麗の属国でなく)独立した王国として認められる。新羅の高官として扱われる安羅の王族で日本に渡来したのが,蘇我馬子その人ではなかったかという説すらあり(中臣鎌足が百済の王子だったという説を彷彿とさせる),自らの出身を示す(安羅国の村)アスカ,すなわち飛鳥を本拠地とすることになる。滋賀県草津に新羅王子が祭神の安羅神社があるのも関係しているかもしれない。つまり,蘇我氏は,仏教を採用したことで,みかけは親百済でも,もとは新羅に近かった可能性が高いと考えられるのである。
そして,581年に建国した隋が,589年中国全土を再統一すると,百済と新羅が積極的に朝貢するなか,高句麗は距離を置き,半島全土を支配すべく百済・新羅への侵攻を企図,両国から助けを求められた隋の2代目煬帝が高句麗征討に乗り出すと,その間を狙って,百済が旧加耶諸国領を回復すべく新羅に侵攻する。
以上のように,継体天皇の側近として伸長したとされる蘇我氏であるが,朝鮮半島で日本とつながりの深った百済系の伽耶諸国のうち,とくに,日本府が置かれていたという安羅の王族出だという蘇我稲目が,継体天皇の子の2人天皇を弑殺し(後を継いだ形跡が無い),欽明天皇を擁立して,新たな文明たる仏教を武器に覇権を握ろうと,親百済政権を樹立(王権簒奪)したらしく,大伴氏が再び勢力を拡大するはずのところ,直後に金村が失脚する事態になったのは,その陰謀によるものと考えられる。蘇我氏にとって,残る大きなライバルは,オシ系以来の神道を支える物部氏ということになり,神道を支配する物部氏に対して,仏像崇拝問題を利用して,暗躍することになるのである。
筑紫磐井~オシ系のルーツたる九州北部の有力者で,抵抗するもハタ系王朝に敗れた~
継体天皇21年(西暦527年)に起きた「磐井の乱」は,筑紫磐井が,新羅の支援を受けて倭王権と対峙した大事件として「日本書紀」「古事記」に記され,任那復興のために派遣された近江毛野を阻止したことに始まり,毛野が'昔は同じ釜の飯を食ったではないか'というも,'使者になんか従わない'と戦を起こしたため,物部麁鹿火によって討伐された。古代史の会「人物で学ぶ日本古代史 1:古墳・飛鳥時代編」(2022年)によれば,「反逆者か,もう一人の王か,それとも」のサブタイトルがつけられている磐井が生前に造った自らの墓は,福岡県八女市岩戸山古墳とされ,北部九州では最大規模で,ムリテの江田船山古墳に近いことからも,倭王権の最有力者であったとみられ,この事件は,倭王権が,新羅を中心に独自の外交ルートを持って危険な存在となっていた磐井を討伐して,その一元化を実現したこと,それ以上に,磐井の力の象徴だった糟屋屯倉が献上されて,ミヤケ制が始まり,それによって国造制が成立したことが大きく,歴史のターニングポイントであったという。
欽明天皇~その子は,敏達,用明,崇峻から,歴史上,生没年の明確な最初の推古天皇まで兄弟~
一般には,継体天皇をして,現在の天皇に至る一つの王朝としているが,古代史の会「人物で学ぶ日本古代史 1:古墳・飛鳥時代編」(2022年)によれば,継体は,前大王との血縁関係で正統性が無く,仁賢天皇の娘手白香と結婚したことによって担保されており,厳密には,両者の子の欽明天皇によって誕生したことになる。継体に続く,尾張連草香の娘目子媛との子,安閑,宣化天皇については,即位年,没年にいろいろ矛盾があり,欽明を認めないグループとの対立があったためで,両者の存在さえ疑わしいとする説すらあり,また,天皇の権威を確立する部民制,ミヤケ制の導入,任那復興会議が開催されること,日本独自の厚葬墓である前方後円墳に葬られた最後の大王であることなどから,現在に続くサブタイトルにあるように,「世襲王権の始祖」とみなせるという。実際,欽明没後に即位したのは宣化の娘との子敏達,その没後は蘇我稲目の娘との子用明,続いて,稲目の別の娘との子崇峻,そして,用明と同母で,敏達の皇后であった推古が,歴史上,生没年の明確な最初の人物として登場,欽明から世襲王権が開始され,政体の安定化,国家の形成が大きく前進したのである。
ハ:仏教を武器に,神道の物部氏を倒して,覇権を握った蘇我馬子
隋という強力な帝国が中国に登場したことを背景に,(後に,織田信長がキリスト教を笠に着て,既成仏教を叩いたように)蘇我馬子が百済伝来の仏教を笠に着て,オシ系がつくった神道を支える物部守屋を討滅するという,史実が明確になっている日本史上最初の大事件(587年の丁未の変)を起こし,倭名に「ササギ」が入る崇峻天皇を擁立するものの,意のままにならないことから,弑殺するという恐るべきことまでして,いずれも血縁のある推古天皇を擁立,聖徳太子を摂政にして,まさに,蘇我王朝を実現するのである。
ここで再び倉塚曄子「古代の女」によって補足すると,日本古来のヒメミコ制,つまり,霊的能力をもった女王と,その兄・弟の男王による国家支配の名残がまだ生きていて,推古天皇を戴かざるを得なかったということになり,男王として,甥の聖徳太子が摂政にされたと考えることができるだろう。
実に,中国では蘇我馬子が王であると思われていたということで(後の江戸時代に徳川将軍が王と思われていたように),有名な小野妹子も,中国で蘇因高と名乗っているので,蘇我馬子その人ではないかとさえ言われるほどであった。伝説にすぎないかもしれないが,憲法十七条など,日本の原型を創り出すとともに,「天皇記」「国記」などの史書編纂をしたというから,(政権の正統性を示すべく)日本神話の第一段がまとめられたと考えられる。
守屋の遺族たちは諏訪へ落ち延びてモレヤ神となり,善光寺には守屋柱,諏訪大社のご神体守屋山となるに至ったことは既に述べたが,そのことが物部氏がいかに全国的に強大な勢力を持っていたかを示すものといえるだろう。いずれにしても,蘇我氏が陰謀をもってライバルを潰して行き,天皇を戴いて実権を握る姿は,次に登場する藤原氏を彷彿とさせる。しかし,百済王族出身の中臣鎌足からみれば,蘇我馬子は配下の一小国の王子に過ぎず,滅ぼされることになるのである。ずっと後,(マツ系とはいえ,呉では被支配層の末裔)豊臣秀吉と(マツ系本流の呉太白の末裔)徳川家康の関係と同じように見える。
以上見て来たように,徐福渡来後,さらに言えば卑弥呼登場後,いわゆる天皇を擁立して実権を振るう支配層が,朝鮮半島との関係で親百済,親新羅のような形で交替してきたが,朝鮮半島での相克が高まるのに対応して,この傾向が明確になって行く。これまで,当然のごとくに,天皇の呼称を使ってきたが,実際は,大王(オオキミ)といわれ,各豪族間の綱引きの力関係で定まるものであった。史実が明確になっている日本史上最初の大事件(587年の丁未の変)を制した蘇我馬子が,推古天皇を擁立したのは,それまでの豪族間の調整を無視する力づくのものであったことで,新たな時代に入ったことを示すと同時に,推古天皇もまた生没年が確実な初めての天皇ということで,587年は,日本史年表の起点となり,ようやく歴史時代に入るわけである。
物部氏の滅亡によって,神武・崇神・応神・継体皇統という形で続いてきたオシ系とそれにつながるハタ系の天皇による支配も終わったと言える。聖徳太子は厩戸皇子であり,その生誕伝説がキリストのそれに極めて似ていると言われるが,おそらく太子も頭脳明晰であったことなどユダヤ人であり,その伝説は,秦氏を介して中国から伝来したネストリウス派キリスト教(景教)の影響で,キリストに並ぶ天才として創り上げられたのだろう。本拠地が斑鳩の里で,まさに河内と大和の境界であること,秦河勝が広隆寺を建てるのを支援したこと,平安京遷都の前にすでにあったとされ,聖徳太子によって造られたという六角堂も,その形は,ダビデの星に由来すると考えられることなど,秦氏と極めて強い関係にあり,なお応神皇統が続いていることにもなるが,聖徳太子の死とともに,秦氏すなわちユダヤ系の人たちの力は一気に没落,蘇我馬子の子蝦夷が一族を無きものにしてしまうに至り,応神皇統は完全に終わりを告げる。
聖徳太子に関連する史跡は,推古天皇陵などとともに,応神皇統の天皇陵の集中する河内と大和を結ぶ斑鳩にあるが,聖徳太子はオシ系(ハタ系)最後の華であり,それが太子信仰を生んだのだろう。フリーメーソンとの関係が取り沙汰される日本銀行発行の高額紙幣に聖徳太子像が使われたのもムベなるかなだ。太子の遺児一族も抹殺されてしまうと,ユダヤ系の秦氏を繋ぎとめるものもなくなり,ヨーロッパのユダヤ人と同じように,次第に差別され貶められ,芸能などを業とするいわゆる河原者にもなって行ったようだ。
ところで,天皇制のことを考えてみると,その権威が,位階の授与と元号をはじめとする暦によっているのはいうまでもないが,その二つともが,大陸から輸入されたもので,日本古来のものでは無く,大和魂などを強調する面々にとっては最大の矛盾といえ,天皇の存在を危ういものにすることも否めない。その解決策として創り出されてきたのが,聖徳太子という人物と,その伝説であろう。それ故,近年,「聖徳太子はいなかった」というような過激な書物が出たし,確かに,聖徳太子の具体的な史実はあまり定かではなく,今後,蘇我氏との関係も含めて,見直しが求められる。
こうして,蘇我氏のいわゆる専横が始まるが,大陸では,隋は4度にわたって高句麗に侵攻するも成果があげられなかったばかりか,隋本体の疲弊を招き,部下の反抗を受けて618年煬帝は暗殺され,李淵が唐を建国するに至る。唐は,隋を超える圧倒的な力を背景に,朝鮮の三国をそれぞれに,中国支配の古地である遼東郡,帯方郡,楽浪郡に割り当てる形で冊封し(高句麗はランクとして一つ上に扱われた),安定を図ろうとしたが,唐の権威を背景に百済が新羅への侵攻しようとすると,新羅は隋との戦いで疲弊していた高句麗への侵攻を図るというように抗争は続く。新羅に初の女王が登場後,642年に,百済は旧加耶諸国領の回復を実現し,久しぶりの隆盛迎えるが,新羅の力を得られなくなった直後の645年に,百済王族と思われる中臣鎌足が中大兄皇子を唆して蘇我氏を討滅(乙巳の変)するに至るのである。
第2話:中臣鎌足と天智天皇,天武・持統天皇,そして藤原不比等による,天皇神話の確立
一行にまとめてしまえば,百済王族中臣鎌足が天智天皇とともに端緒を開き,王権簒奪した天武天皇が天皇,日本の称号はじめ骨格をつくり,持統天皇が天皇を神にし,藤原不比等が日本神話を仕上げ,クダラ的藤原氏の時代の礎をつくったということになろう。全く別の角度からみれば,皇極(斉明)天皇に始まり,持統天皇という存在感大きい天皇を経て,不比等が擁立した元明,元正天皇,そして,不比等の娘で,聖武天皇にもまさる存在だった光明皇后,そして,その娘の孝謙(称徳)天皇が天皇制の危機を招くという,実に,転変著しい女帝の時代でもあった。
イ:クダラ系藤原氏の祖中臣鎌足とナカ系の中大兄皇子による乙巳の変
専横はなはだしい蘇我入鹿は,蹴鞠を通じて親しくなったという中臣鎌足に唆された中大兄皇子により,645年に,滅ぼされるのであるが(乙巳の変),張本人たる中臣鎌足が,突然のように歴史に登場してくることが,かねてより,謎であった。このことについて,朝鮮三国時代の百済のところでも触れた,関裕二「藤原氏の正体」のいうとおり,554年に新羅に完敗した百済から,再興を図るべく日本に亡命した王族のなかに,中臣鎌足がいたとみるのが分かりやすく,631年に人質として来日していた王子扶余豊璋その人だったとしても不思議はないと考えられる。前節で,安羅出身だった蘇我氏が,アスカ(飛鳥)を本拠地にしたのと同様,おそらく支配地だった伽耶(カ)出身を示す村(スカ),すなわち春日(カスガ)を本拠地としていたことからも予想されることではあるが・・・。
641年,27歳の時に歴史に忽然と登場した鎌足は,631年には18歳ということで,まさに王子扶余豊璋にふさわしい年齢であり,百済滅亡翌年には各地で百済の遺臣らによる復興軍が蜂起,そのうちの鬼室福信が倭に渡来して,631年以来人質に置かれていた百済王子扶余豊璋の帰国を要請している。(新羅で武烈王が崩御した)661年には,中大兄皇子が,その帰国を認めるとともに派兵も決定するが,662年に帰国した扶余豊璋は,翌年,鬼室福信の謀叛を疑って殺害させるなど内部抗争もあって,倭・百済復興軍は有名な白村江の戦で,唐・新羅連合軍の前に大敗してしまう。中大兄皇子が政権奪取した乙巳の変には大々的にでてくる中臣鎌足が,その後の動静についてほとんど明らかになっていないことも,このように動いていたのだとすれば頷けよう。なお,新羅の配慮で,倭の残兵は百済の遺臣とともに帰国し(新羅のやり方には常に敗者を丁重に扱う特徴が見られる),倭に残っていた扶余豊璋の弟はそのまま帰化して百済王(コニキシ)という姓を与えられている。
ところで,のちに,大内氏の本拠になる山口の西側部分は吉敷川を軸にした吉敷とういう地域で,そのまま名字にしている人たちもおり,"キシキ"と読まれている。もともとの"キシキ"という語に,漢字を当てたものであることは,当然とみられ,歴史との関係で,各所に見られる"〇〇キ"という語と同様,"キシ"という人たちが来たところを示すだろう。そこで,"キシ"とは何ものかを調べてみると,なんと,「釈日本紀」の秘訓に,百済の王族を示すものとして,"君"を"キシ"といい,"王"は"コキシ",大王になると"コニキシ"という訓みが伝えられているのである。扶余豊璋の弟に与えられた百済王(コニキシ)という姓のもとの語が"キシ"なのであるから,まさに,吉敷の地は,百済王族がまとまって亡命してきたこと場所だったのである。>大内氏
ついでながら,百済亡命後,倭に亡命し,百済復興をめざした百済王族鬼室福信の姓「キシツ」は奇妙な感じがするが,"キシ"が百済王族のことを指す語であると知れば,「"キシ"つ」は,すなわち「"百済王族"の」と単刀直入の姓であることも分かり,百済奪還をめざして,斉明天皇率いる倭軍が潮待ちをした伊予国熟田津の近くには,来住と書いてキシと読む町もあることにも興味が惹かれよう。
その山口のすぐ北側が長門国,すなわちナカ系の本拠地のひとつであったことから,そのナカ系の支援も得て渡来した百済王族が,中臣氏の姓を借りることになったのは自然の成り行きだっただろう。そして,古代では,皇子の名に,乳母の家柄の名が入れられるのが習わしだったということなので,中大兄皇子の乳母がナカ系であったことが知られ,鎌足との縁が,幼い時からのもので,以心伝心の関係にあったことすら示しているのである。鎌足の死去から,その子の藤原不比等が登場するまでの様子も不明であり,長州(山口県)が,重要な役割をしていたとみて良いだろう。
神武東征伝説から,応神東征説までを,振り返ってみても,どういうわけか,現在の大分県,宮崎県から,四国に渡り,そのまま東進,あるいは岡山県を経て東進というように,山口県が避けられており,朝鮮半島の諸国との関係で,奴の国を迂回しなければならなかった事情があったと考えられるので,百済王子を匿うには絶好の場所でもあったのではないだろうか。
さらに,内倉武久「謎の巨大氏族・紀氏」によれば,年号(元号)が日本全体に行き渡る正式なものになったのは,大宝律令による大宝からで,それ以前には,いわゆる私年号があちこちで使われており,そのほとんどが朝鮮で使用されていた年号で,九州年号といわれる。"市民の古代研究員"によって発掘された一覧を見ると,長野県善光寺のように存在そのものが特別なものは別にして,山口県での使用例が異常に多いことが分かる。つまり,長州では,百済の年号を使い続けていたと考えられるのである。
鎌足の本姓は,藤氏だったことから,藤原姓を与えられ,のちに藤原不比等が,わざわざ藤原姓を自らの一族のみに限るとして,中臣姓の痕跡をも消そうとしたのも当然であった。蛇足ながら,鎌足は当初,鎌子と呼ばれており,"子"というのは,孔子,孟子と同様,単なる敬称であるとすれば,鎌(カマ)の語に意味があるように見える。鎌の字がそのままを表しているとすれば,まさに鉄器文明化した農耕民族,つまり百済に近いことが示され,長州の本拠地萩に鎌浦の地名があり,カマが釜の字になると,現在でも,長州の下関とフェリーで直結する韓国の釜山につながることになる。
(付)最新の資料による中臣鎌足の百済王子説の再検討。
新古代史の会「人物で学ぶ日本古代史 1: 古墳・飛鳥時代編」(2022年)において,まず「中臣鎌足~積善藤家の祖~」の項をみると,知られている鎌足の伝記は,「日本書紀」には極めて簡単に,「大織冠伝」には,かなり詳しく記述されているものの,前者は藤原不比等が藤原氏の正統性を示すべく差配し,後者は藤原仲麻呂が,藤原氏の祖たる中臣鎌足の偉大さを強調すべく独自のアレンジを加えたものであって,そもそも,資料としての価値が疑われるものであるが,後者に従えば,まず,「舒明朝の初めに良家の子を簡び錦冠を授け朝廷の祭祀を掌る中臣氏の宗業を嗣がしめたが,鎌足だけは固辞して摂津三国の別業に退いた」という。>そもそも中臣氏ではなかったということではないだろうか。また,中大兄皇子が天智天皇になったことを禅譲と強調しているのは,孝徳と対立して飛鳥に帰還した直後に,紫冠と封戸が与えられたということなどから,そもそも,鎌足は軽皇子(孝徳天皇)の即位を画策し,孝徳天皇とは良好な関係にあったが,天智天皇に乗り換えたのであり,蹴鞠伝説などは,大陸の類似の話の借用という。>いずれにしても,皇位に就き得る人物を利用して権力を築こうとしたということになる。究極の創作は,孝徳天皇が即位した大化元年に大錦冠を授けられたという話で,大錦冠が制定されたのは大化3年であり,そもそも,鎌足の改新に関わる事蹟は,ほとんど史料上にみられないという。>要するに,全く異なる扱いを受ける立場にあった人物ということになろう。鎌足は死の直前に,天智天皇から大織冠と大臣の位と藤原姓を賜与されたが,大織冠は後述する百済王子豊璋のほかに例はなく,死去すると,百済からの亡命者沙宅紹明がその碑文を撰したという。さらに,正室は鏡女王とされているが,王族を妻とするのはあり得ないと,虚構説もあるという。>鎌足が百済王子であったことを示しているといえるのではなかろうか。
もう一つ「余豊璋と百済王子~百済王家の滅亡とその後裔~」の項をみると,百済王子余豊璋は,倭に滞在中,百濟が新羅に滅ぼされたため,その翌年の661年,復興を目指す鬼室福信ら遺民の要望で帰国し,百済王に冊立されるも,その翌年,確執を生じていた福信を斬殺,白村江の戦に敗れ,高句麗に逃亡し,以後,消息不明とされいて,本当に百済王子であったのか,いつ来日し,それは,亡命か,使者か,人質かが謎とされている上,帰国に際して,中大兄皇子から織冠の位を授けられ,多氏の娘を妻に与えられて故国に護送されたという。そして,兄豊璋とともに来日したという弟善光が百済王氏(クダラノコニキシ)の祖になり,有名な百済王敬福らを輩出したという。>前述の話と符合する上,その後は不明になっていることから,鎌足百済王子説を否定し去るには不十分で,百済王族を示すキシの名が後々大きな意味を持って行くことも,大内氏の項で述べることにつながると言えよう。
なお,政権獲得にあたって,蘇我氏によって没落させられた物部氏の復活の願望も取り入れたとすれば,本来物部氏のものであった鹿島神宮を自らのものにしてしまうことができたと思われる。
この間,大陸では,唐の太宗も相変わらず目の上のタンコブのような高句麗の存在に,同じ645年には,その征討を企図して出兵し,各地で激戦を繰り広げるが,結局全軍の撤退を余儀なくされ失敗に終わる。その後,新羅の内紛に乗じて百済が再び侵攻したため,新羅は倭に助けを求めるも,乙巳の変後で叶わず,新羅の金春秋は,649年から,唐の服装採用を許可されてその権威が利用できたのも束の間,太宗の崩御によって窮地に陥いるが,この年侵攻してきた百済を,軍事力というより軍の統制が断然上回っていたことで撃退すると,654年,群臣に奉じられて武烈王になり,早速,唐の律令を模範に格を制定する(日本で天武天皇が中国の諸制度を採用するのに対応するといえよう)。翌年,百済は再び新羅に侵攻するが,659年,武烈王の要請を受けた唐の高宗が出兵し,ついに滅亡してしまう。余談であるが,後の日本の源平の戦いで,源氏が勝利したのはその統制力であったとされ,源氏がシラギ系であったことを示すものでもあろう。
(付)伊予国,そして熟田津
滅亡した百済を奪還すべく,斉明天皇が率いた軍が,潮待ちのために滞在した伊予の熟田津について,額田王の有名な歌があるが,額田王は壱岐国の出であり,アマ系すなわち卑弥呼の末裔にも当たる巫女的な女性であったと思われる。卑弥呼が死んだ後を継いだのが臺(台)与(トヨ)で,トヨの国のもとになったとされるが,トヨはまた,壱岐由来を示すように,壱与すなわちイヨとも表記され,伊予の旧表記が伊与であったことを見れば,そのまま壱与であり,豊後灘を挟んで,豊の国の向いの伊予国のもとにもなったと考えられる。想像をたくましくすれば,トであり,イであるのは,ものとの伊都国を二つに分けたものでもある。とすれば,額田王にとっては,熟田津こそ,自らの原郷であり,それ故にこそ,あの傑作が生まれたともいえよう。
その伊予では,崇神朝との微妙な関係をともにし,すでに支配していたクマ系の久米氏と一体になったようである。ついでながら,同じクマ系の紀貫之が土佐に出向したのも,照葉樹林民族としては当然であったろう。そして,周防灘を挟んで向かいの周防国の吉敷(キシキ)が百済王族末裔の地であることを示すように,伊予にもまた,来住と書いて,キシという地があるように,百済王族末裔もいたようである。実際,百済奪還をめざす倭軍には,百済王族の鬼室(キシ・ツ=の)福信が将軍としていたのである。しかるに,歴史時代に入ると,伊予の国衙は,物部氏出身とされる越智氏が支配する現在の今治に置かれようになったのである。記紀には,伊予国についての記載が非常に少ないということであるが,大和朝廷には記すのが困難な地でもあったのだろう。
(付終り)
ここでまた,道教の話になるが,大帝国だった唐は,実は,仏教を蔑み,道教を重んじた国だったため,仏教を究めるべく遣唐使の船で唐に渡った日本の僧は,有名な円仁をはじめ,苦労することになる。そもそも,あの鑑真が,あれほどまでの困難を乗り越えて日本に来ようとしたのも,唐の仏教の行く末に絶望していたからと考えられる。いずれにしても,政権のために,遣唐使が持ち帰ったものは,道教にかかわるものが多かったということになり,後述するように,神話体系の再構築にも大きな影響を及ぼしたといえよう。
ようやく即位できた天智天皇が,670年に,日本で最初の整った形での全国的な戸籍「庚午年籍」を始めたこと,現代の戸籍が,明治維新後の,明治5年式戸籍(一般的には「壬申戸籍」に始まることは,良く知られているが,戸籍が,日本人全てを登録したものであると言いながら,天皇には戸籍が無く,苗字も無いのである。このことは,天皇のルーツはもちろん,その時代における,天皇の血のつながりをも隠そうとするもので,結果として,いわゆる万世一系が成り立っているのである。おそらく,ルーツに関わったユダヤ人の知恵だったのだろう。
さて,中臣鎌足の登場は,新羅が支配する朝鮮半島を追われた百済が日本を支配しようとしたことによるものではあるが,乙巳の変で蘇我入鹿を滅ぼすものの,天皇家そのものは新羅渡来の応神皇統の延長にあり,蘇我氏全体との関係も途切れず,親新羅の姿勢を変えなかった孝徳天皇が654年に崩御して後も,斉明天皇の力が強く,なかなか即位できないうち,鎌足の意向に添うべく新羅に侵攻して,663年,白村江の戦で大敗,その圧力を避けるべく667年,大津京に遷都,翌年に母天皇が死去して,ようやく即位し,鎌足に藤原姓を授与するものの,まもなく死去,壬申の乱に突入することになる。
斉明天皇は,中大兄皇子の母で,史上初めて皇后から天皇になった皇極天皇が,史上初めて重祚して斉明天皇になったのであるが,庭園等の大きな施設を造ったことが,遺跡の発掘で明らかになっており,そのなかで,「天宮」とも呼ばれた両槻宮(フタツキノミヤ)という建物は,道教の,仏教でいえば寺院にあたる道観である可能性が高く,庭園も,道教の神仙思想にもとづく様式であったようで,それほど,道教の影響の大きかったということである。
ここでまた,倉塚曄子「古代の女」をみてみると,大化の改新とはいいながら,なお,ヒメミコ制の名残は続いていて,国家の安定支配のためには,霊能の力を持った女王の存在が必要であったことから,母に重祚してもらった(この場合のミコは兄弟でなく男子ということになる)といえるが,「日本書紀」には,斉明天皇は巨大な土木事業などによって人民を苦しめたというのをはじめ,きわめて悪い女帝として描かれていて,律令国家にとって,霊能は排除されるべきものという建前もさることながら,自らの支配の正統性を示すことを目的として神話「日本書紀」をまとめた藤原不比等の意図が反映しているようである。つまり,自らの父が担いだ天智天皇の立派さを示すため,その時代に生じたマイナス面は全て斉明天皇に押しつけようとしたということである。
いずれにしても,中臣鎌足の段階では,蘇我馬子が,推古天皇を戴いて覇権を握ったようにはいかず,その方式を確立するのは,子の藤原不比等に託されるのである。
ロ:アマ系大海人皇子による壬申の乱から持統天皇死去まで~天皇親政によるシラギ系政権
天智天皇が崩御すると,その翌年の672年に,その後継の大友皇子に対して,天智の弟の大海人皇子が謀叛,大内乱となった壬申の乱を制して,天武天皇として即位,まさに,王権簒奪であり,大海人皇子は,その名が示すようにアマ系の海部氏,すなわち,応神天皇を支えた氏族に養育されていることから,シラギ系の巻き返しでもあった。新羅からの圧力への恐怖から,諸豪族の間に,親新羅の強力な天皇を求める意識が芽生えたことが,その背景にあったともみられ,後の元寇や明治維新など,日本人は内部では抗争していても,大きな外圧が生じると一気に神国として一体となってしまうあり方がこの時生まれたともいえるだろう。
天武天皇は,皇族を重視する親政により,ヒメミコ制から男王支配への一元化を完成させただけでなく,浄御原令によって本格的な律令制の導入を図るとともに,初めて,日本という国名や,天皇という呼称を用い,史書「日本書紀」編纂に着手するなど,現在につながる枠組みをつくり,さらには,本格的な首都となる藤原京の建設も企図したが,志半ばで倒れてしまう。一つだけ触れておくと,天武天皇は,国土支配の枠組みを評制から,郡制へ変えたのであるが,その令を諸国に出すにあたって,長門国のみ除外していて,学界の謎とされてきたが,長門がそもそも藤原氏の支配下にあったことを考えれば当然であったといえよう。
クダラ系天智天皇の娘でありながら,諱が鸕野讚良(ウノノササラ)というように,シラギ系であるままに,天武天皇を支え続けた持統皇后は,夫の遺志を継ぐべく,とりあえず称制し,天武天皇との間の子である草壁皇子を皇位につかせようとするものの,夭折してしまったため,自らが天皇に就くことを企図するが,そこで障害になったのが,夫の天武天皇が王権を簒奪したという事実であった。そのため,天皇の地位というものが,神から授かれるもの,いわゆる天皇神授による正当化を図るべく,現在では当たり前のように思われている,天照大神から始まる神話や,それに対応する儀式などを創り上げたのである。>神様の家系図
何度か触れてきたように,神武天皇からの歴代天皇の漢風諡号は,孝謙上皇皇時代に,淡海三船が一括して撰進したものであるが,持統の名は,継体持統という熟語からとったもので,継体天皇同様,断絶を回避する役割を担った天皇であることを示しているので,その存在は,正確に認識されていたといえよう。ついでながら,天智,天武と,神でなく,天を用いて両者をセットにしたことは,その後の日本の創始者であることも示そうとしたものだろう。>漢風諡号
壬申の乱によって,中臣鎌足の試みは頓挫するかに見えたが,その子藤原不比等が,持統天皇に仕え,天皇の覚え目出度かった女官県犬養(のちに橘姓を与えられる)三千代に接近して,婚姻関係を結ぶと,持統天皇が天智天皇の娘であったこともあって,おそらく,前述の天皇神話づくりの相談にものるなどして地位を築き,藤原姓を自らの一族,すなわち正統的百済王族に限ることを実現し,百済に学んで,日本史上最初で最大の都城であるとともに,藤原の名を冠する藤原京の建設や,大宝律令の編纂も主導,その完成直後に,持統天皇が死去すると,以後,蘇我馬子が推古天皇を戴いたのと同じように,藤原不比等は,元明天皇,元正天皇を擁立して覇権を確立するのである。
この間,朝鮮半島では,百済滅亡後,高句麗内に政治的混乱が起きたのを知った唐の高宗が,前回の失敗を取り戻すべく,666年に出兵を決定,668年,扶余城を落としたのに続いて,新羅にも出兵を命じ,平壌城を陥落,こうして,朝鮮において,最も歴史が古く勢威もあった高句麗もついに滅亡してしまう。その結果,唐の圧力が直接及ぶ状態になるとともに,高句麗遺臣らの復興運動にも悩まされた新羅が,高句麗王族高安勝に金姓を与えて新羅の貴族とし取り込むうち,かつての高句麗北部に靺鞨や渤海が勃興,成長して,唐も朝鮮半島から手を引かざるを得なくなり,735年,唐の玄宗は大同江以南の地を新羅に割譲,以後,統一新羅は安定して成長して行くことになる。
付け加えると,律令国家の形成とともに,巫術・卜術の役割は減じて行くが,なお,諸儀礼の卜定などにおいて重要な役割をしていて,神祇官には卜部が置かれ,かのアマ系卑弥呼のルーツで伊都国に属していた対馬・壱岐から選ばれていたというから,その名残の強さが知られる。その他,伊豆国からも選ばれていたというから,伊豆国が九州北部を追われた伊都国の人たちによってつくられたことも間違いなく,平氏のルーツがイト系であることへの傍証にもなるだろう。
蛇足ながら,仏教史上,聖徳太子や行基と並ぶ重要人物で修験道の祖ともされながら,699年,伊豆に流されたという役小角(エンノオヅヌ)は,かつてマツ系(出雲族)の後裔が拠点とし,百済ともつながっていた大和の葛城の地で生まれ,呪術その他極めて道教的要素を備えた人物であったが,本姓は賀茂氏だったといい,まさに,日本に渡来した当時の呉の国人の遺伝子を体現していて,国譲りして敗れたマツ系のシンボルになったと考えられる。ずっと後の徳川家康が,マツ系の復活であったことを説明する際に,再び登場するだろう。
ハ:藤原不比等の覇権,その子孫と皇族との抗争から,道鏡登場による危機まで~奈良時代
前項末を繰り返すことになるが,持統天皇が皇后の時以来側近であった橘三千代に,鎌足の子不比等が接近して結婚,権力を握るようになり,藤原姓を自らの一族に限定することにも成功する。702年持統天皇が死去すると,あとを継ぐ適当な男子がいないのをいいことに,蘇我氏の方法をなぞるように,繋ぎとして,未婚皇女を元明天皇,元正天皇としてたてるとともに,新たに平城京という本格的な首都を建設して,単に守旧派を遠ざけただけでなく,天皇,貴族,寺社などが活動する舞台を生み出し,持統天皇が創り上げた"神授による天皇"を支える藤原氏という形で支配を正当化するように,それまでの神話体系「日本書紀」をクダラ系の立場で書き換えて(蘇我氏を貶めて)完成,以後の日本の神話の決定版にしてしまうに至る(「播磨風土記」などの編纂者もクダラ系らしく,不比等が自ら都合よくなる方向でまとめさせた可能性がある)。
この間も,親新羅のアマ系天武天皇系が続いており,その不比等が死去すると,皇族の巻き返しが始まるが,不比等の男子が策謀して長屋王の変を起こし,ついに不比等の娘を,民間初になる光明皇后にして,蘇我氏の血統から,藤原氏の血統への転換に成功するものの,今度は,天然痘の流行で不比等の男子4人が全て死去してしまい,再び天皇側(聖武天皇と橘諸兄)が巻き返しにでるが,光明皇后の存在によってつながれたばかりか,光明皇后が天皇を唆せて,東大寺・大仏や国分寺・同尼寺などの大事業で浪費させ,藤原仲麻呂の智恵で,正倉院に名を借りて,シラギ系が持つ武器その他財宝一切を取り上げてしまったという説まである。
聖武天皇の死で藤原一族も巻き返し,なお親新羅勢力が強いなか,光明皇后の存在を背景に,藤原仲麻呂が覇権を握るが,その専横ぶり以上に,皇族に限られる(オシ系の称号)恵美押勝を名乗ったため,光明皇后が死去すると,その娘で,母と対立していた孝謙上皇に討滅されてしまい,孝謙が重祚して称徳天皇になると,そこに,物部氏に近いとされる弓削氏(弓月国をルーツとする秦氏の可能性もある)から出た道鏡が登場して,称徳に接近して権力を振るうようになり,天皇制自体が危機に陥るに至る。
ここで,クダラ系藤原氏得意の策謀で,769年宇佐八幡宮の神託のバクチを打つことになる。宇佐八幡宮は応神天皇を祀る,つまりシラギ系のシンボルで,神託を受けに行った和気清麻呂の和気氏は吉備地方の出ながら,応神皇統の天皇の倭名に"ワケ"の含まれることが多いように,新羅時代からの天皇側近であったと考えられ,藤原百川らは,これを利用して,クダラ系(天智系)天皇の復活を策し,あまり意味の無い存在だった光仁天皇を介在させた後,ついに,のちに偉大な天皇とされる桓武天皇を登場させ(これが,平成の天皇が述べた百済との関わりの原点),以後,天皇を戴く藤原氏という構図(すなわちクダラ系藤原氏)が長く続いて行くことになる。
この間,すでに,蘇我氏に排除され,藤原氏の覇権で,復活する可能性の無くなった大伴氏の末裔家持による「万葉集」の編纂がなされるが,そののち,紀貫之の「古今集」,後鳥羽上皇の「新古今集」が誕生するように,和歌をして,敗者の生きる道を開いたのである。
ついでながら,この頃活躍する行基の祖の王仁氏は,徐福の故郷山東省出身の漢族学者の家系で,戦乱を避けて,朝鮮北部の漢が建国した楽浪に行き,その滅亡で,4世紀後半に百済経由で日本に渡来したといわれる。
第3話:クダラ系藤原氏の(陰謀によるライバル追放の)長期政権~平安時代
シラギ系が武力によって直截に覇権を握るのに対し,クダラ系は陰謀によって覇権を握るのが得意で,クダラ系藤原氏は,良く知られているように,天皇の利用と陰謀によるライバル氏族の排除によって,覇権を維持し続けるのである。
イ:宇佐八幡宮神託で実現した,桓武・嵯峨天皇による親政と,クダラ系藤原氏の伸長
桓武天皇が,現代までつながるクダラ系天皇の祖として特別な存在になっているだけでなく,その子の嵯峨天皇も,天皇権力をいかんなく発揮したが,その間,桓武天皇を生み出した事実を背景に,藤原氏は,入内によって天皇家の外戚になるという直接な方法とともに,得意の陰謀で,勢力を伸長していく。その端的なものが,皇族がライバルになることを未然に防止することで,有名な桓武平氏を端緒とする,(それまでは,橘諸兄ぐらいしかなかった)臣籍降下で,源氏も,その皮切りは嵯峨源氏であった。桓武天皇が,平城京のしがらみを排すべく,平安京を建設したのも,藤原氏が活躍しやすい舞台を提供したことになり,長く都になるのである。>桓武平氏
桓武天皇は,父光仁天皇の死去で,44歳になってようやく即位したが,すでに十分に実力が培われていて,早くも784年,平城京のしがらみから脱すべく,長岡京遷都を企図するが,翌年,この事業を推進していた藤原種継が暗殺され,しかも皇太弟早良親王が連座して廃され,淡路国へ流される途中死ぬという事件によって,中断しただけでなく,以後,早良親王の怨霊に悩まされることになる。その10年後,ようやく平安京という新首都を実現させると,国土統一のため,蝦夷征討にも本格的に取り組み始め,801年,渡来系の坂上田村麻呂を抜擢して征夷大将軍とし,その巧妙な戦略によって,奥地の胆沢地方まで平定するに至るが,両者に要した巨額の費用が財政の圧迫,民生の窮乏を招き,805年に,参議藤原緒嗣の意見を用いて両事業を停止,翌年,没した。このことからも,独裁的天皇とはいえ,その意見を聞かざるを得ないほど,藤原氏の存在は大きいのである。
桓武天皇の皇后はもちろん藤原氏の乙牟漏で,その第2皇子に誕生した嵯峨天皇は,806年,父桓武天皇の死去後,同母兄平城天皇を支え,3年後,病気になった平城天皇の譲位をうけて践詐したが,810年,平城上皇が寵妃藤原薬子らとともに,多数の官人をひきいて平城旧京に移り,"二所朝廷"の観を呈したため,坂上田村麻呂以下の兵を発して征圧,薬子は自害,その兄仲成を射殺した。いわゆる薬子の変で,その後,都での処刑は保元の乱まで,350年行われないことからも,平安時代は,ある意味で江戸時代と同様,平和な時代でもあった。
ようやく独裁的な力を握ると,朝廷行事の再構築を始め,多くの皇子を臣籍降下し,皇女を貴族に降嫁させたが,とくに寵愛する藤原冬嗣の子良房に,皇女を降嫁させたことが,藤原氏覇権の因になる。820年には,基本法たる律令を補足・修正するための法令集「弘仁式」「弘仁格」を,翌年には,朝廷の儀式を整備して「内裏式」をまとめた後,823年,37歳になると,側近がこぞって反対するのを押し切って,異母弟淳和天皇に譲位,自らは人臣の列に入ろうするも,太上天皇の尊号を贈られて君臨,以後,自動的に上皇になるのでなく,天皇によって与えられる地位となり,存する空間も天皇の内裏とは別にすることが定まった。10年後,淳和天皇が,嵯峨天皇の子の仁明天皇に譲位して後も,上皇のままで,842年,没した。直後に,藤原良房の陰謀による承和の変で,政局はたちまち不安定化,摂関政治の幕が開かれる。
ロ:藤原氏の覇権確立(摂関政治)で,藤原道長の栄華に至る
嵯峨上皇の覚え目出度かった父冬嗣以上の力量を発揮するようになっていた藤原良房は,842年,38歳の時に,嵯峨上皇が死去するや,皇位継承の問題から春宮坊で起きた不穏な動きを利用して,伴健岑・橘逸勢らを謀反の罪で捕え,淳和天皇の皇太子を廃し,妹順子の生んだ仁明天皇の子道康親王を皇太子にして,一気に覇権を握る。右大臣に昇り,娘明子を皇太子のもとに入内させ,太政官符や宣旨発給の上卿を独占するうち,850年,良房の専横におされて仁明天皇が死去,文徳天皇が即位すると娘明子は皇后となり,皇子惟仁親王を出産,外祖父となるや,先例を無視して,親王をわずか生後8ヵ月で立太子させる。
857年には,90年ぶりに生前太政大臣に任じられ,翌年,文徳天皇が急逝すると,惟仁親王を,初の幼帝清和天皇として即位させ,事実上の摂政をつとめることになる。世情不安が広がるなか,866年,応天門放火事件が勃発すると,真相究明が進まないうちに,人臣の初の摂政となり,結局,大伴氏末裔で,有能な伴善男に責任を負わせて配流に処し,源信,弟良相らライバルの芽も摘んで,872年,没した。
良房の養嗣子になった藤原基経は,当然のごとく,順調に出世し,872年,36歳の時,養父良房が死去するとともに,初の藤氏長者となり,4年後,清和天皇が自分の妹高子を母とする陽成天皇に譲位すると,摂政に就任,884年,乱行が絶えなかった陽成を退位させ,当時55歳の仁明天皇の皇子時康親王(光孝天皇)が即位。すでに太政大臣になっていたが,光孝の外戚ではなく,地位が不安定なことから,職務内容の明示を求め,実質上の関白となる。ところが,887年,光孝が崩ずる直前に,臣籍に下っていた第7子源朝臣定省が皇太子に立てられ,宇多天皇として即位すると,関白の任務に問題が生じ,職を解かれたのも同然と,政務を行なわず,宇多は結局,屈服させられた。もはや,天皇すら,その職を左右できないほどに,藤原北家を隆盛させて没した。
そして,陰謀の仕上げになったのが,基経の長男藤原時平が仕掛けた,あまりにも有名な菅原道真の左遷であるが,これは,自らも百済王の末裔と称していた三善清行が方略試を受けた際,問答博士だった道真によって不合格になり,一夜にして白髪になったことに始まり,清行は,その後,国司となって「意見十二箇条」を出すほど有能で,その怨念が,時平を動かすもとになったのである。道真の祖はまた,学者家系大江氏の祖でもある土師氏であるが,その名の通り,ルーツは土器(今で言えば陶磁器)製造に携わった氏族で,その先進地の出雲から呼ばれたということなので,遡ればマツ系だったかもしれない。
900年頃に統一新羅の分解が始まり,907年にはあの唐すら滅亡してしまい,918年,王建が,高句麗王を追放し,三国を統一した高麗国を建国するなど,外国からの圧力が無くなっていたことから,藤原氏が,陰謀に明け暮れることができた。909年に,時平が早世すると,兄と違って温厚聡明な弟の忠平が,朝廷の首班となり,930年に,朱雀天皇が即位すると,醍醐天皇の親政で,長期にわたって置かれてこなかった摂政になる。その間,地方の支配は行き届かなくなっており,935年に,ついに新羅が滅亡して,新羅軍兵士が大量に渡来してくると,問題が一気に噴出,日本南関東全体に勢力を広げていた平氏間で覇権を獲得した平将門が,新皇を名乗って,中央に対して反乱を起こし,それに呼応するように,瀬戸内海で,藤原広嗣も反乱を起こすなど,天皇制の危機といえる事態になり(いわゆる承平天慶の乱),辞意を上奏したが認められず,941年,全てが平定されると,何事もなかったかのように,関白になるほど信頼されて,藤原摂関家隆盛の祖になったのである。しかし,次論で述べるように,平将門の乱は,源平はじめ武家勃興の契機となり,結果として,クダラ系藤原氏の政治に引導をわたすことになるのである。
その後は,969年の,いわゆる安和の変で,源高明を排除して後は,ライバルとなるような他の氏族はいなくなるが,陰謀の血筋は,藤原摂関家内での抗争に至り,転変の後,覇権を獲得した藤原道長による最盛期となって,王朝文化が花開くのである。道長の栄華ぶり等は,あまりに知られているので,省略するが,清少納言,紫式部をはじめとする,世界でも類をみない,女流文学の隆盛は,承平天慶の乱の前に,早くに排除されていた豪族紀氏の末裔の紀貫之が,のちに,古今伝授という伝統ができるほどの「古今集」を編纂したこと,それ以上に,'男もすなる日記といふものを女もしてみむとてするなり'の冒頭で知られる「土佐日記」を著したことが契機になっていることを指摘しておきたい。
なお,表向き藤原氏の出自が中臣氏とされていたこともあって,応神天皇以後の皇室の祭祀を司って来た忌部氏の力が削がれ,忌部氏が復活を訴え出るようなことも起こっている。マユツバとも思われるが,'くだらない'の語源は'百済でない','しらじらしい'の語源は'新羅らしい'というように,日本のなかでは,クダラ系の人たちが,シラギ系の人たちを蔑む傾向になったのも,クダラ系政権が長く続いたことによるのだろう。
ハ:院政による天皇家の巻き返しと桓武平氏・清和源氏の伸長
藤原氏の時代,内部抗争のある間は,優秀な人材が育ち,政権は維持されたが,藤原北家が覇権を握り,世襲化が進むに従って人材不足に陥り(まるで自民党の歴史を見ているよう),道長の死の直後に,再び関東で平忠常が乱を起こし,道長の子頼通には入内させるべき女子が誕生せず,東北地方で前九年合戦が起こるとともに,末法思想が登場したこともあって,衰退が始まる。1068年には,藤原氏系の出生でない後三条天皇が登場,頼通も摂政を辞めざるを得なくなって,衰退が加速する。後三年合戦の最中の1086年に,白河上皇が院政を始め,1107年,自らの子鳥羽天皇を即位させて院政を確立,クダラ系藤原氏政権は終焉を迎える。
院政時代を始めた白河法皇の特異な性格,その最期を飾る,後白河法皇の今様の評価や,絵巻物の創作など,ユニークな文化には,天皇であればできなかった活動が反映されているように見える。また,院政時代の上皇は,盛んに熊野詣でをしたことで知られ,その理由は主として末法思想によるものとされるが,神武天皇が熊野に上陸して大和入りしたことへの回帰,つまり,天皇自身の拠り所を確認して権威を高めようとしたものとも考えられる。
院政時代,藤原摂関家が重用した源氏に対抗して,院を警固すべく重用したのが平氏で,これが,結局,平氏の覇権を招き,源平の戦を経て,朝廷が支配する体制そのものまで,終わらせることになる。また,後三年合戦の終わった1087年,いわゆる奥州藤原氏政権が確立,以後,まさに都での非クダラ系政権の院政に対峙するかのように,東北地方でクダラ系政権の時代に入り,都をも凌駕するような文化を花開かせることになるのである。つまり,院政時代は,平将門の乱で登場する,武家三流の伸長と重なっているので,以下,次論に委ねることとする。
この章TOPへ
ページTOPへ
第6論:平将門の乱契機に登場した,坂東武家三流の盛衰~平安時代後半
あらかじめ,平将門の乱直前の坂東の支配状況を,地図にして,みておくことにする。
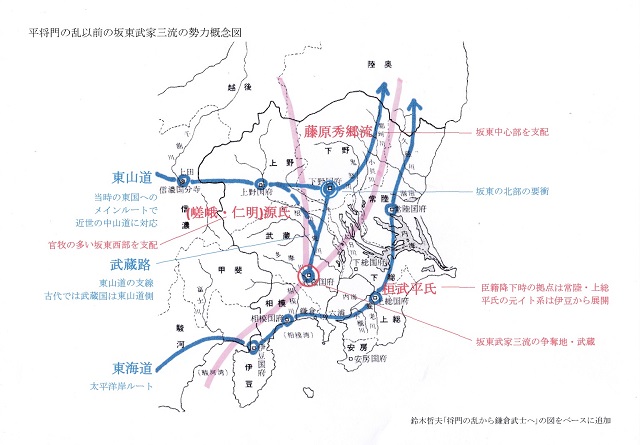
前論同様,第二講「時代循環のパターン」も参照してもらいたい。>時代循環のパターン
第1話:平清盛を生み出し,武家政権への端緒となる桓武平氏(イト系)
早くに拡がったナカ系と,邪馬台国との抗争で東進を余儀なくされたイト系にそれが率いるアマ系という,海洋民族特有の派手さ・乱暴さが,新たな時代を開く一方で,命取りになる。
イ:桓武平氏の成立から,将門の乱まで
臣籍降下(皇族に姓を与えて民間人としてしまうこと)は,敏達天皇の末裔葛城王が橘諸兄になったのが始まりとされる。藤原不比等が覇権を握ったことから,妻の県犬養三千代が女帝元明天皇から橘姓を賜り,その三千代が不比等の前に結婚していた美奴王との間の子が葛城王で,生母の姓になったと思われる。
皇位継承を確実なものにするため,天皇には皇子が多く誕生するように図られるが,皇子の子王子以降の皇族はどんどん増えてしまうことになり,その結果,皇位継承が争いの原因にもなってくるため,まず,その数を減らすべく考案されたのが臣籍降下ということになる。不比等の死,その4人の男子が天然痘の流行で死去したために,藤原氏の覇権は失われていたが,宇佐八幡宮の神託によって,権力を回復し始めると,皇位継承問題以上に,藤原氏自身が自らの権力を行使しやすくするために,皇族の数を減らすべく,臣籍降下を天皇に働きかけることによって,平氏は桓武天皇から光孝天皇までの4流24氏,源氏は嵯峨天皇から正親町天皇までの21流(男子に限っても)何百氏にもなるが,臣籍降下した皇族は自らの力で生きるのはやはり困難で,ほとんどは3代もたたないうちに消えてしまう。
坂東諸国においては,826年に,上総・常陸・上野の三国が,親王任国とされ,葛原親王が,これら三国の太守を歴任している。中央での地位向上の可能性を失った王臣貴族は,フロンティア東国に活路を見出すべく,現地留任を望んだが,そのためには,現地豪族と婚姻関係を結ぶことが必須条件であった。葛原親王の孫の高望王が,889年に,臣籍降下して平氏姓を賜り,高望王とその子孫が,(すでに述べたように)東進し,伊勢を経て,伊豆を拠点に,太平洋沿岸部を常陸国方面まで展開していた上古の伊都国の末裔(イト系)たちと婚姻,彼らが,高望王を祖とする家系図をつくっていったことによって,桓武平氏が形成されていったと考えられる。>「平将門の乱以前の坂東武家三流の勢力概念図」
蛇足ながら,長崎県五島出身の平田敬一郎(開銀と地域公団総裁)や,まさにナカ系の那珂氏を祖とする常陸江戸氏の末裔の江戸英雄(三井のリーダー)は,かつての平氏を彷彿とさせるような堂々とした体躯と容貌をしていたことで有名であった。
在地豪族だけでなく,後述する源氏や秀郷流との間にも様々な婚姻関係が結ばれ,源氏化する平氏もでてくるなど,源平という単純な区別はできなくなっていくが,海洋民族型の平氏と,騎馬民族型の源氏という血は争えず,場面に応じて,出現することになろう。
高望王が臣籍降下した同じ889年に,鎮守府将軍良持の子に生まれ,その遺領を継いだ平将門は,伯父の良兼一族と対立,良兼の舅で前常陸大掾の源護と戦って,その子扶らを討ち,それを助けた伯父平国香を殺し,叔父良正の軍を打ち破って以降,一族の間で,大規模な私闘を繰り返し,勝ち抜くことで,武士としての盛名を挙げ,朝廷の政策に対応して,国司と地方豪族との紛争の調停に乗り出すが,失敗して,939年,常陸国衙を攻略,印縊を奪って国司を捕らえ,ついに,国家に叛乱,短時日のうちに坂東を占領して,新皇を名乗り,一族配下を国司に任命して,独立を宣言するに至ったが,朝廷の将門追討軍参加要請に応えた藤原秀郷の前にあっけなく討ち死にしてしまった。海洋民族特有の派手さ・乱暴さで,新たな時代を開こうとしたとたん,命取りになったといえよう。
とはいえ,将門の乱の結果,秀郷が一気に東国武士の祖として登場,末裔からは奥州藤原氏が誕生し,秀郷の軍に加わった平貞盛は,西上して中央軍事貴族化,末裔の清盛が平家政権に至り,ひょんなことから,将門の乱を予告したことになって評価された清和源氏の経基の末裔の頼朝が,ついに,武家政権を誕生させるに至るなど,平将門の乱は,日本史上,実に大きなできごとであったといえよう。
ロ:西上して伊勢平氏となり,院と結びついて覇権を握るまで
940年,藤原秀郷に従って,将門の乱を制した桓武平氏国香流の貞盛は,恩賞として従五位下に叙せられ,京の右馬助に任じられると,翌年,瀬戸内海で反乱を起こした藤原純友対策に,配下兵士が閲兵を受けるなど,早速,中央軍事貴族として活動を開始,947年には,藤原秀郷の後を継いで,鎮守府将軍にもなっている。
貞盛の四男維衡は,イト系が東進した際に一拠点になった伊勢に本拠を移し,同じように伊勢に移っていた叔父良兼流の致頼と抗争するも勝利して,伊勢平氏となり,その曽孫正盛は,瀬戸内を支配するようになって,密貿易を通じて財力を貯え始め,院政を開いていた白河上皇に伊賀の所領を寄進するなどして,清和源氏頼義の子,義家が後三年の役後冷遇されるのと対照的に,1095年に設置された(院警固の)北面の武士となり,義家の嫡男義親を追討して武名を上げるなどして,院政時代における桓武平氏興隆の基礎を築いた。
東端に厳島神社,西端に壇之浦がある周防国は,いわば平氏の原郷ともいえる場所で,その中ほど,現在の山口市近くに,平安時代において銅銭を製造した唯一の場所の名残である鋳銭司(すぜんじ)村があるが,そこが藤原純友に襲撃された後に登場する平氏は,この地の銅を活用し,大陸との交易を通じて財をなし,やがて覇権を握ることになる。のちの,大内氏時代初期に,京都代官に任にあったのが,平井俊治・道助だったということなので,姓からみて平氏出身といえよう。
その子忠盛は,さらに重用されて,藤原宗子(池禅尼)を正室とし,山陽・南海両道の海賊を追捕使に抜擢され,直後に白河上皇が死去するも,鳥羽上皇に引き継がれ,1132年,ついに,武家初の内昇殿が認められるに至った。その直後には,大宰府を無視して日宋貿易に関与,大宰府が強制監査に入ろうとするも,鳥羽院の威を借りて拒否し,巨利の一部を鳥羽院に還元することで,さらに関係を強化,続けて,山陽,南海の海賊追討となって,多数の海賊を降伏させた上,自らの家人に組織化して,日宋貿易を飛躍的に強化するという知恵者ぶりを発揮,藤原家成が院近臣筆頭の地位を確立すると,妻の宗子が家成の従兄弟であったことから,親密な関係を築いていく。受領の最高峰となる播磨守に転じ,右京大夫も兼任,公卿への昇進も間近となったが,果たせずに,没した。
そして,忠盛の子清盛となり,1156年,鳥羽上皇の死去とともに勃発した保元の乱と,その3年後の平治の乱を制して覇権を握り,栄華の極に達したわけであるが,良く知られているので,1164年に,イト系のシンボル厳島神社に,有名な平家納経をしたことのみにとどめて後は省略,後白河院との間に確執が生じたところから述べる。
1172年,高倉天皇への,清盛が娘徳子の入内で専横ぶりが高まり,1177年,耐えきれなくなった後白河法皇の近臣による"鹿ケ谷の陰謀(平氏打倒の謀議)"が,密告により発覚,死罪,配流になり,翌年に,徳子が高倉天皇の皇子を出産すると,すぐに皇太子にしたことで,対立は激化,翌年,清盛が"治承のクーデター"を起こし,軍勢を率いて京都を制圧して,後白河院政を停止,1180年,ついに,日宋貿易・海賊支配の拠点であった大輪田泊(現在の神戸)福原に遷都を強行する。
高倉天皇が京都に留まるうち,後白河法皇の皇子で,自らも清盛に所領を没収された以仁王が,清和源氏の長老で,突出して従三位に叙せられていた源頼政の勧めで,平氏追討の令旨を全国に雌伏する源氏に発し,自らも挙兵するも追討軍に追われて戦死したが,源氏の一斉蜂起となり,京都に還都した清盛は,開戦間もなく熱病に倒れ,5年に渡る源平合戦の末,平家滅亡に至った。源頼朝は,1159年の平治の乱で清盛に敗れた義朝の嫡男で,死罪になるところを,清盛の母池禅尼の助命嘆願で伊豆への流罪になったのであるから運命は皮肉なものである。
源平合戦は,典型的な騎馬民族と海洋民族の戦いでもあったが,戦い当初,平清盛の命を受けた平重衡ら平氏軍が,東大寺・興福寺など奈良の仏教寺院を焼失させた"南都焼討ち"は,まさに海洋民族の乱暴さが現れたものといえよう。
平清盛の登退場は,弱体化した王侯貴族が軍人の力を利用してその地位を引き上げた結果,ついには軍事クーデターを招き,政権をとった軍人が独裁政治を行って自滅するという,近年においても発展途上国でよく見られるパターンが,我が国では800年あまり前に起こっていたといえる。華美を求め恐怖政治を行う(派手で乱暴)というやり方は,ラテン系など海洋民族出身者に共通し,古い体制を変えるべく破壊するには,こういった存在が必要なようであるが,それがまた,命取りになったといえる。>のちに,下克上の口火を切った北条早雲も,決着をつけた織田信長も平氏である。
ハ:将門の乱後の坂東平氏,源平合戦で滅亡後の落人,倭寇・水軍への展開
平将門の乱後,東国に残された桓武平氏諸流からは,北条,千葉,畠山,三浦,梶原などの氏が発生し,貞盛流,良兼流が伊勢に去った後に入ってきた清和源氏に従属,しだいに騎馬民族化して行き,源頼朝に従って,伊勢平氏と戦うことになったことから,源平合戦は,平平合戦でもあった。このうち,北条氏は格が高かったらしく,坂東平氏のルーツたるイト系の拠点伊豆国に住して,平治の乱後,池禅尼に命を救われた幼い源頼朝が,北条時政のもとに預けられ,その娘政子と結婚,頼朝が初の武家政権鎌倉幕府を開いた後,死去するや,主にライバルとなる平氏諸氏を排除して,執権北条氏として,覇権を握ることになるのである。
源平合戦の結果,平家は滅亡,陸に残った者は,のちに有名になる多くの平家の落人部落を生み出すが,白川郷はじめ合掌造りは,農家としては大建築であるが,船をつくる平家にとって,建築構造はずっと簡単であったこと,船を漕ぐことはもちろん,漁業集落を見てもすぐ分かるように,海洋民族は,密集するのが自然であり,それが,大家族として合掌造りに対応しているともいえよう。栃木県の法師温泉も,平家の落人で有名であるが,多様な山菜はもちろん,山椒魚まで食するのは,海藻や様々な海産物のことを思えば,きわめて当然といえよう。
ほとんど知られていないが,源氏の落人の村というものがあり,長野県の川上村はその典型で,農業が不得意なことから,落葉松林のなかの貧しい村で,漬物が無かったことからも騎馬民族らしいところであったが,近年,レタスの大産地として有名になっている。騎馬民族の農業は,アメリカの農業を見れば分かるように,広い面積を同じ作物で埋め尽くし,収穫したものをコンボイで出荷するといったものになるが,川上村のレタス栽培はまさにそれに対応する。山梨のブドウも,騎馬民族による同一作物の大面積栽培と考えられる(あまり言いたくないが,かつての勝沼など,観光客から収奪するという感じでもあった)。
いずれにしても,源平の合戦は,騎馬民族と海洋民族が激突した点で,典型的な民族戦争だったともいえる。ここで,改めて,自分の民族の遺伝子を確認してみるのも,一興だろう。⇒コラム「遺伝適性を知るための民族ルーツ論」
大和朝廷の成立過程で,アマ系を中心に,海洋民族のうち,陸上で定着し得なかった者たちが,海賊化していったことは想像に難くないが,平将門の乱が武家勃興の原因になったように,同時期(939年)に起きた藤原純友の乱は,伊予で瀬戸内海の海賊の鎮圧にあたっていたのが,逆に,海賊の頭目になり,陸上にも進出,大宰府まで襲撃し,朝廷に反乱,以後,海賊たちが陸の抗争に巻き込まれていくということで,海賊の歴史を変えた。純友は藤原北家支流の藤原良範の子といいながら,生年が定かでなく,伊予の豪族越智氏一族の子が,良範が伊予国司であった時代に養子になったという説があり,純友の乱の時には,越智氏は朝廷側についたというから,純友に利権を奪われたことも考えられる。
藤原純友が討たれて,支配者を失った海賊らは行き場を失うが,海賊は平将門が討伐されたことで,貞盛流が西上し,平正盛の代には,(前述したように)イト系の本領を発揮して,これら海賊を配下に納めて,日宋貿易を主導して巨利を得,白河上皇に接近,子の忠盛は武家初の院昇殿を認められ,その子清盛の栄華に至るも,源平の合戦で平家は滅亡,支配者となった源氏は騎馬民族で,海への眼が少なく,戦功を挙げた者への恩賞は土地であったため,海賊らにとって,何のメリットも無く,さらに,元寇というとてつもない外圧を受けたため,海岸線は防衛の場となり,行き場を失った海賊らは,かつての日宋貿易の伝手を頼ってか,大陸との間に,倭寇として展開するようになる。>前期倭寇
平家の末裔を示すものが多いとされる頭に「平」の字のつく苗字を,マツ系,ナカ系などと同様に,「日本の苗字ベスト10000」で拾って,その分布を見てみると,87位の平野を筆頭に,平田,平井,平山,平川,平松,平岡,平林,平そのもの,平尾,平沢,平塚,平賀が1000位以内にあるように多く,これらを合計しただけでも,全苗字で10番目に多い加藤を上回る人口を占める。それぞれの,苗字には,地域的な偏りがみられるが,全体として,①千葉はじめ南関東や瀬戸内海周辺など,もともと平氏の根拠地であった地域,②栃木はじめ山間地の多い,平氏の落人として知られる地域,③西南九州(島嶼部を含む。沖縄に特化して多い平良姓も平氏に関係があるかもしれない)という,後述する倭寇にかかわる地域に多いことから,確かに,平氏の末裔たちである可能性が高いようだ。
第2話:源頼朝を生み出し,武家政権を確立した清和源氏(シラギ系)
イ:将門の乱を契機に,坂東の覇権を確立した清和源氏
新羅から応神天皇戴く秦氏が渡来した時,多くのシラギ系の人たちも渡来し,ともに,九州から東進して,秦氏の本拠地太秦の北に,シラギ系地名を示す嵯峨野があり,秦氏が集中するという近江の国には,シラギ系も集中し,近江八幡つまり応神天皇を示すところには,シラギ系の人たちと思われる全国の佐々木氏すべての家系が収められ,仁徳天皇の和風諡号にもふくまれるササギの名にもつながる沙沙貴神社があるなど,つねにセットになっている。
東進の最後の地,坂東の北部には,上野国のものを表す大豪族上毛野氏がいたことが知られているが,対朝鮮・対蝦夷関係での軍事・外交伝承として,神功皇后49年,荒田別と鹿我別は将軍に任命され,新羅に派遣された。そして新羅の軍を破り7国を平定してのち,百済の近肖古王と貴須王子と会見した。応神天皇15年,荒田別・巫別(鹿我別と同一人物とされる)が百済に派遣され,王仁を連れ帰った。仁徳天皇53年,竹葉瀬が,貢調しない新羅の問責のため派遣された。途中で白鹿を獲たため,一旦還って仁徳天皇に献上し,再度赴いた。のち,弟の田道(たぢ)も新羅を討ったとあるように,応神天皇が新羅から渡来したことを隠すような神話に対応している。神功皇后が新羅の神の末裔であることと同様,応神天皇とともに渡来した新羅人とみても良いだろう。
おそらく,応神天皇渡来時に同行してきた新羅人であった可能性があり,新田,足利氏など,のちに源氏の主流とされる氏族も,その名から見て,シラギ系で,上毛野氏の末裔とみて良いかもしれない。埼玉県新座郡は,もとは新羅郡といわれ,758年に,政権によって移住させられた新羅人の地域であるが,このほか,高麗人の地とされるものも,民族としてはシラギ系であると考えられることから,稲作には適さない坂東の北西部は,主として騎馬民族のシラギ系の人たちが住んでいたとみて良いと思われる。のちに,養蚕が盛んになり,近年に至るまで,現在の八高線のルートが"日本のシルクロード"と言われるようになったのも,(すでに述べた)養蚕民族の神白山神社にもつながるシラギ系の人たちの地帯であることを示している。
以下,奥富敬之 「天皇家と源氏 臣籍降下の皇族たち」をベースに,清和源氏の展開をみていくこととする。桓武平氏の桓武天皇に続く嵯峨天皇も,王子を臣籍降下させて嵯峨源氏が生まれ,以後,正親町天皇まで18流の源氏が誕生する。その大部分は文人で,村上源氏を筆頭に,公家として勢力を築いて行くが,安和の変で源高明が失脚したように,藤原氏の陰謀の前に衰退を余儀なくされる。9世紀後半,俘囚の叛乱や群盗の蜂起が相次ぐ坂東で,とくに西部に多かった官牧を守るべく配置された王臣貴族は,名が一字の嵯峨・仁明源氏であった。官牧を実際に運営していたのは,前述の騎馬民族のシラギ系であったと考えられる。>「平将門の乱以前の坂東武家三流の勢力概念図」
嵯峨源氏の源融流には,摂津国の渡辺氏とその分流松浦氏(いずれも海洋民族側なのでかなり異質),宇多源氏の一部には,新羅系の拠点である近江国の佐々木氏が取り込まれて武家となり,六角氏・京極氏などが派生する。魏志倭人伝の末盧国からつながるとみられる肥前松浦氏は嵯峨源氏の祖渡辺綱の支流を名乗るが,源氏といいながら渡辺姓が示すように海洋民族で,結局水軍松浦党を率いて平氏に属すことになった。
平将門の乱当時,武蔵介であった源経基は,軍事貴族としてのダメぶりが知られていて,単なる噂の段階で,京に逃亡して訴えたところが,のちに現実になったことから一気に評価され,翌年の藤原純友の乱に押領使として起用され,純友の部将を生け捕りにして,面目をほどこした。その後,経基流の清和源氏は,貞盛流の桓武平氏,秀郷流藤原氏とともに,中央軍事貴族の一角を担うことになるが,その契機になったのが,経基の子満仲が,969年に密告によって,安和の変を起こし,源高明を失脚させ,以後,経基流の清和源氏が摂関家に奉仕することになったことによる。
清和源氏の武蔵国進出は,それ以前に当地に権益を有していた名が一字の嵯峨・仁明源氏と婚姻関係を結んで権益を継承していったことにより,満仲も,武蔵守源俊の娘と結婚して頼光をもうけるなど,武蔵国に根付くようになり,摂関家の傭兵になったことで,自らも坂東ほか諸国の国司を歴任し,鎮守府将軍にまでなる。その間,平将門の乱を平定後,武蔵国司,武蔵守となっていた藤原秀郷の子千晴とライバル関係になっていたが,安和の変では,源高明に仕えていた千晴をまず失脚させるという,摂関家と,自らの障害を一挙に排除する政治的才覚を発揮したのである。
ちなみに,大江匡房が著した「続本朝往生伝」の武士の項では,ベスト5の筆頭に挙げられ,次が弟の満政,5番目には嫡男の頼光まで入っている。頼光が武名を轟かせることは,ついに無かったが,以後の清和源氏は,名に"頼"の文字を入れることが,清和源氏の嫡流であることを示すことになる。
坂東においては,将門の乱後,秀郷の子千晴が武蔵国の将門の勢力を奪取し,桓武平氏と藤原秀郷流の間,あるいはそれぞれの一族間での紛争が頻発,中央の強権者藤原道長が死去するや,1028年,平将門の叔父平良文の子孫で,道長の子の教通の家人であった平忠常の乱として爆発,朝廷は平直方を追討使するも鎮圧できずにいたが,3年後,頼光の異母弟で,兄と違って坂東武士の棟梁になろうとしていた頼信を起用して,ようやく平定,頼信の武名は一気にあがり,面目を失った平直方は,娘を頼信の嫡男頼義に嫁がせ,それまで桓武平氏の勢力圏だったところが,清和源氏の勢力圏に一変するに至る。直方から5代目の子孫が北条時政で,その娘政子が,頼義から5代目の義朝の子頼朝に嫁いだのだから,歴史は面白い。
次いでながら,頼信が石清水八幡宮に納めた告文が発見され,清和源氏は,実は陽成源氏だったことが判明,陽成は祖とするには問題の多い天皇であったことから,白河院政で冷遇された八幡太郎義家が,重用されている桓武平氏に対抗すべく清和源氏に書き換えたらしい。同時に,さらに遡った祖を"武の神"応神天皇とする八幡信仰であった由来も明らかにしているが,このことが,すでに坂東に展開していた騎馬民族のシラギ系を取り込んで,有力な武家として飛躍する契機になったとも考えられる。
避けては通れない話として触れておきたいのは,被差別民の話で,屠殺や皮革業に携わっていたため,殺生を禁じる仏教社会から排除されていった人たちであるが,彼らもまた,シラギ系騎馬民族が主体で,当然のように八幡神を祀っている。また,シラギ系の本国朝鮮では,なぜ日本のような軍事政権にならなかったのだろうかということについては,儒教にもとづく文民支配の思想の中国の影響がそれほど強かったからと思われる。
源頼義は,騎馬民族を代表するように際立った馬好きの一方,父頼信を裏切って不貞を働いた生母を許さず自分から義絶,さらに,藤原道長に忌まれて逼塞していた小一条院に仕えるなど,その正義感は異色で,武人としての血は高齢になっても衰えないという人物であったから,坂東武士のほとんどがその指揮に従うようになったという。63歳になって,陸奥守に就任すると,勇躍して現地に赴任,俘囚の安倍頼良を挑発し続け,1051年,前九年の役が始まるが,安倍頼良を討つものの,その子貞任,宗任の巻き返しで劣勢に陥り,1062年,出羽の俘囚清原武則の援を得てようやく,貞任を討ち,宗任を捕らえて乱を平定するが,陸奥国は清原氏に併呑されてしまう。命じられて,宗任らを伊予に住まわせ,皇民としたが,それが,安倍晋三のルーツである。
平定翌年,相模由井郷に石清水八幡宮を勧請して,鶴岡八幡宮の起源とし,嫡男義家が,石清水八幡宮で元服して"八幡太郎"と称し,三男義光が, 近江国の新羅明神で元服して"新羅三郎"と称したように,源頼義は,応神朝八幡宮の秦氏を支えたシラギ系を結集するシンボルになるに相応しい人物であったといえよう。のち,近江国の佐々木氏や京極氏はじめ,全国のシラギ系を核に武家源氏として統合されて行くことになる。
ロ:院政下の冷遇を,藤原摂関家との関係で凌ぐ
八幡太郎義家は,前九年の役で,父頼義に従い,窮地の父を助けて,安倍兄弟と激闘,終結した時は24歳で,陸奥国の果実を清原氏にさらわれたことに怨念を抱いていて,21年後の1083年,ようやく鎮守府将軍になって現地に赴任するや,清原氏の内紛につけこみ,私兵をもって,戦闘を開始したが,敵もさるもので,3年後に,ようやく鎮定するも(後三年の役),陸奥国は手に入らず,藤原清衡による,奥州藤原氏という地方政権を誕生させ,源頼朝によって滅ぼされるまで続くのである。
悪いことに,この間に,中央では,白河上皇による院政が開始され,対立する摂関家が重用していた清和源氏に冷たくあたるようになっていて,朝廷はこの争乱を私闘と断じて恩賞を行わず,かえって陸奥守を解任されたことから,私財を投じて部下に褒美を与え,人望が高まって東国武士との間の主従結合が強化され,"天下第一武勇之士"と評され,義家の名声を頼って諸国の在地有力者がその田畠を義家に寄進したため,ついに荘園の停止を命じられる。
さらに,院の嫌がらせは続き,次男義親が,源氏の御曹司というのに,辺境の対馬国司に任じられた上,理由も分からず謀叛人とされ,こともあろうに,その討伐の任を下されるが,その苦悩に耐えられなかったためか,まもなく死去して,親子相撃の悲劇は回避されるも,追討の後任には桓武平氏正盛が選ばれ,義親の首を持って帰る前に恩賞を与えることが決定しているほど,院政は平氏を重用した。三男の義国も叔父の新羅三郎義光と私闘していたため,結局,四男の義忠が後継者になる。ところが,またしても,白河院政の陰謀で,義忠は叔父義光に暗殺され,義忠の子で14歳の為義が後を継ぐが,検非違使に任じられたのは50歳で,同じ年齢の平忠盛は刑部卿で,院昇殿を許されているほどの屈辱であった。
1145年頃,為義が坂東の地盤を任せていた嫡男義朝が上洛,摂関家に従順だった父と異なり,鳥羽院に仕えたことから,すぐに昇進を重ね,1153年には,従五位上の下野守となって,父の位階を一段追い抜くことになって,親子対立,1156年に勃発した保元の乱で,崇徳上皇側になった為義に対し,義朝は,自らの献策で圧勝した後白河上皇側ということになった。義朝は,自首してきた父為義の助命を必死に願うも,強硬な後白河院側近信西により,自らの手で斬首するように迫られ,実行を配下に委ねて逃れるも,信西に対する怨みが胚胎,1159年,藤原信頼と組んで,信西の首を斬るに至るが,帰京した平清盛に討たれ(平治の乱),以後,平家の専横時代となる。
この時,清盛の母池禅尼に命が救われ,伊豆に配流されていた義朝の嫡男頼朝が,1180年に挙兵し,平家を滅亡に追い込んで,それまで耐え忍んできた清和源氏代々の労が報われるのである。以仁王に,頼朝ら清和源氏に決起を促す令旨を出すよう働きかけた源頼政は,武名を轟かせることのなかった頼光の5代末裔で,保元の乱と平治の乱で勝者の側に属し,平氏政権下で源氏の長老として中央政界に留まった上,平清盛から信頼され,1178年,74歳になって,武士としては破格の従三位に昇り公卿に列するが,その直後に,清和源氏の目を覚まさせる役割を果たしたことになる。
ハ:源頼朝が,桓武平氏,奥州藤原氏を討滅し,シラギ系武家政権確立
1180年に,以仁王の令旨を受けて,平氏打倒に決起した源頼朝は,早速,御家人制度を始め,侍所を設けて和田義盛を侍所別当に任じ,平広常を誅滅するなど,強い態度で,独立心の強い坂東武士を次々と配下に取り込み,1185年には,平家を滅亡に追い込むとともに,鎌倉には公文所,問注所を設けて,統治の機関を整備。1190年に,はじめて上洛して後白河法皇に対面,権大納言・右近衛大将に任ぜられるも固辞,1192年,法皇が死去して,ようやく征夷大将軍に補任され,武家政権の首長が征夷大将軍に任ぜられる慣例がひらかれる。
源平の合戦は,いうまでもなく騎馬民族の源氏と海洋民族の平氏が起こした内戦で,アメリカの南北戦争のように,大国の発展には避けて通れない,新たな時代を開くための内乱,まさに民族戦争と言っても良いようなもので,実際,その後の武家政権は,アメリカの南北の意識のように,源平交替という意識の上に動いて行くことになる。騎馬民族源氏による武家政権は,戦功のあった武士に所領を与えることで報い,確実に配下にする方式をとったことから,滅亡に至った平家ばかりでなく,陸の土地に関係のない海洋民族は,見捨てられ,自ら生きるべく,海賊化,倭寇化して行くことになるのは,すでに述べた通りである。
その間,弟義経が,弟であることを理由に,御家人になることを拒絶,それに乗じた後白河法皇が,義経を配下に入れて,頼朝追討の院宣を出すに至るが,他の御家人に応じるものはなく,義経は潜行の挙句,奥州藤原氏秀衡のもとに逃れて匿って貰ったのも束の間,秀衡が死去すると,子の泰衡は,頼朝の圧力に耐えきれず,義経の首を鎌倉に届けるも,時すでに遅く,1189年,奥州藤原氏は滅亡させられた。頼義,義家の前九年,後三年の役以来の宿題は,4,5代後の頼朝によって,ついに果たされたのである。
1184年には,参議藤原光能の子で,学問の名門大江家の養子になっていた大江広元を招き,公文所(政所)を開設して別当とする。以後,事務官僚のトップとして,数多くの政策に関与,幕府の基礎固めをするとともに,ことあるごとに上洛して,朝幕関係の安定化に努め,1199年の頼朝没後も,政子の信任を受けて将軍側近の立場を保持し,執権政治確立の基礎固めをして行く。頼朝が,いわゆる貴種(皇族がルーツ)であったことから,天皇の権威は存続,シラギ系武家政権ができたとはいえ,クダラ系藤原氏のやり方が浸透していくことにもなった。
なお,頼朝は,南九州薩摩を中心に秦氏出身の島津氏を大将に相模の有力武士らを配置,以後,島津氏は大大名として,長期にわたって独立性を保ち,琉球を配下に収めて後には,大陸との貿易で富を蓄え,同じく,大陸との貿易で富を蓄える長州とともに,明治維新を実現することになる。薩摩藩島津氏が,秦氏出身であることがイギリスとの連携を生み出し,後述するように,長州が,中臣鎌足とつながる特別な存在であった大内氏をルーツとすることが大きな意味を持つのである。
第3話:将門の乱を制して東国武士の祖となった藤原秀郷から,奥州藤原氏へ(秀郷流)
源平の歴史はかなり知られているが,秀郷流についてはあまり知られていないので,野口実「伝説の将軍 藤原秀郷」をベースに,少し詳しく述べる。
イ:藤原氏系武人(中央軍事貴族)の登場から,秀郷が将門の乱を制するまで
坂東に在留した王臣貴族は,在地の豪族との婚姻などにより,武力を高めることになったが,850年頃から,坂東の俘囚の叛乱や群盗の蜂起が相次ぎ,それを鎮圧するためにも,これら軍事貴族の配置が求められるようになった。藤原秀郷の登場は,曾祖父で魚名の子藤成が下野国に赴任した際,在地の土豪鳥取氏の娘と結婚し,その子豊沢が,中央での栄達を求めず,下野の在庁官人になったことに始まる。下野の国府(現在の栃木市)は東山道の陸奥への拠点にあることから,俘囚・群盗を鎮圧する役割を課されるようになったが,下総・常陸方面で,その子村雄も下野大掾を継ぐとともに,鳥取氏との婚姻で,不動の在地有力者になった。>「平将門の乱以前の坂東武家三流の勢力概念図」
藤原村雄の子に生まれた秀郷も,有力土豪鹿島氏の外孫になっていて,下野掾になっていたところに,939年,平将門の乱が起きるが,889年に高望王が臣籍降下して始まった桓武平氏よりも,すでに在地性はかなり濃厚になっていた。一説によれば,この889年に,将門と同じく秀郷も誕生している。史料上の初見は,「日本紀略」916年の記事で,一族を主体に武力集団を率いた反国衙的行動によって配流の処罰が下されるも,国司に再度の命が下されていることから,簡単には手を出せないほどの力を有していたことが分かる。929年にも,その濫行に,近隣諸国からの兵士が動員されており,ことによれば,将門と立場が入れ替わるような存在になっていた。蛇足ながら,江戸時代に博徒が,近代に入ってヤクザが,反社会的悪党でありながら,国家等の手先として,他の悪党を制するという存在になるのと同じようにみえる。
将門の乱に,京の人々が怯えるなか,翌940年,朝廷が,藤原忠文を征東将軍とし,在地土豪の将門討伐への決起を促したのに応え,8人の追捕凶賊使(押領使)の一人として参加すると,征討軍が到着する以前に,平国香の子貞盛らを従え,老練な計略を用いて,将門の軍を一気呵成に破り,自身で将門の打ち首にし,自らの使者が,京にもたらして,獄門にかけられた。名声は一気に高まって,東国武士の祖として伝説化されるともに,子孫は"都の武者"(中央軍事貴族)として活躍することになる。"老練な計略を用いて"とあるように,深謀遠慮型の秀郷は,およそ武人的でなく,クダラ系藤原氏そのものの人物であった。
ちなみに,将門の乱に呼応するように,(あわせて承平天慶の乱と呼ばれる)瀬戸内海で乱を起こした藤原純友は,藤原北家の右大弁藤原遠経の孫であるが,海賊を取り締まる伊予掾となって赴任すると,その後も現地に留まって,逆に海賊を率いるようになり,ついに,国家に叛乱するようになったという点で,地理的には遠く離れているとはいえ,同時代的現象であったといえよう。そして,純友の乱平定後,行き場を失った海賊たちが倭寇化していくのである。
ロ:秀郷流藤原氏の成立と,"俵藤太"伝説の形成
将門の乱鎮定における抜群の功績で,従四位下と,地方豪族として破格の位階に叙せられて,下野守,武蔵守となり,将門と同類であったにもかかわらず,存在を国家から認められ,坂東北部に軍事的覇権を確立する。平貞盛のように,自身が京に上って,中央軍事貴族になる選択はしなかったが,関白藤原忠平の日記の947年の記事に,秀郷が権中納言源高明を通じて,平将門の遺された兄弟が謀叛を起こそうとしていると奏上していることから,源高明を中央権門として存立基盤を固めていたことが分かる。958年に死去したと伝えられている。
弓射騎兵の武芸故実の祖として"秀郷将軍"と呼ばれ,鎮守府将軍に任じられたことも確実で,清和源氏の征夷大将軍に拮抗する,というより,"将軍"といえば鎮守府将軍のことをいうように,名誉の表徴として,時々間をあけながらも,百年近く,子孫に世襲された。鎮守府とは,古代蝦夷経営のために,陸奥国に置かれた軍政府で,当初は国司と兼任であったが,やがて,独立性を強めて行き,秀郷が任じられた頃には,奥六郡の地域の徴税権を持ち,蝦夷との交易にも独自の権限を持つに至るとともに,鎮守府の活動の兵站基地が坂東諸国であったことから,俘囚・群盗の鎮圧に活躍した軍事貴族が続々と任じられるようになっていた。
967年の村上天皇崩御の際,秀郷の子千晴と源満仲が,固伊勢関使に任じられることになり,ともに辞退するも,満仲のみ受理されていることから,2年後に,満仲の密告で勃発した安和の変で,源高明よりも前に,千晴が検挙され,隠岐に流されたことに関係するとみられている。とはいえ,秀郷流藤原氏の族長権は弟の千常に移って,中央軍事貴族としての地位は失われることなく,やがて武蔵介になった千常を中心に,秀郷流藤原氏が勢力を拡張していく。史料で,鎮守府将軍への補任が明らかになるのは,千常の子文脩からで,その記事から,秀郷流藤原氏が摂関家を本主と仰いでいたことも知られる。
1045年に,寛徳の荘園整理令が発せられると,北坂東での利権を保持すべく,秀郷流藤原氏のうち,本流というべき文脩の子兼光の系統は,中央軍事貴族の地位を捨てて,在地領主となる道を選択したが,その弟文行の系統は,その子が佐渡守に任じられたことから,佐藤氏と呼ばれ,摂関家の家人として,"都の武者"の立場を維持し続ける。曽孫季清の代に,院を警固する,いわゆる"北面の武士"になり,その孫が,かの有名な西行(佐藤義清)で,歌人としてつとに知られているが,実は,秀郷流故実を伝える弓馬の芸の達人でもあった。
「吾妻鏡」に書かれている,源頼朝と西行の邂逅は偶然のようにとれるが,西行が奥州藤原秀衡のもとに東大寺再建の資金の勧進に向かう途中で,頼朝にも資金を約束させるため,秀郷流武芸の第一人者で,東国の武士にとって垂涎の的である自らを売り込むべく図ったものとみられ,頼朝にとっても,奥州藤原氏の動向が気になるところであったから実現したらしい。実際,頼朝は自ら樹立した武家政権の正統性を確立すべく,武芸の作法の統合を図るにあたって,秀郷流を重視していたことも知られている。
のちにつくられる"俵藤太"伝説も,その多くが京都で成立していることから,中央軍事貴族としての存在が大きかったことも伺える。鎌倉幕府の成立後,頼朝が,それまで秀郷流嫡流とみなされていた足利氏に替わって,小山氏を嫡流とみなしたことなどによって,坂東に割拠する在地武士団の勢力図は大きく塗り替わることになり,のちに,足利氏が鎌倉幕府を倒す伏線になった。
ハ:奥州藤原氏の栄華も,源頼朝により滅亡
平泉の奥州藤原氏は,1047年の「藤氏長者宣」に,陸奥国在住と記された藤原経清の子孫であるが,同文書に,その父とある正頼は,実に,前述の秀郷流藤原氏のうち,本流というべき文脩の子鎮守府将軍兼光の子であることから,秀郷を祖とすることに矛盾はない。11世紀半ば,陸奥国で,安倍氏が国司と争い,これに清和源氏の源頼義が介入して前九年の役なり,足掛け12年の戦いののち,(のちの出羽国の)清原氏の加勢を得た頼義が勝利,敗死して滅亡した安倍貞任の姉か妹が嫁いだ藤原経清も斬首されたが,清原氏に再嫁,経清との間の子が長じて清原清衡を名乗ることになる。
清衡は,一族の内紛によって,後三年の役となり,白河上皇による院政が始まった年とされる1086年の翌年に,源頼義の子義家の援軍を得てようやく勝利,陸奥全体を実質的に支配するようになり,1092年,平泉の地に,自立した政権を樹立して,奥州藤原氏が成立した。1124年には,有名な中尊寺金色堂を建立し,1128年に死去,その翌年には白河上皇も死去している。
後を継いだ基衡までは,実質的支配力はあるものの,形式上は在庁官人でしかなかったが,院の近臣で陸奥守として下向してきた藤原基成の娘を子の秀衡の嫁に迎え入れ,院に影響を及ぼしたことから,鳥羽上皇が死去して勃発した保元の乱の翌年1157年に父の死で後を継いだ秀衡が,1170年に,鎮守府将軍に任じられたことで,陸奥の権益が決定的なものになった。このことは,中央を実質的に支配していた平家が,陸奥における秀衡の実力を認めて軍事警察権を委任したものであると同時に,平家の経済基盤たる日宋貿易が陸奥の砂金によって支えられていたことによる。
秀衡は,源氏が一斉蜂起した翌年の1181年には,源氏を背後から牽制したい平氏政権によって陸奥守に任じられ,武門としての地位も飛躍するが,1185年に平氏が滅亡,逸脱した行為をとったため,兄源頼朝から追捕されることになった義経を匿い,頼朝からの引き渡し要求を拒み続けるうちに死去,1189年,子の泰衡は,義経を自殺に追い込んで,頼朝との和平を模索するもかなわず,滅亡させられるに至った。清衡が白河上皇と,基衡が鳥羽上皇と,秀衡が後白河上皇とそれぞれ同時期に権力を握っているさまは,まさに,院政と奥州藤原氏政権が並行した現象であったことを示しているといえよう。
念のためつけ加えておくと,埴原和郎によれば,奥州藤原氏三代の遺体計測結果は,京都人の体形を示しており,藤原秀郷の末裔とみて間違いないという。
のち,南北朝動乱期の1335年に,高位の北畠顕家が鎮守府将軍に任じられたことを端緒に,秀郷流小山氏が台頭,足利氏による源氏の正統性が流布したため消えるとはいえ,秀郷流の血統が脚光を浴びるとともに,"俵藤太"伝説の完成をみる。秀郷の居宅のあった地が田原だったことから,伝説化される際に,俵藤太の名がつけられたという。
さて,桓武平氏や清和源氏と同じように,それまで土着していた様々な民族の武士が,秀郷流藤原氏と婚姻関係を結ぶことによって,その出であることを語るようになる。小山氏のほか,シラギ系と思われる足利氏,イト系と思われる下河辺氏など実に様々であるが,藤原秀郷直系の西行すなわち佐藤氏はじめ,伊藤,進藤,武藤,加藤,後藤など,始祖とする人物の,あるいは世襲した"官職の一字"と氏名の"藤"をつなげた苗字は,藤原氏出身の武士にのみ見られる現象で,11世紀後半から始まり,宮城県にやたらに佐藤姓が多いのは,奥州藤原氏の政権を支えた信夫郡司流の佐藤氏で,その佐藤氏から,(山内)首藤氏が生まれている。最近,注目されるようになった渋沢栄一は,埼玉県深谷の名家の出であるが,そのルーツは,秀郷流であった。
ついでながら,摂関家を戴く藤原本家の方は,五摂家の近衛・鷹司・九条・二条・一条を筆頭に,歌の冷泉,あるいは富小路まで,主として,邸宅のあったところの名で呼ばれ,明治維新後,そのまま姓になっていて,藤の文字は含まれない。
この章TOPへ
ページTOPへ
第7論:天皇の権威を背景とする武家政権時代~中世
前論同様,第二講「時代循環のパターン」も参照してもらいたい。>時代循環のパターン
第1話:天皇戴くクダラ系藤原氏に倣い,将軍を戴いて覇権を握ったイト系北条氏~鎌倉時代
イ:陰謀によるライバル排除と,疑似天皇制のような将軍戴く執権制
1199年,圧倒的権威と武力で,北条,千葉,畠山,三浦,梶原氏など,桓武平氏出身も多い坂東武士たちを御家人として統率してきた将軍源頼朝が(不慮の事故で?)死去すると,それぞれが覇権を握ろうと,平氏ゆえの乱暴さが爆発する。長男頼家は伊豆修善寺に幽閉されて死に,次いで嗣立された次男実朝も1219年に,頼家の遺児公暁に暗殺されて,貴種たる源氏将軍家は三代で断絶してしまう。この危機的状況に,頼朝の妻,北条政子は,頼朝が信任していた大江広元のアドバイスを得ながら,次々と的確に対応し,北条氏の覇権を確立し,さらには,朝廷の権威まで減じてしまう。
1199年,頼朝が死去,跡を頼家の外家である比企能員が権力を狙ったのに対し,頼家がみずから訴訟を裁くのを停め,有力御家人の合議によることにし(危機①,以下,北条政子が大江広元のアドバイスを受けながら,対処し解決したこと),1203年,頼家が重病になったことから,地頭職を実朝や頼家の長男一幡に分与する案にも,比企能員が不満を示すと,時政とともに比企氏を滅ぼし,一幡を殺し,頼家を出家させて伊豆の修禅寺に幽閉,実朝を将軍に擁立し,時政を執権とする(危機②)。この結果,桓武平氏の北条氏が実権を握るが,1205年,時政が後妻牧の方(政子の継母)と謀って実朝を廃し,女婿の平賀朝雅を将軍に立てようとしたのに対し,弟の義時とともに実朝を守り,父を伊豆に隠退させる(危機③)。
1213年には,和田合戦を乗り切って,北条氏の覇権を確立(危機④),1219年,実朝が頼家の遺子公暁に殺されると(危機⑤),後鳥羽上皇の皇子を鎌倉に迎えようとするも許されず,かわりに摂関家から,頼朝の遠縁のわずか2歳の藤原頼経を迎えて,自らが実質上の将軍(鎌倉殿)となり,俗に"尼将軍"と呼ばれるに至る。1221年,ついに,後鳥羽上皇が討幕の兵を挙げる最大の危機「承久の乱」になるが,御家人たちに幕府の恩を説いて奮起を促し,都に攻め上らせ,勝利を収めた(危機⑥)。そして,1224年,義時が没し,その子泰時が執権となると,泰時の継母伊賀氏が,子の政村を執権,女婿の一条実雅を将軍にしようとしたが,これも抑えて泰時を救い,執権政治を安泰ならしめて,直後に,没した(危機⑦)。大江広元も,後を追うように,没している。
1224年,41歳で,3代執権になった北条泰時は,まず,執権嫡流の得宗家を確立,1225年,実質的な将軍の役割を果たしていた伯母政子が死去すると,政治改革を行い,独裁から合議に転換させて,執権政治を確立。1232年には,御家人間の相論における公平な裁判の規範となる,初の武家法典「御成敗式目」を制定,この間,大飢饉には,領民の救済に努め,並行して,都市鎌倉も整備し,興福寺,延暦寺など,武装僧徒には断固たる態度で抑圧するなど,善政を謳われたが,1242年,四条天皇が没し後嗣が問題になると,皇位に干渉し,貴族たちの反対を抑えて土御門上皇の皇子(後嵯峨天皇)を即位させて,のちの南北朝への原因をつくったところで死去した。
兄の経時を継いで,1246年,19歳で5代執権になった北条時頼は,直後に一族の名越光時を誅し,将軍藤原頼経を追放(宮騒動),翌年には,安達景盛と計って,三浦泰村一族を滅ぼし(宝治合戦),1252年には,将軍藤原頼嗣を追放して,待望の皇族将軍(後嵯峨天皇の皇子宗尊親王)を実現,北条政子を彷彿とさせる陰謀ぶりで,執権北条氏の権威の増大を図る間,御家人を公平に扱うとともに,撫民的な善政を行い,1256年,病気になると,出家。追慕する御家人が多く,何度も出家制止令を出すほどであった。その後も,院政のように,権力を保持し,公家権力の背景となる天台宗の寺院を,臨済宗へ宗旨替えさせて,武家体制仏教を確立,後に,回国伝説を生み出す自由な活動をし,1260年,日蓮が「立正安国論」を呈じてくると,伊豆に配流したが,1263年,36歳という若さで没した。
泰時,時頼までは,源氏化していた平氏の良さが表れて,名執権といわれる人物であったが,根っこの方では海賊などともつながっているため,いわゆる得宗による恐怖政治の萌芽が生じ,地方では,例の播磨国を代表にいわゆる悪党が跋扈し始める。そうしたところに,史上かつてない国難といわれる蒙古襲来(元寇,実質的には,シラギ系の多い高麗人との戦)が起きる。
ロ:元寇による権力集中で,海洋民族の乱暴さが露わになる得宗独裁・悪党時代
1268年,17歳の時,高麗使藩阜の渡来直後に,時頼の子北条時宗が8代執権に就任,3年後にも,モンゴル使趙良弼が渡来するも無視,1274年,ついに,元寇(文永の役)になるも,元使杜世忠を竜ノ口に斬るなど一貫して対モンゴル強硬政策をとり,国難を理由に,高麗進攻計画,防塁築造,非御家人の軍役動員など,まさに総動員体制をすすめ,幕府を独裁政権にしてゆくと同時に,守護職や重要所領を北条一門で独占する,いわゆる得宗専制を強化,1281年の再度の元軍の来寇も退け,幕府の権威は絶大になるが,3年後,33歳の若さで没した。
時宗という強力な執権が没するや,平氏の乱暴さが一挙に噴き出し,後を継いだ執権貞時の乳母の夫で内管領になった平頼綱が,元寇で御家人をまとめる役割を果たしていた安達泰盛とその一族を滅ぼし(霜月騒動),専制による恐怖政治を実施,8年後,ようやく,その権勢を警戒した貞時によって討たれるが,以後,平氏の乱暴さばかりの,いわゆる得宗専制,悪党横行時代となり,これといった文化を生むことなく崩壊して行く。
そのなかで,信仰心の厚かった北条時宗は,蘭渓道隆,大休正念に深く師事し,その招きで無学祖元が来朝し建長寺の住持となり,円覚寺を建て祖元を開山とするなど,元との間の交易は成り立っていて,以後も,交易船を利用した,元,日いずれの禅僧の往来も盛んで,五山文化を準備することになる。
「高麗史」の,1223年の項に,「倭が寇する」という記事が初めて登場,源平合戦に敗れた海洋民族平氏と,その平氏が支配していた海賊たちが行き場を失って進出したものと思われるが,その50年後には,熟字「倭寇」として使われるようになるほど頻繁になるのは,元寇によって,海防が一気に強化され,もはや,日本の側では活動できなくなったことに対応しているようだ。
なお,高麗国は,形式的には,高句麗の後継のようにみえるが,日本との距離関係でみれば,実質的には,新羅人が多い国であったといえる。
ハ:天皇親政を夢見た"異形の王権"後醍醐天皇~武家政権内の交替を招く
後醍醐天皇という特異な天皇が政権を取り戻すべく立ち上がり,新田・足利氏ら正統的源氏の支えを得て,1333年鎌倉幕府を滅亡に追い込み,建武の中興を実現するものの,足利尊氏の反抗で,1336年あっけなく崩壊,単に中世の中間点を示すに留まり,いわゆる室町幕府が樹立される一方,混乱の南北朝時代となるとともに,北朝が正統とされてする。
北条執権の介入によって,皇統は大覚寺・持明院両統に分裂していたが,北条執権政治の弱体化を見た後醍醐天皇は,1318年に,即位を勝ち取るや,その特異な個性を発揮,幕府によって制限された王権を回復すべく,3年後の親政開始とともに,専制的支配をめざし,1324年には,早くも討幕を企てて失敗(正中の変)するもくじけず,再び計画して失敗(元弘の変),捕らわれて隠岐に流されたが,なおめげず,1333年,隠岐を脱出,諸国に挙兵を呼びかけると,源氏嫡流ながら北条氏の配下になっていたことに我慢できずにいた足利高(尊)氏が呼応,ついに幕府を滅ぼす。
建武新政を開始するも,その専制ぶりが,武将・貴族たちの強い反発を招き,足利高(尊)氏の離反で,3年後にはあっけなく瓦解,結果として,シラギ系の足利政権が誕生し,北朝が正統とされ,シラギ系天皇も復活。後醍醐天皇は,吉野に南朝を開いて,幕府に対抗し,1339年の没後も,南北朝時代が続くことになる。
第2話:シラギ系足利氏による,武家政権の建て直しから,公武一体化で破綻するまで~室町時代
イ:南北朝という天皇制の異常下の,シラギ系清和源氏の正統派足利氏政権
足利氏は,源氏将軍断絶後,清和源氏の嫡流として御家人の間で重んじられ,北条氏と肩を並べる存在であったが,しだいに圧迫を受けるようになり,尊氏の祖父家時のころから源氏再興の志を抱くようになっていた。1331年,討幕めざす後醍醐天皇による元弘の乱が起こると,前執権北条高時から,父貞氏の死去にあったばかりのところに出陣を命じられ,深い憤りを覚えて,北条氏打倒の決意,天皇側について,討幕を実現させる。すると,本来の源氏再興の志から,後醍醐天皇による建武の中興に謀反し,持明院統の光厳上皇の院宣を受け,後醍醐天皇側の楠木正成軍を破って入京,光厳上皇の弟光明天皇を立て,新幕府の開設を宣言。後醍醐天皇は吉野に逃れて,朝廷を開き,南北朝対立の時代となる。尊氏は北朝から将軍宣旨を受けるもののまだ弱く,後醍醐天皇が死去した後も,北畠親房の指導で南朝の抵抗が続くうち,尊氏の弟直義が南朝側についたことで観応の擾乱が始まり,1352年,尊氏が直義を毒殺してようやく決着,幕府は安定するが,なお,南朝の抵抗は続く。
尊氏の嫡男義詮は,関東を重視する父の命により,東国武士結集の役割を果していたが,,鎌倉に弟基氏をおいて上洛し,観応の擾乱に対処。尊氏の死で,将軍職を継ぐと,細川清氏を執事に任じるが,南北朝動乱で,清氏が従兄弟の細川頼之に討たれると,足利一門中将軍家につぐ高い家柄をもち,清氏と対立していた旧直義党の斯波高経に幕政の補匠を要請するとともに,関東でも旧直義党の上杉憲顕を招いて関東管領の任務を委ね,その子憲春を関東執事として,基氏との関係を修復。さらに,南朝方の大内弘世や,直冬党の山名時氏も幕府に復帰させて,幕府体制をほぼ安定させる。そして,死を目前にすると,お目付け役に細川頼之を初の管領につけて,子の義満に将軍職を譲る(時あたかも大陸で明が建国された年)。
義詮の弟,鎌倉に残った基氏は,初代の鎌倉公方になり,自らも時期将軍を狙っていたが,義詮の死の直前に死去,子孫が幕府と対立していくことになり,また,義詮は,将軍を継いだ当初,細川清氏を執事に採用したが,死の直前に,鎌倉幕府における執権のような役の管領を設け,清氏を討った従兄弟の細川頼之をつけたこともまた,細川一族の間の抗争を招くなど,幕府が弱体化していく種も撒かれたのである。
古代(奈良・平安時代)最強の公卿クダラ系藤原氏の道長に対応するように,中世(鎌倉・室町時代)最強の将軍になる足利義満は,将軍職を継ぐも,幕政はなお管領細川頼之が取り仕切っていたが,1378年,20歳になると,華麗な室町御所を造営し,後円融天皇の行幸を仰いで誇示,翌年には,政変で頼之が追放されて,実権を掌握,24歳には,父祖を超えて,左大臣に上り,二条良基を摂政に,自らは内覧となって,全権を掌握し,翌年,源氏の長者となり,武家で初めての准三宮に至る。1392年,南北朝の合一を実現し,翌年,後円融上皇が死去すると,自ら上皇相当の位置から政務を処置,翌1394年,36歳になると,将軍職を長子義持に譲って太政大臣に昇り,翌年,出家するも,依然として政務を見る。翌年には,九州探題今川貞世(了俊)を突然罷免したことで,朝鮮貿易の利権を得た大内義弘が,一気に伸長したため,1399年,彼を討って抑え(応永の乱),天下統一事業の仕上げとして,明との交渉を開始,明からの倭寇禁圧要請に応え,1404年,明帝から,日本国王と認められて冊封関係を結び,日明公貿易(勘合貿易)の制度を成立させ,1408年,後小松天皇の北山第行幸直後,ついには,王権簒奪かと思われた矢先に,没したのである。
ロ:クダラ系藤原氏の文化に飲み込まれて弱体化,応仁の乱に至る
足利義満は,室町御所を造営してまもなく,左大臣に上り,二条良基を摂政に,自らは内覧となって,全権を掌握すると,尊氏,義詮が進めてきた王朝・本所権力の幕府吸収政策の総仕上げ,「北野天神縁起絵巻」制作に続いて,「融通念仏縁起絵巻」を制作して全国流布させるという壮大な絵巻プロジェクトを立ち上げ,1393年,後円融上皇が死去すると,自ら上皇相当の位置から政務を処置,1397年には,金閣寺ほか多数の殿舎より成る北山第(鹿苑寺)を造営,政庁を兼ねて,絵合せの一大イベントをするなど,公武社交の場とした。
義満はまた,禅宗寺院統制のために五山制度を整備し(五山・十刹・諸山),義堂周信,春屋妙葩らの禅僧を重用したほか,自身も,和歌,連歌,楽,書に秀で,猿楽を好んで,観世親子を見出し,中国渡来の文物を愛玩するなど,文化の面でも傑出した指導者で,藤原道長による王朝文化が古代の絶頂であったのと同様,義満によるいわゆる北山文化は,中世の絶頂であったが,同時に,公武合体が一気に進み,義満没後,シラギ系足利政権は,クダラ系藤原氏の文化に飲み込まれて弱体化していくことになる。
源氏を始め騎馬民族は,王侯貴族などの守旧派をうまく使い,農民ら土着の人たちを支配するのが得意で,中国においても歴代王朝の多くは騎馬民族であるが,彼らはまた自らの文化を欠くため,結局上下の文化の中に埋没して弱体化しモラルも崩壊して行く。足利将軍時代は,まさに,その典型といえよう。
後を継いだ将軍義持が,父義満の威光に抵抗して逆の政策をとるようになるものの,その遺産の上で平和が保たれるが,ほぼ同時に鎌倉公方になった足利持氏の反抗に悩まされるうちに出家,義持は子の義量に将軍を譲るも義量は早世,その後再び政務を司った義持が,後継将軍や嗣子を定めることもせずに没したため,,将軍不在になってしまい,側近協議の上,候補者のうちから籤引きで選ぶことになり,1428年足利義教が将軍に就くが,その正当性に不安があったのか,恐怖政治を敷いて独断専行したため(世阿弥の配流もその犠牲),地方で土一揆が起こり始めるなど,周囲の反発が強くなって行き,1441年,ついに将軍義教は暗殺されてしまう(嘉吉の乱)。
以後,将軍の力は落ちて行き,管領が頻繁に交替,嫌気した将軍足利義政が政務を放棄してしまい,妻の日野富子が表に出るようになるなか,管領家を中心にさまざまな確執が重なって,応仁の乱の勃発に至る。
クダラ系藤原氏の側でも,2代将軍義詮の時代の関白二条良基が武家と融合する連歌文化を創始,8代将軍義政は政治から逃避して,1467年には,戦国時代の幕開けとなる応仁の乱を引き起こす原因をつくるに至るものの,他方,東山文化として,現在につながる多くの様式の創始に関与,義政時代にほぼ重なるように,公家の側には,文化的巨人といわれる関白一条兼良が存在,兼良はじめ,応仁の乱で疎開を余儀なくされた一流の公家たちが地方に京文化を広めるというおまけまでついた。
義満が,南北朝合一を実現するに際し,皇位は大覚寺統(南朝)・持明院統(北朝)を交互にたてるようにしたことで,皇位継承に問題を残したが,足利義教は,自らの正統性のためにも,天皇の権威を高めることに努め,1428年,呼応するように傍流から践祚した後花園天皇が,義教暗殺後も長く在位,学問諸芸に通じることによる天皇の権威を確立し,"中興の英主"になった。1464年に,譲位して上皇になると,左大臣(将軍)足利義政を院執事として院政を敷き,猿楽,蹴鞠という共通の趣味で気の合った義政夫妻と親交するうち,応仁の乱が勃発,戦乱を終わらせようと執念を燃やすもまもなく没したが,義政夫妻がその最期を看取っただけでなく,義政は戦乱中の外出に反対する細川勝元の反対を押し切って,葬儀から四十九日の法要まで全てに参列しており,まさに,天皇家と将軍家が一体になるような公武合体の極に至っている。
足利義満の北山文化の観阿弥・世阿弥から,義政の東山文化の善阿弥・能阿弥・芸阿弥・相阿弥まで,阿弥号を持ち,独自の才能を発揮して,武家文化の興隆に貢献した人たちがいたことも指摘しておきたい。桜井哲夫「一遍と時衆の謎」から導かれるのは,戦で負けたり,主君の命に背いたりして,逃げ込む先にあったのが一遍の時宗であり,いわゆるアジールで,当然,都市の匿名性のなかに紛れこむことから,時宗は都市型宗教でもあった。とくに,南北朝の動乱は,他の戦とは全く異なり,それ以上の権威が無い天皇を戴いて,南北朝に別れて戦うのであるから,精神的障害が大きかった可能性が高く,それが,時宗が飛躍的に伸張した原因と考えられる。もともと武士である故,陣僧となって,戦う武士をサポートするとともに,同朋衆になるなど,生計を確保すべく,それぞれが,何らかの特技を身につける必要があったことから,多様な人材が登場,近世を準備することになる。南北朝合一後も,戦国時代においては同様の役割を果たすことになるが,真宗が一向宗化することで吸収され,織田信長によって,戦国時代が終わるとともに,一気に衰退していったのも,当然であったといえよう。江戸幕府初期の,万能の芸術家として知られる本阿弥光悦が最後になるのだろう。
ハ:平氏末裔が主導する前期倭寇の盛衰と琉球王国の出現(イト系)
足利義満の死は,大内氏の朝鮮利権を復活させ,倭寇禁圧の結果,琉球王国を代表に,倭寇末裔による地域政権ができ,また,水軍化して,戦国武将の抗争も激化していくことになる。>水軍
田中健夫「倭寇~海の歴史」をベースに,若干付け加える形で述べると,「高麗史」の,1223年の項に,「倭が寇する」という記事が初めて登場(倭は,大陸から見た日本の蔑称で,中国正史で,呼び名が倭から日本に替わったのは,天武天皇が国名を正式に日本としたことに対応して,「唐書」からになる),その50年後には,熟字「倭寇」として使われるようになるほど頻繁になり,太宰少弐資頼が勝手に高麗と交易し,その高麗が,元の圧力を受けて弱体化したことで,高麗の賤民とも結びつき,日本で観応の擾乱の起きた1350年には一気に本格化。造船ばかりか,医療まで,技術を持っていた者も多く,高麗に投降した場合でも,重用され,政府の中枢にまで入る者までいた。三港には,大きな日本人居留地ができ,対馬の宗氏や,大内氏,少弐氏などを特別扱いにして限定するも,多数の倭人が渡航,接待の費用も増大し,その結果,朝鮮の人たちの経済を圧迫して,窮した人たちが,倭寇に頼るという悪循環になった。
元と日本は,国としては対立する一方で,市舶司をおいた慶元に限って,正式な貿易船の往来を認めていたことから,それを利用した日元の禅僧の往来も頻繁で,幕府が警固していたため,通商がうまく行かない時に,官憲に乱暴狼藉を働く程度ことが専らで,倭寇の記事そのものが少なかったが,明が登場すると,連年のように倭寇の記事がでるようになり,朝貢体制を重視する明は,倭寇の禁圧を様々なルートで日本に求め,やがて,圧倒的な権力を握った義満によって禁圧され,日明間の正式な勘合貿易に一元化される。行き場を失った倭寇のうち,武力に優れる者は,その後に輩出する戦国武将らの水軍になり,また,琉球王国を建国した尚巴志や,肥前の大村氏のように,交易をしやすく,陸上の支配者の強くなかった土地に,根拠を定めるようになる。
義満は,日明通交のため,博多商人の肥富(コイツミ)の言に従い,同朋衆祖阿(ソア,素阿弥)を正使に,使節を派遣した。祖阿は異色の商人楠葉西忍の父で義満の時代に渡来した天竺聖と同一人物といい,天竺はインド以西を指し,西忍の幼名がムスルであったというから,中東アラビア方面の出身であったとみられる。肥富は安芸小早川氏の一族小泉氏の出身とされ,小早川氏のルーツは相模国足柄郡小早川村であったとされることなどから,肥富という奇妙な名が先で,それを小泉にするようになったとも考えられる。余談ながら,その子孫ともみられる小泉純一郎の風貌がユダヤ人的でもあり,肥富がユダヤ商人であった可能性も否定できない。
足利義満の死に続く,対馬の宗貞茂の死というスキをついて,1419年,明が倭寇の中国側の本拠地を徹底的に攻撃し,ほぼ同時期に,李氏朝鮮が対馬に侵攻(応永の外寇)したこともあって,壊滅的な打撃を受けた前期倭寇は終焉を迎え,倭寇が転じた水軍をも配下に置く本格的な戦国武将の抗争の時代になっていく。博多などに代わって,琉球那覇の地位が一気に向上,琉球王の使者になることで,朝鮮での扱いが格段に良くなることから,博多商人などが,盛んに偽称して問題になっている。遣明船については,大内氏は,もっぱら博多商人を使っていて,堺商人を使う細川氏の勢力と抗争,1528年,中国の寧波で,自らの使者が細川氏の使者と争いを起こして勝利,以後,遣明船の権利を独占することになる。
吉成直樹「琉球王国は誰がつくったのか 倭寇と交易の時代」によれば,
琉球語は北部九州語がルーツで,南下していく都度分岐,最後は南九州語から分かれて,11~12世紀に,琉球列島に到達した人たちによると考えられている。それまでは,(前述したように)北方の蝦夷と近い縄文人,つまり弥生人の渡来で押し出されてきた人たちの住むいわゆる未開の地で,本土ではとうの昔に無くなっていた縄文文化が保たれていた。最大の島(沖縄本島)ですら農業に適さない土地柄であったことから,交易というより,海賊的で,1243年に漂着した本土の人の記録でも,頭目が武装集団を従える異人と記されている。
喜界島は,平安時代には,大宰府と密接につながる,南方諸島支配の拠点であったことから,北部九州人は,喜界島において,早くから,朝鮮ともつながって,南方交易を支配し,11~12世紀には,中国の陶磁器も流通するような勢力で,おそらく平氏とも関係していたことから,1188年,源頼朝に征討された。この時期が,琉球正史で初の王とされ,1187年に即位して1237年に死去したという舜天王と,時期的に重なることや,鎮西八郎為朝が王になったという伝説もあることから,喜界島から逃亡してきた人たちによって,琉球国の歩が始まったとみて良いと思われる。
そして,13世紀後半から大型グスクの造営が始まり,14世紀後半には,高麗国の影響で構造的な革新がなされ,いわば,本土における戦国時代のように,群雄割拠の状態になった。勝連グスクの王は,阿麻和利(アマワリ)というから,アマ系であった可能性があり,その前の王は,茂知附(モチヅキ)すなわち望月と日本の姓そのものであった。その望月氏は,信濃国滋野氏の流れと伝えられることから,海洋民族であったと考えられる。
この間,13世紀半ばから広がってきた倭寇の勢力圏にとりこまれ,1389年に,倭寇が高麗で略取した奴隷を,中山王察度が高麗に送還したという記録があるように,奴隷貿易までしていたことが知られる。1360年に即位に即位して王統を開いたという察度は,朝鮮語のサトが地方官などを意味したことから,高麗から渡来したのではないかといわれる。いわゆる琉球三山時代においては,それぞれが東シナ海交易圏の主体者になっていたが,いずれも,中国との交渉ができたのは,中国人居住地久米村があったことによる。北山王国は全く異質であったとようで,明の建国により,元に仕えていたイラン系遊牧民アラン人が渡来し,居住して交易商人になったといわれる。隼人が中央アジアの遊牧民トカラ族であったことにもつながる話といえよう。
1368年に,中国で建国された明の洪武帝は,倭寇禁圧を,とりあえず日本の王とみなされていた(九州にいた)南朝の懐良親王に要求するも埒が明かず,琉球に鉾先を向け,1372年,招諭に応えて朝貢してきた察度に対して,破格の待遇をしている。やがて,将軍足利義満が明から国王として認知されるようと,その要請に応じて,1406年に倭寇を禁圧,勘合貿易を開くに至り,倭寇の頭目たちは一気に新たな場を求めざるを得なくなる。
1410年即位した尚巴志は,まさにそれに対応するように渡来,鉄器製造,交易に優れて,父の思紹をたてて,一気に琉球を統一したと考えれる。その本拠地佐敷グスクは,それまでのグスクとは異なり,本土中世の城郭そのものであった。琉球王国は明の倭寇対策によってできたといえよう。ついでながら,肥前国大村氏も,15世紀前半に突如登場したこと,交易を主体にして勢力を伸ばしたこと,藤原純友の末裔つまり海賊がルーツであることを自称していたことなどから,琉球と同様,倭寇であったと考えられる。
なお,琉球建国に,平氏が関わっていたとすれば,糸満という地名や,糸数という名字など,伊都国の末裔を示すイト系が多いのも,頷けよう。イメージをたくましくすれば,琉球列島の日本本土と中国や南方との関係が,航海技術の発展によるスケールの違いを別にすれば,上古の時代の伊都国のあり方に,良く似ているようにみえる。そして,敵対することになった邪馬台国に当たるのが強藩薩摩であり,その先の場が無かったことが,結局,薩摩藩の支配下に置かれてしまうという不幸の始まりになったのである。
ところで,源頼朝による武家政権発足とともに,相模の国から島津氏が薩摩に配されることになりi,その島津氏の本姓は秦氏をルーツとする惟宗氏であることはすでに述べたが,ここで,中国に対する琉球以上に,朝鮮に対して,地理的。歴史的に密接な関係を有している対馬についても触れておこう。荒木和憲「対馬宗氏の中世史」を読みながら勝手に解釈をしてみると,江戸時代には,対馬の主が宗氏であることは,当然のようになっていたが,その宗氏もまた,島津氏と同様,惟宗氏すなわち秦氏をルーツとし,鎌倉幕府発足の頃,幕府の守護の埒外ながら,対馬に進出していたらしく,北条執権の頃には,守護代のような位置になっていたらしい。そして,琉球の王国発足前と同じように,宗氏一族の間で抗争が絶えなかったが,倭寇の活動が禁止されたことから,琉球王国が成立し,肥前国に大村氏が登場したのと同じ頃に,対馬においても,倭寇の主体たる平氏(イト系)の参入があったらしく,それを利用する形で,のちに藩主になる宗氏の覇権が確立,いわば宗王国が成立したと見られる。こうしてみれば,大陸との関係は,全く倭寇によって築かれたと言わざるを得ないだろう。
第3話:大内氏が将軍代役になるも,下克上で,武家政権の秩序が崩壊~戦国時代
イ:大内氏はクダラ系藤原氏の直系だった
戦国時代に入ると,百済の末裔と称し,朝鮮との貿易で財力を蓄えた周防の大内氏が,公家その他京の文人を救済する形で,雪舟を代表に,山口に芸術を花開かせ,大内義興時代には,京都に在留して,将軍の代役を務めるに至る。1573年に,織田信長によって,将軍義昭が追放され,足利幕府が滅亡するまで,細々と,足利将軍は続くが,その間も,公卿の三条西実隆が文化面で大きな役割を果たすなど,足利時代は全体を通して,支配者はシラギ系ながら,文化的にはクダラ系の時代であったといえる。足利将軍が藤原氏に取り込まれたことが,応仁の乱を勃発させ,中世の幕府体制を壊すとともに,クダラ系藤原氏といえる大内氏の覇権を招いたといえよう。大内氏はまた,第9論で述べるように,長州人のルーツにもなったのである。
桓武平氏のところで述べたように,いわば平氏の原郷ともいえる周防の瀬戸内海沿岸中ほどには,平安時代において銅銭を製造した唯一の場所の名残である鋳銭司があり,そこが藤原純友に襲撃された後に登場する平氏は,この地の銅を活用し,大陸との交易を通じて財をなし,やがて覇権を握ったという。その鋳銭司に関連するが,大内氏は,古代からの長登銅山に関わり,世界遺産になった石見銀山を発見,朝鮮半島から当時の先端精錬技術灰吹法を導入したことなどでも知られる。
ところで,明治維新の主役は長州人という言い方がされるが,長州とは,現在の地名では山口県で,旧国名では,長門国と周防国を合わせたものであり,中臣鎌足のところで述べたように,百済王族だった鎌足を受け入れ,中臣姓を称することができるようにして,ナカ系の乳母に育てられた中大兄皇子と乙巳の変を起こして,歴史に登場させた場所なのである。その証拠として示したように,大内氏の都山口の西半に広く吉敷(キシキ)という地名が広がり,キシすなわち百済王族が,キすなわち来たところを示しているからで,戦後の長州人を代表する岸信介の「岸」姓は,百済王族の「キシ」そのものを表し,その正統な末裔であることになり,岸信介の弟の佐藤栄作,外孫の安倍晋三が,ともに長期政権を担った,影の理由である気さえしてくる。
その長州一帯を支配した大内氏は,自らのルーツは百済であるとし,京の貴族,すなわち藤原氏ときわめて近しい関係にあったこと,戦国時代に入ると,山口に公卿らを招いたばかりか,一時は,京で将軍の代わりまで務めたことなど,権謀術数にたけた百済人ぶりを発揮したといえ,何事も武力で決着しようとした源氏に代表される新羅人とは対照的なのである。以上のことからだけでも,長州人,そのもとになった大内氏は,かつての藤原氏の遺伝子を強固に持っていることが推測されるのである。
大内氏を飛躍させたのは,1395年,大内義弘が,(まさに,クダラ的藤原氏のやり方の)讒言によって,九州探題の今川貞世を左遷させて,朝鮮の利権を奪取して巨利を挙げるようになったことによる。金の力だけでなく,藤原氏との歴史的関係もあって,応仁の乱では,政広が将軍の代わりをし,1491年には,義興が入京して,将軍そのもののような存在になり,遣明船の利権をも独占するようになるが,1518年には,山口に戻り,1528年,中国の寧波で,自らの使者が細川氏の使者と争いを起こしたりして威信も低下,戦国武将が次々と登場するようになるなか,義隆が,ザビエルの布教を許可した翌年,家臣の謀反により滅亡に至り,交替するように,織田信長が登場するのである。
ここで,大内氏について,どんな存在であったかを,改めて検証してみよう。
はじめ,多々良姓を名乗っていたのは,東国の三浦氏などと同様,平氏出身を示すとともに,古代のタタラ製鉄,そこから起こった'タタラを踏む'という言葉があるように,鉄器民族を示すものでもあが,その一方,自らの氏族のルーツを,百済王としていて,一般の解説では,朝鮮半島との交易を有利に進めるためにそうしたのだろうといわれ,確かに,朝鮮貿易を通じてつくりあげた多額の財を寄付することで,皇室や公家を味方につけたといわれるすが,それだけではとても,大内氏が京都の公家,さらには朝廷と特別な関係を結ぶことができたことを説明しきれないと思われる。もともと周防の在庁官人であった大内氏の,初期の当主盛見がいみじくも,'武将としての才能に欠ける自分が,戦乱を勝ち抜いて周防・長門両国を支配できるようになったのは仏神のおかげだ'と述べていることに,そもそも武家ではないと自覚していたことが示されているようであり,他の守護には見られないシステマティックで整然とした統治機構を確立したことからも,武家(武闘)の才より,公家(文治)の才があったといえるのではないだろうか。
タイミングよく出版された伊藤幸司編「大内氏の世界をさぐる」を読んでみると,大内氏が京都の公家たちと関係を結ぶことができたのは,長門国に転法輪三条家の荘園があり,それを守ってきたことによるということで,転法輪の語がつくのは,ほかにもある三条家と違い,藤原北家直系,つまり,摂関家に極めて近いことを示しているという。なぜ,ここに,そんなにも大事な荘園があったのかを考えてみれば,それが,中臣鎌足の時以来のもの,百済王子であった鎌足が一時的に中臣姓を借りた土地であったが,鎌足の息子不比等が藤原氏を独占して以降,中臣氏が忘れ去れたように消されてしまうこととも符合,何よりも,大内氏が,わざわざ百済王子の子孫であることを表明したことから,本当に,鎌足以降の藤原氏と血のつながりあった可能性すら考えられるのである。それが全く分からなくなっているのは,絶対に明らかにしてはいけない秘密,タブーになってしまったからだろう。百済王の末裔を示そうとしてつくあげた神話もまた,藤原不比等が「日本書紀」によって支配を確立したことを彷彿とさせる。
だとすれば,大内氏が異例な官位昇進をしたことや,実質的に南北朝合一を実現し得たこと,維新前夜に起きた"七卿落ち"のトップが,転法輪三条家の実美であったことなど,全てが符合してくる。そして,大内義興が,追放された将軍足利義尹を奉じて上洛し,覇権を握ったのは,織田信長が足利義昭を奉じて上洛したのより60年も前であるが,そもそも,鎌足が中大兄皇子を奉じて,覇権を握ろうとしたことの再現でもあったろう。また,豊臣秀吉が死後神格化されたのを遡ること100年以上,大内政広が亡父教弘の神格化を実現しているが,これには,吉田神道の事実上の創始者吉田兼倶が深く携わったといい,のちの靖国神社の話につながることは言うまでもなかろう。ただ,神格化の話そのものは藤原氏とはつながらないので,神事を司ったとされる中臣氏の血がでたものかもしれない。
さらに,政広の運動の結果,教弘に,従三位が追贈されたが,室町将軍家ですらなかったことで,武家秩序を覆すものであったといわれる。上洛した義興は,将軍足利義尹が沙汰始すると,帰国を示唆,京都を治めるには義興しかいないと考える朝廷自らが慰留に乗り出し,義興がそれに応えるや,従四位下に叙し,続いて,生前の大内当主としては初めてとなる従三位,それも朝廷自身の意志によるという異例の昇進をさせるのである。大内義隆に至っては,武士としては破格の従二位に叙せられ,位階の上では,将軍と主従逆転してしまうのである。このような扱いがありうるのは,前述したように,藤原摂関家との特別な関係なくしては考えられないだろう。
それだからこそ,勘合貿易を独占し,南北朝合一をもなしえたということで,その結果,大内氏は中央にも匹敵する地方政権を確立したが,このようなものは,奥州藤原氏を彷彿とさせるところがある。存在は全く異なるものであったとはいえ,奥州藤原氏も,前述したように,藤原氏の末裔であったのである。
そして,小京都の代表山口は,数ある小京都とは比較にならず,極めて多数の公家,それに付帯する形で,雪舟や宗祇など一流文化人が来訪・滞在して形成されたのであり,その象徴として,関白でもあった二条良基と大内政広が合作「新撰菟玖波集」を残しており,朝廷公認のもと,戦国時代に唯一,伊勢神宮を山口に勧請することができたのである。その後も,関白にして大学者の一条兼良,内大臣にまで上がった三条西実隆という,文化面での公家による武家支配を象徴する人物とも,最も親しく付き合っていることから,やや強引ではあるが,時代の流れの上に位置付けてみると,大内氏は,源頼朝の起こした鎌倉幕府を,平氏系の北条氏が牛耳ったように,源氏の足利将軍を牛耳る藤原氏として,武家社会に抑えられていた平安貴族を復活させる役割を担っていたかに思える。
ロ:下克上の口火を切った北条早雲も,決着をつけた織田信長も平氏(イト系)
北条早雲は,伊勢新九郎長氏と称されたように,桓武平氏で,室町幕府政所を世襲した伊勢氏の一族の出身と言われるが,若い頃の経歴は全く不明で,1467年,35歳の時に,応仁の乱が勃発した際には,将軍足利義視に仕えていて,義視が伊勢に下るのに従ったが,翌年に,義視が帰洛するのに従わず,伊勢にとどまり,駿河の守護大名今川義忠に嫁いでいた義視の妹北川殿の縁によってか,招かれて駿河下向。今川氏に身を寄せ,石脇城を居城としたらしい。10年後の今川家の内紛に際して,扇谷上杉家から派遣されてきた太田道潅と出会い,調停によって収拾したことから,ようやく,歴史に登場。1486年に,道潅が謀殺されるや,犯人の今川氏の庶家小鹿範満を駿府の館に攻めて自害させ,竜王丸を駿府に移して今川家の家督とし,この功績により,興国寺城主となる。
1491年,60歳を目前にして,堀越公方の足利茶々丸を討ち,平氏のルーツたるイト系の坂東の拠点,かの北条政子の故郷,伊豆に到達する。戦国時代を告げる事件としても名高く,伊豆を平定後,目的を達したと思ったのか,出家するが,1495年には,相模の小田原城を攻めて,これを奪い,関東進出の拠点を確保するとともに,韮山に城を築いて居城とする。1504年,72歳にして,今川氏親とともに,扇谷上杉朝良を助けて顕定と武蔵の立川原で戦い勝利をおさめ,京都の医者陳定治を小田原に招いて透頂香(外郎)の製造販売を行わせるなど,城下の整備を図り,翌年には,「伊勢宗瑞十七カ条」を制定して,検地を始め,領国支配体制を基礎固めした上,相模の征服を開始,鎌倉へ入ると,荒廃した鎌倉の再興を誓ったことが知られる。1516年,ついに三浦氏を滅亡させて,相模を征服,その3年後,87歳という長寿で,伊豆の韮山城で没した。
こうして,北条早雲は,いわゆる後北条氏の祖となり,その末裔は,北条氏政・氏直父子が,豊臣秀吉に滅ぼされるまで,町民が城主を慕う小田原城下町を経営し続けた。
以後,いわゆる下克上の世となり,武将が乱立し,諸民族がシャッフルされることになるが,1543年の鉄砲伝来,1549年のザビエルの来日後に登場した,平氏の織田信長が,鉄砲,キリシタンに素早く対応して,ライバル(寺院勢力も含む)を撃破,最後は,源氏の足利将軍を追放して覇権を握ることになる。それとともに,源平交代という観念ができ,後述するように,源氏に関係なかった徳川家康が源氏と名乗ることになるのである。
ハ:行き場を失った倭寇,変じて水軍となる(イト系ほか)
鷹橋忍「水軍の活躍がわかる本: 村上水軍から九鬼水軍,武田水軍,倭寇…まで」によれば,水軍とは,海賊,傭兵,輸送人,交易人を兼ねたような存在で,大名,領主などの軍事組織に組み込まれながら,主従関係は無く,より良い報酬を求めて寝返りも頻繁であった。語源が,そもそも兵士,軍隊のことであって,海の技術・技能者を表している海賊とは異なり,合法的な存在であるとは言っても,陸の土地に執着しないため体制外にあり,それゆえ歴史に記載されず,分かりにくくなった。主な収入源は,海上警固,(海の)関料,傭兵であった。前述したように,1406年に将軍足利義満が倭寇を禁圧したことから,水軍化したものが多い。
倭寇時代の商用船が使われていたが,16世紀に大型の軍事専用船が登場して本格化,織田信長が覇権を握る1570年頃に最盛期となる。有名な村上水軍はずっと毛利氏の支配下にあったが,1578年,これを破った織田信長が,瀬戸内海の制海権を握り,飛躍することになる。豊臣秀吉の朝鮮出兵においても,九鬼嘉隆の日本丸など安宅船多数が渡航,嘉隆は,その後も大規模な安宅船をつくるも,諸大名の力を削いで,交易を中央に一本化しようとする秀吉のバハン政策,徳川家康による安宅船没収によって一気に衰退,鎖国政策により,船は無用になり進歩は止まった。
水軍の最初に登場するのが,宗像大社の宮司一族が率いた宗像水軍で,難破船の引揚げ修理が大きな収入であったといい,村上水軍はじめ,瀬戸内海の島々を本拠地とするもののほか,後北条氏の支配する伊豆(八丈島まで支配し,小笠原諸島を発見したともいわれる),安宅船づくりの中心になった九鬼水軍(九鬼嘉隆は大名にまでなった)の志摩つまり伊勢平氏の本拠地など,平家のルーツたるアマ系,イト系のシンボル宗像はじめ,まさに源氏につぶされた平家の生きざまが露わになる。また,松浦党(水軍)は,後期倭寇の中核になるが,中国南部呉の末裔のマツ系として当然かもしれない。>後期倭寇
最も有名になった村上水軍は,源頼義の甥仲宗が村上源氏の娘と結婚,名にナカが入ること,その子が信濃に土着したことから,海洋民族の血が出てくることになったと思われ,その孫の定国が,平家の勃興期に,瀬戸内海に進出したことに始まる。伊予の新居大島を拠点に,芸予諸島の塩を抑え,源氏出ながら,平氏が主体の(後白河法皇)院近臣となり,海上警固を担った。源平合戦においては,棟梁だった清長は,平家の策謀に引っ掛かって破れ,一旦は消えるが,義弘の時代に,越智氏の流れで,もともと伊予の有力な水軍河野家が危機に陥った時,その要請に応えて救い,英雄になって再登場,毛利家の水軍として活躍し,最後の村上武吉はさまざまな作品に取り上げられる人物になった。
全く異なるものとして,津軽十三湊を拠点にした安東水軍がある。前九年の役で征討された安倍貞任の子の末裔で,蝦夷を背景に,朝鮮,中国,琉球までもと交易して巨利を得たが,南部氏に敗れた上,大津波に襲われて,跡形も無く消え去った。(前述したように)北方から南下してきたツングース系で,刀伊の寇をおこした女真族と同様,騎馬民族が海洋民族化したものと考えられる。ついでながら,貞任の子宗任は伊予に連れてこられ,安倍晋三はその末裔にもあたるという。
この章TOPへ
ページTOPへ
第8論:それまで支配とは無縁だった町人が活躍する時代~近世
前論同様,第二講「時代循環のパターン」も参照してもらいたい。>時代循環のパターン
第1話:大航海時代に対応,旧体制を破壊して新たな時代の幕を開けた織田信長(イト系)
イ:中国人が主体になった後期倭寇
ポルトガルの商売は,南アジアでは胡椒という産物をヨーロッパの銀・銅と交換することに意味があったが,日本では産物でないのはもちろん,肉食文化でないため,商品にもならず,それどころか,日本の金・銀・銅の保有・生産額自体が驚くべき多額で,それに対するニーズも無かったことから,はじめから植民地化する理由は無く,倭寇とのつながりもあって,ほとんど密貿易的状態が続くことになる。
田中健夫「倭寇~海の歴史」をベースに,若干付け加える形で述べると,1547年に,大内氏が滅亡して,遣明船が終わるとともに,明の福建省を中心とした南部沿海商人が倭寇化,(かつて呉の民族が日本に渡航したように),日本の海賊・水軍を取り込んでいく形で,いわゆる後期倭寇の時代になる。1514年には,マラッカのポルトガル人が中国に進出し始め,これら南部沿海商人と結託,植民地化の志向の無い彼らは,交易拠点の確保が目的で,やがて,琉球王国人と出会って高く評価することになる。そして,戦国武将のように,有力な海賊と頭目が輩出するようになって,明による討伐が繰り返され,1526年に,許棟4兄弟が滅ぼされた後に登場したのが,最後の大頭目とされる王直で,日本の五島列島を活動の根拠地とした上,(マツ系直系であった故に,話も通じたと思われる)松浦氏に招かれて平戸に居住した(長崎県と福建省は現在でも深いつながりがある)。
平戸という地名も,平氏との関係を思わせるが,苗字の平戸のルーツは,常陸国那珂郡平戸村といい,桓武平氏が展開していたところで,平戸のほか,関東の後北条氏や伊勢の港なども活動拠点にしたというから,まさに,平氏の末裔たちとのつながりが深かったといえるだろう。ちなみに,開銀の名総裁であった平田敬一郎は,平氏の棟梁を思わせる風貌としても知られたが,先祖は五島列島の人であったといい,三井のリーダーだった江戸英雄は,茨城県出身であったが,やはり,平氏の末裔を思わせるところがあった。
キリシタン時代に入ると,ポルトガルの貿易にも関与,種子島への鉄砲伝来も,王直の密貿易船によるものとされるなど,キリシタン宣教師の渡来も合わせて,その後の平戸の大発展の礎をつくり(かの有名な明の遺臣鄭成功もここで生まれている),1545年には,博多商人の助左衛門を仲間に引き入れ,大友氏,大内氏とも交渉をもつようになって,倭寇国王といった存在にまでなったが,1553年,中国側の拠点が掃討され,平戸に逃げ帰ると,以後数年,大船団を率いて,中国の沿岸を襲い,後期倭寇の最盛期になるものの,1557年に降伏し,翌々年に斬首された。その後も,倭寇の残党が,台湾を基地に,フィリピンはじめ南方へ襲撃したりするが,オランダの登場,明の海禁令の解除,豊臣秀吉の海賊(バハン)禁止令などによって,一気に衰退し,16世紀末には終息,江戸時代の博徒,明治維新後のヤクザへと繋がって行くことになる。
中国側の史料によれば,倭寇の日本人には,薩摩,肥後,長州の三州が最も多いと書かれており,この時に培われた密貿易のルートが,徳川幕府時代にも続けられて,巨富を蓄えることになり,結果として,明治維新につながったともいえよう。大友宗隣は,明の鄭舜功が倭寇の禁圧を要請すべく来訪してきたように,日本側倭寇のボスであり,(九州探題今川貞世を,讒言によって左遷させ,朝鮮の利権を奪取した)大内氏は海賊と癒着していて,いずれもキリシタンを容認していることから,倭寇とキリシタンが一体であったことが伺える。平氏出身の織田信長は,鉄砲や宣教師の活用はもちろん,これら密貿易とつながって,水軍の活用にも優れたことから,覇権を握るに至ったのである。
大友宗麟という,ユニークなキリシタン大名について補足しておくと,まず,鎌倉時代初期から,大友氏が豊後を支配し続けたのは,瀬戸内海の海賊とつながって,物資だけでなく,中央の情報入手にも長けていたらしいこと,そのルーツが相模国足柄であることから,一般に言われているように,藤原秀郷流でなく,平氏すなわちイト系であると思われる。宗麟が,日向にキリシタンの理想郷をつくろうとしたのは,一つには,天皇を超える神を認めるという,伊都国と邪馬台国の対立がもとにあって,平将門が関東に王国をつくろうとしたこと,もう一つは,北条早雲に始まる後北条氏が,領民一体となる国をつくったことに通じるところがあるように感じられる。
ロ:(物理的な武器)鉄砲と(精神的な武器)キリシタンの影響
平氏出身の織田信長は,まず海洋民族一般の開放性で際立ち,渡来した鉄砲という物理的武器と,キリシタンという精神的武器をいち早く受け入れ,平氏特有の派手さと乱暴さでも際立って,戦国時代に終止符を打った。
キリシタンの影響については,海老沢有道「日本キリシタン史」に従うこととするが,同書には,鉄砲のことも触れられているので,まず,述べておくと,種子島への鉄砲伝来の評判はたちまち全国に広まり,紀伊根来の杉之坊は津田堅物を種子島に派遣し,屏太郎または皿伊且侖に製法を伝習せしめ,堺の鍛工芝辻清右衛門にも伝えられ,堺ではまた,橘屋又三郎が直接種子島から習得したほか,平戸や豊後にも伝えられ,伝来後,数年もたたないうちに,将軍足利義輝の耳に入り,島津・大友両氏は,度々,鉄砲を献上,それによって,近江の国友らが直ちに製造を開始,1549年,信長が五百挺の製造を依頼し,翌年には納めたとの記事があるなど,国産化は急速に進み,普及したことは間違いなく,1565年には,福田入港のポルトガル船が,平戸・堺の商船隊と交戦したばかりか,朝鮮や明に,日本の銃が伝わるほどになっていた。信長は,単に,鉄砲を使用するだけでなく,隊列を組ませて,銃撃させるなど,戦法をも工夫することで,他の武将たちを圧倒していった。
大航海時代そのものが世界史的動きであったが,同時に起こったイエズス会の世界布教も内実がつまったものとして,世界史的事象であり,日本の近世化を一気に促進させる一方,ヨーロッパからは想像もできなかった高度な文明に直面したことでも,他に類例を見ない事例であったといえる。織田信長は,1568年に入洛して,覇権を握ったとはいえ,戦国大名はなお,それぞれに王国的主権をもっていて,いわゆるキリシタン大名もかなりいたが,信長にとっての統一事業の当面の障害は,延暦寺を頂点とする仏教勢力であって,1570年,まさに平氏の乱暴さをもって,比叡山を焼討ちしたことは,新井白石も,残忍とはいえ,功績であると認めざるを得ないものであった。しかるに,もう一つの勢力,石山本願寺を核とする国家のような真宗教団が,戦国大名や,追放したはずの,将軍足利義昭と連携して立ちはだかり,その他,法華宗,興福寺などの仏教勢力を潰すことに注力しているところに,新たな思想と文化をもたらしたキリシタンはまさに願ってもないもので,宣教師を厚遇して,仏教の腐敗を痛罵させたりしているが,キリシタン大名高山右近を味方につける際,そうしなければ,信者を皆殺しにすると脅していることからも,信仰とは全く関係ないものであった。いずれにしても,仏教の教団は支配力を失い,徳川時代には,行政の(とくに戸籍管理の)出先機関にまで成り下がるのである。
戦国時代という,命を守ることの困難さや,下克上はじめ,究極の利己主義がはびこる世の中で,既成仏教の僧侶は堕落して救済にならず,一向一揆,法華一揆は,戦国の混乱を一層増すだけという時代に,キリシタンが登場,それまでの日本人に欠けていた合理的(科学的,実践的)思考をもたらすのである。
イエズス会のザビエルは,マラッカで,鹿児島出身のヤジロウに巡り合い,文明のレベルの高さを知って,日本布教を志し,ポルトガル国王などの意向を無視して,独断で来日する。のちに,織田信長の信頼を得ることになるヴァリニャーノとともに,宣教師としてはトップレベルの人材で,彼らキリシタンが,日本文明に対応した布教ができるよう賢明な努力をしたことも,日本の近世化という点で,幸いしたといえるだろう。1592年,天草で,日本での布教手引書として,「ドチリナ・キリシタン」が刊行され,以後,さまざまな工夫をしていく一方,一度,信者になった不干斎ハビアンが棄教し,1605年に,これに反論する形で,キリシタンを排撃する書「妙貞問答」を刊行することにもなる。
天正期(1573~1592年)には,連年,1,2万名の新信者が増加,1587年に,豊臣秀吉が「伴天連追放令」を出して後も,勢いは落ちず,1590年代に最盛期を迎え,30数万人に達したものと推定される。当時の日本の全人口を2,700万人とすれば,1.3%ほどの信者がいたことになり,東日本への布教はなされていなかったので,西日本では,2%に達していただろう。維新後,明治15年のキリスト教信者は,わずか5,000人で,全人口の0.013%にしかならないのに,当時の社会にもたらした影響の大きかったことを思えば,キリシタン時代は,その100倍以上の勢力であって,如何に影響が大きかったか想像できよう。それ故に,激しい弾圧を招くことになるのである。
弾圧の時代,大名や武家層,そこにつながる特権階層や貿易商人らが,次々脱落するのに対し,一般庶民の信仰は根強く,禁教によって,それまでの社会のつながりが断ち切られ,かえって純粋なものになって行く。「ドチリナ・キリシタン」などによって,初めて文字を与えられ,文化思想に開眼させられ,それを自己のものにする能力を与えられ,つまり,キリシタンの教育が,自立した庶民層の形成,女性の解放に寄与し,近世を準備したといえるのである。戦国武将松永久秀の命で,ある訴訟事件を担当した結城忠正は,偶然,京都の町人ディエゴと接し,キリシタンは追放される旨,脅したところ,堂々と論じたてたことに驚嘆,入信まもない町人が,これほど確信に満ち,論理的に説明できるのなら,その教育は本当に優れたものと,パアデレの来訪を求め,自らキリシタンになったという。
キリシタンの話を横に置くと,おそらく宣教師らともにユダヤ系商人が多数来日,ハタ系につながる商人的な人たちの血を目覚めさせ,蒲生氏郷や後の三井高利など,いわゆる近江商人が勃興,伝来した鉄砲の製造管理を担わされた堺の商人は,のちの「死の商人」を先取りする茶人となって暗躍,吉田光由の「塵劫記」に始まり,のちに関孝和という天才を生む和算の勃興も,そういったユダヤ人の影響抜きには考えにくいと指摘する人さえいる。そもそも信長が安土の地を選んだのは,秦氏を祖とする伊賀・甲賀の忍者などとの連携を考えてのことだったともいわれる。
ハ:国際自由都市・堺の出現
信長が戦国時代を終わらせたところに,ポルトガル商人が登場,キリシタン以来,戦国武将の戦のレベルも知っているポルトガルは,日本を植民地化することは及びもつかず,世界の銀を支配することになって,繁栄を謳歌するようになり,その象徴が自由都市堺であった。
前話文献からの引用になるが,ポルトガル貿易が広まるとともに,博多などの貿易都市において町人意識の高まりがみられ,とくに,京に近い堺では,細川氏が貿易権を失うにつれて独立的機運が強まり,会合(えで)衆によって市政が運営され,戦国の争乱をよそに,自由都市的発展をしていった。宣教師らの書簡にも,堺は広大で人口多く商人が集住し,ヴェネチアの如く,元老たちによって治められており,日本国中,堺ほど安全なところは無く,戦の勝敗にかかわらず,この町に来れば,皆が平和に仲良く暮らし,礼節をもって交際していると記されるほであった。
「国際堺学を学ぶ人のために」の中で,中村博武が記すところによれば,堺商人の活躍は,応仁の乱によって,瀬戸内航路が閉鎖されたことから,南海航路に進出し,琉球貿易を通して鹿児島と密接につながり,進出してきたポルトガル商人と連携することで,繁栄を謳歌するようになる。ザビエルが京都に向かおうとして堺に至り,大内氏から紹介された豪商日比屋了桂の家に滞在,堺の街の繁栄を目の当たりにして,国王に,堺にポルトガル商館を設置するよう建言するも実現しなかったが,イエズス会士は,ポルトガル商人を介して,長崎・マカオ間の日明貿易に深く関与するようになり,堺の豪商も,大型船を使用して参加,平戸には,10隻近くが碇泊していたという。
堺の自治は,1419年,相国寺の子院の崇寿院領となっていた堺南荘の住民が,訴えを起こして認められ,1431年,住民自らが年貢を請け負う組織を形成したことが契機になり,町内での争いごとを禁ずることで,自治都市となり,畿内で迫害や動乱が起こるたび,宣教師らにとって,格好の避難場所になった。この平和主義の根源は,仏教寺院の集積によるもので,堺商人が,戦乱の波及を防ぐとともに,寺院を通じて,権力者とつながることで,貿易利権を守ろうとしたことによる。しかるに,反キリシタンの急先鋒たる法華宗が多かったため,堺には,キリシタンは,あまり広がらなかった。了桂の家の蔵の一つをミサのための集会場として,毎日密かに集まったという。
数は少なかったが,小西立佐・行長父子のような優れたキリシタンも登場,立佐は,1566年頃,ハンセン病者救護のための慈善病院を設立,50人ほど収容するほどになり,1625年まで存続した。のち,豊臣秀吉からは,生糸貿易のために重用されて,堺政所(奉行)に任じられ,行長は,瀬戸内航路監視の任にあたり,キリシタン大名になるのである。新たに来日したヴァリニャーノが織田信長の信頼を得たこともあって,1585年には,堺にも,教会堂が完成,住宅や病院が建設され,南蛮医学も伝わり,呉服屋安右衛門の島田清庵は,教会で医療を学び,医を生業にしたといわれる。これまた,庶民のレベルの高さを示しているだろう。
キリスト教の根源の一つ,霊魂不滅を説くことが最大の目的となったザビエルは,日本人の理性の高さを認め,学殖豊かなヌエスに,日本赴任を命じた。ヌエスは,プラトン,アリストテレスなどの蔵書を携えて来日,当代随一の医者で学者曲直瀬直三が,1584年に受洗したのは,霊魂不滅の問答の結果によるという(オシ系のところで触れたが,マナセという特異な姓は,おそらくユダヤ人の支族の名からきており,彼自身に,キリスト教の問答を受け入れる要素があったとも思われる)。堺でキリシタンになった人物には,僧侶,医師,武士など知識階級が多く,畿内全域でもそうであったことから,プラトン由来の魂の永遠論が,日本の知識人に説得力を発揮したことを示しているといえよう。
堺の製造業としては,絹織物,鉄砲鍛冶,金細工などが栄えており,前話で述べたように,1565年には,製造した鉄砲を用いて,小豆島の福田港で,ポルトガル船が,平戸・堺の商船隊と交戦している。職人のレベルも高く,キリシタンになった金細工師が制作した祭壇画は,宣教師自身が,ヨーロッパ本家のものより優れていると認めている。そして,有名な千利休による茶振舞が,富裕な町衆の間で流行,了桂の客人として招かれたアルメイダは,茶道具が宝石のように高価で取引されること以上に,振舞の様式の洗練ぶりに感嘆している。堺では,民間人による出版も盛んで,1528年に「医書大全」,1590年に「節用集」など,実用書が出版されている。
織田信長は,平氏の派手さと乱暴さの代表選手ではあるが,ロックリー・トーマス「信長と弥助」によれば,謁見の際,宣教師ヴァリニャーノが護衛のために連れてきた黒人奴隷を,その肌の黒さが本物だと分かった途端,人物の優れていることを見抜き,敬して接したどころか,弥吉という名を与え,自らの小姓にまでしてしまう海洋民族らしい開明的なところがあった。その弥吉は,本能寺の変で,信長の側にいながら,唯一殺害を免れた人物でもあったが,それは,清和源氏の嫡流を自認して周囲のものを見下していた明智光秀が,殺すに値しないもの,それどころか,動物のような存在とまでいっているのと対照的であり,ここにもなぜ,光秀が信長に謀叛を起こしたのかの理由が垣間見えるようである。一介の黒人が,一国を支配する者の側近になったと言うことで,世界史上,稀有な事件として,近年,各国の意識ある人たちにおいて,弥助は,シンボル的な存在になっている。
同書にはまた,マカオの開拓者で,日本ビジネスにも精力的に取り組んだランディロという人物が,ポルトガル王族の末裔と称してはいたが,実は,海賊船船長として貿易を営んでいたユダヤ人であったということ,それどころか,マカオの商人の大半が,隠れユダヤ人だったということ,つまり,ポルトガル商人の実質は,ユダヤ人が握っていたことが書かれており,堺の商人の主な取引先がマカオであったことから,堺を介して,ユダヤ人による日本人への影響があったことは,否定しようがないだろう。ルーツがユダヤ人である可能性の高い,近江の蒲生氏郷,三井らは,ユダヤ人と出会い,お互い分かっていなかったかもしれないが,触発された可能性があり,また,和算など江戸時代の文化につながって行く。家康の顧問,ウィリアム・アダムズ,ヤン=ヨーステンらの存在も,すでに,ヨーロッパトップの国々の人との交際になじんでいたからこそ,可能になったといえよう。
第2話:マツ系による国の奪還~露払いとしての豊臣秀吉
下克上によって,武士の間での上下が意味なくなった上,キリシタンの影響で,庶民が人権に目覚めたように,源平でなかった豊臣秀吉,徳川家康が,自らの力を再認識し,国家権力奪取に目覚めたとみることができる。秀吉が,全国統一を成し遂げたことで,日本人としての国民意識も芽生えたと考えられよう。
イ:究極の下克上・豊臣秀吉のルーツ
出自すら分からないような身分(河原乞食,非人説すらある)から,全国統一に至った豊臣秀吉こそ,究極の下克上であったといえるだろう。年譜を簡単に辿れば,18歳の時に,信長の草履取りになって以降,次々と,戦功や築城能力で累進し,近江長浜城主になってなお奮闘,1582年,46歳の時,備中高松城での毛利氏との決戦を目前に,信長暗殺の報に接する(本能寺の変)や,直ちに毛利氏と講和を結んで兵をかえし,山崎の戦で明智光秀を破るとともに,信長の後継を宣言,反対する宿老の柴田勝家をも滅ぼして,覇権を握るや,全国制覇にのり出す。外交的手段で家康をも臣従させる手腕を見せ,朝廷の権威をかりて,関白,太政大臣となり,まさに,身分制社会の頂点に立つに至り,堺の千利休・津田宗及らを茶頭に,北野大茶会を催すなどしながら,1590年,小田原の後北条氏を滅亡させて,全国統一を達成すると,かねてから服属を求めていた明国を討つため,2度にわたって朝鮮出兵にしたが苦戦に陥り,1598年に没したということになり,それぞれの事柄については,様々に解説されてきている。
ところが,その出自については,公式には,尾張国中村で,織田信秀に仕えた足軽木下弥右衛門の子に生まれたというが,それも養父であったというから,それまでの支配層とは全く別の民族であったと考えて良いだろう。唯一の手掛かりとなるのが,養父の木下姓ということになるが,この姓が,上鴨社氏人・下鴨社祠官膳部などに見られるということから,次節の家康のところで詳しく述べることを先取りしていえば,崇神東征で大和朝廷ができる際に,国譲りした,あのマツ系であった可能性が高い。
そもそも,秀吉は,猿のような風貌だったといい,国譲りする際に登場した長髄彦を思い起こさせ,大坂城という,それまでになかった広い低湿地帯の城と城下町は,かつての呉の地に似ており,家康の江戸城に引き継がれるのである。末盧国のところで述べたように,濃尾平野のいわゆる木曽三川が,呉の国の地同様,"江"と呼ばれるのをはじめ,岐阜あるいは"蘇"がつく中国南部に類似する地名が多く見られ,鵜飼はじめ極めて古い文化を有しているなど,マツ系の民の集積地にふさわしい。有力武将の輩出はじめ,日本史上重要な役割をし,関東・関西の中間に位置しながら,なぜ首都になれなかったのか,まさに,抑えられた民族マツ系の地であったからとさえ思えるのである。>末盧国
そして,紛争を禁止する惣無事令,正確な土地を保障する太閤検地,治安維持の根本になる刀狩り(一般人は武器を持たない,現代の鉄砲所持禁止にまでつながる),身分を保障する士農工商ほか,新たに登場した庶民(町民)に対応する,それまでになかった支配システムを創出し,これまた,家康は,それを引き継ぎ,具体的な施策にしただけともいえるのである。付け加えれば,戦に優れていたのは,春秋の呉と同時代の「孫子の兵法」を身につけていたと想像するのも一興である。
家康と何が違ったかといえば,松の字の入った姓でなかった,やはり,末盧国のところで述べたように,呉太白の子孫,すなわち王族でなく,支配されていた側と思われ,それが,松平の徳川家康にとって,潰す対象になったのだろう。にもかかわらず,マツ系であるゆえ,アマテラスに対抗するように,自ら神になることを目的とし,家康の東照宮とは比較にならないが,秀吉も豊国神社に祀られているのである。源氏であれば八幡神があるのはもちろん,平氏,藤原氏なども,自ら神になろうとはしないはずである。天皇家との関係でみれば,出自の低さ故か,その権威に頼ろうとしており,王族末裔だった家康との差も歴然とする。さらに,中国まで支配を夢見たのも,先祖が支配されていた側の末裔としては,当然の心情だったのかもしれない。
それらを別にしても,秀吉が一代で終わらざるを得なかったのは,実子ができなかったことであろう。正妻北政所に子が無く,側室らにも全くできなかったことから,秀吉はいわゆる男性の不妊症であったと考えられ,おそらく自ら出身の部落の男子を利用して,寵愛する淀殿に長男鶴松を誕生させるも夭折,同じ頃,片腕だった弟秀長が病死,実母大政所も死去して,心境が一変し,千利休を自刃させたともいう。そこで再び,やはり極秘に部落の男子を利用して秀頼が誕生すると,表向きはあくまでも実子であったことから,政権を支えてきた甥秀次との関係が不和となり,一族もろとも,切腹させられたが,その残酷さには,秀頼が実子でなかったことを隠すのが如何に大きなことであったのかも示しているのではないだろうか。
ロ:マツ系ならではの支配理念を打ち出した豊臣秀吉
前述のように,それまでの,源平という正統的な武家とは全く異なるマツ系の豊臣秀吉は,それら先輩の武家の支配はもちろん,それ以前の,クダラ系藤原氏とも異なる,全く新しい統治方式を打ち出し,その後を受けて,長い江戸時代を築いた同じマツ系の徳川家康の施策の多くが,秀吉の施策を受け継ぎ,さらに,徹底させたものになっているのである。
本能寺の変の翌年の1583年,豊臣秀吉は,大坂の築城を開始する。もともとこの地は,石山本願寺があった場所であったが,織田信長の安土城ですら,山上に築造され,広い城下町を意識したものでは無かったのに対し,単に,地の利が優れていただけでなく,低湿地帯とはいえ,平らで広い土地に,町人たちをも集まる城下町を整備して行こうとするもので,ルーツが低湿地帯を臨む呉の国の,マツ系ならではの発想で,着々と整備して行くが,城下町までを囲み込む惣構を築いたところで,1598年,秀吉は死去,徳川家康の支配下になって,ストップしてしまうだけでなく,大坂の陣によって,灰燼に帰してしまう。しかしながら,大坂城の発想は,同じマツ系の家康が,江戸の城下町整備の先行モデルになったことは,間違いないだろう。
関白となって国政を行うようになった秀吉は,1585年,全国各地の大名に,世の中の争いを無くすことを目的とする「惣無事令」を発した。法令の主な内容は,大名間の領土紛争,村同士の水論・山論を禁止することであったが,この政策に従わなかったことを大義名分に,関東の後北条氏を滅ぼすことになる。
全国統一を前にした秀吉は,1588年,海民の武装解除を目的に,海賊,水軍の首領に,海賊行為をしない旨の連判の誓紙を出させる「海賊停止令」を発する。倭寇を意味するバハンの禁止令ともいわれるように,織田信長時代に隆盛だった後期倭寇は,中国人主体であったとはいえ,日本の大名と関係して,その警固や経済的繁栄に貢献,全国統一をめざす秀吉にとっては,排除すべきものであったのである。それも,「豊臣政権体制の大名となるか,特定の大名の家臣団となるか,武装放棄して百姓となるか」いずれかを迫り,海での警固料を徴収する権利も禁止したため,倭寇,海賊,水軍は消滅するに至るのである。同年に出された「刀狩令」と同等の兵農分離策でもあり,海商を自らの政権下に組み込み,明朝との勘合貿易はじめ,海外貿易を完全に支配しようとするものでもある。そして,徳川家康が,関ヶ原の戦が終わるや,御朱印船を始めること,1609年に,個々の大名が勝手に貿易をしないようにする大船建造の禁を発令したことにつながるのである。
倭寇・水軍は,その活動の場を失い,その多くは,東南アジアの日本町で,その後のオランダ貿易にも関わり,陸に上がらざるを得なかった者が,おそらく博徒などになり,明治維新後のヤクザにもつながる,反社会的ながら,国家権力を行使する上で欠かせない存在になった。また,倭寇時代には,その取り締まりの過程で,一部は,朝鮮や中国の地にいつくようになったことから,現在もなお,大陸と裏でつながる,様々な犯行組織が存在することにもなるのである。
「海賊停止令」と同じ1588年に,「刀狩令」を発令,武士が,農民を完全に支配でき,反乱を未然に防止するため,農民たちが独自に隠し持っていた武器を接収したのであるが,江戸時代が,長く平和であったことに直結しているばかりか,近年になって,銃社会アメリカの悲惨な事件を見たり,聞いたりする時,日本が銃砲所持を禁止していることの良さ,そのルーツでもあることを思えば,如何に優れた施策であったか思い知る。
全国統一を達成した秀吉は,その翌年の1591年に,「身分統制令」を発令,その内容は,侍(若党),中間,小者ら武家奉公人が百姓・町人になること,百姓が耕地を放棄して商いや日雇いに従事すること,逃亡した奉公人をほかの武家が召抱えることなどを禁じたもので、,文禄・慶長の役を控えて武家奉公人と年貢を確保する意図があったとされている。これまた,江戸時代の士農工商の先取りともいわれるが,そのような社会全般の身分統制でなく,武家奉公人の身分統制を目的とした法令で,むしろ,江戸時代の奉公人制度に関する法令の先がけとされるようになった。とはいえ,家康が士農工商の制度を考える契機になったことは間違いないだろう。
織田信長時代から,奉公人木下藤吉郎(豊臣秀吉)は,検地の実務を担当しており,本能寺の変後,明智光秀を山崎で討つと,山崎周辺の寺社地から台帳を集め権利関係の確認を行うなど検地を本格化させていく。1591年に,太閤を名乗って以降,全国的に実施して行くのが,「太閤検地」で,その土地がどれだけの量の米を生産出来るかを,隅々まで綿密に調べて行く。同時に,生産量を示す単位を統一すべく,「石高制」を導入,米の量を計る秤の単位まで統一させたが,江戸時代が,年貢によって長期に存続する根本的な制度になるのである。
1592年関白豊臣秀次の名で出された「人掃い令」は,いわゆる戸籍調査の実施で,一村の人数や性別,職業を書類に明記する事を義務付けたものであり,これによって,士農工商の基礎が出来上がり,身分制度はさらに進化して,江戸時代が長く続くことになる。
なお,秀吉においては中途半端であった「バテレン追放令」は,徳川2代将軍秀次の時代に,とてつもなく強化され,3代将軍家光の時代には,鎖国に至るのであるが,貿易に関心の高かった秀吉においては,思いもよらないことであったろう。
ついでながら,下克上の典型とされ,一目置かれた信長にまで反抗して,自刃に至ったことで毀誉褒貶の大きい松永久秀(弾正)は,近年,事務・交渉能力が優れていたことで登場し,朝廷と関係を築くことで権力を握るようになったもので,信長への反抗も,本能寺の変の先駆ではないかと再評価されるようになってきたが,松永の姓からしてマツ系であり,出自が明らかではないという点からも,秀吉に先駆する,近世への露払い的な人物であったと考えられる。松永久秀は,美濃の斎藤道三の傘下にあったと言われるが,実は,道三の父で別名が松波と言われた人物についていたらしく,また,久秀が最後に本拠とした生駒の近くには,松尾山があり,日本最古の厄除け寺といわれる松尾寺があって,かつてのマツ系の本拠地であったと見られることなども,裏付けになろう。
ハ:東南アジアへ進出するも,帰国できなかった倭寇の末裔(南洋日本町)
後期倭寇の間に日本の利権が東南アジア方面に広がり始め,その終焉をもたらした,豊臣秀吉,徳川家康の御朱印船によって,本格的な展開が始まる。岩生成一「南洋日本町」によれば,ご朱印船以前の,1593年,秀吉による呂宋(ルソン)派遣に始まり,1604年に,家康によって,正式な御朱印船となって以降,1636年に鎖国となるまでの間,御朱印船360隻近く,その他も15隻あって,ポルトガルから利権を奪うとともに,南洋移住が進み,フィリピンのマニラ東南郊に2か所(ディラオとサン・ミゲル),交趾(コーチすなわちハノイで,後のベトナム)の現在のダナンに2か所(フェフォ,ツーラン),柬埔寨(カンボジヤ)のピニャールとプノンペン,暹羅(シャム)のアユタヤには独立した日本町が形成された。
最大であった交趾の2か所には,最盛期に,それぞれ数十軒の日本人の家があったといい,町長役であった林喜右衛門や角屋七郎兵衛は交趾の名士でもあった。柬埔寨では,新興ながら,鎖国後,唯一の交易相手になったオランダ人との共存のような状態で,最盛期には3~400人の日本人がいたと考えられる。近年もなお,東南アジアで,唯一カンボジヤと安定的な関係なのは,この時からと考えられ,第1章で述べたように,日本にも,クメール人の血が入っていることも大きいであろう。暹羅(シャム)のアユタヤは,最盛期に600人で,日本町として最大であった。
そのアユタヤは,かの山田長政が渡航した地でもあるので,少し立ち入ってみる。山田長政は,駿府の商人の家に育っていたが,1607年,17歳の時,徳川家康が新築なった駿府城に来て,海外貿易に従事する豪商らが集結し,町が俄かに活気づくにも拘らず,放浪に出,沼津藩主大久保忠佐の駕籠かきになるが,1612年,沼津藩主が死去すると,駿府の豪商滝佐右衛門・太田治右衛門の船で堺から長崎に渡り,長崎から台湾を経てシャムに入る。1620年,30歳で,アユタヤ日本町の頭領となる。翌年には,シャム国王の使者が江戸城で秀忠に謁見して,以後,日本とシャムが親密になり,オランダを次第に駆逐するなか,日本人部隊を率いてスペイン艦隊を破り,オーククンに任ぜられる。翌年,日本町が全焼するも,再建し,翌々年には,オークルオングに昇進。再び,スペイン艦隊を破り,アユタヤ王朝防衛に貢献して,1626年,36歳にして,オークプラ・セーナピモックに昇進して絶頂期となり(日本人傭兵700人前後を率い,町の人口は3000人余りだったという),1629年,酒井忠世に書状を出すとともに,長政の船が長崎に到着し,シャムの使節が将軍家光に謁見。酒井忠世より長政に返事が出され,ついに最高位のオークヤー・セーナピモックに昇進するが,直後に,王が暗殺されたため,アユタヤを脱出,ナコンシータマラートを平定して,リゴール王になるものの,翌年,毒殺されてしまう。
山田長政は,鎖国前に死去してしまったが,その他の,東南アジアの日本人のほとんどは,鎖国とともに,現地に取り残されたのであり,東南アジア諸国のうち,とくに日本人の多かった4カ国との関係が,現在でも良好なのは,この人たちのお蔭であろう。
第3話:徳川家康が覇権を握り,朝廷をも超える全国支配を確立(崇神東征時の国譲りからの奪還)
イ:マツ系の真打(呉太白の末裔)の徳川家康
豊臣秀吉軍侵攻による朝鮮との敵対関係は,秀吉の死後,1600年の関ヶ原の戦を制して1603年に幕府を開いた徳川家康の登場によって修復され,朝鮮通信使まで往来する友好的関係になるが,なぜこんなにすぐに関係を修復できたのか謎であり,それ以上に,以後,1868年の明治維新まで265年平和が保たれ,鎖国までしながら,江戸の人口が世界一になっただけでなく,当時の世界各国を凌駕するようなハイレベルの文化を実現するなど,実際,欧米の歴史家から,パックス・トクガワーナと呼ばれ,オスマン帝国,清帝国に並ぶ本格的な帝国であったさえいわれるほどになったのはなぜなのか,という途轍もない謎を解明するキーは,前項で述べたように,徳川家康こそ,マツ系の支配者の呉太白の末裔で,徳川時代はその復活であったということなのである。してみれば,豊臣秀吉は,まさに,その露払いの役であったということになろう。
まず言えるのは,江戸時代は,一面,平安時代に類似するクダラ的な時代であり,家康が自称する通りの清和源氏の出身ならば,シラギ的な時代となるはずなのだ。彼のルーツは良く知られているように松平氏すなわちマツ系で,そのマツ系が伊勢の松阪から渥美半島を経て浜松に至る途中の三河国加茂郡松平郷に由来するということなので,末盧国のところで述べたように,呉太伯の子孫であった可能性が高いのである。家康にはまた,富士講行者の長谷川角行と密かに親交していた逸話があるが,その角行は,名前に角の字を入れているように,役小角の霊告によって行者になったといわれ,その役小角は,持統天皇のところで述べたように,マツ系の本拠地葛城の賀茂氏の出であったということなので,加茂郡は,応神朝秦氏が,マツ系を特別に処すべく,松尾大社と一体のものとして創建した上賀茂,下鴨神社の領地であったことを示している。賀茂神社は葵祭りで有名であるが,徳川将軍が三つ葵の御紋を使っていたのだから疑いようもなく,天皇家とは特異な関係を有していたということにもなろう。末盧国のところで,中国でも倭人を"呉の太伯の子孫"とする説があることを述べたが,徳川家康が重用した儒学者林羅山がこの話を支持していたことも裏付けになるだろう。つまり,徳川家康が長期にわたって安定的に続くような幕府の仕組みを創り得たのも,呉の国の歴史に学んだ可能性が高いということである。
さらに付け加えれば,家紋の,葵は「アフヒ」で日向と同様,太陽に逢う意とされ,葵科でない菊科のヒマワリも漢字で向日葵と表記されるなど,いわば天照大神の代用になっているようである。これらことを本当だと思わせるのは,家康自身が神になりたがっていたことで,歴代天皇で神がつくのは全て王朝の開祖であることと関係し,東照宮に照の文字が入っているのは,天照大神との繋がりを意識していると考えて当然だろう。ついでながら,上賀茂,下鴨神社と一体とされる松尾大社は,その名が示すように,マツ系のために創られた神社であるが,その社領は,徳川将軍の朱印状によって許されていて,社職の最高位の正神主に,その差配が任されたということなので,徳川氏自身が,マツ系であることを認めているのである。>松尾大社
良く知られているエピソードで,家康は長篠の戦に出た時,恐怖に震え,大便を漏らしてしまったことを自らの戒めにしていが,とても新羅的武将の姿とはいえない。上野国新田氏の支流で得川(エガワ・現在の太田市)の出であるとして,清和源氏の出身と偽ったのは,征夷大将軍の資格を得るために必要だったからで,徳川姓が得川を読み替えたものと説明できたからだろう。しかもルーツたる得川氏は時宗の僧であったというから,時宗が河原乞食など,最も下層の人たちに対応した宗教であることからも,豊臣秀吉にも重なる話で,国譲りしたマツ系との関係が裏付けられるだろう。そして,末盧国そのものが,朝鮮半島で百済領域になるところと繋がっていて,百済建国後も,マツ系の末裔葛城氏以来関係が深く,秀吉が朝鮮を蹂躙して間もないのに,再び友好関係を結べたのも何らかのルートがあったとしか考えられないのである。江戸幕府は,クダラ系政権というより,マツ系政権であったというのが結論になろう。文化面でも,平安時代は文学,室町時代は庭園がピークとすれば,江戸時代は絵画がピークになるが,そのルーツを辿れば,室町時代の水墨画,さらにいえば中国江南の文化につながるのである。
秀吉同様,自ら神になることを求め,東照宮がつくられる。源平交代説から,平氏信長の次ということで源氏を名乗ったが,本当に源氏の出であるとすれば,八幡が神様であり,自らが神になろうとすることはない。菅原道真を代表に祟りを怖れて神にするか,善政や治水事業などで恩恵を受けた人たちが,してくれた人を祀るか,明治維新後の軍神思想など,色々あるが,自ら求めて神になろうとするのは異例であり,東照宮はまた,その規模,華麗さにおいて際立ったものである。
家康が祀られた日光は,820年に空海がこの地を訪れた際,二荒山(ふたらさん=語源は補陀洛)の「二荒」を「にこう」と音読みし,「日光」の字を当てたという,アマテラスそのものを表す畏るべきものなのであるが,西すなわち京都に対して,東は自らが照らしているのだという強い自覚を示すとともに,マツ系の最終的拠り所の諏訪大社に対置(諏訪湖に対する中禅寺湖)させたものと思われる。徳川家康と日光の関係についてさらにつめてみると,家康は江戸の開発を円滑にできるようにするため,現在の江戸川を河口としていた利根川が氾濫を繰り返していたのを防ぐべく,現在の関宿あたりで利根川を分流させて,ナカ系に対応する別の水系であった鬼怒川につなげて,現在の銚子の方に注ぐようにしたのであるが(水運で野田が醤油を中心に発展する契機にもなった),その結果,鬼怒川水系最上流部に当たる日光の神様が,江戸すなわち徳川家の守護神になったということでもあるようだ。>新・上州遷都論
ところで,なぜ日光の地が選ばれたかということも,地名そのものが太陽であるからといえるが,さらに,なぜ特別の地になったのか考えてみると,海洋民族ナカ系に案内されて,オシ系が全国に展開した際,押上から利根川(荒川も)を遡上して忍(オシ)の地に王国をつくり(ついでながら,家康は忍藩重視していて,"知恵伊豆"こと松平信綱を配置した),さらに支流の鬼怒川を遡上したところで,華厳の滝に遭遇,その姿が東征した崇神の上陸地熊野の神々しい目印那智の滝と類似していたことから,特別の地と意識されたと考えられる。そして,日光の地名は,前述したように,ユダヤ系の秦氏出身の空海が名付けたということにも鍵があろう。
話は別になるが,徳川家康がイギリス人ウィリアム・アダムズを重用したことも,ユダヤ人レベルの話で通ずる部分があり,明治維新時のグラバーに近い役割であったと考えられる。すでに触れたように,三井財閥はその氏神が蚕の社ということで,秦氏に直結しているが,このことが,江戸時代に三井が飛躍した大きな理由であるような気さえしてくるのである。
網野義彦・宮田登・上野千鶴子「日本王権論」によると,江戸幕府は,天皇の賀茂への行幸の復活は認めるものの,禊だけはやらせなかったといい,今までの話からいえば当然であるが,本書はじめ,(世界も含めて)多くの歴史研究において,「なぜ,徳川幕府時代になってもなお,天皇家の存在を必要としたのか」「なぜ,明治天皇がすんなりと徳川将軍の江戸城にはいり,そのまま皇居になったのか」などが問題になっている理由も明らかなのではないかと思われる。維新時の江戸城の無血開城は,まさに,崇神東征時の国譲りの再現であったのだ。
最近,ふるさと納税のことで,泉佐野市と政府との間の戦いが話題になったが,市長の苗字が千代松であるばかりでなく,泉佐野とその周辺には松のつく苗字が多いことからも(松井知事,松浪健太・・・・),この辺りはマツ系の拠点ようである。泉佐野が,江戸時代に天領であったのは,マツ系である徳川氏にとって大事な場所だったということ,それ故,維新後の政府に反抗的なことが判明し,とくに,安倍政権が明治維新の中核の長州人であることで一層強くなっているのだろう。さらに,佐野(サノ)が神武天皇を表すことはよく知られているが,崇神東征の際,ここで上陸しようとして,長髄彦の一族に抵抗され,熊野の方に廻ったということなので,すでに述べたように,長髄彦もマツ系であることなど,泉佐野から,さまざまな疑問が氷解していくようにみえる。
ロ:マツ系ならではの統治のしかた(幕藩体制等)で,超長期政権が実現する
江戸時代の日本は,小さいながらも,同時代の清やオスマンのように,一つの帝国であったといわれ,独特の幕藩体制で,戦を失った武家が支配し,いわゆる町人が大衆文化を先駆,世界的にも稀有な鎖国下の繁栄を現出したのであるが,もし,前項で示したように,徳川がマツ系であったからとすれば,一層,納得いくものになろう。そこで,たまたま発見した二つの論文によって,考察してみよう。
第一の論文は,京都大学の吉本道雅による「中国先秦史の研究」で,その要旨によると,まず,呉のあった春秋時代,諸侯国が都城を強化すべく軍役負担者を集住させ,この都城が"國"と称されるようになり,春秋的な"國人"も成立したといい,そのまま,幕藩体制における城下町をイメージさせる。ついで,春秋時代の"國人"には,恩恵授受を媒介とする私的な人的結合関係がみられ,それまでの,個々の利害にもとづく単純な君臣関係でなく,「道」という客観的規範にもとづく新しい君臣関係になったといい,これまた,幕府と藩主,各藩主とその家臣の関係に,そのまま当てはまるように見える。さらに,春秋時代の国制を特徴づけている「世族支配体制」について,複数の世族が,「卿」という地位を独占して世襲し,それが,諸侯国の統治機構として維持され,覇者体制と相互補完的に政治社会秩序を構成したが,その覇者体制が弛緩すると,国君が世族を打倒して"国君専権"を樹立することもあり,また,国君専権を安定的に維持するため,統治機構が全面的に官僚制によって編成されていったといい,やはり,幕藩体制そのものを見ている感じである。
なお,本論文では,呉について,わざわざ一章「系譜の分析」をたてて,呉が春秋諸国のなかでは,辺境にあって,もともと長江流域で最強であった楚の分族であることを主張していたが,楚と対抗して中原と交流するようになって,周の分族太伯の後裔を自称するようになったという。つまり,マツ系は,彼らが主張する呉太伯その人の末裔ではないことになるが,日本における諸家系,源平のところでも述べたように,それら氏族が力量を発揮するには,どうしても貴種性が必要で,それが,臣籍降下と結びついて,桓武平氏,清和源氏などになり,現在でも,ふつうには,桓武平氏の祖は高望王,清和源氏の祖は経基王とされているのと同じことであろう。
もう一つは,国際武道大学の林伯原・周佩芳による「古代中国における武士及び武士階層に関する研究~日中比較の視点を含めて~」で,春秋戦国時代は,文武がともに重視され,どちらを軽視しても政治を円滑に運用することができないと強く認識されていた。とくに,孔子の弟子で侍衛であった子路ほか,門下の侍が,孔子の教え「礼,楽,射,御,書,数」を良く守って行動したのをはじめ,孔子の影響が強かったことを指摘している。また,司馬遷の祖先が,代々剣術を教えることを職業としていたというは,戦を失った武士の生き方のモデルになったであろう。いずれにしても,武士階層は文士階層に対して,有力な社会階層であった,つまり,武士が支配する社会は必ずしも否定されていなかったらしい。
春秋戦国時代を終わらせた秦の始皇帝は,中央専制支配を強めるため,民間の武器を没収・焼却しただけでなく,以後,その所有や武芸の訓練も禁止,そして,漢の武帝が,国家統一の体制に理論的な根拠を与える指導理念を確立するため,大臣董仲舒の策を用いて,儒学を官学とし,その他の諸子百家の学派すべてを排斥するに至る。マツ系の出で,その後の中国の歴史も知っている徳川家康が,官学として,朱子学を採用するようになったことも当然であったといえよう。
ハ:世界的にも特異な鎖国下の繁栄~西欧に先駆けて大衆化~パックス・トクガワーナ
まず,織田信長のお蔭で,既成の仏教が叩き潰され,庶民は,坊さんのくだらない説教を恭しく聴く必要がなくなり,同じく,信長のおかげで,楽市楽座など,自由に商売ができるようになったこと,次に,下克上を目の当たりにして,自らの生まれにかかわらず,道が開かれる可能性のあることを知ったところに,キリシタンのお蔭で自意識に目覚め,キリシタンとともに来日したユダヤ人はじめ,様々な人たちに,学問や仕事について触発されたところに,徳川家康のお蔭で,ついに戦のない世の中が訪れたのである。江戸時代の日本が,前述のように,一つの帝国で,パックス・トクガワーナといわれるのは,身分を逸脱さえしなければ,ほとんど自由であったことである。その点,ヨーロッパがなお,キリスト教の強い支配下にあったのとは,対照的であった。
当時,すでに,世界一識字率が高かったといわれる状況において,僧侶や武士には,それなりに教養等を身につけた人たちがいたのはもちろんで,仕事が無くなって,生活のために稼がざるを得なくなった彼らにとって,自意識に目覚めた庶民(町人ばかりか農民まで)を相手にすることが早道なのは当然であっただろう。というわけで,鎖国下にありながら,ヨーロッパをすら先行するような文化が醸成されて行くのである。そこで,以下に,江戸の初期から,幕末(シーボルト以前)にかけて,どのような人物によって,どのように展開していったのかを,簡単に,辿ってみよう。すでに,権力者たる武将らに取り入る術を身につけていた一部町人らは,いわゆる豪商になるが,その後は,その他の町人も含めて,まさに資本主義を先行するような方法を次々と開発していったことも忘れてはならない。
マツ系の観点から補足しておくと,首都江戸は,中国の(春秋だけでなく三国時代の)呉の地に,のち(日本の古墳時代)に花開いた晋の首都健康について,大室幹雄が著した「園林都市~中世中国の世界像」の目次にある,「自然を愛して開いた都市」「ランドマークの文化と自然」「牛車とおしゃべり文化」「園芸的世界」等々,まさに,園林都市そのものを再現するような都市でもあったといえる。
その嚆矢であるとともに,幕末まで衰えることなく続いたのが和算,西欧でいえば数学であり,脳の構造上,基本になるものであることは言うを待たず,算盤も普及させて,江戸時代の日本人の基礎をつくったものともいえるので,少し詳しく記す。
その和算の祖吉田光由は,佐藤健一「江戸のミリオンセラー'塵劫記'の魅力」などによれば,豊臣秀吉が死去した1598年に,豪商角倉了以の分家の医師の子に生まれ,数学に興味を持ち,「割算書」の著者毛利重能に学ぶもすぐに理解してしまい,吉田流算術元祖の角倉了以につき,来日まもないイタリア人宣教師で数学に優れるスピノラにも接触した可能性がある。了以の死去後は,子の素庵について,吉田流算術を伝授される。1622年の元和の大殉教で,スピノラは殉教,毛利重能の消息も不明,同年,数学書「諸勘分物」を刊行した百川治兵衛も佐渡に逃避行していることから,数学の知識の多くが,キリシタンによってもたらされたことが推定できると同時に,豪商も単なる商人でなく,数学を身につけていたことも分かる。素庵から蔵書全てを譲られると,それらを手本に,1627年,29歳の時,「塵劫記」を刊行。内容はもちろん,素庵の親友本阿弥光悦の挿絵装幀を得,普及し始めた算盤のマニュアルの役割もあって,大ヒット,その後も追加,編纂し直し,多色刷りと刊行し続け,1634年刊行の普及版「新編塵劫記」は,江戸時代を通してベストセラーとなる。その後転変とするうち,同じ毛利門下だった今村知商が和算書を刊行したのに対抗,1641年,43歳の時,根本的に書直した「新編塵劫記」を,末尾に12の遺題をつけて刊行,1653年,55歳の時,この遺題に初めて挑戦した榎並和澄が「参両録」を書いて,答術を発表するとともに,自ら新たに8つの遺題を提出,以後,遺題継承が流行,和算が大いに発達,幕末まで続くのである。キリシタン取調べが一段と厳しくなるなか,61歳で,筆を断ち,74歳で,没したが,角倉一族の墓所に埋葬できず,弟子渡辺藤兵衛により密かに豊後国西国東郡夷に移されたという。
そして,松尾芭蕉や井原西鶴といったほぼ同年齢の天才と同じ元禄時代に,和算の天才関孝和が登場する。1642年に誕生し,独学で「塵劫記」を読んで,高次方程式の解法「天元術」をマスターするとともに,次々と遺題の答えを出し,「古今算法記」の15問全部を一気に解いて,1674年,32歳の時,「発微算法」と題して発表,算盤を使わずに手計算できる「傍書法」を確立して,和算を飛躍的に発展させる。ライプニッツが行列式を考案したのより10年も前(1683年)に,自著のなかで,同じ解法を示し,ベルヌーイ数についても,その1年前に,算木で説明するため見かけは全く異なるものの,内容は正確に対応するもの発表するほどであった。関流の和算の祖になるものの,あまりに難解だったところ,20歳ほど年下の愛弟子建部賢弘が,1685年に,「発微算法」の解説書「発微算法演段諺解」を刊行して,多くの人が理解できるようにしただけでなく,関が,円周率について,多角形を細かくしていく方式で,小数点以下11桁まで導いたのに対し,無限級数展開を世界に先駆けて行い,一気に,41桁まで導いたほどのレベルであった。いずれにしても,天才においては,一般人との間をつなぐ人物の存在が,社会全体に普及させるのに不可欠であるが,そういう役割をする人物もまたいたことが,文化の厚みを示しているといえるだろう。
その他については,いくつか拾って,簡単に記すこととする。
官学の朱子学に対し,民間では,陽明学が学ばれるようになるが,その嚆矢も,開府まもない頃の中江藤樹で,単なる知識でなく,行動を伴うことにこそ意味があるする,陽明学の根本を示す"知行合一"の思想は,民間思想のベースとなる。陽明学ではないが,孔子・孟子など直接原典にあたり字句の忠実な解釈から研究すべきとして,古文辞学を唱えた荻生徂徠(1666~1728)は,中野剛志のいうとおり,日本史上,最もプラグマティックであった天才的思想家で,世が世ならば,同時代のイギリスの天才的思想家ジョン・ロック(1632~1704)あたりと,知能指数の高さを争ったと思われる。民間の学は,陽明学をベースにしていたことから,救荒作物の甘藷でばかり知られる青木昆陽が,徳川吉宗に召されて後は,蘭学の開祖のような役割をすると,有名な杉田玄白ほかを契機に,蘭学は,抵抗なく本格化して行き,幕末にかけて,宇田川家,桂川家など,世襲するような学者一族を生み出し,シーボルトを経て,欧米の近代科学が容易に受け入れられる素地をつくることになる。吉宗の時代には,官学の「湯島聖堂」に対抗するように,大坂で,幕府公認の学校「懐徳堂」が設立されたことも忘れてはならない。
天文学においては,幕末近くになっての在野の大学者麻田剛立の存在が大きく,弟子で天文方になった高橋至時が,かの伊能忠敬の師になったのは良く知られている。その麻田剛立と親交のあったのが,孤高の大哲学者三浦梅園である。科学思想家・啓蒙家としては,長崎の商家出の西川如見が,1695年,47歳の時に,日本で最初の世界商業地理書というべき「華夷通商考」を,1708年,60歳の時には,その増補版を刊行して,海外事情の普及に貢献,鎖国下で合理的認識を先駆し,富永仲基,海保青陵,山片蟠桃など天才的な人物も含めて,幕末にかけて,いわゆる経世家を多数輩出,これまた,文明開化を準備していたといえよう。全く別に,江戸の身分制度を根本から否定する独創的な思想家安東昌益,女性解放思想の先駆只野真葛も忘れることはできない。農業については,武家出身ながら,浪人となって,近畿・中国・九州を巡遊して農業調査し,自ら開墾して農業生活,その後も,諸国を巡遊して老農の意見を徴し,貝原益軒とも親交するようになって影響を受けながら,生涯をかけて著述に専念し,1696年,73歳,日本初の体系的農書「農業全書」を著して,まもなく没した宮崎安貞に始まり,幕末には,農業組合を先駆した大原幽学,そして有名な二宮尊徳に至る。幕末にかけて,国友藤兵衛,久米通賢,工楽松右衛門ら,すぐれた技術家が輩出,極めつけは,明治維新まで生きて,東芝の祖になった田中久重で,まさに,近代工業にそのまま移行するのである。
落語は,僧侶の安楽庵策伝が,1628年に,噺の種になる「醒睡笑」を著したのに始まり,1681年,鹿野武左衛門が座敷で,1684年に,露五郎兵衛が,京の祇園・北野天満宮・四条河原などの盛り場や神社仏閣の祭礼開帳の場所で,群集を前に演じたことで流行するが,寛政の改革で禁止されたのを,1816年に,烏亭焉馬(初代)が再興,幕末の桂文治以降,現代につながる落語家の輩出になって行く。僧侶から転じたものとして,囲碁の本因坊算砂,美術の本阿弥光悦が,同じく開府まもなくの人物であり,光悦は俵屋宗達を見出して,のちの尾形光琳につながる絵画の分野を開く。伊丹城主荒木村重の末子に生まれるも,父が,織田信長に反抗したため,落ち延びることになった岩佐又兵衛は,1615年には,越前の藩主松平忠直に買われて恩顧を受けて,次々,傑作を描いて,浮世絵の祖とされるが,いわゆる,浮世絵の様式になるのは,1660年に,初めての挿絵画家として登場する菱川師宣からで,1765年に,鈴木春信が本格的カラーの錦絵を描き,喜多川歌麿など,なお美人画,役者絵が中心だったものが,幕末に,葛飾北斎という天才を産むに至る。北斎より前の,伊藤若冲や,与謝蕪村の登場する天明期の画家は,浮世絵ようなローカルなものを超え,世界の画家と並べても,一流といえるような作品を次々と創作している。
戦を失った武士が転じた先の典型は剣術指南であろう。その皮切りになったのは,薩摩の島津氏に仕えていた東郷重位で,27歳の時,京都で,もと佐竹家臣で天寧寺の僧善吉から天真正自顕流を学び,以後,生涯にわたって不敗。戦の無くなった開府まもなく,初代薩摩藩主島津家久に知られ,1604年,43歳の時,家久師範の体捨流東新之丞と立合わされ,一瞬にして勝利し,逆に師に迎えられ,薩摩示現流創始者になった。61歳の時,家久の参勤交代に従って江戸に出た際,柳生流の旗本二人から試合を申し込まれ,あっという間に勝利,最後の立合いになった。以後,伝書の編纂に取り組み,82歳にして,没した。最後の相手,あまりにも有名な柳生流の,柳生宗矩は,1601年に,徳川家師範,1623年に将軍になった家光の師範になり,禅僧沢庵とも親交があって,67歳の頃,沢庵から「不動智神妙録」を書き与えられて,柳生新陰流兵法の理論体系の完成,家光,沢庵,宗矩3者の身分を超えた人間関係は,江戸幕藩体制の完成に大きな力となった。70歳の時,子の十兵衛に授けた「兵法家伝書」は,近世剣術界に大きな影響を与える。続いて登場した,伝説の宮本武蔵が,1645年,61歳に死去する直前に,究極の書「五輪書」を書き上げ,そして,200年後の幕末に,千葉周作,斎藤弥九郎の道場が,維新の志士を鍛えることになるのである。
武士から転じて,新たな文化を拓いたのが,鈴木正三で,大坂の陣が終わるとまもなく,禅僧になり,1624年,45歳の時には,庶民へも説法し始め,53歳の頃の「二人比丘尼」はじめ仏教説話で,仮名草子を先駆,続いて,僧侶浅井了意が,1657年,45歳の頃から,仮名草子を書き始め,70歳頃まで書き続けて,質量ともに最大の作家となった。それに代わるように,1682年,浮世草子「好色一代男」で登場したのが,天才作家井原西鶴で,1692年の「世間胸算用」まで,傑作を書き続けて,翌年,没したが,その年には,天才俳人松尾芭蕉が「奥の細道」を完成させて,翌年に没しただけでなく,先述したように,天才数学者関孝和,さらには,天才言語学者契沖,少し後になるが,天才ミュ-ジカル作家近松門左衛門と,かの犬将軍徳川綱吉のもと,元禄時代はまさに,天才の時代であった。念のため,芭蕉の登場も,開府まもない頃の,松永貞徳,西山宗因による,俳句の確立があってのことである。天才とはいえずとも,同時代の貝原益軒は,綱吉が将軍になった年,50歳頃から,死の直前の有名な「養生訓」まで,30年以上にわたって,啓蒙書を書き続けた,今でいえば,売れっ子評論家であった。江戸時代後半になると,西沢一風,江島(屋)其磧など,自ら著作しながら,印刷出版する者が現れ,山東京伝に続いて,出版だけでなく,メディア支配を先駆するような蔦屋重三郎が登場する一方,十返舎一九のような,近代につながる職業作家も登場する。
現在においても,日本を代表する財閥系企業の住友の祖の一人とされる蘇我理右衛門(あの蘇我氏の末裔か)は,1590年,18歳の時,豊臣秀吉が大仏をつくるというので,多くの銅吹き屋の集まる京都で,{泉屋}と号する吹屋を開業,一家あげて熱心な涅槃宗門徒だったことから,門兄住友政友の姉を妻に迎え,友以が誕生,友以が住友政友の養子となり,1702年,別子銅山の永代稼行権を獲得し,幕府の御用銅増産のため,多大の援助を受けて,住友家の発展はゆるぎないものにしたことで,政友とともに,住友の祖になった。住友に並ぶ三井もまた,伊勢の豪商の娘で,織田信長に滅ぼされた近江の武士三井高安(ハタ系といわれる)の長男で,松阪に新居を構えた高俊に嫁いだ三井殊法が,もともと,聡明で優れた商才を持ち,武家の出で商売に疎い夫に替わって,家業の質屋と酒・味噌の商いを順調に伸ばし,4男それぞれには商売をさせ,4女は次々と有力な商家に嫁がせ,夫の死後,1635年,末子の高利を江戸にやり,その高利が,1652年に金融業を始め,1673年,江戸および京都に店を開き呉服業(越後屋)を創業,店前売りの新商法を始めて大ヒットさせた翌年に没し,三井の祖になった高利の母として,今なお,尊崇されている。少し前までは,財閥の一つとして有名だった鴻池も,武士の子に生まれ,父が討たれたことから,商売に関わるようになった山中新六が,1598年,28歳の時,四斗入の酒樽二個を一駄として江戸送り,他に先駆けて大量輸送を始め,44歳の時に,家憲「子孫制詞条目」を定め,多くの男子それぞれに商売をさせるとともに,1619年,大坂に鴻池屋を開き,以後,事業を拡大させていくことに始まる。この他,開府当初には,和算のところで登場した角倉了以・素庵,淀屋个庵,茶屋四郎次郎3代,河村瑞賢など,名だたる豪商が多く登場している。
以上の他,賀川玄悦,山脇東洋,吉益東洞,華岡青洲,浅田宗伯など,医者の鑑とでもいえそうな人や,浄瑠璃の竹本義太夫,歌舞伎の市川團十郎家など,まさに,現代のアメリカのブロードウェイのような娯楽の提供者であったし,断片的ながら,文楽や川柳のようなユニークな文化を生み出した人など,まだまだいくらでも思いついてくるが,この辺にしておこう。
この章TOPへ
ページTOPへ
第9論:長州支配で,クダラ的藤原政治が復活する~近現代
武家政治がいかに定着していたかは,明治維新も,武家が主導したことから明らかであるが,その主体は,ハタ系をルーツとする島津氏の薩摩と,大内氏以来のクダラ系を主体とする長州との連携であり,それまで続いてきた北朝すなわちシラギ系の孝明天皇に替わって,南朝すなわちクダラ系の明治天皇を立てることで実現する。足利氏は,後醍醐天皇に謀叛したとして嫌われ者になり,関係者は肩身の狭い思いをすることになる。マツ系の徳川氏から,オシ系の天皇への大政奉還,無血開城は,古代の国譲りの再現であったように見える。天皇側近のクダラ系藤原氏が巻き返しはじめたことや,島津氏がハタ系であったことから,イギリスとの連携,さらにはフリーメーソンのグラバーに繋がって,維新への強力な援護射撃を受けることができたのも大きい要因だっただろう。
前論同様,第二講「時代循環のパターン」も参照してもらいたい。>時代循環のパターン
第1話:権威までも失った天皇家の長い抵抗が,明治維新につながる
世界的にも不思議がられているように,無くしてしまっても良かったと思える天皇家を存続させたのは,秦氏により,天皇家と一体化される仕組みがつくられていたからだろう(松尾大社,上賀茂・下鴨神社,葵祭)。天皇の権威は利用されるだけになった。
イ:江戸開府当初の,後陽成天皇,後水尾天皇と東福門院
桓武平氏出の織田信長は,上洛することが支配の源泉であること,すなわち,天皇の権威を十分に認識しており,マツ系とはいえ下層の出であった豊臣秀吉も,天下を掌握するためには,天皇の権威を借りざるを得なかったが,呉太白の末裔を自認する徳川家康においては,天皇すら,支配下に置くようになり,徳川将軍が,家臣らを掌握するための官位の出どころとして,利用するだけになってしまったといえる。
戦国時代の動乱で,朝廷の財政は逼迫し権威も地に落ちかけていたことから,織田信長は,時の正親町天皇を保護するという大義名分によって京都を制圧すると,様々な政策や自身の援助によって財政を回復させるとともに,敵対する勢力だった朝倉義景,足利義昭,石山本願寺との戦いにおける講和に,正親町天皇の勅命を利用,その間に,信長に,貴重な蘭奢待の切り取りを許可したことが,今でも話題になるといった関係であった。
豊臣秀吉も,正親町天皇に御料地や黄金を献上して,関白の座を得,後を継いだ後陽成天皇には,信長に追放されていた将軍足利義昭を伴って参内,義昭が,征夷大将軍職を朝廷に返上したことで,室町幕府は正式に滅亡したのである。秀吉の演出した天皇の聚楽第行幸は,自らが天下を支配したことを演出したもので,朝鮮出兵は,明を征服した暁には後陽成天皇を明の皇帝として北京に遷すという誇大妄想から来ており,さすがに,秀吉に対して"無体な所業"であると諭すなど,天皇の権威は高まった。
1600年に,徳川家康が政権を握るに至って,状況は一変,自らの後継について干渉され,武家伝奏が設置されて,天皇が監視されるという事態になり,直後に,相次いで発覚した宮中女官の密通事件(猪熊事件)に激怒するも,幕府の措置は手ぬるいものに終って不満を抱き,以後,孤独の中で暮らし,やがて退位するに至ったのである。この間,家康は政仁親王(後水尾天皇)への徳川秀忠の娘和子(東福門院)の入内を求められ,先例のないこととして拒否するも,圧力に屈して,応じることになり,以後,父子も不和になった。
後水尾天皇は,1611年,15歳で,後陽成天皇のあとをうけて即位したが,将軍徳川秀忠から禁中並公家諸法度や,所司代,付武家などを通して種々の干渉が加えられるなか,1620年,秀忠の娘和子が女御となり,天皇の母中和門院と対面,その配慮で,和子を受入れ,親密になって行く。幕府は皇居を造営し,新たに1万石の御料を加え,4年後には,和子を中宮に冊立,形式的には尊崇される。1626年に,中宮御所法度も制定され,秀忠,続いて将軍家光が上洛し,二条城に行幸するが,以後幕末まで,非常時除いて天皇が禁中を出ることも,将軍の上洛も止むことから,朝廷の存在は,ほぼ,無視されるものになったといえよう。翌年の紫衣事件で,朝廷の面目は完全につぶされた上,翌々年,将軍家光の乳母春日局が無位無官の身で拝謁するという前例のないことが敢行され,ついに,不満を爆発させ,突如,和子所生の興子内親王(明正天皇)に譲位,和子は東福門院となり,以後,明正・後光明・後西・霊元の4天皇,51年にわたり院政をしき続け,東福門院も国母であり続けることになる。この間,天皇が,幕府にあてつけるように,朝廷文化を育むことに努めるのと並行するように,東福門院は,毎年雁金屋に膨大な注文を出し続け,この間,幕府が度々倹約令を出すも意に介さず,道楽し続け,1678年,重病で死去,天皇は,後を追うように,その2年後,時代を画すことになる将軍が家綱から綱吉に替わる1680年,84歳という長寿をもって没している。余談ながら,東福門院が死去して,雁金屋への注文が激減,道楽できなくなり,画家として稼ぐことになったのが,御曹司尾形光琳である。
ロ:ピークとしての光格天皇と民間尊皇思想の高まり(維新の遠因)
1758年,のちに,尊皇思想が具体化ししていく端緒として,宝暦事件として有名になる事件が起きる。ことの次第は,儒者,神道家で,家塾を開いていた竹内式部が,武家に政権を奪われた朝家の政権回復の心構えを説く一方,激しく将軍を誹謗したことに,現状に不満をもつ門弟の徳大寺公城,正親町三条公積,烏丸光胤,西洞院時名ら公卿が感銘を受け,朝権回復を志すようになったことから,朝幕間の関係悪化に発展するのを恐れた前関白一条道香らが,彼らを永蟄居など処罰して,天皇の周囲から排除,式部については,京都所司代松平輝高に連絡して幕府にゆだね,翌年,京都町奉行は式部を重追放に処し,宇治山田へ退去させられたが,この頃になると,幕府の支配力に陰りが見え始め,その他にも,尊皇論者が輩出する。
この宝暦事件で,竹内式部の弁護を行った山県大弐は,甲斐国に生まれ,若くして,幕藩体制への批判思想を身につけ,内部からの革命をと思っていたところ,将軍側用人大岡忠光に見出され,取り込まれてしまうが,宝暦事件直後には,のちに吉田松陰にも影響を与える「柳子新論」を脱稿,1760年,忠光が死去すると大岡家を辞し,家塾を開いて,大きな影響を及ぼし,いよいよ行動に移そうとした矢先,門弟に密告され,1767年,式部父子はじめ,国学の師や藩主名代・門人ら多数とともに捕縛,江戸に送還され,首謀者として斬罪となった(明和事件)。処刑に際しての立派な態度が獄吏をも感銘させたという。山県姓のルーツは美濃国ながら,現在も,長州に集中的に多いことから,維新後,長州閥を主導する山県有朋にもつながると思われる。
そのような時代状況のなか,皇位継承危機に,傍流から天皇になり,長期に在位,幕府に対抗して,復古再興に努め,権威を高めたのが光格天皇といわれるので,藤田覚「光格天皇 自身を後にし天下万民を先とし」に従って,やや,詳しく生涯を追ってみることにしよう。
田沼意次が老中になる前年の,1771年に,中御門天皇の弟直仁親王に始まる最も新しい宮家閑院宮2代典仁親王と第六王子に生まれるが,母も異例に身分が低い浪人医師の娘であったことから,皇位には程遠い存在であったが,8歳の時,後桃園天皇が急逝,それを秘しての朝幕の交渉で,白羽の矢が立ち,形式的に天皇の養子にされ,江戸時代初の実子でない異例の天皇になり,父たる上皇はおらず,最後の女性天皇だった後桜町上皇がそのまま続く。まもなく,実父閑院宮典仁親王の御所内での席次が,父の弟の左大臣鷹司輔平より下という低さに驚愕,太上天皇の尊号宣下を願い,幕府から拒否されるも,経済的な優遇措置を引き出すなど,有能ぶりを発揮していく。
1786年,15歳の時,田沼意次の失脚に続く,将軍家治の死去による幕府の動揺をみすかしてか,早くも自ら朝廷政務を主導,強引に,朔旦冬至旬,新嘗祭を実施し,復古再興に取組み始める。翌年,松平定信が寛政の改革を始めた年,米価高騰に,御所千度参りが始まると,追い散らさないように指示,参加者は約五万人になり,直訴も受け入れて,幕府に,空前となる窮民救済を申し入れて実現させ,古儀採用の新御所造営について,幕府の了解を勝ち取ると,(30年にわたって)平安時代の大内裏の考証に没頭してきた裏松光世(固禅)をブレーンに,御所を復古造営し遷幸,華麗な行列が人々に強烈な印象を与え,公家の間でも,空前の復古ブームになる。
その間,実父閑院宮典仁親王への太上天皇尊号宣下の沙汰書が老中松平定信に達して,問題が本格化するが,関白鷹司輔平が幕府よりのためラチが開かず,1791年(20歳),鷹司輔平を更迭して,一条輝良を関白にし,尊号宣下について公卿群議で圧倒的支持を得るも,松平定信の不信を買い,翌年,中止するに至り,完全な敗北に終わる。朝廷の権威を回復すべく,神武天皇から120代という皇統意識をもった署名を始め,高位高官を含む,前代未聞の多数の堂上公家を一度に処分,'図らずも天皇になった'という意識から,残っていた石清水・賀茂臨時祭の再興を表明するなどするうち,尊号事件を素材に広く流布した実録物では,朝廷が勝利した筋書きで,偶然即位することになった天皇への同情がみられるなど,庶民の間では,朝幕の力関係は逆転し始める。
1807年(36歳)のロシア船狼藉事件では,ついに,幕府から報告がなされ,以後,対外情勢も朝廷報告の対象になり,開府初期からの大政委任論は衰えて行く。1813年,石清水臨時祭が380年ぶりに再興,後桜町上皇が死去すると,供養のための真言百八遍奥書に「大日本国天皇兼仁合掌敬白」と自署,当時,ほとんど使われていなかった天皇という意識を明確にした後,1817年(46歳),恵仁親王(仁孝天皇)に譲位。在位年数38年は,後花園天皇を超える異例の長さで,2019年に明仁天皇が生前退位して,"光格天皇以来"と表現され,にわかに注目されることになった。仁孝天皇もすでに18歳になっていて,形式的な院政ではあったが,多くのことについて,意見を聞かれ,指示を与えており,まさに,最高実力者であった。
1822年(51歳),将軍徳川家斉が,従一位左大臣,将軍就任前の世子家慶が,正二位内大臣,御台所も従二位と,いずれも先例を超える昇進を認めたお礼に,幕府から修学院御幸の再興を勧められ,翌々年,90年ぶりの修学院御幸,その行列を多くの町民が見学した。以後,毎年のように,修学院御幸をしていたが,大塩平八郎の乱の翌年,中風を発し,1840年,69歳で没した。翌年,874年ぶりに天皇号が贈られ,諡号も合わせると954年ぶりの再興で,再興にかけた生涯を象徴するものとなった。
光格天皇の朝廷復古活動に対応するように,民間でも,急速に尊皇思想が高まってくる。
林子平・蒲生君平と並ぶ"寛政の三奇人"の一人として知られる高山彦九郎は,上野国新田郡で桓武平氏秩父氏の末裔に生まれ,宝暦事件が起きた年は,まだ11歳であったが,「太平記」を読み,南朝の忠臣たちが志を遂げられなかったことを憤って,尊王の志を抱き,1764年,17歳に家出,諸国を回遊して,一流学者を訪ね,江戸では,細井平洲の学塾に出入り,禁裏に入って幾度か節会を拝観などするうち,1783年,36歳になる頃には,堂上公卿との親交も強くなり,1789年,尊号事件が起こると,公卿らと結託して薩摩藩を味方に引き入れる計画をたてるなどして,光格天皇の耳にも名が聞こえるまでになったが,林子平が拘引されて身の危険を感じ,島津氏への説得を行う役を担って九州に旅立つも,1793年,尊号事件の処理に怒り,久留米まで引返し,幽囚中の子平の死を追うように,憤慨のあまり自刃した。急速に尊皇思想が高まった時代を象徴する存在であったといえよう。
同じく"寛政三奇人"の一人として知られる蒲生君平は,下野国宇都宮の生まれであるが,田沼意次が失脚した1786年,18歳の時に,自らの祖が蒲生氏郷の庶族から出ていることを知り,名門の名を辱しめないことを誓って,自ら蒲生氏を名乗り,別に家を興した。1790年には,高山彦九郎の後を追って陸奥国に赴いたが会えず,帰路,仙台に林子平を訪ねるなど,三奇人は相互に認めあっていたようで,ロシア南下にともなって北方問題がやかましくなってくると,「今書」2巻を著わして時弊を論じるなどしていたが,1796年,28歳になると,歴代天皇の陵墓が荒廃していることをなげいて,「山陵志」論述を志し,各地の陵墓を調査,5年がかりで完成,その後も,国防と尊王を論じ続けるうち,知己友人の援助により,1808年,ようやく「山陵志」の出版が実現,幕末尊王論の先駆をなすものとなったが,5年後,45歳で病没した。蒲生氏のルーツは秦氏とも,鴨氏ともいわれる。
ハ:幕府と対抗した孝明天皇と,将軍家茂に降嫁した妹和宮
孝明天皇は,徹底した攘夷指向を持つように育ち,1846年,15歳で,父仁孝天皇の崩御のあとをうけて践昨するや,早くも,海防を厳重にするよう,歴代天皇として初めて,対外問題について,幕府に勅命。ペリー来航後,アメリカの圧力を受けた幕府は,1858年,日米修好通商条約調印の勅許を奏請,27歳の天皇は当時の大多数の公家衆と同様に開国を憂慮して勅許を見合わせたが,幕府は,勅許を待たずに調印したばかりか,蘭・露・英の諸国とも条約を締結したため,激怒して譲位を決意,幕府と水戸藩に勅諚を下して,叡旨の貫徹を図るも,幕府が釈明し続けた上,反対派の抑圧を始めたため,不満ながら受け入れる。以後も,盛んに勅下して,朝廷権威を回復して行く。
1860年,桜田門外の変で,大老井伊直弼が暗殺されると,幕府は低下した威信を回復するため,公武の融和を策し,皇妹和宮の将軍徳川家茂への婚嫁を奏請,天皇は,和宮の不同意を知って退けるも,再三の懇請を拒否しがたく,ついに勅許。結果として,朝廷は幕府に対して優位に立つことになる。この間,朝廷内では,攘夷派公卿の勢力が伸長,志士らとともに,攘夷親征を企図して,大和行幸を求めるに至るが,天皇は,これを無謀の挙とするとともに,討幕へと突き進む情勢を深く憂い,密かに中川宮尊融親王(朝彦親王)をしてその阻止を謀らしめ,八月十八日の政変となり,以後,政局が禁門の変・長州征討と目まぐるしく推移するうち,内外の情勢は次第に天皇の素志と反対の方向に進み,1865年,英・米・仏・蘭4国公使共同の要求によって,ついに条約を勅許,翌年,薩長両藩の盟約が成り,政局が討幕に向けて急展開するなか,痘瘡に罹って没した。そのタイミングから,暗殺説も絶えないことになる。
京都守護職の会津藩主松平容保への信任は特に厚かった一方,尊攘派公家が長州勢力と結託して様々な工作を計ったことなどから,長州藩には最後まで嫌悪の念を示し続けたという。
孝明天皇が践祚した年,その妹として誕生した和宮は,5歳の時,有栖川宮熾仁親王の婚約者になったが,日米修好通商条約の勅許問題や,将軍継嗣問題によって悪化した朝幕関係を融和するために,1860年,14歳の時,幕府から,徳川家茂へ降嫁するよう求められ,兄の孝明天皇は拒絶しするも,朝権の回復の足がかりとしようとする岩倉具視の献策で,攘夷鎖国の実行を条件に勅許,本人は強く固辞するも,周囲の説得に抗しきれず,これを受けいれ,翌年,江戸城に入り,翌々年には,婚儀がおこなわれ,御台所と称した。その翌年,1864年には,上洛直前の家茂に対して,攘夷を実行するように求めるなど,自らの使命を自覚して実行するうち,翌々年,20歳になったところで,第二次幕長戦争(長州征伐)の渦中,家茂が大坂城で死去すると,徳川家に嫁いだ身を自覚して,徳川家存続や無血開城に尽力,戊辰戦争に際しては,皇族の出でありながら,降嫁した徳川家の救済や,征東軍の江戸進撃の猶予を政府に嘆願する健気さを見せ,終戦後,徳川家の駿府移封を待って,京都に移住,28歳になって,東京に移住,家茂の眠る増上寺目前の麻布の地に邸を賜ったが,3年後に,急逝した。
その和宮の姑にあたるのが,徳川家茂の父将軍家定の正室天璋院(篤姫)で,今和泉島津家当主島津忠剛の娘に生まれたが,将軍世子家定の室候補の問い合わせに,ペリーが来航した1853年,18歳の時,島津斉彬の偽装工作で,その実子とされ,篤姫と名を改め,江戸芝藩邸到着直後に,家定が13代将軍となる。いよいよという時,安政大地震が起こって,婚姻延期,3年後,近衛家の養女となり,名を敬子と改めて,江戸城入城して婚礼,御台所となるが,翌々年には,島津斉彬に続き,家定も死去してしまい,天璋院と号する。1861年に,江戸城に入った和宮と初対面で,礼節を欠いたと朝廷側で問題になるも,本人間は不仲にならず,養父島津斉彬に逆らって擁立に反対した一橋慶喜が,1867年に大政奉還して裏切られ,幕府表方が不甲斐ないところ,徳川家存続のために,和宮とともに,目を見張る奔走,江戸城開城後は,潔く退城して,一橋邸に移居し,家茂が次期将軍に内命しながら慶喜に奪われた田安亀之助の養育に専念し,和宮の6年後に没した。
第2話:長州人を軸にしてみた維新前後(大塩平八郎の乱から,明治14年の政変まで)
さて,維新の実現は,いわゆる薩長土肥でなされたが,維新後すぐに,土肥を外して薩長だけになり,ついには薩摩すら排斥されて,長州が覇権を握るに至る。長州は維新前,天皇にたてついて征伐されたように朝敵とされながら,本来天皇の最大のサポート役であった会津藩などを朝敵にしてしまった上,天皇を左右して大戦にまで至らしめ,靖国神社を武器に国民を誘導するなど,その専横ぶりは,まさにかつての藤原氏を彷彿とさせるもので,大内氏のところで述べたとおり,長州人は,いわばクダラ系藤原氏の末裔のような存在なのである。>大内氏
余談ながら,敗戦に至る最大の問題は,海洋民族が主たる長州が陸軍を支配,それに対して,本来騎馬民族である薩摩が海軍を担うという,根本的なネジレがある上,統治の不得意な海洋民族が軍を握ってしまったことによるとも考えざるを得ない。前章で述べたように,マツ系だった徳川の葵の紋は別にして,天皇家が菊の御紋であるのに対し,将軍家は桐の紋章であったのを,維新後の日本政府が使用していることも,クダラ系藤原氏のしたたかさが見えるようである。
「日本史リズム」のところで述べたように,維新前後というのは,出発点になったとみられる1837年の大塩平八郎の乱から,近代に向けて決着した1881年の明治14年の政変までということになる。そこで,長州を軸に,維新を実現したいわゆる薩長土肥に,尊皇攘夷論に大きな影響を与えた水戸藩の動向など加えながら,その経緯を辿ってみよう。
イ:大塩平八郎の乱から,ペリー来航まで
1837年に起きた大塩平八郎の乱を受けて,幕府が始めた天保の改革に対応するように,長州藩でも,1840年代から,毛利藩政への改革に向けての動きが始まり,それを進めようとする(革新)正論派と,それまでの藩政を守ろうとする(保守)俗論派の対立が生じる。こういった動きは,他の諸藩にもみられるが,すでに述べたように,長州人は,意見の合わないものを受け入れない,排除するという性格が強いため,1860年代にかけて,その対立が激化して行く。
1937年,大塩平八郎の乱は全国に衝撃を与え,越後の生田万が決起し,摂津でも騒動が起きるなか,水戸藩の藤田東湖が,乱の記録「浪華騒擾記事」をまとめ,それも受けて,翌年,藩主徳川斉昭が,幕府に内憂外患の意見書を提出,長州萩藩では,村田清風を起用して改革開始,1841年には,水戸藩校弘道館が開設され,翌々年,萩藩でも,村田清風の改革案を実施に移す。
その後は,大石学「幕末維新史年表」によれば,1844年,佐賀藩では,大砲の設置や,銃の製造を開始。水戸藩主徳川斉昭が,藩政改革の行き過ぎを問われて,隠居・謹慎処分。長州では,(正義派)村田清風が失脚し,(俗論派)坪井九右衛門一派に戻る。1846年には,前論で取り上げたように,践祚した孝明天皇が,歴代天皇として初めて,対外問題で,幕府に勅命し,水戸藩主徳川斉昭が,海外情勢についての意見書を提出,翌1847年,佐賀藩は,種痘でも全国に先駆けるなど,この段階では,明らかに近代化の先陣を切っていた。続くように,薩摩藩が,砲術館を設け,野戦砲や火薬の製造を開始し,水戸藩主徳川斉昭が,外国人追放の意見書を提出,長州では,藩政改革に失敗した(俗論派)坪井が失脚するなど,足元が定まらない。
1848年,薩摩藩で,密貿易によって藩の財政を立て直し,家老に昇進した調所広郷が,密貿易が幕府に露見した責任をとって自害し,土佐藩が,山内豊重(容堂)が新藩主となって,ようやく登場した翌1849年,薩摩藩で,お由良騒動が起き,改革の英主島津斉彬の登場に待ったがかかる。翌1850年,佐賀藩は,ついに反射炉を完成させ,大砲を製造するに至り,翌1851年,土佐出身の捕鯨家で,太平洋で遭難し,アメリカで教育を受けた中浜万次郎が帰国,独自の役割を果たして行く。薩摩藩では,島津斉彬がようやく藩主となり,一気に近代化が進む。そして,翌1852年,脱藩して遊学していた長州藩士吉田松陰が,強制送還されて謹慎処分となるが,翌年には,不憫に思った藩主の配慮で,10年間諸国遊学の許可をもらったところに,ペリー来航となるのである。
ロ:ペリー来航から,大政奉還・王政復古まで(国譲りの再現)
1853年のペリー来航を契機として日本中に広がる攘夷運動のなかでも,排他性の強い長州人の攘夷ぶりは際立ったものになるが,そこに吉田松陰という,自らも老中間部詮勝の暗殺を企てるなど,テロリスト的要素をもつ稀有のアジテーターが登場,わずか数年の間しかなかった松下村塾を通じて,絶大な影響を及す。
藩主から,10年の遊学許可を貰った直後,ペリー来航の報に接するや,浦賀に出かけて黒船をまのあたりにし,翌年,再来中のアメリカ艦に,闇にまみれて漕ぎ着けるも送り返され,江戸の獄に入れられたのち,引き渡された藩によって,萩の野山獄に投じられると,教育者の資質を発揮し始め,1855年に出獄すると,叔父が開いていた"松下村塾"で講義,思想が過激になるとともに,公然と通う者も輩出,以後,長州の維新の志士の多数が学ぶに至るも束の間,幕府に睨まれ,斬首刑に処せられ,わずか4年で終わる。その後,維新に至っていなければ,志士らはテロリストでしかなく,松陰は天才的アジテーターといわれるに留まったかもしれない。
孝明天皇も攘夷の思想が強かったため,尊皇攘夷へと飛躍するが,井伊直弼が暗殺された1860年を経ると,"松下村塾"トップ高杉晋作がイギリス大使館焼き討ち事件を起こし,1863年,開明派の代表たる長井雅樂が謹慎・自刃に追い込まれたように攘夷運動がピークになるなか,開国しようとする幕府の意向で,朝廷では公武合体派の力が強まり,八月十八日の政変となり,すでに述べたように,敗れた攘夷派が長州に"七卿落ち"する(応仁の乱時の山口大内氏のところに公卿らが都落ちするのに対応)。すると,その翌年には,朝廷を攻撃する暴挙に出て,朝廷を守ろうとする京都守護職の会津藩はもちろん,前年の薩英戦争に敗れて早くも公武合体派に転じていた薩摩藩などが参加した幕府軍に敗れる。この段階では,薩長は敵対関係で,長州藩こそ朝敵だったわけである。
同じ頃,前年の外国船に対する砲撃に報復すべく,下関に来訪した四国艦隊に砲撃されて敗退,講和したこともあって,攘夷派の公家中山忠光が下関で暗殺されるなど,開国派に転じるかに見えたのも束の間,1865年には,正義派を称する高杉晋作が再び決起(この時には伊藤博文すら参加していた),第二次長州戦争が始まる。ここまでみていると,長州藩というのは,朝廷・幕府・外国すべてを敵にし,しかも内乱状態が続いているということで,ほとほと,異なる意見を受け入れることができない人たちだと思えてしまう。
吉田松陰と違って,全く知られていないが,太平洋戦争の敗戦によって,その存在が,一つの国家支配の装置になっている靖国神社のもとをつくった青山清もまた,生粋の長州人であった。青山幹雄ほか「靖国の源流」によれば,松陰より15年前,萩の産土神椿八幡宮宮司の長男に生まれ,中年になるまでは,目立った動きはなかったが,1863年,48歳の時に,八月十八日の政変の七卿落ちに触発されて,(本講義で述べていることを裏付けるかのように)大内氏時代の"国風振興"調査を始め,同志と「神祇道建白書」を藩に提出し,翌年,"七卿落ち"の一人錦小路頼徳が,現地で病死してしまうと,彼を神として祀るように申し出た。第一次長州征討で福原越後が自刃すると,藩政府に申し出て,国のために死んだ人を神として祀ることを許され,福原越後の神霊を祀り,下関の桜山招魂社で初の招魂祭を斎行,同時に,松陰の神霊も祀っている。
明治維新に向けた藩のエネルギーのようなもの考えると,薩摩藩の場合,鎌倉時代からの大名,支配が得意なハタ系をルーツとする島津氏のもとで育まれた藩民性のようなものがあって,それが,徳川幕府から,圧力をかけ続けられたことに反発,まさに幕府を倒すことが目的であったという点でわかりやすいが,長州の場合,戦国時代までは,大内氏支配のもと,いわば一つの地域国家だったところ,毛利氏の支配に代わって,徳川幕藩体制に組み込まれたわけで,おそらく,毛利氏支配への反発が先にあっての,反幕だったように見える。それ以上に,尊皇攘夷,とくに,外国人(ヨソ者)を排除しようとする攘夷のエネルギーは強烈で,それが,一度は朝敵になり,いわゆる"七卿落ち"として知られる事件にもなったのであるが,攘夷派の公家が山口に落ち延びてきたのも,大内氏時代の縁がもとになっているといえよう。
長州藩中心に述べてきたため,付け加えのようになるが,薩摩藩では,藩主の島津久光自らが主導して,急進派を粛清,生麦事件後の薩英戦争で,一気に開国派に転じて行くのは,ユダヤ系秦氏出身ゆえ,イギリスと相通じた可能性があり,さらに,薩長同盟に至る前段としてのフリーメーソンのグラバー,そして,薩長同盟を実現させた土佐藩坂本龍馬の役割の存在の大きかったことを指摘しておく。
ハ:明治維新・戊辰戦争から,明治14年の政変まで
1866年,薩摩藩も本格的に反幕になり,坂本龍馬のおかげで,いわゆる薩長同盟が実現,第二次長州戦争では幕府に勝利,さらに,孝明天皇が崩御して明治天皇が践祚,高杉晋作も死去してしまい,一気に白紙転換するチャンスが到来するや,まさに手の平を返すのである。討幕の密勅が最初に出されたのが長州藩だったのは,大内氏のところで述べてきたことと関わりがありそうだが,それはともかく,大政奉還,王政復古となり,新政府が覇権を握るための最後の戦い戊辰戦争に突入,ここでも,長州藩が主力部隊になった会津藩への攻撃とその後の処理の残酷さが際立つ。薩摩藩の方は,西郷隆盛が江戸城の無血開城を実現し,箱館で,最後の最後まで戦った幕臣榎本武揚はじめ主要な人物を,戦後早くに赦免し,政府の重要なポストに登用しているのである。
ところで,いまだに不審がられている最後の将軍徳川慶喜の行動については,江戸城の無血開城とあわせてみると,徳川氏がマツ系であったことを知っていれば,1500年前,崇神東征の時に,マツ系民族が国譲りしたことを,再び,実行したに過ぎない,つまり,血を流すことを避けることの方に意味があり,それだからこそ,250年の平和の時代も続いたということなのである。
ここで改めて,徳川慶喜についてみてみると,吉宗以来,紀州系の将軍が続くなか,盛んに意見をすることで幕閣と対立した,御三家水戸の徳川斉昭の七男という末流ながら,俊才を見込まれ,家康の直系筋ということもあって,改革派の幕閣や諸藩から,将軍継嗣の候補に挙げられるも,井伊直弼の登場で排除されてしまう。直弼が暗殺されるや,改革派の期待がますます高まるも,母親が皇族出身だったことから,孝明天皇に配慮して,攘夷を支持する姿勢を示し,"二心殿"と呼ばれる矛盾した状態になるが,八月十八日の政変で,情勢が一変すると,朝廷からの,軍の最高司令官任命を受諾して,禁門の変などで大活躍しながら,幕政改革も指揮する力量を発揮,木戸孝允をして,家康の再来とまで畏怖させるほどで,将軍就任直後に,孝明天皇が死去し,攘夷派に配慮する必要が無くなると,兵庫開港を実現して,開国への道を一気に広げるのである。さらに,薩長の機先を制して,大政奉還したが,王政復古のクーデタによって,官位を剥奪され,駿府で謹慎生活となると,家康の遺産を守るべく,江戸を火の海にしないよう苦心,その後の長い人生を,多趣味に暮らし,まさに,近代的個人主義を先取りした,国譲りに相応しい傑物であったといえよう。
徳川慶喜は,家康直系であることによって登場し,そのことが,大政奉還という国譲りによって,幕府を終わらせる役割を担う大義でもあったのである。
戊辰戦争も終わったことから,1869年,長州の軍政トップ大村益次郎によって招魂社が建立されるが,その直後に彼が暗殺されてしまう。長州の大半の兵に帰郷命令が出て不満が爆発したからで,その後も諸隊の反乱が続き,やはり開明派ですぐれた人物といわれる広沢真臣も暗殺されるが,やがて鎮圧される。その後は,後述するように,クダラ系藤原氏そのもののような陰謀によるライバル排除が続くようになり,新政府の軍という重要な部署については,軍制改革を任された山県有朋の力が急成長,のちに,伊藤博文が暗殺されると,いわゆる権力の専横ぶりが見られるようになる。いずれにしても,自らの藩にいた優れた人材を次々と亡き者にしてしまう,その結果,二流の長州人が支配するようになっていくことを,どのように考えたら良いのだろうか。
ところで,太平洋戦争後の日本を統治する上でかかせないものになった靖国神社のもとつくった長州人青山清の幕末の活動については前項に記したが,その後,1867年に,長州藩が,朝廷から討幕の密勅受けると,密かに錦の御旗(官軍旗)を制作し,翌年,維新がなると,東征大総督有栖川宮熾仁親王の命で,江戸城で官軍側戦没者のための招魂祭を主宰。1689年,大村益次郎が九段坂上に招魂社を仮設(東京招魂社)した直後,刺客に襲われ死去すると,その遺志を受けて,宇部に維新招魂社を建立。1871年には,太政官布告で神官の世襲が禁止されて,国家神道が始まるとともに,兵部省に出仕して招魂社御用掛となり,翌年,兵部省が陸軍省になるとともに,山県有朋を祭主に,棟上式と遷宮式で祭典掛を務め,1874年の東京招魂社への明治天皇の初行幸で奉仕(祭主は山県有朋),以後,毎年御親幸に参列,1879年,別格官幣社に加えられて,靖国神社になるとともに,初代宮司に就任し,西南戦争の官軍側戦没者の招魂祭を行い,12年,在職のまま,没している。
戦後,靖国神社に対する国民の複雑な思いが消えないのは,そのルーツに長州支配があり,それが,長州人の排除の論理で,戦死したものは敵味方なく弔うという博愛の論理とは正反対,朝敵であった奥州列藩の人たちはもちろん,西郷隆盛すら祀られていないという徹底ぶりなのである。
ついでながら,長州藩の無謀ぶりがあっても,維新そのものを成し遂げられ,覇権を握ろうとする長州人を抑えることができたのは,軸になる人物として,公平無私といわれる薩摩藩の大久保利通がいたからであることはいうまでもない。蛇足ながら,薩摩の軍人の代表東郷平八郎の軍人としてのすごさに対して,長州の代表乃木希典は,戦地で多くのミスを犯し,多くの兵士を失った,とても優れた将とは言えない軍人で,明治天皇崩御に殉死したことでのみ,神様になったということになろう。太平洋戦争に至って,一層,開明的な海軍の薩摩,陰謀的な長州の陸軍の違いが鮮明になるのである。
明治維新に至る過程で,朝廷を守っていた会津藩などに戦争を仕掛け,まさに朝敵そのもであったのに,戊辰戦争になるや,手の平を返して,会津藩などを朝敵として苛酷に攻め,維新後は,まず薩摩と組んで,土肥を排除,薩長という言葉の影に隠れて,実際には,薩摩をも排除,山県有朋に代表されるように,国民の意向はおかまいなしに,弾圧政策をとり,かつて敵であった奥州などの諸藩出身者も都合よければ味方に取り入れ,最後は,天皇をも利用して,日本を戦争に持ち込みながら,戦後,まもなく,安倍晋三の祖父岸信介が素知らぬ顔で復活するという有様である。平安時代の,天皇など,時の権力に取り入って,登場の機会をつくり,一旦登場してしまうと,陰謀でライバルとなる氏族を次々排除,摂関となって天皇を思うように利用した,あの藤原氏そのものであるといえよう。
明治維新は薩長が主導したとはいえ,当初は土佐・肥前藩も一緒になった薩長土肥という四藩であったことが大きかったのはいうまでもないが,岩倉使節団の米欧歴訪で,大久保利通らが不在になるなか,西郷隆盛を主とする征韓論が起こる。1873年の使節団の帰国とともに,長州人木戸孝允の意見により,公家岩倉具視が上奏するという形で否定されたことから,政変となり,西郷とともに,土佐の板垣退助,肥前の江藤新平,副島種臣など,優れた人材も一緒に下野してしまう(明治六年の政変)。
大久保利通が薩摩の同胞西郷を切ったのは,近代化を定着させるために涙を呑んでのことであったが,大政奉還の動きをつくった土佐藩のシンボルともいえる板垣は,下野すると,自由民権運動という,さらに時代を先取りするような行動を起こし,肥前の江藤新平は司法制度はじめ近代国家の基本設計をし,副島種臣は維新直後の外交で日本の存在を世界に示して一目を置かれるほどの人物であった。要するに,長州主導で薩長土肥のうちの二藩が排除されたのである。岩倉具視の役割を考えてみると,公家と密接につながった大内氏の話そのままで,見ようによっては,明治維新は,一部とはいえ,平安時代の公家支配の復活をも含んでいるといえよう。
そして,佐賀の乱,西南戦争などの内乱,大久保利通の暗殺などを経て,維新体制が確立したのが1881年の,いわゆる明治十四年の政変であるが,生前の大久保の後継指名もあって,長州の伊藤博文が覇権を握り,残っていた肥前の大物大隈重信を追放してしまう。まるで,平安時代の,藤原良房による承和の変をみているようだ。伊藤博文は,長州人としては珍しく,世界的視野を持ち,異なる意見にも耳を傾けるという点で首相に相応しかったといえるが,内閣制度,議会制度ができると,内閣と議会の,要するに,官僚と民間人の争いのなかで,一方的に官僚側に立ち,かつ軍部を押さえる山県有朋の力が次第に強くなっていく。さすがに排除できなかった薩摩については,とりあえず,体よく利用して行くことなるのである。
第3話:山県有朋による陰謀型長州人の覇権の確立
山県は伊藤よりも年上であったが,人を見る目のある大久保によって伊藤が後継者になったので,その伊藤が暗殺されるや,山県の傍若無人ぶりが露わになってくる。世間では,薩長支配として,常に薩摩とセットにされているが,薩摩藩出身者は,西郷隆盛と大久保利通の狭間でうかつに政治的に動けなかったことに加え,優秀な軍人たちが政治的野心を持たなかったこともあって,たくみに利用され,実質は長州閥のみの支配にされていったといえるだろう。伊藤博文を朝鮮総督に祭り上げ,結果として排除することになったのは,かつての,藤原摂関家内の抗争を思わせる。
近代日本が,長州人支配のもとにあることを確認するため,首相官邸のホームページで歴代総理大臣の在職日数をみてみると,1875(明治18)年12月に内閣が発足して,長州人伊藤博文が総理大臣になって以降,わずかな総理大臣不在の時期を除いて,安倍晋三首相が退陣する2020(令和2)年9月までの52,122日間に,62人の総理大臣が誕生した。そのうち,山口県すなわち長州出身者は,戦前は,伊藤に加えて,山県有朋,桂太郎,寺内正毅,田中義一,戦後は,岸信介,佐藤栄作,安倍晋三と,人数は8人で,13%とすくないが,在職日数は,延べ15,569日と30%を占め,一人当たり平均でほぼ2000日,6年近くになり,これに,藤原氏的政治の復活ということから,近衛秀麿,西園寺公望の公家トップ,皇族の東久邇宮,さらに,実質長州人といわれる菅直人の4人を加えると,在職日数は18,510日で,35.5%にもなる。残りの50人で,33,612日ということは,一人当たり672日で,長州人首相の3分の1に過ぎなくなる。ちなみに,薩長のもう一派,鹿児島県出身の総理大臣は2代目の黒田清隆,4,6代目の松方正義,22代目の山本権兵衛の3人しかおらず,在職日数の平均も678日で,以後は,全く出ていない。これらのことだけでも,長州人がいかに策謀に優れて長期政権をつくってきたか,薩長とはいいながら,薩摩人が権力を握ったことはほとんど無かったことが分かってもらえるだろう。以下,段階に応じて,簡単に整理しておく。
イ:伊藤博文暗殺から,戦争に突き進むまで
覇権が確立したのは,桂太郎からで,桂自身通算2886日と,安倍晋三に追い越されるまでは1位の長さであり,公家西園寺公望と交替する"桂園内閣"というたくみな方法で続けたことから,両者を一人とみれば,4300日近く,つまり12年近くにもなる。桂,寺内正毅,そして,張作霖爆殺事件爆殺事件を起こし,即位まもない昭和天皇から叱責されて,内閣総辞職,まもなく急死してしまう田中義一まで,いずれも陸軍軍人出身であり,長州人内閣はまた陸軍内閣でもあったといえよう。その結果,国民的人気を背景に登場した,世が世なら,摂関家トップの近衛秀麿は,日中戦争を泥沼化させ,日米開戦への道づくりをしてしまったのである。
大正デモクラシーを謳歌し,社会主義が広がる間,長州支配の陸軍が伸長,山県有朋が大正天皇をバカにし,のちの昭和天皇の妃選定に口を出すなど,天皇をも見下す姿勢が,結局は大戦を招き,国民を悲劇に落とし込んだことは言うまでもない。はじめは,宮内大臣になっていた大久保利通の息子牧野伸顕が抵抗していたが,親英米派として狙われ,二二六事件によって,ついに失脚させられてしまう。そして,近衛文麿首相は,藤原摂関家の筆頭家の出なので,関白が実質国家の宰相だった平安時代の藤原道長,遅くとも,その子の頼通までとすれば,実に,900年ぶりの宰相関白の復活だったといえるだろう。
ロ:敗戦から,岸信介首相登場まで
敗戦直後は,新憲法制定前ではあるが,戦前からの首相選びというわけにもいかず,最初の首相には,皇族の東久邇宮稔彦王がなった。戦前に,満州国のトップ官僚であった岸信介は,敗戦で,A級戦犯になったが,アメリカが,共産主義と戦うことが至上命題になって,手の平を返して釈放されると,1955年,保守合同で,自由民主党が実現する波に乗ったばかりか,国民はじめ誰もが認めた合同後最初の首相石橋湛山が,わずか2か月で,病気のために引退という,思わぬことから,首相の座を射止め,戦後の,長州人内閣の幕を開ける。
長州陸軍による無謀な戦争が,天皇や国民に苛酷な運命をもたらしたにもかかわらず,その反省もないうちに復活した岸首相の姓は,前述したように,百済王族を示すキシそのものであり,クダラ系藤原氏的時代の到来を,これほど象徴する人物はいない。いわば,現代政界の貴種であり,その弟の佐藤栄作,孫の安倍(安倍貞任の末裔というものも加わる)が強かったのも当然だろう。あの平安時代に,天皇制の危機とさえいわれた平将門の乱後,何事もなかったかのように,摂政藤原忠平が復活し,道長の栄華に至ったことを思い起こさせるようだ。
念のため,第2次世界大戦における戦没者数を,都道府県別に集計したものを見てみると(ホームページ「みちのく歴史フォト散歩」),東京大空襲,広島,長崎の原爆という,本土に住んでいるだけでの一般住民の大量の死は別とし,実際の戦闘による死者数で,当時の人口比では,長州の山口県の1.9%を基準に,それよりも多いのが,特別に悲惨な状況に追い込まれた沖縄の21.3%を別格に,多い順に,三重県,香川県の4.4%,福島県の4.1%,佐賀県の4.0%,福井県の3.8%,宮崎県の3.7%,山形県,宮城県の3.6%,山梨県の3.3%,岩手県,長野県の3.2%,鳥取県の2.9%,栃木県,奈良県,高知県,長崎県の2.6%,岡山県の2.5%,群馬県の2.4%,和歌山県,茨城県の2.3%,千葉県の2.2%,岐阜県の2.1%,青森県,新潟県,静岡県の2・0%で,都道府県数で過半になるだけでなく,一見して分かるのは,近代以前から差別的扱いを受けている沖縄はもちろん,戊辰戦争に敗れた東北諸県(福島,山形,宮城,岩手,青森,新潟),維新後に排除された土肥(佐賀,高知,長崎),そして,徳川御三家(和歌山,茨城,静岡)であり,やはり,意図的に,より厳しい戦線に送られたと考えて良さそうだ。
岸首相と同じ頃,全く反対側の共産党議員だった野坂参三も,生粋の長州人で,1955年に,中国から復帰して,共産党第一書記になっていて,保革対決のなか,国民を欺いたまま,熱狂的支持を得続けている。
ハ:戦後の長期政権を代表する佐藤栄作から安倍晋三まで
安保闘争後の,国民の政治離れ,経済優先ムードのなか,政界有力者を互いに戦わせる人事を駆使,クダラ系藤原氏そのままのような,陰謀による長期政権で,東京オリンピックから大阪万博までの高度成長を実現させた佐藤栄作は2798日(8年近く),そして,戦う敵すらいなくなった安倍晋三は,ついに,桂太郎を超える3188日という最長記録になったのである。その安倍の長期政権を実現させることになったのは,小沢一郎のしかけによる小選挙区制の導入で,あり得なかったと思えた民主党政権が実現したものの,準長州人の菅直人が,国民のためにではなく,自らの権力維持にしか関心がない,まさに長州人的なところが露わになって破綻したことによるのである。
戦後の自民党政治の政策の大半は,庶民出身の稀有の政治家田中角栄によるものであり,佐藤栄作後,後継になると思われていた福田赳夫が敗れ,田中角栄が首相になるや,いわゆるエスタブリッシュ勢力は,アメリカとともに,金権問題で退場させ,それでも力足りず,ロッキード事件で失脚させたが,優れた人材多くを見出し,多くの弟子を教育していた田中の勢力はその後も続く。いわば,藤原氏が菅原道真を追放したようなもので,その祟りはずっと続いているようだ。その後も,陰謀によって,少しずつ田中系の有能な政治家を排除してきたが,田中直系の小沢一郎が,ついに,民主党政権を実現させるも,その政権のダメぶりが露わになると,止めを刺すように,残った人材すべてを排除,ライバルがいなくなって,安倍長期政権が実現した。そのダメぶりを示した張本人が,準長州人といえる菅直人であったのだから,なんとも言いようがない。
安倍政権の傲慢ぶりにアイソをつかしている人は多いのに,何故か居座り続けていること,彼自らが長州人であることを誇りにし,明治維新が,あたかも長州人にのみ成し遂げられたように言っていることなどを見ていると,長州人とは一体何者なのかを考えざるを得ない。お友達,つまり自分にとって都合の良い人は何が何でも大事にし,少しでも反対なら,すぐにでも排除,国民はおろか,天皇をも見下す姿勢,まさに「桜を見る会」に象徴される人間性は何処から生まれてきたのだろうか。安倍晋三の傲慢さは,彼固有の性格に由来するのではなく,長州人共通の性格であることを示すため,野党の側の代表的長州人を挙げて見よう。
そもそも,第一次安倍政権が崩壊したことを端緒に,民主党が政権を握るという二大政党定着への足掛かりができたというのに,菅直人が党首になるや,原発事故への対処だけでなく,消費税アップなどで,国民を裏切り,その結果,民主党が自滅したことが,現在の安倍政権を生んだといえる。安倍首相は,臆面もなく,'悪夢の民主党時代'と言っているが,その菅直人も,父の勤務地の山口県宇部で生まれ育っているから,半ば長州人で,彼の政界での出世を見ると,社会党のシンボル土井たか子に付き添う形で登場,草の根風に振舞って国民の人気を得ていたが,小沢一郎のお蔭で民主党ができ,最初は,鳩山由紀夫というお坊ちゃんを立てて政権を握ったとたん,若手を利用して,まず小沢一郎を,続けて,鳩山由紀夫を平気で斬ってしまうという冷たさで,その結果が,どうしようもない野党の状況を招いているのに,何の反省もない。
さらに思い出すのは,前項の繰り返しになるが,萩の商家に生まれた正真正銘の長州人,共産党の野坂参三で,100歳という人生の最後の最後になって明らかになったのは,戦前に,ソ連で日本人の同胞を裏切って刑死させ,戦後は,仲間を裏切り,国民を騙して,圧倒的人気を得たことなど,やはり長州人の体質そのもののように見える。
安倍長期政権を可能にした最大の理由が,強力なライバルがいなくなったことにあるのは,共通認識と思うが,確かに,気配りの竹下登元総理が死去して以降,自民党内でも,それなりに見識や力を持った野中務,亀井静香,鈴木宗男はじめ,多くの人たちが,極端な場合は犯罪のでっち上げまで含めて,排除されたり,牙を抜かれたりしてきた。
明治維新において,当初は朝敵だったものが,薩摩を利用して維新を達成するや,天皇を支配するに至り,吉田松陰をシンボルに,長州の神社をルーツにする靖国神社を利用,国家を支配する存在になる。無謀な大戦によって国民に犠牲を強いたにもかかわらず,岸信介首相によって復活,今や,その孫たる安倍首相の独裁といった状況になり,モリカケ問題はもちろん,世界遺産になった近代産業遺産も,本来なら九州のみであったところ,産業には関係のない松陰の存在を理由に,山口県までゴリ押しで入れてしまう。安倍首相に限らず,かつて共産党委員長として絶大な人気を誇った野坂参三,近い所では,民主党党首だった菅直人など,長州出身の人たちは,自らの権力を振るうためには,同志や国民をも平気で裏切るという点で共通しているのは否定しようがないだろう。いずれにしても,戦後も,長州の,あるいは長州が差配できる首相を戴いてきたことからでも,世界からは,日本国民が本当に反省しているとは見えなくてもやむを得ないだろう。
全くの付けたしではあるが,近現代の芸術分野を象徴する映画や漫画のルーツを辿ると,平安時代末の絵巻物であり,振り返れば,武家政権の登場は,天皇家がクダラ系藤原氏に支配されてしまったことにもよるのであり,その後の武家政権時代を通じて,朝廷との関係がぎくしゃくするのも当然であったといえるが,その底流で,没落した秦氏由来の芸能民との関係が,後白河法皇の白拍子や今様,足利時代の能役者や義政の善阿弥起用から,織豊政権の茶人,徳川時代の将棋・囲碁の棋士など闘いの芸能,さらに家康の本阿弥優遇など,連綿と続いていることも,藤原氏を除いた部分での,天皇家との関係を示唆するものではないかと思われる。
この章TOPへ
ページTOPへ
特論:天皇制の枠組~諡号と神話と元号と
歴代の天皇や記紀に登場する神については,それぞれ該当する項で,断片的に取り上げてきたが,天武・持統天皇と藤原不比等によって編纂されたものが元になり,漢風諡号を撰進した淡海三船は桓武天皇の時代に没していることから,新天皇の誕生を機会に,改めて,天皇の名前や日本神話の構成を見直してみるべく,一覧で見ることのできる図を作成したところ,かなり,簡潔に証明できるものになった。ついでに,元号についても,始まりは「大化」であるが,定着したのは,持統天皇時代の「大宝」なので,「令和」になったのを機会に,改めて,見直してみたい。
第1話:天皇神授と皇位継承
中大兄皇子(天智天皇)の娘で,父の弟の大海人皇子の妃になった後の持統天皇は,父が死に際して,子の大友皇子(異母弟)に皇位を継がせようとしたのに対して,夫が壬申の乱を起こすと,それを支えて勝利に導き,夫が天武天皇として即位すると,皇后になる。天武天皇は,律令制の確立をはじめ,日本国としての統一を図るべく,神話の蒐集編纂と,初の本格的な都・藤原京の建設にとりかかるが,志半ばで倒れてしまう。皇后であった持統は,子の草壁皇子が幼かったことから,自ら天皇になろうとするが,夫はいわば皇位の簒奪者で,天智天皇の皇子も遺っていて,群臣の意見をまとめることができないため,自ら皇位に就く正統性を,神から授かったものにすべく,天皇が天照大神の子孫であると,神話を再構成し,儀式を整えて,突破する。それまでの,天皇は,群臣らの総意に基づいて選ばれていたので,平成や令和になっての新天皇にみるような,いわゆる万世一系の,神がかった即位というものは,まさに,持統天皇によって始められたのである。
我々はまた,戦前なら,神武天皇から歴代の天皇の名を諳んじ,戦後は,戦争への反省もあって,古い天皇の存在に疑いを抱くようになったとはいえ,応神天皇以降の天皇の名など,かなりの天皇の名を,歴史的な事件とも対応させて,自然に覚えるようになっている。ところが,このように漢字2文字に天皇をつけて呼ぶ,いわゆる漢風諡号というものが始まったのは,聖武天皇の娘の孝謙天皇(重祚して称徳天皇)の時代に,その命で,当時一流の文人官僚だった大友皇子の曽孫・淡海三船が,神武天皇から聖武天皇まで一括撰進したものなのである。これらの名を誰がいつつけたのか何の疑いも持たずに,歴代天皇の系図などが作られ,かなり自然に名を覚えてしまうのは,淡海三船の名づけ方が,それほど的確で優れたものであったということだろう。彼は,桓武天皇の代にもなお要職についていたが,その在位中に死去してしまうので,桓武天皇以後の天皇の名は,淡海三船に倣ってつけられていくことになった。
そこで,天照大神からの皇祖神,神武天皇から桓武天皇に至る歴代天皇のつながりがどのようになっているか,本文中で述べて来たことに対応してみることができるよう,以下に,示す。
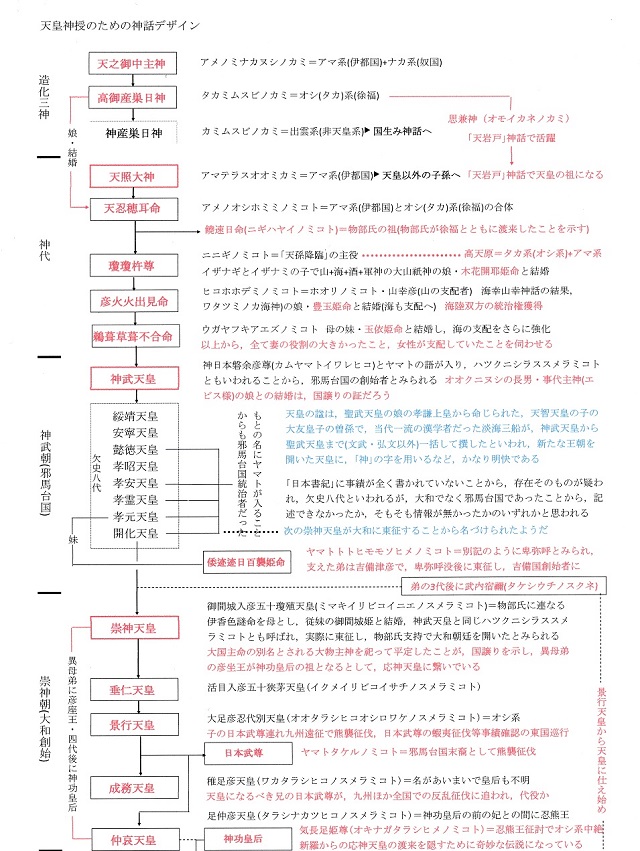
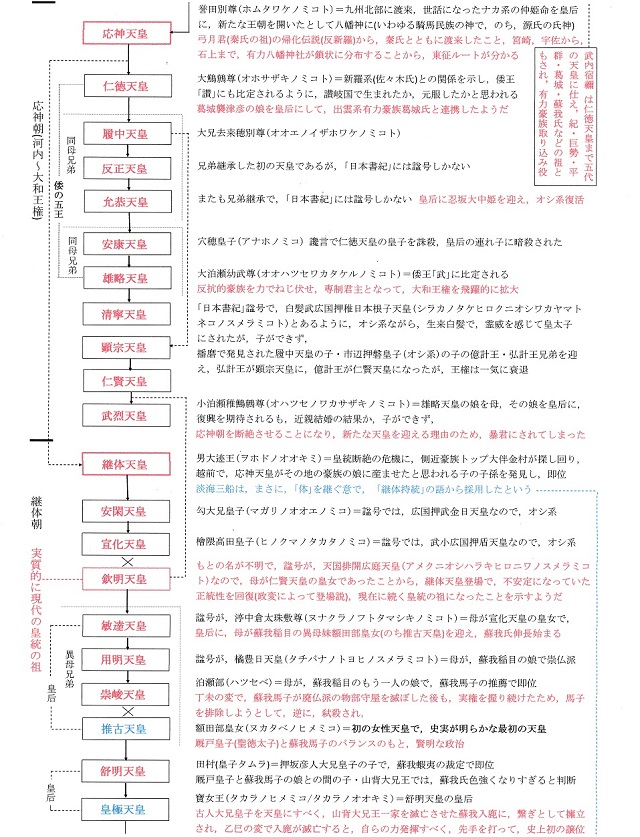

第2話:記紀神話と諸民統合
天皇を戴いて統治するという仕組みが藤原氏によって確立したことに異論は無いと思われる。その張本人たる藤原不比等は,持統天皇を支えて,天皇神授への神話の再構成から,藤原京の建設,大宝律令の完成まで貢献し,父の中臣鎌足が天智天皇から与えられた藤原姓を,自らの家族に限り,他家は中臣姓に戻すことに成功する。持統天皇が死去すると,記紀の編纂を利用して,一族の祖となる神を皇族につながる位置に収めるなどして,権威を高めて覇権を獲得,自らは死去してしまうが,娘の光明子が民間出身としては初の(聖武天皇の)皇后になるに至り,子孫が天皇を戴いて国を支配する道を開いたのである。
とはいっても,彼がなした改変はほんの一部でしかなく,そもそもの記紀神話は,各地に伝えられた話をまとめたものから編纂されていて,八百万の神々の体系がどのようにつくられているかを,最近出版されたばかりの,戸部民夫著「日本の神様の"家系図"」を参考に分析したところ,渡来した徐福集団が,邪馬台国を建設していく過程で,様々な氏族との融和を図るべく,道教の体系をベースに語り始め,崇神天皇の東征による国譲りの諸問題を経て,応神天皇とともに渡来した(徐福が仕えた秦の始皇帝家臣の末裔)秦氏が,神社の創建とあわせて詳細に固めていった様子がうかがえる。
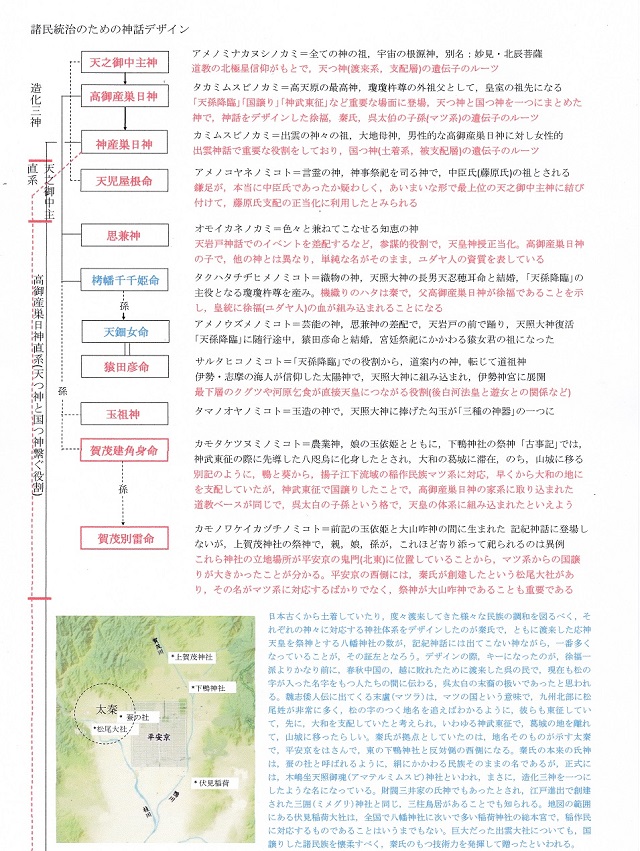
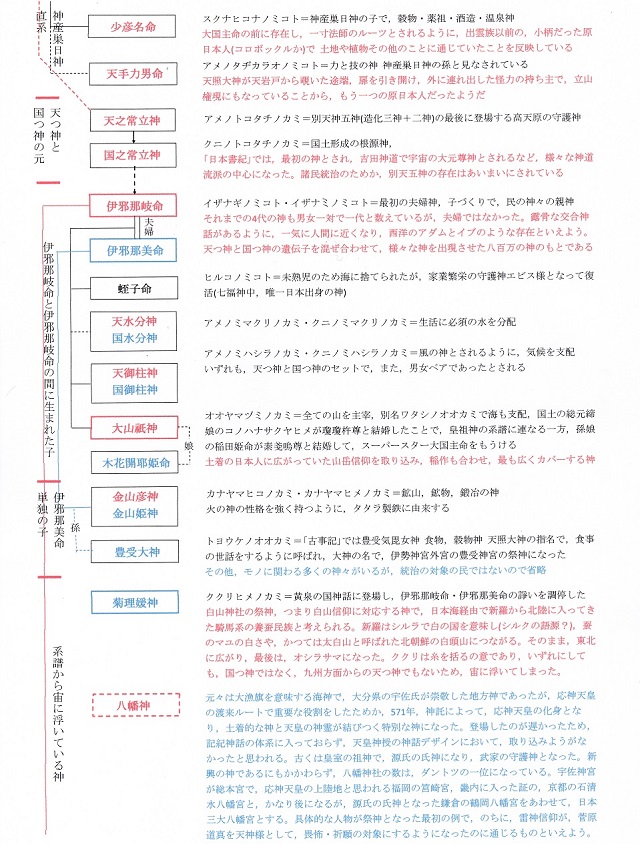
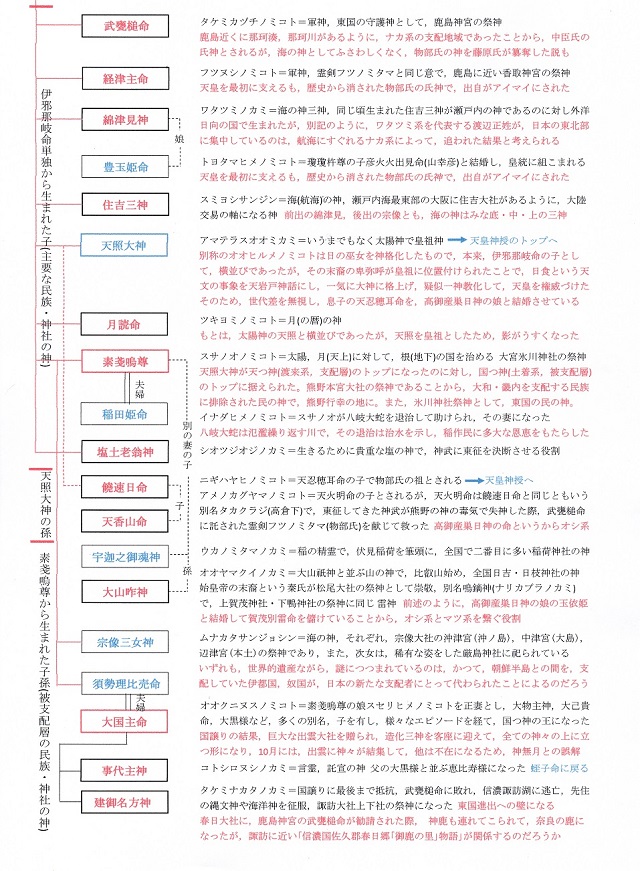
第3話:天皇交替と元号変更
明治維新後の初めての(異例な)天皇の生前退位によって,新天皇が即位し,元号が「令和」に変わった。「令和」の語そのものも話題になったが,この機会に,天皇の交替と元号の変更との関係を振り返ってみるべく,詳細な対照年表を作成してみたところ,そこからも,日本史の大きな状況を捉えることができる。
よく知られているように,元号は中国起源のもので,その昔,朝貢国であった韓国やベトナムなど広く使われていたが,近代に入ると,皇帝や王制の廃止とともに,本家の中国,台湾も含めて,使われなくなり,今や,天皇制の続く日本でのみ使われるものになってしまった。それほど,元号と天皇制とは一体のもので,日本文明の特徴の一つになってしまっているため,廃止論が出ても広がらないのだろう。
したがって,天皇の交替の際に元号を変更するというのが,原則であるのはもちろんであるが,それが法制度的に固定化されたのは,明治維新後のことで,かつては,天皇の権威を示すため,あるいは,利用するため,瑞兆や凶事等があった際にも,簡単に,元号が変更された。元号が頻繁に変更され,天皇すら交替が多くなるのは,その時代が,何等かの意味で,不安定であったことを示し,逆に,元号の変更が少ないほど,さらに,天皇の交替が少ないほど,その時代が,天皇の権威によって安定的に保たれていたことを示しているといえるだろう。
日本における元号の採用は「大化の改新」で有名な「大化」をもって始まるとされている。「大化の改新」そのものについては,その後の研究によって,「改新」そのものの存在が疑われ,時代のエポックとしては,「乙巳の変」というのが一般的になっているが,暦という人々の生活を制約するものに,初めて元号を採用したこと,つまり中国の方式を取り入れたという点に限ってみれば,日本史上の大きなエポックであったことは確だろう。
しかしながら,「大化」の次の「白雉」の後は,「大宝律令」で有名な「大宝」が登場するまで元号は無かった,つまり,天智,天武,持統天皇の間は,中国方式を取り入れることに抵抗が強かったか,躊躇したか,意識されなかったのか,いずれにしても,「大宝律令」という中国の法制度の整備とセットになって,ようやく定着したということになる。つけくわえれば,「大化の改新」の際には,法制度の整備が無かった,つまり「改新」はなかったということになるのではないだろうか。
持統天皇の没後,覇権を握った藤原不比等から,転変を経て,天皇制の最大の危機になった道鏡を,宇佐八幡宮の神託によって追放するまでの,いわゆる奈良時代は,「和銅」や「養老」など,主として瑞兆による元号や,孝謙(称徳)天皇時代に限られる四文字元号があったこと,どうも,新たな文化たる元号を楽しんでつけていたように見える。そのなかで,聖武天皇の在位に対応して「天平」が長く続いたことから,「天平文化」というように,その時代の文化を元号で一括表現できる利点も生まれ,のちの江戸時代の「元禄文化」「天明文化」「化政(文化・文政)文化」というように,気楽に使うようにもなっている。
宇佐八幡宮の神託で,新たに即位することになったのは,八親等も離れた光仁天皇で,その子桓武天皇へのつなぎの役割をし,さらに,その子の嵯峨天皇が主役の,いわゆる大天皇の時代(平安初期)になる。個々の天皇の寿命は短いながらも,「延暦」「弘仁」など,明治維新後のように,天皇交替と元号変更が,1対1で対応しているので,天皇の権威が強かったことも示される。
そして,再び藤原氏が覇権を握ることになるのが,嵯峨上皇崩御とともに起こした「承和の変」で,長かった承和の時代が終わるとともに,元号が立て続けに変更されることから,確かに,政治的危機があったことが伺える。その後は,「貞観」「延喜」など,時代を象徴する元号を代表に,天皇交替と元号変更がほぼ1対1に対応しているので,藤原摂関が他の氏を抑えて,それなりの安定を現出していたということになろう。
「承平・天慶の乱」,すなわち,平将門の乱と藤原純友の乱という天皇制をゆるがす大事件が起きて,平安時代も後半に入るのであるが,今度は,藤原一族のなかでの覇権争いから始り,東北地方での反乱や,仏教の末法思想も重なって,人心が不安定になったのを示すかのように,元号が頻繁に変更される時代が続く。白河上皇による本格的な院政に入ると,権威の異常化を示すように,元号の変更はさらに頻繁になり,そのまま,平家の登場から,鎌倉時代の武家政権へとなだれ込み,天皇の交替も,幕府の思惑によって,頻繁になってきて,天皇にとっては,元号変更でしか権威を示せなくなったこともあって,超頻繁といった状況になる。
執権北条時頼・時宗時代は,支配力が強かったこともあって,元号変更はやや減るが,その後は,後醍醐天皇が登場して鎌倉幕府が滅亡するまで,元号変更は超頻繁になり,時代の不安定さが強く示される。南北朝に入って,二つの元号が併存するという異常事態が続いた後,足利義満の力で南北朝が統一され,その子の足利義持もなお力をもっていたことから,元号「応永」が長く続くが,「嘉吉の変」から「応仁の乱」に至る,室町幕府崩壊のプロセスにそのまま対応するように,長く在位した,後花園天皇は,光仁天皇以来の八親等も離れた皇族から即位したため,自らの権威を高めるべく,頻繁に元号変更して権威を回復,「中興の英主」と評されるに至った。
その後は,戦国時代から江戸時代全般にかけて,天皇交替は,在位期間もそれなりに長く安定的になるが,天皇が完全に影のような存在になってしまったこと,将軍側からの圧力を受けるまでもない存在として,元号変更の頻度も少なくなったといえるのだろう。そのなかで,江戸幕府に抵抗して権威を発揮しようとした後水尾天皇が,結局,幕府の圧力に屈して譲位してしまい,後水尾上皇がなお存命中に登場した霊元天皇が再び権威を回復しようとするまでの期間と,桜町天皇時代,そして,維新前夜の孝明天皇時代に,一時的に元号が頻繁に変更されることからも,やはり,時代の不安定さを示すものになっている。
明治維新後の一天皇一元号という定めのもとでは,元号変更の頻度等から時代状況を推量することはできなくなってしまうのである。
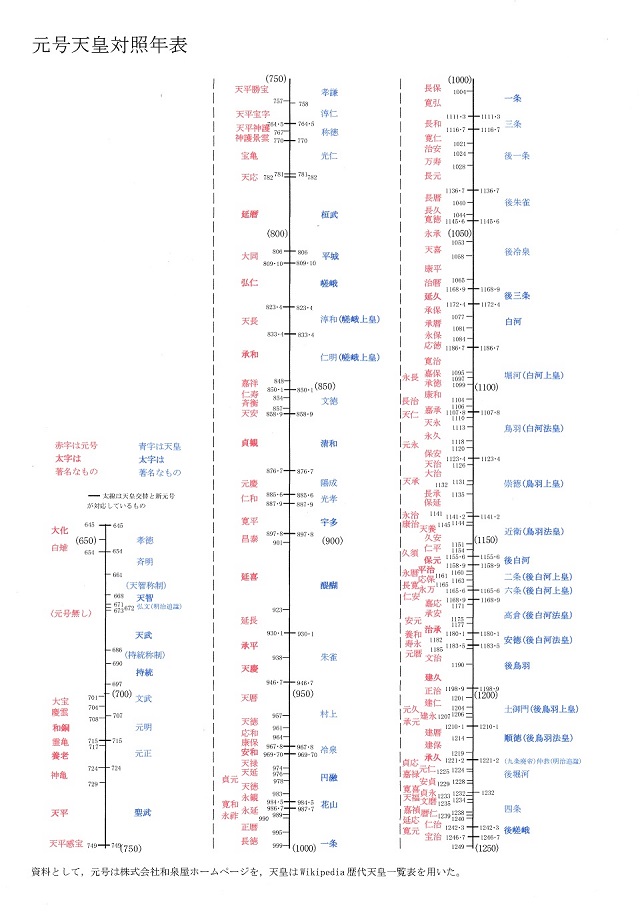

この章TOPへ
ページTOPへ