「心理学」(岩波文庫)
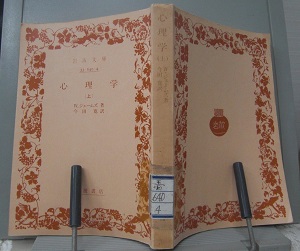
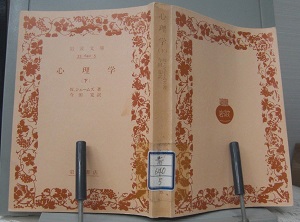
藤波尚美「ウィリアム・ジェームズと心理学」より
藤波は,「はじめに」で,「(前略)心理学科でジェームズを研究しようとして,疑いの目を向けられて,日本での評価の低いことを感じただけでなく,研究を進めるうちに,自身のジェームズ評価とアメリカでのジェームズ評価の温度差を痛感する記述に出合うことになった。それは,科学的心理学の誕生をドイツとアメリカにおける<二重の誕生>ととらえ,合理主義の伝統のあるドイツにおいてはヴントの「生理学的心理学綱要」(1874),経験論の伝統にあるアメリカにおいてはジェームズの「心理学原理」(1890)によって。科学的心理学が始まったと見るものであった。(後略)」と,本書を著す契機を述べている。>ドイツにあって,ジェームズを受け入れたユングは珍しい存在であった。第一章の最初に「心理学者ジェームズ」の項を設け,「一般にジェームズはプラグマティズムの祖として知られている。(中略)近年,プラグマティズムの再評価がなされるに伴い,ジェームズも見直されている。」というが,日本でのプラグマティズムの受け入れも中途半端に終わっていたと見てよいだろう。そして,心理学の教科書や心理学史において,ジェームズがどのように取り上げられてきたかに章を割いたのち,第五章で,ジェームズ自身の「心理学への希望と失望」を評伝的に語る。>ここに,ドイツの心理学者であったユングとの出会いの話がでてこないのが不思議であり,本書全体をとおして一言もないのは残念である。
第六章で「現代に生きるジェームズ」を取り上げたのち,最後の第七章に「人間ジェームズとアメリカ性」で,ジェームズが「憂鬱症の病気を癒し,慢性的な病的妄想を払いのけうるような心理学は,霊魂の本質に関する神々しい洞察よりも,確かに優れている。」述べていたというのは,実際に役立つことをめざすプラグマティズムであり,そういいながらも,「ジェームズにとって科学と宗教を和解させることが非常に重要な意味を持っており,心霊研究の主要な目的であった。」「宗教とともにジェームズの関心の焦点であったのは,人間性であった。「宗教的経験の諸相」のサブタイトルはまさに<人間性の研究>であるし,「プラグマティズム」においては,さまざまな哲学的な考え方の違いを哲学者の気質から説明しようとしている。」という。>ここに,ユングへの影響の核心があると思われる。
最後の最後を,「比類なくアメリカ的」とし,「会ったことのない心理学者にさえ,師として尊敬され,紙とインクにさえぎられたときでさえも依然として人間であり続けている。」との評価を引用,「ジェームズにとって心理学,ひいては科学が<目的それ自体というより方策>だという点である。これはヨーロッパと異なったアメリカ独自の科学観である。(中略)ヨーロッパの心理学よりも<プラグマティックで折衷的で楽観的>なのである。」と結んでいるが,この違いは大きいように思われる。
ジェームズ著作集「純粋経験の哲学」(岩波文庫)
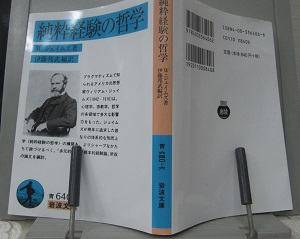
西田幾多郎「善の研究」(1911年)について
中央公論社「西田幾多郎(日本の名著47)」(上山春平編,1984年)収録による上山春平による「絶対無の研究」と題した西田幾多郎についての解説のなかの,「善の研究」の節に,「純粋経験と宗教的体験」の見出しがあり,西田が深い共感を示したベルグソンやジェイムズは,西田が「純粋経験」という概念によって示唆しようとした宗教的な解放感に近い主客未分,知情意未分の状態を,「純粋持続」とか「意識の流れ」ということばで表現した。ベルグソンの最後の著書が「道徳と宗教の二源泉」であり,ジェイムズに西田の愛読した「宗教経験の諸相」があったことは,おそらく偶然ではあるまいとある。西田はもちろんベルグソンに先立ってジェイムズが存在していること,年代からみても「純粋経験」そのものもジェイムズからの影響であったことあきらかであるなど,錯誤はあるが,三者が,相通ずる哲学者であったことをよく示している。
あまりにも著名で,日本人であれば必読といわれるような書なので,内容について立ち入ることは避けるが,以下に示す本書の章立て,つまりカタチからいえることのみ述べたいと思う。
第一編 純粋経験
第一章 純粋経験,第二章 思惟,第三章 意志,第四章 知的直観
第二編 実在
第一章 考究の出立点,第二章 意識現象が唯一の実在である,第三章 実在の真景,第四章 真実性はつねに同一の形式をもっている,第五章 真実性の根本的方式,第六章 唯一実在,第七章 実在の分化発展,第八章 自然,第九章 精神,第十章 実在としての神
第三編 善
第一章 行為 上,第二章 行為 下,第三章 意志の自由,第四章 価値的研究,第五章 倫理学の諸説 その一,第六章 倫理学の諸説 その二,第七章 倫理学の諸説 その三,第八章 倫理学の諸説 その四,第九章 善(活動説),第十章 人格的善,第十一章 善行為の動機(善の形式),第十二章 善行為の目的(善の内容),第十三章 完全なる善行
第四編 宗教
第一章 宗教的要求,第二章 宗教の本質,第三章 神,第四章 神と世界,第五章 知と愛
一見して分かるように,四つの編はいわゆる「起承転結」になっており,「純粋経験」から説き起こしているだけでなく,多くの章のタイトルからも,ジェームズからの影響は明らかであるが,それ以上に,「転」にあたる核が「第三編 善」であり,西田の独創が溢れている「善の研究」なのであることはいうをまたない。
その「第三編 善」のなかを見ると,善にかかわるものとして,まず「行為」を取り上げ,次にその背景となる「意志」にゆき,諸説を解説したのち,「善(活動説)」そのもの,つまり核のなかの核といえる章となり,ぞの動機,目的,それらをふまえた完全なる善行で終わるが,この編のなかでも,「起承転結」が全うされている。いずれにしても,「善」は行為が思惟でなく行為が前提であり,そのためには意志が必要であること,つまり「知情意」の「知」「情」ではできない,同情などは何の善でもないことを示していて,デザイン論で述べたことを強く裏付けるものといえよう。そのために,第一編で,「意志」の章立てしており,「第二編 実在」で,現実世界に関わることであることを示しているといえる。そして,結すなわち,善の極致になるのが「第四編 宗教」であるということは,近代社会が失った宗教(信仰)こそが「善」を体現するものであるということになる。>「デザイン三講」の概念のところでも述べたが,宗教こそ,最古で最大のデザインなのである。以下,核になっている「第三編 善」について,デザイン論と関係のありそうな記述を拾っていってみよう。
冒頭の第一章「行為 上」は,「人間は何をなすべきか,善とはいかなるものであるか,人間の行動はどこに帰着すべきかというような実践的問題を論ずることとしよう。しかして人間の種々の実践的方面の現象はすべて行為という中に総括できると思うから」と,「行為」について論じ始め,「本能的動作と区別すべき,目的が明瞭に意識せられている動作である。・・・今行為の意識現象を論ずるということはすなわち意志を論ずることになる。」としたうえで,「行為」と一体である「意志」がいかにして起こるかを論じ,「一の統覚作用である。」と,統合された意識であることを指摘,「或ることを想像することとこれを実行するのとはどうしても異なるように思われるのである。」と,まさにプラグマティズムそのもののようで,「統一作用の根本となる統一力を自己と名づくるならば,意志はその中にてもっとも明らかに自己を発表したものである。」>デザイン行為そのものを示すような論で結ばれている。
第一章「行為 下」は,「行為」がまた「身体」と一体であることを論じ,「第三章 意志の自由」は,ジェームズの「自由意志」と同様,「意志」は個々人に属する独自のものであることを論じ,「意識の根柢たる理想的要素,換言すれば統一作用なるものは,(第二編)「実在」で論じたように,自然の産物でなくして,けって自然はこの統一によりて成立するのである。こは実に実在の根本たる無限の力であって,これを数量的に限定することはできない。ぜんぜん自然の必然的法則以外に存するものである。われわれの意志はこの力の発現なるがゆえに自由である,自然的法則の支配は受けない。」と結んでいる。>デザインが(科学的)「知」とは別のものであることを示す根拠になりそうな言葉である。
核中の核「第九章 善(活動説)」は,第五章から第八章にかけての「倫理学の諸説」で,「善についての種々の見解を論じかつその不十分なる点を指摘したので,自ら善の真正なる見解はいかなるものであるかが明らかになったと思う」とした上で,「善とはただ意識の内面的要求より説明すべきものであって外より説明すべきものではない。」「善は何であるかの説明は意志そのものの性質に求めねばならぬことは明らかである。・・・意志は他のための活動ではなく,おのれみずからのための活動である。」「意志の発展完成は直ちに自己の発展完成となるので,善とは自己の発展完成であると見ることができる。すなわちわれわれの精神が種々の能力を発展し円満なる発達を遂げるのが最上の善である。」>その後に,わざわざカッコ書きで,アリストテレースのいわゆるentelechie(完成作用)が善であるとまでくると,残念ながら,西田にしてなお,西洋哲学の束縛のもとにあったことが分かる。
この後,善の概念は美の概念と接近してくる。」と,芸術との混同が生じ,「第十章 人格的善」「第十一章 善行為の動機(善の形式)」「第十二章 善行為の目的(善の内容)」をみても,混乱は続き,最後の「第十三章 完全なる善行」で,個人の中での統一が,すなわち社会との関係の一体化を実現するというような論になっている。>ユングのマンダラ論にも通じるが,それも含めて,残念ながら,日本独自の哲学までになっているとはいえないと思わざるを得ない。「善の研究」が,日本を代表するものになったのは,おそらく,それまでにはなかった完成された体系にあり,日本人をして,西洋に完全に追いついたと感じさせたことにあると思われ,結論的には,ジェームズの手の平の上にあったということになる。
私論になるが,要は,「他者」への,すなわち社会への視点が欠けていることが問題であり,デザイン論で述べたように,「知情意」「真善美」は本来,社会が成立するための共通基盤のためにあるということ,「知・真」は,社会での人々の(他者との)共通理解のためのもの,「情・美」は,社会での人々と(他者と)共感するためのものであるのと同様,「意・善」は,社会の人々に(他者)になんらかの形で役立つ,助けになること(言葉は悪いが共助)ということなのだろう。
余談ながら,本書(日本の名著47)の最後に収録されている「古義堂を訪う記」(古義堂とは伊藤仁斎の古宅跡)のなかに,「西洋は学,東洋は教え,学よりも教えというひとには,往々仁斎徂徠の学のごときを軽視する傾きがある。いわく山崎闇斎の学からは勤王の志士が出て,ついには維新の大業を成したが,仁斎徂徠の学にはそういうものは出ないと,とくに徂徠のごときはあたかも無用の学であるかのごとくに考える人もある。しかし私は闇斎を尊重するにやぶさかではないが,仁斎徂徠を軽視すべきでないと思う,教えには原理というもががなければならない。しかして原理というのは,人間の深い真実を把握したものでなければならない,すなわち真理でなければならない。(以下略)」と述べている。」>デザイン論で,「世界に誇りうる日本のプラグマティズム思想家・荻生徂徠」の項を置いたように,西田幾多郎が,ジェームズの影響を強く受けていたことを示すものといえるのではないだろうか。
ジェームズ「プラグマティズム」(岩波文庫)
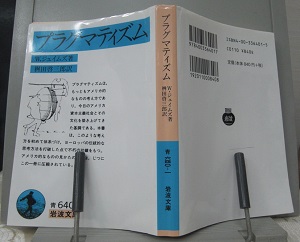
W・ジェイムズ著作集6「多元的宇宙」(日本教文社)
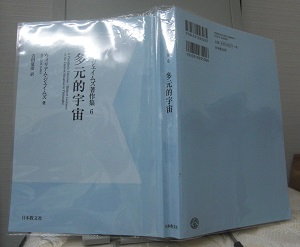
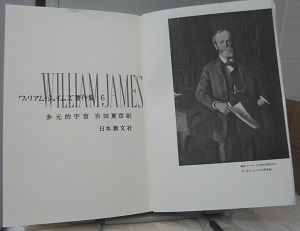
檜垣立哉(大阪大学)「ベルクソンとアメリカ哲学~ジェイムズとパースとの関連において~」
アンリ・ベルクソン(1859~1941)と,ウィリアム・ジェイムズ(1842~1910)およびチャールズ・サンダース・パース(1839~1914)という二人のアメリカの哲学者は,19世紀末の哲学的文脈を共有しているが,(本文中でみたとおり)ジェイムズは一世代若いベルクソンを高く評価して,書簡による交流まであった。心霊学まで含む心理学の研究をしていたことでも資質の近さを感じさせる一方,本来のプラグマティズムをはみ出すような思想的影響もあった。パースは直接的にはベルクソンに言及していないが,「多元的宇宙」本文で後述する付録で,ジェイムズが「パース氏の見解は,その到達する道は大変異なっている,ベルクソンのそれとはまったく合致している」と記しており,パースがジェイムズ宛書簡でこれを拒絶しているものの,重なる部分のあったことは否定できないいう。3人には,主として連続性を重視する点で共通し,とくに,ジェイムズとベルクソンの間には,純粋経験と持続ということで類縁関係にある。続けて,微分と連続性の思考の面をみると,両者がともに,グスタフ・テオドール・フェヒナーの思想に着目し,「ゼノンの逆理」から無限小の問題に接近していることが重要であるとする。その中で,西田幾多郎が,「善の研究」の「版を新たにするに当って」で,フェヒナーの「夜の見方に対する昼の見方」の文を引用するように,フェヒナーは「夜の見方」である科学に足して懐疑的な「昼の見方」を重視し,「純粋経験」に近い記述を称揚しているという。フェヒナーには「死後の生活についての小冊子」という著作もあって,ジェイムズの注意を引いているが,このことも,ジェイムズを介して,ベルクソンとフェヒナーの重なりを考える可能性を開いているという。後半は,「パースとベルクソン1 実在論」と「2 方法論」として,ジェイムスと同じくらいの分量割いて論じていることを記すにとどめておく。
猪口純「ジェイムズ『多元的宇宙』のプラグマティズム」
序章の冒頭は,「思弁的<プラグマティズムの復権>」で,<プラグマティズム>とは,観察可能な現実における具体的効果のうちに物事の本質を看取しようとする思考形式の総称であるとした上で,そのことへの理解が進まず,プラグマティズムの大成者ジェイムズが描写した宇宙論が,プラグマティズムの方法に関する深い洞察と,その方法に則った幅広い知見の総合によって導出された理論でありながら,プラグマティストの仕事して紹介される例は稀であるとし,次の「<ただひとつ>が真理なのか」で,ジェイムズは,科学であれ宗教であれ,諸対象それぞれの持つ独自の実在性を,そしてまた我々一人一人の内的経験を,最終的に幻想と断じて非現実に帰してしまうような考え方になっていることについて,我々に,今一度自らに向かい真剣に問うてみよと迫ったのであるという。そして,「いっそう<あり得そうなこと>は何か」で,ジェイムズの著書「プラグマティズム」の大半は,二者択一の形式によって絶対的な判定を求めてやまない我々の習慣に対する批判で占められているが,真に重要なのは,「真理の複数説」と一体で打ち出された意識現象・意識経験の実在性の肯定であり,実際あり得そうなことは,「個々の意識が受け取りまた作り出すことこそが物事の大もとであって,我々が普段客観的な世界とみなしているような時間・空間・歴史の方が二次的な派生物ではないか」との仮説に到達し,ただひとつ・ひとつづきの現実が存在するとするより,無数の現実があるという仮説の方が,より<経験>に即している点で蓋然性があるのではないかと主張している。>一連の説明は,きわめて分かりやすく,プラグマティズムの本質をついているだけでなく,デザイン論にとって,現実が無数であるがゆえに,未来に向けてより適した答えを見出すためにこそ,デザインの必要性があるという,これまた本質的な理由を明示しているといえよう。
続く「プラグマティズムの逆説」で,ジェイムズが,人間とは「認識的生活においても行為的生活においても創造的」で,実際に「真理を<生みつける>」存在である,つまり人間は,あるときには既存の,実際的な作用と同義の<実在>に再形成を施し,またあるときには既存の諸力を素材として新しい<実在>を付け加えているという。>人間みなデザイナであるというデザイン論の裏付けに聞こえてしまうが,猪口が,経験論的には飛躍と思えるような見解という語を挟んでいるのは,まさに,「知」の世界の論にはなり得ないということ,言い換えれば,「意」の世界に入ってしまっているということなのだろう。 そして,この項の最後に,プラグマティズムの大元となったチャールズ・S・パースの思想との間の,懸隔と近似,<経験>という概念の適用範囲を大きく押し広げた根本的経験論と古典的経験論との距離,額面上親和的に見える多元的宇宙と多世界・複数世界説との差異,政治社会的実践における応用を旨としたネオ・プラグマティズムとの基本的態度における不一致,科学的知見に依拠したシステム論的思想との共通点と対立点などが,ジェイムズの思想を際立たせるとして論を進めるとし,「<多元的宇宙>概観」で,①多元的宇宙において,現象することと実在することとは同義である(現象即実在),②多元的宇宙は複数の<宇宙>によって構成される。ここで<宇宙>とは組織的まとまりを持つ個的存在の毎瞬間の<経験>を意味する,③<宇宙>は<純粋経験>と同義である。各<純粋経験>は<私有化>の機能を有し,個別に統一を志すと整理してくれている。>ユングの思想に直接的につながるものであることも理解できよう。 序章最後の「ジェイムズ再読の今日的意義」で,最終的に<何も捨て去らない>ヴィジョンが経験論的態度の貫徹によって,あるいは少なくとも経験論的態度を貫こうとする意志の帰結として形成されている事実に目を向ける必要があると言い,ジェイムズが,すべての個的存在=純粋経験に統一への意志をもった主体性を認め,ひいてはあらゆる個的存在に幾ばくかの心的要素が具わっていることを認める汎神論的立場に我々を引き連れていくという。>デザイン論の書としても意義のありそうな書であるといえる。
あとの本文は読んでもらうこととして省略するが,最後にあたる第4章「多元的宇宙論のシステム論的解釈~その有効性と限界」の第3節「四象限の累進的進化の構図~内面性の復権」に,一般にニューエイジ思想の代表的論客として知られるウィルバーを取り上げ,1990年代半ば頃から少なくとも2006年前後までの彼の思索は,自らの実践的関心(瞑想を通じた各人の自己内省の理論)を離れ,万人が立場によらず応用可能な,領域横断的・統合的視座の確立を志向,中期ウィルバーと呼ばれるこの期間の理論的考究の最大の成果が,古今の世界観や思想的見地を四つに区分する,四象限の図式であると紹介している。>この図をみるとすぐに,個的で内面的という「私・意志的」という象限がユングに,集合的で内面的という「私たち・文化的」という象限がデザインに対応するものであることがつかめるので興味深く,本講義の最後(第三講の最後)に,ケン・ウィルバー「インテグラル心理学~心の複雑さと可能性を読み解く意識発達モデル」(2000年,日本語訳は門林奨で,2021年,日本能率協会マネジメントセンター)記すつもりである。
W・ジェイムズ著作集2「信ずる意志」(日本教文社)
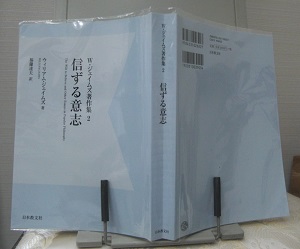
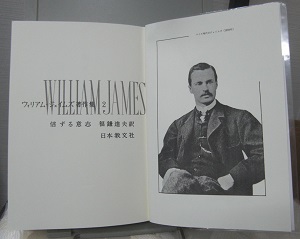
ジェームズ「宗教経験の諸相」(岩波文庫)
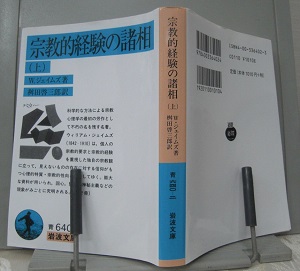
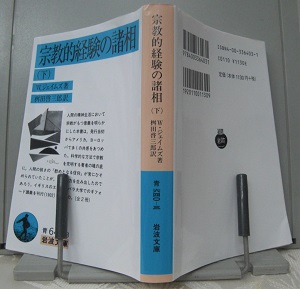
はじめに一言:ユングがジェームズから影響を受けたとすれば,そもそもジェームズがどんな人物であったかを知らねばならない。下記の小目次を見るだけでも,ある程度,想像できるのと思われるが,やはり,中身を良く読んで欲しい。>以下は補足のコメント
小目次
・・第一論:そもそも,アメリカに心理学を拓いて知られるようになった
・・・・・・第一話:大著「心理学原理」を出版するまで
・・・・・・第二話:ジェームズの心理学(短縮版「心理学要論」の内容)
・・・・・・第三話:パース,プラグマティズムと出会って,哲学を志向するようになった
・・第二論:そして,プラグマティズムを哲学として広めて,世界的になった
・・・・・・第一話:西田幾多郎にまで影響を与えた「純粋経験」の哲学
・・・・・・第二話:講演記録「プラグマティズム」が出版され,アメリカの哲学になった
・・・・・・第三話:ジェームズの世界観の集大成「多元的宇宙」を遺した
・・第三論:さらに,独自の宗教観もあり,ユングを掻き立てることになった
・・・・・・第一話:信仰・道徳に関する諸論文を自らまとめた「信ずる意志」
・・・・・・第二話:ユングに決定的な影響を与えた「宗教経験の諸相」
・・・・・・第三話:小木曽「ユングとジェイムズ」にみるユングへの影響
第一論:そもそも,アメリカに心理学を拓いて知られるようになった
ジェームズ「心理学要論」(1892年,今田寛の日本語訳「心理学」(岩波文庫,上が1992年,下が1993年)による)⇒フォト
第一話:大著「心理学原理」を出版するまで
今田寛の解説によると,ウィリアム・ジェームズは,1842年,アメリカのニューヨークで生まれ,実業界で成功した祖父の遺産で経済的に恵まれ,生涯定まった職業を持たずに,思索,執筆,講演,交友との論争を送っていた父ヘンリーの方針で,正規の初等教育を受けず,家庭教師と度々のヨーロッパ長期旅行で教養を身につけ,自由で知的な雰囲気のなかに育った。兄弟の一人には,後に小説家として名をなしたヘンリーがいる。>ちなみに,日本語訳のあるヘンリーの「鳩の翼」を読むと,プラグマティズムを小説にしたような作品である。
様々なことに興味を持つようになって,シラキューズ大学を卒業後,ブラジル探検に参加して,生物学への関心が高まり(Wikipediaによる),1861年(19歳),ハーバード大学の理学部に入り,化学,解剖学なども専攻したが,1864年に医学部に入り,1869年(27歳)に卒業,医学博士になるものの医者になる気はなく,30歳になるまでの3年間,精神的危機に陥って療養生活を送り,幅広い読書を日課とする。>互いに類似する時期があったも,ユングと意気投合した理由になろう。 自らの適性として,家庭時代には画家を,学生になってからは哲学をめざすことを考えていたという。>まさに自らの専門の定まらない,というよりは専門家になりたがらない性格が出ており,学者になるようなタイプではなかった。私自身にもそういうところがあるので共感できるし,また,ユングにも大きな影響を与えたように,人々を啓蒙,先導していくような人物であったといえる。
医学部を中断して,ヨーロッパに滞在しているときに,心理学に興味を持ち,卒業後は心理学関係の書を読み漁っている。>自らの適性を知ろうとしていたことに関係すると思われ,また,心理学が,ユングの育ったドイツを中心とするヨーロッパで盛んであったこととも関係,これもまたユングと意気投合する理由であったろう。 卒業後,精神的危機に陥った際,1870年(28歳)に,フランスの哲学者ルヌヴィエールの考えに接し,意志と自由の有効性を信じる行為を知ったことから,脱出できたという。>のちにプラグマティズムの啓蒙者となる原点になったと考えられる。 そして,1872年に,学生時代の化学の教師であった,ハーバード大学総長のエリオットから生理学の講師に任命され,以後,1907年に引退するまでも35年に及ぶ教壇生活が始まり,心身ともに救われるのである。>学者には適していなかったが,教師という啓蒙者は,最適の職業であったといえる。
1875年に「生理学と心理学の関係」という題で講義を始め,自らは好まなかった実験室も設置,アメリカの大学における,最初の心理学の講義であり,実験室になった。1876年には助教授になり,「生理学的心理学」を開講,教科書にはスペンサーの「心理学原理」を用いた。1874年以来,出版社ホルトが,アメリカ人の学者による,進化論を基盤とした「アメリカ科学叢書」の出版を企画していたが,1878年に,その一冊として依頼されたのが「心理学原理」で,執筆期間2年,教科書として使えるよう500ページ程度の約束であったが,結果として,12年を要し,1890年に出版されたときには,28章構成,二巻,1393ページもの大著となり,「アメリカ心理学の独立宣言の書物」として不朽の名著になったのである。しかるにあまりにも大部であったため,1892年に短縮版「心理学要論」が出版された。
この間,1878年の結婚後,1880年には哲学の助教授となり,1885年には教授に昇格,「心理学原理」「心理学要論」の出版後は,心理学者と呼ばれるより哲学者と呼ばれることを好むようになった。1902年に,病める心を扱って,宗教心理学のみならず臨床心理学の古典にもなった「宗教的経験の諸相」を出版して以降は,1907年(65歳)の「プラグマティズム」はじめ,哲学の著作が続くことになる。>いずれも,ユングに強い影響を与えたものなので,第二,第三論に譲る。 名声が高まって,アメリカはもとよりヨーロッパの方々の大学から講演に招待され,名誉学位を受け,一般の人たちを対象にした講演も増えて,影響力が高まったが,1907年,病弱を理由に退職し,前述のように,哲学的著作を続け,1910年に没した。>ユングは,ジェームズの最晩年出会ったのである。 アメリカ心理学会の第3代,第14代会長をつとめたが,また,生涯にわたって関心をもった心霊学の学会にも属して,副会長,会長をつとめた。>ここでも,従妹の影響で降霊術に興味を抱くようになっていたユングと意気投合しただろう。唐突ではあるが,ニュートンが魔術に心酔していたように,単なる「知・真」を越えた,不可解なものに惹かれることが,大きなことを成し遂げたり,多くの人に影響を与えるような人物に共通しているようにみえる。
今田寛のあとがきによれば,本書の日本における翻訳は三度目である。第一回は,福来友吉によるもので,(原書出版10年後の)1902年に同文館から出版され,二回目は,今田寛の父今田恵により,1927年に,岩波書店の「心理学名著叢書」の第一巻として出版され,1939年に岩波文庫に入れられて以降,版を重ねたが,1976年を最後に絶版になっていたので,それ以来17年ぶりであり,原書の出版以来,ちょうど100年目ということになる。>帝大で心理学を教えていた福来友吉は,33歳の時,この書を翻訳して催眠術に興味を抱くようになり,日本の超心理学のパイオニアになって,"念写の福来"として世界的な心霊学者になるも,帝大を追放されてしまう。
第二話:ジェームズの心理学(短縮版「心理学要論」)の内容
本書の冒頭には,ジェームズが書いた「序」があり,「(前略)私はこの<序文>を利用して「心理学原理」について一言述べることを禁じ得ない。私の批評家が大体において非常に寛大であったことに対して私は心から感謝しなければならない。しかしこの人たちは,私の章の配列が無計画で不自然であるという非難と,これに対する一つの同情的な弁解,すなわちこの書物は大部分雑誌論文を集めたものであるから,一つの型にはめてつくられた論文のような体系を望むことは無理であるという弁解,この二点において一致していた。(中略)私は,われわれの最もよく知っている具体的な心的側面から始めて,抽象作用によって後に自然に知るようになるいわゆる要素に進むのが適当な教授上の順序であると思ったために,意図的にその順序に従ったのである。心をその「構成単位」から「構築する」というこれと逆の順序には,説明上の優雅さという利点はあり,それによって整然と整理された目次をつくることはできるけれども,この利点はしばしば現実と真実を犠牲にして獲得できるものである。(中略)われわれに与えられたままの具体性をもって意識状態全体にできる限りの注意を払うことによって,実際には心をより生きた状態で理解できるものと考えるのである。この細分された要素の死後研究は,人為的抽象による研究であって,自然事物の研究ではない。(後略)」と述べざるを得なかった。>演繹的思考に毒されれている「(科学至上主義的な)学問」の,いわゆるアカデミスムが大きな問題であることを批判すると同時に,プラグマティストとしての面目躍如で,心理学のように,人間社会に直接関わるようなものになれば,というより,研究論文の体裁よりも,具体的成果の方に意義があると思えば,パースの言うアブダクション的論述が適当であることを示しているといえる。
とりあえず,章立てと分量(ページ数)を示しておく。
| 第一章 | 序章 | 10p |
| 第二章 | 感覚総論 | 26p |
| 第三章 | 視覚 | 25p |
| 第四章 | 聴覚 | 16p |
| 第五章 | 触覚,温度感覚,筋肉感覚,痛覚 | 20p |
| 第六章 | 運動の感覚 | 9p |
| 第七章 | 脳の構造 | 15p |
| 第八章 | 脳の機能 | 34p |
| 第九章 | 神経活動の一般的条件 | 18p |
| 第十章 | 習慣 | 23p |
| 第十一章 | 意識の流れ | 34p |
| 第十二章 | 自我 | 57p |
| 第十三章 | 注意 | 30p |
| 第十四章 | 概念 | 8p |
| 第十五章 | 弁別 | 13p |
| 第十六章 | 連合 | 35p |
| 第十七章 | 時間の感 | 10p |
| 第十八章 | 記憶 | 21p |
| 第十九章 | 想像 | 15p |
| 第二十章 | 知覚 | 31p |
| 第二十一章 | 空間の知覚 | 21p |
| 第二十二章 | 推理 | 26p |
| 第二十三章 | 意識と運動 | 4p |
| 第二十四章 | 情動 | 24p |
| 第二十五章 | 本能 | 33p |
| 第二十六章 | 意志 | 61p |
| 終章 | 心理学と哲学 | 11p |
| (序章と終章を除いた本文の計) | 603p |
第一章「序章」で,「本書では心理学を一自然科学として取り扱うつもりである。これには一言の説明が必要である。大抵の思想家は,すべての事物に関する<科学>は根底ではただ一つあるのみで,すべてが知りつくされるまでは何一つとして完全に知ることはできないという信仰をもっている。」と,科学至上主義を痛烈に批判し,「心の状態,およびそれが経験する認識に関する暫定的知識体系こそが,私が一自然科学としての<心理学>と称するものである。(中略)不完全な言述も,しばしば実際上は必要である。」とし,「本書において触れることができるのは,ただ人間の心のみである。」と,動物実験などは参考程度に過ぎないとし,「心的事実はこれが認知する物的環境と切り離して研究することは適当ではない。」し,「心的生活は元来有目的的である。」,そして,「意識の状態の直接の条件は大脳半球における何らかの活動である。この主張は多くの病理的事実の支持を得ており,生理学者の理論の根底に横たわるものではあるが,決定的証拠をあげることは困難である。」「生理学的心理学の根底にあるのは,作業仮説であり,不十分であることを確かめる唯一の方法は,目の前に現れるすべての場合にこれを真剣に適用みることである。」と続けていることから,しつこいようであるが,ジェームズは,プラグマティズムが身についていたといえ,最後に,論の組み立ての基本として,解剖学的に神経系統が三つの主要な部分,(1)刺激流を内部に伝達する線維,(2)刺激流を転向する中枢器官,(3)刺激流を外部に伝達する線維があり,(1)は感覚,(2)は大脳作用(あるいは知的作用),(3)は動作の傾向に対応,曖昧な点があるが,実際上の便宜があるから,反対意見はあろうけれども許されるものと思う。」と,述べていることからも揺るぎはない。>パソコンに例えれば,(1)は,キーボードやファイル読み込みなど,何らかの形でインプットすること,(2)は,パソコン内で,何らかの計算や変換をすること,そして(3)は,モニターの画面上や,DVDなどにアウトプットすることに似ている。
第二章「感覚総論」から第六章「運動の感覚」までの90p分(序・終章を除いた全体の約7分の1)が,(1)の感覚に対応するのはいうまでもなく,主として生理学的に詳しく解説,,大学で生理学を担当していたジェームズの該博な知識が示されている。そして,第七章「脳の構造」から第十章「習慣」までの90p分(感覚と同じ量)が,(2)大脳作用に対応するのもにあてられている。第八章までは,その後の研究が大きく進んでいるため,今田が解説で述べているように,今日的意味なくなっているが,とくに,「神経活動の一般的条件」で,「習慣」を非常に重要な条件であると,章を改めて(第十一章)論ずることに注目しておく必要がある。「神経中枢,特に大脳半球が習慣を獲得する能力のことである。獲得された習慣は,生理学的見地から見れば脳内に形成された神経発射の新通路に他ならず,それによって以後入って来る刺激が流れ出ようとするのである。観念の連合,知覚,記憶,推理,意志の教育なども,正にそのような発射通路が新たに形成された結果として理解するのが最もよい。」と,(3)の動作の傾向へのつなぎとしている。>その後に続く,習慣を身につけることの重要さについての解説を読めば,そのほとんどが「意(志)」に通じるものであり,パースも習慣を重視していて,プラグマテイズムの本質を表すものの一つであることを付け加えておきたい。 そして,(1)感覚と合わせても,全体の3割にしかならず,ジェームズが動作の傾向という表現を用いているのは,その後の章立てを見れば分かるように,動作それ自体よりも,どのような動作として表れるか,抽象的あるいは哲学的に把握するもので,ジェームズの考える心理学の本質が示され,ユングと意気投合したばかりか,現代心理学の源流とみなされるようになったといえよう。
その最初の第十一章「意識の流れ」であるが,今田が解説で,「ジェームズはその心理学の方法として内省(内観),それも,あるがままに見る自然な自己観察を用い,意識の特徴として<流れ>を見出した。<意識の流れ>はジェームズの心理学の中心である。(中略)意識を要素に分かたず,まとまりある全体としてとらえる姿勢はゲシュタルト心理学を思わせる。<泣くから悲しい><逃げるから恐い>のであって,その逆ではないといい,後に,ジェームズ・ランゲ説(情動の末梢起源説)として知られるようになる。」と述べている。>本書の核になる章であり,ユングに影響を与えたのはもちろん,一般に衝撃を与えたことは想像にかたくない。まさに,プラグマテイズムによる固定観念を覆すようなものといえる。
次の第十二章「自我」は最後の,第二十六章「意志」に並ぶ多くのページが割かれており,個々人の違いを重視する姿勢が明らかである。(1)被知の自我では,「人が我と呼ぶものと我がものと呼ぶものとの間の区別をするのは困難である。」とし,客我の三つの構成要素それぞれについて,「身体がわれわれ各人の物質的客我の核心である。」「人の社会的客我とは,彼がその仲間から受ける認識である。」「精神的客我とは,私の意識状態,心的能力,諸傾向を具体的に集めた全体の意味である。」とする。次に来るのが,「構成要素が引き起こす自我の感情および情動,すなわち自己評価」で,最後に,「構成要素が促す動作として,自己追求と自己保存があり,これらの言葉には,われわれの根本的な本能的衝動を数多く含んでいる。」と指摘,さまざまに解説したのち,最後に,物質的,社会的,精神的客我と,自己追求,自己保存をタテヨコにクロスさせた表にして,対応する事例を書き込んでいる。(2)知者としての自我では,「経過的意識の統一」「別個の心的状態は<融合>し得ない」「結合媒体としての霊魂」「人格的同一の感」「被知の自我の同一性」「知者としての自我の同一」「主我が客我を取り入れる方法」「自我の変化と複雑化」と,いわゆるアイデンティティの確立や崩壊に関わる事項を説明した上で,「異常妄想」「転換的自我」「霊媒あるいは憑依」ついて,心霊学に強い関心を抱いていたジェームズらしい解説で終わる。>最後の結びのところで,神の存在,信仰についても公平に論じるべきであるとしているところまで含めて,ユングと共感するところがあったと考えられる。
第十三章「注意」から第二十五章「本能」までは,自我が,これら多くのことそれぞれや,その組み合わせによって,最終的な反応に結びつくことを,懇切丁寧に説明していて,納得させられるものであり,第十四章「概念」は,ページ数は非常に少ないものの,「異なる心的状態が同じ意味をもち得る。」「抽象的,普遍的および蓋然的対象の概念。」「何物も,新しい心の状態で概念されなければ,同じものと概念され得ない。」と,要点を突いていること,第二十二章「推理」に,「類似連合による援助」の項があり,「(前略)ミルの論理学を読んだ人であれば,彼の有名な<実験的研究の四方法>すなわち類同法,差異法,剰余法,共変法の中の功利(ユティリティ)の基礎としてすぐに認められるであろう。これらはすべて類似の事例のリストを提供しており,その中から求める性質がころがり出て心を打つのである。そこで類似による連合が高度に発達している心は,このような事例のリストを自発的に形成する心でることが明かである。(中略)天才とは類似による連合が異常に発達している点において凡人と異なっていると考えることは一般に異論のないところである。」とあるのは,まさに,デザイン論で,暗黙知の一つのキーとしたアナロジーの話を強く裏付けるものである。第二十四章「情動」では,「環境内のある対象に対して特徴的に感じる傾向が情動であり,行動する傾向が本能である。(次章で,全ての衝動は本能であると言っている。)」と明確に区別し,「情動の種類は無数である。」という。>ジェームズは触れていないが,芸術につながるものであることはいうまでも無いであろう。
本文最後の第二十六章「意志」は,最後に置かれただけでなく,最も多くのページを割いている。>第十二章「自我」で述べたように,それと対応して,ジェームズの言いたかったことの多くが詰め込まれているのはもちろんであるが,「意」を根拠とするデザイン論にとっても重要であるに違いない。 まず有意的動作として「欲望,願望,意志は誰でも知っている心の状態で,定義によってこれ以上明らかになるわけでないほど自明である。(中略)目的がわれわれの力の及ぶところにあると信ずるならば,われわれは欲望し,所有や実行が現実のものになることを意志する。そして意志するや否や,あるいは一定の準備条件が満たされた後に,それはまもなく現実になるのである。」といい,「今まで述べてきた自動的,反射的なものではなく,予め欲望され意図されたものであるから,なんらかの見通しをもってなされるということで,第二次的行為であるということを,意志の心理学はまず理解して置かねばならない。」「(目的遂行のために)滞りなく抵抗なく動作が継続して起こるための決定条件は,心の中に葛藤する観念がないことのように思われる。」>統合されているということだろう。 「決断そのものの形式について見れば,五つの主要な類型に区別できる。その第一は,合理的類型といえるもので,新しい問題が起きる度に戸惑うことのないよう,推理の場合と同じように,正しい概念を追求することである。具体的なジレンマは名札をつけて現れるものではない。賢い人というのは,特殊な場合の必要に最もよく適合する名称を見つけることのできる人である。<合理的な>人は,ある動作がいずれの役に立つか有害であるかを平静に確認するまでは,その動作について決定しない人である。そして,全ての証拠が<揃う>前に最終的な命令を下す二つの類型があり,第四の類型は突然に思慮が終結する。第五の最後の決断の類型では,証拠は全て揃っている前提で,合理的清算がなされたという感じが存在する場合は,それを理由に天秤を傾け,しない感じがしている場合は,自らがいわば創造的寄与によって天秤を傾けるという,ゆっくり静かな意志の高まりがみられる場合であるが,意志の高まりとは形而上学に何を示すのかは,分かっていない。」その後,「努力の感じ」「意志の(不)健全」「爆発的意志」「阻止性意志」などを論じ,「努力は一つの本来的な力のように感じられる。」という時,意志を鍛えて,健全なものにすることの意義を言い,「動作の源泉としての快苦」のところで,やや唐突に,「<善>という種類は<快>という種類よりもはるかに多数の行動動機を含んでいる。」と出てくる。>デザイン論でも述べているように,西洋における「善」が,アリストテレスによる「自らにとって快いこと」に拠っているがためのものであろう。「意志とは心とその<観念>の間の関係である。」「意志的努力とは注意の努力である。」ときて,最後に,「<自由意志>の問題」「努力現象の倫理的価値」とあるのは,自らも述べているように,終章「心理学と哲学」に入ってしまっているもので,もはや心理学者より哲学者たらんとするジェームズのはやる気持ちが表れていると言えよう。
ジェームズの心理学については,「心理学原理」出版120年を記念するかのように,藤波尚美「ウィリアム・ジェームズと心理学~現代心理学の源流」(勁草書房,2009年)が出版されているので紹介しておく。⇒コラム
第三話:パース,プラグマティズムと出会って,哲学を志向するようになった
プラグマティズムは,1870年代初頭,マサチューセッツ州ケンブリッジの,パースとジェームズを含む若手学徒6名が,皮肉を込めて名付けた「形而上クラブ」での討論から始まったとされ,背景も立場も異なる彼らに共通していたのは,カントの哲学への反省を踏まえて,人間の思考は本質的に行為と結びついたものであるという認識であり,1877年に,パースが,これらを体系的に整理し,「われわれの観念を明晰にする方法」を発表,このなかで,「プラグマティズムの格率」を提示したことに始まるのである。その語は,カントが用いた(英語では)プラクティック(実践的)とプラグマティック(実用的)について,前者が「実践理性批判」に対応する抽象的な語であるのに対し,ギリシャ語で「行動」を意味する後者こそが,人間の幸せという目的に結び付くものであるとパースがこだわったことによってつけられたという。>まさに,"用"の哲学であるといえる。
パースによって打ち立てられたプラグマティズムを自らの哲学的背景とし,プラグマティズムを社会に広めることが自らの使命であると,様々な啓蒙活動を続け,その後20年もたった時に,すでにアメリカを代表する知識人になっていたジェームズが,カリフォルニア大学の哲学会の講演で,友人パースの説として,「プラグマティズムの格率」を紹介したことで一躍脚光を浴びることになり,1906年末のボストンのロウエル大学,翌年初めのニューヨークのコロンビア大学で講演,その記録が,ジェームズの代表的著作「プラグマティズム」として出版され,ユングも愛読したという。実は,パースが構想したものとは大分隔たりがあったようで,近年では,原典たるパースへの回帰が進んでいるが,ユングは,ジェームズの強調した「相互に違った価値観を認め合う多元主義」,つまり,真理は永遠普遍の絶対者によって規定されるものではないという考え方に強く共感するとともに,心理学者でもあったジェームズは,気質の違いの類型化を提示,哲学の歴史が合理論と経験論の対立の歴史になっているのも,その気質の違いによるとした。>その影響を受けたことが,「タイプ論」に結実していったことは疑えない。
これで分かるように,ジェームズは,ハーバード大学の講師になるのとほぼ同じ頃から,「形而上クラブ」の仲間とともに討論を始め,「心理学原理」に取り掛かったのは,パースによって,プラグマティズムが示された直後であったということで,それをまとめるのにかけた12年の間も,それと並行して,プラグマティズムを深化させ,1890年の出版後は,プラグマティズムを広めることを自らの使命とするようになったのも当然であった。そして,「心理学原理」によって,その名が世界的に知られるようになったこともあって,後述するように,西田幾多郎らにまで影響を与える著作を次々と発表するようになったのである。
この論TOPへ
ページTOPへ
第二論:そして,プラグマティズムを哲学として広めて,世界的になった
はじめに一言:代表作の「プラグマティズム」の講演・出版は晩年になるが,それまでに,プラグマティズムに関わる多くの論文を発表し,また,「プラグマティズム」後,死去する直前には,集大成となる「多元的宇宙」の講演・出版があるので,以下,順を追ってみていきたい。
第一話:西田幾多郎にまで影響を与えた「純粋経験」の哲学
まず,「プラグマティズム」に至るまでの著作を,伊藤邦武編訳によるジェームズ著作集「純粋経験の哲学」(岩波文庫,2004年)によって見てみよう。⇒フォト
伊藤邦武の解説によれば,「本書は,「純粋経験の哲学」という表題の下に,アメリカの哲学者ウィリアム・ジェイムズの形而上学,あるいは彼の言葉でいう「世界観」を展開した諸論文をまとめて,一書としたものである。ジェイムズはこれらの論文を発表する以前に,すでに「心理学原理」(1890)や「宗教的経験の諸相」(1902)によって,記述的心理学と宗教心理学の分野で国際的な名声を博していた。また,哲学者としては,プラグマティズムの立場に立った,真理の理論や信念の理論を発表し,国内外で論争の的になっていた。しかし,彼自身は,そのその宗教心理学やプラグマティズムの認識論を基礎づけるために,形而上学の体系的構築が必要であることを痛感して,1904年から1905年にかけて,集中的にこのテーマを追究し,その成果を一連の雑誌論文として発表していった。そして,1908年から1909年にオックスフォード大学で「哲学の現在の状況について」という表題の下で連続講演を行ない,その講演原稿を「多元的宇宙」として出版する際に,これらの形而上学的論文の一部を,その補遺として巻末に加えることにした。このことは,「多元的宇宙」の思想が1904年から1905年の諸論文の延長上にあり,それをさらに発展させたものであることを意味している。そこで,本書では1904年から1905年の形而上学的論文の主要なものと,「多元的宇宙」での主要な議論が窺われる部分と合わせて一書とすることで,ひとつの世界観としてのジェイムズの体系を提示してみようとしたのである。」としている。
そして,伊藤が「ジェイムズにとって'今では物事を他のパターンでは考えられない'というその思考のパターンが,純粋経験の哲学であり,根本的経験論の方法」で,「ジェイムズの哲学から~少なくともその思想展開の一時期において~強い影響を受けたベルクソン(1859~1941),ラッセル(1872~1970),西田幾多郎(1870~1945)らは,いずれもジェイムズの思想を単なる哲学における方法論の刷新ということ以上に,新しい形而上学の構想と解している。彼らはこの哲学の革新性に強い感銘を受けるとともに,それを修正したり,あるいは乗り越えようとするなかで,彼ら自身の独自の哲学を練り上げていったともいえるであろう。」というように,哲学史上,巨大な革新であり,巨大な影響を及ぼしたものであるといえよう。とくに,デザイン論でも触れたように,西洋であいまいな,ジェームズですら明解になっていない「善」について,ジェームズの「純粋経験」の影響を受けた西田の主著「善の研究」について,本講でも,改めて見直したいところである。
「多元的宇宙」に関するものついては,「純粋経験」に関する諸論の延長にあるものの,1907年の「プラグマティズム」よりも後の1909年で,「多元的宇宙」を最後に,翌年には亡くなるので,いわばジェームズの世界観の集大成で,まとまった本として出版されたため,遺言にもあたる。小木曽由佳「ユングとジェイムズ」でも,最後の第五章を「個性化と多元的宇宙」を立てているように,多方面に影響を与えたものなので,別書ジェームズ「多元的宇宙」(1909年のオックスフォード大学マンチェスター・カレッジでの講義録),吉田夏彦訳(日本教文社「W・ジェイムズ著作集6」2015年)により,独立させて論じることにする。
以下,本論に入る。
第一章「<意識>は存在するのか」1904年
「思考」と「物」とは種類を異にするふたつの対象の名前である。・・・最初は「精神と物質」「魂と身体」という対比が用いられて,同等の,一対の等価な実体とされてきたが,あるとき,カントが魂の重みを骨抜きにして超越論的自我を導入して以来,この二極関係は非常にバランスを欠いたものになってしまった。>魔術を失わせたデカルトに始まる西洋近代の問題が指摘され,アメリカがヨーロッパとは異なる思想的存在であることも示す。
「意識」という言葉が,ある機能を表していることを強調したいのである。物質的な事物の素材と対比される意味で,われわれの思考をつくっているとされる,原初的な素材とか存在の質などは存在せず,ただ経験のなかにあって思考が果たす機能というものがあり,この機能の作用のゆえにこうした存在の質といったものが措定されることになったということである。この機能とは<認識する>ということである。>定義した上で,
わたし(ジェームズ)のテーゼはこうである。もしもわれわれが世界の内にただひとつの原初的な素材のみが存在し,この素材によってすべてのものがつくられているのだという想定から出発するならば,そして,もしもわれわれがこの素材を「純粋経験」と呼ぶのであれば,そのときには,認識するという作用は,純粋経験の特定の部分どうしが互いにもちうる関係として容易に説明できるであろう。>明解な公理を示す。
<わたしが信じるには,経験とはそのような内的二元性をもつものではない。経験が意識と内容に分離されるのは,引き算によってでなく足し算によってである>~足し算とはすなわち,経験のある所与の一片に他の経験の断片の集合が加えられることによって,その一片がさまざまな仕方で,異なった二種類の用途あるいは機能を果たすようになるということである。>説得力のある話し方。
経験の二元性を具体的に理解しようとするこのような方法に,最初のくさびを打ち込んだのはロックとバークリーである。ロックは「観念」という語を物と思考の両方に無差別に適用しようとし,バークリーは,常識が実在と呼ぶものは哲学者が観念という語で意味するものにほかならない,といった。・・・「プラグマティック」な方法を,最初に使用しようとしたのは彼らであったと思われる。>現在でも,ロックは,プラグマティズムの遠祖とされている。
第二章「純粋経験の世界」1904年
現代の哲学をとり巻く状況には,誰も気づかずにはいられないような奇妙な不安定感が漂っている。・・・これらの学派的な解決にたいする不満の大部分は,それらがあまりにも抽象的でアカデミックにすぎるという感情に起因しているようである。・・・青年たちが求めているのは,たとえ論理的な厳密さや形式上の純粋さを多少犠牲にしてででも,より多くの生の実感がこめられているような哲学なのである。>ユングに通じる。
経験論が根本的であるためには,その理論的構成において,直接に経験されないいかなる要素も認めてはならず,また,直接に経験されるいかなる要素も排除してはならない。このような哲学にとっては,<経験どうしを結びつける関係はそれ自体が経験される関係であり,経験されるいかなる種類の関係も,他のすべてのものと同様に,その体系において,「実在的なもの」として数えられなければならない。>
哲学はつねに文法上の不変化詞にお伺いを立ててきた。with,near,next,like,towards,against,because,for,through,my,これらの言葉は,親密性と包含性の度合いにかんして低い方から高い方へとほぼ順番に並べられた,連接的関係のタイプを表す言葉である。われわれは経験をまたずアプリオリに,「with」を含まずに「near」のみからなる宇宙を想像することが可能である。(他も同様で)これらはぞれぞれ独自の統一性をもった宇宙となるであろう。人間の経験の宇宙は,その時々の各部分において,こうした統一性のひとつであるとともに,すべての統一性の度合いを含んだものでもある。それがさらに高度な絶対的統一の度合いを享受できるかどうか,それは表面のみからでは判断できないひとつの謎である。>多元的宇宙への萌芽。
哲学にとってもっとも大きな困難を突き付けてきた連接的関係は,<共-意識的推移>とでも呼ぶべきものであり,これによってひとつの経験は,ともに同じ自我に属する別の経験へと推移する。・・・わたしの経験とあなたの経験はさまざまな外的な仕方で<共にある>が,わたしのそれはわたしの経験へ,あなたのそれはあなたの経験へと,まったく異質な仕方で推移する。われわれの個人的な歴史の各々のうちで,主観,対象,関心,目的は,<現に連続的であるか,連続的であることが可能である。>個人的歴史は時間における変化の過程であり,<この変化そのものが直接に経験されるもののひとつである。>この場合の「変化」とは,非連続的な推移と対比される連続的な推移を意味している。>過程や動きを重視する姿勢は,「心理学原理」においても明らかであった。
主観と対象が絶対的に非連続なものに扱われてきたことによる経験論の陥穽を縷々述べた上で,「わたしにはまさにここにおいてこそ,プラグマティズムの方法を適用するための絶好の機会が与えられている,と思われるのである」と,以降に自らの説を展開した後,「以上をもって純粋経験の哲学の概要は示された。本論の冒頭で,わたしはこの哲学をモザイク的な哲学と称した。実物のモザイクでは,寄せ木の各片は土台に支えられて組み合わされているが,他の哲学では,この土台に相当するものとして,実体や超越論的自我,あるいは絶対者を考える。これに対して根本的経験論には土台は存在しない。この哲学では,各片がそれぞれの縁で組み合わさり,それらの間に経験される推移が接着剤の役目を果たすのである。(以下略)」と巧みな比喩で結論づけている。
第三章「活動性の経験」1905年
心理学会会長として,年次大会で会員に語ったもので,冒頭,「心理学会会員の皆様」の見出しで,「講演の主題を思案した結果,われわれの活動性の経験というのが適当と思うようになった。その理由は,この主題がもともと興味ぶかいうえに,近年これにかんして多くの議論がなされているとはいえ,いまだ決定的な結論に至っていないだけでなく,わたし自身最近,心理学的な現象にかんする諸問題をある種の体系的な仕方で扱うことにますます興味を覚えるようになり,他の人々にもそれに興味をもってもらいたいと思うようになったからである。」と,啓蒙者ジェームズの面目躍如で,「根本的経験論」を,心理学という実際世界に結びつける形で話をし,「<本物の活動性の主体とは何か>という問いはそれゆえ,<実際の結果はどうなるか>という問いに帰着する。この問いの関心は劇的な関心である。本物の活動性の主体が何であるかということは,物事がどうなるかということなのである。」>プラグマティズムの本質も明示している。
以下,第四章「ふたつの精神はいかにしてひとつの物を認識しうるのか」1905年,第五章「純粋経験の世界における感情的事実の位置」1905年は省略し,第六章「変化しつつある実在という考え方について」(雑誌には未発表で「多元的宇宙」補遺1909年),第七章「経験の連続性」(「多元的宇宙」第七講「経験の連続性」1909年),第八章「多元的宇宙」(「多元的宇宙」第八講「結論」1909年)については,前述のとおり,第三話の別書に譲ることとし,日本を代表する哲学者西田幾多郎が,ジェームズの純粋経験の哲学から影響を受けて著し,代表作になった「善の研究」に触れておきたい。⇒コラム
第二話:講演記録「プラグマティズム」が出版され,アメリカの哲学になった
ジェームズ「プラグマティズム」(1907年,舛田啓三郎訳(1952年,岩波文庫版1957年)による)⇒フォト
本書は,ジェームズの著作で最も影響も与え,読まれ続けているもので,ジェームズといえばプラグマティズムを代表する哲学者ということにもなったのであるが,出版された著作のうちでは最も薄く(短く),読みやすいものであることもその理由であろう。
舛田の解説によれば,前半のジェームズの評伝にあたる部分は,第一話とほとんど同じなので省略するが,ジェイムズはパースのプラグマティズムを哲学の一方法として受け取り,一つの真理論として発展させたが,パースの思想の一面をことさらに強調したものでしかなかったため,1905年に,パースは一つの手紙で,「ジェイムズはみずからをプラグマティストと称しており,そして疑いもなくこの問題についての彼のもろもろの概念を私から引き出したのであるが,彼のプラグマティズムと私のそれとの間には,本質的な違いがある」と書き,「プラグマティズムとは何か」という論文で,「筆者は,自分の子供"プラグマティズム"がこれほどにまで増長したのを見て,別れの時がきたことを感じ,"プラグマティシズム"の語を誕生させたい。この語ならさらわれる心配はない」と述べて,プラグマティズムが彼の意図するものとは違った方向に発展し,濫用されつつあるのを嘆いている。
そして,その違いの主要な一つは,パースにおいて科学的論理学の方法の一つとして提唱されたものが,ジェイムズによって哲学の広い領域にもちこまれ,哲学上の相対立する学説を調停できるような方法であるばかりでなく,真理の理論にまで拡張されてしまったことにあるだろう。>パースにおいては,あくまでも「知」の範囲であったものを,「意」の方に広げてしまったということになるが,デザイン論で,背景となる哲学にとりあげたように,ジェイムズがこのように反応したことが,「知」の限界を感じていたことにも起因しているようにも見える。ユングのプラグマティズムの受け取り方も,あくまでもジェイムズを通してのもので,パースが創始した本来のものではないことになるが,それ故,ユングが強く影響を受けたのであり,互いに相通ずることが大きかったということになろう。それでも,ジェイムズの性格上,あまりに性急に,あまりにどぎつく言ってしまったこと,というより,ジェイムズが本来的に学者でなかった,まさにデザイナであったということを示すものともいえるのではないだろうか。私自身,パースに傾倒していたのも,デザインとは何かを考え続けての上のことだったのである。
ジェイムズのプラグマティズムが本来のものとは関係がないとしても,プラグマティズムとして知られる哲学上の運動は,疑いもなくジェイムズのこの講演,この書物によって強力に押し出されたのであって,アメリカの哲学は,ジェイムズから,ヨーロッパの哲学とは独立した歩みをはじめたと言えるのである。その教養において,好みにおいて,また交友において,まったくのコスモポリタンであるジェイムズが,そのプラグマティズム的志向のために,期せずしてアメリカ哲学の創始者になりえたのである。>まさに歴史の偶然を示すものにもなっている。
本文に入るが,扉に,「私が初めてプラグマティックな心の寛さを学んだ人,また,なお世にいますならば,われらの指導者として仰ぎたく思う人であるから」ジョン・ステュアート・ミルにささぐとある。>ジェイムズにとっては,ミルこそが,プラグマティズムの祖ということになる。
「序」に,関心を持つ人のための参考書として,ジョン・デューイ「論理学の研究」を基本的なものとし,デューイの他の論文も挙げていることから,デューイをプラグマティズムの承継者とみなしていることが明かであり,また,初めて読む人への手ほどきとして,F・C・S・シラー「ヒューマニズム研究」,さらに,G・ミロー「合理的なもの」,「形而上学評論」に掲載されたル・ロワの論説,「キリスト教哲学年誌」に掲載されたブロンデルとド・サイイの諸論も参照されたいとしており,これらによって,ジェームズのプラグマティズム観が読み取れると思われる。
その第一講は「哲学におけるこんにちのディレンマ」で,およそ一個の人間に関して最も実際的で重大なことは,なんといってもその人の抱いている宇宙観であるとし,哲学の歴史はその大部分が人間の気質の衝突であり,・・・これによって哲学者たち相互の著しい差異を説明しようと思う・・・じつは彼(その哲学者)の気質の方が,客観的な前提のいずれよりも強く哲学者の傾向を定めるのであると,まさに,心理学で世に知られるようになったジェームズの見方が登場する。そして,文学で純粋主義者とリアリスト,美術で古典派とローマン派,政治で官憲主義と無政府主義,行儀作法で形式主義者と自由振舞い派のような気質の差異があるように,哲学では,抽象的な永遠の原理に偏執する「合理論者」と,ありのままの雑多な事実を愛好する「経験論者」の対立があるといい,それぞれに,「軟らかい心」と「硬い心」という名を与えて,以下のように表にしている。
| 軟らかい心の人 | 硬い心の人 |
| 合理論的(原理に拠る) | 経験論的(事実に拠る) |
| 主知主義的 | 感覚論的 |
| 観念論的 | 唯物論的 |
| 楽観論的 | 悲観論的 |
| 宗教的 | 非宗教的 |
| 自由意志論的 | 宿命論的 |
| 一元論的 | 多元論的 |
| 独断的 | 懐疑的 |
>一見したところでは,多くの点で,私は軟らかい心の人に属するが,主知主義的,観念論的,一元論的については,逆であると思われ,また,これらを含めて,軟らかいと硬いの対比も気になるところである。ジェームズには,ユングがタイプ論の基本とした内向型と外向型の対比は無いが,これも,軟らかい心の人が内向型で,硬い心の人が外向型であると言えるものの,人間関係としてみた場合には,内向型の人が硬く,外向型の人が軟らかくみえるので,直観的に分かりにくくなってしまうが,いずれにしても,ユングに影響を与えたのは,ジェームズも,さまざまな人間の対立の基本が,気質の違いにあるととらえていたことにあると言ってよいだろう。
そして,歴史的な人物の対立の例を縷々挙げて行きながら,突然,両種の要求を満足させることことのできる一つの哲学として,プラグマティズムという奇妙な名前のものを提唱すると述べ,聴衆に対し,人間関係の衝突を救ってくれるものとして興味を抱かせるたくみな話の持って行き方になっているが,プラグマティズムへの誤解の種になっていくのは当然かもしれない。>デザイン論の観点からいえば,ジェームズの言っていることは,「共の創出」そのものいってよいだろう。
第二講の「プラグマティズムの意味」に入るが,前講を受けるように,プラグマティックな方法は元来,これなくしてはいつはてるとも知れないであろう形而上学上の論争を解決する一つの方法なのであると,取りようによっては,魔法のように聞こえる。そして,この語はギリシャ語のプラグマから来ていて,行動を意味し,英語の「practical実際的」という語と派生を同じくする。この語がはじめて哲学に導き入れられたのは,1878年チャールズ・パース氏によってであった。「通俗科学月報」の「いかにしてわれわれの観念を明晰にすべきか」と題する論文で,パース氏は,われわれの信念こそほんとうにわれわれの行動を支配するものであることを指摘した後,およそ一つの思想の意義を明らかにするには,その思想がいかなる行為を生み出すに適しているかを決定しさえすれば良い。その行為こそわれわれにとってはその思想の唯一の意義である(後略)と述べている。>これがデザイン論での拠り所になっているのは言うまでもない。 以上がパースの原理であり,プラグマティズムの原理である。この原理は二十年の間,全く何びとの注意も惹かずにあったのであるが,私がカリフォルニア大学の哲学大会での講演で,この原理を持ち出して,この語が広まったという。>パースのことをきちんと位置付ける一方で,自らが広めたという自負の大きいことも分かる。 そして,プラグマティズムは,もろもろの学説も同様であるが,一つの方法,道具でしかなく,つねに特殊に訴える点で名目論に一致し,実際的見地を強調する点においては功利主義に,言葉の上だけの抽象を軽蔑する点においては実証主義と一致すると述べる時には,かなり本来のプラグマティズムになっている。>名目論の話は,デザイン論における名づけに関係すると思われる。功利主義の話は,実際,プラグマティズムと混同されることが多く,日本では嫌われる語でもあって浸透できなかったともいえる。実証主義になってしまうと,近年の科学一般と何の変わりもなくなってしまう。そこで実用主義という語が使われることもあるが,あまりに軽い言葉で,これまた伝わらない。結果として,プラグマティズムという片仮名を使うことになったが,結局,日本人には伝わらない言葉になってしまっているのが残念である。
第三講の「若干の形而上学的問題のプラグマティズム的考察」では,唯物論の限界を述べた後,おそらく,「宗教経験の諸相」を著すようなジェームズであったがゆえに,プラグマティズム本来の考え方から逸脱して,宗教,神の話に入り,「神の目的もただ人間を造ってこれを救うのにあるのではなく,むしろ自然界の広大な機構の働きだけを通じて創造と救済を行わしめようとするにある,とわれわれは言いたい。(中略)このような見方をすると,(神の)設計説の形式は救われることになるが,この説の含む伝統的な,心やすい,人間的な内容は失われてしまう。設計者はもはや古来の人間に似た神ではない。神の設計はわれわれ人間には理解できぬまでに広大なものになったのである。(中略)単に「設計」という言葉だけではなんの効果もなく,また何一つ説明しない。それは最も空虚な原理である。」 >以下,縷々のべていることを突き詰めれば,要は,神は自然界を設計(デザイン)したのではない,設計とは人為的な行為で,自然界に設計(デザイン)の語を用いるべきでないということで,逆説的に,デザイン論にもつながるようにみえる。さらにもう一つ論じつくされた<自由意志の問題>を取り上げたいと,「自由意志は一つの原理であり,人間に付け加えられた一つの積極的な能力ないし徳であって,これによって人間の威信はなぜともなく高められる。(中略)自由意志とは,プラグマティックに言えば,<この世界に新しいものが出現する>ということ,すなわち,世界の最も深い諸要素においても,また表面にあらわれる現象においても,未来は過去を同一的に繰り返すものでも模倣するものでもないことを期待する権利という意味である。(中略)自由意志は,ちょうど絶対者,神,精神ないし設計などと同じように,一般宇宙論上の<約束>説である。」,以下,縷々述べていることはそのまま,デザイン論の根拠である「意」と「善」と「未来」が一体のものであること,人間は皆デザイナであることなど,そのままの話に聞こえてしまう。
第四講の「一と多」は,ジェームズの最後となる「多元的宇宙論」につながるものであるが,ジェームズが「われわれの知性が真に目指すものは,多様性だけでもなければ統一性だけでもなく,<全体性>である。この全体性にあっては現実の種々相にあかるいということがその関連を理解することと同様に重要である。詮索欲は体系化の情熱と同じ歩調で歩くのである。」>というのを聞くと,これまた,デザイン論の話ではないかと,耳を疑うほどになってしまう。そこで,「宇宙に一という述語を与えるその仕方が異なるにしたがって,その結果に違いが見えてくる。その仕方のいちじるしいものを順次に記してみよう。」というジェームズに従って,頭のところだけ記すと,①世界は少なくとも<論議の一つの主題>である。②事物は<連続的>であろうか。③事物を実際上連続させる途はほかにも数えきれぬほどある。④誘導あるいは不誘導というこれらの体系はすべえ世界の<因果的統一>という一般的な問題に組み入れてよい。⑤事物間に認められる統合の種類のうち最も重要なのは,プラグマティックに言えば,事物の<類的>統一性である。>デザイン論のアナロジー・シンメトリー・マンダラに対応。 ⑥「世界は一である」という言葉のもちうるもう一つの意味は<目的の統一>ということである。>デザインは目的をもって成り立つ。 ⑦事物の間には<美的統合>も認められる。>従来のデザインの一般的考え方。 ⑧過去百年にわたって一元論的思想の<大きな思惟手段>となったものは,<唯一の認識者>という考えであった。以上縷々述べた最後に,「なぜ私が第二講で,プラグマティズムはあらゆる学説を<硬化させまいとする>ものだと言ったかわかってもらえたはずであると思う。(中略)プラグマティズムは,事物間の統一と不統一の均衡がどうあるか,まさにそのことを経験が最後的に見届けるのを待つのであるから,明らかに多元論の側につかざるをえない。」と結んでいる。
第五講の「プラグマティズムと常識」は,プラグマティズムが常識を重視するものであることを,第六講の「プラグマティズムの真理観」では,真理は観念と「実在」との一致を意味していていることを自明のこととするのは,主知主義者と同じであるが,プラグマティズムは,「実在」が何を意味するのかを問い,真であることでとは現実生活にどのような差異を生じるのか,その真理はいかにして実現されるにかを問題にする。<真の観念とはわれわれが同化し,効力あらしめ,確認しそして検証することができる観念で,偽なる観念とはそうできない観念>であり,「真理であるから有用である」とも,「有用であるから真理である」とも言えるのである。われわれの説く真理は,複数の真理,導きのもろもろの過程であり,具体的な事物のうちに実現せられていて,<報いてくれる>という特質だけしか共有しない真理であるとし,合理論者がプラグマティストと決定的に異なるのは,彼らが,実在そのものか真理そのものかが変易するものでることを決して認めないことであり,プラグマティズムが未来の前方に目を向けるのに対して,後方を振り向き過去の永遠に面を向けるのである。>プラグマティズムが「過去」「知」でなく「未来」「意」のものであることを示していることを確認しておこう。
第七講の「プラグマティズムと人本主義(ヒューマニズム)」はそれを受けるように,「われわれは認識的生活においても行為的生活においても創造的である。」とし,イタリアにおけるプラグマティズムの指導者パビーニ氏が,この考えこそ人間における神のごとき創造的な門戸を開くものと,狂喜しているという。>これも,デザインそのものを語っていることになろう。 人の話になったためか,多元論と一元論の立場の選択には気質の違いが働いていると,第一講の話題が再登場,合理論的な心の人は,極端な言い方をすると,頑固な純理論家肌で,権威を尊重する性質を持っているのに対して,徹底的なプラグマティストというものは,至極のんきな無政府主義的な部類の人間である。>私自身まさにその通りである。 そして,最後の第八講は「プラグマティズムと宗教」となるが,第一講での硬い心と軟らかい心の調停者としてプラグマティズムを想い起して貰いたい,プラグマティックな原理に立つとき,われわれは生活に有用な帰結が流れ出てくる仮説ならばいかなる仮説でもこれを排斥することができないとして,科学や哲学から否定されてきたものを受け入れる宗教の復活を訴えることになる。>第一話で述べたように,ベルクソンや西田幾多郎に共通するものであり,ジェームズがユングに最も影響を与えたのが「宗教的経験の諸相」であることを想い起せば,当然の帰結であり,上山春平によれば,パースとデューイも,宗教と科学を矛盾するものとしてでなく,むしろ相互にたすけあうべきものとしてとらえていた点で同じであった。
>全体として,パースが創始したプラグマティズムからはかなり逸脱したものであったため,その後の,プラグマティズムの展開にさまざまな誤解を生むことも否定できないとも言われるが,そもそも哲学の話をするところが,現代心理学の源流ともされる「心理学原理」を出版したほどのジェームズでもあったため,冒頭から,哲学者の気質の違いが哲学に反映するという話になっていて,このことが,哲学を敬遠しがちな一般の人たちにも興味を抱かせたことは間違いないだろう。その違いが,ユングのタイプ論でいえば,内向型だったパースに対して,ジェームズが外向型であることにも起因しているようにみえるのも面白い。とはいうものの,神の設計について語りながら,人間の設計の意義を述べている点で,デザイン論に直結するものであることも見逃せない。
第三話:ジェームズの世界観の集大成「多元的宇宙」を遺した
ジェームズ「多元的宇宙」(1909年のオックスフォード大学マンチェスター・カレッジでの講義録,吉田夏彦訳(日本教文社「W・ジェイムズ著作集6」2015年による)⇒フォト
第一講 いろいろなタイプの哲学的な考え方:「プラグマティズム」で論じた,二つの気質の違いによる二つのタイプの哲学に準じたものなので,とくに述べることは無いが,中ほどで,「哲学のような学科では,人間性のひらかれた空気とのむすびつきを失い,職業上の伝統だけによって考えるということは,実に致命的なことなのであると言い,ドイツでは形式があまりに職業化されたために,教職をえて書いたものはだれでも,~どんなにおかしな人であろうとも~その学問の歴史に,丁度,琥珀に封じこめられた蝿のように,未来永劫にたちあらわれる権利を獲得すると言う。(以下略)」 >痛烈なアカデミスム批判があり,ユングと相通じたのは言うまでもない。
第二講 一元論的観念論:そして,とくに批判の対象となるタイプの哲学について解説,「(イギリスで)ベンサムと功利主義派のもっていた影響力が,良かれ悪しかれ,観念論者の手に移ったということは,ほとんど否定できない。・・・'ライン河がテームズ河に流れこんだ'とホブハウス氏は警告した。」と,(ドイツを中心とした)大陸の哲学がイギリスの哲学を支配していると訴える。
第三講 ヘーゲルとその方法:続いて,「あの不思議な,そうして力強い天才ヘーゲルは,観念論的な汎神論の思想界における勢いを強めるにあたり,直接的にも間接的にも,ほかのすべての影響をあわせた以上の貢献をした。」と,その弁証法について,「この思考図式のこつを,一ぺんのみこんでしまうと,この図式からのがれることはむずかしくなる。みるものすべてがこの図式になる。だれかが何かをいうと,すぐそこに矛盾がふくまれているのを感じることが習慣になる。」>私自身,いまだにそれを脱し切れていないことを痛感せざるを得ない。「このヘーゲル流の考え方の高貴さを否定できるものは,多分いないだろう。もし哲学に壮大なるスタイルがあるとすれば,これはたしかに壮大なスタイルをもっている。」とまで述べたのち,「ヘーゲルの手つづきにみられる,奇妙な点について注意しなくてはならない。この奇妙さに関する最終判断は,私の第七番目の講義で下される。だからここでは,ほんのついでにふれるだけである。ヘーゲルは,経験の有限な直接所与は,それ自身の他者ではないが故に'真ではない'ものである,と考えている。」あたりから,絶対主義の話に進んで解説,「これまでのところ,私の結論はこうなる。絶対者の仮説は,ある種の宗教的な平和をもたらす点において,もっとも重要な合理化機能をいとなむけれども,知的な観点からは,決定的に非合理なものである。<理想的に>完全な全体とは,たしかに,その<部分もまた完全な全体>であるはずである。~もし我々が論理にたよりうるのだとすれば,何よりもまずこの定義のために論理を使うことができる筈である。」とし,最後に,絶対主義に対する告発に,あと二点だけ加えるとして,「まず,<絶対者は演繹的な目的のためには無益なものである>ということ,(中略)第二に,絶対者は常に,理想的に,すべてを知っているものとして,定義されている。(後略)」と,結んでいる。
第四講 フェヒナーについて:こういった絶対主義と通ずるように見え,同じドイツ人でもありながら,気質的に正反対の極にあるものとして,グスタフ・テオドル・フェヒナーの哲学を取り上げ,その強烈な具体性とディテイルの豊かさに驚嘆するという。人類が知っているもっとも偉大な「科学」の中で,弁証法が使われた例は一つも思い浮かべることができないと,ヘーゲルを再否定したのち,科学の成果に貢献したのは,観察やアナロジーによる仮説からの演繹だけであり,フェヒナーは,実在に関する形而上学的な結論を出すのに,これ以外の方法は使わなかったといい,まず,彼の生涯を紹介している。Wikipediaで調べてもわずかなことしか書かれていないので,以下,ジェームズの紹介に従う。
フェヒナーは,1801年にザクセンで田舎教師の息子に生まれ,1817年から没する1880年までの60余年間,ライプツィヒに住んだ典型的な昔風のドイツ人学者であり,常に貧乏だったなか,思想の中でのみ行われた贅沢は豪華なものであった。21歳の時,ライプツィヒの大学の医学の卒業試験に合格したが,医者にならずに物理学に一生を捧げることを決心,10年後に教授になるまでの間,生活のために莫大な著作をした。化学や薬学の雑誌の編集をしたり,八巻からなる百科辞典を編集し,うち三分の一は自ら記述する一方,本職の物理学では,電気学に熱心で,動物電気の測定は,今日にいたるまで古典的なものになっている。それだけでなく,この間,ミーゼス博士の名で,半分哲学的で半分はユーモア文学的な著作を多数公けにしたが,何回も版を重ね,このほか,詩や文学的な随筆や芸術論などがある。>ここまで聞いただけでも,ゲーテにも匹敵するような全人的人物であったが,残念ながら,現在,日本で翻訳されているものは無い。
これらによる過労と貧困の上,網膜における残像の観察をし続けたための眼病によって,38歳頃,ひどい神経衰弱におそわれ,3年間,全く活動できなくなった。当時はこういった病は天罰と考えられていたので,突然快方に向かい出した時には,本人も周囲も奇跡と受取り,信仰によって救われたと,以後,その信仰を完成して世界に伝えることを目的とするが,その間にも,原子の理論の古典的著作や,精神物理学についての実験的力作で,科学的な心理学の基礎を築いたとも,実験美学の著作で,その基礎を開いたともいわれるなど,多くのことを成し遂げ,彼が死んだ時には,ドイツの学者の理想を実現した人物,すなわち,思想においては大胆なほど独創的であり,生活においては質素であり,真理と学問に対しては地味で温和で勤勉な奴隷であり,その上誰にもよく分かるすばらしい文体の持主であったと,ライプツィヒ全体が嘆き悲しんだ。
フェヒナーが,最後の著作「ゼンダヴェスタ」(1901年)で,楽しそうに書いている昼間の眺めの文に見られるように,学者だけでなく普通の人々までが,精神的なものを自然の中の原則とは考えず,これを例外とみなす根強い習慣があるのは,原罪のようにあやまったものであり,我々の生命はより偉大な生命によって養われ,我々の個性はより大きな個性によって支えられているのであるという。>ゼンダヴェスタが,ZEND AVESTAであれば,ゾロアスター教の経典ことであることも含めて,まさに,ユングの思想,集団的無意識を先取りするようなものいえよう。
フェヒナーが,昼間の眺めを生々と物語るために使った大きな道具は,アナロジーであった。彼の書物の大部分のページには,合理的な論証は見出されず~実用生活で人びとが使っているような推論だけがみいだされる。ベインは,天才を,アナロジーを発見する能力と定義した。フェヒナーが発見したアナロジーは莫大なものであるが,彼は,同様に差異をも強調しており,アナロジーにたよる推論に見られる共通の欠陥は,差異をみとめないことであるといい,全著作を通じて,差異とアナロジーを対等にとりあつかっている。彼が用いている推論のタイプは,ほとんど子供らしいほど単純なものであり,彼の結論そのものは,ただ一ページで書上げることができるが,この人の<力>は,全く,彼の具体的な想像の豊かさ,彼がつぎつぎと考察する論点の多様さ,彼の学識が集まっておよぼす効果,彼の徹底性,ディテイルにおけるそのたくみさ,驚くほど着実なスタイル,彼のページを輝かせる真面目さ,そうして最後に,(また聞きにたよっているのではなく)<見る>人間,(職業的な哲学的文筆家の群の一人としてでなく)権威をもつもののごとくにかたる人としての彼の印象,によっているからである。
以下,縷々述べたのち,フェヒナーについてこれ程くわしくのべたのは,一つには,現在の超越主義の密度のうすさを,対比によってはっきりさせるためであった。スコラ哲学には厚みがある。ヘーゲル自身も厚みがある。しかしイギリスやアメリカの超越主義哲学は薄っぺらい。哲学においては,論理よりも情熱的なヴィジョンの方が重要なのだとすれば~私はそうだと信じている。(中略)私がフェヒナーを私の題目の一つとしたのには,もっと深い理由もある。<意識的な経験は,自由に複合しあい,またはなれあう,>とする彼の仮定は,絶対主義が,我々の精神の永遠な精神に対する関係を説明するのに使うのと同じ仮定であり,また経験主義が,人間の精神は,より下級の精神的要素から合成されている,と説明する際に使うのと同じ仮定であるが,この仮定は,厳密な検査なしに通してよいものではない。次回の講義においては,この仮説を検討するであろうと,結んでいる。
>実は,本特別講義の最後に取り上げる「インテグラル心理学」で,著者のケン・ウィルバーが開眼することになった人物もフェヒナーで,本書を彼に捧げているほどである。ウィルバーがジェームズの「多元的宇宙」を知らなかったとは思えないが,その部分に至ったところでもう一度ここに戻ってもらえれば幸いである。
第五講 意識の複合:前講の結びを受けて,私(ジェームズ)が論じようとするのは,いわゆる意識の諸状態は,自由に離れあい,また結びあうことができる。そうして,より広い経験の領域の諸部分をかたちづくる際にも,その自己同一性を,そのままのかたちで保っているという仮定であるとして,「心理学原理」の著作を振り返って,縷々述べた後,比較的若く極めてオリジナルなフランスの思想家,アンリ・ベルグソン教授の影響を受けなかったら,これほど晴れ晴れとして,論理を哲学の深い領域から,単純な実践の生活に投げ返すというようなことはしていなかっただろうと告白し,ベルグソンの哲学に対する功績のうち,当面の目的にもっとも肝要なものは,主知主義に対する批判,というより,主知主義を,決定的かつ望みないまでにうちほろぼしたとして,以下,自らのいうところの主知主義について解説している。>ユングがジェームズによって開眼したように,ジェームズはベルクソンによって開眼したのである。
第六講 主知主義に対するベルグソンの批判:自らを開眼させてくれたベルクソンについて,「ベルグソンのオリジナリティはあまりにも豊富であるので,彼の観念の多くは,私を全く当惑させる程であり,彼を全面的に理解している人がいるかどうかは疑しいと思う。」「ベルグソンの学識はきわめて広大であり,しかもこれを表現する方法のたくみさは驚くべきものである。」「難しいものを易しいものにしてくれるものがあるとすれば,それはベルグソンの文体のようなものをいうのであろう。」と,まるでファンのような言葉を繰り返したのちに,本題に入って解説,内容は省略するが,「ベルグソン教授は,こういうわけで,伝統的なプラトンの教えを完全にひっくりかえすのである。彼は,知的な認識をより深いものとは呼ばず,より表面的なものと呼ぶ。」「実在を概念に分解してしまえば,もはや,その全体性を再建することはできない。ばらばらになったものをいくら寄せあつめても,具体的なものをつくり出すことはできない。」と言う時,ジェームズ自身の,「知」が全てになってしまった,科学至上主義への批判であると同時に,なぜデザインかという問題につながる話としてもとらえることができる。
>実は,ゼンダヴェスタの語を知りたいと,インターネットを検索していたところ,檜垣立哉(大阪大学)「ベルクソンとアメリカ哲学」という論文を見つけたが,ジェームズとパースを同等に扱っている上,「多元的宇宙」において,ジェームズが大きく扱ったフェヒナーについても論述していることから見逃せない論文と思われるので,コラムで紹介しておこう。⇒コラム
第七講 経験の連続性:ここにきて,ジェームズが本講義で述べたかったのが,前講のコラムに示した檜垣立哉「ベルクソンとアメリカ哲学」にも論じられている,パースとともに,ベルクソンと共有する思想「経験の連続性」にあったことが分かるのであるが,それはさておき,冒頭部分で。「哲学は,本質的に,上からくる事物のヴィジョンである。哲学は単に,事物のディテイルを感じるのみならず,その理解可能な設計図をみとり,その形式と原理,カテゴリーと規則,秩序と必然性とを認識するものである。それは,建築者がもつ,あのすぐれた観点にたつ。」と述べているのは,使われている「設計」「建築者」などの語からも,「哲学者はデザイナである」と言っているように聞こえる。実際,この後に続いて述べていることから,哲学が軽視されるようになったのは,主知主義すなわち「知」が支配するようになったことによる,論証ばかり重視し,証拠の無いものは認めないという科学至上主義によるということであり,「哲学」が「知」の世界の最上位にあるという幻想は,もはやパラドクスでしかないということになろう。
終わりの方では,そのパラドクスを,ジェームズ自身が,「私は,概念や言葉によって言い表されたものだと自分でいっている当のものを,概念や言葉によって記述しようとする空しい努力をつづけ,私自身をも諸君をも疲れさせている。<はなし>つづけるかぎり主知主義が依然として支配力をふるっているのである。」と率直に述べ,「生への歓喜は,話すことによっては得られない。それは<行為>である。諸君を生へかえらせるためには,諸君に模範となる実例を与えなくてはならない。ベルグソンがやったように,我々がそれをつかって話している概念は,<実用>の目的のためにつくられたのであって,洞察の目的のためにつくられたのではない。」と,プラグマティズムに立ち帰り,「哲学は,ソクラテスやプラトンの時代からずっとまちがった道を歩んできたのである。主知主義の困難に対する<主知主義的な>解決は。絶対に得られない。(主知主義にとって)この困難からぬけだす真の道は,このような解決を発見することではなく,この問題に対して端的に耳を閉じることである。」とまで,断じる。>もはや,ジェームズ自身に,「知」つまり学者であることを止め,「意」つまりデザイナになって欲しいと言いたくなってしまうくらいである。
第八講 結論:そのようにして,「知」を否定した結果の結論の冒頭は,自らの宗教経験にもとづいて,「死後に思いがけずも続いている生活の経験」を考えていると述べている。>何はともあれ,この講義が自らの最後の遺言のようなものであるということとも重なるのであろう。ただ,死後という時,人々は個人を脱し,人類の未来に関わりたいという願望にも重なり,ここに,ユングのいう集団的無意識と通じるものがあるだけでなく,「意」が未来対応のもので,「共」を創出するためにあるということと一致するともいえる。
昨今,「精神治療」宗教と知られているように,我々が極度の絶望状態におちいった後,新しい生の領域が開けるという現象・・・その際に得られる宗教的経験は,自然の輪郭をやわらげ,ふしぎな可能性とパースペクティヴを開くというように,以下,宗教的経験への傾倒がみられる。>すでにのべたように,ベルクソンや西田に共通するものであるが,もはや宗教回帰を考えることが困難になってしまった現代においては,デザイン論で述べた「暗黙知」の世界として捉え直し,いかにして暗黙知の世界に入り,いかにして新たな形式知の世界に蘇生するかを詰めていくことが大事であるように思われる。
そして,結論の結論は,一元論から脱した,多元的な宇宙へと結ばれる。
付録C 「変化しつつある実在という考え方について
付録につけられた論文のうち,未発表であったCのみが訳出されているが,これは,第一話の,伊藤邦武編訳によるジェームズ著作集「純粋経験の哲学」(岩波文庫,2004年)にも,わざわざ章立てで収録されていることからも重要な論文であり,今回の講義において,プラグマティズムを語りながら,その創始者であり,仲間であったパースことに触れないできたため,自身にとって,パースがベルクソンに並ぶ存在であること,本講で言えなかったことで是非とも付け加えておきたいこと,といった趣旨のものである。>余計とは思うが,前半,同一性とか因果性で意味のないものを結びつけてしまう危険の例を述べるなかに,なぜか「ペルリ監督は,ある意味で,日本の新しい政体の原因だったし,この新政体はロシア帝国議会の原因だった。しかし,ペルリがロシア帝国議会の原因だと言い張ってみたところで,ほとんど何の約にも立たないだろう。」とあるのが面白い。
本題に入ると,「モニスト」誌の第一,二,三巻(1890年~1893年)に,チャールズ・S・パース氏の一連の論文がのっているが,これ等の論文はあまりに独創的なので,直ちに,人びとの眼をひきつけることはできなかったようだ。・・・パース氏の見解は(それが得られた筋道は大いに違っているが)ベルグソンの見解とまったく相覆うものである。・・・パースの「機会説」は,だから,ベルグソンの「真の持続」と,実質的に同義語である。・・・新しさが突然飛び込んでくると,世界の理性的な連続をくもらせるという抗議に,パースは,「機会説」と「連続説」を統合して'agapastisism'の名を与えて退けるが,これは,ベルグソンの「創造的進化」と正に同じものである。・・・パースは,変化にむかう「無限小」な傾向について,数学的概念が,同一にして他者ならんとするもの,<成り立つ>ためには<解消>しなくてはならない同一性のパラドックスをすべて含んでいるという。
ところが,その最後の部分に,半ば唐突に,「現実を通じて同一の線を跡付けて行くことの不可能性を,大変誇張したやり方ではっきり見せてくれるような考えを抱いている友人が,私に一人ある。」とした上で,彼の考え方によると,歴史を「科学的」なものにするのには,ただ,次のようにしさえすればよい。まず,任意の二つの時代(たとえば,十三世紀の終りと,十九世紀の終り)の内容を精確に定義し,次に,この二つの時代の一つから一つにむかっている変化の方向を精確に規定し,最後に,この方向線を未来にむかって延長すると,我々は,未来の任意の時点における,ものごとを実際の状態を規定できるようになる。(と言いながら)我々はみな,このように「歴史」を考えることがきわめて非現実的であることを知っているが,パースやベルグソンや私の信じているような連続的な多元論が現実の姿なら,展開現象はすべて,もっとも単純なものでさえ,我々の科学ににとって,手におえないものとなるだろう。というのは,科学が,現実の展開について,近似的な,ないし統計的に一般化されたそれでなく,文字通り精確な絵を我々に提供しようとするふりをしているとしての話であるが。と結んでいる。>一見分かりにくいが,疑似科学のことを批判するものであろう。そうはいいながら,友人の話を紹介しているのは,歴史についてのこのような方法に説得力がありそうなことを感じているからだと思われ,実は,私が日本史話三講でとりあげている「時代循環のパターン」そのものの方法であることに驚いている次第であるが,私としては,科学でなくデザインであり,そのように歴史をとらえることで,未来に対処する可能性が開けると考える次第である。興味あれば見てもらいたい。⇒日本史話の「時代循環のパターン」にジャンプ
吉田夏彦は「訳者あとがき」冒頭で,「現代のアングロサクソン哲学を代表する二大傾向としては,ふつう,プラグマティズムと分析哲学とがあげられる。この二つの哲学は,哲学の伝統に意識的にさからうこと,端的にいえば,伝統的な哲学における問題の新しい解決をめざすというよりは,古来の哲学における問題の提出のしかたそのものを批判していること,でも有名である。だから,これ等の哲学を理解し,その手法をものにするためには,必ずしも,伝統的な哲学の知識を必要としないとも考えられる。この点が,これ等の哲学が一部の読者をひきつけ,一部の読者に反発を感じさせる所以となっているのであろう。」と,哲学史上の位置づけを明快に述べている。>つまり,プラグマティズムは,それまでの「知」の世界を脱するものということであり,これこそが,「意=デザイン」の背景になる哲学であるということを示すものといえよう。
そして,「本書は,プラグマティズムの哲学もまた,絶対的観念論との対決から生まれ出た面のあることをしめしている書物として,・・・(また)現在,一般人には心理学の祖としてしか記憶されないフェヒナーを,哲学者として,かつ大きな共感をもって取り上げている点,ジェイムズが強い反感をもっていたといわれるヘーゲルに対しても,できるかぎりは,同情をもってこれを理解しようとしている点,ベルグソンに対する傾倒ぶりが熱情的に表現されている点など,歴史的にきわめて興味深いものである。」ことを指摘してする一方,「(論理の重視と軽視という項を設けて)ジェイムズは,哲学において,論証の技術よりは,むしろ,ヴィジョンの方を重視する哲学者である。・・・本書の後半に至って,論理が哲学において果たす役割を,急に低く評価しだす。」といい,論証の誤りの多いことも指摘している。>プラグマティズムの創始者パースのような頭脳明晰さに至っていなかったため,ジェームズの書「プラグマティズム」による広がりが,その正当な評価を損なうことになってしまったことも否めないであろう。その一方,あまりに論証を重視するがために,一般の人たちに影響を及ぼすことができない現代の科学的知の状況からみれば,ジェームズは学者というよりデザイナに近い存在であったともいえよう。
猪口純が出版したばかりの「ジェイムズ『多元的宇宙』のプラグマティズム~経験の彼方を問う経験論~」(晃洋書房・2021年)からも見直しておこう。⇒コラム
この論TOPへ
ページTOPへ
第三論:さらに,独自の宗教観もあって,ユングを掻き立てることになった
はじめに一言:いままでの話で,随所に,ジェームズのユングへの影響について触れてきたが,決定的な影響を与えたのはジェームズ「宗教経験の諸相」(1901年,日本語訳は舛田啓三郎,岩波文庫,上が1969年,下が1970年)で,本書は,ジェームズが,エディンバラ大学に招聘されて,1901年とその翌年の2回にわたって行ったギフォード講義「宗教経験の諸相」の講演録であるが,1896年に依頼を受ける(正式指名は1898年)と,アメリカの学者として初めてイギリスの大学に招聘される名誉にすぐに決意,宗教的体験を記録した伝記など,宗教関係の文献を広く渉猟,1897年初めには,本書序文で,「貴重な報告」を提供してもらった「面識はないが真の友人」と感謝するイースト・ノースフィールドのランキン宛の手紙に,すでに準備が整いつつあると告げている。しかし,そこに至る前,ジェームズは,1879年から96年までの十数年間に公けにした信仰および道徳に関する諸論文を,ジェイムズ自身が一巻にまとめて世に問うた,ジェームズ「信ずる意志」(1897年,日本語訳は福鎌達夫,日本教文社「W・ジェイムズ著作集2」,2015年)があるので,そこから入ることにする。1897年といえば,1890年に「心理学原理」を出版して大注目されるも,自らは哲学者になろうと決意して後,初めてまとまった著作として出版したものであり,ジェームズの覚悟もみられる書といえよう。そして,最後に,第二講以降のユングの話につなげるべく,そもそも本特別講義の契機になった小木曽由佳「ユングとジェイムズ~個と普遍をめぐる探求」(2014年,創元社)から,ポイントになりそうなところを拾うこととする。
第一話:信仰・道徳に関する諸論文を自らまとめた「信ずる意志」
ジェームズ「信ずる意志」(1897年,日本語訳は福鎌達夫,日本教文社「W・ジェイムズ著作集2」,2015年による)⇒フォト
「序」で,ジェームズは,今まで大学の講演に呼ばれるつど,その内容を評論誌に発表してきたが,それらをまとめてみると,自らが<根本的経験論>と呼ぶところの,明確な哲学的態度を示しているので,この際,一巻にまとめることにしたといい,一元論と多元論との相違は,哲学上のあらゆる相違のうちで,おそらくもっとも意味深いものであろうと記していることから,この問題が,早くから,ジェームズの考え方の軸になっていたことが分かる。そして,(科学学界における)信仰を受入れる素朴な性能の麻痺状態と宗教的領域への内気な<意志欠乏症>とは,かれらの精神的弱点の特殊な形態であるが,この弱点は,真理に関するあらゆる難破の危険を,必ず免れさせることになる科学的証拠と称せられるものが存在するという考えが念入りに染みこまされたために,惹き起こされたのであると,デザイン論で指摘した科学至上主義問題について,的確に指摘し,もっとも真に近い科学的仮説は,よくそういわれるように,もっともうまく「はたらく」仮説であるが,宗教的仮説にかんしても事情はそれと違うわけではない。宗教はどんどん人間の心から消え去っていったが,ある信仰箇条は,あらゆる世の転変を通じてもちこたえ,こんにちでさえこれまでにまさる生命力を保持していると,本書の意義も謳っている。最後のところで,本書をまとめるにあたっての諸論文の改訂は,ほとんどが(分量を減らすための)削除であって,新たな内容の加筆はあわせても一ページ半をこえなかったであろうと,考え方が一貫して変わっていないと誇っている。
扉のタイトルには,「信ずる意志」に続けて,その他一般むき哲学論文集とあり,扉裏には,旧友チャールズ・サンダース・パースにささぐとして,往時の彼の哲学上の友情に,また近年の彼の書著作に,私は表し報いうる以上の励みと助力を負うていると,自らの哲学的展開へのパースへの感謝を率直に述べていて,この頃は,まだ両者の間に齟齬はなかったといえる。あらかじめ,本書の章立てとその分量(ページ数)を示しておく。
| 第一章 | 信ずる意志 | 41p |
| 第二章 | 人生は生き甲斐があるか | 43p |
| 第三章 | 合理性の感情 | 59p |
| 第四章 | 反射作用と有神論 | 43p |
| 第五章 | 決定論のディレンマ | 49p |
| 第六章 | 道徳哲学者と道徳生活 | 38p |
| 第七章 | 偉人とその環境 | 52p |
| 第八章 | 個人の重要性 | 11p |
訳者あとがきによれば,原典には,このあとに,第九章「あるヘーゲル主義」,第十章「心霊現象研究のこれまでの成果」があるが,日本語訳のW・ジェイムズ著作集として,この一冊のみが分厚くなってしまうというそれだけの理由から割愛されたことを詫びている。第七章までのページ数に大きな差が無いのは,大学における講演という,おそらくほぼ同じ時間に話したものを文字化したことによるからで,ジェームズが,改訂はほとんど削除だけであったといっていることから,ページ数の少ないものほど,削除が多いことによると思えるが,第三章が厚いのは,ジェームズが指摘しているように,講演録の前に雑誌に発表した論文を加えているからである。第八章がとくに少ないのは,そこでジェームズが述べているように,第七章が呼び起こした二つの応答に対するもので,補遺として加えたものであることによる。
以下,適宜抜粋してコメントしてみる。
第一章「信ずる意志」は,全体のタイトルにも使われているように,ジェームズの考えをもっとも簡潔に示すもので,「信仰<を>義とすること,いいかえれば論理一辺倒な知性人に,事実上それを強いるわけには行かないけれども,われわれが宗教上のことがらを信じる態度をとる権利の養護」なのである。まず,われわれの信念に提示されるものすべてを<仮説>とすると,生きている仮説とは,それが提示される当事者の心に本当に可能なものとして訴える力のある仮説であり,仮説が生きているか死んでいるかは,それ固有の性質ではなく,それを考える個々人に対する関係で,それを測る尺度は個々人の行動意思にほかならない。>つまり,行動につながるかどうかということである。
そして,「一般にわれわれは,自分に用のない事実や理論を一切信じない。・・・われわれの確信は知性以外の性能に左右される。」ことを前提に,<数々の命題中のどれか一つの選択が,その性質上,知的な根拠に基づいては決められえない正真正銘の選択であるいかなる場合にも,その選択はわれわれに固有な感情によって決められることが単に合法的であるばかりでなく,必ずそれによって決められなければならない。というのも,このような状況のもとで「問題を決定せず,未解決のままにしておけ」と語ること自体が,そのイエスかノーかを決めることとまったく同様,一つの感情的な決定であり,また真理を失う同じ危険にさらされているからである>というテーゼを擁護している。決定されなければならないのは,思考がどこから由来するかではなしに,それがなにをみちびくかである。>過去とは関係なく未来を決めなければならないということ。
<道徳的問題>は,直接には,それを解くために感覚的な証明を期待することのできぬ問題の形をとってあらわれる。道徳的問題とは,感覚的に存在するものではなしに,善とはなにか,あるいはもし善が存在するとすればそれはどのようなものか,といった問題であると出てくるが,「善」について,それ以上にならないのは,デザイン論でも述べたように,アリストテレスによる「善」になお拘束されている西洋哲学の問題でもあるといえるが,とにかく道徳的信念をいだくか,いだかぬかという問題は,われわれの意志によって決められると述べているのを見れば,「意」と「善」が一体であると認識していることは確かである。>道徳は外部の形式(デザイン)で,善は個々人の心の問題か。
そして,「なんびとも他人の生き方を拒んではならないし,また口ぎたなくののしりあうべきでもない,それどころかわれわれは相手の心の自由を互いに細かく気をくばって謙虚に認めあわなければならない。そうすることによって,はじめて知性の共和国が具現される。」というのを聞けば,ジェームズが西洋的個人主義を脱して,東洋に近い心情を有し,これが,ユングとかなり相通じるものであったと思えるし,共和国という言葉には,デザイン論で述べた「共の創出」と重なるものがある。
第三章「合理性の感情」では,「哲学的な自然の概念が労力を節約するための一方策であり,思考上の極度の節約や手段の経済への熱情は<特に際立った>哲学的熱情である。」と述べているが,デザイン論で述べた,情報理論との関係におけるデザインの意義そのままである。そして,「ある人たちには,それに匹敵する識別への熱情,全体を捉えるよりも部分に<なじもう>とする衝動があり,哲学的態度は,これら二つの渇望の均衡のいかんによって決められ,どちらか一方に偏ったものは,人々に広く受け入れられない。・・・多様と統一との仲立ちをする唯一の途は,多様な諸項目をそれらのうちに見いだされるある共通な本質の事例として組み入れることである。このようにものごとを広範な<いくつかの種類>に分類することが哲学的統一化のための第一段階であるとすれば,それらの関係や行為を広範な<いくつかの法則>に分類することはその最終段階である。」とあるのも,デザイン論の暗黙知に入る前の形式知と,暗黙知を経たあとの形式知の話にそのまま重なる。ということは,哲学は科学でなくデザインであるといっても過言ではなくなり,実際,以下続く文については,抜粋やコメントを省略するが,そのままデザイン論として読むことができるといえる。
第五章「決定論のディレンマ」では,「第一に,われわれが世界にかんしてかずかずの理論をたて,それを相互に論議する場合,われわれがそうするのは,われわれに主観的な満足を与えるようなものごとについての考想に達せんがためなのである。また第二に,二つの考想が存在し,しかもその一方が他方にくらべ,全体としていっそう合理的なように思われるとすれば,その方がいっそう真に近いと仮定する権利がある。」という仮定から出発して,決定論がさまざまな問題を引き起こしていることを論じている。
第六章「道徳哲学者と道徳生活」では,「倫理学には,切り離して考えられなければならない三つの問題があり,<心理学的問題>として,道徳的な観念や判断の歴史的<起源>をたずね,<形而上学的問題>として,「善」や「悪」や「責務」という言葉の<意味>がまさしくなんであるかを問い,<決疑論的問題>として,哲学者が人間の責務の真のありかたを確定しうるような人びとの認めるさまざまな善悪の<尺度>は何かを問いただす。」として,論を始めているが,結論的に言ってしまえば,ジェームズをしても,アリストテレスの束縛から脱し得ていないと言わざるを得ない。繰り返しになるが,「知・真」が社会の人々の共通の理解のため,「情・美」が社会の人々の共感のためである以上に,「意・善」は,社会の人々の役に立つ,助けになることであるはずで,他者を前提としない西洋の個人主義の限界を示しているようにみえる。>残念ながら,西田幾多郎の「善の研究」も,文明開化の果てのものであったことはすでに述べたとおりである。
第七章「偉人とその環境」と,それを受けた形の第八章「個人の重要性」は,デザイン論での,デザインやデザイナの概念や,デザインは個人に属し,デザイナになるにはそれだけの環境が必要であるという話との関連で読んでみるのも面白いであろう。
第二話:ユングに決定的な影響を与えた「宗教経験の諸相」
ジェームズ「宗教経験の諸相」(1901年,日本語訳は舛田啓三郎,岩波文庫,上が1969年,下が1970年による)⇒フォト
舛田の解説によれば,ジェームズの伝記を書いた(ラルフバートン)ペリーが,「ギフォード講義は,(父が1882年に亡くなった)子としての孝心および個人的な経験に発したものであると同時に,90年代の彼を支配していた心理学的関心を表現したものである。」と書いていること,その前半は,のちに,「プラグマティズム」で,「私自身は,神の証しは第一義的には内的な個人的経験のうちにある,と信じている」と書いているように,ジェームズの生涯の思索を支配したものであり,後半の心理学的関心とは,心霊現象へ興味をもって,精神病理学,異常心理学の研究に強い関心を示したことをいうが,舛田は,ジェームズが,1869年から翌年にかけて,自ら「宗教的憂鬱」と呼ぶ恐ろしい精神的不安と,そこから抜け出した個人的体験がもっとも大きい動機であったのではないかという。ジェームズは,この危機が,「生きる支えとなるような哲学を欠いているところから生じた,生きようとする意志の衰退~道徳的無力感に起因する活動の麻痺であった」とし,フランスのルヌーヴィエの自由意志説から啓示を受けて脱したという。そして,第一話で示した,ジェームズの最初の論文集「信ずる意志」(1897年)に見られるような意志的な種類の宗教となって結実し,善を求めて悪と戦う道徳的意志は,人間の強さから生ずる「戦う信仰」とならざるをえなかった。>危機を脱した直後から,パースたちとの形而上学クラブが始まって,プラグマティズムがまさに自然に吸収されていくのであり,「信ずる意志」がパースに捧げられているのである。
この講義の原稿は,ジェームズが第二回の講義のためにアメリカを立つ前に印刷に回され,帰国した時には,「宗教経験の諸相~人間性の研究」というタイトルで出版されていて,大成功をおさめ,驚くべき売れ行きを示した。アメリカの学者ばかりでなく,1903年初のベルクソンはじめ,ヨーロッパの多くの学者も絶賛の書簡を寄せたのである。1911年,ジェームズの「プラグマティズム」のフランス語訳が出版された際,ベルクソンは序文を書いてこれを推奨したが,同じような魂と思想をもって互いに尊敬し合った友に対する真の理解を示すとともに,深い親愛の念を感じさせるもので,ジェームズを語った他のいかなる論説も及ばぬ,美(?)事な文章であるという。>ユングに影響を与えたのも当然であった。 そして,ジェームズの「プラグマティズム」は宗教的経験に起源があるとベルクソンが言うとおり,ギフォード講義の準備を始めてからまもなく着想されたもので,1898年のカリフォルニア大学でのジェームズの講演「哲学的概念と実際的効果」は,プラグマティズムの烽火と言われ,この新しい哲学の誕生を告げた記念すべき論文として知られる。>パースのプラグマティズムの格率を世に知らしめたもの。気質を異にして異なる方向に進んだパースも,この書を「人間の心の洞察のゆえに」,ジェームズの書物のなかでも「最善のもの」であると高く評価し,ジェームズを「人間の魂を描くことのできた芸術家」であると讃えたのである。
舛田は最後に,この書の題名が「宗教」と「経験」と「諸相」のいわば三一的構造をもつジェームズ哲学の特質を,実に適切に表現していると感嘆していたところ,ジャック・パーサンも同様のことを述べているのを知ったという。>さすがに本質をついているが,付け加えれば,三一的構造は,プラグマティズムを創造したパースの本領でもあった。 さらに,追記する形で,原著の扉裏で,ジェームズが,子としての感謝と愛情をこめてささげているE・P・Gとは,義母ギッペンスのことで,妻への気持ちも間接的に伝え,子という形で亡父への気持ちも表現しているが,ジェームズが,本書の結論で,宗教的生活の特徴として数えている最後のもの,すなわち「平安の気持」と「愛情の優越」の生きた模範であったからだという。
あらかじめ,本文の章立てと分量(ページ数)を示しておくと,
| 第一講 | 宗教と神経学 | 33p | |
| 第二講 | 主題の範囲 | 38p | |
| 第三講 | 見えない者の実在 | 37p | |
| 第四・五講 | 健全な心の宗教 | 74p | (一講平均37p) |
| 第六・七講 | 病める魂 | 56p | (一講平均28p) |
| 第八講 | 分裂した自己とその統合の過程 | 36p | |
| 第九講 | 回心 | 40p | |
| 第十講 | 回心~結び | 62p | |
| ―――以上,上巻(前期分)計 | 376p | ||
| 第十一・十二・十三講 | 聖徳 | 101p | (一講平均34p) |
| 第十四・十五講 | 聖徳の価値 | 71p | (一講平均36p) |
| 第十六・十七講 | 神秘主義 | 78p | (一講平均39p) |
| 第十八講 | 哲学 | 39p | |
| 第十九講 | その他の特徴 | 39p | |
| 第二十講 | 結論 | 51p | |
| ―――以上,下巻(後期分)計 | 379p | ||
| 書物にする際につけた後記 | 10p |
>一見して,毎回同じであったと思われる講義時間に対応して,几帳面といえるほど,分量も同じにしており,当然のことながら,前・後期それぞれ最後の講義時間が長かった分多くなっていること,ふつうは,講義録を書物にする場合,再構成したり,追加・削除・改訂などが多々あると思われるのに,わずかな後記を付けているだけなので,20回にもわたる講義に先立って,そのタイトルを見れば,それだけで何を語ろうとしているのか,その順序も含めて実によく構築されていていることが分かるが,このことは,今まで取り上げてきたどの書物にも共通しており,ジェームズのデザイナぶりが窺える。そのデザイン力以前に,各講義のタイトルそのものが,ユングが,精神医学において重視し,悩んでいたことに直結するものであり,決定的な影響を与えたといえるだろう。
もともとが,アメリカの心理学を創始し,プラグマティズムを世間に周知せしめるような,単に博学とは言い切れないジェームズが,膨大な資料を活用し,満を持してまとめたものであり,ユングの転生にも決定的な影響を与えることになったものであるゆえ,とても個々の内容には入れず,適当につまみ出して述べることも,バチが当たると思えるので,皆さんには,本書を読んで頂くこととするが,デザインつまりカタチの面から言えそうなことと,プラグマティズムや「善」など,何度もでてきたことについて関係のありそうなをことがでてきた場合のみ,取り上げてみよう。
第一講「宗教と神経学」で,既往の唯物論的な(精神)病理学を否定,心に重きをおく(精神)神経学の面から入るが,中間に,「善」にかかわる話として,内在的な基準と外面的な基準とは,(例えば)内面的に幸福であるということと,役にたつというということとは,必ずしも一致しない。「善い」と直接に感じられることも,「真」とは限らないとして,酔っぱらった状態としらふの状態の差異を例に出しているのをみると,「善」についての定義があいまいなのは今まで述べてきたのと変わらないが,それに続くかたちで,天才の業績を病気の果実であるという説が横行しているのを断固否定しているのが面白い。そして,聖テレサの存在をも,<直接の明白性>,<哲学的合理性>,および<道徳的有用性>から評価している。>プラグマティズムそのものといえよう。
第二講「主題の範囲」では,宗教とは,<個々の人間が孤独の状態にあって,いかなるものであれ神的な存在と考えられるものと自分が関係していることを悟る場合だけに生ずる感情,行為,経験である>と定義し,世間では一般に宗教的だと呼ばれながら,神というものを仮定しない思想体系がいろいろあり,その例として仏教をあげて,無神論的な体系であるとしている。>仏教や儒教を取り入れて深化させた日本は,自然に,人の創造すなわちデザインが身についている可能性があるとも考えられる。 結論として,<かくして,宗教は,どのみち必要なものを,容易にし,よろこんで行わせるのである>。そして,もし宗教がこの結果を成就しうる唯一の原動力であるとすれば,宗教が私たちの生活の本質的な機関となり,私たちの本性の他の部分ではそれほどうまく果たせない一つの機能を果たしてくれるのであるとしている。>これまた,プラグマティズムそのものといえる。
第三講「見えない者の実在」では,私たちの見ることのできない対象に対する信仰のもっている心理的特質の二,三について,諸君の注意をうながしたいと思う。すべて私たちの態度は,道徳的,実際的であれ,感情的であれ,宗教的態度と同じく,私たちの意識の「対象」,つまり,実在的にせよ観念的にせよ,私たち自身とならんで存在していると信じられる事物,に起因するとし,以下,さまざまな事例を列挙することで証明しようとしているが,一種のアブダクションであろう。そして,合理主義が支配していることが,これらを隠すことになっているとする。>「知」の支配への反論であるが,なお「知」を脱していないところに歯がゆさが残る。
第四・五講「健全な心の宗教」では,そもそも悪を全く感ずることのない人物として詩人ホイットマンの例を挙げながら,万物を善であると見るこのような傾向を健全な心と名づけるとき,そうなるには,事物について直接的に幸福を感じる無意識的な方法と,事物を抽象的に善と考える意志的あるいは組織的方法のあることを区別しなければならず,・・・楽観的な心の傾向を意識的に用いる人は哲学に旅立つことになる。>わが身を振り返ってみてなるほどと思う。 健全な心を一つの宗教的態度として組織的に涵養するのは,少しも不合理なことではないとし,「進化論」が,キリスト教を追い出して,あたかも宗教の代用品になってしまったと嘆くなどしたのち,精神治療の教養の源泉をなすものの一つは四福音書であるが,精神治療運動のもっとも著しい特徴をなすものは,はるかに直接的な霊感であり,実際的成果をあげたことが普及の理由であるとし,以下,さまざまな事例を列挙して,アブダクション的に証明して行くのである。
第六・七講「病める魂」では,健全な心の気質が,苦悩を長引かせることができないため,ものごとを楽観的にみようとする気質で,それが,善こそが,理性的存在たる者の心すべき根本的事柄であると考えるような(前講の精神治療に関わる)特殊な宗教(前講の精神治療に関わる)の基礎になったが,それとは対照的に,悪を最大限度に拡大させてゆく,悪い面の方が世界の本質であると考える気質がある。ここで,ラテン系の方が前者に傾いているのに対して,ゲルマン系は,罪を単数形の大文字でみてしまう傾向があるという指摘は,今では,口にしにくい民族論かもしれないが,ゲルマン系が,プロテスタントが登場させ,資本主義と組み合わさって,世界を支配するようになったことに繋がっていると思えば,面白い指摘でもある。そして,前講同様,さまざまな事例を列挙して,アブダクション的に証明して行く。>(以下,小木曽の書より)この講義の最後は,「圧倒的な恐怖という形」をとった「もっとも悪質の憂鬱」の一例として,ある手記を取り上げ,のちに,これが自分自身の体験であると告白している。1869年,ハーバード大学から医学博士号を授与されたジェイムズは,この時期,健康状態の悪化から慢性的な鬱症状に悩まされ,深刻な病状に至り,ついに「自殺」こそが自由意志の最も正当なる表現と考えるまでに至ったが,翌年になって,フランスの哲学者シャルル・ルヌービエの「一般批判論集」の中の自由意志に関する一節に出会い,衝撃を受け,「死と復活」の意味を感受することになったことは,既に述べた。
第八講「分裂した自己とその統合の過程」は,タイトルから見て,本書全体のなかでも,ユングに大きな影響を及ぼした講とみられるが,前の4回の講義で見た二つの型が,その極端な形,すなわち純粋な自然主義と純粋な救世主義という二つの形として著しい対照をなしているとした上で,困難にうちかって内心の統一と平安に到達する過程について,徐々に生ずる場合,突然起こる場合があり,また,感情の変化によって生ずる場合,行動力の変化によって生ずることもあるとして,それまで同様,事例を列挙して行くことになるが,その最初に,日本人が仏教の戒律によって体得する自制,自ら,怒りと気苦労を取り除くことができると語った例を挙げている。>東洋の宗教への理解が,ユングの共感を得たことも間違いない。
第九講「回心」,第十講「回心~結び」では,冒頭,回心する,再生する,恩恵を受ける,宗教を体験する,安心を得る,というような言葉は,それまで分裂していて,自分は間違っていて下等であり不幸であると意識していた自己が,宗教的な実在者をしっかりとつかまえた結果,統一されて,自分は正しくて優れており幸福であると意識するようになる,緩急さまざまな過程を,それぞれあらわすものであると定義している。>一言でいえば,統合過程であろう。 けっして回心することのない人があり,ありえない人もいるが,・・・信仰上の用語でいえば,一生涯「不毛」と「乾燥」人であり,・・・場合によっては,知的なものが原因になっていると一蹴した上で,以下,またしても事例を列挙,意志的な型の回心の例は多いが面白くないとして,潜在意識的な影響が豊富で突発してしばしばひとを驚かせる自己放棄型について詳しく解説している。>聴衆に期待を抱かせるような結びに至るのは流石である。
第十一・十二・十三講「聖徳」,第十四・十五講「聖徳の価値」では,冒頭で,愛,献身,信頼,忍耐,勇敢などについて人間性がこれまでなしえた最高の行為は,宗教的理想のためになされたものであったとし,人間の性格というものは,知性とは違ったものであって,性格に関するかぎり,個人差の原因は,主として<情緒的刺激の感受性の相違>,および,そこから生ずる<衝動と抑制の相違>にあるとし,相反する感情が混じり合っている場合,「イエス」と「ノー」の両方の声が聞こえることになり,そこでその衝突を解決するために,「意志」が呼び出されるのであり,真の意志は単なる願望とは全く違うと明確に指摘する。そして,人間が宗教を自己の人格的エネルギーの中心として生き,霊的な感激によって動かされるようになると,その人間はいろんな点ではっきりと以前の肉体的自己とは違ったものになるが,このように,古くからの性癖が急速に一掃されるということには,潜在意識の影響が決定的役割を演じているのだと思わないわけにはいかない。>ユングそのものである。
そして,ようやく,タイトルの聖徳というのは,宗教が人間の性格に実らせるふくよかな果実をあらわす集合名辞であることを示して,ふつうに生じる果実の例である<慈愛><兄弟愛>をスタートに,以下,さまざまな果実について,事例を挙げながら詳しく解説して行く。それを受けて,価値を論じる段になると,直接,私(ジェームズ)の方法を事実に適用してみようと,プラグマティズムの見方になるのは当然として,すべての聖徒たちに見いだされる人間的な慈愛,またある聖徒たちに見られる過剰な慈愛こそ,真に創造的な社会的力であり,ある種の徳の実現が,彼らの人間的な慈愛によってのみ可能であることを認めることができ,聖徒たちこそ善の創造者であり,<作者>であり,増進者であるという。・・・聖徒は善の有力な酵素であり,地上をいっそう天国的な秩序へと徐々に変えてゆく人である。>ここにきてようやく東洋での善と同じような見方になり,この善を,聖徒らという特別な人たちがなすというのは,デザイン論からみると,荻生徂徠のいう聖人に対応するデザイナに当たるが,誰もがデザイナであるためには,誰もが善を為すべきであるということになる。
第十六・十七講「神秘主義」では,前の講義の後半,ジェームズは(もっぱら「知」ばかりを優先する)現代文明を批判することで,本人もいうとおり,幾度となく問題を提出しながら避けてきた神秘主義の話にようやくつなげ,ある経験が,次の四つの標識をそなえていれば,「神秘主義」「神秘的」と呼んで良いのではないかと提唱する,①経験した者が<言い表わしようがないということ>,②感情の状態に似ているが知識の状態のようでもある<認識的性質>,③長い時間つづくことができない<暫時性>,④一度あらわれると自らの意志ではどうしようもなくなる<受動性>を挙げて研究すべき群と言うにとどまり,以下,典型的と思われる神秘体験の事例を数多く挙げたのち,世界の主な宗教は,こういった神秘体験に入る方法を養成しているとして,ヒンズー教のヨガ,仏教の禅,イスラムのスーフィー派などを挙げて,解説している。>ユングと大きくつながる部分。
第十八講「哲学」は,神秘主義という,「知」の世界が避けて通るものの話をしたのから一転して,哲学の話に持ち込むやり方も流石であるが,哲学は,その発表する結論がいやしくも妥当なものであるならば,普遍的に妥当すべきことを要求する。・・・哲学は果たして,宗教的な人間がもっている神的なものの意識が真実であるという保証の刻印を押すことができるであろうか?と問い,感情というものが宗教の深い深い源泉であり,哲学的な方式や神学的な方式は第二次的な産物であると信じている,つまり,宗教的感情というものがかつて一度も存在したことのないような世界には,そもそも哲学的な神学など形成されえたものかどうか疑わしいと,自ら答えている。そして,一連の議論を経たのち,優れて独創的なアメリカの哲学者チャールズ・サンダース・パース氏は,これらの人々を本能的に導いている原理を,個々のの特殊な場合におけるその適用から取り出し,この原理を根本的なものとして抜き出して,プラグマティズムと名づけたとして,その論を紹介,プラグマティズム的に考えると,道徳的な属性はまったく違った意義をもってくる。それは恐怖と期待を積極的に規定し,聖なる生活の土台であるとし,教義神学の証明の不毛ぶりをついて,(異端とされる)ヨブ記はそのような証明を断然きっぱりと乗り越えてしまっている。・・・途方にくれ挫折した知性,けれども神の現前を信ずる心~これが,自己自身に対しても現実に対しても真剣な,そしてどこまでも宗教的な人の状況なのである,と言い,プラグマティズムの立場からみると,神の重要性の最たるものは,神の懲罰的な正義であると注記している。最後は,もし哲学が形而上学と演繹とを捨てて,批判と帰納につき,そして進んで神学から宗教の科学に変身するならば,哲学は非常に役立つことができると結んでいる。>ユングの著した「ヨブへの答え」については,彼の遺言の書として,第三講第二論で,触れることになる。
第十九講「その他の特徴」では,神秘主義と哲学とを一巡して,元の道に戻ってきたとし,宗教をもっている個人に対する効用,そしてこのような個人自身が世界に与える効用,これらこそ宗教のなかに真理があるということの最善の論拠であるとした上で,最後の結論に至る前に,宗教的意識のもっている他の特徴的な要素のいくつかの一言するとし,まず,人が,ある宗教を選ぶ場合,その決定にあたって美的生活が演ずる役割(教会建築や宗教音楽),次に,たいがいの宗教書に挙げられている,宗教のもっとも本質的な三つの要素,犠牲,告解,とくに,祈りの役割(儀式化されたものでもある),最後に,宗教生活のあらわれと私たちの存在の潜在意識的な部分とが関連している場合が非常に多いという事実(霊感や開示)を,それぞれ解説している。>今まで触れずにきたが,ここまでくると,デザイン論で,デザインという概念をつめる際に,もっとも古くかつ大きいものとして宗教があるとしたことと繋がる話であったと思わざるを得ない。
第二十講「結論」:簡潔な結論とはいかないのは当然であるので,ジェームズがとくに言っておきたいと思われるところを拾ってみると,「個人は,自分の狂いに悩み,その狂いを正常でないと感じている限り,その狂いを意識的に越えているのであり,少なくとも,何かより高いものが存在するなら,それに触れているのである。・・・解決あるいは救いの段階に達すると,その人は,自分の真の存在は,自分自身のより高い萌芽の部分であることを,これと同一性質の,より以上のものと境を接して連続していることを意識するようになり,このより以上のものは,彼の外部の宇宙で働いておりながら,それと現実に接触することができ,彼の,より低い部分が砕け散ってしまったときに,辛うじてそれにしがみついて,救われることができるようなものであることを知るのである。」「私は仏教のことはしらないが,業(ごう)という仏教の教義について私が了解した限りでは,原理的に賛成する。」「このまったくプラグマティックな宗教観は,ふつう,一般の人々には当然のことと見なされているものである。・・・私は宗教をプラグマティックに解する方が,いっそう深い見方だと信じている。この見方は,宗教に魂と同時に肉体を与える,すべて現実的なものが要求せざるをえないように,この見方も自分自身の領分として或る特有な事実の領分を宗教に要求させる。」などである。
付け加えられた短い「後記」で,「私が問題を,このようにぶっきらぼうに述べるのは,学者仲間の思想の大勢が私とは反対の方向をとっているからである。そして,私は自分がまるで,せっかく開いている戸が目の前で閉められ,錠を下ろされるのを見たくないなら,急いでその開いている戸に背を向けなければならない人間のような気がする。」「一元論的な見方を支持する人々は,このような多神論に対して(ついでながら,この多神論こそつねに一般民衆の事実上の宗教であったし,今日でもそうなのである),万物を含む唯一神が存在しない限り,私たちの安全の保障はどこまでも不完全であると言うであろう。」などと記しているのも,とくに言いたかったからだろう。
第三話:小木曽「ユングとジェイムズ」にみるユングへの影響
小木曽由佳「ユングとジェイムズ~個と普遍をめぐる探求」(2014年,創元社)より第2章:タイプ理論とプラグマティズム~"個人的方程式"としての諸類型
ジェイムズと会って3年後の1912年,再び渡米したユングは,フォーダム大学での講演で,ジェイムズの「プラグマティズム」からの長い引用とともに,「自らの導きの糸として受け取った」と明言し,1914年の論文「精神病の意味」には,「私は,ジェイムズがプラグマティズムに関する本の中で行った,二つのタイプに関する優れた叙述をとくに強調したい」と記述,この論文がそもそも1908年のチューリッヒでの学術講演の講義録で,6年後に出版される際に書き加えられたことからも,ジェイムズからの影響がいかに大きかったかが示されている。1913年のフロイトと訣別後で,まだ精神的衝撃の小さかった時に,ユングは,「タイプ論」への準備ともいえる講演「心理的諸タイプ」を行っているが,すでに,ジェイムズの理論の要約の域を越えて,そのまとめ方や解釈において独自性が現れており,「タイプ論」では,「第8章:現代哲学におけるタイプの問題」全体が,ジェイムズによる類型の解説に充てられることになる。そして,ジェイムズから受けた,心理学的認識は常に主観的な偏重によって構成されていることに気づくことというプラグマティズムの先の,ユングの独自性は,そうするためには,観察者が自分自身の人格の範囲に十分に精通していることが必要であり,それができるのは,集合的判断という平均化する影響から高度に自由になり,それによって自分自身の個性を明確に理解するに至る場合だけであり,これこそが,ユングの「個性化」の原典であるという。>デザイナたらんとする人も当然に心すべきことと思われる。
第3章:「赤の書」と「タイプ論」~「私」の神話をめぐる探求
1913年の講演「心理的諸タイプ」から,1921年に「タイプ論」が上梓されるまでの8年間は,「赤の書」に示される,ユングの無意識との格闘の時期と全く重なっていることを見過ごすわけにはいかないが,ユング自身,1925年のセミナーで,「経験的な素材はすべて患者から得たものですが,その問題の解決は,内側から,無意識の過程に関する私の観察から得たものです。私は,タイプの本の中で,外の体験と内の体験という二つの流れを融合させようと試みました。」と述べている。また,前記の「タイプ論」の第8章の最終節に「ジェイムズの見解を批判するために」で,プラグマティズムの方法がいかに不可欠であろうとも,この方法はあまりにも多くの断念を前提としており,創造的形成に欠けることはほとんど避けがたい」というのは,プラグマティズムは,個々人の葛藤をいかに解消するかという問題については扱わないからである。>デザインはその葛藤を乗り越えるためのものと思う。ジェイムズであったが故の限界で,パースに戻ることが必要なのではなかろうか。 「赤の書」において顕著なのは,多種多様の対立物のペアで,「深みの精神」と「この時代の精神」に始まり,「生・死」「光・闇」など抽象性の高いものから,具体的な人物の形をとったものであるが,全体を通じてユングのイメージに登場する預言者サロメと盲目の少女サロメに注目し,それらが,「タイプ論」における対立物の結合という,「心理的諸タイプ」に見られなかった新たな重要なテーマになると,「第5章:プロメテウスとエピメテウス」を取り上げて論じている。>対立は,二元論という西洋思想の根幹に関わるもので,本講義の第二講「赤の書」内で触れるように,第三者が登場することによる場面変化があることから,ユングはそれを乗り越えようとしていたのである。 最後に,個別的なイメージ体験を突き詰めた「赤の書」と,一般的な理論としての「タイプ論」は,現れ方や方向性こそ大きく異なるが,ユングという個人の中で,分かちがたく結びつき,創造的に交流していたはずであると結んでいる。>まさに,暗黙知と新たに産まれる形式知の関係であろう。
第4章:個性化と宗教的経験
その後も,自らの神話ともいえる「赤の書」への取り組みを続けていたが,1928年にヴィルヘルムから「黄金の華の秘密」を受けとると,そこに書かれた道教の錬金術に,「現実への道を見出し」,もはや「赤の書」に取組むことはできなくなったと,1930年を境に,完全に遠ざかってしまい,以後,晩年に至るまで,錬金術の研究に没頭することになる。それでも,「自伝」で,「赤の書」は,私の生涯の仕事の<第一資料>と表現して,自らのうちに潜勢的に存在したことを認めている。それよりも,「タイプ論」で,人間の成すいかなる判断も,その人のタイプに制限されており,いかなる観点も,相対的なものであるという認識をもたらした。その結果,こうした多様性を補償する統一性への問いが頭をもたげたのであると回想している。言い換えれば,「個別性」を担保して「普遍性」にいかにつなげるかということで,ここで,ユングが,ジェイムズのもう一つの主著「宗教的経験の諸相」を,著作・講演等において頻繁に取り上げているが注目されるのである。ジェイムズが,個々人の個別的な体験を重視しながら,それにとどまることなく,共通性を論じようとしていること,とくに,「制度的宗教」と「個人的宗教」を厳密に区分し,後者を「より根本的」で「根源的な事柄」と明言することへの共鳴が看取され,ユングの宗教論のうちに顕著な類縁性として現れることになる。ユングは,1936年の論文「元型~特にアニマ概念をめぐって」で,「諸相」の「記述的」方法論や,日常の意識に対して垂直に突き上げてくるような「超」意識的な(秀逸な)体験の事例を多数取り扱っていることを高く評価しており,真理とは,事実であって,判断ではないという認識など,ここでも,両者はほとんど重なるのである。
ジェイムズがのちに自らの体験と告白した「諸相」の七講「病める魂」の最後の極端な鬱症状の事例と同様,ユングも「死と復活」を体験,一度は「圧倒的」な力の前になすすべもなく,バラバラに砕き去られた自我が,ある統合性をもって再度まとめ上げられる。この変容は,憂鬱以前への回帰を意味しない。>新たな自我ということであり,デザイン論での,暗黙知後の新たな形式知に対応するものである。また,統合ということが,ユングをして錬金術の曼荼羅に没入させることになったが,デザイン論上,暗黙知でカタチにまとめあげるのがマンダラであるとしたことに対応するのである。さらに,小木曽が,ユングは「宗派」宗教を過小評価していたわけでないとして,わざわざ付け加えているのは,教義もまた,人間の力を超え出た非合理なものを説明する体系としては,学問的な理論などよりもはるかに洗練されたものと考えられるとしているのは,デザイン論中で,宗教こそ最古最大のデザインであると述べたことと,見事に一致している。
第5章:個性化と多元的宇宙
小木曽は,ユングが「個性化」論で目指した<個性>の意味について,「個別性」を見直し,ジェイムズ晩年の著作「多元的宇宙」を手掛かりに,「赤の書」に始まるユングの思想が,錬金術への傾倒を通して,最終的にどのような着地点を見出したのかを追うとして,まず,ユングの「個性化」論の特質を論じたのち,「個別性」と「普遍性」に関する問いこそ,ジェイムズが自らに課した問題でもあり,「多元的宇宙」において,自らのプラグマティズムを支える世界観について「多」と「一」の問題を提出,多元論こそ世界に対する「親密さ」を育てるものであるとして,多個型を奉ずる「多元論」「根本的経験論」を,全体形を奉ずる「一元論」「絶対論の哲学」と対比して論を展開しているとする。ユングが,ジェイムズの「多元的宇宙」について直接言及していないため,ユング自身の意見を知ることは難しいとした上で,ユング派の元型的心理学の提唱者ヒルマンが,現代心理学の理論構成の根幹における「多神論か一神論か」の葛藤として問い直し,ユングの心理学が「多神論的心理学」であると相対化したとことに言及,ヒルマンの1971年の論文によれば,「多か一か」という問いの響きそのものが,われわれがいかに「一」に向かう傾向に支配されているかを示していて,「統一」や「統合」という概念が,「多数性」や「多様性」よりも発達している印象を与え,神学では,一神論が,多神論やアミニズムより進化した高次の形態であるという説がまことしやかに論じられ,ユング心理学でも,「自己」が「アニマ」などの元型に比べて上位に置かれ,他の元型は「自己」の前段階としか見なしていないと疑義を提出したが,この論文の10年後の追記の末尾に,ジェイムズの「多元的宇宙」を,半ば唐突に引き合いに出しながら,「個別性。それこそ。私がジェイムズと,~そしてユングと共有するところである。・・・ジェイムズにとって個別性とは,個性化の過程を通して達成されるものではなく,すでにそこに,<それが見える通りに>存在するものなのである。」と,さらに,見直しを進めている。
小木曽は,錬金術と決定的な出会いをしたユングが,その研究を進めて行くうち,「個別性」に結び付く二重の「普遍性」,すなわち,第一に,錬金術師の<作業>の中にユング自身の「個別的」な試みの「普遍性」(形式としての普遍性)を,第二に,錬金術の世界観において「個別性」を突き詰めた先に示されたものとしての「普遍性」(内容としての普遍性)を見出したのではないかいう。ユングが「赤の書」で行っていた取り組みは,まさに,<作業>の普遍性であったが,錬金術研究を通して,「赤の書」に閉じ込めた「個別的」な世界は,歴史的な試みとしての「普遍性」とつながり,別の他者の「個別的」な取り組みをも結びつけることを可能にする理論的支柱を得,最後の著作「結合の神秘」に至るという。「結合の神秘」の最後には,「一なる宇宙」という概念をめぐって,「普遍性」の問題を直接取り上げ,考察しており,錬金術において最も重要な<賢者の石>の製造にかかわるドルネウスの「重要な例外」としての議論を解説する中で,「経験的世界の多様性は経験的世界の統一を基礎として成立している」「われわれの経験的世界の背景は実際に「一なる宇宙」であるように思われる」といった世界観を随所に示しており,結論として,ジェイムズの「多元的宇宙」とユングの「一なる宇宙」が指しているものは,偶然とは思えないほどの一致点を示しているのではないだろうかと結論づけている。>たぶん,なんとしてでも「一元論」を抑えるべく,ジェイムズが提示した「多元的宇宙」であったが,錬金術を身につけたユングは,そのさらに先に,「一なる宇宙」があるといっているのではないだろうか。天文科学において,無数の銀河が見つかっていることに例えれば,「一元論」は,われわれの属する銀河系のみがすべてであるように見ているのに対し,「一なる宇宙」は,その無数の銀河全体を指し示す宇宙ということであろう。デザインにおいても,安易な一元論は止めにしてほしいものだ。
>以下,余談になるが,ユングが代表作となる大著「タイプ論」を出版してもなお,迷いのあったところ,道教の錬金術の曼荼羅に出会って,その思想が確立したことを想えば,ジェームズが「心理学原理」を出版してもなお,それを専門とせず,プラグマティズムに出会って,その思想が確立したことが,そのまま対応しているようにも見える。そして,ジェームズが偏りのない思想へと展開できたのは,ヨーロッパの哲学者ベルクソンによるといわれていることから,ジェームズはユングを通じて,ヨーロッパにその思想を返したともいえよう。
この論TOPへ
ページTOPへ