引田康英の九品塾・選択講座
歴史人物にまなぶ 年齢適活三講
第Ⅰ講:活動を究める
職能からみた新日本人論:スポーツとデザインに可能性
はじめに
1)子供たちを全人的な人間に育てる
少子化で日本の人口減少が進み始めるなか,子供を増やそうという掛け声は大きいものの,その基本となる女性を支える政策をはじめ,対策がほとんど進んでいないのは周知の通りです。それ以上に,これからの社会を担っていく子供たちが失われてしまう事件が何と多いことでしょうか。幼児虐待死やいじめによる自殺,出会い系サイトで起きる犯罪や,いわゆるドラッグによる無謀な事故など,挙げて行けばキリがありません。
かつては家族や地域社会がしっかりして防がれていましたが,今や子供たちの親がすでにモラル崩壊の時代に生まれ育っているのみなたず,まともな親たちがキチンと育てようとしても,周りから冷ややかにみられたり,テレビなどで新しい機器などに対応するのが当然というような風潮の圧力にあって,とても抗しきれない状況でもあります。学校教育の崩壊ぶりも,すでに当然のようになってしまっていますが,このなかで本当に子供のための教育を考える先生がいても,周囲から煙たがられ,排斥されてしまうのが実情のようです。大学ですら,かつて厳しく採点しようとした教授が出た時,上からの圧力でできなくなってしまったことが報じられたことがあるくらいで,かように学生を甘やかしてきたことから,世界における日本の大学の評価のランキングは地に落ちてしまいました。
その一方で,最近のテニスの錦織選手,ゴルフの松山選手や,オリンピックや世界大会でメダルを取るような多くの選手など,世界で戦うスポーツ選手たちが輝き,単に強いというだけでなく,インタビューなどで分かるように,その背景にある知性やモラルも,その他一般の人たちを遙かに超えていることで戦えているのであり,現代で最も全人的な人たちであるといえるでしょう。
学校が荒れたり,青少年の非行などの問題は,身体の成長期に無理をして頭ばかりの教育をしていることが原因(受験戦争そのものが悪いのではありませんが)と思われます。身体が急成長する中3から高1にかけて成績ダウンするのは寧ろ当然なので,中高一貫教育にするとともに,子供たちを,このような全人的人間として育てて行くこと,和気藹々の友達的でない,互いに切磋琢磨するスポーツによって訓練することが求められるのではないでしょうか。
2)多様な人生を送る充実した社会人になる
すっかり学歴社会となってしまった日本では,まず大学を出ているかいないかで差別があり,就職先も,親やメディアなどによって,大企業ばかりを指向するように仕向けられ,政府は口では中小企業が大事といいながら,具体的な政策は何もしていません。建設職人やトラック運転手などへの尊敬の念は微塵もなく,親は子供に勉強しなければああいう仕事をしなければならなくなってしまう,つまり落ちこぼれてしまうと平気で差別的な発言をします。職人などが評価されないできたのも,「知」の偏重によったからで,結局,日本の社会経済構造は頭でっかちになってしまって,実際にものを造ったり,足固めをする人たちがいなくなってしまいました。自称建築家は一杯いるのに職人さんはいない。しかも,頭といいながら「知」の訓練さえしていない。身体を使って,時間をかけて努力していく人たちのことを評価せず,さらに言えば,その力を認知することすらできなくなってしまっているのです。
大企業その他の大組織に入ったとしても,単に出世を願って遮二無二働くか,人脈つくりに勤しむか,いわゆる歯車の一つになってしまうことに耐えられず,仕事以外のことにうつつを抜かすかであり,落ちこぼれた人たちの多くが契約社員だったり,アルバイト的な仕事を選択しなければならず,結局何のために働いているのかさえ分からなくなり,それがまた,犯罪などに結びつくことになってしまっていると言えるでしょう。そういった社会の中で,差別をされている側が見返すのが,かっては芸能の世界であり,今やスポーツの世界ということになりますが,テレビなどで,芸能やスポーツのスターが喧伝されると,その人たちはもちろん素質があるのでっすが,それに加えてどれだけ努力し,また世間に登場するために,どれだけ多くの人たちに支えられているのかも見ずに,自分がすぐにでもスターになれるような幻想を抱き,当然ながらほとんどは挫折脱落して行き,これまた結果として犯罪等に結びついて行くのも,多々目にします。ヨーロッパでは,バスの運転手もスーツを着ているくらいに誇りを持ち,尊敬もされていますし,日本のように,仕事のためを理由に,どんどん東京をはじめとする大都市に出てしまうわけでもなく,地域に落ち着いてなんとか生活して行こうとしていますから,失業率も高くなっているわけで,仕事だけでなく,人生全体を充実させようとする気持ちが強いということです。
職業としてしかとらえられないため,人生を空しくしているのであり,既に述べましたように,職能という形で捉えれば,極めて多様な世界があり,職業よりは相互に対等に評価されるものになっています。実際,過去に社会に大きな貢献をしてきた人たちを見てみますと,さまざまな形で多様な人生を送っていますが,全人的人間として成長してきたからこそ可能であったと言えるでしょう。また,官僚が学歴社会,受験社会そのものの代表であるとすれば,本来政治家は「知っていること」ではなく,国民のためになにをしてくれるか「やっていること」で評価されるもので,学歴は関係ないはずです。国民も政治家の話していることにだまされず,実際にやっていることを見て評価を下すようにしなければなりません。近年でも,田中角栄など学歴がなくてもケタ違いの力量を発揮した政治家がいますし,私の尊敬していた市町村長は,小学校しかでていなかったり,夜学で苦労したような人たちでしたが,事の本質を見抜く力がずっとあり,政策上の知恵も大きく,そして何よりも,私心を超えて市町村民の未来のために働いていました。
3)個の自立により快適な第三の人生を送る高齢者になる
前項に続きますが,日本人の多くは,男性は企業などに属し,女性は専業主婦もしていられず,生活のためにパートに出るなどしているうちに齢を取ってしまい,とくに男性は定年になるとどうして良いか分からない状態に追い込まれ,それが家庭問題ばかりか,恥ずかしいことにストーカーをする者の過半は高齢者という事態まで招いています。社会人として多様な人生を送ってこなかったツケが回ってきているといえるでしょう。ボランティアなどが求められていても,実際はオリンピックなど華のある場や災害などが起きた時に集中的に集まるだけで,本来の困難な問題に継続して取り組むようなものは避けられてしまています。
これらのことは,自立していないことから来るもので,齢を取るまでに,自ら感じ,自ら考え,自ら行動を起こす,いわゆる「知・情・意」に対応する全人的な人格形成が必要なのです。この段階では,スポーツなどはかなり困難になりますが,全人的な生き方に対応するものとしてデザインが考えられます。それも,いわゆるカッコウでなく,例えば紀貫之が「古今集」と「土佐日記」によって王朝文学の礎を築いたような,より広い範囲に対する判断力をも加えたデザインならば,まさに後世に遺すに相応しいものといるでしょう。
地球温暖化,臓器移植,騒音,介護等々,ともすれば二律背反的になってしまう困難なパブリックの問題を解決して行くのにもデザインが大きな役割をするのではないかと思われます。公共の場での傍若無人ぶりや騒音等々。各人が避けることのできないようなものに対して,避ける自由も保障しなければなりませんが,逆に他に影響のない方式である限り,全く自由にすることも必要なのです。タバコなども子供の前でプカプカやっている限り,子供が吸うことをとめることはできません。個としては自立し,チーム(社会)の一員としての自覚と責任感を有するということでもあるのです。
一般的日本人を逸脱して評価が分かれたかつてのサッカー選手中田英寿の話に耳を傾けてみますと,自らが自由でいたいから努力するのであり,外国での一人暮らしも楽しんで,ノスタルジーは全く無い。日本のファンとはインターネットの電子メールで結ばれており,マスコミなどでは自分の考えがストレートに訴えられないので非常に救われているということです。今やっていることに集中し,まわりのオダテや悪口にはなどには全く乗らない,まさに自立の典型といえるでしょう。
1:「知情意」(知美体)をあわせもつ全人的な生き方
1)今の日本人を形成してきた西欧近代は,あらゆることを「知」の問題として扱おうとします。身体的に修得するような技能までも,実践知,あるいは暗黙知など「知」の一つとみなします。しかし,「知」として扱う限り,いわゆる頭の問題(生物学的に脳の問題であることは勿論であるが)としてしまい,知識や知能のレベルに還元され,どこまで理解できるかということになります。しかし,芸術は理解するものではなく,感じるものであるということは,かつてもちいられてきた「知情意」というとらえ方をすれば,いわゆるハート(心)すなわち「情」であるとすれば良く分かります。さらに,政治や企業などものごとを実行していくことは,「意」であり,頭と心に対して,体であるといえるでしょう。
2)全人的なものが「知情意」を兼ね備えることであるとすると,「情」の民族であるといわれる日本人は,何でも情に訴えようとするため,問題の本質を見失ってしまいます。西欧近代の影響後,「知」の比重が極めて高くなり,それが詰め込み教育として批判され,「心」すなわち「情」の教育が大切であると叫ばれますが,「知」といっても,西欧近代の本来の科学的精神は置き去りであり,「情」を強調することは,その傾向をますます助長することになります。本来必要なのは「意」の教育であるはずなのです。歴史的に見れば,「知」の人材は勿論,多くの人が知っている,あるいはファンであるような人物は,それぞれの段階で,今の日本の礎を創って来た,まさに「意」の人たちなのです(政治,宗教・・・)。さらに言えば,歴史を創るのは世界中どこでも「意」の人材であるはずで,端的な例を示せば,原子力そのものの存在や理解は学者によって得られましたが,それを原爆として使うかどうかは,(軍事も含む広義の)政治そのものでしかないということなのです。
3)「知」の世界は,要するに「どこまで知っているか」ということであり,現代がまさにそうであるように,学者や官僚など専門家が幅をきかす(彼らはマイナスの現象や状況について,それがどうなっているかなどを説明はしてくれても,自らそれを改変できないことは勿論,どうしたら良いかについてすら殆ど答えてくれません)。「情」の世界は,本当は「どこまで感じることができるか」ということのはずであり,それを磨いているのが芸術家のはずですが,感じ方のレベル差は趣味の違いに還元されてしまい,芸術をも知識教育の中で扱うことにより,「知っている」「知らない」で評価をしてしまい,その結果若い芽を摘んでしまっています。「知」にばかりに依存している今の社会は,色々意見を言う人は一杯いますが,意志をもって実行しようとする人は殆どいません(テレビなどの専門家の話は結局何の効果も及ぼしません)。シナリオなしの一回限りで決着するようなこと(いわゆる危機管理など)への能力は「知」の教育からは得られず,政治家や企業人にはそういった人材が非常に少なくなっているのが現状でしょう。
2:「意」の復権-1:未来を先取りしているスポーツ選手(最近のスポーツ選手に見る新しい日本人像)
1)最近の若いスポーツ選手の魅力
この度のピョンチャン冬季オリンピックでも示されましたように,二十前後のスポーツ選手たちは,単に強い,巧いということを超えているようです。日の丸から自立し(組織にとらわれず,世界を相手),みずからの哲学を持ち,だからといって,傍若無人に勝手に動くのではなく,チームのため,期待する人たちのためにやっています。さまざまな面で閉鎖的な日本の中で,国民の気分に大きな影響与えていますように,スポーツだけは,各人の思想や考え方を超えて,意識を結集することができるのです。古い話ですが,サッカーの中田英寿などは,ワールド・カップの前までは,生意気だなどの理由でスポーツ紙などの扱いが悪かったのに,世界的に活躍するようになるや,一般紙や全国放送のテレビまでが中田様々という按配です。伊達公子の引退などのさわやかさ(その後再登場して世界を驚かせましたが)も,自らの限界を認識して,次のことをやろうとするもので,能力ないものが地位に汲々としがみつく姿とは正反対のものです。スポーツは本来「意」であるべきものなのに,日本ではすべて「情」で反応してしまうところに,当の選手たちの姿を全く歪めてしまっていることも指摘しておきましょう。
2)スポーツ全体に共通する魅力
世界に目を広げても,サッカーのクリスチャーノ・ロナウドを代表に,その世界のファンに限らず,老若男女を超えて世界中の人達の耳目を集めるのは,スポーツ選手でしょう(音楽なども確かに民族を超えて世界に広がりますが,世代が極めて限定されていると思います)。スポーツは何故多くの人を感動させるのでしょうか。そこには,一般の世界では得られない(と思われている)ことの全て(公正さ,明確な評価,努力すれば報われる・・・)が埋まっているからだと思います。一流のスポーツ選手は判断力,決断力,集中力等々,そして何よりも挑戦し続け,危険を恐れない勇敢(無謀な冒険とは違う)な精神など,一般の人材に求められる能力,それも極めて優れたものを持っています。また,スポーツの試合は,決着までに,シナリオのないドラマを生み出すことも多いからでしょう。
3)スポーツは老化防止の運動とは違う(人間にとってスポーツとは一体何なのか)
明確なルールの上での自由競争と公正な評価(努力すれば報われる)という,近年の政治経済等々で求められていることがすでに実現していて,もしそういった社会が実現したらどういう感じになるか,そのイメージを与えてくれています。身体を使うことが「意志」を育て,結局は自分しかないという自覚を生みます。野原を駆け回ったり,身体を使う様々な子供の遊びも,判断力,決断力,集中力等々,そして何よりも挑戦し続け,危険を恐れない勇敢(無謀な冒険とは違う)な精神などを養っていると思われます。そして,師弟の関係,指導者やライバルの比重が大きいのも特徴です。もし,一人の力全体を10 とすれば,まず素質はなければならないですが,その大きさは1,その上での努力が大きいことは勿論ですが,せいぜい3,そして本当に開花するのは指導者やライバルの力によるのであって,その大きさは残りの6つくらいになるでしょう。
3:「意」の復権-2:これからは皆が(未来を拓く)デザイナに
九品塾トップのデザイン三講参照
素質,努力,指導,機会の話
ある人が到達した成果のレベルを数値で表すと,その構成は,素質が1,努力が3,指導が3,機会(時代, ライバルの存在, その他の運)が3,この順で間を抜くことはできない。努力をしない人には,指導の効果がないし,そこに時代が合うと,最大限発揮されるということ。素質の1について1~ 10 の幅があるとすると,たとえ素質が1しかない人でも,すべてが成されれば10 の成果に到達し,素質が最大の10 あっても何もしない人と同じになれる。したがって,すべての人の成果は1~ 100 の間にある。
親の責任は「子供が育つ環境」に対してあるのであって,身体的,素質的なことに対してでは無い。>もし,そこまでの責任を持たされるなら,とても親にはなりたくないだろう>逆に子供も身体的,素質的な面で親に感謝する必要はない(逆に身体障害などで親を恨んでもいけない)=「身体八腑これを父母に受く」の否定>身体的には2代前の誰か(1/4),素質的には3代前の誰か(1/8)を受ける=強い競争馬の子孫で強くなるのは3代後といわれる>昔なら3代前と直接接触できることは殆どなかった。
脳とコンピュータの関係の話
脳(脳細胞組立OS)=社会(個人組立OS= 政治+ 宗教+ モラルなど)>英米型資本主義はOS そのものを壊した?
脳とパソコンの対応=ハードディスクのレベル+ ビデオボードなど(読字障害は脳内で文字の画像入力を音声に変換する装置がうまく働かない)笑えぬ笑い・夢のない夢・巧まざる巧みさ・・・
脳の中におさめられたまとまった一つの存在=コンピュータのシステムファイルにあたる>現実のものと照合することによって,体系的に吸収,思考=情報集約システム(ホログラム, レーザー, ディスク・・・)>主観と客観を統合するもの(認知科学)
機械の遺伝(設計図=人為的に与えられる),進化,突然変異情報収集・理解力の強さ=デザインされた脳=脳の容量不足を補うための外在化=単純記憶がまずそうであるが,大きなことをまとめて収容する能力=全体をつかみとる能力,全体を構築する能力脳の統合ができない=精神障害=箱庭療法・マンダラ療法(ユング)=脳の構造の再統一育ちのプロセスで,脳の中に統一されたパターンを形成している民族や人=多くのことをイメージ処理できるので「頭が良い」(システムファイルがよくできている)=ユダヤ人(カバラ・タルムード=生まれた時から脳内に型がつくられる。ノーベル賞多数)>かっての論語教育など,こういった訓練が必要宗教・マンダラ・観学(密教),ナバホ・インディアンの「砂絵」(毎回砂絵を描くという行為によって世界像を統一)ユダヤ人が優秀なのは,頭の中に基本OS(タルムード)が組み込まれているから(そのOSもウィンドウズのようにレベルが高い)=意志も強くなる>かっての日本人も幼いうちに論語など叩きこまれたが,これも基本OSにあたる。戦後は自由に育てるということで,基本OSのない脳ばかりつくってきた。
当然のことであるが,基本となるOSがなければ,どんなアプリケーションもインストールできない(人間として成長しない)。>OSそのものは人間を枠にはめるものではない(大体子供の時にはその意味すらわからない)>心=アプリケーション・頭= CPU+OS・体= INPUT/OUTPUT 機器(センサー=いわゆる五感)>環境はスペースシステムとして脳に叩きこまれている。それが壊されると全てが変わってしまう(壊れた時に記憶も全て無くなる)=ボケ,改宗,インディアン>システムの修復(デザイン,地形ほか)>遺伝子プログラム=記憶・文化プログラム=演算>記憶に使っていた部分を演算に(個人としても,人類としても)>究極のパソコン=世界的プロバイダのインターネット・携帯電話機能・GPS付きモバイル>テープレベルか,シーケンシャルファイルか,ランダムアクセスファイルか,ハードディスク並か,CD-ROM レベルか・・など人の脳のレベル
パソコンとの関係=幼児期から児童期にかけての教育(ユダヤや昔の論語など)は、パソコンに基本OS をインストールすることに同じ>成長期=様々なアプリケーションをインストールすることに同じ(現在の教育はアプリケーションなしで単にデータを入力している状態)>人間にはパソコンのように外部から簡単にアプリケーションを入れるわけにはいかない=まず家庭などでの基本OS にあたる教育、その上で自ら挑戦して行くことによる吸収が必要(受け身では成長しない)
世界的に有名なアーティスト村上隆が,戦後の日本人の脳にはOSが無いと認めた上で,そういった人物が何かを成し遂げようとするには「オタク」になるしかないという指摘をしていたのが印象に残る。
第1論:活動分野型の捉え方(リスト)
・・・第1話:伝統的な三分法に割り当てて見る
・・・第2話:座標軸を設定し,その象限から考えて見る
・・・第3話:活動分野・型のリスト
第2論:時代が人を創る(歴史)
・・・第1話:各分野型・サブ型の時代推移~職能分化の歴史的プロセス
・・・第2話:女性が文化をつくる~自立する女性
・・・第3話:現代に類似する各時代末の分野型
第3論:注目されるデザイナ的人物
・・・第1話:統治のデザイン
・・・第2話:文化のデザイン
・・・第3話:社会のデザイン
わが国では,職業などを選ぶ機会が高校や大学を卒業する時に限られるが,この年齢では,自らの適性を掴みかねている場合が多く,いわゆる個性教育の弊害などから,無理に自らの個性を強調して,誤った選択をしてしまうことも多いと思われる。個性は自ら主張するものではなく,ある集団において他人から認知されることで分かるものであり,その典型は相撲など最も型に嵌った組織において特徴的に現れる。個性というよりは,自らやりたいもの,あるいは適性のあっていそうなものを選ぶのが良く,場合によっては使命感を持って選ぶこともあって良い。この段階で,一度は選択してしまったものの,どうも自分には合ってていないとばかり,直ぐに止めてしまうことも多々見られるが,こらから述べるように,職業には,それぞれ相当な幅があるものなので,「石の上にも3年」などと言われるように,じっくり見つけて行くことも必要である。この幅に対応すべく,限定的な職業という語でなく,職能という語を用いたい。また,転職する場合には,自らにとってより良いものでなければ意味は無く,二股人生など多様な生き方を実践することも考えられる。とくに,近年の問題は,いわゆる定年後の生き方(いわゆる第三の人生)の問題で,ここにこそ自分に最も相応しい職能選びがあるのではないだろうか。
職業の種類については,国勢調査に対応するものや,厚生労働省のハンドブック的なものなど公的なものから,就活にからんで様々なものが出回っているが,次々に新しい職業が誕生する一方,用を成さなくなってしまう職業も出て来るため,これらの資料ではなかなか対応できず,特に役所のものは現状後追い型のため,それこそ用を成さなくなってしまっている。かつては,職業別電話帳などである程度掴むこともできたが,最近の変化はとてつもなく,とても追いつけるものでなくなっている。また,政治家や芸術家,芸能人やスポーツ選手など表に目立つ個人への評価がどうしても高くなり,これら個人が登場するためには,作家であれば雑誌編集者など,スポーツ選手であれば良き指導者など,支える人物が重要で,さらに辿って行けばその裾野は広がるばかりなのだ。かつて,NHKの人に聞いた話では,最近はディレクターに成りたがる者ばかりで,プロデューサーをめざす者がいないと嘆いてたが,その後はディレクターどころか,キャスターに成りたがる者ばかりになっているのではないだろうか。イタリア映画の黄金期を見れば,フェリーニ,ヴィスコンティなど有名監督以上に,プロデューサーのカルロ・ポンティの方が有名であった。このように,目立つ者ばかりを目指す社会はとても強靭な社会とはいえず,職能分野として大枠で捉えるようにすることが必要になってくるのである。
そこでまず,職能選択したり,第三の人生を送ったりする上で,まず知っておくと良いいくつか枠組みを提示し,分野型として,リスト化することを試みてみよう。
わが国では昔から,社会を様々な三分法で整理し,(大量複雑な情報を縮約して)あれこれ悩まずに済ます知恵を発揮してきたが,近年,そういったものが忘れされれてしまったようである。
その代表的なものとして,まず,「真・善・美」から,職能との関係を見てみると,「真」は,当然ながら世の中で何が本当であるか,真実を見極めたいということであり,もちろんどの分野においてもベースになるものであるが,とくに,「学問」分野に求められ,近代に入り科学が登場したことで,その方向は一層高まっている。また,社会で起きる様々なできごとから,真実を見極めるという点で「官僚」にも対応するものでしょう(現実には全くそうなっていないが)。いずれにしても,「真」は,社会をつくる人々の共通の理解の基本になるものでなければならないだろう。「善」は,分かりやすく言えば,他人のためになる,社会のために働きたいという意識に対応,職能としては「福祉」を始めとする社会的な活動が代表的なもので,そのルーツとしての「宗教」はもちろん,「企業」などでも,起業の際に意識される場合が多いと思われる。日本では職能のみならずあらゆる面で性善説がとられて来たが,近年,その足元が不確かになる事件が続出してきているように見える。「美」は,自ら感じるところのものが拠り所であるものの,社会の多くの人々に共感を呼び起こすことで,人生を豊かにし,結果として社会を美しくして行くもので,当然ながら,詩歌・小説から絵画・彫刻,さらに諸芸能を含むいわゆる「芸術」が対応し,近代以降派生するものが多い分野でもある。そして,あらゆる職能において「美」意識が求められるようにもなってきているのも事実だろう。
次に「知・情・意」について,「知」は,いわゆる知識で,「真」に対応し,過去の蓄積をふまえ,頭脳でいえば記憶力(過去)に対応,もちろんどの分野でも必要であるが,「学問」「官僚」においては基礎的なものといえる。「情」は,まさに感情の動きを表し,「芸能」を始め芸術の「美」に対応するのを始め,日本人の「情」はあらゆる分野で研ぎ澄まされ,世界に冠たるものとなっているが,他方,その場その場の「情」に左右される刹那的なもの(現在対応)になってしまうため,未来を構築するのが不得意であることが課題になる。宗教や社会福祉なども当然「情」が基本であるが,次の「意」無くしては長続きしないと思われる一方,裁判や官僚などにこそ,「情」が求められるのではないだろうか。「意」は,未来を築く意志に対応するものであるが,日本人の最も弱いところであり,「政治」や「企業」など最も「意」を必要とする分野ですら,意志の強い人物が嫌われるため,結果として,政治も企業も弱体化して行くことが多い。社会福祉活動などとの関係で見れば「善」にも対応しており,後述のスポーツやデザインという新しい分野は,まさに,「意」に対応するものである。
さらに「頭・体・心」(その変形としての「心・技・体」)で見ると,「頭」が「真」「知」に,「心」が「美」「情」に対応することは言うまでもないが,「体」が「善」「意」に対応するものであることを改めて認識する必要があると思われる。というのは,明治維新後,とくに敗戦後は,いわゆる文武両道が廃れ,頭ばかりの教育になって,身体を鍛えることを怠ってきたため,結果として,「善」「意」の力もどんどん落ちて来ていると見られるからである。このことを端的に示すのが,後述するように,現在もっとも輝いている国際的に活動しているスポーツ選手たちが,最も頭が良く,心豊かであることであることに示され,彼らにこそ,未来の日本を拓く可能性があると言えるくらいである。変形の「心・技・体」の方では,「技」が「頭」に対応,つまり過去から伝承されたものが「技」であり,それをどれだけ磨いたかということに対応するものだろう。
以上について,「過去・現在・未来」指向との関係で整理すると,「真」と判断するためには,それまでの事実が参照されるということで「過去」に対応,「知」はそれ以上に「過去」指向(Ⅰ型)であり,「善」「意」はこれからの社会をより良きものにしていこうとする点で「未来」指向(Ⅲ型)なのに対し,「美」は現に目の前のものとして制作したり演じたりする点で「現在」指向的であり,それに反応する「情」は刹那的になってしまうところが問題であるが,まさに「現在」指向(Ⅱ型)というように,三つの型になり,次に述べることも合わせて,下表のように整理される。
すなわち,この分類を敷衍して,ものごとの証明の方法について考えて見ると,「演繹法」というのは,明らな事実(真=数学の定理や公理など)とみなされることから論理的に導くという点で,Ⅰ型であり,「帰納法」というのは,ありえないものを排除して行くことで証明しようとするもので,例えば警察などの犯人探しなど,目前の問題を解決する点でⅡ型と言える。Ⅲ型については,証明の方法が無いということで,政治問題などの選択が困難であるとされてきたが,C.S.パースが提示した「アブダクション」は,多くの相矛盾するような問題について,全てに矛盾が生じないような一つの体系的モデルを構築することがその証明になるという方法である。たとえば,無から有を生じるとされる建築の設計などがまさにそうであり,(証明されて)確信を持てるからこそ建設できるので,広くデザインの基本になるものと考えられる。カントの三つの批判についても,「純粋理性批判」がⅠ型に,「実践理性批判」がⅢ型に,「判断力批判」がⅠ型に対応するものであることも分かる。他にも色々対応が考えられるが,維新の三傑では,木戸孝允がⅠ型,西郷隆盛がⅡ型,大久保利通がⅢ型に,ロシアの同時代の三巨人では,ドストエフスキーがⅠ型,トルストイがⅡ型,レーニンがⅢ型に対応しているなどと,想定してみるのも面白いだろう。⇒デザイン論(知情意論再考~「意」の復権を求めて)
以上を踏まえて,極力現代の職能に対応させる形で整理するため,(結果は別にして)「社会を対象に活動しようとするか」「自分(内面)を中心に活動しようとするか」を分ける軸と,(原則として)「勝負(競争)があるか」「勝負は関係無いか」を分ける軸をクロスさせることて,四つの象限をつくってみる。
おそらく最もきつい社会対象かつ競争主体の象限は,まさに人々の支配に関わる活動で,まず熾烈な競争でそのトップに立ちたいという政治分野が核となるが,その政治を実行して行くための,熾烈な出世競争のある官僚分野と,政治の安定を支えるものの現実に勝負が決まってしまう軍事分野がセットになる。古代の公家時代に官僚が登場し,中世の武家時代になって,軍事と境目のつかない政治家を輩出することになった。これら全体を支配体制活動として,前述の三つの型との関係で見直すと,政治分野は意志をもって未来を拓くということからⅢ型に,官僚分野は過去の事例などの積み重ね,すなわち知識に基づいて処理することからⅠ型に,軍事分野はまさに目前に起こることに対処するという点でⅡ型に,おおむね対応すると見て良い。政治には意志をもって未来を拓くことを,官僚には誤りのない知性を,軍事にはむやみに人を殺さない情を求めたく(西郷隆盛がまさに身をもって示したもの),また,それぞれの分野への適性もそうあって欲しいと願わずにいられない。
次に,社会を対象とし競争の関係ない象限を考えると,次項の「歴史的に見た職業の変遷」でも述べるように,日本では,仏教伝来以降優れた僧らが社会のために働いてきたことに始まり,明治維新後でもキリスト教関係の人たちが大きな役割を果たしたように,宗教分野がそのまま対応する。非競争であるが故に,人々から厚い支持を受けるようになると,前記の政治分野から排斥されることも多くなる一方,自らの保全のために,政治に密着したり,政治を動かそうとした宗派が生まれること,現在もなおそのような動きがあるのは本末転倒といえるのではないだろうか。近代科学によって一気に拡大した学問分野は,もともと学者でもあった僧から,また知識をベースとして学者に近い面のある前記の官僚から分化独立したものと考えると,最近の先端科学に見られるように,学問がまさに競争そのものになってしまったことが如何に問題を孕んでいるか,これが本当の意味での学問であるかということも考えなければならない。さらに人命を助けるという古くからの医療や,人々を啓蒙しようとする教育に加え,近代になって福祉その他様々な形の献身的な活動が,もともと人を救う宗教分野や,民生に対応する官僚分野から分化独立する形で社会分野を形成してきたと言える。つけ加えれば,医者は本来,人の命を助ける究極の「善」に対応する存在であったのが,医学者という学問分野に取り込まれ,人の命よりも,研究の対象としか見なくなった者が多くなってきたのが気になるところであり,それ故,相変らず人の命を救うことを専らの役割とする看護師の存在が重要になってきているようにも見える。
これらをまとめて社会貢献活動として,前述の三つの型との関係で見直すと,過去の知的ストックをベースし真を求める学問分野はⅠ型そのものであり,善意にもとづいて,恵まれない人たちのためなど様々な形で未来を拓こうとする社会分野はⅢ型に,本来の目の前の人たちを救おうとするとともに,多くの美を生み出してきた宗教分野はⅡ型に,おおむね対応するといえるだろう。宗教分野は,もともとは,Ⅰ,Ⅲ型までカバーしていたが,分化の結果,Ⅱ型だけに矮小化してしまい,目前の救済といいながら,実際には単なる神頼みだったり,大仰な結婚式や葬式をする役割にまで堕してしまっていることには言葉も無い。
三番目に,支配体制活動の対極に位置し,それ以上に古くから人類の基本的な活動としてある,いわゆる芸術に近い,自分のしたいことを競争と関係無くしようとする自己追求活動がある。詩歌など原初的なものから,物語や小説,さらには評論や思想など,宗教分野の僧に始まり,学問分野ともつながる著述分野,装飾古墳などに始まる絵画を核に,彫刻や建築から,近代の最も時空間的に統合された映画に至る様々な造形分野,もともとは詩歌と一体であったとされる歌謡や舞踊に始まり,日本独自の様々な口演や,歌舞伎から劇・映画の俳優に至る,人前で身体を使う芸能分野に,大きく分けることができる。これらいわゆる芸術的行為は,自分すなわち個を突き詰めて行った結果普遍性を獲得し,社会を構成する人々の共感を生み,互いの気持ちを通じ合うようにするものと言える。
同じく,前述の三つの型との関係で見直すと,未来に向けて形を遺すのが主体の造形分野がⅢ型に,演じるごとに消えてしまう,まさに現在にのみ意味のある芸能分野がⅡ型に,そして,ストックされてきた様々な知識などを作品化して行く著述分野がⅠ型に対応すると見て良いだろう。こういった区分はあくまでも大枠の話で,著述分野でも,詩歌などは芸能と一体となる部分が多く,「情」に対応するものとして捉えられるのはもちろんであり,さらに,「真・善・美」との関係でいえば,この活動全体が「美」に対応するのはいうまでもなく,「頭・心・体」といった区分では,芸能分野は,まさに「体」に対応するものといえるなど,かなり複合的な関係になっていることを指摘しておかねばならない。
最後に残った象限は,競争を前提に自己発現をしたいという挑戦追求活動になるが,これこそ最も新しく登場してきたもので,まず,近世に始まり,近代に入って飛躍した様々な実業分野がある。次に,戦が無くなったことで生じた武道にもつながるとともに,サッカーのワールドカップに見られるように戦争の代償行為であり,結果として平和に貢献すると見られるスポーツは,本当に新しく,まさに競争そのものを体現していて,ほとんどが仮想現実化されてきた社会の中で,かなり現実性を感じさせてくれるとともに,一流選手たちが語るのを見ると,現在最も優れた人間像でなかろうかとさえ思えるものだろう。以上のような明確なものではなく,また,発明や技能,様々な仕掛け人や破天荒な活動のように,見方によっては,いつの時代にもあったと言えるもの,ジャーナリストのように,著述というよりは,社会を告発したり啓蒙しようとすべく新たに登場した活動など,バラバラのように見えるが,他の活動に比して実践的であることが共通していることから,実践分野としてくくることとする。
同じく,前述の三つの型との関係で見直すと,挑戦追求活動全体がⅢ型に対応すると言えるが,スポーツは,過去の記録や知識を基礎としている点でⅠ型に対応し,「真・善・美」では「美」に,「頭・体・心」では「体」に対応,すなわち"知体美"という最もすばらしい全人的統合であるとも考えられる。こういった見方をすれば,日々の利潤に追われる実業分野がⅡ型的で,発明を代表に未来を拓く実践分野がⅢ型的であると考えることもできよう。
以上のことをまとめた図が「活動ジャンルマップ」で,このマップのどの辺に自分が対応しそうか考えてみることで,活動の方向が少しでも見えて来ればと願うものである。
マップをつくるにあたっては,世界に例の無い日本独自の天皇制により,職能選択の対象にはならないものの,日本人全般に放射光のようにかかり,良くも悪くも,社会の活動を超えて存在する皇室が,座標の原点とし,職能としては最も古い支配体制活動を上に置くと,反時計回りに,社会貢献活動,自己追求活動,挑戦追求活動と,おおむね,社会の活動として,基礎になるものから,より個人的,挑戦的活動に展開する順になる。
各象限相互の間で相互に近い分野を見ると,社会の安定や人々の生活向上に直接的に関与するなどの点で,官僚分野が社会分野に,自ら知り得た知識等を文字化して広く伝えるというような点から,学問分野が著述分野に,身体を使い能動的であることや破天荒さも大きな意味を持つなどの点で,芸能分野が実践分野につながり,最後にスポーツを代表とする競技分野が,前述のように,その代償行為となってきた支配体制活動の軍事分野とつながって,四つの象限が環になって完結することになる。
以上とは別に,職業の変遷のところでも述べるように,どの職能にも入らずに名を残した人たちがいる。一番分かりやすいのは,いわゆる陰の女性で,歴史上大きな役割をした人物も数多い,同様に,日記など詳細な記録を残した人物の存在価値も計り知れない。また,日本独自の隠遁(脱社会)や犯罪など反社会,さらには日本を脱出して海外で活躍したり,外国出身ながら日本人として活動する人物たちは,4つの象限全てに架る背景となる特異分野として位置づけた。この特異分野が皇室分野と直結したものであるという含みをも持たせてあるが,関心ある方は「日本私史三講」のⅠ:統治変遷のプロセスをご覧頂きたい。なお,自らの適性を知るためには,同じページのコラム「遺伝適性を知るための民族ルーツ論」を見れば,何かの参考になるだろう。
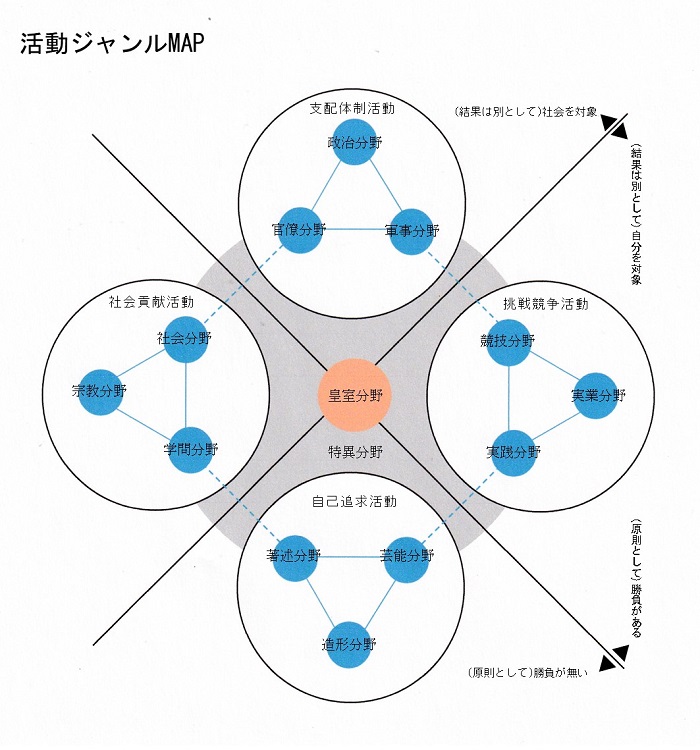
活動ジャンルMAPにもとづき,かつ,現在までに作成した3,635人の歴史人物の一枚年譜をめくりながら,活動の分野に対応する型を,以下のようにリスト化し,思いつくままに該当する一般的な分類例やコメント,基本的な数字として,人数と全数に対する比率を記しておく。リスト化するにあたって,従来の枠組みでは表せないようなものもあり,独自のものが登場するが,少しでも分かりやすくなるよう,その型に対応する,著名な歴史人物を例示するようにした。当然のことながら,中世から近世にかけての著名な人物が,武将であり,大名であるように,歴史人物の多くは,一つの分野型にあてはまらない。そこで,サブ型として,二つまで,示すようにした。もちろん,それ以上にまたがる人物もいるが,少なくとも,その人物を表す上で,欠かせないと思われるものを記し,サブ型の人数と全数2,168人に対する比率についても示しておく。
1:天皇型:天皇・上皇・法皇・皇太子・・・(48人,1.32%)。当然ながら,この型がサブ型にはなり得ない。
2:皇后型:皇后・中宮・女院・皇太后・国母・女御・後宮・天皇乳母・・・(26人,0.71%)。サブ型(1人,0.05%)
3:皇族型:皇子・皇女・天皇の兄弟・その他皇族として扱われているもの・・・(21人,0.57%)。サブ型(3人,0.14%)
1:支配体制活動>(結果は別として)社会対象+(原則として)勝負ある活動
1:国家支配型:(宰相・将軍・摂関・執権・老中首座など)実質的に国を支配する政権トップ。(87人,2.39%)。サブ型は,天皇でも,実質的に国家を支配する権力のあった人物や,権力補佐型でありながら,実質的に国家支配した人物などで,琉球は別の国であったことから,国王は,国家支配型でもある(21人,0.97%)。
2:地域支配型:(首長・大名・守護・探題・公方・知事など)現代においても,県知事,市長村長とレベルはさまざまであるが,一つにまとまった地域のトップになる人物(80人,2.20%)。サブ型は,戦国大名のように,武将でありながら地域を支配していた人物や,幕藩体制の老中首座も本拠は藩主で地域支配型(49人,2.26%)。
3:権力補佐型:国家地域を問わず,(老中・公卿・管領・連署・藩政家・側用人・閣僚・家老など)支配者を補佐,表に立つより,支えるのが得意な人物で,のちのコンサルタントにも通じる面もあり,前の二つの型には,優れた補佐がいた場合が多い(141人,3.88%)。サブ型は,当然ながら,この型の人物が,のちに支配型になる,現代でいえば,閣僚から首相になるような場合が多い(40人,18.5%)。
4:党派活動型:(政党+官僚+地方政治家・政治画策家・自由民権・共産+社会主義者・ファシスト・右翼など)維新後,近代に入っては国会をつくる運動から始まる,いわゆる政治団体を主とするものや,世界の影響で,社会主義,共産主義などさまざまな活動が登場し,現代に至っている。戦後の民主主義のもとでは,政権を握って,閣僚から首相になる場合も出るが,一匹狼型で,結局破綻してしまう人物も多い(87人,2.39%)。人生の一部として政治活動する人物も多いことから,サブ型も多くなる(65人,3.00%)。
5:時代変革型:(主に明治維新の志士とその支援者)古代から中世,中世から近世への時代変革は,それに対応する人物がいたのは当然であるが,それらは次の軍事分野の武将らに含まれてしまう。これが,もっと広い層の多岐にわたる形で登場するのが,いわゆる維新の志士らであり,この反対者や関係者も含めて,他に分けられないため,新たな型とする。維新前の時点ではテロリストに近い人物も多い(51人,1.40%)。また,支援者はもちろん,本業がある人物も多く,サブ型が多くなっている(41人,1.89%)。
6:政治思想型:(経世家・儒学者・各主義+政治理論主唱者)哲学者などに近い面もある(69人,1.90%)。近代の党派活動の多くは,イデオロギーと裏腹であり,サブ型も多い(48人,2.21%)。
1:統率型:(武将・司令官・統領・艦長など)中世,とくに戦国時代には,1-1政治分野の2:地域支配型のように,多くの1:統率型の武将が登場し,近代に入っては,政治から離れた軍人としての司令長官を代表とする1:統率型が登場することになる(61人,1.68%)。古代における蝦夷征伐の将軍をルーツとして,鎌倉幕府以降の武家政権のトップは,形式的に,天皇から征夷大将軍という地位を授けられることで成り立っているが,これらの将軍はじめ,執権や管領などは,一義的には,1-1政治分野の1:国家支配型としてあげられ,サブ型になるため多くなる(54人,2.49%)。
2:補佐型:(部将・将校・上級など)1:統率型を補佐する,表に立つより,支えるのが得意な人物で,政治の補佐型や官僚の総務秘書型にも類似,以下の型も合わせて,組織重視という点で官僚分野にも近い(65人,1.7%)。統率型や地域支配型などへ出世することなどでサブ型も(28人,1.29%)。
3:戦闘警固型:(指揮・兵・随行など)古代において,上は,天皇や上皇,摂関家を守る武士から,荘園を守るものなど,中世の武家政権を担うもの,武士の活躍の場が無くなった江戸時代を飛ばして,近代の軍人でまさに戦争の場に出,太平洋戦争での悲劇も(27人,0.74%)。サブ型には,院を警護する北面の武士であった西行も(17人,0.78%)。
4:参謀工作型:(参謀・軍人官僚・軍部行政官など)もともと統率型,補佐型の武将,部将自らも担い,中世の黒子の僧はじめ,連歌師,茶人,俳人ら様々な人材が活用されるてきたが,近代の軍制になって,分離独立,官僚に近いものになる。近代になって,多くの組織で現場と企画が分離し対立を招いているのと同様,実戦部隊との間に齟齬を生じた上,官僚と結託して増長,敗戦に導くことになった(31人,0.85%)。サブ型には,統率型に出世したり,閣僚になる人物も(16人,0.74%)。
5:装備技術型:(築城・造船・航空機・兵站・剣術・砲術など)中世から近世初めにかけて,武将自身が築城その他の技術者であった場合が多いが,その後,装備技術に際立つものも登場,近代に入って様々なものが登場し,産業の発展も先導するなど,後述の発明技術型にも近い(15人,0.41%)。サブ型の具体例は,メインが医療型の軍医(11人,0・50%)。
6:軍政思想型:(兵法・国防・武士道・軍学者など)もともと中国から伝わった孫子の兵法などが戦の基本で,新たな発想も含めて,中世全般にわたって武将自身が担っていたが,皮肉なことに,戦が無くなった江戸時代になって,国家支配者とは独立に,この型のものが登場する(9人,0.25%)。政治思想型にも近く,サブ型に(6人,0.28%)。
1:総務秘書型:(天皇側近ほか朝廷官人・能吏など)もともとは,天皇に仕えて,なんでもこなす人物が出発点で,歴史を遡るほどトップと直結して多くのことを処理する,以下のような型に分類できない人物が多く,近年においても,その業務が表に明確にならないものの,省庁をとりまとめるトップが大臣官房秘書課になっている(40人,1.10%)。幅広く対応できることで,サブ型にも(25人,1.15%)。
2:財務再建型:(大蔵・日銀・藩政改革など)維新政府で省庁がつくられるにあたり,古代に用いられていた大蔵省の名がそのまま使われたように,古いものであるが,そもそも国家権力が民から吸い上げる,つまり「入り」のみ管理していれば良いようなものであったことから,財政再建ということが目的になるのは,江戸時代になってからで,殖産や民政と表裏一体にもなる(15人,0.41%)。最も困難な役回りで,守旧勢力の抵抗も強く,能力高くとも,サブ型も少ない(9人,0.42%)。
3:外務通訳型:(大使等外交官・通詞・伝奏+申次・遣唐使・外交僧など)島国で鎖国的な日本では単なる通訳的な立場であり,本格的外交官は育ちにくかったが,開国とともに,国際関係が一気に拡大したのに伴い,主要な型に(33人,0.91%)。近世以前の朝廷と幕府間や対立する大名間なども一種の外交であり,サブ型に(22人,1.01%)。
4:法務学識型:(学者官僚・明法家・文章博士・裁判官・法制家・有職故実など)鎌倉幕府でも評定衆と言われたように,古代から支配組織の維持や人民統治において,問題が生じた時にどう裁くが基本であった。過去の判例などが最も重要なため,菅原道真のような学者官僚の力が大きい。敗戦後は三権分立で司法が分離独立され,それまでとは異なる統治システムになっている(34人,0.94%)。後述の学問分野に最も近いことで,サブ型に(12人,0.55%)。
5:内務民政型:(警察・医療衛生・教育文化(官学)・福祉・町奉行・寺社奉行・代官・所司代・地方行政官・宗教・監獄など)直接国民に関わるもので,明治維新後,内務(省)官僚が大きな力を持つようになった(45人,1.24%)。国民の福祉を真剣に考える官僚らは,後述する社会分野と直接的につながり,サブ型に(20人,0.92%)。
6:殖産技術型:((農林・通産・運輸・逓信)・経団連・博覧会・植民地経営・園芸・開拓(土木・建築・都市・植林)・鉄道・鉱山・測量・水産・造船など)国民の生活を豊かにするため産業基盤を整備する役割で,社会分野の殖産型にもつながる(65人,1.79%)。自ら起業したり,企業が発展することで,次第に役割を縮小して行き,サブ型に(19人,0.88%)。
2:社会貢献活動>(結果は別として)社会対象+(原則として)勝負無い活動
1:医療型:(医者(教育)・看護(教育)・赤十字・病院経営・医師会・種痘・産児制限・薬剤・助産婦・救ライなど)人命を救うという点で最も古くから存在し,理科的な学問を開拓する役割も担った(59人,1.62%)。集中しなければならない一方,指導者的レベルでもあり,サブ型はそこそこにある(29人,1.34%)。
2:福祉型:(児童・少年・孤児・障害者・点字・感化・老人・貧民・自閉症など)様々なハンディを抱える人たちを救済するもの(35人,0・96%)。何等かの仕事をするうち,福祉に生き甲斐を感じるようになるサブ型が多い(24人,1.11%)。
3:教育型:(学校経営・服飾・栄養・YMCA・生涯教育・音楽・道場・綴り方・工業・家政など)人材育成という最も未来指向の社会活動(69人,1.90%)。誰でも,自らの活動があるレベルに達すると,若い人を教育したくなるらしく,サブ型が際立って多い(134人,6.18%)。
4:解放型:(女性・部落・労働者・弁護士・義民(農民解放)・公害被害者・主婦連・消費者・土地・出獄人・告発・占領・反原発・デモなど)近代に入って,さまざまな差別・搾取・弾圧・被害などから人々を解放する活動が成されて来た。江戸時代の一揆も農民差別からの解放活動と見ることができる(71人,1.95%)。生涯,集中し続けなければならない場合が多く,サブ型は非常に少ない(19人,0.88%)。
5:殖産型:(新田開拓・篤農・都市開発・地場産業・灯台・報徳・移民・水運・植林・治水・組合・コンサルタント・農書・起業支援・職業紹介・養蚕など)行政のやっているのを待っていられず自ら献身する人たち(50人,1.38%)。何等かの活動に関わるうちに,取組み始める場合も多く,サブ型は多めになる(40人,1・85%)。
6:文化型:(図書館・伝統芸能復興・メセナ・エスペラント・国際親善・スポーツ・愛国・YWCA・反戦平和・シンクタンク・青年・野鳥保護・近代建築普及・サロン・革命支援・児童絵画・建築・音楽・演劇・映画・啓蒙・パトロンなど):最後に豊かになることで,また自然や伝統が失われて行くことに対して,様々なボランティア活動も登場(54人,1.49%)。教育型のように,自らの活動があるレベルに達すると,社会に広めて行きたくなるらしく,サブ型が際立って多い(110人,5.07%)。
1:教導僧型:(開祖・学僧・回国・教団主・護持など)日本の仏教宗派の開祖や高僧は,空海をはじめ,世界的に見ても高いレベルにあり,人々を救済する一方,政治支配の上でも大きな役割を果たしてきた(77人,2.12%)。これを超える別の活動は無く,サブ型はわずか(4人,0.18%)。
2:活動僧型:(外交・西域探検・画僧・寺院復興・社会事業・勤皇・工作・五山文学・編纂・梵語・書・霊能など)僧職にあって芸術や学問,外交など他分野に業績を発揮したもの(41人,1.13%)。他分野が主の場合はそれぞれの項に入るので,サブ型は多くなる(31人,1.43%)。
3:神道周辺型:(神道・行者・修験道・陰陽道・占い・国家神道行政など)仏教伝来以前からあった原始宗教的なものが天皇との関係で連綿と続き,明治維新になって国家神道化された(18人,0.50%)。国策に関わるので,サブ型もそこそこ(8人,0.37%)。
4:新興宗教型:(禊教・天理教・ユートピア・救世軍など)現在の有力な仏教宗派も登場した当時は新興宗教であったことはいうまでもないが,それは問わず,異端的なものに限る(25人,0.68%)。サブ型で出来るようなものでは無い。
5:キリスト教型:(牧師・神学など)近世初頭のキリシタンも(26人,0.72%)。明治維新後のキリスト教信者はかつての仏教僧のように様々な面で社会的貢献をしてきたことから,サブ型が多い(32人,1.48%)。
6:その他型:(宗教学者・心学(教育)・チベット・イスラム・インド哲学・心霊学・各宗教理論や支援など)最後に上記に該当しない様々な宗教的活動(16人,0.44%)。数は少ないが,ユニークな人物ばかりで,古い順に,何人か紹介すると,日本初の往生伝「日本往生極楽記」を著して,浄土思想を普及させ,「方丈記」に影響を与えた「池亭記」を著した慶滋保胤,町人のための思想を確立,その普及・実践に献身,社会教育やボランティアを先駆した心学の祖・石田梅岩,托鉢・奉仕・懺悔の共同体{一燈園}を開き,説話集「懺悔の生活」がベストセラーになった西田天香,43歳の時,地位財産一切放棄して説法始め,会員組織により,各界のトップを多数訓育,京セラの稲盛和夫によって,その存在が広く知られることになった中村天風など。サブ型は(7人,0.32%)でみると,日本の超心理学のパイオニアで,"念写の福来"として世界的になるも,帝大を追放された福来友吉や,国家主義者として,戦前の悪の一人とされるも,排他的日本主義を批判,学識あるアジア主義者として,ユニークな生涯を送った大川周明が,近いところでは,ほぼ同時期に誕生した,日本が世界に誇る二人の宗教学者,「東洋人の思惟方法」以降,比較思想宗教の国際的権威となり,膨大な業績を遺した中村元とイスラム神智学研究・コーラン学においては世界的な権威の井筒俊彦がいる。
1:数理天文型:(和算・暦・天文・測量・地図・理論物理学など)脳の基本となる最も抽象的な世界で,古代からの天文・暦に加え,江戸時代に和算として独自の発展をした(33人,0.91%)。サブ型は,非常に少ない(5人,0.23%)。
2:自然科学型:(蘭学・本草(動植物)・博物・化学・物理・地震・地質・気象・医学・遺伝・解剖・栄養・自然対象工学(水利など)など)最も科学らしい分野で,医学から発展し,蘭学や本草学として近代科学への準備が成された(69人,1.90%)。サブ型は少ない(21人,0.97%)。
3:人文科学型:(考古学・歴史・地理・心理・宗教・人類学・有職故実・民俗・考証・風俗・文化人類・比較文化・美術史など)近代になって西欧から入ってきたものであるが,考証学など江戸時代に準備されていた(62人,1.71%)。歴史地理など,在野の学者もいて,サブ型が多くなる(43人,1.98%)。
4:社会科学型:(経済(史)・法学・法制史・政治・財政・経営・植民地政策・教育・女性問題・下層社会・行政・統計・家政・都市工学など)西欧においてすら全く新しい分野(49人,1.35%)。数理系に近い面もあって,サブ型は少ない(19人,0.88%)。以上三つの科学を,第1話三分法で見ると,観測データが基本の自然科学が1型,生活記述が基本となる人文科学が2型,未来予測を目的とする(政治につながる)社会科学が3型に対応する。
5:文学言語型:(漢文学・国文学・アイヌ語・外国語・文人・歌学・書誌・謡曲文・古今伝授など)日本語という特異な言語から独自に発展した分野で,かなりのレベルの学者を輩出(49人,1.35%)。古代中世の学識型官僚や,近世の国学者らに,本業と並行して取組んでいる人物など,サブ型はかなり多くなる(61人,2.81%)。
6:蒐集編纂型:(事典・辞書・地誌・地図・年表・伝記・民族音楽・蔵書・奇石・エンサイクロペディストなど)必ずしも学問では無いが,学問ほか何をやるにしても基本になれうようなデータベースの構築で,最も過去指向の作業であるともいえる。江戸時代の伊能図や群書類従など世界的に見ても偉大な業績がかなりある(52人,1.43%)。誰でも,その気になればできるものであるが,学問のベースになるものとして,この分野に入れたもので,サブ型はかなり多い(56人,2.58%)。
3:自己追求活動>(結果は別として)自己対象+(原則として)勝負無い活動>いわゆる芸術家
1:詩歌型:(韻文。和歌・俳句・連歌・狂歌・漢詩・川柳・作詞・・・)文字にならない段階から始まり,歌謡など芸能分野ともつながるもので,さまざまなタイプが選択でき,職業としない場合も多いことから,著述分野の3分の1を占める。歴史的には,男子は専ら漢詩を詠んでいたのに対し,紀貫之の貢献で女性による仮名文字和歌が始まる(162人,4.46%)。誰でもしているようなものなので,サブ型に挙げる人物にはレベル高いものが多い(72人,3.32%)。
2:小説型:(散文。各種小説・各種物語・各種草子・戯作・児童文学など)世界最古とされる紫式部の小説「源氏物語」という遺産を有し,江戸時代には西欧にも先駆ける西鶴のいわば大衆小説,さらに近代小説へと展開。それなりの力量で,時間もかけなくてはならず,近代には職業となって飛躍,読者のニーズにも対応することから,詩歌以上に多い(170人,4.68%)。当然のことながら,専業とするものが多く,サブ型は少なくなる(35人,1.61%)。
3:脚本型:(劇作・脚本・笑話作者・漫才台本・浄瑠璃作者・講談・字幕など)劇に近い能・浄瑠璃・歌舞伎など日本独自のもの,さらに世界に例を見ない落語・漫才など,芸能分野の:口演型にも強く関わるように,自らのなかに閉じないことから,数は少ない(27人,0.74%)。前記の小説型の人物がサブ型にしている場合も多く,比率は同程度(15人,0.69%)。
4:随筆鑑賞型:(随筆・日記文学・紀行文・毒舌諷刺・鑑賞・(伝記・逸話など)短文集・五山文学など)清少納言の「枕草子」や紀貫之の「土佐日記」に始まる随筆や(記録ではない)日記文学など,個人の感想主体の日本独自の文化。このような個人の情に訴える鑑賞文学が発達したため,本当の意味での批評文化は形成されなかったともいえ,この型がメインになる人物は少ない(18人,0.50%)。逆にサブ型には,メインがどんな分野型であっても,評判になる随筆等を書いている人物が多く登場する(38人,1.75%)。
5:批評解説型:(俳論・歌論・解説者・美術・外国文学・雑学・(思想哲学)科学技術史・科学思想・(美学)美術史・啓蒙著述家・雑誌編集・ドキュメンタリー・伝記作家・ノンフィクションなど)分析と意見を述べるもので,2-3:学問分野に極めて近い。実際,学問を志しながら転向したケースも見られる。また,時事・告発・煽動などを主とするジャーナリストに対し,冷静かつ長期的なものであり,いわゆる啓蒙で,日本人全体のレベルアップに貢献してきた(65人,1.79%)。サブ型は,様々な分野型を本業としている人物が,啓蒙等のために著述するため,かなり多くなる(58人,2.68%)。
6:哲学思想型:最も深い思索を表す哲学的なもので,政治思想型や:軍政思想型にも近い(38人,1.05%)。サブ型には,主要な宗教の開祖のものも入れるるので多くなる(38人,1.75%)。
1:平面型:(諸絵画・書・版画・写真・エッチング・織物など)現在においてもなお絵画が大半であるが,一定の平面の枠内に造形するもの全てに共通し,取組やすいこともあって,詩歌型に近い数であり,この分野の半数以上を占める(153人,4.21%)。サブ型は,近世までは,文人といわれていた人たちは,当然のように,絵画もやっていたことなどによる(52人,2.40%)。
2:立体型:(彫塑・陶器・ガラス・彫金・木工・七宝・漆芸・人形・生花など)やはり古くからある彫刻を中心に三次元で造形するもの全て共通するが,いずれも特化したものなので,思ったより少ない(28人,7.70%)。生涯専念するようなものなので,サブ型はさらに少ない(8人,0.37%)。
3:空間型:(建築・造園・土木など)人々が出入りしたり内部を動き回ったり,遠方からの見え方なども期待される,いわば四次元の大規模な造形であり,多数の人間が関わって実現するため,さまざまな能力が必要である(32人,0.88%)。サブ型が意外に多いのは,コンドルやレーモンドなど日本で活躍したした外国人,夭折の詩人立原道造はすでに建築家であったこと,著名な禅僧の夢窓疎石が禅庭の造園家であったことなど,様々なことによる(23人,1.06%)。
4:商品型:((グラフィック・インダストリアル・インテリア)デザイン・料理・服飾・美容・広告・図案・装幀など)産業社会・資本主義の発展に対応するように,商品価値を決定づける造形として発達したもので,まだ少ないが,最近は公共的なものも含めて,多くの人たちの利用を期待する全てのものに必須に成りつつある(22人,0.61%)。新たな挑戦になっているので,サブ型は,さらに少ない(8人,0.37%)。
5:ストーリー型:(漫画・アニメ・絵巻など)古代の絵巻から始まる,いわば平面+時間という日本独自の造形であり,今や日本の漫画やアニメが世界を席巻しているが,いわゆる漫画家は,戦時下から登場し始めたもので新しく,少ない。描かれる絵以上にストーリー性が評価されているのは,2:小説型の基本である物語文化が基礎にあるからと考えられる(9人,0.25%)。当然ながら,サブ型はさらに少ない(4人,0.18%)。
6:シーン型:(演劇映画監督・映画脚本・プロデューサ・興行・解説・装置・技術・撮影・TVドラマなど) 以上全てを統合するような空間+時間の造形で,近代に入っての映画が登場,劇が一過性であるのに対し,映画は後世に残る一つの作品を造形するもので,根本的に異なるといえよう。とはいえ,役者や舞台装置など,多くが共通するため,導入されるや,爆発的に拡がった(33人,0.91%)。片手間にできるようなものでは無く,サブ型は少ない(11人,0.51%)。
1:楽曲型:(作曲・演奏・指揮・筝曲・古楽復原・謡曲・これら研究・普及など)古代から様々な楽器があり,イベントなどで活躍。オーケストラなど大編成になる一方,歌謡への伴奏としても発達。江戸時代以前の邦楽では,盲人が生活して行くために制度化されていたのも忘れてはいけない(43人,1.18%)。サブ型(10人,0.46%)。
2:歌謡型:(オペラ・流行歌・義太夫・ゴゼ唄・浪曲・常磐津・弾語り・シンガーソングライター・演歌師など)詩歌型と不可分のものとして最も古くから存在,現代でも歌詞が極めて重要な役割(33人,0.91%)。サブ型(8人,0.37%)。
3:口演型:(落語・漫才・演歌師・講談・漫談など)日本語という独特の言語が育んだ日本独自の文化。形として残らないため良く分からないが,江戸初期の「太平記読み」が大きな役割をしたらしい(27人,0.74%)。サブ型はとくに少ない(3人,0.14%)。
4:舞踊型:(能舞・バレエ・日本舞踊・モダンダンス・振付など)古代からの舞に近世からの踊が加わる(28人,0.77%)。サブ型はさらに少ない(2人,0.09%)。
5:演劇型:((役者)映画・舞台・歌舞伎・文楽人形使い・ミュージカルなど)歌舞伎役者から映画俳優まであり,現代においても,選択している人が多いように,この分野の3分の1以上を占める(84人,2.31%)。サブ型はかなり少なくなるが,現代でも,職業を変えるのが難しいと問題になっている(17人,0.78%)。
6:芸人アイドル型:(奇術・剣劇・ストリップ・見世物・タレント・アイドル)他に分類しにくいが,その他さまざまな形で演じたり,人気を得ることが意味をもっている,笠森お仙,松旭斎天一・天勝ような人物(7人,0.19%)。メインの職能とは言えず,サブ型が多くなるのは当然だろう。在原業平もこの型でこそ,存在が分かるような気がするし,タレントの草分け三木鶏郎の凄さも明確になる(12人,0.55%)。
4:(挑戦活動)競争的>(結果は別として)自己対象+(原則として)勝負ある活動
1:発明技術型:(軍艦・鉄道・施工・製鉄・織機・自動車・謄写版・印刷・土木・建築・都市・機械・窯業・電気・航空・化学・品質管理・模型・楽器など)人工物を生み出す工学に対応。実業分野の製品生産型の多くはここから始まり,近年は常時発明競争にさらされている状況にあり,軍事分野の装備技術型での競争も激しいが,もともとはオタク的個人のユニークな頭脳によって成されてきたものである(42人,1.16%)。サブ型は,製造会社の起業家の大半発明家であることなどによる(34人,1.57%)。
2:伝承技能型:(左官・石工・地図・製陶・織物・鉄砲・操船・宮大工・模型・絵付・刺繍・醸造・調律など)技能伝承しながら新たな飛躍を生み出したり,造形分野に近い作品を生み出したりするものであるが,いわゆる,無名の作家が大部分なので少ない(13人,0.36%)。そでも,別の分野型で名を遺した者により,サブの方が多くなる(18人,0.83%)。
3:コンサル仕掛型:(花火・仕掛屋・博覧会プランナー・イベント興行師・国際会議セット・画商・コンサルタント・権力側隠密(スパイ)など)その時点のみのイベント型造形や政治その他の分野を助けその実績が上がるようにする裏方活動,名前はほとんど表に出ないが,歴史的に大きな役割をした者が多い。例を挙げたいところであるが,著名な人物はほとんどおらず,対象とする活動も千差万別なので,トップページの年齢適活年譜リストから拾い出し,一枚年譜を見て貰いたい(29人,0.80%)。まさに,黒子である場合がほとんどなので,表向きの分類には出て来ないため,サブ型は,際立って多くなる(70人,3,23%)。
4:本業超越型:(財界トップ・業界支配・メセナ・福祉・親善・パトロン・支援・殖産・文化導入など)自ら関わる企業等の枠を超えて,産業界全体,さらには国民全体に関わるような事業や活動をするもの。社会分野等とは異なり,あくまでも本拠地での活動が基本になる。注目すべき人物を挙げてみると,維新直後から企業設立や経済界組織形成で資本主義を先導,社会・公共事業にも広く関係し,本業が何かわからないくらい超越している,最近,とくに話題の渋沢栄一を代表に,古い方から,甲州商人先駆者で,十組問屋の危機救い三橋会所を設置するなど,江戸経済を支配した杉本茂十郎,近代政商を先駆し,関西財界を指導,"東の渋沢・西の五代""大阪発展の恩人"と言われる五代友厚,台湾統治経済を確立,一高校長として影響大,国際連盟事務局次長後,国際平和に尽力した新渡戸稲造,造園家,林学者で,日本の国立公園行政で指導的役割をはたし,"国立公園の父"とよばれる田村剛,群馬交響楽団の創設はじめ,幅広く地域文化を先導し,巨大な足跡を残した実業家井上房一郎,そして,最も近いところで,{石川島}{東芝}再建で"企業再建の神様"といわれ,高齢になって{臨調}{行革審}会長になって,国民からも敬された土光敏夫らいる(33人,0.91%)。本業があるという前提故に,サブ型は,コンサル仕掛け型以上に際立って多い(102人,4.70%)。
5:ジャーナリスト型:(ドキュメント・報道写真・記録映画・ルポライター・雑誌編集など)新聞雑誌等が主体であったため,一見著述分野のように見えるが,本来的に時事問題について告発や煽動をする活動であって,近年では映画や写真,テレビその他さまざまな手段によるものが多くなっている(47人,1.29%)。サブ型には,他の分野型に入れられる人物でも,報道写真家など告発に努めるものが入るので,それなりに多くなる(47人,2.17%)。
6:奔放夢想型:次々に挑戦して開拓したり,複数(3つ以上)の分野で業績を上げたり,道楽に徹して業績になってしまったり,バサラなど破天荒であることが他者に影響を与えたりするもので,血液型ではB 型,民族型では海洋型,気質型では躁鬱気質に特化して現れるようだ。出来る限り,どの人物にについても,いずれかの分野型に入れるようにしたが,マルチ人間の典型で,多くの発明・創出・著作をしたが,世になじまず思わぬ最期になった江戸時代の平賀源内,維新後の変革期を象徴する破天荒な人生を送り,日本の近代劇運動に先駆的役割をした川上音二郎,"新しい女"の中でも際立って特異,"仏教界のスター"から,作家として華開くも早世した岡本かの子,近いところでは,歌人,劇作家,演出家,映画監督,競馬評論家など,一言では括れない天才的マルチ人間だった寺山修司など,どうしても,この型こそ第一という人物がいることも否定できないだろう(24人,0.66%)。従って,サブ型はかなり多くなる(53人,2.44%)。
1:豪商財閥型:(豪商・政商・商社・財界指導者・コンツェルン・保険・証券・投機・軍需・貿易・海運など)実業分野のトップを切って金の力を背景に政治権力と結びつく豪商が登場したように,金融を基本とするもの,権力との関係で利益を得るものなどが該当,実業界ネットワークの要にもなる(81人,2.23%)。サブ型(21人,0.97%)。
2:国土開発型:(炭鉱・電力・鉄道(国鉄含む)・鉱山・石油・製鉄・航空機・化学・運輸通信・商社・パルプ・武器火薬類・砂糖・水産振興・捕鯨など)政治権力との関係無しには事業展開しにくいもので,官僚分野の殖産技術型ともつながりが深い(33人,0.91%)。サブ型(16人人,0.74%)。
3:農水食品型:(酪農・ブドウ酒・農場経営・真珠・煙草・茶)生業から脱した農林水産業やその輸出入や卸などに関わるもので,社会分野の殖産型ともつながる(15人,0.41%)。サブ型(9人,0.42%)。
4:製品生産型:((工場)機械・製糸・造船・地場産業・建設含む)国民の購入するようなものを生産し名の知られる最も企業らしいもの(41人,1.13%)。サブ型(21人,0.97%)。
5:販売サービス型:(一般商品の物販・クリーニング・外食・化粧品・美容・ファッションなど)顧客と直接接するもの(衣食住)の物販やサービスで,日常的に縁が深い(28人,0.77%)。サブ型(17人,0.78%)。
6:メディア娯楽型:(出版・新聞・興行・映画配給・娯楽・印刷・広告・諸劇場経営など)国民に情報を伝え,あるいは娯楽を提供して喜ばすことによって利益を得るもので,時代とともに変遷も著しい。芸能分野との関係が大きく,実践分野のジャーナリスト型の能力も必要である(48人,1.32%)。サブ型(17人,0.78%)。
4 から6 までの型は,消費者と直接つながるため,造形分野の商品型との関わりも強い。
3.00%)。サブ型については,初めの3型は,いわゆる現役の時の名が残り,引退すると消えてしまうものなので,ほとんど無く,後の3型は,本業のあることが普通なので,かなり多くなるように,明確に分かれる(50人,2.31%)。
1:棋士型:(囲碁・将棋・これら指導者など)僧や和算家などによって,近世に入って急速に広がり,世界的に見ても独自かつ高度に発展した,いわば頭の戦(14人,0.39%)。サブ型は無い。
2:武道型:(武道家・剣士・力士・これら指導者など)江戸時代に入って戦を失った武士から始まる,武具や体によるまさに戦の代償行為で,いわば心の戦(23人,0.63%)。サブ型(3人,0.14%)。
3:スポーツ型:(各種スポーツ選手(監督)・レーサー・これら指導者など)明治維新後,西欧に追随するように始まり,近年急速に拡大しつつある,新たな体の戦。相撲のように,武道から始まったものが,スポーツとして見るとおかしな部分が多々あることもやむをえないか(27人,0.74%)。サブ型(2人,0.09%)。
4:探検紀行型:(冒険・探検・登山・紀行・登山ガイドなど)個の確立と対応するように登場した極限的挑戦活動であるが,経典を求めて,チベットに行くなどは,僧というよりも探検家に近い(22人,0.61%)。自然風土や人文を対象とする研究など必然的なものもあり,サブ型はかなり多い(19人,0.88%)。
5:競技振興型:(諸競技ジャーナリズム・評論・教育・体育協会・競技団体など)上記の諸競技をサポート(16人,0.44%)。とくに,本業のある場合が多いので,サブ型は非常に多い(19人,0.88%)。
6:茶道鑑識型:(香道・(動物等の闘い)・(数奇者)・グルメなども)独自に発展した茶道についてはどの分野にも入れにくいものであるが,少なくとも茶道が闘茶に始まり,それに近接する鑑識や香道などがまさに五感の戦いであり勝負が決まることから,この分野に入れた(13人,0.35%)。近代に入っても,茶人としても有名な実業家がおり,サブ型も多い(7人,0.32%)。
1:陰の女性型:(宮中・妻・側室・局・大奥・芸妓・乳母・生母・妾・娘・諜報・女中・秘書など)近世までは,日本では男性を支える以上に,男性を利用したり,支配して歴史を左右したケースが多い。足利義政の室の日野富子は,"御台所"として非凡な能力を発揮,中世を代表する女性の一人で,一時は義政の代りをしたほどで,サブ型を,政治分野の国家支配型に,徳川家康の側室の一人阿茶局は,才智にたけて,大奥を統制し,政治的にも家康・秀忠をサポートし,家光の乳母の春日局家康に直訴して家光の将軍継嗣に成功,大奥を牛耳り,無冠無位で参内,ともに,サブ型を,官僚部門の総務秘書型にしなければならないほどの人物だったし,ラフカディオ=ハーンの妻になったセツは,彼を,小泉八雲へと変身させるほどの存在であった。(30人,0.83%)。男女差別が強く,本業がありながら,男性を支えている場合も多く,サブ型も多くなり,没落武家の子三井高俊に嫁ぎ,商家として確立すべく家業差配し,息子らを訓育,高利が三井の祖になった三井殊法や,会津藩の悲劇後,若年でアメリカ留学,大山巌と結婚し"鹿鳴館の華"になり,看護活動支援の一方,様々な批判に苦労した大山捨松などがいるが,全体として,どちらをメインにするか,サブにするか,難しい(21人,0.97%)。
2:記録伝承型:(日記・覚書・口承・紀行など)特定の職能でなく,世の中の諸事を記録したり,口承したりすることで,後世に貢献するものも多々あり,そのことでのみ名が残る人物も多い。近世には,神坂次郎の「元禄御畳奉行の日記」で知られた朝日重章のように,日記が無ければ,名を遺すことのなかった人物もいれば,菅江真澄のように,東日本各地を旅して回り,当時の民俗を知る上で貴重な彩色絵紀行文を多数残し,広く知られる人物もいるが,近代に入っても,「特命全権大使米欧回覧実記」で近代化に貢献した久米邦武に対し,後半生を,あらゆることを日記に書き付けることにを費やした枢密院議長倉富勇三郎もいたという按配である(18人,0.50%)。もちろん,本業のある場合が普通なので,サブ型はかなり多く,さらに,さまざまな形の記録を遺している(26人,1.20%)。
3:脱社会型:(隠遁・孤高・アウトサイダー・食事療法・異端・逃避・隠居主体など)西行以来,日本人が憧れるものになっているが,鴨長明のように,実は職能分野からの落ちこぼれも多い。この二人を超えるような人物はいないが,何人か例を挙げれば,すべてからの自由を求め,茶を売りながら放浪し仏道全う,京の若者に多大の影響を与えた売茶翁こと高遊外,庵に住んで農民や子どもと交流,最晩年に貞信尼と出会って,大らかな書歌を遺した良寛,若くして隠居,清貧に甘んじながら,歌作革新,主君の出仕勧誘も辞退し,正岡子規の発掘で著名になった橘曙覧,2人の放浪の自由律俳人種田山頭火と尾崎放哉,画壇のあり方に不審抱き,奄美大島に居を定めて孤高・異端を通し,没後に発見・評価された田中一村など,どの人物もレベルは高い(24人,0.66%)。本業があってこその脱社会でもあるので,サブ型もかなり多く,その多くは著しておくこと名で,なるほどと言える人物であるが,社会から逃げた将軍足利義政と徳川家斉を入れたことを指摘しておく(33人,1.52%)。
4:反社会型:(密貿易・博徒・侠客・性科学・超心理学・犯罪者・ポルノ・異端・仇討ち・敵方スパイ・アナーキスト・テロリストなど)時代によって何が反社会的であるかは異なることもある。博徒やヤクザもかつては必要悪のように見なされ,講談などの材料にもなった(27人,0.74%)。サブ型は,本業の関係で起こす反社会活動など(12人,0.55%)。
5:在外活動型:(留学・追放・亡命・貿易・諸工作・キリシタン・文化・親善・難民・隠れ軍人・漂流者・大陸浪人・残留兵・国際結婚など。外交官・軍人・植民地支配は別)日本人は海外に出て行った者に冷たいところがあって,移住者たちが在地で大きな貢献をしていることなどあまり知られていない。このことが,海外に飛躍しようとする青年たちが増えない理由にもなっているが,島国である故,遭難などが契機になる場合もあり,かなり大きな数になる(96人,2.64%)。在外活動の分野型の方が重要な場合もあり,サブ型も多い(32人,1.48%)。
6:準日本人型:(沖縄・在日・アイヌ・亡命・帰化・混血外国籍・漂流者など)同様に,日本に入ってくる人たちどころか,もともと日本人社会を構成するはずの,アイヌや沖縄県民,いわゆる在日といわれる朝鮮系の人たち全てに冷たいところがあり,このことが日本のガラパゴス化と関係することは言うまでもない(33人,0.91%)。当然のことながら,サブ型は少ない(9人,0.42%)。
この章TOPへ
ページTOPへ
まず,歴史人物がどんな時代に活動したかを把握するため,データベースの作成には,日本史話三講の第Ⅱ講:時代循環のパターンで示した,以下のような時代区分を用いた。⇒詳しく知りたい人方は,当該ページへ。
Ⅰ古代(飛鳥・奈良・平安): 587年:丁未の変・・~1156年:保元の乱・・
Ⅰ-1:時代生成: 587年:丁未の変・・~ 769年:宇佐八幡神託
Ⅰ-1-1:前体制破壊期:587年:丁未の変・・~ 645年:乙巳の変・・
Ⅰ-1-2:再統一運動期: 645年:乙巳の変・・~ 702年:持統天皇没・
Ⅰ-1-3:新体制樹立期: 702年:持統天皇没・~ 769年:宇佐八幡神託
Ⅰ-2:時代前半: 769年:宇佐八幡神託~ 941年:承平天慶乱終
Ⅰ-2-1:時代建設期: 769年:宇佐八幡神託~ 806年:桓武天皇没・
Ⅰ-2-2:矛盾露呈期: 806年:桓武天皇没・~ 842年:承和の変・・
Ⅰ-2-3:偏向撹乱期: 842年:承和の変・・~ 941年:承平天慶乱終
Ⅰ-3:時代後半: 941年:承平天慶乱終~1156年:保元の乱・・
Ⅰ-3-1:時代再興期: 941年:承平天慶乱終~1027年:藤原道長没・
Ⅰ-3-2:理念衰退期:1027年:藤原道長没・~1086年:院政始・・・
Ⅰ-3-3:時代破綻期:1086年:院政始・・・~1156年:保元の乱・・
Ⅱ中世(鎌倉・室町):1156年:保元の乱・・~1543年:鉄砲伝来・・
Ⅱ-1:時代生成:1156年:保元の乱・・~1225年:北条政子没・
Ⅱ-1-1:前体制破壊期:1156年:保元の乱・・~1180年:源氏一斉蜂起
Ⅱ-1-2:再統一運動期:1180年:源氏一斉蜂起~1199年:源頼朝没・・
Ⅱ-1-3:新体制樹立期:1199年:源頼朝没・・~1225年:北条政子没・
Ⅱ-2:時代前半:1225年:北条政子没・~1333年:鎌倉幕府滅亡
Ⅱ-2-1:時代建設期:1225年:北条政子没・~1263年:北条時頼没・
Ⅱ-2-2:矛盾露呈期:1263年:北条時頼没・~1284年:北条時宗没・
Ⅱ-2-3:偏向撹乱期:1284年:北条時宗没・~1333年:鎌倉幕府滅亡
Ⅱ-3:時代後半:1333年:鎌倉幕府滅亡~1543年:鉄砲伝来・・
Ⅱ-3-1:時代再興期:1333年:鎌倉幕府滅亡~1408年:足利義満没・
Ⅱ-3-2:理念衰退期:1408年:足利義満没・~1467年:応仁の乱始・
Ⅱ-3-3:時代破綻期:1467年:応仁の乱始・~1543年:鉄砲伝来・・
Ⅲ近世(安土桃山・江戸):1543年:鉄砲伝来・・~1837年:大塩平八郎乱
Ⅲ-1:時代生成:1543年:鉄砲伝来・・1616年:徳川家康没・
Ⅲ-1-1:前体制破壊期:1543年:鉄砲伝来・・~1582年:本能寺の変・
Ⅲ-1-2:再統一運動期:1582年:本能寺の変・~1600年:関ヶ原の戦・
Ⅲ-1-3:新体制樹立期:1600年:関ヶ原の戦・~1616年:徳川家康没・
Ⅲ-2:時代前半:1616年:徳川家康没・~1709年:徳川綱吉没・
Ⅲ-2-1:時代建設期:1616年:徳川家康没・~1651年:徳川家光没・
Ⅲ-2-2:矛盾露呈期:1651年:徳川家光没・~1680年:徳川綱吉将軍
Ⅲ-2-3:偏向撹乱期:1680年:徳川綱吉将軍~1709年:徳川綱吉没・
Ⅲ-3:時代後半:1709年:徳川綱吉没・~1837年:大塩平八郎乱
Ⅲ-3-1:時代再興期:1709年:徳川綱吉没・~1751年:徳川吉宗没・
Ⅲ-3-2:理念衰退期:1751年:徳川吉宗没・~1786年:田沼意次失脚
Ⅲ-3-3:時代破綻期:1786年:田沼意次失脚~1837年:大塩平八郎乱
Ⅳ近代(明治・大正・昭和・平成):1837年:大塩平八郎乱~
Ⅳ-1:時代生成:1837年:大塩平八郎乱~1881年:明治14年政変
Ⅳ-1-1:前体制破壊期:1837年:大塩平八郎乱~1853年:ペリー来航・
Ⅳ-1-2:再統一運動期:1853年:ペリー来航・~1868年:明治維新・・
Ⅳ-1-3:新体制樹立期:1868年:明治維新・・~1881年:明治14年政変
Ⅳ-2:時代前半:1881年:明治14年政変~1945年:敗戦・・・・
Ⅳ-2-1:時代建設期:1881年:明治14年政変~1905年:日露戦争終・
Ⅳ-2-2:矛盾露呈期:1905年:日露戦争終・~1931年:満州事変・・
Ⅳ-2-3:偏向撹乱期:1931年:満州事変・・~1945年:敗戦・・・・
Ⅳ-3:時代後半:1945年:敗戦・・・・~
Ⅳ-3-1:時代再興期:1945年:敗戦・・・・~1973年:石油ショック
Ⅳ-3-2:理念衰退期:1973年:石油ショック~2001年:小泉内閣・・
図にしてみると,時代循環のパターンがよく分かる。
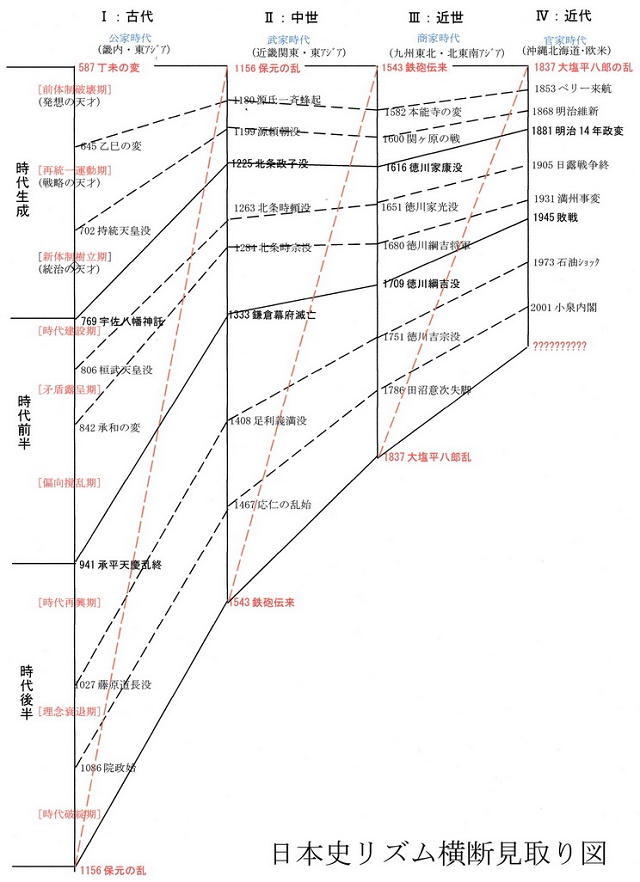
「はじめに」で示した時代区分を,各分野型・サブ型とをクロスさせて作成した表をみながら,それそれの歴史的な推移を見てみよう。⇒PDFファイル「時代別分野型数」,「時代別サブ型数」
0:皇室分野:古代の人物全体の数の2割を占め,中世においても1割を超えて,大きな存在になっているのは当然としても,江戸時代では,ほとんどゼロになってしまい,明治維新によって威信を回復したと言っても,ごく僅かで,天皇制の歴史においては,江戸幕府の始まりが,最大の転換であったことが,改めて認識される。また,古代の前半には,サブ型で,政治分野の国家支配型が多いように,実権を発揮していたが,後半は,藤原氏の支配を反映して,皇后型が多くなるのは当然として,中世においても,天皇型,皇族型が多いことは,武家政権に対抗するだけの存在で,権威を保ち続けていたと言えよう。
1-1:政治分野:まず,1:国家支配型は,日本で年代が明かな歴史の始まる推古天皇が,そもそも蘇我馬子が戴いて登場し,藤原不比等が覇権を握って以降,天皇自身が国家権力を発揮することはほとんど無く,古代の後半は藤原摂関家であり,中世がとくに多くなるのは,将軍から,その将軍を戴く執権や管領など,次々と覇権を握る人物が変わって行くからであり,2:地域支配型は,古代末に初めて,奥州藤原氏という国家から半ば独立した地域支配者が登場,中世には,サブ型で,守護大名や戦国大名という地域支配者が出てくる一方,琉球王国という,日本全体から見れば地域支配者であるが,王国として,国家支配者であったものも登場,近世の幕藩体制になると,藩主が老中になるような仕組みによって,メインの型にも,サブ型にも多くなり,近世が,まさに地域支配をベースにした国家,帝国に近いものであったことを示している。その点,維新後の近代は,都道府県知事,市町村長など,地方自治が謳われるものの,国家支配者の内閣総理大臣(首相)がほとんどで,地域支配者として登場する人物は少なく,まさに中央集権国家になってしまっている。3:権力補佐型がどの時代にも多いこと,5:時代変革型が維新前後に限られ,4:党派活動型がその後に出現していることなどは,分類の定義上当然として,6:政治思想型について,政治支配に対応する儒学は古代では法務学識型の官僚であって表に出るほどでなかったが,江戸時代にとくに多く,幕藩体制を支える朱子学や,それに対抗するかのように起こった民間の陽明学など,活発な議論が,結果として,時代を長く続かせたと言えよう。それに対して,近代のそれは,党派活動と裏腹のイデオロギー的なものであって,社会をまとめるより分解する方向に働いている。
1-2:軍事分野:1:統率型が,平安時代末の平氏の軍事支配から,戦国時代の闘争を経て,戦のなくなる江戸時代の前まで,つまり,中世から近世初めにかけて,集中的に多いのは当然であるが,とくに,サブ型が多いのは,前述したのように,将軍,執権,管領などの国家支配型が多かったからであり,まさに,世界のなかでも際立つ軍事国家の時代であったということであり,江戸時代に入ると,武家支配であっても,形式的な肩書の将軍戴く文治国家になって,いなくなってしまう。明治維新後は,近代国家の軍として,政治家の支配下になり,そのなかでの1:統率型になるが,いわゆる軍国主義の伸長によって,政治を超える権力を握り,悲劇に至ったこと,敗戦によって,軍そのものが無くなくなってしまうという,世界でも稀な状態になって,屈折した平和国家の時代を送っているが,改めて,江戸時代の文治国家のあり方を見直したくなる。鎌倉幕府以降の武家政権のトップは,形式的に,古代における蝦夷征伐の将軍ということで,天皇から征夷大将軍という地位を授けられることで成り立っているが,これらの将軍は,一義的には,1-1政治分野の1:国家支配型としてあげられ,ここではサブ型となる。中世,とくに戦国時代には,1-1政治分野の2:地域支配型のように,多くの1:統率型の武将が登場し,近代に入っては,政治から離れた軍人としての司令長官を代表とする1:統率型が登場することになる。2:補佐型や3:戦闘警固型は,分類の定義を反映し,4:参謀工作型と5:装備技術型も,すでに述べたように,もともと,1:統率型や2:補佐型の武将が有していた職能が,近代の軍になって分化したものといえ,6:軍政思想型も,もともと中国から伝わった孫子の兵法などが戦の基本で,新たな発想も含めて,中世全般にわたって武将自身が担っていたが,皮肉なことに,戦が無くなった江戸時代になって,国家支配者とは独立にこの型のものが登場する。
1-3:官僚分野:まず,古代に多いことが目に付くように,朝廷は官僚によって運営されていたが,職能としては,未分化のため,1:総務秘書型としており,サブ型にも多いのは,他の活動によって,歴史に名を遺す人物が多かったことを示している。明確な職能としては,古代においては,中国に見倣うことが全てであり,4:法務学識型が特別な存在になっていて,後の,学者のルーツでもあり,明治維新後にも,政府の存在,国際関係などを明確にするため,大きな役割を担った。中世においては,官僚に当たる役の大半を武将,武士が担っているため不明確で,江戸時代に入ると,いわゆる幕僚として,サブ型で,1:総務秘書型に記されるものがいるのは別として,5:内務民政型と6:殖産技術型の官僚とみなせる人物が一気に登場増大しており,国家の安定を維持し財源を確保するための領民支配がいかに進んだかを示し,まさに近代を準備したと言える。面白いのは,3:外務通訳型が中世までいないことで,外国といえば中国であった古代は,官人自らが漢語ができ,そうでなくても筆談で成立するようなものであったし,外交と言う点では,これまた仏僧に依存することが多かった。中世に入っても,つきあう範囲は中国文化圏内であり,漢語そのものまで仏僧に依存するのが普通であったため,この型のものは登場しない。江戸時代に入って,オランダという新たに常時付き合うことになる国ができたため,通詞という形で明確に登場し,蘭学を通じて,近代化の道を開くことになる。これとは別に,朝鮮との複雑な関係もまた,この型を必要にすることになった。近代に入って,一気に世界に投げ込まれたことで,爆発的に増えただけで無く,官僚のなかでの,地位も高くなった。2:財務再建型も,前述したように,そもそも国家権力が民から吸い上げる,つまり「入り」のみ管理していれば良かった古代,中世では無用な存在であって,財政再建ということが目的になるのは,江戸時代になってからで,殖産や民政と裏腹のものになったのである。
2-1:社会分野:古代・中世にはメインの方では出て来ないが,サブ型には,5:殖産型と6:文化型がでてくるのは,前者は荘園などの増収のため,後者は,まさに貴族的生活を示すようだ。1:医療型は,一見古そうに見えるが,科学的知識の無いところでは,所詮,仏だのみ,神だのみであり,実に,近世,江戸時代に入って,一気に盛んになる。民が生きて行く上での基本となる5:殖産型も,古代から中世にかけて,長く仏僧らに担われてきたが,近世に入ると,年貢に対応すべく,民の側での殖産に関わる人物が輩出,前者とともに,近代を準備する。それら以外は,近代に入って登場し一気に増大するが,サブ型でみれば,3:教育型は近世に多いことから,近代を準備していることが分かる。近代における6:文化型は,一般の人たちの生活レベルが高くなり,古代の貴族のようなゆとりある活動を始めた証でもあるが,その裏返しとして,差別もまた明らかになり,維新とともに,部落解放,女性解放などが噴き出し,大正デモクラシー期に労働者解放など合わせて,4:解放型が飛躍的に拡大するのである。1-3:官僚分野は,国家としての取り組みであるが,それらを待っていてはどうしようもなく,民のなかでの自らの取り組みがなされると言う点で,つながるものであり,繰り返すまでもなく,古代は,そのほとんどを仏僧に依存,多くは,民に自主性が芽生える中世において登場し,近代を準備することになる。2:福祉型は,中世以前は村社会近世における助け合いでカバーされており,近世のいわゆる大衆社会化に対応して,数の多かった盲人を支える座や稼ぐことのできる針灸ができたが,明治維新後,欧米に対応する形で広がり,大正デモクラシー期に飛躍,3:教育型については,,近世には,いわゆる官学が整備され,それに続くように,寺子屋から様々な塾,私学のような懐徳堂の出現,官民中間の藩校の整備へと拡大して行き,近代を準備することになる。維新後も,官学が整備する以前に慶応義塾があり,官学として東大しか無い時期に,早大の前身たる専門学校が登場,大正デモクラシー期には,いわゆる自由教育,女性教育を中心に飛躍的に広がるのである。
2-2:宗教分野:社会分野のところで,何度も述べたように,そのもとになったのは,仏教の僧であったが,民衆からの支持を得ることで,政治分野に対峙し,ある意味,民を育成支配する存在であり,つねに政治の側から,利用され,排除されてきたのである。そのなかでも,1:教導僧型は,初めて日本独自の仏教を拓いた空海,最澄を皮切りに,いわゆる開祖になるようなレベルの著名な僧たちが主であるが,それ以前においての,誰もがその名を知っている行基は,土木事業その他の殖産をはじめ,教育,福祉その他,幅広く社会分野に対応し,中世に登場する叡尊とその弟子忍性は,福祉に特化した教導僧であった。特定の分野への貢献という点で歴史に名を遺す2:活動僧型になると,国家の不備を補うように,連綿と輩出している。3:神道周辺型は,仏教より古いはずのものであるが,歴史人物として登場するのは,渡来した仏教,さらには,政治の基礎になった儒教とも対抗すべく,取り組まざるを得なくなったものであり,明治維新の廃仏毀釈・国家神道という異常を産み出すことにもつながっている。新たに登場する宗派は,その時点で4:新興宗教型といえるが,現時点から見ても新興宗教と言えるものは中世に登場,幕末から維新への,戦時から敗戦への,民の動揺に対応するかのように,段階的に飛躍している。5:キリスト教型については,戦国時代の民の心労に対応するように入ってきたカトリック(キリシタン)の影響があるが,明治維新後の動揺に対応して浸透したプロテスタントは,そもそも,慈善という形で,福祉や教育に大きな役割を果たし,近代化に貢献した。6:その他型は,リストのところで記したように,千差万別なので,ここでは触れない。
2-3:学問分野:これもまた,そのほとんどを仏僧が担っていたが,政治の背景は儒教で,官僚分野の法務学識型が,いわゆる漢学を担っていた。まず,やむを得ずこの分野に入れた6:蒐集編纂型については,嵯峨天皇の時代には,辞典のようなものが創られはじめ,万葉集,古今集や懐風藻なども,この範疇に入ると考えれば,最も古い時代から連綿と,さまざまなものごとについての蒐集編纂型の人物が登場する。とくに,何度も指摘するように,古今集のその後の影響を見れば,編纂した紀貫之は,歌人以上に,この型にしなければならない人物とも言えよう。そして,日本語の特殊性,漢学など中国との関係などから,5:文学言語型が古代に始まった最初の学問で,同じように,各時代に重要な業績を挙げる学者が連綿と続き,江戸時代の後半には,いわゆる国学が登場,大学者ともいえる本居宣長の業績は,現在もなお,日本人意識に強い影響を与え続けている。その後は,学問と言えるようなものは長く登場しなかったが,戦のなくなった江戸時代に入るや,いわずとしれた「塵劫記」に始まる和算が天文暦学ともつながり,時代を通して発展的に続けられ,幕末維新時に,西洋科学を吸収する基礎にもなった1:数理天文型,それに続いて,中国から入った,主として薬草を対象とした本草学をもとに,植物学に近いものが登場し,さらに,蘭学によって,物理学や化学に展開,西洋科学を吸収する基礎にもなった2:自然科学型,蘭学による科学的思考が,歴史地理などにも結び付いて3:人文科学型となり,明治維新後,とくに日露戦争後の日本至上主義の高まり,大陸への関心などから飛躍的に高まって行く。そして,世界においても新しい4:社会科学型は,維新後はヨーロッパの法制度などへの関心,敗戦後は,アメリカ資本主義の影響で,経済へと広がって行く。
3-1:著述分野:学問と社会とのつながりも一般的には著述によって行われることから,ここに登場。1:詩歌型は,古代では,中国とのつながりで漢詩が主体であり,王朝文化とともに和歌が広がる。中世には連歌,近世には俳諧,近代に入って,和歌は短歌になり,西洋詩が広がり,どの時代も多く,次々と積み重ねられ,大正デモクラシー期に爆発するように,言わば,日本人にとっての基礎的な素養でもあり,サブ型は,それ以上に多い。2:小説型については,紫式部の「源氏物語」は,世界最古の小説といわれるが,物語は小説ではないともいい,現代の小説家につながるもとは,元禄時代の井原西鶴といえ,近世には小説に類する様々な形のものが流行しては消えることを繰り返し,幕末の文化文政時代に登場する十返舎一九が,近代の職業作家の嚆矢となる。そして,坪内逍遥の啓蒙によって,いわゆる小説家が次々に登場,大正デモクラシー期の自由な雰囲気によって飛躍するのである。ついでながら,ファンが多い村上春樹が,芥川賞もとっていなく,国内の小説家からは敬遠されて,もっぱら外国で活動しているのは,彼の作品が,まさに物語であることによるのであり,ノーベル文学賞で世界に知られたガルシア=マルケスの「百年の孤独」も物語といえる。3:脚本型は,芸能の演劇型や口演型に対応,浄瑠璃,歌舞伎,それとは別に落語と,近世に開花,近代に入って,演劇,漫才,映画などへ広がり,やはり大正デモクラシー期に飛躍する。4:随筆鑑賞型は,王朝文化での,清少納言の「枕草子」と数々の女流日記文学が,その後の日本文化の基本となるもので,中世の吉田兼好の「徒然草」を経て,サブ型の方に極めて多く現れるようになり,近代に入ると,多くの分野型の人物が,随筆でも名をなすようになった。5:批評解説型は,随筆に近い評論から,中世には,言語文学の批評解説で深まり,近世,近代へと対象も広がり,どの時代にも,人々を啓蒙しようとする人物がいて,同程度の比率になっており,本業の分野型のものを啓蒙しようとため,サブ型も多く,満州事変後には,国家国民の拠り所を求めるように飛躍する。空海に始まる多くの教導僧の著述は,極めて深い6:哲学思想型のものであり,サブ型をみると,古代,中世とも非常に多いが,メインの方では,近世において,儒学を背景とした思想家が輩出,デザイン三講でとりあげた荻生徂徠のように,プラグマティックな天才的思想家も登場,その影響で,多くの合理的な思想をもつ,いわゆる経世家を輩出し,近代を準備するとともに,西洋の影響を受けた哲学者にも優れた人物を生むことになる。
3-2:造形分野:言葉を介さないと言う点で,もっとも原初的でもあるが,それ故に伝わらないできた面も大きい。1:平面型は,著述とつながる書家とともに,画家も古代に登場,中世の山水画を経て,近世には,最近,人気の集中している若冲だけでなく,その時代の世界のレベルを超える画家が輩出,絶頂期を迎えただけでなく,商品化の対象になる浮世絵も登場し,幕末の文化文政期には戯作の挿絵との関係で飛躍,そして近代の西洋画,写真などへと広がり,それらが民に消化される時期と対応する大正デモクラシー期に飛躍する。2:立体型は,仏像など古代に登場するが,彫刻家という点では,中世を開いた運慶に始まり,近世の円空や木喰五行の仏像多作などもあるが,全体に少なく,近世には陶芸が広がり,近代に入って,ロダンの影響を受けた彫刻とともに,大正デモクラシー期に飛躍する。3:空間型は,ものづくりとしては最も総合的なデザインといえるもので,建築もまた古代以前からあり,斉明天皇の時代の庭園跡なども発見されているが,中世には,禅僧との関係で造園家といえる存在が登場,武将の多くは築城などの点で建築家でもあり,近世には,小堀遠州が,大名というより,建築家,造園家として扱われ,また,優れた大工棟梁が,幕府の建築部門を担ったりするが,職業としての建築家は,近代に入って,西欧の建築学教育が浸透したことにより,大正デモクラシー期に飛躍する。造園の方は,なお,植木職人の世界が続く一方,林学などの分野型でも,優れた造園家が登場している。4:商品型は,近代に資本主義が入って,いわゆるデザイナが登場することに対応,その嚆矢は,画家としては,単なる人気作家に近い竹久夢二で,デザイナとすれば,時代を先駆けた天才であった。宣伝広告と結びついたデザイナが登場し,それが満州事変後の国家宣伝に利用されることで飛躍,戦後のデザインが受け入れられにくい原因にもなった。現在,世界に広がる日本の漫画は,その場面展開が際立っていることから,5:ストーリー型としており,戦後に飛躍するが,そのルーツは絵巻物であり,この分野で日本を世界に冠たるものにしたといえるが,後白河法皇の文化政策で多くの傑作が描かれているものの,作者不明で,鳥獣戯画の作者が覚猷(鳥羽僧正)に例えられ,中世の土佐光信,近世の土佐光起,岩佐又兵衛くらいしか分かっていないのが残念である。6:シーン型は,演劇,映画など,西欧由来の,時間を総合的にデザインするもので,近代に始まるが,次の芸能に登場する俳優について見れば,近世の歌舞伎とつながることは明らかで,単に,その舞台の演出などの作者が分からない,あるいは,座元自身ができたことによる。映画は,その発生時期が,日本の満州事変からの戦時に対応して爆発し,戦後に繋がるのである。
3-3:芸能分野:時間に関わり,身体を用いる芸能にはまた,日本独自のものが多い。1:楽曲型については,雅楽については古代から続くものの,特定の音楽家が知られず,近世に入り,盲人福祉との関係で登場した天才八橋検校によって筝曲が飛躍,近代には西洋音楽の作曲,演奏になるが,天才滝廉太郎は別として,戦争との関係で,優れた作曲家の名が消える一方,歌謡曲や演歌との関係で,独占的に請け負う著名な作曲家が出現している。2:歌謡型は,近世早くに登場した浄瑠璃は,義太夫節などといわれるように歌謡が主体であり,近代に入って,演歌,歌謡曲などの大流行をみる。3:口演型の代表,浄瑠璃と同じ頃に登場した落語は,漫才その他のものがでてきても食われることなく,現代にまでそのまま続く,日本独自のものになっている。4:舞踊型は,まず確立したのが中世に始まる能舞で,現代にも続いており,近代には,全く異なる,バレエ,ダンスが登場。続いて登場する歌舞伎は,舞台で演じる役者に熱中するように,5:演劇型であり,前項で述べたように,そのまま近代の演劇につながるところがある。ここまで,いずれも,著述分野や造形分野の多くの型と同様,大正デモクラシー期に飛躍している。戦後の,とくにテレビとともに登場するタレントなるものは,それだけで新たな型に挙げることには躊躇されるが,定義のところで示したように,様々な芸人,あるいはアイドル的存在と一緒にしてみれば,古代や近世にも,そのことによって名を遺している人物に思い当たることから,6:芸人アイドル型とした。
4-1:実践分野:分類定義のところで述べたように,本講のなかで,他に割り振りにくいものの,社会への関与の仕方が実践的で,その影響の大きいものを集め,独自の型に分けたが,実践的であることは,身体を使う度合いが大きいことでもあり,前項の芸能分野につながるものでなないかと,ここに置いている。1:発明技術型は,ものづくりに対応し,鉄砲が由来するや,時を経ずして,輸出国になるほでのレベルで,それを支配した織田信長が近世を開くことになり,色々な発明家が登場,幕末の天才発明技術家田中久重が,現在に続く東芝の祖になったように,欧米から新たなものが次々と入ってくる近代に,飛躍することになる。近世までの芸能は,まさに2:伝承技能型でもあったが,ここでは,前者と同様,ものづくりに対応,当然,古代からの型ではあるが,名が残るようになったのは,近代への発明技術につながる維新前夜で,突然のように多く現れる。3:コンサル仕掛型は,中世において,武将官間の交渉を僧が担っていることで歴史に登場,それ以前にも,僧は外交通訳で大きな役割をし,その後は,連歌師や俳人,茶人など,様々なところに出入りしても疑われない人たちもその役を担い,結果として危険なことにもなるように,サブ型の方で,その存在の大きさが良く分かる。近代に入っても,政治の黒幕は似た存在であるが,いわゆるコンサルタントとして,明確な職業が登場し,メインの分野型になるのである。4:本業超越型は,自らの業界全体の振興,さらには,民すべてのためになる活動につながるもので,社会分野に対応するように,大正デモクラシー期に飛躍する。近代に入るや否や,幕末の幕府批判に続くように,新政府批判の告発が一気に増大,5:ジャーナリスト型が活発になり,一般に広く知られる人物が輩出,大正デモクラシー期に飛躍するが,敗戦後は,アメリカ支配が枷になっているのか,いわゆるジャーナリズムでの告発は少なく,近年ますます衰えているのが気になるところであるが,報道写真のように,メインの分野型では,写真家すなわち造形分野の平面型であるものの,サブ型としてのジャーナリスト型の方こそメインではないかと思わせる人物もいる。そして,時代に関係なく,6:奔放夢想型として捉えるしかない人物が,社会を色づけている。芸能分野との関係でみれば川上音二郎,この分野のなかの発明技術との関係では平賀源内がその典型であると思われるが,大正デモクラシー期には,自由の雰囲気を裏付けるように,有象無象のこの型の人物が出てきている。
4-2:実業分野:近代の資本主義によって登場する企業に対応するが,すでに江戸時代に準備されていた面もある。1:豪商財閥型は,江戸時代初期には,幕府につながる有力な豪商が登場して,近世の象徴になり,財閥の代表,三井,住友の発祥もそれに続いているように,近代を準備したが,敗戦後,形式的には財閥は解体され消えてしまう。2:国土開発型は,近世の初めに,豪商の一員角倉了以が,地域経済の発展のためにと取り組み,著名な河村瑞賢のように,国内での輸送を円滑にして利益を挙げようと,幕府の許可のもと,河川開発,海運整備などに取り組んで大きな貢献をした者もいたが,維新後の鉄道や,敗戦後の高速道路のように,近代に飛躍する。3:農水食品型は,近世までは,農業は,すべて庶民に依存していて,時の権力者がそれらを取り上げてしまう形であったが,水産業には,後述の「にんべん」のようなものも登場している。近代には,国民が豊かで自由になる大正デモクラシー期には,消費者に近いことから,著名な企業が次々登場する。現代において,日本を代表する4:製品生産型は,近代に入り,世界と競争していく上で基本になった型であり,欧米から,あまり遅れることなく次々と誕生,世界レベルの発明技術にもことかかず,農水食品型に対して,戦時,敗戦後も続けて多い。5:販売サービス型は,江戸時代中頃に,髙津伊兵衛が創業した,削り節やふりかけ,調味料を製造,水産加工品メーカーとして業界最古参の「にんべん」が,一般には,日本橋の老舗店舗として知られる。良く知られているように,デパート三越のルーツは,財閥三井のスタートにもなっている三井呉服店であり,代々継いでいく点で,豪商財閥型に類似する。6:メディア娯楽型については,そのような施設等ができて流行ったのも,江戸時代に,今で言う大衆化が進んだことによるのであり,サブ型に多いように,大衆に呼応する仮名草子や浮世絵などを扱う書肆を営みながら,自ら作家になる人物もいるが,後期には,現代においても,この型の天才と見なされる蔦屋重三郎がでてくるのである。近代に入ってすぐに,実践分野のジャーナリスト型と表裏一体に,多くの新聞社が登場,やがて,現在なお有名な新聞社や出版社が続々誕生,大正デモクラシー期になると,宝塚歌劇,松竹,吉本興業と,現在もなお派手に活動している企業が誕生するなど,後述するように,文化のデザイナとしての役割が大きい。
4-3:競技分野:1-2軍事分野は,相手を打ち負かすための血みどろの戦いであり,戦国時代は,世界でもまれに見る複雑怪奇な内乱で,アジアに進出してきたポルトガルはじめヨーロッパ列強も,恐れをなして,植民化に二の足を踏まざるを得なかったのであるが,その内乱を打ち止めにして,戦を無くしてしまった徳川幕府もまた,世界に先駆けた政権であった。いわゆる競技は,古代においても,歌合せほかの遊びとしてあったが,戦を無くしたことによって登場する競技は,命がけでもあるという点で,戦の代替物であり,そのなかでも新しいスポーツにおいて,大谷翔平のように,世界的に活躍するような選手こそが,現代における本当の一流人物であり,新たな時代を担っていくことが期待されるのである。こうして,この分野が軍事分野とつながることによって,活動のマンダラは完結する。⇒「職能からみた新日本人論」 戦に代わる男の戦いとして最初に登場したのが,6:茶道鑑識型で,茶そのものを当てる闘茶であり,それがベースになって茶道ができ,茶道具などによって,鑑識もまた戦いとして広がっていき,武将が茶道と直結しているのも当然であるが,企業間の競争は,現在の戦いでもあって,企業のトップのなかには,茶人として著名な人物も多いのである。そして,囲碁将棋の1:棋士型もまた,もともとは仏僧の世界では普通のもので,武将たちも楽しんでいたようであるが,戦がなくなる近世に入るとともに,専門職として登場し,現代なお大きなニュースになっており,続いて,まさに戦そのものの代替になった2:武道型が,近代に入って,西欧文化の3:スポーツ型に展開,世界でも新しい巨大な分野としてスポーツが続々生まれており,日本では,戦時の国威発揚と関連して拡がり,戦後につながって行くが,それと呼応するように,スポーツに対応するものが主の5:競技振興型が登場,この三者を繋ぐ結節点になった嘉納治五郎の存在の大きさが分かる。最後に,他人との戦いでは無く,辺地や登山など挑戦する4:探検紀行型をこの分野に入れたが,これも,近世の平和がもたらし,著述分野の随筆鑑賞型のように,様々な,分野型の人物が国内を探検紀行,近代には,世界各国を旅するサブ型が多い。
X:特異分野:以上のように,(日本の)社会との関係で明確に位置付けられない様々な活動が,社会全体を豊かなものにしていることは言うまでもないが,近年,欧米文化の影響もあって,その多くが否定されるようになってきた。いずれにしても,開国後に一気に増大する最後の外国人型以外は,時代と直接関わらないものではあるが,言葉は悪いが'歴史は女によって創られる'のは一面真理を突いていて,1:陰の女性型こそがその活動の主体であったことさえある。随筆鑑賞では無い本来の意味での日記など,なにかしら記録を遺す2:記録伝承型は,その時代の活動としては意味なくとも,本当の歴史を知るためにも貴重なもので,そのことによって,歴史的人物として名を遺すことになる。サブ型を見ると,幕末維新時や戦時戦後に多くなっているが,当然であろう。属している社会から逐電や隠遁する3:脱社会型は,平安末の西行が始めて,その後の多くの人物において理想的生き方にもなったが,現実には容易いことでは無く,おちこぼれその他によって,社会との関係を断たれている場合も多い。4:反社会型については,単純に,世の中を変えようと権力に向かうことを入れてしまうと,どこか矛盾してしまう。できるだけ冷静に見て,いわゆる犯罪に当たるものや,暴力団のように反社会的な活動に絞る。この型が,大正デモクラシー期に多くなっているのは,テロ社会の始まりにも対応しているが,平和や豊かさに溺れ,他人のことに思い至らない時代の表れで,近年の世界の状況にも似ているようだ。海難漂着なども含めて,日本という島国においては,理由はどうであれ,また,国内で評価されるかどうかにかかわらず,5:在外活動型には特別の意味があろう。同じく,島国日本においては,古代の鑑真から,江戸初期のアダムズ,維新を支えたグラバーや維新後のお雇い外国人まで,数は少なくとも半ば日本人として活動して決定的影響を及ぼした6:準日本人型の人物がいる。沖縄は,かつては琉球王国というべつの国であった故,他の日本人と同列には扱えないし,近代の植民地やアイヌの問題など,難題も多い。近代に入って,日本に亡命してきたロシア人の影響が多いのと同様,中世の元僧,近世の明僧などについても,さらに拾っていきたいものである。
天皇型:国家支配型といえるのは,蘇我氏の支配を脱し,日本国成立の礎をつくった天智,天武,持統天皇,それに続く,藤原不比等が確立寸前に至るも,その子らのいわゆる<藤原四卿没>によって混乱に陥り,孝謙(称徳)天皇は,淡海三船をして現在でも誰もが当たり前のように口にするそれ以前の天皇の漢風諡号を撰じさせるも,道鏡をして,天皇の地位脅かすに至らせ,<宇佐八幡神託>によって危機回避,その後近世まで続く平安京をつくった桓武天皇,そして,日本人意識を昂揚する国風文化を主導した嵯峨天皇までであろう。その後,摂関藤原氏の支配を脱し,院政という方式を編み出すも,すぐに没してしまった後三条天皇,実際に始まった院政期には奥州藤原氏が栄華を誇るように,とても国家支配型とは言えないし,武家政権から権力を取り戻そうとした後鳥羽天皇は配流され,一時的に国家支配型になった後醍醐天皇も,結局敗れてしまった。維新により,見かけ上権力を握った明治天皇も,国家支配型といえないことは言うまでもないだろう。なお,最初に登場する推古天皇を支えた聖徳太子も,皇族型ながら実質的には国家支配型の天皇ともみなされるだろう。つけくわえれば,リストで取り上げている嵯峨天皇までの16人の天皇のうち,いわゆる女帝は,推古天皇,持統天皇はじめ6人になり,そのうち2人は重祚しているので,実質8人と半分にあたる。つまり,男女平等に近かったといえ,天皇を利用とする時の政権が,天皇は男系に限るものにしたのである。さらに,不比等というより橘三千代の娘で人民最初の皇后になった光明皇后が,夫の聖武天皇の大仏に至る仏教振興策に影響を及ぼしたことは良く知られているが,教導僧に導かれるように施薬院や悲田院などの福祉施設を設置,嵯峨天皇の皇后であった橘嘉智子は,聖武天皇を支え,光明皇后の異父兄の橘諸兄の曽孫に当たり,橘氏の子弟のために大学別曹学館院を設立しているなど,皇室は近代に至るまで,福祉型,教育型などを先行する役割を担って行く。
1-1:政治分野の1:国家支配型:古代は,蘇我馬子に始まり,クーデタで権力奪取した中臣鎌足に始まる藤原氏が摂関となり,道長の栄華を迎えるも,その子頼通で終わり,院政期の空白を経るうち,サブ型が,1-2軍事分野の1:統率型の平清盛が現れて中世に入り,源頼朝により武家政権が始まる。以後,実質的な国家支配型は執権北条氏となるが,足利尊氏によって国家支配型の将軍が復活するものの,政治から逃げてしまう将軍義政の登場によって,応仁の乱が勃発,以後の将軍は力を発揮することができずに,いわゆる戦国時代の空白,混乱期になってしまう。その状態に止めを刺して近世の幕を開いた織田信長と,それに続く豊臣秀吉が実質的な将軍の役割をし,江戸幕府を開いて名実ともに将軍になった徳川家康まで,サブ型が,1-2軍事分野の1:統率型の人物であって,武家政権そのものであった。それ以降続く徳川将軍は,形式的に留まり,サブ型から国家支配型が消えるのと並行して,かつての摂関藤原氏に類似し,近代の内閣首相につながる首席老中が実質的な国家支配型になるのである。そのなかで,家光以降,綱吉,吉宗,かつての天皇のように,自ら実質的な国家支配型になった将軍が見られるが,11代将軍徳川家斉のいわゆる大御所政治を含めて55年に及ぶ支配は,大奥入り浸りで,民を無視し,地方の有力藩が力を持つようになると言う点で,古代の院政期のようなものであり,その後,幕藩体制は崩壊して行き,最後の将軍慶喜が大政奉還,大久保利通はじめ,いわゆる志士,つまりサブ型が,5:時代変革型の人物の国家支配となり,内閣,帝国憲法,帝国議会という現代につながる政権の基礎を確立した伊藤博文を初代として,首相が国家支配型になるのである。
1-2:軍事分野の1:統率型:坂上苅田麻呂を代表に古代には朝廷の国家支配を維持すべく将軍が置かれてきたが,天皇の地位をも狙ったと言われる平将門の乱を契機に,東国で平氏,源氏の武士が勃興,前述のとおり,平清盛以降,家康まで,もっとも上位にあるべきこの型の人物は,国家支配型として挙げられることになる。そして,南北朝を契機に,大内氏や朝倉氏から,北条早雲や今川氏親以降,地方レベルながら,この型のものが登場,後の幕藩体制を準備する1-1:政治分野の2:地域支配型のものがサブ型に記されるよになり,戦国時代の著名な人物が次々登場,信長の登場で終止符を打たれ,家康によって,まさに地域支配者たる藩主になるのである。このように,中世においては,国家支配,地域支配と軍事分野の統率型が一体であり,それらが明確に分離独立する,徳川幕府による近世の始まりは,西洋近代の始まりと,時代的に軌を一にしている。
1-3:官僚分野:古代の朝廷において,中国から制度を導入したこととの関係で,中国語をマスターすることを一義的に,いわゆる漢学を専門とする4:法務学識型の人物の名が登場,その最初の,聖武天皇の時代に,初の漢詩集「懐風藻」をまとめ,続く,孝謙天皇のもと,歴代天皇すべての漢風諡号を考案した超人的文人淡海三船は別にして,菅原道真の祖父清公が,学者官人家系の菅家の基礎をつくり,いわゆる文章生という,官僚分野のなかで法務学識の専門家を育てていく,明治維新後の東大法学部にあたるような仕組みができ,大江匡衡に始まり,匡房という大学者を生み,鎌倉幕府の創設期を支えた広元に至る大江家まで,多くの人材が輩出,その最後を,中世への大変革期に,権力者たちに信頼され,菅原道真以来,儒学者で唯一人没後神になった清原頼業が飾る。中世には,これら官僚は儒学者となり,学者として独立,武家ほか広く教育をし始めたらしく,世界最古の大学ともいわれる足利学校の誕生を見るのであるが,それを再興して,結果的に近世を開く準備をしたのが,将軍足利義教と関東公方足利持氏の間の調整に苦労した管領上杉憲実であり,教育型として忘れてはならない人物といえよう。
2-2:宗教分野の1:教導僧型:日本国の形成の始まりは大陸からの仏教の伝来にあり,すべての社会的な活動分野型の人物に先駆けて,登場したのが1:教導僧型で,民衆教化と社会事業に全力を投入し,宇治橋造橋伝説もある道昭に続いて登場した行基は,知識集団組織して民衆を教導,膨大な社会土木事業を営んで,早くも国家支配型に対抗するような存在となり,国家は大仏造立を契機に彼を取り込み,初の大僧正にしたのであるが,すでに,2-1:社会分野の3:教育型と5:殖産型のもとになっている。最澄が開き,円仁,円珍によって整備された比叡山は,その後,僧になろうとする者のほとんどが最初に出家して学び始めるという点で,巨大な教育機関でもあったが,その後に登場し定着する宗派の本山も同様に教育機関であり,とくにその傾向の著しい本願寺などが広がって行ったのも当然であろう。したがって,教導僧型はその名に含まれているように,同時に,2-1社会分野の3:教育型であり,2-3学問分野にもつながるものなので,サブ型には記していない。空海に始まり,その後も道元など,著作によって間接的に時間を超えて教導していく者については,3-1著述分野の6:哲学思想型に分化していく元になる。同時に,興福寺や延暦寺の僧兵に始まり,一向一揆から始まる信長と対決が極致になった本願寺など,軍事分野さえ持っていたということになる。2-1社会分野の2:福祉型については,とくに,今日につながる明確な取り組みをした叡尊とその弟子忍性が特記される。2:活動僧型については,学僧が学問に特化したもの,歌僧,画僧など,それぞれに早くから別分野で確立しているものなど別にして,最初に登場すし不比等のアドバイザになった道慈はじめ,源頼朝と院との間奔走した文覚,承久の乱の黒幕尊長など,4-1実践分野の3:コンサル仕掛型の僧は多く,中世になって"黒衣の宰相"と呼ばれる活動僧よりコンサル仕掛型として挙げられる賢俊,満済以降も,今川義元の兵法参謀になった太原崇孚,幕府創始期に宗教行政の中心になった天海,公武斡旋に奔走した松花堂昭乗など枚挙にいとまない。
以上述べてきたように,職能は,文明が進むとともに,多様になるが,その歴史をパターン化すると,動植物の系統樹のように,必ず何らかのものから派生,分化,転化してきて,その間には,動植物同様,隆盛から衰退し,ついには絶滅してしまうものも見られるということになる。そういう観点に立って,作成した下図に従い,以下に,整理しておく。
まず,統治された社会(文明)が実現する以前からの生業としての農林水産業は,職能以前のものとして,取り上げず,また,日本では,天皇制という世界的に見ても特異な統治システムが形成され,当然のことながら,皇室は職能選択の対象にならないことが前提となるが,そもそも社会というものが登場した時点で最初に必要になったのは,外敵から守るための軍人であり,それと一体になる形で当該社会を治める長(オサ)であった。その支配のもと,農耕や狩猟など,始めはジェンダーによる分化が始まり,その一方で,社会化する上で個々人に生じる様々な葛藤を救う巫女のようなものが発生したと考えられる。
文明化が始まると,軍事(武断)よりも政治(文治)が重要になり,長(オサ)周辺の政治家と,それを支える官僚的職業が分化,政治・官僚・軍事三分野による支配が確立,以後,天皇と公卿,将軍と藩主など,様々な体制ではありながら現代まで続く。さらに文明が進み,軍事の比重の下がる場合も生じると,その代替として武道が登場し,西欧ではスポーツに進化していく。現在のサッカーの国際的な対戦が,現実には敵対している国同志でも実施されたりするのを見ると,まさに,戦争の代償行為であり,戦争を無くす手がかりさえあるように感じられる。ところで,憲法九条で軍事を否定するわが国は,その先を行っているといえるだろうか。
同様に,巫女的なものはいわゆる宗教となり,日本では仏教伝来による僧侶がその中核を成すようになる。初期の僧は,行基を始め,今日でいうところの社会事業・活動家でもあり,その後の高僧は皆,学問の先端を担い,中世以降は画僧など,芸術家をも先取りする。僧が社会活動家や学者に分化して行く結果,本来的宗教の役割はどんどん小さくなり,大半のお寺は,最早葬式などのためにしか存在しないような些末なものになってしまった。いずれにしても,宗教・社会・学問については,人民を支える社会貢献分野として括ることができると言える。
芸術分野は,人類誕生以来の情動としての歌謡や絵画がルーツであるが,文明化とともに宗教を支えるものとなり,わが国でも,かつて,文人のように詩歌や書画全てをこなしていたものが,近世に入ると,西欧のように,自己追求型の芸術家が登場,文字による文筆,様々な造形などの芸術家に分化する一方,下層階級のものだった芸能が支配層に取り入れられて,芸術分野に入ってくる。
近世に登場した,市のレベルの,また国家的に統制された貿易のレベルで行われてきた商業的なものや,職人レベルから発展する工業的なものが,近代に入って,企業として大きく広がって行き,わが国では西欧の近代化とほぼ同じ頃には国家とつながる豪商が登場,江戸時代を通じて様々な取引の手法を発展させてきたので,明治維新後の近代化にスムーズに対応できたと言える。企業に至らずとも,今まで述べて来たような職業の枠におさまらない実践的なものも,どんどん登場しており,グローバル化の競争社会のなかで,大きな役割を持つようになると考えられる。この競争という点でスポーツも一緒であり,実際,世界的レベルで戦っている選手たちの言動を見ると,現代日本では最も優れた人物が多い感じさえするのである。
職能選択の対象にはならないが,社会を構成するものとして,まず歴史を通じて,男や家庭を支える存在として大きな役割をしてきた(陰の)女性群があり,日本の神様の大元は天照大神で女性とされ,古くは母系社会であり,女・男(西欧ではなど)や,女性が天皇になってもそのまま天皇(西欧では)とされるなど,西欧でのManとWoman,KingとQueenなどのように,言葉の上での差別,つまり本質的差別は無かったが,明治維新以後,西欧化とともに男を支えることが強調され,本格的差別が始まったといえる。ついでながら,西欧では,兄弟に長幼の別が無いのに対し,東アジアでは厳然と区別されるように,長幼の差別が強く,これが若手の登場への阻害要因になっていることは否定できまない。その上でも,年齢に関係無く実力が評価されるスポーツ選手は,やはり未来を先取りしているように見える。そのほか,社会から排除されてきた被差別民や河原者,それとは別に,海賊やそこから派生したヤクザ,あるいは博徒など反社会的と言われながらも社会の安定に果たしてきた役割が無視できないもの,あるいは日本文化特有の,隠遁・遊行・放浪など脱社会的存在がある。他方,日本社会は移民や高度成長期の中東の企業者など海外に出た日本人には冷たい社会であり,同時に,外国人もあまり受け入れない社会なので,海外で活動した日本人,日本人として活動した数少ない外国人も特記される。その他,日記や伝承で社会に貢献する者も多く,これら全てを,社会の通奏低音的な存在として捉える必要があるといえだろう。
現代は,いわゆる専門家(スパシャリスト)ばかりになってしまい,世の中の大きな問題に対処できないため,専門バカとも言われ,ジェネラリストの育成や全人的人間への回帰の必要性なども叫ばれているが,系統樹のあり方から見てもあまり期待できず,さりとて,職能分野をどのようにネットワークさせれば,統合された答えを導きだすことができるのかも分からないというのが現実だろう。
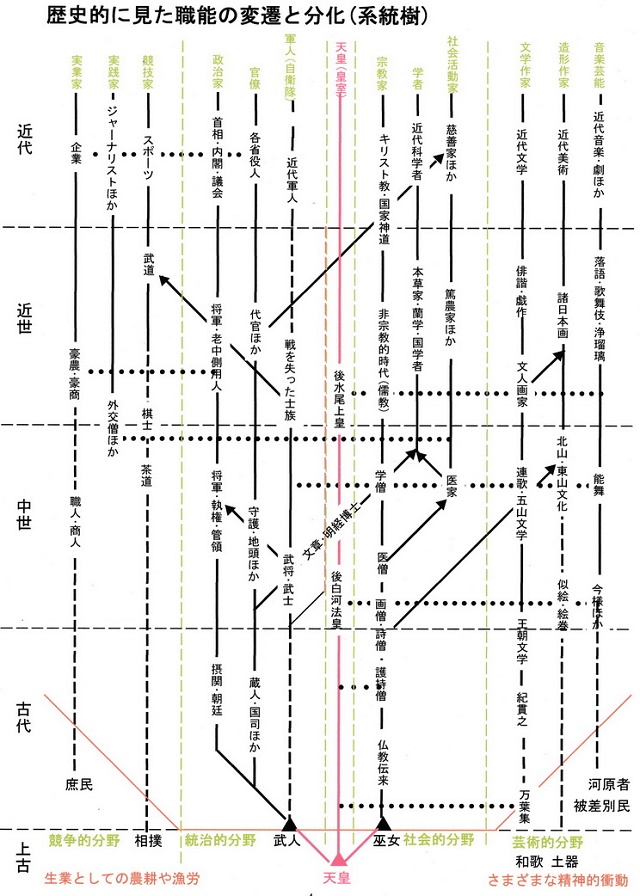
女性だけを対象に,第1話と同様,「はじめに」に示した時代区分と活動の分野型をクロスして,該当する人数を記入した表によって,分析してみよう。⇒PDFファイル「時代別分野型数(女性)」
その前に,そもそも,女性の全体の数・比率と,分野ごとのそれを確認しておくと,まず,一枚年譜の作成にあたっては,できる限り女性を取り上げるように努めたつもりであるが,データベース化した段階の総数3,635人に対して,531人,率にして14.1%にとどまっている。ちなみに,ほぼこの値と同じ7分の1という比率は,国勢調査などの調査に関わって有名な"嘘つき率"だあり,男子に偏った大学等で,教室での比率がこの値になると,女性が多くなったと感じるキーになるものなので,データベースとしては,ギリギリの数字にはなったとも言える。
女性の比率を分野型別にみると,定義上,女性が100%になる皇后型を含む皇室分野と,同じく陰の女性を含む特異分野は,また,一般の人の職能対象でもないので,除外すると,まず,支配に関わる活動で,完全なゼロの1-2:軍事分野のほかの1-1:政治分野,1-3:官僚分野もほとんどゼロに近く,女性首相の登場への期待が大きいのも当然だろう。
次に,社会のサポートに関わる活動をみると,2-1:社会分野は,総数112人で3分の1を占めて多く,そのなかでも,福祉型が60%と際立って多く,福祉はまさに女性によって支えられていることが明確になり,直接的に女性解放めざす解放型と,間接的に女性解放をめざす教育型のいずれもが43%台,看護師が支える医療型が30%強と多く,文化型でも,18%強と,平均の比率を上回っているが,殖産型だけは,ほとんどゼロである。2-2:宗教分野は,全体としては,13%弱と,平均の比率をわずかに下回るものの,新興宗教型とキリスト教型は,ともに数も,比率もほぼ3分の1と同じで多いのが目立つが,それに続く2-3:学問分野が,全体として3.5%しかいないことに驚く。もっとも開明的であるべき分野がもっとも差別的であることを如実に見せられているようで,九品塾の基本講義のデザイン論のところで指摘した科学至上主義の問題の証にもなっている。
いわゆる芸術に関わる活動に入ると,3-1:著述分野は,全体としても,4分の1近くと多く,とくに,随筆鑑賞型が半数を越え,詩歌型が36%近くと多いのは,一般の印象通りと思われる。3-2:造形分野は,全体として1割余りと少ないのが残念ではあるが,近代に登場してきた商品型で,27%余りいることに救われる。3-3:芸能分野に移ると,女性が当然のように多い芸人アイドル型があるものの数が少ないので無視して,全体で37%弱と著述分野より若干多くなり,とくに,歌謡型は54%余り,舞踊型がちょうど半数,数の多い演劇型でも,38%と,この分野全体の比率とほぼ同じになっている。このように,芸術に関わる活動においては女性が多く,いわゆる文化の歴史は,女性によってつくられていると言って過言ではなかろう。
つけたしのようになるが,競争にかかわる活動では,4-1:実践分野が全体で7%強,4-2:実業分野で6%強,4-3:競技分野でも9%強と少なく,最初の支配に関わる活動同様,社会への影響も大きいので,今後の活動に期待したい。
ようやく,時代別の分析に入るが,初めに,第1話と同様,表に記入されている数字は,当該時代に活動していた人物の数で,活動期間の長い人物は,前後複数の時代にも重複して数えられていることから,延べ人数になっていることを指摘しておきたい。そのため,右側最後に,実数と実数としての比率を示しておいたが,近代には,延べ人数の値がかなり大きくなったりするものの,その時代ごとの比率には大きな違いは無いので,傾向を分析する程度では全く問題は無いと思う。また,古代,中世,近世,近代に分けたそれぞれの時代について,実数での女性の割合を見てみておくと,古代が,220人中37人で16.8%,中世が,245人中22人で9.0%,近世が,692人中55人で7.9%であり,近代は今までのところで,2,478人中417人,古代と全く同じ比率の16.8%ということは,近代において女性が進出したということを前提とするならば,古代における女性の多さが明確になり,中世は戦の時代であった故,少ないのは当然としても,戦の無くなる近世の比率は古代の半分以下になっているのは,儒学による統治システム,はっきり言えば,論語によるものだろう。
活動の分野型でみると,まず,0:皇室分野は,古代においては,天皇型が14.5%,皇后型が39.5%と,皇室分野だけで,全体の6割近く,権威の頂点が,まず,アマテラスの末裔とされる女帝であり,一時的には,国家支配の権力を発揮する男性の天皇が出るものの,藤原氏の支配が始まると,権力を剥奪されてしまい,女性である皇后が大きな役割を発揮するようになったと言え,武家政権になる中世においても,皇后型の比率は37%余りと高い。近世には,徳川政権の支配で,ほとんどゼロになり,天皇の力が回復されたという近代に入っても,その数は無に等しく,この点からみても,古代と中世はつながるが,近世以降は全く別ということで,ある意味,西欧の近代化と軌を一にしているとも言えよう。
1-1:政治分野は,国家支配型は,鎌倉幕府創設期(Ⅱ-1-3)に,1人いるだけであるが,言うまでも無く,歴代最強の女性といわれる北条政子であるが,男尊女卑の歴史観のなかでは,陰謀にたけた悪女のように扱われ,源頼朝は止むを得ないとして,北条義時の陰になるような位置づけになっているのが残念であり,一枚年譜を冷静に見てもらえれば,武家政権の革命が定着する軸になったのは,政子その人であり,のちの徳川家康,明治維新の大久保利通に匹敵するような存在であった。そして,中世の最後,応仁の乱後の戦国時代(Ⅱ-3-3)に一人あげられる陰の女性型の人物もまた,すぐに分かる通り日野富子であり,政治から逃避してしまった夫の代役を務め,サブ型で国家支配型にあげられるような女性であったことから,徹底して男性の時代と見られる中世も,優れた女性が幕を開き,優れた女性によって,幕を閉じられたと言っても,過言ではないだろう。近代になって登場する党派活動型によって,女性がかなり進出したようにみえるが,比率をみれば話にならないほど少ないのは,現在なお問題になっている。
女性がゼロの軍事分野を飛ばして,1-3:官僚分野をみると,全体では政治分野と同程度の少なさであるが,古代において,宇佐八幡宮の神託の和気清麻呂が有名であるが,もともとは優秀な女官であった姉の和気広虫が派遣されるところを,その代役として派遣されたといい,持統天皇の信頼を得,再婚した藤原不比等の昇進を支援,夫没後も娘光明子の立后を実現した橘三千代,歌舞の才で采女として出仕し,廉謹貞潔で典侍まで出世し,日本史上,最も古く記録された女官飯高諸高など,男性に引けを取らない人物がいたのである。近世初めには,豊臣秀吉の正室で,実子を得ずも,秀吉の正式な代理人として扱われ,公武から慕われた北政所,徳川家康の側室ながら,才智にたけて,大奥を統制し,政治的にも家康・秀忠をサポートした阿茶局,徳川家光の乳母から,家康に直訴して家光の将軍継嗣に成功,大奥を牛耳り,無冠無位で参内するまでに至った春日局など,一義的には陰の女性ながら,サブ型に,総務秘書型を挙げなければならない女傑がいて,まさに,歴史を動かしていたこと指摘しておこう。
その官僚分野につながり,そのほとんどが近代に登場して爆発的に増加した2-1:社会分野は,前述したように,女性が多い分野であるが,女性全体のなかでも,2割以上を占めるように,近代社会は,まさに女性によって支えられているにもかかわらず,女性差別から抜け出せないでいるのは,なんとも情けない。端的に分かりやすい例で言えば,医療型で,医者という職能は,本来,人の命を助けることを目的としてきた神聖なものであったはずなのに,西欧近代の科学至上主義によって医学となり,患者は,その研究対象でしかなくなり,生身の人間として扱われなくなっていることは,多くの人が感じていることでもあろうが,その冷たさを救っているのが,ほとんどが女性の看護師であることもまた,多くの人が感じていることでもあろう。人数も多いので,当然に知っておいた方が良さそうな人物を,生年の早い順に挙げると,1:医療型では,兼山の娘で,失脚憤死した父の尊厳回復を胸に,遺族全員が幽閉されるなか耐え忍び,赦免後,医者として活動,生涯孤高で,谷秦山が"詩文小町の妙,経術大家の風"と激賞した野中婉,苦難の道を歩んで女医第一号となり,医者として成功するも,牧師と再婚し,北海道へ渡った荻野吟子,わが国最初の女医養成機関(現在問題抱える東京女子医大の前身)を創立,女性の教養と地位の向上につとめた吉岡弥生,日本の看護婦を先駆・代表する生涯を送り,世界初のナイチンゲール記章受章者にもなった萩原タケ,松沢病院を世界屈指のものにし,"松沢の母"と呼ばれる石橋ハヤ,2:福祉型では,<戊辰戦争><磐梯山噴火><日清戦争>と,ことあるごとに,孤児等の救済に努めた瓜生岩,知的障害があった長女を孤女学院に預けた縁で,石井亮一と再婚,以後,滝野川学園経営に生涯をかけた石井筆子,財閥の娘で外交官の妻だったが,<敗戦>後,混血戦争孤児のための施設を開設,救済に尽力した澤田美喜,3:教育型では,亀井門三女傑で,志士らと交流,維新後,頭山満が入塾し,塾生の多くが内乱に関与,まさに男まさりの高場乱,生涯女子教育に専念,画家としても一家を成し,独身を通した跡見花蹊,7つにして最初の派遣女子留学生,女子教育に目覚めて奔走し,女子英学塾(津田塾大学)を創設した津田梅子,婦人記者の先駆,夫と{婦人之友}発刊後,キリスト教に基く{自由学園}創設した羽仁もと子,日本初のOLとなった後,{ドレスメーカー女学院}を創設,服飾デザインの発展に生涯をかけた杉野芳子ほか,学校創設した人物は多数にのぼる。4:解放型は,まさに女性解放であって,廃娼運動に生涯,少額寄付の大衆参加策を次々と発案した一方,キリスト者として人生最後も全うした久布白落実,{青踏}発刊,女権宣言して端緒を開き,戦後,日本婦人団体連合会初代会長になった平塚らいてう,山川均の妻で,母性保護論争で論壇に登場,<敗戦>後,労働省の初代婦人少年局長になった山川菊栄,婦人参政権運動一筋に生き,戦後は理想選挙を唱えて参議院議員となり,圧倒的な支持を得た市川房枝,<大正デモクラシー>期に婦人セツルメント運動始め,<敗戦>後に{主婦連}創立,消費者運動の草分けになった奥むめおなど多数。2人しかいない5:殖産型は,夫と"いぶし飼い"創案し,夫没後,伝習所を開設した永井いと,<敗戦>による華族廃止で開拓農民となり,全国的活動と,対照的な前後半生を生きた徳川幹子,そして,6:文化型は,東京新宿{中村屋}の女主人で,夫とともに芸術家を支援し,<大正デモクラシー>を代表するサロンにした相馬黒光,劇作家として第一人者になると,{女人芸術}創刊して多くの女性を支えた長谷川時雨,戦前はタゴールの来日などに尽力,戦後は,日本人初のソ連入りなど,国際的に大活躍した高良とみ,夫と戦前からの映画の洋画輸入や戦後の邦画国際化に貢献,国立フィルムセンター設立にも尽力した川喜多かしこ,といったところか。
2-2:宗教分野をみると,中世後半に尼僧が,近世初期にはキリシタンがというように全く異なる宗教ながら,それぞれ,その時代の女性の14%前後の比率を占めていることが,この時代の女性がいかに苦難の状態にあったかを物語っているようだ。2-3:学問分野は,前述のように,露骨に女性差別の強いことから,11人しかいないが,それだからこそ,名を遺すに至った女性のレベルは高く,生年の古い順に,儒学者の妻で,越後高田藩主からの要請で,女訓書「唐錦」6部13巻を書き上げた大高坂維佐子,日本初の女性博士で,高女用教科書書くも文部省が黙殺,文化勲章推薦も前例無いと紫綬褒章に終わった保井コノ,帝国大学初の女子学生,日本初の女性理学士で,2人目の女性理学博士になった黒田チカ,女性の大学進学ができず,理研研究生となって,緑茶の研究で,わが国女性の農学博士第1号になった辻村みちよ,転変の後,俗事は夫に任せて自宅から一歩も出ずに研究,女性史学を確立した高群逸枝,それに,サブ型では,早くから栄養問題を啓蒙,<敗戦>後,基礎食品群を提唱,長寿社会化への道を開いた香川綾,第二次大戦下,キュリー夫人の指導で,フランスの博士号を取得,戦後も,フランスで研究活動した湯浅年子などである。
3-1:著述分野は,古代から近代に至るまで,その時代の女性全体の2~30%と,ほぼ同じ比率で登場しており,いかに日本文化のベースになっているかを示している。そのなかで,古代の藤原道長とその次のいわゆる王朝文化の時代(Ⅰ-3-1,2)と,近世の元禄時代から文化文政期(Ⅲ-2-3~Ⅲ-3-3)にかけてに限られて多く登場すること,近代の大正デモクラシー期(Ⅳ-2-2)以後爆発的に増えることから,人物について,ここでは省略するが,後述の「際立つ時代」「大正デモクラシー」のとろで,取り上げることになるだろう。3-2:造形分野については,あまり目立つ人物はいないが,商品型との関係で,後述の「デザイナ的人物」で触れられよう。3-3:芸能分野については,歌舞伎が,近世初めの有名な出雲阿国に始まるとされるも,風紀統制のためと,男性に限るものにされてしまい,結局,明治維新後の近代の演劇型で爆発的に登場,女性の自立において,大きな分野になったが,よく知られている人物も多いので,省略させてもらおう。
前述のように,4-1:実践分野,4-2:実業分野,4-3:競技分野においては,女性は極めて少ないが,その女性たちが,どんな人物であったかは,今後のためにも知っておいてもらいたいので,何人か紹介すると,没落武家の子三井高俊に嫁ぎ,商家として確立すべく家業差配し,息子らを訓育,高利が三井の祖になった三井殊法,三井の娘に生まれ,維新に際し婚家のために立ち上り,女性解放・教育にも尽力した広岡浅子,紡績工場設立し,嫁のウメとともに{大同毛織}の開祖とされる栗原イネ,婿養子の夫とともに{三省堂}を創業,大ヒットで成長するも,百科辞典で倒産した亀井万喜子,わが国女子体育界の先達井口阿くり,無敵の女流武芸者として名声を得,諸女子校で教授,薙刀術の世界をリードし続けた園部秀雄,体操教員検定に女性として初めて合格,体操選手の名門{藤村学園}を創り上げた藤村トヨ,{講談社}創立者野間清治の妻で,事業の半分を負担して"創業の母"と呼ばれ,子夫急逝で自ら社長になった野間左衛,"新しい女"の中でも際立って特異な人生を送り,"仏教界のスター"から,作家として華開くも早世した岡本かの子,夫の道楽をヒントに{吉本興業}を創設,関西芸能界を支配するに至った吉本せい,天才的スプリンターで,日本女子選手初の五輪メダリストとなるも,冷たい世論に,夭折した人見絹枝,美容学校設立を皮切りに,化粧品や美容器具の販売まで多角的な経営で,山野美容帝国をつくった山野愛子らである。
最期に,X:特異分野については,1:陰の女性型が,中世後半から近世にかけて圧倒的に多いことは前述したとおりであるが,近代に入ると,5:在外活動型が1:陰の女性型と同程度の比率になっているのは,開国によって,差別の国から逃避するという意味のあったことも忘れてはならない。
前項で述べたように,日本史上,芸術的活動の際立つ文化的な時代として有名なのは,古代における王朝文化と,近世における元禄文化であるが,まず,前者については,嵯峨天皇の弘仁文化の時代には,日本化が始まり,紀貫之の,後述する日本文化のデザインによって,平安時代の栄華を実現した藤原道長の庇護のもと,女流文学を主体とする王朝文化が開花するということになる。
嵯峨天皇(上皇)の弘仁文化の時代は,はじめにの時代区分では,Ⅰ-2-2②と③にあたり,まず,最澄,空海によって日本化された仏教が創始されたのを背景に,菅原清公という道真につながる学者家系が始まり,藤原緒嗣,冬嗣という藤原摂関家の礎が築かれ,現存アジア最古の法典「令義解」の編纂した清原夏野と,その法解釈が長く範とされた讃岐永直,日本最古の百科事典「秘府略」編など才能を発揮した滋野貞主,「続日本後紀」20巻完成させた春澄善縄という学者のような法務官僚が次々登場するなか,史上初めて画家として名の残る百済河成が登場する。
そして,紀貫之が,若くして「古今集」を編纂,その「仮名序」によって,近世まで続く和歌路線を敷いたばかりか,晩年,土佐守として現地赴任したのを契機に,有名な'男もすなる日記といふものを,女もしてみむとてするなり'の書き出しで始まる,初の仮名文学「土佐日記」を著して,まもなく没した,Ⅰ-2-3③の時代を経て,その刺激と対応するように,和歌から,女流文学が開花し始め,女流藤原道長の栄華が齎した王朝女流文化が頂点に達する時代,Ⅰ-3-1③に入るが,この時代前後は,現代も超人気の陰陽師安倍晴明,日本初の往生伝「日本往生極楽記」を著して浄土思想を普及させた慶滋保胤と,「往生要集」を撰述し,公家社会に対応する地獄極楽イメージ鮮明な仏教を創始した源信,学者輩出する大江家の中興の祖となった大江匡衡とその妻で「栄花物語」の作者にも擬せられる赤染衛門,道長の妨害にも屈しなかった硬骨漢で,上下,女性からも信頼された藤原実資,マルチタレントな文人藤原公任,上下各層から愛され独自の書を確立した藤原行成,摂関家内の争いに敗れるも最後まで堂々と生きた藤原隆家といった,かなりの男性人物も輩出する。
王朝文化を現出した人物について,女性に限って,生年順に示してみると,"理想の女房"といわれ,優れた作品を遺し,「伊勢集」は女流私家集・日記文学の嗜矢となった伊勢,その娘で,幼い頃から80歳近くで没するまで,様々な人たちとの贈答歌を中心に,創作し続けた中務,王朝女流文学の嚆矢「蜻蛉日記」の著者として知られる藤原道綱母,大江匡衡の妻としても大きな役割を果たし,「栄花物語」の作者にも擬せられる赤染衛門,そして,言わずと知れた,「枕草子」の著者として,日本の随筆文化の祖となった清少納言と,世界の長編小説を先駆ける傑作「源氏物語」を書いた紫式部という頂点を迎えるのと対応するかのように,道長の娘,上東門院彰子が,王朝女流文化のパトロネージュとなり,摂関家栄華の極から衰退まで,長い人生を送ることになり,'古の奈良の都の八重桜けふ九重に匂ひぬるかな'でたちまち歌才が知れわたった伊勢大輔,宮中の指導的歌人になった相模,紫式部の娘で,高齢になっても宮廷の歌合せの主役を務め,子為家の代詠もした大弐三位,孤独な晩年に,人生回想の「更級日記」を著し,「夜半の寝覚」ほかの物語作者とも伝えられる菅原孝標女まで,錚錚たる人物が輩出するのである。
もう一つの際立つ時代は,近世の元禄文化とされるが,それによって大衆文化への幕が切られたということであって,吉宗の娯楽政策によって,大衆,とくに女性が,文化消費者から自立へと向かい,天明文化と,それに続く,化政文化に至るのである。
まず,特異な将軍徳川綱吉のもと開花した元禄文化は,時代区分でも,そのまま綱吉時代のⅢ-2-3にあたるが,視覚障害者教育のパイオニア杉山和一,吉川神道を開いた吉川惟足,「北野天神縁起絵巻」などを多くの傑作遺した土佐光起,東西廻り航路開拓した河村瑞賢,栄利求めず塾で教育に努め新井白石ら逸材を輩出した木下順庵,呉服店開き財閥三井家の家祖となった三井高利,古義学を創始した伊藤仁斎,"水戸黄門"徳川光圀,「養生訓」ほかの貝原益軒,江戸浮世絵の実質的な開祖菱川師宣,各地に木彫仏像残した円空,貞享暦を完成し天文方世襲の祖渋川春海,天才的和算家関孝和と業績を体系化して以後の発展を基礎づけた建部賢弘,万葉仮名表記の発見など天才的業績の契沖,近代小説を準備した天才作家井原西鶴,上方落語の開祖露五郎兵衛と"江戸落語の祖"鹿野武左衛門,天才俳人松尾芭蕉,鎖国下で合理的認識を先駆,日本で初めて世界地誌を著した西川如見,天才脚本家近松門左衛門を起用し義太夫節で近世浄瑠璃を確立した竹本義太夫,"光琳模様"の尾形光琳と兄を支えた陶芸家乾山,歌舞伎を創出し最高役者の祖市川団十郎(初代),そして,デザインの哲学的根拠をも開いた天才的思想家荻生徂徠と,これだけ天才が集中的に輩出するのは,世界的みても稀有であろう。
そして,吉宗による庶民を大事にする政策の時代(Ⅲ-3-1②)を受け継ぐかのように,現在もなお毀誉褒貶は多いが,田沼意次が齎した自由経済によって,天明文化が開花(Ⅲ-3-2),すべてからの自由を求めて京の若者に多大の影響を与えた売茶翁こと高遊外,その後に輩出する文人の先駆服部南郭や多才な風流人で南画の先駆柳沢淇園,独自の公案体系確立し,臨済宗中興の祖となった白隠慧鶴,国学を深めた賀茂真淵とそれを受けて現代にも影響及ぼす復古思想の完成者本居宣長,その宣長との論争に敗れるも傑作遺した上田秋成,甘藷研究を認められて幕府に出仕し蘭学の祖になった青木昆陽,日本初の医学的解剖を行い実証的医学開いた山脇東洋,今や江戸期の画家で人気トップの伊藤若冲に鬼才の絵師曾我蕭白,妻玉瀾とともに画業に没頭した池大雅,俳諧・南画ともに超一流の与謝蕪村,写実様式を確立した円山応挙,浮世絵の飛躍的発展させた鈴木春信に美人画最高峰の鳥居清長,一流の浮世絵師で人気トップの戯作者山東京伝,日本初の経緯度入り全図を作成出版し農民出身では異例の侍講になった長久保赤水,"川柳の祖"柄井川柳,自由奔放な新しい感覚の鬼才で,各分野で時代を先駆した建部綾足に天才的マルチ人間平賀源内,弄石ブームを起し近代考古学を先駆した木内石亭,偉大な植物学者小野蘭山,実証主義者らのサロンの主木村蒹葭堂,私学{懐徳堂}の黄金期形成した中井竹山,歌舞伎を門閥にとらわれない合理的な興行制度にした金井三笑,名所図会のジャンルの嚆矢秋里籬島,「近世畸人伝」の伴蒿蹊,天文方の主流を形成する多くの俊秀育てた麻田剛立,西洋思想の導入につとめた司馬江漢,日本人離れをした大哲学を構築した三浦梅園,驚くべき自由経済思想「夢の代」を著す山片蟠桃,天明文壇を主導した大田南畝,天才的出版業者蔦屋重三郎,「解体新書」の登場に関わった中川淳庵,前野良沢,吉雄耕牛,杉田玄白。塙保己一の大事業もこの時代に着手されているといったように,元禄文化に勝るとも劣らない時代が現出するのである。
その田沼意次が失脚させられ,松平定信による寛政の改革によって,自由な文化が抑圧され,喜多川歌麿らの悲劇はあるものの,大衆の欲望は止まらず,文化文政時代の,いわゆる化政文化に続いていくのである。
そこで,王朝文化と同じように,天明文化を現出した女性に限って,生年順に拾ってみると,5歳時の俳句で世人驚かし,夫と北村季吟らに学んで創作続け,夫死去後は,尼僧としても存在感を示した田捨女,文武をかねそなえた上,文芸の才が愛され諸侯が招聘した井上通女,儒学者の妻で,越後高田藩主からの要請で,女訓書「唐錦」6部13巻を書き上げた大高坂維佐子,そして,理知的で平俗な作風で名声を得,人柄を端的に示す句'朝顔に釣瓶とられてもらひ水'を遺し,現在も良く知られる加賀千代(女)の後は,漢詩・連歌にすぐれ,歴史物語・紀行文など集中的に著作するも,本居宣長の批判に激昂し激減した荒木田麗(女),生涯に8冊という当時としては驚異的な数の句集・撰集を残した榎本星布尼,琴士として栄誉をきわめ,当時の女性として比類のない旅行家で,華やかで多彩な一生を送った田上菊舎(尼),幕末に際立って開明的な「独考」を著し,厳しい批判受け絶交された滝沢馬琴により名が遺った只野真葛,夫死後の家業と育児による心労を脱すべく,俳句を始めて一流にまでなり,多くの俳友と交流した市原多代女,若くして「伊勢物語」の語句,古今・後撰・拾遺の詠風を蒐集分類編纂し,最晩年に藩主の命で「歌集」を遺した岩上登波子,農民ながら,貴族から歌才を愛でられて交流,"伊豆の袖子"として"加賀の千代"と並称された菊池袖子,蘭斎の長女で,頼山陽と結婚できず,一生独身も,一流の才能を発揮して全国に知られた江馬細香,同じく,頼山陽との交際で知られ,生涯嫁がず,絵筆一本で家族を養い,自由人としての生き方を全うした平田玉薀から, 化政文化の,幕末の動乱期に,生涯の大半を遊歴の中に過ごし,女流三傑の一人と謳われた原采蘋,幕末に,女性ながら評判の儒者となり,維新後も,衰えるところがなかった篠田雲鳳と,そのまま維新に突入していくのである。
現在の我々に直接つながる近代において,維新後,西洋文明を吸収し,日清・日露戦争を経て,いわゆる列強の仲間入りをするまで成長,そして,明治天皇の死によって重しのとれたところに,一方では国粋主義が進んで思想的弾圧が始まるものの,第一次世界大戦によるバブルと吉野作造らによる民本主義が浸透で,国民の意識が一気に自由化する。そして,この時代を象徴するように,初めての庶民首相原敬が登場するも暗殺されてしまう時点を境に,冒頭の方で記したように,民の方で登場する人物が飛躍的に増大する。念のために,その時期(Ⅳ-2-2③)に登場あるいは活躍のピークを迎えた人物を絞ってみると,表のように619人に上り,総数3635人の6分の1(17.0%)にもなり,女性の数は119人で総数531人の22.4%とさらに多くなる。ところが,知られているように,この後,満州事変が起こって,いわゆる15年戦争期に入り,戦局が進むに連れ,多くが苦難の道を迎える状況になるのである。そういった意味も含めて,参考になる人物は多いと思われるので,表から適宜拾って,一枚年譜を参照して貰いたい。⇒EXEL「大正デモクラシー登場」
念のため,0:天皇型から1-3:1-3:官僚分野までの88人,2-2:宗教分野の13人,X:特異分野49人を別にし,男女あわせた数で確認してみると(カッコ内は,総数と比率),2-1:社会分野は,全体で,75(338,22.1%)と。5分の1あまりがこの時期に登場,うち,1:医療型が,6(59,10.2%),2:福祉型が,3(35, 8.6%),3:教育型が,11(69,15.9%),4:解放型が,36(71,50.7%),5:殖産型が,5(50,10.0%),6:文化型が,14(54,25.9%)というように,なかでも,4:解放型が際立って多いが,LGBTはじめ,現在もあらゆる差別からの解放の動きは強い。2-3:学問分野は全体として,58(314,18.5%)で,1:数理天文型が,1(33, 3.0%),2:自然科学型が,12(69,17.4%),3:人文科学型が,17(62,27.4%),4:社会科学型が,18(49,36.7%),5:文学言語型が,6(49,12.2%),6:蒐集編纂型が,4(52, 7.7%)となり,3:人文科学型,4:社会科学型と多くなっているのは当然として,1:数理天文型と6:蒐集編纂型が非常に少ないのは,こういった時代には,籠って研究するようなオタク的人物は向いていないということなのだろう。
3-1:著述分野は全体として,103(480,21.5%)と,この時期に登場したものが5分の1強と平均を上回っているが,1:詩歌型が,32(162,19.8%),2:小説型が,48(170,28.2%),3:脚本型が,6(27,22.2%),4:随筆鑑賞型が,0(18, 0.0%),5:批評解説型が,12(65,18.4%),6:哲学思想型が,5(38,13.1%)となっていて,4:随筆鑑賞型は,サブ型に回っているため0で,自己主張の強い2:小説型の伸びが著しいのは当然としても,6:哲学思想型がかなり少ないのが気になるところであり,前項の学問分野同様,じっくり考えるような人物には向かない時代であったといえ,現代にも続いているのが気になるところである。3-2:造形分野は全体としても,77(277,28.5%)と飛躍するなかで,1:平面型が,40(153,26.1%),2:立体型が,5(28,17.9%),3:空間型が,15(32,46.9%),4:商品型が,4(22,18.2%),5:ストーリー型が, 1(9,11.1%),6:シーン型が,12(33,36,4%)となっていて,3:空間型が際立って多いのは,その大半を占める建築家が,現代も同様,人気の職業だったことを示し,6:シーン型が多いのは,この時期映画が一気に盛んになったことを,5:ストーリー型が少ないのは,大半を占める漫画家が輩出するのは戦後になってからということを示す。3-3:芸能分野は全体として,57(222,25.7%)で,1:楽曲型が,9(43,20.9%),2:歌謡型が,10(33,30,3%),3:口演型が,9(27,33.3%),4:舞踊型が,5(28,17.9%),5:演劇型が,23(84,27.4%),6:芸人アイドル型が1(7,14.3%)と,個々の内容は変化しても,この時期により多く登場しているものが多い。
4-1:実践分野も全体として,40(188,21.3%)と多くはなるものの,1:発明技術型が,6(42,14.3%),2:伝承技能型は,0(0,0.0%),3:コンサル仕掛型が,5(29,17.2%),4:本業超越型が8(33,24.2%),5:ジャーナリスト型が,15(47,31.9%),6:奔放夢想型が,6(24,25.0%)となっていて,2:伝承技能型が無いのは当然かもしれないが,5:ジャーナリスト型,6:奔放夢想型,4:本業超越型はやや多いのに,3:コンサル仕掛型,1:発明技術型など,広く皆のためになるものへの取り組みが少ないのも,現在に続く自己中心的になった時代の表れのように見える。4-2:実業分野は全体として,24(224,10.7%)と,すでに多くの企業等が活動している段階で,会社員も多くなった国民の状況を反映して,全体的には少ないが,1:豪商財閥型が,3(61,4.9%),2:国土開発型 が,9(33,27,3%),3:農水食品型が,3(15,20.0%),4:製品生産型が,7(41,17.1%),5:販売サービス型が,2(28,7.1%),6:メディア娯楽型は,16(46,34.8%)と,とくに多く,戦後に拡がっているメディア娯楽型のものの大部分がこの時期に起こっていることを示し,2:国土開発型がやや多いのも,国民の移動に関わる鉄道関係が多いことによる。最後に,4-3:競技分野は全体として,19(109,17.4%)少な目なのは,1:棋士型が,2(14,14.3%),2:武道型が,3(23,13.0%),3:スポーツ型が,8(27,29.6%),4:探検紀行型が,3(22,13.6%),5:競技振興型が,3(10,30.0%),6:茶道鑑識型が0(13,0.0%)と,3:スポーツ型と5:競技振興型が,ともに3割とやや多いことは,この時期にスポーツが盛んになり始めて,戦後に盛んになっていくことを示すのと対照的に,それ以外の項目は少なく,もはや,廃れてきたことを反映して,この時期が,まさに,時代の大きな転換点になっていると言って良いだろう。それでも,4:探検紀行型が少なめなのは,挑戦的精神の衰えを示しているようで気になるところである。
以上のような状況を踏まえた上で,大正デモクラシー期に登場した注目すべき女性を,分野型別に拾ってみると,まず,2-1社会分野の3:教育型で,早くから栄養問題を啓蒙,<敗戦>後,基礎食品群を提唱,長寿社会化への道を開いた香川綾,日本初のOLとなった後,{ドレスメーカー女学院}を創設,服飾デザインの発展に生涯をかけた杉野芳子,新渡戸稲造の要請で東京女子大学創立責任者,学長になると,左翼学生を弾圧から守った安井てつがいるが,4:解放型は,まさに女性解放運動の盛り上がりを反映するように,婦人参政権運動一筋に生き,戦後は理想選挙を唱えて参議院議員となり,圧倒的な支持を得た市川房枝,大杉栄とともに虐殺される短い生涯に,3度結婚し7人の子,多くの評論・翻訳を残した伊藤野枝,<大正デモクラシー>期に婦人セツルメント運動始め,<敗戦>後に{主婦連}創立,消費者運動の草分けになった奥むめお,"新しい女"を代表するような苦闘の人生を送った尾竹紅吉,四角恋愛で<大杉栄傷害事件>を起こすも,文筆を主に女性解放・人権擁護活動に生涯をかけた神近市子,{文化学院}創立し,{読売新聞}の身上相談欄を長く担当,<敗戦>後も多方面に活躍した河崎なつ,廃娼運動に生涯,少額寄付の大衆参加策を次々と発案した一方,キリスト者として人生最後も全うした久布白落実,{青踏}発刊,女権宣言して端緒を開き,戦後,日本婦人団体連合会初代会長になった平塚らいてう,山川均の妻で,母性保護論争で論壇に登場,<敗戦>後,労働省の初代婦人少年局長になった山川菊栄と,数も多く,知名度も高い人物がおり,6:文化型では,戦前はタゴールの来日などに尽力,戦後は,日本人初のソ連入りなど,国際的に大活躍した高良とみに,日本女子大学長への道を歩む間,国際的な平和活動を推進し続けた上代タノと,ともに,戦後の日本で大きな役割。女性蔑視の強い2-3:学問分野でも,帝国大学初の女子学生,日本初の女性理学士で,2人目の女性理学博士になった黒田チカ,女性の大学進学ができず,理研研究生となって,緑茶の研究で,わが国女性の農学博士第1号になった辻村みちよ,詩人として登場,転変の後,俗事は夫に任せて自宅から一歩も出ずに研究,女性史学を確立した高群逸枝がいる。
3-1:著述分野に入ると,1:詩歌型には,文壇の花ともてはやされるも,独自の歌境開き,女流歌人の第一人者と称された今井邦子,西条八十から絶賛されて次々創作するも,夫の反対で絶筆,離婚し自殺した金子みすゞ,虚子のとなえる客観写生を超越,名声が全国に響くも,言動激しく除名絶縁され,孤独になった杉田久女,夫の死後,奔放な生き方をし,戦前はムッソリーニと握手,戦後はベトナム救援運動の先頭にたった深尾須磨子,妾腹ながら叔母が大正天皇の母という家柄に生まれ,その拘束から脱した情熱的人生を歌に詠んだ柳原白蓮が,2:小説型には,100歳に近い生涯,男性遍歴を重ねながら小説を創作し続けるとともに,和服デザイナとしても活躍した宇野千代,作品発表して女子大中退に追い込まれ,結婚を家族に反対されて精神を病み,死の直前に脚光を浴びた尾崎翠,若くして登場,晩年に,被差別部落扱う「橋のない川」を書き続けて決定的評価になった住井すゑ,「海神丸」で登場し,精緻な観察眼とみずみずしい精神保ち,100歳で没するまで傑作を書き続けた野上弥生子,戦前にプロレタリア作家として確立,戦時の苦難乗り越え,一貫して反逆的個性を発揮し続けた平林たい子,女性の自立扱う名作「伸子」書き,{共産党}の宮本顕治と結婚,獄中の夫を支えながら創作続け,早世した宮本百合子と,いわゆるビッグネームが多い。そして,3-2:造形分野の4:商品型には,総合美容先駆し繁昌するとともに,啓蒙活動を行った遠藤波津子と,丸ビルに美容院開業し,初のマネキンクラブなど,美容界向上発展に貢献した山野千枝子がいる。3-3:芸能分野では,7人と多い2:歌謡型には,名をあげるほどの人物はいないが,4:舞踊型には,石井漠の義妹として舞台で活躍,創作舞踊で高い評価,舞踊研究所を設立して,多くのダンサーを育成した石井小浪,高田舞踊研究所創設し,夫没後も俊秀育成,モダンダンス界に大きな足跡を残した高田せい子,苦闘の末,装束無しの「安宅」が話題で,観世流シテ方初の女性師範も,なお苦闘の生涯を送った津村紀美子,新舞踊運動の先頭に立ち,藤蔭流を興して多くの人材を輩出,日本舞踊家の地位を確立した藤蔭静樹がおり,14人もいる5:演劇型には,日本映画界の草分け女優の一人となって,蒲田映画の初期黄金時代を築いた川田芳子,夫と{築地座}創設,夫の戦死で隠遁,12年ぶりに復帰の{文学座}最初の大女優になるも,突然退場した田村秋子,貿易商と結婚,モスクワで演劇に開眼,翻訳劇の貴婦人を当り役に{俳優座}の精神的支柱となった東山千栄子,帝劇案内嬢から,松井須磨子を見て女優を夢み,どんな役も引受け,"新国劇の母"に至った久松喜世子,真摯に"新しい女"を生きて新劇女優となり,一世を風靡,共に夢を求めた島村抱月の後を追って自殺した松井須磨子,子役から芸術座経て新派に移り,没するまで若さと美しさ保ち,"八重子十種"の名演を遺した水谷八重子,若くして新劇舞台の名女優となり,<敗戦>後,当り役「夕鶴」のおつうで,上演1000回の記録した山本安英と,ビッグネームも多い。
4-1:実践分野では,5:ジャーナリスト型に,戦時下に{生活と趣味之会}を運営するなど,女性に生活経済情報を提供し続けた大田菊子の一方で,男子と対等に闘おうと挑戦,自ら操縦して訪欧飛行すべく決行準備中に病没した北村兼子,草創期の婦人紙誌で啓蒙活動,飛躍をめざして留学するも,早世した小橋三四子と,絵にかいたような挑戦と挫折の2人が。4-2:実業分野でも,6:メディア娯楽型に,{講談社}創立者野間清治の妻で,事業の半分を負担して"創業の母"と呼ばれ,子夫急逝で自ら社長になった野間左衛と,夫の道楽をヒントに{吉本興業}を創設,関西芸能界を支配するに至った吉本せいがおり,X:特異分野の5:在外活動型には,性の遍歴の末,ソ連に逃亡,<敗戦>後も現地に留まり,演劇を学び直して演出家としても成功した岡田嘉子,アメリカで子育て,夫急逝で帰国するも,娘のため再渡米,日本人初の米国ベストセラー作家になった杉本鉞子,渡米留学して卒業後,偶然ボストン美術館東洋部に招かれ,美術品を整理・考証した平野千恵子,「蝶々夫人」を当り役に国際的に活躍し,日本のオペラ歌手の可能性を内外に強く印象づけた三浦環がいる。
。
日本史話三講の第Ⅱ講:時代循環のパターンで示しているように,現代は,近代の末期(Ⅳ-3-3③)で,古代末の院政期(Ⅰ-3-3③),中世末の戦国時代(Ⅱ-3-3③),近世末期の文化文政時代(Ⅲ-3-3②③)に対応するが,まずもって,院政期は,その語が示すように,国家中枢権力が不明になったばかりか,上皇らが,もっぱら内輪のことにしか関心を抱かず,貴族らも遊びに夢中で地方の民を顧みず,時を並行して,奥州藤原氏という,別の政権が存在しこと,戦国時代もまたその語の示すとおり,国家の中枢権力たる将軍の力が無いどころか,足利義政のように政治から逃避してしまい,いわゆる下克上の無秩序な時代で,庶民はそれに翻弄され,落ち着いて何かをすることができなかったこと,そして,近世末期の文化文政時代は,その時代の前から後まで,実に55年間,将軍の座にあった徳川家斉は,良く知られているように,大奥入り浸りで,政治のことは無関心,それを受けるように,江戸の町民も,遊び惚けるだけで地方の農民たちを顧みないという,権力の空白が無秩序な世界をつくっているという点で共通しているが,そういった時代で,どのような分野型に,際立った人物が出ているかを見れば,何を目指せば良いか参考になるだろう。
院政期が始まるのは,特異な独裁者的天皇で,藤原摂関家衰退の間隙をついた白河天皇により,上皇となって,天皇を超える権力を発揮するのであるが,内裏に代わる政治の場仙洞御所を守る北門の武士として社会に出た西行が,突然遁世して世間を驚かせ,漂泊しながら名声欲も保ち,その生き方は,後世に多大な影響を及ぼすことになったことから,まさに,遁世者の象徴,X:特異分野の3:脱社会型の先駆者である。また,大僧正に登りつめる一方,絵巻物「鳥獣人物戯画」の作者に擬せられる鳥羽僧正こと覚猷は,院政期の終りとともに登場し,保元の乱によって,中世に入るなか,絵巻物文化を開花させた後白河法皇につながるとともに,現代,世界を席巻している,日本のアニメ漫画の始祖,つまり3-2:造形分野の5:ストーリー型に入る人物であると言えよう。そして,それまでの時代つくってきた公家社会を壊す役割を担うことになる公家,"日本一の大学生"の才能で,伝統社会に反逆,<保元の乱>を余儀なくされ,敗死した藤原頼長,法体で鳥羽院近臣トップとなり,院死後,<保元の乱>で勝利も<平治の乱>で敗れ自殺した藤原通憲と,次の時代,つまり武家政権への道を開く,源平の武士軍団を確立していく,後三年合戦鎮圧も恩賞なく,私財提供で武士の鑑となり,のち,武家として初の院昇殿になった源義家(八幡太郎),父正盛同様,日宋貿易による財力で,白河院の寵を得,武家初の内昇殿,平氏の地位を高めた平忠盛が重要で,古代から中世への転換を象徴,その在り方が後世へ多大の影響を与えた文人学者政治家の大江匡房,優れた学者として変革期の権力者たちに信頼され,菅原道真以来,儒学者で唯一人没後神になった清原頼業も注目される。
多くの武将が名が知られるが,戦でなくても,現実の世の中は戦争のようなものとの観点から,さまざまな形で取り上げられているので省略するが,そもそも,戦国時代の始まり<応仁の乱>が起きるのは,室町幕府8代将軍足利義政が,政治力を欠いて逃避してしまったことによるのであり,義政自身,まさに,X:特異分野の3:脱社会型の人物であったといえるが,それまで禅僧の世界であった作庭について,義政が自らの隠遁の地を整備すべく,75歳過ぎに相国寺の作庭で登場した善阿弥を起用,のちの造園家の始まりになったことや,ユニークな生涯で"風狂"と"頓智小僧"のイメージが定着している臨済僧一休宗純,そして,日本独自の漂白の詩人として連歌を代表し,和歌の西行と俳諧の芭蕉を繋ぐ役割を担う飯尾宗祇ら,X:特異分野の3:脱社会型の典型になる人物たちによって,東山文化が花咲く。
とくに,日本中世における水墨画の大成者で,画家として個人名が出る先駆けとなった雪舟等楊,室町期最高の大和絵作家で,土佐派を中興し,「清水寺縁起絵巻」ほか肖像画など傑作を遺した土佐光信,そして,武家出仕唯一の(画僧で無い)俗人絵師。若くして雪舟が認める才を示し,狩野派の祖になった狩野正信と,新障壁画様式確立して,狩野派の発展の基礎をつくり,後世,神格化された狩野元信と,錚錚たる画家,つまり3-2:造形分野の1:平面型が登場,近世に花開く絵画の世界を準備したこと,"佗数奇"を深化し,書院茶の湯を仏寺の方丈の理念に叶う四畳半茶の湯にした村田珠光と,それを大成し,千利休ら堺商人へ伝え"堺流茶の湯開祖"となるも,早世した武野紹鴎による4-3:競技分野の6:茶道鑑識型の始まりが重要であるが,作品に感銘した斎藤妙椿が城の包囲を解き,伝来の古今集を宗祇に講義し"古今伝授の祖"になった東常縁,伊勢流武家故実の大成,つまり蒐集編纂型の,室町幕府政所執事伊勢貞宗,中国から金元時代に興った李朱医学を初めて日本に導入し,近世医学興隆の祖になった田代三喜,神儒仏混合の唯一神道を創始,地方の神社に神位,神職に位階を授与する制度を創設した吉田兼倶など,近世をの文化をデザインする人物が目白押しに登場,さらに,古代末と同様,関白まで務めて政界を引退後,大学者として,公武合体の文化のブレーンの役割をした一条兼良と,応仁の乱期も京都に留まり,生活に窮しながらも,公武合体の象徴として尊敬され続けた三条西実隆という大学者の存在,今川氏の外交官として諸国を巡遊,宗祇・肖柏と連歌史代表する「水無瀬三吟」「湯山三吟」を遺した柴屋軒宗長と,朝廷財政逼迫のため武将間を奔走,貴族社会を詳細に示す日記「言継卿記」を遺した山科言継も見逃せない存在である。
化政期は,時代区分では,Ⅲ-3-3②③に対応し,際立つ時代にところで述べた天明文化の主役をつとめた錚々たる天才作家たちのなかには,伊藤若冲や大田南畝など,松平定信による寛政の改革(Ⅲ-3-3①)という衝撃を超えて,この時代にもなお,活躍している人物もかなりいるが,活動や業績の主たる時代が,この期にある人物について,拾うことにする。
まず,あげられるべき人物は,商人・名主として実績を挙げた後,50過ぎに天文・測量を学んで,初めて詳細な日本地図を作成した伊能忠敬と,盲目ながら,「群書類従」編纂刊行の大事業を成し遂げ,堅実な考証で近代史学を先駆した塙保己一という,2人の巨人を代表に,日本文学史を先駆する「国文世々の跡」や,現代も読まれる「近世畸人伝」などを著した伴蒿蹊,長命であった小野蘭山が幕府に採用されて,江戸時代最大の博物誌「本草綱目啓蒙」を刊行し,本居宣長が30余年かけた「古事記伝」で国学を完成,宝暦事件に連座して長期に逼塞の間,平安内裏の考証に没頭した裏松光世が,復古図ろうとする光格天皇に認められて,一躍時の人になったほか,20年かけ,彩色した本格的な日本初の植物図鑑「本草図譜」96巻92冊を著し,借金までして出版した岩崎灌園,今日なお批判に耐える金石文・古泉学の基礎を築いた狩谷掖斎,初期に優れた地方書「地方凡例録」を著した庄屋の大石久敬,神田の名主斎藤幸雄は,「江戸名所図会」発案して出版計画の許可得たところで急逝(のち,子が継ぎ,孫が完成),豪商鈴木牧之が,民俗資料としても貴重な「北越雪譜」出版に生涯をかけた,あるいは,当代随一の古銭研究家になった福知山藩主朽木昌綱,幕閣を務め,文化事業にも熱心で,自ら動物図鑑を編纂した藩主堀田正敦,藩政マニュアル「創垂可継」以降,多くの書物を編集・著作した黒羽藩主大関増業,雪の結晶の観察記録「雪華図説」と<大塩平八郎の乱>の鎮定で名を残した古河藩主土井利位と,続々出てくる学者大名,500余人の歴史人物を描いた「前賢故実」を出版し,近代歴史画隆盛に先鞭をつけた菊池容斎のように,いわゆる専門家でない人物のなかにも,蒐集編纂をしようとするものが多く,まさに,2-3:学問分野の6:蒐集編纂型の時代であったといえる。
また,東日本各地を旅して回り,当時の民俗を知る上で貴重な彩色絵紀行文を多数まとめた,ある意味で蒐集編纂型の「遊覧記」を遺した菅江真澄は,X:特異分野の2:記録伝承型の人物になっているが,サブ型に示すように,脱社会型の人物でもあり,庵に住んで農民や子どもと交流,最晩年に貞信尼と出会って,大らかな書歌を遺した,この時代を代表する僧良寛と,致仕して自由の境涯を歩み,一揆発生に革新的な藩政改革建言するも受け入れられず,致仕して自由の境涯を歩み,巨匠になった田能村竹田,趣味に溺れて罷免された後,自由人として,天真爛漫奔放な傑作を次々と描いた浦上玉堂は,まさに,脱社会型の典型であったし,庶民教化に尽くし,隠棲後も敬慕を受け,絵は独自の"厓画無法"の境地に達した仙厓義梵,「雨月物語」後の苦難と本居宣長との論争を経て,漂白の生活に入り,孤独のうちに「春雨物語」を遺した上田秋成,苦渋に満ちた過酷な生涯のなか,弱者へのいたわりと童心を保って,人生詩の傑作を遺した俳人小林一茶も,自ら望んだ訳ではないが,脱社会型でもあったといえよう。異学の禁で仕官の道絶たれ,世の無用者を自認して詩酒に沈湎しながら,大立者として聳立した亀田鵬斎,同じく,<寛政の改革>閉門を契機に,書の"千蔭流"創始,国学研究も深めて江戸派重鎮になった加藤千蔭,民政重視の藩政,病気で致仕後学問に専念,高齢になって名随筆「甲子夜話」を書き続けた松浦静山,詩文・書画を愛し,各地を遊歴するなか著した「日本外史」が幕末志士に大きな影響を与えた頼山陽も,見方を変えれば,脱社会型の人物で,さらに,すでに述べてきた,将軍徳川家斉,女流画家平田玉薀,女流漢詩人原采蘋も加えれば,まさに,X:特異分野の3:脱社会型の時代でもあった。
また,天明文化期に,日本初の銅版画に成功,「世界図」を制作し,その後も西洋思想の導入につとめ,奇行も多かった司馬江漢を受け継ぐように,西洋科学踏まえた重商主義的貿易論で門弟を多数養成した本多利明,全国数十藩の財政再建し,驚くべき自由経済思想の「夢の代」著した山片蟠桃,「稽古談」ほか多くの著作講義で,画期的な重商主義論を展開した海保青陵,富国強兵の絶対主義的国家構想の書を次々発表した佐藤信淵,自然科学史の画期「窮理通」を著した帆足万里ら,まさに近代を準備する経世家と呼ばれる人物,3-1:著述分野の5:批評解説型,6:哲学思想型,あるいは4-1:実践分野の3:コンサル仕掛型,さらには,2-1:社会分野の3:教育型にも対応する一言ではくくれない人物が集中的に輩出したこと,さらに,新式の帆や運送船を開発,築港にも従事して海運の振興に貢献した工楽松右衛門,独創に富み,次々と発明して人々を驚嘆させた鉄砲鍛冶国友藤兵衛,実業にも役立つ多くの機械や装置を開発した久米通賢,幼時より次々と発明,世界に優る万年時計に至り,{東芝}の祖になった田中久重など,4-1:実践分野の1:発明技術型も錚々たる人物を輩出,そのほか,オランダ内科医書翻訳の嚆矢「西説内科撰要」を出版,研究の普及発展を促進する記念碑になった宇田川玄随,オランダ語翻訳に専念,現行の天文物理用語,文法から,"鎖国"など一般語彙まで創出した志筑忠雄,「気海観欄」を著し,物理学の紹介者として不朽の名を残した青地林宗,内服全身麻酔剤を案出し,世界に先駆けて全身麻酔手術に成功,華岡流外科創始者となった華岡青洲,あるいは,蔵書を拠出し私財を投じて,日本初の公開図書館開設し,将来にわたる安定的運営を図った青柳文蔵,自邸{山本読書室}に多くの門人を迎え,知識の解放による社会変革めざした"稀代のオタク"の山本亡羊,幕末に合理的農業技術に関する多くの著作を成し,明治維新後に大きく評価された大蔵永常,新技術導入で家業を盛り返し,日本初の民営の窮民救済基金{感恩講}を構築,没後も続いた那波祐生,間宮林蔵に先立ち樺太が島であると確認,アイヌ交易の官営化企図し,その保護に努めた松田伝十郎,十組問屋の危機救い三橋会所を設置するなど,江戸経済を支配した杉本茂十郎,飢饉に対処すべく諸マニュアルを執筆・頒布,後半生を全て救済活動に賭けた熊谷蓮心,一歩先の日本を眺めた開国論者で,藩主土井利位を全面的に補佐しながら,多くの業績を遺した鷹見泉石,その最後に登場する,没落実家を自力再興後,農村を企業的組織とする"報徳仕法"で諸藩の農村復興させた二宮尊徳,農協の先駆となる世界初の産業組合で農村振興したが,革命恐れる幕政の犠牲になった大原幽学など,近代の西欧化を受け止める準備をした多くの実践的な人物も輩出している。
当然のことながら,明治維新につながる人物が出始めた時代でもあるので,それら人物を示しておくと,時代に警鐘を鳴らし,「山陵志」で尊皇論を先駆した蒲生君平,"国体"の確立と弛緩した国内制度の改革という尊王攘夷論を開発した後期水戸学の祖藤田幽谷,独自の宗教的な説と精力的な活動で大きな影響,幕府に嫌われ,失意のうちに没した平田篤胤,水戸藩主徳川斉昭の側近,神道と儒学を合わせた大義名分論で尊王穣夷運動に大きな影響会沢正志斎,豊後国日田で,{咸宜園}開き,卓越した精神と近代的教育で,全国から多くの俊才を集めた広瀬淡窓,そして,奉行所与力として"三大功績"を挙げ,<大塩平八郎の乱>を起こして<明治維新>の扉開いた大塩平八郎(中斎)と,西洋の先進性に開眼し,幕府の鎖国政策を批判,<蛮社の獄>で自殺を余儀なくされた渡辺崋山に至る。
いわゆる官(幕府)が堕落し,地方を顧みない状況のなか,都(江戸)では,いわゆる文化文政の文化が爛熟したといわれる近世末ではあるが,なかには,上記のように,しっかりした民がいて,明治維新後の近代化を準備していたことが分かると,現代の状況はどうなのか,自らは何ができるのか問わざるを得ない。
そのほか,化政期文化を象徴するような人物を,何人か挙げておくと,琴士として栄誉をきわめ,当時の女性として比類のない旅行家で,華やかで多彩な一生を送った田上菊舎(尼),応挙門下で,師の画風からは全く逸脱するも,機知あふれる傑作描いて花形的存在になった長沢蘆雪,江戸写実劇完成して劇壇重鎮となり,最晩年に最高傑作「東海道四谷怪談」を著した鶴屋南北,独自の筝歌で,それまでの生田流系の地歌・箏曲を圧し,江戸中に普及させた山田検校,あまりにも著名な葛飾北斎,読者の嗜好に合わせて「東海道中膝栗毛」を書き続け,原稿料が生計の職業作家の嚆矢になった十返舎一九,師山東京伝踏み越え,「椿説弓張月」で不動の地位,失明の中,執念で「南総里見八犬伝」完成させた滝沢馬琴,「浮世風呂」「浮世床」だけでなく,化粧品・売薬もヒットさせるなど商才抜群だった式亭三馬,実証的な作風で,「偽紫田舎源氏」で第一人者になるも,<天保の改革>の犠牲になった柳亭種彦,蘭斎の長女で,頼山陽と結婚できず,一生独身も,一流の才能を発揮して全国に知られた江馬細香,「春色梅児誉美」が熱狂的歓迎,人情本で一世を風靡するも,<天保の改革>で処罰され,憤死した為永春水,"歌舞伎十八番"を選定・公表したが,<天保の改革>で江戸十里四方追放の憂き目に遭った市川団十郎(7代),独学でさまざまな教養を身につけ,隠居許可後,次々著作実践,近郊の人々から敬愛された菅原源八,激変の時代に対応,猫絵・謎解き絵ほかユニークな浮世絵を描き続け,"横浜絵"にも先鞭をつけた歌川国芳,司馬江漢が開発した名所絵の浮世絵版「東海道五十三次」「名所江戸百景」などの傑作を遺した歌川広重と言ったところか。
この章TOPへ
ページTOPへ
九品塾においては,その必須項目を,デザイン三講としており,誤解を恐れずに簡単に述べると,日本の近代化を促した西欧文明が,あまりにも「知」を優先してきたこと,人間の精神活動を表す,いわゆる「知・情・意」の,残りのものが軽視されている一方,日本人は,長い歴史の積み重ねのなかで培われた「情」にあまりにも引きずられてしまうことを憂え,本講つまり年齢適活の,本論つまり「活動を究める」冒頭で提示した,いわゆる「知・情・意」が,「真・善・美」や「過去・現在・未来」と対応する枠組にもとづいて,「知」は,社会を構成する人々の共通の理解のため,知識を共有することにあって,いわゆる科学に対応し,「真」と「過去」とセットになること,「情」は,互いに共感できるため,つまり感受性を共有するためにあって,いわゆる芸術に対応し,「美」と「現在」とセットになることを示した上で,残された「意」と,それとセットになる「善」と「未来」こそ,デザインであることを指摘した。⇒「必須科目:科学・芸術とならぶデザイン三講」
つまり,デザインは,社会を構成する人々が共通の土俵の上に立って,円滑に行動できるようにして行く,つまり,他者のためになる「善」によって,「未来」を創造していくことであり,近年,西欧文明の行き詰まりを眼にするにつけ,その哲学的なルーツを,ギリシャのアリストテレスにしたことで,まさに,「知」の世界,つまり科学は,大発展したのであるが,「情」の世界,つまり芸術は,アリストテレスの「詩学」自体,プラトンとの違いが論争になっているように曖昧であること,何よりも,「意」とセットになる「善」をして,それが,他者のために役立つというような,日本人ばかりでなく,西欧文明以外の地域では,当然のように思われているそれではなく,自分にとって善いことと定義してしまったことが,その後の,西欧文明の個人主義化を進め,結果として,世界を分断するに至ってきたことは言うまでもないだろう。
そして,ついに「知」のみの極致とも言われるAIが登場,多くの人々が,自ら考えることを止め,何が本当か分からなくなる時代が来るのではないかと恐れ,少なくとも,官僚や学者のように,過去の知識に依存するような職能の存在意義が問われることになるのはもちろん,多くの職能が,AIとロボットにとって代わられるの可能性は高い。それに対処するには,科学者,芸術家に代わり,デザイナになることというのが,本塾での講義の意義であるが,現在,流布している商品その他のものづくりに対応する,いわゆるデザイナでなく,より多くの人々を,より長い期間,同じ土俵に載せるような,制度やルール,モラルや方法などを提示する人たちこそ,本当の意味でのデザイナであり,その分野型では分からない後世に大きな影響を及ぼす人物,開祖とされるような人物,科学や芸術においても,いわゆるパラダイムの変換になるようなものを提示した人たちは,科学者,芸術家以上にデザイナであった人物であった。そういう観点から,日本の歴史人物のなかのデザイナ的なを,統治のデザイン,文化のデザイン,社会のデザインという枠組みで拾ってみたい。
日本という国を統治した国家支配型の人物のうち,歴史に名を遺すような人物には,「時代をつくる」という点で,当然のように,デザイナ的人物である場合が多いが,国家支配者になって初めて,その才を発揮することができるのであって,それには,時代の変化など,さまざまな要因のあることはいうまでも無く,興味ある人は,「日本史話三講」のうちの「統治変遷のプロセス」を読んで貰いたい。また,地域支配型の人物も,優れた人物は,その地域をデザインしていることになり,さらに,現在における企業の社長など,さまざま組織の優れたトップもまた,その組織のデザイナである場合が多いことも,指摘しておく。
生没年が確実な最古の人物は,推古天皇であるが,物部守屋を攻滅して覇権を握った蘇我馬子は,崇峻天皇を弑殺して,その推古天皇を擁立,つまり,天皇は権威であって,実際に権力を振るうのは,天皇を戴いた国家支配者という,いわゆる天皇制のあり方を最初にデザインしたのは蘇我馬子であり,実際のところは不明なものの,「冠位十二階」の制定や,「三経義疏」著作などによって,仏教立国等日本国家への基本骨格を提示した聖徳太子とともに,国家を始動させたが,太子,馬子,推古天皇が相次いで死去すると,馬子の孫の入鹿の専横が始まり,途切れる。
そこに登場したのが中臣鎌足の唆しによって,クーデタを起こして実権を握った中大兄皇子は,皇太子のままではあったが,天皇自身が国家支配者たるべく,律令体制への改革を進めたが,ようやく天智天皇として即位するも,近江令を施行したところで,子の大友皇子を後継者とする前に,志し半ばで早世,壬申の乱で,大友皇子を破って実権を握った,弟の大海人皇子は,妃だった天智天皇の妹を皇后として,天武天皇として即位するや,皇族を重視する親政により,ヒメミコ制から男王支配への一元化を完成,日本という国名,天皇という称号を始めて用い,病臥ののちは,皇后の助けも得て,のちの法律のもとになる浄御原律令,官位のもとになる八色の姓という,律令国家の基本をデザイン,さらには史書「日本書紀」編纂に着手し,本格的な首都となる藤原京の建設も企図したが,やはり志し半ばで早世してしまう。
皇后は,そのまま称制して政治を行ううち,天皇に立てる予定だった,子の草壁皇子が没してしまったため,自ら即位(持統天皇)し,夫の天武の志を継いで,藤原京を建設し,孫の軽皇子(文武天皇)に譲位後も,上皇として後見,これまた初の本格的な大宝律令を制定,施行を見届けて没し,結果として,持統天皇は,律令国家の基盤を確立した優れた国家支配者であったが,それ以上に,そもそも,夫が武力によって天皇の座を簒奪しただけでなく,その妻である自分までもが天皇になったことの,正統性をいかに示すかということに腐心せざるを得ず,毎年のように,吉野行幸しながら,天皇の地位というものが,神から授かれるもの,いわゆる天皇神授による正当化を図るべく,現在では当たり前のように思われている,天照大神から始まる神話や,それに対応する儀式などを創り上げた,凄いデザイナであった。
その持統天皇の事業を支えることで,急速に力を伸ばしたのが藤原(中臣)鎌足の子,藤原不比等で,娘宮子を文武天皇の夫人とし,おそらく藤原京に関わったことで,自らの一族のほかの藤原氏はすべて元の中臣氏に戻すことに成功,大宝律令の施行でさらに飛躍,天皇が没するや,政界トップに立ち,支配を確実にすべく平城京を建設して興福寺を建立,さらに,宮子一人だけを天皇の配偶者とし,その子首皇子(のちの聖武天皇)を立太子させた上で,娘光明子を夫人にしてしまうことなど,律令国家を確立し,のちの藤原摂関家による国家支配体制の基礎をつくった上,自らの一族にとって都合の良くなるように修正しながらも,天武天皇が始め,持統天皇によって神話化された「日本書紀」を完成させて没したことで,これが,現在に至るまで,日本史の最大の拠り所になっていることから,藤原不比等もまた大デザイナであった。
その「日本書紀」の最後の校訂にあたっては,唐から帰国した僧道慈が顧問になったと言われ,のちに,聖武天皇が詔した国分寺のモデルプランの作成者と言われるように,デザイナ的人物であったようだ。のちに触れる淡海三船は,編纂した「懐風藻」に,彼が長屋王の招宴を辞退した時の漢詩を入れ,'性甚だ骨鰻,時に容れられず'という面があったと指摘している。不比等没後の政界を主導し,文化サロンの中心でもあったが,不比等の子の陰謀で悲劇的な最期となった長屋王もまた,百万町歩計画を図り,三世一身法を始め,多賀城を設置するなど,デザイナ的人物であった。そして,皇族外初の皇后になった光明皇后は,聖武天皇に働き掛けて,仏教に基づく慈悲の施策を実行,国分寺や大仏等も実現し,天皇の没後には,東大寺に,その遺品を献納したことで,正倉院ができたことから,やはり,デザイナ的人物であったと言えよう。
ここで,国家支配型ではないが,日本史における極めつけのデザイナといえる淡海三船に触れないわけにはいかない。彼は,生来,極めて聡明であったが,悲劇に終わった大友皇子の孫,つまり,天智天皇直系であったことから,天武天皇系で藤原氏が支配しているでは出世の道が閉ざされ,出家し,僧として学問を磨くうち,孝謙天皇の代に入った29歳の時,初の漢詩集「懐風藻」を編纂,名は伏せられているものの,天智天皇の代から藤原四卿までの漢詩を収め,大友皇子や,先述の道慈など,何人かに伝記を付していて,三船の撰であることは明らかで,大伴家持が,これに対抗して「万葉集」を編纂するほどの影響を与えたことから,すでに,後述する文化のデザイナであると言える。そして,聖武天皇の死後には,母光明皇后の力を背景に専横究める藤原仲麻呂を抑えようとする孝謙天皇にとって格好の存在となり,36歳の時には,譲位する孝謙天皇の命で,神武から父聖武天皇までの漢風諡号を一斉選進したが,なお名は秘せられていた。本論でも天皇の名を当たり前のように用いてきたが,戦前の暗誦はさておき,教科書はもちろん,日本史やそれに関わる作家らすべてが,当たり前のように用いている天皇の名は,三船がまとめてつけたものであるだけでなく,たとえば,持統天皇という名は,少しでも古代史に感心ある人なら誰でも知っている継体天皇の名が,まさに,断絶しそうになった天皇家の体を継ぐものであることとセットで,正統性を保つという名であることを始め,名に神のつく天皇は,新たな王朝を開いた天皇であり,天智,天武とセットにしていることなど,全ての名に,その天皇の存在が示され,だからこそ,あたかも最初からあったように思ってしまう,デザインの極にあると言える。つけくわえておくと,孝謙天皇が重祚した称徳天皇が,道鏡に篭絡されたため,左遷されてしまうが,直後の宇佐八幡宮の神託によって,天智天皇系が復活するや,藤原氏も一目置かなければならない存在となり,桓武天皇の即位後,まもなく没した。
その桓武天皇は,1000年以上,首都となる平安京をつくったことでデザイナだったし,長く規範とされた法令集「弘仁格」「弘仁式」,朝廷の儀式を整備した「内裏式」をまとめた嵯峨天皇もまたデザイナであったが,それ以後は,そういった国家支配者が出ず,古代は終焉を迎える。
公家政権から武家政権への交替という,日本史上最大の変革は,保元の乱後の平氏の専横によって,源氏の一斉蜂起となり,決断力と実行力で抜きんでた源頼朝が平氏を滅ぼし,さらに,奥州藤原氏を滅ぼして全国統一,鎌倉幕府を開いたことで決着するが,軍事力による支配を貫徹すべく,守護・地頭を置くことや,御家人に対してまでも,厳しく公平な裁判を行うべく,鎌倉に公文所・問注所を置くなど,武家政権の基本路線を敷き,朝廷との融和を図ろうと工作するうち,あっけなく横死してしまう。頼朝が,政権奪取とともに,これらの施策を次々と行うことができたのは,学者家系大江匡房の曾孫の大江広元をブレーンにしていたことにより,夫の頼朝没後,そのあとを取り仕切った北条政子も,そのまま,大江広元をブレーンにして,天皇を戴くように,将軍を戴く執権制度を創出するとともに,あとを狙う御家人らの陰謀,反乱を,頼朝にも引けを取らない決断力と実行力で乗り切って,北条氏の覇権を確立,尼将軍と呼ばれるに至り,ついには,朝廷に政権を取り戻そうと兵を起こした後鳥羽天皇に対してまで,弟の執権義時とその子泰時だけでなく,御家人らすべてに奮起を促して勝利(承久の乱),その直後に,義時が死ぬと,またしても起きた陰謀を抑え,執権泰時の政治を安泰ならしめて没したが,大江広元も,その後を追うように没したのである。その後,長期に続く武家政権の礎は,源頼朝,北条政子,大江広元が一体となって,デザインしたと言えよう。
その北条泰時は,その後の武家政権が拠所とする最初の武家法典「御成敗式目」を制定するなど,デザイナであったが,執権政治を確立する一方,皇位継承に介入して,のちの南北朝分裂への種を撒き,その孫で,反北条勢力を一掃して専制確立した執権北条時頼も,後に回国伝説を生む活動によって,公家政権を支えた天台宗の寺々を,武家政権に対応する臨済宗に宗旨替えさせるなど,まさしくデザイナであったが,時頼の子時宗の時代に,いわゆる元寇があり,国を挙げて戦って勝利したため,いわゆる得宗専制が進んで,悪党が横行,皇位の不安定化とも相まって,鎌倉幕府は衰退に向かい,ついに,後醍醐天皇を支えた足利尊氏に滅ぼされるに至る。
すると,足利尊氏は,後醍醐天皇に叛旗を翻して,いわゆる室町幕府を発足させる一方,南北朝分裂を招いてしまった上,足利政権には,五山文化,北山文化,東山文化といった語が目につくように文化のデザイナはいたものの,統治のデザイナがおらず,ついには,応仁の乱となって戦国時代に入ってしまう。いわゆる武将は,戦うことのプロであってデザイナでは無いが,なかには,越前一国支配を実現して"中興の祖"となり,最古の分国法「条々」筆者に仮託された朝倉孝景,役職や地位を捨てて東方に道を拓き,戦国武将の嚆矢になり,後北条氏初代北条早雲,その後継で,天才的戦略で後続戦国武将の手本になり,理想的内政により,江戸の太平を先駆したとなった北条氏康,家法「今川仮名目録」で戦国大名今川氏の基礎をつくった今川氏親,戦国一の勇将ながら病で早世したが,「甲州法度」で民政を先駆し,治水事業などに天才を発揮した武田信玄,戦国から近世への転換に的確に対処して,のちの南部藩の基礎を築いた南部信直など,領国支配をデザインした人物もいて,近世を準備したとも言える。
そして,いわゆる破壊的創造の天才織田信長が登場して,戦国時代を終わらせるが,現代の経済特区ともいえる自由都市堺の出現とも結びつく,いわゆる楽市楽座を定着させ,近世の町人社会を準備したという点だけでも,織田信長は,デザイナであったと言えるだろう。本能寺の変で没した信長の後,覇権を握った豊臣秀吉は,源頼朝のように,決断力と実行力で全国統一を成し遂げただけでなく,紛争を禁止する「惣無事令」,正確な土地を保障する「太閤検地」,治安維持の根本になる「刀狩り(一般人は武器を持たない,現代の鉄砲所持禁止にまでつながる)」,身分を保障する「士農工商」など,まさに,近世をデザインしたのであり,関ヶ原の戦を制した徳川家康は,征夷大将軍になって幕府を開くや,国と地方を一体化しながらも,地方が独自性を発揮できる幕藩体制を導入するとともに,寺院や朝廷までをも対象に,次々と,ご法度を公布して反抗しそうな勢力を封じ込める一方,有能な人材を登用して,江戸の城下町とそれに繋がる利根川付け替えや,玉川上水などの基盤整備にも着手し,林羅山を用いて,朱子学を国家支配の論理とするなど,ほとんど完璧ともいえる全国支配の体制を構築,一つの帝国とも見れる長期安定政権を確立したということから,統治のデザイナとして,最も優れた人物を,一人だけあげると,250年にわたる帝国を創始した徳川家康になろう。
しかし,徳川時代がそんなに長く続くのは,家康一人によってできるはずも無いことは明らかで,時代の継続,活性化を図ったデザイナ的人物を何人か挙げておくと,武家諸法度など諸制度を整備し,鎖国を完成,将軍の権威を高め幕藩体制を盤石にした3代将軍徳川家光,家光の異母弟で,会津の藩主になると,後々まで慕われる藩政の基礎を築き,家光没後は,将軍家綱を支え,明暦の大火が起こると,焼死者を供養する回向院を建立したばかりか,焼失した江戸城天守閣の再建を取り止めて町の再建に努め,武家諸法度に殉死の禁止を加えるなどした保科正之,熊沢蕃山との出会いもあって,質素倹約の"備前風"を普及,好学で名君とされた岡山藩主池田光政,「大日本史」の編纂・水戸学・文化財保護など,名君を超え,"水戸黄門"として伝説化した徳川光圀,徳川宗家の血筋が途絶えたため,老中らに推されて,紀州徳川家から将軍になるや,庶民が花見を楽しめるよう,隅田川を皮切りに,桜の名所を次々整備,洋書の輸入制限を緩和し,目安箱を設けて将軍への直訴まで可能にし,町奉行に抜擢した大岡忠相により,のちの,武蔵野などの発展にもつながる新田整備その他庶民の生活に資する政策によって,文化的にも,江戸が日本の中心になるようにした8代将軍徳川吉宗,範を示して藩政改革を推進して,<寛政の改革>のモデルとなり,地方政府を代表する名君になった米沢藩主上杉鷹山などがいる。
そうした泰平のなかにあって,維新への道をデザインする人物が出てくるが,生年の早い順に挙げてみると,江戸幕府初期に,早くも,後世の尊王運動に影響を与える垂加神道唱え,俊秀輩出して官学の林家を圧倒した山崎闇斎と,官学の朱子学を攻撃して播州に流され,のちの赤穂義士,さらには維新の志士の精神的支柱になった山鹿素行が現れ,徂徠派で稀にみる常識人ながら,萩藩校{明倫館}の基礎を築き,後世へ大きな影響を及ぼす山県周南,時代に警鐘を鳴らし,「山陵志」で幕末の尊皇論を先駆した蒲生君平,"国体"の確立と弛緩した国内制度の改革という尊王攘夷論を開発した後期水戸学の祖になった藤田幽谷,特異な個性で,諸藩に先駆け天保改革,尊王攘夷標榜して幕閣と対立,維新への道を開いた水戸藩主徳川斉昭と,その側近で,神道と儒学を合わせた大義名分論を唱え尊王穣夷運動に大きな影響を及ぼす会沢正志斎らが挙げられ,幕末の志士の指導者で,攘夷を不可とするほど革命的であったため,暗殺された佐久間象山,短い生涯の中,維新後を担う人材を育成し,自ら切り込み隊長役を務めて,刑死した吉田松陰によって,いよいよ,維新へ突入して行き,決定的役割を果たすも,その実現目前に暗殺された坂本龍馬ということになる。
そういった著名な人物では無いが,緒方洪庵や佐久間象山と同じ頃に生まれた横井小楠は,肥後国で,天保の改革の頃には,学問と政治の一致をめざす実学を唱えて,徳富蘇峰の父を最初の弟子とする私塾を開き,福井藩を訪れて,由利公正らに多大の影響を与えたことで,ペリー来航後,福井藩主の賓師として招かれると,「国是三論」にまとめられる交易論などによって指導,福井藩は巨大な利益を挙げるに至り,以後,維新の志士が次々と来訪し,藩主松平慶永のブレーンとして,江戸で活躍するも,事件で失脚,熊本藩から士籍剥奪処分を受け,沼山津に閑居するが,翌年には,井上毅が来訪して「沼山対話」を,その翌年には,元田永孚が来訪して「沼山閑話」を発表するなど,維新後の世界への構想は,志士たちの行動に根拠を与え続けた,一番のデザイナであった。勝海舟をして,'天下で恐ろしい人物、それは横井小楠と西郷南洲だ',さらには,'横井の言うことを西郷が実現したら,日本は大変なことになる'とまで言わしめたたが,そのとおりに,維新が実現して参与になるも,尊攘派生き残りの不満分子集団に暗殺されてしまった。いずれにしても,いわゆる維新の志士は,失敗していればテロリストでしかなく,デザイナでは無いが,背後に,新時代に向けてのデザイナがいたことで,維新が実現したのである。
そして,維新後は,近代への確固たる信念のもと,絡み合う多数の人材のなか,一つの軸になり,近代日本の船出を実現させるも,暗殺されてしまう大久保利通と,大久保によって後継に指名された伊藤博文こそ,大日本帝国憲法はじめ近代日本の諸制度を確立したという点で,一番のデザイナであったが,司法制度はじめ近代国家の基本設計を成したが,薩長派と対立,<佐賀の乱>起こして刑死した江藤新平,幕末に西洋科学を身につけ,2度渡英した体験から,近代日本の外交を確立した寺島宗則,軍制をデザインし,最初の勲一等・海軍大臣・海軍大将で,薩長間や陸海軍間の調停者になった西郷従道,警視庁はじめ近代警察行政を確立した川路利良,郵便制度の創始・電話事業の開始・国字改良など,維新直後のメディア近代化に決定的役割を果たした前島密,日本銀行を創設,"松方財政"で,資本主義社会の基礎を築き,維新政府の天才の一人と言われる松方正義,大名として先進的活動,維新後は,佐野常民と赤十字を創設発展させ,賞勲制度を創設差配した大給恒,薩長藩閥で無いにもかかわらず,帝国憲法・教育勅語など重要な政策・起草に指導的な役割をした井上毅と,デザイナ的人物はことかかず,それだからこそ,近代化が円滑に進んだともいえる。
艦隊各船の名称体系を構築した山本権兵衛:1891年海軍省官房主事になると,西郷従道海相を補佐して,海軍の改革・陸軍に対する海軍の地位向上に努め,その手腕は"権兵衛大臣"とまで評せられた。戦艦大和はじめ戦艦には国名,第一巡洋艦には赤城はじめ山名,第二巡洋艦には川名,砲艦には明石など名所旧跡の名,そして駆逐艦には,雪・雲・波・霧のさまざま名をつけるというネーミングの傑作を編み出し,1905年,天皇にプレゼンテーション,御意を得て具現化した(岩永嘉弘「ネーミング全史」による)。
その後も,台湾経営,満鉄初代総裁として大陸経営の基礎,東京市長時代には震災復興の大構想を打ち出した後藤新平,学者の道を捨て,市長になって市政の黄金時代を現出するも,現職のまま没した関一,卓越した先見性・指導力で,長期にわたって区画整理や水道事業等に取り組んだ井荻村長内田秀五郎,戦後は,長期に瀬戸内海の直島町長を務め,近年アートの島として有名になる基礎の全てをつくった三宅親連など,地域支配型に,多くのデザイナが輩出する。
国政においては,低学歴ながら実力で首相になり,金脈問題・ロッキード事件で失脚し,未だに,毀誉褒貶の多い田中角栄は,敗戦まもなく衆議院議員になると,早速,議員立法で,建築士法を通過させて,一級建築士第1号になったのはともかく,その後も,トップ当選を続け,住宅公団法その他,戦後復興から高度成長に対応して,重要な法案のほとんどにかかわって実現,郵政相になると,テレビ放送局すべてに一斉予備免許を与え,オリンピックに対応して,新幹線や高速道路建設に端緒をつけたばかりでなく,その後の,国土高速交通網を構想し,いまだに,それにのっとって建設が続けられ,佐藤内閣の通産相の時には,日米繊維交渉を決着させ,首相になるや,日中国交回復を実現,さらには,首都ではないとは言え,遷都に近い筑波研究学園都市を実現させるなど,戦後の日本の最大のデザイナであったことは,認めざるを得ないだろう。
日本人なら,最も古い歌集「万葉集」でそれを編纂したのが大伴家持であることは,誰もが知っている。大和朝廷発足以来,天皇を支えてきた名族大伴氏は,和歌のもとと言われる久米歌の久米氏と同族で,藤原不比等が覇権を握って以降,他の名族同様,抑えられるが,不比等の四人の男子が,天然痘流行で全員没したことから,巻き返しを図ろうとしていたところに,第1話で述べたように,752年,淡海三船が編纂した,日本初の漢詩集「懐風藻」が高く評価されたことに刺激されて,「万葉集」の編纂を始めたが,757年の橘奈良麻呂の乱に連座して,藤原仲麻呂によって因幡に左遷され,762年には,仲麻呂の専横に反対する藤原良継の乱に連座して,薩摩に左遷され,結局,この間に,自身が読んだ歌を,最末尾に入れた状態で終わる。その後,乱を起こした仲麻呂は討滅されるも,宇佐八幡宮の神託後になって,ようやく京に戻り,780年,63歳には,参議・公卿に昇り,持節征東将軍に任命された翌年,陸奥国多賀城で没した。「万葉集」最後の歌以降の家持の歌が伝わらないのはもちろん,藤原氏の抑える朝廷では,漢詩が主流で,「万葉集」が,いわゆる万葉仮名を多く用いた漢字で書かれていたことの存在自体もあって,その存在が知られるのは,実に,平安時代半ばになってからと言われるので,大伴家持は,優れた蒐集編纂者ではあったが,デザイナとすることはできない。
家持が没した時の桓武天皇は,第1話でに述べた通り,自ら国家支配者として,近世まで都として続く平安京を造営,いわゆる平安時代が始まるが,その子の嵯峨天皇は,自らも三筆の一人というレベルで,強い権威により,長期安定の文治的時代,宮廷中心の弘仁文化を創出して,のちの花開く王朝文化の祖とされ,なお,晩唐の影響を強く受けていたとはいえ,が空海,最澄の仏教が,まさに,日本化したものとして大きな存在であったように,いわゆる国風文化の準備をしたことは間違いないだろう。
その嵯峨天皇が没するやいなや,承和の変を起こした藤原良房によって,藤原氏の専横が始まり,その後の天皇の権力は無きものとなるが,大伴家持が,藤原氏への抵抗すべく「万葉集」を編纂したことが端的に示すように,和歌は,いわゆる敗者の抵抗の象徴のような存在であって,ついに,醍醐天皇が,初の勅撰和歌集となる「古今集」を撰することを企図することになり,その撰を託されたなかの一人紀貫之は,やはり,大伴氏と同様,古代からの名族ながら排除されてきた紀氏の一員として,全力を振るうことになる。ついでに言えば,その後も,単に戴かれるだけで,権力を発揮できない天皇にとって,勅撰和歌集の編纂は大きな拠所となり,のちに,鎌倉幕府から権力を取り戻そうとした後鳥羽天皇は,その象徴のような存在になった。
「古今集」編纂の一員に選ばれた紀貫之は,その機会を最大限に利用し,女性の際立つ時代のところでも述べたように,その「仮名序」によって,のちに,古今伝授として,近世まで続く和歌路線を敷いたばかりか,晩年,土佐守として現地赴任したのを契機に,有名な'男もすなる日記といふものを,女もしてみむとてするなり'の書き出しで始まる,初の仮名文学「土佐日記」を著して,王朝女流文学を準備,歌人としての貫之の作品は,トップレベルとは言えないが,デザイナとしては,抜きんでた人物と言えよう。もともと出世のあての無い貫之は,屏風歌歌人として出発,歌合に出詠するうち,すでに述べたよう,この頃には知られるようになっていた「万葉集」にあやかった「新撰万葉集」に採用されるなど,歌人としての道を歩むうち,901年の漢学者菅原道真の左遷によって,藤原氏が後宮対策とした仮名の使用が自由になり,903年,内蔵助に採用された藤原兼輔と親交して,その庇護を受け,醍醐天皇が撰進を命じた「古今和歌集」に,従兄の紀友則らとともに選者になると,編纂をリードして専念,わずか2年後の905年,和歌史を批判する仮名序をつけて奏上,まさに国風文化の幕を開いたのは,33歳の時であった。しかるに,官職の方は不遇のままで,930年,土佐守に任じられて,初めて地方に赴任,翌年には醍醐天皇が,その2年後には,藤原兼輔も死去するなど,庇護者を相次いで失い,平安時代最大の危機,平将門の乱の始まった63歳の時,孤立無援のなか帰京して,「土佐日記」を創作,以後,醍醐天皇の遺勅を奉じて,「新撰和歌集」を編むも陽の目を見ず,自らの屏風歌中心に「貫之集」を編んだ上,「新撰和歌集」に孤愁の心境を示す真名序をつけ,74歳で没した。
古代末の院政期に,朝廷の歌人として登場した藤原俊成は,1140年,西行の遁世に衝撃を受けて,傑作'世の中よ道こそなけれ思ひ入る 山の奥にも鹿ぞ鳴くなる'を詠み,翌年,それも含む「述懐百首」などで,崇徳院の歌壇の殊遇を受けて,傑作を続けるも,1156年の保元の乱後,歌壇は崩壊し,崇徳院は,配流先の讃岐で死去してしまうが,朝廷歌壇のリーダーになり始めると,平清盛が太政大臣になった年,御子左家に帰って俊成と改名,翌年の54歳の時,住吉神社に籠って和歌に命をかける覚悟,63歳の時,関白九条兼実の和歌師範に迎えられ,六条家の権威と劇的交替,源氏が蜂起し,平氏が滅亡して,鎌倉幕府の発足するという日本史上の劇的変化の間,後白河院から「千載和歌集」撰進の院宣が下って,ついに,第一人者となり,完成させて奏覧後,"寂寥感"から"優艶美"への転換に決着をつけると,83歳という高齢になって,史上最高とされる歌論書「古来風体抄」を式子内親王に献進,後鳥羽院の信頼を得,子定家とともに,新古今様式を開花させ,最後まで,指導者の地位を保って,90歳で没した。藤原俊成は,公家社会から武家社会に劇的転換に,和歌の面で応じた文化のデザイナであったといえよう。
父俊成のデザインのもと,後鳥羽院に認められて,「新古今和歌集」を編纂するも,院との確執著しかった藤原定家が,その後,現在に至るまで,和歌を革新した歌聖として崇められことになっているわけであるが,現在もなお,正月行事や競技として定着している「小倉百人一首」を撰しているのだから,藤原定家もまた,優れたデザイナであったことは間違いない。そして,武家からの権力奪回を試み,失敗して配流された後鳥羽天皇は,その地で,最期まで「新古今和歌集」の編纂に執念示して,敗者の典型になったのである。そして,応仁の乱が始まった翌年,作品に感銘した斎藤妙椿が城の包囲を解かれた東常縁が,1471年から2年かけて,伝来の古今集を宗祇に講義して"古今伝授の祖"になり,近世に続いて行くのである。
和歌からは,その後,まず,武家社会に対応する連歌が派生,鎌倉幕府が滅亡して,足利政権が始まると,文化的には,いわゆる公武合体になって行くが,その口火を切った関白家の二条良基は,南北朝の動乱で本職が翻弄されるなか,武家社会の文化的価値を初めて認め,地下の連歌師救済に師事してすぐに,連歌論書「連理秘抄」を著し,1352年に,観応の擾乱が終わって時代が落ち着くと,救済とともに,連歌最初の準勅撰集「菟玖波集」を編纂して連歌道を確立しただけでなく,歌人頓阿との間で「愚問賢注」を著して,二条派を庇護して文壇指導者となり,晩年には,足利義満のサロンを指導して北山文化を創造するなど,まさに,文化のデザイナであった。そして,足利義満没後の動乱の世に連歌に専心,1467年の応仁の乱勃発少し前には連歌論書「ささめごと」を著して,最高の連歌師宗祇はもちろん,最高の俳諧師芭蕉にまで影響た心敬も挙げておかねばならない。
次に派生したのが俳諧で,室町幕府の滅亡直前に,連歌師の子に生まれた松永貞徳は,地下の歌人としても一流になる一方,徳川幕府が始まってまもなく俳諧を始め,やがて貞門と呼ばれる俳壇ができると,家光の鎖国令が始まる1632年,63歳の時,自ら生まれ変わったと,姿を童形に改めて隠居,俳諧全盛を導く革命を起こし,家光が没した年には,80歳にして,膨大緻密な俳論書「俳諧御傘」を著し,初めて,日常通俗の言葉に詩的価値を認める文学史上の革命を起こし,まさに,'貞徳無くして芭蕉無し'といわれる,大デザイナであった。その貞徳が死去するや,初めて俳諧の発句を披露し,西鶴らに推されて,「江戸俳諧談林十百韻」を催行して談林派の祖になった西山宗因は,貞門に批判的であったが,平易な独自の俳境拓き,芭蕉らの登場を直接的に促す役割を担い,その天才芭蕉の最も良き理解者で信頼され,門人からも敬服された向井去来が,いわゆる蕉門を確立する。そして,俳諧からは,現在もなおメディアで話題になる川柳が派生するが,その祖とされる柄井川柳は,自らは句作せず,狂歌に押されながらも付句集「柳多留」編纂を続けたデザイナ的人物であった。
そして,明治維新になって,西欧文化の流入に対抗する必要に迫られた和歌,俳句は,正岡子規によって,劇的変化をすることになる。良く知られているので,簡単に記せば,1889年の帝国憲法の発布まもなく,25歳の時,陸羯南の縁で,日本新聞社に入ると,紙上で,まず,俳句ついて季語などによる革新に専念,1894年の日清戦争後,カリエスで病臥するようになった後も,弟子の高浜虚子が創刊した{ホトトギス}を指導して普及させる一方,31歳の時,有名な「歌よみに与ふる書」の連載を始め,2回目の「再び歌よみに与ふる書」では,'貫之は下手な歌よみにて古今集は下らぬ集に有之候'と書きだす激烈さで,「万葉集」を称揚するなど,決定的影響を及ぼして早世,まさに,近代詩歌文化のデザイナになった。貫之同様,子規も,歌人・俳人としてのみ捉えると,作品のレベルは,トップになるような存在ではないが,与えた影響は甚大であり,デザイナ(というよりはアジテータかもしれないが)として捉えることの必要性が分かってもらえるだろう。子規の打ち出した短歌は,{アララギ}の編集発行を主導した島木赤彦によって,歌壇進出に大きく寄与し,いわゆるアララギ派といわれる人が,近代短歌の主流になる。
最後に,西欧文化によって始まった近代詩に触れておくと,口語自由詩を完成させ,おそらく印刷された表現を意識した独自のアフォリズムを展開,近代詩の世界を大きく転換させた萩原朔太郎,西欧文芸の紹介につとめ,名訳詩集「海潮音」で詩歌壇に決定的な影響を与えただけでなく,結果として,日本語文字には無かったヴィを(V音のカタカナ表記であるが,B音なのに間違って使うくらい)定着させた上田敏の二人を挙げておきたい。
和歌とそこから派生した連歌や俳諧以外の芸術,芸能に関わるデザイナ的人物について,時代を追って簡単にみると,
まず,武家政権への変わり目に登場し,女性芸人乙前から習った今様の歌謡を集成した「梁塵秘抄」をまとめて民間芸能にお墨付きを与えたこと以上に,現代において,世界冠たるストーリー漫画のルーツたる絵巻物を振興するなど,中世への,文化の大転換を主導した後白河法皇が挙げられる。
鎌倉時代の終りに登場,公武の間に多数の支持者を得,七代の天皇から国師号,日本禅宗の主流の元になった夢窓疎石は,36歳以降,景勝の地に次々隠棲しながら,修行の場として庭園を制作するうち,後醍醐天皇を受け,1333年の鎌倉幕府滅亡後,臨川寺の開山になるとともに,枯山水の名園を制作,南北朝分裂後は,新将軍足利尊氏とその弟直義からも帰依され,64歳の時,西芳寺中興開山になると,傑作"苔寺の庭園"を制作,その後は,天龍寺の造営に腐心し,71歳,大伽藍と庭園の美観「天龍寺十境」を定めて,5年後に没したが,その後,禅寺に次々名園が生まれて行くことから,夢窓疎石こそ,庭園文化のデザイナと言って良いだろう。
統治のデザイナは出なかったものの,国家支配者として北山文化のデザイナであった足利義満もとに,"能楽の祖"になった世阿弥が登場する。11歳の時,父観阿弥とともに猿楽能を演じて,それを見学した義満から絶大な庇護を与えられ,21歳,父の死去して観世大夫を継ぎ,36歳の時には,将軍義満の台臨をえて,天下の名声を得るに至るも,45歳,義満が急逝,父の方針に悉く逆らう後嗣の将軍義持によって失脚,不遇のなか,55歳には,のちに「花伝書」にまとめられる,子らへの相伝の著述を開始,以後,能の創作も含めて,立て続けに著述,その内容は,極めて体系的かつ緻密,のちの能楽者の拠り所になるもので,まさに,能舞のデザイナであった。59歳には,出家し,成長した長男元雅に観世大夫を譲るも引退したわけでなく,一座は大発展して,自らも円熟の境に達するが,65歳の時,籤引きで登場した特異な将軍義教の弾圧によって,能を演じることもできなくなっただけでなく,後嗣元雅も早世して悲嘆,71歳,ついに,佐渡に流され,80歳頃に没した。ついでながら,佐渡では,のちに,能楽が広がって,現在に至っていることは,良く知られているが,そのほか,順徳天皇など,レベルの高い人物が,多く流されたことで,独自の文化が育まれいる。
8代将軍足利義政は,禅僧一休宗純の指導によって,芸術(芸能)的活動において,後世につながるさまざまなものが登場する時期に対応するような繊細な人物で,政治から逃避し,応仁の乱の勃発を招いた国家支配者としては失格であったが,一休が没した年,45歳に閉居すると,東山山荘の造営に没頭,銀閣を建てるとともに,名園を整備し,一休が指導してきたものも含めて,のちに東山文化の時代とも言われることから,文化のデザイナとしての役割は大きかったと言える。例えば,1461年に,相国寺の庭園を制作して,史上初めて作庭家として名が出る善阿弥を登用,彼は,すでに,75歳という高齢で,その後,彼は集中的に作庭するが,義政が東山山荘の造営を始めたのは,彼が死去した年なので,善阿弥に学んだことが活かされたと考えられる。
東山文化を代表する人物として挙げられる雪舟は,応仁の乱が勃発した年に,明に渡って決定的影響を受け,水墨画を大成する大画家になったのであるが,将軍足利義政の御用絵師になる小栗宗湛に絵画を学び,名を知られぬ時の絵が雪舟に感嘆され,1483年,義政が,東山山荘の絵を雪舟に描かせようとした際,固辞した雪舟から推薦されて御用絵師になった狩野正信がおり,その長男で父以上の画才を発揮した狩野元信は,幕府の弱体化で,活動の場を,上層町衆ほか,寺院,朝廷,公家らに広げて,新障壁画様式確立,その孫の狩野永徳が,信長に呼応して画風革新,秀吉の大建築に次々と大作,安土桃山様式として狩野派を確立したことで,元信は,後世,神格化された。また,和歌の項で述べたように,連歌もまた,この時代に開花するが,東山文化時代に,後世につながるさまざまなものが登場したという点で代表的のは茶道であろう。
すでに,戦ではない平和的な競技として,中国から伝来した闘茶が,室町幕府創設に貢献したバサラ大名佐々木道誉によって広がっていたが,興福寺配下の寺に入門していた村田珠光は,衆徒らの間に流行していた闘茶に耽溺して寺を追われ,放浪の後,足利義政が将軍になってまもなく,29歳の時,大徳寺の真珠庵に落ち着いて,一休宗純に参禅し,連歌師心敬や飯尾宗祇らとも親交して,"佗数奇"の理念を深化,書院茶の湯を仏寺の方丈の理念に叶う四畳半茶の湯に改め,1462年,40歳の時には,義政の茶道師範となり,義政が東山山荘に隠棲後も指導を続けて,80歳で没して,"茶の湯開山"となった村田珠光は,茶道の最初のデザイナであった。そして,珠光が没した年に生まれ,大徳寺で出家して,"わび"の美学を確立後,珠光の開いた茶道を大成し,千利休ら堺商人へ伝え"堺流茶の湯開祖"になった武野紹鴎が次のデザイナになり,紹鴎に学んで,茶道の大成者で現代の茶道の祖になった大デザイナ千利休に至るが,言うまでも無く,あまりに秀吉政権に隠然たる勢力をもったため,切腹させられ,中断してしまうが,,将軍家光の時代に,仕官せずに千家の再興に努め,その子をルーツに,表・裏・武者小路という,現代に続く,千家茶道の家元を確立した,孫の千宗旦を最後に,茶道文化は,優れたデザイナが続いたことによって,揺るぎないものになったと言えよう。
茶道のルーツである闘茶と同じように,戦に代わる競技である碁将棋は,僧の間では,古くからなされていて,戦国時代には,武将たちの間でも盛んにされるようになり,信長,秀吉につかえた本因坊算砂が,本当に戦を無くした家康にも重用され,近世囲碁の基礎を確立して,本因坊家の始祖になり,世襲する形で明治維新後まで続くが,中央棋院に本因坊免状発行権委譲して,実力制採用,棋風も革新して碁界を近代化し,現在まで盛んに続くようにした本因坊秀哉と,将棋もまた,近世以来,名人は世襲であったが,維新後,自ら世襲名人を辞退して,実力名人制を導入し,将棋界の近代化を実現,その結果,現在の藤井聡太名人に至るまで,何人もの天才棋士を生んで,隆盛を保たせるようにした関根金次郎は,まさに,棋界のデザイナであった。
徳川時代に入って,戦に出ることの無くなった武士たちは,後述するように,全く異なる分野に転身して,新たな世界を開く人物になっていく一方,戦に代わる武術として,いわゆる文武両道の,武を担うようになるが,その端緒を開いたのは,新陰流を確立し,近世剣術を革新,徳川将軍兵法師範として治国経世までも教えた柳生宗矩で,後々まで模範にされる剣術のデザイナであり,不敗のまま実戦を離れて独自兵法を完成後,恩受けた城主の死に,「五輪書」を書上げて没した宮本武蔵という天才を得,幕末には,近代的な教授法と昇段制の改革などで俊秀が集まり,江戸随一の道場の名声を得た千葉周作や,彼と類似の生涯を送り,道場には高杉晋作・桂小五郎ら維新の主役が集まった斎藤弥九郎,あるいは,幕臣として江戸の無血開城実現に貢献,明治天皇の侍従になる一方,無刀流剣術の開祖になった山岡鉄舟ら,近代を開くことに貢献するに至る。
武術に近いものの,大きな身体や土俵という舞台での振舞いなどで,歌舞伎役者などに近い人気稼業ともいえる相撲は,幕藩体制のなかで,大名間の平和的競争の一環として,いわゆるお抱え力士という形で広がっていったが,天明期に登場した,天下無敵の強さに人徳があって江戸随一の人気を得るも,現役中,流行性感冒で早世した第4代横綱谷風梶之助や,化政期の,強いばかりでなく,学もあって,13年間の巡業日記の他,多くの記録を残した無敵の大関雷電為右衛門らによって,国民的競技となり,維新を迎えると,一場所2敗を恥じて引退,両国国技館の建設はじめ,相撲の近代化と発展に貢献した梅ケ谷藤太郎,恵まれない体格ながら革新相撲で横綱になり,引退6年後,日本選手権で現役横綱ら倒して優勝するほど強かった栃木山守也,その弟子で,若乃花と小兵の名横綱同志の"栃若時代"を創り,引退後は名理事長として多大の業績を遺した栃錦清隆らによって,今なお,いわゆる国技として,NHKでも特別扱いされている。近年,モンゴル人力士が長く横綱を独占,中には,その振舞いが問題になる力士も登場,国技として問われる以前に,そもそも相撲は,近代に西洋から入って来たスポーツにあたるものなのどうかといった難問は未解決のままになっている。
それはさておき,近世の武術から,スポーツ,さらにはその振興まで一挙にデザインした人物,嘉納治五郎は,桜田門外の変のあった年に生れ,塾でいじめに遭い,維新で消えてしまった柔術家を,入学していた開成学校が帝国大学になった年,なんとか探し出して学ぶや,一気に頭角を現し,来日したアメリカのグラント将軍の前で披露,卒業した翌年,22歳で,{講道館}を開塾,26歳には,新道場を建設し,諸流派を統合,柔道として確立し,門人の活躍も始まるなか,33歳には,第一高等中学校長,37歳には,東京高等師範校長になり,体育科を新設して,教師の養成に努める。日露戦争後の49歳,クーベルタン男爵に請われて,アジアで最初のIOC委員となり,翌々年には,大日本体育協会を設立して初代会長,その翌年には,自ら団長となってストックホルムに行き,日本のオリンピック初参加を実現,校長,会長を退任後も,オリンピックには参加し続け,満州事変翌年の72歳の時のロサンゼルス大会での華々しい成果を挙げ,二・二六事件の起きた年,カイロで開催のIOC総会で,ついに,東京オリンピックの招致に成功するに至ったが,翌々年,その帰途,氷川丸戦中で肺炎のため急逝,巨人と言うにふさわしい生涯であった。
その他,体育スポーツ振興において,大きな役割をした人物を挙げておくと,"普通体操"の普及・卓球の移入・女子体育の発展などに貢献し,日本の"学校体育の父"になった坪井玄道,わが国女子体育界の先達井口阿くり,体操教員検定に女性として初めて合格し,体操選手の名門{藤村学園}を創り上げた藤村トヨ,日本サッカー界の大先達で'サッカーの神様'竹腰重丸ら,そして,嘉納治五郎のあとを受け継ぐ人物には,民事訴訟の権威で,大日本体育協会長になり,日本スポーツ界をリードした岸清一,政財界で活躍する一方,アマチュアスポーツの振興に尽力し,国民体育大会も創始した平沼亮三,オリンピック日本人初の金メダリストで,日本の陸上競技の発展に尽くし"日本陸上界の父"になった織田幹雄,「社会体育論」を提唱し,オリンピックに生涯をかけ,嘉納が招致するも戦争で中止になった東京大会を,戦後,実現・成功に導いた田畑政治,選手としてメダリスト,東京大会を成功に導き,近代スポーツのあり方に警鐘鳴らし続けた大島鎌吉,そして,身体障害者のスポーツ振興をはかり,"日本パラリンピックの父"と呼ばれる中村裕に至る。
つけたしになるが,自然や文化を対象に挑戦する探検紀行型は,古来からそういった人物がいるものの,意識的になったのは,西洋から個人主義的指向が入ってきてからで,日本の領土確保に心をくだき,「日本風景論」は大きな影響,殆ど全大陸を旅行した志賀重昂と,銀行勤めの傍ら,日本の登山文化の基礎を築いた小島烏水が際立つほか,幕府の蝦夷支配に反発し辞職,新政府でアイヌ地名を漢字化も,アイヌ政策に失望し辞職した松浦武四郎,日本人初のラサ入り,「西蔵旅行記」が大ヒット,両ラマから大蔵経入手,チベットブームを起こした河口慧海,本願寺宗主として,中央アジアで発掘調査を実施し,負債と疑獄で隠退後,大アジア主義の先導役となった大谷光瑞ら,大きな目標のもと,探検紀行した人物も多い。
戦そのものを終わらせた徳川時代には,文学の分野で,大坂の陣が終わるや,禅僧に転身して仏教復興運動を起こし,仏教説話が仮名草子の先駆になった鈴木正三,出家して住職になった後,仮名草子を書き始め,質量ともに最大の作家となった浅井了意ら,武士から転身した人物が,その後につながる大衆文学の準備,元禄時代には,天才井原西鶴が古典的な物語を脱して,初めて庶民の生活を題材に創作して,近代小説を準備,幕末の,読者の嗜好に合わせて「東海道中膝栗毛」を書き続け,本格的職業作家の嚆矢になった十返舎一九に至る。
絵画の分野では,幕府が,織豊時代に確立した狩野派を採用したのに対し,書画,漆芸,陶芸に通じ,家康からの土地に"芸術家村"を開いて新時代の芸術をリードした本阿弥光悦という優れた文化のデザイナによって,光悦が協業した俵屋宗達を皮切りに,在野の大画家と言えるような人物が輩出して行き,初の挿絵画家として独自の画風開拓し大流行させた菱川師宣が,浮世絵の実質的な開祖になるとともに,元禄文化を先駆し,天明文化を先駆した鈴木春信が,多色刷木版画錦絵を誕生させて,浮世絵を飛躍的に発展させる一方,多くの画家が,その人物の才に留まるなか,伝統画派全て否定して写実様式を確立し,円山応挙によって,円山派という一派ができるのは,近代への準備に呼応するものとも言えよう。
戦国時代末から織豊時代には,藤堂高虎代表に,武将の多くが城郭建築家であったが,関ヶ原の戦直後に徳川家康に用いられた中井正清は,重要な城郭や寺社を担当して信頼,幕府の関わるさまざまな建築を担う中井役所の祖となり,一級の建築・造園を数多く設計し,茶道でも将軍師範・遠州流の祖になった大名で万能の芸術家と言える小堀遠州は,いわゆるデザイナの大人物であったし,義太夫節を創始,{竹本座}を開き,近松門左衛門作品が大当り多数,近世浄瑠璃を確立した竹本義太夫,現代まで続く団十郎のパターンと市川宗家を確立した市川団十郎(2代),"歌舞伎十八番"を選定・公表したが,<天保の改革>で江戸十里四方追放の憂き目にあった市川団十郎(7代),フィクサーとして,門閥にとらわれない合理的な興行制度や合作に適した作者式法を確立した金井三笑らは,現代でもなお盛んな歌舞伎のデザイナであった。そして,徳川時代初期に,僧侶として最高位あった安楽庵策伝が,仏教普及のため近世話芸を確立,「醒睡笑」で落語の創始者になり,観客を前に口演する"辻ばなし"で超有名人となった露五郎兵衛は,上方落語の開祖とされ,仕方噺を得意として本職となるも,筆禍で遠島,赦免即憤死した"江戸落語の祖"鹿野武左衛門,その他の人物の活躍で発展を続け,幕末に創作噺で地位を得,維新後は近代落語を確立,多くの門下を育て黄金時代開いた三遊亭円朝によって,ますます発展していることなど,近代の多くが,近世の文化の続きにあることも,確認しておきたい。音楽については,現行の筝曲の原点「六段」など近世筝曲確立し,盲人音楽家専業化も実現した天才音楽家・八橋検校などがいたものの,近代化における西欧の影響が大き過ぎたと言える。
近代に入って以降は,かなり知られているので省略するが,本職がどうであれ,文化のデザイナとして評価すべき人物を,生年順に,挙げておきたい。早稲田大学を拠点に文芸活動を指導,先取りと献身で,多大な影響を与えた坪内逍遥,官僚として{東京美術学校}創設,俊材を育成するも排斥され,以後,思索と海外活動に転換した岡倉天心,その天心のもとに傑作描き,その遺志を継いで{日本美術院}を再興,画壇の一大勢力にした横山大観,図書館長になるや"巡回文庫""十門分類表"など革新的な試みも,内務官僚と確執で自殺した佐野友三郎,日本と世界のお伽話を集大成,童話口演の全国行脚に努め,近代日本児童文学の生みの親になった巌谷小波,銀行勤めの傍ら,日本の登山文化の基礎をつくった小島烏水,政治風俗を風刺して一世を風靡,雑誌{東京パック}を発刊して後進育成し,漫画隆盛の基礎をつくった北沢楽天,日本映画独自のジャンルを確立し,映画製作所も設立した"日本映画の父"牧野省三,新劇界の草創期に新しい世界を追求,{築地小劇場}で新劇俳優多数を育成するも,早世した小山内薫,{赤い鳥}を創刊・主宰し,児童文学を開拓・主導して,早世した鈴木三重吉,{日本野鳥の会}を起し,鳥類・自然保護運動の先頭に立って活動,優れた随筆も遺した中西悟堂と,{山階鳥類研究所}を開設し,鳥類全てに和名,日本の鳥類学研究,自然保護に指導的役割を果たした山階芳麿,戦前・戦後一貫して朝鮮はじめ地域の伝統文化に取組み,"民芸運動"を創始・展開した柳宗悦,軍国主義の進む中,次々と傑作を書いて探偵小説分野を確立,後進の育成にも尽力した江戸川乱歩,漫才の台本を通じて,新方向を開拓し,多数の漫才師を育成した秋田実,戦時下に報道写真の理念と方法を紹介,多くの俊才を育て,<敗戦>後も,{岩波写真文庫}でリードした名取洋之助,戦前は夫と洋画輸入,戦後は邦画国際化に貢献,国立フィルムセンター設立にも尽力した川喜多かしこ,長く{映画之友}編集長をつとめ,{友の会}を主宰,テレビの映画批評を開拓して圧倒的支持された淀川長治らである。
ついでながら,現在一般に使われる,いわゆるデザイナ(商品型)について,忘れてはいけない人物を,生年順に記しておくと,商業美術を先駆け,現代日本のグラフィックデザインの礎を築いた杉浦非水,日本でのコピーライターの嚆矢(当時の呼び名ではアドライター)の片岡敏郎,"美人画"で一躍有名になり,写真・印刷を初めて活用して商業デザインを先駆するも挫折,画家というよりデザイナだった竹久夢二,自らの取組みに疑念を抱き続けながらも,多くの人材を育てた昭和宣伝広告の先駆者太田英茂,日本のグラフィックデザインの先駆者で,アール・デコで知られ,{資生堂}の企業イメージをつくった山名文夫,タイポグラフィーをテコに,装幀(ブックデザイン)を中心に,時代をリードした原弘,"お茶の間洋裁""ニューきもの"など草分け的存在で,皇室御用達になった田中千代,{桑沢デザイン研究所}を創立,東京造形大学へ発展した桑沢洋子,40過ぎに通産省から転身,椅子はじめ多くの傑作を生み出し,先導したが,自殺した剣持勇,グラフィックデザイナー先駆者,<東京オリンピック>で第一人者,社会的地位向上に尽力した亀倉雄策,大量生産・大量消費社会に疑問を投げかけ,独自のものづくりのデザインを開拓した秋岡芳夫,テレビCM制作のジャンルを開拓,次々受賞して天才といわれるも,絶頂のなか自殺杉山登志というところであるが,自殺多いのは芸術家指向と資本主義広告先端との矛盾からではないだろうか。太字にした3人は,いわゆるデザイナをデザインしたと言えるような人物である。
古代の日本では,明治維新後に,西洋の学問を取り入れて消化に努めたように,中国の学問を消化するのに努め,学問は,公的には,朝廷の,いわゆる文人官僚,本講の活動の分野型で言えば,官僚分野の法務学識型が担い,書類を整え,判断を下す,近代の学問の法学にあたる分野が中心の,いわゆる漢学,見方によっては,儒学であり,文献等の蓄積や,幼時からの教育が大きな比重を占めるため,いわゆる学者家系が醸成された。その最初が,古代随一の学者とされ,悲劇の結末によって,天神様になった菅原道真が出た菅家で,祖父清公が,遣唐使の一員として,空海,最澄とともに入唐,新知識を得て帰国し,平城天皇即位とともに登用されるや地方行政に功績を挙げ,嵯峨天皇によって,大学頭に抜擢され,天皇が譲位後も,朝儀の整備その他に重用され,ついには公卿になり,嵯峨上皇と同じ年に没した,子の是善が継いだことで始まり,道真失脚後も学者家系として続き,鎌倉時代に入って,土御門天皇の侍読になった菅原為長は,当代の大才と言われ,菅家では,道真以来の公卿になった。もう一つ有名なのが,菅原清公に師事した,大江音人の興した大江家であるが,菅家のようにはいかず,その力が発揮されるのは,藤原道長時代に,一条天皇の侍読に抜擢されて,中興の祖になった大江匡衡からで,その曾孫,大江匡房は,古代から中世への転換を象徴,その在り方が後世への指針となって多大の影響を及ぼし,その曾孫,大江広元は,統治のデザインのところで紹介したように,源頼朝,北条政子のブレーンとなって,鎌倉幕府の確立に貢献,余談ながら,競走馬の血統で,その才能が最も出るのは,血が8分の1,つまり曽孫であること,そのままである。
そう言った学者家系でなくても,法的効力を有する現存アジア最古の法典「令義解」の編纂はじめ,多くの治績をあげた清原夏野,正確な判決で,その法解釈は長く範とされたが,法隆寺僧訴訟事件では伴善男と対立した讃岐永直,日本最古の百科事典「秘府略」編など才能を発揮,皆に慕われ,承和の変直後に公卿・参議になった滋野貞主,当代一流で,孤高を保ち政変にも巻き込まれず,「続日本後紀」20巻完成させた春澄善縄,正義感に溢れた経世家で,菅原道真と衝突,その左遷で昇進し,「意見十二箇条」など建言した三善清行,当代一流ながら官位は不遇。公家社会衰退期の新人類で「本朝文粋」「新猿楽記」を遺した藤原明衡,優れた学者として変革期の権力者たちに信頼され,菅原道真以来,儒学者で唯一人没後神になった清原頼業,有職故実や朝儀に通じ源平双方が重用,詳細な日記「山槐記」を遺し,「今鏡」「水鏡」著者説もある中山忠親など,現代なら,学問の世界でトップ級と言うだけでなく,デザイナとしても,大きな役割をした人物がいたことを,知っておいてほしい。のちのことになるが,室町時代の後半には,関白まで務めて政界を引退後,応仁の乱で苦労しながら,日本一の大学者として,公武合体の文化のブレーンの役割を果たした一条兼良と,その後継者的な存在で,応仁の乱期も京都に留まり,生活には窮しながらも,公武合体の象徴として尊敬され続けた三条西実隆も加えられるだろう。
古代において,在野の学問は,仏教僧が担っていたが,そのなかに,僧と言うよりは学者であるという人物と,その人物が拓いた学問分野が登場する。藤原良房が人民初の摂政となり,その養子基経が初の関白になる,まさに藤原氏専横が進む最中,日本独自の草木成仏の思想を確立しただけでなく,わが国梵語論の原点となる画期的な書を著し,同時に,日本語の性質も究明して,五十音図の原型をも発明した天台僧安然であり,蒐集編纂型を前提とした言語文学型を主流とする日本の学問の最初のデザイナと言えよう。そして,鎌倉幕府の名執権北条時頼の時代に,「万葉集」の研究を飛躍的に発展させた「万葉集註釈」20巻を完成した僧仙覚が伝えた「万葉集」をもとに,江戸の元禄時代前夜,万葉仮名表記の発見など,僧契沖が天才的業績をあげる。
これらをもとに,いわゆる国学を創始した荷田春満は,赤穂浪士の復仇の支えをなした後,「万葉集」講義を核に,多くの門人を育てて,幕府とも間接的に学問上の交渉をし,その子,荷田在満は,田安宗武に「国歌八論」を呈して国歌論争になり致仕するが,後任に,ライバルであったが,父の創始した国学を受け継いだ賀茂真淵を推挙,その真淵から刺激を受けた本居宣長が「古事記伝」に着手,30余年かけて完成させたそれは,復古思想の極限としての国学をも完成させることになり,現代もなお,右翼思想はじめ大きな影響を及ぼしていることから,本居宣長は,大学者である以上に,大デザイナであったと言える。
その間には,初めて「日本書紀」全体の注釈書をまとめ,日本初の五十音順国語辞典「和訓栞」を作成した谷川士清,名著「古言梯」を著し,その後の歴史的仮名遣い研究に貢献した楫取魚彦といった,言語文学面で,優れたデザイナ的学者がいたことも,関係があったと考えられる。
ここで,宗教では無く,人々の考え方,生き方に大きな影響を与える,学問と言い切ることには躊躇するものの,現代における哲学,すなわち最もデザインに近い哲学思想型の学問に触れたいが,当然のことながら,それら人物の著作を読んで貰う方が大事と思われるので,簡単に列記すると,まず,中世での,公家社会から武家社会への大変革に,日本人初の体系的な歴史「愚管抄」を著した慈円,後醍醐天皇の没後,回復めざし,南朝の正統を主張した「神皇正統記」ほか膨大な執筆をした北畠親房の2人の歴史思想が挙げられる。
近世に入ると,生年順に,不敗のまま実戦を離れて独自兵法を完成,恩受けた城主の死に,「五輪書」を書上げて没した宮本武蔵,遅い登場ながら,養生に努めて長寿を保って,多分野に膨大な著作をし,晩年の"益軒十訓"が,大きな影響をもたらした貝原益軒,日本における陽明学派の始祖とされ,近畿に勢力を持った中江藤樹,近世思想が段階的に深化して行く元になる古義学を創始した伊藤仁斎,家宣が将軍になるや,ブレーンとして"正徳の治"を現出するも,理想に過ぎ失脚した新井白石,官学の朱子学を攻撃して播州に流され,赤穂義士,さらには維新の志士の精神的支柱になった山鹿素行,武士道に関する談話を藩士田代陣基が筆記して「葉隠」が成立,後世大きな影響を与えた山本常朝,そして,デザイン論で,背景となる哲学に取り上げた,独自の思想で学派を確立,観念より実利を重んじ,将軍以下広く影響を及ぼした荻生徂徠後には,徂徠門下ながら,道徳と経済バランスをめざす独自の説を展開,後世に大きな影響を及ぼした太宰春台,江戸中期に身分制度を根本的に否定,近年,その驚くべき先進的思想が知られるようになった安藤昌益,文化人類学要素をもった革命的思想「出定後語」「翁の文」を提示して,早世した富永仲基,生涯田舎村を離れず独学で,日本人離れをした大哲学を構築した三浦梅園,徂徠学を講じて朱子学を圧倒したため<寛政異学の禁>の標的となり,失意の中,放火自殺した亀井南冥,全国数十藩の財政再建,失明の乗り越え,驚くべき自由経済思想「夢の代」を著した山片蟠桃,「稽古談」ほか多くの著作講義で,商品経済の発達による富国説く画期的重商主義論を展開した海保青陵,鎖国下で合理的認識を先駆,日本で初めて世界地誌を著し,町人や百姓の心得も説いた西川如見,西洋流の天文・測量・地理を踏台に,重商主義的貿易論で大きな影響を与え,仕官せずに門弟を多数養成した本多利明,詩文・書画を愛し,各地を遊歴するなか著した「日本外史」が幕末志士に大きな影響を与えた頼山陽,独自の宗教的説と精力的活動で大きな影響及ぼすも,幕府に嫌われ,失意のうちに没した平田篤胤と,近世には,近代と比較にならないほど,多くの,ハイレベルな哲学思想家が輩出,このこともまた,江戸時代が長く続いた大きな理由の一つであったと言えるだろう。
近世の学問で,よく知られているのは,西洋の数学とは全く別に,日本独自の和算が盛んになり,その水準も,西洋に引けを取らないものだったということであるが,その和算の祖吉田光由は,豪商吉田家を受け継ぎ,吉田流算術元祖でもあった角倉了以の分家の医師の子に生まれ,数学に興味を持ち,了以の死去後は,子の素庵について,吉田流算術を伝授され,素庵から蔵書全てを譲られると,それらを手本に,江戸時代も始まってまもない,1627年,29歳の時,「塵劫記」を刊行。内容はもちろん,素庵の親友本阿弥光悦の挿絵装幀を得,普及し始めた算盤のマニュアルの役割もあって,大ヒット,その後も追加,編纂し直し,多色刷りと刊行し続け,1634年刊行の普及版「新編塵劫記」は,江戸時代を通してベストセラーとなる。その後,転変とするうち,同じ毛利門下だった今村知商が和算書を刊行したのに対抗,1641年,43歳の時,根本的に書直した「新編塵劫記」を,末尾に12の遺題をつけて刊行,1653年,55歳の時,この遺題に初めて挑戦した榎並和澄が「参両録」を書いて,答術を発表するとともに,自ら新たに8つの遺題を提出,以後,遺題継承が流行,和算が大いに発達,幕末まで続くのであるから,まさに,和算文化のデザイナといえる。
そして,西洋数学の先駆的内容含む高度なものに革新し,"算聖"と崇められる天才関孝和が登場し,その弟子で,自らも天才を発揮した建部賢弘が,その業績を体系化して解説,関を祖とする関流という,その時点でのトップの和算家が継ぐ仕組みが,江戸時代最後まで続くが,関孝和が,初めて筆算を採用したことの効果も大きかったと思われ,その点からも,関自身デザイナ的人物だったと言える。関流のほかにも,いくつかの流派が生まれ,幕末には,これらの流派すべてをマスターし,日本初の対数表ほか多くの業績を挙げた和算家小出兼政が登場する。和算はまた,暦をつくるための暦学,すなわち天文学と密接につながっているが,元禄時代には,碁方安井算哲の子ながら,棋力の限界を悟って天体観測に専念,貞享暦を完成し,天文方世襲へ至った渋川春海と,天明時代に登場し,伊能忠敬の師高橋至時をはじめ多くの俊秀育て,幕末までの天文方の主流を形成した麻田剛立を,デザイナ的人物として挙げておく。
博物学につながって行く本草学は,元禄時代に,動植物の研究で,好学の金沢藩主前田綱紀から藩儒に召し抱えられ,本草学の典拠とされてきた明の李時珍の「本草綱艮」を補おうとした綱紀の命で,稲生若水が「庶物類纂」362巻をまとめたのを端緒に,数多くの人物が現れて隆盛に向かうが,特に際立つのは,稲生若水門下の逸材松岡恕庵に本草学を学んだ小野蘭山で,師の死去後も独学で研鑽し,開塾すると,講義と執筆に専念,田沼意次時代に入った34歳には,「花彙」8巻を完結,のちに,そのオランダ語訳が,桂川甫周からシーボルトに寄贈され,そのフランス語訳も出版されるほどで,日本植物学を世界に知らしめただけでなく,70歳には,幕府に招かれ,幕命で,江戸期最大の博物誌「本草綱目啓蒙」をまとめて,81歳で没したが,シーボルトをして'日本のリンネ'と言わしめた巨人であった。その蘭山に入門した岩崎灌園は,直後に師が没するも,若年寄堀田正敦から後継として認められて,研究著作を続け,44歳の時,20年かけてまとめた,彩色した本格的な日本初の植物図鑑「本草図譜」96巻92冊を幕府に献上するとともに,富豪の本草家に借金し,豪華本として出版しており,そのまま,のちの牧野富太郎につながって行く。
さらに,天才平賀源内が,田村藍水から本草学を学ぶと,師を説得して,薬品会を開催し,物産会の嚆矢なり,物産学へ展開した直後に,田沼意次時代,いわゆる天明文化期に入るが,早くから奇石の蒐集に取りつかれていた木内石亭が,全国に知られるようになったのも,36歳のこの頃で,田沼意次の失脚後には,弄石ブームを起して華々しい老後を迎えただけでなく,生涯をかけた厳密な研究で近代考古学を先駆している。
日本の自然科学は,本草学によって始まったと言えるが,それが,近代につながるものとして開花するのが蘭学で,将軍徳川吉宗のが,享保の大飢饉に際し,「甘藷考」を献上してきた青木昆陽を登用して,甘藷の試作・普及に努めたことは良く知られているが,飢饉が収まると,吉宗は,昆陽を書物方に抜擢,オランダ語の学習を命じられた青木昆陽は,まず,「和蘭話釈」を著し,さらに,「和蘭文訳」を,吉宗の死去後も,10集になるまで続けたことに始まると言って良い。それを受けるように,オランダ語の本を見せられて発奮した中津藩医の養子前野良沢は,すでに46歳になっていたが,青木昆陽に入門するも,直後に,師が死去したため,藩に許可得て,長崎に留学,そこで購入した本のなかに,「ターヘルアナトミア」が含まれており,直後に江戸に出た際,杉田玄白に誘われて,死刑囚の腑分けに立ち会い,有名な「解体新書」訳出の中心的役割ながら名前掲載固辞したため,実際の解剖と照合した玄白が,蘭学の祖になるが,その後もオランダ語の研究を進めて,藩主から"蘭化"の号を名を与えられた前野良沢こそが,蘭学のデザイナであったと言えよう。その後の隆盛は記すまでもないが,オランダ語翻訳に専念,現行の天文物理用語,文法から,"鎖国"など一般語彙まで創出した志筑忠雄を代表に,わが国に化学を本格的に紹介し,現在も使用される多くの語を創作,西欧諸科学の導入に尽力した宇田川榕庵,西洋理化学の導入に尽力,化学・電気・蛋白等の訳語も創出,日本の科学史に画期を成した川本幸民などが,近代科学へのデザイナ的役割をした人物であろう。彼らとは別に,言語文学型において,京都蘭学の草分けで,「和蘭語法解」翻訳公刊し,近代日本の語学の基礎をつくった藤林普山も忘れてはならない。
近代の人文科学(歴史・地理・言語)のもとになった人物には,詳細な日本地図の伊能忠敬と,「群書類従」編纂刊行した塙保己一を別格としても,水戸学史論を代表し,「大日本史」の論拠を整えた栗山潜鋒,書誌や考古遺品用い,今日なお批判に耐える精確さで研究,金石文・古泉学の基礎を築いた狩谷掖斎,平城京と条理制を研究して初めて復原図を作成するなど,のちの奈良文化財研究所の礎を築いた北浦定政,宝暦事件で長期に逼塞の間,平安内裏の考証に没頭,復古図る光格天皇登場で一躍時の人になった裏松光世,緻密な紹介解説に画家の挿絵溢れる「都名所図会」が大ヒット,名所図会ジャンルの嚆矢になった秋里籬島,それに刺激された祖父が企画し,父が固めた「江戸名所図会」を完成。「武江年表」ほか記録編纂,詳細な日記も遺した斎藤月岑,民俗資料としても貴重な「北越雪譜」出版に生涯をかけた鈴木牧之,長く水戸藩学監を務めた後,幕府に召され,蝦夷関係史料を集大成し現行地名の漢字表記を選定した前田夏蔭など,官民問わず,優れた学者が輩出している。
明治維新によって,学問が西洋由来の科学になった近代について,いわゆる理系では,まず,近世の和算・暦学につながる理論物理学は,日本で初めて,世界的物理学者になり,土星型原子模型を提示して世界に広めた長岡半太郎を受け継ぐように,皆,カタチからアプローチするきわめてデザイナ的な人物で,中間子理論の湯川秀樹,ひも理論の朝永振一郎はじめ,ノーベル賞を受賞者も多く,明解な弁証法的三段階法で一世を風靡した武谷三男も,まさに,その一員であった。
蘭学の延長たる自然科学全体に広げると,日本の医学界を開拓した北里柴三郎,日本における近代鉱物学の創始者で,晩年には科学的な書誌学も開拓した和田維四郎,日本に理論化学を紹介し,世界水準にして行く一方,学術体制の整備にも尽力して"化学の父"になった桜井錠二,<敗戦>後の日本の脳生理学興隆の中心で,初めて"脳死判定"基準をまとめた時実利彦,30代半ばのフロンティア軌道理論で世界に知られ,60過ぎに,日本人初のノーベル化学賞になった福井謙一と,デザイナ的人物は枚挙に暇なく,とりわけ,世界で最初の栄養研究所を創設し,日本独自の栄養学を開拓,国家的栄養基準を主導した佐伯矩,探検による発見をもとに"照葉樹林文化論"を提唱,"分類の発想"とともに広く影響を及ぼした中尾佐助は,まさにデザイナであったと言えよう。
特記したいのは,日本の庭園の歴史を担う造園につながる林学で,デザイン三講のところで詳しく触れているように,デザインの極ともいえる明治神宮内苑の森を実現を主導した本多静六は,苦学して多大の業績を挙げ,"日本林学の父"となる一方,堅実な蓄財で"明治の億万長者"となり多大の寄付するなど,生き方そのものがデザイナの鑑と言える人物で,神宮内苑整備時に,本多の助手であった上原敬二もまた,その後,日本の造園学,造園設計,造園教育の確立を主導,さらに,本多教授のもと,1年先輩の上原と切磋琢磨した田村剛が,日本の国立公園行政で指導的役割をはたし,"国立公園の父"とよばれるに至るなど,まさに,デザイナ一家を形成している。
文系に移ると,まず,日本古来の学問である文学言語型で,全くの独学で,万葉仮名や漢字音を研究,文字字体体系化の先駆的業績を挙げ,第一人者になった大矢透や,留学もせずに英語の達人,英文法,英語教育の基礎確立,英語国でない諸国にも影響を与えた斎藤秀三郎を代表に,現代の国語学の生みの親となった上田萬年,その弟子で,音声学・民族学など幅広い分野で指導力を発揮し,晩年に,定番となる国語辞書「広辞苑」を生んだ新村出,国文法研究の基礎を確立した山田孝雄,近代国語学で傑出し,所論の大部分が学界の定説になった橋本進吉のほか,三上章や原田信一など,ユニークかつ際立つ日本語学者も多い。そして,画期的な国語辞書「言海」をはじめ,辞典の編修・文典の著述・国字問題に著しい業績を挙げた大槻文彦,30年以上かけ,大空襲を乗越え,中国の「康煕字典」をしのぐ「大漢和辞典」を完成した諸橋轍次という人物を介して,蒐集編纂型に目を向けると,独学で「大日本地名辞書」を刊行,能楽や宴曲でも偉大な業績をあげた吉田東伍,若くして豪農を継ぎ,空前絶後の「日本山嶽志」を著して自費出版,日本山岳会を支え続けた高頭式,無学歴ながら,近世文人の百科全書ともいえる膨大な伝記を書き残し,多大の影響を与えた森銑三,世界五十数カ国の民族音楽を訪ねて,音楽の意味を問い続け,大きな影響を及ぼした小泉文夫など,専門的学問と関係ないいわゆる素人のような人物が,学問の基礎とも言えるデータベースを作っていること,後世の人たちに役立つという点で,まさに,デザイナ的であることも忘れてはいけない。
人文科学型に目を転じ,中世・近世のところで述べたように,学問(科学)と言い切ることには躊躇する哲学・思想を別にすると,言文一致による史料の読み方で,日本史近代化の基礎を築いた三宅米吉,暗黒時代とされてきた鎌倉・室町時代を,初めて固有な価値持つ"中世"と位置付けた原勝郎,転変の後,俗事は夫に任せて自宅から一歩も出ずに研究,女性史学を確立した高群逸枝,中世町衆,とくに芸能を対象に"林屋史学"形成,学界のみならず市民層にも影響を与えた林屋辰三郎,"大塚史学"と称される独自の史観を確立し,広く"市民社会"派の人々を啓蒙した大塚久雄などの日本史学者のほか,わが国の実験心理学の創始者で,日本初の記号論理学者と言われ,哲学・論理学にも精通した元良勇次郎,民家こそ建築の原点と近代建築や都市計画批判,現代風俗を研究する考現学など独特思考を展開した今和次郎,比較文化学を開拓し,その確立と後進育成に努めて退官,長年の魅力的研究成果を次々発表した島田謹二などが挙げられる。
特記されるのは,独自の民俗学を開いた柳田国男で,兄弟皆が各分野で一流になるような家系に生れ,農政学を専攻して,農商務省に入るとともに,早大で講義し,著作を続けるも全く受け入れられずに挫折,日露戦争後の33歳の時,九州旅行した際,椎葉村など山間奥地を訪れ感動するとともに,古来からの人民を発見するとともに,岩手県遠野出身の佐々木喜善から伝承する話を聞いて魅惑され,翌年,遠野を訪れ,その翌年に,「遠野物語」を発表して,民族学研究を開始,明治天皇が没した翌年の1913年に,{郷土研究}を創刊し,44歳の時,貴族院議長らと対立して退官すると,翌年,{朝日新聞}に招かれ,紀行文を発表する一方,自宅で懇話会を開始,論説委員として7年間社説を担当した後には,方法論の確立に努めながら,後進を指導し,論文を発表,60歳になると,全国的な山村調査を実施し,全国の民俗学愛好家による{民間伝承の会}を組織し,機関誌{民間伝承}を刊行,敗戦後の72歳には,自宅に,民俗学研究所を発足させ,76歳には,文化勲章,86歳に「海上の道」をまとめて,翌年,没した。歌人だった折口信夫が,1913年に,創刊された{郷土研究}に投稿して,のちに,民俗学的国文学と言われる"折口学"を展開,肺結核で療養中に,柳田から,{郷土研究}への投稿を勧められた宮本常一は,二・二六事件のあった1936年,29歳の時,渋沢敬三の支援で,「周防大島」を刊行したのを皮切りに,各地を,徹底して歩くことで,日本の民俗学に新しい地平を開くなど,広く深く浸透して行くが,科学という点では,疑問符がついてしまうことも,否定できない。
西欧でも新しく広がり始めた社会科学については,日本の統計学の開祖杉亨二,日本私法学の開拓者梅謙次郎,日本における政治学を創始した小野塚喜平次,日本経済史学を開拓・確立した内田銀蔵,自由主義福祉国家論を先駆し,<大正デモクラシー>を先導した福田徳三,日本における都市社会学と生活論を創始した奥井復太郎,生涯かけた体系的著作「民法講義」で学界の源流になった我妻栄らがいるが,最もデザイナ的人物は,雁行形態論を発明,日本人学者理論で最も世界的になった赤松要であろう。戦後は,東大に復帰して復興期の経済政策を指導した有沢広巳,わが国における経営史研究の開拓者で,戦後改革や日本経済発展に主導的な役割を果した脇村義太郎がいる。
最後に,学問とするには無理があるが,現在の活動の分類ではここに入れざるを得ない,啓蒙・思想(著述分野の批評解説型と哲学思想型)について,おそらく,この論の「はじめに」で述べたような,科学,芸術に並ぶ,デザインという活動があれば,そこに入れられるだろうから,そもそもが,デザイナ的人物ということになるが,生年順に見ると,近代哲学の最初の移植者で,"哲学""理性""主観"等の語を考案,軍人精神確立にも寄与した西周,大ヒットの「西国立志編」など新思想の普及に努め,女子・幼児・盲唖教育に尽力した中村正直,まさに近代思想のデザイナと言える福沢諭吉,日本人初の哲学教授。欧米哲学を紹介し,"形而上"はじめ多くの訳語をつくった井上哲次郎,「輿地誌略」「西洋史略」など文明開化啓蒙者として貢献した内田正雄,合理的科学思想に徹して"妖怪博士"と呼ばれ,仏教の革新運動・国粋論的顕揚に奔走し,{哲学堂}を建設した井上円了,文化のデザイナでもある岡倉天心,ベストセラー「二千五百年史」はじめ在野を代表する名著を遺した竹越与三郎,日本のプラグマティズムを先駆した田中王堂,「善の研究」で衝撃をもたらし,"場所の論理"など,独自の哲学が大きな影響を及ぼした西田幾多郎,<維新>後否定されていた江戸時代の考証を在野で先駆,独自の学問的世界を樹立した三田村鳶魚,"国民思想史"の視点から厳密な文献批判で記紀の捏造を論証した津田左右吉,日本主義的科学論で戦時政策に関わり,敗戦でA級戦犯になって,服毒自殺した橋田邦彦,「"いき"の構造」によって日本の哲学に新生面,"実存"などの語を定着させた九鬼周造,大正期の「古寺巡礼」,戦時下の「風土」,戦後の「鎖国」と,常に日本の独自性を強調した和辻哲郎,戦前昭和期のもっとも輝かしい思想家で,「構想力の論理」は,そのままデザイン論といえる三木清,戦時下に反ファシズムの"羽仁史学"で影響を及ぼし,全共闘シンパとして「都市の論理」がベストセラーになった羽仁五郎,<敗戦>直後に,衝撃的な「第二芸術論」ほか,作品の新評価軸を提示し,文学界に甚大な影響を及ぼした桑原武夫,優れた企画展・野外彫刻展や賞の創設と審査など,戦後日本の近代美術館普及に尽力した土方定一,<敗戦>後,時流に対応して常に学界のトップランナーとなり,大きな影響を及ぼした清水幾太郎,<戦時>下に独自の中国観を育て,<日中国交回復>まで中国紹介啓蒙の評論活動をした竹内好,<軍国主義>時代に日本の美を称揚して一世を風靡,<敗戦>で文壇から抹殺されるも,復活した保田與重郎,「東洋人の思惟方法」以降,比較思想宗教の国際的権威となり,膨大な業績を遺した中村元,在野の評論家で,保守系メディアで活躍,時代を先駆し"山本学"ファンの多い山本七平,ユング心理学の紹介者・解説者として絶大な影響力を持った秋山さと子らとなる。
日本の社会の形成は,大陸からの仏教伝来によって登場した僧によって始まり,日本独自の教祖の輩出によって展開,いわゆる教団ができる以前に,民衆教化と社会事業に全力を投入,遺言により初の火葬となり,宇治橋造橋伝説もある道昭,知識集団組織して民衆を教導,膨大な社会土木事業を営んだ行基がいる。そして,聖武天皇・光明皇后の統治デザインによる,国民の"こころのシンボル"ともいうべき東大寺大仏造立には,その宗教的中核となり,開眼の後,初代東大寺別当に任ぜられ,開山になった良弁がいて,それに,協力した行基は,初の大僧正になる。その後も引き続いて,東大寺造営に生涯を賭けた技術官僚佐伯今毛人がいたこと,天皇・皇后が,藤原不比等のところで述べたように,道慈のモデルプランに基づいて,全国に国分寺建設を進めていったことなどで,聖徳太子以来の仏教立国が目に見える形になり,仏教は,人々の"こころ"を支える基盤になったのである。
これらの,いわゆる宗派・教団以前の僧たちは別にして,平安時代に,日本独自の仏教の端緒となる,真言宗を開いた空海と天台宗を開いた最澄以降,浄土宗の法然,臨済宗の栄西,曹洞宗の道元,浄土真宗の親鸞,日蓮宗の日蓮というように,いわゆる開祖となる僧が次々と登場するが,これら偉大な僧たちは,デザイナのレベルを超える存在であり,いわゆる宗派・教団として定着させた人たちこそがデザイナであったといえる。まず,真言宗を開いた空海は,文化,教育,社会事業まで実績を残した万能の天才で,伝説化し,マンダラを代表に,デザインの神様のような存在で,直接的に,弘法大師を敬う人たちは極めて多いが,真済や真雅が,東寺教団として定着させた宗派の信徒数は,現在,150万人弱。宗派としての広がりというデザインからみれば,権力者の宗教としては,天台宗と臨済宗が,いわゆる,民衆の宗教としては,真宗と日蓮宗が抜きんでていると言えよう。
空海と,ほとんど同時期に,最澄が開いた天台宗は,最澄を継いで天台宗を興隆,山門派の祖となり,藤原良房と伴善男両者から信奉された円仁と,天台宗を円仁に続いて興隆させ,園城寺を復興して,寺門派の宗祖となった円珍によって教団として定着し,公家を支える宗教になったばかりでなく,その後の僧のほとんどが,まず,比叡山で修行し始めるなど,現在に至る日本仏教の変遷の原点になるのである。70過ぎて家康に招かれ,100を超える長命で,江戸幕府創始期に幕府の宗教行政の中心になった天海は,天台僧であった。近年の,信徒数は,150万人余で,真言宗と変わらず,民衆のものにはなっていないことが分かる。
日本独自の仏教である念仏の祖空也は,教団形成に至らずとも,その伝承は,僧以外にも大きな影響を与え,慶滋保胤が,日本初の往生伝「日本往生極楽記」を著し,浄土思想を普及,源信が,「往生要集」を撰述し,公家社会の末法思想に対応する地獄極楽イメージ鮮明な仏教を創始,それに対応するように,専修念仏に開眼し,大変革期に続々登場する新宗派の開祖の嚆矢になった浄土宗の開祖法然が登場するも,なお公家社会に対応するもだったため,鎌倉幕府以降の武家政権下では,いわば底流のように目立たなくなってしまうが,現在でも,信徒数が600万人余りと2番目に多い宗派で,近代に入って,忽然と登場したのが,桁違いの頭脳と言われた渡辺海旭で,浄土宗初の留学生となり,社会事業はじめ,「大正新修大蔵経」刊行など膨大な業績を遺した。
法然の弟子,浄土真宗の開祖親鸞は,「教行信証」を著し,"悪人正機説"などで仏教を根本的に変革,自ら教団形成して,真に民衆のものとし,没後にも,浄土真宗の3代(法然・親驚・如信)伝持を主張,本願寺を創建し,真宗教団の基礎を確立した覚如,本願寺教団の再興して大発展の基礎をつくった中興の英主蓮如ら,優れた教団デザイナを輩出して,農民層に浸透,近代に入っても,廃仏毀釈に抵抗,国民教化政策を瓦解させ信教の自由を獲得,海外伝道や監獄教誨にも尽力した島地黙雷,廃仏毀釈に立ち向かうべく改革に取組み,教団を再確立した赤松連城,親鸞の精神を説き,本郷に求道学舎と求道会館を建設,学生・知識人を感化した近角常観ら,すぐれた僧を輩出して拡大,最近の信徒数ランキングでも,1位が本願寺派,2位が大谷派で,それぞれ,750万人前後になっている。
武家対応とされる禅宗(臨済宗)の祖は,武家社会に対応する新たな仏教禅宗(臨済宗)を将来・確立,後の茶道拓く茶の栽培利用を啓蒙した栄西で,栄西自身が源実朝に取り入り,鎌倉幕府も,天台宗はじめ,公家仏教と対抗すべく,武家を支える宗教として採用,執権北条時頼の統治デザインで,本格的に入替を進めて,国家の宗教に位置付けられ,足利義満が,統治の方策として,京都五山,鎌倉五山として,確立した。そして,中世の間だけでも,真言密教と禅を融合し,念仏とも未分化ながら,栄西を継いで,日本への禅導入を促した退耕行勇,東福寺の開山で,公武の帰依者多く日本初の国師号,静岡茶の祖でもある円爾弁円,東福寺三世で南禅寺開山の無関普門,大宰府の崇徳寺に定住して活動し,現代臨済宗の源流となった南浦紹明,公武の間に多数の支持者を得,七代の天皇から国師号,日本禅宗の主流になった夢窓疎石,日本最初の仏教通史「元亨釈書」を著わし,五山文学の先駆者で,かつ主流のもとになった虎関師錬,大徳寺を開創し,夢窓国師の禅風を厳しく批判した宗峰妙超,夢窓疎石の甥で,初代の僧録事,政界にも大きな影響力をもち,五山文芸にも優れ,中国にまで名声が及んだ春屋妙葩,学徳当代一で尊崇を集め,中国人が自国人の作と思ったほどの詩作者だった義堂周信,五山文学で周信と双璧,足利義満のブレーンとなり,五山を統轄,公武の帰依を受けた絶海中津,政治力に優れて足利義教・義政に重用され,日本初の外交史書「善隣国宝記」を撰した五山文学僧瑞渓周鳳,東山文化の芸術家らの指導者で,ユニークな生涯で"風狂"と"頓智小僧"のイメージが定着した一休宗純,今川義元の兵法参謀となり,大名間の和議斡旋に尽力,今川文化を育む役割もした太原崇孚と,名僧を輩出,近世には,足利学校を中興し,家康の命で出版事業"円光寺版"を遺した閑室元佶,最初の日本式の禅寺はじめ多くの寺を開創,難解な禅を庶民に理解できる禅へ脱皮させた盤珪永琢,名利求めず,衆生済度のために東奔西走,独自の公案体系確立し,臨済宗中興の祖となった白隠慧鶴,そして,近代に入ってもなお,儒学から禅門に入り,維新後,鎌倉禅を盛大に導く基礎を開き,"円覚寺中興の祖"となった今北洪川,国際的に行動し,多くの門人の生き方に影響を及ぼした釈宗演,その門人で,英米と深い関係を築き,仏教や禅思想を広く世界に紹介,内外の学者から尊敬された鈴木大拙と名僧の輩出は続くものの,なお,支配層の仏教の主流であって,民衆には浸透しておらず,信徒数ランキングに登場しない。
それに対して,同じ禅宗でも,坐禅を中心とする厳しい修行生活の拠点{永平寺}を開いた道元の曹洞宗は,個人の救済,修行であって,曹洞宗を初めて民衆化し地方に展開し,能登総持寺開祖になった瑩山紹瑾などにより,現在でも,信徒数360万人余りと,4位につけている。
幕府に「立正安国論」提示,受難の生涯の中,法華信仰を確立した日蓮に始まり,教祖の名がそもまま宗派の名になっている日蓮宗は,日蓮滅後の混乱した法華経の教えを糺すべく献身,京都本能寺を創建して,日蓮宗の教勢を拡大した日隆,迫害受けて"なべかむり日親"になるも,大赦後,本法寺復興,京都に日蓮宗の教勢を一気に拡大した日親が示すように,町人対応の宗教となり,国家権力と対抗するというより,宗教による支配を意識して,さまざまな派に分裂,近世以降の都市化とともに,その時々の新興宗教として発展する。明治維新時の,今日の日蓮宗の基礎をつくった新井日薩により,現在の日蓮宗本体での信徒数は,350万人弱で,曹洞宗に次いでいるが,近代に入っても分裂する体質はなお続いて,{立正安国会}{国柱会}を起こし,法華経に基く体系的教学で,宮沢賢治はじめ,多分野の人材に影響をおよぼした田中智学,「人生地理学」で名をなした後,日蓮宗に入信,弟子の戸田城聖とともに創価学会を創立した牧口常三郎が,戦時弾圧で獄死,戦後,再建して大教団にした戸田城聖は,政教分離の新憲法を誤魔化すように,公明党をつくって,政界に進出,近年には,与党になるに至り,信徒数も公称800万世帯を超えるという。一方,満州事変の頃,小谷喜美らが,法華信仰から起こした霊友会を,長沼妙佼とともに脱会し,日中戦争開始時に,{立正佼成会}を開いた庭野日敬は,戦後の妙佼死去後,大教団にするとともに,諸宗教間の対話や世界平和運動の先頭に立って活動,庭野の死去後は,表立った活動は見られなくなるものの,信徒数はなお,200万人を超えている。
ところで,日本独自の仏教である念仏を唱えるも,教団形成に至らなかった空也の後を継ぐように,鎌倉時代に,寺を持たず,生涯踊念仏によって布教行脚をした一遍が開いたとされる時宗は,一遍の最初の弟子の他阿が,一遍の死後に,確立発展させた事実上の開祖で,以上の宗派から外れた下層民対応のものとなり,世阿弥,善阿弥,本阿弥等々,姓に阿弥のつく人物は,時宗の信徒であることを示すとともに,他阿は,一遍を超える尊称になっているという。
仏教以外の宗教についても触れておくと,まず,神道について,文化庁の発表している人口,信者というより帰属,おそらく氏子数は,8,790万人と仏教のそれ,おそらく檀家数8,390万人をわずかに上回っていることに,やはりというか,驚きでもある。日本神話,神社体系等,そのスタートからデザインされたものと言われる神道でもあるが,歴史時代に入ってからは,仏教,儒教の広がりに対抗して,神儒仏混合の唯一神道を創始し,地方の神社に神位,神職に位階を授与する制度を創設した吉田兼倶こそが,最大のデザイナと言え,儒教の伸張を受けて,伊勢神道を神儒合一的に革新し,近世化に大きな役割を果たした出口延佳,神道を,儒仏に対抗する,国家経世の学として普及することを意図し,吉川神道を開いた吉川惟足,国学四大人の後を受け,日本中心思想の学風を樹立して,明治初頭の神祇行政の礎になった大国隆正,維新に際し,出直しを図り,古儀を尊重して復興整備に努め,国家神道の確立に貢献した御巫清直など,皆デザイナ的であり,そもそも戦死者を祀るという招魂社を構想した萩八幡宮司で,明治維新に際し,招魂社を建てるも暗殺された大村益次郎を継いで,靖国神社初代宮司になった青山清も,現在もなお靖国神社が不可侵のようになっていることから,恐るべきデザイナであったといえよう。
織豊時代のキリシタン,つまりカトリックはさておき,近代に入っての,プロテスタントのキリスト教信者の為した活動には瞠目すべきものがあるが,信者数は60万人どまりで,なお50万人いるカトリックとあわせても,110万人と少ない。キリスト教そのものについて,日本人をリード,神学的傑作と無教会主義を生み,多くの人材輩出した内村鑑三は,もともと,土木建築的指向もあったこととあわせて,デザイナであったといえる。
最後に,宗教と言うには無理かもしれないが,近世において,町人のための思想を確立し,その普及・実践に献身,社会教育やボランティアを先駆した石田梅岩の心学は,その後の影響からみて,大きいものであった。
いわゆる大衆社会の始まる近世において初めて,国策としての民生が意識されるようになり,近代を準備した。<享保の改革>を推進して幕藩体制を再構築した将軍徳川吉宗は,庶民娯楽を展開するほど,民生を重視,大岡忠相を町奉行に抜擢して具体化,忠相は,公平な裁判と優れた市政で,異例の出世,大名にまでなるが,彼によって発掘された多くの人材,川崎宿の疲弊を救い,「民間省要」で幕府徴用,治水通船で地域振興し,支配勘定格に至った田中丘隅などもいたことも忘れてはならない。
中世の終りに,すでにもっとも必要とされた医療においては,中国の金元時代に興った李朱医学を初めて日本に導入し,近世医学興隆の祖になった田代三喜が登場,田代に学んだ曲直瀬道三は,足利義輝以降,公武のトップ次々診察,医学校を開き,日本医学中興の祖となっていたが,吉宗時代に入ると,初めて産鉤を使用して母体を救い,正常胎位の発見,「産論」の刊行で大きな貢献をした賀川玄悦,人体解剖への抵抗が強い中,日本初の医学的解剖を行い,「蔵志」刊行して,実証的医学の契機になった山脇東洋,偏見を排し,名著多数の一方,長府藩製糖業も創始した永富独嘯庵,その示唆を受け,内服全身麻酔剤を案出し,世界に先駆けて全身麻酔手術に成功,華岡流外科創始者となった華岡青洲と名医が続出,佐倉に{順天堂}を開設し,診療とともに子弟教育した佐藤泰然によって,維新後すぐに,わが国初の私立病院が出現するに至るのである。
福祉面においては,元禄時代に,盲人の杉山和一(検校)が,管鍼術で治療範囲を飛躍させるとともに,開塾して広め,鍼術で唯一人神社になっておおり,まさに,視覚障害者教育のパイオニアであったが,その他は,幕末になってようやく,家業を盛り返すと,日本初の民営の窮民救済基金{感恩講}を構築した那波祐生,飢饉へ対処すべく諸マニュアルを執筆・頒布,後半生を全て救済活動に賭けた熊谷蓮心など,近代に続く人物が登場する。
古くからある教育面においても,近世になると,栄利求めず塾で教育に努め,朝鮮通信使の高評価で幕府儒官となり,新井白石ら逸材輩出した木下順庵,{懐徳堂}の黄金期を形成し,松平定信諮問に超合理的経世論「草茅危言」献上した中井竹山,豊後国日田で{咸宜園}開き,卓越した精神と近代的教育で,全国から多くの俊才を集めた広瀬淡窓,そして,{松下村塾}より早く{適塾}を開き,維新に活躍する多くの人材を育てた緒方洪庵に至る,教育そのものを本業とする人物が輩出する。
近代に入って,明治維新の新政府においても,医学行政官として,ドイツ医学の採用決定に貢献をするも,不遇の晩年となった相良知安,近代医療や衛生を先導し,女子の医者への進出を支援するなど,時代に先駆けた長与専斎,唱歌・体操・教科書・教育学など文部行政で先駆者となる一方,余生を吃音矯正に捧げた伊沢修二,帝国図書館設立を実現,その発展と館員育成に奮闘するも,更迭された"日本の図書館の父"田中稲城,長く東京美術学校長をつとめ,文展の創設はじめ,美術行政教育を長期に主導した正木直彦など,優れた民生官僚が輩出するが,その多くは,大久保利通の人材発掘によっている。民間においても,一貫して人民主権を説き,部落解放論,癌宣告などにも著しい先進性を示した中江兆民という優れた啓蒙者を得,いわゆる自由民権運動を経て,"民本主義"を唱えた吉野作造らによって,<大正デモクラシー>を迎え,大衆文化が開花するが,その頃には,政府の方でも,長く文部行政を主導し,多くの制度改革を実現した岡田良平,官僚として文部行政の中枢的位置を占めた澤柳政太郎が,退官後,成城小学校を中心に新教育運動を指導したりしている。以下,近代に入って飛躍した,民間における社会活動についてみていくこととする。
まず,医療型では,戊辰戦争の箱館で敵味方無く治療して日本赤十字を,貧民救療で民間福祉を先駆した高松凌雲,<西南戦争>で戦傷者を官賊の別無く救療する{博愛社}創設し{日本赤十字社}になった佐野常民,維新直後に陸軍軍医制度を確立し,引退後,大磯に日本初の海水浴場を開いた松本良順,私財を投じて明治薬学専門学校ほか2校を創立,医学用語を統一した画期的辞典も刊行した恩田重信,明治天皇詔に触発され,医療の社会化の実践を先駆し,医業国営論を提唱した鈴木梅四郎,日本の精神医学を開拓し,多くの近代精神医学者を育てた呉秀三,その教えを受け,精神病院に新風もたらし,神経症に行動中心の"森田療法"を開発,多くの信奉者を得た森田正馬,わが国最初の女医養成機関(後の東京女子医大)を創立,女性の教養と地位の向上につとめた吉岡弥生,梅毒特効薬で世界初の抗生物質サルバルサンを開発,多くの患者を救い,医に生涯をかけた秦佐八郎,石原式色盲検査表はじめ,色盲研究に多大の貢献をした石原忍,"オギノ式避妊法"を開発して世界に貢献し,子宮癌にも独自の手術法を考案した荻野久作,日本の植民地下の台湾人で,独自の思想「真・善・美」による杏林大学・病院を創立した松田進勇らがいる。
福祉型では,それぞれのハンディを,それぞれに根本的に支える方策などをデザインした人物として,キリスト教出版事業で獄中体験,出獄人保護運動に努め,"わが国免囚保護事業の父"になった原胤昭と,監獄改良に取り組み,制度廃止後も家庭学校で非行少年の感化に務め続けた留岡幸助,日本の監獄学の草分けで権威となり,退官して事業を推進,現在の民生委員制度の原型もつくった小河滋次郎,日本点字の父石川倉次と,視力障害を契機に,点字楽譜の祖となり,回復後は,家業の医師として名を成した佐藤国蔵,最初の日本人キリスト教社会事業家で,孤児院を創始し,"近代社会事業の父"といわれる石井十次,精神薄弱児問題に生涯を捧げ,収容施設を創始し,教育を開拓した石井亮一,大阪府知事になるや,方面委員規程を公布,全国統一の制度となり,現在の民生委員制度につなげた林市蔵,晩年になって,障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会を結成し,次々と成果を挙げた矢島せい子,自閉症児は治癒不可能という世界的学説を覆し,"生活療法"を唱えて実践した北原キヨらがいる。
教育型では,幕末に蘭学塾を開き,<維新>で海軍操練所の教師に招聘され,異色の{攻玉社}を始めた近藤真琴,幕臣として<戊辰戦争>に敗れた士族子弟救済に尽力,キリスト者として青年教育に生涯をかけた江原素六,アメリカで信者となって維新後に帰国,{同志社}と日本組合教会の基礎を確立した新島襄,大隈重信を支えて東京専門学校時から中核となり,日本有数の私学に築き上げるまで,生涯をかけた高田早苗と,ともに発展させ,早稲田実業を創立した天野為之,7つにして最初の派遣女子留学生,女子教育に目覚めて奔走し,女子英学塾を創設した津田梅子,官僚として文部行政の中枢的位置を占めた後,成城小学校を中心に新教育運動を指導した澤柳政太郎,独学で,児童心理学研究草分けとなり,全人教育に生涯をかけ,感銘を与え続けた高島平三郎,理論・実践両面から,児童教育・新教育運動をリードし,"日本のペスタロッチ"と言われる野口援太郎,言文一致の唱歌を創始し,その普及に生涯をかけ,童謡流行の先駆になった田村虎蔵,婦人記者の先駆,夫と{婦人之友}発刊後,キリスト教に基く{自由学園}創設した羽仁もと子,最初の受験参考書がヒット,{考え方研究社}を興して多数著作刊行し,受験屋として有名になった藤森良蔵,全人教育を唱えて成城学園町を開発後,理念実現に向けて玉川学園を創設し,長期に実践した小原国芳,洋裁学校と洋裁店を開設し,長期にわたって,服飾デザイン界を主導した山脇敏子,日本初のOLとなった後,{ドレスメーカー女学院}を創設,服飾デザインの発展に生涯をかけた杉野芳子,独自の才能教育"スズキ・メソッド"を開発,世界に普及し,奏者を輩出した鈴木鎮一,早くから栄養問題を啓蒙,<敗戦>後,基礎食品群を提唱,長寿社会化への道を開いた香川綾,{東海大学}を創立してマンモス大学へ発展させ,国際的に幅広く活動した松前重義,<敗戦>直後に{子供のための音楽教室}を開設,小澤征爾ら逸材を輩出した斎藤秀雄,教師こそが初等教育の原点と,教組と国との間に立って,全国的な模範となる実践活動をした斎藤喜博,女性の生涯学習から始め,全ての人間に広げた場{東京コミュニティカレッジ}を設立した小泉多希子らがいる。
そして,近代に入って一気に広がった解放型では,まず,部落解放について,維新直後に穢多非人廃止を訴え,晩年は未解放部落の融和事業に専念した大江卓,差別撤廃運動をするうち,政策転換した政府に登用され,融和事業を推進した三好伊平次,{水平社}名考案し創立大会開催。戦時下の国家社会主義も,戦後は部落解放同盟リードした阪本清一郎,次に農民,労働者解放で,{日本農民組合}を創設して以後,農民関連組織の先頭に立って政治活動を続けた杉山元治郎,日本初の近代的労働組合を組織し,生活協同組合も先駆した高野房太郎,{友愛会}を創立,ILO創設にも参画して急発展させ,労働運動右派の大御所として君臨した鈴木文治,{友愛会}を日本労働総同盟とし会長,日本国憲法下初代衆議院議長になった松岡駒吉,さらに,女性解放で,廃娼運動に生涯,少額寄付の大衆参加策を次々と発案し,キリスト者として人生を全うした久布白落実,{青踏}発刊,女権宣言して端緒を開き,戦後,日本婦人団体連合会初代会長になった平塚らいてう,婦人参政権運動一筋に生き,戦後は理想選挙を唱えて参議院議員となり,圧倒的な支持を得た市川房枝,大正期に婦人セツルメント運動始め,<敗戦>後に{主婦連}創立,消費者運動の草分けになった奥むめお,そして,占領からの解放で,沖縄復帰運動に尽力し,初の公選で琉球政府主席,復帰後初の沖縄県知事となった屋良朝苗らがいるが,現在もなお,女性解放は途上にあり,あらたに,障害者差別からの解放,いわゆるLGBTと,差別問題は尽きない。
最後になったが,本論における"活動"に,直接関わる度合いの高いものとして,生きるための経済・殖産・実業を取り上げる。
古代から,国庫の収入源は農業であったが,それを含めて,殖産・経済が国策として取り上げられるのは,六角定頼を初見として,戦国武将の多くが始めた楽市を,織田信長が,統治のデザインの一つ,楽市・楽座令として確立したこと,また,豊臣秀吉の検地は,農業からの収入増と一体であったことから,まさに,近世の始まりを告げるものになった。徳川政権初期の,財政基盤の確立し,地方巧者として,以後の手本となった伊奈忠次に始まり,筑後川堤防築造で三方潟開発の大事業を実現したのを始め,業績多数で,"治水の神様"になった成富兵庫,川崎宿の疲弊を救い,「民間省要」で幕府徴用,治水通船で地域振興し,支配勘定格に至った田中丘隅,一揆で大庄屋から流浪の身,30年放浪の後,高崎藩に抱えられ,江戸時代で最も優れた「地方凡例録」を著した大石久敬,藩主上杉鷹山の施策を実質的に推進,サバイバル書「かてもの」ほか膨大な著作を成した莅戸太華,幕末の,幕府きっての切れ者でフランスとの交渉にあたり,多くの偉業をなしたが新政府軍斬刑になった小栗忠順と,幕藩それぞれに,優れた殖産技術型官僚がいた。
民間でも,私財投じて開墾後,貝原益軒の影響受け,生涯をかけて日本初の体系的農書「農業全書」を著した宮崎安貞,日本で最も早く書かれ,また寒冷地における優れた農業技術書「会津農書」を著した佐瀬与次右衛門,村起こしのために独自の農業技術史論「百姓稼穡元」はじめ,多くの著作を成した石田春律,江戸中期に合理的農業技術に関する多くの著作を成し,明治維新後に大きく評価された大蔵永常,広大な荒地の白糸台地を灌漑する通潤橋を企画・実現し,没後,神社に祭られた布田保之助,農協の先駆となる世界初の産業組合で農村振興したが,革命恐れる幕政の犠牲になった大原幽学,そして,没落実家を自力再興後,農村を企業的組織とする"報徳仕法"で諸藩の農村復興した二宮尊徳と,その門弟で「報徳記」を著わし,報徳社運動の指導者の一人になった富田高慶,同じく,門下で,報徳運動を指導,箱根湯本で福住旅館を再興し,一帯の観光事業を推進した福住正兄らがいる。
明治維新後の近代に入っても,幕末きっての財政通で,藩の殖産政策・新政府の金融政策に関与,「五ヵ条の誓文」原案も起草した由利公正,郵便制度の創始・電話事業の開始・国字改良など,維新直後のメディア近代化に決定的役割をした前島密,維新政府の天才の一人で,日本銀行を創設,"松方財政"で,資本主義社会の基礎を築いた松方正義,工部省・工学校を創設し"日本の工学の父"。霞が関官庁街の計画者で,訓盲院も開校した山尾庸三,駒場農学校・大日本農会・山林会・水産会・博物館の創設など,産業振興の基礎をつくった田中芳男,日本最初の博物館を創設し,博覧会事業に治績をあげた町田久成,日本初の鉄道建設に従事し,機関車の国産化のため会社を設立,"鉄道の父"になった井上勝,大日本水産会創設し,水産伝習所初代所長となり,わが国近代漁業を創始,洋上捕鯨にも先鞭をつけた関沢明清,東京工業学校を創設して校長となり,工業教育の最高指導者となった手島精一,産業近代化の指針を次々建言するも罷免,以後,民間で奮闘するも不遇の前田正名,日本の近代鉄鋼技術を確立し,鉄冶金学の発展につくした野呂景義,工科大学初代学長・工学博士第1号で,退官後も,土木行政・工学を全面的に指導した古市公威,現在のいちごのルーツなど,日本の園芸界の基礎を築き,新宿御苑改修で造園学の祖にもなった福羽逸人,日本の近代漁業振興の最大の指導者伊谷以知二郎,八幡製鉄の創業を担い,日本鋼管を創立するなど,"近代産業の父"今泉嘉一郎,パナマ運河開削に唯一の日本人技術者,荒川放水路などの大事業,技術者のモラルも示した青山士,戦時体制下,{理化学研究所}所長を務め,理研コンツェルンを形成して,人材を輩出した大河内正敏,満鉄調査部で中国の鉄道を指導,<敗戦>後は,新幹線実現の中心人物となった十河信二と,戦時下に名機D51を設計,"新幹線"を構想し,<敗戦>後,十河総裁のもとで実現させた島秀雄というように,その後の時代をデザインした殖産技術型官僚は多い。
そのまま,社会分野の殖産型につながり,郡山の豪商で,安積開墾の中條政恒を援け,開成社を組織し,近代郡山の基礎をつくった阿部貞行,天竜川治水,磐田植林,三方原開墾,出獄人保護など,社会のために一生を捧げた金原明善,維新直後に横浜の基盤整備事業をして高島町に名を遺し,"高島易断"の開祖にもなった高島嘉右衛門,7つの娘梅子を留学生に出すほど開明的で,欧米農業の導入紹介に努め,禁酒・禁煙・盲唖運動もした津田仙,明治時代における報徳運動の最高指導者で,俊秀輩出,日本最初の信用組合の創設者岡田良一郎,明治中期の老農。農村計画やイネの品種はじめ精緻かつ膨大な書を著し,全国遊説もした石川理紀之助,父の後を継ぎ,新時代に対応すべく試行錯誤,三河農会を結成し,地域農業と金融界に貢献した古橋義真,ピューリタンのユートピア建設と類似した精神で,{赤心社}による北海道農場開拓事業に邁進した澤茂吉,十和田湖ヒメマス生みの親で,十和田湖観光開発の基礎をつくった和井内貞行,'稲のことは稲に聞け,農業のことは農民に聞け'という言葉で有名な横井時敬,石原莞爾のブレーンとして国家統制経済をめざし,戦後の"日本株式会社"の礎となった宮崎正義,農民教育を推進,"日本のデンマーク"愛知県安城の礎を創り,自由な生き方で多面的貢献をした山崎延吉,多数の組織の長務め,"産業組合の独裁王"と称せられるに至った千石興太郎,農政記者でスタート,{家の光}を成功に導き,農山漁村文化協会を創立してユニークな活動をした古瀬伝蔵,農事試験場で水稲新品種を次々開発,多数の小唄等を作詞作曲し,全国的展開を図った岩槻信治,戦後,農山漁村文化協会を率い,独自の文化運動を展開した岩渕直助らがいる。
さらに,国策・民間のいずれとも言えない,国につながる民という形で,初の実業といえる豪商が登場するのも,織豊時代からで,徳川時代には,維新後の財閥,さらには現代につながる財閥系の企業が誕生していることからも,実業面で,近世は,近代を準備,それ以上に,欧米の資本主義さえ,先取りしていたと言えるのである。織豊に接近して豪商の先駆けとなり,博多の都市計画や朝鮮との交渉に関わった島井宗室を皮切りに,博多復興し諸産業振興して"博多三傑"も失意の晩年,茶の湯研究史料「宗湛日記」を遺した神屋宗湛,武士・商人として,早くから家康を支え,その天下取りに貢献した茶屋四郎次郎(初代・清延)という初期の豪商を経て,2代将軍秀忠時代には,銅吹き屋の集まる京都で,吹屋{泉屋}を開業し,住友銅業の業祖とされる蘇我理右衛門が,3代将軍家光時代には,醸造業で出発し,大名貸,海運業まで展開,鴻池の祖になった山中新六,4代将軍家綱時代には,革新的商法を創始,多くの子に恵まれ,商売の各分野を担当させ,財閥三井家の家祖になった三井高利が登場し,幕末維新の動乱期に,無学文盲も才覚で{三井}番頭になり,大財閥への基礎築き,日本経済近代化に貢献した三野村利左衛門と,住友家を存亡の危機から救い,住友財閥と大阪経済発展の基礎をつくった広瀬宰平という人物が出た三井・住友は,敗戦の財閥解体も乗り越えて,現在に至っているのである。そして,維新後に,維新直後に政府と手を結んで海運業を独占,巨利を得て,三井とも壮絶な抗争をして早世した岩崎弥太郎は,弟岩崎弥之助,子岩崎久弥という良き後継を得て,三菱財閥の祖になったのである。
また,江戸幕府創設期には,豪商吉田家の分家だった角倉了以が,自らの意志で,安南貿易による巨富を河川開発につぎ込んで大きな貢献をし,明暦の大火で巨利を得た河村瑞賢が,陸奥と間の東西廻り航路開拓ほかに尽力,遂に士族に至ったように,国土開発企業のルーツも近世に始まり,幕末維新期には,諸河川を開削して通船事業を支配,初期薩長交易を主導し,志士を強く支援した中野半左衛門(景郷)や,横浜開港を機に西欧建築の様式を吸収,傑作を遺して,{清水建設}の祖となった清水喜助(2代),三都定飛脚問屋の当主だったが,維新で,官営郵便の創業で打撃を受け,陸運会社に転換して成功した吉村甚兵衛といった人物も登場する。
維新後には,欧米と対抗すべく近代化を図る国策に呼応して,西南戦争で巨利挙げ{藤田組}創始し,大阪財界主導した藤田伝三郎,コークスという当時廃棄物でコストゼロの資源に着目,セメント工業を興し浅野財閥になった浅野総一郎,三大遠洋航路開設などで{日本郵船}を世界最大級に発展させ,日本企業の海外進出の航路を確立した近藤廉平,地方政界から中央に出,東武鉄道再建し"鉄道王"になった根津嘉一郎,日本鋼管を創立し経営,日本製鉄への合同拒否し,民営製鉄業リーダーになった白石元治郎,福沢諭吉の婿養子で,相場師で財をなし,様々な仕事に熱中しながらも余裕失わず,近代日本の電気産業の基礎をつくった福沢桃介,"電力王"になるも戦時の国家管理に反対退去,戦後に九電力体制発足させ"電力の鬼"になった松永安左ヱ門,官僚から転じて,"電鉄王"になり,土地開発から東急コンツェルンを構築,教育にも貢献した五島慶太,早くから石油販売,<敗戦>後,国際石油資本・政府・GHQと闘い,文化事業にも貢献した出光佐三,箱根開発で五島慶太と死闘,{西武グループ}を創り上げた堤康次郎,海外油田の開発などで活躍し,戦前は"満洲太郎",戦後は"アラビア太郎"の愛称を得た山下太郎など,錚錚たる人物を輩出するのである。
製造業への橋渡しとなる発明技術については,近世末に,新式の帆や運送船を開発,築港にも従事,海運の振興に貢献し,諸大名に知られた工楽松右衛門,独創に富み,オランダ銃もとにした気砲など,次々と発明して人々を驚嘆させた国友藤兵衛,実業にも役立つ多くの機械や装置を開発し,塩田開拓などで藩財政改革にも功績を遺した久米通賢と,実用に供する発明をする人物が続々登場,極めつけは,幼時より次々と発明,世界に優る万年時計に至って,天才的技術者と言われ,維新後には企業化して,{東芝}の祖になった田中久重で,まさに,技術立国日本を象徴する人物であった。その後も,廃仏毀釈で失職し転換,理化学機器を発明して{島津製作所}を興した島津源蔵(初代)と,後を継ぎ,発明や製品化の才能で,大企業に発展させた島津源蔵(2代),{日本楽器製造(ヤマハ)}を創業,ピアノの国産化に成功し,大発展の基礎をつくった山葉寅楠,わが国電気工学界初期の指導者で,{東芝}ルーツの片方{東京電気}を創業し,"日本のエジソン"といわれる藤岡市助,自動織機の発明改良に生涯をかけ,{豊田紡織}設立,大自動車会社{トヨタ}の祖となった豊田佐吉,{立石電機(オムロン)}創業し,オートメーション・システム機械で,世界的企業にした立石一真といった,発明家で企業家といった人物の一方で,日本初の電気雑誌{電気之友}を創刊し,開発・啓蒙に努め,電話掛け言葉'もしもし'も発案した加藤木重教,日本初の本格的バイオリン"スズキバイオリン"が世界的になった鈴木政吉,「服部時計店」など銀座の風景に貢献し,職工問題や新工法に挑戦し続けた建築家伊藤為吉,わずか5分の遅刻で受験できず電気時計を発明,動力源として,世界に先駆け乾電池を発明した屋井先蔵,"八木アンテナ"を発明するも無視されるが,イギリス軍の戦利品から,一躍に世界的評価を得た八木秀次,写真電送法を発明し世界的に普及させた丹羽保次郎,自動車安全のエアバッグを世界に先駆けて発明するも,冷笑され,負債抱えて無理心中した小堀保三郎,戦時下にブラウン管や受像回路を発明,テレビ放送の基礎築くも<敗戦>で評価が遅れた高柳健次郎,旧制中学の時に多極真空管を発明し,日本のエレクトロニクスを開拓した天才的技術者安藤博というように,企業化せずとも,世界的な発明をした人物にはことかかない。
どちらかと言えば,発明よりも企業化の方が優先している人物として,実業分野の製品生産型をみると,開港で巨利を得,維新政府から委嘱され,三菱に対抗する造船所のちの{川崎重工業}を創設した川崎正蔵,{森村組}創設し,{ノリタケ}{東洋陶器}{日本碍子}に至る一流窯業企業群のルーツになった森村市左衛門,前田正名の言葉に触発され,{郡是製糸(グンゼ)}を設立し発展させた波多野鶴吉,時計国産化を先駆,{服部時計店}を設立し,飛躍を重ねて,"東洋の時計王"に至った服部金太郎,日本の鉄骨建築を先駆して震災復興に貢献,横河グループ創業者になった横河民輔,水道管製造から始め,産業機械等総合メーカーとなる礎までつくった{クボタ}の創業者久保田権四郎,工業振興のリーダー足らんと大志,久原房之助に出会って,日立製作所の礎をつくるに至った小平浪平,わが国自動車工業のパイオニアで,小型車の代名詞"ダットサン"とタクシーが登場する契機になった橋本増治郎,日本初の民間飛行機製作所設立して大軍需会社にし,戦時体制下は政治家として活動した中島知久平,家業を発展させるべくゴム業界に進出,{ブリヂストン・タイヤ}を興して世界的企業にした石橋正二郎,シャープ・ペンシルで成功も大震災で出直し,{シャープ}を創業し,世界的電機メーカーにした早川徳次,町工場を総合電機メーカーに発展させ,経営哲学で<敗戦>後の復興象徴,世界的存在になった松下幸之助,{リコー}創業,戦争前後を代表する経営者で,常識の裏をかくアイディア社長として一世を風靡した市村清,<敗戦>直後に自動車会社を設立,オートバイから出発し,世界の{ホンダ}に発展させた本田宗一郎,{日本電気}を情報機器産業化して初の生え抜き社長になり,身近なものなるように努めた小林宏治,<敗戦>直後に{ソニー}を興し,盛田昭夫と共に世界企業に発展させた後,幼児教育に尽力した井深大といったところになろう。
そして,日ごろ,いわゆる消費者につながる企業,農水食品型,販売サービス型,メディア娯楽型も,大衆文化始まった近世に登場,例えば,天明期に髙津伊兵衛が創業した{にんべん}は,削り節やふりかけ,調味料など,業界最古参の水産加工品メーカーであるが,一般には,日本橋の老舗の店として知られ,化政期に,京都の呉服店の丁稚奉公から,時流に乗って古着専門のを開店した飯田新七が始めた{高島屋}は,業界としては衰えつつあるデパートにおいて,唯一,力を保っている。維新後について拾ってみると,直後の文明開化に"あんパン"を発明,大ヒットで宮内省御用達,{木村屋}の祖になった木村安兵衛,福沢諭吉に共感,維新直後に,外国書籍輸入以降幅広い事業に取組むも,挫折した{丸善}創業の早矢仕有的,牛鍋ブームに乗り,20余人の妾に次々とチェーン店を持たせて,{いろは}王国を築いた木村荘平,{三井物産}から{日本麦酒}の経営に転じ,三社合同の{大日本麦酒}設立して君臨,"ビール王"になった馬越恭平,薬事官僚になるも,医薬分業を目指して下野,{資生堂}薬局を興して化粧品産業へと展開した福原有信,国産初の両切り紙巻タバコを発売,人気銘柄次々で"日本のたばこ王"になった村井吉兵衛と,度肝抜く広告で,日本人の喫煙スタイルを紙巻タバコに一変させた岩谷松平の壮絶な争い,真珠養殖に取り組んで成功,鑑定家としても一流の折り紙,"世界の真珠王"となった御木本幸吉,,熱心なクリスチャンで,"そろばんを抱いた宗教家"といわれた,{ライオン}創業者の小林富次郎,浅草に{神谷バー},牛久にワイン醸造所{シャトーカミヤ}創設,洋酒文化を拓いた神谷伝兵衛,日本初の百貨店{三越}を創業して経営改革を進め,人々の消費行動を根本的に変革した日比翁助,様々なアイディアを次々具体化して,別府温泉を世界に知らしめた油屋熊八,"花王石鹸"の製造・販売をスタートに,宣伝工夫で発展,油脂石鹸業界に君臨した長瀬富郎,酪農を導入して,{雪印}の前身となる組合連合会にまで発展させた"北海道酪農の父"宇都宮仙太郎,{大洋漁業}を創立,<敗戦>直後の決断で,日本最大の漁業会社とする礎を築いて没した中部幾次郎,池田菊苗のグルタミン酸ソーダの特許を得,全く新しい商品"味の素"とし,大企業に発展させた鈴木三郎助,高峰譲吉のタカヂアスターゼを核に,一商人から世界的製薬企業{三共}へ発展させた塩原又策,放浪体験と信仰をもとに,日本初のドライ・クリーニングを開発し,{白洋舎}を創業した五十嵐健治,{カルピス}創業し<大正デモクラシー>象徴する"初恋の味"など,卓越したアイディアマンだった三島海雲,{サントリー}のルーツ{寿屋}を設立し,本格的国産ウィスキーの販売を始めた鳥井信治郎,{寿屋}に招かれ国産初のウィスキー製造も失敗,北海道に渡って{ニッカウヰスキー}興した竹鶴政孝,月賦販売の{丸井}を創業,<敗戦>後,若者ショッピングへと発展させ,クレジット社会に先鞭をつけた青井忠治,"アリナミン"の開発に成功し,武田薬品工業を業界トップに押し上げた(6代目)武田長兵衛,美容学校設立を皮切りに,化粧品や美容器具の販売まで多角的な経営で,山野美容帝国にした山野愛子,女性下着会社{ワコール}を興し世界的企業にした塚本幸一,日本で初めて美容を総合的に指導するチャーム・スクールを開校,その後も革新的に活動した大関早苗らを挙げておく。
最後に,いわゆる実業界において,消費者との関係が特殊な,実践分野のジャーナリスト型とも一体のメディアと,芸能分野などと一体の娯楽に関わる企業についてみてみると,前者においては,近世天明期に登場し,反骨精神をもって江戸を代表する出版業者になるも,<寛政の改革>によって失意の最期になった蔦屋重三郎,後者においては,能舞の観世座や,浄瑠璃の竹本義太夫など,演じる方が主であった人物が多数おり,歌舞伎の明治座など,特定の人物を挙げにくいものも多いので,ここでは,幕末に,人形浄瑠璃を復興させ,現代につながるその代名詞文楽座の始祖となった植村文楽軒を挙げるに止める。
元手が少なく,誰でも挑戦できることから,維新とともに,爆発的に増大した新聞については,幕臣としてフランス交渉するうち<明治維新>,即座にジャーナリストに転身し,先導的役割をした栗本鋤雲,自ら新聞を発行して開化期の風俗を面白可笑しく描き,維新直後の文学空白期を埋めた仮名垣魯文,幕末に多くの著訳を成し,<維新>に,日本人による初の新聞を発行した柳河春三らに続いて,"国民主義"の{日本}の社主・主筆として言論一筋に生き,正岡子規を世に出した陸羯南,蘇峰の{国民之友}発刊翌年,{日本人}を発刊,哲学的に幅広く発言し,学界にも影響を与えた三宅雪嶺,{国民之友}{国民新聞}で一世を風靡も,変節して戦時体制に協力,<敗戦>後文化勲章を返上した徳富蘇峰など,自らの意見を公表すべく新聞を発行したジャーナリスト型が挙げられる。
企業として確立したものは,大阪で{朝日新聞}創刊に参加,所有権を譲り受け,東京に進出して大発展の基礎をつくった村山龍平,{藤田組}支配人のまま,{毎日}経営に参画し,{朝日}に拮抗する企業として確立した本山彦一,日本初の推理小説を出版後,{万朝報}を発刊,翻案小説と暴露記事で爆発的売れる大衆紙を成立させた黒岩涙香,仙台で{河北新報}を発刊,有力地方紙として全国に知られるに至る一力健治郎,新聞への情報提供や広告掲載という点から,他に先駆けて通信と広告事業を扱う企業を着想し,後に大企業に発展する{電通}を創業した光永星郎,反権力大衆新聞{二六新報}を刊行し,<日露戦争>前夜に一世を風靡した秋山定輔,警察官僚から転身,{読売新聞}を再興し,プロ野球を始め,戦後は民間テレビ局を開設した正力松太郎らがいる。
その他,{東洋経済新報}で長く啓蒙活動,<敗戦>後に首相の座につくも,病気で潔く引退した石橋湛山,リベラリストとして,日本国家の進む方向に絶えず危険信号を送り,抵抗を続けた桐生悠々の2人が特筆される。{朝日新聞}が,現在でも特別扱いを受けているように見えるのは,徳富蘇峰・石河幹明とともに"三名主筆"と称され,作家の起用など特筆すべき足跡を残した池辺三山,{大阪朝日新聞}で,民本主義の言論を主導するも,"白虹事件"で不遇になった鳥居素川,百年先を見据えた名記者で,新聞社の体制を次々と革新した杉村楚人冠,自由主義最大の論客として発言続けたが,戦時下インサイダーに転じた長谷川如是閑ら,人材に恵まれたことも大きい。
大正デモクラシーによって,飛躍した出版に目を向けると,百科全書家で,ベストセラー「食道楽」後,食と身体の研究,生食・断食・穴居まで実践報告した村井弦斎,反骨の新聞・雑誌を次々と創刊し<大正デモクラシー>を先駆した宮武外骨,<日露戦争>以降,時流に合わせて次々と主張,直接購読雑誌は戦後まで愛読者のいる茅原華山,論壇を指導し,{中央公論}を権威ある総合誌に育て上げたが,病気で早世した滝田樗陰らの役割は大きいが,浮世絵の保存・研究及び普及と新版画の創製出版に尽くした最後の版元渡邊庄三郎の存在も忘れてはならない。
新聞同様,企業として確立した人物に注目すると,50過ぎて{博文館}設立するや次々世間を驚かし,{太陽}創刊{当用日記}発行など挑戦続けた大橋佐平を皮切りに,自著出版のため{平凡社}を創設し「大百科事典」を刊行。時代に対応して活動した下中弥三郎,{講談社}を創業して次々と雑誌を刊行し,新聞・レコードも擁する一大マスコミ王国に野間清治,{岩波書店}創業,定価販売や造本・校正などで信頼,文庫・新書など生み出版界リードした岩波茂雄,{改造社}を設立,世界の一流人招待,円本ブーム等時代を先駆も,孤高のため一代で終った山本実彦,戯曲作品で成功後,{文芸春秋社}を開業し,創設した{芥川賞}{直木賞}が,作家の登竜門になった菊池寛,書物の美へのこだわりが"第一書房文化"と讃えられ,"出版一代論"唱えて廃業した長谷川巳之吉らがいる。
戦後には,<敗戦>によって{電通}社長になると,世界的な広告会社へ発展させ,日本の広告界の確立にも尽力吉田秀雄,敗戦後再出発した{文芸春秋}で,名企画を次々と打ち出し,国民雑誌に育て上げた池島信平,週刊誌の嚆矢{週刊新潮}以降,戦後ジャーナリズムを主導,黒子に徹して新潮社"天皇"になった斎藤十一,戦後の{中央公論社}の企画をリードした永倉あい子らによって,それぞれ再活性された。なお,戦前「人物評論」で挫折,復興後,「無思想人宣言」を発表,辛辣な評論や流行語を発し,"マスコミ大将"になった大宅壮一や,大政翼賛会のアイディアマンとして知られ,<敗戦>直後に,{暮しの手帖}を創刊,独創的編集で一時代を画した花森安治という人物の存在も忘れられない。
出版より少し遅れて始まる娯楽は,内容は様々であるが,大正デモクラシーに始まり,戦時下に発展,戦後に爆発する。その皮切りは,都市近郊私鉄経営のため,宝塚歌劇・ターミナルデパートなど近代娯楽を開拓した小林一三で,双子の兄弟で,{松竹}を設立し,歌舞伎界を支配後,{東宝}と対抗して映画全盛時代を築いた白井松次郎と大谷竹次郎,日本映画独自のジャンルを確立し,映画製作所も設立した"日本映画の父"になった(マキノ)牧野省三,夫の道楽をヒントに{吉本興業}を創設,関西芸能界を支配するに至った吉本せいと,その弟で,戦前から戦後にかけ,非凡な才で次々大衆演芸事業を起こし,{吉本興業}を業界トップにした林正之助,妻かしことともに,戦前からの映画の洋画輸入や戦後の邦画国際化に貢献した川喜多長政,共産党から転向1号,仏文学翻訳経て製紙業界,<敗戦>後{サンケイグループ}築き活躍した水野成夫に,一介の会社員から,階段を駆け上がるように,フジサンケイグループ総帥になった鹿内信隆など,企業トップのほか,近代的小市民映画路線確立し,<敗戦>前後の長い間,{松竹}に繁栄をもたらした城戸四郎,戦時下にアメリカ式手法で映画事業の基盤,<敗戦>後も{アート・シアター}など影響力を発揮した森岩雄,大衆と向かい合う表現を模索,娯楽番組の原型を作ったNHKのプロデューサー丸山鉄雄らも挙げておきたい。
最後の最後に,「活動を究める」上で,現在も重要な職業紹介の制度をつくった人物として,わが国の職業紹介事業の基礎をつくり,民間組織だった職業紹介所を公的なものにした豊原又男を挙げたい。分野型の分類上,やむを得ず,メインを,社会分野の殖産型,サブを,官僚分野の殖産技術型に入れてあるが,個々のものに対応しているしているのではなく,その上に立つようなものであり,以下に記すように,まさに,デザイナ中のデザイナと言える人物であった。その師で,現在の大日本印刷のルーツ秀英舎を起こし,工場法制定に貢献した佐久間貞一と,同じ佐久間門下の親友で,「日本之下層社会」を出版して,大きな反響を起こした横山源之助の両者についても,追って,一枚年譜に加えていきたい。
豊原又男は,明治維新直後の1872年に,新潟県蜂岡の旧三根山藩家臣で,戊辰戦争に敗れた直後,有名な"米百俵"の出荷を担当し,長谷川から豊原に改姓した春雄の六男に生れ,事業に失敗した父が自害して家計破綻し,向学心に燃えるも,小卒で終わり,代用教員になって貯蓄,19歳の時,意を決して上京,転変の後,24歳の時,安田善次郎と東京建物の創立を企図していた佐久間貞一を紹介され,面会するや心服,翌年,安田と意見衝突して撤退した佐久間に従い,彼が経営する(後に大日本印刷になる)秀英舎に勤めるとともに,佐久間が取り組んでいた職工問題の研究に従事するうち,農商務省の工場法策定委員に選ばれた佐久間が,直後に急逝,その遺志を継ごうと決意する。1899年の27歳,早くも処女作「資本と労働の調和」を出版し,同じ佐久間門下の良きライバル横山源之助の「日本之下層社会」出版を支援し,跋文を寄せる一方,農商務省が新設した臨時工場調査会のアドバイザに呼ばれて,委員長桑田熊蔵の薫陶を受け,「佐久間貞一小伝」を刊行,1911年,恩師の遺志である工場法が施行されると,翌年には,その解説書を出し,第1回工場監督官会議で講義,東京府の嘱託にもなって縁ができるなか,1920年,48歳の時,それまでの研究を集大成した名著「労働紹介」を出版するとともに,神田駅ガード下の一角に,自ら命名した中央工業労働紹介所が開設されるに至った。1923年の関東大震災で紹介所が全焼した折には,ジュネーヴでのILO総会に出席していため,信頼する職員に任せて,ドイツの傷痍軍人の職業訓練を視察するなど研究を進め,2年後に,飯田橋の新庁舎に移ると,高松宮来臨の栄誉や,百貨店女店員募集に一万人を超える女性が殺到したりするなか,求人者,求職者双方の立場に立った職業紹介と,実態調査や統計分析に努めて,日本一の紹介所にしていきながら,国営化運動をし続け,日中戦争の始まった1937年,国への移管が決まり,秩父宮・同妃来臨の栄誉を最後に,所長解職,現場を離れ,以後は,江戸時代の奉公人制度から説き起こす「職業紹介事業の変遷」を刊行するなどして,敗戦まもなく没した(巻町双書23「わが国職業紹介事業の父 豊原又男翁」による)。
⇒コラム(素質,努力,指導,機会の話)
⇒コラム(脳とコンピュータの関係の話)
この章TOPへ
ページTOPへ
・・・第1話:伝統的な三分法に割り当てて見る
・・・第2話:座標軸を設定し,その象限から考えて見る
・・・第3話:活動分野・型のリスト
第2論:時代が人を創る(歴史)
・・・第1話:各分野型・サブ型の時代推移~職能分化の歴史的プロセス
・・・第2話:女性が文化をつくる~自立する女性
・・・第3話:現代に類似する各時代末の分野型
第3論:注目されるデザイナ的人物
・・・第1話:統治のデザイン
・・・第2話:文化のデザイン
・・・第3話:社会のデザイン
第1論:活動分野型の捉え方(リスト)
はじめに
わが国では,職業などを選ぶ機会が高校や大学を卒業する時に限られるが,この年齢では,自らの適性を掴みかねている場合が多く,いわゆる個性教育の弊害などから,無理に自らの個性を強調して,誤った選択をしてしまうことも多いと思われる。個性は自ら主張するものではなく,ある集団において他人から認知されることで分かるものであり,その典型は相撲など最も型に嵌った組織において特徴的に現れる。個性というよりは,自らやりたいもの,あるいは適性のあっていそうなものを選ぶのが良く,場合によっては使命感を持って選ぶこともあって良い。この段階で,一度は選択してしまったものの,どうも自分には合ってていないとばかり,直ぐに止めてしまうことも多々見られるが,こらから述べるように,職業には,それぞれ相当な幅があるものなので,「石の上にも3年」などと言われるように,じっくり見つけて行くことも必要である。この幅に対応すべく,限定的な職業という語でなく,職能という語を用いたい。また,転職する場合には,自らにとってより良いものでなければ意味は無く,二股人生など多様な生き方を実践することも考えられる。とくに,近年の問題は,いわゆる定年後の生き方(いわゆる第三の人生)の問題で,ここにこそ自分に最も相応しい職能選びがあるのではないだろうか。
職業の種類については,国勢調査に対応するものや,厚生労働省のハンドブック的なものなど公的なものから,就活にからんで様々なものが出回っているが,次々に新しい職業が誕生する一方,用を成さなくなってしまう職業も出て来るため,これらの資料ではなかなか対応できず,特に役所のものは現状後追い型のため,それこそ用を成さなくなってしまっている。かつては,職業別電話帳などである程度掴むこともできたが,最近の変化はとてつもなく,とても追いつけるものでなくなっている。また,政治家や芸術家,芸能人やスポーツ選手など表に目立つ個人への評価がどうしても高くなり,これら個人が登場するためには,作家であれば雑誌編集者など,スポーツ選手であれば良き指導者など,支える人物が重要で,さらに辿って行けばその裾野は広がるばかりなのだ。かつて,NHKの人に聞いた話では,最近はディレクターに成りたがる者ばかりで,プロデューサーをめざす者がいないと嘆いてたが,その後はディレクターどころか,キャスターに成りたがる者ばかりになっているのではないだろうか。イタリア映画の黄金期を見れば,フェリーニ,ヴィスコンティなど有名監督以上に,プロデューサーのカルロ・ポンティの方が有名であった。このように,目立つ者ばかりを目指す社会はとても強靭な社会とはいえず,職能分野として大枠で捉えるようにすることが必要になってくるのである。
そこでまず,職能選択したり,第三の人生を送ったりする上で,まず知っておくと良いいくつか枠組みを提示し,分野型として,リスト化することを試みてみよう。
第1話:伝統的な三分法に割り当てて見る
わが国では昔から,社会を様々な三分法で整理し,(大量複雑な情報を縮約して)あれこれ悩まずに済ます知恵を発揮してきたが,近年,そういったものが忘れされれてしまったようである。
その代表的なものとして,まず,「真・善・美」から,職能との関係を見てみると,「真」は,当然ながら世の中で何が本当であるか,真実を見極めたいということであり,もちろんどの分野においてもベースになるものであるが,とくに,「学問」分野に求められ,近代に入り科学が登場したことで,その方向は一層高まっている。また,社会で起きる様々なできごとから,真実を見極めるという点で「官僚」にも対応するものでしょう(現実には全くそうなっていないが)。いずれにしても,「真」は,社会をつくる人々の共通の理解の基本になるものでなければならないだろう。「善」は,分かりやすく言えば,他人のためになる,社会のために働きたいという意識に対応,職能としては「福祉」を始めとする社会的な活動が代表的なもので,そのルーツとしての「宗教」はもちろん,「企業」などでも,起業の際に意識される場合が多いと思われる。日本では職能のみならずあらゆる面で性善説がとられて来たが,近年,その足元が不確かになる事件が続出してきているように見える。「美」は,自ら感じるところのものが拠り所であるものの,社会の多くの人々に共感を呼び起こすことで,人生を豊かにし,結果として社会を美しくして行くもので,当然ながら,詩歌・小説から絵画・彫刻,さらに諸芸能を含むいわゆる「芸術」が対応し,近代以降派生するものが多い分野でもある。そして,あらゆる職能において「美」意識が求められるようにもなってきているのも事実だろう。
次に「知・情・意」について,「知」は,いわゆる知識で,「真」に対応し,過去の蓄積をふまえ,頭脳でいえば記憶力(過去)に対応,もちろんどの分野でも必要であるが,「学問」「官僚」においては基礎的なものといえる。「情」は,まさに感情の動きを表し,「芸能」を始め芸術の「美」に対応するのを始め,日本人の「情」はあらゆる分野で研ぎ澄まされ,世界に冠たるものとなっているが,他方,その場その場の「情」に左右される刹那的なもの(現在対応)になってしまうため,未来を構築するのが不得意であることが課題になる。宗教や社会福祉なども当然「情」が基本であるが,次の「意」無くしては長続きしないと思われる一方,裁判や官僚などにこそ,「情」が求められるのではないだろうか。「意」は,未来を築く意志に対応するものであるが,日本人の最も弱いところであり,「政治」や「企業」など最も「意」を必要とする分野ですら,意志の強い人物が嫌われるため,結果として,政治も企業も弱体化して行くことが多い。社会福祉活動などとの関係で見れば「善」にも対応しており,後述のスポーツやデザインという新しい分野は,まさに,「意」に対応するものである。
さらに「頭・体・心」(その変形としての「心・技・体」)で見ると,「頭」が「真」「知」に,「心」が「美」「情」に対応することは言うまでもないが,「体」が「善」「意」に対応するものであることを改めて認識する必要があると思われる。というのは,明治維新後,とくに敗戦後は,いわゆる文武両道が廃れ,頭ばかりの教育になって,身体を鍛えることを怠ってきたため,結果として,「善」「意」の力もどんどん落ちて来ていると見られるからである。このことを端的に示すのが,後述するように,現在もっとも輝いている国際的に活動しているスポーツ選手たちが,最も頭が良く,心豊かであることであることに示され,彼らにこそ,未来の日本を拓く可能性があると言えるくらいである。変形の「心・技・体」の方では,「技」が「頭」に対応,つまり過去から伝承されたものが「技」であり,それをどれだけ磨いたかということに対応するものだろう。
以上について,「過去・現在・未来」指向との関係で整理すると,「真」と判断するためには,それまでの事実が参照されるということで「過去」に対応,「知」はそれ以上に「過去」指向(Ⅰ型)であり,「善」「意」はこれからの社会をより良きものにしていこうとする点で「未来」指向(Ⅲ型)なのに対し,「美」は現に目の前のものとして制作したり演じたりする点で「現在」指向的であり,それに反応する「情」は刹那的になってしまうところが問題であるが,まさに「現在」指向(Ⅱ型)というように,三つの型になり,次に述べることも合わせて,下表のように整理される。
すなわち,この分類を敷衍して,ものごとの証明の方法について考えて見ると,「演繹法」というのは,明らな事実(真=数学の定理や公理など)とみなされることから論理的に導くという点で,Ⅰ型であり,「帰納法」というのは,ありえないものを排除して行くことで証明しようとするもので,例えば警察などの犯人探しなど,目前の問題を解決する点でⅡ型と言える。Ⅲ型については,証明の方法が無いということで,政治問題などの選択が困難であるとされてきたが,C.S.パースが提示した「アブダクション」は,多くの相矛盾するような問題について,全てに矛盾が生じないような一つの体系的モデルを構築することがその証明になるという方法である。たとえば,無から有を生じるとされる建築の設計などがまさにそうであり,(証明されて)確信を持てるからこそ建設できるので,広くデザインの基本になるものと考えられる。カントの三つの批判についても,「純粋理性批判」がⅠ型に,「実践理性批判」がⅢ型に,「判断力批判」がⅠ型に対応するものであることも分かる。他にも色々対応が考えられるが,維新の三傑では,木戸孝允がⅠ型,西郷隆盛がⅡ型,大久保利通がⅢ型に,ロシアの同時代の三巨人では,ドストエフスキーがⅠ型,トルストイがⅡ型,レーニンがⅢ型に対応しているなどと,想定してみるのも面白いだろう。⇒デザイン論(知情意論再考~「意」の復権を求めて)
| Ⅰ | 知 | 真 | 頭 | 過去 | 演繹 | 純粋理性批判 |
| Ⅱ | 情 | 美 | 心 | 現在 | 帰納 | 判断力批判 |
| Ⅲ | 意 | 善 | 体 | 未来 | アブダクション | 実践理性批判 |
第2話:座標軸を設定し,その象限から考えて見る
以上を踏まえて,極力現代の職能に対応させる形で整理するため,(結果は別にして)「社会を対象に活動しようとするか」「自分(内面)を中心に活動しようとするか」を分ける軸と,(原則として)「勝負(競争)があるか」「勝負は関係無いか」を分ける軸をクロスさせることて,四つの象限をつくってみる。
おそらく最もきつい社会対象かつ競争主体の象限は,まさに人々の支配に関わる活動で,まず熾烈な競争でそのトップに立ちたいという政治分野が核となるが,その政治を実行して行くための,熾烈な出世競争のある官僚分野と,政治の安定を支えるものの現実に勝負が決まってしまう軍事分野がセットになる。古代の公家時代に官僚が登場し,中世の武家時代になって,軍事と境目のつかない政治家を輩出することになった。これら全体を支配体制活動として,前述の三つの型との関係で見直すと,政治分野は意志をもって未来を拓くということからⅢ型に,官僚分野は過去の事例などの積み重ね,すなわち知識に基づいて処理することからⅠ型に,軍事分野はまさに目前に起こることに対処するという点でⅡ型に,おおむね対応すると見て良い。政治には意志をもって未来を拓くことを,官僚には誤りのない知性を,軍事にはむやみに人を殺さない情を求めたく(西郷隆盛がまさに身をもって示したもの),また,それぞれの分野への適性もそうあって欲しいと願わずにいられない。
次に,社会を対象とし競争の関係ない象限を考えると,次項の「歴史的に見た職業の変遷」でも述べるように,日本では,仏教伝来以降優れた僧らが社会のために働いてきたことに始まり,明治維新後でもキリスト教関係の人たちが大きな役割を果たしたように,宗教分野がそのまま対応する。非競争であるが故に,人々から厚い支持を受けるようになると,前記の政治分野から排斥されることも多くなる一方,自らの保全のために,政治に密着したり,政治を動かそうとした宗派が生まれること,現在もなおそのような動きがあるのは本末転倒といえるのではないだろうか。近代科学によって一気に拡大した学問分野は,もともと学者でもあった僧から,また知識をベースとして学者に近い面のある前記の官僚から分化独立したものと考えると,最近の先端科学に見られるように,学問がまさに競争そのものになってしまったことが如何に問題を孕んでいるか,これが本当の意味での学問であるかということも考えなければならない。さらに人命を助けるという古くからの医療や,人々を啓蒙しようとする教育に加え,近代になって福祉その他様々な形の献身的な活動が,もともと人を救う宗教分野や,民生に対応する官僚分野から分化独立する形で社会分野を形成してきたと言える。つけ加えれば,医者は本来,人の命を助ける究極の「善」に対応する存在であったのが,医学者という学問分野に取り込まれ,人の命よりも,研究の対象としか見なくなった者が多くなってきたのが気になるところであり,それ故,相変らず人の命を救うことを専らの役割とする看護師の存在が重要になってきているようにも見える。
これらをまとめて社会貢献活動として,前述の三つの型との関係で見直すと,過去の知的ストックをベースし真を求める学問分野はⅠ型そのものであり,善意にもとづいて,恵まれない人たちのためなど様々な形で未来を拓こうとする社会分野はⅢ型に,本来の目の前の人たちを救おうとするとともに,多くの美を生み出してきた宗教分野はⅡ型に,おおむね対応するといえるだろう。宗教分野は,もともとは,Ⅰ,Ⅲ型までカバーしていたが,分化の結果,Ⅱ型だけに矮小化してしまい,目前の救済といいながら,実際には単なる神頼みだったり,大仰な結婚式や葬式をする役割にまで堕してしまっていることには言葉も無い。
三番目に,支配体制活動の対極に位置し,それ以上に古くから人類の基本的な活動としてある,いわゆる芸術に近い,自分のしたいことを競争と関係無くしようとする自己追求活動がある。詩歌など原初的なものから,物語や小説,さらには評論や思想など,宗教分野の僧に始まり,学問分野ともつながる著述分野,装飾古墳などに始まる絵画を核に,彫刻や建築から,近代の最も時空間的に統合された映画に至る様々な造形分野,もともとは詩歌と一体であったとされる歌謡や舞踊に始まり,日本独自の様々な口演や,歌舞伎から劇・映画の俳優に至る,人前で身体を使う芸能分野に,大きく分けることができる。これらいわゆる芸術的行為は,自分すなわち個を突き詰めて行った結果普遍性を獲得し,社会を構成する人々の共感を生み,互いの気持ちを通じ合うようにするものと言える。
同じく,前述の三つの型との関係で見直すと,未来に向けて形を遺すのが主体の造形分野がⅢ型に,演じるごとに消えてしまう,まさに現在にのみ意味のある芸能分野がⅡ型に,そして,ストックされてきた様々な知識などを作品化して行く著述分野がⅠ型に対応すると見て良いだろう。こういった区分はあくまでも大枠の話で,著述分野でも,詩歌などは芸能と一体となる部分が多く,「情」に対応するものとして捉えられるのはもちろんであり,さらに,「真・善・美」との関係でいえば,この活動全体が「美」に対応するのはいうまでもなく,「頭・心・体」といった区分では,芸能分野は,まさに「体」に対応するものといえるなど,かなり複合的な関係になっていることを指摘しておかねばならない。
最後に残った象限は,競争を前提に自己発現をしたいという挑戦追求活動になるが,これこそ最も新しく登場してきたもので,まず,近世に始まり,近代に入って飛躍した様々な実業分野がある。次に,戦が無くなったことで生じた武道にもつながるとともに,サッカーのワールドカップに見られるように戦争の代償行為であり,結果として平和に貢献すると見られるスポーツは,本当に新しく,まさに競争そのものを体現していて,ほとんどが仮想現実化されてきた社会の中で,かなり現実性を感じさせてくれるとともに,一流選手たちが語るのを見ると,現在最も優れた人間像でなかろうかとさえ思えるものだろう。以上のような明確なものではなく,また,発明や技能,様々な仕掛け人や破天荒な活動のように,見方によっては,いつの時代にもあったと言えるもの,ジャーナリストのように,著述というよりは,社会を告発したり啓蒙しようとすべく新たに登場した活動など,バラバラのように見えるが,他の活動に比して実践的であることが共通していることから,実践分野としてくくることとする。
同じく,前述の三つの型との関係で見直すと,挑戦追求活動全体がⅢ型に対応すると言えるが,スポーツは,過去の記録や知識を基礎としている点でⅠ型に対応し,「真・善・美」では「美」に,「頭・体・心」では「体」に対応,すなわち"知体美"という最もすばらしい全人的統合であるとも考えられる。こういった見方をすれば,日々の利潤に追われる実業分野がⅡ型的で,発明を代表に未来を拓く実践分野がⅢ型的であると考えることもできよう。
以上のことをまとめた図が「活動ジャンルマップ」で,このマップのどの辺に自分が対応しそうか考えてみることで,活動の方向が少しでも見えて来ればと願うものである。
マップをつくるにあたっては,世界に例の無い日本独自の天皇制により,職能選択の対象にはならないものの,日本人全般に放射光のようにかかり,良くも悪くも,社会の活動を超えて存在する皇室が,座標の原点とし,職能としては最も古い支配体制活動を上に置くと,反時計回りに,社会貢献活動,自己追求活動,挑戦追求活動と,おおむね,社会の活動として,基礎になるものから,より個人的,挑戦的活動に展開する順になる。
各象限相互の間で相互に近い分野を見ると,社会の安定や人々の生活向上に直接的に関与するなどの点で,官僚分野が社会分野に,自ら知り得た知識等を文字化して広く伝えるというような点から,学問分野が著述分野に,身体を使い能動的であることや破天荒さも大きな意味を持つなどの点で,芸能分野が実践分野につながり,最後にスポーツを代表とする競技分野が,前述のように,その代償行為となってきた支配体制活動の軍事分野とつながって,四つの象限が環になって完結することになる。
以上とは別に,職業の変遷のところでも述べるように,どの職能にも入らずに名を残した人たちがいる。一番分かりやすいのは,いわゆる陰の女性で,歴史上大きな役割をした人物も数多い,同様に,日記など詳細な記録を残した人物の存在価値も計り知れない。また,日本独自の隠遁(脱社会)や犯罪など反社会,さらには日本を脱出して海外で活躍したり,外国出身ながら日本人として活動する人物たちは,4つの象限全てに架る背景となる特異分野として位置づけた。この特異分野が皇室分野と直結したものであるという含みをも持たせてあるが,関心ある方は「日本私史三講」のⅠ:統治変遷のプロセスをご覧頂きたい。なお,自らの適性を知るためには,同じページのコラム「遺伝適性を知るための民族ルーツ論」を見れば,何かの参考になるだろう。
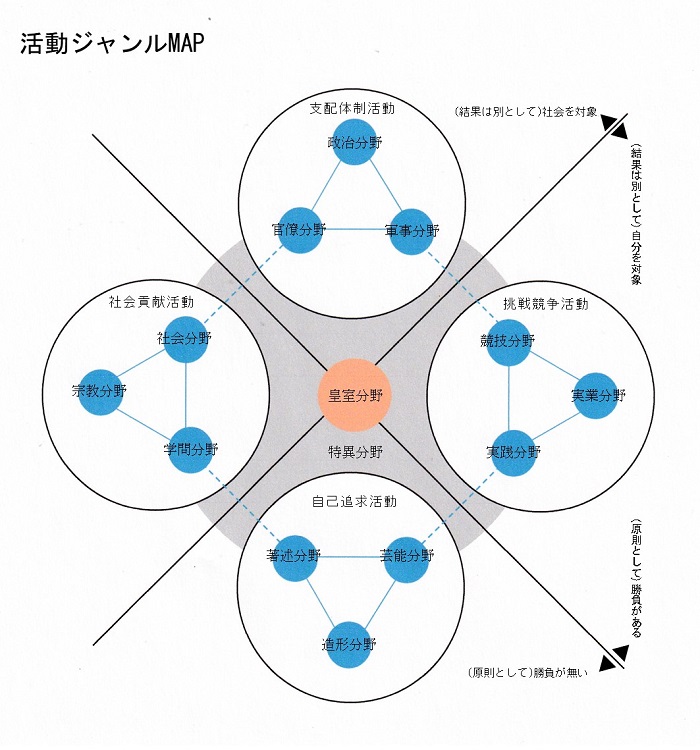
第3話:活動分野・型のリスト
活動ジャンルMAPにもとづき,かつ,現在までに作成した3,635人の歴史人物の一枚年譜をめくりながら,活動の分野に対応する型を,以下のようにリスト化し,思いつくままに該当する一般的な分類例やコメント,基本的な数字として,人数と全数に対する比率を記しておく。リスト化するにあたって,従来の枠組みでは表せないようなものもあり,独自のものが登場するが,少しでも分かりやすくなるよう,その型に対応する,著名な歴史人物を例示するようにした。当然のことながら,中世から近世にかけての著名な人物が,武将であり,大名であるように,歴史人物の多くは,一つの分野型にあてはまらない。そこで,サブ型として,二つまで,示すようにした。もちろん,それ以上にまたがる人物もいるが,少なくとも,その人物を表す上で,欠かせないと思われるものを記し,サブ型の人数と全数2,168人に対する比率についても示しておく。
0:皇室分野:
世界に例の無い日本独自の存在(シンボル),そもそも一般の国民とは別の存在で,残念ながら,職能選択外になる(95人,2.61%)。サブ(4人,0.18%)。1:天皇型:天皇・上皇・法皇・皇太子・・・(48人,1.32%)。当然ながら,この型がサブ型にはなり得ない。
2:皇后型:皇后・中宮・女院・皇太后・国母・女御・後宮・天皇乳母・・・(26人,0.71%)。サブ型(1人,0.05%)
3:皇族型:皇子・皇女・天皇の兄弟・その他皇族として扱われているもの・・・(21人,0.57%)。サブ型(3人,0.14%)
1:支配体制活動>(結果は別として)社会対象+(原則として)勝負ある活動
1-1:政治分野:
"未来"対応の統合的・創出的な分野であるが,日本では天皇制のため,欧米のように真の革命を経た市民社会が形成されず,戦後民主主義で選挙制度も確立されたとはいえ,国民と政治の間は乖離したままであることは誰しもが思うところであろう(515人,14.16%)。サブ型(264人,12.18%)1:国家支配型:(宰相・将軍・摂関・執権・老中首座など)実質的に国を支配する政権トップ。(87人,2.39%)。サブ型は,天皇でも,実質的に国家を支配する権力のあった人物や,権力補佐型でありながら,実質的に国家支配した人物などで,琉球は別の国であったことから,国王は,国家支配型でもある(21人,0.97%)。
2:地域支配型:(首長・大名・守護・探題・公方・知事など)現代においても,県知事,市長村長とレベルはさまざまであるが,一つにまとまった地域のトップになる人物(80人,2.20%)。サブ型は,戦国大名のように,武将でありながら地域を支配していた人物や,幕藩体制の老中首座も本拠は藩主で地域支配型(49人,2.26%)。
3:権力補佐型:国家地域を問わず,(老中・公卿・管領・連署・藩政家・側用人・閣僚・家老など)支配者を補佐,表に立つより,支えるのが得意な人物で,のちのコンサルタントにも通じる面もあり,前の二つの型には,優れた補佐がいた場合が多い(141人,3.88%)。サブ型は,当然ながら,この型の人物が,のちに支配型になる,現代でいえば,閣僚から首相になるような場合が多い(40人,18.5%)。
4:党派活動型:(政党+官僚+地方政治家・政治画策家・自由民権・共産+社会主義者・ファシスト・右翼など)維新後,近代に入っては国会をつくる運動から始まる,いわゆる政治団体を主とするものや,世界の影響で,社会主義,共産主義などさまざまな活動が登場し,現代に至っている。戦後の民主主義のもとでは,政権を握って,閣僚から首相になる場合も出るが,一匹狼型で,結局破綻してしまう人物も多い(87人,2.39%)。人生の一部として政治活動する人物も多いことから,サブ型も多くなる(65人,3.00%)。
5:時代変革型:(主に明治維新の志士とその支援者)古代から中世,中世から近世への時代変革は,それに対応する人物がいたのは当然であるが,それらは次の軍事分野の武将らに含まれてしまう。これが,もっと広い層の多岐にわたる形で登場するのが,いわゆる維新の志士らであり,この反対者や関係者も含めて,他に分けられないため,新たな型とする。維新前の時点ではテロリストに近い人物も多い(51人,1.40%)。また,支援者はもちろん,本業がある人物も多く,サブ型が多くなっている(41人,1.89%)。
6:政治思想型:(経世家・儒学者・各主義+政治理論主唱者)哲学者などに近い面もある(69人,1.90%)。近代の党派活動の多くは,イデオロギーと裏腹であり,サブ型も多い(48人,2.21%)。
1-2:軍事分野:
言わずもがなであるが,文武の一方,武の支配であり,目の前の敵を倒すことが求められる"現在"対応の分野であるが,戦後の日本では軍隊が無いためほとんど意識されなくなってしまっている。戦前はまさに軍人の時代であり,さかのぼれば,日本という国は,鎌倉幕府で公家政権から武家政権に移ってから江戸時代まで,世界的に見れば極めて長く続いた軍事国家であり,その間の戦国時代もまた世界でも例の少ない内乱の時代で,武将が輩出するなど,歴史人物として大きな分野を占める(208人,5.72%)。サブ型には,江戸時代に入って戦を失ったり,明治維新で武家が失職したりすることで,学芸や商売に転向し,新たな時代を切り開いた人物も多い(132人,6.09%)。1:統率型:(武将・司令官・統領・艦長など)中世,とくに戦国時代には,1-1政治分野の2:地域支配型のように,多くの1:統率型の武将が登場し,近代に入っては,政治から離れた軍人としての司令長官を代表とする1:統率型が登場することになる(61人,1.68%)。古代における蝦夷征伐の将軍をルーツとして,鎌倉幕府以降の武家政権のトップは,形式的に,天皇から征夷大将軍という地位を授けられることで成り立っているが,これらの将軍はじめ,執権や管領などは,一義的には,1-1政治分野の1:国家支配型としてあげられ,サブ型になるため多くなる(54人,2.49%)。
2:補佐型:(部将・将校・上級など)1:統率型を補佐する,表に立つより,支えるのが得意な人物で,政治の補佐型や官僚の総務秘書型にも類似,以下の型も合わせて,組織重視という点で官僚分野にも近い(65人,1.7%)。統率型や地域支配型などへ出世することなどでサブ型も(28人,1.29%)。
3:戦闘警固型:(指揮・兵・随行など)古代において,上は,天皇や上皇,摂関家を守る武士から,荘園を守るものなど,中世の武家政権を担うもの,武士の活躍の場が無くなった江戸時代を飛ばして,近代の軍人でまさに戦争の場に出,太平洋戦争での悲劇も(27人,0.74%)。サブ型には,院を警護する北面の武士であった西行も(17人,0.78%)。
4:参謀工作型:(参謀・軍人官僚・軍部行政官など)もともと統率型,補佐型の武将,部将自らも担い,中世の黒子の僧はじめ,連歌師,茶人,俳人ら様々な人材が活用されるてきたが,近代の軍制になって,分離独立,官僚に近いものになる。近代になって,多くの組織で現場と企画が分離し対立を招いているのと同様,実戦部隊との間に齟齬を生じた上,官僚と結託して増長,敗戦に導くことになった(31人,0.85%)。サブ型には,統率型に出世したり,閣僚になる人物も(16人,0.74%)。
5:装備技術型:(築城・造船・航空機・兵站・剣術・砲術など)中世から近世初めにかけて,武将自身が築城その他の技術者であった場合が多いが,その後,装備技術に際立つものも登場,近代に入って様々なものが登場し,産業の発展も先導するなど,後述の発明技術型にも近い(15人,0.41%)。サブ型の具体例は,メインが医療型の軍医(11人,0・50%)。
6:軍政思想型:(兵法・国防・武士道・軍学者など)もともと中国から伝わった孫子の兵法などが戦の基本で,新たな発想も含めて,中世全般にわたって武将自身が担っていたが,皮肉なことに,戦が無くなった江戸時代になって,国家支配者とは独立に,この型のものが登場する(9人,0.25%)。政治思想型にも近く,サブ型に(6人,0.28%)。
1-3:官僚分野:
前項の武に対する文の支配であり,日常世界の諸活動に対して,知識に基づいて専門的に処理するという点で,先例主義に象徴されるように,"過去"対応の分野である。脱官僚が政策のキーワードになっているが,10 年ほど前には大蔵省という名があったように,日本の官僚支配は天皇制と一体となった古くからのもので,武家政権となった後も,幕僚などという形で巧みに整備されてきた。実際, 国連やEU などを見ても,何らかの形で世界の一部でも支配しようとする組織であれば,官僚は必須であり,結局は官僚独自の世界が組織全体を動かすようになる一方,官僚の超保守的体質が戦争などの激変を嫌いその歯止めにもなって行く(232人,6.38%)。サブ型には,近世では,直接庶民のために活動する人物,近代に入ると,政治家に転じる人物など(107人,4.94%)。1:総務秘書型:(天皇側近ほか朝廷官人・能吏など)もともとは,天皇に仕えて,なんでもこなす人物が出発点で,歴史を遡るほどトップと直結して多くのことを処理する,以下のような型に分類できない人物が多く,近年においても,その業務が表に明確にならないものの,省庁をとりまとめるトップが大臣官房秘書課になっている(40人,1.10%)。幅広く対応できることで,サブ型にも(25人,1.15%)。
2:財務再建型:(大蔵・日銀・藩政改革など)維新政府で省庁がつくられるにあたり,古代に用いられていた大蔵省の名がそのまま使われたように,古いものであるが,そもそも国家権力が民から吸い上げる,つまり「入り」のみ管理していれば良いようなものであったことから,財政再建ということが目的になるのは,江戸時代になってからで,殖産や民政と表裏一体にもなる(15人,0.41%)。最も困難な役回りで,守旧勢力の抵抗も強く,能力高くとも,サブ型も少ない(9人,0.42%)。
3:外務通訳型:(大使等外交官・通詞・伝奏+申次・遣唐使・外交僧など)島国で鎖国的な日本では単なる通訳的な立場であり,本格的外交官は育ちにくかったが,開国とともに,国際関係が一気に拡大したのに伴い,主要な型に(33人,0.91%)。近世以前の朝廷と幕府間や対立する大名間なども一種の外交であり,サブ型に(22人,1.01%)。
4:法務学識型:(学者官僚・明法家・文章博士・裁判官・法制家・有職故実など)鎌倉幕府でも評定衆と言われたように,古代から支配組織の維持や人民統治において,問題が生じた時にどう裁くが基本であった。過去の判例などが最も重要なため,菅原道真のような学者官僚の力が大きい。敗戦後は三権分立で司法が分離独立され,それまでとは異なる統治システムになっている(34人,0.94%)。後述の学問分野に最も近いことで,サブ型に(12人,0.55%)。
5:内務民政型:(警察・医療衛生・教育文化(官学)・福祉・町奉行・寺社奉行・代官・所司代・地方行政官・宗教・監獄など)直接国民に関わるもので,明治維新後,内務(省)官僚が大きな力を持つようになった(45人,1.24%)。国民の福祉を真剣に考える官僚らは,後述する社会分野と直接的につながり,サブ型に(20人,0.92%)。
6:殖産技術型:((農林・通産・運輸・逓信)・経団連・博覧会・植民地経営・園芸・開拓(土木・建築・都市・植林)・鉄道・鉱山・測量・水産・造船など)国民の生活を豊かにするため産業基盤を整備する役割で,社会分野の殖産型にもつながる(65人,1.79%)。自ら起業したり,企業が発展することで,次第に役割を縮小して行き,サブ型に(19人,0.88%)。
2:社会貢献活動>(結果は別として)社会対象+(原則として)勝負無い活動
2-1:社会分野:
身体をかけて他人を救う道を拓くという点で,意="未来"対応の分野であるが,人々を救済することは,もともとは,次の宗教分野が担ってきたものであり,また,官僚分野の内務民政型や殖産技術型のなかには,真に人々のためになるように献身的に働いた人物もいが,近代の西欧からの影響や,社会がより豊かになってきたことで,急速に独立拡大している分野といえる(338人,9.30%)。型によって,それに集中しなければならないものと,何かの本業を超えて行うものがあるが,トータルとして,サブ型が多い(356人,16.50%)。1:医療型:(医者(教育)・看護(教育)・赤十字・病院経営・医師会・種痘・産児制限・薬剤・助産婦・救ライなど)人命を救うという点で最も古くから存在し,理科的な学問を開拓する役割も担った(59人,1.62%)。集中しなければならない一方,指導者的レベルでもあり,サブ型はそこそこにある(29人,1.34%)。
2:福祉型:(児童・少年・孤児・障害者・点字・感化・老人・貧民・自閉症など)様々なハンディを抱える人たちを救済するもの(35人,0・96%)。何等かの仕事をするうち,福祉に生き甲斐を感じるようになるサブ型が多い(24人,1.11%)。
3:教育型:(学校経営・服飾・栄養・YMCA・生涯教育・音楽・道場・綴り方・工業・家政など)人材育成という最も未来指向の社会活動(69人,1.90%)。誰でも,自らの活動があるレベルに達すると,若い人を教育したくなるらしく,サブ型が際立って多い(134人,6.18%)。
4:解放型:(女性・部落・労働者・弁護士・義民(農民解放)・公害被害者・主婦連・消費者・土地・出獄人・告発・占領・反原発・デモなど)近代に入って,さまざまな差別・搾取・弾圧・被害などから人々を解放する活動が成されて来た。江戸時代の一揆も農民差別からの解放活動と見ることができる(71人,1.95%)。生涯,集中し続けなければならない場合が多く,サブ型は非常に少ない(19人,0.88%)。
5:殖産型:(新田開拓・篤農・都市開発・地場産業・灯台・報徳・移民・水運・植林・治水・組合・コンサルタント・農書・起業支援・職業紹介・養蚕など)行政のやっているのを待っていられず自ら献身する人たち(50人,1.38%)。何等かの活動に関わるうちに,取組み始める場合も多く,サブ型は多めになる(40人,1・85%)。
6:文化型:(図書館・伝統芸能復興・メセナ・エスペラント・国際親善・スポーツ・愛国・YWCA・反戦平和・シンクタンク・青年・野鳥保護・近代建築普及・サロン・革命支援・児童絵画・建築・音楽・演劇・映画・啓蒙・パトロンなど):最後に豊かになることで,また自然や伝統が失われて行くことに対して,様々なボランティア活動も登場(54人,1.49%)。教育型のように,自らの活動があるレベルに達すると,社会に広めて行きたくなるらしく,サブ型が際立って多い(110人,5.07%)。
2-2:宗教分野:
現に目の前にいる他人を救おうという点で,情="現在"対応の分野とみなせる。日本では,仏教が入って来て初めて,宗教といえるもの,人物が登場し,また主体になったが,それに対応するように,古来からの,単なる信仰であった神道が,宗教らしさを持ちはじめ,仏教由来も含めて,さまざまな新興宗教が登場するとともに,欧米から,キリスト教の流入,刺激も大きな要素になった。疑似宗教とも見られる儒教については,日本では政治的な支配思想であり,また,漢学や儒学など,学問の主流にもなっていったことから,宗教としては取り上げず,他の分野の型に,適宜含まれることになる(203人,5.58%)。生涯をかけるものであり,サブ型は少ない(80人,3.69%)。1:教導僧型:(開祖・学僧・回国・教団主・護持など)日本の仏教宗派の開祖や高僧は,空海をはじめ,世界的に見ても高いレベルにあり,人々を救済する一方,政治支配の上でも大きな役割を果たしてきた(77人,2.12%)。これを超える別の活動は無く,サブ型はわずか(4人,0.18%)。
2:活動僧型:(外交・西域探検・画僧・寺院復興・社会事業・勤皇・工作・五山文学・編纂・梵語・書・霊能など)僧職にあって芸術や学問,外交など他分野に業績を発揮したもの(41人,1.13%)。他分野が主の場合はそれぞれの項に入るので,サブ型は多くなる(31人,1.43%)。
3:神道周辺型:(神道・行者・修験道・陰陽道・占い・国家神道行政など)仏教伝来以前からあった原始宗教的なものが天皇との関係で連綿と続き,明治維新になって国家神道化された(18人,0.50%)。国策に関わるので,サブ型もそこそこ(8人,0.37%)。
4:新興宗教型:(禊教・天理教・ユートピア・救世軍など)現在の有力な仏教宗派も登場した当時は新興宗教であったことはいうまでもないが,それは問わず,異端的なものに限る(25人,0.68%)。サブ型で出来るようなものでは無い。
5:キリスト教型:(牧師・神学など)近世初頭のキリシタンも(26人,0.72%)。明治維新後のキリスト教信者はかつての仏教僧のように様々な面で社会的貢献をしてきたことから,サブ型が多い(32人,1.48%)。
6:その他型:(宗教学者・心学(教育)・チベット・イスラム・インド哲学・心霊学・各宗教理論や支援など)最後に上記に該当しない様々な宗教的活動(16人,0.44%)。数は少ないが,ユニークな人物ばかりで,古い順に,何人か紹介すると,日本初の往生伝「日本往生極楽記」を著して,浄土思想を普及させ,「方丈記」に影響を与えた「池亭記」を著した慶滋保胤,町人のための思想を確立,その普及・実践に献身,社会教育やボランティアを先駆した心学の祖・石田梅岩,托鉢・奉仕・懺悔の共同体{一燈園}を開き,説話集「懺悔の生活」がベストセラーになった西田天香,43歳の時,地位財産一切放棄して説法始め,会員組織により,各界のトップを多数訓育,京セラの稲盛和夫によって,その存在が広く知られることになった中村天風など。サブ型は(7人,0.32%)でみると,日本の超心理学のパイオニアで,"念写の福来"として世界的になるも,帝大を追放された福来友吉や,国家主義者として,戦前の悪の一人とされるも,排他的日本主義を批判,学識あるアジア主義者として,ユニークな生涯を送った大川周明が,近いところでは,ほぼ同時期に誕生した,日本が世界に誇る二人の宗教学者,「東洋人の思惟方法」以降,比較思想宗教の国際的権威となり,膨大な業績を遺した中村元とイスラム神智学研究・コーラン学においては世界的な権威の井筒俊彦がいる。
2-3:学問分野:
既に存在している(した)ものごとを分析整理することを目的にする,知="過去"対応の分野で,いわゆる学者や研究者が主体になり,科学が基本になった現代の職能として一般的な職能のひとつになっている(314人,8.64%)。サブ型は,数理系のように専門特化していないものは少ないが,全体としては,第一義のものと同程度の比率になっている(205人,9.45%)。1:数理天文型:(和算・暦・天文・測量・地図・理論物理学など)脳の基本となる最も抽象的な世界で,古代からの天文・暦に加え,江戸時代に和算として独自の発展をした(33人,0.91%)。サブ型は,非常に少ない(5人,0.23%)。
2:自然科学型:(蘭学・本草(動植物)・博物・化学・物理・地震・地質・気象・医学・遺伝・解剖・栄養・自然対象工学(水利など)など)最も科学らしい分野で,医学から発展し,蘭学や本草学として近代科学への準備が成された(69人,1.90%)。サブ型は少ない(21人,0.97%)。
3:人文科学型:(考古学・歴史・地理・心理・宗教・人類学・有職故実・民俗・考証・風俗・文化人類・比較文化・美術史など)近代になって西欧から入ってきたものであるが,考証学など江戸時代に準備されていた(62人,1.71%)。歴史地理など,在野の学者もいて,サブ型が多くなる(43人,1.98%)。
4:社会科学型:(経済(史)・法学・法制史・政治・財政・経営・植民地政策・教育・女性問題・下層社会・行政・統計・家政・都市工学など)西欧においてすら全く新しい分野(49人,1.35%)。数理系に近い面もあって,サブ型は少ない(19人,0.88%)。以上三つの科学を,第1話三分法で見ると,観測データが基本の自然科学が1型,生活記述が基本となる人文科学が2型,未来予測を目的とする(政治につながる)社会科学が3型に対応する。
5:文学言語型:(漢文学・国文学・アイヌ語・外国語・文人・歌学・書誌・謡曲文・古今伝授など)日本語という特異な言語から独自に発展した分野で,かなりのレベルの学者を輩出(49人,1.35%)。古代中世の学識型官僚や,近世の国学者らに,本業と並行して取組んでいる人物など,サブ型はかなり多くなる(61人,2.81%)。
6:蒐集編纂型:(事典・辞書・地誌・地図・年表・伝記・民族音楽・蔵書・奇石・エンサイクロペディストなど)必ずしも学問では無いが,学問ほか何をやるにしても基本になれうようなデータベースの構築で,最も過去指向の作業であるともいえる。江戸時代の伊能図や群書類従など世界的に見ても偉大な業績がかなりある(52人,1.43%)。誰でも,その気になればできるものであるが,学問のベースになるものとして,この分野に入れたもので,サブ型はかなり多い(56人,2.58%)。
3:自己追求活動>(結果は別として)自己対象+(原則として)勝負無い活動>いわゆる芸術家
3-1:著述分野:
かつては文人という言葉が大きな意味を持ち,現在でも歌会始めが恒例であるように,特異な日本語によって洗練されてきた日本人が最も得意とし,また強く反応するもので,人名辞典等に最も多く登場し,年譜なども,詳細に作成された人物が多い。日本では近代以降,外国文学の翻訳が極めて多く,翻訳で名をなした人物も多いので,翻訳している作品の型に応じて入れて置く(480人,13.20%)。素養として身につけて置けば,書くことだけで,特別な場所やお金も入らず,サブ型も多くなる(256人,11.81%)。1:詩歌型:(韻文。和歌・俳句・連歌・狂歌・漢詩・川柳・作詞・・・)文字にならない段階から始まり,歌謡など芸能分野ともつながるもので,さまざまなタイプが選択でき,職業としない場合も多いことから,著述分野の3分の1を占める。歴史的には,男子は専ら漢詩を詠んでいたのに対し,紀貫之の貢献で女性による仮名文字和歌が始まる(162人,4.46%)。誰でもしているようなものなので,サブ型に挙げる人物にはレベル高いものが多い(72人,3.32%)。
2:小説型:(散文。各種小説・各種物語・各種草子・戯作・児童文学など)世界最古とされる紫式部の小説「源氏物語」という遺産を有し,江戸時代には西欧にも先駆ける西鶴のいわば大衆小説,さらに近代小説へと展開。それなりの力量で,時間もかけなくてはならず,近代には職業となって飛躍,読者のニーズにも対応することから,詩歌以上に多い(170人,4.68%)。当然のことながら,専業とするものが多く,サブ型は少なくなる(35人,1.61%)。
3:脚本型:(劇作・脚本・笑話作者・漫才台本・浄瑠璃作者・講談・字幕など)劇に近い能・浄瑠璃・歌舞伎など日本独自のもの,さらに世界に例を見ない落語・漫才など,芸能分野の:口演型にも強く関わるように,自らのなかに閉じないことから,数は少ない(27人,0.74%)。前記の小説型の人物がサブ型にしている場合も多く,比率は同程度(15人,0.69%)。
4:随筆鑑賞型:(随筆・日記文学・紀行文・毒舌諷刺・鑑賞・(伝記・逸話など)短文集・五山文学など)清少納言の「枕草子」や紀貫之の「土佐日記」に始まる随筆や(記録ではない)日記文学など,個人の感想主体の日本独自の文化。このような個人の情に訴える鑑賞文学が発達したため,本当の意味での批評文化は形成されなかったともいえ,この型がメインになる人物は少ない(18人,0.50%)。逆にサブ型には,メインがどんな分野型であっても,評判になる随筆等を書いている人物が多く登場する(38人,1.75%)。
5:批評解説型:(俳論・歌論・解説者・美術・外国文学・雑学・(思想哲学)科学技術史・科学思想・(美学)美術史・啓蒙著述家・雑誌編集・ドキュメンタリー・伝記作家・ノンフィクションなど)分析と意見を述べるもので,2-3:学問分野に極めて近い。実際,学問を志しながら転向したケースも見られる。また,時事・告発・煽動などを主とするジャーナリストに対し,冷静かつ長期的なものであり,いわゆる啓蒙で,日本人全体のレベルアップに貢献してきた(65人,1.79%)。サブ型は,様々な分野型を本業としている人物が,啓蒙等のために著述するため,かなり多くなる(58人,2.68%)。
6:哲学思想型:最も深い思索を表す哲学的なもので,政治思想型や:軍政思想型にも近い(38人,1.05%)。サブ型には,主要な宗教の開祖のものも入れるるので多くなる(38人,1.75%)。
3-2:造形分野:
言葉にすることができない抽象性をもった表現形態で,文や対面の不得意な人に対応している(277人,7.62%)。著述分野と違い,それぞれの型に特化していることもあって,サブ型は多くない(106人,7.62%)。1:平面型:(諸絵画・書・版画・写真・エッチング・織物など)現在においてもなお絵画が大半であるが,一定の平面の枠内に造形するもの全てに共通し,取組やすいこともあって,詩歌型に近い数であり,この分野の半数以上を占める(153人,4.21%)。サブ型は,近世までは,文人といわれていた人たちは,当然のように,絵画もやっていたことなどによる(52人,2.40%)。
2:立体型:(彫塑・陶器・ガラス・彫金・木工・七宝・漆芸・人形・生花など)やはり古くからある彫刻を中心に三次元で造形するもの全て共通するが,いずれも特化したものなので,思ったより少ない(28人,7.70%)。生涯専念するようなものなので,サブ型はさらに少ない(8人,0.37%)。
3:空間型:(建築・造園・土木など)人々が出入りしたり内部を動き回ったり,遠方からの見え方なども期待される,いわば四次元の大規模な造形であり,多数の人間が関わって実現するため,さまざまな能力が必要である(32人,0.88%)。サブ型が意外に多いのは,コンドルやレーモンドなど日本で活躍したした外国人,夭折の詩人立原道造はすでに建築家であったこと,著名な禅僧の夢窓疎石が禅庭の造園家であったことなど,様々なことによる(23人,1.06%)。
4:商品型:((グラフィック・インダストリアル・インテリア)デザイン・料理・服飾・美容・広告・図案・装幀など)産業社会・資本主義の発展に対応するように,商品価値を決定づける造形として発達したもので,まだ少ないが,最近は公共的なものも含めて,多くの人たちの利用を期待する全てのものに必須に成りつつある(22人,0.61%)。新たな挑戦になっているので,サブ型は,さらに少ない(8人,0.37%)。
5:ストーリー型:(漫画・アニメ・絵巻など)古代の絵巻から始まる,いわば平面+時間という日本独自の造形であり,今や日本の漫画やアニメが世界を席巻しているが,いわゆる漫画家は,戦時下から登場し始めたもので新しく,少ない。描かれる絵以上にストーリー性が評価されているのは,2:小説型の基本である物語文化が基礎にあるからと考えられる(9人,0.25%)。当然ながら,サブ型はさらに少ない(4人,0.18%)。
6:シーン型:(演劇映画監督・映画脚本・プロデューサ・興行・解説・装置・技術・撮影・TVドラマなど) 以上全てを統合するような空間+時間の造形で,近代に入っての映画が登場,劇が一過性であるのに対し,映画は後世に残る一つの作品を造形するもので,根本的に異なるといえよう。とはいえ,役者や舞台装置など,多くが共通するため,導入されるや,爆発的に拡がった(33人,0.91%)。片手間にできるようなものでは無く,サブ型は少ない(11人,0.51%)。
3-3:芸能分野:
聴衆・観衆相手に演じるという点で,対人指向,目立ちたがりが適し,その場限りのもので,臨場感そのものに意義がある(テレビやビデオで見ても臨場感は得られない)という点で,典型的な"現在"対応の分野である。それ故に,芝居などは何回も繰り返して演じられ,ビートルズがレコードを選んだのに対して,ローリングストーンズはあくまでもライブにこだわるのである。あとを残さないという点で,年譜等を作成するのが困難である一方,何らかの形で世襲になっているものが多いのも特徴である(222人,6.11%)。生涯をかける場合が多く,いずれも,サブ型は少ない(52人,2.40%)。1:楽曲型:(作曲・演奏・指揮・筝曲・古楽復原・謡曲・これら研究・普及など)古代から様々な楽器があり,イベントなどで活躍。オーケストラなど大編成になる一方,歌謡への伴奏としても発達。江戸時代以前の邦楽では,盲人が生活して行くために制度化されていたのも忘れてはいけない(43人,1.18%)。サブ型(10人,0.46%)。
2:歌謡型:(オペラ・流行歌・義太夫・ゴゼ唄・浪曲・常磐津・弾語り・シンガーソングライター・演歌師など)詩歌型と不可分のものとして最も古くから存在,現代でも歌詞が極めて重要な役割(33人,0.91%)。サブ型(8人,0.37%)。
3:口演型:(落語・漫才・演歌師・講談・漫談など)日本語という独特の言語が育んだ日本独自の文化。形として残らないため良く分からないが,江戸初期の「太平記読み」が大きな役割をしたらしい(27人,0.74%)。サブ型はとくに少ない(3人,0.14%)。
4:舞踊型:(能舞・バレエ・日本舞踊・モダンダンス・振付など)古代からの舞に近世からの踊が加わる(28人,0.77%)。サブ型はさらに少ない(2人,0.09%)。
5:演劇型:((役者)映画・舞台・歌舞伎・文楽人形使い・ミュージカルなど)歌舞伎役者から映画俳優まであり,現代においても,選択している人が多いように,この分野の3分の1以上を占める(84人,2.31%)。サブ型はかなり少なくなるが,現代でも,職業を変えるのが難しいと問題になっている(17人,0.78%)。
6:芸人アイドル型:(奇術・剣劇・ストリップ・見世物・タレント・アイドル)他に分類しにくいが,その他さまざまな形で演じたり,人気を得ることが意味をもっている,笠森お仙,松旭斎天一・天勝ような人物(7人,0.19%)。メインの職能とは言えず,サブ型が多くなるのは当然だろう。在原業平もこの型でこそ,存在が分かるような気がするし,タレントの草分け三木鶏郎の凄さも明確になる(12人,0.55%)。
4:(挑戦活動)競争的>(結果は別として)自己対象+(原則として)勝負ある活動
4-1:実践分野:
まとまった一つの分野としては説明しにくいが,年譜に多く現れ,社会に直接的に関わる,実践的な活動に,その活動をなるべく的確に表すような型にしたもので,本講義の特徴でもある(188人,5.17%)。つまり,普通の分類には無いものなので,当然のように,サブ型が多くなるが,このことが,一般の職能選択が問題であることも示している(322人,14.85%)。1:発明技術型:(軍艦・鉄道・施工・製鉄・織機・自動車・謄写版・印刷・土木・建築・都市・機械・窯業・電気・航空・化学・品質管理・模型・楽器など)人工物を生み出す工学に対応。実業分野の製品生産型の多くはここから始まり,近年は常時発明競争にさらされている状況にあり,軍事分野の装備技術型での競争も激しいが,もともとはオタク的個人のユニークな頭脳によって成されてきたものである(42人,1.16%)。サブ型は,製造会社の起業家の大半発明家であることなどによる(34人,1.57%)。
2:伝承技能型:(左官・石工・地図・製陶・織物・鉄砲・操船・宮大工・模型・絵付・刺繍・醸造・調律など)技能伝承しながら新たな飛躍を生み出したり,造形分野に近い作品を生み出したりするものであるが,いわゆる,無名の作家が大部分なので少ない(13人,0.36%)。そでも,別の分野型で名を遺した者により,サブの方が多くなる(18人,0.83%)。
3:コンサル仕掛型:(花火・仕掛屋・博覧会プランナー・イベント興行師・国際会議セット・画商・コンサルタント・権力側隠密(スパイ)など)その時点のみのイベント型造形や政治その他の分野を助けその実績が上がるようにする裏方活動,名前はほとんど表に出ないが,歴史的に大きな役割をした者が多い。例を挙げたいところであるが,著名な人物はほとんどおらず,対象とする活動も千差万別なので,トップページの年齢適活年譜リストから拾い出し,一枚年譜を見て貰いたい(29人,0.80%)。まさに,黒子である場合がほとんどなので,表向きの分類には出て来ないため,サブ型は,際立って多くなる(70人,3,23%)。
4:本業超越型:(財界トップ・業界支配・メセナ・福祉・親善・パトロン・支援・殖産・文化導入など)自ら関わる企業等の枠を超えて,産業界全体,さらには国民全体に関わるような事業や活動をするもの。社会分野等とは異なり,あくまでも本拠地での活動が基本になる。注目すべき人物を挙げてみると,維新直後から企業設立や経済界組織形成で資本主義を先導,社会・公共事業にも広く関係し,本業が何かわからないくらい超越している,最近,とくに話題の渋沢栄一を代表に,古い方から,甲州商人先駆者で,十組問屋の危機救い三橋会所を設置するなど,江戸経済を支配した杉本茂十郎,近代政商を先駆し,関西財界を指導,"東の渋沢・西の五代""大阪発展の恩人"と言われる五代友厚,台湾統治経済を確立,一高校長として影響大,国際連盟事務局次長後,国際平和に尽力した新渡戸稲造,造園家,林学者で,日本の国立公園行政で指導的役割をはたし,"国立公園の父"とよばれる田村剛,群馬交響楽団の創設はじめ,幅広く地域文化を先導し,巨大な足跡を残した実業家井上房一郎,そして,最も近いところで,{石川島}{東芝}再建で"企業再建の神様"といわれ,高齢になって{臨調}{行革審}会長になって,国民からも敬された土光敏夫らいる(33人,0.91%)。本業があるという前提故に,サブ型は,コンサル仕掛け型以上に際立って多い(102人,4.70%)。
5:ジャーナリスト型:(ドキュメント・報道写真・記録映画・ルポライター・雑誌編集など)新聞雑誌等が主体であったため,一見著述分野のように見えるが,本来的に時事問題について告発や煽動をする活動であって,近年では映画や写真,テレビその他さまざまな手段によるものが多くなっている(47人,1.29%)。サブ型には,他の分野型に入れられる人物でも,報道写真家など告発に努めるものが入るので,それなりに多くなる(47人,2.17%)。
6:奔放夢想型:次々に挑戦して開拓したり,複数(3つ以上)の分野で業績を上げたり,道楽に徹して業績になってしまったり,バサラなど破天荒であることが他者に影響を与えたりするもので,血液型ではB 型,民族型では海洋型,気質型では躁鬱気質に特化して現れるようだ。出来る限り,どの人物にについても,いずれかの分野型に入れるようにしたが,マルチ人間の典型で,多くの発明・創出・著作をしたが,世になじまず思わぬ最期になった江戸時代の平賀源内,維新後の変革期を象徴する破天荒な人生を送り,日本の近代劇運動に先駆的役割をした川上音二郎,"新しい女"の中でも際立って特異,"仏教界のスター"から,作家として華開くも早世した岡本かの子,近いところでは,歌人,劇作家,演出家,映画監督,競馬評論家など,一言では括れない天才的マルチ人間だった寺山修司など,どうしても,この型こそ第一という人物がいることも否定できないだろう(24人,0.66%)。従って,サブ型はかなり多くなる(53人,2.44%)。
4-2:実業分野:
現代のいわゆる企業が主体で,一般的に,最も多くの人々が関わっているので,分かりやすい分野であるが,歴史的には,近世初期に,豪商と言われるものが多数登場しており,現代の金融企業につながって,資本主義を支えていることから,それを最初の型とし,最後に,著述分野や芸能分野,あるいは,ジャーナリスト型とも非常に近いメディア娯楽型をおくことにした(224人,6.16%)。挑戦し続けなければならない分野のためか,全体に,サブ型は少なめである(101人,4.65%)。1:豪商財閥型:(豪商・政商・商社・財界指導者・コンツェルン・保険・証券・投機・軍需・貿易・海運など)実業分野のトップを切って金の力を背景に政治権力と結びつく豪商が登場したように,金融を基本とするもの,権力との関係で利益を得るものなどが該当,実業界ネットワークの要にもなる(81人,2.23%)。サブ型(21人,0.97%)。
2:国土開発型:(炭鉱・電力・鉄道(国鉄含む)・鉱山・石油・製鉄・航空機・化学・運輸通信・商社・パルプ・武器火薬類・砂糖・水産振興・捕鯨など)政治権力との関係無しには事業展開しにくいもので,官僚分野の殖産技術型ともつながりが深い(33人,0.91%)。サブ型(16人人,0.74%)。
3:農水食品型:(酪農・ブドウ酒・農場経営・真珠・煙草・茶)生業から脱した農林水産業やその輸出入や卸などに関わるもので,社会分野の殖産型ともつながる(15人,0.41%)。サブ型(9人,0.42%)。
4:製品生産型:((工場)機械・製糸・造船・地場産業・建設含む)国民の購入するようなものを生産し名の知られる最も企業らしいもの(41人,1.13%)。サブ型(21人,0.97%)。
5:販売サービス型:(一般商品の物販・クリーニング・外食・化粧品・美容・ファッションなど)顧客と直接接するもの(衣食住)の物販やサービスで,日常的に縁が深い(28人,0.77%)。サブ型(17人,0.78%)。
6:メディア娯楽型:(出版・新聞・興行・映画配給・娯楽・印刷・広告・諸劇場経営など)国民に情報を伝え,あるいは娯楽を提供して喜ばすことによって利益を得るもので,時代とともに変遷も著しい。芸能分野との関係が大きく,実践分野のジャーナリスト型の能力も必要である(48人,1.32%)。サブ型(17人,0.78%)。
4 から6 までの型は,消費者と直接つながるため,造形分野の商品型との関わりも強い。
4-3:競技分野:
基本的には,過去の蓄積の上で,勝負や記録にこだわるものなので,"過去"対応であり,また,相手の存在が前提になるものであるが,自然風土を相手にする探検紀行や,近年,発展著しい,競技振興についても,それぞれ型とした(109人3.00%)。サブ型については,初めの3型は,いわゆる現役の時の名が残り,引退すると消えてしまうものなので,ほとんど無く,後の3型は,本業のあることが普通なので,かなり多くなるように,明確に分かれる(50人,2.31%)。
1:棋士型:(囲碁・将棋・これら指導者など)僧や和算家などによって,近世に入って急速に広がり,世界的に見ても独自かつ高度に発展した,いわば頭の戦(14人,0.39%)。サブ型は無い。
2:武道型:(武道家・剣士・力士・これら指導者など)江戸時代に入って戦を失った武士から始まる,武具や体によるまさに戦の代償行為で,いわば心の戦(23人,0.63%)。サブ型(3人,0.14%)。
3:スポーツ型:(各種スポーツ選手(監督)・レーサー・これら指導者など)明治維新後,西欧に追随するように始まり,近年急速に拡大しつつある,新たな体の戦。相撲のように,武道から始まったものが,スポーツとして見るとおかしな部分が多々あることもやむをえないか(27人,0.74%)。サブ型(2人,0.09%)。
4:探検紀行型:(冒険・探検・登山・紀行・登山ガイドなど)個の確立と対応するように登場した極限的挑戦活動であるが,経典を求めて,チベットに行くなどは,僧というよりも探検家に近い(22人,0.61%)。自然風土や人文を対象とする研究など必然的なものもあり,サブ型はかなり多い(19人,0.88%)。
5:競技振興型:(諸競技ジャーナリズム・評論・教育・体育協会・競技団体など)上記の諸競技をサポート(16人,0.44%)。とくに,本業のある場合が多いので,サブ型は非常に多い(19人,0.88%)。
6:茶道鑑識型:(香道・(動物等の闘い)・(数奇者)・グルメなども)独自に発展した茶道についてはどの分野にも入れにくいものであるが,少なくとも茶道が闘茶に始まり,それに近接する鑑識や香道などがまさに五感の戦いであり勝負が決まることから,この分野に入れた(13人,0.35%)。近代に入っても,茶人としても有名な実業家がおり,サブ型も多い(7人,0.32%)。
X:特異分野:
最後に,以上の分野型に入らないが,年譜に登場する歴史人物全ての活動をカバーすべく,下支え・犠牲・潤滑剤・複合魅力化など,言わば社会の味付けになる特異なものを集めて,分野型にした(230人,6.33%)。サブ型が当然のようなものも多い(133人,6.13%)。1:陰の女性型:(宮中・妻・側室・局・大奥・芸妓・乳母・生母・妾・娘・諜報・女中・秘書など)近世までは,日本では男性を支える以上に,男性を利用したり,支配して歴史を左右したケースが多い。足利義政の室の日野富子は,"御台所"として非凡な能力を発揮,中世を代表する女性の一人で,一時は義政の代りをしたほどで,サブ型を,政治分野の国家支配型に,徳川家康の側室の一人阿茶局は,才智にたけて,大奥を統制し,政治的にも家康・秀忠をサポートし,家光の乳母の春日局家康に直訴して家光の将軍継嗣に成功,大奥を牛耳り,無冠無位で参内,ともに,サブ型を,官僚部門の総務秘書型にしなければならないほどの人物だったし,ラフカディオ=ハーンの妻になったセツは,彼を,小泉八雲へと変身させるほどの存在であった。(30人,0.83%)。男女差別が強く,本業がありながら,男性を支えている場合も多く,サブ型も多くなり,没落武家の子三井高俊に嫁ぎ,商家として確立すべく家業差配し,息子らを訓育,高利が三井の祖になった三井殊法や,会津藩の悲劇後,若年でアメリカ留学,大山巌と結婚し"鹿鳴館の華"になり,看護活動支援の一方,様々な批判に苦労した大山捨松などがいるが,全体として,どちらをメインにするか,サブにするか,難しい(21人,0.97%)。
2:記録伝承型:(日記・覚書・口承・紀行など)特定の職能でなく,世の中の諸事を記録したり,口承したりすることで,後世に貢献するものも多々あり,そのことでのみ名が残る人物も多い。近世には,神坂次郎の「元禄御畳奉行の日記」で知られた朝日重章のように,日記が無ければ,名を遺すことのなかった人物もいれば,菅江真澄のように,東日本各地を旅して回り,当時の民俗を知る上で貴重な彩色絵紀行文を多数残し,広く知られる人物もいるが,近代に入っても,「特命全権大使米欧回覧実記」で近代化に貢献した久米邦武に対し,後半生を,あらゆることを日記に書き付けることにを費やした枢密院議長倉富勇三郎もいたという按配である(18人,0.50%)。もちろん,本業のある場合が普通なので,サブ型はかなり多く,さらに,さまざまな形の記録を遺している(26人,1.20%)。
3:脱社会型:(隠遁・孤高・アウトサイダー・食事療法・異端・逃避・隠居主体など)西行以来,日本人が憧れるものになっているが,鴨長明のように,実は職能分野からの落ちこぼれも多い。この二人を超えるような人物はいないが,何人か例を挙げれば,すべてからの自由を求め,茶を売りながら放浪し仏道全う,京の若者に多大の影響を与えた売茶翁こと高遊外,庵に住んで農民や子どもと交流,最晩年に貞信尼と出会って,大らかな書歌を遺した良寛,若くして隠居,清貧に甘んじながら,歌作革新,主君の出仕勧誘も辞退し,正岡子規の発掘で著名になった橘曙覧,2人の放浪の自由律俳人種田山頭火と尾崎放哉,画壇のあり方に不審抱き,奄美大島に居を定めて孤高・異端を通し,没後に発見・評価された田中一村など,どの人物もレベルは高い(24人,0.66%)。本業があってこその脱社会でもあるので,サブ型もかなり多く,その多くは著しておくこと名で,なるほどと言える人物であるが,社会から逃げた将軍足利義政と徳川家斉を入れたことを指摘しておく(33人,1.52%)。
4:反社会型:(密貿易・博徒・侠客・性科学・超心理学・犯罪者・ポルノ・異端・仇討ち・敵方スパイ・アナーキスト・テロリストなど)時代によって何が反社会的であるかは異なることもある。博徒やヤクザもかつては必要悪のように見なされ,講談などの材料にもなった(27人,0.74%)。サブ型は,本業の関係で起こす反社会活動など(12人,0.55%)。
5:在外活動型:(留学・追放・亡命・貿易・諸工作・キリシタン・文化・親善・難民・隠れ軍人・漂流者・大陸浪人・残留兵・国際結婚など。外交官・軍人・植民地支配は別)日本人は海外に出て行った者に冷たいところがあって,移住者たちが在地で大きな貢献をしていることなどあまり知られていない。このことが,海外に飛躍しようとする青年たちが増えない理由にもなっているが,島国である故,遭難などが契機になる場合もあり,かなり大きな数になる(96人,2.64%)。在外活動の分野型の方が重要な場合もあり,サブ型も多い(32人,1.48%)。
6:準日本人型:(沖縄・在日・アイヌ・亡命・帰化・混血外国籍・漂流者など)同様に,日本に入ってくる人たちどころか,もともと日本人社会を構成するはずの,アイヌや沖縄県民,いわゆる在日といわれる朝鮮系の人たち全てに冷たいところがあり,このことが日本のガラパゴス化と関係することは言うまでもない(33人,0.91%)。当然のことながら,サブ型は少ない(9人,0.42%)。
この章TOPへ
ページTOPへ
第2論:時代が人を創る(歴史)
はじめに
まず,歴史人物がどんな時代に活動したかを把握するため,データベースの作成には,日本史話三講の第Ⅱ講:時代循環のパターンで示した,以下のような時代区分を用いた。⇒詳しく知りたい人方は,当該ページへ。
Ⅰ古代(飛鳥・奈良・平安): 587年:丁未の変・・~1156年:保元の乱・・
Ⅰ-1:時代生成: 587年:丁未の変・・~ 769年:宇佐八幡神託
Ⅰ-1-1:前体制破壊期:587年:丁未の変・・~ 645年:乙巳の変・・
Ⅰ-1-2:再統一運動期: 645年:乙巳の変・・~ 702年:持統天皇没・
Ⅰ-1-3:新体制樹立期: 702年:持統天皇没・~ 769年:宇佐八幡神託
Ⅰ-2:時代前半: 769年:宇佐八幡神託~ 941年:承平天慶乱終
Ⅰ-2-1:時代建設期: 769年:宇佐八幡神託~ 806年:桓武天皇没・
Ⅰ-2-2:矛盾露呈期: 806年:桓武天皇没・~ 842年:承和の変・・
Ⅰ-2-3:偏向撹乱期: 842年:承和の変・・~ 941年:承平天慶乱終
Ⅰ-3:時代後半: 941年:承平天慶乱終~1156年:保元の乱・・
Ⅰ-3-1:時代再興期: 941年:承平天慶乱終~1027年:藤原道長没・
Ⅰ-3-2:理念衰退期:1027年:藤原道長没・~1086年:院政始・・・
Ⅰ-3-3:時代破綻期:1086年:院政始・・・~1156年:保元の乱・・
Ⅱ中世(鎌倉・室町):1156年:保元の乱・・~1543年:鉄砲伝来・・
Ⅱ-1:時代生成:1156年:保元の乱・・~1225年:北条政子没・
Ⅱ-1-1:前体制破壊期:1156年:保元の乱・・~1180年:源氏一斉蜂起
Ⅱ-1-2:再統一運動期:1180年:源氏一斉蜂起~1199年:源頼朝没・・
Ⅱ-1-3:新体制樹立期:1199年:源頼朝没・・~1225年:北条政子没・
Ⅱ-2:時代前半:1225年:北条政子没・~1333年:鎌倉幕府滅亡
Ⅱ-2-1:時代建設期:1225年:北条政子没・~1263年:北条時頼没・
Ⅱ-2-2:矛盾露呈期:1263年:北条時頼没・~1284年:北条時宗没・
Ⅱ-2-3:偏向撹乱期:1284年:北条時宗没・~1333年:鎌倉幕府滅亡
Ⅱ-3:時代後半:1333年:鎌倉幕府滅亡~1543年:鉄砲伝来・・
Ⅱ-3-1:時代再興期:1333年:鎌倉幕府滅亡~1408年:足利義満没・
Ⅱ-3-2:理念衰退期:1408年:足利義満没・~1467年:応仁の乱始・
Ⅱ-3-3:時代破綻期:1467年:応仁の乱始・~1543年:鉄砲伝来・・
Ⅲ近世(安土桃山・江戸):1543年:鉄砲伝来・・~1837年:大塩平八郎乱
Ⅲ-1:時代生成:1543年:鉄砲伝来・・1616年:徳川家康没・
Ⅲ-1-1:前体制破壊期:1543年:鉄砲伝来・・~1582年:本能寺の変・
Ⅲ-1-2:再統一運動期:1582年:本能寺の変・~1600年:関ヶ原の戦・
Ⅲ-1-3:新体制樹立期:1600年:関ヶ原の戦・~1616年:徳川家康没・
Ⅲ-2:時代前半:1616年:徳川家康没・~1709年:徳川綱吉没・
Ⅲ-2-1:時代建設期:1616年:徳川家康没・~1651年:徳川家光没・
Ⅲ-2-2:矛盾露呈期:1651年:徳川家光没・~1680年:徳川綱吉将軍
Ⅲ-2-3:偏向撹乱期:1680年:徳川綱吉将軍~1709年:徳川綱吉没・
Ⅲ-3:時代後半:1709年:徳川綱吉没・~1837年:大塩平八郎乱
Ⅲ-3-1:時代再興期:1709年:徳川綱吉没・~1751年:徳川吉宗没・
Ⅲ-3-2:理念衰退期:1751年:徳川吉宗没・~1786年:田沼意次失脚
Ⅲ-3-3:時代破綻期:1786年:田沼意次失脚~1837年:大塩平八郎乱
Ⅳ近代(明治・大正・昭和・平成):1837年:大塩平八郎乱~
Ⅳ-1:時代生成:1837年:大塩平八郎乱~1881年:明治14年政変
Ⅳ-1-1:前体制破壊期:1837年:大塩平八郎乱~1853年:ペリー来航・
Ⅳ-1-2:再統一運動期:1853年:ペリー来航・~1868年:明治維新・・
Ⅳ-1-3:新体制樹立期:1868年:明治維新・・~1881年:明治14年政変
Ⅳ-2:時代前半:1881年:明治14年政変~1945年:敗戦・・・・
Ⅳ-2-1:時代建設期:1881年:明治14年政変~1905年:日露戦争終・
Ⅳ-2-2:矛盾露呈期:1905年:日露戦争終・~1931年:満州事変・・
Ⅳ-2-3:偏向撹乱期:1931年:満州事変・・~1945年:敗戦・・・・
Ⅳ-3:時代後半:1945年:敗戦・・・・~
Ⅳ-3-1:時代再興期:1945年:敗戦・・・・~1973年:石油ショック
Ⅳ-3-2:理念衰退期:1973年:石油ショック~2001年:小泉内閣・・
図にしてみると,時代循環のパターンがよく分かる。
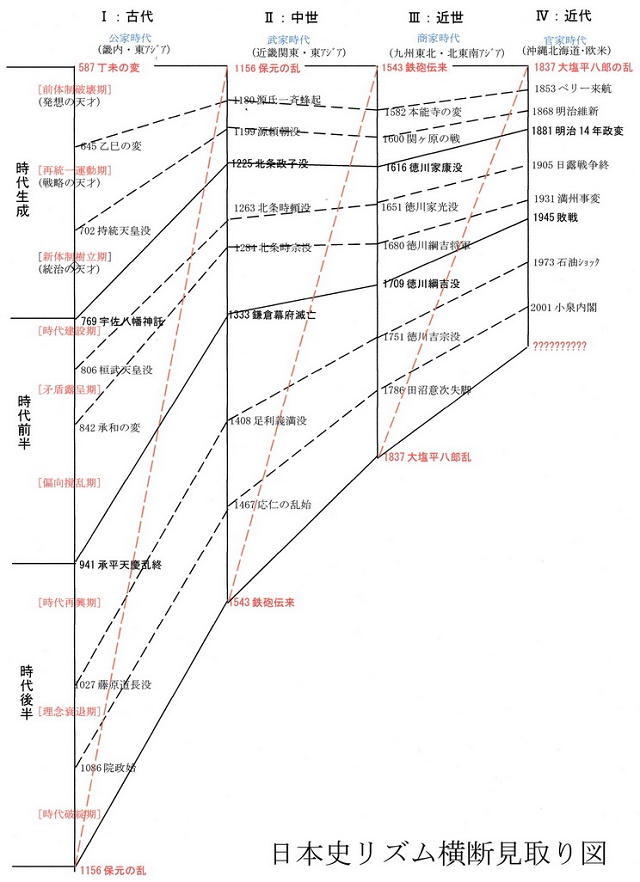
第1話:各分野型・サブ型の時代推移~職能分化の歴史的プロセス
1:時代別にみた分野型の特徴
「はじめに」で示した時代区分を,各分野型・サブ型とをクロスさせて作成した表をみながら,それそれの歴史的な推移を見てみよう。⇒PDFファイル「時代別分野型数」,「時代別サブ型数」
0:皇室分野:古代の人物全体の数の2割を占め,中世においても1割を超えて,大きな存在になっているのは当然としても,江戸時代では,ほとんどゼロになってしまい,明治維新によって威信を回復したと言っても,ごく僅かで,天皇制の歴史においては,江戸幕府の始まりが,最大の転換であったことが,改めて認識される。また,古代の前半には,サブ型で,政治分野の国家支配型が多いように,実権を発揮していたが,後半は,藤原氏の支配を反映して,皇后型が多くなるのは当然として,中世においても,天皇型,皇族型が多いことは,武家政権に対抗するだけの存在で,権威を保ち続けていたと言えよう。
1-1:政治分野:まず,1:国家支配型は,日本で年代が明かな歴史の始まる推古天皇が,そもそも蘇我馬子が戴いて登場し,藤原不比等が覇権を握って以降,天皇自身が国家権力を発揮することはほとんど無く,古代の後半は藤原摂関家であり,中世がとくに多くなるのは,将軍から,その将軍を戴く執権や管領など,次々と覇権を握る人物が変わって行くからであり,2:地域支配型は,古代末に初めて,奥州藤原氏という国家から半ば独立した地域支配者が登場,中世には,サブ型で,守護大名や戦国大名という地域支配者が出てくる一方,琉球王国という,日本全体から見れば地域支配者であるが,王国として,国家支配者であったものも登場,近世の幕藩体制になると,藩主が老中になるような仕組みによって,メインの型にも,サブ型にも多くなり,近世が,まさに地域支配をベースにした国家,帝国に近いものであったことを示している。その点,維新後の近代は,都道府県知事,市町村長など,地方自治が謳われるものの,国家支配者の内閣総理大臣(首相)がほとんどで,地域支配者として登場する人物は少なく,まさに中央集権国家になってしまっている。3:権力補佐型がどの時代にも多いこと,5:時代変革型が維新前後に限られ,4:党派活動型がその後に出現していることなどは,分類の定義上当然として,6:政治思想型について,政治支配に対応する儒学は古代では法務学識型の官僚であって表に出るほどでなかったが,江戸時代にとくに多く,幕藩体制を支える朱子学や,それに対抗するかのように起こった民間の陽明学など,活発な議論が,結果として,時代を長く続かせたと言えよう。それに対して,近代のそれは,党派活動と裏腹のイデオロギー的なものであって,社会をまとめるより分解する方向に働いている。
1-2:軍事分野:1:統率型が,平安時代末の平氏の軍事支配から,戦国時代の闘争を経て,戦のなくなる江戸時代の前まで,つまり,中世から近世初めにかけて,集中的に多いのは当然であるが,とくに,サブ型が多いのは,前述したのように,将軍,執権,管領などの国家支配型が多かったからであり,まさに,世界のなかでも際立つ軍事国家の時代であったということであり,江戸時代に入ると,武家支配であっても,形式的な肩書の将軍戴く文治国家になって,いなくなってしまう。明治維新後は,近代国家の軍として,政治家の支配下になり,そのなかでの1:統率型になるが,いわゆる軍国主義の伸長によって,政治を超える権力を握り,悲劇に至ったこと,敗戦によって,軍そのものが無くなくなってしまうという,世界でも稀な状態になって,屈折した平和国家の時代を送っているが,改めて,江戸時代の文治国家のあり方を見直したくなる。鎌倉幕府以降の武家政権のトップは,形式的に,古代における蝦夷征伐の将軍ということで,天皇から征夷大将軍という地位を授けられることで成り立っているが,これらの将軍は,一義的には,1-1政治分野の1:国家支配型としてあげられ,ここではサブ型となる。中世,とくに戦国時代には,1-1政治分野の2:地域支配型のように,多くの1:統率型の武将が登場し,近代に入っては,政治から離れた軍人としての司令長官を代表とする1:統率型が登場することになる。2:補佐型や3:戦闘警固型は,分類の定義を反映し,4:参謀工作型と5:装備技術型も,すでに述べたように,もともと,1:統率型や2:補佐型の武将が有していた職能が,近代の軍になって分化したものといえ,6:軍政思想型も,もともと中国から伝わった孫子の兵法などが戦の基本で,新たな発想も含めて,中世全般にわたって武将自身が担っていたが,皮肉なことに,戦が無くなった江戸時代になって,国家支配者とは独立にこの型のものが登場する。
1-3:官僚分野:まず,古代に多いことが目に付くように,朝廷は官僚によって運営されていたが,職能としては,未分化のため,1:総務秘書型としており,サブ型にも多いのは,他の活動によって,歴史に名を遺す人物が多かったことを示している。明確な職能としては,古代においては,中国に見倣うことが全てであり,4:法務学識型が特別な存在になっていて,後の,学者のルーツでもあり,明治維新後にも,政府の存在,国際関係などを明確にするため,大きな役割を担った。中世においては,官僚に当たる役の大半を武将,武士が担っているため不明確で,江戸時代に入ると,いわゆる幕僚として,サブ型で,1:総務秘書型に記されるものがいるのは別として,5:内務民政型と6:殖産技術型の官僚とみなせる人物が一気に登場増大しており,国家の安定を維持し財源を確保するための領民支配がいかに進んだかを示し,まさに近代を準備したと言える。面白いのは,3:外務通訳型が中世までいないことで,外国といえば中国であった古代は,官人自らが漢語ができ,そうでなくても筆談で成立するようなものであったし,外交と言う点では,これまた仏僧に依存することが多かった。中世に入っても,つきあう範囲は中国文化圏内であり,漢語そのものまで仏僧に依存するのが普通であったため,この型のものは登場しない。江戸時代に入って,オランダという新たに常時付き合うことになる国ができたため,通詞という形で明確に登場し,蘭学を通じて,近代化の道を開くことになる。これとは別に,朝鮮との複雑な関係もまた,この型を必要にすることになった。近代に入って,一気に世界に投げ込まれたことで,爆発的に増えただけで無く,官僚のなかでの,地位も高くなった。2:財務再建型も,前述したように,そもそも国家権力が民から吸い上げる,つまり「入り」のみ管理していれば良かった古代,中世では無用な存在であって,財政再建ということが目的になるのは,江戸時代になってからで,殖産や民政と裏腹のものになったのである。
2-1:社会分野:古代・中世にはメインの方では出て来ないが,サブ型には,5:殖産型と6:文化型がでてくるのは,前者は荘園などの増収のため,後者は,まさに貴族的生活を示すようだ。1:医療型は,一見古そうに見えるが,科学的知識の無いところでは,所詮,仏だのみ,神だのみであり,実に,近世,江戸時代に入って,一気に盛んになる。民が生きて行く上での基本となる5:殖産型も,古代から中世にかけて,長く仏僧らに担われてきたが,近世に入ると,年貢に対応すべく,民の側での殖産に関わる人物が輩出,前者とともに,近代を準備する。それら以外は,近代に入って登場し一気に増大するが,サブ型でみれば,3:教育型は近世に多いことから,近代を準備していることが分かる。近代における6:文化型は,一般の人たちの生活レベルが高くなり,古代の貴族のようなゆとりある活動を始めた証でもあるが,その裏返しとして,差別もまた明らかになり,維新とともに,部落解放,女性解放などが噴き出し,大正デモクラシー期に労働者解放など合わせて,4:解放型が飛躍的に拡大するのである。1-3:官僚分野は,国家としての取り組みであるが,それらを待っていてはどうしようもなく,民のなかでの自らの取り組みがなされると言う点で,つながるものであり,繰り返すまでもなく,古代は,そのほとんどを仏僧に依存,多くは,民に自主性が芽生える中世において登場し,近代を準備することになる。2:福祉型は,中世以前は村社会近世における助け合いでカバーされており,近世のいわゆる大衆社会化に対応して,数の多かった盲人を支える座や稼ぐことのできる針灸ができたが,明治維新後,欧米に対応する形で広がり,大正デモクラシー期に飛躍,3:教育型については,,近世には,いわゆる官学が整備され,それに続くように,寺子屋から様々な塾,私学のような懐徳堂の出現,官民中間の藩校の整備へと拡大して行き,近代を準備することになる。維新後も,官学が整備する以前に慶応義塾があり,官学として東大しか無い時期に,早大の前身たる専門学校が登場,大正デモクラシー期には,いわゆる自由教育,女性教育を中心に飛躍的に広がるのである。
2-2:宗教分野:社会分野のところで,何度も述べたように,そのもとになったのは,仏教の僧であったが,民衆からの支持を得ることで,政治分野に対峙し,ある意味,民を育成支配する存在であり,つねに政治の側から,利用され,排除されてきたのである。そのなかでも,1:教導僧型は,初めて日本独自の仏教を拓いた空海,最澄を皮切りに,いわゆる開祖になるようなレベルの著名な僧たちが主であるが,それ以前においての,誰もがその名を知っている行基は,土木事業その他の殖産をはじめ,教育,福祉その他,幅広く社会分野に対応し,中世に登場する叡尊とその弟子忍性は,福祉に特化した教導僧であった。特定の分野への貢献という点で歴史に名を遺す2:活動僧型になると,国家の不備を補うように,連綿と輩出している。3:神道周辺型は,仏教より古いはずのものであるが,歴史人物として登場するのは,渡来した仏教,さらには,政治の基礎になった儒教とも対抗すべく,取り組まざるを得なくなったものであり,明治維新の廃仏毀釈・国家神道という異常を産み出すことにもつながっている。新たに登場する宗派は,その時点で4:新興宗教型といえるが,現時点から見ても新興宗教と言えるものは中世に登場,幕末から維新への,戦時から敗戦への,民の動揺に対応するかのように,段階的に飛躍している。5:キリスト教型については,戦国時代の民の心労に対応するように入ってきたカトリック(キリシタン)の影響があるが,明治維新後の動揺に対応して浸透したプロテスタントは,そもそも,慈善という形で,福祉や教育に大きな役割を果たし,近代化に貢献した。6:その他型は,リストのところで記したように,千差万別なので,ここでは触れない。
2-3:学問分野:これもまた,そのほとんどを仏僧が担っていたが,政治の背景は儒教で,官僚分野の法務学識型が,いわゆる漢学を担っていた。まず,やむを得ずこの分野に入れた6:蒐集編纂型については,嵯峨天皇の時代には,辞典のようなものが創られはじめ,万葉集,古今集や懐風藻なども,この範疇に入ると考えれば,最も古い時代から連綿と,さまざまなものごとについての蒐集編纂型の人物が登場する。とくに,何度も指摘するように,古今集のその後の影響を見れば,編纂した紀貫之は,歌人以上に,この型にしなければならない人物とも言えよう。そして,日本語の特殊性,漢学など中国との関係などから,5:文学言語型が古代に始まった最初の学問で,同じように,各時代に重要な業績を挙げる学者が連綿と続き,江戸時代の後半には,いわゆる国学が登場,大学者ともいえる本居宣長の業績は,現在もなお,日本人意識に強い影響を与え続けている。その後は,学問と言えるようなものは長く登場しなかったが,戦のなくなった江戸時代に入るや,いわずとしれた「塵劫記」に始まる和算が天文暦学ともつながり,時代を通して発展的に続けられ,幕末維新時に,西洋科学を吸収する基礎にもなった1:数理天文型,それに続いて,中国から入った,主として薬草を対象とした本草学をもとに,植物学に近いものが登場し,さらに,蘭学によって,物理学や化学に展開,西洋科学を吸収する基礎にもなった2:自然科学型,蘭学による科学的思考が,歴史地理などにも結び付いて3:人文科学型となり,明治維新後,とくに日露戦争後の日本至上主義の高まり,大陸への関心などから飛躍的に高まって行く。そして,世界においても新しい4:社会科学型は,維新後はヨーロッパの法制度などへの関心,敗戦後は,アメリカ資本主義の影響で,経済へと広がって行く。
3-1:著述分野:学問と社会とのつながりも一般的には著述によって行われることから,ここに登場。1:詩歌型は,古代では,中国とのつながりで漢詩が主体であり,王朝文化とともに和歌が広がる。中世には連歌,近世には俳諧,近代に入って,和歌は短歌になり,西洋詩が広がり,どの時代も多く,次々と積み重ねられ,大正デモクラシー期に爆発するように,言わば,日本人にとっての基礎的な素養でもあり,サブ型は,それ以上に多い。2:小説型については,紫式部の「源氏物語」は,世界最古の小説といわれるが,物語は小説ではないともいい,現代の小説家につながるもとは,元禄時代の井原西鶴といえ,近世には小説に類する様々な形のものが流行しては消えることを繰り返し,幕末の文化文政時代に登場する十返舎一九が,近代の職業作家の嚆矢となる。そして,坪内逍遥の啓蒙によって,いわゆる小説家が次々に登場,大正デモクラシー期の自由な雰囲気によって飛躍するのである。ついでながら,ファンが多い村上春樹が,芥川賞もとっていなく,国内の小説家からは敬遠されて,もっぱら外国で活動しているのは,彼の作品が,まさに物語であることによるのであり,ノーベル文学賞で世界に知られたガルシア=マルケスの「百年の孤独」も物語といえる。3:脚本型は,芸能の演劇型や口演型に対応,浄瑠璃,歌舞伎,それとは別に落語と,近世に開花,近代に入って,演劇,漫才,映画などへ広がり,やはり大正デモクラシー期に飛躍する。4:随筆鑑賞型は,王朝文化での,清少納言の「枕草子」と数々の女流日記文学が,その後の日本文化の基本となるもので,中世の吉田兼好の「徒然草」を経て,サブ型の方に極めて多く現れるようになり,近代に入ると,多くの分野型の人物が,随筆でも名をなすようになった。5:批評解説型は,随筆に近い評論から,中世には,言語文学の批評解説で深まり,近世,近代へと対象も広がり,どの時代にも,人々を啓蒙しようとする人物がいて,同程度の比率になっており,本業の分野型のものを啓蒙しようとため,サブ型も多く,満州事変後には,国家国民の拠り所を求めるように飛躍する。空海に始まる多くの教導僧の著述は,極めて深い6:哲学思想型のものであり,サブ型をみると,古代,中世とも非常に多いが,メインの方では,近世において,儒学を背景とした思想家が輩出,デザイン三講でとりあげた荻生徂徠のように,プラグマティックな天才的思想家も登場,その影響で,多くの合理的な思想をもつ,いわゆる経世家を輩出し,近代を準備するとともに,西洋の影響を受けた哲学者にも優れた人物を生むことになる。
3-2:造形分野:言葉を介さないと言う点で,もっとも原初的でもあるが,それ故に伝わらないできた面も大きい。1:平面型は,著述とつながる書家とともに,画家も古代に登場,中世の山水画を経て,近世には,最近,人気の集中している若冲だけでなく,その時代の世界のレベルを超える画家が輩出,絶頂期を迎えただけでなく,商品化の対象になる浮世絵も登場し,幕末の文化文政期には戯作の挿絵との関係で飛躍,そして近代の西洋画,写真などへと広がり,それらが民に消化される時期と対応する大正デモクラシー期に飛躍する。2:立体型は,仏像など古代に登場するが,彫刻家という点では,中世を開いた運慶に始まり,近世の円空や木喰五行の仏像多作などもあるが,全体に少なく,近世には陶芸が広がり,近代に入って,ロダンの影響を受けた彫刻とともに,大正デモクラシー期に飛躍する。3:空間型は,ものづくりとしては最も総合的なデザインといえるもので,建築もまた古代以前からあり,斉明天皇の時代の庭園跡なども発見されているが,中世には,禅僧との関係で造園家といえる存在が登場,武将の多くは築城などの点で建築家でもあり,近世には,小堀遠州が,大名というより,建築家,造園家として扱われ,また,優れた大工棟梁が,幕府の建築部門を担ったりするが,職業としての建築家は,近代に入って,西欧の建築学教育が浸透したことにより,大正デモクラシー期に飛躍する。造園の方は,なお,植木職人の世界が続く一方,林学などの分野型でも,優れた造園家が登場している。4:商品型は,近代に資本主義が入って,いわゆるデザイナが登場することに対応,その嚆矢は,画家としては,単なる人気作家に近い竹久夢二で,デザイナとすれば,時代を先駆けた天才であった。宣伝広告と結びついたデザイナが登場し,それが満州事変後の国家宣伝に利用されることで飛躍,戦後のデザインが受け入れられにくい原因にもなった。現在,世界に広がる日本の漫画は,その場面展開が際立っていることから,5:ストーリー型としており,戦後に飛躍するが,そのルーツは絵巻物であり,この分野で日本を世界に冠たるものにしたといえるが,後白河法皇の文化政策で多くの傑作が描かれているものの,作者不明で,鳥獣戯画の作者が覚猷(鳥羽僧正)に例えられ,中世の土佐光信,近世の土佐光起,岩佐又兵衛くらいしか分かっていないのが残念である。6:シーン型は,演劇,映画など,西欧由来の,時間を総合的にデザインするもので,近代に始まるが,次の芸能に登場する俳優について見れば,近世の歌舞伎とつながることは明らかで,単に,その舞台の演出などの作者が分からない,あるいは,座元自身ができたことによる。映画は,その発生時期が,日本の満州事変からの戦時に対応して爆発し,戦後に繋がるのである。
3-3:芸能分野:時間に関わり,身体を用いる芸能にはまた,日本独自のものが多い。1:楽曲型については,雅楽については古代から続くものの,特定の音楽家が知られず,近世に入り,盲人福祉との関係で登場した天才八橋検校によって筝曲が飛躍,近代には西洋音楽の作曲,演奏になるが,天才滝廉太郎は別として,戦争との関係で,優れた作曲家の名が消える一方,歌謡曲や演歌との関係で,独占的に請け負う著名な作曲家が出現している。2:歌謡型は,近世早くに登場した浄瑠璃は,義太夫節などといわれるように歌謡が主体であり,近代に入って,演歌,歌謡曲などの大流行をみる。3:口演型の代表,浄瑠璃と同じ頃に登場した落語は,漫才その他のものがでてきても食われることなく,現代にまでそのまま続く,日本独自のものになっている。4:舞踊型は,まず確立したのが中世に始まる能舞で,現代にも続いており,近代には,全く異なる,バレエ,ダンスが登場。続いて登場する歌舞伎は,舞台で演じる役者に熱中するように,5:演劇型であり,前項で述べたように,そのまま近代の演劇につながるところがある。ここまで,いずれも,著述分野や造形分野の多くの型と同様,大正デモクラシー期に飛躍している。戦後の,とくにテレビとともに登場するタレントなるものは,それだけで新たな型に挙げることには躊躇されるが,定義のところで示したように,様々な芸人,あるいはアイドル的存在と一緒にしてみれば,古代や近世にも,そのことによって名を遺している人物に思い当たることから,6:芸人アイドル型とした。
4-1:実践分野:分類定義のところで述べたように,本講のなかで,他に割り振りにくいものの,社会への関与の仕方が実践的で,その影響の大きいものを集め,独自の型に分けたが,実践的であることは,身体を使う度合いが大きいことでもあり,前項の芸能分野につながるものでなないかと,ここに置いている。1:発明技術型は,ものづくりに対応し,鉄砲が由来するや,時を経ずして,輸出国になるほでのレベルで,それを支配した織田信長が近世を開くことになり,色々な発明家が登場,幕末の天才発明技術家田中久重が,現在に続く東芝の祖になったように,欧米から新たなものが次々と入ってくる近代に,飛躍することになる。近世までの芸能は,まさに2:伝承技能型でもあったが,ここでは,前者と同様,ものづくりに対応,当然,古代からの型ではあるが,名が残るようになったのは,近代への発明技術につながる維新前夜で,突然のように多く現れる。3:コンサル仕掛型は,中世において,武将官間の交渉を僧が担っていることで歴史に登場,それ以前にも,僧は外交通訳で大きな役割をし,その後は,連歌師や俳人,茶人など,様々なところに出入りしても疑われない人たちもその役を担い,結果として危険なことにもなるように,サブ型の方で,その存在の大きさが良く分かる。近代に入っても,政治の黒幕は似た存在であるが,いわゆるコンサルタントとして,明確な職業が登場し,メインの分野型になるのである。4:本業超越型は,自らの業界全体の振興,さらには,民すべてのためになる活動につながるもので,社会分野に対応するように,大正デモクラシー期に飛躍する。近代に入るや否や,幕末の幕府批判に続くように,新政府批判の告発が一気に増大,5:ジャーナリスト型が活発になり,一般に広く知られる人物が輩出,大正デモクラシー期に飛躍するが,敗戦後は,アメリカ支配が枷になっているのか,いわゆるジャーナリズムでの告発は少なく,近年ますます衰えているのが気になるところであるが,報道写真のように,メインの分野型では,写真家すなわち造形分野の平面型であるものの,サブ型としてのジャーナリスト型の方こそメインではないかと思わせる人物もいる。そして,時代に関係なく,6:奔放夢想型として捉えるしかない人物が,社会を色づけている。芸能分野との関係でみれば川上音二郎,この分野のなかの発明技術との関係では平賀源内がその典型であると思われるが,大正デモクラシー期には,自由の雰囲気を裏付けるように,有象無象のこの型の人物が出てきている。
4-2:実業分野:近代の資本主義によって登場する企業に対応するが,すでに江戸時代に準備されていた面もある。1:豪商財閥型は,江戸時代初期には,幕府につながる有力な豪商が登場して,近世の象徴になり,財閥の代表,三井,住友の発祥もそれに続いているように,近代を準備したが,敗戦後,形式的には財閥は解体され消えてしまう。2:国土開発型は,近世の初めに,豪商の一員角倉了以が,地域経済の発展のためにと取り組み,著名な河村瑞賢のように,国内での輸送を円滑にして利益を挙げようと,幕府の許可のもと,河川開発,海運整備などに取り組んで大きな貢献をした者もいたが,維新後の鉄道や,敗戦後の高速道路のように,近代に飛躍する。3:農水食品型は,近世までは,農業は,すべて庶民に依存していて,時の権力者がそれらを取り上げてしまう形であったが,水産業には,後述の「にんべん」のようなものも登場している。近代には,国民が豊かで自由になる大正デモクラシー期には,消費者に近いことから,著名な企業が次々登場する。現代において,日本を代表する4:製品生産型は,近代に入り,世界と競争していく上で基本になった型であり,欧米から,あまり遅れることなく次々と誕生,世界レベルの発明技術にもことかかず,農水食品型に対して,戦時,敗戦後も続けて多い。5:販売サービス型は,江戸時代中頃に,髙津伊兵衛が創業した,削り節やふりかけ,調味料を製造,水産加工品メーカーとして業界最古参の「にんべん」が,一般には,日本橋の老舗店舗として知られる。良く知られているように,デパート三越のルーツは,財閥三井のスタートにもなっている三井呉服店であり,代々継いでいく点で,豪商財閥型に類似する。6:メディア娯楽型については,そのような施設等ができて流行ったのも,江戸時代に,今で言う大衆化が進んだことによるのであり,サブ型に多いように,大衆に呼応する仮名草子や浮世絵などを扱う書肆を営みながら,自ら作家になる人物もいるが,後期には,現代においても,この型の天才と見なされる蔦屋重三郎がでてくるのである。近代に入ってすぐに,実践分野のジャーナリスト型と表裏一体に,多くの新聞社が登場,やがて,現在なお有名な新聞社や出版社が続々誕生,大正デモクラシー期になると,宝塚歌劇,松竹,吉本興業と,現在もなお派手に活動している企業が誕生するなど,後述するように,文化のデザイナとしての役割が大きい。
4-3:競技分野:1-2軍事分野は,相手を打ち負かすための血みどろの戦いであり,戦国時代は,世界でもまれに見る複雑怪奇な内乱で,アジアに進出してきたポルトガルはじめヨーロッパ列強も,恐れをなして,植民化に二の足を踏まざるを得なかったのであるが,その内乱を打ち止めにして,戦を無くしてしまった徳川幕府もまた,世界に先駆けた政権であった。いわゆる競技は,古代においても,歌合せほかの遊びとしてあったが,戦を無くしたことによって登場する競技は,命がけでもあるという点で,戦の代替物であり,そのなかでも新しいスポーツにおいて,大谷翔平のように,世界的に活躍するような選手こそが,現代における本当の一流人物であり,新たな時代を担っていくことが期待されるのである。こうして,この分野が軍事分野とつながることによって,活動のマンダラは完結する。⇒「職能からみた新日本人論」 戦に代わる男の戦いとして最初に登場したのが,6:茶道鑑識型で,茶そのものを当てる闘茶であり,それがベースになって茶道ができ,茶道具などによって,鑑識もまた戦いとして広がっていき,武将が茶道と直結しているのも当然であるが,企業間の競争は,現在の戦いでもあって,企業のトップのなかには,茶人として著名な人物も多いのである。そして,囲碁将棋の1:棋士型もまた,もともとは仏僧の世界では普通のもので,武将たちも楽しんでいたようであるが,戦がなくなる近世に入るとともに,専門職として登場し,現代なお大きなニュースになっており,続いて,まさに戦そのものの代替になった2:武道型が,近代に入って,西欧文化の3:スポーツ型に展開,世界でも新しい巨大な分野としてスポーツが続々生まれており,日本では,戦時の国威発揚と関連して拡がり,戦後につながって行くが,それと呼応するように,スポーツに対応するものが主の5:競技振興型が登場,この三者を繋ぐ結節点になった嘉納治五郎の存在の大きさが分かる。最後に,他人との戦いでは無く,辺地や登山など挑戦する4:探検紀行型をこの分野に入れたが,これも,近世の平和がもたらし,著述分野の随筆鑑賞型のように,様々な,分野型の人物が国内を探検紀行,近代には,世界各国を旅するサブ型が多い。
X:特異分野:以上のように,(日本の)社会との関係で明確に位置付けられない様々な活動が,社会全体を豊かなものにしていることは言うまでもないが,近年,欧米文化の影響もあって,その多くが否定されるようになってきた。いずれにしても,開国後に一気に増大する最後の外国人型以外は,時代と直接関わらないものではあるが,言葉は悪いが'歴史は女によって創られる'のは一面真理を突いていて,1:陰の女性型こそがその活動の主体であったことさえある。随筆鑑賞では無い本来の意味での日記など,なにかしら記録を遺す2:記録伝承型は,その時代の活動としては意味なくとも,本当の歴史を知るためにも貴重なもので,そのことによって,歴史的人物として名を遺すことになる。サブ型を見ると,幕末維新時や戦時戦後に多くなっているが,当然であろう。属している社会から逐電や隠遁する3:脱社会型は,平安末の西行が始めて,その後の多くの人物において理想的生き方にもなったが,現実には容易いことでは無く,おちこぼれその他によって,社会との関係を断たれている場合も多い。4:反社会型については,単純に,世の中を変えようと権力に向かうことを入れてしまうと,どこか矛盾してしまう。できるだけ冷静に見て,いわゆる犯罪に当たるものや,暴力団のように反社会的な活動に絞る。この型が,大正デモクラシー期に多くなっているのは,テロ社会の始まりにも対応しているが,平和や豊かさに溺れ,他人のことに思い至らない時代の表れで,近年の世界の状況にも似ているようだ。海難漂着なども含めて,日本という島国においては,理由はどうであれ,また,国内で評価されるかどうかにかかわらず,5:在外活動型には特別の意味があろう。同じく,島国日本においては,古代の鑑真から,江戸初期のアダムズ,維新を支えたグラバーや維新後のお雇い外国人まで,数は少なくとも半ば日本人として活動して決定的影響を及ぼした6:準日本人型の人物がいる。沖縄は,かつては琉球王国というべつの国であった故,他の日本人と同列には扱えないし,近代の植民地やアイヌの問題など,難題も多い。近代に入って,日本に亡命してきたロシア人の影響が多いのと同様,中世の元僧,近世の明僧などについても,さらに拾っていきたいものである。
2:分化する前の元になった分野・型とその内容
天皇型:国家支配型といえるのは,蘇我氏の支配を脱し,日本国成立の礎をつくった天智,天武,持統天皇,それに続く,藤原不比等が確立寸前に至るも,その子らのいわゆる<藤原四卿没>によって混乱に陥り,孝謙(称徳)天皇は,淡海三船をして現在でも誰もが当たり前のように口にするそれ以前の天皇の漢風諡号を撰じさせるも,道鏡をして,天皇の地位脅かすに至らせ,<宇佐八幡神託>によって危機回避,その後近世まで続く平安京をつくった桓武天皇,そして,日本人意識を昂揚する国風文化を主導した嵯峨天皇までであろう。その後,摂関藤原氏の支配を脱し,院政という方式を編み出すも,すぐに没してしまった後三条天皇,実際に始まった院政期には奥州藤原氏が栄華を誇るように,とても国家支配型とは言えないし,武家政権から権力を取り戻そうとした後鳥羽天皇は配流され,一時的に国家支配型になった後醍醐天皇も,結局敗れてしまった。維新により,見かけ上権力を握った明治天皇も,国家支配型といえないことは言うまでもないだろう。なお,最初に登場する推古天皇を支えた聖徳太子も,皇族型ながら実質的には国家支配型の天皇ともみなされるだろう。つけくわえれば,リストで取り上げている嵯峨天皇までの16人の天皇のうち,いわゆる女帝は,推古天皇,持統天皇はじめ6人になり,そのうち2人は重祚しているので,実質8人と半分にあたる。つまり,男女平等に近かったといえ,天皇を利用とする時の政権が,天皇は男系に限るものにしたのである。さらに,不比等というより橘三千代の娘で人民最初の皇后になった光明皇后が,夫の聖武天皇の大仏に至る仏教振興策に影響を及ぼしたことは良く知られているが,教導僧に導かれるように施薬院や悲田院などの福祉施設を設置,嵯峨天皇の皇后であった橘嘉智子は,聖武天皇を支え,光明皇后の異父兄の橘諸兄の曽孫に当たり,橘氏の子弟のために大学別曹学館院を設立しているなど,皇室は近代に至るまで,福祉型,教育型などを先行する役割を担って行く。
1-1:政治分野の1:国家支配型:古代は,蘇我馬子に始まり,クーデタで権力奪取した中臣鎌足に始まる藤原氏が摂関となり,道長の栄華を迎えるも,その子頼通で終わり,院政期の空白を経るうち,サブ型が,1-2軍事分野の1:統率型の平清盛が現れて中世に入り,源頼朝により武家政権が始まる。以後,実質的な国家支配型は執権北条氏となるが,足利尊氏によって国家支配型の将軍が復活するものの,政治から逃げてしまう将軍義政の登場によって,応仁の乱が勃発,以後の将軍は力を発揮することができずに,いわゆる戦国時代の空白,混乱期になってしまう。その状態に止めを刺して近世の幕を開いた織田信長と,それに続く豊臣秀吉が実質的な将軍の役割をし,江戸幕府を開いて名実ともに将軍になった徳川家康まで,サブ型が,1-2軍事分野の1:統率型の人物であって,武家政権そのものであった。それ以降続く徳川将軍は,形式的に留まり,サブ型から国家支配型が消えるのと並行して,かつての摂関藤原氏に類似し,近代の内閣首相につながる首席老中が実質的な国家支配型になるのである。そのなかで,家光以降,綱吉,吉宗,かつての天皇のように,自ら実質的な国家支配型になった将軍が見られるが,11代将軍徳川家斉のいわゆる大御所政治を含めて55年に及ぶ支配は,大奥入り浸りで,民を無視し,地方の有力藩が力を持つようになると言う点で,古代の院政期のようなものであり,その後,幕藩体制は崩壊して行き,最後の将軍慶喜が大政奉還,大久保利通はじめ,いわゆる志士,つまりサブ型が,5:時代変革型の人物の国家支配となり,内閣,帝国憲法,帝国議会という現代につながる政権の基礎を確立した伊藤博文を初代として,首相が国家支配型になるのである。
1-2:軍事分野の1:統率型:坂上苅田麻呂を代表に古代には朝廷の国家支配を維持すべく将軍が置かれてきたが,天皇の地位をも狙ったと言われる平将門の乱を契機に,東国で平氏,源氏の武士が勃興,前述のとおり,平清盛以降,家康まで,もっとも上位にあるべきこの型の人物は,国家支配型として挙げられることになる。そして,南北朝を契機に,大内氏や朝倉氏から,北条早雲や今川氏親以降,地方レベルながら,この型のものが登場,後の幕藩体制を準備する1-1:政治分野の2:地域支配型のものがサブ型に記されるよになり,戦国時代の著名な人物が次々登場,信長の登場で終止符を打たれ,家康によって,まさに地域支配者たる藩主になるのである。このように,中世においては,国家支配,地域支配と軍事分野の統率型が一体であり,それらが明確に分離独立する,徳川幕府による近世の始まりは,西洋近代の始まりと,時代的に軌を一にしている。
1-3:官僚分野:古代の朝廷において,中国から制度を導入したこととの関係で,中国語をマスターすることを一義的に,いわゆる漢学を専門とする4:法務学識型の人物の名が登場,その最初の,聖武天皇の時代に,初の漢詩集「懐風藻」をまとめ,続く,孝謙天皇のもと,歴代天皇すべての漢風諡号を考案した超人的文人淡海三船は別にして,菅原道真の祖父清公が,学者官人家系の菅家の基礎をつくり,いわゆる文章生という,官僚分野のなかで法務学識の専門家を育てていく,明治維新後の東大法学部にあたるような仕組みができ,大江匡衡に始まり,匡房という大学者を生み,鎌倉幕府の創設期を支えた広元に至る大江家まで,多くの人材が輩出,その最後を,中世への大変革期に,権力者たちに信頼され,菅原道真以来,儒学者で唯一人没後神になった清原頼業が飾る。中世には,これら官僚は儒学者となり,学者として独立,武家ほか広く教育をし始めたらしく,世界最古の大学ともいわれる足利学校の誕生を見るのであるが,それを再興して,結果的に近世を開く準備をしたのが,将軍足利義教と関東公方足利持氏の間の調整に苦労した管領上杉憲実であり,教育型として忘れてはならない人物といえよう。
2-2:宗教分野の1:教導僧型:日本国の形成の始まりは大陸からの仏教の伝来にあり,すべての社会的な活動分野型の人物に先駆けて,登場したのが1:教導僧型で,民衆教化と社会事業に全力を投入し,宇治橋造橋伝説もある道昭に続いて登場した行基は,知識集団組織して民衆を教導,膨大な社会土木事業を営んで,早くも国家支配型に対抗するような存在となり,国家は大仏造立を契機に彼を取り込み,初の大僧正にしたのであるが,すでに,2-1:社会分野の3:教育型と5:殖産型のもとになっている。最澄が開き,円仁,円珍によって整備された比叡山は,その後,僧になろうとする者のほとんどが最初に出家して学び始めるという点で,巨大な教育機関でもあったが,その後に登場し定着する宗派の本山も同様に教育機関であり,とくにその傾向の著しい本願寺などが広がって行ったのも当然であろう。したがって,教導僧型はその名に含まれているように,同時に,2-1社会分野の3:教育型であり,2-3学問分野にもつながるものなので,サブ型には記していない。空海に始まり,その後も道元など,著作によって間接的に時間を超えて教導していく者については,3-1著述分野の6:哲学思想型に分化していく元になる。同時に,興福寺や延暦寺の僧兵に始まり,一向一揆から始まる信長と対決が極致になった本願寺など,軍事分野さえ持っていたということになる。2-1社会分野の2:福祉型については,とくに,今日につながる明確な取り組みをした叡尊とその弟子忍性が特記される。2:活動僧型については,学僧が学問に特化したもの,歌僧,画僧など,それぞれに早くから別分野で確立しているものなど別にして,最初に登場すし不比等のアドバイザになった道慈はじめ,源頼朝と院との間奔走した文覚,承久の乱の黒幕尊長など,4-1実践分野の3:コンサル仕掛型の僧は多く,中世になって"黒衣の宰相"と呼ばれる活動僧よりコンサル仕掛型として挙げられる賢俊,満済以降も,今川義元の兵法参謀になった太原崇孚,幕府創始期に宗教行政の中心になった天海,公武斡旋に奔走した松花堂昭乗など枚挙にいとまない。
3:歴史的にみた職業の発生・分化・転化・衰退パターン
以上述べてきたように,職能は,文明が進むとともに,多様になるが,その歴史をパターン化すると,動植物の系統樹のように,必ず何らかのものから派生,分化,転化してきて,その間には,動植物同様,隆盛から衰退し,ついには絶滅してしまうものも見られるということになる。そういう観点に立って,作成した下図に従い,以下に,整理しておく。
まず,統治された社会(文明)が実現する以前からの生業としての農林水産業は,職能以前のものとして,取り上げず,また,日本では,天皇制という世界的に見ても特異な統治システムが形成され,当然のことながら,皇室は職能選択の対象にならないことが前提となるが,そもそも社会というものが登場した時点で最初に必要になったのは,外敵から守るための軍人であり,それと一体になる形で当該社会を治める長(オサ)であった。その支配のもと,農耕や狩猟など,始めはジェンダーによる分化が始まり,その一方で,社会化する上で個々人に生じる様々な葛藤を救う巫女のようなものが発生したと考えられる。
文明化が始まると,軍事(武断)よりも政治(文治)が重要になり,長(オサ)周辺の政治家と,それを支える官僚的職業が分化,政治・官僚・軍事三分野による支配が確立,以後,天皇と公卿,将軍と藩主など,様々な体制ではありながら現代まで続く。さらに文明が進み,軍事の比重の下がる場合も生じると,その代替として武道が登場し,西欧ではスポーツに進化していく。現在のサッカーの国際的な対戦が,現実には敵対している国同志でも実施されたりするのを見ると,まさに,戦争の代償行為であり,戦争を無くす手がかりさえあるように感じられる。ところで,憲法九条で軍事を否定するわが国は,その先を行っているといえるだろうか。
同様に,巫女的なものはいわゆる宗教となり,日本では仏教伝来による僧侶がその中核を成すようになる。初期の僧は,行基を始め,今日でいうところの社会事業・活動家でもあり,その後の高僧は皆,学問の先端を担い,中世以降は画僧など,芸術家をも先取りする。僧が社会活動家や学者に分化して行く結果,本来的宗教の役割はどんどん小さくなり,大半のお寺は,最早葬式などのためにしか存在しないような些末なものになってしまった。いずれにしても,宗教・社会・学問については,人民を支える社会貢献分野として括ることができると言える。
芸術分野は,人類誕生以来の情動としての歌謡や絵画がルーツであるが,文明化とともに宗教を支えるものとなり,わが国でも,かつて,文人のように詩歌や書画全てをこなしていたものが,近世に入ると,西欧のように,自己追求型の芸術家が登場,文字による文筆,様々な造形などの芸術家に分化する一方,下層階級のものだった芸能が支配層に取り入れられて,芸術分野に入ってくる。
近世に登場した,市のレベルの,また国家的に統制された貿易のレベルで行われてきた商業的なものや,職人レベルから発展する工業的なものが,近代に入って,企業として大きく広がって行き,わが国では西欧の近代化とほぼ同じ頃には国家とつながる豪商が登場,江戸時代を通じて様々な取引の手法を発展させてきたので,明治維新後の近代化にスムーズに対応できたと言える。企業に至らずとも,今まで述べて来たような職業の枠におさまらない実践的なものも,どんどん登場しており,グローバル化の競争社会のなかで,大きな役割を持つようになると考えられる。この競争という点でスポーツも一緒であり,実際,世界的レベルで戦っている選手たちの言動を見ると,現代日本では最も優れた人物が多い感じさえするのである。
職能選択の対象にはならないが,社会を構成するものとして,まず歴史を通じて,男や家庭を支える存在として大きな役割をしてきた(陰の)女性群があり,日本の神様の大元は天照大神で女性とされ,古くは母系社会であり,女・男(西欧ではなど)や,女性が天皇になってもそのまま天皇(西欧では)とされるなど,西欧でのManとWoman,KingとQueenなどのように,言葉の上での差別,つまり本質的差別は無かったが,明治維新以後,西欧化とともに男を支えることが強調され,本格的差別が始まったといえる。ついでながら,西欧では,兄弟に長幼の別が無いのに対し,東アジアでは厳然と区別されるように,長幼の差別が強く,これが若手の登場への阻害要因になっていることは否定できまない。その上でも,年齢に関係無く実力が評価されるスポーツ選手は,やはり未来を先取りしているように見える。そのほか,社会から排除されてきた被差別民や河原者,それとは別に,海賊やそこから派生したヤクザ,あるいは博徒など反社会的と言われながらも社会の安定に果たしてきた役割が無視できないもの,あるいは日本文化特有の,隠遁・遊行・放浪など脱社会的存在がある。他方,日本社会は移民や高度成長期の中東の企業者など海外に出た日本人には冷たい社会であり,同時に,外国人もあまり受け入れない社会なので,海外で活動した日本人,日本人として活動した数少ない外国人も特記される。その他,日記や伝承で社会に貢献する者も多く,これら全てを,社会の通奏低音的な存在として捉える必要があるといえだろう。
現代は,いわゆる専門家(スパシャリスト)ばかりになってしまい,世の中の大きな問題に対処できないため,専門バカとも言われ,ジェネラリストの育成や全人的人間への回帰の必要性なども叫ばれているが,系統樹のあり方から見てもあまり期待できず,さりとて,職能分野をどのようにネットワークさせれば,統合された答えを導きだすことができるのかも分からないというのが現実だろう。
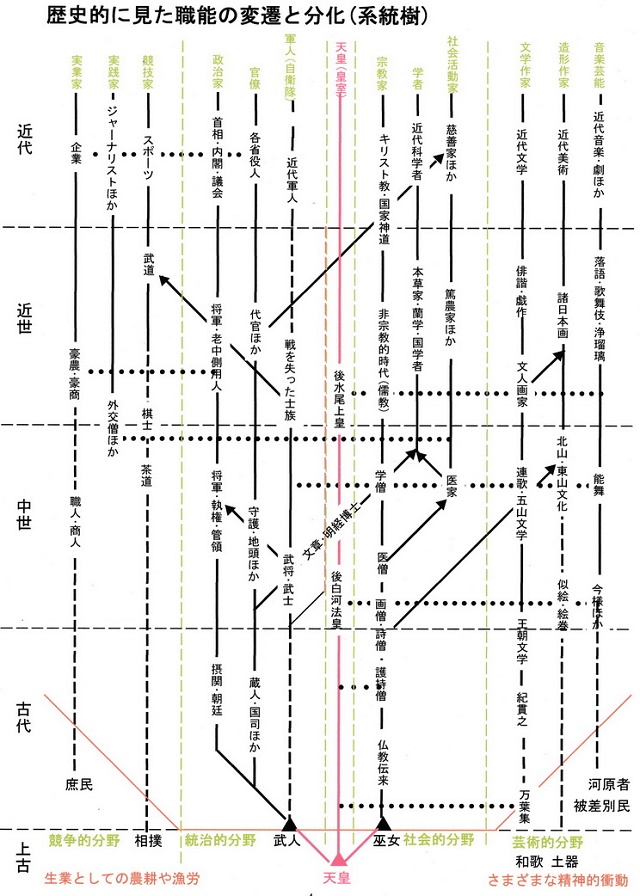
第2話:女性が文化をつくる~自立する女性
1:時代別にみた女性の分野型
女性だけを対象に,第1話と同様,「はじめに」に示した時代区分と活動の分野型をクロスして,該当する人数を記入した表によって,分析してみよう。⇒PDFファイル「時代別分野型数(女性)」
その前に,そもそも,女性の全体の数・比率と,分野ごとのそれを確認しておくと,まず,一枚年譜の作成にあたっては,できる限り女性を取り上げるように努めたつもりであるが,データベース化した段階の総数3,635人に対して,531人,率にして14.1%にとどまっている。ちなみに,ほぼこの値と同じ7分の1という比率は,国勢調査などの調査に関わって有名な"嘘つき率"だあり,男子に偏った大学等で,教室での比率がこの値になると,女性が多くなったと感じるキーになるものなので,データベースとしては,ギリギリの数字にはなったとも言える。
女性の比率を分野型別にみると,定義上,女性が100%になる皇后型を含む皇室分野と,同じく陰の女性を含む特異分野は,また,一般の人の職能対象でもないので,除外すると,まず,支配に関わる活動で,完全なゼロの1-2:軍事分野のほかの1-1:政治分野,1-3:官僚分野もほとんどゼロに近く,女性首相の登場への期待が大きいのも当然だろう。
次に,社会のサポートに関わる活動をみると,2-1:社会分野は,総数112人で3分の1を占めて多く,そのなかでも,福祉型が60%と際立って多く,福祉はまさに女性によって支えられていることが明確になり,直接的に女性解放めざす解放型と,間接的に女性解放をめざす教育型のいずれもが43%台,看護師が支える医療型が30%強と多く,文化型でも,18%強と,平均の比率を上回っているが,殖産型だけは,ほとんどゼロである。2-2:宗教分野は,全体としては,13%弱と,平均の比率をわずかに下回るものの,新興宗教型とキリスト教型は,ともに数も,比率もほぼ3分の1と同じで多いのが目立つが,それに続く2-3:学問分野が,全体として3.5%しかいないことに驚く。もっとも開明的であるべき分野がもっとも差別的であることを如実に見せられているようで,九品塾の基本講義のデザイン論のところで指摘した科学至上主義の問題の証にもなっている。
いわゆる芸術に関わる活動に入ると,3-1:著述分野は,全体としても,4分の1近くと多く,とくに,随筆鑑賞型が半数を越え,詩歌型が36%近くと多いのは,一般の印象通りと思われる。3-2:造形分野は,全体として1割余りと少ないのが残念ではあるが,近代に登場してきた商品型で,27%余りいることに救われる。3-3:芸能分野に移ると,女性が当然のように多い芸人アイドル型があるものの数が少ないので無視して,全体で37%弱と著述分野より若干多くなり,とくに,歌謡型は54%余り,舞踊型がちょうど半数,数の多い演劇型でも,38%と,この分野全体の比率とほぼ同じになっている。このように,芸術に関わる活動においては女性が多く,いわゆる文化の歴史は,女性によってつくられていると言って過言ではなかろう。
つけたしのようになるが,競争にかかわる活動では,4-1:実践分野が全体で7%強,4-2:実業分野で6%強,4-3:競技分野でも9%強と少なく,最初の支配に関わる活動同様,社会への影響も大きいので,今後の活動に期待したい。
ようやく,時代別の分析に入るが,初めに,第1話と同様,表に記入されている数字は,当該時代に活動していた人物の数で,活動期間の長い人物は,前後複数の時代にも重複して数えられていることから,延べ人数になっていることを指摘しておきたい。そのため,右側最後に,実数と実数としての比率を示しておいたが,近代には,延べ人数の値がかなり大きくなったりするものの,その時代ごとの比率には大きな違いは無いので,傾向を分析する程度では全く問題は無いと思う。また,古代,中世,近世,近代に分けたそれぞれの時代について,実数での女性の割合を見てみておくと,古代が,220人中37人で16.8%,中世が,245人中22人で9.0%,近世が,692人中55人で7.9%であり,近代は今までのところで,2,478人中417人,古代と全く同じ比率の16.8%ということは,近代において女性が進出したということを前提とするならば,古代における女性の多さが明確になり,中世は戦の時代であった故,少ないのは当然としても,戦の無くなる近世の比率は古代の半分以下になっているのは,儒学による統治システム,はっきり言えば,論語によるものだろう。
活動の分野型でみると,まず,0:皇室分野は,古代においては,天皇型が14.5%,皇后型が39.5%と,皇室分野だけで,全体の6割近く,権威の頂点が,まず,アマテラスの末裔とされる女帝であり,一時的には,国家支配の権力を発揮する男性の天皇が出るものの,藤原氏の支配が始まると,権力を剥奪されてしまい,女性である皇后が大きな役割を発揮するようになったと言え,武家政権になる中世においても,皇后型の比率は37%余りと高い。近世には,徳川政権の支配で,ほとんどゼロになり,天皇の力が回復されたという近代に入っても,その数は無に等しく,この点からみても,古代と中世はつながるが,近世以降は全く別ということで,ある意味,西欧の近代化と軌を一にしているとも言えよう。
1-1:政治分野は,国家支配型は,鎌倉幕府創設期(Ⅱ-1-3)に,1人いるだけであるが,言うまでも無く,歴代最強の女性といわれる北条政子であるが,男尊女卑の歴史観のなかでは,陰謀にたけた悪女のように扱われ,源頼朝は止むを得ないとして,北条義時の陰になるような位置づけになっているのが残念であり,一枚年譜を冷静に見てもらえれば,武家政権の革命が定着する軸になったのは,政子その人であり,のちの徳川家康,明治維新の大久保利通に匹敵するような存在であった。そして,中世の最後,応仁の乱後の戦国時代(Ⅱ-3-3)に一人あげられる陰の女性型の人物もまた,すぐに分かる通り日野富子であり,政治から逃避してしまった夫の代役を務め,サブ型で国家支配型にあげられるような女性であったことから,徹底して男性の時代と見られる中世も,優れた女性が幕を開き,優れた女性によって,幕を閉じられたと言っても,過言ではないだろう。近代になって登場する党派活動型によって,女性がかなり進出したようにみえるが,比率をみれば話にならないほど少ないのは,現在なお問題になっている。
女性がゼロの軍事分野を飛ばして,1-3:官僚分野をみると,全体では政治分野と同程度の少なさであるが,古代において,宇佐八幡宮の神託の和気清麻呂が有名であるが,もともとは優秀な女官であった姉の和気広虫が派遣されるところを,その代役として派遣されたといい,持統天皇の信頼を得,再婚した藤原不比等の昇進を支援,夫没後も娘光明子の立后を実現した橘三千代,歌舞の才で采女として出仕し,廉謹貞潔で典侍まで出世し,日本史上,最も古く記録された女官飯高諸高など,男性に引けを取らない人物がいたのである。近世初めには,豊臣秀吉の正室で,実子を得ずも,秀吉の正式な代理人として扱われ,公武から慕われた北政所,徳川家康の側室ながら,才智にたけて,大奥を統制し,政治的にも家康・秀忠をサポートした阿茶局,徳川家光の乳母から,家康に直訴して家光の将軍継嗣に成功,大奥を牛耳り,無冠無位で参内するまでに至った春日局など,一義的には陰の女性ながら,サブ型に,総務秘書型を挙げなければならない女傑がいて,まさに,歴史を動かしていたこと指摘しておこう。
その官僚分野につながり,そのほとんどが近代に登場して爆発的に増加した2-1:社会分野は,前述したように,女性が多い分野であるが,女性全体のなかでも,2割以上を占めるように,近代社会は,まさに女性によって支えられているにもかかわらず,女性差別から抜け出せないでいるのは,なんとも情けない。端的に分かりやすい例で言えば,医療型で,医者という職能は,本来,人の命を助けることを目的としてきた神聖なものであったはずなのに,西欧近代の科学至上主義によって医学となり,患者は,その研究対象でしかなくなり,生身の人間として扱われなくなっていることは,多くの人が感じていることでもあろうが,その冷たさを救っているのが,ほとんどが女性の看護師であることもまた,多くの人が感じていることでもあろう。人数も多いので,当然に知っておいた方が良さそうな人物を,生年の早い順に挙げると,1:医療型では,兼山の娘で,失脚憤死した父の尊厳回復を胸に,遺族全員が幽閉されるなか耐え忍び,赦免後,医者として活動,生涯孤高で,谷秦山が"詩文小町の妙,経術大家の風"と激賞した野中婉,苦難の道を歩んで女医第一号となり,医者として成功するも,牧師と再婚し,北海道へ渡った荻野吟子,わが国最初の女医養成機関(現在問題抱える東京女子医大の前身)を創立,女性の教養と地位の向上につとめた吉岡弥生,日本の看護婦を先駆・代表する生涯を送り,世界初のナイチンゲール記章受章者にもなった萩原タケ,松沢病院を世界屈指のものにし,"松沢の母"と呼ばれる石橋ハヤ,2:福祉型では,<戊辰戦争><磐梯山噴火><日清戦争>と,ことあるごとに,孤児等の救済に努めた瓜生岩,知的障害があった長女を孤女学院に預けた縁で,石井亮一と再婚,以後,滝野川学園経営に生涯をかけた石井筆子,財閥の娘で外交官の妻だったが,<敗戦>後,混血戦争孤児のための施設を開設,救済に尽力した澤田美喜,3:教育型では,亀井門三女傑で,志士らと交流,維新後,頭山満が入塾し,塾生の多くが内乱に関与,まさに男まさりの高場乱,生涯女子教育に専念,画家としても一家を成し,独身を通した跡見花蹊,7つにして最初の派遣女子留学生,女子教育に目覚めて奔走し,女子英学塾(津田塾大学)を創設した津田梅子,婦人記者の先駆,夫と{婦人之友}発刊後,キリスト教に基く{自由学園}創設した羽仁もと子,日本初のOLとなった後,{ドレスメーカー女学院}を創設,服飾デザインの発展に生涯をかけた杉野芳子ほか,学校創設した人物は多数にのぼる。4:解放型は,まさに女性解放であって,廃娼運動に生涯,少額寄付の大衆参加策を次々と発案した一方,キリスト者として人生最後も全うした久布白落実,{青踏}発刊,女権宣言して端緒を開き,戦後,日本婦人団体連合会初代会長になった平塚らいてう,山川均の妻で,母性保護論争で論壇に登場,<敗戦>後,労働省の初代婦人少年局長になった山川菊栄,婦人参政権運動一筋に生き,戦後は理想選挙を唱えて参議院議員となり,圧倒的な支持を得た市川房枝,<大正デモクラシー>期に婦人セツルメント運動始め,<敗戦>後に{主婦連}創立,消費者運動の草分けになった奥むめおなど多数。2人しかいない5:殖産型は,夫と"いぶし飼い"創案し,夫没後,伝習所を開設した永井いと,<敗戦>による華族廃止で開拓農民となり,全国的活動と,対照的な前後半生を生きた徳川幹子,そして,6:文化型は,東京新宿{中村屋}の女主人で,夫とともに芸術家を支援し,<大正デモクラシー>を代表するサロンにした相馬黒光,劇作家として第一人者になると,{女人芸術}創刊して多くの女性を支えた長谷川時雨,戦前はタゴールの来日などに尽力,戦後は,日本人初のソ連入りなど,国際的に大活躍した高良とみ,夫と戦前からの映画の洋画輸入や戦後の邦画国際化に貢献,国立フィルムセンター設立にも尽力した川喜多かしこ,といったところか。
2-2:宗教分野をみると,中世後半に尼僧が,近世初期にはキリシタンがというように全く異なる宗教ながら,それぞれ,その時代の女性の14%前後の比率を占めていることが,この時代の女性がいかに苦難の状態にあったかを物語っているようだ。2-3:学問分野は,前述のように,露骨に女性差別の強いことから,11人しかいないが,それだからこそ,名を遺すに至った女性のレベルは高く,生年の古い順に,儒学者の妻で,越後高田藩主からの要請で,女訓書「唐錦」6部13巻を書き上げた大高坂維佐子,日本初の女性博士で,高女用教科書書くも文部省が黙殺,文化勲章推薦も前例無いと紫綬褒章に終わった保井コノ,帝国大学初の女子学生,日本初の女性理学士で,2人目の女性理学博士になった黒田チカ,女性の大学進学ができず,理研研究生となって,緑茶の研究で,わが国女性の農学博士第1号になった辻村みちよ,転変の後,俗事は夫に任せて自宅から一歩も出ずに研究,女性史学を確立した高群逸枝,それに,サブ型では,早くから栄養問題を啓蒙,<敗戦>後,基礎食品群を提唱,長寿社会化への道を開いた香川綾,第二次大戦下,キュリー夫人の指導で,フランスの博士号を取得,戦後も,フランスで研究活動した湯浅年子などである。
3-1:著述分野は,古代から近代に至るまで,その時代の女性全体の2~30%と,ほぼ同じ比率で登場しており,いかに日本文化のベースになっているかを示している。そのなかで,古代の藤原道長とその次のいわゆる王朝文化の時代(Ⅰ-3-1,2)と,近世の元禄時代から文化文政期(Ⅲ-2-3~Ⅲ-3-3)にかけてに限られて多く登場すること,近代の大正デモクラシー期(Ⅳ-2-2)以後爆発的に増えることから,人物について,ここでは省略するが,後述の「際立つ時代」「大正デモクラシー」のとろで,取り上げることになるだろう。3-2:造形分野については,あまり目立つ人物はいないが,商品型との関係で,後述の「デザイナ的人物」で触れられよう。3-3:芸能分野については,歌舞伎が,近世初めの有名な出雲阿国に始まるとされるも,風紀統制のためと,男性に限るものにされてしまい,結局,明治維新後の近代の演劇型で爆発的に登場,女性の自立において,大きな分野になったが,よく知られている人物も多いので,省略させてもらおう。
前述のように,4-1:実践分野,4-2:実業分野,4-3:競技分野においては,女性は極めて少ないが,その女性たちが,どんな人物であったかは,今後のためにも知っておいてもらいたいので,何人か紹介すると,没落武家の子三井高俊に嫁ぎ,商家として確立すべく家業差配し,息子らを訓育,高利が三井の祖になった三井殊法,三井の娘に生まれ,維新に際し婚家のために立ち上り,女性解放・教育にも尽力した広岡浅子,紡績工場設立し,嫁のウメとともに{大同毛織}の開祖とされる栗原イネ,婿養子の夫とともに{三省堂}を創業,大ヒットで成長するも,百科辞典で倒産した亀井万喜子,わが国女子体育界の先達井口阿くり,無敵の女流武芸者として名声を得,諸女子校で教授,薙刀術の世界をリードし続けた園部秀雄,体操教員検定に女性として初めて合格,体操選手の名門{藤村学園}を創り上げた藤村トヨ,{講談社}創立者野間清治の妻で,事業の半分を負担して"創業の母"と呼ばれ,子夫急逝で自ら社長になった野間左衛,"新しい女"の中でも際立って特異な人生を送り,"仏教界のスター"から,作家として華開くも早世した岡本かの子,夫の道楽をヒントに{吉本興業}を創設,関西芸能界を支配するに至った吉本せい,天才的スプリンターで,日本女子選手初の五輪メダリストとなるも,冷たい世論に,夭折した人見絹枝,美容学校設立を皮切りに,化粧品や美容器具の販売まで多角的な経営で,山野美容帝国をつくった山野愛子らである。
最期に,X:特異分野については,1:陰の女性型が,中世後半から近世にかけて圧倒的に多いことは前述したとおりであるが,近代に入ると,5:在外活動型が1:陰の女性型と同程度の比率になっているのは,開国によって,差別の国から逃避するという意味のあったことも忘れてはならない。
2:文化際立つ時代と女性
前項で述べたように,日本史上,芸術的活動の際立つ文化的な時代として有名なのは,古代における王朝文化と,近世における元禄文化であるが,まず,前者については,嵯峨天皇の弘仁文化の時代には,日本化が始まり,紀貫之の,後述する日本文化のデザインによって,平安時代の栄華を実現した藤原道長の庇護のもと,女流文学を主体とする王朝文化が開花するということになる。
嵯峨天皇(上皇)の弘仁文化の時代は,はじめにの時代区分では,Ⅰ-2-2②と③にあたり,まず,最澄,空海によって日本化された仏教が創始されたのを背景に,菅原清公という道真につながる学者家系が始まり,藤原緒嗣,冬嗣という藤原摂関家の礎が築かれ,現存アジア最古の法典「令義解」の編纂した清原夏野と,その法解釈が長く範とされた讃岐永直,日本最古の百科事典「秘府略」編など才能を発揮した滋野貞主,「続日本後紀」20巻完成させた春澄善縄という学者のような法務官僚が次々登場するなか,史上初めて画家として名の残る百済河成が登場する。
そして,紀貫之が,若くして「古今集」を編纂,その「仮名序」によって,近世まで続く和歌路線を敷いたばかりか,晩年,土佐守として現地赴任したのを契機に,有名な'男もすなる日記といふものを,女もしてみむとてするなり'の書き出しで始まる,初の仮名文学「土佐日記」を著して,まもなく没した,Ⅰ-2-3③の時代を経て,その刺激と対応するように,和歌から,女流文学が開花し始め,女流藤原道長の栄華が齎した王朝女流文化が頂点に達する時代,Ⅰ-3-1③に入るが,この時代前後は,現代も超人気の陰陽師安倍晴明,日本初の往生伝「日本往生極楽記」を著して浄土思想を普及させた慶滋保胤と,「往生要集」を撰述し,公家社会に対応する地獄極楽イメージ鮮明な仏教を創始した源信,学者輩出する大江家の中興の祖となった大江匡衡とその妻で「栄花物語」の作者にも擬せられる赤染衛門,道長の妨害にも屈しなかった硬骨漢で,上下,女性からも信頼された藤原実資,マルチタレントな文人藤原公任,上下各層から愛され独自の書を確立した藤原行成,摂関家内の争いに敗れるも最後まで堂々と生きた藤原隆家といった,かなりの男性人物も輩出する。
王朝文化を現出した人物について,女性に限って,生年順に示してみると,"理想の女房"といわれ,優れた作品を遺し,「伊勢集」は女流私家集・日記文学の嗜矢となった伊勢,その娘で,幼い頃から80歳近くで没するまで,様々な人たちとの贈答歌を中心に,創作し続けた中務,王朝女流文学の嚆矢「蜻蛉日記」の著者として知られる藤原道綱母,大江匡衡の妻としても大きな役割を果たし,「栄花物語」の作者にも擬せられる赤染衛門,そして,言わずと知れた,「枕草子」の著者として,日本の随筆文化の祖となった清少納言と,世界の長編小説を先駆ける傑作「源氏物語」を書いた紫式部という頂点を迎えるのと対応するかのように,道長の娘,上東門院彰子が,王朝女流文化のパトロネージュとなり,摂関家栄華の極から衰退まで,長い人生を送ることになり,'古の奈良の都の八重桜けふ九重に匂ひぬるかな'でたちまち歌才が知れわたった伊勢大輔,宮中の指導的歌人になった相模,紫式部の娘で,高齢になっても宮廷の歌合せの主役を務め,子為家の代詠もした大弐三位,孤独な晩年に,人生回想の「更級日記」を著し,「夜半の寝覚」ほかの物語作者とも伝えられる菅原孝標女まで,錚錚たる人物が輩出するのである。
もう一つの際立つ時代は,近世の元禄文化とされるが,それによって大衆文化への幕が切られたということであって,吉宗の娯楽政策によって,大衆,とくに女性が,文化消費者から自立へと向かい,天明文化と,それに続く,化政文化に至るのである。
まず,特異な将軍徳川綱吉のもと開花した元禄文化は,時代区分でも,そのまま綱吉時代のⅢ-2-3にあたるが,視覚障害者教育のパイオニア杉山和一,吉川神道を開いた吉川惟足,「北野天神縁起絵巻」などを多くの傑作遺した土佐光起,東西廻り航路開拓した河村瑞賢,栄利求めず塾で教育に努め新井白石ら逸材を輩出した木下順庵,呉服店開き財閥三井家の家祖となった三井高利,古義学を創始した伊藤仁斎,"水戸黄門"徳川光圀,「養生訓」ほかの貝原益軒,江戸浮世絵の実質的な開祖菱川師宣,各地に木彫仏像残した円空,貞享暦を完成し天文方世襲の祖渋川春海,天才的和算家関孝和と業績を体系化して以後の発展を基礎づけた建部賢弘,万葉仮名表記の発見など天才的業績の契沖,近代小説を準備した天才作家井原西鶴,上方落語の開祖露五郎兵衛と"江戸落語の祖"鹿野武左衛門,天才俳人松尾芭蕉,鎖国下で合理的認識を先駆,日本で初めて世界地誌を著した西川如見,天才脚本家近松門左衛門を起用し義太夫節で近世浄瑠璃を確立した竹本義太夫,"光琳模様"の尾形光琳と兄を支えた陶芸家乾山,歌舞伎を創出し最高役者の祖市川団十郎(初代),そして,デザインの哲学的根拠をも開いた天才的思想家荻生徂徠と,これだけ天才が集中的に輩出するのは,世界的みても稀有であろう。
そして,吉宗による庶民を大事にする政策の時代(Ⅲ-3-1②)を受け継ぐかのように,現在もなお毀誉褒貶は多いが,田沼意次が齎した自由経済によって,天明文化が開花(Ⅲ-3-2),すべてからの自由を求めて京の若者に多大の影響を与えた売茶翁こと高遊外,その後に輩出する文人の先駆服部南郭や多才な風流人で南画の先駆柳沢淇園,独自の公案体系確立し,臨済宗中興の祖となった白隠慧鶴,国学を深めた賀茂真淵とそれを受けて現代にも影響及ぼす復古思想の完成者本居宣長,その宣長との論争に敗れるも傑作遺した上田秋成,甘藷研究を認められて幕府に出仕し蘭学の祖になった青木昆陽,日本初の医学的解剖を行い実証的医学開いた山脇東洋,今や江戸期の画家で人気トップの伊藤若冲に鬼才の絵師曾我蕭白,妻玉瀾とともに画業に没頭した池大雅,俳諧・南画ともに超一流の与謝蕪村,写実様式を確立した円山応挙,浮世絵の飛躍的発展させた鈴木春信に美人画最高峰の鳥居清長,一流の浮世絵師で人気トップの戯作者山東京伝,日本初の経緯度入り全図を作成出版し農民出身では異例の侍講になった長久保赤水,"川柳の祖"柄井川柳,自由奔放な新しい感覚の鬼才で,各分野で時代を先駆した建部綾足に天才的マルチ人間平賀源内,弄石ブームを起し近代考古学を先駆した木内石亭,偉大な植物学者小野蘭山,実証主義者らのサロンの主木村蒹葭堂,私学{懐徳堂}の黄金期形成した中井竹山,歌舞伎を門閥にとらわれない合理的な興行制度にした金井三笑,名所図会のジャンルの嚆矢秋里籬島,「近世畸人伝」の伴蒿蹊,天文方の主流を形成する多くの俊秀育てた麻田剛立,西洋思想の導入につとめた司馬江漢,日本人離れをした大哲学を構築した三浦梅園,驚くべき自由経済思想「夢の代」を著す山片蟠桃,天明文壇を主導した大田南畝,天才的出版業者蔦屋重三郎,「解体新書」の登場に関わった中川淳庵,前野良沢,吉雄耕牛,杉田玄白。塙保己一の大事業もこの時代に着手されているといったように,元禄文化に勝るとも劣らない時代が現出するのである。
その田沼意次が失脚させられ,松平定信による寛政の改革によって,自由な文化が抑圧され,喜多川歌麿らの悲劇はあるものの,大衆の欲望は止まらず,文化文政時代の,いわゆる化政文化に続いていくのである。
そこで,王朝文化と同じように,天明文化を現出した女性に限って,生年順に拾ってみると,5歳時の俳句で世人驚かし,夫と北村季吟らに学んで創作続け,夫死去後は,尼僧としても存在感を示した田捨女,文武をかねそなえた上,文芸の才が愛され諸侯が招聘した井上通女,儒学者の妻で,越後高田藩主からの要請で,女訓書「唐錦」6部13巻を書き上げた大高坂維佐子,そして,理知的で平俗な作風で名声を得,人柄を端的に示す句'朝顔に釣瓶とられてもらひ水'を遺し,現在も良く知られる加賀千代(女)の後は,漢詩・連歌にすぐれ,歴史物語・紀行文など集中的に著作するも,本居宣長の批判に激昂し激減した荒木田麗(女),生涯に8冊という当時としては驚異的な数の句集・撰集を残した榎本星布尼,琴士として栄誉をきわめ,当時の女性として比類のない旅行家で,華やかで多彩な一生を送った田上菊舎(尼),幕末に際立って開明的な「独考」を著し,厳しい批判受け絶交された滝沢馬琴により名が遺った只野真葛,夫死後の家業と育児による心労を脱すべく,俳句を始めて一流にまでなり,多くの俳友と交流した市原多代女,若くして「伊勢物語」の語句,古今・後撰・拾遺の詠風を蒐集分類編纂し,最晩年に藩主の命で「歌集」を遺した岩上登波子,農民ながら,貴族から歌才を愛でられて交流,"伊豆の袖子"として"加賀の千代"と並称された菊池袖子,蘭斎の長女で,頼山陽と結婚できず,一生独身も,一流の才能を発揮して全国に知られた江馬細香,同じく,頼山陽との交際で知られ,生涯嫁がず,絵筆一本で家族を養い,自由人としての生き方を全うした平田玉薀から, 化政文化の,幕末の動乱期に,生涯の大半を遊歴の中に過ごし,女流三傑の一人と謳われた原采蘋,幕末に,女性ながら評判の儒者となり,維新後も,衰えるところがなかった篠田雲鳳と,そのまま維新に突入していくのである。
3:現代につながる大正デモクラシーの爆発
現在の我々に直接つながる近代において,維新後,西洋文明を吸収し,日清・日露戦争を経て,いわゆる列強の仲間入りをするまで成長,そして,明治天皇の死によって重しのとれたところに,一方では国粋主義が進んで思想的弾圧が始まるものの,第一次世界大戦によるバブルと吉野作造らによる民本主義が浸透で,国民の意識が一気に自由化する。そして,この時代を象徴するように,初めての庶民首相原敬が登場するも暗殺されてしまう時点を境に,冒頭の方で記したように,民の方で登場する人物が飛躍的に増大する。念のために,その時期(Ⅳ-2-2③)に登場あるいは活躍のピークを迎えた人物を絞ってみると,表のように619人に上り,総数3635人の6分の1(17.0%)にもなり,女性の数は119人で総数531人の22.4%とさらに多くなる。ところが,知られているように,この後,満州事変が起こって,いわゆる15年戦争期に入り,戦局が進むに連れ,多くが苦難の道を迎える状況になるのである。そういった意味も含めて,参考になる人物は多いと思われるので,表から適宜拾って,一枚年譜を参照して貰いたい。⇒EXEL「大正デモクラシー登場」
念のため,0:天皇型から1-3:1-3:官僚分野までの88人,2-2:宗教分野の13人,X:特異分野49人を別にし,男女あわせた数で確認してみると(カッコ内は,総数と比率),2-1:社会分野は,全体で,75(338,22.1%)と。5分の1あまりがこの時期に登場,うち,1:医療型が,6(59,10.2%),2:福祉型が,3(35, 8.6%),3:教育型が,11(69,15.9%),4:解放型が,36(71,50.7%),5:殖産型が,5(50,10.0%),6:文化型が,14(54,25.9%)というように,なかでも,4:解放型が際立って多いが,LGBTはじめ,現在もあらゆる差別からの解放の動きは強い。2-3:学問分野は全体として,58(314,18.5%)で,1:数理天文型が,1(33, 3.0%),2:自然科学型が,12(69,17.4%),3:人文科学型が,17(62,27.4%),4:社会科学型が,18(49,36.7%),5:文学言語型が,6(49,12.2%),6:蒐集編纂型が,4(52, 7.7%)となり,3:人文科学型,4:社会科学型と多くなっているのは当然として,1:数理天文型と6:蒐集編纂型が非常に少ないのは,こういった時代には,籠って研究するようなオタク的人物は向いていないということなのだろう。
3-1:著述分野は全体として,103(480,21.5%)と,この時期に登場したものが5分の1強と平均を上回っているが,1:詩歌型が,32(162,19.8%),2:小説型が,48(170,28.2%),3:脚本型が,6(27,22.2%),4:随筆鑑賞型が,0(18, 0.0%),5:批評解説型が,12(65,18.4%),6:哲学思想型が,5(38,13.1%)となっていて,4:随筆鑑賞型は,サブ型に回っているため0で,自己主張の強い2:小説型の伸びが著しいのは当然としても,6:哲学思想型がかなり少ないのが気になるところであり,前項の学問分野同様,じっくり考えるような人物には向かない時代であったといえ,現代にも続いているのが気になるところである。3-2:造形分野は全体としても,77(277,28.5%)と飛躍するなかで,1:平面型が,40(153,26.1%),2:立体型が,5(28,17.9%),3:空間型が,15(32,46.9%),4:商品型が,4(22,18.2%),5:ストーリー型が, 1(9,11.1%),6:シーン型が,12(33,36,4%)となっていて,3:空間型が際立って多いのは,その大半を占める建築家が,現代も同様,人気の職業だったことを示し,6:シーン型が多いのは,この時期映画が一気に盛んになったことを,5:ストーリー型が少ないのは,大半を占める漫画家が輩出するのは戦後になってからということを示す。3-3:芸能分野は全体として,57(222,25.7%)で,1:楽曲型が,9(43,20.9%),2:歌謡型が,10(33,30,3%),3:口演型が,9(27,33.3%),4:舞踊型が,5(28,17.9%),5:演劇型が,23(84,27.4%),6:芸人アイドル型が1(7,14.3%)と,個々の内容は変化しても,この時期により多く登場しているものが多い。
4-1:実践分野も全体として,40(188,21.3%)と多くはなるものの,1:発明技術型が,6(42,14.3%),2:伝承技能型は,0(0,0.0%),3:コンサル仕掛型が,5(29,17.2%),4:本業超越型が8(33,24.2%),5:ジャーナリスト型が,15(47,31.9%),6:奔放夢想型が,6(24,25.0%)となっていて,2:伝承技能型が無いのは当然かもしれないが,5:ジャーナリスト型,6:奔放夢想型,4:本業超越型はやや多いのに,3:コンサル仕掛型,1:発明技術型など,広く皆のためになるものへの取り組みが少ないのも,現在に続く自己中心的になった時代の表れのように見える。4-2:実業分野は全体として,24(224,10.7%)と,すでに多くの企業等が活動している段階で,会社員も多くなった国民の状況を反映して,全体的には少ないが,1:豪商財閥型が,3(61,4.9%),2:国土開発型 が,9(33,27,3%),3:農水食品型が,3(15,20.0%),4:製品生産型が,7(41,17.1%),5:販売サービス型が,2(28,7.1%),6:メディア娯楽型は,16(46,34.8%)と,とくに多く,戦後に拡がっているメディア娯楽型のものの大部分がこの時期に起こっていることを示し,2:国土開発型がやや多いのも,国民の移動に関わる鉄道関係が多いことによる。最後に,4-3:競技分野は全体として,19(109,17.4%)少な目なのは,1:棋士型が,2(14,14.3%),2:武道型が,3(23,13.0%),3:スポーツ型が,8(27,29.6%),4:探検紀行型が,3(22,13.6%),5:競技振興型が,3(10,30.0%),6:茶道鑑識型が0(13,0.0%)と,3:スポーツ型と5:競技振興型が,ともに3割とやや多いことは,この時期にスポーツが盛んになり始めて,戦後に盛んになっていくことを示すのと対照的に,それ以外の項目は少なく,もはや,廃れてきたことを反映して,この時期が,まさに,時代の大きな転換点になっていると言って良いだろう。それでも,4:探検紀行型が少なめなのは,挑戦的精神の衰えを示しているようで気になるところである。
以上のような状況を踏まえた上で,大正デモクラシー期に登場した注目すべき女性を,分野型別に拾ってみると,まず,2-1社会分野の3:教育型で,早くから栄養問題を啓蒙,<敗戦>後,基礎食品群を提唱,長寿社会化への道を開いた香川綾,日本初のOLとなった後,{ドレスメーカー女学院}を創設,服飾デザインの発展に生涯をかけた杉野芳子,新渡戸稲造の要請で東京女子大学創立責任者,学長になると,左翼学生を弾圧から守った安井てつがいるが,4:解放型は,まさに女性解放運動の盛り上がりを反映するように,婦人参政権運動一筋に生き,戦後は理想選挙を唱えて参議院議員となり,圧倒的な支持を得た市川房枝,大杉栄とともに虐殺される短い生涯に,3度結婚し7人の子,多くの評論・翻訳を残した伊藤野枝,<大正デモクラシー>期に婦人セツルメント運動始め,<敗戦>後に{主婦連}創立,消費者運動の草分けになった奥むめお,"新しい女"を代表するような苦闘の人生を送った尾竹紅吉,四角恋愛で<大杉栄傷害事件>を起こすも,文筆を主に女性解放・人権擁護活動に生涯をかけた神近市子,{文化学院}創立し,{読売新聞}の身上相談欄を長く担当,<敗戦>後も多方面に活躍した河崎なつ,廃娼運動に生涯,少額寄付の大衆参加策を次々と発案した一方,キリスト者として人生最後も全うした久布白落実,{青踏}発刊,女権宣言して端緒を開き,戦後,日本婦人団体連合会初代会長になった平塚らいてう,山川均の妻で,母性保護論争で論壇に登場,<敗戦>後,労働省の初代婦人少年局長になった山川菊栄と,数も多く,知名度も高い人物がおり,6:文化型では,戦前はタゴールの来日などに尽力,戦後は,日本人初のソ連入りなど,国際的に大活躍した高良とみに,日本女子大学長への道を歩む間,国際的な平和活動を推進し続けた上代タノと,ともに,戦後の日本で大きな役割。女性蔑視の強い2-3:学問分野でも,帝国大学初の女子学生,日本初の女性理学士で,2人目の女性理学博士になった黒田チカ,女性の大学進学ができず,理研研究生となって,緑茶の研究で,わが国女性の農学博士第1号になった辻村みちよ,詩人として登場,転変の後,俗事は夫に任せて自宅から一歩も出ずに研究,女性史学を確立した高群逸枝がいる。
3-1:著述分野に入ると,1:詩歌型には,文壇の花ともてはやされるも,独自の歌境開き,女流歌人の第一人者と称された今井邦子,西条八十から絶賛されて次々創作するも,夫の反対で絶筆,離婚し自殺した金子みすゞ,虚子のとなえる客観写生を超越,名声が全国に響くも,言動激しく除名絶縁され,孤独になった杉田久女,夫の死後,奔放な生き方をし,戦前はムッソリーニと握手,戦後はベトナム救援運動の先頭にたった深尾須磨子,妾腹ながら叔母が大正天皇の母という家柄に生まれ,その拘束から脱した情熱的人生を歌に詠んだ柳原白蓮が,2:小説型には,100歳に近い生涯,男性遍歴を重ねながら小説を創作し続けるとともに,和服デザイナとしても活躍した宇野千代,作品発表して女子大中退に追い込まれ,結婚を家族に反対されて精神を病み,死の直前に脚光を浴びた尾崎翠,若くして登場,晩年に,被差別部落扱う「橋のない川」を書き続けて決定的評価になった住井すゑ,「海神丸」で登場し,精緻な観察眼とみずみずしい精神保ち,100歳で没するまで傑作を書き続けた野上弥生子,戦前にプロレタリア作家として確立,戦時の苦難乗り越え,一貫して反逆的個性を発揮し続けた平林たい子,女性の自立扱う名作「伸子」書き,{共産党}の宮本顕治と結婚,獄中の夫を支えながら創作続け,早世した宮本百合子と,いわゆるビッグネームが多い。そして,3-2:造形分野の4:商品型には,総合美容先駆し繁昌するとともに,啓蒙活動を行った遠藤波津子と,丸ビルに美容院開業し,初のマネキンクラブなど,美容界向上発展に貢献した山野千枝子がいる。3-3:芸能分野では,7人と多い2:歌謡型には,名をあげるほどの人物はいないが,4:舞踊型には,石井漠の義妹として舞台で活躍,創作舞踊で高い評価,舞踊研究所を設立して,多くのダンサーを育成した石井小浪,高田舞踊研究所創設し,夫没後も俊秀育成,モダンダンス界に大きな足跡を残した高田せい子,苦闘の末,装束無しの「安宅」が話題で,観世流シテ方初の女性師範も,なお苦闘の生涯を送った津村紀美子,新舞踊運動の先頭に立ち,藤蔭流を興して多くの人材を輩出,日本舞踊家の地位を確立した藤蔭静樹がおり,14人もいる5:演劇型には,日本映画界の草分け女優の一人となって,蒲田映画の初期黄金時代を築いた川田芳子,夫と{築地座}創設,夫の戦死で隠遁,12年ぶりに復帰の{文学座}最初の大女優になるも,突然退場した田村秋子,貿易商と結婚,モスクワで演劇に開眼,翻訳劇の貴婦人を当り役に{俳優座}の精神的支柱となった東山千栄子,帝劇案内嬢から,松井須磨子を見て女優を夢み,どんな役も引受け,"新国劇の母"に至った久松喜世子,真摯に"新しい女"を生きて新劇女優となり,一世を風靡,共に夢を求めた島村抱月の後を追って自殺した松井須磨子,子役から芸術座経て新派に移り,没するまで若さと美しさ保ち,"八重子十種"の名演を遺した水谷八重子,若くして新劇舞台の名女優となり,<敗戦>後,当り役「夕鶴」のおつうで,上演1000回の記録した山本安英と,ビッグネームも多い。
4-1:実践分野では,5:ジャーナリスト型に,戦時下に{生活と趣味之会}を運営するなど,女性に生活経済情報を提供し続けた大田菊子の一方で,男子と対等に闘おうと挑戦,自ら操縦して訪欧飛行すべく決行準備中に病没した北村兼子,草創期の婦人紙誌で啓蒙活動,飛躍をめざして留学するも,早世した小橋三四子と,絵にかいたような挑戦と挫折の2人が。4-2:実業分野でも,6:メディア娯楽型に,{講談社}創立者野間清治の妻で,事業の半分を負担して"創業の母"と呼ばれ,子夫急逝で自ら社長になった野間左衛と,夫の道楽をヒントに{吉本興業}を創設,関西芸能界を支配するに至った吉本せいがおり,X:特異分野の5:在外活動型には,性の遍歴の末,ソ連に逃亡,<敗戦>後も現地に留まり,演劇を学び直して演出家としても成功した岡田嘉子,アメリカで子育て,夫急逝で帰国するも,娘のため再渡米,日本人初の米国ベストセラー作家になった杉本鉞子,渡米留学して卒業後,偶然ボストン美術館東洋部に招かれ,美術品を整理・考証した平野千恵子,「蝶々夫人」を当り役に国際的に活躍し,日本のオペラ歌手の可能性を内外に強く印象づけた三浦環がいる。
。
第3話:現代に類似する各時代末の分野型
日本史話三講の第Ⅱ講:時代循環のパターンで示しているように,現代は,近代の末期(Ⅳ-3-3③)で,古代末の院政期(Ⅰ-3-3③),中世末の戦国時代(Ⅱ-3-3③),近世末期の文化文政時代(Ⅲ-3-3②③)に対応するが,まずもって,院政期は,その語が示すように,国家中枢権力が不明になったばかりか,上皇らが,もっぱら内輪のことにしか関心を抱かず,貴族らも遊びに夢中で地方の民を顧みず,時を並行して,奥州藤原氏という,別の政権が存在しこと,戦国時代もまたその語の示すとおり,国家の中枢権力たる将軍の力が無いどころか,足利義政のように政治から逃避してしまい,いわゆる下克上の無秩序な時代で,庶民はそれに翻弄され,落ち着いて何かをすることができなかったこと,そして,近世末期の文化文政時代は,その時代の前から後まで,実に55年間,将軍の座にあった徳川家斉は,良く知られているように,大奥入り浸りで,政治のことは無関心,それを受けるように,江戸の町民も,遊び惚けるだけで地方の農民たちを顧みないという,権力の空白が無秩序な世界をつくっているという点で共通しているが,そういった時代で,どのような分野型に,際立った人物が出ているかを見れば,何を目指せば良いか参考になるだろう。
(1)古代末(院政期)
院政期が始まるのは,特異な独裁者的天皇で,藤原摂関家衰退の間隙をついた白河天皇により,上皇となって,天皇を超える権力を発揮するのであるが,内裏に代わる政治の場仙洞御所を守る北門の武士として社会に出た西行が,突然遁世して世間を驚かせ,漂泊しながら名声欲も保ち,その生き方は,後世に多大な影響を及ぼすことになったことから,まさに,遁世者の象徴,X:特異分野の3:脱社会型の先駆者である。また,大僧正に登りつめる一方,絵巻物「鳥獣人物戯画」の作者に擬せられる鳥羽僧正こと覚猷は,院政期の終りとともに登場し,保元の乱によって,中世に入るなか,絵巻物文化を開花させた後白河法皇につながるとともに,現代,世界を席巻している,日本のアニメ漫画の始祖,つまり3-2:造形分野の5:ストーリー型に入る人物であると言えよう。そして,それまでの時代つくってきた公家社会を壊す役割を担うことになる公家,"日本一の大学生"の才能で,伝統社会に反逆,<保元の乱>を余儀なくされ,敗死した藤原頼長,法体で鳥羽院近臣トップとなり,院死後,<保元の乱>で勝利も<平治の乱>で敗れ自殺した藤原通憲と,次の時代,つまり武家政権への道を開く,源平の武士軍団を確立していく,後三年合戦鎮圧も恩賞なく,私財提供で武士の鑑となり,のち,武家として初の院昇殿になった源義家(八幡太郎),父正盛同様,日宋貿易による財力で,白河院の寵を得,武家初の内昇殿,平氏の地位を高めた平忠盛が重要で,古代から中世への転換を象徴,その在り方が後世へ多大の影響を与えた文人学者政治家の大江匡房,優れた学者として変革期の権力者たちに信頼され,菅原道真以来,儒学者で唯一人没後神になった清原頼業も注目される。
(2)中世末(戦国時代)
多くの武将が名が知られるが,戦でなくても,現実の世の中は戦争のようなものとの観点から,さまざまな形で取り上げられているので省略するが,そもそも,戦国時代の始まり<応仁の乱>が起きるのは,室町幕府8代将軍足利義政が,政治力を欠いて逃避してしまったことによるのであり,義政自身,まさに,X:特異分野の3:脱社会型の人物であったといえるが,それまで禅僧の世界であった作庭について,義政が自らの隠遁の地を整備すべく,75歳過ぎに相国寺の作庭で登場した善阿弥を起用,のちの造園家の始まりになったことや,ユニークな生涯で"風狂"と"頓智小僧"のイメージが定着している臨済僧一休宗純,そして,日本独自の漂白の詩人として連歌を代表し,和歌の西行と俳諧の芭蕉を繋ぐ役割を担う飯尾宗祇ら,X:特異分野の3:脱社会型の典型になる人物たちによって,東山文化が花咲く。
とくに,日本中世における水墨画の大成者で,画家として個人名が出る先駆けとなった雪舟等楊,室町期最高の大和絵作家で,土佐派を中興し,「清水寺縁起絵巻」ほか肖像画など傑作を遺した土佐光信,そして,武家出仕唯一の(画僧で無い)俗人絵師。若くして雪舟が認める才を示し,狩野派の祖になった狩野正信と,新障壁画様式確立して,狩野派の発展の基礎をつくり,後世,神格化された狩野元信と,錚錚たる画家,つまり3-2:造形分野の1:平面型が登場,近世に花開く絵画の世界を準備したこと,"佗数奇"を深化し,書院茶の湯を仏寺の方丈の理念に叶う四畳半茶の湯にした村田珠光と,それを大成し,千利休ら堺商人へ伝え"堺流茶の湯開祖"となるも,早世した武野紹鴎による4-3:競技分野の6:茶道鑑識型の始まりが重要であるが,作品に感銘した斎藤妙椿が城の包囲を解き,伝来の古今集を宗祇に講義し"古今伝授の祖"になった東常縁,伊勢流武家故実の大成,つまり蒐集編纂型の,室町幕府政所執事伊勢貞宗,中国から金元時代に興った李朱医学を初めて日本に導入し,近世医学興隆の祖になった田代三喜,神儒仏混合の唯一神道を創始,地方の神社に神位,神職に位階を授与する制度を創設した吉田兼倶など,近世をの文化をデザインする人物が目白押しに登場,さらに,古代末と同様,関白まで務めて政界を引退後,大学者として,公武合体の文化のブレーンの役割をした一条兼良と,応仁の乱期も京都に留まり,生活に窮しながらも,公武合体の象徴として尊敬され続けた三条西実隆という大学者の存在,今川氏の外交官として諸国を巡遊,宗祇・肖柏と連歌史代表する「水無瀬三吟」「湯山三吟」を遺した柴屋軒宗長と,朝廷財政逼迫のため武将間を奔走,貴族社会を詳細に示す日記「言継卿記」を遺した山科言継も見逃せない存在である。
(3)近世末(化政期)
化政期は,時代区分では,Ⅲ-3-3②③に対応し,際立つ時代にところで述べた天明文化の主役をつとめた錚々たる天才作家たちのなかには,伊藤若冲や大田南畝など,松平定信による寛政の改革(Ⅲ-3-3①)という衝撃を超えて,この時代にもなお,活躍している人物もかなりいるが,活動や業績の主たる時代が,この期にある人物について,拾うことにする。
まず,あげられるべき人物は,商人・名主として実績を挙げた後,50過ぎに天文・測量を学んで,初めて詳細な日本地図を作成した伊能忠敬と,盲目ながら,「群書類従」編纂刊行の大事業を成し遂げ,堅実な考証で近代史学を先駆した塙保己一という,2人の巨人を代表に,日本文学史を先駆する「国文世々の跡」や,現代も読まれる「近世畸人伝」などを著した伴蒿蹊,長命であった小野蘭山が幕府に採用されて,江戸時代最大の博物誌「本草綱目啓蒙」を刊行し,本居宣長が30余年かけた「古事記伝」で国学を完成,宝暦事件に連座して長期に逼塞の間,平安内裏の考証に没頭した裏松光世が,復古図ろうとする光格天皇に認められて,一躍時の人になったほか,20年かけ,彩色した本格的な日本初の植物図鑑「本草図譜」96巻92冊を著し,借金までして出版した岩崎灌園,今日なお批判に耐える金石文・古泉学の基礎を築いた狩谷掖斎,初期に優れた地方書「地方凡例録」を著した庄屋の大石久敬,神田の名主斎藤幸雄は,「江戸名所図会」発案して出版計画の許可得たところで急逝(のち,子が継ぎ,孫が完成),豪商鈴木牧之が,民俗資料としても貴重な「北越雪譜」出版に生涯をかけた,あるいは,当代随一の古銭研究家になった福知山藩主朽木昌綱,幕閣を務め,文化事業にも熱心で,自ら動物図鑑を編纂した藩主堀田正敦,藩政マニュアル「創垂可継」以降,多くの書物を編集・著作した黒羽藩主大関増業,雪の結晶の観察記録「雪華図説」と<大塩平八郎の乱>の鎮定で名を残した古河藩主土井利位と,続々出てくる学者大名,500余人の歴史人物を描いた「前賢故実」を出版し,近代歴史画隆盛に先鞭をつけた菊池容斎のように,いわゆる専門家でない人物のなかにも,蒐集編纂をしようとするものが多く,まさに,2-3:学問分野の6:蒐集編纂型の時代であったといえる。
また,東日本各地を旅して回り,当時の民俗を知る上で貴重な彩色絵紀行文を多数まとめた,ある意味で蒐集編纂型の「遊覧記」を遺した菅江真澄は,X:特異分野の2:記録伝承型の人物になっているが,サブ型に示すように,脱社会型の人物でもあり,庵に住んで農民や子どもと交流,最晩年に貞信尼と出会って,大らかな書歌を遺した,この時代を代表する僧良寛と,致仕して自由の境涯を歩み,一揆発生に革新的な藩政改革建言するも受け入れられず,致仕して自由の境涯を歩み,巨匠になった田能村竹田,趣味に溺れて罷免された後,自由人として,天真爛漫奔放な傑作を次々と描いた浦上玉堂は,まさに,脱社会型の典型であったし,庶民教化に尽くし,隠棲後も敬慕を受け,絵は独自の"厓画無法"の境地に達した仙厓義梵,「雨月物語」後の苦難と本居宣長との論争を経て,漂白の生活に入り,孤独のうちに「春雨物語」を遺した上田秋成,苦渋に満ちた過酷な生涯のなか,弱者へのいたわりと童心を保って,人生詩の傑作を遺した俳人小林一茶も,自ら望んだ訳ではないが,脱社会型でもあったといえよう。異学の禁で仕官の道絶たれ,世の無用者を自認して詩酒に沈湎しながら,大立者として聳立した亀田鵬斎,同じく,<寛政の改革>閉門を契機に,書の"千蔭流"創始,国学研究も深めて江戸派重鎮になった加藤千蔭,民政重視の藩政,病気で致仕後学問に専念,高齢になって名随筆「甲子夜話」を書き続けた松浦静山,詩文・書画を愛し,各地を遊歴するなか著した「日本外史」が幕末志士に大きな影響を与えた頼山陽も,見方を変えれば,脱社会型の人物で,さらに,すでに述べてきた,将軍徳川家斉,女流画家平田玉薀,女流漢詩人原采蘋も加えれば,まさに,X:特異分野の3:脱社会型の時代でもあった。
また,天明文化期に,日本初の銅版画に成功,「世界図」を制作し,その後も西洋思想の導入につとめ,奇行も多かった司馬江漢を受け継ぐように,西洋科学踏まえた重商主義的貿易論で門弟を多数養成した本多利明,全国数十藩の財政再建し,驚くべき自由経済思想の「夢の代」著した山片蟠桃,「稽古談」ほか多くの著作講義で,画期的な重商主義論を展開した海保青陵,富国強兵の絶対主義的国家構想の書を次々発表した佐藤信淵,自然科学史の画期「窮理通」を著した帆足万里ら,まさに近代を準備する経世家と呼ばれる人物,3-1:著述分野の5:批評解説型,6:哲学思想型,あるいは4-1:実践分野の3:コンサル仕掛型,さらには,2-1:社会分野の3:教育型にも対応する一言ではくくれない人物が集中的に輩出したこと,さらに,新式の帆や運送船を開発,築港にも従事して海運の振興に貢献した工楽松右衛門,独創に富み,次々と発明して人々を驚嘆させた鉄砲鍛冶国友藤兵衛,実業にも役立つ多くの機械や装置を開発した久米通賢,幼時より次々と発明,世界に優る万年時計に至り,{東芝}の祖になった田中久重など,4-1:実践分野の1:発明技術型も錚々たる人物を輩出,そのほか,オランダ内科医書翻訳の嚆矢「西説内科撰要」を出版,研究の普及発展を促進する記念碑になった宇田川玄随,オランダ語翻訳に専念,現行の天文物理用語,文法から,"鎖国"など一般語彙まで創出した志筑忠雄,「気海観欄」を著し,物理学の紹介者として不朽の名を残した青地林宗,内服全身麻酔剤を案出し,世界に先駆けて全身麻酔手術に成功,華岡流外科創始者となった華岡青洲,あるいは,蔵書を拠出し私財を投じて,日本初の公開図書館開設し,将来にわたる安定的運営を図った青柳文蔵,自邸{山本読書室}に多くの門人を迎え,知識の解放による社会変革めざした"稀代のオタク"の山本亡羊,幕末に合理的農業技術に関する多くの著作を成し,明治維新後に大きく評価された大蔵永常,新技術導入で家業を盛り返し,日本初の民営の窮民救済基金{感恩講}を構築,没後も続いた那波祐生,間宮林蔵に先立ち樺太が島であると確認,アイヌ交易の官営化企図し,その保護に努めた松田伝十郎,十組問屋の危機救い三橋会所を設置するなど,江戸経済を支配した杉本茂十郎,飢饉に対処すべく諸マニュアルを執筆・頒布,後半生を全て救済活動に賭けた熊谷蓮心,一歩先の日本を眺めた開国論者で,藩主土井利位を全面的に補佐しながら,多くの業績を遺した鷹見泉石,その最後に登場する,没落実家を自力再興後,農村を企業的組織とする"報徳仕法"で諸藩の農村復興させた二宮尊徳,農協の先駆となる世界初の産業組合で農村振興したが,革命恐れる幕政の犠牲になった大原幽学など,近代の西欧化を受け止める準備をした多くの実践的な人物も輩出している。
当然のことながら,明治維新につながる人物が出始めた時代でもあるので,それら人物を示しておくと,時代に警鐘を鳴らし,「山陵志」で尊皇論を先駆した蒲生君平,"国体"の確立と弛緩した国内制度の改革という尊王攘夷論を開発した後期水戸学の祖藤田幽谷,独自の宗教的な説と精力的な活動で大きな影響,幕府に嫌われ,失意のうちに没した平田篤胤,水戸藩主徳川斉昭の側近,神道と儒学を合わせた大義名分論で尊王穣夷運動に大きな影響会沢正志斎,豊後国日田で,{咸宜園}開き,卓越した精神と近代的教育で,全国から多くの俊才を集めた広瀬淡窓,そして,奉行所与力として"三大功績"を挙げ,<大塩平八郎の乱>を起こして<明治維新>の扉開いた大塩平八郎(中斎)と,西洋の先進性に開眼し,幕府の鎖国政策を批判,<蛮社の獄>で自殺を余儀なくされた渡辺崋山に至る。
いわゆる官(幕府)が堕落し,地方を顧みない状況のなか,都(江戸)では,いわゆる文化文政の文化が爛熟したといわれる近世末ではあるが,なかには,上記のように,しっかりした民がいて,明治維新後の近代化を準備していたことが分かると,現代の状況はどうなのか,自らは何ができるのか問わざるを得ない。
そのほか,化政期文化を象徴するような人物を,何人か挙げておくと,琴士として栄誉をきわめ,当時の女性として比類のない旅行家で,華やかで多彩な一生を送った田上菊舎(尼),応挙門下で,師の画風からは全く逸脱するも,機知あふれる傑作描いて花形的存在になった長沢蘆雪,江戸写実劇完成して劇壇重鎮となり,最晩年に最高傑作「東海道四谷怪談」を著した鶴屋南北,独自の筝歌で,それまでの生田流系の地歌・箏曲を圧し,江戸中に普及させた山田検校,あまりにも著名な葛飾北斎,読者の嗜好に合わせて「東海道中膝栗毛」を書き続け,原稿料が生計の職業作家の嚆矢になった十返舎一九,師山東京伝踏み越え,「椿説弓張月」で不動の地位,失明の中,執念で「南総里見八犬伝」完成させた滝沢馬琴,「浮世風呂」「浮世床」だけでなく,化粧品・売薬もヒットさせるなど商才抜群だった式亭三馬,実証的な作風で,「偽紫田舎源氏」で第一人者になるも,<天保の改革>の犠牲になった柳亭種彦,蘭斎の長女で,頼山陽と結婚できず,一生独身も,一流の才能を発揮して全国に知られた江馬細香,「春色梅児誉美」が熱狂的歓迎,人情本で一世を風靡するも,<天保の改革>で処罰され,憤死した為永春水,"歌舞伎十八番"を選定・公表したが,<天保の改革>で江戸十里四方追放の憂き目に遭った市川団十郎(7代),独学でさまざまな教養を身につけ,隠居許可後,次々著作実践,近郊の人々から敬愛された菅原源八,激変の時代に対応,猫絵・謎解き絵ほかユニークな浮世絵を描き続け,"横浜絵"にも先鞭をつけた歌川国芳,司馬江漢が開発した名所絵の浮世絵版「東海道五十三次」「名所江戸百景」などの傑作を遺した歌川広重と言ったところか。
この章TOPへ
ページTOPへ
3:注目されるデザイナ的人物
はじめに
九品塾においては,その必須項目を,デザイン三講としており,誤解を恐れずに簡単に述べると,日本の近代化を促した西欧文明が,あまりにも「知」を優先してきたこと,人間の精神活動を表す,いわゆる「知・情・意」の,残りのものが軽視されている一方,日本人は,長い歴史の積み重ねのなかで培われた「情」にあまりにも引きずられてしまうことを憂え,本講つまり年齢適活の,本論つまり「活動を究める」冒頭で提示した,いわゆる「知・情・意」が,「真・善・美」や「過去・現在・未来」と対応する枠組にもとづいて,「知」は,社会を構成する人々の共通の理解のため,知識を共有することにあって,いわゆる科学に対応し,「真」と「過去」とセットになること,「情」は,互いに共感できるため,つまり感受性を共有するためにあって,いわゆる芸術に対応し,「美」と「現在」とセットになることを示した上で,残された「意」と,それとセットになる「善」と「未来」こそ,デザインであることを指摘した。⇒「必須科目:科学・芸術とならぶデザイン三講」
つまり,デザインは,社会を構成する人々が共通の土俵の上に立って,円滑に行動できるようにして行く,つまり,他者のためになる「善」によって,「未来」を創造していくことであり,近年,西欧文明の行き詰まりを眼にするにつけ,その哲学的なルーツを,ギリシャのアリストテレスにしたことで,まさに,「知」の世界,つまり科学は,大発展したのであるが,「情」の世界,つまり芸術は,アリストテレスの「詩学」自体,プラトンとの違いが論争になっているように曖昧であること,何よりも,「意」とセットになる「善」をして,それが,他者のために役立つというような,日本人ばかりでなく,西欧文明以外の地域では,当然のように思われているそれではなく,自分にとって善いことと定義してしまったことが,その後の,西欧文明の個人主義化を進め,結果として,世界を分断するに至ってきたことは言うまでもないだろう。
そして,ついに「知」のみの極致とも言われるAIが登場,多くの人々が,自ら考えることを止め,何が本当か分からなくなる時代が来るのではないかと恐れ,少なくとも,官僚や学者のように,過去の知識に依存するような職能の存在意義が問われることになるのはもちろん,多くの職能が,AIとロボットにとって代わられるの可能性は高い。それに対処するには,科学者,芸術家に代わり,デザイナになることというのが,本塾での講義の意義であるが,現在,流布している商品その他のものづくりに対応する,いわゆるデザイナでなく,より多くの人々を,より長い期間,同じ土俵に載せるような,制度やルール,モラルや方法などを提示する人たちこそ,本当の意味でのデザイナであり,その分野型では分からない後世に大きな影響を及ぼす人物,開祖とされるような人物,科学や芸術においても,いわゆるパラダイムの変換になるようなものを提示した人たちは,科学者,芸術家以上にデザイナであった人物であった。そういう観点から,日本の歴史人物のなかのデザイナ的なを,統治のデザイン,文化のデザイン,社会のデザインという枠組みで拾ってみたい。
第1話:統治のデザイン
日本という国を統治した国家支配型の人物のうち,歴史に名を遺すような人物には,「時代をつくる」という点で,当然のように,デザイナ的人物である場合が多いが,国家支配者になって初めて,その才を発揮することができるのであって,それには,時代の変化など,さまざまな要因のあることはいうまでも無く,興味ある人は,「日本史話三講」のうちの「統治変遷のプロセス」を読んで貰いたい。また,地域支配型の人物も,優れた人物は,その地域をデザインしていることになり,さらに,現在における企業の社長など,さまざま組織の優れたトップもまた,その組織のデザイナである場合が多いことも,指摘しておく。
生没年が確実な最古の人物は,推古天皇であるが,物部守屋を攻滅して覇権を握った蘇我馬子は,崇峻天皇を弑殺して,その推古天皇を擁立,つまり,天皇は権威であって,実際に権力を振るうのは,天皇を戴いた国家支配者という,いわゆる天皇制のあり方を最初にデザインしたのは蘇我馬子であり,実際のところは不明なものの,「冠位十二階」の制定や,「三経義疏」著作などによって,仏教立国等日本国家への基本骨格を提示した聖徳太子とともに,国家を始動させたが,太子,馬子,推古天皇が相次いで死去すると,馬子の孫の入鹿の専横が始まり,途切れる。
そこに登場したのが中臣鎌足の唆しによって,クーデタを起こして実権を握った中大兄皇子は,皇太子のままではあったが,天皇自身が国家支配者たるべく,律令体制への改革を進めたが,ようやく天智天皇として即位するも,近江令を施行したところで,子の大友皇子を後継者とする前に,志し半ばで早世,壬申の乱で,大友皇子を破って実権を握った,弟の大海人皇子は,妃だった天智天皇の妹を皇后として,天武天皇として即位するや,皇族を重視する親政により,ヒメミコ制から男王支配への一元化を完成,日本という国名,天皇という称号を始めて用い,病臥ののちは,皇后の助けも得て,のちの法律のもとになる浄御原律令,官位のもとになる八色の姓という,律令国家の基本をデザイン,さらには史書「日本書紀」編纂に着手し,本格的な首都となる藤原京の建設も企図したが,やはり志し半ばで早世してしまう。
皇后は,そのまま称制して政治を行ううち,天皇に立てる予定だった,子の草壁皇子が没してしまったため,自ら即位(持統天皇)し,夫の天武の志を継いで,藤原京を建設し,孫の軽皇子(文武天皇)に譲位後も,上皇として後見,これまた初の本格的な大宝律令を制定,施行を見届けて没し,結果として,持統天皇は,律令国家の基盤を確立した優れた国家支配者であったが,それ以上に,そもそも,夫が武力によって天皇の座を簒奪しただけでなく,その妻である自分までもが天皇になったことの,正統性をいかに示すかということに腐心せざるを得ず,毎年のように,吉野行幸しながら,天皇の地位というものが,神から授かれるもの,いわゆる天皇神授による正当化を図るべく,現在では当たり前のように思われている,天照大神から始まる神話や,それに対応する儀式などを創り上げた,凄いデザイナであった。
その持統天皇の事業を支えることで,急速に力を伸ばしたのが藤原(中臣)鎌足の子,藤原不比等で,娘宮子を文武天皇の夫人とし,おそらく藤原京に関わったことで,自らの一族のほかの藤原氏はすべて元の中臣氏に戻すことに成功,大宝律令の施行でさらに飛躍,天皇が没するや,政界トップに立ち,支配を確実にすべく平城京を建設して興福寺を建立,さらに,宮子一人だけを天皇の配偶者とし,その子首皇子(のちの聖武天皇)を立太子させた上で,娘光明子を夫人にしてしまうことなど,律令国家を確立し,のちの藤原摂関家による国家支配体制の基礎をつくった上,自らの一族にとって都合の良くなるように修正しながらも,天武天皇が始め,持統天皇によって神話化された「日本書紀」を完成させて没したことで,これが,現在に至るまで,日本史の最大の拠り所になっていることから,藤原不比等もまた大デザイナであった。
その「日本書紀」の最後の校訂にあたっては,唐から帰国した僧道慈が顧問になったと言われ,のちに,聖武天皇が詔した国分寺のモデルプランの作成者と言われるように,デザイナ的人物であったようだ。のちに触れる淡海三船は,編纂した「懐風藻」に,彼が長屋王の招宴を辞退した時の漢詩を入れ,'性甚だ骨鰻,時に容れられず'という面があったと指摘している。不比等没後の政界を主導し,文化サロンの中心でもあったが,不比等の子の陰謀で悲劇的な最期となった長屋王もまた,百万町歩計画を図り,三世一身法を始め,多賀城を設置するなど,デザイナ的人物であった。そして,皇族外初の皇后になった光明皇后は,聖武天皇に働き掛けて,仏教に基づく慈悲の施策を実行,国分寺や大仏等も実現し,天皇の没後には,東大寺に,その遺品を献納したことで,正倉院ができたことから,やはり,デザイナ的人物であったと言えよう。
ここで,国家支配型ではないが,日本史における極めつけのデザイナといえる淡海三船に触れないわけにはいかない。彼は,生来,極めて聡明であったが,悲劇に終わった大友皇子の孫,つまり,天智天皇直系であったことから,天武天皇系で藤原氏が支配しているでは出世の道が閉ざされ,出家し,僧として学問を磨くうち,孝謙天皇の代に入った29歳の時,初の漢詩集「懐風藻」を編纂,名は伏せられているものの,天智天皇の代から藤原四卿までの漢詩を収め,大友皇子や,先述の道慈など,何人かに伝記を付していて,三船の撰であることは明らかで,大伴家持が,これに対抗して「万葉集」を編纂するほどの影響を与えたことから,すでに,後述する文化のデザイナであると言える。そして,聖武天皇の死後には,母光明皇后の力を背景に専横究める藤原仲麻呂を抑えようとする孝謙天皇にとって格好の存在となり,36歳の時には,譲位する孝謙天皇の命で,神武から父聖武天皇までの漢風諡号を一斉選進したが,なお名は秘せられていた。本論でも天皇の名を当たり前のように用いてきたが,戦前の暗誦はさておき,教科書はもちろん,日本史やそれに関わる作家らすべてが,当たり前のように用いている天皇の名は,三船がまとめてつけたものであるだけでなく,たとえば,持統天皇という名は,少しでも古代史に感心ある人なら誰でも知っている継体天皇の名が,まさに,断絶しそうになった天皇家の体を継ぐものであることとセットで,正統性を保つという名であることを始め,名に神のつく天皇は,新たな王朝を開いた天皇であり,天智,天武とセットにしていることなど,全ての名に,その天皇の存在が示され,だからこそ,あたかも最初からあったように思ってしまう,デザインの極にあると言える。つけくわえておくと,孝謙天皇が重祚した称徳天皇が,道鏡に篭絡されたため,左遷されてしまうが,直後の宇佐八幡宮の神託によって,天智天皇系が復活するや,藤原氏も一目置かなければならない存在となり,桓武天皇の即位後,まもなく没した。
その桓武天皇は,1000年以上,首都となる平安京をつくったことでデザイナだったし,長く規範とされた法令集「弘仁格」「弘仁式」,朝廷の儀式を整備した「内裏式」をまとめた嵯峨天皇もまたデザイナであったが,それ以後は,そういった国家支配者が出ず,古代は終焉を迎える。
公家政権から武家政権への交替という,日本史上最大の変革は,保元の乱後の平氏の専横によって,源氏の一斉蜂起となり,決断力と実行力で抜きんでた源頼朝が平氏を滅ぼし,さらに,奥州藤原氏を滅ぼして全国統一,鎌倉幕府を開いたことで決着するが,軍事力による支配を貫徹すべく,守護・地頭を置くことや,御家人に対してまでも,厳しく公平な裁判を行うべく,鎌倉に公文所・問注所を置くなど,武家政権の基本路線を敷き,朝廷との融和を図ろうと工作するうち,あっけなく横死してしまう。頼朝が,政権奪取とともに,これらの施策を次々と行うことができたのは,学者家系大江匡房の曾孫の大江広元をブレーンにしていたことにより,夫の頼朝没後,そのあとを取り仕切った北条政子も,そのまま,大江広元をブレーンにして,天皇を戴くように,将軍を戴く執権制度を創出するとともに,あとを狙う御家人らの陰謀,反乱を,頼朝にも引けを取らない決断力と実行力で乗り切って,北条氏の覇権を確立,尼将軍と呼ばれるに至り,ついには,朝廷に政権を取り戻そうと兵を起こした後鳥羽天皇に対してまで,弟の執権義時とその子泰時だけでなく,御家人らすべてに奮起を促して勝利(承久の乱),その直後に,義時が死ぬと,またしても起きた陰謀を抑え,執権泰時の政治を安泰ならしめて没したが,大江広元も,その後を追うように没したのである。その後,長期に続く武家政権の礎は,源頼朝,北条政子,大江広元が一体となって,デザインしたと言えよう。
その北条泰時は,その後の武家政権が拠所とする最初の武家法典「御成敗式目」を制定するなど,デザイナであったが,執権政治を確立する一方,皇位継承に介入して,のちの南北朝分裂への種を撒き,その孫で,反北条勢力を一掃して専制確立した執権北条時頼も,後に回国伝説を生む活動によって,公家政権を支えた天台宗の寺々を,武家政権に対応する臨済宗に宗旨替えさせるなど,まさしくデザイナであったが,時頼の子時宗の時代に,いわゆる元寇があり,国を挙げて戦って勝利したため,いわゆる得宗専制が進んで,悪党が横行,皇位の不安定化とも相まって,鎌倉幕府は衰退に向かい,ついに,後醍醐天皇を支えた足利尊氏に滅ぼされるに至る。
すると,足利尊氏は,後醍醐天皇に叛旗を翻して,いわゆる室町幕府を発足させる一方,南北朝分裂を招いてしまった上,足利政権には,五山文化,北山文化,東山文化といった語が目につくように文化のデザイナはいたものの,統治のデザイナがおらず,ついには,応仁の乱となって戦国時代に入ってしまう。いわゆる武将は,戦うことのプロであってデザイナでは無いが,なかには,越前一国支配を実現して"中興の祖"となり,最古の分国法「条々」筆者に仮託された朝倉孝景,役職や地位を捨てて東方に道を拓き,戦国武将の嚆矢になり,後北条氏初代北条早雲,その後継で,天才的戦略で後続戦国武将の手本になり,理想的内政により,江戸の太平を先駆したとなった北条氏康,家法「今川仮名目録」で戦国大名今川氏の基礎をつくった今川氏親,戦国一の勇将ながら病で早世したが,「甲州法度」で民政を先駆し,治水事業などに天才を発揮した武田信玄,戦国から近世への転換に的確に対処して,のちの南部藩の基礎を築いた南部信直など,領国支配をデザインした人物もいて,近世を準備したとも言える。
そして,いわゆる破壊的創造の天才織田信長が登場して,戦国時代を終わらせるが,現代の経済特区ともいえる自由都市堺の出現とも結びつく,いわゆる楽市楽座を定着させ,近世の町人社会を準備したという点だけでも,織田信長は,デザイナであったと言えるだろう。本能寺の変で没した信長の後,覇権を握った豊臣秀吉は,源頼朝のように,決断力と実行力で全国統一を成し遂げただけでなく,紛争を禁止する「惣無事令」,正確な土地を保障する「太閤検地」,治安維持の根本になる「刀狩り(一般人は武器を持たない,現代の鉄砲所持禁止にまでつながる)」,身分を保障する「士農工商」など,まさに,近世をデザインしたのであり,関ヶ原の戦を制した徳川家康は,征夷大将軍になって幕府を開くや,国と地方を一体化しながらも,地方が独自性を発揮できる幕藩体制を導入するとともに,寺院や朝廷までをも対象に,次々と,ご法度を公布して反抗しそうな勢力を封じ込める一方,有能な人材を登用して,江戸の城下町とそれに繋がる利根川付け替えや,玉川上水などの基盤整備にも着手し,林羅山を用いて,朱子学を国家支配の論理とするなど,ほとんど完璧ともいえる全国支配の体制を構築,一つの帝国とも見れる長期安定政権を確立したということから,統治のデザイナとして,最も優れた人物を,一人だけあげると,250年にわたる帝国を創始した徳川家康になろう。
しかし,徳川時代がそんなに長く続くのは,家康一人によってできるはずも無いことは明らかで,時代の継続,活性化を図ったデザイナ的人物を何人か挙げておくと,武家諸法度など諸制度を整備し,鎖国を完成,将軍の権威を高め幕藩体制を盤石にした3代将軍徳川家光,家光の異母弟で,会津の藩主になると,後々まで慕われる藩政の基礎を築き,家光没後は,将軍家綱を支え,明暦の大火が起こると,焼死者を供養する回向院を建立したばかりか,焼失した江戸城天守閣の再建を取り止めて町の再建に努め,武家諸法度に殉死の禁止を加えるなどした保科正之,熊沢蕃山との出会いもあって,質素倹約の"備前風"を普及,好学で名君とされた岡山藩主池田光政,「大日本史」の編纂・水戸学・文化財保護など,名君を超え,"水戸黄門"として伝説化した徳川光圀,徳川宗家の血筋が途絶えたため,老中らに推されて,紀州徳川家から将軍になるや,庶民が花見を楽しめるよう,隅田川を皮切りに,桜の名所を次々整備,洋書の輸入制限を緩和し,目安箱を設けて将軍への直訴まで可能にし,町奉行に抜擢した大岡忠相により,のちの,武蔵野などの発展にもつながる新田整備その他庶民の生活に資する政策によって,文化的にも,江戸が日本の中心になるようにした8代将軍徳川吉宗,範を示して藩政改革を推進して,<寛政の改革>のモデルとなり,地方政府を代表する名君になった米沢藩主上杉鷹山などがいる。
そうした泰平のなかにあって,維新への道をデザインする人物が出てくるが,生年の早い順に挙げてみると,江戸幕府初期に,早くも,後世の尊王運動に影響を与える垂加神道唱え,俊秀輩出して官学の林家を圧倒した山崎闇斎と,官学の朱子学を攻撃して播州に流され,のちの赤穂義士,さらには維新の志士の精神的支柱になった山鹿素行が現れ,徂徠派で稀にみる常識人ながら,萩藩校{明倫館}の基礎を築き,後世へ大きな影響を及ぼす山県周南,時代に警鐘を鳴らし,「山陵志」で幕末の尊皇論を先駆した蒲生君平,"国体"の確立と弛緩した国内制度の改革という尊王攘夷論を開発した後期水戸学の祖になった藤田幽谷,特異な個性で,諸藩に先駆け天保改革,尊王攘夷標榜して幕閣と対立,維新への道を開いた水戸藩主徳川斉昭と,その側近で,神道と儒学を合わせた大義名分論を唱え尊王穣夷運動に大きな影響を及ぼす会沢正志斎らが挙げられ,幕末の志士の指導者で,攘夷を不可とするほど革命的であったため,暗殺された佐久間象山,短い生涯の中,維新後を担う人材を育成し,自ら切り込み隊長役を務めて,刑死した吉田松陰によって,いよいよ,維新へ突入して行き,決定的役割を果たすも,その実現目前に暗殺された坂本龍馬ということになる。
そういった著名な人物では無いが,緒方洪庵や佐久間象山と同じ頃に生まれた横井小楠は,肥後国で,天保の改革の頃には,学問と政治の一致をめざす実学を唱えて,徳富蘇峰の父を最初の弟子とする私塾を開き,福井藩を訪れて,由利公正らに多大の影響を与えたことで,ペリー来航後,福井藩主の賓師として招かれると,「国是三論」にまとめられる交易論などによって指導,福井藩は巨大な利益を挙げるに至り,以後,維新の志士が次々と来訪し,藩主松平慶永のブレーンとして,江戸で活躍するも,事件で失脚,熊本藩から士籍剥奪処分を受け,沼山津に閑居するが,翌年には,井上毅が来訪して「沼山対話」を,その翌年には,元田永孚が来訪して「沼山閑話」を発表するなど,維新後の世界への構想は,志士たちの行動に根拠を与え続けた,一番のデザイナであった。勝海舟をして,'天下で恐ろしい人物、それは横井小楠と西郷南洲だ',さらには,'横井の言うことを西郷が実現したら,日本は大変なことになる'とまで言わしめたたが,そのとおりに,維新が実現して参与になるも,尊攘派生き残りの不満分子集団に暗殺されてしまった。いずれにしても,いわゆる維新の志士は,失敗していればテロリストでしかなく,デザイナでは無いが,背後に,新時代に向けてのデザイナがいたことで,維新が実現したのである。
そして,維新後は,近代への確固たる信念のもと,絡み合う多数の人材のなか,一つの軸になり,近代日本の船出を実現させるも,暗殺されてしまう大久保利通と,大久保によって後継に指名された伊藤博文こそ,大日本帝国憲法はじめ近代日本の諸制度を確立したという点で,一番のデザイナであったが,司法制度はじめ近代国家の基本設計を成したが,薩長派と対立,<佐賀の乱>起こして刑死した江藤新平,幕末に西洋科学を身につけ,2度渡英した体験から,近代日本の外交を確立した寺島宗則,軍制をデザインし,最初の勲一等・海軍大臣・海軍大将で,薩長間や陸海軍間の調停者になった西郷従道,警視庁はじめ近代警察行政を確立した川路利良,郵便制度の創始・電話事業の開始・国字改良など,維新直後のメディア近代化に決定的役割を果たした前島密,日本銀行を創設,"松方財政"で,資本主義社会の基礎を築き,維新政府の天才の一人と言われる松方正義,大名として先進的活動,維新後は,佐野常民と赤十字を創設発展させ,賞勲制度を創設差配した大給恒,薩長藩閥で無いにもかかわらず,帝国憲法・教育勅語など重要な政策・起草に指導的な役割をした井上毅と,デザイナ的人物はことかかず,それだからこそ,近代化が円滑に進んだともいえる。
艦隊各船の名称体系を構築した山本権兵衛:1891年海軍省官房主事になると,西郷従道海相を補佐して,海軍の改革・陸軍に対する海軍の地位向上に努め,その手腕は"権兵衛大臣"とまで評せられた。戦艦大和はじめ戦艦には国名,第一巡洋艦には赤城はじめ山名,第二巡洋艦には川名,砲艦には明石など名所旧跡の名,そして駆逐艦には,雪・雲・波・霧のさまざま名をつけるというネーミングの傑作を編み出し,1905年,天皇にプレゼンテーション,御意を得て具現化した(岩永嘉弘「ネーミング全史」による)。
その後も,台湾経営,満鉄初代総裁として大陸経営の基礎,東京市長時代には震災復興の大構想を打ち出した後藤新平,学者の道を捨て,市長になって市政の黄金時代を現出するも,現職のまま没した関一,卓越した先見性・指導力で,長期にわたって区画整理や水道事業等に取り組んだ井荻村長内田秀五郎,戦後は,長期に瀬戸内海の直島町長を務め,近年アートの島として有名になる基礎の全てをつくった三宅親連など,地域支配型に,多くのデザイナが輩出する。
国政においては,低学歴ながら実力で首相になり,金脈問題・ロッキード事件で失脚し,未だに,毀誉褒貶の多い田中角栄は,敗戦まもなく衆議院議員になると,早速,議員立法で,建築士法を通過させて,一級建築士第1号になったのはともかく,その後も,トップ当選を続け,住宅公団法その他,戦後復興から高度成長に対応して,重要な法案のほとんどにかかわって実現,郵政相になると,テレビ放送局すべてに一斉予備免許を与え,オリンピックに対応して,新幹線や高速道路建設に端緒をつけたばかりでなく,その後の,国土高速交通網を構想し,いまだに,それにのっとって建設が続けられ,佐藤内閣の通産相の時には,日米繊維交渉を決着させ,首相になるや,日中国交回復を実現,さらには,首都ではないとは言え,遷都に近い筑波研究学園都市を実現させるなど,戦後の日本の最大のデザイナであったことは,認めざるを得ないだろう。
第2話:文化のデザイン
1)最も古くからあって現在も続く和歌と,そこから派生した連歌,俳諧
日本人なら,最も古い歌集「万葉集」でそれを編纂したのが大伴家持であることは,誰もが知っている。大和朝廷発足以来,天皇を支えてきた名族大伴氏は,和歌のもとと言われる久米歌の久米氏と同族で,藤原不比等が覇権を握って以降,他の名族同様,抑えられるが,不比等の四人の男子が,天然痘流行で全員没したことから,巻き返しを図ろうとしていたところに,第1話で述べたように,752年,淡海三船が編纂した,日本初の漢詩集「懐風藻」が高く評価されたことに刺激されて,「万葉集」の編纂を始めたが,757年の橘奈良麻呂の乱に連座して,藤原仲麻呂によって因幡に左遷され,762年には,仲麻呂の専横に反対する藤原良継の乱に連座して,薩摩に左遷され,結局,この間に,自身が読んだ歌を,最末尾に入れた状態で終わる。その後,乱を起こした仲麻呂は討滅されるも,宇佐八幡宮の神託後になって,ようやく京に戻り,780年,63歳には,参議・公卿に昇り,持節征東将軍に任命された翌年,陸奥国多賀城で没した。「万葉集」最後の歌以降の家持の歌が伝わらないのはもちろん,藤原氏の抑える朝廷では,漢詩が主流で,「万葉集」が,いわゆる万葉仮名を多く用いた漢字で書かれていたことの存在自体もあって,その存在が知られるのは,実に,平安時代半ばになってからと言われるので,大伴家持は,優れた蒐集編纂者ではあったが,デザイナとすることはできない。
家持が没した時の桓武天皇は,第1話でに述べた通り,自ら国家支配者として,近世まで都として続く平安京を造営,いわゆる平安時代が始まるが,その子の嵯峨天皇は,自らも三筆の一人というレベルで,強い権威により,長期安定の文治的時代,宮廷中心の弘仁文化を創出して,のちの花開く王朝文化の祖とされ,なお,晩唐の影響を強く受けていたとはいえ,が空海,最澄の仏教が,まさに,日本化したものとして大きな存在であったように,いわゆる国風文化の準備をしたことは間違いないだろう。
その嵯峨天皇が没するやいなや,承和の変を起こした藤原良房によって,藤原氏の専横が始まり,その後の天皇の権力は無きものとなるが,大伴家持が,藤原氏への抵抗すべく「万葉集」を編纂したことが端的に示すように,和歌は,いわゆる敗者の抵抗の象徴のような存在であって,ついに,醍醐天皇が,初の勅撰和歌集となる「古今集」を撰することを企図することになり,その撰を託されたなかの一人紀貫之は,やはり,大伴氏と同様,古代からの名族ながら排除されてきた紀氏の一員として,全力を振るうことになる。ついでに言えば,その後も,単に戴かれるだけで,権力を発揮できない天皇にとって,勅撰和歌集の編纂は大きな拠所となり,のちに,鎌倉幕府から権力を取り戻そうとした後鳥羽天皇は,その象徴のような存在になった。
「古今集」編纂の一員に選ばれた紀貫之は,その機会を最大限に利用し,女性の際立つ時代のところでも述べたように,その「仮名序」によって,のちに,古今伝授として,近世まで続く和歌路線を敷いたばかりか,晩年,土佐守として現地赴任したのを契機に,有名な'男もすなる日記といふものを,女もしてみむとてするなり'の書き出しで始まる,初の仮名文学「土佐日記」を著して,王朝女流文学を準備,歌人としての貫之の作品は,トップレベルとは言えないが,デザイナとしては,抜きんでた人物と言えよう。もともと出世のあての無い貫之は,屏風歌歌人として出発,歌合に出詠するうち,すでに述べたよう,この頃には知られるようになっていた「万葉集」にあやかった「新撰万葉集」に採用されるなど,歌人としての道を歩むうち,901年の漢学者菅原道真の左遷によって,藤原氏が後宮対策とした仮名の使用が自由になり,903年,内蔵助に採用された藤原兼輔と親交して,その庇護を受け,醍醐天皇が撰進を命じた「古今和歌集」に,従兄の紀友則らとともに選者になると,編纂をリードして専念,わずか2年後の905年,和歌史を批判する仮名序をつけて奏上,まさに国風文化の幕を開いたのは,33歳の時であった。しかるに,官職の方は不遇のままで,930年,土佐守に任じられて,初めて地方に赴任,翌年には醍醐天皇が,その2年後には,藤原兼輔も死去するなど,庇護者を相次いで失い,平安時代最大の危機,平将門の乱の始まった63歳の時,孤立無援のなか帰京して,「土佐日記」を創作,以後,醍醐天皇の遺勅を奉じて,「新撰和歌集」を編むも陽の目を見ず,自らの屏風歌中心に「貫之集」を編んだ上,「新撰和歌集」に孤愁の心境を示す真名序をつけ,74歳で没した。
古代末の院政期に,朝廷の歌人として登場した藤原俊成は,1140年,西行の遁世に衝撃を受けて,傑作'世の中よ道こそなけれ思ひ入る 山の奥にも鹿ぞ鳴くなる'を詠み,翌年,それも含む「述懐百首」などで,崇徳院の歌壇の殊遇を受けて,傑作を続けるも,1156年の保元の乱後,歌壇は崩壊し,崇徳院は,配流先の讃岐で死去してしまうが,朝廷歌壇のリーダーになり始めると,平清盛が太政大臣になった年,御子左家に帰って俊成と改名,翌年の54歳の時,住吉神社に籠って和歌に命をかける覚悟,63歳の時,関白九条兼実の和歌師範に迎えられ,六条家の権威と劇的交替,源氏が蜂起し,平氏が滅亡して,鎌倉幕府の発足するという日本史上の劇的変化の間,後白河院から「千載和歌集」撰進の院宣が下って,ついに,第一人者となり,完成させて奏覧後,"寂寥感"から"優艶美"への転換に決着をつけると,83歳という高齢になって,史上最高とされる歌論書「古来風体抄」を式子内親王に献進,後鳥羽院の信頼を得,子定家とともに,新古今様式を開花させ,最後まで,指導者の地位を保って,90歳で没した。藤原俊成は,公家社会から武家社会に劇的転換に,和歌の面で応じた文化のデザイナであったといえよう。
父俊成のデザインのもと,後鳥羽院に認められて,「新古今和歌集」を編纂するも,院との確執著しかった藤原定家が,その後,現在に至るまで,和歌を革新した歌聖として崇められことになっているわけであるが,現在もなお,正月行事や競技として定着している「小倉百人一首」を撰しているのだから,藤原定家もまた,優れたデザイナであったことは間違いない。そして,武家からの権力奪回を試み,失敗して配流された後鳥羽天皇は,その地で,最期まで「新古今和歌集」の編纂に執念示して,敗者の典型になったのである。そして,応仁の乱が始まった翌年,作品に感銘した斎藤妙椿が城の包囲を解かれた東常縁が,1471年から2年かけて,伝来の古今集を宗祇に講義して"古今伝授の祖"になり,近世に続いて行くのである。
和歌からは,その後,まず,武家社会に対応する連歌が派生,鎌倉幕府が滅亡して,足利政権が始まると,文化的には,いわゆる公武合体になって行くが,その口火を切った関白家の二条良基は,南北朝の動乱で本職が翻弄されるなか,武家社会の文化的価値を初めて認め,地下の連歌師救済に師事してすぐに,連歌論書「連理秘抄」を著し,1352年に,観応の擾乱が終わって時代が落ち着くと,救済とともに,連歌最初の準勅撰集「菟玖波集」を編纂して連歌道を確立しただけでなく,歌人頓阿との間で「愚問賢注」を著して,二条派を庇護して文壇指導者となり,晩年には,足利義満のサロンを指導して北山文化を創造するなど,まさに,文化のデザイナであった。そして,足利義満没後の動乱の世に連歌に専心,1467年の応仁の乱勃発少し前には連歌論書「ささめごと」を著して,最高の連歌師宗祇はもちろん,最高の俳諧師芭蕉にまで影響た心敬も挙げておかねばならない。
次に派生したのが俳諧で,室町幕府の滅亡直前に,連歌師の子に生まれた松永貞徳は,地下の歌人としても一流になる一方,徳川幕府が始まってまもなく俳諧を始め,やがて貞門と呼ばれる俳壇ができると,家光の鎖国令が始まる1632年,63歳の時,自ら生まれ変わったと,姿を童形に改めて隠居,俳諧全盛を導く革命を起こし,家光が没した年には,80歳にして,膨大緻密な俳論書「俳諧御傘」を著し,初めて,日常通俗の言葉に詩的価値を認める文学史上の革命を起こし,まさに,'貞徳無くして芭蕉無し'といわれる,大デザイナであった。その貞徳が死去するや,初めて俳諧の発句を披露し,西鶴らに推されて,「江戸俳諧談林十百韻」を催行して談林派の祖になった西山宗因は,貞門に批判的であったが,平易な独自の俳境拓き,芭蕉らの登場を直接的に促す役割を担い,その天才芭蕉の最も良き理解者で信頼され,門人からも敬服された向井去来が,いわゆる蕉門を確立する。そして,俳諧からは,現在もなおメディアで話題になる川柳が派生するが,その祖とされる柄井川柳は,自らは句作せず,狂歌に押されながらも付句集「柳多留」編纂を続けたデザイナ的人物であった。
そして,明治維新になって,西欧文化の流入に対抗する必要に迫られた和歌,俳句は,正岡子規によって,劇的変化をすることになる。良く知られているので,簡単に記せば,1889年の帝国憲法の発布まもなく,25歳の時,陸羯南の縁で,日本新聞社に入ると,紙上で,まず,俳句ついて季語などによる革新に専念,1894年の日清戦争後,カリエスで病臥するようになった後も,弟子の高浜虚子が創刊した{ホトトギス}を指導して普及させる一方,31歳の時,有名な「歌よみに与ふる書」の連載を始め,2回目の「再び歌よみに与ふる書」では,'貫之は下手な歌よみにて古今集は下らぬ集に有之候'と書きだす激烈さで,「万葉集」を称揚するなど,決定的影響を及ぼして早世,まさに,近代詩歌文化のデザイナになった。貫之同様,子規も,歌人・俳人としてのみ捉えると,作品のレベルは,トップになるような存在ではないが,与えた影響は甚大であり,デザイナ(というよりはアジテータかもしれないが)として捉えることの必要性が分かってもらえるだろう。子規の打ち出した短歌は,{アララギ}の編集発行を主導した島木赤彦によって,歌壇進出に大きく寄与し,いわゆるアララギ派といわれる人が,近代短歌の主流になる。
最後に,西欧文化によって始まった近代詩に触れておくと,口語自由詩を完成させ,おそらく印刷された表現を意識した独自のアフォリズムを展開,近代詩の世界を大きく転換させた萩原朔太郎,西欧文芸の紹介につとめ,名訳詩集「海潮音」で詩歌壇に決定的な影響を与えただけでなく,結果として,日本語文字には無かったヴィを(V音のカタカナ表記であるが,B音なのに間違って使うくらい)定着させた上田敏の二人を挙げておきたい。
2:その他の芸術,芸能
和歌とそこから派生した連歌や俳諧以外の芸術,芸能に関わるデザイナ的人物について,時代を追って簡単にみると,
まず,武家政権への変わり目に登場し,女性芸人乙前から習った今様の歌謡を集成した「梁塵秘抄」をまとめて民間芸能にお墨付きを与えたこと以上に,現代において,世界冠たるストーリー漫画のルーツたる絵巻物を振興するなど,中世への,文化の大転換を主導した後白河法皇が挙げられる。
鎌倉時代の終りに登場,公武の間に多数の支持者を得,七代の天皇から国師号,日本禅宗の主流の元になった夢窓疎石は,36歳以降,景勝の地に次々隠棲しながら,修行の場として庭園を制作するうち,後醍醐天皇を受け,1333年の鎌倉幕府滅亡後,臨川寺の開山になるとともに,枯山水の名園を制作,南北朝分裂後は,新将軍足利尊氏とその弟直義からも帰依され,64歳の時,西芳寺中興開山になると,傑作"苔寺の庭園"を制作,その後は,天龍寺の造営に腐心し,71歳,大伽藍と庭園の美観「天龍寺十境」を定めて,5年後に没したが,その後,禅寺に次々名園が生まれて行くことから,夢窓疎石こそ,庭園文化のデザイナと言って良いだろう。
統治のデザイナは出なかったものの,国家支配者として北山文化のデザイナであった足利義満もとに,"能楽の祖"になった世阿弥が登場する。11歳の時,父観阿弥とともに猿楽能を演じて,それを見学した義満から絶大な庇護を与えられ,21歳,父の死去して観世大夫を継ぎ,36歳の時には,将軍義満の台臨をえて,天下の名声を得るに至るも,45歳,義満が急逝,父の方針に悉く逆らう後嗣の将軍義持によって失脚,不遇のなか,55歳には,のちに「花伝書」にまとめられる,子らへの相伝の著述を開始,以後,能の創作も含めて,立て続けに著述,その内容は,極めて体系的かつ緻密,のちの能楽者の拠り所になるもので,まさに,能舞のデザイナであった。59歳には,出家し,成長した長男元雅に観世大夫を譲るも引退したわけでなく,一座は大発展して,自らも円熟の境に達するが,65歳の時,籤引きで登場した特異な将軍義教の弾圧によって,能を演じることもできなくなっただけでなく,後嗣元雅も早世して悲嘆,71歳,ついに,佐渡に流され,80歳頃に没した。ついでながら,佐渡では,のちに,能楽が広がって,現在に至っていることは,良く知られているが,そのほか,順徳天皇など,レベルの高い人物が,多く流されたことで,独自の文化が育まれいる。
8代将軍足利義政は,禅僧一休宗純の指導によって,芸術(芸能)的活動において,後世につながるさまざまなものが登場する時期に対応するような繊細な人物で,政治から逃避し,応仁の乱の勃発を招いた国家支配者としては失格であったが,一休が没した年,45歳に閉居すると,東山山荘の造営に没頭,銀閣を建てるとともに,名園を整備し,一休が指導してきたものも含めて,のちに東山文化の時代とも言われることから,文化のデザイナとしての役割は大きかったと言える。例えば,1461年に,相国寺の庭園を制作して,史上初めて作庭家として名が出る善阿弥を登用,彼は,すでに,75歳という高齢で,その後,彼は集中的に作庭するが,義政が東山山荘の造営を始めたのは,彼が死去した年なので,善阿弥に学んだことが活かされたと考えられる。
東山文化を代表する人物として挙げられる雪舟は,応仁の乱が勃発した年に,明に渡って決定的影響を受け,水墨画を大成する大画家になったのであるが,将軍足利義政の御用絵師になる小栗宗湛に絵画を学び,名を知られぬ時の絵が雪舟に感嘆され,1483年,義政が,東山山荘の絵を雪舟に描かせようとした際,固辞した雪舟から推薦されて御用絵師になった狩野正信がおり,その長男で父以上の画才を発揮した狩野元信は,幕府の弱体化で,活動の場を,上層町衆ほか,寺院,朝廷,公家らに広げて,新障壁画様式確立,その孫の狩野永徳が,信長に呼応して画風革新,秀吉の大建築に次々と大作,安土桃山様式として狩野派を確立したことで,元信は,後世,神格化された。また,和歌の項で述べたように,連歌もまた,この時代に開花するが,東山文化時代に,後世につながるさまざまなものが登場したという点で代表的のは茶道であろう。
すでに,戦ではない平和的な競技として,中国から伝来した闘茶が,室町幕府創設に貢献したバサラ大名佐々木道誉によって広がっていたが,興福寺配下の寺に入門していた村田珠光は,衆徒らの間に流行していた闘茶に耽溺して寺を追われ,放浪の後,足利義政が将軍になってまもなく,29歳の時,大徳寺の真珠庵に落ち着いて,一休宗純に参禅し,連歌師心敬や飯尾宗祇らとも親交して,"佗数奇"の理念を深化,書院茶の湯を仏寺の方丈の理念に叶う四畳半茶の湯に改め,1462年,40歳の時には,義政の茶道師範となり,義政が東山山荘に隠棲後も指導を続けて,80歳で没して,"茶の湯開山"となった村田珠光は,茶道の最初のデザイナであった。そして,珠光が没した年に生まれ,大徳寺で出家して,"わび"の美学を確立後,珠光の開いた茶道を大成し,千利休ら堺商人へ伝え"堺流茶の湯開祖"になった武野紹鴎が次のデザイナになり,紹鴎に学んで,茶道の大成者で現代の茶道の祖になった大デザイナ千利休に至るが,言うまでも無く,あまりに秀吉政権に隠然たる勢力をもったため,切腹させられ,中断してしまうが,,将軍家光の時代に,仕官せずに千家の再興に努め,その子をルーツに,表・裏・武者小路という,現代に続く,千家茶道の家元を確立した,孫の千宗旦を最後に,茶道文化は,優れたデザイナが続いたことによって,揺るぎないものになったと言えよう。
茶道のルーツである闘茶と同じように,戦に代わる競技である碁将棋は,僧の間では,古くからなされていて,戦国時代には,武将たちの間でも盛んにされるようになり,信長,秀吉につかえた本因坊算砂が,本当に戦を無くした家康にも重用され,近世囲碁の基礎を確立して,本因坊家の始祖になり,世襲する形で明治維新後まで続くが,中央棋院に本因坊免状発行権委譲して,実力制採用,棋風も革新して碁界を近代化し,現在まで盛んに続くようにした本因坊秀哉と,将棋もまた,近世以来,名人は世襲であったが,維新後,自ら世襲名人を辞退して,実力名人制を導入し,将棋界の近代化を実現,その結果,現在の藤井聡太名人に至るまで,何人もの天才棋士を生んで,隆盛を保たせるようにした関根金次郎は,まさに,棋界のデザイナであった。
徳川時代に入って,戦に出ることの無くなった武士たちは,後述するように,全く異なる分野に転身して,新たな世界を開く人物になっていく一方,戦に代わる武術として,いわゆる文武両道の,武を担うようになるが,その端緒を開いたのは,新陰流を確立し,近世剣術を革新,徳川将軍兵法師範として治国経世までも教えた柳生宗矩で,後々まで模範にされる剣術のデザイナであり,不敗のまま実戦を離れて独自兵法を完成後,恩受けた城主の死に,「五輪書」を書上げて没した宮本武蔵という天才を得,幕末には,近代的な教授法と昇段制の改革などで俊秀が集まり,江戸随一の道場の名声を得た千葉周作や,彼と類似の生涯を送り,道場には高杉晋作・桂小五郎ら維新の主役が集まった斎藤弥九郎,あるいは,幕臣として江戸の無血開城実現に貢献,明治天皇の侍従になる一方,無刀流剣術の開祖になった山岡鉄舟ら,近代を開くことに貢献するに至る。
武術に近いものの,大きな身体や土俵という舞台での振舞いなどで,歌舞伎役者などに近い人気稼業ともいえる相撲は,幕藩体制のなかで,大名間の平和的競争の一環として,いわゆるお抱え力士という形で広がっていったが,天明期に登場した,天下無敵の強さに人徳があって江戸随一の人気を得るも,現役中,流行性感冒で早世した第4代横綱谷風梶之助や,化政期の,強いばかりでなく,学もあって,13年間の巡業日記の他,多くの記録を残した無敵の大関雷電為右衛門らによって,国民的競技となり,維新を迎えると,一場所2敗を恥じて引退,両国国技館の建設はじめ,相撲の近代化と発展に貢献した梅ケ谷藤太郎,恵まれない体格ながら革新相撲で横綱になり,引退6年後,日本選手権で現役横綱ら倒して優勝するほど強かった栃木山守也,その弟子で,若乃花と小兵の名横綱同志の"栃若時代"を創り,引退後は名理事長として多大の業績を遺した栃錦清隆らによって,今なお,いわゆる国技として,NHKでも特別扱いされている。近年,モンゴル人力士が長く横綱を独占,中には,その振舞いが問題になる力士も登場,国技として問われる以前に,そもそも相撲は,近代に西洋から入って来たスポーツにあたるものなのどうかといった難問は未解決のままになっている。
それはさておき,近世の武術から,スポーツ,さらにはその振興まで一挙にデザインした人物,嘉納治五郎は,桜田門外の変のあった年に生れ,塾でいじめに遭い,維新で消えてしまった柔術家を,入学していた開成学校が帝国大学になった年,なんとか探し出して学ぶや,一気に頭角を現し,来日したアメリカのグラント将軍の前で披露,卒業した翌年,22歳で,{講道館}を開塾,26歳には,新道場を建設し,諸流派を統合,柔道として確立し,門人の活躍も始まるなか,33歳には,第一高等中学校長,37歳には,東京高等師範校長になり,体育科を新設して,教師の養成に努める。日露戦争後の49歳,クーベルタン男爵に請われて,アジアで最初のIOC委員となり,翌々年には,大日本体育協会を設立して初代会長,その翌年には,自ら団長となってストックホルムに行き,日本のオリンピック初参加を実現,校長,会長を退任後も,オリンピックには参加し続け,満州事変翌年の72歳の時のロサンゼルス大会での華々しい成果を挙げ,二・二六事件の起きた年,カイロで開催のIOC総会で,ついに,東京オリンピックの招致に成功するに至ったが,翌々年,その帰途,氷川丸戦中で肺炎のため急逝,巨人と言うにふさわしい生涯であった。
その他,体育スポーツ振興において,大きな役割をした人物を挙げておくと,"普通体操"の普及・卓球の移入・女子体育の発展などに貢献し,日本の"学校体育の父"になった坪井玄道,わが国女子体育界の先達井口阿くり,体操教員検定に女性として初めて合格し,体操選手の名門{藤村学園}を創り上げた藤村トヨ,日本サッカー界の大先達で'サッカーの神様'竹腰重丸ら,そして,嘉納治五郎のあとを受け継ぐ人物には,民事訴訟の権威で,大日本体育協会長になり,日本スポーツ界をリードした岸清一,政財界で活躍する一方,アマチュアスポーツの振興に尽力し,国民体育大会も創始した平沼亮三,オリンピック日本人初の金メダリストで,日本の陸上競技の発展に尽くし"日本陸上界の父"になった織田幹雄,「社会体育論」を提唱し,オリンピックに生涯をかけ,嘉納が招致するも戦争で中止になった東京大会を,戦後,実現・成功に導いた田畑政治,選手としてメダリスト,東京大会を成功に導き,近代スポーツのあり方に警鐘鳴らし続けた大島鎌吉,そして,身体障害者のスポーツ振興をはかり,"日本パラリンピックの父"と呼ばれる中村裕に至る。
つけたしになるが,自然や文化を対象に挑戦する探検紀行型は,古来からそういった人物がいるものの,意識的になったのは,西洋から個人主義的指向が入ってきてからで,日本の領土確保に心をくだき,「日本風景論」は大きな影響,殆ど全大陸を旅行した志賀重昂と,銀行勤めの傍ら,日本の登山文化の基礎を築いた小島烏水が際立つほか,幕府の蝦夷支配に反発し辞職,新政府でアイヌ地名を漢字化も,アイヌ政策に失望し辞職した松浦武四郎,日本人初のラサ入り,「西蔵旅行記」が大ヒット,両ラマから大蔵経入手,チベットブームを起こした河口慧海,本願寺宗主として,中央アジアで発掘調査を実施し,負債と疑獄で隠退後,大アジア主義の先導役となった大谷光瑞ら,大きな目標のもと,探検紀行した人物も多い。
戦そのものを終わらせた徳川時代には,文学の分野で,大坂の陣が終わるや,禅僧に転身して仏教復興運動を起こし,仏教説話が仮名草子の先駆になった鈴木正三,出家して住職になった後,仮名草子を書き始め,質量ともに最大の作家となった浅井了意ら,武士から転身した人物が,その後につながる大衆文学の準備,元禄時代には,天才井原西鶴が古典的な物語を脱して,初めて庶民の生活を題材に創作して,近代小説を準備,幕末の,読者の嗜好に合わせて「東海道中膝栗毛」を書き続け,本格的職業作家の嚆矢になった十返舎一九に至る。
絵画の分野では,幕府が,織豊時代に確立した狩野派を採用したのに対し,書画,漆芸,陶芸に通じ,家康からの土地に"芸術家村"を開いて新時代の芸術をリードした本阿弥光悦という優れた文化のデザイナによって,光悦が協業した俵屋宗達を皮切りに,在野の大画家と言えるような人物が輩出して行き,初の挿絵画家として独自の画風開拓し大流行させた菱川師宣が,浮世絵の実質的な開祖になるとともに,元禄文化を先駆し,天明文化を先駆した鈴木春信が,多色刷木版画錦絵を誕生させて,浮世絵を飛躍的に発展させる一方,多くの画家が,その人物の才に留まるなか,伝統画派全て否定して写実様式を確立し,円山応挙によって,円山派という一派ができるのは,近代への準備に呼応するものとも言えよう。
戦国時代末から織豊時代には,藤堂高虎代表に,武将の多くが城郭建築家であったが,関ヶ原の戦直後に徳川家康に用いられた中井正清は,重要な城郭や寺社を担当して信頼,幕府の関わるさまざまな建築を担う中井役所の祖となり,一級の建築・造園を数多く設計し,茶道でも将軍師範・遠州流の祖になった大名で万能の芸術家と言える小堀遠州は,いわゆるデザイナの大人物であったし,義太夫節を創始,{竹本座}を開き,近松門左衛門作品が大当り多数,近世浄瑠璃を確立した竹本義太夫,現代まで続く団十郎のパターンと市川宗家を確立した市川団十郎(2代),"歌舞伎十八番"を選定・公表したが,<天保の改革>で江戸十里四方追放の憂き目にあった市川団十郎(7代),フィクサーとして,門閥にとらわれない合理的な興行制度や合作に適した作者式法を確立した金井三笑らは,現代でもなお盛んな歌舞伎のデザイナであった。そして,徳川時代初期に,僧侶として最高位あった安楽庵策伝が,仏教普及のため近世話芸を確立,「醒睡笑」で落語の創始者になり,観客を前に口演する"辻ばなし"で超有名人となった露五郎兵衛は,上方落語の開祖とされ,仕方噺を得意として本職となるも,筆禍で遠島,赦免即憤死した"江戸落語の祖"鹿野武左衛門,その他の人物の活躍で発展を続け,幕末に創作噺で地位を得,維新後は近代落語を確立,多くの門下を育て黄金時代開いた三遊亭円朝によって,ますます発展していることなど,近代の多くが,近世の文化の続きにあることも,確認しておきたい。音楽については,現行の筝曲の原点「六段」など近世筝曲確立し,盲人音楽家専業化も実現した天才音楽家・八橋検校などがいたものの,近代化における西欧の影響が大き過ぎたと言える。
近代に入って以降は,かなり知られているので省略するが,本職がどうであれ,文化のデザイナとして評価すべき人物を,生年順に,挙げておきたい。早稲田大学を拠点に文芸活動を指導,先取りと献身で,多大な影響を与えた坪内逍遥,官僚として{東京美術学校}創設,俊材を育成するも排斥され,以後,思索と海外活動に転換した岡倉天心,その天心のもとに傑作描き,その遺志を継いで{日本美術院}を再興,画壇の一大勢力にした横山大観,図書館長になるや"巡回文庫""十門分類表"など革新的な試みも,内務官僚と確執で自殺した佐野友三郎,日本と世界のお伽話を集大成,童話口演の全国行脚に努め,近代日本児童文学の生みの親になった巌谷小波,銀行勤めの傍ら,日本の登山文化の基礎をつくった小島烏水,政治風俗を風刺して一世を風靡,雑誌{東京パック}を発刊して後進育成し,漫画隆盛の基礎をつくった北沢楽天,日本映画独自のジャンルを確立し,映画製作所も設立した"日本映画の父"牧野省三,新劇界の草創期に新しい世界を追求,{築地小劇場}で新劇俳優多数を育成するも,早世した小山内薫,{赤い鳥}を創刊・主宰し,児童文学を開拓・主導して,早世した鈴木三重吉,{日本野鳥の会}を起し,鳥類・自然保護運動の先頭に立って活動,優れた随筆も遺した中西悟堂と,{山階鳥類研究所}を開設し,鳥類全てに和名,日本の鳥類学研究,自然保護に指導的役割を果たした山階芳麿,戦前・戦後一貫して朝鮮はじめ地域の伝統文化に取組み,"民芸運動"を創始・展開した柳宗悦,軍国主義の進む中,次々と傑作を書いて探偵小説分野を確立,後進の育成にも尽力した江戸川乱歩,漫才の台本を通じて,新方向を開拓し,多数の漫才師を育成した秋田実,戦時下に報道写真の理念と方法を紹介,多くの俊才を育て,<敗戦>後も,{岩波写真文庫}でリードした名取洋之助,戦前は夫と洋画輸入,戦後は邦画国際化に貢献,国立フィルムセンター設立にも尽力した川喜多かしこ,長く{映画之友}編集長をつとめ,{友の会}を主宰,テレビの映画批評を開拓して圧倒的支持された淀川長治らである。
ついでながら,現在一般に使われる,いわゆるデザイナ(商品型)について,忘れてはいけない人物を,生年順に記しておくと,商業美術を先駆け,現代日本のグラフィックデザインの礎を築いた杉浦非水,日本でのコピーライターの嚆矢(当時の呼び名ではアドライター)の片岡敏郎,"美人画"で一躍有名になり,写真・印刷を初めて活用して商業デザインを先駆するも挫折,画家というよりデザイナだった竹久夢二,自らの取組みに疑念を抱き続けながらも,多くの人材を育てた昭和宣伝広告の先駆者太田英茂,日本のグラフィックデザインの先駆者で,アール・デコで知られ,{資生堂}の企業イメージをつくった山名文夫,タイポグラフィーをテコに,装幀(ブックデザイン)を中心に,時代をリードした原弘,"お茶の間洋裁""ニューきもの"など草分け的存在で,皇室御用達になった田中千代,{桑沢デザイン研究所}を創立,東京造形大学へ発展した桑沢洋子,40過ぎに通産省から転身,椅子はじめ多くの傑作を生み出し,先導したが,自殺した剣持勇,グラフィックデザイナー先駆者,<東京オリンピック>で第一人者,社会的地位向上に尽力した亀倉雄策,大量生産・大量消費社会に疑問を投げかけ,独自のものづくりのデザインを開拓した秋岡芳夫,テレビCM制作のジャンルを開拓,次々受賞して天才といわれるも,絶頂のなか自殺杉山登志というところであるが,自殺多いのは芸術家指向と資本主義広告先端との矛盾からではないだろうか。太字にした3人は,いわゆるデザイナをデザインしたと言えるような人物である。
3:学問
古代の日本では,明治維新後に,西洋の学問を取り入れて消化に努めたように,中国の学問を消化するのに努め,学問は,公的には,朝廷の,いわゆる文人官僚,本講の活動の分野型で言えば,官僚分野の法務学識型が担い,書類を整え,判断を下す,近代の学問の法学にあたる分野が中心の,いわゆる漢学,見方によっては,儒学であり,文献等の蓄積や,幼時からの教育が大きな比重を占めるため,いわゆる学者家系が醸成された。その最初が,古代随一の学者とされ,悲劇の結末によって,天神様になった菅原道真が出た菅家で,祖父清公が,遣唐使の一員として,空海,最澄とともに入唐,新知識を得て帰国し,平城天皇即位とともに登用されるや地方行政に功績を挙げ,嵯峨天皇によって,大学頭に抜擢され,天皇が譲位後も,朝儀の整備その他に重用され,ついには公卿になり,嵯峨上皇と同じ年に没した,子の是善が継いだことで始まり,道真失脚後も学者家系として続き,鎌倉時代に入って,土御門天皇の侍読になった菅原為長は,当代の大才と言われ,菅家では,道真以来の公卿になった。もう一つ有名なのが,菅原清公に師事した,大江音人の興した大江家であるが,菅家のようにはいかず,その力が発揮されるのは,藤原道長時代に,一条天皇の侍読に抜擢されて,中興の祖になった大江匡衡からで,その曾孫,大江匡房は,古代から中世への転換を象徴,その在り方が後世への指針となって多大の影響を及ぼし,その曾孫,大江広元は,統治のデザインのところで紹介したように,源頼朝,北条政子のブレーンとなって,鎌倉幕府の確立に貢献,余談ながら,競走馬の血統で,その才能が最も出るのは,血が8分の1,つまり曽孫であること,そのままである。
そう言った学者家系でなくても,法的効力を有する現存アジア最古の法典「令義解」の編纂はじめ,多くの治績をあげた清原夏野,正確な判決で,その法解釈は長く範とされたが,法隆寺僧訴訟事件では伴善男と対立した讃岐永直,日本最古の百科事典「秘府略」編など才能を発揮,皆に慕われ,承和の変直後に公卿・参議になった滋野貞主,当代一流で,孤高を保ち政変にも巻き込まれず,「続日本後紀」20巻完成させた春澄善縄,正義感に溢れた経世家で,菅原道真と衝突,その左遷で昇進し,「意見十二箇条」など建言した三善清行,当代一流ながら官位は不遇。公家社会衰退期の新人類で「本朝文粋」「新猿楽記」を遺した藤原明衡,優れた学者として変革期の権力者たちに信頼され,菅原道真以来,儒学者で唯一人没後神になった清原頼業,有職故実や朝儀に通じ源平双方が重用,詳細な日記「山槐記」を遺し,「今鏡」「水鏡」著者説もある中山忠親など,現代なら,学問の世界でトップ級と言うだけでなく,デザイナとしても,大きな役割をした人物がいたことを,知っておいてほしい。のちのことになるが,室町時代の後半には,関白まで務めて政界を引退後,応仁の乱で苦労しながら,日本一の大学者として,公武合体の文化のブレーンの役割を果たした一条兼良と,その後継者的な存在で,応仁の乱期も京都に留まり,生活には窮しながらも,公武合体の象徴として尊敬され続けた三条西実隆も加えられるだろう。
古代において,在野の学問は,仏教僧が担っていたが,そのなかに,僧と言うよりは学者であるという人物と,その人物が拓いた学問分野が登場する。藤原良房が人民初の摂政となり,その養子基経が初の関白になる,まさに藤原氏専横が進む最中,日本独自の草木成仏の思想を確立しただけでなく,わが国梵語論の原点となる画期的な書を著し,同時に,日本語の性質も究明して,五十音図の原型をも発明した天台僧安然であり,蒐集編纂型を前提とした言語文学型を主流とする日本の学問の最初のデザイナと言えよう。そして,鎌倉幕府の名執権北条時頼の時代に,「万葉集」の研究を飛躍的に発展させた「万葉集註釈」20巻を完成した僧仙覚が伝えた「万葉集」をもとに,江戸の元禄時代前夜,万葉仮名表記の発見など,僧契沖が天才的業績をあげる。
これらをもとに,いわゆる国学を創始した荷田春満は,赤穂浪士の復仇の支えをなした後,「万葉集」講義を核に,多くの門人を育てて,幕府とも間接的に学問上の交渉をし,その子,荷田在満は,田安宗武に「国歌八論」を呈して国歌論争になり致仕するが,後任に,ライバルであったが,父の創始した国学を受け継いだ賀茂真淵を推挙,その真淵から刺激を受けた本居宣長が「古事記伝」に着手,30余年かけて完成させたそれは,復古思想の極限としての国学をも完成させることになり,現代もなお,右翼思想はじめ大きな影響を及ぼしていることから,本居宣長は,大学者である以上に,大デザイナであったと言える。
その間には,初めて「日本書紀」全体の注釈書をまとめ,日本初の五十音順国語辞典「和訓栞」を作成した谷川士清,名著「古言梯」を著し,その後の歴史的仮名遣い研究に貢献した楫取魚彦といった,言語文学面で,優れたデザイナ的学者がいたことも,関係があったと考えられる。
ここで,宗教では無く,人々の考え方,生き方に大きな影響を与える,学問と言い切ることには躊躇するものの,現代における哲学,すなわち最もデザインに近い哲学思想型の学問に触れたいが,当然のことながら,それら人物の著作を読んで貰う方が大事と思われるので,簡単に列記すると,まず,中世での,公家社会から武家社会への大変革に,日本人初の体系的な歴史「愚管抄」を著した慈円,後醍醐天皇の没後,回復めざし,南朝の正統を主張した「神皇正統記」ほか膨大な執筆をした北畠親房の2人の歴史思想が挙げられる。
近世に入ると,生年順に,不敗のまま実戦を離れて独自兵法を完成,恩受けた城主の死に,「五輪書」を書上げて没した宮本武蔵,遅い登場ながら,養生に努めて長寿を保って,多分野に膨大な著作をし,晩年の"益軒十訓"が,大きな影響をもたらした貝原益軒,日本における陽明学派の始祖とされ,近畿に勢力を持った中江藤樹,近世思想が段階的に深化して行く元になる古義学を創始した伊藤仁斎,家宣が将軍になるや,ブレーンとして"正徳の治"を現出するも,理想に過ぎ失脚した新井白石,官学の朱子学を攻撃して播州に流され,赤穂義士,さらには維新の志士の精神的支柱になった山鹿素行,武士道に関する談話を藩士田代陣基が筆記して「葉隠」が成立,後世大きな影響を与えた山本常朝,そして,デザイン論で,背景となる哲学に取り上げた,独自の思想で学派を確立,観念より実利を重んじ,将軍以下広く影響を及ぼした荻生徂徠後には,徂徠門下ながら,道徳と経済バランスをめざす独自の説を展開,後世に大きな影響を及ぼした太宰春台,江戸中期に身分制度を根本的に否定,近年,その驚くべき先進的思想が知られるようになった安藤昌益,文化人類学要素をもった革命的思想「出定後語」「翁の文」を提示して,早世した富永仲基,生涯田舎村を離れず独学で,日本人離れをした大哲学を構築した三浦梅園,徂徠学を講じて朱子学を圧倒したため<寛政異学の禁>の標的となり,失意の中,放火自殺した亀井南冥,全国数十藩の財政再建,失明の乗り越え,驚くべき自由経済思想「夢の代」を著した山片蟠桃,「稽古談」ほか多くの著作講義で,商品経済の発達による富国説く画期的重商主義論を展開した海保青陵,鎖国下で合理的認識を先駆,日本で初めて世界地誌を著し,町人や百姓の心得も説いた西川如見,西洋流の天文・測量・地理を踏台に,重商主義的貿易論で大きな影響を与え,仕官せずに門弟を多数養成した本多利明,詩文・書画を愛し,各地を遊歴するなか著した「日本外史」が幕末志士に大きな影響を与えた頼山陽,独自の宗教的説と精力的活動で大きな影響及ぼすも,幕府に嫌われ,失意のうちに没した平田篤胤と,近世には,近代と比較にならないほど,多くの,ハイレベルな哲学思想家が輩出,このこともまた,江戸時代が長く続いた大きな理由の一つであったと言えるだろう。
近世の学問で,よく知られているのは,西洋の数学とは全く別に,日本独自の和算が盛んになり,その水準も,西洋に引けを取らないものだったということであるが,その和算の祖吉田光由は,豪商吉田家を受け継ぎ,吉田流算術元祖でもあった角倉了以の分家の医師の子に生まれ,数学に興味を持ち,了以の死去後は,子の素庵について,吉田流算術を伝授され,素庵から蔵書全てを譲られると,それらを手本に,江戸時代も始まってまもない,1627年,29歳の時,「塵劫記」を刊行。内容はもちろん,素庵の親友本阿弥光悦の挿絵装幀を得,普及し始めた算盤のマニュアルの役割もあって,大ヒット,その後も追加,編纂し直し,多色刷りと刊行し続け,1634年刊行の普及版「新編塵劫記」は,江戸時代を通してベストセラーとなる。その後,転変とするうち,同じ毛利門下だった今村知商が和算書を刊行したのに対抗,1641年,43歳の時,根本的に書直した「新編塵劫記」を,末尾に12の遺題をつけて刊行,1653年,55歳の時,この遺題に初めて挑戦した榎並和澄が「参両録」を書いて,答術を発表するとともに,自ら新たに8つの遺題を提出,以後,遺題継承が流行,和算が大いに発達,幕末まで続くのであるから,まさに,和算文化のデザイナといえる。
そして,西洋数学の先駆的内容含む高度なものに革新し,"算聖"と崇められる天才関孝和が登場し,その弟子で,自らも天才を発揮した建部賢弘が,その業績を体系化して解説,関を祖とする関流という,その時点でのトップの和算家が継ぐ仕組みが,江戸時代最後まで続くが,関孝和が,初めて筆算を採用したことの効果も大きかったと思われ,その点からも,関自身デザイナ的人物だったと言える。関流のほかにも,いくつかの流派が生まれ,幕末には,これらの流派すべてをマスターし,日本初の対数表ほか多くの業績を挙げた和算家小出兼政が登場する。和算はまた,暦をつくるための暦学,すなわち天文学と密接につながっているが,元禄時代には,碁方安井算哲の子ながら,棋力の限界を悟って天体観測に専念,貞享暦を完成し,天文方世襲へ至った渋川春海と,天明時代に登場し,伊能忠敬の師高橋至時をはじめ多くの俊秀育て,幕末までの天文方の主流を形成した麻田剛立を,デザイナ的人物として挙げておく。
博物学につながって行く本草学は,元禄時代に,動植物の研究で,好学の金沢藩主前田綱紀から藩儒に召し抱えられ,本草学の典拠とされてきた明の李時珍の「本草綱艮」を補おうとした綱紀の命で,稲生若水が「庶物類纂」362巻をまとめたのを端緒に,数多くの人物が現れて隆盛に向かうが,特に際立つのは,稲生若水門下の逸材松岡恕庵に本草学を学んだ小野蘭山で,師の死去後も独学で研鑽し,開塾すると,講義と執筆に専念,田沼意次時代に入った34歳には,「花彙」8巻を完結,のちに,そのオランダ語訳が,桂川甫周からシーボルトに寄贈され,そのフランス語訳も出版されるほどで,日本植物学を世界に知らしめただけでなく,70歳には,幕府に招かれ,幕命で,江戸期最大の博物誌「本草綱目啓蒙」をまとめて,81歳で没したが,シーボルトをして'日本のリンネ'と言わしめた巨人であった。その蘭山に入門した岩崎灌園は,直後に師が没するも,若年寄堀田正敦から後継として認められて,研究著作を続け,44歳の時,20年かけてまとめた,彩色した本格的な日本初の植物図鑑「本草図譜」96巻92冊を幕府に献上するとともに,富豪の本草家に借金し,豪華本として出版しており,そのまま,のちの牧野富太郎につながって行く。
さらに,天才平賀源内が,田村藍水から本草学を学ぶと,師を説得して,薬品会を開催し,物産会の嚆矢なり,物産学へ展開した直後に,田沼意次時代,いわゆる天明文化期に入るが,早くから奇石の蒐集に取りつかれていた木内石亭が,全国に知られるようになったのも,36歳のこの頃で,田沼意次の失脚後には,弄石ブームを起して華々しい老後を迎えただけでなく,生涯をかけた厳密な研究で近代考古学を先駆している。
日本の自然科学は,本草学によって始まったと言えるが,それが,近代につながるものとして開花するのが蘭学で,将軍徳川吉宗のが,享保の大飢饉に際し,「甘藷考」を献上してきた青木昆陽を登用して,甘藷の試作・普及に努めたことは良く知られているが,飢饉が収まると,吉宗は,昆陽を書物方に抜擢,オランダ語の学習を命じられた青木昆陽は,まず,「和蘭話釈」を著し,さらに,「和蘭文訳」を,吉宗の死去後も,10集になるまで続けたことに始まると言って良い。それを受けるように,オランダ語の本を見せられて発奮した中津藩医の養子前野良沢は,すでに46歳になっていたが,青木昆陽に入門するも,直後に,師が死去したため,藩に許可得て,長崎に留学,そこで購入した本のなかに,「ターヘルアナトミア」が含まれており,直後に江戸に出た際,杉田玄白に誘われて,死刑囚の腑分けに立ち会い,有名な「解体新書」訳出の中心的役割ながら名前掲載固辞したため,実際の解剖と照合した玄白が,蘭学の祖になるが,その後もオランダ語の研究を進めて,藩主から"蘭化"の号を名を与えられた前野良沢こそが,蘭学のデザイナであったと言えよう。その後の隆盛は記すまでもないが,オランダ語翻訳に専念,現行の天文物理用語,文法から,"鎖国"など一般語彙まで創出した志筑忠雄を代表に,わが国に化学を本格的に紹介し,現在も使用される多くの語を創作,西欧諸科学の導入に尽力した宇田川榕庵,西洋理化学の導入に尽力,化学・電気・蛋白等の訳語も創出,日本の科学史に画期を成した川本幸民などが,近代科学へのデザイナ的役割をした人物であろう。彼らとは別に,言語文学型において,京都蘭学の草分けで,「和蘭語法解」翻訳公刊し,近代日本の語学の基礎をつくった藤林普山も忘れてはならない。
近代の人文科学(歴史・地理・言語)のもとになった人物には,詳細な日本地図の伊能忠敬と,「群書類従」編纂刊行した塙保己一を別格としても,水戸学史論を代表し,「大日本史」の論拠を整えた栗山潜鋒,書誌や考古遺品用い,今日なお批判に耐える精確さで研究,金石文・古泉学の基礎を築いた狩谷掖斎,平城京と条理制を研究して初めて復原図を作成するなど,のちの奈良文化財研究所の礎を築いた北浦定政,宝暦事件で長期に逼塞の間,平安内裏の考証に没頭,復古図る光格天皇登場で一躍時の人になった裏松光世,緻密な紹介解説に画家の挿絵溢れる「都名所図会」が大ヒット,名所図会ジャンルの嚆矢になった秋里籬島,それに刺激された祖父が企画し,父が固めた「江戸名所図会」を完成。「武江年表」ほか記録編纂,詳細な日記も遺した斎藤月岑,民俗資料としても貴重な「北越雪譜」出版に生涯をかけた鈴木牧之,長く水戸藩学監を務めた後,幕府に召され,蝦夷関係史料を集大成し現行地名の漢字表記を選定した前田夏蔭など,官民問わず,優れた学者が輩出している。
明治維新によって,学問が西洋由来の科学になった近代について,いわゆる理系では,まず,近世の和算・暦学につながる理論物理学は,日本で初めて,世界的物理学者になり,土星型原子模型を提示して世界に広めた長岡半太郎を受け継ぐように,皆,カタチからアプローチするきわめてデザイナ的な人物で,中間子理論の湯川秀樹,ひも理論の朝永振一郎はじめ,ノーベル賞を受賞者も多く,明解な弁証法的三段階法で一世を風靡した武谷三男も,まさに,その一員であった。
蘭学の延長たる自然科学全体に広げると,日本の医学界を開拓した北里柴三郎,日本における近代鉱物学の創始者で,晩年には科学的な書誌学も開拓した和田維四郎,日本に理論化学を紹介し,世界水準にして行く一方,学術体制の整備にも尽力して"化学の父"になった桜井錠二,<敗戦>後の日本の脳生理学興隆の中心で,初めて"脳死判定"基準をまとめた時実利彦,30代半ばのフロンティア軌道理論で世界に知られ,60過ぎに,日本人初のノーベル化学賞になった福井謙一と,デザイナ的人物は枚挙に暇なく,とりわけ,世界で最初の栄養研究所を創設し,日本独自の栄養学を開拓,国家的栄養基準を主導した佐伯矩,探検による発見をもとに"照葉樹林文化論"を提唱,"分類の発想"とともに広く影響を及ぼした中尾佐助は,まさにデザイナであったと言えよう。
特記したいのは,日本の庭園の歴史を担う造園につながる林学で,デザイン三講のところで詳しく触れているように,デザインの極ともいえる明治神宮内苑の森を実現を主導した本多静六は,苦学して多大の業績を挙げ,"日本林学の父"となる一方,堅実な蓄財で"明治の億万長者"となり多大の寄付するなど,生き方そのものがデザイナの鑑と言える人物で,神宮内苑整備時に,本多の助手であった上原敬二もまた,その後,日本の造園学,造園設計,造園教育の確立を主導,さらに,本多教授のもと,1年先輩の上原と切磋琢磨した田村剛が,日本の国立公園行政で指導的役割をはたし,"国立公園の父"とよばれるに至るなど,まさに,デザイナ一家を形成している。
文系に移ると,まず,日本古来の学問である文学言語型で,全くの独学で,万葉仮名や漢字音を研究,文字字体体系化の先駆的業績を挙げ,第一人者になった大矢透や,留学もせずに英語の達人,英文法,英語教育の基礎確立,英語国でない諸国にも影響を与えた斎藤秀三郎を代表に,現代の国語学の生みの親となった上田萬年,その弟子で,音声学・民族学など幅広い分野で指導力を発揮し,晩年に,定番となる国語辞書「広辞苑」を生んだ新村出,国文法研究の基礎を確立した山田孝雄,近代国語学で傑出し,所論の大部分が学界の定説になった橋本進吉のほか,三上章や原田信一など,ユニークかつ際立つ日本語学者も多い。そして,画期的な国語辞書「言海」をはじめ,辞典の編修・文典の著述・国字問題に著しい業績を挙げた大槻文彦,30年以上かけ,大空襲を乗越え,中国の「康煕字典」をしのぐ「大漢和辞典」を完成した諸橋轍次という人物を介して,蒐集編纂型に目を向けると,独学で「大日本地名辞書」を刊行,能楽や宴曲でも偉大な業績をあげた吉田東伍,若くして豪農を継ぎ,空前絶後の「日本山嶽志」を著して自費出版,日本山岳会を支え続けた高頭式,無学歴ながら,近世文人の百科全書ともいえる膨大な伝記を書き残し,多大の影響を与えた森銑三,世界五十数カ国の民族音楽を訪ねて,音楽の意味を問い続け,大きな影響を及ぼした小泉文夫など,専門的学問と関係ないいわゆる素人のような人物が,学問の基礎とも言えるデータベースを作っていること,後世の人たちに役立つという点で,まさに,デザイナ的であることも忘れてはいけない。
人文科学型に目を転じ,中世・近世のところで述べたように,学問(科学)と言い切ることには躊躇する哲学・思想を別にすると,言文一致による史料の読み方で,日本史近代化の基礎を築いた三宅米吉,暗黒時代とされてきた鎌倉・室町時代を,初めて固有な価値持つ"中世"と位置付けた原勝郎,転変の後,俗事は夫に任せて自宅から一歩も出ずに研究,女性史学を確立した高群逸枝,中世町衆,とくに芸能を対象に"林屋史学"形成,学界のみならず市民層にも影響を与えた林屋辰三郎,"大塚史学"と称される独自の史観を確立し,広く"市民社会"派の人々を啓蒙した大塚久雄などの日本史学者のほか,わが国の実験心理学の創始者で,日本初の記号論理学者と言われ,哲学・論理学にも精通した元良勇次郎,民家こそ建築の原点と近代建築や都市計画批判,現代風俗を研究する考現学など独特思考を展開した今和次郎,比較文化学を開拓し,その確立と後進育成に努めて退官,長年の魅力的研究成果を次々発表した島田謹二などが挙げられる。
特記されるのは,独自の民俗学を開いた柳田国男で,兄弟皆が各分野で一流になるような家系に生れ,農政学を専攻して,農商務省に入るとともに,早大で講義し,著作を続けるも全く受け入れられずに挫折,日露戦争後の33歳の時,九州旅行した際,椎葉村など山間奥地を訪れ感動するとともに,古来からの人民を発見するとともに,岩手県遠野出身の佐々木喜善から伝承する話を聞いて魅惑され,翌年,遠野を訪れ,その翌年に,「遠野物語」を発表して,民族学研究を開始,明治天皇が没した翌年の1913年に,{郷土研究}を創刊し,44歳の時,貴族院議長らと対立して退官すると,翌年,{朝日新聞}に招かれ,紀行文を発表する一方,自宅で懇話会を開始,論説委員として7年間社説を担当した後には,方法論の確立に努めながら,後進を指導し,論文を発表,60歳になると,全国的な山村調査を実施し,全国の民俗学愛好家による{民間伝承の会}を組織し,機関誌{民間伝承}を刊行,敗戦後の72歳には,自宅に,民俗学研究所を発足させ,76歳には,文化勲章,86歳に「海上の道」をまとめて,翌年,没した。歌人だった折口信夫が,1913年に,創刊された{郷土研究}に投稿して,のちに,民俗学的国文学と言われる"折口学"を展開,肺結核で療養中に,柳田から,{郷土研究}への投稿を勧められた宮本常一は,二・二六事件のあった1936年,29歳の時,渋沢敬三の支援で,「周防大島」を刊行したのを皮切りに,各地を,徹底して歩くことで,日本の民俗学に新しい地平を開くなど,広く深く浸透して行くが,科学という点では,疑問符がついてしまうことも,否定できない。
西欧でも新しく広がり始めた社会科学については,日本の統計学の開祖杉亨二,日本私法学の開拓者梅謙次郎,日本における政治学を創始した小野塚喜平次,日本経済史学を開拓・確立した内田銀蔵,自由主義福祉国家論を先駆し,<大正デモクラシー>を先導した福田徳三,日本における都市社会学と生活論を創始した奥井復太郎,生涯かけた体系的著作「民法講義」で学界の源流になった我妻栄らがいるが,最もデザイナ的人物は,雁行形態論を発明,日本人学者理論で最も世界的になった赤松要であろう。戦後は,東大に復帰して復興期の経済政策を指導した有沢広巳,わが国における経営史研究の開拓者で,戦後改革や日本経済発展に主導的な役割を果した脇村義太郎がいる。
最後に,学問とするには無理があるが,現在の活動の分類ではここに入れざるを得ない,啓蒙・思想(著述分野の批評解説型と哲学思想型)について,おそらく,この論の「はじめに」で述べたような,科学,芸術に並ぶ,デザインという活動があれば,そこに入れられるだろうから,そもそもが,デザイナ的人物ということになるが,生年順に見ると,近代哲学の最初の移植者で,"哲学""理性""主観"等の語を考案,軍人精神確立にも寄与した西周,大ヒットの「西国立志編」など新思想の普及に努め,女子・幼児・盲唖教育に尽力した中村正直,まさに近代思想のデザイナと言える福沢諭吉,日本人初の哲学教授。欧米哲学を紹介し,"形而上"はじめ多くの訳語をつくった井上哲次郎,「輿地誌略」「西洋史略」など文明開化啓蒙者として貢献した内田正雄,合理的科学思想に徹して"妖怪博士"と呼ばれ,仏教の革新運動・国粋論的顕揚に奔走し,{哲学堂}を建設した井上円了,文化のデザイナでもある岡倉天心,ベストセラー「二千五百年史」はじめ在野を代表する名著を遺した竹越与三郎,日本のプラグマティズムを先駆した田中王堂,「善の研究」で衝撃をもたらし,"場所の論理"など,独自の哲学が大きな影響を及ぼした西田幾多郎,<維新>後否定されていた江戸時代の考証を在野で先駆,独自の学問的世界を樹立した三田村鳶魚,"国民思想史"の視点から厳密な文献批判で記紀の捏造を論証した津田左右吉,日本主義的科学論で戦時政策に関わり,敗戦でA級戦犯になって,服毒自殺した橋田邦彦,「"いき"の構造」によって日本の哲学に新生面,"実存"などの語を定着させた九鬼周造,大正期の「古寺巡礼」,戦時下の「風土」,戦後の「鎖国」と,常に日本の独自性を強調した和辻哲郎,戦前昭和期のもっとも輝かしい思想家で,「構想力の論理」は,そのままデザイン論といえる三木清,戦時下に反ファシズムの"羽仁史学"で影響を及ぼし,全共闘シンパとして「都市の論理」がベストセラーになった羽仁五郎,<敗戦>直後に,衝撃的な「第二芸術論」ほか,作品の新評価軸を提示し,文学界に甚大な影響を及ぼした桑原武夫,優れた企画展・野外彫刻展や賞の創設と審査など,戦後日本の近代美術館普及に尽力した土方定一,<敗戦>後,時流に対応して常に学界のトップランナーとなり,大きな影響を及ぼした清水幾太郎,<戦時>下に独自の中国観を育て,<日中国交回復>まで中国紹介啓蒙の評論活動をした竹内好,<軍国主義>時代に日本の美を称揚して一世を風靡,<敗戦>で文壇から抹殺されるも,復活した保田與重郎,「東洋人の思惟方法」以降,比較思想宗教の国際的権威となり,膨大な業績を遺した中村元,在野の評論家で,保守系メディアで活躍,時代を先駆し"山本学"ファンの多い山本七平,ユング心理学の紹介者・解説者として絶大な影響力を持った秋山さと子らとなる。
第3話:社会のデザイン
1:こころ(精神的ベースとしての宗教)
日本の社会の形成は,大陸からの仏教伝来によって登場した僧によって始まり,日本独自の教祖の輩出によって展開,いわゆる教団ができる以前に,民衆教化と社会事業に全力を投入,遺言により初の火葬となり,宇治橋造橋伝説もある道昭,知識集団組織して民衆を教導,膨大な社会土木事業を営んだ行基がいる。そして,聖武天皇・光明皇后の統治デザインによる,国民の"こころのシンボル"ともいうべき東大寺大仏造立には,その宗教的中核となり,開眼の後,初代東大寺別当に任ぜられ,開山になった良弁がいて,それに,協力した行基は,初の大僧正になる。その後も引き続いて,東大寺造営に生涯を賭けた技術官僚佐伯今毛人がいたこと,天皇・皇后が,藤原不比等のところで述べたように,道慈のモデルプランに基づいて,全国に国分寺建設を進めていったことなどで,聖徳太子以来の仏教立国が目に見える形になり,仏教は,人々の"こころ"を支える基盤になったのである。
これらの,いわゆる宗派・教団以前の僧たちは別にして,平安時代に,日本独自の仏教の端緒となる,真言宗を開いた空海と天台宗を開いた最澄以降,浄土宗の法然,臨済宗の栄西,曹洞宗の道元,浄土真宗の親鸞,日蓮宗の日蓮というように,いわゆる開祖となる僧が次々と登場するが,これら偉大な僧たちは,デザイナのレベルを超える存在であり,いわゆる宗派・教団として定着させた人たちこそがデザイナであったといえる。まず,真言宗を開いた空海は,文化,教育,社会事業まで実績を残した万能の天才で,伝説化し,マンダラを代表に,デザインの神様のような存在で,直接的に,弘法大師を敬う人たちは極めて多いが,真済や真雅が,東寺教団として定着させた宗派の信徒数は,現在,150万人弱。宗派としての広がりというデザインからみれば,権力者の宗教としては,天台宗と臨済宗が,いわゆる,民衆の宗教としては,真宗と日蓮宗が抜きんでていると言えよう。
空海と,ほとんど同時期に,最澄が開いた天台宗は,最澄を継いで天台宗を興隆,山門派の祖となり,藤原良房と伴善男両者から信奉された円仁と,天台宗を円仁に続いて興隆させ,園城寺を復興して,寺門派の宗祖となった円珍によって教団として定着し,公家を支える宗教になったばかりでなく,その後の僧のほとんどが,まず,比叡山で修行し始めるなど,現在に至る日本仏教の変遷の原点になるのである。70過ぎて家康に招かれ,100を超える長命で,江戸幕府創始期に幕府の宗教行政の中心になった天海は,天台僧であった。近年の,信徒数は,150万人余で,真言宗と変わらず,民衆のものにはなっていないことが分かる。
日本独自の仏教である念仏の祖空也は,教団形成に至らずとも,その伝承は,僧以外にも大きな影響を与え,慶滋保胤が,日本初の往生伝「日本往生極楽記」を著し,浄土思想を普及,源信が,「往生要集」を撰述し,公家社会の末法思想に対応する地獄極楽イメージ鮮明な仏教を創始,それに対応するように,専修念仏に開眼し,大変革期に続々登場する新宗派の開祖の嚆矢になった浄土宗の開祖法然が登場するも,なお公家社会に対応するもだったため,鎌倉幕府以降の武家政権下では,いわば底流のように目立たなくなってしまうが,現在でも,信徒数が600万人余りと2番目に多い宗派で,近代に入って,忽然と登場したのが,桁違いの頭脳と言われた渡辺海旭で,浄土宗初の留学生となり,社会事業はじめ,「大正新修大蔵経」刊行など膨大な業績を遺した。
法然の弟子,浄土真宗の開祖親鸞は,「教行信証」を著し,"悪人正機説"などで仏教を根本的に変革,自ら教団形成して,真に民衆のものとし,没後にも,浄土真宗の3代(法然・親驚・如信)伝持を主張,本願寺を創建し,真宗教団の基礎を確立した覚如,本願寺教団の再興して大発展の基礎をつくった中興の英主蓮如ら,優れた教団デザイナを輩出して,農民層に浸透,近代に入っても,廃仏毀釈に抵抗,国民教化政策を瓦解させ信教の自由を獲得,海外伝道や監獄教誨にも尽力した島地黙雷,廃仏毀釈に立ち向かうべく改革に取組み,教団を再確立した赤松連城,親鸞の精神を説き,本郷に求道学舎と求道会館を建設,学生・知識人を感化した近角常観ら,すぐれた僧を輩出して拡大,最近の信徒数ランキングでも,1位が本願寺派,2位が大谷派で,それぞれ,750万人前後になっている。
武家対応とされる禅宗(臨済宗)の祖は,武家社会に対応する新たな仏教禅宗(臨済宗)を将来・確立,後の茶道拓く茶の栽培利用を啓蒙した栄西で,栄西自身が源実朝に取り入り,鎌倉幕府も,天台宗はじめ,公家仏教と対抗すべく,武家を支える宗教として採用,執権北条時頼の統治デザインで,本格的に入替を進めて,国家の宗教に位置付けられ,足利義満が,統治の方策として,京都五山,鎌倉五山として,確立した。そして,中世の間だけでも,真言密教と禅を融合し,念仏とも未分化ながら,栄西を継いで,日本への禅導入を促した退耕行勇,東福寺の開山で,公武の帰依者多く日本初の国師号,静岡茶の祖でもある円爾弁円,東福寺三世で南禅寺開山の無関普門,大宰府の崇徳寺に定住して活動し,現代臨済宗の源流となった南浦紹明,公武の間に多数の支持者を得,七代の天皇から国師号,日本禅宗の主流になった夢窓疎石,日本最初の仏教通史「元亨釈書」を著わし,五山文学の先駆者で,かつ主流のもとになった虎関師錬,大徳寺を開創し,夢窓国師の禅風を厳しく批判した宗峰妙超,夢窓疎石の甥で,初代の僧録事,政界にも大きな影響力をもち,五山文芸にも優れ,中国にまで名声が及んだ春屋妙葩,学徳当代一で尊崇を集め,中国人が自国人の作と思ったほどの詩作者だった義堂周信,五山文学で周信と双璧,足利義満のブレーンとなり,五山を統轄,公武の帰依を受けた絶海中津,政治力に優れて足利義教・義政に重用され,日本初の外交史書「善隣国宝記」を撰した五山文学僧瑞渓周鳳,東山文化の芸術家らの指導者で,ユニークな生涯で"風狂"と"頓智小僧"のイメージが定着した一休宗純,今川義元の兵法参謀となり,大名間の和議斡旋に尽力,今川文化を育む役割もした太原崇孚と,名僧を輩出,近世には,足利学校を中興し,家康の命で出版事業"円光寺版"を遺した閑室元佶,最初の日本式の禅寺はじめ多くの寺を開創,難解な禅を庶民に理解できる禅へ脱皮させた盤珪永琢,名利求めず,衆生済度のために東奔西走,独自の公案体系確立し,臨済宗中興の祖となった白隠慧鶴,そして,近代に入ってもなお,儒学から禅門に入り,維新後,鎌倉禅を盛大に導く基礎を開き,"円覚寺中興の祖"となった今北洪川,国際的に行動し,多くの門人の生き方に影響を及ぼした釈宗演,その門人で,英米と深い関係を築き,仏教や禅思想を広く世界に紹介,内外の学者から尊敬された鈴木大拙と名僧の輩出は続くものの,なお,支配層の仏教の主流であって,民衆には浸透しておらず,信徒数ランキングに登場しない。
それに対して,同じ禅宗でも,坐禅を中心とする厳しい修行生活の拠点{永平寺}を開いた道元の曹洞宗は,個人の救済,修行であって,曹洞宗を初めて民衆化し地方に展開し,能登総持寺開祖になった瑩山紹瑾などにより,現在でも,信徒数360万人余りと,4位につけている。
幕府に「立正安国論」提示,受難の生涯の中,法華信仰を確立した日蓮に始まり,教祖の名がそもまま宗派の名になっている日蓮宗は,日蓮滅後の混乱した法華経の教えを糺すべく献身,京都本能寺を創建して,日蓮宗の教勢を拡大した日隆,迫害受けて"なべかむり日親"になるも,大赦後,本法寺復興,京都に日蓮宗の教勢を一気に拡大した日親が示すように,町人対応の宗教となり,国家権力と対抗するというより,宗教による支配を意識して,さまざまな派に分裂,近世以降の都市化とともに,その時々の新興宗教として発展する。明治維新時の,今日の日蓮宗の基礎をつくった新井日薩により,現在の日蓮宗本体での信徒数は,350万人弱で,曹洞宗に次いでいるが,近代に入っても分裂する体質はなお続いて,{立正安国会}{国柱会}を起こし,法華経に基く体系的教学で,宮沢賢治はじめ,多分野の人材に影響をおよぼした田中智学,「人生地理学」で名をなした後,日蓮宗に入信,弟子の戸田城聖とともに創価学会を創立した牧口常三郎が,戦時弾圧で獄死,戦後,再建して大教団にした戸田城聖は,政教分離の新憲法を誤魔化すように,公明党をつくって,政界に進出,近年には,与党になるに至り,信徒数も公称800万世帯を超えるという。一方,満州事変の頃,小谷喜美らが,法華信仰から起こした霊友会を,長沼妙佼とともに脱会し,日中戦争開始時に,{立正佼成会}を開いた庭野日敬は,戦後の妙佼死去後,大教団にするとともに,諸宗教間の対話や世界平和運動の先頭に立って活動,庭野の死去後は,表立った活動は見られなくなるものの,信徒数はなお,200万人を超えている。
ところで,日本独自の仏教である念仏を唱えるも,教団形成に至らなかった空也の後を継ぐように,鎌倉時代に,寺を持たず,生涯踊念仏によって布教行脚をした一遍が開いたとされる時宗は,一遍の最初の弟子の他阿が,一遍の死後に,確立発展させた事実上の開祖で,以上の宗派から外れた下層民対応のものとなり,世阿弥,善阿弥,本阿弥等々,姓に阿弥のつく人物は,時宗の信徒であることを示すとともに,他阿は,一遍を超える尊称になっているという。
仏教以外の宗教についても触れておくと,まず,神道について,文化庁の発表している人口,信者というより帰属,おそらく氏子数は,8,790万人と仏教のそれ,おそらく檀家数8,390万人をわずかに上回っていることに,やはりというか,驚きでもある。日本神話,神社体系等,そのスタートからデザインされたものと言われる神道でもあるが,歴史時代に入ってからは,仏教,儒教の広がりに対抗して,神儒仏混合の唯一神道を創始し,地方の神社に神位,神職に位階を授与する制度を創設した吉田兼倶こそが,最大のデザイナと言え,儒教の伸張を受けて,伊勢神道を神儒合一的に革新し,近世化に大きな役割を果たした出口延佳,神道を,儒仏に対抗する,国家経世の学として普及することを意図し,吉川神道を開いた吉川惟足,国学四大人の後を受け,日本中心思想の学風を樹立して,明治初頭の神祇行政の礎になった大国隆正,維新に際し,出直しを図り,古儀を尊重して復興整備に努め,国家神道の確立に貢献した御巫清直など,皆デザイナ的であり,そもそも戦死者を祀るという招魂社を構想した萩八幡宮司で,明治維新に際し,招魂社を建てるも暗殺された大村益次郎を継いで,靖国神社初代宮司になった青山清も,現在もなお靖国神社が不可侵のようになっていることから,恐るべきデザイナであったといえよう。
織豊時代のキリシタン,つまりカトリックはさておき,近代に入っての,プロテスタントのキリスト教信者の為した活動には瞠目すべきものがあるが,信者数は60万人どまりで,なお50万人いるカトリックとあわせても,110万人と少ない。キリスト教そのものについて,日本人をリード,神学的傑作と無教会主義を生み,多くの人材輩出した内村鑑三は,もともと,土木建築的指向もあったこととあわせて,デザイナであったといえる。
最後に,宗教と言うには無理かもしれないが,近世において,町人のための思想を確立し,その普及・実践に献身,社会教育やボランティアを先駆した石田梅岩の心学は,その後の影響からみて,大きいものであった。
2:くらし(健康で文化的な生活のための民生)
いわゆる大衆社会の始まる近世において初めて,国策としての民生が意識されるようになり,近代を準備した。<享保の改革>を推進して幕藩体制を再構築した将軍徳川吉宗は,庶民娯楽を展開するほど,民生を重視,大岡忠相を町奉行に抜擢して具体化,忠相は,公平な裁判と優れた市政で,異例の出世,大名にまでなるが,彼によって発掘された多くの人材,川崎宿の疲弊を救い,「民間省要」で幕府徴用,治水通船で地域振興し,支配勘定格に至った田中丘隅などもいたことも忘れてはならない。
中世の終りに,すでにもっとも必要とされた医療においては,中国の金元時代に興った李朱医学を初めて日本に導入し,近世医学興隆の祖になった田代三喜が登場,田代に学んだ曲直瀬道三は,足利義輝以降,公武のトップ次々診察,医学校を開き,日本医学中興の祖となっていたが,吉宗時代に入ると,初めて産鉤を使用して母体を救い,正常胎位の発見,「産論」の刊行で大きな貢献をした賀川玄悦,人体解剖への抵抗が強い中,日本初の医学的解剖を行い,「蔵志」刊行して,実証的医学の契機になった山脇東洋,偏見を排し,名著多数の一方,長府藩製糖業も創始した永富独嘯庵,その示唆を受け,内服全身麻酔剤を案出し,世界に先駆けて全身麻酔手術に成功,華岡流外科創始者となった華岡青洲と名医が続出,佐倉に{順天堂}を開設し,診療とともに子弟教育した佐藤泰然によって,維新後すぐに,わが国初の私立病院が出現するに至るのである。
福祉面においては,元禄時代に,盲人の杉山和一(検校)が,管鍼術で治療範囲を飛躍させるとともに,開塾して広め,鍼術で唯一人神社になっておおり,まさに,視覚障害者教育のパイオニアであったが,その他は,幕末になってようやく,家業を盛り返すと,日本初の民営の窮民救済基金{感恩講}を構築した那波祐生,飢饉へ対処すべく諸マニュアルを執筆・頒布,後半生を全て救済活動に賭けた熊谷蓮心など,近代に続く人物が登場する。
古くからある教育面においても,近世になると,栄利求めず塾で教育に努め,朝鮮通信使の高評価で幕府儒官となり,新井白石ら逸材輩出した木下順庵,{懐徳堂}の黄金期を形成し,松平定信諮問に超合理的経世論「草茅危言」献上した中井竹山,豊後国日田で{咸宜園}開き,卓越した精神と近代的教育で,全国から多くの俊才を集めた広瀬淡窓,そして,{松下村塾}より早く{適塾}を開き,維新に活躍する多くの人材を育てた緒方洪庵に至る,教育そのものを本業とする人物が輩出する。
近代に入って,明治維新の新政府においても,医学行政官として,ドイツ医学の採用決定に貢献をするも,不遇の晩年となった相良知安,近代医療や衛生を先導し,女子の医者への進出を支援するなど,時代に先駆けた長与専斎,唱歌・体操・教科書・教育学など文部行政で先駆者となる一方,余生を吃音矯正に捧げた伊沢修二,帝国図書館設立を実現,その発展と館員育成に奮闘するも,更迭された"日本の図書館の父"田中稲城,長く東京美術学校長をつとめ,文展の創設はじめ,美術行政教育を長期に主導した正木直彦など,優れた民生官僚が輩出するが,その多くは,大久保利通の人材発掘によっている。民間においても,一貫して人民主権を説き,部落解放論,癌宣告などにも著しい先進性を示した中江兆民という優れた啓蒙者を得,いわゆる自由民権運動を経て,"民本主義"を唱えた吉野作造らによって,<大正デモクラシー>を迎え,大衆文化が開花するが,その頃には,政府の方でも,長く文部行政を主導し,多くの制度改革を実現した岡田良平,官僚として文部行政の中枢的位置を占めた澤柳政太郎が,退官後,成城小学校を中心に新教育運動を指導したりしている。以下,近代に入って飛躍した,民間における社会活動についてみていくこととする。
まず,医療型では,戊辰戦争の箱館で敵味方無く治療して日本赤十字を,貧民救療で民間福祉を先駆した高松凌雲,<西南戦争>で戦傷者を官賊の別無く救療する{博愛社}創設し{日本赤十字社}になった佐野常民,維新直後に陸軍軍医制度を確立し,引退後,大磯に日本初の海水浴場を開いた松本良順,私財を投じて明治薬学専門学校ほか2校を創立,医学用語を統一した画期的辞典も刊行した恩田重信,明治天皇詔に触発され,医療の社会化の実践を先駆し,医業国営論を提唱した鈴木梅四郎,日本の精神医学を開拓し,多くの近代精神医学者を育てた呉秀三,その教えを受け,精神病院に新風もたらし,神経症に行動中心の"森田療法"を開発,多くの信奉者を得た森田正馬,わが国最初の女医養成機関(後の東京女子医大)を創立,女性の教養と地位の向上につとめた吉岡弥生,梅毒特効薬で世界初の抗生物質サルバルサンを開発,多くの患者を救い,医に生涯をかけた秦佐八郎,石原式色盲検査表はじめ,色盲研究に多大の貢献をした石原忍,"オギノ式避妊法"を開発して世界に貢献し,子宮癌にも独自の手術法を考案した荻野久作,日本の植民地下の台湾人で,独自の思想「真・善・美」による杏林大学・病院を創立した松田進勇らがいる。
福祉型では,それぞれのハンディを,それぞれに根本的に支える方策などをデザインした人物として,キリスト教出版事業で獄中体験,出獄人保護運動に努め,"わが国免囚保護事業の父"になった原胤昭と,監獄改良に取り組み,制度廃止後も家庭学校で非行少年の感化に務め続けた留岡幸助,日本の監獄学の草分けで権威となり,退官して事業を推進,現在の民生委員制度の原型もつくった小河滋次郎,日本点字の父石川倉次と,視力障害を契機に,点字楽譜の祖となり,回復後は,家業の医師として名を成した佐藤国蔵,最初の日本人キリスト教社会事業家で,孤児院を創始し,"近代社会事業の父"といわれる石井十次,精神薄弱児問題に生涯を捧げ,収容施設を創始し,教育を開拓した石井亮一,大阪府知事になるや,方面委員規程を公布,全国統一の制度となり,現在の民生委員制度につなげた林市蔵,晩年になって,障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会を結成し,次々と成果を挙げた矢島せい子,自閉症児は治癒不可能という世界的学説を覆し,"生活療法"を唱えて実践した北原キヨらがいる。
教育型では,幕末に蘭学塾を開き,<維新>で海軍操練所の教師に招聘され,異色の{攻玉社}を始めた近藤真琴,幕臣として<戊辰戦争>に敗れた士族子弟救済に尽力,キリスト者として青年教育に生涯をかけた江原素六,アメリカで信者となって維新後に帰国,{同志社}と日本組合教会の基礎を確立した新島襄,大隈重信を支えて東京専門学校時から中核となり,日本有数の私学に築き上げるまで,生涯をかけた高田早苗と,ともに発展させ,早稲田実業を創立した天野為之,7つにして最初の派遣女子留学生,女子教育に目覚めて奔走し,女子英学塾を創設した津田梅子,官僚として文部行政の中枢的位置を占めた後,成城小学校を中心に新教育運動を指導した澤柳政太郎,独学で,児童心理学研究草分けとなり,全人教育に生涯をかけ,感銘を与え続けた高島平三郎,理論・実践両面から,児童教育・新教育運動をリードし,"日本のペスタロッチ"と言われる野口援太郎,言文一致の唱歌を創始し,その普及に生涯をかけ,童謡流行の先駆になった田村虎蔵,婦人記者の先駆,夫と{婦人之友}発刊後,キリスト教に基く{自由学園}創設した羽仁もと子,最初の受験参考書がヒット,{考え方研究社}を興して多数著作刊行し,受験屋として有名になった藤森良蔵,全人教育を唱えて成城学園町を開発後,理念実現に向けて玉川学園を創設し,長期に実践した小原国芳,洋裁学校と洋裁店を開設し,長期にわたって,服飾デザイン界を主導した山脇敏子,日本初のOLとなった後,{ドレスメーカー女学院}を創設,服飾デザインの発展に生涯をかけた杉野芳子,独自の才能教育"スズキ・メソッド"を開発,世界に普及し,奏者を輩出した鈴木鎮一,早くから栄養問題を啓蒙,<敗戦>後,基礎食品群を提唱,長寿社会化への道を開いた香川綾,{東海大学}を創立してマンモス大学へ発展させ,国際的に幅広く活動した松前重義,<敗戦>直後に{子供のための音楽教室}を開設,小澤征爾ら逸材を輩出した斎藤秀雄,教師こそが初等教育の原点と,教組と国との間に立って,全国的な模範となる実践活動をした斎藤喜博,女性の生涯学習から始め,全ての人間に広げた場{東京コミュニティカレッジ}を設立した小泉多希子らがいる。
そして,近代に入って一気に広がった解放型では,まず,部落解放について,維新直後に穢多非人廃止を訴え,晩年は未解放部落の融和事業に専念した大江卓,差別撤廃運動をするうち,政策転換した政府に登用され,融和事業を推進した三好伊平次,{水平社}名考案し創立大会開催。戦時下の国家社会主義も,戦後は部落解放同盟リードした阪本清一郎,次に農民,労働者解放で,{日本農民組合}を創設して以後,農民関連組織の先頭に立って政治活動を続けた杉山元治郎,日本初の近代的労働組合を組織し,生活協同組合も先駆した高野房太郎,{友愛会}を創立,ILO創設にも参画して急発展させ,労働運動右派の大御所として君臨した鈴木文治,{友愛会}を日本労働総同盟とし会長,日本国憲法下初代衆議院議長になった松岡駒吉,さらに,女性解放で,廃娼運動に生涯,少額寄付の大衆参加策を次々と発案し,キリスト者として人生を全うした久布白落実,{青踏}発刊,女権宣言して端緒を開き,戦後,日本婦人団体連合会初代会長になった平塚らいてう,婦人参政権運動一筋に生き,戦後は理想選挙を唱えて参議院議員となり,圧倒的な支持を得た市川房枝,大正期に婦人セツルメント運動始め,<敗戦>後に{主婦連}創立,消費者運動の草分けになった奥むめお,そして,占領からの解放で,沖縄復帰運動に尽力し,初の公選で琉球政府主席,復帰後初の沖縄県知事となった屋良朝苗らがいるが,現在もなお,女性解放は途上にあり,あらたに,障害者差別からの解放,いわゆるLGBTと,差別問題は尽きない。
3:なりわい(生きるための殖産・経済・実業)
最後になったが,本論における"活動"に,直接関わる度合いの高いものとして,生きるための経済・殖産・実業を取り上げる。
古代から,国庫の収入源は農業であったが,それを含めて,殖産・経済が国策として取り上げられるのは,六角定頼を初見として,戦国武将の多くが始めた楽市を,織田信長が,統治のデザインの一つ,楽市・楽座令として確立したこと,また,豊臣秀吉の検地は,農業からの収入増と一体であったことから,まさに,近世の始まりを告げるものになった。徳川政権初期の,財政基盤の確立し,地方巧者として,以後の手本となった伊奈忠次に始まり,筑後川堤防築造で三方潟開発の大事業を実現したのを始め,業績多数で,"治水の神様"になった成富兵庫,川崎宿の疲弊を救い,「民間省要」で幕府徴用,治水通船で地域振興し,支配勘定格に至った田中丘隅,一揆で大庄屋から流浪の身,30年放浪の後,高崎藩に抱えられ,江戸時代で最も優れた「地方凡例録」を著した大石久敬,藩主上杉鷹山の施策を実質的に推進,サバイバル書「かてもの」ほか膨大な著作を成した莅戸太華,幕末の,幕府きっての切れ者でフランスとの交渉にあたり,多くの偉業をなしたが新政府軍斬刑になった小栗忠順と,幕藩それぞれに,優れた殖産技術型官僚がいた。
民間でも,私財投じて開墾後,貝原益軒の影響受け,生涯をかけて日本初の体系的農書「農業全書」を著した宮崎安貞,日本で最も早く書かれ,また寒冷地における優れた農業技術書「会津農書」を著した佐瀬与次右衛門,村起こしのために独自の農業技術史論「百姓稼穡元」はじめ,多くの著作を成した石田春律,江戸中期に合理的農業技術に関する多くの著作を成し,明治維新後に大きく評価された大蔵永常,広大な荒地の白糸台地を灌漑する通潤橋を企画・実現し,没後,神社に祭られた布田保之助,農協の先駆となる世界初の産業組合で農村振興したが,革命恐れる幕政の犠牲になった大原幽学,そして,没落実家を自力再興後,農村を企業的組織とする"報徳仕法"で諸藩の農村復興した二宮尊徳と,その門弟で「報徳記」を著わし,報徳社運動の指導者の一人になった富田高慶,同じく,門下で,報徳運動を指導,箱根湯本で福住旅館を再興し,一帯の観光事業を推進した福住正兄らがいる。
明治維新後の近代に入っても,幕末きっての財政通で,藩の殖産政策・新政府の金融政策に関与,「五ヵ条の誓文」原案も起草した由利公正,郵便制度の創始・電話事業の開始・国字改良など,維新直後のメディア近代化に決定的役割をした前島密,維新政府の天才の一人で,日本銀行を創設,"松方財政"で,資本主義社会の基礎を築いた松方正義,工部省・工学校を創設し"日本の工学の父"。霞が関官庁街の計画者で,訓盲院も開校した山尾庸三,駒場農学校・大日本農会・山林会・水産会・博物館の創設など,産業振興の基礎をつくった田中芳男,日本最初の博物館を創設し,博覧会事業に治績をあげた町田久成,日本初の鉄道建設に従事し,機関車の国産化のため会社を設立,"鉄道の父"になった井上勝,大日本水産会創設し,水産伝習所初代所長となり,わが国近代漁業を創始,洋上捕鯨にも先鞭をつけた関沢明清,東京工業学校を創設して校長となり,工業教育の最高指導者となった手島精一,産業近代化の指針を次々建言するも罷免,以後,民間で奮闘するも不遇の前田正名,日本の近代鉄鋼技術を確立し,鉄冶金学の発展につくした野呂景義,工科大学初代学長・工学博士第1号で,退官後も,土木行政・工学を全面的に指導した古市公威,現在のいちごのルーツなど,日本の園芸界の基礎を築き,新宿御苑改修で造園学の祖にもなった福羽逸人,日本の近代漁業振興の最大の指導者伊谷以知二郎,八幡製鉄の創業を担い,日本鋼管を創立するなど,"近代産業の父"今泉嘉一郎,パナマ運河開削に唯一の日本人技術者,荒川放水路などの大事業,技術者のモラルも示した青山士,戦時体制下,{理化学研究所}所長を務め,理研コンツェルンを形成して,人材を輩出した大河内正敏,満鉄調査部で中国の鉄道を指導,<敗戦>後は,新幹線実現の中心人物となった十河信二と,戦時下に名機D51を設計,"新幹線"を構想し,<敗戦>後,十河総裁のもとで実現させた島秀雄というように,その後の時代をデザインした殖産技術型官僚は多い。
そのまま,社会分野の殖産型につながり,郡山の豪商で,安積開墾の中條政恒を援け,開成社を組織し,近代郡山の基礎をつくった阿部貞行,天竜川治水,磐田植林,三方原開墾,出獄人保護など,社会のために一生を捧げた金原明善,維新直後に横浜の基盤整備事業をして高島町に名を遺し,"高島易断"の開祖にもなった高島嘉右衛門,7つの娘梅子を留学生に出すほど開明的で,欧米農業の導入紹介に努め,禁酒・禁煙・盲唖運動もした津田仙,明治時代における報徳運動の最高指導者で,俊秀輩出,日本最初の信用組合の創設者岡田良一郎,明治中期の老農。農村計画やイネの品種はじめ精緻かつ膨大な書を著し,全国遊説もした石川理紀之助,父の後を継ぎ,新時代に対応すべく試行錯誤,三河農会を結成し,地域農業と金融界に貢献した古橋義真,ピューリタンのユートピア建設と類似した精神で,{赤心社}による北海道農場開拓事業に邁進した澤茂吉,十和田湖ヒメマス生みの親で,十和田湖観光開発の基礎をつくった和井内貞行,'稲のことは稲に聞け,農業のことは農民に聞け'という言葉で有名な横井時敬,石原莞爾のブレーンとして国家統制経済をめざし,戦後の"日本株式会社"の礎となった宮崎正義,農民教育を推進,"日本のデンマーク"愛知県安城の礎を創り,自由な生き方で多面的貢献をした山崎延吉,多数の組織の長務め,"産業組合の独裁王"と称せられるに至った千石興太郎,農政記者でスタート,{家の光}を成功に導き,農山漁村文化協会を創立してユニークな活動をした古瀬伝蔵,農事試験場で水稲新品種を次々開発,多数の小唄等を作詞作曲し,全国的展開を図った岩槻信治,戦後,農山漁村文化協会を率い,独自の文化運動を展開した岩渕直助らがいる。
さらに,国策・民間のいずれとも言えない,国につながる民という形で,初の実業といえる豪商が登場するのも,織豊時代からで,徳川時代には,維新後の財閥,さらには現代につながる財閥系の企業が誕生していることからも,実業面で,近世は,近代を準備,それ以上に,欧米の資本主義さえ,先取りしていたと言えるのである。織豊に接近して豪商の先駆けとなり,博多の都市計画や朝鮮との交渉に関わった島井宗室を皮切りに,博多復興し諸産業振興して"博多三傑"も失意の晩年,茶の湯研究史料「宗湛日記」を遺した神屋宗湛,武士・商人として,早くから家康を支え,その天下取りに貢献した茶屋四郎次郎(初代・清延)という初期の豪商を経て,2代将軍秀忠時代には,銅吹き屋の集まる京都で,吹屋{泉屋}を開業し,住友銅業の業祖とされる蘇我理右衛門が,3代将軍家光時代には,醸造業で出発し,大名貸,海運業まで展開,鴻池の祖になった山中新六,4代将軍家綱時代には,革新的商法を創始,多くの子に恵まれ,商売の各分野を担当させ,財閥三井家の家祖になった三井高利が登場し,幕末維新の動乱期に,無学文盲も才覚で{三井}番頭になり,大財閥への基礎築き,日本経済近代化に貢献した三野村利左衛門と,住友家を存亡の危機から救い,住友財閥と大阪経済発展の基礎をつくった広瀬宰平という人物が出た三井・住友は,敗戦の財閥解体も乗り越えて,現在に至っているのである。そして,維新後に,維新直後に政府と手を結んで海運業を独占,巨利を得て,三井とも壮絶な抗争をして早世した岩崎弥太郎は,弟岩崎弥之助,子岩崎久弥という良き後継を得て,三菱財閥の祖になったのである。
また,江戸幕府創設期には,豪商吉田家の分家だった角倉了以が,自らの意志で,安南貿易による巨富を河川開発につぎ込んで大きな貢献をし,明暦の大火で巨利を得た河村瑞賢が,陸奥と間の東西廻り航路開拓ほかに尽力,遂に士族に至ったように,国土開発企業のルーツも近世に始まり,幕末維新期には,諸河川を開削して通船事業を支配,初期薩長交易を主導し,志士を強く支援した中野半左衛門(景郷)や,横浜開港を機に西欧建築の様式を吸収,傑作を遺して,{清水建設}の祖となった清水喜助(2代),三都定飛脚問屋の当主だったが,維新で,官営郵便の創業で打撃を受け,陸運会社に転換して成功した吉村甚兵衛といった人物も登場する。
維新後には,欧米と対抗すべく近代化を図る国策に呼応して,西南戦争で巨利挙げ{藤田組}創始し,大阪財界主導した藤田伝三郎,コークスという当時廃棄物でコストゼロの資源に着目,セメント工業を興し浅野財閥になった浅野総一郎,三大遠洋航路開設などで{日本郵船}を世界最大級に発展させ,日本企業の海外進出の航路を確立した近藤廉平,地方政界から中央に出,東武鉄道再建し"鉄道王"になった根津嘉一郎,日本鋼管を創立し経営,日本製鉄への合同拒否し,民営製鉄業リーダーになった白石元治郎,福沢諭吉の婿養子で,相場師で財をなし,様々な仕事に熱中しながらも余裕失わず,近代日本の電気産業の基礎をつくった福沢桃介,"電力王"になるも戦時の国家管理に反対退去,戦後に九電力体制発足させ"電力の鬼"になった松永安左ヱ門,官僚から転じて,"電鉄王"になり,土地開発から東急コンツェルンを構築,教育にも貢献した五島慶太,早くから石油販売,<敗戦>後,国際石油資本・政府・GHQと闘い,文化事業にも貢献した出光佐三,箱根開発で五島慶太と死闘,{西武グループ}を創り上げた堤康次郎,海外油田の開発などで活躍し,戦前は"満洲太郎",戦後は"アラビア太郎"の愛称を得た山下太郎など,錚錚たる人物を輩出するのである。
製造業への橋渡しとなる発明技術については,近世末に,新式の帆や運送船を開発,築港にも従事,海運の振興に貢献し,諸大名に知られた工楽松右衛門,独創に富み,オランダ銃もとにした気砲など,次々と発明して人々を驚嘆させた国友藤兵衛,実業にも役立つ多くの機械や装置を開発し,塩田開拓などで藩財政改革にも功績を遺した久米通賢と,実用に供する発明をする人物が続々登場,極めつけは,幼時より次々と発明,世界に優る万年時計に至って,天才的技術者と言われ,維新後には企業化して,{東芝}の祖になった田中久重で,まさに,技術立国日本を象徴する人物であった。その後も,廃仏毀釈で失職し転換,理化学機器を発明して{島津製作所}を興した島津源蔵(初代)と,後を継ぎ,発明や製品化の才能で,大企業に発展させた島津源蔵(2代),{日本楽器製造(ヤマハ)}を創業,ピアノの国産化に成功し,大発展の基礎をつくった山葉寅楠,わが国電気工学界初期の指導者で,{東芝}ルーツの片方{東京電気}を創業し,"日本のエジソン"といわれる藤岡市助,自動織機の発明改良に生涯をかけ,{豊田紡織}設立,大自動車会社{トヨタ}の祖となった豊田佐吉,{立石電機(オムロン)}創業し,オートメーション・システム機械で,世界的企業にした立石一真といった,発明家で企業家といった人物の一方で,日本初の電気雑誌{電気之友}を創刊し,開発・啓蒙に努め,電話掛け言葉'もしもし'も発案した加藤木重教,日本初の本格的バイオリン"スズキバイオリン"が世界的になった鈴木政吉,「服部時計店」など銀座の風景に貢献し,職工問題や新工法に挑戦し続けた建築家伊藤為吉,わずか5分の遅刻で受験できず電気時計を発明,動力源として,世界に先駆け乾電池を発明した屋井先蔵,"八木アンテナ"を発明するも無視されるが,イギリス軍の戦利品から,一躍に世界的評価を得た八木秀次,写真電送法を発明し世界的に普及させた丹羽保次郎,自動車安全のエアバッグを世界に先駆けて発明するも,冷笑され,負債抱えて無理心中した小堀保三郎,戦時下にブラウン管や受像回路を発明,テレビ放送の基礎築くも<敗戦>で評価が遅れた高柳健次郎,旧制中学の時に多極真空管を発明し,日本のエレクトロニクスを開拓した天才的技術者安藤博というように,企業化せずとも,世界的な発明をした人物にはことかかない。
どちらかと言えば,発明よりも企業化の方が優先している人物として,実業分野の製品生産型をみると,開港で巨利を得,維新政府から委嘱され,三菱に対抗する造船所のちの{川崎重工業}を創設した川崎正蔵,{森村組}創設し,{ノリタケ}{東洋陶器}{日本碍子}に至る一流窯業企業群のルーツになった森村市左衛門,前田正名の言葉に触発され,{郡是製糸(グンゼ)}を設立し発展させた波多野鶴吉,時計国産化を先駆,{服部時計店}を設立し,飛躍を重ねて,"東洋の時計王"に至った服部金太郎,日本の鉄骨建築を先駆して震災復興に貢献,横河グループ創業者になった横河民輔,水道管製造から始め,産業機械等総合メーカーとなる礎までつくった{クボタ}の創業者久保田権四郎,工業振興のリーダー足らんと大志,久原房之助に出会って,日立製作所の礎をつくるに至った小平浪平,わが国自動車工業のパイオニアで,小型車の代名詞"ダットサン"とタクシーが登場する契機になった橋本増治郎,日本初の民間飛行機製作所設立して大軍需会社にし,戦時体制下は政治家として活動した中島知久平,家業を発展させるべくゴム業界に進出,{ブリヂストン・タイヤ}を興して世界的企業にした石橋正二郎,シャープ・ペンシルで成功も大震災で出直し,{シャープ}を創業し,世界的電機メーカーにした早川徳次,町工場を総合電機メーカーに発展させ,経営哲学で<敗戦>後の復興象徴,世界的存在になった松下幸之助,{リコー}創業,戦争前後を代表する経営者で,常識の裏をかくアイディア社長として一世を風靡した市村清,<敗戦>直後に自動車会社を設立,オートバイから出発し,世界の{ホンダ}に発展させた本田宗一郎,{日本電気}を情報機器産業化して初の生え抜き社長になり,身近なものなるように努めた小林宏治,<敗戦>直後に{ソニー}を興し,盛田昭夫と共に世界企業に発展させた後,幼児教育に尽力した井深大といったところになろう。
そして,日ごろ,いわゆる消費者につながる企業,農水食品型,販売サービス型,メディア娯楽型も,大衆文化始まった近世に登場,例えば,天明期に髙津伊兵衛が創業した{にんべん}は,削り節やふりかけ,調味料など,業界最古参の水産加工品メーカーであるが,一般には,日本橋の老舗の店として知られ,化政期に,京都の呉服店の丁稚奉公から,時流に乗って古着専門のを開店した飯田新七が始めた{高島屋}は,業界としては衰えつつあるデパートにおいて,唯一,力を保っている。維新後について拾ってみると,直後の文明開化に"あんパン"を発明,大ヒットで宮内省御用達,{木村屋}の祖になった木村安兵衛,福沢諭吉に共感,維新直後に,外国書籍輸入以降幅広い事業に取組むも,挫折した{丸善}創業の早矢仕有的,牛鍋ブームに乗り,20余人の妾に次々とチェーン店を持たせて,{いろは}王国を築いた木村荘平,{三井物産}から{日本麦酒}の経営に転じ,三社合同の{大日本麦酒}設立して君臨,"ビール王"になった馬越恭平,薬事官僚になるも,医薬分業を目指して下野,{資生堂}薬局を興して化粧品産業へと展開した福原有信,国産初の両切り紙巻タバコを発売,人気銘柄次々で"日本のたばこ王"になった村井吉兵衛と,度肝抜く広告で,日本人の喫煙スタイルを紙巻タバコに一変させた岩谷松平の壮絶な争い,真珠養殖に取り組んで成功,鑑定家としても一流の折り紙,"世界の真珠王"となった御木本幸吉,,熱心なクリスチャンで,"そろばんを抱いた宗教家"といわれた,{ライオン}創業者の小林富次郎,浅草に{神谷バー},牛久にワイン醸造所{シャトーカミヤ}創設,洋酒文化を拓いた神谷伝兵衛,日本初の百貨店{三越}を創業して経営改革を進め,人々の消費行動を根本的に変革した日比翁助,様々なアイディアを次々具体化して,別府温泉を世界に知らしめた油屋熊八,"花王石鹸"の製造・販売をスタートに,宣伝工夫で発展,油脂石鹸業界に君臨した長瀬富郎,酪農を導入して,{雪印}の前身となる組合連合会にまで発展させた"北海道酪農の父"宇都宮仙太郎,{大洋漁業}を創立,<敗戦>直後の決断で,日本最大の漁業会社とする礎を築いて没した中部幾次郎,池田菊苗のグルタミン酸ソーダの特許を得,全く新しい商品"味の素"とし,大企業に発展させた鈴木三郎助,高峰譲吉のタカヂアスターゼを核に,一商人から世界的製薬企業{三共}へ発展させた塩原又策,放浪体験と信仰をもとに,日本初のドライ・クリーニングを開発し,{白洋舎}を創業した五十嵐健治,{カルピス}創業し<大正デモクラシー>象徴する"初恋の味"など,卓越したアイディアマンだった三島海雲,{サントリー}のルーツ{寿屋}を設立し,本格的国産ウィスキーの販売を始めた鳥井信治郎,{寿屋}に招かれ国産初のウィスキー製造も失敗,北海道に渡って{ニッカウヰスキー}興した竹鶴政孝,月賦販売の{丸井}を創業,<敗戦>後,若者ショッピングへと発展させ,クレジット社会に先鞭をつけた青井忠治,"アリナミン"の開発に成功し,武田薬品工業を業界トップに押し上げた(6代目)武田長兵衛,美容学校設立を皮切りに,化粧品や美容器具の販売まで多角的な経営で,山野美容帝国にした山野愛子,女性下着会社{ワコール}を興し世界的企業にした塚本幸一,日本で初めて美容を総合的に指導するチャーム・スクールを開校,その後も革新的に活動した大関早苗らを挙げておく。
最後に,いわゆる実業界において,消費者との関係が特殊な,実践分野のジャーナリスト型とも一体のメディアと,芸能分野などと一体の娯楽に関わる企業についてみてみると,前者においては,近世天明期に登場し,反骨精神をもって江戸を代表する出版業者になるも,<寛政の改革>によって失意の最期になった蔦屋重三郎,後者においては,能舞の観世座や,浄瑠璃の竹本義太夫など,演じる方が主であった人物が多数おり,歌舞伎の明治座など,特定の人物を挙げにくいものも多いので,ここでは,幕末に,人形浄瑠璃を復興させ,現代につながるその代名詞文楽座の始祖となった植村文楽軒を挙げるに止める。
元手が少なく,誰でも挑戦できることから,維新とともに,爆発的に増大した新聞については,幕臣としてフランス交渉するうち<明治維新>,即座にジャーナリストに転身し,先導的役割をした栗本鋤雲,自ら新聞を発行して開化期の風俗を面白可笑しく描き,維新直後の文学空白期を埋めた仮名垣魯文,幕末に多くの著訳を成し,<維新>に,日本人による初の新聞を発行した柳河春三らに続いて,"国民主義"の{日本}の社主・主筆として言論一筋に生き,正岡子規を世に出した陸羯南,蘇峰の{国民之友}発刊翌年,{日本人}を発刊,哲学的に幅広く発言し,学界にも影響を与えた三宅雪嶺,{国民之友}{国民新聞}で一世を風靡も,変節して戦時体制に協力,<敗戦>後文化勲章を返上した徳富蘇峰など,自らの意見を公表すべく新聞を発行したジャーナリスト型が挙げられる。
企業として確立したものは,大阪で{朝日新聞}創刊に参加,所有権を譲り受け,東京に進出して大発展の基礎をつくった村山龍平,{藤田組}支配人のまま,{毎日}経営に参画し,{朝日}に拮抗する企業として確立した本山彦一,日本初の推理小説を出版後,{万朝報}を発刊,翻案小説と暴露記事で爆発的売れる大衆紙を成立させた黒岩涙香,仙台で{河北新報}を発刊,有力地方紙として全国に知られるに至る一力健治郎,新聞への情報提供や広告掲載という点から,他に先駆けて通信と広告事業を扱う企業を着想し,後に大企業に発展する{電通}を創業した光永星郎,反権力大衆新聞{二六新報}を刊行し,<日露戦争>前夜に一世を風靡した秋山定輔,警察官僚から転身,{読売新聞}を再興し,プロ野球を始め,戦後は民間テレビ局を開設した正力松太郎らがいる。
その他,{東洋経済新報}で長く啓蒙活動,<敗戦>後に首相の座につくも,病気で潔く引退した石橋湛山,リベラリストとして,日本国家の進む方向に絶えず危険信号を送り,抵抗を続けた桐生悠々の2人が特筆される。{朝日新聞}が,現在でも特別扱いを受けているように見えるのは,徳富蘇峰・石河幹明とともに"三名主筆"と称され,作家の起用など特筆すべき足跡を残した池辺三山,{大阪朝日新聞}で,民本主義の言論を主導するも,"白虹事件"で不遇になった鳥居素川,百年先を見据えた名記者で,新聞社の体制を次々と革新した杉村楚人冠,自由主義最大の論客として発言続けたが,戦時下インサイダーに転じた長谷川如是閑ら,人材に恵まれたことも大きい。
大正デモクラシーによって,飛躍した出版に目を向けると,百科全書家で,ベストセラー「食道楽」後,食と身体の研究,生食・断食・穴居まで実践報告した村井弦斎,反骨の新聞・雑誌を次々と創刊し<大正デモクラシー>を先駆した宮武外骨,<日露戦争>以降,時流に合わせて次々と主張,直接購読雑誌は戦後まで愛読者のいる茅原華山,論壇を指導し,{中央公論}を権威ある総合誌に育て上げたが,病気で早世した滝田樗陰らの役割は大きいが,浮世絵の保存・研究及び普及と新版画の創製出版に尽くした最後の版元渡邊庄三郎の存在も忘れてはならない。
新聞同様,企業として確立した人物に注目すると,50過ぎて{博文館}設立するや次々世間を驚かし,{太陽}創刊{当用日記}発行など挑戦続けた大橋佐平を皮切りに,自著出版のため{平凡社}を創設し「大百科事典」を刊行。時代に対応して活動した下中弥三郎,{講談社}を創業して次々と雑誌を刊行し,新聞・レコードも擁する一大マスコミ王国に野間清治,{岩波書店}創業,定価販売や造本・校正などで信頼,文庫・新書など生み出版界リードした岩波茂雄,{改造社}を設立,世界の一流人招待,円本ブーム等時代を先駆も,孤高のため一代で終った山本実彦,戯曲作品で成功後,{文芸春秋社}を開業し,創設した{芥川賞}{直木賞}が,作家の登竜門になった菊池寛,書物の美へのこだわりが"第一書房文化"と讃えられ,"出版一代論"唱えて廃業した長谷川巳之吉らがいる。
戦後には,<敗戦>によって{電通}社長になると,世界的な広告会社へ発展させ,日本の広告界の確立にも尽力吉田秀雄,敗戦後再出発した{文芸春秋}で,名企画を次々と打ち出し,国民雑誌に育て上げた池島信平,週刊誌の嚆矢{週刊新潮}以降,戦後ジャーナリズムを主導,黒子に徹して新潮社"天皇"になった斎藤十一,戦後の{中央公論社}の企画をリードした永倉あい子らによって,それぞれ再活性された。なお,戦前「人物評論」で挫折,復興後,「無思想人宣言」を発表,辛辣な評論や流行語を発し,"マスコミ大将"になった大宅壮一や,大政翼賛会のアイディアマンとして知られ,<敗戦>直後に,{暮しの手帖}を創刊,独創的編集で一時代を画した花森安治という人物の存在も忘れられない。
出版より少し遅れて始まる娯楽は,内容は様々であるが,大正デモクラシーに始まり,戦時下に発展,戦後に爆発する。その皮切りは,都市近郊私鉄経営のため,宝塚歌劇・ターミナルデパートなど近代娯楽を開拓した小林一三で,双子の兄弟で,{松竹}を設立し,歌舞伎界を支配後,{東宝}と対抗して映画全盛時代を築いた白井松次郎と大谷竹次郎,日本映画独自のジャンルを確立し,映画製作所も設立した"日本映画の父"になった(マキノ)牧野省三,夫の道楽をヒントに{吉本興業}を創設,関西芸能界を支配するに至った吉本せいと,その弟で,戦前から戦後にかけ,非凡な才で次々大衆演芸事業を起こし,{吉本興業}を業界トップにした林正之助,妻かしことともに,戦前からの映画の洋画輸入や戦後の邦画国際化に貢献した川喜多長政,共産党から転向1号,仏文学翻訳経て製紙業界,<敗戦>後{サンケイグループ}築き活躍した水野成夫に,一介の会社員から,階段を駆け上がるように,フジサンケイグループ総帥になった鹿内信隆など,企業トップのほか,近代的小市民映画路線確立し,<敗戦>前後の長い間,{松竹}に繁栄をもたらした城戸四郎,戦時下にアメリカ式手法で映画事業の基盤,<敗戦>後も{アート・シアター}など影響力を発揮した森岩雄,大衆と向かい合う表現を模索,娯楽番組の原型を作ったNHKのプロデューサー丸山鉄雄らも挙げておきたい。
最後の最後に,「活動を究める」上で,現在も重要な職業紹介の制度をつくった人物として,わが国の職業紹介事業の基礎をつくり,民間組織だった職業紹介所を公的なものにした豊原又男を挙げたい。分野型の分類上,やむを得ず,メインを,社会分野の殖産型,サブを,官僚分野の殖産技術型に入れてあるが,個々のものに対応しているしているのではなく,その上に立つようなものであり,以下に記すように,まさに,デザイナ中のデザイナと言える人物であった。その師で,現在の大日本印刷のルーツ秀英舎を起こし,工場法制定に貢献した佐久間貞一と,同じ佐久間門下の親友で,「日本之下層社会」を出版して,大きな反響を起こした横山源之助の両者についても,追って,一枚年譜に加えていきたい。
豊原又男は,明治維新直後の1872年に,新潟県蜂岡の旧三根山藩家臣で,戊辰戦争に敗れた直後,有名な"米百俵"の出荷を担当し,長谷川から豊原に改姓した春雄の六男に生れ,事業に失敗した父が自害して家計破綻し,向学心に燃えるも,小卒で終わり,代用教員になって貯蓄,19歳の時,意を決して上京,転変の後,24歳の時,安田善次郎と東京建物の創立を企図していた佐久間貞一を紹介され,面会するや心服,翌年,安田と意見衝突して撤退した佐久間に従い,彼が経営する(後に大日本印刷になる)秀英舎に勤めるとともに,佐久間が取り組んでいた職工問題の研究に従事するうち,農商務省の工場法策定委員に選ばれた佐久間が,直後に急逝,その遺志を継ごうと決意する。1899年の27歳,早くも処女作「資本と労働の調和」を出版し,同じ佐久間門下の良きライバル横山源之助の「日本之下層社会」出版を支援し,跋文を寄せる一方,農商務省が新設した臨時工場調査会のアドバイザに呼ばれて,委員長桑田熊蔵の薫陶を受け,「佐久間貞一小伝」を刊行,1911年,恩師の遺志である工場法が施行されると,翌年には,その解説書を出し,第1回工場監督官会議で講義,東京府の嘱託にもなって縁ができるなか,1920年,48歳の時,それまでの研究を集大成した名著「労働紹介」を出版するとともに,神田駅ガード下の一角に,自ら命名した中央工業労働紹介所が開設されるに至った。1923年の関東大震災で紹介所が全焼した折には,ジュネーヴでのILO総会に出席していため,信頼する職員に任せて,ドイツの傷痍軍人の職業訓練を視察するなど研究を進め,2年後に,飯田橋の新庁舎に移ると,高松宮来臨の栄誉や,百貨店女店員募集に一万人を超える女性が殺到したりするなか,求人者,求職者双方の立場に立った職業紹介と,実態調査や統計分析に努めて,日本一の紹介所にしていきながら,国営化運動をし続け,日中戦争の始まった1937年,国への移管が決まり,秩父宮・同妃来臨の栄誉を最後に,所長解職,現場を離れ,以後は,江戸時代の奉公人制度から説き起こす「職業紹介事業の変遷」を刊行するなどして,敗戦まもなく没した(巻町双書23「わが国職業紹介事業の父 豊原又男翁」による)。
⇒コラム(素質,努力,指導,機会の話)
⇒コラム(脳とコンピュータの関係の話)
この章TOPへ
ページTOPへ